2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年04月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
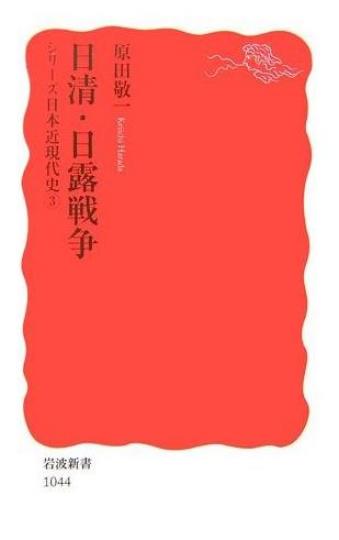
★ 原田 敬一 『日清・日露戦争』 岩波新書 (新刊)
▼ 岩波新書の近現代史シリーズ。 いよいよ佳境。 本日、ご紹介するのは、日清・日露戦争と日本社会の変動をえがいた通史。 これがなかなか面白かった。▼ 簡単におさらいしておこう。▼ 本書は、帝国議会から始まる。 政党の意義を認めないわけではない藩閥勢力は、「吏党VS民党」の初期議会に手を焼いた。 しかし藩閥勢力は、民党の基盤を政府財政を動員(=鉄道建設・民力育成)することで切り崩す、「積極主義」で突破していく。 とはいえ、憲法の規定にないものを、政府が一方的解釈をすることはなく、そのつど合議していったという。 「制度上の権力」(内閣)と「事実上の権力」(元勲)の分裂は、政党政治への待望をひきおこし、やがて伊藤博文の立憲政友会へと帰着。 とりわけ驚くべきことは、 「トルコの憲政失敗」をうけて、与野党とも「憲法と帝国議会の世界史的意義」を自覚していた様子であろうか。 「バカ派」安倍首相の改憲論とは、雲泥の違い。 取り替えてほしいくらいだ。▼ 欧米の承認を受けた下で、国益拡張をめざす、『協調』外交だった日本。 しかし、日清戦争時には転換、清側を挑発しまくって、開戦にもってゆく。 以後50年にわたって、日本軍は、アジアをひたすら歩き続ける。 しかし、24万人の兵士分の輜重輸卒を組織できず、日本は口入屋に依頼して、15万人の人夫を動員することで、兵站を維持したらしい。 「戦争は好景気」も、日清戦争が嚆矢。 日清戦争から日露戦争の間に、戦争記念碑の性格は、『地域代表(生還者も称える)』から、「忠魂碑」へと、天皇制国家イデオロギーに転化したらしい。 「文明の義戦」「文明VS野蛮」のイデオロギーは、学制下、清潔・衛生を叩き込まれた、日清戦争従軍者の目撃した「不潔」「臭い」を通して、身体化されていったのだという議論も、眼から鱗といったところ。▼ 「植民地と戦後経営」の章も興味深い。 台湾総督府の繰り広げた、「原住民殺戮」「相互監視制度」。 「疑獄事件」も頻発して、乃木総督が弾劾されるほどだったらしい。 デモクラシーが進みはじめる内地と、枠外におかれる外地(朝鮮・台湾)。 20世紀初頭までの北海道・沖縄と同様、外地では、憲法が適用されない、大権統治が行われていたという。 権利では参政権、義務では徴兵がなかったらしい。 台湾縦貫鉄道の完成とともに、台湾経済は、対中輸出中心から対米輸出中心に転換。 茶・米・糖・樟脳(楠)の輸出経済が形成されてしまう。 とはいえ、1897年頃までは、欧米商館による間接貿易が7割を占めていた。 なお、戦費負担がおもく、日清戦争後、間接税中心の税体系に大転換したらしい。▼ デモクラシーの苦難のあゆみも面白い。 最初の政党内閣、「隈板内閣」で横行したとされる猟官主義は、欠員を埋めただけであって、表面的な見方にすぎないこと。 明治天皇は、政党政治を嫌い、藩閥(伊藤派・山縣派)・離反した自由党・天皇に包囲されて、大隈内閣は4ヶ月で崩壊してしまったこと。 初耳であることが多い。 なお、市長・助役は、市議会が3名の候補を選出しての任命制だったことは、ご存知であろうか。 有能な人物を地域外から選べる半面、土着市議の利権確保手段となったらしいのだ。 日清戦争は、ジャーナリズムを急成長させ、言文一致体の文章でえがくスタイルを確立させる。 それは、読者の身辺雑記を紙面にかざらせ、小説などの文化をうみおとす。 その一方で、20世紀初頭、鉱毒問題・労働運動といった社会運動の空前のもりあがりを支えたという。 しかし、日露戦争を契機として、退潮してしまう。▼ なにより、外交が面白かった。 条約改正では、イギリス側は、日本が親英政策をとるという期待で改正に応じたという。 また、巷間でいわれてきたような、日英同盟派と日露協商派の対立は存在しない。 政府は、日英・日露協商交渉を並行しておこない、韓国の確保を確実にしようとしていたらしい。 しかも、1904年2月2日のロシア回答は、満韓交換論にもとづいたもので、これが日本軍の電信爆破活動で、駐日ロシア大使館に届かなかったという。なんと、日本は、戦わなくてもいい日露戦争を行ったらしいのだ!!!! いったい、何のために彼らは死んでいったのだろう。 三国干渉では、陸奥外相の楽観論が破綻、急遽イギリスに味方してもらおうとしたもののもらえず、全面降伏に追い込まれたという。 安倍首相の「慰安婦は強制ではなかった発言」みたいでたいへん笑えてしまう(笑)。▼ ひな祭りのとき、男を左、女を右に置くのは、「東京雛」であって、本来の「京雛」ではない。 これが広まったのは、西洋のスタイルを輸入して、天皇の御真影を津々浦々に配したことが原因である、ということを、このブログをお読みの方は、ご存知であろうか。 また、西洋学術を日本が翻訳する以前、中国によって莫大な翻訳が行われていた。 明治期の西洋文化の吸収は、中国による紹介なしには考えられなかった。 現代でも68%が中国漢語、和製漢語は27%らしい。 他にも、黄海開戦は、「アームストロングVSクルップ」の代理戦争だったこと。 国際結婚には、明治当初、国家の許可が必要だったこと。 海軍記念日・陸軍記念日の式典が派手になるのは、1930年代になってからのこと……とかく、刺激的な一冊なのである。 ▼ むろん、「日本は朝鮮に良いこともした」なんてヨタ話は、どこにも載せられていない。 たんたんと植民地帝国に脱皮していく過程がえがかれていく。 「国民」概念の揺籃期日本。 そもそもなかった朝鮮。 むろん、司馬史観や新自由主義史観などは、お呼びではない。 きたるべき、「国民」「大衆」「群集」の出現を感じさせつつ、宗主国と植民地国、2種類の「国民」形成を丁寧にのべていく。 江戸幕府マンセーの第1冊、自由民権運動がぼやけていた第2冊目にはない、なかなか良く出来た概説書という他はない。▼ おすすめ。 評価: ★★★★価格: ¥ 819 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 27, 2007
コメント(2)
-
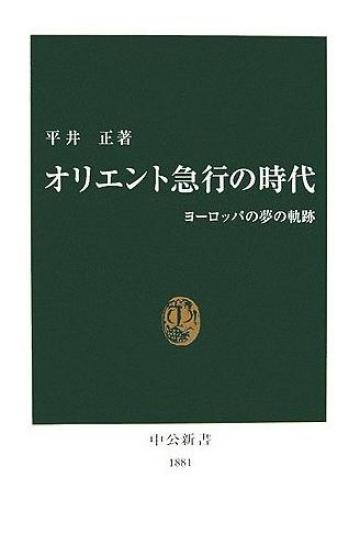
★ 平井正 『オリエント急行の時代』 中公新書 (新刊)
▼ ヨーロッパ鉄道旅行を通した素晴らしい歴史物語の書である。 ゴールデンウィークのご旅行の際、伴侶とされてはいかがだろうか。▼ 1883年10月4日、開業したオリエント急行。 弱小国ベルギーの若者、ナゲルマケールスは、「国際寝台車会社」を創設して、細切れ状態にある鉄道会社と個別交渉の末、運行させたもの。 オリエント急行は、ヨーロッパで例のない、画期的な、豪華列車で国際列車だったらしい。 個人主義ヨーロッパにふさわしい、「コンパートメント(個室寝台)」というものを発明したのも、実はオリエント急行だという。 「へー」ではないか。 ▼ なによりも、「19世紀ヨーロッパ」の薫りがただよっているのが喜ばしい。 ▼ オーストリア・ハンガリー帝国 かの国の鉄道を作ったのは、当初、ロスチャイルド家だったという。 「エルサレム王」なる称号までもつ皇帝、フランツ・ヨーゼフ2世以外、時間をまもるものはいない都市、ウィーン。 オスマントルコが廃棄していったコーヒー豆の袋から始まる、コーヒーハウスの喧噪。 オスマン軍楽隊から始まるクラシック音楽。 ドイツ色の強い王城ブダと、マジャール色の強い商都ペスト。 ハンガリーは、ルーマニアに次いでロマ族が多く、ジプシー音楽がハンガリー情緒とされていた。 オーストリアから独立を企てたコシュート・ラヨシュの墓参にわざわざ出かけた、日本史研究者・黒板勝美の逸話も面白い。 ハンガリー平原は、大地主支配の水不足に苦しむ褐色の平原だったようだ。▼ ルーマニア王国 オリエント急行開通直前、1881年に王制に移行したばかりの国家だったという。 もともとオスマン時代は、自治が認められていたので、黒海沿岸のドブルジャを除けば、あまりトルコ人がいなかった。 むしろ、ファナリオットと呼ばれたコンスタンチノープルのギリシャ人商人が経済を支配していたらしい。 そんな中、1859年、モルダヴィアとワラキアは、クザ公をいだき、同君連合として出発。 1861年、ルーマニア公国が誕生する。 急進的改革は、貴族層の反発を買い、66年、大公追放。 プロイセン王家から王様を連れてきて、ルーマニア語を話せない王様が、君臨していたのだとか。▼ ブルガリア 1883年、オリエント急行開通時には、「公国」としてオスマン朝主権の下、独立したばかり(露土戦争 1878年)だったらしい。 ブルガリア大公の息子は、「鉄っちゃん」趣味が昂じて、領土通過中は、オリエント急行の機関士として、急制動をかけまくり、列車をオモチャにしていたという。 ブルガリアは、ルーマニア同様、オスマン時代、ギリシャ人が牛耳っていた。 そのため、ブルガリア正教会を樹立することで、知識人達は精神的独立を図ったとされる。 本来、西欧近代の創作物にすぎない「古代ギリシャ・イデオロギー」に感染しローマの後裔から「ギリシャ人の末裔」と思いこみ始め独立運動をおこすギリシャ人の姿は、喜劇といってよいだろう。 バルカン半島を悩ますナショナリズムは、ギリシャから始まったのだから。▼ オスマン・トルコ 驚くなかれ。 開業時、イスタンブールまで列車は走っていなかった。 1888年までは、いったん、ブルガリアの港町ヴァルナに出て、そこから船でイスタンブールに行ったという。 イスタンブールは、オリエントの典型的都市ではない。 むしろ、ギリシャ人や西欧人のつどう、国際都市だった。 かつては、巨大な大帝国として、居住制限があるものの通商の自由が認められる、「キャピチュレーション勅令」で片務的特権を欧米人たちに与えたら、いつのまにやら主客逆転。 フランス人たちはイスタンブールのペラ大通りを闊歩。 フランスで印刷された、不正確なコーランが流布して問題になったこともあったという。 アブデュルハミトの専制政治ぶりがエリア・カザンの映画『アメリカ!アメリカ!』に描かれているとは、まったく知らなかった。 人種・民族ではなく、宗教を社会統合の道具としていたオスマン朝の姿は、非常に面白い。▼ 第1次大戦後になると、ヨーロッパは一変してしまう。 もはや王侯貴族はどこにもいない。 一般化したオリエント急行。 豪華サロンカーは過去のもの。 第1次大戦休戦協定調印の舞台は、オリエント急行を運行させていたワゴン・リー社の2419号客車であり、ヒトラーはこの屈辱を決して忘れなかった。 1940年、フランス征服の際、同じ車両で降伏文書署名をさせた挙句、連合国反攻の際、降伏文書調印車両として再々使用されることがないように、1944年、命令で破壊してしまったという。 第2次大戦後は、社会主義国の鉄のカーテンによって、検問の連続。 豪華な食事も提供できず、豪華列車としてのオリエント急行は1962年、定時列車としての「オリエント急行」は1977年に運休してしまう。 最晩年期は「難民列車」だったというから、悲しさもひとしおである。 ▼ 西欧にとっては、エキゾチックな異国情緒をかきたてるオリエント急行も、オリエント側にあたる東欧にとっては、文明を運んでくる列車だった。 オリエント急行開業前までの汽車旅というものは、食堂車がなく、駅に長時間停車して、レストランに入って食事を取っていたらしい。 また「最後の授業」で知られるエルザス・ロートリンゲンは、ドイツ唯一の「帝国国有鉄道」が走っていたものの、ドイツに同化されることなく、第一次世界大戦を迎えたというのも、初めて聞く話である(たいてい、元々ドイツ語圏としか説明されないことが多い)。 ドイツでは、王国固有の鉄道会社が走り、ビスマルクは帝国国有化に失敗。 プロイセンとバイエルンの機関車速度競争は、子供じみていてなかなか楽しかった。 ルーマニアでは、ロマ族は1851年まで奴隷扱いされていたらしい。 ウィーンから先になると、オリエント急行でも、なかなか定時運行ができなかったという。▼ 逸話もふんだんに盛りこまれてたいへん興味深い。 オリエント急行開通時、その乗客は、ルーマニア王カロル1世の離宮に招待され、オスマン皇帝アブデュル・ハミトにまで謁見したという。 靴の先に接吻させるローマ法王と同様、オスマン皇帝は、接見時、ひれ伏させて衣服の裾に接吻させていたらしい。 森鴎外は、日本人として最初期の乗客の1人でありながら、劃期性をまるで理解していなかったらしい。 「列車の王者」たるオリエント急行を利用しないことには、王のステータスを保てないとばかりに、東欧の国王たちも利用すれば、あの伝説の女スパイ、マタ・ハリも利用していたという。 インドのマハラジャたちも利用して、異国趣味に花をそえる。 なお、開通当初は、手荷物車両を2両も連結していたという。 女性の荷物の多さは、日本に限ったことではない。 ▼ とっておきの逸話を紹介しておきたい。 創設者ナゲルマケールスは、オリエント急行をシベリアをこえて東京まで延伸させたかったらしいのだ。 なんとも、残念な話ではないか。 ▼ むろん、「オリエント急行」は、政治とも密接にかかわり、むしろ政治そのものになることもマレではない。 19世紀、鉄道は、支配を維持するため積極的に建設された………チベット・ラサへ向けた中国の鉄道建設を知る人たちにとってはおなじみの図式だろう。 「列車の王者」オリエント急行の運行をめぐって、対立しあう東中欧各国。 最初は、パリ~ウィーン~イスタンブールだったが、シンプロン・オリエント急行(ミラノ・ベオグラード経由)が登場。 第1次大戦後になると、オリエント急行が百花繚乱。 ロンドン~アテネなど様々なオリエント急行が毎週走っていたらしい。 ドイツは、フランスのオリエント支配を象徴するオリエント急行に我慢ならず、バグダット鉄道を建設し、「バルカン列車」なるものを第一次大戦中走らせたものの、敗戦で水の泡。▼ 1988年、日本全国をまわって、今では箱根に鎮座する、「オリエント急行」の客車。 日本だけではない。 今では、タイ~シンガポール、アメリカ、メキシコでは、「オリエント急行」の名を冠する列車が走っているという。 「命がけの通商」から、お気楽なツーリズムへの転換こそ、「オリエンタリズム」「異国趣味」を支えていた。 オリエント急行のみが喚起させる「異国情緒」「未知の世界への憧憬」こそ、『ラインゴルト』『ゴールデンアロー』など、他の単なる豪華列車とはちがい、オリエント急行を「ツーリズムのシンボル」「最高級豪華サービスを提供する不滅のブランド」にさせた原因であるという。 ツアーに行く前に、ぜひ読んでおきたい一冊ではないだろうか。 ▼ ただ、難点をいえば、これは誰に向けて書かれたのか、いまいち分かりかねることだろうか。 「オリエント急行史」「東欧社会史」「ツーリズムの発生史」としてなら、浅いとしか言いようがない。 観光ガイドなら逆に濃くて使えない。 どっちにしろ、散漫な印象をいだいてしまう。 日本人のアジア認識につきまといがちな「知の支配の一形態」=オリエンタリズムを糾弾するならともかく、ヨーロッパ人のアジア認識(=オリエンタリズム)について、日本語で批判的記述をすることに、何か意味があるのだろうか。 旅行先で突っ慳貪な対応を受けた場合、東アジア・東南アジア旅行なら激怒する日本人も、ヨーロッパ~イスラム旅行ぐらいだと、「これが外国旅行というものね」と、借りてきた猫のように大人しい。 元から理解できないイスラムや、精神的に隷属している欧米には、ヘイコラする日本人。 他人のことより、自分のこと、だと思うんだけどね。 オリエンタリズムの解説は、まったくされていないので、「ヨーロッパ人悪い、日本人はやっぱり素晴らしいのだな」と誤解されちゃうんじゃないか? ▼ しかし、ヨーロッパ臭が好きな人にはたまらない一品でしょう。 だいたい、日本人の好きなヨーロッパって、大方、19世紀でしょうしね。 ▼ という訳でお薦めしておきます。 評価: ★★★☆価格: ¥ 903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 24, 2007
コメント(0)
-
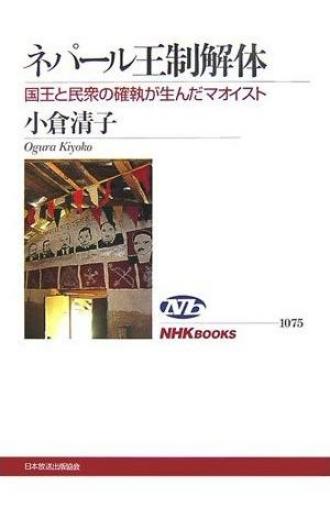
★ ヒマラヤの毛沢東主義派ゲリラ闘争 小倉 清子 『ネパール王制解体』 NHKブックス (新刊) 後編
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 2001年までには、全75郡中、24郡に人民政府を樹立したものの、「9・11」によって、大逆風を受けていた、ネパール共産党毛沢東主義派。 インフラ破壊活動。 スパイの捜索。 住民への脅迫と、強制的寄付の徴収………これでは、何も国王政府とかわらない。 国軍と毛沢東主義派は、武力衝突を続け、1万3千人の死者と、何十万人もの難民を生み出した。 とくに、マオイストの被害者は、ネパール会議派支持者たちだったという。 双方の人権侵害は、国際問題に発展。 しかし7政党の民主化運動を受け、水面下で提携。 2005年10月~11月、毛沢東主義派は、統一共産党、ならびに主要7政党と、「制憲議会選挙」「民主共和制」立て続けに合意書をかわした。 2006年2月、毛沢東主義派プラチャンダ党首は、3月14日より全国無期限ゼネストを指令。 3月19日、毛沢東主義派と7政党合意により、ゼネスト指令取消と、4月6日から7政党による4日間のゼネストと以後の民主化デモが決定されたのである。 ▼ 連日にわたる、警官隊と市民との激しい衝突は、4月21日、50万人をこえる空前のデモに発展することになった。 ここに4月24日、国王が屈服。 5月18日、復活した議会では、国王特権の剥奪が議決される。 毛沢東主義派は、国王の屈服を受け入れた主要7政党、とりわけ共産党の政権参加に難色を示すアメリカの意を体した、会議派のコイララ首相に反発したものの、6月、歴史的な政府と毛沢東派指導部の会談。 2006年11月8日、和平協定締結。 武器を放棄して、議会政治に戻り「新生ネパール」を作る道を選んだ、という。 なかなか、激烈なドラマが展開されていたのである。 ▼ しかし、勘違いしてはならない。 この書は毛沢東主義派を礼賛するものではない。 むしろ逆に近い。 毛沢東主義派の怖さは、いたるところ表現され、かなり手厳しい。 毛沢東主義派のイデオローグ、バフラム・バッタライとプラチャンダ党首の確執。 毛沢東主義派の村民動員のため、遠い村から仕方なく集会に参加した村人。 マオイストに土地を奪われた農民たち。 人民政府の道路建設に「強制的に参加」させられる村人……。 このような記述が実に多い。 毛沢東とプラチャンダ党首の肖像をかかげ、「犠牲は国のため」と教える、毛沢東主義派支配地域の教育現場「マオイスト製造学校」の指摘。 個人的所有のない自給自足のコミューン生活は、決して肯定されない。 どれくらい厳しい生活なのか、随所で触れられている。 ▼ また、「人民戦争」最大の犠牲者は、マオイストと警官であって、武装闘争は構造的貧困から抜け出せない、「貧困層VS貧困層」の戦いにしかなっていない、という。 しかも、毛沢東主義派の武装解除の時期は、いまだ明言されていない。 両軍を合体して「新国軍」とするのは問題が多いからである。 今の国軍は「ネパール版天皇の軍隊」である。 毛沢東主義派の人民解放軍については、いうまでもないだろう。 2007年6月までに行われる「制憲議会選挙」後、すんなりと民主化が進むとは思われないのだ。 ▼ しかし、毛沢東主義派に流れこむ人々の思いを高飛車に評論するようなものでもない。 夫を失ないながら悲しむ様子を見せようとしない女性党員の苦悩。 親戚・縁者を政府に殺され、コミュニストに身を投じた人々。 かれらの思いも、また丁寧にすくいとっている。 ネパールの民主化。 日本が果たしうる役割も大きいだけに、大変興味深い。▼ 部外者からみると、やはり「インドの存在感の大きさ」に驚かされるほかはないだろう。 インドとネパールの往来には、ビザやパスポートはいらない。 そのため、インド拡大主義者批判を繰り広げながら、毛沢東主義派首脳部は、しばしば安全なインドに逃げて人民闘争を続けていたという。 また毛沢東主義派は、教員を中心として、「村」単位で勢力を拡大していったようだ。 「村」に、コミュニストの教員が訪れて、「村」ごとコミュニストに染め上げていく。 たくみに、政府・警察の苛斂誅求による、「反政府」感情を利用して……。 毛沢東主義派が全国で武装闘争ができるほどの組織力を持ちえたのは、モンゴル系マガル族 ――― 差別が少ない自然のコミュニズム、好戦的な性格、頑丈な体躯であり、かれらは下位カーストでもある ――― によるものでありながら、バッタライもプラチャンダも、ヒンズー最高位カースト「バフン」で、幹部たちも高位カーストというのは、大変面白い事実ではないだろうか。 かれらに差別を持ち込んだのは、インド・アーリア系のヒンズー教徒であった・・・おそらくウソとはいえ、実にかれらのオーラルヒストリーを収集していて興味深い。 そもそも、ネパールには、支配者側の史料しか残されていないどころか、オーラル・ヒストリーさえ乏しいというから、驚かされる。 ネパールの民は、歴史を捨てさせられたのである。▼ 強いて批判すれば、地図が付けられていても極めて不十分で、どこの話なのかまるで理解できないことかもしれない。 とはいえ、南アジアを知るためには、最良の一冊であることは、この紹介からの一部わかるのではないだろうか。 ▼ ぜひ、図書館や本屋でみつけ、読んでもらいたい。評価: ★★★★価格: ¥ 1,218 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 17, 2007
コメント(1)
-
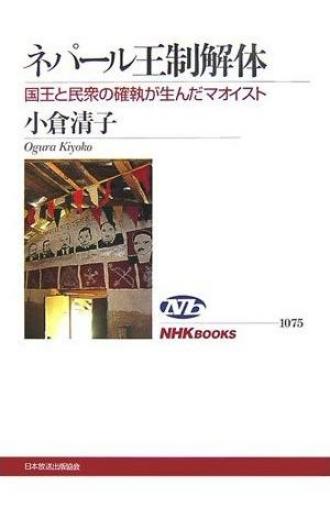
★ ヒマラヤの毛沢東主義派ゲリラ闘争 小倉 清子 『ネパール王制解体』 NHKブックス 前編 (新刊)
▼ 台頭著しい中国の影に隠れてしまいがちな、南アジアの経済発展。 最近、南アジアは、ようやく脚光を浴びはじめたものの、複雑怪奇な政治情勢は、あまり知られていません。 知識不足を埋めるためにも、適切な入門書が望まれる所。 そういう人たちのためには、明石書店が刊行している『○○を知るための△△章』シリーズが大変有効なのですが、今回は、王制が打倒されたばかりのネパール近現代史の本を紹介しましょう。▼ ネパールといえば、何といっても、ネパール共産党毛沢東主義派によるゲリラ闘争が有名です。 問題解決能力のない政党政治家。 暴力革命を夢見るマオイスト。 「ビシュヌ神の生まれ変わり」として、絶対権力で統治を試みる国王権力。 この「3すくみ」は、ネパールには永遠に民主主義が根付かない、と思わせていました。 そこに、前2者に民衆までも合流して、すさまじい政治の地殻変動「民主化運動」の勃発。 そもそも、今どき、どうして毛沢東主義派が? 世界が抱くであろう疑問は、この書で完全に解き明かされていて、たいへん面白い。▼ 要約すると、以下のとおりです。▼ 1990年、民主化運動によって、1960年から続いていたパンチャーヤト制度(国王直接統治)が廃止された。 ところが、ネパール国民会議派のコイララ派とバッタライ派の対立で、政治が機能しなかった。 つい最近まで、国王クーデターによる、独裁政治が続いていたネパール。▼ 1949年、インド・カルカッタで結成されたネパール共産党は、ヒンズー教徒が8割を占めながら、非常に大きな政治的勢力を持ち続けていたという。 それも、分裂を繰り返しながら。 ネパールの共産党系勢力の幅の広さは、過激武装闘争派から、王室側近の共産主義者まであるという。 そんな共産党系の政党は、10を数えたが、民主化運動の時、大同団結する。 穏健派のネパール統一共産党。 そして、過激派のネパール共産党エカタ・ケンドラ。 エカタ・ケンドラは、議会政治を認めていないが、IRAにとってのシン・フェイン党のような表組織、「統一人民戦線ネパール」を結成。 過激派は、「議会の悪事を暴露するため」総選挙に参加していたらしい。 1990年代半ば、議会政治が麻痺したとき、武装闘争を始めたのが、エカタ・ケンドラから分離して結成された、毛沢東主義派。 1996年、ヒンズー差別廃止、土地改革、インドからの影響排除(言語、政治)、世俗国家化、軍・警察の文民統制を要求。 容れられない場合、武装闘争を通告した。 当然政府は無視。 1996年2月13日、人民闘争開始。 このブログ読者も、驚くことであろう。 毛沢東主義派は、極めて新しい政治勢力なのである。 当初は、泡沫に近かった。▼ 当初、ロルパ郡という中央に常々反発していたモンゴル系住民のすむ地域を越えられなかった毛沢東主義派。 ところが、2001年、ナラヤンヒティ王宮における、ビレンドラ国王を含む国王一家全員をディペンドラ皇太子が射殺する事件を契機として、勢力を急激に拡大し始めた。 犯人は、直後に即位したギャネンドラ国王ではないか? 仏像や麻薬の密輸、交通事故。 日頃の悪事にもかかわらず、国王の絶対権力におびえ、口をとざすひとびと。 そこに毛沢東主義派はぶちあげた。 「インド拡大主義者とアメリカ帝国主義者が、ネパールを従属国にすべく、ギャネンドラを手先として、毛沢東主義派弾圧に熱心ではなく中国にも接近していたビレンドラ国王を排除したのだ」と。▼ さて、本書によれば、ネパール近現代史は、陰謀の歴史であるという。 カトマンズでは、日本並みの暮らしをする人々が出現しているというのに、全75郡中15郡では、車が通れる道すらない、絶望的な経済格差が存在するネパール。 13世紀には、温暖な上に、「インド~中国ルート」の要衝、カトマンズ盆地にヒンズー王朝が成立。 ヒンズー化が始まる。 18世紀には、ブリティヒ・ナラヤン・シャハ王によって、ネパール領域内がほぼ統一。 東インド会社と取引して領域を保全するとともに、19世紀からはラナ家が世襲首相としてネパール政治を牛耳り、1951年までラナ家支配が続いたという。 ラナ家打倒のため、ネパール会議派はインド領内を利用して、武装闘争を行ない、国王はインドに逃亡。 インドが仲介する形で、国王帰還するも、独裁政権化。 一時、民主的社会主義を掲げるネパール会議派は、議会の多数を掌握して、土地改革に着手するも、1960年、マヘンドラ国王によるクーデター。 会議派の半数が国王に寝返ってしまう。 ▼ ネパール会議派を掣肘するため、国王が採った政策こそ、「コミュニスト厚遇政策」であったという。インドを掣肘するためには、ヒンズー教の盟主として「ヒンズー王国」をなのり、同時に「中国」にも接近する。 中国に接近するためには、共産党勢力の拡大を奨励する …… 「コミュニスト」「ヒンズー」「中国」の三点セットこそ、ネパール専制王制の基盤。 1972年、ビレンドラ国王即位後も変わらない。 1990年の民主化後も、ビレンドラ国王は、執拗に民主化の骨抜きを図った。 憲法には、「ヒンズー教国教」「国王の非常時大権」が ……… これらこそ、「民主化」後のネパールにおいて、女性・少数民族・カースト差別が続き、2002年10月~2006年4月には、ギャネンドラ国王による独裁政治を産み落とした原因である、という。 メディア規制、電話線切断、移動の自由の剥奪。 釈放命令を受けた被告が、裁判所を出た所で、警察に再逮捕される事態が続発。 国王政権に協力していた会議派とネパール統一共産党が離脱。 2005年8月27日、ネパール統一共産党が「立憲君主制支持」から「民主共和制」へ転換。 同年8月31日、ネパール会議派も「立憲君主制支持」に関する綱領を破棄。 主要7政党による、「王制廃止」「共和制」をもとめる政治運動が開始される。 (その<2>はこちらになる予定。 応援をお願いします。長すぎて1日では終わらなかった)評価: ★★★★価格: ¥ 1,218 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 14, 2007
コメント(1)
-

★ 醍醐寺三宝院への旅
▼ 先週末、中学生の時分から、一番行ってみたかった日本庭園である、醍醐寺三宝院に参詣してきた。 何十年もやりのこしていた宿題を果たした気分だ。 個人的に行きたい庭は、「苔寺」こと西芳寺と、桂離宮と醍醐寺三宝院だったんだけど、前2つは予約制。 とてもふらりとはいけない。▼ 土曜日早朝、ふらりふらりと、カメラを片手に、醍醐寺にむかう。 曇り空。 なんと、4月8日の日曜日には、「醍醐寺桜祭り」があるくらい、醍醐寺は桜の名所らしい。 本当に美しい。 行ってみるまで知らなかったんだけど、醍醐寺は「世界遺産」。 そんな凄いものになっていたとは、醍醐寺に着くまでまったく知らなかった。 所詮、何年か一度、突発的に庭をみたい!!!という衝動にかられて参詣する「にわかファン」。 こんな基礎的なことすら知らないのだから、困ったものだ。 ▼ 本当のお目当ては、むろん三宝院の庭園である。 大名庭園の豪奢さと禅寺の静謐さの中間くらいのお庭。 中学生のとき、写真集でみて、感涙にむせんだものだ。 しかし、いざ、現地でこの目で見てみると、思ったほどではない。 池の配置は見事だけど、とくに緑が薄い。 梅雨とかにいけば、苔の絨毯が映えて、素晴らしい光景が拝めたかもしれない。 加えて、「写真撮影禁止」……庭の絵葉書を売るためとはいえ、せこい商売根性にあきれる。 あとで絵葉書の中で気に入ったものを、ネットにピックアップしてやろうかな。。。。▼ 桜祭り前日だけあって、本当に桜がすばらしい。▼ 名物「しだれ桜」の方は、このようにすでに散ってしまっていた。 たいへん残念である。 しかし、ソメイヨシノの群れは素晴らしい。 下の写真は、三宝院正門から駐車場へ向かう道の眺めなんだけど、すでにワクワクさせる感が漂ってませんか ??? むろん期待を外すことはありません。▼ 実際、その道をくぐると、素晴らしい桜並木です。↓▼ そういえば、桜吹雪とはもっとも美しい日本語のひとつである、といったのは誰だったか。 一番のお目当てだった三宝院は、コケてしまったけど、桜を本当に堪能できた一日でした。 京都近縁の方は、ぜひ一度、「醍醐寺」の桜を拝観しに出かけてはいかがだろうか。▼ 三宝院がダメなら、どんな庭が好きなんだ、と言われると困りますね。 ▼ 個人的ベストは、なぜか中国の庭。 たぶん季節も幸いしたんだろうけど、「蘇州の拙政園」と「揚州の個園」は、本当に絶品だった。 日本的な感性にも、ドンピシャ。 雨にけぶる拙政園は、幻想的としか言いようがない、すばらしい興趣をたたえ、その美しさに呆然として座り込んでいたことを覚えている。 揚州の個園については、「竹林庭園の傑作」。 太湖石という奇岩を使っているんだけど、なんというか、言葉にならない美しさがあるんですよ。 ▼ もし、中国のお庭をみたいと思う方は、いちどツアーで行かれてはいかがだろうか。 この2つの庭園は、絶対、見る価値があるとおもう。▼ 醍醐寺三宝院は、八重桜も満開だった。 この週末をこえることはないのだろう。 桜の花見は、一期一会。 すばらしい旅だったというしかない。 すなおに感謝したい。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 9, 2007
コメント(1)
-
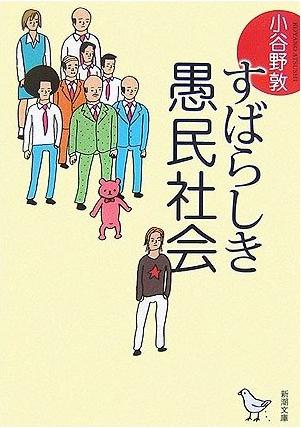
★ 小谷野敦 『すばらしき愚民社会』 新潮文庫 (新刊)
▼ 読書が趣味だと周りに知られると、ある作家を読んでいないことについて、しばしば非難されることがある。 「えー、京極夏彦読んでいないんですか。 てっきり読んでいるものとばかり」 悪かったな。 森博嗣ともども新本格は嫌いなんだ。 「『裏切られた革命』読みましょうよ」 だから、俺はマルクス主義者じゃないんだって。▼ 小谷野敦は、そんな読んでいない人の一人である。 ごたぶんにもれず、「『もてない男』は面白いですよ。 小谷野敦は貴方にあうと思いますよ」なんて、わざわざお節介焼いてくれる。 いらんお世話だ。 だいたいアカデミズムには、「一学者、一仕事」 ――― 学者にとって、本当に素晴らしい仕事は、生涯に1つだけである ――― という恐ろしい格言があるのだよ。 他にも、「学者は処女作に向けて成熟する」というのもあったな。 ▼ 小谷野敦や福田和也や仲正昌樹や香山リカには、膨大な著書がある。 ということは、たくさんの仕事をしているのでは、無論、ない。 逆に「何一つ仕事をしていない」とみるべきなのだ。 彼らが死ぬ直前になって、「俺の真の仕事はこれだ!!」とでも遺言を出してくれたら、まあ読んでみようかね……▼ などなど、減らず口を叩いていたのだが、本屋で偶然、小谷野敦の新刊が出ていたので手に取って立読をはじめたら止まらない。 つい、購入してしまったのである。 うーん、仲正のときとパターンが同じじゃん。 進歩していないねえ。▼ 要するに、ヘナチョコ知識人は去れ、という本である。 エッセイである。 気楽に読む本である。 個人的に面白かった部分を列挙すると…… A 今の若者は、司馬遼太郎すら読まない。 高校と大学を減らせ! B 豊かな社会になると、遺伝によって、 かえって階層移動は起こらなくなってしまう C 武士層は徴税権だけもって土地を持っていない奇妙な貴族階級 D カルスタ派と「江戸ブーム」派の野合で、江戸時代がパラダイスに E 舞妓・芸妓は、徳川期の売春文化の名残 F 「妻」は関東武士の嫁取婚で発生した同居女性、 「女」は通い婚の女性 G 近世を知らない知識人 …… フロイト・ニーチェの悪影響 H 「○○とは何か」は決して真正な問題ではない I 近年、「病理」が多いように感じるのは、 昔はそんなことに構ってられなかったからだ J 所詮、2チャンネルにできることは「うがち」や「ちゃかし」 K 笑われることを恐れるな L ポストモダンは「やけくそ哲学」(『知の欺瞞』の池田雄一書評) M 「家族の多様性」「男女平等」をいいながら男性の貞操義務違反、 「夫が働かない」という訴えに飛びつくフェミニスト弁護士 N 女性のフェミニスト学者は、才色兼備で結婚もしていながら、 そのことを隠し「結婚は桎梏だ」などといいやがる O 性表現を取り締まるんなら、暴力表現も取り締まれ! P 国文学の4悪人、中村真一郎、梅原猛、加藤周一、丸谷才一 Q エンタシスは法隆寺に影響、写楽の正体は不明……はウソ R 禁煙医師連盟に精神科医を加えないのは、体質的に不可能な人 もいることが解ってしまうからだ!!!! S 「喫煙することで世界を我有化するのだ」(BY サルトル) T 嫌煙運動が隠蔽しようとしているのは、 遺伝子が寿命を決定するという事実だ!▼ うーん、たしかに面白い。 なにせ、天皇制反対で再軍備賛成、であんまり考えが違わない。 おまけに、文学の世界なんかあんまり知らないので、結構、目から鱗が落ちたりした。 わたしの友人の見立ては、実に正しかったのかもしれない。▼ ただ、どうみてもオカシイと思える部分も多い。 シニシズムをファシズムと結びつける北田暁大を「シニシズムを礼賛している」と書いたり、あとがきでイスラムの教義の危険性を主張して「異教徒など問答無用で殺しても良いのである」と絶叫したり。 アホかいな。 キリスト教の教義では、「愛」が強調されているから、キリスト教徒は愛溢れて危険のない人々なのか? そんなもの、キチガイを初めとした読み手側が、「聖典」「教義」の中で、「啓示」(欲しいと思っていた文句)を「発見する」だけだろう(小谷野がそうであるように)。 教義うんぬんなんかでは断じてない。▼ 禁煙ファシズムの部分は、暴走というしかない。 「自動車の排ガス」こそ、肺ガンの原因で、禁煙推進団体は自動車から金を貰ってる!!!! まあ、禁煙ファシズム批判全体を知っているわけではないので即断できないが、小谷野は途上国の都市に行った経験がないのだろうか??? 一度でもいいから、途上国の都市に住んでごらん。 日本とは排ガスが比べ物にならないほどキツイから。 目黒区なんて、ぜんぜん排ガスがない地域だよ。 日本くらい、都市の空気が綺麗な国は、本当に少ない。 小谷野の妄想が正しければ、途上国では日本の何倍も排ガスなどの化学物質が舞っているんだから、男女問わず(あたりまえだ)、肺ガン発生率が高くなっていなければおかしい。 そんな統計、すぐ出せるだろう。 くだらないこと言わないで、とっとと実証すればいいのに、何故しないのだ?▼ 私自身まったくタバコを吸わない。 しかし、タバコの煙は、あまり気にならない。 「ちょっと失礼」といわれて、「吸わないでくれ」なんていったことは、一度もない。 てか、タバコの臭いは、子供の頃、好きだった。 ただ、そんな僕でも、吸って良い場所だろとばかりに、何の断りもなく吸い始められたら、さすがにムカっとくる。 この辺が、タバコを吸わない人の典型的な心性ではないだろうか。 結局は、そんな些細なことから、「自動車団体から金をもらう」という誹謗中傷にいたるまで、喫煙者にはデリカシーというのが乏しいのだろう。 「禁煙ファシズム」的状況とは、自らが蒔いた種、としか思えないので、同情する気がまったくおきないのが困りものだ。 ▼ しかし、文庫版で廉価だし、一応買って損は絶対ないとおもう。評価: ★★★価格: ¥ 500 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 6, 2007
コメント(2)
-
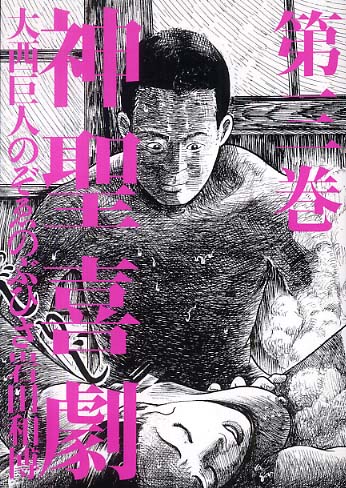
★ 「対右傾化」最終兵器登場! 大西巨人原作、のぞゑのぶひさ作画、岩田和博監修 『漫画 神聖喜劇』全6巻 企画・編集 株式会社メタポゾン 幻冬舎 (新刊)
▼ 感動のあまり、言葉も出ない。 ▼ ながらく、「戦後文学第一等」とされながら、ドストエフスキーもかくやと思わせる、超重量級のヘビーな作品。 そのため、多くの読者の挑戦をはねのけてきた、日本文学史に屹立する金字塔、大西巨人『神聖喜劇』。 この傑作の漫画化が、今年1月末、堂々完結した。 この快著と思想を世に広めるためにも、一文を草しておきたい。 ▼ 大西巨人作『神聖喜劇』とは、なにものぞ。 1942年、対馬砲台へ入営した、東堂太郎2等兵による、日本陸軍内務班にあらわれた日本社会の悪しき体質との3か月間の抗争をえがく、一大長編小説である。 もともとは、野間宏『真空地帯』への批判であったが、もはや見る影もない。 内容は、みるみる脹れあがって、脱稿まで25年の歳月を費やすことになった。 1979年、全5巻完結。 ちくま文庫や光文社文庫などで、手に入れることができる。▼ 主人公東堂太郎は、無政府主義者(=アカ)であった。 かれは、大日本帝国の遂行する「聖戦」のオゾマシイ性格を知り尽くしている。 ところが、病気もちということで、即時帰郷、入営しなくて済むように取りはかろうとした、軍医の好意を拒絶してまで、彼は軍に入営するのだ。 「私はこの戦争に『一匹の犬』として死すべきである」と ……… ▼ この作品は、超人的記憶力の持ち主、東堂太郎二等兵のおこなう、軍隊内での合法的闘争の数々を追うかたちで、話がすすんでいく。 旧日本陸軍は、「無法地帯」(=シャバの論理の通じない真空地帯)では、断じてない。 陸軍のバカバカしいまでの規則遵守体質は、コミカルに描きだされている。 「知りません禁止」「忘れました強制」から、天皇を頂点とした「責任阻却の論理」を丸山真男ばりに暴きだす姿は、共感する人も多いのではないだろうか。 日本陸軍とは、日本社会の縮図だったのである。 シャバと同じように、学歴や身分が幅を利かしている陸軍。 そこでの合法的闘争を通して、もうひとつの主題である、部落差別の悲惨さ、人間の卑小さ、がこれでもかとえがきだされ、容赦がない。 ▼ そして、感動の5巻。 部落出身者であるがため、周囲から暴力に巻きこまれ、事故死でありながら殺人犯として服役していた、冬木照美。 部落出身者にして前科者。 2つのスティグマは、招集された先の皇軍内においても、冬木をつかまえ、決して逃してはくれない。 さまざまな事柄や事件で、冬木は嫌がらせを受けてしまう。 しかし、「模擬死刑の午後」において、冬木照美の苛烈なまでの決意が、上官にむけて吐露されたとき、それはほんの束の間、皇軍の秩序まで瓦解させるのだ!!! 「連帯」の輪の神々しさ! その光明。 しかし、たちまちのうちに暗転してしまい、秩序はふたたび取り戻されてしまう。 その悲しさ。 最も美しいものこそ、実は闇をも産みおとすのか!!!▼ ただの反戦小説ではないのか? そのような本になぜそこまで?? ▼ こうした疑問は、浅はかな思いこみに過ぎない。 この書では、チャンコロを焼き殺した農民下士官も、武士道を体現したような士官も、東堂二等兵という作者の分身を圧倒するほどの異様な存在をもっている。 陸軍への抵抗を通じて出会った、さまざまな人々との交流によって、かれは「この戦争で死ぬべきである」から「この戦争を生きぬくべきである」へと改心をとげていく。 主人公東堂太郎は、日本陸軍ともども、根本的に否定されてしまうのである。 その弁証法的「回生」の過程は、ぜひ確認してほしい。 ▼ 『神聖喜劇』の「凄まじさ」は、逆説的に聞こえるかもしれないが、以上のストーリーにある「のではない」 。 ▼ いわば、日本社会との戦いの物語を「縦糸」とすれば、東堂二等兵の脳内で「俳句」「和歌」「近代詩」「外国文学」「マルクス主義文献」が縦横無尽に呼びだされる、「横糸」の信じられないほどの豊饒さこそ圧倒的なのである。 物語は、引用の凄まじさの前に、遅々として進もうとはしない。 しかし、ストーリーを遅々として進ませない、この「引用」の群れこそ、読者にとっての「よろこび」に他ならない。 いってしまえば、京極夏彦を圧縮したようなものとおもえばいい。 電話帳を上回る厚さが、「よろこび」にかわる一瞬が、貴方にもきっと訪れるだろう。 読者諸賢の聞いたこともがない詩人、文学者たちの作品の断片が、圧倒的な内容をもって、われわれの眼前にせまるのだ。 わたしは、この作品を読んだときくらい、日本に生まれ、日本語を話すことのできる喜びを感じたことはなかった。 ▼ おもえば、『神聖喜劇』ぐらい、読み終えることが悲しかった作品は、ほかになかったのではないか、とさえおもう。 家にこもること3日。 ひたすら読み続けた至福のひととき。 こんな本には、2度と出会うことはできないのではないか。 読んでいるうちに、確信めいたものが脳裏をよぎって、わたしを離さない。 クライマックスに近くなって、読むことの「至福」と読みおえることの「悲しみ」がないまぜになり、滂沱の涙を流しながら読む、奇怪な精神状況に陥ったことを覚えている。 ▼ 読了直後、わたしは、文学を専攻していた後輩に電話をかけた。 むろん、謝罪のためである。 「これまで俺は文学をなめていた。 悪かった。 ごめんなさい」 ▼ この本を読めば、文学とは、世界認識を根底より変容させる可能性を秘めた営みであり、意味の政治学をめぐる戦いの最前線でもあることが痛感できるだろう。 そして、読み終えてしまったわたしは、この感動を2度と体験することができない。 わたしは、今からこの小説を読める人が、本当に羨ましくて仕方がない。 ▼ そこに「絶対無理」と思われていた「神聖喜劇の漫画化」の断行である!!! なんという暴挙。 だが、心配御無用。 漫画は、その素晴らしさをあまり損なうことなく、みごとにまとめあげている。 無骨なキャラクターデザインは、到底、今の漫画ではメインとはいえない。 しかし、読みすすめていくと、このチョイスは、最善であったことがわかるだろう。 もっとも良き理解者たちによる、もっともよき漫画化。 まことに、良い人をえた、というしかない。 われわれの眼前に、『神聖喜劇』小説版という、偉大な作品を読む「手がかり」が与えられたのである。▼ むろん、『神聖喜劇』のエッセンスすべてを漫画で再現することは、不可能であるし達成されてもいない。 とりわけ、引用の「横糸」は、再現不可能である。 田能村竹田も、斉藤史も、壊滅状態にちかい。 面白さは、およそ小説版の3割程度といったところか。 とりわけ、全五巻の最後をかざる、敗戦直後の茫然自失さを圧倒的なまでに表現しているといって過言ではない、齋藤彰吾「序曲」が小説版にもたらした雰囲気は、漫画版では再現されていない。 漫画や画像というメディアにも限界がある。 「漫画」では再現できない、「詩」学のみ持ちうる領域は、確かに存在するのであろう。 しかし、それでも圧倒的な面白さであることは、なんら揺るがない。▼ 大西巨人は、社会主義者である。 かつて、中野重治とともに新日本文学会に属し、60年代、日本共産党を除名された、純正な社会主義者である。 そして、今もなお、社会主義の未来を信じてやまない。 鷲田小弥太は、語る。 大西巨人は誰ともちがう社会主義者である、と。 「目的は手段を正当化しない」「個人の幸せこそ、大事」 …… そこから帰結した、途方もない「克己」を要求する、かれの思想の一端は、もちろん、漫画版に収録された原作者インタビューでも読むことができる。 たとえば、かれは憲法9条を守ろうとしている。 むろん、「自らが死ぬことを厭わずして」である。 すさまじい潔癖さから、『神聖喜劇』の奇怪ともいえる書は、生まれているのだ。 いやしくも、「保守」と自己規定する人物ならば、豊穣な日本文芸の香りともども、一読しておくべき作品である、といってよい。▼ 日本は右傾化している、といわれている。 とくに、小林よしのり『ゴーマニズム宣言』などの影響もあって、若者世代の右傾化が激しいという。 中沢啓治『はだしのゲン』だけでは、持ちこたえられないのだろう。 しかし、何も危惧するにはおよばない。 右傾化を懸念する諸君は、小学校~高等学校のあらゆるクラスに、あらたに『神聖喜劇 漫画版』を並べるだけでよい。 「部落差別」から、「責任阻却の論理」まで、あらゆる日本社会の暗部はえぐられる。 そして、ただ真っ直ぐに生きることだけが、束の間の解放をもたらす「光」たりうることが語られるのだ。 これほど素晴らしい教材など、この世のどこに他にあるというのだろう。▼ このブログを読んでいる諸氏は、ぜひ購入してほしい。 そして、いつか必ず訪れる、絶対譲ることができない局面では、 勇気を振り絞って唱和しようではないか。 「○○二等兵も同じであります!」 ≪小説版≫ 全五巻評価: ★★★★★(∞)価格: 各1,100円 (税込)≪漫画版≫ 全六巻評価: ★★★★価格: 各1,470円 (税込) ただし3巻のみ1,365円 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Apr 1, 2007
コメント(1)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 読書
- ミーちゃんと行く 磐座の旅 香川・…
- (2025-11-16 21:53:59)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- やっと入れた楽天ブログ!これからの…
- (2025-11-09 16:30:43)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-







