2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

★ 矢吹晋 『激辛書評で知る 中国の政治・経済の虚実』 日経BP社 (新刊)
▼ 本当に素晴らしい。 面白い、小気味よい、痛快、と3拍子揃った書物が刊行された。 現代中国の専門家、矢吹晋氏(横浜市立大学教授)の書評を一冊にまとめたもの。 愚にも付かない中国モノが書店に氾濫する惨状に、頭を痛めている人たちには、待ちに待った書物といって良い。 クズ本が一刀両断されている。 ▼ なんといっても、冒頭から圧巻!!!! ユン・チアン『マオ 誰も知らなかった毛沢東』は、けちょんけちょん。 「稀代の悪書」扱い。 コミンテルン史観だの、三文小説だの、旧ソ連アーカイブを強調する虚仮威しは笑止千万だの、悪罵が凄まじい。 そりゃあ、中国共産党設立を1920年とすることで、露骨に毛沢東の権威を引きずり下ろそうとしているのが見え見え。 判断を示さず逃げを打った書評をかいた、国分良成(慶応大)・加藤千洋(朝日新聞)・天児慧(早稲田大)などは、研究者失格を宣言していて、痛快である。 「神格化」を否定するあまり「悪魔化」するのは、悲劇の克服にはならない!!は、我々の胸を打たずにはいられまい。▼ ロバート・クーン『中国を変えた男 江沢民』の紹介も素晴らしい。 江沢民がわざわざクーンに書かせた江沢民の伝記。 饅頭本(葬式のとき配られる本)の類であるが、それなりに使い道があるという。 社会主義諸国の崩壊という危機をのりこえるため、台湾海峡をめぐる疑似緊張状態と反日愛国ナショナリズムの煽動と法輪講弾圧による「安定団結」を旗印にかかげた江沢民政権。 その苛烈な「反日」言動の裏には、本来なら「漢奸的人物の息子」という「成分」のはずの江沢民が、不自然に「革命烈士」の人物の養子に「書き換え」られていることにあるのではないか、と推測する。▼ その反面、報告文学「人と妖のあいだ」で共産党を告発した劉雁宝編『天安門よ、世界に語れ』(社会思想社)や、『天安門文書』については、評価がたかい。 当時の中国の政治グループは三派に分かれていたという。 胡耀邦らの「民主的改革派のグループ」は、「陳雲―胡喬木―トウ(登+こざと偏)力群」の保守派グループに虐められたらしい。 趙紫陽は、「専制政治と自由主義経済」を結合させることを主張していたグループであって、胡耀邦ラインではないという。 トウ小平はこの三派のバランスを保ちながら、政治を仕切っていた。 趙紫陽は怜悧な官僚であり、これが彼が「中国のゴルバチョフ」となれなかった一因であるらしい。 一方、話題になった『天安門文書』とは、李鵬と趙紫陽、天安門事件直前、2つの指導部ができており、そのあとで後者が前者に潰された際、趙紫陽側の文書が流出して、それを編纂したものである、という。 かなりの文書が、とっくに『チャイナ・クライシス』(矢吹晋編)でも収録されているぞ!と宣伝する姿は面白い。 ▼ また、『中国農村崩壊』『中国農民調査』や小説などの書評を通して、現代中国の諸問題を摘出する手腕も冴えている。 2006年9月の上海閥討伐によって、党内を掌握できた胡錦涛のかかえる最大の課題は、「農村は貧しい 農民は苦しい 農業は危うい」で知られる「三農問題」。 農村部では、10年で役人が3倍に増えた所もあるという。 幹部たちは、改革開放を換骨奪胎して身内を登用して私腹を肥やして高利貸をやり、徒党を組んでいる。 それだけなら救いがある。 かつての幹部の不正を告発した人物が、横領事件で訴えられたりするだけでなく、なによりも、汚職と戦うことを決断した若手市長が、腐敗幹部たちの資金流用と上級幹部への賄賂によって、自分が市長に抜擢されたパラドクス ―――― 構造汚職となっているのである。 中国の闇は深い。 ▼ 他にも、台湾論から中国経済論まで、実に幅広い。 むろん、筆者は、独自の観点で論じていく。 藍博洲『幌馬車之歌』と侯考賢『非情城市』の関係の検討。 とくに、今では、常識なはずなのに、忘れられがちになっている台湾論がいい。 「台湾独立の可能性は消えた」が「台湾統一の条件は整っていない」ため、大陸と台湾は現状維持しか採れない。 現在の社会主義市場経済の「社会主義」は、枕言葉にしかなっていない。 読むべき本としては、津上俊哉 『中国台頭 日本は何をなすべきか』(日本経済新聞)や、今や都市が農村に恩返しする時代と喝破している白石和良『農業・農村から見る中国現代事情』(家の光協会)があげられている。 また、大西義久氏の著作(『円と人民元』他)に対しても、著者が高い評価をあたえている。 こちらの評価とも一致していて、たいへん喜ばしい。▼ では、どのような本がクズなのか。 そして、読んではいけないのか。 ベンジャミン・ヤン著・加藤千洋訳『トウ小平 政治的伝記』(朝日新聞社)や、宮崎正弘『本当は中国で何がおこっているのか』(文藝春秋)だという。 さらに、誰を信じてはいけないのか。 どうやら、筆者の物言いをみていくと、信じてはいけない学者・ジャーナリストは、宮崎正弘と中嶋嶺男、長谷川慶太郎に加藤千洋たちのようである。 こいつらは、「人民元大暴落」を言い立てていながら、数年もたたないうちに「中国バブル」を言い立て、中国分裂論を鼓吹しておきながらいつの間にかなかったことに。 オオカミ中年とは言いえて妙、というかオオカミ老年まで交じっている。 また、国分良成、天児慧も要注意みたい。 これでは、有名所の中国学者は全滅じゃないか。 いったい誰を信じれば良いんだろう(泣)。▼ とにかく、本書を評するとすれば、大変勉強になりました、の一言ではないだろうか。 事実をもとに論じることの大切さを痛感させられること疑いない。▼ 1956年、第八回党大会までは、集団指導体制がとられ、毛沢東の独裁というものはなかったらしい。 朱鎔基(湖南省長沙)は清華大学左翼学生リーダーでありながら、右派分子として追放。 87年には序列400番台だった男が、91年副首相。 剛直・剛毅・廉直のため、賄賂を送るものがいない。 「100個の棺桶を準備せよ」「連れだって地獄へ行く」と朱鎔基が啖呵をきった下りは、ぜひ確認して欲しいほどの勇ましさだ。 なんと、朱鎔基の祖先の墓には、爆薬が仕掛けられたことがあるらしい。 すさまじい抵抗をなぎ倒す姿は、感動させられてしまう。 また、毛沢東が『楚辞集註』を田中角栄に送ったのは、誠心誠意謝罪しようとしたのに「迷惑」という言葉を使い、こじらせたことに対して、「迷惑」の典故的書物にあたるから送ったのではないのか、という解釈が示される。 田中角栄の誠心誠意の謝罪も、毛沢東の受け入れも、双方にとって都合が悪いので忘れ去られ、万感の意がこめられた「迷惑」は死んだという。 残念な話である。 ▼ むろん、読書系サイトで、書評の本を採りあげるのは、反則のような気がしないではない。 とはいえ、これほどまでに現代中国に対する充実した書評集は珍しい。 まっとうな、現代中国に関する「常識」が凝集しているからである。 常識を知って異端的言説を述べないかぎり、ただのトンデモに堕してしまう。 ただ、激辛なだけに、ときどき、本当かな?という論理運びも見られることもある。 「迷い、惑わす」が原義の「迷惑」が現在の意味に変化したのは、武士の台頭とその決断主義を支える禅宗の流行に由来するとは、ホントのことなのだろうか。 ちょっと出来すぎた話のように思えないでもない。 ▼ とはいえ、これくらい素晴らしい本は、こと中国モノに関しては珍しい。 貴方の中国認識は、どの程度正しいものか。 ぜひ一度、この本でテストしてみてはいかがだろう。 図書館なり、本屋にいって、ぜひとも購入ないし購読していただきたい本である。評価: ★★★★価格: ¥ 1,575 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Jun 27, 2007
コメント(1)
-
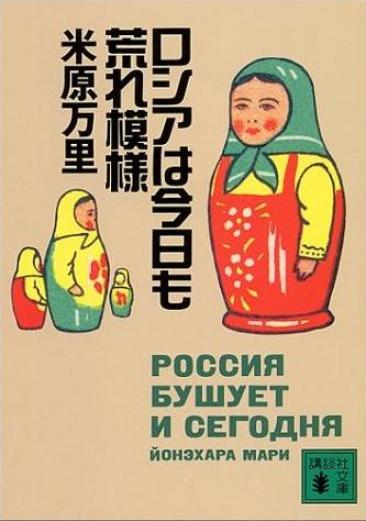
★ 軽やかなロシア社会論 米原万里 『ロシアは今日も荒れ模様』 講談社文庫 2001年
▼ 本日は、2006年5月29日、逝去した、米原万里のロシア・エッセイをご紹介したい。 これ以上、ブログを更新しないと、読者に見捨てられてしまいかねないこともあるのだが、なかなか面白かった。 ▼ 希有のエッセイストにして、ロシア語同時通訳者だった、米原万里。 その文章は、スイスイ軽やかで実に楽しい、はずなのに、題材が「20世紀における最大の実験国家」ソビエト連邦という「悲哀さ」も手伝ってか、何かしら寂寥感や「後味の悪さ」すら感じさせるのである。▼ 冒頭から、ロシアの代名詞、「ウォトカ」についてのお話。 大作曲家ショスタコービッチがロシアの想像を絶する汚いトイレに落ちてしまい、病原菌への感染を怖れてウオッカを体中に塗りたくったら最後、あまりの「熱さ」に一睡もできなかったという。 「温湿布」や「保温」にも、ウォッカは不可欠の存在らしい。 チェルノブイリの事件では、ウォッカこそ放射能の特効薬とされた、という。 零下50度のシベリアでは、窓を拭くのにウォッカを使うとは …… ちなみにウォッカの等級は、純度、精製度で決まるのだとか。 ご存じでしたか?▼ エリツィンの話も、つい最近死んだだけにいたたまれない。 結局、ロシア人を信用できず、一度も選挙の洗礼を受けることなく、アメリカや日本、西側に目が向いていたゴルバチョフ。 金目当てで、統一教会や創価学会会長との会見にも、時間を割いていたらしい。 かれに比べると、エリツィンは、いつも、選挙で信任をもとめたという。 4人に1人はアル中の国だけに、エリツィンは、ロシア人にとって「親父」みたいなもの。 率直すぎる物言い、海部首相やゴルバチョフから受けた仕打ちは忘れない執念深さ、意外とお金に対して清潔(側近や周囲は違う)など、面白い話が多い。▼ ソ連社会については、米原万里にとってオハコ。 ポルノには厳しくても、セックスとアルコールだけは、比較的自由な国家だったらしい。 ゴルバチョフは、節酒令と反アルコールキャンペーンを展開するものの、むしろ「まとめ買い」「原料の砂糖買占」をまねき、靴クリームからアルコールを染み出させることまで行われたのだとか。 貴族階級に担われていたがゆえに、「ひもじさ」という感覚とは無縁のロシア帝国時代の古典文芸。 ソ連社会では、文学・オペラ・バレエ・芝居を始めとするあらゆる領域で、古典が重要視されていたらしい。 社会主義下では、なおさら、文芸は庶民の現実を描くことができない。 かくて、「優雅な美意識」と「現実」との圧倒的「落差」にロシア人は苛まれ続けたという。 卓絶したロシア文化論ではないか。▼ すでに90年頃には、ソ連国家は、末端から機能不全に陥っていたらしい。 「まったく働かない」ように思われるロシア人たちは、ダーチャ(自宅菜園)で週末、クタクタになるまで農作業をする「1億5千万人総兼業農家」状態で、ソ連時代ジャガイモの6割はダーチャで採れていたらしい。 ロシア人の途方もなく「気が長い」一方、しばしば「過激に」なる心性は、ダーチャというバッファーが可能にしている、のだとか。 ロシア人は、義侠心旺盛で、金持ちからふんだくることに良心の呵責を感じないが、貧乏人からはとらない。 日本人がロシア人と商談するときは、「ウサギ小屋」にご招待すれば、成功間違いなし!!!らしい。 とかく、面白い小話に事欠かない。 ▼ 加えて、怪しげな豆知識も面白い。 フィンランドの禁酒法のため、フィンランド人が大挙売春婦とともにレニングラードに押し寄せたため、革命後、法律上の概念として存在しなかった「売春婦」が誕生したのだそうな。 キエフ大公ウラジミールは、キリスト教に改宗するが、それは「妻は4人娶れるけど酒が飲めない」イスラム教より、「妻は1人だけど酒が飲めるキリスト教」を選んだ結果、だという。 ソ連にも、郵便局による新聞宅配制度が存在していたため、郵便当局の思惑が絶大であったらしい。 「北の隣国」ロシア社会を理解したい人にとっては必見の書といえるだろう。 ▼ かつて「世界で社会主義を実現した唯一の国」なる称号をえたこともあった日本は、今や「格差社会」化の中で、沈没寸前である。 ロシア人は、「社会主義」をかかげた実験国家を消滅させ、資本主義の荒波に巻きこまれたことで、「社会主義70年」の間、まったく理解できなかった、≪社会主義の良さ≫を初めて認識できたという。 日本人も、ロシア人同様、「戦後レジーム」を消滅させることで、初めて「戦後レジーム」の良さを認識できることになるのであろうか。 ▼ 時は、まさに参議院選前夜。 悔いのない決断をしたいものである。評価: ★★★☆価格: ¥ 520 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Jun 21, 2007
コメント(0)
-
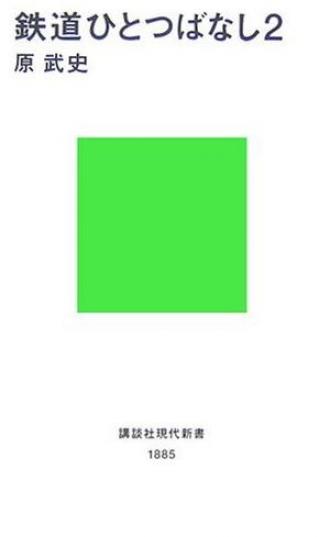
★ 鉄道政治・社会学へのいざない 原武史 『鉄道ひとつばなし 2』 講談社現代新書 (新刊)
▼ 鉄道を通してみえる近代日本。 ただの「鉄っちゃん」のオタク話と思うと、とんでもない大間違い。 前作『鉄道ひとつばなし』の続編だが、続編特有のいい加減さは皆無。 「ひとつばなし」と銘打たれていることから分かるように、講談社『本』に連載されていたコラムをまとめただけ。 まとめただけにすぎないはずなのに、とてもそのようには思えない。 40以上のテーマで、縦横無尽に鉄道を論じていて、とにかく楽しくてたまらないのである。▼ 田舎に新幹線を走らせると、普通、東京に出やすくなると思いがち。 でも実際は、ローカル線の廃止や本数削減によって、かえって不便になってしまう。 東北地方は、東京に出やすくなって東京依存を強める一方、隣県への移動が困難になり、いっそう地方の分断化が進んでいる!!!という戦慄すべき現実をご存じだろうか。 本書では、そんな「常識の罠」を次々と否定していく。 戦時下でも、行楽客であふれた関東私鉄沿線。 地上の専用軌道が環状線運行されている所は、ベルリン以外、大阪と東京しかないという。 地下鉄環状線を含めても、ロンドンに次ぐ古さをもつ、山手線。 高級イメージとは乖離した、東急田園都市線の混雑ぶり。 西武鉄道は、当初学園都市を目指し土地買収こそ積極的だったものの、西武沿線を開発したのは、日本住宅公団や東京都住宅供給公社であって、西武本体ではなかったらしい。 そのため西武駅前は都市計画がないデメリットとして、住宅が密集してバスターミナルもないのだとか。 正力松太郎の夢の欠片、全国唯一の新聞社名の付いた駅名、「よみうりランド」物語も面白い。▼ 近年は、マーガレット酒井順子先生のような、女性の「てっちゃん」が増えているとはいうものの、筆者は、大学生以降、「鉄道オタク」と女の子に思われないように、「隠れキリシタン」のような生き方をしてきたという。 そのためか、故・宮脇俊三先生のあとをついで、自己を妙に客観視する鉄道紀行があるかとおもえば、「あさかぜ」廃止を嘆くくらいなら、鉄道オタクよ、連帯して抗議せんかい!!などと、熱血漢ぶりを示す箇所もあるなど、振幅の激しさがおもしろい。 宮脇先生の衣鉢を継いで書かれた「日本鉄道全線シンポジウム」(なつかしい!)は、スピード化批判が駅名自慢に脱線したりしていて、抱腹絶倒の面白さだった。 「独断・日本の駅100選」ともども、必見の箇所といえよう。 ▼ むろん、原武史は、何もかわっていない。 1876年輸入された御召列車には、鉄道運転制御装置がついていたのに、1891年輸入御召列車には付いていない。 これは「馬車の延長として鉄道を自由に止めることができる」天皇から、「あらかじめ設定されたダイヤに従わざるを得なくなった」天皇への移行があるのだ ……… 。 平成天皇は、グリーン車を利用するなど、開かれた皇室を目指しているため暗殺の危険が増大しているが、「暗殺の対象になる天皇」というものが、昭和で終わってしまったことを示すのだ ……… 。 2003年8月10日に沖縄空港~首里城間に開通したばかりの沖縄都市モノレール「ゆいレール」は、時間や行列にならぶことに無頓着な沖縄市民を教育する役割を担っているのだ ……… 。 地下鉄は、皇居の存在を希薄にしたように、北京・紫禁城の存在を希薄にするだろう ……… 。 女性専用車と在来線グリーン車の時を同じくした復活は、「70年代型民主主義」が破綻したことを示す ……… 。 あいかわらず、原武史節が炸裂していることがお分かりいただけよう。▼ むろん、テーマは日本国内だけにとどまらない。 オレゴン州ポートランド。 そこは、中心部50万/都市圏180万人の人口にすぎないのに、アメリカの都市とは思えぬ70キロもの鉄道路線をかかえ、2~4両の路面電車が、郊外では時速70キロで走っているという。 また、台湾や中国大陸の鉄道事情も収録されているが、イギリス鉄道事情が大変な面白さだ。 ロンドン・ケンブリッジ間は、平均120キロをこえる列車が走るのに、特急・急行・普通といった区別がないらしい。 アリストテレスのいう最高の生活、「観想的生活」をも可能にする、イギリスの緑あふれるホンモノの田園都市の優雅さにはため息がもれてしまうだろう。 私鉄による路線整備が進められたイギリスでは、1948年から1996年しか国鉄は存在せず、汽車を前提として鉄道路線が敷設されたため、橋やトンネルの高さが低く、第三軌条方式でしか電化できない所が多い。 そのため、せっかくのユーロスターも、イギリスではスピードを出せないという。 また、イギリス鉄道は意外と遅れない。 「鉄道は英国の自由主義の実現だ」 ―――― 長谷川如是閑の言葉にはうならされる他はない。 ▼ 本書の白眉は、「失われつつあるもの」「存在しなくなってしまったもの」への哀悼・渇望にあるといえるだろう。 戦前の名残ともいえる客車列車が、国鉄からJRへの移行を契機として消えてしまったこと。 イギリスは鉄道マニア大国だけど、日本とはまったく違うこと。 日本各地の「駅弁」「駅そば」文化を絶滅の危機に追いやる、JR直営店の強引な市場参入に対する告発。 宮脇俊三『時刻表2万キロ』(河出書房)への惜しみない敬意と愛情。 これぐらい郷愁をかき立てられる秀逸な鉄道紀行は、なかなかお目にかかるものではない。 ▼ あいかわらず、理論的にいい加減な部分が散見され、ホンマカイな?というような部分も多い。 たとえば、隣県どおしをつなぐ鉄道や、東京へ向けた鉄道幹線の建設がなかなか進まなかった四国地方では、鉄道とともに全国に普及する「1分単位」で時間を気にする感覚がなかなか定着しなかった、という。 あいかわらず、ラジオやテレビ・学校教育では、1分単位で気にする時間感覚が育てられない、とする説明がどこにもない。 鉄道が走っても時間にルーズな人々はいくらでもいるではないか。 また、PASMOの導入は、「官尊民卑」を打破するのではないか? と言われても、そんなもので無くなる訳がないだろう、とツッコミを入れたくなってしまう。 筆者によれば、鉄道オタクは、助手席に女性を座らせたいというギラギラした所有欲をもつ車オタクとは違い、権力欲とは無縁の「男らしくない」集団だから、鉄道マニアには女装趣味者が現れるのはおかしくはないのだそうだ。 『萌える男』『電波男』の本田透かよ!!!!!お前は!!!(笑)▼ とはいえ、旅行記としても、鉄道うんちく話としても、日本近代史としても、いずれにおいても、水準を満たしていてすばらしい。 鉄道マニアは言うまでもなく、旅行好きな人、日本の近代について考えてみたい人、など、すべての方々にお薦めしておきたい。評価: ★★★★価格: ¥ 777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位 追伸 A 相生のかきめしは美味しいらしい。 一度食べてみたい。↓↓↓↓こちらの本もお薦め↓↓↓↓評価: ★★★★価格: ¥ 777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Jun 13, 2007
コメント(1)
-
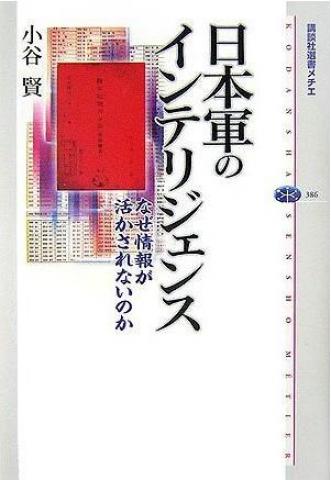
★ 小谷賢 『日本軍のインテリジェンス』 講談社選書メチエ (新刊)
▼ 日本はどうして先の戦争に負けたのか。 この手の類は、本屋に氾濫しているけれど、ここまで充実した本はなかなかお目にかかれない。 現代におけるインテリジェンス活動のあるべき姿にも一石を投じうる、まさしく「史鑑」となりうる著作が上梓されている。 これを機会に、ご紹介しておきたい。 ▼ 本書によれば、日本陸軍は、暗号解読など優れ、中国のみならずアメリカ暗号まで解読していた。 にもかかわらず情報戦に敗北したのは、「作戦重視、情報軽視」「長期的視野の欠如」「セクショナリズム」にみられる、日本軍のインテリジェンス能力の欠如にあるという。 とくに、本来、インテリジェンス活動は、「情報の分析」と「情報の共有」が水平的に連携した形で行われなければならず、「中央情報部(CIA)」のような一元的な情報集約組織によってプールしないと、政策決定者の主観・推測が交じったり、組織間の軋轢で情報の鮮度が失われ、情報が雲散霧消してしまう。 しかし日本では、「作戦」と「情報」が垂直的関係におかれ、インテリジェンス活動がまともに機能しなかったらしい。▼ 第一次大戦によって、インテリジェンス(情報活動)の運用方法は大きく変容したにもかかわらず、日本軍はその変化についていけなかった。 とはいえ、急速に重要度を増したシギント(通信情報)については、相当の解読力を有しており、イギリスやドイツでさえ成しとげられなかった、アメリカの「ストリップ暗号の解読」に成功しているという。 防諜を担当する憲兵隊は、領事館に侵入して、暗号書を始めとする機密文書を盗みまくった。 英米も手を焼き、防諜能力が低い中国側から日本に情報が漏れるので、中国に重要情報を与えない措置さえとられたらしい。 「中ソ重視」の陸軍は、「支那通」などからの情報が多すぎて困るほどだったが、アメリカに対してはまったく逆。 アメリカは、海軍省や外務省の領域と判断、ヒューミント(人的情報)がなかったという。 とはいえ、「仮想敵」国、かつ、鉄壁の防諜能力をもつ対ソ情報収集活動は至難の業にもかかわらず健闘しており、1945年5月には、ソ連の対日参戦の徴候をつかんでいたと言うのだから驚く他はあるまい。▼ 一方、驚愕させられるのは、海軍の防諜・情報能力のお粗末さである。 アメリカ軍の暗号解読はできなかったので、商船運航量と米軍の作戦が連動していることに着目、連合国商船放送から通信量・方位測定によって、作戦地域を割り出していたという。 ヒューミント(人的情報)のため、イギリス人を雇うものの、イギリス側には筒抜け。 しかも、暗号書が盗まれても、自浄能力なし。 その防諜能力はお粗末さの極みで、山本五十六が撃墜死しただけでなく、陸軍がアメリカ・ストリップ暗号を解読していたことさえ、知らされてもらえなかったらしい。 「海軍善玉史観」をすり込まれていた人は、反省すべきであろう。▼ なによりも、「情報分析」に関しての問題点として、作戦重視のため情報分析の専門家が養成されなかったことが挙げられる。 作戦部は、情報部の意見を参考にせず閉め出して作戦立案。 情報部は、作戦部から「要求」が来ないので、どのような情報を提供すればいいのか判断できず、ひたすら情報を集めて渡すのみだから、役に立たない情報しか上にあがってこない。 そのため作戦部は作戦情報を独自に集め出す。 そのため、ますます情報部は作戦に関与できない ……… 以下、無限ループが繰り返されたという。 陸海軍のセクショナリズムは、陸・海軍の情報部同士の提携もゆるさず、情報のプロ(情報部)からみれば「生データ」「偽情報」であるものが、「極秘情報」として上層部に出回ることさえあったという。 ▼ むろん、日中戦争から太平洋戦争初期かけては、戦術レベルでの効果的な情報収集と運用、英米の日本への過小評価もあって、大成功をおさめている。 英米は、しばしば不明瞭な部分を人種的偏見で歪曲して補うことで、空想的優越感に浸っていたからだ。 しかし、敗北の教訓から、頻繁に情報をアップデートして主観を排して迅速に戦場で使用した英米に対して、勝利に浮かれた日本は、陸軍の精神論、海軍の都合の良い楽観主義によって敗北を喫したのだという。 ▼ しかし、それとても、戦略的情報利用の欠如に比べれば、どうでも良くなるほどの些細な過ちにすぎない。 なんと、安倍首相の親戚、松岡洋右外相や陸軍首脳部が推し進めた三国同盟の政策決定の場には、参謀本部の情報部長がいなかったと言うではないか!!!!! 「ドイツの勝利はない」といった駐英武官報告が、握りつぶされていただけではない。 なんと、驚く無かれ。 「独ソ戦が勃発する!」という駐独武官情報は、日本暗号の解読を通してチャーチルがその事実を知って、英米ソの結束に利用したにもかかわらず、日本では「情報を信じない首脳」だらけだったというのだ。 日本では、どんなに決定的な情報を得たとしても、調整によって政策決定をくだす時に間に合わないと、有効活用できないのである。 日本は、独ソ参戦を知らされつつ、南進論を決定したのだ。 また、太平洋戦争開戦直前の対米交渉でも、「情報の政治化」を防ぐための客観的情報評価部署がないため、政権首脳部はオシント(公開情報)で右往左往した挙句、ハル・ノートで観念。 ここまでくると、日本政治は自殺したのだと考える他はない。 ▼ とにかく、『「情報局の世界」の教科書』という趣があるのが嬉しい。 ヒューミント(人的情報)は、シギントの及ばない領域をカバーとかは、素人にはたいへんありがたい指摘であろう。 第一次大戦という総力戦を戦わなかった日本陸軍は、シンガポール攻略までしか計画しておらず、軍事作戦情報しか入手しようとせず、短期的な情報運用しかしなかった。 また政治サイドも情報に基づいて政策決定を行わなかった。 現代日本のインテリジェンス活動にもつながる問題点として、 A 組織化されないインテリジェンス 各自てんでバラバラ B 情報部の地位の低さ C 防諜の不徹底 D 目先の情報運用 E 情報集約機関の不在とセクショナリズム F 長期的視野の欠如による情報要求の不在 (情報を必要とする政治の創設がないと宝の持ち腐れ)を訴えて本書は締めくくられる。▼ なによりも、ソ連との諜報合戦は、スパイ小説さながらの、手に汗を握る凄まじさであるのが楽しい。 スパイは、潜入後、1週間でつかまるソ連KGBの凄さには驚くほかはないだろう。 ポーランドとの盛んな情報交流をおこなうもままならない。 ソ連のスパイを泳がした挙句、密かに逮捕して、逆スパイにしてソ連に送り返しても、NKVD(KGBの前身)にとっつかまってしまう。 関東軍の情報が筒抜けになってしまうことを知るくだりは、たいへん面白い。 また、雑学もかなり面白い。 インテリジェンスを重視していたイギリスは、大学出のインテリに協力をもとめたのに対して、日本は大学生を最前線に送り込んだ。 精神論が大好きな日本陸軍は、敵軍分析も、使う人間が弱いなら弱兵である式精神論で、敵より優位に立てると分析していたりしてなかなか楽しめる。 ▼ ただ、この本を読んで、日本のインテリジェンス活動の弱さが分かった所で、何の対策も打てそうにないのが気にかかる。 本書によれば、情報の水平共有、一元的評価機関の重要性など、「情報を政策に生かす」ことがさかんに唱えられるが、さりとて実践に移すとなるとどうすればいいのか、定かではない。 形式だけなら、AからFまでのことは、明日にでもただち実践に移せるだろう。 いや、実践に移されている内容も多い。 しかし内実はどうなのか? イギリスと日本の違いを、制度の差異に還元するのはたやすいが、制度の実際の運用方法を把握するのは、困難を極める。 戦前のイギリスの情報活動は、実際、どのように運用されていたのか。 本書を読んでもブラックボックスのままなのは、そのせいだろう。 制度を運用するのは、人間であることを忘れているのではないか、と思わないでもない。▼ たまたま、本日の朝刊では、本来、自衛隊の防諜のためのインテリジェンス機関である情報保全隊が、「市民への監視活動」をおこなっていたことが、大々的に伝えられた。 既報によると、イラク派兵反対者を「新左翼系」「共産党系」「民主系」とラベルを貼って諜報活動をおこなっていたという。 何のことはない。 このことは、自衛隊が「自民党系」、いいかえれば「自衛隊は、「自民党の党軍」 ――― あたかも、『中国人民解放軍』が中国共産党の軍隊であるがごとき ――― であることを満天下のうちに知らしめたといえるだろう。 「自衛隊とは自民党の軍隊」であって、日本の軍隊ではないのである。 この厳粛な事実から目をそむけて、だれが「自民党の諜報機関」によるインテリジェンス活動を支持すると言うのか。 インテリジェンス活動は誰のためか。 「国民」「国家」のためとは、「自民党のため」という事実から目をそむけるためのデコイにすぎないのではないか。 その疑問は、本書を最後まで読んでもぬぐうことはできない。▼ とはいえ水準以上のできである。 一読をお薦めしておきたい評価: ★★★★価格: ¥ 1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
Jun 7, 2007
コメント(7)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 読書
- ミーちゃんと行く 磐座の旅 香川・…
- (2025-11-16 21:53:59)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 「困った人たち」とのつきあい方/ロ…
- (2025-11-16 04:53:29)
-







