2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年05月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
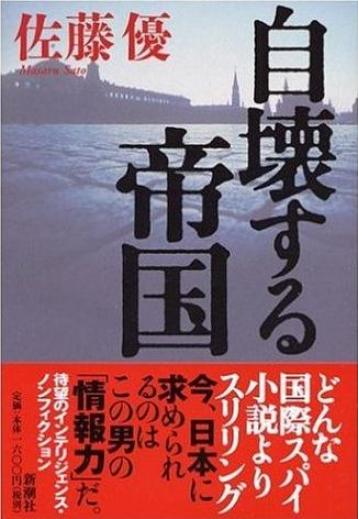
★ 「小谷野敦 VS 佐藤優」 紛争のくだらなさ 佐藤優 『自壊する帝国』 新潮社、2006年5月
▼ 「佐藤優という『罠』」『アエラ』4月23日号を契機にして、佐藤優と小谷野敦は、論争というか、論争にもなってないというか、空中戦・盤外戦を演じているのはご承知のことであろう。 ところが、この紛争、はやくも小谷野敦の劣勢。 山崎行太郎ブログで皮肉られているが、むべなるかな。 ▼ 遊女の平均年齢をめぐる論争といい、macskaとの論争といい、小谷野敦のネットでの論争姿勢は、人を不快にさせるものが多いが、『アエラ』というパブリッシュ・ペーパーでやった以上、言い訳がきかない。 この人の仕掛けた論争で、はたして、まともなものがあったのか。 こんなやり口では、門外漢の人間に、不信を感じさせるだけだろうに。▼ 「猫を償うに猫をもってせよ」で、佐藤優批判の予告めいたものがあった。 佐藤優を全面否定しているような雰囲気だった。 そうなると、否が応でも『アエラ』を期待するだろう。 ところが、あけてびっくり玉手箱。 佐藤優は「言論キムイルソン」「みのもんた」といった、悪口のみ。 肝心の佐藤優批判は、天皇を重要視して『神皇正統記』を称揚するけど現在の天皇は北朝系じゃないか、9条改憲すれば天皇がなくなり、天皇がなくなればファシズムになるなんて論理はおかしい、というもの。▼ なんだかねえ。 「つまらん」としか言いようがないだろう、これでは。▼ 佐藤優なんて、ソ連崩壊ものを立読したことがある程度だが、「戦争放棄」ならぬ「天皇放棄」を唱えるおいらでも、小谷野敦の批判はまるで体をなしていない、と感じざるをえない。 今の天皇至上主義者たちは、今上天皇が北朝の子孫であることなど、「都合が悪いから無視している」なんてレベルではなく、心底、「どうだって良いから無視している」「なんでそんなことが問題になるのか分からないから無視している」に決まってるじゃないか。 ▼ だいたい、『神皇正統記』が「南朝」のみのイデオロギーを指していたのは、南北朝時代だけだろう。 南北朝の時代が終われば、南朝正統を立証する以外にも、転用可能性が開かれる。 そもそも、後醍醐天皇に対する批判的見解ものっている『神皇正統記』は、「南朝イデオロギー」とすら言いがたく、純粋な「北畠親房イデオロギー」なんじゃないの? 『神皇正統記』は、「南朝の正統論のはずで、だとするといまの皇室は北朝の系統で、それについてはどう思っているのか」と聞かれても、誰だって「はあ?そんな勝手な理屈、誰が決めたのですか」としか言いようがない。 実際、佐藤の回答も、木に鼻をくくったようなシロモノだった。 ▼ まあ、天皇制を廃止するとファシズムになる、という佐藤に対して、『そもそもファシズムの原点であるイタリア・ファシズムは王制の下で生じているし、では米国、第三共和制以後のフランス、第二次大戦後のドイツ、イタリア等、共和制の国でどの程度ファシズムが生じたのか、実例をもって論じてもらいたい』と言いたい気持ちは分からないではない。 しかし、肝心の小谷野敦は、 「未来を予測するなら、過去の歴史を根拠にしなければならないはずだ」と、「飛躍」「論証なしに議論」していることに気づいていないのだから、まったく始末におえない。 ▼ それ以上に致命的なのは、小谷野敦の評論家としての「地頭の悪さ」、が露呈してしまった点かもしれない。 ▼ しばしば小谷野は、天皇制を批判する自分こそ左翼、みたいなことを嘲弄まじりに左翼に向け語っているが、真の左翼なら「共和制でファシズムになる、という以上、今の日本がファシズム状況下でないとでもほざく気か!!佐藤優!」くらい言わなくてどうするんだ。 小谷野は左翼を舐めすぎである。▼ だいたい、未来予測に厳密な根拠(それも歴史)を要求するのは、「共和制はファシズムにならない」と反証できないからにすぎまい。 だからこそ、相手に根拠を求めるのだろうが、政治の未来予測に対して、歴史を根拠に議論せよなんて、どう考えても辻褄があっていないだろう。 歴史は繰りかえすから、などと非科学的なことを言うつもりではあるまい。 もっと他に反論方法はなかったのか、と愚痴りたくなる。▼ そもそも小谷野敦は、「共和制は、ファシズムの苦難をくぐり抜けても、実践されなければならない」と、何故、啖呵を切れなかったのか。 どうして、「共和制は、ファシズムになるかならないかに関わらず、たとえファシズムの可能性があろうとも、断じて実現すべき価値を有するものである」ことを力説できなかったのか。 ほんとうに共和主義者ならば、極論すれば、「ファシズムの試練を潜らなければならないからこそ、共和制は素晴らしい」と、言っても良かったはずである。 「たとえファシズムになったとしても、共和制は、ファシズムの危険性なんて問題にならないほど、固有の価値がある」といえない小谷野に、共和主義者を名のる資格があるとは、到底、おもえないのだが。 ▼ 「素朴な実証主義者」と山崎行太郎が「好意的」に書いているが、要は「実証」に逃避しているのである。 批評家としては、致命的なまでにつまんない。 そんなことでは、マルクスどころか、とっくに「過去の作家」になりさがっていた、高橋和己の読み直しまで連載してしまう佐藤優に、勝てるはずがないではないか。 ▼ 佐藤の「圧力」もあって、小谷野は『文学界』の連載を降板させられてしまったらしいが(幸運なことに、と言うべきか、私は読んだことがない)、なんともむべなるかな、といった所である。▼ なお、表題の佐藤優『自壊する帝国』新潮社は、なかなか面白い著作。 足で稼いだ人間にしか理解できない皮膚感覚で論じているので、客観性にはいささか難があるものの、崩壊直前のソ連社会の様子が、くわしく描き出されていてとても面白い。 とくに、ブレジネフ政権下のソ連社会の分析は白眉に近い。 一応、一読をお薦めしておきたい。 評価: ★★★☆価格: ¥ 1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
May 31, 2007
コメント(7)
-

★ 安倍晋三に殺された松岡利勝の冥福を祈る / ほりのぶゆき 『江戸むらさき特急』 全3巻 小学館
写真右:松岡利勝 ▼ 松岡利勝農水相の自殺の一報を聞いたとき、一瞬、安倍晋三がお涙頂戴のためにヒットマンを放って殺害したのかもしれないな、と思ったが、似たようなことを考える人はいるらしい。 山崎広太郎ブログでも、案の定、書かれていた。 やるなあ。 ▼ ほりのぶゆきの傑作4コマ漫画、『江戸むらさき特急』の中で、切腹する武士に対して、介錯人が峰打ちをおこない、「峰打ちじゃ、安心せい」とのたまうシーンがあった。 さしずめ今回の安倍晋三首相は、まさにこの介錯人にあたるだろう。 松岡利勝のような、裸一貫からのしあがった汚職政治家は、割と好みなだけに、かえって腹が立つ。 ▼ 切腹ならぬ、不明朗な企業との癒着を問いただされて、もだえ苦しむ松岡利勝。 「党の方針だから突っぱねなさい」「守り抜くから」と要請され、「大臣職を続けさせる。安心せい」と国会答弁しつづけた安倍晋三。 漫画なら笑いですまされるが、現実には冷血このうえない、羞恥プレイ。 動揺する熊本の支援者たちの声は、かれの耳元に届いていたにちがいない。 最後に緑資源の官製談合事件において、1億3000万円の政治資金をもらっていたことが判明して、絶命してしまった。 ▼ 内閣が持たないから松岡利勝を擁護して、内閣改造でやめてもらう腹。 政権維持を最優先して相手の都合は考えない、という安倍スタイルは、参議院選挙比例区で、サッカー選手三浦知良を擁立しようとした姿にもかいま見える。 苦悶の表情を浮かべながら答弁する松岡。 辞職させて引導を渡してやればいいのに。 ひどいことをするなあ。 何度思わされたことだろう。 ▼ 所詮、小泉~安倍政権下で激増し続けた自殺者(3万人突破、おめでとう!)が、とうとうお膝元の大臣にまで現れたというだけのことかもしれない。 自業自得というべきか。 しかし、マスメディア、とくにテレビと政権との癒着ぶりには、呆れはてた。 なんだよ、「お悔やみ申し上げます」って。▼ ここは、政府自民党がイラク人質事件で傲然とのべたように、「自己責任」以外のどんな言葉を彼と遺族にかけてあげる必要があると言うのかね。 イラクで人質になった無辜の人に言えて、松岡利勝・農水相に言えないとは、どういうことか。 ダブスタの極み。 ▼ ほりのぶゆきの漫画は、『江戸むらさき特急』の最初の2冊が大傑作である。 江戸の時代劇を舞台とした爆笑4コマ漫画なので、ぜひ一読することをおすすめしたい。 ちなみに、絶版状態なので、ブックオフの「ワイド版 100円コーナー」で探すしかない。 ただ、かれの他の漫画は、あまり大したものがない。 かれは山のように4コマ漫画を書いているものの、「荒川道場」を始めとして、あまりにもマンネリ化してしまった。▼ ギャグマンガ家の寿命とは、政治家同様に儚いもの、なのであろうか。 評価: ★★★★価格: 古本屋の時価で ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
May 29, 2007
コメント(1)
-

★ タカ派は「バカ派」 田岡俊次 『北朝鮮・中国はどれほど恐いか』 朝日新書 (新刊)
▼ 平和憲法下の日本では、「紋切り型」の議論が横行しがちだ。 日本では、軍事が忌避されてきたため、軍事・情報とかの国家戦略上重要な問題が蔑ろにされてきた!!!軍事教育を!!などというのも、逆の意味で、「紋切り型」の議論に他なるまい。 言い出すのはたいてい、視野の狭い「軍事オタ」ばかり。 たしかに、おまえたち軍事オタを教育するためにも、軍事学を大学で教えた方がいいかもしれないな、と言いたくなってしまうことが多い。▼ そこで、本書の御登場である。 いやはや素晴らしい。 軍事評論家といえば、兵器オタの水玉蛍之丞の兄(岡部イサク)か、アメリカのポチの志方俊之だけと思ったら大間違い。 日本の悲劇は、田岡俊次以外、ろくな軍事評論家がいやしねえことにあるのではないか、と思わせる迫力に満ちあふれた本である。 本書は一言で要約できよう。 今のタカ派は、「タカ派というよりもバカ派」(by 防衛庁幹部&田岡) バカ派たちの言説をメッタギリしてくれているのだ。▼ バカ派とは、以下のことを口走る人たちのことをいう。 心してチェックしてもらいたい。A 北朝鮮の実戦ミサイルが来る前に先制攻撃せよ ←技術的に不可能B 日本も核武装だ! ←NPT脱退してアメリカを敵に回すの?C 米軍の臨検から戦争に突入する!! ←臨検は相手の同意がいるD 台湾独立で中国軍が侵攻 ←台湾の85%は現状維持E ノドンを日本に打てば自殺行為 ←米基地を叩くついでの日本攻撃の可能性はあるF 北朝鮮の核技術は大したことはない ←威力制御技術をもちノドン搭載可能G ミサイル防衛で対応せよ ←ミサイル防衛は穴だらけで「気休め」程度H 中国は20年以上大軍拡!! ←名目と実質の区別が付かないバカI 中国の軍事費は、公表額の2~3倍だ! ←財政の8割が軍事費というのか?J アメリカの戦争に巻き込まれるなんてサヨクの常套句! ←冷戦時、日中の役割は、ソ連軍の西欧正面から引きはがしK 中国は台湾に特殊部隊を送って、台湾中枢を制圧して全土制圧! ←まともな上陸作戦を立てられない証拠。北朝鮮にやってみろ。L 中国の弾道ミサイルの標的は日本だ! ←標的はその都度ターゲットを入力する上、 ミサイルは垂直上昇するので方向判別は不可能M 中国の「衛星破壊」事件をみよ! ←アメリカが40年前にやって無意味と知った行為の再現O 米中は敵対的関係だ! ←米は、「3つのコミュニケ」重視で、台湾防衛に消極的▼ 中国も韓国も、リアル・ポリティクスの観点から、「北」の崩壊を望んでいない。 北朝鮮には、もはや飛行可能な空軍パイロットがおらず、北進統一を妨げるものが存在しないが、さりとて地下要塞に籠もって、ソウルにむけてロケット弾攻撃をやられれば、100万人の死者が出てしまう。 だからこそ、米軍は外科手術を諦めたらしい。 94年の米朝合意は、とおからず北朝鮮が崩壊するという甘い見通しでおこなわれた。 アメリカが北朝鮮核実験失敗説を吹聴しているのは、北朝鮮核実験よりも日本の核武装の方を警戒しているためらしい。 東京に落ちれば、100万人が死ぬ。 しかし200発のノドンに、何十発の核弾頭をつんで、ダミーもろとも発射されれば、米軍でも湾岸戦争で「スカッド」ハントに失敗したように、ミサイル迎撃は不可能。 核抑止は、「相手が理性的」であることを前提だし、核武装をアメリカは許さない。 「核シェルター」で被害を軽減するか、気休めのミサイル防衛を整備しつつ、「アメリカの核の傘」を言い立てるしか方法はないらしい。▼ 中国脅威論は、ソ連の代わりに敵を作ろうとするだけ、と手厳しい。 「中国の軍拡説」は、ソ連に対して「ギャップ」を強調して予算獲得した、ペンダゴンの常套手段である、「過大見積」にすぎない、という。 近年の上昇は、人件費と装備費の肥大化。 1998年、朱首相は、人民解放軍の副業(退役軍人・家族・兵士たちが2万もの会社を経営していた)にいらだち、給料2倍にするから厳禁を打ち出したらしい。 とはいえ、史上最強の装備を持っていた「民兵」ベトナム軍に中越戦争で敗れた人民解放軍。 、そこは「世界最大の航空博物館」。 50年以上前に初飛行した航空機が、全体の8割を占め、中国側航空機は「見えない距離」から撃墜されてしまう。 ▼ 人民解放軍は「近代化」を進めているものの、装備費はどんどん増えているが、近年の兵器の値段は、べらぼうに高い。 ほとんど買い換え需要という。 保有航空機、保有潜水艦、軍隊の数は、軍の近代化とともに、量を維持することに耐えられないので、急減せざるをえない。 アメリカに対抗するには効果的な潜水艦は減る一方、見栄えがする水上艦のみ増加しているが、これはこれで、各国の技術の寄せ集めにすぎない。 「早期警戒機なき空母」は、所詮、ステータスシンボル。 原潜も動く騒音で、航法水準もミサイル技術も低い。 近年の中国の武器輸入量は、90年代の台湾の武器輸入量に遠くおよばない。 第二次大戦時の飛行機を計算にくみこんだ、『ミリタリーバランス』の数字を信じて、中国軍拡を真顔で論じる、アホな軍事評論家とはいったい誰のことか、知りたくて仕方がない。 ▼ また、中・台衝突をめぐる論議は、必読の箇所といえるだろう。 パワーバランスは、海軍でも、空軍でも、台湾有利であるという。 台湾独立阻止のためには戦争を辞さないといっても、台湾上陸作戦には「ノルマンディー上陸作戦」の3倍の規模が必要となれば、根本的に不可能である。 中国は、「無制限潜水艦戦」以外採りようがなく、世界中から恨まれて、貿易に依存する経済が持たない。 戦争になれば、世界市場を失い、投資は止まり、在米資産は凍結、原油輸入は不可能である。 中国の「反国家分裂法」も現状維持法。 アメリカが公然と現状維持に努めるのも、日中米とも、台湾に独立宣言されて、中・台「2者択一」を迫られたら、かなわない。 台湾軍人も独立反対派が多数、台湾の中国経済依存、を合わせれば、「独立」はない。 さらに、近年は日米関係よりも中米関係の方がよほど親密であるという。 ▼ 個人的には、朝日新聞のリベラルな社風が印象的であった。 1963年頃は、朝日の方が穏健で、他紙は扇情的な左だったことは、左側の川崎泰資・柴田鉄治『NHKと朝日新聞』(岩波書店)の証言(ナベツネ的人物に乗っ取られそうだった朝日)と符合していて、ほぼ事実といってよい。 中央公論『社説対決 読売VS朝日』などは、針小棒大のプロパガンダ、とみなければなるまい。 当時の朝日幹部がみんな海軍士官経験者だったこと。 「非武装中立」なんて与太話を語る社員など、周りに聴いてもいた記憶がないこと。 まあ、4年に1度の国防総省の「国防政策見直し報告(QDR)」において、全体の1%を針小棒大にとりあげ、「軍拡中国に対抗」とした読売・毎日の記事について、防衛庁担当者の「朝日は全文読んで記事を書くけど、他紙は機をみて森を見ず」をわざわざ書いたのは、「報道される側に取りこまれることに批判的じゃなかったのかよ!!!と、さすがに苦笑させられてしまったが。 ▼ 的確な中国認識も冴えわたり、うならされる他はない。 共産党の「商工会議所化」という見立ては、ともかくとしても、中国財政規模の対GNP比率が先進国と比較してかなり低い(地方併せて2割以下)ことは、中国ウオッチャーの常識であるが、氾濫する中国本で触れられることはほとんどない。 経済発展を輸出入に頼れば頼るほど、中国はアメリカと協調的にならざるをえない。 旅順港使用権をえたため、ソ連大使が蒋介石に最後まで随行したこと。 米中接近で、中越対立が激化したこと。 靖国神社参拝への不快感から、米中が親密になりつつあること。 現代中国は、工学部出身者のテクノクラートに支配される官僚国家の伝統のみならず、押しかけ民主主義「民変」まで復活しつつある、という。 また、尖閣諸島とガス田開発は別の問題であって、尖閣諸島では日本有利でも、ガス田開発では中国有利であるらしい。 なにより、ポル・ポト派の大虐殺集団が参加する政権(民主カンボジア)を、日本は米中と一緒になって承認していたことには呆れはてる他はない。▼ ともかく、右翼メディアで憲法論議が盛んなのは、憲法を論議するだけなら法知識程度で済み、膨大な予備知識が必要な軍事から逃避できるからだ、という一節ぐらい、バカ派たちへの根本的な批判、肺腑をつらぬく一撃となっている批判はない。 集団自衛権論議も、台湾海峡防衛に適用すれば、中国への「内政干渉」であって、サンフランシスコ講和条約違反で「侵略」にほかならない。 島嶼防衛論も、全力で台湾独立阻止をしなければならない中国が、日本領土を攻撃して「日米安保条約」発動条件をつくることを前提とした議論であって、とても参謀能力のある連中が作ったシナリオとは思えない。 朝日新聞も、つまらない護憲社説を何本も書くよりも、「現実をみすえろ!!、改憲論議に逃避するな!」と主張した方がはるかに良いと思われる。 ▼ 喚くだけの左派より、法をもてあそぶ観念タカ派は、権力に近いだけに危険。 ほとんど、目からウロコのような体験がえられるだろう。 ぜひ、1度詳しく目を通しておくべき、必須の新書とおもわれる。評価: ★★★★☆価格: ¥ 777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
May 27, 2007
コメント(2)
-
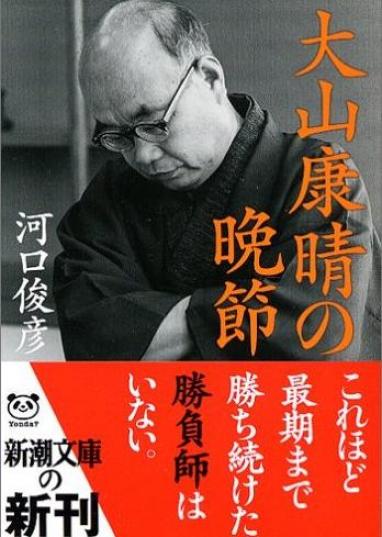
★ 河口俊彦 『大山康晴の晩節』 新潮文庫 / 大崎善生 『聖(さとし)の青春』 講談社文庫
▼ 名人戦移転騒動のあとも、まだまだ余震が収まりそうもない、日本将棋連盟。 米長邦雄会長直々に、女流棋士に経費節減のため独立を薦めておきながら、「独立準備委員会」が資金を募りだすと、手のひらを返して独立派に「切り崩し工作」。 いわゆる、「女流棋士独立騒動」まで勃発させてしまった。 将棋連盟は、5月27日、理事選が行われる。 どうやら、米長再選確実の気配。 参ったね、どうも。 瀬川編入問題といい、米長会長では、こちらの身が持たん。 勘弁してほしい。▼ たまたま、ブックオフを回る機会を利用して、将棋を題材にとりあげたノンフィクション小説を、何冊がまとめて仕入れた。 皆様にもご紹介しておきたい。▼ 河口俊彦『大山康晴の晩節』(新潮文庫 2006年3月)は、不世出の大棋士、大山康晴の奇跡と軌跡を描いた、すばらしいノンフィクションである。 河口師は、プロ棋士(ただし、プロ予備軍である奨励会最多在籍年数という不名誉の記録をもつ)でありながら、華麗な文章をもち、将棋ペンクラブの会長を務めていた。 漫画『月下の棋士』の解説をはじめとして、どこでも拝むことができるが、この本はとりわけすばらしい。▼ 大山康晴といえば、タイトルがまだ3~5つの時代、全冠制覇を続け、名人戦13連覇、タイトル獲得80回、棋戦優勝44回の記録を持つ大棋士である。 タイトルが7つに増えた時代に、7冠王になった羽生善晴ですら、タイトル獲得数は、まだ60台にすぎない。 ただ大山は、なんといっても、ヒーロー升田幸三の敵役であった。 次世代の星、二上達也、加藤一二三などに、盤外戦を徹底的に仕掛け、潰しに潰したため、全盛期、畏敬されこそすれ、人気がまったくなかった。 ▼ 「盤外戦で後輩を潰した大山」という見解は、本書でも踏襲されている。 とはいえ、さすがは、棋士の端くれ。 「盤外戦史観」は、適当な所でやめてしまう。 手どころにおける丁寧な解説を通じて、戦前から戦後すぐにかけて、兄弟子の升田幸三より、大山の方が強くなっていたこと。 宿敵・山田道美は、理論派というよりも終盤の粘りが素晴らしかったこと。 丸田や谷川17世名人が悲運の棋士なのは、素晴らしい一手が、タイトルにまったく結びつかず、知られることなく埋もれてしまうことにある …… 河口師は、どこまでも盤上の真実を追い求め、筆致はどこまでも暖かい。▼ 大山の真の偉大さは、第三期黄金時代ともいうべき、名人位失陥後にある、という部分こそ、本書を他と隔絶した本にさせている見解であろう。 53歳で将棋連盟会長の座についた大山。 歴代一〇指にかぞえられる天才、米長や中原たちも、50歳をこえると、「A級棋士」(トップ10)の地位から陥落せざるをえない。 その一方、大山は、関西将棋会館建設の寄付金を集めるため馬車馬の様に働きながら、60歳になっても、落ちる気配を見せなかった。 挙句、60代前半で、名人戦挑戦者。 60代後半における、A級順位戦残留のための死闘。 羽生との戦い。 2度にわたるガンとの闘病。 A級棋士のまま、逝去。 享年69。 ▼ なによりも、大山将棋の本質は、徹底的な棋士への軽蔑と説くのがすばらしい。 それは、赤紙で徴兵される直前の悲しいできごとにあったという。 「好かれていない自分」を自覚させられる事件。 これを機に、大山は「史上最強」の道をあゆみはじめる。 長考派の棋士で有名な加藤一二三だが、若い頃は大山も長考派。 序盤から長考に長考を重ね、駒組みが終わって開戦するのは残り15分、という将棋は、ザラだったというから面白い。 それでも、決して間違えない将棋ぶりに「精密機械」と呼ばれていたらしい。 年をとると、終盤を間違えるようになってしまう。 そのため大山は、手どころに時間をかける必要を感じて「長考派」をやめてしまう。 年をとっても「長考派」の加藤一二三。 ここに、2人の分岐が生じたという。 加藤一二三は、60過ぎてもA級、という事実から判断すれば、「神武以来の天才」は本当だった、という指摘は、ファンとしてはたまらなくうれしい。▼ 中原16世名人の「林葉直子突撃事件」を初めとして、浮ついていて、組織の体をなしていないようにみえる、日本将棋界。 失って初めて気づく「大山康晴」の存在の大きさ。 ブログをごらんの皆様にも、ぜひご一読してほしい。 評価: ★★★★価格: ¥ 580 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位 ▼ 次にお勧めしたいのは、いっとき、ずいぶん流行っていた、大崎善生『聖の青春』(講談社文庫、2002年)である。 今回、とうとう、手を出してしまった。 独特の文章から薫りたつ、勝負師の生き様は清冽ですばらしい。▼ 本書の主人公は、村山聖。 順位戦では、A級棋士。 幼稚園のときから、腎臓が機能を果たさず、免疫も弱く、すぐ疲れがたまり、細胞が水ぶくれして膨らむ、ネフローゼという病魔に冒されていた。 病院では本を読む生活。 そこで聖は、将棋と運命的な出会いをする。▼ 長く生きられない体をかばいながら、死をつねに間近に感じて生きてきた村山聖。 勝負の世界に入った村山は、「東の羽生、西の村山」とまで並び称されるほどの実力を蓄えていく。 ついには、「終盤は村山に聞け」といわれるほどの青年棋士へと成長。 師匠である森信雄六段を初めとして、さまざまな人に支えられる様子は、感動的というほかはない。 しばしば、見も知らぬ人に、道端に倒れている所を車で拾われ、対局場に連れて行ってもらったこともあったほどである。 病院に運ばれることは日常茶飯事。 何度となく対局を休まなければならない羽目になりながら、それでも聖は、一歩ずつ頂点へのぼっていく。 棋界最高位である「名人位」を目指して。▼ しかし、果たせない。 谷川、なによりも、羽生が村山の前に立ちふさがる。 そして発病。 病名は膀胱がん。 A級棋士のまま逝去。 享年29。▼ なによりも感動させられるシーンは、プロ棋士になることをやめさせるため開かれた親族会議で、まだ中学生の聖が「谷川を倒すには今行くしか無いんじゃ!」と叫ぶ箇所ではないか。 この叫びで、親族会議の空気は一変。 村山は奨励会に入ることが許される。 しかし棋界は、ヤクザのような世界。 師匠選びで躓いてしまう……犯人は灘蓮照。 どんな悪い奴だったのかは、本書を読んで確認してほしい。 ▼ おもえば、谷川名人の誕生は、今も鮮烈に覚えている。 なによりも、加藤一二三ファンの私は、谷川名人誕生とともに、将棋をやめてしまった。 だって、馬鹿馬鹿しいでしょ。 20歳で頂点を極めることが可能な、そんなバカな世界が、あっていいはずがない。 そう思うと、将棋がとてもツマンナイ世界に思えた。 その一方、「谷川を倒すこと」に命をかけて決意した男たちが、たしかにいたのである。 今の羽生世代。 その息吹だけで、懐かしくてたまらない。 ▼ ちょっぴり残念なのは、村山の負の部分ともいえる、母であるトミコへの甘え、女性への異常さ、みたいな部分が、すべて「純粋」「真っ直ぐ」という表現に回収されてしまっている点かもしれない。 「優しさ」ばかりではない、一途ゆえの「残酷さ」「異常さ」「気持ち悪さ」といった負の部分は、甘ったるいオブラートでくるむ必要などなかった。 もっとストレートに書いても、批判しても、よかったのではないか。 また河口氏とはちがい、将棋を嗜むものの、プロのレベルではないため、村山の棋譜を語れていない。 結果、お涙頂戴ノンフィクションになってしまったのが惜しまれる。▼ とはいえ、「泣ける本を読みたい!!!」という方には、一読をお勧めしておきたい本である。 たいていのブックオフには転がっているので、ぜひ一度書架を確認してもらいたい。評価: ★★★☆価格: ¥ 680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
May 16, 2007
コメント(2)
-
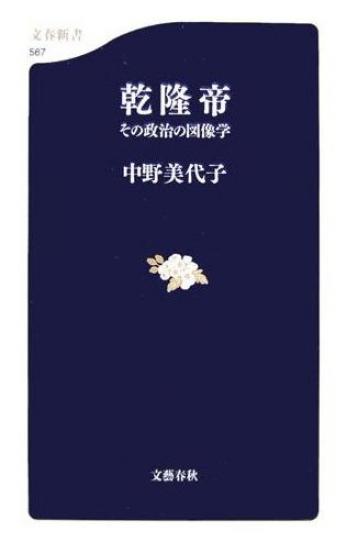
★ 絶版にしろ!! 中野 美代子 『乾隆帝』 文春新書 (最新刊) の絶版を勧告する!
▼ 文春新書の歴史関連書といえば、「ゴミ新書」の代名詞にほかならない。 「君子危うきに近寄らず」。 座右の銘にしていた小生であるが、「図像学」の題名に釣られてしまい、とうとう「外れ籤」を引いてしまった。 空前絶後。 驚天動地。 本書は、「受け売り」と「誇大妄想」「幻想」、ならびに「間違い」のみで構成された、ほとんど何のために出されたのか首をひねるばかりの、凄まじい新書である。 あまりの酷さ。 くわえて、こんな本に金を投じてしまった悔しさのあまり、本来、紹介する順番を無視して、飛び級であえて本書をこのブログで採りあげさせていただく。 怖い物みたさならいざ知らず、こんなものに一銭も出してはならない。▼ そもそも、なぜ乾隆帝を採りあげるのか。 むろん、秦の始皇帝から始まる、伝統中国の皇帝権力の栄光の卓尾を飾る存在だからである。 ▼ さすがに有益な知見も多い。 所詮、想像にすぎないだろうが、雍正帝の太子秘密建儲制度は、ペルシアの皇位継承制度をモデルにしたらしい。 また乾隆帝は、易の繋辞伝(ホントはちょっと違う字の「けい」)に由来する、「天数」である「25」という数字に運命的なものを感じ(そもそも即位は25歳の時)ていて、後継者の嘉慶帝は、乾隆25年生まれだという。 蘇州・獅子林の創設者は、元代の大画家倪さん(=王賛)。 「市民ケーン」の映画の字幕に出ていた「ザナドゥー」が元の上都。 ムガール帝国の夏の都はカシミール。 ▼ ダライ・ラマの「ダライ」とは、「大海」を意味するモンゴル語とはご存じであろうか。 第3世ソーナム・ギャツォ(1543-88)が、アルタン・ハーンから称号を贈られたらしい。また、ダライ・ラマは観音菩薩、タシルンポ寺院の住職パンチェン・ラマは阿弥陀仏の化身というのも初耳であった。 ほかにも、乾隆帝が漢族のコスプレをするのを好んだというのも面白いし、熱河離宮(避暑山荘)にあるという江南庭園もぜひ見てみたいと思わされる。 西洋人の青花磁(染付)にいだくエキゾチズムは、「風俗への興味→自力生産→相手の風俗を西洋画的に画かせる」という段階に進んだが、みな乾隆帝が先回りしていた、というのも、ただの「あてはめ」とはいえ、面白い考え方であろう。▼ しかし、他の箇所は、もう、本当に、どうしようもない。 ▼ とにかく修飾語がまったく意味不明で、文章そのものに理解できない部分が頻出していて読むことに耐えられない。 いろいろな香妃像があることについて、「皇胤の空間化という皇帝の密かな欲望(72頁)」だという。 いったい、これ、なにが言いたいのだろう。 トルファン・ウイグルの帰順を描いた、とても西域とは思えない絵画(西欧人に描かせた)について(221頁)の議論にも、唖然とさせられるほかはない。 たしかに、左上の一部には、よくみると、四角い方形の煉瓦でできたような建物があるのだが、「高昌故城」の「イタリア式」イメージがあるのではないか、といいだすのだ。 なんでいきなり「高昌故城」??? 「高昌故城」を出典と判断できるのは、中野美代子氏くらいのものだろう。 『わたし、「高昌故城」を知ってるわよ』とでも、吹聴したかったのだろうか。 まさか。 「三希堂のだまし絵」と「平安春信図」にいたっては、なにを議論しているのか、何度読み直してもまるで理解できない。 とにかく、頭の中に議論がすーっと入ってこない。 ▼ おまけに本書は、ウー・ホンなる学者の議論の転用をのぞけば、「誇大妄想」「幻影」としか思えないような解釈しか存在していない。▼ たとえば、様々な階層・身分・民族(ラマ僧からヨーロッパ貴族まで!)の衣服を身に着けた、雍正帝の絵画についての議論は、その格好の例であろう。 現実に仮装したかは定かではない雍正帝に対して、「扮装癖」呼ばわりするのもすさまじいが、それだけにとどまらない。 「かれの秘めたる外向きの欲求の絵画的な表現(132頁)」は、別の絵画『十二美人図』を「征服者」「彼女の美や彼女の空間、彼女の文化のあるじ」(ウー・ホンの議論)とする解釈になぞらえて、「敗北した文化と国家にたいし権力を行使する欲望」とするのである。 みたことのない民族・階級・身分の人々(かれは紫禁城をほとんど出なかった)の衣服・文化への「憧憬」、と解釈して、何が問題なのだろう。 そもそも、皇帝以外、誰も観るものもいない絵画に、「敗北した文化」に属する人々の風俗を描かせることで、中野美代子氏は、雍正帝が「誰に対して」「権力」を行使しているといいたいのか。 男がアイドル画像を持っていると、アイドルに対して権力を行使していることになるのか。 バカも休み休みいうがいい。 ▼ ダライ・ラマのかわりに乾隆帝が中央において描かれた、ラマ教の軸装仏画「タンカ」の中野解釈も、これまたすさまじい(カラー挿絵あり)。 満族は四夷の一つだから、四夷を制圧するには、「漢族に仮装したうえでのラマへの仮装という二重構造を意識的に設けざるをえなかった」(178頁)のである、とする。 むろん、タンカには、ラマの衣服を着た乾隆帝しかいない。 どこにも漢族の仮装なんてない。 漢族に仮装した上で、とはいったい何を意味しているのか。 乾隆帝の漢族コスプレ癖を言いたいのか。 ならば、乾隆帝の漢族コスプレが蛮夷ゆえのコンプレックスであることくらい証明しなければなるまい。 ところが完全にスルー。 ▼ ほかにも、誕生日を明示しないことで神秘化を図った(160頁)とか、円明園の細長い区画の意味として、イスラムと西欧文明を「夷狄」として閉じこめたのだとか、意味不明な議論ばかりで、どこに図像「学」をなのる資格があるのか、はなはだ疑念に感じざるをえない。 ▼ しかも、上記のトンデモ解釈以外は、それがどーした、と言いたくなるようなものばかり。 熱河(ジョホール)の離宮にラマ教寺院を大規模に建立したのは、モンゴル族とチベット族の宗教的融和を利用して、遠隔地チベットを皇帝の届くところに移し変えたのだ、なんて言われても、だから何だと言うのですか?としか言いようがない。 ▼ おまけに、「あおり」もまたひどい。 乾隆帝は「スペルマの行方を気にしていた」と書いてあるから、いったい何のことかと思えば、ただの「皇太子になるべき皇子の行方」にすぎない。 しかも、ある特定の時点では存在していない皇妃たちが、ひとつの連作絵画の中に描かれていることについての、乾隆帝が考えていたこととして、秘められた意思として提示されているのだ。 「平たくいえば(54頁)」なんて書いてあるが、平たく言おうが言うまいが、どうして皇妃たちが年齢を無視して描かれることがスペルマの行方を気にしていることになるのか。 おそらく精神病患者でもない限り、理解不能であろう。 ▼ おまけに、初歩的なミステイクも多くてどうしようもない。 イギリスのビクトリア女王は、在位年数64年で、最長在位年数を誇る帝王(本書31頁)なんて、いったいどんな資料を読んでの戯言なのか。 フランス国王ルイ14世は、在位72年。 ハプスブルク家最後の国王(と言っても過言ではない)、フランツ・ヨーゼフは在位68年だ。 ヨーロッパですら、ビクトリア女王は最長在位ではない。 史実かは定かではないらしいが、ササン朝ペルシアのシャープール2世は、在位70年だという。 康煕帝の61年なんて、世界の5本の指にすら入らんぞ。 バカか?中野美代子。 それで北海道大学の名誉教授らしいから、笑わせてくれる。▼ ひどいのになると、ネパールを「チベットと同じラマ教国」視(本書217頁)する始末。 むろん、「世界でただ一つのヒンズーを国教としている国」である。 こんなの、少し調べれば誰でも分かるはずだろう。 編集ともども、いったい何をしているのか。 私の気づかなかった間違いまで含めれば、気が遠くなるほど瑕疵があるに違いない。▼ 読みおえたあと、乾隆帝は何だったのか、乾隆帝の時代とはどんなものだったのか、本書の内容を思い出そうとしても、まるで分からない。 正直いえば、注釈魔にして記録魔である乾隆帝が、あらゆる所で詠みまくった、5万首もある詩を通じて、乾隆年間の社会を活写した方が、はるかに良い本になったのではないだろうか。 総じて、乾隆帝エッセイの域をこえておらず、武侠小説の金庸『書剣恩仇録』(邦訳 徳間文庫)の方が、乾隆年間の入門書としては、はるかにマシである、と断言したい。 中野美代子ほどの地位になれば、どんなクズ本を刊行しようが、裸の王様ならぬ、「裸の女王様」。 周りには、だれも諫める人がいない、という典型的事例ではないだろうか。 少なくとも、金返せ。 これだけは確かである。 もっとも、金かえせ!と罵るようなお前が「君子」を自称するな!と、言われるのは困りものだ。 ▼ もはや、私の言えることは1つしかない。 本書は、中野美代子氏の名誉のためにも、「絶版にされるべき書物」である。▼ 文春新書編集部の、すみやかな、良識ある対処を期待したい。評価: ★価格: ¥ 840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 今のブログ順位
May 10, 2007
コメント(1)
全5件 (5件中 1-5件目)
1










