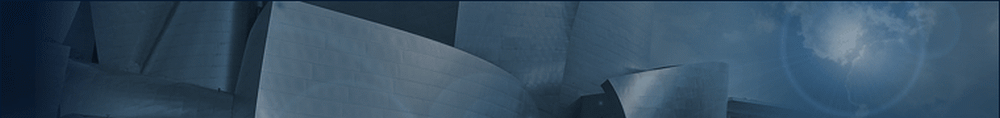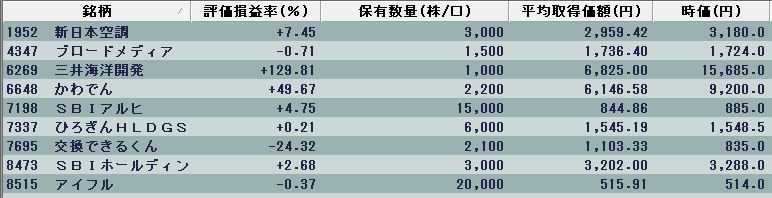2008年12月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

『自己分析』
池見酉次郎著講談社現代新書・・・初版は1968年。出版精神医学の和田氏がまだ小学生で、灘中の受験勉強を始めるか如何かの頃、日本心身医学のパイオニア池見酉次郎氏が生物学をベースにフロイド理論、森田療法、催眠、芸術療法、自律訓練法、アジャセ・コンプレックスに至るまで、網羅的かつ体系的に纏めた一冊。以下は目次。1ストレスからの解放@1現代人のストレス@2ストレスの解消法@3自律訓練法の実際@4系統的な鍛錬法@5芸術療法@6ふれあい@7環境を変える@8「不安」を生かす2自己実現は可能か@1真夜中の心臓発作@2無意識の心@3暗示と祈りの効果@4条件付け@5誤解されている催眠@6インスタント療法の欠陥3自己分析の視点@1愛によるいやし@2心の自己分析@3全人間的に生きる@4慈悲心の再発見@5愛と独立4あるがままに生きる@1とらわれによる悩み@2本当の自分を生きる1は「技術論」として。2は昨今の「できるナンタラ」や「潜在意識のナンタラ」のビジネス自己啓発系を読む前に。オカルトや新興宗教への予防線にもなってくれる。カール・メニンガーの言葉「祈りの神に対する効果の程は判らないが祈ってる人に起こる心身の変化は、科学的研究の対象となる。」が引用されている。日本の場合の例として、禅の瞑想時の動揺度の記録が本書に収録。3は「愛」を始め、宗教めいた言葉が目に付くが、古典的なフロイド理論を簡潔に纏めてあるだけではなく、ユングの名こそ出て来ないが、そのレヴェルの「深み」にまで到達している。大智・大悲と言った仏教的な話をしないと古沢平作がアジャセ・コンプレックスで、何を言わんとしていたか、伝える事も表現する事も不可能。4は動物学者ユクスキュールの著書からの引用で、様々な動物の見る「異なる世界像」を収録。その息子に当たる人物の「人間も、同一の世界に暮らしながら、個人個人で別々の世界観・人生観を持っているので、別々の世界ないし宇宙に住んでいる事になりましょう。」と言う言葉を紹介。自分らしく生きると言う事が、判らないという人には、特に勧める。尚、最後に一言。若しも、「サイコパス・精神病質」と言う種類の人間が居てそれを「仮想敵」として憎んでいるとしたら、その「敵」は単なる「幻想」です。「診断名サイコパス」と言うのは、15年前に精神医学的に消滅済みと考えて良いでしょう。DSM-4の英語版を御覧になれば判る通り、「精神医学的診断基準」としては、既に存在しません。・・日本語版ウイキペディアでもDSM-4で調べられます。但し、情報量は少ない。「反社会性人格障害」で検索されたし。・・多分、「サイコパス」問題が重要と考えている人は「相互理解-誤解」と言う社会心理学的問題を考えているか、個人心理的レヴェルで「共感」の問題を重視しているか、どちらか、または、その両方でしょう。後者の「共感」の問題については本書のp50-53にあります。補足私が本書を読んだのは20歳位の時。和田氏が東大医学部で学生ビジネスや映画作りに明け暮れていた頃です。和田氏の本のレヴューを一冊も書く必要が無いのは、何故か、その理由は本書を読めば判ると思います。また、脳科学のアドヴァンスを考えれば、本書の内容など40年前のものですから、完全に「時代遅れ」になって良い筈なのに全然、そうじゃない。逆に言うと昨今の脳科学の「知見」がこれだけ積み重なったとしても、「脳は未だに、『謎』の多い器官だ」と言えましょう。少なくとも、2008年末の現時点では。上はカレン・ホーナイによる『自己分析』自律訓練法の本。池身氏による。認知療法が出来ないくらいの欝状態ならば此方を勧める。こちらは「健康法」の本。池身氏とヴィクトル・フランクルの出会いの話も収録。池身氏によるストレスコントロール法の本。池身氏による自橿術の本。最もプラグマティック。
Dec 25, 2008
コメント(0)
-

the secret integration
『エントロピー』に関するレヴューは、「あの騙され難い」ドナルド・バーセルミですら、『エントロピー』が「概念小説」だと思い込んで仕舞ったくらいなので、若しもバーセルミだったらと、レムの『虚数』・『完全なる真空』のスタイルで、敢えて、先のようなレヴューを書いてみました。一寸した「お遊び」のようなものです。・・・・・・the secret integration『秘積分』について。・・または、『統合、密やかに』について。・・大衆小説です。凄く判りやすい。田舎の公立中学一年生・・尤も、成績はトップクラスの生徒のレヴェル・・でも読めるくらいの判りやすさで書かれています。逆に、作家サイドで言うと、ピンチョン自身が小説家見習い修行時代を終えるにあたって、「習作」として、「大衆小説」を書いてみた作品なので敢えて、判りやすく書こうとした、と考えて良いでしょう。1964年の作品。時代設定もそのくらいでアメリカでカラーテレヴィの放送が始まった直後くらい。主人公は12歳くらいで、友人に凄く頭のいい子がいる。その他に、主だった友人が「2人」いるが、この「4人」で一寸した「戦争」を行う。もう、3年間も、作戦行動を実行している。その名を「スパルタカス作戦」。最初の部分では、中一レヴェルの数学スノッブ話だが、主人公たちが、「秘密基地」へ出かけていく。キングの『スタン・バイ・ミー』の様に見えるが実は、レイ・ブラッドベリ風の展開へ。ピンチョンはブラッドベリを、相当意識しながら、書いているようにも読める。10月の夜、雨の振る中を、湿った原っぱを抜けて、19世紀末に建設途中のまま放棄され「廃墟」となった「ヴェネチア風テーマパーク」の運河を小舟で進みながら、「大邸宅」の中へ。そこで、突然、挿入される一年前の出来事。黒人ジャズ・ミュージシャンでアルコール依存のマカフィーさんとともに過ごした夜の話。マカフィーさんの、メキシコ湾岸・ニューヨーク・ロサンジェルス・中西部・北部と、合衆国全域を巡る「彷徨の物語」は、JDサリンジャーを思い出させる。しかし、『ライ麦畑』よりも、遥かにスケールがでかくてもっと、ずっと悲壮感が溢れる。最後まで読んでいくと・・・「おおつ!チャンとオチがあるっ!!」80年前後のあじましでおマンガのように「どうせ、オチずに終わるんだろう」と思って読んでいると、良い意味で期待を裏切られます。いや、この時期のピンチョンは、大衆小説には「オチが絶対に必要」と言う「通念」に拘っていたのかも。「インテグレイション・積分・統合」が何を表すかと言うと・・・。RDレインの『経験の政治学』に倣って言うとその人間の人生の「諸経験」の「歴史化」と言う作業と考えて良いでしょう。パースナル・ヒストリー「個人史」の構築。「歴史」ヒストリーは、「物語」ストーリーであり、「自分の人生の物語」と言う「おはなし」を創りあげる必要が、人間にはある。「おはなし」とは、河合隼雄の言う意味での「おはなし」。「私の人生は、偶々、こうでした。その後、また偶々、こうでした。・・・」そんな「偶然性の連続」と言う「『冷たい現実』の集積体としての人生」には普通の人間は耐えられない。従って、「積分」して仕舞う。自分の人生を、記憶に基づいて。但し、「完全な積分」は不可能であり、「記憶の網の目を、いとも簡単にスルリと潜り抜けて漏れ出して仕舞う『実体験』」も、当然ある。だから、ヒストリー「歴史」・ストーリー「物語・おはなし」はフィクションに過ぎない。此れは、年齢が何歳かは関係無い。主人公たちも、12,3歳だけど、チャンと「インテグレイション」しています。「密やかに」そして、「こっそり」と。
Dec 21, 2008
コメント(0)
-

スローラーナー
「線形性問題」停滞中「情報エントロピー」増大中レヴュー物理学専攻者のピンチョンの作品は難解と、良く言われるが物理学を基礎から学び直して、読んで見ればそれ程でも無かろう。大体、大学の一般教養課程レヴェルで良いだろうし、高校物理程度でも割かし、読めるもんだ。取り合えず、『エントロピー』について。閉鎖系と開放系の話。上の階のカリストの部屋が前者、下の階のマリガンが引越退去祝いの馬鹿騒ぎを遣っている部屋が後者。時代設定は1957年2月。場所はワシントンDC。「情報エントロピー」が最も小さくなっている部分はカリストが一緒に暮らしている女の子オーバードに、「熱力学」を口述筆記させている部分、と言うよりも、その内容の部分。例えば「マキアヴェリのように彼は『ヴィルトウ・能力』と『フォルトウナ・運命』の支配力は、まず五分五分であるとした。しかし、この均衡状態が今、出鱈目な要因を導入した為に、確率は押されて、何か、言いようも無い、不定の比率となり、彼はそれを計算するのが怖いのである。」システム・トレーダーは怖くはないし、どんどん計算しちゃう。「机上の計算」等と呼ぶカツオドリ阿呆船長もいるが、そんな奴なんぞ御構い無しに「検証」を続行。randomness の導入の御蔭で儲けられる事が判っているので、確率が50%に為らない事は「実に喜ばしき事」である。参考文献としてはNNタレブのFRB日本語版『まぐれ』を参照。また、トレーダーにとっての「均衡状態」と言うのは「相場の死」を意味する。「マーケットの熱死状態」。マーケットのノイズが減少、均衡しつつあるかと思うと、突然07年夏のような「大馬鹿騒ぎ」が始まる。で、大儲け。また、均衡に向かうかと思っていると08年夏にまた、突然「大馬鹿祭後夜祭」。で、また、大儲け。その繰り返し。『ロケット工学投資法』等が、典型的だが、経済現象を「工学メタファ」で語ってみても、理科系インテリの戯言。物理現象としての「ノイズ・雑音騒音」と言う音響工学的概念と「マーケットの『ノイズ』」と言うメタファの混同。売買「シグナル」も「信号」対「ノイズ」と言う「通信工学」的なコンテクストの中での理解。場合によっては「誤解」だが、「誤解」でも『まぐれ』で儲けられる。ピンチョンの本作と逸れまくりだが、情報エントロピー増大中。例えば、今私の書いた事の80%以上はノイズ。詰まり「戯言」である。村上春樹的な「静けさ」と言うのは、カリストの部屋の中の「人工生態系」のようなもの。レイモンド・カーヴァのようなミニマム文学の「景気の悪い」日常的な暴力性が提示されて、本作は終わる。・・・最後にあらゆる動きがなくなるだろう。個人的には深沢七郎『東京のプリンスたち』よりも、この『エントロピー』の方が、好き。参考文献として、エンリコ・フェルミの『熱力学』を読んで見たいと思うが、「予定」しているだけであり、スケジュール的には「未定」。続きはまた書く。
Dec 17, 2008
コメント(0)
-

『バビロンの塔』
トポロジカルな世界認識『バビロンの塔』について。ホルヘ・ルイス・ボルヘス的な印象をタイトルからも本作前半部からも、与える作品だが、それ程、ボルヘスボルヘスした感じでは無い。テッド・チャン自身も、ファンタジーではなくSFとして本作を位置づけている。先ず、タイトルからして、「字面の部分」だけで『バビロンの籤』や『バベルの図書館』と言ったボルヘスの短編を連想させてしまうが、コンセプトとしては、全く異なる。・・例えば、『バビロンの籤』は、ディックの『偶然世界』に近くまた、『バベルの図書館』は先のトピックで挙げた、エリスンの『俺には口が無い。それでも俺は叫ぶ』に多大な影響を与えていると考えて良かろう。寧ろ、ハーラン・エリスンが『バベルの図書館』より、『俺には・・』の着想を得た、とも考えられる。詰まり「知性」の代わりに「憎悪」を。「情報」の代わりに「暴力」を。そんな感じだ。・・さて、チャンの『バビロンの塔』に話を戻すが前半部のボルヘス的な味付けと言うのは所々に見られるだけで、山尾悠子のように最初から最後まで全部、ボルヘスへのオマージュと言った作品では無い。本当にわかる人にはわかると言った「隠し味」めいたボルヘス風味である。「高い塔」だから、オチは「落ちる」か「倒れる」かだろう、と言う安直さも無い。前半部で主人公たちが塔を登っていくプロセスが「塔での暮らし」の描写と言う「日常性」の中で綴られる。塔の建築資材を運ぶ「車力」たちと一緒に塔に登っていくが、車力たちの家族が塔の中で暮らしていて主人公たちを暖かく迎えてくれる。食事を囲んで一家団欒のシーンなど、「ほのぼの」としたもので80年代の宮崎駿アニメを思い出させる。食ってるものが、また旨そう、に書かれている。干し魚、パン、デーツ、ワイン、果物などがテーブルに並ぶ。やがて、主人公たちは塔の頂に到着して作業開始。「穴」を掘るのだが、此処から途端に、「土木工学SF」になる。花崗岩に掘り進んで行くので、掘削速度は如何見積もっても、一日に2,3センチ程度。もし、このままなら、菊池寛の『恩讐の彼方に』の様になってしまうが、此処でも「問題は『技術』によって解決克服される」。古代バビロニアが作品の時代設定だが「火力採掘法」によって、作業開始。此れは、一転集中的に岩の一部に向かって火を燃やし、加熱膨張したところへ行き成り、水をぶっ掛けて、岩石を収縮させひび割れを起こさせて、この「弱りの来た」部分を集中的に掘っていくという手法である。・・考えて見ると5000年か6000年前のバビロニアで、このテクノロジーが使われていたのに『恩讐の彼方に』の約300年前の、江戸期の日本でこの技術が使われなかったのが奇妙だ。人数の問題ではない。一人か二人でも出来るので何年もかけて、ノミとハンマーだけで掘るよりもずっと、効率的。菊池寛の主題は、そう言う所じゃない、と言うのは重々承知だが、「技術で解決できる種類の問題を、『敢えて』、技術的に解決しようとしない」と言った歴史上の話にテーマを求めてしまうのが日本文学の特徴なのか。相場で言うと、「技術論者」の林輝太郎氏の一連の著作を思い出す。・・話が逸れてしまったが、主人公たちは、彼らと一緒に来てくれた「特殊採掘技能」を持つエジプト人たちと、何年にも亘り、トンネルを掘り続けて、トンネルの中で暮らしながら作業を続ける。この辺りの時間の流れの感覚が昔、流行ったイスパノアメリカ文学的。「魔術的リアリズム」の時間感覚を堪能できる。トンネルを掘っていると「出水」と言うのが恐いがこの作品では『洪水伝説』との絡みで語られている。主人公はその「出水」に出くわし、何とか「上に」出る。ところが、「クラインの壷」。此処で、チャンは主人公に「見事な世界認識」をさせる。古代バビロニアで極普通に用いられていた「ある道具」をメタファとした、全く新しい「世界モデル」に主人公は到達。世界観Aより、世界観Bへ。その「新たな認識」が、人間を、どういう「気持ち」にさせるかは、読者の側の判断。良い意味での「脱力」、「肩の力が抜けちゃう感じ」を感じるかもしれないが、80年代前半時点で浅田彰が言っていた「最低人主義」を髣髴とさせる。
Dec 16, 2008
コメント(0)
-

月利192%
12日金曜日の外貨の下げで、大きく取った。特に、木曜日時点での対円でユーロの独歩高に注目していたので、ユーロ円中心に大儲け。12月は12日時点で月利192.22%だったが、今月と言うか今年はもう、閉店の予定。
Dec 15, 2008
コメント(0)
-

何故ならば「人間だから」だ
『地獄とは神の不在なり』について。「降臨現象」には、天使の降臨と堕天使の降臨がある。通常の「降臨」は一回につき、一体の天使、または堕天使が降臨する。「降臨現象」は複数回起きるので一般には「堕天使達の降臨」などと呼ばれる。堕天使達は、神の意志に従わず何か想像もつかぬような仕事をする為に人間界を「通過」していく。目的地は人間界ではなく、全く別の次元に存在する空間。人間が、堕天使の降臨に遭遇した時「あなた方は何故、神の意志に従わないのか。」と尋ねると堕天使達の答えは何時も決まっている。「俺たちは自分で決める。お前たちもそうしろ。」人間の中には、自分の「自由意志」のもとに生きようとする者もいる。神への信仰とは決然と縁を切る。そういう人間たちは、こう呼ばれる。「ヒューマニズム運動家」。彼らは、死ぬ時に自らの意志で生きた人生を悔いる事も無く、誇り高く「地獄」へと行く。「俺は、自分の意志で自分の人生を生きて来た。神とは、きっぱりと縁を切る為に、『地獄』へ行く事を選択する。何故ならば、自分は『人間だから』だ。」こんな感じだろう。「だって人間だもの」と言う詩人が軟弱かどうかは、兎も角として「ヒューマニズム」を標榜する以上、この作品世界で生きていたとすれば「神」と堂々、渡り合うだけの気概が必要だろう。現実の日本と言う文化圏が如何に優しいか、そのせいで、「邪悪さ」の現れ方が「特殊」になるか、と言う比較文化的な話は、此処では特に、しない。
Dec 14, 2008
コメント(0)
-

リアリストの生き方
「私は理想主義者じゃ無い。自分の出来る事を遣るだけだ。」 ・・・ジム・ゴードン警部補 後にゴッサム市警本部長
Dec 14, 2008
コメント(0)
-

コイン・トス
地方検事ハービー・デントが怒りに燃えて、ジョーカーの手下の一人を裁判にもかけずに裁こうとする。銃を額に突き付けてジョーカーの居場所を言わなければ、と脅迫。「正義とは、結局『運不運』でしか無い」と言わんばかりにコイン・トス。表が出れば、引鉄を引かないが、裏が出れば・・・コインの表が出る。ジョーカーの手下がほっとするが、デントは「もう一回やる。次は如何かな。」二回目にトスされたコインが落ちる前に突然、現れたバットマンが空中のコインを掴み取る。「命を『運不運』で決めるな!」実は、このコインはイカサマで、どちらも表だった。「信念の人」ハービー・デントは偶然や『まぐれ』では、行動しなかった。少なくとも、最初の内は・・・。
Dec 13, 2008
コメント(0)
-

ヒョーロン家
林輝太郎氏でなくとも、自分で売買した事の無い人間があれこれと相場を語るのは、「童貞と処女のセックス談義」に過ぎない、思う人は多かろう。相場の評論家はヒョーロク玉の様なものである。しかし、アマチュアであれプロであれ、文学や芸術や映画の評論は、それがどんなに「くだらねー」内容であっても、評論する「権利」がある。その作品の「購買者」であり、「顧客」だからだ。中には本当に、「金返せ。バカヤロー。」と言いたくなるようなレヴェル超低過ぎ作品もあるが、金を貰ってその印税収入なり何なりで、食っている「クリエイター」はその「金返せ。バカヤロー」の評論とも言えない様な「罵倒」を甘んじて受けねばならない。それが、プロの「クリエーター稼業」と言うものなのである。・・そもそも、この国には「職業選択の自由」があるのだから、そんな風に「論評・批判」されるのが嫌ならば、別の仕事に転職すれば良いのだ。石川R見たいに、著書の批判があると、直ぐにスネてブログのコメント欄を閉鎖して仕舞うのならば、最初ッから本なんか書かなければ良い。誰も彼に「本を書いてください」と頼んでいないのに。唯、一説によると、石川Rが欝が軽くなって来た時に、「本を書いたら」と医者が勧めたらしい、と言う話もある。本当にそうなら、愚かな医者を自分の「主治医」として、選んでしまったのは彼自身の「自己責任」の問題である。医者以外の知り合いか誰かに言われて「真に受けて」書いたとしたら、いい歳をして世の中を「嘗めて」たんじゃないのか、と思う。そんな風だから、サラリーマン時代に「辛酸を嘗める」事になったのだろう。・・話が逸れて仕舞ったが、文芸評論のプロと言うのは、小林秀雄みたいに評論本を書いて喰っている人。一円も儲からないけれど「趣味」で評論している人がアマチュア。他のカルチャー分野の評論の場合も同じ。但し、プロの評論家の本に対する「反批判」もあれば更に、両方とも駄目と言って来る評論家もいて、「百家争鳴」。それが、面白いんですけどね。カルチャー評論の場合は。「火事と喧嘩は江戸の華」と言う通りで、ブログ炎上やら、チャットや掲示板での喧嘩とかが無いとネット社会も詰まらん。勿論、プロは別として、アマが「趣味」で遣ってる事なら嫌になればさっさと辞めちゃう。遣りたくなったら、遣りたい時にだけ遣れば良い。最後の部分は、相場でも同じで毎日、場帖を付けたり、トレード日誌を付けたりするのは重要だが、トレード自体を毎日、または「常に」する必要は無い。この事は、輝太郎氏のみならずドクター・エルダーも『投資苑』シリーズの中で書いている。
Dec 13, 2008
コメント(0)
-

運不運
「正義もモラルも無い、この時代に唯一つだけフェアなものがある。『運不運』だ。」・・・ハービー・デント 『ダーク・ナイト』
Dec 13, 2008
コメント(0)
-

ソラリスの陽のもとに
純粋幾何学的知性について。取っ掛かりとして、映画版『コンタクト』との比較でレヴューして見る。『コンタクト』で最初に琴座のヴェガから、送られてきた信号が、1から200までの素数。ジョディ・フォスターが「数は『宇宙共通語』です。」と言うが、異議あり。カール・セイガンの原作は、兎も角として、ソラリスの様に1個体で1生物種をつくっている場合は、「代数」の概念が必要ないだろう。但し、「超長物」や「対称物」をつくって見たり、二重恒星系を巡る公転軌道を「計算」して、自分でコントロールして仕舞っているので「純粋幾何学的な世界認識」で「思考」しているのかも知れない。考えて見れば、フラクタル理論のマンデルブロも幾何学者だ。彼の本にブラックショールズ式に「対峙」する様な数式が無いのも当然と言えば当然かも。マンデルブロも「ソラリス的」思考をしていたと言っては、SF駄洒落の様なものか。
Dec 8, 2008
コメント(0)
-

あなたの人生の物語
「線形性問題」脇道レヴュー。「線形性問題」を語るならば表題作『あなたの人生の物語』をレヴューするのが本筋だが、その前に「宗教的問題」を少し、片して置きたいので、『地獄とは神の不在なり』を脇道的にレヴューする。『地獄とは』の読後感は、ハーラン・エリスンの『俺には口が無い。それでも俺は叫ぶ』に近い。エリスンの『俺には』で、人間が創りあげた「神」は腹の底から人間を憎んでいた。「神」は世界を完全に創り変え、その「世界」にオングストローム単位の「憎悪」を詰込んだ。「憎しみの稠密状態」とも言うべき「地獄」を「人類」の為に用意し、その中で人間たちを責め苛み、殺し続け最後にこの「世界」に残っていた者は人間と、嘗て人間だったが「神」の手により「人間以外」となった者を含めて4名だけだった。此処からエリスンの『俺には』は始まる。チャンの『地獄とは』では、「宗教的現象」が割と頻繁に現実に起きる「世界」を描いている。「降臨」が起きると、死人も出るし怪我人も出る。家屋建物も倒壊するし火災も発生する。一回の「降臨」で発生する経済的損害は、ざっと見積もって数百万ドル。因みに、ナタナエルの「降臨」では被害総額が800万ドル以上。07年の日本全国のオレオレ詐欺の一年間の総被害額よりも100万ドル程多い金額である。しかし、保険会社は死亡障害火災他に対して、ビタ一文支払わない。「宗教的現象」によって引き起こされた事故災害は、適用対象外だからである。この作品世界では、「保険屋」はぼろ儲けだろう。しかし、「降臨」では厄災を被った多数の人々の一方で祝福・恩寵とも言うべき「奇跡」を体験する少数の人々もいる。一見、「宗教的テーマの不条理SF」の様に見えるが、実は「宗教自体の不条理性をテーマとした『世界観小説』」と読める。・・「世界観小説」と言うのは、スタニスワフ・レムの『枯草熱』の事を翻訳書の沼野氏が、そう呼んでいた。・・レムの作品の多くが、ラストシーンで人間が何らかの「達観」「諦観」と言う認識論的なポイントに到達するのに対して、チャンの『地獄とは』のラストシーンでは主人公は「諦念」と言う情緒的・感情的なポイントに到達する。読後感がエリスンの『俺には』に似ているのは、この作品でもラストで「神」によって「人間以外」に創りかえられ、最早人間ではなくなった主人公が、唯一人生き残って「神」の創った「地獄」を這いずり回りながらも、「人としての尊厳を懸けて、全身全霊で『神』を憎む!」と言う情緒的・感情的なポイントで終わっているからである。エリスンとチャンの二作品は、ヴェクトルが正反対ながら、情緒的次元で中心テーマが語られ、「人間の人間たる所以」が扱われている。続きはまた書く。
Dec 7, 2008
コメント(0)
-

物理法則はいかにして発見されたか
「フェルミ推定」本との絡みでのレヴュー。全体を導き出すのに此処から出発すべきと言う特別の命題は存在するか。また、命題Aはより基本的で、命題Bは二次的性格と区別可能か。数学的には以下の2通りの考え方がある。1.バビロニア式・・・生徒は数多くの例題を解かされ、例題を解いてる内に何か悟る事を期待される。一般的規則を感得するまで、それを継続。「質より量」の勉強法。地方の県立進学校の大学受験数学対策と良く似ている。推論の方法も幾らか弁えているので、一つの命題より別の命題を導く事も、完全に不可能と言う訳では無い。2.ギリシア式・・・別名ユークリッド式。幾何学諸定理の順序構造に気付く事で少数の単純な公理群より、次々に諸定理が導き出される事を発見。現代数学的。公理と証明に専心。現代幾何学はユークリッド幾何学公理群に基づき修正を加えたリーマン幾何学公理群を出発点として、全体系を演繹。予備校の大学受験数学対策的。「量より質」の勉強法。常に決まった公理から出発する方法は新たな定理を見つける為の能率的方法では無い。場合に応じて、勝手な所から出発する方が遥かに能率的。ファインマンによれば、物理はバビロニア式にすべきであり、ギリシア式にすべきでは無い、との主張。私が、「フェルミ推定」本と小泉氏の本のレヴューを通じて対比的に言いたかった事と良く似ている。・・・続きはまた書く。以前、書いた記事で紹介したファインマン物理学の「確率」の章は上記の本にある。期待値±0のシステムでトレーディングを100回程度続けた時のエクイティ・カーブと良く似たグラフも挙げられている。また、コイントスによるランダム・ウォーク実験の「事象を帰納して」数学的モデルへと落とし込んだグラフが、「完全正規分布!!」のベルカーブに、為っているのは「当然と言えば当然過ぎる」のは言うまでも無い。また、この場合は「期待値0」に収斂されていくのも「余りにも当然過ぎる」事ではある。勿論、数学的にだが。
Dec 5, 2008
コメント(0)
-

月利237%
前後したが、11月度月利は237.96%で、最後の週は休暇を取って、本ばっかし読んでいた。某アマゾンに、12月以降ブックレヴューが急に増えたのは、その為。
Dec 5, 2008
コメント(0)
-

月利24%
12月度月利は本日5日時点で24.8%である。アメリカ雇用統計の日なので、既に閉店休業状態。例によって例の如し。
Dec 5, 2008
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1