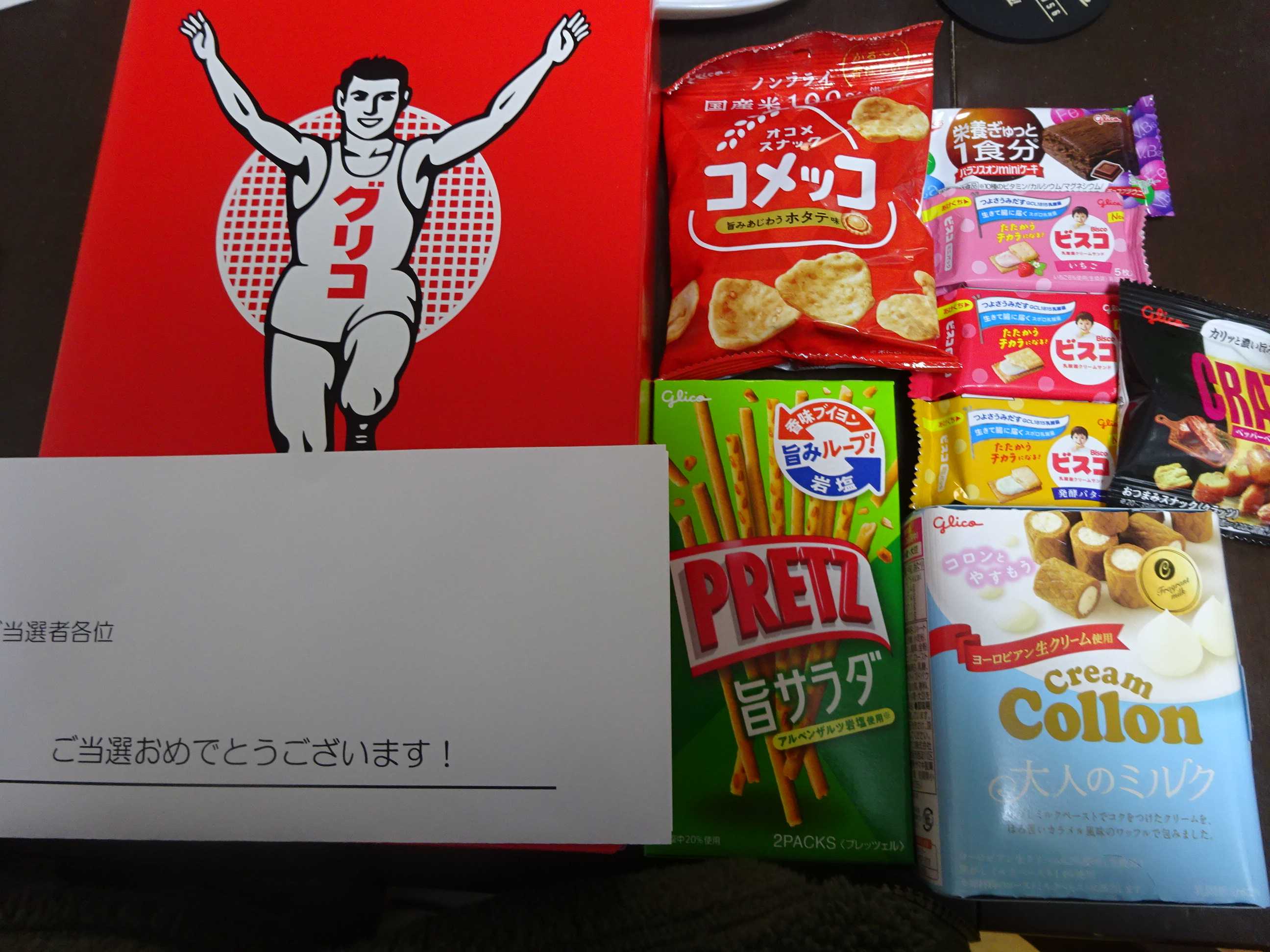2013年06月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

一日中家で過ごす
今日は、一日中家で過ごした。午前中はNHK俳句、日曜美術館などを見て、午後は、世界自然遺産のDVD2本を見て、他には、句集や句誌を読んだり、エッセイを書いたり、俳句を作ったりした。世界自然遺産のDVDは、アジアが、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、中央雨しかが、ベリーズ、キューバ、メキシコ、ドミニカ、パナマなどで、自然の中で生きるいろいろな珍しい生物を知ることができた。今日の画像は、マンションの玄関ロータリーの一角に咲いているムクゲの花。木槿は夏の季語。きはちす、底紅ともいう。韓国の国花。
2013.06.30
コメント(0)
-

「築港」トークショウに参加
今日は、午前中は図書館は行き、午後は、大阪歴史博物館で開催された「築港」トークショウを聞きに行った。図書館では、世界遺産のDVD2本と句集2冊を借りた。画像は、パンフレットを中央に、トークショウの模様。上右は田淵区長。「築港」トークショウは、田端港区長の挨拶で始まり、出演者は次の3人で3部構成であった。1.柳原良平氏(イラストレーター)と山納洋氏(大阪ガス)の対談。柳原氏は大阪築港工事の最大の功労者西村捨三の曾孫に当り、学生時代には船の絵を画くために天保山桟橋に連日通っていたそうだ。サントリーに入り「アンクル・トリス」のキャラクターで有名になった。対談では、戦時中から戦後の築港の様子を思い出しながら、よき時代を回想した。(50分)2.10分の休憩のあと、大阪歴史博物館学芸員の酒井一光氏から、パワーポイントを使った大阪築港の歴史を振り返る話があった。配付資料にも詳しく書かれているが、絵や写真を見ることでより深く知ることができた。(20分)3.続いて、柳原氏、酒井氏、山納氏の3人によるトークが始まった。賑わっていた港の食堂や飲屋や旅館が、荷役作業がなくなる連れてさびれていった。倉庫もみんな空き家になってしまった。今は海遊館だけが賑わっているだけ。今後どうするとという話がなされた。柳原氏の意見はなるにまかせるしかないということだった。(40分)トークショウのあと、歴史博物館7階の「近代都市建設」のコーナーで、築港関係資料の展示解説が行われた。なお、来週7月6日には「築港まち歩き」が行われる。その後、8階の特集展示「大坂の凧」を見た。図はパンフレットより。右上は勝間いか、右下は先週の凧。江戸時代の絵画および文献に挿絵として描かれた凧を実際に再現したものを、文献とともに展示したもの。木村薫氏のコレクションだそうだ。大阪の凧の一つ勝間(こつま)いかは住吉名物となっていたり、泉州の凧も有名だった。
2013.06.29
コメント(0)
-

ミナミへ外出
今日は、心斎橋、難波方面へ外出しただけで、その他は家で過ごした。句集を読んだり、俳句を作ったり、エッセイの構想を考えたり、雑事をしたりで、これといったことはしなかった。今日の写真はツユクサ。マンションの近くの草むらに咲いている。百貨店では、お中元を送ったあと、昼食をとり、店内を見てまわった。露草は、秋の季語。蛍草、月草、青花、うつし花ともいう。
2013.06.28
コメント(0)
-

高大2年目の9日目
今日は、高大2年目の9日目。午前中は服部先生の文学鑑賞近代篇(3)「江戸戯作を読む」で、午後は、大阪教育大教授堀 薫夫先生の共通講座(3)「超高齢化と生涯学習社会の到来」を聞き、その後、マジック同好会の第1回会合に参加した。 写真は、共通講座の模様。パワーポイントの画像は70枚のうちの3枚。江戸戯作は、山東京伝の「金々先生栄花夢」、「人間一生胸算用」、式亭三馬の「浮世風呂」などを読んだ。当時の話ことばの入った面白い読み物であった。登場人物の名前も面白い。「超高齢化と生涯学習社会の到来」の話は割合話ぶりがうまく、いろいろ内容のある話であったが、総花的で、本当に訴えたいことは何かが伝わらなかった。あとは、個人個人が考えよということかもしれない。マジック同好会は17人が集まった。自己紹介のあと、さっそくカードマジックを一つ教えてもらった。
2013.06.27
コメント(0)
-

都市遺産フォーラム「道頓堀の景観復元をめざして」
今日は、午前中は、K病院へ糖尿の診察に行き、午後は、関西大学へ都市遺産フォーラム「道頓堀の景観復元をめざして」を聞きに行った。画像は、パンフレット、フォーラム風景、劇場大工中村儀右衛門資料より、道頓堀復元CGの一コマ、フォーラムタイトル、道頓堀復元ジオラマの一部。K病院での診察は、先日受診したブドウ糖付加試験の結果を聞きに行ったもので、長い間受診していなかったが、やはり境界型糖尿病が続いていることが分かった。カロリーを取り過ぎないことと食後の運動を勧められた。都市遺産フォーラム「道頓堀の景観復元をめざして」は、関大が文科省の補助を受けて研究しているもので、今回のフォーラムは次のような構成で行われた。第1部 講演 道頓堀 いま・むかし 講師:(1)今井 徹(道頓堀商店会会長) 道頓堀が昔の風情を失っていくのが惜しまれる。 (2)鳥居 学(千日山弘昌寺住職) 道頓堀は江戸時代は刑場で墓と寺が多かった。第2部 報告 芝居町道頓堀の景観復元への試み 報告者(1)壱橋寺知子(関大環境都市工学部准教授) 劇場大工中村儀右衛門の遺稿・資料について (2)林 武文(関大総合情報学部教授) 大正8年頃の道頓堀復元CG・道頓堀川からの景観の映写 360度パノラマ景観、キャラクタの動きの紹介第3部 パネルディスカッション 道頓堀の景観復元をめざして パネル(1)栗本智代(大阪ガスエネルギー文化研究所主席研究員) (2)高橋隆博(関大文学部教授) (3)今井 徹 (4)鳥居 学 コーディネーター 桜木 潤(関大大阪都市遺産研究センター特別任用研究員) 今後の進むべき方向についていろいろな意見、提案が出された。フォーラムのあと、中村儀右衛門資料の展観および復元ジオラマの見学を行った。
2013.06.26
コメント(0)
-

一時外出しただけ
今日は、午後一時外出をした以外はほぼ一日中家にいて、昨日の句会のまとめを行った。今日の写真は、句会条のビルの前に植えられているコバノトネリコ。今ちょうど花が咲いている。
2013.06.25
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は、句会資料のプリントをしたあと、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の成績はまあまあで、先生から1句が選ばれ、残り4句は仲間から選ばれた。今日の写真は、会場近くの歩道橋のところに咲いている海紅豆の花。一度咲き終わって二度目の花を咲かせようとしているところ。先生から選ばれたのは次の句。 〇父の日の父の遺影に笑み返す こっぱん (先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・都心にも名園あつて蛍の夜 こっぱん (3票) ・二三日あれば十分梅雨晴間 こっぱん (2票) ・条線の少し曲つてゐる植田 こっぱん (1票) ・短夜の夢は忙しく醒めにけり こっぱん (2票)今日、先生の特選を得たのは次の句。 ◎父の日や思慕と反発未だあり 洋子 (先生特選ほか2票) ◎東大寺抜け蛍火を闇に待つ 茲子 (先生特選ほか1票) ◎父の日の厳しき父を思ひ出す 哲子 (先生特選)今日一番多く表を集めたのは次の句。 〇白きシャツ学園前にどつと下車 昇一 (4票) 〇ほうたるの音なく闇を流れけり 洋子 (4票)先生の句で今日一番人気だったのあ次の句。 ◎短夜の机上散乱せしままに 塩川雄三先生 (5票)以下未完
2013.06.24
コメント(0)
-

淀川探鳥会に参加
今日は、朝から淀川探鳥会に参加した。9時に阪急十三駅に集合し、1時間ほど十三東通り商店街、通称つばめ通りでツバメの巣を4つ見たあと、淀川に出て鳥を観察した。写真は、上段:ツバメの巣、中段:ダイサギ、カワウ、ムクドリ、下段:カルガモの番い。ツバメの巣は今年は4か所、うち一か所は昨日巣立ったばかりで今は空家、他の3つは卵が孵ったばかりで、まだヒナが餌をねだるほどには世徴していない。孵化後、5日くらいで餌をねだるようになり、10日くらいで羽根も生え揃うそうだ。淀川では、ダイサギ、カワウ、オオヨシキリ、セッカ、ヒバリ、ツバメ、ムクドリなどの姿はよく見たが、あまり珍しい鳥は見られなかった。カルガモの番いが陸に上って水溜りをつついているのを長時間観察することができたのが収穫だった。今日見た鳥は、上記7種のほか、キジバト、アオサギ、コサギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、スズメの8種で計15種。帰宅後は、テレビで日本ゴルフツアー選手権を見た。
2013.06.23
コメント(0)
-

「インカ帝国展」へ
今日は、京都文化博物館で開催されている「インカ帝国展」を見に行った。昨日行く予定だったが、雨と台風のため今日の延期したものである。画像はパンフレットより。左上:マチュピチュ、同、左下:キープ、ミイラ包み、貝殻製ミニチュア女性像、12角の石、金製のリャマ像、アリバロ、右上:小型女性人物像、ドン・アロンソ・チワン・インガの肖像ず、右下:金合金製の小型人物像、貫頭衣(チュニック)、ミイラ、ケロ、銀製酒杯アキリャ、スントゥルワシの聖母、マチュピチュを発見したハイラム・ビンガム、100年前のマチュピチュ。2か月以上あった会期が明日で終りになることもあって、今日は物凄い人で混雑していた。ひとつひとつの展示品がよく見られないし、説明文もなかなか読めない。それでも人のすきまからなんとか見たり読んだりして、全部見るのに結局2時間ほどかかってしまった。 展示品は158点あり、次のように分類されていた。第1部 帝国の始まりとその本質 金合金製の小型人物像、貫頭衣(チュニック)など79点第2部 帝国の統治 ミイラ、ケロ、キープなど56点第3部 滅びるインカ、よみがえるインカ 銀製酒杯アキリャ、スントゥルワシの聖母など9点第4部 マチュピチュへの旅 鏡、食器など14点とマチュピチュの3D映画(12分)展示物の多くは壺などの食器、酒器、祭礼用具、農具、装身具、人形、衣類などであったが、最も水らしかったのは、5体のミイラだった。マチュピチュの上を飛んでいるような気分を味わえる3D映画もよかった。栄華を誇りながらもスペイン軍にほろぼされてしまったインカ帝国の姿の一端を垣間見ることができる展覧会だった。
2013.06.22
コメント(0)
-

ほぼ一日中家で過ごす
今日は、当初は京都へ「インカ帝国展」を見に行く予定をしていたのだが、天気予報では大雨が予想されていたのでやむなく中止した。午後雨が止んだので散歩のため一時外出した。それ以外はほとんど家で過ごし、句集を読んだり、俳句を作ったりして過ごした。句集は、高橋将夫の「如意宝珠」と、小川軽舟の「呼鈴」。どちらもいい句集だった。写真は、一時外出して立ち寄った太閤園の庭。中央はギボシの花。
2013.06.21
コメント(0)
-

高大2年目の8日目
今日は、高大2年目の8日目。今日からエッセイ創作の授業が始った。最初の1時間は自己紹介を兼ねて「なぜエッセイ科へ来たか」の受講動機を話し合った。後半の1時間は宿題として書いて来た「雨」と題する800字エッセイを披露し合った。受講動機は2種類あり、一つは「昔から書くことが好きだったから」、もう一つは「苦手に挑戦してみたかったから」。私はもちろん後者。後半のエッセイ披露は、自信のある人から手を上げ、11人が読んだ。みんな流石にいい作品ばかりだった。もちろん私は読んでいない。午後のクラスミーティングは、相変わらず内容のないものだった。今日も写真は撮らなかった。写真は豊里城北大橋。先日、城北公園へ菖蒲を見に行ったときに写したもの。上は橋の上から淀川上流を見たころ、中段は橋を通りながら橋を写したもの、下段は下流側を橋の上から見たところ。
2013.06.20
コメント(0)
-

DVDで劇団四季の「南十字星」を見る
今日は、梅雨本番の日になったので外出はせず一日中家で過ごした。午前中は、DVDで劇団四季の「南十字星」を見、午後はDVDでバレエ「シンデレラ」を見た。その他、今月の句集感想文を仕上げ、明日のエッセイ科の宿題文を書いた。「南十字星」は2004年の作で、DVDのものは2010年上演のもの。太平洋戦争の前後のインドネシアでのある動員学徒の生きざまを描いたもの。主人公の保科勲は京大学生だったが、学徒動員でインドネシアに行く。現地民にも慕われ、オランダ捕虜にも誠実の接したが、上官には意見を言うことが多かった。終戦後、上官の罪を着てBC級戦犯に仕立て上げられ失意のうちに死刑を受ける。この間、現地女性リナとの恋があったり、インドネシアの独立を支援したりする。戦犯というのが、米軍の一方的な感情だけで決められ、なんの落度もない兵士の多くが死刑に書せられて行ったことがよく分かった。無実であってもあえて黙って刑を受け入れることで、遺された日本国民への進駐軍の印象をよくしたいと考えたのだそうだ。上演時間2時間22分だが、民俗舞踊を下りませた内容の濃い舞台だった。
2013.06.19
コメント(0)
-

映画「じんじん」の試写会を見る
今日は、午前中は俳句を考えたり、バレイ「くるみ割り人形」を見直したりして過ごし、午後は、大坂市立図書館で行われた映画「じんじん」の試写会に参加した。2時間10分の大変いい映画だった。途中なんども目頭を押えなければならないほど感動的な作品だった。正式には7月13日からロードショウが始まるそうだ。画像は、左上から、試写会の案内パンフ、図書館の5階ホール、映画の解説をする主演の大地康雄氏、以下映画のシーン。
2013.06.18
コメント(0)
-

城北公園菖蒲園へ
今日は、午前中は、資料の整理などをし、午後は、城北公園の菖蒲園へ行った。午後の強い日差しを受けてやや疲れ気味の花だった。また、数年前と比べ管理が行き届いてなくて荒れた感じがした。
2013.06.17
コメント(0)
-

俳句21の句会に参加
今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見て過ごし、午後は俳句21の句会に参加した。写真は、句会会場の千中パル2階の花壇に今日咲いていた花々。句会の結果は、相変わらず低調で、出句4句のうち2句だけが選ばれた。選ばれたのは次の句。 ◎日本の水が合ふらし通し鴨 こっぱん(2票) ◎十薬の花プラス白プラス白 こっぱん(2票)
2013.06.16
コメント(0)
-

緑懇会の例会で箕面へ
今日は、午前中は、DVDでバレエ「くるみ割り人形」を見、午後は緑懇会会の例会に参加し箕面へ行った。写真は左上から、箕面駅に集合し今日の見どころの説明、渓流の紅葉の若葉、イロハモミジとオオモミジ、滝安寺、山にはツブラジイが多い、菩提樹、山肌にはシダが多い、箕面の滝、最後の締め。昨日、映画「雪の女王」を見たばかりだが、今日見た「くるみ割り人形」第1幕の終りに「雪の女王」が登場するので驚いた。緑懇会のハイキングは生憎の雨となったが、自然の植物に取っては恵みの雨。多少濡れることはあっても、今日の雨をいやと思うことはなかった。箕面国定公園の自然を心行くまで楽しんだ。
2013.06.15
コメント(0)
-

図書館へ行っただけ
今日は、午後図書館へ行っただけで、殆ど一日中家で過ごし、句集を読んだり、俳句を作ったり、図書館で借りたDVDで映画「雪の女王」を見たりした。今日の画像は、マンションの部屋から撮った写真。回りや近所に高いビルが建ち景観が悪くなったが、大阪城の上方は辛うじて見えている。「雪の女王」はアンデルセン童話を映画化したもの。2000年デンマーク作品で、DVDは2005年に日本語版が作成されたもの。図書館では、もう一つのDVD「くるみ割り人形」を借りたが、まだ見ていない。
2013.06.14
コメント(0)
-

高大2年目の7日目
今日は、高大2年目の7日目。午前中は、「文章の書き方2」と「校正の仕方」の講義で、午後は、共通講座で「社会とつながりポジティブに生きるシニア達」という講演だった。文章の書き方の講義は参考になったこともあったが、校正についてはプロでもない趣味の物書きなのであまり必要ではないことではないかと思った。午後の講演の講師は大阪大学の佐藤真一教授。マイクの調子が悪くよく聞き取れなくて残念だった。高齢者社会に向っていることはわかったが、どうすればよいかについてはあまり参考にならなかった。キーワードは、「青春への回帰」、「地域デビュー」、「知的好奇心」・・・画像は、上記講演の中で示された1950以後10年ごとの人口ピラミッド。上左kら1950年、1960年、1970年、中左から1980年、1990年、2000年、下左から2010年、2020年、2050年。、、
2013.06.13
コメント(0)
-

春麗句会に参加
今日は、午前中は句集を読んだり、図書館へ行ったりして過ごし、午後は春麗句会に参加した。帰宅後は、図書館で借りた「ピノキオ 制作70周年記念スペシャルエディション」を見た。70年前の1940年に制作されたものと較べて格段にきれいになっていた。春麗句会には5句出句したが先生から3句が選ばれ、残り2句のうち1句が仲間から選ばれ、1句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 ◎青嵐琵琶湖観光船速む こっぱん (先生特選) ◎耳澄ませ夏野の中で鳥探す こっぱん (先生特選) 〇青簾京の町家の二階窓 こっぱん (先生ほか2票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・十薬にプラス思考を教えらる こっぱん (1票)今日の写真は、マンションの庭にあるザクロの木に咲き始めた花。
2013.06.12
コメント(0)
-

K病院へ検査に行く
今日は、午前中はK病院へ行き、糖尿病の負荷検査を受けた。2時間かかったが、結果は後日分かる。午後は、昨日の句会のまとめを行った。今日の写真はマンションの庭に植えられている紫陽花。咲き始めているが、雨が少ないのであまり精彩がない。
2013.06.11
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は句会の資料をプリントしたり、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の成績は、まずまず~いい方で、5句のうち先生から2句が選ばれ、残りの3句のうち2句は仲間から選ばれ、1句は誰からも選ばれなかった。先生から選ばれたのは次の句。 〇小雨よし雨後されによし花菖蒲 こっぱん (先生ほか5票) 〇斎の日の句会定時に始まりぬ こっぱん (先生)仲間から選ばれたのは次の句。 ・蟻地獄吾もスランプ抜け出せず こっぱん (3票) ・先延ばしもはや限界草むしり こっぱん (3票)今日、千世の特選に鰓茨田のは次の句。 ◎草取れば狭きわが庭広く見ゆ 愛子 (先生特選ほか2票) ◎草取りも腰のご機嫌次第かな 光祐 (先生特選ほか2票) ◎一瞬に蟻すべり落つ蟻地獄 豊子 (先生特選)今日、最多得票と集めたのは、上記こっぱんの花菖蒲の句。先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎草むしり草の匂ひを身にまとひ 塩川雄三先生 (4票)写真は、句会会場の前の歩道橋にところで、今年も咲き始めて海紅豆(でいご)の花。
2013.06.10
コメント(1)
-

DVDで「おくのほそ道を歩こう」を見る
今日は、一日中家にいて、午前中は、テレビでNHK俳句や日曜美術館を見たり俳句を作ったりしながら過ごした。午後からは、図書館で借りたDVDで「おくのほそ道を歩こう2」を見た。日曜美術館では、日本の江戸絵画を収集しているジョープライスとファインバーグのコレクションが紹介されていた。日本人に評価されずに見捨てられていた名品を含め、外国人の審美眼の高さに敬服した1時間だった。「おくのほそ道を歩こう2」は月山から敦賀までの旅だった。画像は、ビデオキャプチャーより。タイトル、芭蕉像、黛まどかと榎本孝明、月山、鶴岡・象潟、親不知・市振、富山、芭蕉と曾良、芭蕉が使った竹杖、素龍書の原本、同・書き出し、DVDの内容。
2013.06.09
コメント(0)
-

DVDでバレエ「ライモンダ」を見る
今日は、午前中図書館へ行った以外は一日中在宅で、午後は図書館で借りたDVDでバレエ「ライモンダ」を見た。「ライモンダ」は、ロシアの作曲者グラズノフの作。2009年新国立劇場バレエ団の演技。中世の南フランス。プロヴァンス城のライモンダ姫に婚約の証のヴェールを渡し、騎士ジャン十字軍の遠征に出掛けるのだった。城ではライモンダの誕生会で開かれ、サラセンの王子アブデラクマンも招待されていた。彼はライモンダに心を寄せる。アブデラクマンがライモンダを略奪しようとしたとき、ジャンが帰って来る。二人は決闘をしジャンが勝つ。ライモンダとシャンの結婚式で幕となる。シンプルなストーリーであるが、それぞれの中味が濃く、心の中を表わすような様々が踊りが散りばめられている。踊り(バレエ)だけを純粋に楽しむための作品だ。始めて見たが、今度は大型画面でもう一度見たいと思う。このDVDでは、主役のライモンダをロシアのバレリーナ、ザハロワが演じている。
2013.06.08
コメント(0)
-

DVDでバレエ「白鳥の湖」を見る
今日は昼に外食に出た以外は一日中在宅で、午前中は句集から秀句の抽出を行い、午後は図書館で借りたDVDでバレエ「白鳥の湖」を見た。「白鳥の湖」は3年前の2月5日に見てブログにも書いているのだが、内容を忘れてしまったので、もう一度見たいと思ったもの。前回のビデオはボリショイバレエ劇場のものだったが、今回のは日本の新国立劇場のもの。時間も前回のが80分だったのに対して134分と長い。特に第3幕が長く、各国の踊りをいろいろ見せてくれていた。ろーと平穏に暮らしていたオデット姫は、ある日突然悪魔ロートバルトに連れさられ白鳥に変えられてしまう。夜の間は人間に戻るのだが、朝になると白鳥になる。ある夜、ジークフリート王子がそのオデット姫を見初め、花嫁を決めるための舞踏会に招待する。舞踏会には悪魔の娘オディールが来ていて王子はオデット姫だと思って求婚する。そのためオデット姫とは結婚できなくなるのだが、悪魔に騙されたと知った王子が悪魔に決闘をしかけ悪魔を倒す。悪魔が倒れると魔法が解け白鳥が姫に返る、というストーリーだ。画像は、DVDの解説書より。解説書表紙、題1幕 乾杯の踊り、第2幕 悪魔ロートバルト、4羽の白鳥の踊り、第3幕 花嫁候補のワルツ、ナポリの踊り、ハンガリーの踊り、王子を誘惑する悪魔の娘、題4幕 コール・ド・バレエ。4
2013.06.07
コメント(1)
-

高大2年目の6日目
今日は、高大2年目の6日目。エッセイの講義はなく、朝から社会活動についての話し合いを行った。話合いは午後も予定されていたが、午前中で終り、午後は、班別の行動で我々の班は隣りの「パル法円坂」で款談を行った。社会活動の日は、9月と2月に一日ずつ2回あるが、9月はクラス全体で、2月は班別の行動とすることになった。社会活動と言っても、施設の見学から慰問までいろいろな形態があるが、クラスの多数意見は施設見学であった。このような社会活動の行先について、昨年は半日のクラスミーティングで決めたが、今日は一日が設定されていた。午前中の授業がない分、損をした気分である。結局一日は使われず、午後は自由時間になってしまった。今日の写真は、難波宮公園にあるトベラ。花が終り白い実が付いている。
2013.06.06
コメント(0)
-

山田盟子の「従軍慰安婦」
今日は、昼飯を外食に出たほかは一日中在宅で過ごした。メール、俳誌読みその他雑事のあと、先日図書館で見かけて借り出していた山田盟子の「従軍慰安婦」を読んでみた。橋下発言で物議をかもしだしている従軍慰安婦だが、その実態がどんなものだったのか、断片的に聞きかじっているに過ぎなかったので、もう少し知っておきたいと思ったのだ。「従軍慰安婦」は山田盟子が1993年に書いた小説である。主人公は黒須かなという芸妓あがりの従軍慰安所の経営者。日本から中国に渡り各地で目にした従軍慰安婦の惨状、日本軍の中国住民に対する略奪、暴行の数々が生生しく綴られている。情景を思い浮かべるだけでも陰鬱な気持ちになり、なかなか読み進むことができない。これ以上読みたくないと思うほどで、3時間ほど読んだがまだ半分も進んでいない。山田盟子は1926年宮城県生れのノンフィクション作家、ジャーナリスト。1991年に出版した「慰安婦たちの太平洋戦争」がベストセラーとなり、「続慰安婦たちの太平洋戦争」「慰安婦たちの太平洋戦争 沖縄編」と続き、1992年「占領軍慰安婦」、1993年「娘子軍哀史」、1993年「従軍慰安婦」と続く。その後も、1996年「ニッポン国策慰安婦」、2003年「女郎花は詩えたか」などを発表。最新刊は、2009年「従軍慰安婦たちの真実」である。彼女の記述の出典は、当時の状況を目撃した生存者からの話だが、誇張や作り話も含まれているという批判も多数出されているようだ。
2013.06.05
コメント(0)
-

淀川ウォーキングと関俳連の会議
今日は、高大同窓会の一つ「東淀川」のイベントで淀川のウォーキングに参加した。夕方からは関俳連(関西俳誌連盟)の常任委員会に出席した。10時に阪急淡路駅に集合、赤川鉄橋、蕪村句碑、毛馬の閘門等を巡るウォーキングのあと、天六まで行き「かんろ」という店で鉄板焼きを食べた。参加者は15名だった。写真は、淡路駅前での集合、赤川鉄橋、同、同、蕪村句碑、毛馬の閘門、淀川洗堰の跡、第一閘門の跡、鉄板焼屋。
2013.06.04
コメント(0)
-

図書館へ行っただけ
今日は、午前中一時図書館へ行っただけで、あとは一日中家で過ごした。俳句の雑誌を読んだり、俳句を作ったり、その他資料の整理など雑事でつぶれてしまった。今日の写真は、先日(5月29日)に彦根城の中堀で見た白鳥。黒鳥もいるそうだがこの日は見なかった。これは渡り鳥のコハクチョウではなく、留鳥のコブハクチョウだと思われる。
2013.06.03
コメント(0)
-

一日中家で過ごす おくのほそ道
今日は、一日中家で過ごした。テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見たり、図書館で借りた「趣味悠々 おくのほそ道を歩こう」のDVDを見たり、雑事で過ごした。「おくのほそ道・・・」は、芭蕉が旅した奥の細道のルートを、黛まどか(俳人)、榎木孝明(俳優、画家)の二人が辿るもので、9回シリースのものである。それぞれ最寄の駅まで電車で行き、徒歩とタクシーを使って一日で回れるところを紹介している。毎回、黛まどかの俳句と榎木孝明の水彩画が発表される。画像は、DVDのビデオキャプチャーから。
2013.06.02
コメント(0)
-

ガラコンサートへ
今日は、午前中は昨日までの旅行の資料の整理をしたり、メールを書いたりしながら過ごし、昼前から出て、西宮のアミティホールで開催された「震災復興祈念のガラコンサート」を聴きに行った。11時20分の阪神梅田発の特急に乗り、会場には11時40分に着いた。12時から座席券を交換するための長い列が出来ていた。いつもよりずっと長い。やはりガラコンサートということで好評なのだろう。12時5分前から引き換えが始まり、私が引き換えたのは12時5分頃だった。席は前から3列目、中央より少し右寄りで、絶好の場所だった。駅前の和食屋で昼食を取り、開演13時半直前に席に着いた。6組のアーチストによる22曲の演奏が、途中10分の休憩挟んで演じられ、最後にアンコール曲が演じられた。3時間たっぷりの充実した内容であった。プログラムは下記の通り。1.水木誠:いのり (島崎央子) ピアノ2.ベートーヴェん:月光ソナタ 同3.エルガー:愛の挨拶 (稲庭 達) ヴァイオリン4.サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン 同5.葉加瀬太郎:情熱大陸 同6.サルトリ:タイム・トゥ・セイ・グッバイ (トゥジュール) サックス7.福島民謡:会津磐梯山 同8.さとう宗幸:青葉城恋唄 同9.レノン/マッカートニ:ヘイ・ジュード 同10.スペイン民謡:セビジャーナス(弥月大治&西田祐加ほか) フラメンコギターほか11.ジプシー・キングス:ボラーレ 同12.スペイン民謡:アレグリアス 同13.C.フランソア:マイ・ウェイ 同14.臼井真:しあわせ運ぶように (ヴォーチェ・ベルステラ) 合唱15.シューベルト:菩提樹 同16.菅野よう子:花は咲く 同17.辛島美登里:サイレント・イヴ 同18.小田和正:言葉にできない 同19.中島みゆき:糸 (森下知子&大島忠則) オカリナとピアノ20.浜 圭介:そして神戸 同 サックスとピアノ21、ビゼー:カルメン組曲 同 オカリナとピアノ22.A.マクブルーム:ザ・ローズ 同 サックスとピアノアンコール曲は、稲庭 達のヴァイオリンでチャルダッシュ、弥月大治らの津軽三味線などが演じられた。今回の入場者は1400人以上で一部立ち見の人も現れるほどだった。写真は、島崎央子、稲庭 達、トゥジュール、弥月大治&西田祐加ほか、ヴォーチェ・ベルステラ、森下知子&大島忠則、稲庭 達、弥月大治&園田健介、全出演者18名。
2013.06.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 西川 ダウンケット入でお買得♪秋冬準…
- (2025-11-24 05:50:06)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 冬の準備、雪吊り。そして久しぶりに…
- (2025-11-24 03:54:14)
-