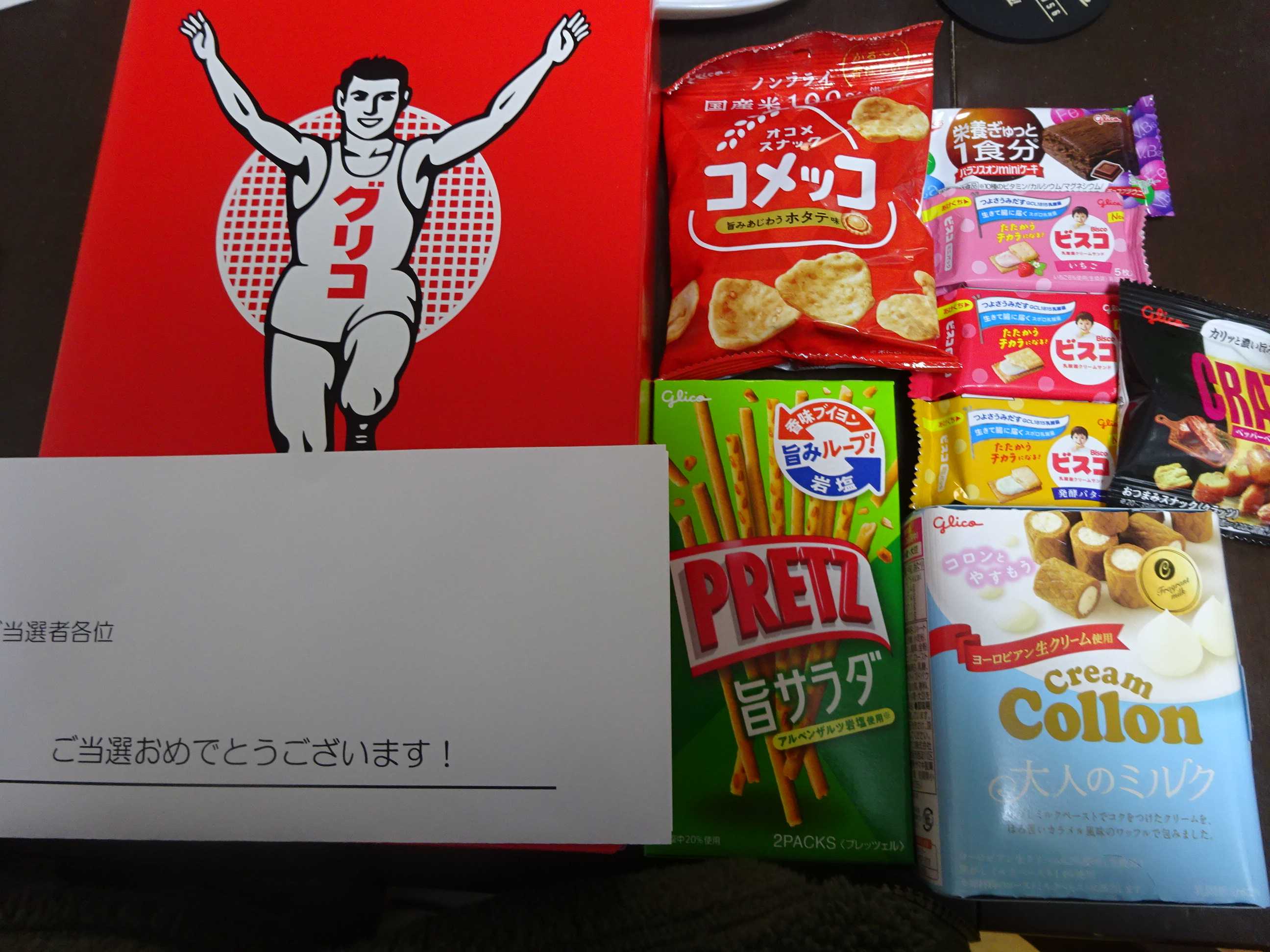2013年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

第九の練習3日目
今日は、午前中は、句会資料の挿絵入れを行ったり、エッセイの宿題を書いたりしながら過ごし、午後は、10000人の第九の練習3日目に参加した。写真は、上:練習会場の模様、下左:枯死したトベラ、下右:アオギリの実。第九の練習に来て楽しいのは、自分はテノールを歌っているが、他のパート(ソプラノ、アルト、バス)のメロディも聴くことができることである。コンサートへ行っても各パートの混じった合唱を聴くだけであるが、各パートのメロティが聴けるのは、練習に参加する者の得典である。しかも、一人の歌声でなく、大勢の斉唱で聞けるのである。各パートに分けると、ソプラノのメロディ以外は、単調なメロディになる部分が多いが、中にはきれいな旋律になるところもあり、そこが楽しい。
2013.08.31
コメント(0)
-

「浮世絵の夏」、「八重の桜」を見る。
今日は、10時ごろから出掛け、京都伊勢丹で開催されている「浮世絵の夏」という展覧会と京都文化博物館で開催されている「八重の桜」という展覧会を見に行った。「浮世絵の夏」は40分ほどで見たが、「八重の桜」は2時間20分もかかった。画像はパンフレットより。左:四条納涼(月岡芳年)ほか、右:四条河原夕涼の図(歌川国貞)、海老蔵の助六(二代歌川豊国)、納涼の夕月(歌川国貞)、中夏夕涼の図(歌川国貞)、四条河原夕涼(歌川広重)、両国花火(歌川広重)、東都両国橋夕涼図(渓斎英泉)、涼み舟(歌川国芳)夏の風物を題材にした浮世絵ばかり120点が展示されていた。展示は、納涼、花火、四条河原(川床)、浴衣、団扇などに分類されていた。江戸の納涼は、隅田川を納涼船で楽しむことが特徴。屋形船、屋根船、猪芽船、花火船、うろうろ舟など。浮世絵の作家は、歌川国貞、国芳、広重が大半だった。画像はパンフレットより。左:新島襄と八重(写真)ほか、右:赤楽島台茶碗、ガベール銃、洋食器、紫檀能尽蒔絵煙草盆、藍縮緬菊花模様小袖、家訓、加茂行幸図屏風、奥羽列藩同盟旗、鶴ヶ城古写真、新島旧邸、昭和3年京都会津会秋季例会記念写真。展示品は210点にも及び、次のように5つに分類されていた。第1章 会津の教え 家訓、日新館童子君など19点。第2章 幕末の京都 松平容保公肖像写真、孝明天皇御宸翰など50点。第3章 会津落城 奥羽列藩同盟旗、白虎隊自刃図、スペンサー銃など47点。第4章 古都復興-覚馬と襄 京都博覧会目録、新島八重遺品、襄遺品など60点。第5章 ハンサムウーマンへ 勲6等宝冠章、赤楽茶碗壽、茶入萬代など33点。
2013.08.30
コメント(0)
-

図書館へ行っただけ 「江戸時代の天満展」
今日は、一時府立中之島図書館へ行ったほかは、家で本(佐藤愛子の「娘と私の部屋」)を読んだり、宿題のエッセイを書いたりして過ごした。中之島図書館では、特別展示「天満」のギャラリートークを聴いたあと、ハリーポッターの最終シリーズ「死の秘宝」を借りた。画像は、中之島図書館のギャラリートーク「絵図と地図に見る江戸時代の天満」。江戸後期の武家屋敷、大塩平八郎邸、川崎東照宮、天満宮、天満青物市場、蔵屋敷などがどこにあったか、学芸員から古地図や浮世絵、古書などを参照しながら説明を受けた。佐藤愛子の「娘と私の部屋」は中学~高校生時代の娘との会話が中心だが、母子両方の心理がよく表されて面白い。ただ、私は男性なので、女性の心理が分からず、そういうものといい程度の理解しかできないが、娘を持つ女性が読めば、もっと面白いのであるう。
2013.08.29
コメント(0)
-

わいわいパソコンの例会
今日は、午前中は、佐藤愛子のエッセイ「娘と私の部屋」を読んだり、DVDで「天山北路を行く」を見たりしながら雑事で過ごし、午後は、わいわいパソコンの例会に参加した。例会は、インターネットに接続できる部屋を予約した積りだったが、世話役の手違いで普通の会議室だったため、予定されていたインターネットの繋ぎながらの勉強はできず、パソコン一般のことを話し合った。 それでも主題はインターネットのこと、その他、ワード、エクセルなどによる図形、写真の取扱い、パソコンに現れる警告メッセージなどの話題も出た。例会のあとはいつもように2次会となった。写真は、N氏紹介のお気に入りの項目と整理方法、警告メッセージの取り扱い、2次会風景。このような警告メッセージは、有料サイトに引き込むものなので無視すればよい。2次会で出たポテトのから揚げは、「北あかり」という銘柄。とてもおいしかったので、早速ネットで注文した。
2013.08.28
コメント(0)
-

午後図書館と眼科へ
今日は、午前中は昨日の句会のまとめを行い、午後は、図書館へ行ったあとK病院の眼科へ眼鏡の処方箋を作りに行った。図書館では、佐藤愛子の「娘と私の部屋」と、池部良の「風が吹いたら」を借りた。今日の画像は、難波宮跡公園の銀杏の木の股の窪みで成長を遂げていたトベラの若木。左上から、昨年9月13日、今年6月6日、7月25日、8月24日時点のトベラ。鳥に運ばれた種子が芽生えたものであるが、去年一年は無事に成長した。今年も7月25日に見たときは元気に成長していたが、この夏の異常高温と雨不足のため、8月24日には残念ながら枯死していた。自然は厳しいものだ。
2013.08.27
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は句会資料のプリントをしたり、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。2名が欠席投句となるので、その短冊書きもした。句会の結果はまあまあで、5句のうち1句が先生から選ばれしかも特選。残りのうち3句が仲間から選ばれた。1句はだれからも選ばれなかった。先生に選ばれたのは次の句。 ◎揃へども揃はざれども盆踊 こっぱん(先生特選ほか4票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・猛残暑吾を殺す気かも知れず こっぱん(4票) ・錆声の読経響けり施餓鬼寺 こっぱん(2票) ・鉦叩リズム楽器を担当す こっぱん(1票)今日、先生の特選に選ばれたのは上記のほか次の句。 ◎買ひ忘れまた買ひに出る盆用意 昇一(先生特選ほか1票) 今日、最高得票を得たのは、上記私の句。先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎朝顔の律儀に花を開きをり 塩川雄三先生(4票)今日の画像は、難波宮跡公園で実を付けたアオギリ。
2013.08.26
コメント(0)
-

高大夏の音楽会へ
今日は、午前中は淀川探鳥会へ行く予定だったが、大雨と雷が予報されていたため休み、家で日曜美術館などテレビを見て過ごした。午後は、相愛学園で開催された高大の夏の音楽会「世界の名曲」を聴きに行った。写真は、チラシを中央にコンサート風景。今日の出演者は、チェロ:斉藤建寛、ピアノ:細見理恵、ソプラノと三味線:掛水さよ、オーボエ:小林千晃、フルート:池本直絵、クラリネット:中平沙希の6人だった。曲目は、ヒューたーのTold at Twilight、バダジェフスカの乙女の祈り、バッヘルベルのカノン、ベートーベンのトリオ、ジョブリンのエンターテイナー、バッハのG線上のアリア、ロジャースのShall we dance(以上1部)、(以下2部)越谷達の助の初恋、貴志康一の力車、リストの愛の夢、カサドの信愛のことば、菅野よう子の花は咲く、中田喜直の夏の思い出、中村八大の上を向いて歩こう だった。
2013.08.25
コメント(0)
-

10000人の第九の練習、大阪の地震展、日本刀とヱヴァンゲリヲン
今日は、午前中は、句会資料の作成や俳句作りで過ごし、午後は、10000人の第九の練習の2回目、その後、大阪歴史博物館へ行き、「大阪の地震」展と「ヱヴァンゲリヲンと日本刀展」を見た。第九の練習は今年で2回目だが、先生の教え方は前回とはまったく異なる。ただ歌えるようになるだけでなく、意味を考えながら気持ちを入れて唄うことを強調される。、図は、パンフレットから。左:表面(地震鯰の取り調べ、ぢしんほうぼうゆり状のこと、震災調査広報チラシ)、右:上2枚:安政南海地震関係、2段目2枚:関東大震災関係、3段目左より:濃尾地震関係、北丹後地震関係、河内大和地震関係、昭和南海地震関係。最近500年の間に大阪に被害を与えた地震は17回起っているそうだ。図は、パンフレットより。左:表面(ロンギヌスの槍、弐号機仕様短刀式波プラグスーツ、零号機仕様脇差龍と槍、真希波マリプラグスーツ仕様短刀)、右上:弐号機仕様短刀式波プラグスーツ、右下:ロンギヌスの槍。ヱヴァンゲリヲンというアニメが知らないが、日本刀の名刀が見られるのかと思って入場したが、期待はずれだった。昔の名刀の展示は一刀もなく、ヱヴァンゲリヲンのアニメに描かれている刀を現代の名工が現実に作り出した名刀が展示されているのだ。いろいろなキャラクターが用いる刀、太刀、小刀、脇差、短刀、ナイフ、剣、槍など18点が展示されていた。日本刀については、その製作方法、各部の名称、歴史的な形状の変化、鍔の例などがパネルで展示されていただけだった。
2013.08.24
コメント(0)
-

一日中家で過ごす
今日は一日中一歩も外へ出ず家で過ごした。メールの返事を書いたり、俳句を作ったり、句集を読んだり、仏像のカタログを読んだりなどである。今日も大阪は猛暑日になり17日連続の記録を更新したが、夕方からは雨となり少し涼しくなった。今日は暦の上で処暑である。写真は、昨日奈良で撮った鹿とせんとくん。鹿は奈良国立博物館の前にて、せんとくんは奈良県庁玄関前にて。句集は茨木和生氏の新句集「薬喰」。難しいことばを使った句が多く、次の字が読めなかった。国栖奏、小綬鶏、大原志、地打、木耳、行々子、夜振、高擌、鵯、石蓴、此の君(を植う)、糠蚊(以上季語)、樏、橡、楤、柃、楢椚、皆伐、苦鱁、鮴、忌負、狩座、鑽り火、饐ゆる。読み方は順に、くずそう、こじゅけい、おおはらざし、いんじうち、きくらげ、ぎょうぎょうし、よぶり、たかはご、ひよどり、あおさ、このきみをうう、ぬかが(以上季語)、かんじき、とち、たら、ひさかき、ならくぬぎ、かいばつ、にがうるか、ごり、いみまけ、かりくら、きりび、すゆる。
2013.08.23
コメント(0)
-

講座「仏教美術へのいざない」3日目と「みほとけのかたち」
今日は、仏像講座の3日目。朝9時20分から2つの講座があり、午後からは、奈良国立博物館で開催されている特別展「みほとけのかたち」を見た。その後、大阪に帰り、難波のミュンヘン南大使館で開催された高大エッセイ科5班の懇談会に参加した。画像は、「みほとけのかたち」の図録の表紙。今日の講座は次のとおりであった。1.「仏像の心とかたち」 西山 厚氏(奈良国立博物館学芸部長)2.「仏像に会うー展覧会案内ー) 岩井共二氏(奈良国立博物館学芸部教育室長)どちらも、仏像鑑賞入門というような内容で、分かり易く有用な講座だった。午後からの展覧会を観る上での予備知識としても役立つものだった。午後は、昨日に引き続いて、じっくりと2度目の展覧会の鑑賞を行った。更に詳しく勉強をしたいと思い、図録(上図)を購入した。展覧会鑑賞のあと、難波に帰り、懇談会に合流した。メンバー9人のうち8人が参加して和やかな会となった。二次会は女性群の案内で、甘党屋に付き合わされた。
2013.08.22
コメント(0)
-

講座「仏教美術へのいざない」2日目と「みほとけのかたち」
今日は、仏像講座の2日目。朝9時20分から4つの講座があり、その後、奈良国立博物館で開催されている特別展「みほとけのかたち」を見た。画像は、パンフレットより。左:パンフレット表面、中:増長天(海住山寺)、薬師如来立像(元興寺)、十一面観音像(奈良国博)、弥勒菩薩立像(林小路町)、愛染明王坐像(奈良国博)、天寿国繍帳(中宮寺)、両界曼荼羅胎蔵界(小嶋寺)、馬頭観音菩薩立像(浄瑠璃寺)、右:菩薩立像(金龍寺)、薬師如来坐像(奈良国博)、釈迦如来坐像(法隆寺)、出山釈迦如来坐像(奈良国博)、誕生釈迦仏立像(個人蔵)、不空羂索官能菩薩像(個人蔵)、弥勒如来坐像(奈良国博)、伽藍神立像(奈良国博)、薬師如来立像(般若寺)今日の講座は次の4つだった。1.曼荼羅と密教の仏たち 森 雅秀氏(金沢大学人間社会学教授)2.仏教説話の美術 加須屋 誠氏(奈良女子大学文学部教授93.仏像の内部に込められた祈り―像内納入品の世界 佐々木 守俊氏(岡山大学准教授)4.仏像の荘厳-截金による荘厳 永井 洋之 (奈良国立博物館学芸部研究員)特別展「みほとけのかたち」は次のように分類されていた。1.みほとけのすがた 観る、服、髪、顏、姿勢(坐、立)、太、大などに分けて21点。2.みほとけのしるし 釈迦(多様)、手、色、光、座、持物などに分けて28点。3.みほとけのからだ 玉眼・彫眼、木、石、銅、金、土、乾漆、素材などに分けて14点。4.みほとけのなかに 納入品のあるほとけとその納入品4点。5.みほとけの霊験あらたかな存在 清涼寺、善光寺、南円堂、長谷寺、矢田寺、春日社、大仏殿など14点。6.みほとけの住処 当麻寺曼荼羅、天寿国繍帳など8点 7.みほとけの宇宙 両界曼荼羅2点通常の、時代蓴とか仏像の種類による分類と違って、面白い分類法で親しみが持てた。
2013.08.21
コメント(0)
-

夏季講座「仏教美術へのいざない」に参加
今日は、奈良国立博物館主宰の夏季講座「仏教美術へのいざない」に参加した。今日から3日間、9つの講座が行われ、今日は3講座があった。画像は、講座のレジメ集、日程表と講座の状況。、会場は、奈良県文化会館。参加者は約700名。今日は、10時半の開会のあと、館長の挨拶のあと、下記のとおり、午前中1件、午後2件の講座があった。 1.「彫刻史研究の六十年」 西村杏太郎(財 美術院国宝修理所理事長) 2.「半跏思唯惟像の成立と展開ーインドから日本まで」 宮治昭氏 名古屋大名誉教授) 3.仏像に見る奈良様と和様」 伊東史朗氏 (和歌山県立博物館長)お寺へ行けば必ず仏像を見ることになるが、仏像のどこを見ればよいか、この講座がそういう「仏像ファン」のための仏像入門講座のようなものだ。今日の話も大変面白かった。最終日の3日目の午後は、奈良国博で開催されている「みほとけのかたち」の観覧が予定されている。
2013.08.20
コメント(0)
-

一日中家で過ごす ザクロ
今日は、一日中家で過ごした。俳句関係の送付資料を仕上げて郵送したあと、高校野球の準決勝を見たり、茨木和生の句集「薬喰」を読んだりした。今日の写真は、マンションに植えられているザクロ。俳句会系の提出資料は、毎月20日が締切りで、その前の数日が忙しい。何でも間際にならなければ取り組まないという癖がいまだに続いているからだ。早め早めに済ませておけばいつも余裕のある生活が送れるのにと思うのだが、どうしてもそれができない。高大のエッセイの夏休みの宿題もまだ全然手をつけていない。これはまだ2週間先の話だ。
2013.08.19
コメント(0)
-

俳句21の句会に参加
今日は、午前中は、高校野球と見たり、句集の紹介文と書いたりしながら過ごし、午後は、千里中央の会場で行われた「俳句21」の句会に参加した。画像は、先日大川で見かけたカルガモ。句会は4句出句6句選で、私の句は、3句が選ばれ、3票、2票、1票の成績だった。それらと次に示す。 〇大輪の朝顔咲かす美容院 こっぱん(3票) 〇古里の山並照らす盆の月 こっぱん(2票) 〇アメジスト色の茄子漬白小鉢 こっぱん(1票)今日の句会で5票以上の得票を得た句は次のとおり。 ◎杉玉の乾ききつたる晩夏かな 良一(5票) ◎夏空の青深ければ青を着る 由紀子(5票) ◎鱧の皮遅れて笑ふ母とゐる タキ子(5票) ◎禄高は年金なれど鰻めし 良一(5票)私は、上記の句はどれも選ばなかった。私がいいと思っ田のは、次の句。 ◎鳴き声の中に泣き声蝉しぐれ 晴彦(2票)これは68年前の鞦韆日のこと。蝉時雨の中に敗戦で泣く人の声があったという。
2013.08.18
コメント(0)
-

10000人の第九の練習へ
今日は、午前中は、高校野球を見たり、子規の「墨汁一擲」を読んだりしながら過ごし、午後は、「10000人の第九」の練習に行った。第九の練習は全部で14回あり、今日がその第1回目。写真は、会場入り口の貼紙、ビアノと講師のマイク、会場風景、着席表。初めに、主宰の毎日新聞の担当者から、挨拶と注意事項などがあり、「今年の申込者は13000余名でそのうち10000人が当選で出演できることになった。」とのこと。ソプラノ:アルト:テノール:バスの比率は、3:4:1:1くらいで、女性が圧倒的に多い。本番は12月1日(日)。
2013.08.17
コメント(0)
-

K病院の眼科へ
今日は、午前中は、高校野球を見たり、子規の「墨汁一滴を読んだりして過ごし、ッ後は、K病院へ眼科の診察に行った。視力は落ちているが、白内障とか緑内障などはあまり進んでいないとのことだった。写真は、大川に入る水力療養バス「ダックツアー」。中央が川に入った瞬間。「ダックツアー」は梅田から毎日5便出ていて90分コース(陸60分、川30分)3600円。
2013.08.16
コメント(0)
-

盆施餓鬼で兄弟が集合
今日は、恒例の盆施餓鬼の日。毎年この日は、古里東近江に兄弟夫婦が集まり菩提寺の引接寺で盆施餓鬼が行われる。弟たちは夜中の間に出発で早朝に現地に着き、我々夫婦は大阪を朝早く発って東近江に向った。施餓鬼が終ったあと墓参りをし、昼食後、愛知川の瓶手まりの館などへ行った。写真は、施餓鬼が行われた引接寺、墓地、同、瓶手まり、同、同、近江上布会館、愛知川宿、同。瓶手まりの館へは、私は一度行ったことがあるが、弟達は知らなかったので、案内したもの。ここはお盆なのに開いていたが、近所の近江上布会館は盆休みのため見ることはできなかった。最後の中仙道の愛知淑を見に行ったが、少し雰囲気は残っているものの、古い町並みは殆どなくなってしまっていた。
2013.08.15
コメント(0)
-

春麗句会に参加
今日は、午後春麗句会に参加したほかは、殆どの時間を高校野球を見ながら過ごした。画像は、マンションの周りに咲いている百日紅。句会の成績はまずまずで、5句のうち先生から4句選ばれうち一句が特選だった。特選となった句は、、 ◎兄弟が揃ひ眺むる盆の月 こっぱん他の句は、 〇ドアノブの朝の手触り涼新た こっぱん 〇茄子の馬へたは頭で尻は尻 こっぱん 〇ぼたばたと果汁こぼして西瓜食ぶ こっぱん大阪桐蔭と日川の試合は、接戦でいい試合だったが、最後はさよならで桐蔭が買ってよかった。エラーをすれば点に結びつくし、いい守りをすればピンチも逃れることができるという見本のような試合だった。
2013.08.14
コメント(0)
-

東洋陶磁美術館へ
今日は昼過ぎまで、高校野球を見ながら、昨日の句会のまとめを行い、彦根東-花巻東戦が終ってから、東洋陶磁美術館へ「白檮廬コレクション-中国古陶磁晴玩」を見に行った。画像は、左:ポスター、右:彩陶双耳壺(新石器時代)、緑褐釉貼花連珠文碗(北斉~随時代)、青白磁刻花牡丹童子文花鉢(北宋時代)白檮廬コレクションとは、東洋陶磁美術館が、奈良県在住の収集家・卯里欣侍氏(号「白檮廬」)から寄贈を受けた中国陶磁、韓国陶磁、中国工芸品など約180点からなるコレクション。今回の展示では、コレクションの中核をなす中国陶磁から約90点を選び、新石器時代から清時代までの約5千年にわたる中国陶磁史を辿ったもの。展示は次のように分類されていた。・中国陶磁の幕開け(新石器時代~漢時代)・青磁の発展(三国時代~宋時代)・鉛釉陶器の展開(南北朝~唐時代)・白磁の誕生(南北朝~宋時代)・黒釉陶磁の多様性(宋・金・元時代)・磁器の時代(元・明・清時代)あまり大きな作品はないが、じっくり見ていても見飽きない美品ばかりであった。高校野球は、昨日は岩国商が負け、今日は、丸亀、彦根東、瀬戸内が負けてしまった。どちらか自分が何等かの関係がある方のチームを応援するのだが、やはり負けるより勝ってくれる方が嬉しいいし、気分もいいものだ。今日はそういう気分になれなかったが、選手は力一杯やっているので気持ちよい。
2013.08.13
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日。午前中は、句会資料のプリントをしたり、出句する5句の選定と最後の推敲などを行った。高校野球では岩国商業が出るので、応援しながら見ていたが、断念ながら前橋育英に接戦の末破れた。いい試合だった。写真は、句会会場前の梯梧の木。一度花が咲いたが、あとはまだ咲かない。いくつかの花は残っている。句会の方はまずまずで、先生から3句選ばれうち一句が特選。他の2句のうち一句は仲間から選ばれた。先生の特選にえらばれたのは次の句。 ◎地震持て選りし西瓜の不味かりき こっぱん(先生特選ほか1) 先生の選に選ばれたのは次の句。 〇打ち揚げに間合ひのあつて花火の夜 こっぱん (先生ほか1票) 〇赤煉瓦倉庫を巡り秋の海 こっぱん (先生)仲間から選ばれたのは次の句。 ・天の川まだ一橋も架けられず こっぱん (1票)今日、千世の特選にえらばれたのは、上記のほか次の句。 ◎漆黒の天に炸裂大花火 豊子 (先生特選)今日、最高得票を得た句は、次の句。 ◎探鳥の時に変調法師蝉 豊子 (先生ほか4票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎常温の酒を愛飲涼新た 塩川雄三先生 (4票)
2013.08.12
コメント(0)
-

一日中家で過ごす
今日も、大阪は今年一番の暑さを更新する日となった。一日中家にいて、俳句を作ったり、本を読んだり、テレビを見たりしながら過ごした。今日の画像は、昨日もらった「大大阪パノラマ地図」(1924年発行)発行所:日下わらじ屋、絵師:美濃部政治郎。中央公会堂の部分をいろいろな倍率で示した。この地図は鳥瞰図となっていて、良く見ると人や電車なども沢山書き込まれている。
2013.08.11
コメント(0)
-

トークサロン「おださくが歩いた大阪」
今日は、午前中は部屋の掃除を行い、午後は、中之島のアートエリアB1で開催された大阪大学21世紀懐徳堂塾主催のトークサロン「おださくが歩いた大阪」を聴きに行った。写真は、パンフレットおよびトークサロンの模様。中央上の写真は4人のパネル(右から、高橋、足立、出原、橋爪各氏。右はNHKのポスター。この催しは、おださく(織田作之助)の生誕100年を記念して作成されたNHKテレビドラマ「間音善哉」の放映を前のキャンペーンを兼ねて開催されたもので、出演は下記の4人だった。・高橋俊郎(大阪市立中央図書館副館長・オダサク倶楽部)・足立?(NHKテレビドラマ「夫婦善哉」制作担当ディレクター)・出原隆俊(大阪大学大学院文学研究科教授)・橋爪節也(大阪大学総合学術博物館館長)オダサクの歩いた大阪について、それぞれの立場からのマニアックな話が聴けてよかったが、まとめる人がいなくて、だらだらと続いたような感じだった。主として高橋氏と橋爪氏の話が多く、あとの2人の発言は少なかったが、司会がいて万遍に話を訊いた方がよいと思った。。話もさることながら、もらった「大大阪パノラマ地図」は有用な資料だ。拡大してよく見るといろいろ興味深いことが発見できるように思う。オダサクの作品に出て来る地名100ほどが明示されているのも嬉しい。なおNHKのテレビドラマ「夫婦善哉」は、森山未来、尾野真千子の主演で、8月24日(土)から4週連続で放映される予定。
2013.08.10
コメント(0)
-

一日中家で過ごす
今日は一日中家で過ごした。今年一番の暑い日だったらしく、何もしないでも汗が染み出るほどだった。高校野球を見たり、長崎原爆忌慰霊祭典を見たり、俳句を作ったり、「墨汁一滴」を読んだりしながら過ごした。今日の画像は、一昨日京都へ行ったときに七条大橋の上から撮ったカワウとアオサギの写真。
2013.08.09
コメント(0)
-

DVDで映画「クロッシング」を見る
今日は、図書館へ行っただけで、一日中家で過ごした。図書館では、DVDの映画「クロッシング」と「命のビザ」、本は、子規の「墨汁一滴」を借りた。始めに、昨日見に行った、京都国立博物館で開催されている「遊び」展のことを書く。「遊び」という現代の語感から想像していたものとは相当違った内容の展覧会であったが、「遊び」というものの歴史を学ぶことができた。図はパンフレットより。左:揚妃撃丸図(部分)、片身替縞蒔絵螺鈿双六盤、舞楽図屏風(部分)、花下遊楽図屏風(部分)、釉下彩鹿島踊図皿旭焼(部分)、玩具船豊臣棄丸用、右:源氏物語画帖(部分)、からくり人形大黒春駒、布袋唐子図(雪村筆)、綾杉地獅子牡丹葵紋蒔絵食器具、京洛年中行事図扇流屏風(狩野元信 部分)、享保雛大内雛、花下遊楽図屏風(部分)。遊びの原形は、神さまを喜ばせるためのもので、奉納という形で演じられた。それが人を楽しませるようになり、酒宴の楽しみ、年中行事(節目での厄除け)、遊山(観光)、遊興と形を変えながら民衆に広まった。文人の間では、清遊と言って琴棋書画をたしなむのが通とされた。動物との戯れも遊びの一つとなり、室内遊戯も進化してきた。そして大人の遊戯から子供の遊びへと広がったのだ。、展示は次の8つに分類されていた。第1章 神々から人へ 釉下彩鹿島踊図皿旭焼、舞楽図屏風など23点第2章 酒宴のたのしみ 綾杉地獅子牡丹葵紋蒔絵食器具など13点第3章 年中行事 京洛年中行事図扇流屏風(狩野元信)、享保雛大内雛など6点第4章 遊山 花下遊楽図屏風など10点第5章 遊興-芸能と大衆 片身替縞蒔絵螺鈿双六盤など13点第6章 清遊-文人のたしなみ 10点第7章 動物のたわむれ 揚妃撃丸図など7点第8章 室内の遊戯 源氏物語画帖など9点第9章 子供の遊び、雑技、曲芸 布袋唐子図(雪村筆)、からくり人形大黒春駒、玩具船豊臣棄丸用など37点。図は「クロッシング」の関連サイトより。「クロッシング」は2004年制作の韓国映画。ノ・ムヒョン大統領の下極秘に撮影が進められたが完成後も公開はできず、イ・イ・ミョンバク大統領に政権交代したあとやっと公開された。日本での初上映は2010年。ある脱北者の苦難の半生を描いたもので、父が先に脱北して家族を呼ぼうとするのだが、結末までに母が死んだり、幼い女友だちが死んだり、悲惨な出来事が続く。ハッピーエンドで終わらせたかった映画だだった。
2013.08.08
コメント(0)
-

恐竜ショウ、「遊び」展、義母の誕生会へ
今日は、午前中は、大丸梅田で開催されている「超・恐竜体験」というショウを見に行き、午後は、京都国立博物館で開催されている「遊び」展を見に行った。帰宅後、介護施設で行われた義母の満98歳の誕生会に出席した。画僧は、パンフレット、説明員、子供による恐竜クイズ、バルーン恐竜のブラキオサウルス(首だけ)、アロサウルス、同。ショウは、30分くらい。初めは説明員の女性が恐竜についての簡単な解説を行い、続いて恐竜クイズ、歯の形から恐竜の種類を当てるもの、続いて、バルーンによる首だけの恐竜を見せ、最後に実物大の縫いぐるみ恐竜アロサウルスが登場。全長6メートルに子供たちの悲鳴と歓声が入り混じる。10分ほどの時間だったが以外と長く感じられた。京都国立博物館の「遊び」展は、ちょっと変わった視点からの展示だった。詳しいことは明日紹介する。京都は猛烈な暑さだった。実はもう一つ博物館に行く予定だったが、取りやめて帰阪。介護施設で行われる義母の98歳の誕生会に駆け付けた。施設では黒板にきれいに飾り付けをしたり、スタッッフからのメッセージカードやカーディガンを贈ってくれたりして、祝ってくれた。義母は、やや認知症の兆候が出始めている程度で身体はまだまだ元気である。下の写真はその状況。
2013.08.07
コメント(0)
-

K病院へ、関俳連常任委員会へ
今日は、原爆記念の日、朝はテレビの中継に合せて被曝者に黙祷を捧げた。午前中はメールを買いたり、俳句を作ったりして過ごし、午後は、K病院へ診察に、夕方からは、関俳連の常任委員会の会合に出た。今日の写真は、7月に広島へ行ったときに撮った平和記念碑と原爆記念館。
2013.08.06
コメント(0)
-

「ミュシャ」展へ
午前中は、句会資料の挿絵探し、俳句誌「俳句界」を読んだりして過ごし、午後は、くらしの今昔館へ「ミュシャーくらしを彩るアールヌーヴォー」という展覧会を見に行った。画像は、パンフレットより。左:パンフレット表面・ジョブ、右上:モナコ・モンテカルロ、ランスの香水「ロド」、装飾資料集PL63、プラリネ・ゴーフルラベル、グラン・クレマン・インペリアル、アールヌーボー期の机、ビスケット缶、木製小椅子、右下:「ミュシャの横顔」展のパンフレット表面、ドライ・エンペリアル、シャンパン・ホワイトスター、スラブの民俗衣装を着た少女、1900年パリ万国博覧会ボスニア・ヘルツェゴビナ館壁画、ウミロフ・ミラー、クオ・ヴァディス。堺市にあるアルフォンス・ミュシャ館には二度行ったことがあるので、ミュシャの作品はよく見ているが、今回は近くで見られるので行ったみた。予想以上に多くの作品が展示されていて、その数大小合わせ140点に及んだ。ミュシャの作品はポスターが有名だが、そのほかにも宝飾品、家具、カーペット、パッケージ、カレンダー、絵葉書などいろいろな商品のデザインをしていたことを知った。なお、この展覧会には、ミュシャに感化を受けた西洋の作家の作品や日本の武田五一の木工作品も展示されていた。、
2013.08.05
コメント(0)
-

部屋の大掃除など
今日は、久し振りに部屋の大掃除をした。乱雑にあちこちに置かれていた資料類を整理し、捨てるものは捨て、保存するものは保存するようにした。ある程度きれいになったが、これ以上整理すると、あとで探し物が増え不便になるので、ほどほどにしておいた。今日は、写真を撮らなかったので、先日長い公園で撮った『緑のトンネル」の中の、南瓜、瓢箪、糸瓜、苦瓜。
2013.08.04
コメント(0)
-

関俳連の夏季吟行大会に参加
今日は、関俳連(関西俳誌連盟)主催の夏季吟行大会の日、あさ8時半に家を出て会場の宝塚へ向った。成績発表は午後1時から行われたが、私の句は2句とも選外だった。写真は、吟行地宝塚の、ハナの道、宝塚大劇場、夢の時計台、手塚治虫記念館、宝塚大橋から大劇場の景観、与謝野晶子の歌碑,大会横断幕、大会の模様、講評する選者の一人・塩川雄三先生。句会の参加者は160名、出句数は540句だったそうだ。選者は16人で各自が10句の入選句を選び、うち3句を特選句とした。初めに各選者から特選句の発表があり、選者から講評が行われた。16人の先生がそれぞれ選んだ特選句はさすがいい句が多く、みんな宝塚らしいいい句だと思った。優秀句は次のとおり。連盟賞 蟻の列大劇場へ向ひけり 熊本直文(俳句春秋)毎日新聞賞 八月の川が脱がせるハイヒール 寺西けんじ(杭)俳句文芸賞 一世紀見据え逸翁像涼し 高池秀和(俳句作家)担当結社賞 堰落つる水の腑抜けて川晩夏 木村良昭(俳句春秋)
2013.08.03
コメント(0)
-

「大阪湾」展、長居公園の蓮
今日は、午前中は句集からの句の抽出をしたあと、長居公園へ「大阪湾」展を見に行った。昼食のあと、長居植物園を散策した。写真は、左:パンフレット、右上:マッコウクジラの骨、展示会場の様子、スナメリ。展覧会の正式名は、「いきものいっぱい大阪湾~フナムシからクジラまで~」というもの。大阪湾の自然に関するいろいろなものが展示されていた。地形、歴史、魚類、鳥類、昆虫類、甲殻類、貝類、爬虫類、樹木、草花、海草など。大阪湾の古図面や絵、漁具、自然保護活動などの展示もあった。私が一番興味を持ったのは野鳥の剥製で、30種類ほどが展示されていた。写真は長居公園の蓮の花。長居植物園で今日咲いていた花は、百日紅、睡蓮、木槿、向日葵、糸瓜、瓢箪、苦瓜などであった。
2013.08.02
コメント(0)
-

下田実花の「ふみつつり」を読む
今日は、一日中家にいて、下田実花の「ふみつつり」を読んだ。その後、今日届いた俳句誌「一向」を詠んだ。今日の写真は最近見かけた花。木槿、木槿、姫向日葵、ゴーヤ。下田実花は俳人であるが、随筆集の文章がうまい。これは、高濱虚子の写生文塾「山会」で勉強した成果であることがわかった。
2013.08.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1