2013年11月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

第九のリハーサル
今日は、午前中は、句集を読んで過ごし、午後は、関西大学で開催された「大阪の近代」出版記念フォーラムを聴きに行ったあと、大阪城ホールで行われた「10000人の第九」のリハーサルに参加した。写真は、上3枚は「大阪の近代」フォーラムの様子、中3枚は大阪城ホールへ集まる団員たち、下3枚はホール内の様子。句集は、岬雪夫の「謹白」、辰巳比呂史の「はや米寿」と小西領南の「冬帽子」。「大阪の近代」は文科省の補助金事業での研究で、「大阪の近代」についての新しい事実を発掘・研究し、その知見をを本にまとめたもの。テーマは、女性の目覚め、大阪の工業化、衛生環境、道頓堀五座、大阪五花街、北船場の会社、大阪城の公園化構想、女性記者・北村兼子、織田作之助、司馬遼太郎など。話を聞いて面白そうだったので、早速購入した。第九のリハーサルは、4時半から始まり、発声練習、第九の練習、合唱曲「海その愛」、「アメージンググレース、「蛍の光」の練習と続き、7時10分に終了した。明日は、9時に集合、修了は18時ごろの予定。10000人が3000人の観客の前で歌うのだ。
2013.11.30
コメント(0)
-

職場OB会
今日は、朝から昨年の高大エッセイ科の同窓会の文集に投稿するエッセイを泥縄で書いた。それを郵送したあと、夕方から出掛け、職場のOB会に参加した。エッセイの題名は「私の日記ブログ」、私が当ブログを初めてから9年余の経緯を2000字にまとめた。読みなおしてみたが、あまりいいエッセイにはなっていない。しかし文才もないし、締切りぎりぎりの執筆だから仕方ない。参加することに意義がある。職場OB会は2か月前から幹事4人が協力して準備してきたもの。開会の1時間半前に集まり、名札の確認、会の進め方、役割分担などを話合い、横断幕の設置、映像の調整などを行った。5時半ごろから徐徐に参加者が集まり始め、開会の6時半には予定の81名が全員そろった。寒い日となったのに、全員遅刻もなく集まったのは凄いことであった。写真は、OB会の模様。開会直前、研究所の現状を説明するS氏、乾杯の音頭はW氏、歓談風景、同、同、集合写真3枚のうちの1、中締めの挨拶、幹事挨拶。開会の辞、物故者への黙祷、研究所の現状説明のあと、乾杯に映り、一年振りの会う懐かしい仲間との楽しい歓談の宴が始まった。宴もたけなわの8時過ぎに集合写真の撮影、続いて中締め、幹事挨拶となり、参加者は三三五五帰路に着いた。我々幹事が会場を出たのは9時15分頃だった。今年で12回目になるが、和やかないい歓談の場となり、参加の皆さんから労をねぎらう言葉をかけられ疲れも吹っ飛んだ気がした。しかし、まだこれから、写真整理や会計報告、郵送などの作業が残っている。
2013.11.29
コメント(0)
-

高大2年目の22日目
今日は高大2年目の22日目、午前中はエッセイ創作実習の6回目、宿題エッセイ「旅」を読み感想を述べ合った。午後は共通講座で田村典子先生(元関西大学教授)の「スポーツを通して健康を語る」と題した講演を聴いた。放課後はマジック同好会に参加した。エッセイは、15人の作品が読まれた。「旅」という題名なので、各自の作品は「忘れられない旅」というものが多く、思い出を懐かしく語るものだったが、中には、半日のツアーを旅と言ってみたり、人生を旅になぞらえて作品もあった。旅ができない事情を書いた作品もあった。同じ旅でも色々な切り口があるものだ。「スポーツを通して・・・」の講演は、高齢者の健康を人体物理学的に論じたもので、やや新鮮な感じであったが、田村式ストレッチ運動については本当に効き目があるのか疑問に思った。写真は、講演風景と使われたスライドの一部。マジックは、文化祭で演じる「ニチリン」の練習をしたあと、新しいカードマジックを2つ習った。1.カードから2つの山を作りどちらかを選んでもらう。「あなたは7の方を選びます」の予言が見事的中する。2.13枚を2組作り、各組とも、13からカウントダウンしながらカードをめくっていき、数が一致したら、残りの札を演者に渡す。2組目も同じ。2つの山の出ている数の合計枚数だけカードをめくっていくと、枚数番目のカードは予言された通りのものになっていう。
2013.11.28
コメント(0)
-

嵐山へハイキング
今日は、わいわいパソコンのメンバーで、嵐山へハイキングに行った。鳥居本から清滝、清滝から落合を通って鳥居本に帰るコースだ。午前中は紅葉晴のいい天気、午後は少し雲が出て雨も少しパラついたが、傘を差すほどのこともなく一日中紅葉三昧の一日を楽しんだ。写真は、渡月橋から、落柿舎、化野念仏寺、鳥居本、清滝隧道、清滝川、昼食、落合、二尊院付近。梅田を8時59分発の特急に乗り、桂で乗り換え、阪急嵐山には9時49分に着いた。今日の参加者は11名。駅前でTさんのリードによる準備体操をして、ハイキングに出発した。11:28渡月橋を渡り、11:35天龍寺の境内を抜けて、10:55野々宮神社、11:12落柿舎、11:41化野念仏寺などの前を通り、11:51鳥居本にを着いた。ここで道は2つに分かれるが、昼食を急ぐためトンネルのある道を選んだ。清滝隧道は5分ほどで抜けると川音が聞えて来た。昼食場所の水辺に12:26到着。各自持参の弁当を広げる。Nさん持参の柚子酒をいただく。その他、昆布と松茸の佃煮、チョコレート、飴、煎餅、柿、ドライフルーツなどを皆さんからお裾分けされる。午後は、さらに上流の神護寺まで行くべく計画されていたが、雲が出始めたため断念。再び鳥居本まで戻ることにした。帰りは道を変えて落合まで渓谷を歩くコース。13:17落合へ向って出発。紅葉と渓流を堪能しながら13:55落合に着く。そこから峠越えの道を取り、14:17峠を通過、14:30鳥居本に到着した。帰りは清涼寺に立ちより15:10-15:20まで休憩、阪急嵐山で15:57発の電車に乗り、梅田には16:53に着いた。梅田でビールを飲んだあと18:30頃に解散した。楽しい一日だった。万歩計は25000歩だとか。このグループは健脚揃い、酒豪揃いだといつも思う。
2013.11.27
コメント(0)
-

OAPのクリスマスツリー
今日は、ほぼ1日中家にいて、昨日の句会のまとめを行ったあと、高大の宿題のエッセイを書いた。また、職場OB会の参加者名簿の作成を行った。今日の写真は、22日に点灯されたOAPのクリスマスツリー。
2013.11.26
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は、出句する5句の選定と最後の推敲を行った。句会の結果は惨々だった。先生から選ばれたのは一句のみ。他の4句のうち2句は仲間から選ばれたが、2句は誰からも選ばれなかった。今日先生から選ばれたのは次の句。 〇神の留守宮司も巫女も羽根伸ばす こっぱん(先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・終末を美しく生き紅葉散る (2票) ・冬の山少し青さの残りゐて (1票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎枯山の律儀に谺返しをり 豊子(先生特選ほか2票) ◎居眠りも趣味の内なり日向ぼこ 隆司(先生特選ほか1票)今日、最高得票を得たのは次の句。 ◎巫女二人話の弾む神の留守 茲子 (先生ほか3票) ◎枯蟷螂身構へ斧を崩さざる 昇一 (先生ほか3票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎音もなく深い空から紅葉散る 塩川雄三先生(3票) ◎小春日和ぼんやりと日を過ごしをり 塩川雄三先生(3票)写真は、天満橋八軒屋浜の夕景。上左:天神橋を見る、上右:天満橋を見る、下:アクアライナー。
2013.11.25
コメント(0)
-

淀川探鳥会 その後第九の佐渡レッスンへ
今日は、午前中は、淀川探鳥会に参加し、その後、第九の佐渡レッスンに参加した。探鳥会では、天気もよく珍しい鳥や変わった生態などを観察することができ、大変有意義に過ごすことができた。珍しい鳥は、イソヒヨドリ、ハッカチョウ、ハイタカ、チョウゲンボウなど。珍しい生態はカワウの大群だ。珍しい植物(ヤノネボンテンカ)も見た。ハイタカを見るのは珍しいそうだ。また、チョウゲンボウは2羽がもつれ合いながら飛んでいた。オオジュリンは声は聞こえていたが、なかなか止まっているところは見られなかった。写真は、ユリカモメとセグロカモメ、イソヒヨドリ、ハッカチョウ、カワウ、モズ、オオタカ、オナガガモ、オオバン、アオサギ。今日見た鳥は、写真の10種のほか次のとおり。 ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カンムリカイツブリ、キジバト、バン、イソシギ、ウミネコ、チョウゲンボウ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、セッカ、ムクドリ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、ベニマシコ、ホオジロ、アオジ、オオジュリン。全部で37種。佐渡レッスンは15時半から17時まで、エルシアターにおいて1000名の合唱団員を集めて行われた。ソプラノ400、アルト300、テノール150、バス150くらいの比率であった。発声練習から始まり各セクションごとに厳しいながらも和やかなレッスンであった。
2013.11.24
コメント(0)
-

鴨川の鳥
今日は、いいお天気で絶好の行楽日和だったが、一日中家にいて、俳句を作ったり、エッセイを書いたり、パズル年賀状を考えたりしながら過ごした。今日の写真は、昨日京都へ行ったとき、七条大橋の上から見た鳥たち。マガモの雌雄、ダイサギ、アオサギである。ユリカモメはまだ見かけない。
2013.11.23
コメント(0)
-

「清朝陶磁」展を見る
今日は、昼前から出掛けて、京都国立博物館で開催されている「魅惑の清朝陶磁」展を見に行った。大阪を10時発の新快速に乗り、11時に会場に着いた。一時間くらいで見る積りだったが、展示数が多く、いい作品も多かったため、見終わったら13時だった。ちょうど2時間かかったことになる。画像はパンフレットより。中国陶磁は、大阪の東洋陶磁美術館で何度も見ているので、あまり珍しいものではないのではないかと思っていたが、意外にきれいな作品や見たこともない造形のものがあり、見応えがあった。東洋陶磁美術館の作品は唐時代から清朝以前のものが多いの対して、今回の展示物はより技術の高い清朝陶磁に限っているので、美しさ、鮮やかさが際立っているのだろう。展示品は212点あり、次のように分類されていた。第1章 行き交う唐船 (オランダの倍の交易量だった) 唐館蘭館図絵巻など13点第2章 出土品が語る (有田焼の全盛時代も輸入されていた) 京都市内遺跡出土清朝陶磁など3点第3章 独自の回路 青花楼閣山水図手付水指、粉彩花卉文紫泥水注など23点第4章 日本からの注文 (日本から清に発注して焼かせた) 青花菱馬水指など21点第5章 旧家伝来の清朝陶磁(角屋、究理堂、田中本家ほか) 粉彩絵替皿(十錦手)、金琺瑯高足杯など63点第6章 江戸時代の中国趣味 染付牡丹唐草鳳凰文透彫大皿など58点第7章 清朝陶磁と近代日本 粉彩梅花喜鵲図象牙瓶、粉彩松鹿図瓶など49点エピーローグ 五彩浮世絵蓋壺など2点展示物は清朝(中国)産の清朝陶磁だけでなく、日本で本物を真似て作られた清朝陶磁も混じっていた。第6章、第7章で日本製が多く、第6章では23点、第7章では23点だった。中には、フランス、イギリス製の清朝陶磁もあった。和歌では、昔の優れた歌の一部を取って新しい歌を作ることを本歌取りというが、陶磁の場合でも、本歌取りと言うらしい。
2013.11.22
コメント(0)
-

高大2年目の20日目
今日は、高大2年目の20日目。午前中は、エッセイについて鶴島先生の白熱教室が行われた。瀬戸内寂聴のエッセイと岡潔のエッセイとを読み、その感想を述べ合った。一人ひとりその感想が異なるのが新鮮な驚きであった。エッセイの内容に賛同する者、反論する者、私のようにただただ感心する者など。午後は、文化祭に向けての準備と、班員のエッセイの合評会。放課後は、マジック同好会に参加した。マジックでは、文化祭用のマジックの練習のあと、ボトルの水が焼失・出現すつマジックを習った。今日は、写真を撮らなかったので、先日撮った写真を載せる。下は、14日夜の大阪城。蒼いライトアップは、世界糖尿病デーを記念して全国一斉に行われたもの。
2013.11.21
コメント(0)
-

恵沢園の菊
今日も、大変寒い日になった。どこへも出ないで一日中家で過ごし、俳句の提出物やエッセイの宿題などをこなした。画像は、昨日行った大阪市立美術館の庭、恵沢園に飾られている菊の花。
2013.11.20
コメント(0)
-

「大阪の至宝」を観る
今日は、午前中は、俳句関係の提出物などの作成や職場のOB会の準備などを行い、午後は、大阪市立美術館で開催されている「再発見!大阪の至宝」という展覧会を見に行った。画像は、パンフレットより。今回の展覧会は、大阪市の美術館・博物館が所蔵している作品の中から選りすぐりの165点を一堂に展示したもの。市立の美術館、博物館所蔵のものばかりなので、これまで何度か見たことのあるものもたくさんあったが、初めて見るものも半分以上はあったと思う。とにかく大量の展示でしかもすべてが見応えのあるものばかりなので、ざっと見て回るだけで優に2時間はかかった。しかし、観客は少ないのでじっくりと見ることができた。同じような企画の展覧会が京都で「京都・美のタイムカプセル」という題で開催されたが、こちらは大勢の観客で混雑していたのと比べ、雲泥の差であった。大阪人の方が美術への関心が低いようである。展示は次のように分かれていた。1章 中国・韓国美術へのあこがれ 阿部コレクションの書画、安宅コレクション、李乗昌コレクションの陶磁器、小野コレクション、山口コレクションの仏像など42点2章 日本美術の豊穣 前田コレクションの絵画、田万コレクションの仏像、絵画、武藤氏寄贈の尾形光琳関係資料、中島氏寄贈の工芸品・絵画、南木コレクションの浮世絵、田原コレクションの鍋島焼、カザールコレクションの根付や調度品、山本コレクションの墨跡、絵画、寺社から寄託の国宝など102点3章 私立美術館に開花したコレクション 泉屋博古館所蔵の古代中国青銅器、黒田古文化研究所所蔵の中国の鏡、滴翆美術館所蔵の京焼の名品、藤田美術館所蔵の茶道具の名品、逸翁美術館所蔵の絵画など7点。4章 大阪近代美術の諸相 住友コレクションの絵画12点、昆虫標本2点会場では、今回の展覧会の説明映像(9分間)が映されていた。また、入場者には、全展示品のリストと、主な展示作品40点がからーで掲載されている小冊子(16ページ)が配付された。美術館のうしろの恵沢園では、菊による装飾が行われていて、きれいであった。
2013.11.19
コメント(0)
-

「大黄金展」を観る
今日は、一時外出した以外は、家にいて句集を読んだり、句集の紹介文を書いたりして過ごした。外出は、高島屋で開催されている「大黄金展」を見るためだった。画像は、大黄金展の展示物より。オグリキャップ、キティ、大黒様、茶碗、お輪、食器、打掛、ゴルフボール、120キロの金塊。展示物の多くは販売品で、等身大のオグリキャップ像は来年の干支(午)にちなんで2014万円の値札がついていた。1億3000万円の茶釜、1000万円のウルトラマン、200万円のお輪、93万円のトランプ、5万円のブローチをはじめ、仏像、仏具、食器、ミニチュア、インテリア、装飾品など1000点が展示されていた。中には120キロの金塊もあり、時価は5億4000万円とのことだった。自由に触れるが、力を入れてもビクとも動かなかった。
2013.11.18
コメント(0)
-

俳句21の句会に参加
今日は、午前中は、NHK俳句、日曜美術館などを見たり、エッセイの宿題を書いたりして過ごし、午後は、俳句21の句会に参加した。句会の成績は惨々で、出句4句中、下記の1句に一点が入っただけだった。 ・枯蓮に残る命の葉の青さ こっぱん今日、高得点を得たのは、次の句。 ◎術前も術後も山の眠りけり 明子(4票) ◎白菜の四分の一で足る暮し 千賀子(4票) ◎水鳥の声の隙間の水光る 良一(4票)今日は、写真を撮らなかったので、先日、万博公園のコスモスの丘で撮ったものを載せる。
2013.11.17
コメント(0)
-

第九の練習12日目
今日は、午前中は、エッセイの宿題を書き始め、午後は、第九の練習の12日目に参加した。そのあと、グランフロント北館地下で開催されていた「パナホームのリフォーム展」を見に行った。第九の練習は今日が最終回、あとは、佐渡裕レッスン、前夜リハーサル、本番の3回だけ。写真は、上:難波宮跡公園の蘇えったトベラ、下:諸注意を述べる毎日新聞スタッフ、花束を受け取る北村憲昭先生(歌唱指導)と三輪佐千子先生(ピアノ伴奏)。
2013.11.16
コメント(0)
-

映画「そして父となる」を観る
今日は、ゴルフのコンペの日だったが、朝起きるとひどい雨が降っていた。最寄の駅へ行くだけでも大変だし、この雨は午前中は止まないとのことだったので、雨の中のプレーも嫌なので、ゴルフ行きは急遽キャンセルした。午前中は、高大の一口レポートをまとめたり、俳句を作ったり、宿題のエッセイの構成を考えたりしながら過ごし、午後は、映画「そして父になる」を見に行った。画像は、関連サイトより。病院で出産時に赤ちゃんを取り違えられたまま6歳までを育てた2つの家族。それまで何の疑いもなく我が子として育てていたある日、突然病院から間違いの事実を知らされたのだ。DNA検査の結果、事実は疑いようもない。両夫婦とも、愛する我が子を手放すのは嫌だと思う。しかし病院の弁護士は子供のためにも親のためにもなるべく早く交換する方がよいと主張する。夫婦も次第にそのように思い始め、毎週末に相手の家で一泊させることから始める。子供の心理、親の心理が複雑に揺れ動く状況をうまく描いていて、感動の2時間だった。主な配役は、福山雅治、小野真知子、樹木希林など。ほかの人の名前は知らない。子役の2人も名演だった。この映画は、今年9月のカンヌ国際映画祭コンペティション部門で審査員賞を受賞したもの。
2013.11.15
コメント(0)
-

万博記念公園へ
今日は、高大に行事・秋の遠足で、万博記念公園を散策した。午前10時にモノレール万博公園駅に集合後、班別に別れて公園内を散策し、午後2時30分に解散した。写真は、太陽の塔、ソラード(森の空中観察路)、展望タワー、花の丘のコスモス園、西大路のプラタナス並木、昼食場所にした水鳥の池広場、バラ園、日本庭園の心字池、日本庭園の散策路。我々5班は、午前中は、園内の南西方面の散策路を歩き、ソラード(森の空中観察路)を通り、展望タワーから公園全体を見渡したあと、花の丘のコスモス園やヒマワリ園を鑑賞し、西大路のプラタナス並木を通って、水鳥の池の広場で昼食を取った。午後は、民俗学博物館、バラ園の前を通り、日本庭園に入り、園内の散策路を東から反時計回りに一周した。太陽の塔の前に2時30分に集合したあと、各自帰路に着いた。天気に恵まれ、紅葉も始まっていて、花も適当に咲いていて、いい遠足となった。 以下、今日作った10句 ・団栗をぶつけ合ひする仲の良さ こっぱん(以下同じ) ・空中の回廊歩く紅葉晴 ・展望塔から絶景照紅葉 ・コスモスの丘にてお茶とチョコレート ・鈴掛の並木通りに大落葉 ・色紙ほどの大き落葉を拾ひけり ・公園の紅葉散るなか昼餉食ぶ ・枯蓮に残る命の葉の青さ ・冬の蝶翅半開きしたるまま ・回遊の庭そこここに石蕗の花
2013.11.14
コメント(0)
-

春麗句会 中之島バラ園
今日は、午前中は、午後の春麗句会のための出句の選定・推敲を行い、その後図書館へ行った。午後は、春麗句会に参加した。図書館では、河出夢ムック「瀬戸内寂聴文学まんだら」とマジックのDVDを借りてきた。図書館の帰りに中之島バラ園に立ち寄った。バラは大分少なくなったががまだかなり咲いていた。写真は中之島バラ園のバラ。句会の結果はまずまずで、先生から5句全部が選ばれたが、特選は1句だけだった。 ◎せつかちも神妙に待つ青写真 こっぱん(先生特選) 註:青写真とは日光写真のこと。他の句で仲間からも選ばれたのは次の句。 〇じわじわと青空消して時雨雲 こっぱん(先生ほか2票) 〇出来栄えを想ひつつ待つ青写真 こっぱん (先生ほか1票)帰宅後は、借りてきた「瀬戸内寂聴」の中の「夏の終り」を読んだ。これは瀬戸内晴美が41歳のとき(1963年)に書いたもので、女流文学賞を受賞した作品。二人の男性と恋愛関係を続ける40歳女性の葛藤を描いている。1962年と言えばは私が23歳の頃でまだ学生だった。この小説が話題になっていたことも知らない。
2013.11.13
コメント(0)
-

「道頓堀連続フォーラム」に参加
今日は、午前中は、昨日の句会のまとめを行い、午後は、道頓堀商店会と関西大学大阪都市遺産研究センターの主催による「道頓堀フォーラムー芝居町の記憶をたどる」に参加した。フォーラムは、千日前の上方ビル4階トリーホールで行われた。内容は下記の通りだた。第1部 講演 「芝居町の記憶」を語る 1.「島之内の風景」 中村 博氏(中村儀右衛門の子孫) 2.「道頓堀と私」 成瀬国晴氏(宝塚大学講師・イラストレーター)第2部 鼎談 「芝居町の記憶」を辿る 出演は、上記2氏に加え、薮田 貫氏(関西大学大阪都市遺産研究センター長)画像は、パンフレットより、左:道頓堀の景観復元CGの一場面、右上:中村儀右衛門の大道具帳より、右下:開演前の会場。講演の二人は、道頓堀に芝居小屋がたくさんあった昭和初期の思い出を話した。中村儀右衛門は明治から大正時代に活躍して建築家で、最近、彼が作成して膨大な量の劇場の設計図が発見された。中村博氏はその孫に当る人。
2013.11.12
コメント(0)
-

今日は句会
今日は句会の日、午前中は句会資料のプリント、出句する5句の選定、最後の推敲などを行った。句会の成績は上々で、5句のうち4句が先生から選ばれうち2句が特選だった。残り一句も仲間から選ばれた。先生から選ばれたのは次の句。 ◎枯園といへども生きてをりにけり こっぱん(先生特選ほか5票) ◎山茶花に教へられたる多作多捨 こっぱん(先生特選ほか5票) 〇木の葉髪妻の部屋には妻のもの こっぱん(先生ほか4票) 〇七五三姉は妹の手を引いて こっぱん(先生ほか1票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・青空を塗り変へてゆく時雨雲 こっぱん(2票)先生の特選句は上記私の2句のみ。今日一番多く票を得たのは、上記私の2句。先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎鴨来たりはや隊列を組んでをり 塩川雄三先生(3票)今日は、いきいき俳句会が発足してからちょうど10年目の日となり、句会のあと、お菓子とコーヒーでささやかながらお祝いの会を行った。当初15名でスタートしたが、メンバーの入れ替わりがあり、現在は10名。うち当初からのメンバーは6名。今日の写真は、一昨日撮った大阪城。
2013.11.11
コメント(0)
-

関西ぱずる会例会
今日は、午前中は、NHK俳句、日曜美術館などを見たあと、マンションの防災訓練に参加し、午後は西宮市中央公民館で行われた関西ぱずる会の199回例会に参加した。防災訓練では、各階廊下、部屋に配置されている消火器の使い方、各階に2~3か所配置されている消火栓の使い方を実体験したあと、防災用具(非常食、飲料水、懐中電灯、ラジオ、携帯充電器、非常トイレなど)の説明があり、その後、空き住戸を借りて、防火扉の開閉テスト、ベランダから下の階に下りる非常はしご、隣のベランダに逃げる隔壁版の突き破り法などを実体験した。写真は、関西ぱずる会で発表・回覧されたパズルや本。ばずる会では、先ず会誌84号が配付され、その後、参加者から順次発表があった。今日の参加者は10名、うち一人は福井市からの参加だった。各自、最近入手したパズルや本の紹介・回覧しながら会は進んだ。今回は、去る11月3日~4日に開催された「パズル会2013」の模様の報告もあり多彩な内容だった。さらに、Nさんが会の席への問題として3題を出題し、参加者はしばし頭をひねった。いつも早解きのHさんが3題とも一番乗りで解いていた。私は1問だけしかできなかった。
2013.11.10
コメント(2)
-

大阪城についての講演と見学
今日は、関西広域連合内シニア大学校「共同講義」の一環として、大阪城についての講演と見学会に参加した。講演は、大阪市歴史博物館4階大ホールにおいて10時から行われた。講師は元大阪城天守閣館長の渡辺武氏、講演テーマは「大坂城の歴史と現状について」で、内容は下記の通りだった。1.大阪城430年の歴史 (1)大坂本願寺と信長の石山合戦 (2)豊臣時代の大坂城 (3)徳川時代の大坂城 (4)近代の大阪城 (5)終戦後の大阪城2.大阪城史研究の進展と現段階の課題3.特別史跡大坂城跡、重量文化財大阪城、そして世界遺産大坂城跡を目指して4.おわりに写真は、講演をする渡辺氏、千貫櫓、蛸石、天守閣、旧大阪市歴史博物館、金蔵、天守閣8階よりの展望。午後は、大阪観光ボランティアガイドの方の案内で、大手門から天守閣までの道筋を2時間かけて見学した。今まで知らなかったことをいろいろ聞くことができた。見学会のあと、天守閣に入り8階からの眺望や、各階の展示物を見た。特別展「大阪城はこのすがた」が開催されていた。
2013.11.09
コメント(0)
-

一日中家で過ごす マリーゴールド
今日は、一日中家で過ごし、俳句の雑誌を読んだり、俳句を作ったりした。今日の画像は、南森町(天神橋筋2丁目)交差点のコーナー花壇に植えられているマリーゴールド。
2013.11.08
コメント(0)
-

高大2年目の21日目
今日は、高大2年目の21日目。午前中は、的場秀恭先生の「俳句入門」、午後は、各自創作エッセイの合評会。放課後は、マジック同好会の例会であった。的場先生の講義は昨年と殆ど同じだったが、忘れていたことも多く、いい復習になった。講義はユーモアたっぷりで楽しい時間だった。3習慣後に俳句1句の宿題が出た。合評会は、夏休みの宿題で書いたエッセイ「自由題」を班員全員で読み合い感想を述べ合った。マジック同好会では、文化祭での出し物の練習と新しいカードマジックを一つ習った。今日の写真は、昨日大和文華館の庭で見かけた紅葉と花など。百日紅、ナンキンハゼ、桜、芙蓉、酔芙蓉、タニウツギ、萩、山茶花、千両。
2013.11.07
コメント(2)
-

「宮川長春」展へ
今日は、昼前から出掛け、学園前の大和文華館で開催されている「宮川長春」展を見に行った。出掛ける前に、宮川長春のことをネットで下調べした。宮川長春(1682-1752)は、江戸時代の浮世絵師ということだが、版画は一枚も描かずすべて肉筆画があることが特徴。浮世絵初期の人で、狩野派および菱川師宣の影響を受けている。長春の画風は弟子勝川春草を経てその弟子勝川春朗(のちの葛飾北斎)に受け継がれたそうだ。画像は、パンフレットおよび関連サイトより。左:立美人図、右:社頭春遊図、風俗図巻(部分)、蚊帳美人図、源氏物語・藤袴図、市川門之助図。よく似た構図の絵が複数枚描かれていて、立美人図は14点、蚊帳美人図は3点、柳下腰掛美人図は4点などが並べて展示されていた。こうした美人図のほか、いろいろな物語や歴史の一場面を描いた図も多く残しているが、その登場人物は遊郭とその客に変っているのが面白い。絵は非常に緻密で一ミリの何分の1の大きさの点や線を使って描かれている。高価な絵の具を使っていて色も非常に鮮やかである。今回の展覧会は、日本にあるほとんどの宮川春潮作品を集め、一堂に展示したもので、春潮一人の展覧会は日本で初めてのことだそうだ。今日は、運よく、ギャラリー・トークがあり、作品の見所について30分ほどのレクチャーがあったのがラッキーだった。絵の鑑賞のあとは、美術館の回りの庭というより山を散策した。紅葉が始まりかけていて、桜、ナンキンハゼ、百日紅などがきれいな赤色を見せていた。以下未完
2013.11.06
コメント(0)
-

ギャラリートーク「学びの風景と書物」
今日は、午前中は、スカイドライブというものを知りその設定・登録を行ったり、算数パズルを解いたり、会社職場OB会の出欠をまとめたり、句集から秀句の抽出をしたりして過ごし、午後は、中之島図書館で開催されたギャラリートーク「学びの風景と書物」というイベントに参加した。画像は、図書館のサイトより。寺子屋は、江戸時代中期以降盛んになり、1750年には大坂に2500ほどあったそうだ。寺子屋とはどんな仕組みであったのかを伺う絵本がいろいろ残されている。入門するときは机を持参し、修了または破門となったときは机を持って帰る。渡辺崋山の絵もあった。明治初期には、この寺子屋がそのまま小学校になったところも多いそうだ。教科書は往来物といい、商売往来、百姓往来、絵入往来、大阪往来などが展示されていた。こうした資料を含めて、寺子屋関連の資料が17点展示されていた。帰りに中之島バラ園に立ち寄ったら、今まさに見頃を迎えていた。夕方からは、関西俳誌連盟の常任委員会に参加した。
2013.11.05
コメント(0)
-

一日中在宅、京都三条通り
今日は、一日中在宅で、会社の職場OB会に出欠のまとめと未回答者への督促を行ったり、関ぱ誌の索引を作ったり、句集の作者の履歴調査をしたり、昨日のバレエの演目のいくつかをYuuTubeで見たりしながら過ごした。今日は写真を撮らなかったので、1日に行った京都三条通りの建物の写真を示す。左上から、中京郵便局、旧日本銀行京都支店、ゐど壽屋(カバン屋)、足袋屋、にほひ袋・石黒香舗、うしのほね・あなぎ、渡邊眼鏡店、牛肉・三島亭、先斗町公園。
2013.11.04
コメント(0)
-

バレエ&ダンスフェスティバルへ
今日は、午前中は、テレビでNHK俳句、日曜美術館などを見たり、句集を読んだりして過ごし、午後は、大阪市中央公会堂で開催された「バレエ&ダンスフェスティバル」を見に行った。写真は、そのパンフレット、プログラム表紙、会場の様子など。この催しは今年で第6回になるようだが、これまでは他の行事と重なっていたためか、あまりよく知らず、今回初めて参加した。中央公会堂の1階大ホールで、14時から21時まで7時間、休憩なくぶっとうしで演じられた。初めの4時間半はバレエ教室などに所属のアマチュアバレリーナによる演技、あとの2時間半はプロのバレリーナ、ダンサー、舞踊家らによる演技であった。前半には26組の出演があり、後半には9組の出演があった。一組の人数は4~20人で全出演者は何百人にもなる。いろいろなバレエの曲を聴くことができ、音楽漬けの一日となった。同じ曲が演じられることも多く、一番多かったのは、「エスメラルダのVa」で7~8回見た。タンバリンを持って踊るバレエで、バレリーナによって上手下手があるようだった。出演者の中には、小学生もいて、中には少年もいた。来年は、10月12日(日)に開催されるそうだ。
2013.11.03
コメント(0)
-

正倉院展へ
今日は、奈良国立博物館で開催されている「正倉院展」へ行った。画像は、正倉院展のパンフレットより。左:漆金薄絵盤(部分)、右:平螺鈿背円鏡、投壺、花喰鳥刺繍裂残片、蘇芳地金銀絵箱、彩絵長花形几、漆金薄絵盤、檜和琴、続々修正倉院子文書第38-8、鹿草木夾纈屏風。自宅を8時40分に出て、近鉄奈良駅には9時50分に着いた。博物館には10時5分に着き40分並んで、10時45分に入場した。12時15分まで見て、昼食をとり、午後は、13時30分から公開講座「慶長櫃が語る正倉院の歴史」を聴いた。講師は正倉院保存課長の成瀬正和氏だった。今回の一番の見ものは、パンフレットに拡大写真が載っている漆金薄絵盤、上に香板を乗せる台だそうだ。じっくり近くで見るためには45分の行列に並ぶようになっていたが、私は2列目から見たがそれで十分に見ることが出来た。その他、平螺鈿背円鏡、鹿草木夾纈屏風、蘇芳地金銀絵箱など、パンフレット掲載の品はみんな立派なものだった。展示品は全部で66点、展示は次のように分類されていた。 1.聖武天皇ご遺愛の品々 平螺鈿背円鏡、鳥毛帖成文書屏風、鹿草木夾纈屏風など11点。 2.天平の音楽と遊び 檜和琴、投壺、漆弾弓など10点。 3.法会の道具 漆金薄絵盤など10点。 4.献納に関わる品々 蘇芳地金銀絵箱など5点。 5.佩飾品と刀子 白牙把水角鞘小三合刀子など5点。 6.年中行事用具 三十足几など4点。 7.正倉院文書 続修正倉院子文書など7点。 8.宝物の保存と整理 正倉院古やく、古櫃、慶長櫃、樹下鳳凰双羊文白綾など11点。 9.聖語蔵の経典 摩訶僧祇律など3点。 公開講座は、正倉院の品を保存するための苦労話として、特に櫃(今回は慶長櫃)についての話があり、盗難の事例についても貴重な話を聞くことができた。
2013.11.02
コメント(0)
-

土門拳「昭和のこどもたち」展へ
今日は、午前中は、句集を読んだりして過ごし、午後は、京都高島屋で開催されている土門拳「昭和のこどもたち」展を見に行った。画像はパンフレットより。左:しんこ細工1945、右:水浴び1936、神田っ子1953、ゴム飛び1954、江東の子ども・とかげ1955、江東の子ども・近藤勇と鞍馬天狗1955、撮影中の土門拳。土門拳(1909-1990)は、仏像写真で有名だが、今回の写真展は昭和の子どもたちを撮ったもの。昔の子どもはよく戸外で遊んだもの。いろいろな遊び方や過ごし方があったが、現在ではまったく見かけることがなくなった。今回の写真展で、そんな昔の子供の生き生きとした暮らし方が蘇えった気がした。展示された写真は約200点、次のようの分類されていた。1.戦前のこども 昭和10年頃から戦前まで2.たくましく生きる子どもたち 戦後の頃3.江東の子ども 昭和28年頃から。現実重視のスナップ。4.こどもたち(東京・地方) まる裸で遊ぶ子ども、おしっこする子ども。 戦後に次女を亡くしたこともあり、子どもへの愛着が強くなる。5.筑豊の子ども 昭和34年頃、炭鉱の街の子どもたち。6.ヒロシマ 原爆症で傷ついた子どもたち7.支え合う子どもたち 障害者支援施設、孤児院、児童相談所の子どもたち
2013.11.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 乾燥しにくいクリーンな暖房**部屋の…
- (2025-11-24 08:30:03)
-
-
-
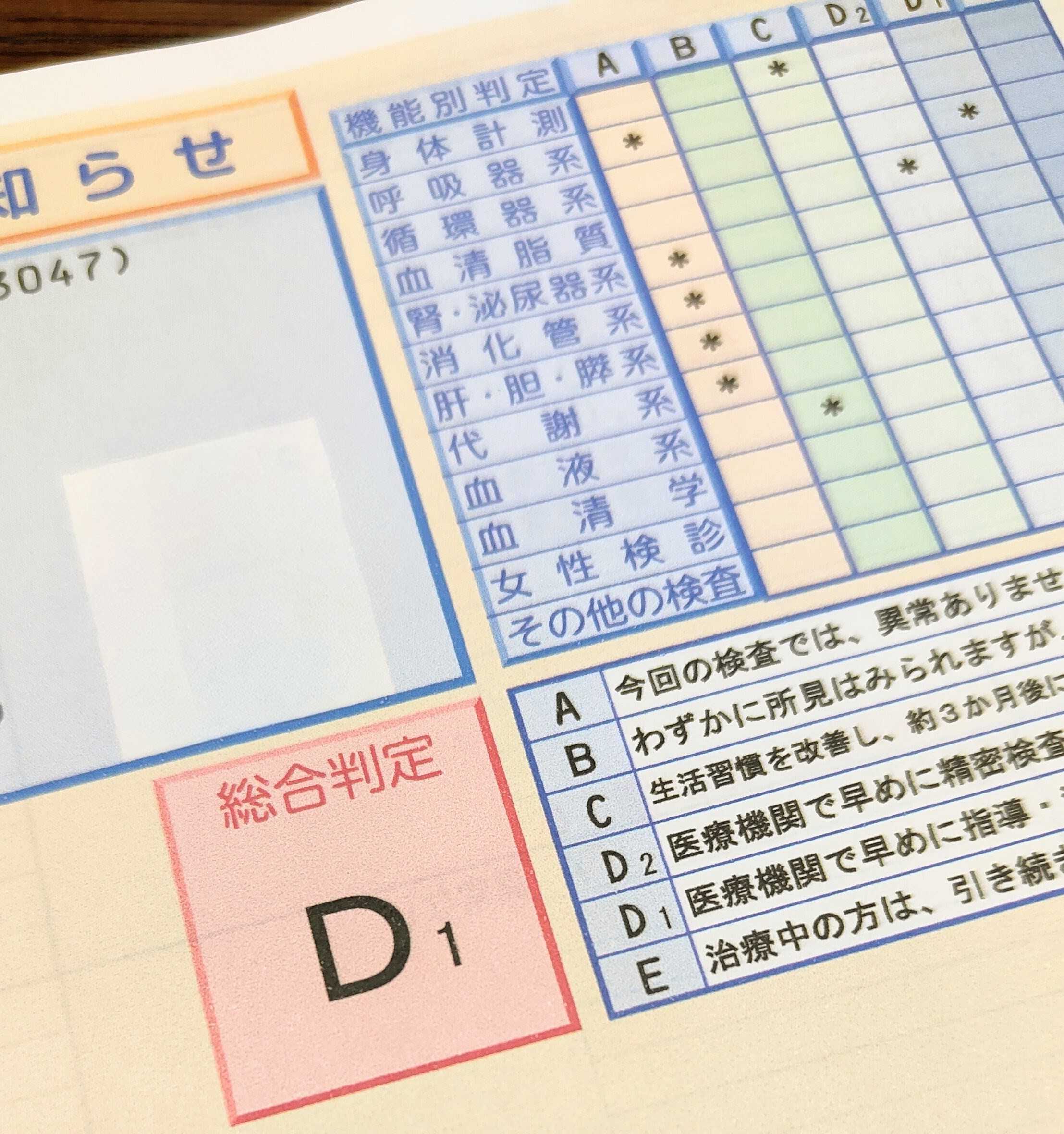
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🍅 My Healthy Life! [Recommended I…
- (2025-11-24 11:12:06)
-
-
-

- たわごと
- へんな女子高生だった
- (2025-11-24 09:01:30)
-







