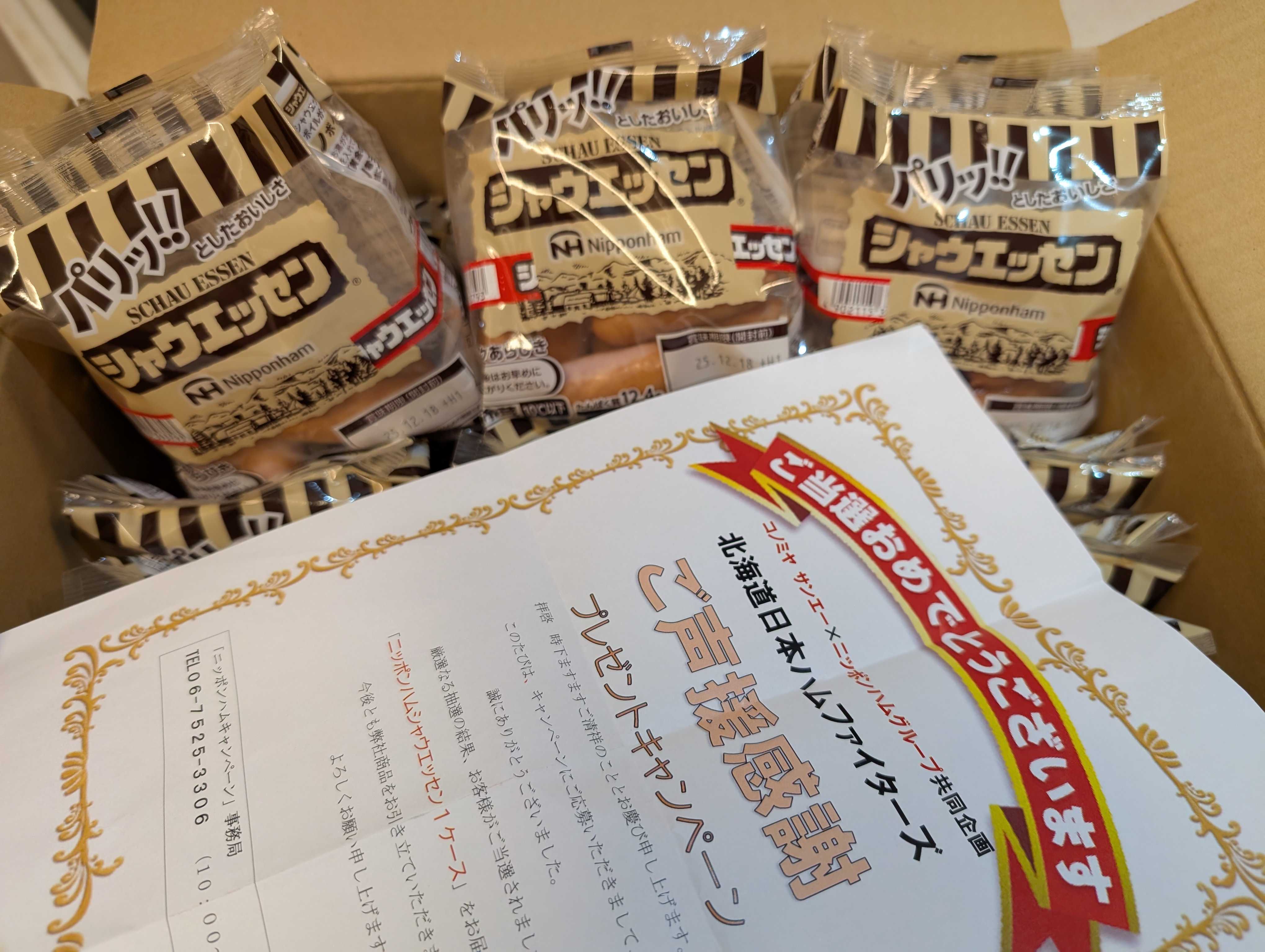2025年03月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

デモンストレーター界のAI化〜将来は人間デモンストレーターとロボットデモンストレーターとの共存になる。
さる3月21日。68歳になった。人生100年だとも言われるこの時代に、「68歳になった」ということは、「もう68歳」と、とらえるべきか、「まだ68歳」と、とらえるべきか。さて。仕事の事前準備や事後報告などの付随事項はともかく、商品をPRして販売するという、おおもとの仕事自体はアナログである私たちの世界でもAI化がじわじわと進行してきている(兵庫県にある試食販売会社リ◯ーンの社長のブログによると、アメリカでは試食ロボットが既に稼働している地域があるそうな)。そのブログ記事を読んだ時、私は素直にこう感じたものだ。「やっぱりね」。何せ、新聞記事もAIが書いてしまう時代である。現場で時折り見かける、商品名とデモンストレーション指示書に書いてあるセールスポイントだけ連呼しているデモンストレーターなんて、ぶっちゃけ、ロボットでいくらでも代替できるわな。しかも、声を出し続けていると疲れてくる人間とは違い、ロボットは故障したり燃料不足などにならなければ、常に一定レベルの労働を提供。しんどい表情は見せず、まして文句など垂れず、ずっとずっと頑張ってくれるのだ。はぁ(溜息)。単に指示されたことだけをこなすのなら、人間デモンストレーターは負けてしまうんだよ、まさしく人間が作ったはずのロボットデモンストレーターに。負けないためには、、、人間デモンストレーターが、これまたまさしく人間であることを「実践的」に証明することだね。プラス、試食の性質上、個別包装されたお菓子や飲料のデモはロボットに出来ても、衛生面や安全面の課題から生鮮品や調理を要するデモは人間でないと出来ないだろうな。つまり、AI搭載のロボットデモンストレーターが現れても、私たち人間デモンストレーターとの共存になる可能性が高い。有人試食は、絶対になくならないやね。まあ、こういうこともありえるかもと、頭の片隅に置いた上で、仕事をしている最近の私である。写真は、春分の日に娘一家と旅した三重県鳥羽市のイルカ島展望台にて。このところ体型もカオもデカくなってきたので「少しカラダを絞らにゃ」と、リフトを使わず徒歩でここまで山道を登った。いい運動だった。
2025.03.29
コメント(0)
-
人間にとって、最大の幸せは、快食・快眠・快便
胃けいれんを起こして10日目の一昨日の夕方。やっと、コーヒーをブラックで飲むことが出来た。久方ぶりに飲んだせいか、「コーヒーって、こんなにも香ばしく、美味しいものやったんやなあ」と、今さらながら認識。コーヒーならではの風味に、セロトニン出まくり。宣伝販売の仕事に就いて22年目。さまざまな場所で、さまざまな商品を、さまざまな人たちに紹介する過程で感じてきた「人間にとって、最大の幸せは、快食・快眠・快便だ」とのポリシーは、今回、「感じ」を超えて「確信」に変わった。美味しく食べて、よく眠って、気持ちよくウ◯チをする。本能にも通じる極めて原始的な感覚こそが、実はいつの時代にもヒトをハッピーにさせる要素なのかも知れない。写真は、コーヒー(Wikipedia).
2025.03.19
コメント(0)
-
胃けいれんの後遺症が治らないうちに連続仕事
胃けいれんの後遺症が完全に無くならぬうちに、明日からまた連続仕事。それ自体はどうということはないんだが、今回の胃けいれん、今までとは違っていやに後遺症がしつこいため、夫も心配してくれている。確かに、これまでは、胃けいれんのあとはけっこうケロリとしていたもんなあ、、、少なくとも、発症後1週間経ってもコーヒーをブラックで飲めないなんてこと、なかった。加齢で消化能力が落ちている?なら、いいんだけれど。折しも、娘に「毎年、誕生日を機会に、自分から自分へのプレゼントとして人間ドックに入りたいが、あれって、カネがかかるんだよなあ」と話していたし、それからまもなくして、血圧と喘息を定期検診してもらっている内科医にも内臓検査の必要性を示唆されたところ。この際、きちんと検査を受けるよ。
2025.03.14
コメント(0)
-

胃けいれんの後遺症〜牛乳を生産する酪農家
胃けいれんの後遺症がまだ続いている。例えば、コーヒー。ブラックで飲むと、飲めないことはないし、コーヒー本来の風味をじゅうぶんに感じることは出来るものの、ぶっちゃけ、未だキツいのだ。それが、牛乳たっぷりの、カフェ・オ・レを超えた「コーヒー牛乳」ならオッケイ(ハチミツを加えたなら、よりオッケイ)。ということは、牛乳に備わるある成分が、恐らくはけいれんで傷ついてしまった胃に優しく作用するのだろう。この成分が何かはわからないし、そのこととは関係ないかも知らないけれど、牛乳を生産する酪農家の戸数は日本の場合、この2025年度、ついに1万人を切ったと言うではないか。これって、、、。ふと、思い出してしまったんだな、宣伝担当を担当したあるメーカーが、自社販売の牛乳の生産者の意向をかんがみ、「適正価格で(我が社の)牛乳を提供します」と、公言し、実行に移したところ、ばったりと売れなくなってしまったこと。販売業の末端にいる我々も困ったものだ。結局、幾月も経たないうちに、元の価格に戻ってしまった。うーん?野菜同様、酪農関連でも言えることだが、生産者と消費者の、それぞれの意向がマッチしない。現在は、実は消費者の方、と言うより消費者に食品を提供する店舗側が強いため、生産者側に「安く、安く」と要求するのだろうし、それがまかり通っているのだろう。もっとも、ここまで酪農人口が減った現在、それがいつまで通用するか?写真は、乳牛の代表、ホルスタイン(Public Domain)
2025.03.13
コメント(0)
-

ブログ再開〜胃けいれん
さて、またブログを書いていこう。前回の記事から少しあいてしまったのは、プライベートでいろいろと用事があったことの他に、ワンシーズンに1回ほどの割で体験する胃けいれんがまたおこり、今回はそれがきつかったことによる(実は今なおささやかながら後遺症が残っている。胃けいれんって、終わった後ではけっこうケロリとするものなんだが。少なくともこれまではそうだった)。まあ、仕事には行きましたけれどね、、、現場に穴をあけるわけにはいかないから(激痛で目が覚めたのは、仕事日当日の午前3時)。それに、たまたま歯痛に悩んでいた夫が歯医者から貰っていた痛み止めの頓服薬を飲んだら、歯痛用なのに胃痛にも効いて、症状が落ち着いたので。そこいらのことも、少しずつ、書いていこう。写真はJR彦根駅で写したもの。ひこにゃんは、やはり可愛い。
2025.03.11
コメント(0)
-

まちは変わる。りんごも変わる〜時代はフルーツに甘味とやわらかさを求めるようになった。
(注)3月2日に書いた記事。今日(2月28日)も、大阪府南部にあるまち富田林で仕事。昨日、ざっと18年ぶりに近鉄富田林駅に降り立ち、その変わりようを、この目で確かめた。18年前、すなわち2007年6月にステーキソースのデモンストレーションのために訪れた大型店は当時とは別の店になり、隣接する形で家電店やら何やらが建ち並び、まるでちょっとしたショッピングセンターみたい。ああ! あの頃とは明らかに違う風景。無理もないか。18年と言えば、生まれたばかりの子ども(赤ちゃん)が大学生になる年月だ。赤ちゃんが成長して変わっていくように、風景もいろいろ取り込んだり、反対に削減したりしながら、変わっていく。変わったと言えば、昨日のデモで担当した商品、りんごもそうだね。私感じるところ、この50年くらいでりんごの風味や食感はかなり変わった気がする。ずばり、甘くなったのだ。そして、柔らかくもなった。ここでお尋ねする。皆さんの中に国光りんごを食べたことのある方はおられるだろうか。国光りんごは、かつて給食にもよく添えられていたりんごで、1960年代半ば以前に生まれた人、すなわち還暦以上の人たちにとっては「りんごの定番」的な存在だった。風味は、現在スーパーなどに出回っているりんごと比べると明らかに甘みも香りも少なく、何より固かった(メーカー名はど忘れしたけれど、「りんごをかじると歯茎から血が出ませんか?」と宣伝文句の中で呼びかける歯磨き粉があった。弱った歯茎を刺激するほど固いものの代表格がりんごだったのだ)。だから、1970年代に入ってにわかに脚光を浴び始めたりんご、スターキングを初めて食べた時に驚かれた同世代は多いのではなかろうか。「何て甘いの!」「何てジャリジャリしていて柔らかいの!」と。とは言え、スターキングも、令和のこの時代にあっては、「甘みが少ない」の「酸っぱい」の「固い」のと言われるだろうな。時代は、いつからか、りんごに、いやフルーツ全体に甘味と柔らかさを求めるようになった。結果、いささか過剰とも感じられるほど甘くて柔らかい品種も登場してきた。この「変わり」には、個々の果物本来の個性を活かす意味合いからも、少し考えるところがあるのではないかと、個人的には感じる。写真は国光りんご(Wikipedia).
2025.03.05
コメント(0)
-

18年ぶりに富田林で仕事。
(注)2月27日に書いた記事。今日と明日。大阪南部にある富田林市で仕事をする。富田林を訪れるのは、2007年の6月以来、実に18年ぶりり。そして、恐らく、今回が遠方地での連続勤務のラストとなろう。電車やバスの乗車時間に、乗車前ないし降車後の徒歩時間も加えたら、交通時間は片道2時間40分をゆうに超える。67歳の今日でも、1日だけなら何とか仕事をこなす体力を考慮した上で行き来できる距離だが、連続となると、今後は微妙なところだね。もっとも、富田林には、ぜひ訪れてみたい箇所がある。歌人の石上露子(いそのかみつゆこ)の生家でもある、旧杉山邸(現在では富田林市管理の重要文化財となっている)。富田林市作成のこのホームページを見ても、短歌はもちろん建築に興味がある方にも、訪れる価値はじゅうぶんあることがわかる。写真は、そのホームページより、杉山邸の外観。
2025.03.05
コメント(0)
-
確定申告
(注)2月27日に書いた記事。毎年毎年、確定申告を済ませるとホッとする。今年は、昨日がその日。安堵と開放感から、これまた例年そうしているように、日が明るいうちから乾杯!いいちこ20度のお湯割りに、ちょっとしたおつまみを添えて。冷蔵庫を開けたら葉ニンニクが残っていたので、卵といっしょに炒めてみたよ。ニラ玉の要領だ。まあ、何度もやっていることなので、さすがに書き方も覚え、ここ2・3年は、自宅で作成した申告書を申告会場に持参してわからない点を会場にいる税務職員に尋ねて書き込むだけになっている。それでも!ああ、億劫なんだな、申告書類を書くのは。宣伝販売の仕事は、私の場合は派遣会社からの請負という形になっており、その性質上、自宅で仕事をするわけではないし、何らかの商品を抱え込むわけでもない。つまり、減価償却だとか棚卸しに関する項目は発生せず、収入を記入したあとは、交通費やら消耗品費やら基本的な経費のみを計上するだけの、真実シンプルな申告書なのだ。なのに、である。領収書を1枚1枚めくりながら、「これは〇〇費」「これは△△費」などと仕訳して電卓を打つ(=ケーサンする)のが、まことにうっとうしい。早い話、めんどくさがりなのだ。「そりゃ1年分の領収書をまとめて処理しようとするからメンドイんだよ。家計簿と同じように毎日は無理でも、ある程度の期間を区切ってその都度その都度すれば、さほど大変なことはないはずだよ」と言って下さる方もいるが、、、ああ、やっぱり出来ないんだ、それが。今後も、確定申告シーズンになると、心に鉛の色みたいな重々しいもやがかかることだろう。ただ、確定申告書を提出する「イベント」自体は、自身の仕事を計数面でも意識し、見直す良い機会ではある。
2025.03.05
コメント(0)
-

雪、しんしん、こんこん。確定申告のしをしていた。
今日の京都は、早朝から雪、雪、雪。しんしん。こんこん。午後からは、確定申告の準備をしていた。
2025.03.03
コメント(0)
-

バスの便は、都会田舎に関係なく、減っている。
(注)2月22日に書いた記事。今日は、京都府南部の複合型商業施設の中にあるスーパーで、きのこのデモ。通常のデモより開始時間が早かったぶん、それに合わせて終了も早く、午後5時過ぎには店を出た。店舗の最寄りバス停まで、カートを引いているのであれば、普通に歩いて10分、速足でも7分から8分かかる。その時は、バスの時間が迫っていた。17時◯◯分発。今は17時△分。「チョイ走り気味に急いだら、ギリギリで間に合うかな」と、ブルゾンの前ジッパーも開いたままで、カートもろともひたすら停留所に向かった。足を早めるため、小声でミッキーマウスのマーチを歌ってリズムを取りながら。大通りが見えてくる。坂道を目的のバスが降りて来るのが見える。おお! 間に合ったではないか。ところがである。横断歩道が近づくに連れて信号が点滅し始め、「アアッ」と、駆け込みセーフを狙ったものの、すんでのところでタッチアウト。赤信号。私が、バス乗り場がある向こう側の歩道へ行く道は閉ざされてしまった。結果、こちらが法律に縛られ、横断歩道を渡らない場所でイライラしながら立ち往しているうちに、バスは坂道を滑り落ち、すうっとそのまま行ったのだ。あーん、あーん、悔しいーーーー。次は17時▫︎▫︎発なんだよ。バスの便は、都会やら田舎やらに関わらず、減っているからねえ。一本のがしたら、数十分待たないといけないのだ。こういうことも、けっこうこたえる年齢になってきた。写真は、バス停留所からの写真。
2025.03.03
コメント(0)
-

無事かえるにホッとする。
写真は、JR南彦根駅にいる(?)無事かえる像。これを見て、ホッとする人は多いのではないか。今日も仕事なり学業なり、あるいは介護なりボランティアなり、おのおの自分のつとめを終え、無事に住処があるまち(むら)に帰ることが出来た。この幸せ。このくつろぎ。作家の、三浦綾子氏は、「今日という1日を終えるために、どれだけ多くの人の祈りがあったことか」と、何かのエッセイで書いていたが、なるほど、そういう見方をすれば、平凡としか感じられない日々も実はそうではないと、考えが変わってくるわなあ。
2025.03.03
コメント(0)
-

きゅうりを炒める? トマトを味噌汁に?〜思考は柔軟に
(注)2月21日に書いた記事。今日は大阪中部にあるまちの駅直結型のスーパーできゅうりのデモ。メニューは、ウィンナーとの炒め物。「は? きゅうりを炒める? あれって生で食べるんとちゃうん?」とおっしゃるあなた。話のタネにでもいいから、一度、炒めたきゅうりを食べてごらん。驚くよ。きゅうりのシャキシャキ感やみずみずしさはない代わりに、青くささが消えて独特の甘さが前面に浮かび上がってくるのだ。これはこれで、生とはまた違った美味しさがある。振り返れば、遠い昔、トマトを宣伝販売するための試食メニューとして「トマトと玉ねぎの味噌汁」を作ることになり、デモ実施店の農産担当者を驚かせたことがある。「ケッタイなメニューやなあ。そんな味噌汁、飲む人、おるんかいな。ワシでもいらんワ。トマトは、切ったそのままを食べてもらうんが、1番味がわかるんや」。確かに。なので、お客さんには、味噌汁と生トマト、両方を試食してもらうことにした。まず、生のトマトを食べてもらう。「美味しい」「味が濃い」など、反応がよかったお客さんに、すかさず「こちらもどうです? 味噌汁になったトマト。けっこうイケますよ。モノは試しです。ぜひ一度」と、トマトと玉ねぎの味噌汁を差し出す。断るお客さんやしぶるお客さんもいるが、好奇心混じりに飲んでみるお客さんもいる。評価は真っ二つと思いきや、これが意外にウケたのだ。「酸味は少しあるけれど、そこがエエ感じやなあ。味噌とトマトはよう合うんや」。何事も決めつけはよくない。「おでんは温かいに限る」いえいえ、冷たいおでんも、真夏にはピッタリよ。「バナナは果物」イエス・イット・イズ。同時に酢と相性がいいから手巻き寿司の具材にもなります。「甘い大学芋はおやつ」基本的にはそう。でも、知っている? 大学芋を肴に芋焼酎を飲むとハマるんだよ。視野を広く持とう。すると、思考は柔軟になり、新しいものも生まれてくる。写真はきゅうり(Public domain).
2025.03.03
コメント(1)
-
悪名は無名に勝る〜小室佳代氏は自分大好き人間
(注)2月21日に書いた記事小室佳代氏が書いたエッセイ本が売れ行き好評でベストセラー間違いなしだと言う。事実、Amazonのレビューでも星5つをつけている人が何人もいる。しかし、出版社も商魂たくましいね。悪名は無名に勝るとの言葉もある通り、佳代氏が出版すれば、「ホウ、あの人が本を出したんかいな。どんなことが書いてあるんやろ。一つ、読んでみようやないか」と、手に取る人が必ず一定数はいる、つまり「売れる」とわかっていての出版なのだから。識者の評価は、概ね芳しくない。「自分大好き人間の一途なまでの息子愛が語られているだけ」と酷評している人もいる。私自身は佳代氏の本を読んでいないので何とも言えないが、ただ一点ひっかかるんだな。本には佳代氏自慢の料理レシピがイラスト入りで載っているとのことだが、何と、どれにも分量が書いていないと言うではないか。こんなのレシピじゃないよ。料理絵日記だよ。「私も作ってみたい」と思う読者がいるかも知れないと、考えなかったのか?やっぱり、識者の1人が表したごとく、このおばさんは自分大好き人間なんだね。
2025.03.03
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1