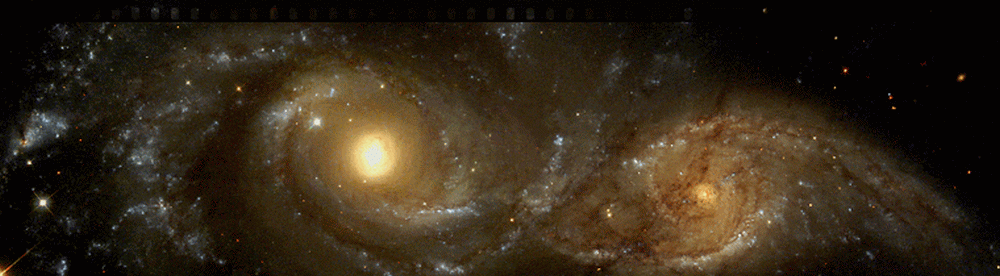2013年01月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

007 ムーンレイカー
「007ムーンレイカー」 Moonraker 1979年 イギリス映画監督 ルイス・ギルバート出演 ロジャー・ムーア ロイス・チャイルズ リチャード・キール やっと年末年始映画の方が一段落しましたので、滞っていた007を一気に見ようシリーズの続きを始めましょう。 第3弾は、シリーズ中最低な出来だと言われている、第11作です。実は、この映画、僕は公開当時、映画館で観ているんですよ。この前作「私を愛したスパイ」で、初めて洋画を映画館で見た僕は、しっかり映画の魅力にはまり、すっかり映画少年になっていました。当時高校生でしたが、週末はわざわざ電車を乗り継ぎ、2時間近くかけて名古屋の大きな映画館まで映画を観に行くという少年でした。このブログの第1回に書いた「2001年宇宙の旅」のリバイバルを観たのもこの時期です。 そして、この「ムーンレイカー」を観て、あまりのひどさに、もう007は見ないぞと思い、実際、この後の007はほとんど見ていないのです。 今回は、そのいたいけな高校生の気持ちを思い出すべく、いつものレンタルビデオ屋(久しぶりですが。)でDVDをレンタルしてきました。 アメリカからイギリスへ空輸中のスペースシャトル“ムーンレイカー”がハイジャックされました。007ことジェームズ・ボンド(ロジャー・ムーア)は、Mの指令を受け、事件の捜査に当たります。 まず、ボンドはシャトルを製造したドラックス社を訪ねるべくカリフォルニアへ向かい、社長の書斎でベニスのガラス工房で製造している製品の設計図を見つけます。 ヴェネツィアへ向かったボンドは、ガラス工房の建物の中に謎の研究所を発見します。そこでは即効性の殺人ガスを研究していました。 Qによると、そのガスの成分はアマゾンにしか存在しない植物のものであるいうことで、ボンドはアマゾンへ向かい、宇宙研究員になりすましていたCIA捜査官ホリー・グッドヘッド(ロイス・チャイルズ)とともに人類をガスで抹殺する計画を知るのでした。 007は、冒頭に必ず1アクションあるのですが、今回は、小型旅客機で移動中のボンドが、美人CAとよろしくやっている(もちろんお約束)ところ、実はそのCAも含め乗員が敵で、上空で襲われ、空中に放り出されてしまいます。危機一髪かと思われたボンドですが、一緒に落ちてきたパイロットのパラシュートを奪ってことなきを得たと思ったところ、続いて落ちてきたジョーズ(リチャード・キール)に襲われ、再び危機一髪です。前作を知っている観客は、ここで、また彼が出るんだ、と大喜びですが、いったい彼(身長218cm)を隠すスペースがどこにあったんだろうとも思っているでしょう。 結局、ボンドもしっかり助かり(当たり前、冒頭で主役が死んだら話にならない。)、ジョーズもしっかり助かり、つかみはOKといったところですが、30数年前に観たまんまの僕としては、この場面のボンドがパラシュートなしで空中を移動する姿の印象が強く残っていて、トンデモな内容の映画だと思わせていた一因でしたが、今回観返してみて、パラシュートを奪うために加速していただけで、普通の行動(トンデモじゃないという意味で)だったことがわかり、「あれ、思っていたのと違うぞ。」と思ってしまいました。 しかし、剣道の防具をつけて竹刀(殺せねえだろ!!)を持った日本人の殺し屋が襲ってきたり、ミリ単位の精密性が必要なはずの宇宙で使う製品の部品をガラス工房で吹いて作っていたり、ヴェネツィアのゴンドラが陸上に(前作のエスプリとは全く逆の作りなのですね。)上がったり、突然行くことになったリオデジャネイロでちょうどよくカーニバルをやっていたり、突然西部劇になったり、明らかに南米の臨時事務所なのにちゃんとマネーペニー(Mの秘書)がいつものように出迎えてくれたり、一度に6機のシャトルが打ち上げられたり、大気圏を離脱するシャトルの中で普通の服で平気だったり、レーザーとか未来的な兵器があるのに決戦が肉弾戦だったり、などなど、笑いをとるために作ったとしか思えない描写ばかりです。 ということで、突っ込みどころをひとつひとつ上げていくとキリがないので、根本的な部分、2点だけ取り上げ、しっかりと突っ込みたいと思います。 ひとつめは、アメリカからイギリスへ空輸中(シャトルって、ああやって運ぶのね。なんか見た目がすごかったけど。)のドラックス社製のスペースシャトルが盗まれ、その行方を捜せと命じられたボンドが、明らかに敵地へ乗り込むようにドラックス社へ向かい、対するドラックス社長も、どう見ても敵対する者として出迎えているということです。 輸送中の自社の製品が盗まれたんですから、どう考えてもドラックス社は被害者ですよね。盗まれたものの捜索をするため、被害者へ加害者の心当たりを聞きに行くというのは理にかなっているのですが、ボンドは、ドラックス社長に面会するとその夜、屋敷の中を物色し、さも当然のように隠し金庫(なぜわかった?)を開け、中にあった書類を何の疑いもなくカメラで撮影しています。この行動、どう考えても、この事件はドラックス社の自作自演だと100%確信した上での行動ですよね。そう疑っているのがわかる描写は全くありませんでしたが。(あれかな、面会したドラックス社長が、どう考えても悪役面しているからかな。それならそうで、一言説明してほしいですが。) ドラックス社長も、ボンドが何をしたのか全く分からずに(分かっていたかもしれないのですが、そういう描写は全くありません。)、ボンドを出迎えていた時にお茶を出していた日本人のおっさんの使用人(あれかな、メイドとか執事とかでなく、あまりにも不自然に日本人のおっさんがお茶を淹れてくれたから怪しいと思ったのかな、ボンドは。)が、突然、剣道の防具をつけて竹刀(どう考えても殺傷能力はないから、殺意はないという判断はしなかったの、ボンドさん。)で襲ってきます。これって、「わが社はあなたの敵ですよ。」と語っているということですよね。しかも、持っている武器が竹刀ですから、殺そうとは思っていないと、語りつつ。(まさか、竹刀で殺そうと思ったとは言いませんよね。) ということで、ボンドはドラックス社があやしいという120%の確信をもって、その後の捜索に当たるわけです。 もうひとつ突っ込みたいのは、ドラックス社が人類を抹殺(考えたら、ものすごく大きな野望ですね。)のために、全世界に毒ガスをばらまこうとしているその方法についてです。 ドラックス社は、その毒ガスをばらまくための兵器と、人類絶滅後の世界で生き残り新世界をつくっていくべく、選ばれたという優秀な人たちを、自社制作のスペースシャトルで、妨害電波装置なるもので姿をかくしている巨大宇宙ステーションまで運び、大気圏外からその毒ガスを搭載した兵器を、地球へ打ちだそうとするわけです。 地球の全土を容易に攻撃でき、なおかつ選ばれた人々は毒ガスに怯えることなく、地球上の惨劇を高みの見物できるという、なかなか良く考えられた合理的な作戦だとは思いますが(お金はかかりすぎですが。)、その攻撃を加える兵器が、あまりにも考えなしで困りました。 その毒ガスを搭載し、地球に向かって打ち出す兵器は、土台こそかなりごつい厚みのある金属と思われるものですが、そこに、ヴェネツィアの手作りガラス工房で作ったコップ状の容器に、毒ガスが入った試験管のような容器(これも透明なので、ガラス、あるいはアクリル製)をおさめ、大きな透明のドーム状のふた(これもガラス、あるいはアクリル製)をかぶせ、全体に球に近い形にしたものですが、はっきり言って、透明のふたはむきだしです。全体として1~2mの大きさのものです。 これって、大気圏突入時にどう考えても融けますよね。金属製の土台は、うまくすれば残るとは思いますが、むき出しになっているガラスかアクリル製の透明なふたや、コップ状の容器、そしてガスの入った試験管のような容器、すべて融けますよね。そして、容器が融けた高温で、漏れたガスは燃えますよね。燃えないまでも、変質しますよね。 果たして、この兵器のうちのいくつが、ガスをその中に留めたまま、地表に到達できるでしょうか。僕ははっきり言って、皆無だと思いますが、どうでしょうか。 ボンドが、この宇宙ステーションに乗り込んでいってこの計画を阻止しようとするのですが、悪者をやっつけるまでの間に、実はこの兵器が3つ打ちだされてしまいます。 最後、悪者をやっつけてスペースシャトルで地球へ帰還しようとするついでに、ボンドとグッドヘッドは、このすでに打ち出されてしまった球状の兵器をわざわざ追いかけて、レーザーで破壊します。2人は必死で追いかけ、大気圏突入ギリギリのところで何とか破壊することに成功するのですが、僕は、「ほかっといても燃え尽きてしまうであろうものを、どうしてあんなに必死になって追いかけるのだろう、バカじゃない???」と、さめた目で見ていて、最後の最後で緊迫する場面と思って作っているであろう、スタッフの気持ちなど全く考えませんでした。これは、ドラックスがバカ?ボンドがバカ?それともスタッフ? ということで、30数年前の印象をあらためて確認できて、満足しています。 この当時、「スターウォーズ」や「未知との遭遇」のヒットで、映画界は空前のSFブームでした。007のスタッフも、やっぱりSFだよなあ、と思って、こんな作品を作ってしまったのですね。科学的知識が乏しいのにもかかわらず。 まあ、SFもののパロディのコメディ作品としてみれば、思いっきり笑えて、楽しい作品ですけどね。ジョーズもずーっと3枚目だしね。彼女もできたし。
2013.01.31
コメント(0)
-

レスラー
「レスラー」 The Wrestler 2008年 アメリカ映画監督 ダーレン・アロノフスキー主演 ミッキー・ローク 年末年始に録画していた作品です。ミッキー・ロークが、ゴールデングローブ賞主演男優賞(ドラマ部門)を受賞し、アカデミー賞でも最有力だ、と当時話題になった作品です。アカデミー賞の受賞は惜しくもなりませんでしたが、最近、「ドミノ」や「アイアンマン2」で、渋くてたくましく男くさい男を好演している彼が渋いロートルのレスラーをどう演じているか是非見たかった作品です。 ランディ・ロビンソン(ミッキー・ローク)は、1980年代、“ザ・ラム”の愛称で一世を風靡した人気レスラーでした。しかし現在は、スーパーでバイトしながら、週末はリングに上がるという、ときには家賃が払えず、大家から閉め出しを喰うこともあるほどギリギリの生活を営んでいました。 家族とも別れて久しい彼の楽しみと言えば、たまに行くバーで、お気に入りのストリッパー、キャシディと酒を飲むことくらいでした。 しかし、プロモーターにかつての名勝負ジ・アヤトラー戦の20周年記念試合の企画を聞き、心躍らせていました。 そんなある日、激しいデスマッチの後、ランディは、突然の心臓発作で倒れてしまいます。長年の激しい試合と、マッチョな肉体を維持するために服用してきた薬のため、彼の体は悲鳴を上げていたのです。 心臓のバイパス手術をしたということで、医者から激しい運動を禁止されたランディは、引退を決意し、人生をやり直そうと、キャシディからのアドバイスもあり、別れていた娘ステファニーと会い、関係を取り戻すことができました。 しかし、深酒をして、娘とのデートの約束をすっぽかしてしまったランディは、ステファニーに愛想を尽かされてしまいます。 自暴自棄になったランディは、バイト先のスーパーでもミスしたことから店頭で暴れ、クビになってしまいます。 やっぱり自分にはリングしかないと決意したランディは、ジ・アヤトラーとの記念試合を再び企画してもらい、心配して駆け付けたキャシディの制止も振り切り、命をかけてリングに上がるのでした。(調子にのって全部あらすじを書いてしまいました。) やられました。観終わった後、涙が止まりませんでした。今も文章を打ちながら思い出して、目がうるんできてしまっています。 かつては、「がんばれ元気」の第2巻(元気のお父さんが死ぬところ、本当に泣ける話です。)以外、何かを見て泣くなんてめったにない僕でしたが、最近は、「ロード・オブ・ザ・リング」のサムを観て泣いたり、「トイレの神様」のフルコーラスを聞いて泣いたり、と、年のせいか、何かと涙もろくなっている僕ですが、この映画は、心の奥底から、泣けてきてしまいました。 やられました。僕のようなさびしいおじさんが見てはいけない作品でした。いろいろとランディの気持ちがストレートに伝わってきて、自然と涙があふれてきてしまったのです。 最後の場面、試合のクライマックス、トップロープからの必殺技“ラム・ジャム”で、飛びかかったところで、プツっと切れて真っ暗になるのは、やっぱり、そういう意味ですよね。(と、打ったところで、また眼が熱くなってきてしまいました。) でも、やっぱりリングの上で迎えることができて彼は本望だったのですかね。そう思いたいです。 試合の前に戦うレスラー同士で打ち合わせをしていたり、控室でドーピングの薬を買う場面があったり、と、プロレスの暗部も包み隠さず描いたことで、やや物議を醸している作品だということですが、ミッキー・ロークが文字通り体を張って大大大熱演を見せてくれた、素晴らしい作品でした。
2013.01.29
コメント(1)
-

クライマーズ・ハイ
「クライマーズ・ハイ」 2008年 日本映画監督 原田眞人出演 堤真一 堺雅人 遠藤憲一 滝藤賢一 高嶋政宏 山崎努 小澤柾悦 まだまだ、年末年始で録画した映画の紹介は続きます。 1985年8月12日、群馬県の御巣鷹山山中に墜落した日航機の事故の取材を巡る、地方新聞社(架空)の奮闘を描いた、以前このブログでも紹介した「半落ち」の作者横山秀夫の同名小説の映画化作品です。 1985年8月12日、北関東新聞社の記者悠木(堤真一)は、仕事終わりに友人の同新聞社販売局員の安西(高嶋政宏)と谷川岳に登る約束で、新前橋駅で待ち合わせをしていました。 しかし、社を出ようとした悠木に県警キャップの佐山(堺雅人)が駆け寄り、耳元で囁きます、「ジャンボが消えたそうです。」と。 急遽、全権デスクに任命された悠木は、現場が混乱する中、安西との約束を果たせず必死で指揮をとります。まず、ジャンボが落ちたのは群馬だろうとほぼ確信し、佐山と神沢(滝藤賢一)を現場の山に送ります。 一方、安西は仕事を必死で処理し、急いで新前橋駅に駆けつけたが電車に間に合わず、そのままクモ膜下出血を発症して意識不明となり日赤病院に運ばれていました。悠木にその事実が知らされたのは翌日で、病院に駆けつけた時には遷延性意識障害のため植物人間のような状態となっていました。 佐山と神沢が必死でつかんだ一番最初の現場雑観は、旧態然とした首脳部の考えから無線が導入されておらず、下山しないと連絡できないことや、輪転機の不調から締め切り時間が早まっていることを、かねてから確執のある等々力部長(遠藤憲一)に知らされていなかったことから、締め切りに間に合わず、記事から落とされしまうのでした。 この題材となっている日本航空123便の事故については、520名もの犠牲者を出しており、その中にかつて一世を風靡した歌手坂本九さんがいたり、奇跡的に4名の生存者がいたり、当時非常に話題になった事故ですから、自分自身、非常に印象深く記憶に残っています。 その事故の裏側の報道陣の奮闘を描いたというだけで、非常に心動かされる題材であり、映画にする意味は多大にあると思います。 そして、お話自体は、ベストラー小説ですし、その内容は感動できる話であることは疑いようがありません。 しかし、この「クライマーズ・ハイ」という題名ちょっと不安でした。“クライマーズ・ハイ”とは、登山者の興奮状態が極限まで達し、恐怖感が麻痺してしまう状態のことです。つまり怖いことが快感になってしまう状態のことで、非常に怖い状態のことです。 この物語、登山が趣味の記者が主人公ということで、他社を差し置いてスクープ記事をゲットし、すっぱ抜くことを登山に例え、異常な興奮状態で、倫理観とか、遺族の気持ちとかを考えずにスクープ記事をすっぱ抜こうとする記者の話かなと、思ってしまったからです。 確かに、主人公悠木は、思いがけず全権デスクに任命され、結構な興奮状態で、連日の記事を作っています。そして、事故の原因についてのスクープを巡っての攻防がこの映画のクライマックスになってくるわけですが、ここで“クライマーズ・ハイ”になって、たいへんなことをしでかさないかな、と不安だったわけです。 で、どうなったかというと、ここでは詳しいことを述べることはやめておきますが、結果としては、安心しています。最後の最後になって、悠木は冷静でした。このある意味どんでん返しの結末は、良かったのではないでしょうか。僕は、原作も、TVドラマ版も観ていませんので、そういう意味では、ドキドキできてよかったです。 ということで、お話的には、いい話だな、と思ったわけですが、実は手放しにいい映画だと思ったわけではありません。 それは、全体を通して、緊迫感がいまいちだなと思ったことです。確かに、紙面を巡って、駆け引きをしたり、どなり合ったり、結構激しいやり取りの描写がみられるのですが、何かいまいちの感が否めないのです。 その原因は何かなと考えるに、画面のリアリティがいまいちなのではないかと思いました。 例えば、北関東新聞社の会社内がきれいすぎるということ。 舞台は1985年です。新聞社とか、雑誌の編集部とかって、もっとゴチャゴチャしているイメージが有りませんでした? 狭いスペースに事務机(よくある灰色のやつね。)がたくさん並んでおり、その上には書類やファイルが山積みになっており、灰皿には吸殻が山積みで、その間に無精ひげだらけで見るからに寝不足でくわえ煙草の男がボサボサ頭を掻きながら、原稿(手書き)を書いている、かつての新聞社って、そんなイメージではないですか? なんか、この映画の北関東新聞の社内って、きれいすぎるんですよね。さすがに、全机にCPが並んでいるということはありませんでしたが、なんか今どきのオフィスという感じで、広々として、スマートなんですよね。 また、佐山と神沢が必死の思いで登山をし、まだ自衛隊や地元の消防団たちが遺体の収容や生存者の捜索をしている事故現場にたどり着き、その悲惨さを目の当たりにするのですが、その事故現場に、バラバラになった機体はあるのですが、乗員乗客の遺体が全く見えないんですよ。自衛隊員が袋にくるまれた遺体らしきものを運んでいる描写はありましたが。バラバラになったり、血だらけになったりして、機体の破片とともに転がっているはずの遺体が全くないんですよね。 まあ、子どもも観るわけだし、遺族にも観せる予定があって、倫理的に問題があるという判断なのかもしれませんが、佐山と神沢は、少し出遅れており、山の中で若干迷っているような描写もあったので、もうすでに遺体の収容は済んでしまってからの到着だったのかと思ったのですが、その後、2人の話に出てくる現場の様子とあまりにも違うので、違和感を持ってしまいました。 とりわけ、神沢は本来は地域報道班(つまり地元のほのぼのとしたニュースばかり扱ってきたということですかね。)で、今回駆り出されて、初めて死体を目の当たりにしたと言っていたこともあり、この後、必死の思いで作ってきた原稿が、時間切れで初日の紙面に間に合わなかったこともあり、精神的に参ってしまうという展開になってしまうのですが、彼が見たものと、画面に見えていたものがあまりにも違いすぎるので、なぜ彼がああなってしまった(一応どうなったのかは秘密にしておきましょう。)のか、リアリティが感じられないのです。 それから、話の本筋とは関係ない(でもきっと、作っている側としては関係していると主張すると思いますが。)ところが、気になりました。 例えば、安西がクモ膜下出血で倒れること、登山仲間としての安西の存在は必要だと思いますが、なぜ倒れ、植物人間にならなければいけないのか、全くわかりません。 例えば、ワンマン社長(山崎努)のわがままぶりとセクハラの件、そして、それと関連して、悠木の母親の件、社長があんなに個性的である必要は全く感じませんし、ましてや、悠木が社長の隠し子である説や、悠木の母親がパンパンだった話は、全く必要ないですよね。 何か話を盛り込みすぎて本筋がぼけてしまうような気がしました。いくら原作にある話だ(原作は読んでいないんで分かりませんが。)としても、いらないものはどんどん切っていいと思いますよ。 ということで、とてもお話的には感動できる話なのですが、どうも今ひとつだったという感想でした。なるほど、日本アカデミー賞に、作品賞をはじめ、多数ノミネート(日本アカデミー賞では、“優秀○○賞”というので非常に紛らわしいのですが。)されていますが、受賞は0というのは、そういうわけなんですね。(ちなみにライバルはあの「おくりびと」でしたので、しょうがないという話もありますが。) ところで、主演の堤真一が優秀主演男優賞というのはわかりますが、堺雅人の優秀助演男優賞というのは、疑問を持ってしまいました。 確かに、よくない演技だとは思いませんでしたが、演技派の彼としては今ひとつ目立っていなかったような気がします。 僕は、彼より、何かと悠木と対立していた等々力部長役の遠藤憲一(LPガスの人です。本当に多くの作品に脇役で出演している、いい役者さんです。) や、事故の現場の生々しさから精神的に参ってしまう神沢役の滝藤賢一(大河ドラマ「龍馬伝」で、薩摩藩家老小松帯刀を好演していた人です。または、「踊る…」で、新任の中国人刑事をやっていた人です。)の方が、目立っていたと思います。 でも、この日本の映画界というのは、こういう地道に脇役でがんばっている人には、脚光を当てないんですよね。日本アカデミー賞では、助演賞でも他の映画では主役をやっている人ばかりノミネートされていますからね。(ちなみに、堤真一は、この同じ回で、「容疑者Xの献身」で、優秀助演男優賞にも入っています。) どうも、コナン映画が毎回優秀アニメ賞に入っているのと同じ、大人の事情が匂ってきますね。
2013.01.28
コメント(0)
-

地球が静止する日
「地球が静止する日」 The Day the Earth Stood Still 2008年 アメリカ映画監督 スコット・デリクソン出演 キアヌ・リーブス ジェニファー・コネリー この間「金曜ロードショー」で放映していたのを、録画していたものを、今日やっと観ました。1951年の古典的名作SF「地球の静止する日」のリメイクです。(“が”と“の”の違いに注目して、間違えないでね。) ある夜、プリンストン大学で教諭をする地球外生物学者、ヘレン・ベンソン博士(ジェニファー・コネリー)の自宅にアメリカ政府のエージェントが突然やってきました。 強制的にある非常事態への協力を求められたヘレンは1年前に他界した夫の連れ子であるジェイコブを隣人に預け、あわただしく公用車に乗り込みます。 すでに政府は軍を総動員出動させ警戒態勢を敷き、町は異様なまでに静まり返っていました。 政府がヘレンのほかに核物理学・天文学・地質学などの権威を招集したのは、木星の外側で観測された謎の物体への対策を講じるためで、小惑星と思われるその物体は想定外の進路を信じがたい速度で移動し、マンハッタンへと迫っています。 しかし、物体が地上に達するはずの瞬間には何も起きず、まばゆい光を放つ巨大な球体がセントラルパークへと舞い降りてきました。 防護服をきたヘレンらが近づくと、球体の中から一体の生命体と大きなロボットが姿を現します。動揺した兵士の1人が発砲してしまい、銃弾を浴びた生命体はヘレンの目の前で昏倒しました。 政府は生命体を医療施設へ運び、懸命の治療をします。生命体の体にメスを入れると、灰色の有機物質の皮が剥がれ落ち、その下から人間そっくりの男性の体が姿を現しました。 意識を取り戻した生命体(キアヌ・リーブス)は自分の名をクラトゥと名乗り、地球を助けに来たと、ヘレンに告げます。 環境問題の究極の解決方法の映画ですね。地球環境を守るために、その環境を破壊の原因を元から断つという方法ですね。 謎の生命体クラトゥは、地球を助けるためにやってきました。そう、人類を助けるためにではなく、地球を助けるためにです。そして、地球を助けるために、1番手っ取り早く、最も効果のある方法は、その元凶である人類を地球上から一掃することなのです。まあ、確かに傍から見たらたった1種の生物が、これほど1惑星を支配するという状況は、異常だと思えます。 クラトゥが乗ってきたと思われる謎の球体、考えられないようなスピードで宇宙空間を移動し、地球に衝突するかと思いきや突如スピードを落とし、ニューヨークのセントラルパークに軟着陸します。この正体は何でしょう。 映画の中で、この球体から現れた生命体クラトゥを皆、エイリアンだと認識しています。ネットで調べたこの映画の感想を述べている皆さんの多くも、彼はエイリアン、つまりこの宇宙の中のどこか他の天体からやってきたものだと思っています。 しかし、クラトゥはただの一度も、自分が他の天体から来たということは言っていません。 彼の正体は何でしょう?? 実は、劇中にそのヒントとなる描写が有ります。 まず、ヘレンが呼ばれ、事態の説明を受けているとき、異常なスピードで飛んでいる謎の物体が、重力の影響を受けずに飛んでいるという説明が有ります。重力の影響を受けないということは、その物が質量をもった物質ではないということです。 しかし、セントラルパークに軟着陸した大きな青く光る球体の中から、謎の生命体と巨大なロボットが現れるのです。これらは明らかに、質量をもった物体です。 つまり、この球体を送り込んできたものは、この宇宙全体で共通するはずの物理法則を超越した存在ということです。それは何者でしょうか。 また、映画の中で、球体が色々な地球上の生物を自らの中に取り込み、捕らえている描写があり、続けてセントラルパークの1体をのぞいて、他の世界中に現れた多数の球体は地球から去っていったという描写があり、その情報を知った国防長官は、「ノアよ、これはノアの方舟だわ。」と言います。 はい、わかりましたね。人類を滅ぼそうとクラトゥを送り込んできた存在は、ほかの天体からやってきたエイリアンではないのです。 すべての物事を超越した存在、この世界のすべてを創造した存在、そして、自らの姿に似せて作った人類が間違った方向に行ってしまったら簡単に滅ぼしてしまったという存在、なのです。つまり、この映画は、“ノアの方舟”あるいは“ソドムとゴモラ”のお話だったのです。 ということで、ネットで、エイリアンがどうとか、さもわかったように意見している皆さん、ちょっと恥ずかしいですよ。
2013.01.27
コメント(1)
-

ボーダー
「ボーダー」 Righteous Kill 2008年 アメリカ映画監督 ジョン・アヴネット出演 ロバート・デ・ニーロ アル・パチーノ やっぱり年末年始に録画していた映画です。 ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノという、超ベテラン演技派2大巨頭の共演という割には、全く話題にならなかった、クライム・サスペンスです。 ニューヨーク市警のルースター(アル・パチーノ)とターク(ロバート・デ・ニーロ)は、30年という長きに渡ってコンビを組み、いつも一緒に事件を追ってきた2人には強い絆がありました。 その頃、市内では連続殺人事件が発生していました。被害者はいずれも、過去に犯罪をした者や犯罪をしながら処罰されていない者で、その現場には、必ず詩を書いたカードが残されていました。 市警は刑事の関与を疑い始め、タークにも捜査の手が伸びてしまいます。 ルースターとタークはその疑いを晴らすべく、捜査を始めますが…。 なんかちっともハラハラドキドキしない、ぬる~~~~いサスペンスなんですけど、どうしてでしょう。 2人の名優は、アップになった表情とか観ると確かに、迫力があって奥深い意味深な表情なのですが、まあ、2人ともはっきり言ってご老人ですし、動きに切れがないのはしょうがないのですが、それをそれらしく見せない演出とか、編集とかはいくらでもできそうな気もしますし、話が進んでいっても捜査がなかなか進まない、脚本にも責任がありそうです。 まあ、だいたいが、2人が最前線で捜査する刑事という設定に無理があるのではないでしょうか。ふつうは、捜査を指示するボスとか、警察署長とかをやっている年代ですよね。もしくは、どっかの古畑さんのように、拳銃持って犯人を追っかける役ではなくて、頭を使って推理する頭脳派刑事ならわかりますが。(ルースターの方は、わざわざチェスをしている場面を挿入したりして、頭脳派であることを強調していますが、全く捜査には生かされていません。) というか、アメリカでは頭を使って犯罪をする犯人が皆無で、だいたいが拳銃を使った力技で強盗や殺人をするヤツばかりだからでしょうか。(いや、確かアメリカにも、かつてはコロンボさんとか、頭脳派刑事がいたはずですが。) とにかくぬる~~~~い展開で、タークが草ソフトボールをする場面とか、年甲斐もなく若い女刑事(タークと比べれば若いということで、実際は結構おばさんですが。)とよろしくやっている場面とか、事件とは関係ない描写(実は監督とかは意味ある場面だと位置づけているのかもしれませんが、はっきり言って、僕には意味わかりませんでした。)が、ところどころ挿入されて、ますます退屈極まる展開です。 そして、最後はどんでん返しのつもりだけど、はっきり言って観客の95%が予想していた通りの展開で、真犯人が明らかになり、事件は解決するのです。 もう、名優2人がもったいないというしかありませんでした。
2013.01.26
コメント(0)
-

ライラの冒険 黄金の羅針盤
「ライラの冒険 黄金の羅針盤」 The Golden Compass 2007年 アメリカ映画監督 クリス・ワイツ出演 ダコタ・ブルー・リチャーズ 二コール・キッドマン ダニエル・クレイグ またまた、年末年始のTVで放映していた映画です。 比較的最近の映画ですし、CMなどで盛んに宣伝していたので、実は観たかった作品です。どうやらイギリスでは人気のファンタジー小説が原作のようですが、全く知りませんでした。 人間の魂が“ダイモン”という動物の形で人体の外にある世界でのお話です。 両親のいない少女ライラ(ダコタ・ブルー・リチャーズ)は、唯一の保護者・叔父のアスリエル卿(ダニエル・クレイグ)に、寄宿学校に預けられていました。 ある日、謎の美女コールター婦人(二コール・キッドマン)に連れ出され、飛行船で旅に出ることになります。学寮長は、アスリエル卿から預かっていた、真実を知ることができるという、黄金の羅針盤を餞別にライラに渡します。 ところが、ライラは、コールター夫人が子どもたちを誘拐しているという謎の組織ゴブラーの一員で、友だちのビリーやロジャーがさらわれていることを知り、コールターのもとを逃げ出します。 ゴブラーの追手に捕まりそうになるライラでしたが、そこに、さらわれたビリーの母親を含めたジプシャンたちが現れ、助けられました。 こうしてライラはジプシャンたちとともに、誘拐された子どもたちを救う旅に出るのでした。 というのが前半のあらすじですが、実は、冒頭のいくつかの場面について、わざと書いていません。 その場面とは、ビリーたち悪ガキグループがライラの仲良しのロジャーをいじめ、それをライラがビリーに呪いの門と毒のガウンという明らかにうその話をしてロジャーを助ける場面、久々にライラのもとを訪れたアスリエル卿が、マジステリアムという教会風な組織の人間に毒入りワインで殺されそうになるところをたまたまクローゼットに隠れていたライラが阻止する場面、アスリエル卿が映写機で、そのマジステリアムの人も含め、おそらくは学校の関係者たちに、謎の“ダスト”というものの説明をしている場面、マジステリアムの偉い人たちと推測される年輩の男たちがよからぬ相談をしている場面(しかも、その中の1番偉そうな人がクリストファー・リーという大御所です。)、などです。 なぜわざと書かなかったかというと、お話のこの後の展開に全く関係がないからです。とりわけ、この物語の最重要人物であるはずのアスリエル卿を殺そうとするマジステリアムなる組織は、この後、言葉としてすら、全く出てきません。 そうしたよくわからない場面も含め、映画の冒頭で、おそらくは説明が不十分だからでしょうが、疑問に思うところがたくさん出てきて、はっきり言って、お話がよくわからず、観続けるのが非常に苦痛でした。 ロジャーやビリーなどの子どもたちは、ライラと一緒に学校にいるわけではないようだけど、どうして一緒に遊んでいるのか、コールター夫人に学校関係者たちが全く逆らえないのはどうしてか、そもそもコールター夫人とは何者か、学校の生徒らしき少年たちが晩餐にずらっと並んでいる中に、ライラと同じぐらいの女の子が全くいないのはどういうわけか、ライラの両親はいずこに、なぜ叔父さんのアスリエル卿はライラを預けるのか、仰々しく登場する飛行船の中の場面が全くないのはどうしてか、マジステリアムの人はどうしてアスリエル卿を殺そうとするのか、コールター夫人はどうしてライラを連れて行くのか、などなど。 その後、ライラが、ジプシャン(この人たちの立場もよくわかりません。)たちといっしょに旅を始め、よろいグマのイオレク・バーニソンと仲間になってきたとこら辺から、お話が面白くなってくるんですが、そこまでで1時間近くかかっているんですよね。もうちょっと何とかならなかったのでしょうか。 しかも、実は初めから3部作の予定のためでしょうか、冒頭の疑問の多くが結局解決されないまま、非常に尻切れトンボのまま、終わってしまうんですよね。非常に残念です。 どうも、脚本に問題がありそうですね。 非常に口が達者(ウソツキという話もありますが。)で、度胸もあり、自ら道を切り開いていけるライラや、非常に義理堅く、いざという時に頼りになる、よろいグマのイオレクのキャラクターは魅力たっぷりで、“ダイモン”という非常にユニークな設定もあり、作りようによっては、非常に面白い話になったと思われるのに、はなはだ残念です。
2013.01.25
コメント(0)
-

シンデレラマン
「シンデレラマン」 Cinderella Man 2005年 アメリカ映画監督 ロン・ハワード出演 ラッセル・クロウ レネー・ゼルウィガー ポール・ジアマッティ まだまだ年末年始に撮りためた映画の紹介は続きます。 世界恐慌期に、実在したボクサー・ジェームズ・J・ブラドッグの物語です。 1928年、上り調子で世界戦も間近なボクサー、ジェームズ・J・ブラドッグ(愛称ジミー、ラッセル・クロウ)は、妻メイ(レネー・ゼルウィガー)と3人の子どもと豪邸に暮らしていました。 5年後、1933年、ブラドッグ一家は、ぼろいアパートで暮らしていました。世界的な大不況のため、港での日雇労働も毎日できるわけでなく、貧困にあえいでいたのです。 そんな中、試合の準備中、マネージャーのジョー(ポール・ジアマッティ)は、ジミーが右手を痛めていることに気付きますが、金を稼ぎたいというジミーに熱望され、試合をすることを容認してしまいます。 その試合中、ジミーはますます右手を痛めてしまい、クリンチを繰り返すしかなく、無気力試合と判断され、無効試合となり、ファイトマネーももらえず、ライセンスも取り上げられてしまいます。 右手のけがを隠して日雇労働で働くジミーでしたが、思うように稼げず、生活は苦しくなるばかりです。とうとう電気も止められ、メイはジミーが仕事に行っている間に、子どもたちを親せきに預けてしまいます。 ジミーは、恥も外聞も捨て、救済センターに援助を求め、ボクシング委員会にも無心に行き、何とか滞納していた電気代を払うことができ、子どもたちを呼び戻しました。 そんな状況を知ったジョーは、試合直前にけがをした選手の代わりに出場する話を持ってきます。そして、その試合でジミーは勝ってしまうのです。 ジミーの実力を再認識したジョーは、家財道具を売り払い、ジミーのライセンスを復活させ、試合を組んできました。ここからジミーの快進撃が始まります。 冒頭、ボクサーとして絶好調のジミーでしたが、突然5年後、つまり世界恐慌に入ってからの、貧困にあえいでいる場面に切り替わります。その間、何があったのかは、詳しく語られておりません。確かに社会全体が突然、大不況に陥ってしまうのですが、ボクサーとして好成績を上げていれば、そんなに落ち込むことはないはずですが、その辺何が起こっていたのかは、はっきりわかりません。 その後、けがが原因の無気力試合でライセンスを取り上げられ、貧困のズンドコ、じゃなくてどん底になってしまうのですが、マネージャーのジョーが持ちかけてきた、実は期待の新鋭の“かませ犬”としての意味合いだった試合で、ジミーは貧困のどん底の中、ろくにトレーニングもしていないのに、勝ってしまいます。そして、その後は、連戦連勝の快進撃です。 ジェームズ・J・ブラドッグというボクサーは、どうやらすごく強いボクサーのようです。じゃあ、いったい1928年から1933年の、この映画で語られていない5年間の間、いったい何があったのでしょうか。 冒頭の好調な場面からいきなり何の説明もなく、貧乏な場面に移ってしまい、「あれ、いったい何があったの???」と疑問に感じながら、その後の貧困のどん底であえいでいる姿を見せられてしまうので、ますます「???」という頭のまま、話が進んでしまい、感動のストーリーのはずが、いまいち乗り切れませんでした。 それから、ライセンスを取り上げられる原因となった無気力試合になってしまったときのクリンチの仕方が、タックルのように肩からぶち当たっていき、いかにもクリンチをするためだけに前に向かっているように見え、そんな見え見えのクリンチなら、無気力試合と認定されてもしょうがないなあ、と思ってしまいました。 だから、その後の貧困な場面に感情移入できませんでした。 そして、後半の快進撃が、トレーニングをしている描写がほとんどないので、全くリアリティを感じられませんでした。だって、最後は世界タイトルマッチまで行ってしまうんですよ。必死のトレーニングをしなければ、そこまで上がっていくのは容易なことではないでしょう。 トレーニングをせずに連戦連勝でき、世界タイトルマッチまで進めるのでしたら、とんでもない天才ボクサーで、貧困にあえいでいた時期というのはいったい何なんだ、という話になりますよね。 だから、感動のストーリーに、今ひとつ乗り切れませんでした。 このお話、基は実話ですから、お話の展開に間違いはないでしょう。 だから、実際は空白の5年間の間には、のっぺきならない事情があるのだろうし、快進撃の裏には、本当はすごいトレーニングをしているはずです。 どうも、貧困にあえいでいるブラドッグ一家の描写に力を入れるあまり、大事な部分を省略してしまったのではないでしょうか。これは、脚本家の責任でしょうか。せっかくの感動のシンデレラストーリーが台無しです。 ということで、非常にがっかりした、という次第です。 主役のラッセル・クロウが、貧乏なボクサー役ということで、非常にスマートになっており、役作りのために、結構大変な減量をしたんだなあ、と思うと、非常に残念でなりません。
2013.01.24
コメント(1)
-

パーマネント野ばら
「パーマネント野ばら」 2010年 日本映画原作 西原理恵子監督 吉田大八出演 菅野美穂 小池栄子 池脇千鶴 夏木マリ 江口洋介 宇崎竜童 まだまだ、年末年始にTVでやっていた映画の紹介は続きます。 この映画、比較的最近の映画なので、名前だけは記憶に有りました。しかし、その内容は、確か菅野美穂が主演だったよなあ、ということぐらいで、全く何も知りませんでした。 ある田舎の漁村にある唯一の美容院「パーマネント野ばら」。なおこ(菅野美穂)は離婚し、娘を連れて、母(夏木マリ)の経営するこの美容院に身を寄せていました。 美容院は町の女たちの「たまり場」と化していて、 あけっぴろげに自分たちの悲哀や愚痴をこぼし合い、罵り合い、笑いあっていました。 なおこの2人の友人も男運が悪く、みっちゃん(小池栄子)はフィリプンパブを経営しながらヒモ男に金をせびられ、 ともちゃん(池脇千鶴)も付き合う男が皆暴力男で、捨てられてばかりいるのです。 なおこは、地元中学校教師のカシマさん(江口洋介)と密会を繰り返していました。 しかし、愛情を感じながらもなおこは掴み所のないカシマさんの態度に、戸惑いと孤独を感じていたのです。 田舎の漁村に暮らす、だらしない男たちとたくましく生きる女たちの姿を、コメディタッチで描いたお話でした。とりあえず。 みっちゃんは、フィリピンパブを切り盛りしていて、見るからにたくましい女性です。(小池栄子さんの個性そのままです。)ヒモ状態と化している旦那が、店の女の子に手を出しているということで逆上し、車で旦那を引き、自らも怪我してしまいます。 ともちゃんは、見た目はおとなしい地味な女(あまりにも地味すぎて、最初誰かわかりませんでした。)です。どうにも男運が悪いそうで、暴力を受けた上に捨てられてばかりだそうです。今の旦那は、暴力はしないそうですが、ギャンブルばかりしていて、とうとう家に帰ってこなくなってしまい、なおこが山に潜伏しているのに偶然出会うが逃げられ、その後、死体で発見されるというオチになってしまいました。 なおこの母は、町で唯一のパーマ屋を切り盛りし、出戻ってきた娘と孫の世話をし、とたくましいですが、再婚した夫(なおこはニュー父ちゃんと呼んでいるらしい、宇崎竜童)には逃げられてしまっています。(ニュー父ちゃんは別の家で、もっと年上の女と暮らしています。) “パーマネント野ばら”の常連客、パンチパーマの3人のおばちゃんたち(もちろん3人ともいい体格をしています。)は、店に集まっては、下ネタ連発でわいわい騒いでいます。その中のひとりが、気に入った男(細身の中年男)をラブホテルに連れ込んだ、という話が挿入されています。 そんな豪快というか、破天荒というか、たくましく生きる女たちのエピソードの中、なおこが、学校の理科室で、体育館で、トンネルのある山道(帰り道?)で、カシマさんと逢瀬を楽しむ場面が挿入されます。 カシマさんは、まさに理想的なカッコいい男で、なおこをとても大切に扱ってくれます。なおこも、彼と会っている時は、恋する乙女といった感じで、非常にかわいいしぐさや表情を見せています。(思わず、「惚れてまうやろー!!!」と叫んでしまいそうになるくらいです。) しかし、なにか、この2人の場面だけは、豪快な女たちの喧騒とは、まるで別世界で、非常に違和感がありました。 実は最後にその違和感が何かというのは明らかになるのですが、カシマがトンネルの所で一瞬消えてしまったり、2人で行った温泉への小旅行の時、突然先に帰ってしまったり、という風に、実はちゃんと伏線が作られていたのです。(その伏線のおかげで、僕は、「もしかして……。」と思ってしまいましたが。) というわけで、豪快なたくましい女たちに囲まれながら、唯一まともに見えるなおこが、実はとんでもない秘密を抱えているのですが、それは観てのお楽しみということにしておきましょう。 ということで、いろいろなエピソードを笑いながら、ラストはちょっと驚かされつつも、温かい気持ちになれる、そんな日本映画お得意のちょっといい話でした。 しかし、宇崎竜童さんって、本当はロックンローラーなのに、田舎の農家のオッチャンが異様に似合うのはどうしてでしょうか。
2013.01.21
コメント(1)
-

レンブラントの夜警
「レンブラントの夜警」 Nightwatching 2007年 カナダ・フランス・ポーランド・ドイツ・オランダ・イギリス映画監督 ピーター・グリーナウェイ出演 マーティン・フリーマン エヴァ・バーシッスル レンブラントの絵は好きです。明るいところはより明るく、暗いところはより暗く、その陰影を強調した画面は、主張したい部分がより強調され、ドラマチックな印象を与えます。そうしたドラマチックな演出が何かしら心を揺さぶられるからです。 とりわけ、その作品中最も有名な代表作「夜警」(実はこれは通称であり、正しくは、「フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長の市民隊」という題であり、昼間の情景を描いた絵画です。)は、明るい部分と暗い部分をより強調してドラマチックな印象を受ける、いわゆる“レンブラント・ライト”と呼ばれる斜めから当たる強い光の中、大きな画面に多くの人物を配し、同じポーズのものはひとりもおらず、それぞれがそれぞれの思いの表情を見せており、今まさに隊が出発するぞという時の喧騒な場面をリアルに切り取っており、そこから様々な音が聞こえてくるような感じがします。 しかし、実はこの絵画は、集団肖像画として描かれており、描かれている人物がそれぞれ依頼人であり、その位置や描かれ方に差があり、依頼人たちからは不評だったということを聞いています。 この絵が描かれた17世紀は、オランダ黄金時代と呼ばれており、オランダ(正しくはネーデルランド連邦共和国)が世界で1番勢いがあった時代です。世界中に植民地を持ち、輸入などの利益で非常に潤っていました。鎖国中の日本の長崎出島での独占貿易を始めたのもこの時代です。 したがって、裕福な人が多く、自らの姿を子々孫々に残しておこうと、肖像画を描かせる人々も多かったようです。 そんな時代、妻と裕福な画商であるその父親の力で、レンブラント・ファン・レインは、若くして自分の工房を持ち、多くの弟子もいた、売れっ子肖像画家でした。 当時の肖像画を注文する人々の感覚は、現代人が記念写真を撮るようなものだったと思われます。だから、大事なことは、自分自身の姿をよりそのままに写し取ることであり、集団肖像画では、ひとりひとりの注文主の肖像をひとりひとりよくわかるように描くことが必要なので、その見え方に差があってはいけないのです。 だから、肖像画家は、芸術家であってはいけないのです。大事なのは、お客さまの姿を正確に写し取る(時には美化したりすることもあったかな?)ことであり、そこに、自分の主張や思いが込められてはいけないのです。 しかし、レンブラントは芸術家でした。相手の姿を写し取るだけでは飽き足らず、自分の作品にドラマチックな場面を構成したかったのです。 そうした中で、「フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長の市民隊(通称「夜警」)」は作製され、不評を買い、その後徐々にレンブラントは没落していったのです。 と、僕は理解していました。そんな名画の製作秘話のようなものを描いた映画かな、と思い、非常に興味をひかれて鑑賞したわけです。 1641年、オランダ、肖像画家として成功したレンブラント(マーティン・フリーマン)は35歳にして人生の絶頂期にいました。妻のサスキア(エヴァ・バーシッスル)は画商を務め、ふたりは着々と富を築いていたのです。 1642年、アムステルダムの市警団から集団肖像画を依頼されますが、レンブラントは乗り気ではありません。しかし、産後の体調が優れないサスキアのためにいやいやながらも承知し、レンブラントは注文主の人となりを理解するために市警団の人間と付き合っていきます。 まず軍曹のロンバウト・ケンプの身辺に踏み込み、そこに罪の匂いを嗅ぎつけます。彼の表の顔は孤児院院長だが、裏では子供たちに売春させ、養女にした姉妹には自ら虐待を加えていたのです。 ある日、隊長が訓練中の誤砲で死んだという報せが入ります。副隊長が逃亡したため、新たな次期隊長と副隊長が任命されました。英国王女の来訪が間近で、この護衛任務にあたれば、栄誉と利益が待っています。そこに市警団の陰謀を感じたレンブラントは、絵筆で彼らの罪を告発することを決意します。 市警団はスキャンダルの宝庫でした。たどり着いた真相にレンブラントの心は沸き立ちます。 しかし、長男の産後、体調がすぐれないまま、妻のサスキアが亡くなってしまいます。 そんな悲しみの中、レンブラントはなんとか肖像画を完成させます。その出来上がった作品を見た市警団はレンブラントに罵声を浴びせ、陰湿な復讐を決意するのです。 確かに、「夜警」の製作にまつわるお話を描いた映画に間違いはなかったですが、ちょっと、僕の思惑と違いました。 レンブラントは集団肖像画を依頼してきた市警団のスキャンダルを告発するために「夜警」を描いたという思ってもみなかった設定だったのです。 やられました。僕は、芸術作品というものは、もっと純粋に描かれるものだと思っています。確かに作品のテーマとか、そこの込めた思いとかありますが、それが、宝物の隠し場所だったり、何かの暗号だったり、表面的なテーマとは違う読み方ができたり、といったことは違うと思うのです。 なぜ、人の姿を単純に写し取ることに飽き足らず、自分自身の芸術を描きたかったという、芸術家としての純粋な思いが、当時の肖像画の風潮にそぐわなかった、という芸術家の苦しみのようなものをテーマにするのではいけなかったのでしょうか。時代にマッチできなかった先駆的芸術家の苦悩のようなものがテーマではいけなかったのでしょうか。 映画の最後で、出来上がった「夜警」を見て、誰だかが「これは絵画ではない、演劇だ。」と言っている場面がありましたが、当時の“絵画”に対する認識というのはそうなんですよね。見たものをきれいに写し取ることが“絵画”だったわけです。そこに、作者の思惑による創作は入ってはいけないと思われていたのです。 現代ではそれは違うはずです。“絵画”は、物をその通りに写し取るものではなく、自分の“思い”を画面に表現することです。だからこそ、シャガールの人物は宙に浮いているわけだし、ピカソは様々な角度からとらえたモチーフをひとつの画面に再構成しようとするわけです。 その最後のせりふに象徴されるような、“絵画”に対する当時と現代との認識の違い、芸術としての“絵画”を描いた先駆的存在だったレンブラント、その辺をテーマにするべきではなかったのだろうか。 というか、余計なミステリーを盛り込んだおかげで、レンブラントの芸術に対する純粋な思いがないがしろにされているようで、ちょっと怒りを覚えたほどです。 レンブラントは好きな画家の1人ですし、その代表作「夜警」も好きです。 この映画は、前述の最後のせりふに合わせて、わざわざ、全編演劇のような画面で描かれており、衣装など非常に当時のものを研究して用意されていますし、とても気を使って丁寧に作られている作品だということはわかりましたが、芸術家レンブラントが描いた代表作を、スキャンダルまみれにしたということで、僕は、大嫌いです。
2013.01.20
コメント(3)
-

名探偵コナン 天国へのカウントダウン
「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」 2001年 日本映画監督 こだま兼嗣出演 高山みなみ他いつもの皆さん 年末に、「金曜ロードショー」で放映していましたね。 コナン映画第5弾、例の“黒の組織”が初めて映画の中で事件に絡んでくる作品で、コナン映画史上、もっともよく出来ているという評判の作品です。 コナンは、阿笠博士や少年探偵団とキャンプの帰り、西多摩市に新しく完成したツインタワービルを訪れました。すると、偶然、蘭や小五郎たちと遭遇します。蘭たちは、小五郎の後輩であるツインタワービルオーナーの常盤美緒に招待されていたのです。 コナン達はツインタワービルに入り、パーティに出席する市議会議員の大木岩松、日本画の巨匠・如月峰水、ビルの設計者・風間英彦、常葉の秘書である沢口ちなみ、「TOKIWA」専務の原佳明と知り合います。 その直後、ビルの玄関前にジンの愛車ポルシェ356Aが停まっていたことが判明し、“黒の組織”が何をしに来たのか、コナンは警戒します。 その夜、タワー内のホテルの一室で大木岩松が何者かに殺害され、遺体の横には割られたお猪口が一つ置いてありました。 大木岩松殺人事件の調査を始める少年探偵団は、原佳明の遺体を発見してしまいます、彼の横にも割れたお猪口が見つかっているのです。警察はお猪口から連続殺人として捜査を進めます。 タワー関係者の殺人事件が相次いだために、警察はタワーオープンパーティの延期を要請しますが、パーティは予定通り行われることになり、コナン達も出席することとなります。 しかし、パーティの最中、オーナーの常盤美緒が遺体で発見され、さらに“黒の組織”によって仕掛けられた爆弾が地下4階と地上40階で爆発します。コナンと蘭は避難経路を絶たれて絶体絶命の危機に陥ったが、辛くも脱出することができましたが、先にエレベーターで降りたはずの少年探偵団の姿がなかったのです。 なるほど、なかなかよく出来た作品でした。 ツインタワービルの完成に纏わる連続殺人事件、そこに”黒の組織”を絡め、爆発するビルからの脱出アクションと、灰原哀のドラマをうまく盛り込み、コンパクトにまとめられています。(上映時間100分です。) 今回の主役は、灰原哀です。 コナンファンなら、いまさら説明するまでもありませんが、一応、知らない人のために説明しておきましょう。 帝丹小学校1年B組の“少年探偵団”の一員である灰原哀は、実は18歳で、本名は宮野志保といいます。 もとは“黒の組織”の一員で、薬品の開発などを担当していた科学者で、“シェリー”と名乗っていましたが、組織に姉宮野明美が殺されたことで、組織を裏切ろうとしたが、監禁され、コナンが飲まされたクスリを飲み、体が小さくなってしまったため、脱出できたのです。 コナンの正体を知る阿笠博士に保護され、彼の家に居候しています。常に“黒の組織”の存在におびえているため、その情報を得やすい、コナンの身近にいる方がよいという判断からです。 そんな、灰原が、自分の居場所を模索するドラマが、サイドストーリーとして、殺人事件や爆破事件と絡んでくるわけです。 あいかわらず、“黒の組織”のやること(今回はツインタワービル爆破)が、秘密組織に似つかわしくなく派手だとか、犯人の残していくお猪口のメッセージは誰に向けてのものかとか、ミステリーとしては答えが簡単すぎるとか、少年探偵団と阿笠博士は一体1年に何回キャンプ(「名探偵コナン」のお話は、裏設定として、全編を通して、同じ1年をランダムに描いているというのがあります。だから彼らは学年が変わらないそうです。)すれば気が済むんだとか、少年探偵団死体発見しすぎとか、突っ込みどころもたくさんありますが、他のコナン映画のひどさ(特に「紺碧の棺」、以前の記事参照。)に比べたら、うまくまとまっていると思いました。 少年探偵団の歩美ちゃんや光彦君の淡い恋心もうまく絡めてあって、上手に伏線も回収できており、変なゲスト声優も起用されておらず、まあ、及第点を挙げてもいいかなと思う作品です。(なにこの上から目線!!??)
2013.01.19
コメント(2)
-

ジョゼと虎と魚たち
「ジョゼと虎と魚たち」 2003年 日本映画原作 田辺聖子監督 犬童一心出演 池脇千鶴 妻夫木聡 上野樹里 前々から、いい映画だとは聞いていたのですが、なかなか手が出ず、興味を持っていながら見ていなかった作品です。この年末に地上波で放映していたので、録画しておきました。 大学生の恒夫(妻夫木聡)は、バイト先の雀荘で、妙な噂を耳にします。それは、夜明けに乳母車を押して歩く奇妙な老婆の話でした。 ある日の明け方、店の用事で出かけた恒夫は、乳母車を押す老婆に出合います。 恒夫が恐る恐る乳母車を覗くと中には、年頃の女の子がいました。 恒夫は興味をひかれ、2人についていきます。女の子は、自らをサガンの詩の登場人物になぞらえ、ジョゼ(本名はくみ子、池脇千鶴)と名乗る、足の不自由な子でした。 恒夫は、適当にSEXさせてくれる女友達もおり、お嬢様然とした美人の彼女・香苗(上野樹里)もおり、バイトに精を出し、そろそろ就活でもするか、といった感じのごく普通の大学生です。 ジョゼは、原因不明だが、生まれつき足が動かない子で、両親に疎まれたため施設で育ち、祖母に引き取られてからは、“コワレモノ”と言われ、世間の目に触れないように育てられてきており、楽しみといえば、祖母が時々拾ってきてくれる本を読む事と、人目の少ない夜明けに行く、乳母車に乗せられての散歩だけでした。 そんな2人の恋愛物語です。 いやあ、いい映画でした。恋愛ものは苦手なのですが、この映画は純粋にいいと思ってしまいました。 以下、何がよかったか触れていきますが、過分にネタバレも含んでおりますので、結末を知りたくない人は読まないようにね。 何がいいって、やっぱりまず脚本でしょう。 文字通り箱入り娘で、半ば軟禁状態で育てられたため、人との接し方がわからず、口のきき方もわからない、ジョゼのぶっきらぼうなしゃべり方、世間知らずで、わがままで、実はさみしがり屋だけど、強がっている、そんな彼女のキャラクターを如実に表しています。 しかも、全編を通して同じようにぶっきらぼうなのですが、恒夫とジョゼ、2人の関係が変化するにしたがって、微妙に変化していくところ絶妙です。 最初は、警戒心から、言葉足らずな感じだったのが、親密になって来るにつれて、だんだん親しみが籠ってきて、男女の関係になってからは、わがままいっぱいだけど愛情が籠っており、別れを意識し始めてからは、なんとなく感慨深げになってきます。 もちろん、それは池脇千鶴の演技力のなせる技かもしれませんが、脚本のうまさがそれを引き出しているのは否定できないでしょう。 また、意味の深い、印象に残るセリフの数々があるということ。 例えば、「お前は“コワレモノ”だから、その分をわきまえなきゃいけないんだ。」と言うおばあさんとか、「あんたのその武器が憎い」と言った香苗に対し、「だったら、その足切ればいいじゃないか。」と返すジョゼとか、「世界で一番Hなことしていいよ。」とか、「私はその暗い海の底にいたんよ。」とか。 それから、原作の短編を1本の映画に作り上げるために、つけ足したところの見事さ。 恒夫の彼女だった見るからにお嬢様な香苗の存在、ラストに2人を別れさせたところなど、テーマをより深くえぐり出しているような感じがします。 次に、出演者の皆さんの巧みな演技。 妻夫木は、初めは興味本位で、そして同情から純粋な恋愛へ発展し、結局は現実を考えて、その重みに耐えかねて身を引く、という、まさに現代の若者そのものを、全くの自然体で演じています。こういう自然な感じというのが実はすごく難しかったりするんですよね。 上野樹里は、相談したいことがあると言いながらしっかりモーションを掛けてきて、大した覚悟もないのに格好だけで福祉を勉強したいという、いかにもで、その存在が鼻に付くお嬢様を好演しています。 このときなんと17歳だそうで驚きですが、「スイングガールズ」でブレイクする前の年です。もちろん、「のだめ」の大ブレイクはもっと後になります。 しかし、「のだめ」のイメージと、インタビューやバラエティで、時々見られる素の彼女の天然イメージからすると信じられないほどのお嬢様ぶりです。 実はとってもきれいな子だったんですね。どうも僕の中では、「のだめ」のイメージが抜け切れません。大河は見ていないので。 そして、なんといっても、ジョゼ役の池脇千鶴です。 とにかく、いちいちのセリフ、仕草が、憎たらしいほどすごいです。 煮物のレンコンを味見させた後の箸を、しばらくそのまま出したままにするところとか、唐突に手を握られ、思わず力を込めてしまうところとか、長らくの軟禁生活のため、仮面のように張り付いてしまった無表情なのに、微妙に目つきが違ったり、口の端で笑ったりとか、「帰れって言われて帰る奴は本当に帰れ!!。」と言いながら、背中をたたく仕草とか、もう、TVの前で、「惚れてまうやろー!!」と何度叫んでしまったことでしょうか。 まだ、20歳そこそこのはずですが、自らブラウスとブラジャーを取るベッドシーンも含めて、なんとすごい子だろうと思ってしまいました。 身障者と暮らすということ、対等な人間であろうとすること、そういうことを、どう考えたらいいのか、しっかりと考えさせられる作品でした。 しかし、ラスト、ジョゼと別れた後で、「障害者に彼氏取られた」発言をした香苗と共に去っていく恒夫、というのはちょっといかがなものか、と思ってしまったのは、私だけではないはずです。そこまで恒夫の株を下げなくてもいいだろう、と思ってしまいました。素晴らしい映画ですが、そこだけはいただけませんでした。
2013.01.16
コメント(3)
-

ショコラ
「ショコラ」 Chocolat 2000年 アメリカ・イギリス映画監督 ラッセ・ハルストレム出演 ジュリエット・ビノシュ ジョニー・デップ ジョディ・デンチ キャリー=アン・モス アルフレッド・モリーナ 年末年始に、地上波で夜中に映画がいっぱい放映されていました。そのうちのひとつです。確か、まだ、売れていないころのジョニー・デップが出ているヤツだなあ、と思い、どんな映画かはよく考えず、録画しておきました。 フランスのある村に一組の親子が北風とともにやってきました。その親子・ヴィアンヌ(ジュリエット・ビノシュ)とアヌークは、マヤから受け継がれるチョコレートの効能を広めるため世界中を旅していて、この村でも老女・アルマンド(ジョディ・デンチ)から借りた物件でチョコレート店の開店準備を始めます。 ヴィアンヌは、一人一人の希望にぴったりと合うチョコレートを差し出し、その不思議なチョコレートの作用から村人達を惹きつけていきます。とりわけ、夫の暴力に悩むジョセフィーヌや、その奔放な性格のせいで厳格な娘カロリーヌ(キャリー=アン・モス)から絶縁されているアルマンドにとっては、ヴィアンヌの明るく朗らかな人柄やチョコレートの美味しさと不思議な効果は、ひとときの安らぎとなるのです。 しかしミサにも参加しようとせず、私生児であるアヌークを連れたヴィアンヌの存在は、敬虔な信仰の体現者で村人にもそれを望む村長のレノ伯爵(アルフレッド・モリーナ)の反感を買ってしまいます。レノは村人たちに、ヴィアンヌのチョコレート店を悪魔的で堕落したものだと説いて出入りを禁じるのです。 そんなある日、村にジプシーの一団が流れ着きます。レノによって村人たちから「流れ者」としてボイコットされる彼らと境遇を同じくするヴィアンヌは、そのリーダーであるルー(ジョニー・デップ)と思いを交わします。そんな様子を知ったレノは、ますますヴィアンヌに対する風当たりを強めていくのでした。 閉鎖的で排他的な村に流れてきた親子が、チョコレートを通じて、村人と心通わせ、村の人々も、その親子も心が癒されていくという、心洗われるドラマでした。 信教に敬虔な堅物の村長レノ伯爵も、奔放な母親からの反発で息子に厳しかったカロリーヌも、厳格な母親のおかげで祖母に合わせてももらえていなかった息子リュックも、娘との確執で孫に会わせてもらえなかったアルマンドも、夫からDVを受けていたジョセフィーヌも、流れ者で行く先々で歓迎されず寂しい思いを持っていたジプシーのリーダー・ルーも、そして、主人公のヴィアンヌ・アヌークの親子も、みんな救われるという、心温まるお話でした。(たったひとり、DVしていたジョセフィーヌの夫だけは救われませんでしたが。) まあ、ちょっと時間が空いた時に観る、心癒される佳作といった感じでしょうか。 初対面で、日曜のミサに行かない宣言をしてしまったヴィアンヌは、堅物で敬虔なクリスチャンである村長のレノ伯爵ににらまれてしまいます。また、ルーたちジプシーは、その存在自体敬遠されてしまいます。そして、村長は村人たちを煽り、ヴィアンヌ親子やジプシーたちを排除しようと動き始めます。 僕は常々こういった異教徒や不信心者を排除しようとする、とりわけ熱心な信教家ほどみられるこの傾向が非常に気になっています。特に、キリスト教、イスラム教にその傾向が強いように見受けられますが、なぜ、自分の信じるところと違うというだけで、その人の人となりや性格など全く考えずに毛嫌いしたり、排除したり、攻撃したりするのでしょうか。 確かに、男女関係とか、親友とかのように、深く付き合うのには宗教的な一致は必要かと思いますが、ふつうの知り合い、ご近所さんぐらいの付き合いなら、別に宗教的に一致しなくてもいいんじゃないでしょうか。あいさつ程度の表面的な付き合いにとどめておくとか、相手にしないでおくとかではいけないのでしょうか。なぜ、積極的に排除しようとしたり、嫌がらせをしたりしなければならないのでしょうか。 魔女狩り、宗教裁判、十字軍、ナチスのユダヤ迫害、中東戦争など、人の歴史が始まって以来、宗教的な対立や支配、戦争など、人の生死に関わる争いが起こっています。 そういった異教徒を積極的に排除しようする意識が、その一因となっているということは否めない事実でしょう。 「信じる者は救われる」というお題目は、裏を返せば、「信じない者は救われない、排除しよう」ということになっていくわけで、人々を救うはずの宗教が、人々の争いの元になっているというのは、本末転倒ではないでしょうか。 そんな“裏テーマ”を、この映画から感じてしまいました。 ところで、ヴィアンヌが店を構えた家の大家アルマンドに反発するあまり、息子を厳しくしつけているカロリーヌ、何となく見覚えがあるなあ、と思っていたら、何と、「マトリックス」の主人公救世主ネオの彼女となる、戦う女トリニティーでした。 黒いレザーファッションに身を固め、勇ましく戦う女からはかけ離れた、長い髪で、女性らしいワンピース姿でしたが、その独特の冷たさを秘めた鋭い目力は隠しようが有りませんでした。 やっぱり彼女は、その容貌から、こういった冷たさを持った女しかできないのでしょうか。ちょっと気になります。(以前からこのブログをご存知の方はよくわかっているとは思いますが、僕のタイプからは180度離れている女性ですが。) あと、アルマンド役のジョディ・デンチというイギリスのベテラン女優さんが、偏屈な老女を装いながら、その優しさ、寂しさを密かに匂わせるというなかなか老獪な演技力を発揮し、圧倒的な存在感を出しているのが、さすがだなあ、と思ってしまいました。 そう、あの、007シリーズで、Mを演じている大女優さんです。 ということで、元々はギタリストだったジョニー・デップのギター演奏も観られる、お得な佳作を今回は紹介しました。
2013.01.13
コメント(3)
-

インディ・ジョーンズ/最後の聖戦
「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」 Indiana Jones and the Last Crusade 1989年 アメリカ映画製作総指揮 ジョージ・ルーカス監督 スティーヴン・スピルバーグ出演 ハリソン・フォード ショーン・コネリー リバー・フェニックス ジョン・リス=デイヴィス デンホルム・エリオット 前回の記事のため、ショーン・コネリーの007を見たら、そういえばインディのお父さんで、彼がいい味を出していたなあ、と思い、この映画をまた観てしまいました。 1938年、冒険家として、また考古学教授として多忙な日々を過ごすインディ・ジョーンズ(ハリソン・フォード)に、大富豪ドノヴァンから相談が持ちかけられます。イエス・キリストの聖杯の所在を示す重大な遺物を手に入れたが、調査隊の隊長が行方不明になり、それを探して欲しいというのでした。 最初は渋っていたインディでしたが、その行方不明になった隊長というのが自分の父、ヘンリー・ジョーンズ(ショーン・コネリー)であると聞き、仕方なく依頼を承諾しました。 インディは、父と旧知の仲である副学長のマーカス(デンホルム・エリオット)とともに、父が最後に消息を絶ったヴェネツィアに向かうのでした。 この映画、なんといってもショーン・コネリー演じるインディの父、ヘンリー・ジョーンズに付きます。 次から次へ続くアクションで、ジェットコースタームービーだった前作「魔宮の伝説」との差別化を図るためにか、今回はアクションは控えめで、どちらかというと、お父さんを登場させて、その絡みをコメディタッチの描くことに重点が置かれているようです。 このお父さんヘンリー・ジョーンズ・シニア(実はインディの本名はヘンリー・ジョーンズ・ジュニアだったのです。お父さんからジュニアと呼ばれるたびに嫌がっており、その呼び方を嫌い、自らインディアナ・ジョーンズと名乗っているようです。)は、長年、イエス・キリストの聖杯を研究しているようで(その研究成果が詰まっている彼のメモ帳が、今回の重要アイテムとして登場します。)、インディのような研究者兼冒険家ではなく、文献などでとことん調べる、書斎派の研究者の様です。 研究一筋で、世俗に疎いタイプの天然ボケキャラで、敵(もちろんナチス)の隠れ家で軟禁されているという状況にもかかわらず、助けに来たインディから、聖杯の在り処がわかったというニュースを聞き、興奮してしまったり、敵の戦車の中に捕まっているマーカスを助けに来たのにもかかわらず、久々の再会にはしゃいでしまい、脱出できずに自分も捕まってしまったり、ナチスの飛行船から脱出用の小型機に2人で乗り込み逃げ出した時も、後部座席の機関銃で、敵機を撃つようにインディに言われますが、勝手がわからず、自機の垂直尾翼を撃ってしまったり、というように、天然ぶり全開の描写が目白押しです。 そんなヘンリーの天然ボケに、せっかちなインディが突っ込みを入れるといった感じで、2人の会話はまるで漫才の様です。 もう完全に、「ヘンリー・ジョーンズの最後の聖戦」という題名の方がふさわしいような、存在感に、さすがのインディも終始食われっぱなしです。まさに百戦錬磨のベテランの存在感でしょうか。 しかし、実はこの2人12歳しか離れておらず、ちょっと親子というには歳が近すぎます。若く見えるハリソン・フォード(たぶんここでは30代ぐらいの設定でしょう。)と、老けて見える(特に頭部が)ショーン・コネリーなので、大丈夫なのでしょうね。 また、今回は、冒頭でまだ少年期のインディ(リバー・フェニックス)の活躍が描かれているのも見どころです。 そこで、カウボーイハットやムチ、蛇嫌いなどのインディの特徴の由来が明らかになるところは、ファンにとってはたまらないものがあるでしょう。 もちろん、まだまだ若い少年ですから、いつにもまして体を張ったアクション全開で描かれており、冒頭のつかみとしては満点です。 ちなみに、第1作でも登場する、エジプトでの協力者、サラ-に扮しているジョン・リス=デイヴィスですが、「ロード・オブ・ザ・リング」3部作では、ドワーフのギムリを演じています。 「ロード・オブ・ザ・リング」のドワーフは低身長の種族なので、CG処理で、終始、120cm位になっています。(フロドたちホビットよりは大きいですが。) でも実際は、インディよりも大きい大男だったんですね、 ということで、コメディ感たっぷりで、シリーズ4作中、僕が1番好きな作品を、今回は紹介しました。後の3作も、またいつか紹介しますね。 ところで、副題に“最後の”とあるので、シリーズがこれで終わりなんだと勘違いしている方がたくさんおられるみたいですが、聖戦(ここでは十字軍のことですかね。)が最後という意味なので、シリーズが最後という意味ではないはずです。その証拠に第4作が作られていますからね。第5作はちょっとハリソン・フォードの歳を考えると、難しいですかね。
2013.01.09
コメント(3)
-

007 ロシアより愛をこめて
「007 ロシアより愛をこめて」 007 From Russia from Love 1963年 イギリス映画監督 テレンス・ヤング出演 ショーン・コネリー ダニエラ・ビアンキ ロバート・ショウ ロッテ・レーニャ 007映画50周年記念ということで、007シリーズをすべて観返そうと宣言しての第2弾です。今回は、シリーズ中最高傑作と言われる、シリーズ第2作をお送りします。ジェームズ・ボンドは、セクシー&タフガイとして、やっぱり1番と言われる、初代ショーン・コネリーです。 犯罪組織「スペクター」は、ドクター・ノオの陰謀を阻止した英国海外情報局の諜報員007ことジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)の暗殺、そして暗号解読機“レクター”を強奪するという計画を立案しました。 実はスペクターの幹部であるソ連情報局のクレッブ大佐(ロッテ・レーニャ)は、真相を知らない部下の情報員タチアナ・ロマノヴァ(ダニエラ・ビアンキ)に暗号解読機を持ってイギリスに亡命すること、またそこにはボンドが連行する事が条件だと言うことを命令します。 ボンドは、罠の匂いを感じつつも、トルコのイスタンブールに赴きます。 しかし、そこにはスペクターの刺客・グラント(ロバート・ショウ)が待っていました。 この映画の何が傑作なのかと言うと、007シリーズにありがちな荒唐無稽さ、SFっぽさが全くなく、スパイ映画としての緊迫感、肉体派アクションに徹しているというところでしょうか。 それは、今回の悪役グラントの存在が大きいでしょう。 冒頭、グラントがワイヤーが出てくる腕時計を使い、ボンドの首を絞め、抹殺する場面から始まります。実はそれは訓練で、ボンドのマスクをかぶった別人だったのだが、ここで観客は、グラントの恐ろしさを知るとともに、訓練のため、容赦なく人の命を奪うことのできる組織の冷徹さも知らされるのです。 そして、前半は、なかなかグラントとボンドの対面をさせず、ボンドが動くたびに、その背景にチラッと尾行するグラントの姿を見せ、緊迫感を煽っています。 そして、後々語り継がれることとなるオリエント急行での対決の場面となるのです。 そのオリエント急行の場面で活躍するのが、秘密兵器のいろいろな仕掛けつきのアタッシュケースです。 冒頭、上司のMから、今回の任務を言い渡されるジェームズ・ボンド、ここで、秘書のマニーペニーとちょっとHなやり取りがあるのはお約束なのでしょうが、もうひとつのお約束が、開発局のQから渡される新兵器の説明です。今回の新兵器は、いろいろなカラクリ付きのアタッシュケースです。組み立て式のライフルが入っていたケースには、困った時のために50枚の金貨がしこまれており、いざという時のためにナイフが飛び出す仕組み、そして留め金を横に回しておかないで開けると煙幕のガスが出てくる仕組みです。 この秘密兵器をうまく使い、ボンドは危機を脱することができるのです。やっぱりスパイ映画はこうでなくっちゃ、という場面です。 それから、忘れちゃいけないのが、やっぱりお約束のボンド・ガールです。 ソ連の女スパイ・タチアナ・ロマノヴァ役のダニエラ・ビアンキ、本当にきれいな人です。歴代ボンド・ガール中ナンバー1という呼び声も高い彼女ですが、かつてミス・ローマとしてミス・ユニバースにも出場経験のあるイタリア女性です。本当に色っぽくて、美しい女性で、もちろん、ボンドといい仲になるのは、お約束ですが、第一線で活躍していたソ連の女スパイということなのだが、終始、ボンドの言いなりで、自分から積極的に動こうとしないのが、気になりました。また、ソ連のスパイで、亡命したいというのは実は作戦で、最後にどんでん返しがあるのかなと思っていたのですが、それもなく、ただのきれいな女性というだけでした。この後、他の映画で、という話は全く聞かなかったので、結局ただきれいというだけの女性でした。 それから、もうひとり忘れてはならない女性がいます。実はスペクターの幹部となっている、ソ連情報部のクレッブ大佐役のロッテ・レーニャです。 彼女に言わせれば、歴代最高齢のボンド・ガールだそうですが、さすがにちょっと無理があります。しかし、要所要所に登場するその存在感は大したもので、ドイツの舞台で主に活躍していたオーストリア人の女優さんです。(最後の場面は追い詰められてのこととはいえ、ちょっと滑稽でした。) ということで、初代ボンド・ショーン・コネリーのセクシー&タフガイな魅力をたっぷり楽しめる傑作を今回は紹介しました。
2013.01.06
コメント(3)
-

ウィンターズ・ボーン
「ウィンターズ・ボーン」 Winter’s Bone 2010年 アメリカ映画監督・脚本 デブラ・グラニク主演 ジェニファー・ローレンス 「X-MENファースト・ジェネレーション」で、若き日のミスティークを十二分な存在感で好演し、注目していた若い女優さん(ちょっとタイプだったのでということもありますが。)が、米アカデミー賞の主演女優賞にノミネート(作品・脚色・助演男優賞も)された作品があるという情報を得て、それは観てみなければと思い、レンタルしてきました。 調べてみたら、サンダンス映画祭でグランプリを受賞した作品で、彼女も、アカデミー賞だけでなく、様々な映画賞の主演女優賞にノミネートされており、いくつかの賞を受賞しているようです。 ちなみにサンダンス映画祭というのは、ロバート・レッドフォードが主催する映画祭で、「明日に向かって撃て」で彼が演じた“サンダンス・キッド”から、名付けられたもので、インディペンデント映画を上映する映画祭です。「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」や「セックスと嘘とビデオテープ」や「ソウ」などが注目され、ケヴィン・スミス、クエンティン・タランティーノなどの監督が世に出てくるきっかけになっています。 ミズーリ州の山中の村で、17歳の少女リー(ジェニファー・ローレンス)はまだ幼い弟と妹、そして精神を病んだ母を抱え、一家の生活を支えていました。 ドラッグを製造・販売していた父のジェサップは警察に捕まっており、懲役刑を言い渡されていました。 ある日、保釈保証人が現れ、自宅と土地を保釈金の担保にして保釈中だということ、翌週の裁判に彼が出廷しなければ、家と土地は没収されてことを告げていきます。 リーは伯父や村人たちに父の消息を聞いて回りますが、何故か誰もが彼女と会うことすら拒もうとします。やがて彼女はどうやら父が既に死んでいるらしいことを察します。 アメリカという国は、世界のリーダーを自負しており、最先進国であるがごとく印象を持っている人が多いと思いますが、実は生活保護とか、健康保険とか福祉的な部分では、全く充実してはおらず、生活弱者が、犯罪に走る率が非常に高い国です。 そんな社会に最下層で、何とか、自分と家族を守ろうとするけなげな少女の物語です。 父の消息を調べて回るうちにリーは、村のみんなが何か隠し事をしていることに気付きます。どうやら、麻薬の製造・販売は、村全体で作る“組織”の仕事らしく、父のジェサップは、その“組織”の掟に逆らい、その秘密を暴こうとしているらしいことに気づくのです。 実は保釈金は、家・土地を担保にしただけでは足りなかったのですが、何者かが現れ、その足りない分の現金を払っていたということがわかり、父は”組織”の秘密をばらさないために始末するために保釈されたのだ、ということをリーは推察したのでした。(ネットで、感想を調べていたら、「保釈金の足りない分はだれが払ったの?」などという見当違いなことを言っている人がいました。そのくらい推察しなさいよ。恥ずかしいです。) 僕は、観ていて、だんだん腹が立ってきました。生活弱者に優しくないアメリカという国にはもちろんなのですが、ここでは、むしろ、“組織”のボスに対してです。 リーが、話を聞きたいと、“組織”のボスを訪ねて行ったところ、彼は全く会ってくれませんでした。仕方がないので、彼の職場に直談判に行ったところ、その夜、リーは“組織”の女たちのリンチを受けてしまいます。 何というボスでしょう。確かに父のジェサップは、“組織”の掟を破ったので、処分されてもしかたないでしょう。しかし、彼の家族、とりわけ何も知らない子どもたちには何の罪もありません。ジェサップを処分するのなら、その残される家族は、“組織”が守ってやらなければいけないでしょう。それが“組織”のボスの責任でしょう。 それなのに、真実を知ろうとするリーから逃げ回るだけではなく、傷めつけて黙らせようとするなんて、愚の骨頂です。そんなことだから、ジェサップに裏切られるのですよ。 なんてことを思ってしまいました。 結局、伯父のティアドロップ(父の兄)の手助けもあり、何とかリーと幼い弟妹は、救われます。(しかし、リーはおぞましい経験をさせられます。それは何かは内緒にしておきます。題名と関係ある、とだけ語っておきましょう。) とにかく、リーの孤軍奮闘ぶりは素晴らしいです。もちろん、それを演じているジェニファーが素晴らしいのです。今後大注目の新人です。
2013.01.04
コメント(3)
-

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」
「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」The Lord of the Ring : The Return of the King 2003年 ニュージーランド・アメリカ映画監督 ピーター・ジャクソン出演 イライジャ・ウッド ショーン・アスティン ビリー・ボイド ドミニク・モナハン イアン・マッケラン ヴィゴ・モーテンセン オーランド・ブルーム ジョン・リス=デイヴィス ということで、第3弾です。 本作は、米アカデミー賞の作品賞・監督賞・脚本賞など過去最多タイの11部門を受賞しています。実は「1」「2」も、作品賞などにノミネートされていますが、視覚効果賞とか美術賞とか技術系の賞のみの受賞に留まっています。どうやら、アカデミー賞協会の皆さんは、「1」の時も「2」の時も、その作品の完成度には注目していましたが、「1」も「2」も明らかに完結していないので、その評価はすべて完結してからと思っていたようで、この映画の完成で3部作が完結したことにより、作品賞受賞ということになったようです。まあ、話はしっかりつながっているので、3本で1つの物語という解釈でしょうか。 この第3部の題は“王の帰還”、その王とは、もちろん、イシルドゥア王の末裔アラゴルン(ヴィゴ・モーテンセン)のことです。彼は強く決断力にも長け、王としての素質は十分ですが、イシルドゥアがかつての冥王サウロンを倒し“指輪”を手に入れながら、葬り去ることができなかったことを恥じ、“さすらい人”に、身をやつしていたのです。 この物語は、そんな彼が、ホビットのフロド(イライジャ・ウッド)たちの“指輪”を捨てる旅に加わることにより、サウロンの精神が支配し、闇の魔法使いサルマンが組織するオークやウルク=ハイの軍勢と戦う中で、人間の王となることを決意する物語でもあるのです。 前作の最後で、ローハンでの戦いに辛くも勝利し、そのままローハンに留まっていたアラゴルンのところへ、裂け谷に住むエルフの長エルロンドがやってきます。彼は裂け谷に保管されていた、かつてサウロンを倒した時に砕けたイシルドゥアの剣を打ち直し、アラゴルンに渡そうと持ってきたのです。そして、“死者の道”と呼ばれる場所に、かつてイシルドゥアに忠誠を誓いながら果たさなかったため成仏できず彷徨っている死者たちがいる、アラゴルンが命じるならば彼らは戦いに加わるだろうと、助言を与えます。 アラゴルンは、エルロンドの助言に従い、エルフの弓の名手レゴラス(オーランド・ブルーム)と、ドワーフの戦士ギムリ(ジョン・リス=デイヴィス)とともに“死者の道”に向かい、幽霊たちを説得し、戦いに参加させることに成功します。 そのおかげで、無数の援軍を得て、闇の軍勢に圧倒されていた人間軍は、形勢を逆転することができたのです。 幽霊たちがアラゴルンに従ったということは、イシルドゥアの剣を持っていた彼を、幽霊たちはイシルドゥアの後継者、つまり、人間の王として認めたということに他ならず、アラゴルン自身が、人間の王と成る覚悟を見せたということです。 一方、前作の最後、サルマンの本拠地を壊滅させるという大活躍を見せた、ホビットのやんちゃ坊主コンビ、ピピン(ビリー・ボイド)とメリー(ドミニク・モナハン)ですが、今回は別々に行動します。 ピピンは復活した魔法使い白のガンダルフ(イアン・マッケラン)とともに、闇の軍勢の攻撃されている人間の国ゴンドールへ向かいます。もちろんガンダルフとともに、戦闘に加わるピピンですが、いかんせん小柄(ホビットとしては普通)なため、はっきり言って、あまり戦力になりません。 しかし、敗色濃厚なため、精神的に追い詰められ、ご乱心するゴンドールの執政デネソールが、戦闘から離れ、虫の息だが、まだ息のある息子ファラミア(「1」で旅の仲間に加わるが、惜しくも途中で亡くなってしまうボロミアの弟。)を火葬しようとするのを、体を張って阻止したのがピピンでした。 メリーは、ローハンで、ゴンドールへの援軍に加わろうとしますが、ローハンのセオデン王と、軍を指揮している王の甥エオメルに、ホビットには荷が重いということで、認めてもらえませんでした。 すると、女ということで出陣させてもらえなかった、王の姪(エオメルの妹)エオウィンに呼ばれ、一緒によろいを着て馬に乗り、密かに援軍に加わるのです。 この物語、主人公はフロド、次にアラゴルンですが、実はヒーローは、ずーっとフロドに付き従っているホビットの庭師サム(ショーン・アスティン)です。 サムは、フロドが“指輪”のことをガンダルフから聞いているところについ居合わせてしまったときから、時には助け、時には励まし、ずーっとフロドに付き従ってきたのです。特に「2」からゴラムが道案内のため同行するようになってからは、密かに“指輪”の奪還を目論んでいるゴラムを常に警戒し、その暗躍を阻止してきたのです。 しかし、モルドールまであと1歩という岩山まで来たとき、ゴラムの策略に引っ掛かり、フロドが、“指輪”の魔力に徐々に魅せられて行き、だんだんと精神的に不安定になって来たこともあり、とうとうフロドに疎まれ、仲たがいをしてしまいます。 ところが、サムはめげませんでした。その後、岩山の洞窟で、フロドが巨大なクモに襲われ、毒のため動けなくなり、糸でぐるぐる巻きにされてしまったとき、フロドに「帰れ!!」と言われてしまいましたが、実は離れてついて来ていたサムが現れ、勇敢に巨大なクモの怪物と戦い、退けることに成功します。その上、サムがクモと戦って退けた直後、突然現れた数人のオークに、動けないフロドをさらわれてしまいましたが、オークたちの後を追い、勇敢に戦い、オークたちを倒し、見事にフロドを救います。 そして、溶岩がゴロゴロしている火山を登り始めてからは、やはり“指輪”の魔力にさいなまれ、途中で力尽きて倒れてしまったフロドに、「おれに指輪は運べないけど、フロド様は運べます。」と言い、ほぼ同じ大きさ(サムの方がやや太めです。ゴラムはサムのことを“デブのホビット”と呼んでいました。)のフロドを抱え、山を登り始めるのです。この場面、もう涙なしには見られません。 フロドは、最後に「お前がいてくれてよかったよ、サム。」とついつぶやきますが、本当に、サムがいなかったら、フロドはその使命を果たすことはできなかったでしょう。僕は心の奥底からそう思います。 最後に王となったアラゴルンが、4人の小さな仲間たちに向かって、「礼を言う。」と言って頭を下げる場面があります。カメラは4人のホビットを映しながら、フロドにズームしていきますが、僕は、「違うだろ!!サムだろ、ズームするのは。」と思わず突っ込んでしまいました。そして、その後のサムの結婚式の場面、心の奥底から「よかったね、サム。」と思っていました。 ということで、「ホビット・サムの大冒険」を見たい人は、とにかく思いっきり覚悟して、体力と時間が有り余っているときに、一気に見るといいでしょう。9時間以上かかりますが。
2013.01.03
コメント(2)
-

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔
「ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔」 The Lord of the Rings : The Two Towers 2002年 ニュージーランド・アメリカ映画監督 ピーター・ジャクソン出演 イライジャ・ウッド ショーン・アスティン ビリー・ボイド ドミニク・モナハン イアン・マッケラン ヴィゴ・モーテンセン オーランド・ブルーム ジョン・リス=デイヴィス クリストファー・リー それでは、第2弾です。 前作の最後で、3つに分かれてしまった旅の仲間たちです。 ホビットのやんちゃ坊主コンビ、ピピン(ビリー・ボイド)とメリー(ドミニク・モナハン)は、敵の魔法使いサルマンのホビットを生きたまま連れて来いという命令で、オークとウルク=ハイの軍勢にさらわれたのです。(サルマンはホビットが“指輪”を持っているという情報を仕入れていて、本当はフロドを捕まえたかったらしい。) さすらい人(実は人間の王となるべき存在)のアラゴルン(ヴィゴ・モーテンセン)と弓の名手のエルフの王子のレゴラス(オーランド・ブルーム)とドワーフの戦士ギムリ(ジョン・リス=デイヴィス)はピピンとメリーを助けに、敵を追って行きます。 そして、主人公のホビット・フロド(イライジャ・ウッド)とサム(ショーン・アスティン)は、本来の目的である、“指輪”を葬り去るために、モルドールへ向かうのです。 この映画で注目すべきは、やはり、新登場のゴラムでしょう。 2人でモルドールへ向かうフロドとサム、すぐに何者かがつけてきていることに気がつきます。待ち伏せして捕まえてみると、それは、“指輪”の元の持ち主であるゴラムでした。 彼は、元々はホビットに近縁の種族でしたが、“指輪”を手に入れてからは、その魔力に魅せられ、“指輪”を“愛しい人”と呼び、その魔力により“餓鬼”のような姿に豹変し、長い年月を生きながらえてきたのです。(その時の模様は、「3」の冒頭で描かれています。) その“愛しい人”がなぜ、ホビットのビルボ・バギンズ(やはりその魔力に魅せられつつあったが、ガンダルフに説得され、“指輪”を息子のフロドに託して旅に出た。)の手に渡ったのかが描かれているのが、このほど公開が始まった「ホビット」3部作ということで、とても楽しみです。 ゴラムは、2人をモルドールへ道案内すると言い、同行しつつ、スキあらば“指輪”を奪おうとしています。しかし、少ないながらも残っている良心との呵責にさいなまれ、次第に2重人格的になっていきます。 アラゴルン・レゴラス・ギムリの3人は、ひたすら走ってピピンとメリーをさらって行ったウルク=ハイの軍団を追いますが、彼らが逃げて入っていった森の中で、復活したガンダルフ(イアン・マッケラン、進化して“白のガンダルフ”になっています。)に、2人の無事を知らされます。その後は、ガンダルフとともに、悪の魔法使いサルマン(クリストファー・リー)の軍団に狙われている、人間の国ローハンを救うべく、戦闘に参加します。 そして、僕的に大注目のピピンとメリーですが、さらわれたウルク=ハイの軍団が、ローハンの兵士たちに襲われた混乱に乗じて、逃げ出すことに成功します。 2人が逃げ込んだ先は、ファンゴルンの森でした。そこにはエント族と呼ばれる木の精が住んでいました。 ガンダルフの口添えで、そのエント族に保護されたピピンとメリーですが、2人は、体も大きく強大な力を持っているエント族を、何とか戦いに参加させられないだろうかと画策し、その内容は伏せておきますが、大きな成果(たぶん、今回の1番の成果です。)を上げています。 「1」の最初でガンダルフの花火をいたずらして、大爆発を起こしてひんしゅくを買っていたように、ただのいたずら好きなやんちゃ坊主ペアだった2人ですが、成り行きでついてきてしまった2人ですが、彼らなりに闇の勢力との戦いのことを考え、小さな体で非力な自分たちだが、何とか助けになりたいと努力しているのです。 もちろんそれは、“指輪”を葬り去らなければならない使命を帯びている、フロドの姿に心打たれたということもあるのだと思いますが、外界との交流が少ないホビット庄を出て、旅をすることで、世の中の大変な状況を理解し、自分たちも何かしなければと思ったのだと思います。彼らの成長が手に取るようにうかがえて、頼もしい限りです。 彼らは、「3」でも大活躍しているので、また語りたいと思います。 もちろん、「1」同様、壮大な“中つ国”の世界を見事に映像化していることは語るまでもないことですで、その美しく、迫力のある映像は、一見の価値ありです。 では、次回もお楽しみに。
2013.01.02
コメント(3)
-

ロード・オブ・ザ・リング
「ロード・オブ・ザ・リング」The Lord of The Rings : The Fellowship of the Ring 2001年 ニュージーランド・アメリカ映画監督 ピーター・ジャクソン出演 イライジャ・ウッド ショーン・アスティン ビリー・ボイド ドミニク・モナハン イアン・マッケラン ヴィゴ・モーテンセン オーランド・ブルーム ショーン・ビーン ジョン・リス=デイヴィス イアン・ホルム リヴ・タイラー クリストファー・リー あけましておめでとうございます。見事に“マヤの予言”(?)は外れ、無事に迎えた2013年のお正月、その新春第1弾は、歴史に残る名作をご紹介します。 皆さんご存じのJ・R・R・トールキンの「指輪物語」の実写映画化作品です。 世界的大ベストセラーですが、実写映画化は難しいと言われていた作品です。何しろ現実世界と全く違う世界が舞台ですし、エルフ、ドワーフ、オーク、ゴラムなど異形の者や様々な怪物などが続々と登場しますし、何といっても、主人公がホビットという小人です。最新のCG技術を駆使できるようになり、やっと製作できるようになったのです。 このほど、その前日譚に当たる「ホビット 思いがけない冒険」(3部作の第1部)が劇場公開され、話題になっていますので、この正月休みに「ロード・オブ・ザ・リング」3部作をあらためて、一気に観返してみようと、昨日から2年越しで鑑賞しました。(はっきり言って疲れました。何しろ全部合わせると9時間を超えますからね。) “中つ国”という、人間やエルフ・ドワーフ・ホビットなど妖精や魔物が共存する世界のお話で、遠い昔に冥王のサウロンが、様々な邪心を込めて作り上げた“指輪”を巡る物語です。 ホビット庄に住むビルボ・バキンズ(イアン・ホルム)が、なぜか持っていた伝説の魔の“指輪”を、息子のフロド(イライジャ・ウッド)が受け継ぎます。魔法使い灰色のガンダルフ(イアン・マッケラン)の助言を受け、仲間たちに助けられながら、冥王サウロンの精神が支配する国モルドールの“滅びの山”の火口に投げ込むしか破壊する術のない指輪を、闇に葬るために旅をする物語です。 冥王の復活をもくろみ、指輪を手に入れようとする、ガンダルフの先輩の魔法使いで、今は魔の手に落ちたサルマン(クリストファー・リー)が組織するオークやウルク=ハイの軍団や、元は人間の王であったが“指輪”の魔力に魅せられてサウロンの下僕となったナズクルなどの追手を退けながら、魔物も住む困難な道を進んでいかなければなりません。 その旅の仲間は、魔法使いガンダルフをはじめ、同じホビットのサム(ショーン・アスティン)、ピピン(ビリー・ボイド)、メリー(ドミニク・モナハン)、かつて“指輪”を手に入れながらその野望のため捨てられなかった人間の王イシルドゥアの子孫であることを恥じ、さすらい人となっていた人間の王となるべき勇者アラゴルン(ヴィゴ・モーテンセン)、弓の名手のエルフ・レゴラス(オーランド・ブルーム)、ドワーフ族の戦士ギムリ(ジョン・リス=デイヴィス)、人間の国ゴンドールの執政の息子で実は“指輪”を手に入れたいと思っているボロミア(ショーン・ビーン)です。 もう世界的大ベストセラーですから、お話が面白い事はわかっています。ですから、大事なことは、いかにリアルにファンタジーな世界を作り上げるかにかかっています。いかに壮大で、感動的な物語だとしても、その映像がチャチかったり、わざとらしかったり、違和感があったりしたら台無しです。 そういう意味で、この映画の映像は見事でした。どこまでもどこまでも、ファンタジーな世界を見事に作り上げています。時にはロケ、時には全面CG、そして合成。どの場面を見ても現実感は0です。見事にファンタジーな“中つ国”を作り上げています。 とりわけ圧巻は遠景です。かわいらしい家が並ぶホビット庄、どこまでも続く草原、ひたすら続く岩山、いかにもの禍々しい雰囲気の魔の国モルドール、一時ガンダルフが捕まっていたやたらと高いサルマンの塔と、その下にあるオークたちが武器を作っている工房、などなど、とにかくその完璧さに圧倒されます。 また、旅の仲間たちのキャラがいちいち魅力的だということです。 主人公のフロドが一番平凡(もちろんホビットですから、いちいちCGで小人に加工されていますが、)というのはよくあるパターンですが、常に控えめながら意志の強そうなところを所々うかがわせるホビットのサム(彼の素晴らしさについては「3」で語りましょう。)、何かしら秘密を秘めていそうなところをいちいちうかがわせる魔法使いのガンダルフ、最初から“指輪”に興味津津で、その風貌から(まあ、どうしても悪役顔だからね、彼は。)そのうち必ず問題を起こすであろうことが見え見えなゴンドールのボロミア、行動がいちいち自信たっぷりでプライドが高そうなエルフのレゴラス、非常に負けず嫌いでレゴラスに対する対抗心が見え見えで分かりやすいドワーフのギムリ、人生を投げてさすらい人になったのはいいが持って生まれたリーダー気質が捨てきれない、エルフの姫君アルウェン(リヴ・タイラー)とラブラブな色男アラゴルンなど、皆が皆、個性的なメンバーです。 その中でも僕が気に入ったのは、何となく成り行きでついてきてしまった、ホビットのやんちゃ坊主コンビ、ピピンとメリーです。 一応サムはその“指輪”に関する大変な事情をガンダルフとフロドが話しているところを立ち聞きしてしまい、危険な旅だということをある程度覚悟して旅立っているのですが、ピピンとメリーの2人は、フロドとサムが旅立った直後に成り行きで合流し、全く事情も知らず、何となくついてきてしまった、当初はお笑い担当のにぎやかし程度の役割かなと思われました。 ところが、エルフの里“裂け谷”で関係者一同が“指輪”の処理方法について会議し、モルドールの“滅びの山”の火口まで捨てに行くしかないということになった後、事情がわかった上(ピピンについては?ですが。)で、その一行に加わることに志願し、旅先でボロミアとアラゴルンに剣を習っているなど、それなりに覚悟して、真剣に取り組んでいることがわかります。実は、彼らが大活躍するのは「2」「3」にとってあり、残念ながら、この「1」では、オークの一団にさらわれてしまうところで終わってしまうので、いまいち活躍できないで終わってしまっていますが、今後の彼らの成長がうかがえて、とても楽しみになります。 ラストは、どう考えてもお話はまだまだ続きます、という感じで、この映画は終わります。でも、もともと全世界の方々が、お話については知っており、最初から3部作にすることは、明言されていたので、当然覚悟されたことです。というより、この映画のグレードの高さに今後の続編のクオリティーが高いことを期待し、楽しみになって来ます。 まあ、とにかくまちがいなく映画史に残る名作のひとつに数えられる完成度の高い作品です。時間と覚悟が十二分にある時にお勧めの逸品です。
2013.01.01
コメント(3)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- おすすめアイドル
- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…
- (2025-10-25 17:37:46)
-
-
-

- パク・ヨンハくん!
- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…
- (2025-11-19 16:29:25)
-
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- Stairway to Heaven - Led Zeppelin …
- (2025-12-05 00:00:07)
-