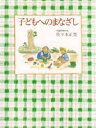
『 子どもへのまなざし
』
2日前
公開しています。
平日は忙しい日が多く、今日もちょっとだけ進みます。
まあ、ぼちぼちいきましょう。(^、^;)
===========================
『 子どもへのまなざし
』
読書メモ3 (p192より)
・子どもは親の言ったとおりにはしないで、
親のやっているとおりにやる。
・基本的に教育というのは、たいていの場合、
相手の言うことを聞いていればいい
。
・ 口
でやる教育は避けて、
心とかしぐさとか物腰、行動で教育をする。
・自分でできない分だけ口うるさくなっている。
口うるさいとは、そういうこと。
(参照したのはp192だけですが、一応p248までで付箋を貼ったところを
チェックし終わりました。次回は「豊かな社会がもたらしたもの」の章から。)
===========================
「 鏡の法則
」というのがありますが、
これと似たようなことを言っている気がします。
「鏡の法則」的なことは、人間関係では非常によく起こりますね。
子どもに望んでいる姿を、自分自身が実践してそれを見せられたらベストなのですが、なかなかそうはいかないところも。。。
だからこそ、「 自己成長 」をめざすことが大事なのですが。
僕は教師になって以来、
「言葉が多すぎる」
とよく言われてきました。
(なる前からかな・・・。)
どうしても説明したがる、言葉が長くなる傾向があります。
このブログにしても、長くなる傾向が!(^^;)
本当は、 言葉は少なく、端的に。
言葉よりもむしろ行動で示す。
これが、いいんだろうな、と思います。
端的な言葉で、 無駄な言葉を言わない
教育実践としては、
向山洋一
先生が思い浮かびます。
近頃久しぶりに向山先生の著書を読み返していますが、
子どもにどんな言葉で話をするのか、
授業に限らず、朝会での話など多彩な分野で、
事前によく吟味し、これ以上ないほど無駄な言葉を削った、
効果的な言葉を使われているのが分かります。
「どんな言葉を使うのか」 これは教育方法の一つの大きな課題です。
録音して自分の声を聞くのはとても恥ずかしいですが、
授業中の教師の声をすべて録音して後で聴く
と、
いかに不用意で意味のないことを言っているかよく分かります。
また、声の抑揚や、強調、強弱、聞きやすさなども、
録音するとあからさまに分かってこわいぐらいです。
自分と向き合うことは恥ずかしいですが、教師として、やっておきたいと思っている「修行法」の一つです。
今回も反省を胸に・・・次回へ続きます。
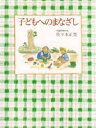
子どもへのまなざし
』
(佐々木正美、福音館書店、1998、1700円)
☆以下のブログランキングに参加しています。
日記に共感していただけた方はどうかクリックください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。 (^0^)
![]()
![]() ブログ王ランキング
ブログ王ランキング
-
算数テストでの九九表の使用 ~『学習指… 2024.05.18
-
年度初め! 2023.04.08
-
油引き(ワックスがけ)の大失敗! 2023.03.17
PR
Category
カテゴリ未分類
(57)生活をよくする
(204)共に生き、共に育つ
(174)たのしいべんきょう
(146)体育
(12)本の紹介
(176)音楽♪
(275)道徳 等
(12)問題解決
(104)考え方
(146)個人的な日記
(161)話し合い・話す・聞く
(36)特別支援教育
(188)小学校
(78)阪神間 地域情報
(36)PC・デジタル関係
(328)教材・教具
(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸
(15)旅行(温泉含む)
(75)環境保護・エコ
(26)仕事術
(74)英語学習
(26)作文・書くこと・漢字
(20)よのなか(社会)
(47)いのち
(27)人間関係・コミュニケーション
(90)子育て
(33)算数
(11)地震・防災
(16)心理・カウンセリング・セラピー
(30)読む・音読・朗読
(9)エクセルでのプログラミング
(21)北播丹波 地域情報
(4)教員免許
(2)教育改革
(34)休校期間お役立ち情報
(21)映画 等
(15)創造性をはぐくむ
(5)プレゼン
(12)通級
(2)健康
(3)ゲーム
(1)Keyword Search
Free Space
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
Calendar
Comments



