2009年10月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

Bar BESO(ベッソ): 驚きと感動のカクテル・アーチストに出逢える酒場/10月31日(土)
誰が名付けたか知らないけれど、大阪・北新地には、実力派バーテンダーの「三羽ガラス」と言われている3人がいる。 私のブログでも以前紹介したBar・Kの松葉道彦マスター、そして「エルミタージュ」というBarの田外(たげ)博一マスター(このブログでは未紹介)、そして3人目が、きょう日記で紹介するBar・BESO(ベッソ)の佐藤章喜マスター=写真右下=である。3人は同世代(40代)で年齢も近い。 BESOは北新地に店を構え、ことし10周年を迎えた。私も先般お祝いの週間の際訪れ、ささやかな記念の品を贈った。 店は毎夜、佐藤さんの素晴らしいカクテルを味わいたい客で溢れているが、実は、私が本格的に佐藤マスターと親しくなったのはここ5、6年の話である。 もちろん過去に、関西のカクテル・コンクールで、佐藤さんの見事なパフォーマンスを見たことはあったし、全国大会でも上位に入賞するなど輝かしい成績をおさめていることは当然知っていた。 佐藤さんの店にはすでに、彼のファン=常連客がしっかりついていたので、私のような新参者が入り込む余地はないと思い、時たま顔を出す程度だった。しかしここ数年は、私と友人が不定期で個人的に開いているウイスキー・テイスティングの集いに佐藤さんも参加してくれたりするうち親近感が深まり、以前より頻繁にBESOの扉を開けるようになった(以下の写真3枚は、BESOでつくって貰った素晴らしいカクテルの一例)。 佐藤マスターのどこが凄いのかと言えば、やはり、その独創的で、アーティスティックなカクテルの技であろう。飲んだら凄いカクテルをつくるバーテンダーは数多いが、ヴィジュアルという点でも客も唸らせるカクテルをつくるバーテンダーは、私はあまり知らない。佐藤さんはそんな一人である。 例えば、BESOのハウス・ウイスキーはホワイト・ホースであるが、ウイスキーのハイボールを頼むと、まずホワイトホースを入れたグラスの中に氷を数個入れてステアし、ウイスキーを十分に冷やす。 そしてその氷は捨てて、新しい氷と入れ替え、再度ステアし、ソーダを注ぎ、さっとレモンピール(流れるように美しい所作)。最後にモルト・ウイスキーをひと吹きスプレーする。このモルトはなんと、ホワイトホースのキー・モルトの一つであるタリスカー。ここまで芸の細かいサービスをするBARはちょっとない。 カクテルだって、スタンダードはもちろん、普通のスタンダードではないひと工夫が施されているし、オリジナルも驚きの連続で、デコレーション(飾り)一つとっても、目の前で見事な技を見せてくれる。黒トリュフを浮かべるコニャクベースのマティーニも佐藤さんのオリジナルだが、そんな発想を、誰が思い付くだろうか。 そのマシンガンのようなトークも凄い。うんちくを垂れすぎる訳でもなく、押しつけがましくもなく、客を楽しませる。吹き出る汗をふくのを忘れるくらい話し好きなのだ。体全体を使った激しいシェーキングも、見るものを圧倒する。本当にサービス精神の固まりのような人だ。 東京のバーテンダーにもテクニシャンは多いが、ここまで研究熱心で、凄い人はそういない。佐藤さんはこの業界では珍しい、奄美大島育ちという変わりダネだが、今では大阪を代表する、全国に誇れるバーテンダーだと私は自信を持って言える。 大阪以外の皆さん、大阪へ来たらぜひBESOにお越し下さい。どのカクテルもきっと驚きの連続で、これまで経験したことのないような満足が得られると信じます。【Bar・BESO(ベッソ)】大阪市北区曽根崎新地1丁目2-12 橘ビル4F 06-6345-3848 午後6時~午前2時(土は午前0時まで) 日祝休 ※店名の「BESO」とはスペイン語で「口づけ」という意味だとか。チャージ¥1000【追記】BESOはその後、次の住所へ移転されました。大阪市北区堂島1-3-35 新陽第二ビルB1F 06-4256-6232こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/31
コメント(0)
-

近頃撮った写真あれこれ/10月29日(木)
久しぶりに、近頃撮った写真あれこれをご紹介(9月の写真もあるけど、許してね(笑))。 こんな巨大なアヒルがそのへんの川にいたら、びっくりするよね。 大阪・天満橋、八軒屋浜前の船着き場前にいました。愛嬌ある顔してま~す。 「水都大阪2009」というイベントのキャンペーンのため登場しているそうです。 このアヒル、ゴム製らしいです。そして、オランダ人のデザイナーが造ったらしいです(でも、なんでオランダ人なの?)※残念ながら、このアヒル、今はもう浮かんでいませんので、ご容赦を。 これ、会社帰りのスペイン・バルで撮りました。シェリーの樽です。スペイン帰りのマスターのお土産です。 でも、樽は樽でも(写真でも分かるでしょうが)ポリ・タンク樽。中身はオロロソ・シェリーとのこと。 向こうじゃスーパーで売ってるそうです。日本円で700円くらいとか(安い!)。 マスターにおごってもらいましたが、飲んだらオロロソにしては、ちょっと軽かったです。 でも、スーパーでタンク入りのシェリーを売ってるなんて、いいですね。日本でも手頃な値段でシェリーが買えれば嬉しいなぁ…。 これ見ただけで、何の植物(木)かを分かった人は凄い。 まぁ、ブドウの木(苗)だっていうのは分かるかなぁ…。 でも、ブドウはブドウでも、ただのブドウじゃない。 これ、赤ワインの女王を生む「カベルネソーヴィニョン」の木。 でも、ワインを造るつもりで育てているんじゃないよ。 1年目は、絶対実は成らないって言われているから、今はとにかく枯らさないように、冬越しさせることで必死です。 最初の写真がアヒルだったからという訳でもないが、最後の写真も鳥。 神戸・ポートアイランドにある人気ポット「野鳥園」へ行ってまいりました。 ここでは、大きなケージの中でたくさんの鳥たちと至近距離で触れ合えます。 この鳥(名前は何だったかな?)は、人慣れしていて、手から直接エサを食べてくれます。でも、やはり至近距離に来ると、クチバシに指が噛まれそうでちょっと怖い。 野生の鳥たち(ケージの中なので、厳密には「野生」とは言えませんが…)をこんなに側で見るのは初めての経験です。みんな愛嬌が合って、可愛いです。皆さんも、ぜひ一度野鳥園へお越し下さい。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/29
コメント(4)
-

近頃飲んだウイスキーあれこれ(5): 新顔2題/10月27日(火)
うらんかんろが最近飲んだウイスキーの話題を2つ。 以前、08年6月22日の日記で紹介したアイラ島で8番目の蒸留所「キルホーマン(KILCHOMAN)」。そのキルホーマンからこのほど、ついに初のオフィシャル・モルトのボトルが発売されました=写真左。 2005年6月に操業を始めたキルホーマン蒸留所からは、これまでにもオフィシャルのニュー・ポット(3年未満熟成の酒)が、「ニュー・スピリッツ」という名前で3~4種類ほど発売されていましたが、今度はいよいよ「シングルモルト・ウイスキー」です。 英国の法律で、ウイスキーと名乗れるためには「最低3年間、熟成させなければならない」というルールがあります。すなわち、キルホーマンでようやく瓶詰めできる3年熟成のモルト・ウイスキーが誕生したということです。 うらんかんろはすでに「ニュー・スピリッツ」は味わい、そのクオリティを高く評価していました。だから、満を持して登場した「オフィシャル・モルト」には、個人的にも大きな期待を寄せていました。 46度で売り出された初のモルトは、ニュー・スピリッツの流れをくんで、ピートの効いたしっかりした味わいです。3年熟成にしてはボディはとてもしっかりしています。しかし、色合いを見て、僕は「えっ?」と不思議に思いました。3年にしては色がしっかりした琥珀色をしているのです。 あるBARのマスターさんに「3年でこんな濃い色が出るんですか?」と聞いてみました。するとマスター曰く。「おそらくは(カラメル色素で)色付けしているでしょう。3年じゃこんな色は出ません。ただ、色付けは(英国の)法律上認められているんです」と。 僕は考え込んでしまいました。キルホーマンはなぜ、3年熟成そのままの色でボトリングしなかったのか。色が薄くても、旨ければいいじゃないかと思います。カラメルの「化粧」を加えて熟成年数を多く見せることは、犯罪ではないのかもしれないけれど、僕は釈然としません。 ウイスキーでも「樽出し」とか「無濾過(ノン・チルフィルター)」とか、そういう「ありのまま」が好まれる時代です。だからキルホーマンも素直に、正直に、ありのままを出したほしかったと思うのは僕だけでしょうか。 ◇ ◇ ◇ もう一つの話題は、サントリーがついに国内発売に踏み切った「響12年」=写真右。チーフ・ブレンダーの興水精一さんをして「私の最高傑作」と言わしめたブレンディド・ウイスキーです。欧州で先行発売されたので、国内で飲めるのはいつかと心待ちにしていました。 これまで「響」は17年、21年、30年の3種しかありませんでした。ノンチル・フィルタードでアルコール度数55.5度の「響」もあります(ありました?)が、最近は姿を見ません。発売をやめたのでしょうか? オーセンティックBARでは、せいぜい「17年」が飲まれるくらいで、21年や30年は高嶺の花でした。お値段も結構する(普通1杯1500円前後はします)ので、僕自身も「17年を飲むくらいなら、モルトを飲む」ことが多かったのです。 しかし、手頃なお値段で飲める「響」が誕生するなら、それは嬉しいことです。「12年」は名前は同じ「響」ですが、これまでの「響」とは味の趣がかなり違います。「響」であって、「響」でない別のウイスキーのようです。 それは、興水さんも言うように、様々な個性的なモルトに、超長熟モルト(おそらく「ミズナラ樽のモルト」のことか)と梅酒樽熟成のモルトを少しずつブレンドし、さらに多彩なグレーン・ウイスキーで仕上げているためでしょう。 とくに、この梅酒樽熟成のモルトが効いています。舌の上でころがしても、テイスティング・グラスで味わっても、梅酒の甘い香りがほのかに立ち上ってきます。「12年」のキャラを決めるポイントになっていると言ってもいいでしょう。ほかにもプラムのような果実香やハチミツ香も漂います。 この絶妙の配合(ブレンド)が、「響12年」の芳醇で、フルーティで、ほのかに甘いキャラクターを形作っています。サントリーはなぜか、ハイボールで飲むのがおすすめだというポスターやチラシも作っていますが、僕はぜひストレートで、「12年」の素晴らしさを味わってほしいと思います。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/27
コメント(2)
-

昼下がりのクラシック at 甲子園会館/10月25日(日)
我が家から歩いてもそう遠くないところに、「甲子園会館」=写真左=という石造りの、趣のある建物があります。ことし「国の登録有形文化財」にも指定され、地元住民にも親しまれている建物です。 建物はどこかで見たような印象がある、ホテルのような外観です。それもそのはず、この建物は1930年(昭和5年)に、「甲子園ホテル」として建てられました。 当時としては、最先端をゆく豪華な洋風ホテルだったそうで、「阪神間の社交場」として、人気を集めたと言います。 設計者はあの旧「帝国ホテル」本館(現在は愛知県犬山市の明治村に移築)を設計したフランク・ロイド・ライト(1867~1959)の愛弟子で、遠藤新(えんどう・あらた、1889~1951)という建築家でした(遠藤は他には「自由学園目白講堂」など優れた学校建築を残しました)。 遠藤は、旧帝国ホテルのデザインを参考にしながら設計したため、外観や内装などはかなり似た造りとなっています。戦前は、「東の帝国、西の甲子園」と並び称されたそうです。 しかし、甲子園ホテルは戦況悪化とともに廃業。1944年に海軍病院となり、敗戦後は米軍に接収され将校宿舎となりました。 米軍撤収後は国の管理となり、1965年(昭和40年)に地元・西宮の武庫川学院という学校法人に払い下げられました(写真右は、裏側から見た甲子園会館。建物裏には広い庭園が広がっています)。 武庫川学院は現在、この建物を「甲子園会館」と名付け、同学院が運営する女子大の生活環境学部建築学科のキャンパス(教室)として使っているほか、時折、建物を地域住民に開放してコンサートなどを開いています(写真左=建物の柱一つとっても手の込んだ装飾が施されている)。 前置きがだいぶ長くなりましたが、この甲子園会館で先日、地域住民を対象にしたクラシックの無料コンサートが開かれるというお知らせがあり、甲子園会館の内部をまだ見たことがないうらんかんろも楽しみでお邪魔してきました。 コンサート会場は、ホテル時代は宴会場・ダンスホールだった場所(西ホール)ということです。200人程度のキャパですが、見る限りは立ち見も含め300人近く集まっている盛況ぶりです(写真右=玄関ロビー。明治村で見た旧帝国ホテルの雰囲気にそっくりでした)。 出演者は、武庫川学院の音楽学部の学生たち(ソリスト)と民間のプロ・オーケストラ(小編成です)。プログラムも嬉しいことに、僕の大好きなモーツアルトが中心です。 まず、歌劇「ドン・ジョバンニ」からのアリアを、学生たちが交代で歌いました。モーツアルトの曲だから、とても耳に心地よい、きれいなメロディです。曲と曲の合間には司会役の教授らしい方が、曲の内容を丁寧に説明してくれるので理解を助けてくれます。 アリアの後は、ウエーバーのクラリネット協奏曲。ウエーバーとモーツアルトは無関係のように見えますが、司会者が「モーツアルトの奥さんコンスタンツェは、ウエーバーの姪(めい)なので、実は親戚なのです」と意外な事実を教えてくれました。 フィナーレはモーツアルトの「ピアノ協奏曲17番」=写真左。大きなホールで聴くピアノ協奏曲もいいですが、このような小ホールで聴くのは演奏者の息づかいまで感じられ、最高です。 おそらくモーツアルトが生きていた時代は、こういう小編成で、室内で音楽を楽しんだのでしょうが、僕らも昼下がりの数時間、至福のひとときを貰いました。武庫川学院さん、有難う! 武庫川学院は今後も年に数回、この甲子園会館でこうした地元住民向けの無料コンサートを開いていくとのことです。嬉しいですね。またお邪魔できるのが楽しみです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/25
コメント(4)
-
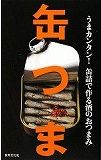
「缶つま」って知ってる?/10月24日(土)
「缶つま」って知ってますか? その名の通り、市販の缶詰の中身を活用し、ひと工夫を加えた「(酒の)つまみ」という意味なんですが、今、この「缶つま」が静かなブームとのことです。約130種類の料理を紹介した「缶つま」という本(世界文化社刊、税込み1050円)=写真左=まで出ています。 とにかく手に入りやすい市販の缶詰を使って、料理の素人でも、短い時間で、簡単にできるというのが「缶つま」の魅力です。もし、ご家庭のコンロが3口であれば、5~6種類の料理を同時並行にやっても、30分以内で出来ます。突然の来客に出す手軽な一品にもなります。 で、うらんかんろもこの本を参考にしながら、「缶つまで晩ご飯」に挑戦いたしました。メニューは6種類。1「ひよこ豆の素揚げ」、2「アスパラガスの冷製2種」、3「マッシュルームのベーコン炒め」、4「コンビーフ・チリコンカン」、5「オイルサーディンのキッシュ風」、6「ホタテのスープ」。 それぞれの作り方を簡単に説明しておくと、まず1の「ひよこ豆の素揚げ」=写真右=は、ひよこ豆を缶詰から出し、水気をしっかり切った後、180度くらいの油でカラっと揚げます。 揚げたら、熱いうちに素早く塩、コショウをするだけ。製作時間は5分ほど。食べる直前に揚げるのがベストですが、冷えても全然美味しいです。 2の「アスパラガスの冷製2種」=写真左=はホワイトアスパラの缶詰を使います。マリネ液に漬けるのと、黒胡椒などのスパイス(クローブ、ナツメグ、パプリカ・パウダーなどお好みで)だけでシンプルに食べるのとの2種。 前者はマリネ液がポイント(玉ネギとパセリのみじん切りにハチミツと粒マスタードを加えてよく混ぜます)。これをアスパラガスにかけて漬けておくだけ。これも5分で出来ます。飾りでうずらの卵の水煮を添えます。 3の「マッシュルームのベーコン炒め」=写真右=は、マッシュルーム(ホール)の缶詰、ベーコン、パセリ、パルメザンチーズ、バゲット(フランスパン=1本の3分の1~4分の1くらいを)を使います。 (1)まず、食べやすい大きさにちぎったバゲットを油をひかないフライパンで少し焦げ目がつくまで焼いて置いておきます。 (2)次に、2~3cmに切ったベーコンとマッシュルーム(缶汁は捨てる)をオリーブオイルで炒めます。 (3)(2)にバゲットを加えて、バルサミコ酢と黒胡椒、パルメザンチーズを振りかけ、味を整えたら完成です。これは10~15分かかります。 4の「コンビーフ・チリコンカン」=写真左=の材料は、コンビーフ缶(ノザキ社製がおすすめ)、ビーンズ・ミックス缶、トマト缶、フライドオニオン。 コンビーフをしっかり炒めた後、ビーンズ缶とトマト缶、フライドオニオンを加えてさらに炒めます。最後にウスター・ソース、チリパウダー、黒胡椒で味付けをしておしまい。5~10分で出来ます。 このコンビーフ・チリコンカンはそのまま食べても、バゲットにのせて食べても美味しいという優れもの。しかも保存が効くので、作り置きができます。 5の「オイルサーディンのキッシュ風」=写真右=は、オーブンを使った一品です。 耐熱皿にオイルサーディンとパプリカ(短冊型に食べやすい大きさに切る)を並べ、ピザ用チーズ、フライドオニオンを散らします。そして、上から卵液(卵1個、牛乳4分の1カップ、塩・胡椒少々)をかけて、オーブンで20分ほど焼けば完成。 最後の6「ホタテのスープ」=写真左=はホタテの缶詰を缶汁ごと小鍋にいれて温めます。そして、水250ccと白ワイン50ccを加えます。 彩りにミックス・ベジタブルも少し入れて、最後に、洋風っぽく見せるためにクレソンを散らします。これも5分もあればOK。 で、この6品を食べた感想ですが、3と4は最高! 定番メニューにして、また作ってみようと思う気になりました。1もビールにも白ワインにもめちゃ合いますし、2もマリネ液に漬けた方は高い評価でした。しかし5と6は、連れ合いと「あまりたいしたことはない」という意見で一致しました。 皆さんも「缶つま」に一度挑戦してみてはいかがでしょうか? 工夫次第でとても缶詰とは思えない素晴らしい一品に変身しますよ。【おことわり】文中で紹介した作り方は本と同じものもありますが、うらんかんろの好みで若干アレンジを加えているものもあります。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/24
コメント(4)
-

なぜ、なぜ、そんなに早く…/10月17日(土)
2回続けて訃報について記さないといけないのが、とてもつらいです。元フォーク・クルセダーズで、サディスティック・ミカ・バンドのリーダーでもあったミュージシャン・加藤和彦さん(62)=(写真 ( C )朝日新聞社 )=が軽井沢のホテルの部屋で自殺したとのニュース! ショックで言葉を失いました。 フォークルのコンサートには昔、何回も行ったし、アマチュア時代の「フォークル」解散を記念してつくった限定版のアルバムも持っているくらいなのに…。彼の、おしゃれな曲づくりのセンスには敬服していたし、ギター・テクニックには、随分勉強させられました。 なぜ、自殺したのか? 孤高の芸術家、ミュージシャンには他人には分からない悩みがあれこれあったのか…? それにしても、自殺なんて…。自ら命を断つなんて…、悲しすぎます、切なすぎます。 私生活では3度(福井ミカさん→安井かずみさん→中丸美千絵さん)の結婚&離婚・死別と波乱多い人生でしたが、最近では、アルフィーの坂崎さんと「和幸」というユニットを組んで、精力的に活動していました。 作曲家としては全盛期を過ぎたとは言え、彼にはまだまだ活躍できる舞台があったはずです。それなのに、なぜ、なぜ、なぜ? 答えが聞きたいよー、加藤さん。
2009/10/17
コメント(0)
-
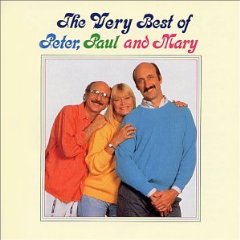
マリー・トラバースさんを悼む/10月3日(日)
いさかか旧聞で申し訳ありませんが、1960~70年代に活躍した米国のフォークグループ「ピーター、ポール&マリー(PP&M)」のマリー・トラバースさんが9月16日、がん(白血病という話です)のため、米コネティカット州の病院で亡くなられました。72歳でした。 マリーさんは、ケンタッキー州ルイビル生まれ。グループは60年代前半にニューヨークで結成され、「風に吹かれて」「パフ」「花はどこへ行った」「500マイル」「天使のハンマー」「我が祖国」などのヒット作を送り出しました。「風に吹かれて」はボブ・ディラン作でしたが、この曲がきっかけで日本でもディランの存在が知られるようになりました。 PP&Mは民主党支持者で、ベトナム反戦運動や、黒人差別撤廃を求めた公民権運動にも精力的に取り組んだミュージシャンでした。「悲惨な戦争」など反戦的なメッセージソングを積極的につくり、若者に大きな影響を与えました。今でも反戦集会や市民集会では、「我が祖国」がよく歌われますが、これもPP&Mがそのきっかけをつくったものでした。 小学生でギターを始めた僕が最初、ギターの練習の課題曲としてよくチャレンジしたのがPP&Mでした。「悲惨な戦争」でアルペジオを習い、さらに「パフ」でツー・フィンガー、「くよくよするな」でスリー・フィンガーのピッキングを覚えました。 マリーさんの担当はギターでなく、ヴォーカルでした。そしてPP&Mの歌は3部のハーモニーのコーラスであることが多かったのですが、その中で「芯を貫いていた」のは彼女のしっとりとした歌声でした。 マリーさんのパートを男声で歌うのはしっくりこない感じもしたのですが、僕はよくPP&Mの曲をギターで弾き語りしました。PP&Mを手本にしっかりスリー・フィンガーを練習したおかげで、後に自分のバンドでCSN&Y(クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング)の曲を演奏した時、おおいに役に立ちました。 PP&Mの生の歌声は中学生の頃、当時の大阪府立体育会館でのコンサートで聴きましたが、音響がいまいちの会場もものともせず、素晴らしい曲の数々を聴かせてくれて、ますますギターやPP&Mの曲にのめり込んだものでした。当時のほっそりしたマリーsんの姿(晩年はおばちゃん体型になりましたが(失礼!))は今も目に焼き付いています マリーさんの存在なくして、PP&Mというグループはあり得なかったと僕も思いますし、多くのファンも同じ思いでしょう。僕にとっても、PP&Mとの出会いなくして、今の音楽の素養もなかった訳ですから、彼女には、ただただ感謝するしかありません。 マリーさんはグループ活動休止の後も、終生、国内外で人権擁護活動に力を注ぎました。そんな真摯で、ヒューマンな人間性には頭が下がる思いです。72歳は、天に召されるにはまだ若すぎる歳です。彼女の歌声がもう聴けないと思うと本当に切ない気持ちになります。今はただ、心からご冥福をお祈りしたいと思います。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/10/03
コメント(2)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










