2015年08月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

Harry's ABC Of Mixing Cocktails:世界初の体系的カクテルブックの中身とは(21)Sidecar/8月27日(木)
◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル 18.サイドカー(Sidecar) 「サイドカー(Sidecar)」はクラシック・カクテルの代表格の一つで、その名はオートバイの横に取り付けて走る四輪の乗り物に由来します(第一次世界大戦で軍用バイクとして開発され、一躍有名になりました)。カクテル誕生の由来や時期については、これまで以下のように数多くの説が紹介されてきました。とりわけ(1)と(2)の2説は有名で、どちらも複数の文献やWeb専門サイトでよく取り上げられてきました。(1)第一次世界大戦(1914~18)中、パリのレストラン・バーで、コニャックを飲んでいた軍人(米軍人、フランス軍人、ドイツ軍人の3説あり)の元に、「急いで軍の本部へ戻れ」という指令が来た。度数の強いコニャックを短時間で飲み干さなければならないその軍人が、バーテンダーに「ホワイト・キュラソーとレモン・ジュースで割ってくれ」と頼んだのが始まり(出典:多数の文献やWeb専門サイト)。※このレストラン・バーがどこかは不明。(2)第一次大戦後の1931年、パリの「ハリーズ・ニューヨーク・バー」の経営者、ハリー・マッケルホーンが、いつもサイドカー付きのオートバイに乗って来店する常連客のために考案した(出典:Wikipediaほか多数)。(3)パリのリッツ・ホテルは、「サイドカーはリッツ・ホテルのBarで誕生した」と主張している(出典:Wikipedia英語版)。(4)1922年、ロンドンの社交クラブ「バックス・クラブ(The Buck’s Club)」(1919年創業)の初代バーテンダー、パット・マクギャリー(Pat MacGarry)が紹介し、英国内で広めた(出典:PBOのHPやWikipedia英語版 ※「考案者」という表現はしていない)。(5)ロバート・ヴェルマイヤー(Robert Vermeire)のカクテルブック「Cocktails and How To Mix Them」(1922年刊)には、「サイドカーはフランスではとても人気のあるカクテルで、マクギャリーがロンドンへそのレシピ紹介した」としている(出典:Wikipedia英語版)。(6)デヴィッド・エンベリー氏(David Embury)の著書「The Fine Art Of Mixing Drinks」(1948年刊)は、「第一次大戦中、パリに駐留していたサイドカー好きの米陸軍軍人のために、あるビストロが考案した」と伝える(出典:同)。 今回連載のメインテーマでもあるハリー・マッケルホーン(Harry MacElhone)のカクテルブック「 Harry's ABC of Mixing Cocktails」(1919年刊)には、もちろん「サイドカー」は収録されています。というか、サイドカーは現時点では、「Harry's ABC of Mixing Cocktails」が世界初出の文献です。 「Harry's ABC…」の発刊年(1919年)から考えると、欧州では、少なくとも1910年代後半には社交クラブや街場のバーで登場していたことになり、1920~30年代誕生説は誤りだということになります(写真=Sidecar @ Bar Savoy Kitanozaka, Kobe)。 それでは考案者は誰だったのかと言えば、従来、国内外のカクテルブックやWEBの専門サイトでは、「ハリー・マッケルホーンが考案者」と紹介されることが数多く見られました。これは、マッケルホーンが興したパリの「ハリーズ・ニューヨーク・バー」で「サイドカー」がオープン(1923年)以来ずっと看板カクテルだったこと、そして彼の店が「サイドカー」の普及に大きな役割を果たしたことが背景にあるのでしょう。 しかし、以前にもうらんかんろが「カクテル--その誕生にまつわる逸話」という連載で書いたように、考案者と言われるマッケルホーン自身は、自著(「Harry’s ABC…」)の「Sidecar Cocktail」の項で、「ロンドンの社交クラブ『バックス・クラブ』のバーテンダー、パット•マクギャリーのレシピ」と記しているのです。マッケルホーンは、同著収録のカクテルで自身が考案したものについては、「自分のオリジナルである」と明記していますので、「サイドカー」が自らの考案であれば、間違いなくそう記したはずです。 うらんかんろは、マッケルホーン自身が否定している以上、サイドカーの「マッケルホーン考案者」説はもはや取り上げるべきではないと思っています。なので、いまだに国内外の新刊のカクテルブックで、「マッケルホーンが考案した」と間違って紹介しているのを見ると、残念でなりません(「マルガリータ=流れ弾起源説」のように、後世のつくり話が一人歩きして、間違ったまま"定説化"してしまう典型的な例かもしれません)。 ただし、マッケルホーンが「考案者(Created by)」とは書かず「レシピ(Recipe by)」と記していることから、上記(4)、(5)の説のように、当時(1910年代)パリで流行していたブランデー・ベースのカクテルを知ったマクギャリーが、自らが働く社交クラブで若干アレンジして提供し始めたという推測も成り立つかと思います(マッケルホーン自身は、1910年代後半は同じロンドンの社交クラブ「The Ciro's」で働いていましたし、マクギャリーから情報は難なく入手できたはずです)。 いずれにしても、1910年代の知見を反映したマッケルホーンの著書を信じるならば、現状では、「サイドカー」はやはり、ロンドンのバーテンダー、パット・マクギャリー氏が考案した(あるいは、現在のスタンダードレシピの基礎をつくった)と考えるのが一番信頼に値すると思われます。 さて、「Harry's ABC…」収録のレシピはどうかと言えば、「ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモンジュース3分の1」(シェイク・スタイル)です。「ハリーズ・ニューヨーク・バー」では現在でもこのオリジナル・レシピを頑固に守っているそうです。 しかし、1920~30年代のカクテルブックをみると、「サイドカー」のレシピは大きく分けて2つの流れが見受けられます。その一つは、マッケルホーンの本と同じ「3つの材料等量レシピ」。これは「フレンチ・スタイル」と呼ばれています。そして、もう一つは、「英国スタイル」と言われるレシピで、「ブランデー(2分の1)、コアントロー(またはホワイト・キュラソー、トリプルセック)(4分の1)、レモン・ジュース(4分の1)」です。「英国スタイル」は「The Savoy Cocktail Book」の著者、ハリー・クラドック(Harry Craddock)によって考案されたとのことです(出典:Wikipedia英語版)。 では、1900~1950年代の主なカクテルブック(「Harry's ABC…」以外)は「サイドカー」をどう取り扱っていたのか、どういうレシピだったのか、ひと通りみておきましょう。 「Dary's Bartenders' Encyclopedia」(ティム・ダリー著、1903年刊)米、「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」(ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米、「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」(トム・ブロック著、1917年刊)米 いずれも掲載なし・「The Savoy Cocktail Book」(ハリー・クラドック著、1930年刊)英 本文中に挙げた英国風レシピ(シェイク・スタイル)。・「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」(1930年刊)米 ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモンジューズ3分の1(スタイル不明)・「The Artistry Of Mixing Drinks」(フランク・マイアー著 1934年刊)仏 ブランデー2分の1、コアントロー4分の1、レモンジュース4分の1(シェイク)・「World Drinks and How To Mix Them」(ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊)米 ブランデー2分の1、コアントロー2分の1(ステア・スタイル) ※3つの材料等量レシピのものは「Sidecar No4」という名で収録。・「The Official Mixer's Manual」(パトリック・ギャヴィン・ダフィー著、1934年刊)米 ブランデー2分の1、コアントロー4分の1、レモンジュース4分の1(シェイク)・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S.クロケット著 1935年刊)米 掲載なし・「Mr Boston Bartender’s Guide」(1935年刊)米 ブランデー1onz(30ml)、コアントローオ0.5onz(15ml)、レモンジュース4分の1個分(シェイク)・「Café Royal Cocktail Book」(W.J.ターリング著 1937年刊)英 ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモンジューズ3分の1(シェイク)・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」(ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ブランデー1onz(30ml)、コアントローオ0.5onz(15ml)、レモンジュース4分の1個分、砂糖でスノー・スタイルにしたカクテルグラスに注ぐ(シェイク)・「Esquire Drink Book」(フレデリック・バーミンガム編、1956年刊)米 サイドカーNo1=ブランデー3分の2、コアントロー3分の1、レモンジュース1dash(シェイク)、サイドカーNo2=ブランデー3分の1、コアントロー3分の1、レモンジューズ3分の1(シェイク) 日本へは「サイドカー」は、少なくとも1920年代までに伝わり、日本初の体系的カクテルブックの一つと言われる「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)で初めて紹介されています。前田氏のレシピは、「Harry's ABC…」と3つの材料の分量比は同じですが、「アンゴスチュラ・ビターズを一振り」加えるところだけが違っています。 「サイドカー」は今日のバーでも不動の人気を誇るスタンダード・カクテルの一つです。もちろん誕生当初は「オリジナル」だった訳ですが、多くのバー・ファンの心をつかみ、またたく間に世界中に普及しました。シンプルな材料のコンビネーションが生み出す奥行きのある味わい、アルコールと酸味と甘味の絶妙のバランス。100年後でも、多くの人々に愛されている理由が分かるような気がします。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/27
コメント(0)
-
Bar UK 9月の店休日について/8月24日(月)
バーUKマスターから、9月の店休日についてのお知らせです。 9月は以前にもお知らせしましたように9月10日(木)~18日(金)の間、店主が欧州へ旅するため、大変申し訳ございませんが、長期のお休みを頂きます(帰国日の18日はひょっとしたら、営業するかもしれませんが…)。 従って、現時点では、6日(日)、10日(木)~18日(金)、20日(日)、27日(日)が店休日となる予定です(なお、シルバー・ウイークの21~23日は、午後3時~10時で営業いたします)。 ※店休日、営業時間等に変更が生じる場合は、このバーUK公式HP&Blog上にて、すみやかにお知らせいたします。 以上、何卒よろしくお願いいたします。 【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途、水曜と土曜にそれぞれ月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。午後4時~7時はノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/24
コメント(0)
-

Bar UK 写真日記(31)/8月23日(日)
2週間ぶりのBar UK 写真日記です。(By うらんかんろ) ベリーニ(Bellini)と言えば、スパークリング・ワインとフレッシュの桃を使った有名なカクテルですが、マスターは、Bar UKの開業以来、お客様の注文がなかったこともあって、店では一度もつくったことがなかったそうです(桃もいつもある訳ではありませんし…)。しかし先日、初めてその注文があったため、挑戦いたしました。幸い、お客様からは「桃の風味や香りがよく残って、甘ったるくない美味しさ」と好評価を頂いて、満足そうでした。 マスターは、その後もフードメニューの研究に頑張っています。これはチーズのモルト・ウイスキー漬け。完成は2~3週間後なのですが、果たしてお味はどうでしょうか? メニューに載る日は来るでしょうか? マスターは、店に備え付けのドリンクメニュー冊子の内容を大幅に拡充しました。これまで、8頁だったのを一気に12頁に。「おすすめ」頁は従来より増えて3頁に、カクテルの頁も見開きになりました。「より詳しく、より親切に」を目指したとのことです。 「オープン1周年のお祝いに」と懇意なバーのマスターから、素敵なプレゼント(ウイスキーのオールド・ボトル)が届きました。サントリーの「ゴールド」というブレンディド・ウイスキーで、このボトルは、1980年代前半に流通していたもの。この頃、マスターは成田一徹さんと出会いました。「懐かしい思い出が、いっぱい蘇ってくるお酒です」としみじみ。 Bar UKにはポートワイン樽熟成のモルト・ウイスキーも何本かあるので、マスターは「やはり、ポートも1本は必要かな」とトゥニー・ポートを仕入れました。銘柄は、マスター自身も昔訪れたことがあるサンデマン(Sandeman)。甘口のお酒が好きな方にはおすすめです。飲み方はストレートかロックでもいいし、ソーダ割りにしても意外と美味しいとのことです。 これも新顔の、とてもユニークなデザインのボトル。木樽での長期熟成タイプのメキシカン・ラム「モカンボ(Mocambo)」です。濃厚で、チョコレートやカカオのような香りがする、芳醇な味わいです。ストレートでも、ロックでもいけますよ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/23
コメント(0)
-

9月29日から成田一徹切り絵作品展@神戸/8月22日(土)
Ofiice Ittetsuからのお知らせです。******************************** 「成田一徹 切り絵作品展」のご案内 2年に一度行われる神戸市主催の芸術祭「神戸ビエンナーレ 2015」の期間中、「成田一徹 切り絵作品展」を開催させていただくことになりました。 神戸新聞に連載し、『神戸の残り香』『新・神戸の残り香』に収録した作品に加えて、昨年末に刊行いたしまし『NARITA ITTETSU to the BAR』から神戸のバーの作品を加えた計45点を展示する予定です。 成田一徹が、独自の目線で切り取った“神戸”を感じていただけたらと願っております。 会期 9月29日(火)~10月12日(月 祝) 開場時間 平日 8:15~17:30 土日祝 10:00~17:30 ※ 最終日は15:00まで 会場 神戸市役所1号館2F 神戸市民ギャラリー 神戸市中央区加納町6-5-1 JR 阪急 阪神「三宮」南へ徒歩約6分 お問合せ mail:office-ittetsu@cosmos.zaq.jp 神戸ビエンナーレについてのお問合せ先 神戸市市民参画推進局文化交流部 (078)322-5165 ※切り絵は、出展予定の「地蔵盆」(『神戸の残り香』所収)
2015/08/22
コメント(0)
-
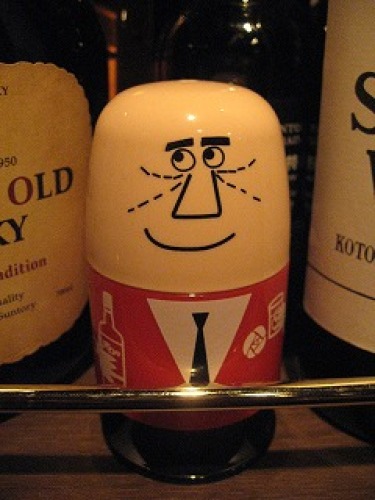
追悼:柳原良平さん/8月19日(水)
「アンクルトリス」の生みの親でもある、画家でイラストレーターの柳原良平さんが亡くなった(柳原さんご夫妻は、成田一徹さんのバー切り絵作品集「to the BAR」でも、横浜のバー「Three Martini」の頁で登場してくださった)。 アンクルトリスは、うらんかんろが子どもの頃から、愉快で楽しいキャラクターだった。有名な「トリスを飲んでハワイへ行こう」のCMは、子どもに、「いつかは海外旅行」という夢を見させてくれた。ウイスキーを飲めば、体の下から上へだんだん赤くなっていく「彼」が大好きだった。 大人になってからは、トリスおじさんは酒場に欠かせない、酒呑みに愛されるキャラに変わった。僕が行くほとんどの酒場の、どこかに「彼」はいた。生涯、ウイスキーとの思い出はいつも「彼」と共にあった。 柳原さん、唯一無比の、素敵なキャラクターを生んでくれて、本当に有難うございます! トリスおじさんは、日本中の酒場で、永遠に生き続けますよ。http://digital.asahi.com/articles/ASH8M5KMWH8MULOB00N.html
2015/08/19
コメント(0)
-
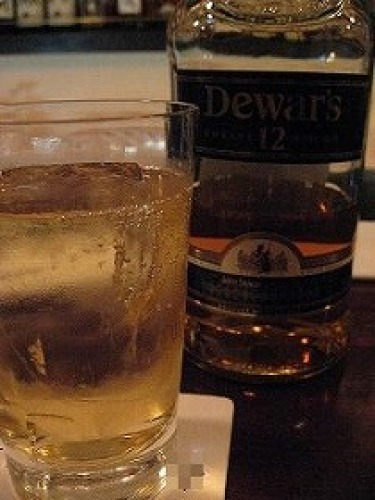
Harry's ABC Of Mixing Cocktails:世界初の体系的カクテルブックの中身とは(20)Scotch Highball/8月18日(火)
◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル 17.スコッチ・ハイボール(Scotch Highball) 「ハイボール(Highball)って、カクテルなの?」と疑問に思われる方も多いかもしれませんが、バー業界ではハイボールもれっきとしたカクテルの一つなのです。蒸留酒(主としてウイスキー)とソーダと氷(お好みでレモンピール等)。材料やつくり方は極めて単純ですが、だからこそ、お酒の選択やつくる過程での小さなこだわりが、その完成度に大きく影響するドリンクでもあります。 欧米では、ウイスキーなどの蒸留酒は当初、ソーダを加えない「クラスタ(Crusta)」「デイジー(Daisy)」「コブラー(Cobbler)」等の飲み方がまず発展してきました。このため、「ハイボール」が普及し始めるのは意外に遅く19世紀後半になってからで、欧米のカクテルブックで初めてハイボールが登場するのも、うらんかんろが調べた限りでは、1882年刊の「Bartender's Manual」(Harry Johnson著)が最初です。少なくともこの頃(1880年代)には、バーや一般家庭では、それなりに知名度のある飲み方になっていたようです。 なお、現代では単にハイボールと言えば、「ウイスキーのソーダ割り」を指すことが多いのですが、20世紀前半までは、ハイボールのベースのお酒は必ずしもウイスキーとは限らず、ベースが蒸留酒であれば(時には一部の醸造酒でも!)、原則何でも「ハイボール」と呼んでいました。 時代が進むにつれて、「ハイボール」のベースの酒はウイスキーがメインとなります。「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」(1919年刊、ハリー・マッケルホーン著)では「Scotch Highball」という名前で登場しています。そのレシピは分量表記ではなく、文章で綴られていますが、内容も同時代のカクテルブックとは違い、異彩を放っています。「大きめのタンブラーに角氷を1個入れ、レモンピールをする。ウイスキーを客(Customer)に渡し、自身で(好みの量を)注いでもらう。そしてソーダで満たす」。マッケルホーンが「客自身が、好みの濃さ、味わいに仕上げればいい」と思っていたのが面白いところです。 ちなみに日本では現在でも、ウイスキーのソーダ割りは「ハイボール」という言い方が一般的ですが、米国も含む現代の欧米では、「スコッチ・アンド・ソーダ(Scotch and Soda)」と言わなければ、なかなか通じません。「ハイボール」は欧米では現在でも、あくまで「蒸留酒のソーダ割り」というお酒に過ぎず、蒸留酒の種類を指定しなければ、なかなか理解してもらえないようです(写真=Scotch Highball @ Morita Bar, Osaka)。 また、「ハイボール」と言えば、現代では通常はソーダ割りを指しますが、欧米では、昔から「****・ハイボール」というカクテルは必ずしもソーダ(炭酸水)割りではありませんでした。実際、古い1890~1930年代くらいのカクテルブックでは、水やジンジャー・エールなどで割っても「****・ハイボール」と呼んでいます。「ハイボール」という名前の由来として、「ソーダの泡がプクプクと上へ立ち上がる様からその名が定着した」と記しているカクテルブックがありますが、この説明にはまったく根拠がないことになります(ハイボールの語源・由来については、拙ブログの「カクテルの逸話連載(45)」ご参照を)。 日本でも1950年代までのカクテルブックには、欧米の影響の残っていたのか、水で割っても、ジンジャー・エールで割っても「****・ハイボール」と呼んでいるケースが目に付きます。しかし時代が進むにつれて、「****・ハイボール」という呼称は、ソーダで割ったロング・カクテルに限定的に使われるようになり、今日に至っています。 それでは、1880~1940年代の主なカクテルブック(「Harry's ABC…」以外)は「(スコッチ・)ハイボール」をどう取り扱っていたのか、ひと通りみておきましょう。・「How To Mix Drinks」(ジェリー・トーマス著、1862年刊)米、「American Bartender」(ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」(トム・ブロック著、1917年刊)米、「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」(1930年刊)米 以上5冊には掲載なし ・「Bartender’s Manual」(ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米 ウイスキー1Wineglass、角氷(Lump of Ice)2~3個、ソーダ・「Modern American Drinks」(ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米 スコッチ・ウイスキー1jigger、角氷1個、ソーダ・「Dary's Bartenders' Encyclopedia」(ティム・ダリー著、1903年刊)米 ウイスキー1Wineglass、小さめの角氷1~2個、ソーダ・「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」(ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米 バーボン(またはライ、スコッチ)・ウイスキー1Wineglass、角氷1個、ソーダ・「The Savoy Cocktail Book」(ハリー・クラドック著、1930年刊)英、ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを・「The Artistry Of Mixing Drinks」(フランク・マイアー著 1934年刊)仏 ウイスキー1Glass、角氷1個、ソーダ(※「ブランデー、ジン、ラム等でも同様に」と)・「World Drinks and How To Mix Them」(ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 ウイスキー1.5jigger(約70ml)、角氷数個、ソーダ・「The Official Mixer's Manual」(パトリック・ダフィー著、1934年刊行)米 ウイスキー1~2jigger、角氷、ソーダ、好みでレモンピール(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S.クロケット著 1935年刊)米 ウイスキー1jigger(約45ml)、角氷、ソーダ(※「その他の蒸留酒等でも同様に」と)・「Mr Boston Bartender’s Guide」(1935年初版刊)米 スコッチ・ウイスキー2onz(60ml)、角氷1個、ジンジャーエール(ソーダでも可)、好みでレモンピール・「Café Royal Cocktail Book」(W.J.ターリング著 1937年刊)英 ウイスキー(バーボン、ライ、スコッチ、アイリッシュ)1Glass、角氷1個、ソーダ(好みでジンジャー・エールを使っても可)、好みでレモンピールを・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」(ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ウイスキー4分の1、角氷2個、ソーダ4分の3(※「Scoth and Soda」の名で掲載) なお、日本へはスコッチ・ハイボールは、少なくとも1920年代までに伝わり、「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)にも収録されています。ただし、秋山氏のレシピは「好みの量のウイスキーと冷たいソーダ水」だけです。氷の長期保存法については、明治維新以降、岩塩やオガクズを使う等の方法はある程度は確立されていましたが、この時代、氷はまだ大変貴重なものでした。氷を保管する大掛かりな設備(氷室)を持っていたのは一流ホテルの厨房くらいで、街場のバーではそう大量には保管できなかったでしょう(秋山氏が働いていた宮内庁の厨房はどうだったのでしょうか)。 昭和の初めには、氷式の木製冷蔵庫が商品化されました。しかし、氷はあくまで保冷のためのもので、ドリンクに直接入れることは少なかったようです。秋山氏のレシピは氷を入れない「サンボア・スタイルのハイボール」に近いですが、ウイスキーはもちろん常温保存(サンボアグループは冷凍庫保存の店が多い)なので、冷たさを感じるのは最初の一口だけだったかもしれません。もっとも、現代でも欧米のバーでは、スコッチ・アンド・ソーダを頼んでも氷はほんのわずかしか入れてくれません。これは元々、冷たいアルコール・ドリンクをあまり好まない文化(人種)的な背景があるのでしょう(英国でも、パブで出されるビールは概してぬるいのです)。 日本のバーの現場で、氷が日常的に登場するのは、木製の氷式冷蔵庫が普及し始めた1925〜30年頃以降で、さらに、気兼ねなく使えるようになるのは実用型の電気冷蔵庫・冷凍庫がお目見えした1950年代になってからです。バーに氷があるのは当たり前に思っている現代の私たちですが、冷たいハイボールを味わう幸せを感じる時、どうか、初期のバー文化を支えていた人たちの苦労に、少しだけでも思いを寄せてみてください。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/18
コメント(0)
-
アクセスが100万件を超えました!/8月17日(月)
お陰様で、この楽天Blog「酒とピアノとエトセトラ」(Bar UK公式HP&Blog)への通算アクセス数が、本日、100万件を超えました。 2004年11月のスタート以来、12年目での達成でした。今後とも、Bar UKからのお知らせはもちろん、皆様のお役に立てる様々な情報発信に努めてまいります。何卒よろしくお願いいたします。 うらんかんろ
2015/08/17
コメント(2)
-
Bar UK マスターからのお知らせ(9月の長期休暇について)/8月10日(月)
Bar UKマスターからのお知らせです。 ********************************** 来月9月のバーUKの店休日は、今月下旬に改めて、この公式HP等で告知させて頂く予定ですが、取り急ぎのお知らせです。 9月10(木)~18日(金)は店主は欧州へ旅するため、店も長期休暇を頂きます。何卒ご理解・ご了承の程よろしくお願いいたします。18日は午前中に帰国いたしますので、体調次第ではひょっとしたら、夕刻から店を開けるかもしれませんが、あまり期待しないでくださいませ(笑)。 以上、誠に勝手を申しますが、何卒よろしくお願いいたします。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/10
コメント(0)
-

Bar UK 写真日記(30)/8月9日(日)
2週間ぶりのBar UK写真日記です(By うらんかんろ)。 マスターは、お客様から1周年記念の素敵なプレゼントを頂きました。「Bar UK」の門燈やコースターにもなった成田一徹さんの切り絵原画の図柄をもとにした飴細工の作品です。とても素晴らしい出来あがりなので、感激したマスターは早速バックバーに飾りました。 これもお客様から頂いた1周年の御祝。「ジョン・ベッグ(John Begg)」というスコッチ・ブレンディドのオールドボトルです。実は、マスターは以前同じボトルを1本持っていたのですが、あるテイスティングの集いに提供したため、今はありませんでした。「70~80年代のブレンディドの中でも、とても評価の高い銘柄です。また1本ほしいなぁと思っていたので」と嬉しそうなマスターです。 これは新顔のお酒です。いま人気のアイラモルト「キルホーマン(Kilchoman)」の新商品、2015年発売のシェリーカスクです。しっかりしたボディに濃厚なシェリーの香りがたっぷり。文句なしの旨さですよ。 これも新顔のお酒で、ジンです。米シカゴの小規模な蒸留所「KOVAL」で丁寧につくられたプレミアム品です。ジンらしいきりっとした味わいの中にも複雑な香りが感じられます。ボトルのデザインもとてもおしゃれです。ストレートかロックで味わうのがベストだそうです。 自己研鑽のためには、マスターは時間のある限り、機会があればどこへでも出かけていきます。この日は尊敬する店主Nさんが営む岐阜市のバー「BAROSSA」へ。BAROSSAでマスターは5杯のお酒を味わいましたが、「材料の扱い方、つくり方などすべてが驚きで、とても勉強になりました」とのこと(写真は、テキーラ&シェリー・ベースのトマトカクテル)。 マスターの初歩的な質問の数々にも、Nさんは嫌な顔一つ見せることなく丁寧に答えてくれたそうです。嬉しいですね。学んだことは、きっと、今後バーUKでも仕事にも生かされることでしょうね。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/09
コメント(0)
-
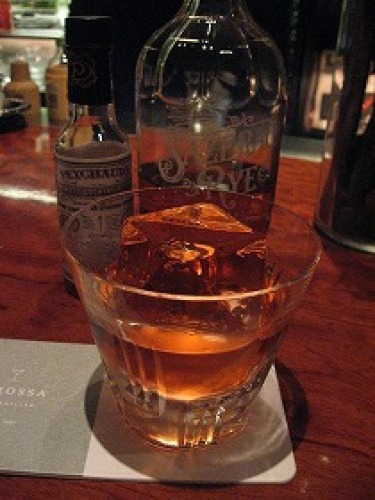
Harry's ABC of Mixing Cocktails:世界初の体系的カクテルブックの中身とは(19)Sazerac/8月7日(金)
◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル 16.サゼラック(Sazerac) 「サゼラック(Sazerac)」は、1850年代、米国ニュー・オーリンズのバー「サゼラック・コーヒー・ハウス」で誕生したと伝わる、最初期の代表的なクラシック・カクテル(出典:Wikipedia英語版ほか。末尾の【注】もご参照)です。考案者は、このバーのオーナーだったアーロン・バード(Aaron Bird)であるとWikipedia英語版は紹介しています(出典:The Sazerac of New Orleans: A History from the Sazerac Company Archives )。 しかし、欧米のカクテルブックに「サゼラック」が登場するのはかなり後のことで、うらんかんろが現時点で確認している限り、20世紀に入ってからです。確認できる最も古い文献は、サヴォイホテルのチーフ・バーテンダー、ハリー・クラドック(Harry Craddock)が著した「The Savoy Cocktail Book」(1930年刊)です。そのレシピは、「ライ・ウイスキー1Glass、アンゴスチュラ・ビターズ(またはペイショーズ・ビターズ)1dash、角砂糖1個、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす)、レモンピール」(ステア・スタイル)です。 「サゼラック」は元々は、同名のコニャックをベースにしたカクテルでした。しかし、1870年にフランス全土のブドウ畑が病害虫で壊滅状態になったため、米国へ輸出されるコニャックが激減。その結果、代用品としてライ・ウイスキーが使われるようになり、そのまま定着したとのことです(現在では、ライの代わりにバーボンを使うレシピもよく見られます)。 さて、「Harry's ABC of Mixing Cocktails」(1919年刊)には、「Zazarac」というカクテルが登場していますが、「Sazerac」はなぜか収録されていません。「Zazarac」のレシピは、「ライ・ウイスキー3分の1、バカルディ・ラム6分の1、アニゼット(マリブ・リザール)6分の1、ガム・シロップ6分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、オレンジ・ビターズ1dash、アブサン3dash、レモンピール」(シェイク・スタイル)となっていて、ラムが加わるところ以外は、ほとんど「サゼラック」と言っていいでしょう。 ちなみにWikipedia英語版では、この「Zazaracは、Sazeracのバリエーションである」と説明しています。20世紀初頭には間違いなく「Sazerac」は欧州にバーにお目見えしていたのですが、マッケルホーンはなぜか、「Sazerac」は無視して、そのバリエーションと言われる「Zazarac」の方をを取り上げています(その理由はよく分かりません。ちなみに、サヴォイ・カクテルブックは「Sazerac」と「Zazarac」の両方を取り上げています)(写真=Sazerac @ BAROSSA Cocktailier, Gifu City)。 末尾でも紹介している「The Artistry of Mixing Drinks」(1934年刊)の著者フランク・マイアー(パリのリッツホテルのバーテンダー)は、同書の「Sazerac」の項で「SazeracとZazaracの間で混乱・混同が見られている」という注目すべきコメントを記したうえで両方を収録し、別のカクテルであることを強調しています。つまり、1920~30年代ですら、バーの現場では両者の混同があったようです。ちなみに、マイヤーが紹介した「Zazarac」はバーボンウイスキー・ベースで、ソーダも加えるレシピになっています。 なお、現在も市販されている「Harry's ABC…」の復刻改訂版(1986年刊)では、「Zazarac」は消えて、「Sazerac」に代えられています。レシピは「アニス4dash(でグラスを濡らす)、アンゴスチュラ・ビターズを振った角砂糖1個、ロックアイスを入れて、バーボン・ウイスキー60mlを満たす」(ステア・スタイル)となっています。 では、1880~1950年代の主なカクテルブック(「The Savoy Cocktail Book」以外)は「サゼラック」をどう取り扱っていたのか、どういうレシピだったのか、ひと通りみておきましょう。・「Bartender’s Manual」(ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米、「American Bartender」(ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、「Modern American Drinks」(ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米、「Dary's Bartenders' Encyclopedia」(ティム・ダリー著、1903年刊)米、「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」(ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米、「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」(トム・ブロック著、1917年刊)米、・「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」(1930年初版刊、2008年復刻版刊)米 いずれも掲載なし・「The Artistry Of Mixing Drinks」(フランク・マイアー著 1934年刊)仏 サゼラック・ブランデー1Glass、キュラソー1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、ペルノー1dash(事前にグラスを濡らす)(ステア・スタイル)・「The Official Mixer's Manual」(パトリック・ギャヴィン・ダフィー著、1934年刊)米 ライ・ウイスキー1jigger、ペイショーズ・ビターズ1dash、角砂糖1個、ペルノー(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「World Drinks and How To Mix Them」(ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 ウイスキー4分の3jigger、ペイショーズ・ビターズ2dash、シロップ2分の1tsp、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル) ※同書にはサヴォイ・カクテルブックと同様、「Zazarac」も収録されていて、そのレシピは「ウイスキー2分の1jigger、バカルディ・ラム1tsp、アニゼット1tsp、シロップ1tsp、アブサン3dash、アンゴスチュラ・ビターズ3drops、オレンジ・ビターズ1dash(シェイク・スタイル、カクテルグラスで)」となっています。・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S.クロケット著 1935年刊)米 バーボンまたはスコッチ・ウイスキー1jigger、スイート・ベルモット1dash、アブサン1dash、ペイショーズ・ビターズ2~3dash(スタイルは不明)・「Mr Boston Bartender’s Guide」(1935年初版刊)米 ライまたはバーボン・ウイスキー2onz(60ml)、ビターズ2dash、角砂糖2分の1個分、アブサン4分の1tsp(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「Café Royal Cocktail Book」(W.J.ターリング著 1937年刊)英 ライ・ウイスキー1Glass、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、角砂糖1個、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル)・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」(ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 ライ・ウイスキー1onz、シロップ1dash、ペイショーズ・ビターズ1dash、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンツイスト(ステア・スタイル)・「Esquire Drink Book」(フレデリック・バーミンガム著 1956年刊)米 バーボンまたはライ・ウイスキー60ml、角砂糖2分の1個、ペイショーズ・ビターズ3dash、ペルノー(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(ステア・スタイル) 日本へはサゼラックは、少なくとも1920年代までに伝わり、「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)、「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)の両書に収録されています。すなわち、あのサヴォイ・カクテルブック(1930年刊)より早く、印刷物に掲載されたサゼラックとしては世界で最も早いということになります。欧米よりも日本の方で早く紹介されたという点が面白いところです。なお、両書に収録されたレシピは以下の通りです。 秋山本=サゼラック・ブランデー1ジガー、ビターズ3滴、ガムシロップ小さじ1杯、レモンピール(シェイク・スタイル)、前田本=ウイスキー1オンス、アンゴスチュラ・ビターズ1振り、角砂糖1個、アブサン(事前にグラスを濡らす)、レモンピール(シェイク・スタイル、カクテルグラスで)。 秋山本は、初期のスタイルのサゼラック・レシピを再現していると言ってもいいでしょう。これに対して、前田本はサヴォイ・レシピとほぼ同じです。サヴォイが刊行される6年も前に、こうしたレシピが日本に伝わっていたことはとても驚くべきことです(秋山氏、前田氏はどのようにして、このレシピを知り得たのかとても興味が募ります)。マッケルホーンが「Harry's ABC…」を発刊した頃(1919年)、サゼラックが欧米のバーですでに普通に飲まれるカクテルだったことを裏付ける傍証でもあります。 さて現代の日本では、標準的なレシピはどうなっているかと言えば、戦後は意外なことですが、1963年の「JBAカクテルブック」(金園社刊)、1984年刊の「サントリー・カクテルブック」(TBSブリタニカ刊)、2005年刊の「カクテルバイブル」(福島勇三著、象形社刊)くらいしか収録例がありません。そのレシピを紹介すると以下の通りです。 JBAカクテルブック=ライ・ウイスキー5分の4、シュガー2分の1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、アブサン1dash サントリー・カクテルブック=ウイスキー1Glass、シュガー1tsp、アロマチックビターズ1dash カクテルバイブル=ライ・ウイスキー5分の4、シュガー1tsp、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、アブサン1dash(事前にグラスを濡らす) 「カクテルバイブル」の著者の福島さんは88歳の現在も(東京・赤坂の永楽倶楽部バー・コーナーで)カウンターに立つ、人格、技量ともに素晴らしい業界の大先輩です。終戦直後、進駐軍のバーからずっとバーテンダーの仕事を続けておられる、「生き字引」のような方でもあります。その福島さんが半世紀以上前から、ずっと書きとめてこられたレシピが、一冊の本に結実した訳です。 「クラシック・カクテルの再評価を」といつも繰り返しているうらんかんろとしては、30年余り途絶えていた日本国内での「Sazerac」カクテルに、改めて光をあててくださった福島さんには、感謝してもし切れないほどです。 【注】Sazeracは、「ペイショーズ・ビターズ(Peychaud's Bitters)」の考案者でもあるニューオーリンズの仏系移民、アントワーヌ・ペイショー(Antoine Peychaud)が1830年代に考案したという説をとなえるサイト( http://ycos.sakura.ne.jp/Cocktail/cgi-bin/cdb_form.cgi?../Whisky/Sazerac.key )もありますが、裏付ける資料は示されていません。ただし、ペイショーは1869年~80年まで「サゼラック・コーヒーハウス」で働いていたこともあり、オーナーのアーロン・バード(サゼラックの考案者であると伝わる)にレシピの改良等でアドバイスをした可能性は十分に考えられます。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/07
コメント(0)
-
Bar UK マスターからのお知らせ/8月6日(木)
Bar UKマスターからのお知らせです。************************************* 皆さま、連日猛暑が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? Bar UKは猛暑にも負けず、元気に通常営業をいたしております。 クーラーの効いた店内で、冷たいビールやハイボールで喉を潤し、ホッと一息をつかれてはいかがでしょうか。美味しいフードもあれこれご用意いたしております。 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 なお今月の残りの店休日は、今週末の8日(土)&9日(日)と、お盆期間中の15日(土)&16日(日)、そして23日(日)、26日(水)、30日(日)です。これ以外の日は通常営業いたしております。大阪キタでのお買い物帰り等にぜひお立ち寄り頂ければ幸いです。 以上、何卒よろしくお願いいたします。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円
2015/08/06
コメント(0)
-

Harry's ABC Of Mixing Cocktails:世界初の体系的カクテルブックの中身とは(18)Rob Roy/8月2日(日)
◆「Harry's ABC Of Mixing Cocktails」にみるクラシック・カクテル 15.ロブ・ロイ(Rob Roy) 「ロブ・ロイ」は有名なカクテル「マンハッタン(Manhattan)」のベースをスコッチ・ウイスキーにしたヴァージョンとも言え、「Scotch Manhattan」「Perfect Manhattan」という異名もあります(ちなみに、カクテルの「マンハッタン」は1870~1885年頃に誕生しています → 当連載の「マンハッタン」ご参照)。 現代の標準的なレシピは、「スコッチ・ウイスキー3分の2(または2分の1)、スイート・ベルモット3分の1(または2分の1)、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=マラスキーノ・チェリー」(ステア・スタイル)というところでしょうか。「ロブ・ロイ」とは18世紀のスコットランドの有名な義賊、ロバート・ロイ・マクレガー(Robert Roy MacGregor)のニックネームです。 誕生の経緯について従来、バー業界や文献等では、「1920年代前半にロンドン・サヴォイ・ホテルのバーテンダーのハリー・クラドック(Harry Craddock=The Savoy Cocktail Bookの著者)が考案した」という説が比較的よく知られてきました。 しかし近年になって、Wikipedia英語版が「1894年、ニューヨークのウォルドルフ・アストリア・ホテルのバーテンダー(名前は不明)が、オペレッタ「ロブ・ロイ」のプレミアを記念して考案した」という別の説を紹介しています(根拠資料は「Sudhir Andrews:Textbook Of Food & Beverage Management」とのこと。しかし、末尾にも登場する「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」上ではこの説についての言及はなかったので、真偽の程は定かではありません)。 ハリー・マッケルホーン(Harry MacElhone)の「Harry's ABC of Mixing Cocktails」の初版(1919年刊)には(もちろん)「ロブ・ロイ」は掲載されています。そのレシピは、「スコッチ・ウイスキー3分の2、イタリアン(スイート)・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=チェリー、シェイク・スタイル」です。レシピは現代とほぼ同じで、シェイクかステアの違いくらいです(写真=Rob Roy@Bar Cadboll, Osaka)。 すなわち、「Harry's ABC…」が1910年代末までにバーの現場に登場した主要なカクテルは収録しているという前提に立てば、従来のハリー・クラドック考案説は疑わしくなってきますし、一方で、「1890年代前半にニューヨークのウォルドルフ・アストリアのバーテンダー考案した」という説も、下記にも紹介している1890~1920年の間に刊行された米国のカクテルブックで「ロブ・ロイ」を収録している例が一切見当たらないことからも、どの程度信用していいのかよく分かりません(マッケルホーン自身は残念ながら、「ロブ・ロイ」誕生の由来については何も触れていません)。 結論として、うらんかんろが持っている古い欧米の主要なカクテルブックで、「Harry's ABC…」以前に「ロブ・ロイ」を収録している例はなく、現時点では、「ロブ・ロイ」は「Harry's ABC…」が初出文献ということになります。ただし考案者については、「現時点では不明」としておくのが研究者としては、一番誠実な姿勢かと思っています。 では、1880~1950年代の主なカクテルブック(「Harry's ABC Of …」以外)は「ロブ・ロイ」をどう取り扱っていたのか、どういうレシピだったのか、ひと通りみておきましょう(なお、現代ではステアでつくるのが一般的かと思いますが、1934年刊の「The Artistry Of Mixing Drinks」より前は、すべてシェイクです)。・「Bartender’s Manual」(ハリー・ジョンソン著、1882年刊)米、「American Bartender」(ウィリアム・T・ブースビー著、1891年刊)米、「Modern American Drinks」(ジョージ・J ・カペラー著、1895年刊)米、「Dary's Bartenders' Encyclopedia」(ティム・ダリー著、1903年刊)米、「Bartenders Guide: How To Mix Drinks」(ウェーマン・ブラザース編、1912年刊)米、「173 Pre-Prohibition Cocktails)」 & 「The Ideal Bartender」(トム・ブロック著、1917年刊)米 いずれも掲載なし・「The Savoy Cocktail Book」(ハリー・クラドック著、1930年刊)英 スコッチ・ウイスキー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=チェリー(シェイク・スタイル)・「Cocktails by “Jimmy” late of Ciro's」(1930年初版刊、2008年復刻版刊)米 スコッチ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=チェリー(シェイク・スタイル)・「The Artistry Of Mixing Drinks」(フランク・マイアー著 1934年刊)仏 スコッチ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=チェリー(ステア・スタイル)・「The Official Mixer's Manual」(パトリック・ギャヴィン・ダフィー著 1934年刊)米 スコッチ・ウイスキー1jigger、スイート・ベルモット3分の2jigger、アンゴスチュラ・ビターズ2dash、レモンツイスト(ステア・スタイル)・「World Drinks and How To Mix Them」(ウィリアム・T・ブースビー著、1934年刊行)米 スコッチ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ2drops、飾り=チェリー(ステア・スタイル)・「The Old Waldorf-Astoria Bar Book」(A.S.クロケット著 1935年刊)米 スコッチ・ウイスキー2分の1、スイート・ベルモット2分の1、オレンジ・ビターズ1dash(ステア・スタイル)・「Mr Boston Bartender’s Guide」(1935年初版刊)米 スコッチ・ウイスキー1.5onz(45ml)、スイート・ベルモット4分の3onz(23ml)、オレンジ・ビターズ1dash(ステア・スタイル)・「Café Royal Cocktail Book」(W.J.ターリング著 1937年刊)英 スコッチ・ウイスキー2分の1、スイート・ベルモット4分の1、ドライ・ベルモット4分の1、アンゴスチュラ・ビターズ3dash、飾り=チェリー(ステア・スタイル)・「Trader Vic’s Book of Food and Drink」(ビクター・バージェロン著 1946年刊)米 スコッチ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、飾り=チェリー(ステア・スタイル)・「Esquire Drink Book」(フレデリック・バーミンガム著 1956年刊)米 スコッチ・ウイスキー3分の2、スイート・ベルモット3分の1、ビターズ1dash(ステア・スタイル) さて、日本へロブ・ロイはいつ頃紹介されたのかと言えば、日本初の体系的カクテルブック「カクテル(混合酒調合法)」(秋山徳蔵著、1924年刊)、「コクテール」(前田米吉著、1924年刊)ともに収録されていることからも、1920年代前半までには伝わっていたことは間違いありません(しかし、なぜかレシピはスイート・ベルモットではなく、ドライ・ベルモットです。欧米ではドライ・ベルモットを使った場合、「ドライ・ロブ・ロイ」と呼ばれます)。 なお、日本国内のバーでは、「ロブ・ロイ」が注文されているのを、僕はあまり見たことがありません。アルコール度数が高いショート・カクテルということで、女性に敬遠されていることも大きいのかもしれません。ならば、男性客の皆さんにもっと頑張って、カッコ良く飲んで頂きたいのですが。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2015/08/02
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1










