全205件 (205件中 1-50件目)
-

エキシージ
台座をつけて本体を載せてみたら、 ステーにこんなにも隙間がwとりあえず台座を削って取り付け。Paypalに申請して、セラーからは代金を取り戻す。サイドステップとフロントリップもカーボン化。
2022/09/05
コメント(0)
-

エアロパーツ
リアウイングをカップカータイプのものに交換。ただし中華製なので、まともには付けられないなぁ。↑ノーマルはこうだがこうなったけど…流石中華。クオリティ低すぎ。
2022/08/22
コメント(0)
-

久しぶりに楽天に来てみた。
こんな車やこんな車で、日々忙しくしております。
2022/08/01
コメント(0)
-

久しぶりに
まぁ、こんな感じで元気にしておりまする
2012/05/04
コメント(0)
-
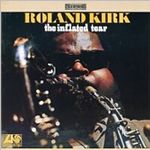
The Inflated Tear 溢れ出る涙
盲目の辻説法師。 そのグロテスクな外見にだまされるな。 ラサーンが出す音はまごう事なきJAZZそのものだ。 ジャズの伝統的なエッセンスを表現している。 外見のグロさに反比例してすばらしい音を出す。 黒い黒い、うねるようなリズムを。 ジャズの一般的な概念から逸脱している音を出すカークは、普段がんじがらめのビジネス社会で働いて者にとっては、救いの音楽ともいえる。 カークの発するドロドロの血の色に染まった音には、魂の叫びが感じられる。 このカークこそは生で聴きたかったと思う。 Roland Kirk / The Inflated Tear (1968) 邦題『溢れ出る涙』 3本のサックスを同時に吹いたり、鼻でノーズフルートを吹いたり、何でもやります。 そのカークの後期の名作。 だがまだラサーン化はしていない。 トレーンの純粋さが受け入れられた時代にはこの赤裸々なカークは受け入れられなかったのであろうかギミックだまがい物だと批評されたという話を聞く My Favorite Things のフレーズを吹いたかと思うと黒いうねりの後いきなり叫びだしたり、もーやりたい放題やるカーク。一見、正統的なJAZZではないように見える。でも、聴けば聴くほどJAZZだなぁと思う。The Black And Crazy BluesA Laugh For RoryMany BlessingsFingers In The WindThe Inflated TearThe Creole Love CallA Handful Of FivesFly By NightLovellevelliloquiI'm Glad There Is You
2007/03/04
コメント(0)
-
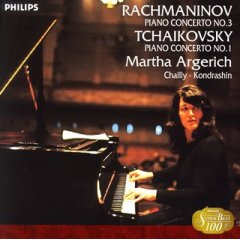
ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23
さて、久しぶりに日記でも書いてみる。チャイコフスキーのピアノ協奏曲 その中でも一番好きなのがこのアルゲリッチとコンドラシンの80年ごろの作品だ。 アマゾンのレビューを一通り見たが、誰もがアルゲリッチばかりを褒めている。 並みの天才ならその才能を焼き尽くしてしまうほどのコンダクター、コンドラシンあってこその名演ではないだろうか。 ミスタッチを単なるミスとして捉えていないか? そのミスにいたるまでの第3楽章の流れをなんと聴くか。 アルゲリッチのピチカは走る。 明らかにオケよりも走っている。 このコンドラシンVSアルゲリッチの戦いをなんと聴くか。 アルゲリッチの煌きを食うほどのオケは当時のコンドラシン以外ではなし得なかったものではないだろうか。 >「アルゲリッチにはテクニックが衰えない内にこの曲の再録音を希望したいです‥。」 この演奏の数年後にコンゴラシンがなくなってしまった今となっては、この演奏の再演は望めない。 惜しむらくは録音レベルが悪いことだが、それを補って余りある名演だと思う。 この演奏を名演だと思える自分の感覚は無くしたくはない。
2007/03/04
コメント(0)
-
Letter To Evan
Letter To Evan / Bill Evans (1980.7.21)久しぶりに日記を書こうかと思えるようになってきた。休んでいる間に、楽天広場での盟友と勝手に思っていた執事氏もここを辞められ寂しくなったなぁ。彼には残っていただきたかった。自分もミクシで遊んでばかりで放置状態でえらそうな事は言えないが。自分の思いを届けたいと願う相手が居なくなったから書かなくなったのか。自分の中でのこの日記のテーマ『敗戦処理』が終わったから書かなくなったのか。理由はもう忘れた。昨日まで暑かったと思っていたのが、一日たてば肌寒い夜になったりする9月。冴え冴えと光るというのはこういう月の事をいうのだろう。月が遠くなったように感じ、ふと人恋しくなったりする。9月は自分にとってはエヴァンスの月だ。と、理由をつけてこの1枚。1980年最後の夏を迎えたエヴァンスのヨーロッパツアー。1ヶ月にわたるそのツアーのハイライトとして、この日演奏を行ったロニースコッツでは2週間の間、演奏を行った。この演奏は、本人には無断で録音されていたものだが、一応はその遺族の了解を得て今から10年ほど前に発表されたものだ。当時は『Consecration』という超弩級の発掘音源が発表された後で、自分の中ではそれほど評価は高くなかったのだが、精神力が指を動かさせているキーストンコーナーの現存最後の演奏や、崩壊してゆく自己との戦いのさなかのバートヘンニンゲンでのライブと比べると、十分カジュアルに聴ける演奏だ。紹介のあと、静かにピアノから始まる『Emily』ジョニー・マンデル作曲の映画音楽で、60年代からずっと演奏し続けてきた曲だ。静かな右手から始まる。直線的なオブリガードが美しい。2曲目は私の大好きな『Days of Wine and Roses』この曲からラストトリオのつむぎ出す音のとりこになった。一番大好きなナンバーだ。1ヶ月後のキーストンコーナーでの演奏で聴かれるような破綻はどこにも無い。マーク・ジョンソンはやはりいいベーシストだ。同じフレーズを多用するのはこの当時の彼の若さから来るものだろうが、さほどマイナスには感じない。激しい情熱的なこの曲が大好きだ。『Knit For Mary F.』情熱的な酒バラとの対比で凄くクールに感じるが、音の対比は大きい。聴衆はその前の酒バラの盛り上がりの方がよかったのか、拍手がまばらだ。『Your Story』は何かのアナグラムだと読んだ気がするが、詳細は失念した。2小節ごとの対比が綺麗な演奏だ。『Stella By Starlight』『My Man's Gone Now』を経てラストは離れた故郷の息子を想い書いた曲『Letter to Evan』その息子、エヴァン・エヴァンスも音楽の道に進んで入るものの、父親の資産を食い潰す以外はろくな作品は残してはいない。静かにピアノのソロから始まり、2コーラス目からベース、ブラシが徐々に聴こえてくる。1.Emily2.Days of Wine and Roses3.Knit For Mary F.4.Like Someone in Love5.Your Story6.Stella By Starlight7.My Man's Gone Now8.Letter to Evan『My Romance』も『Nardis』もないが、この時期のレパートリーとしては標準的な曲か。さて、またボチボチといくかな。そろそろ。
2006/09/21
コメント(1)
-
生きている限り進化
「いつも自分の演奏を友人や若い演奏家に聴いてもらい、自分が進化しているかどうか確かめている。自分自身では、時とともに失っている部分もあるし、進化しているところもあると思う。自分が今後どういうふうに進むのか難しい所に来ている。もう若くはないし、しかしとても年をとったというわけでもない。私は60歳を越して、日本では大人になった(還暦)と言うらしいが、自分にはなにかをやりとげたという気持ちはさらさらない。すべきこと、学ぶべきことが山のようにある。生きている限り、進化していきたい」 とは、昨年来日した際のマルタ・アルゲリッチの言葉。 ちょうど仕事で行き詰まりを感じて悩んでいた自分には、ストレートにこの言葉が入ってきた。 密林を迷い迷った挙句に急に目の前が開けたような。 自分が身に付けた技術を否定され、自分が作り上げたものが他人の手によりまるで砂の城のように脆くも崩され、自分の無力を感じていた時に聞いたアルゲリッチの言葉、自分とは天と地ほどの差があるとは言え、その時点での自分を進化させるきっかけとなった。 千変万化、そうだ自分のモットーはそうだった。 常に前を向いてゆこう。 久しぶりに取り出して聞いた、アルゲリッチとコンドラシンの火花散る演奏に涙が出そうになるくらい感動した。 与えられたポストで何かを身につけてゆけばいいさ。 どこに居ても何かを身に付ける姿勢いれば、どんな境遇にも耐えられる。 打たれ強く行こう。 今日は姪っ子と佐渡裕氏のヤングピープルズコンサートへ。 氏のライフワークとも言える、子供のためのコンサート。 とにかく楽しい。 今年のテーマは『指揮者ってなあに?』 氏のあの人懐っこい笑顔で、全身を使って、子供たちに判りやすく自分の仕事を教えてくれる。 『たくさんのオーケストラに触れると楽しい』 あ、この台詞、朝比奈先生の口からも聞いた台詞だ。 ”楽しい” ああ、結果として自分が行き詰まりから脱したのも、それだったなと。 氏のエネルギーは強烈でいい力を今日も貰った。 ちょっと空回りするところは相変わらずだが。 まぁそのオーバージェスチャー的なところも氏の持ち味か。 決して、”相手は子供だから”という手抜きではない。 久しぶりに聞きたくなって朝比奈先生と大フィルの『エロイカ』を。 朝比奈先生の英雄エロイカ 大らかな流れで、かといて冗長すぎず、素朴な中でも前進力を決して失わない。 朝比奈隆の職人芸が生きている。 私が朝比奈先生のタクトを聴きに行きだした頃はもう既にかなりの高齢で、明らかな出来・不出来の差があったように思うが、この70年代の師のタクトはすばらしい。 遅い。 でも、遅いからといって、その音の推進力を失っているわけではない。 同時期の新日本フィルとのモノの方がいいという声もあるけど、私はこの大フィルとの演奏の方がいいと思う。 生きている限り・・・昨年の今日のこの日、亡くなった知人が居る。その事を知ったのは更に日が経ってからだったが。自分の誕生日に亡くなられた、その事を知った時、何も言えなくなった。自分は生きている。ゆっくりでも歩いてゆこう。あせらずに。さあ、またボチボチと行くか。
2006/08/12
コメント(0)
-
ドラマ 1リットルの涙
フジテレビ系列で、今日火曜日からドラマが始まりました。このドラマは本当にあった話です。木藤亜也さんが本当に生きた、その話です。亞さん からいただいた本は、何人もの手垢がつき、もうずいぶん汚れました。そろそろバラバラになりそうなので、新しいものを本屋で求めようかと思ってます。見て、読んで、何を考えるかは人それぞれ。私は『自分はいろいろな力を貰った』としかいえません。歌手の山川豊さんはこの本を座右宝として、何度も読み続けているそうです。どんなに辛くてもそれに打ち勝とうと、決して嘆くまいと。1リットルの涙 応援サイト__________________________________________________________________________________________私は生れ変わりました。身障者であっても知能は健常者と同じであると思っていました。着実に1段づつ上った階段を、踏みはずして下まで転げ落ちた、そんな感じです。先生も友達もみな健康です。悲しいけどこの差はどうしようもありません。私は東高を去ります。(注:彼女が1年間だけ通った高校。その後養護学校に転校)わたしは身障者という重い荷物を、ひとりでしょって生きていきます。こう決断を下すのに、少なくとも一リットルの涙が必要だったし、これからは、もっともっといると思います。__________________________________________________________________________________________是非是非、いろんな方にこの本を読んでみてもらいたい。
2005/10/11
コメント(4)
-
1980.09.15
ありがとうありがとうこんなにもすばらしい音楽を残してくれて。ミスター ウィリアム・ジョン・エヴァンス。
2005/09/15
コメント(0)
-
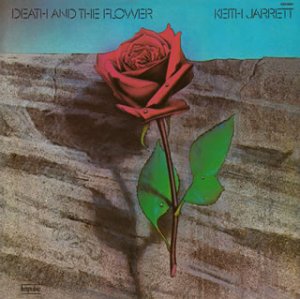
Death and the flower / Keith Jarrett
生と死の幻想『私たちは生と死の間を生きている。あるいはそのように自分自身を納得させている。本当は自らの生の絶えまのない瞬間に、生まれつつあると同時に、死につつもあるのだ。 私たちはもっと花のようにつとめるべきである。彼らにとっては毎日が生の体験であり、死の体験でもあるから。それだけに私たちは花のように生きるための、覚悟を持たなければならないだろう。 死を友とし、忠告者として考えよう。彼らは私たちを生に目覚めさせ、また晴れやかに花を咲かす。私たちの生、それはこの世で限られたものなのだから。永遠を知るまでこのことを考えよう。やがて死の幻想を求めることを忘れるだろう。しかし人生の幻影、最初の大いなる幻影を見失う以前に、このようなことをすべきでない。なぜならば、こうするために私たちは何度も死ななければならず、それを知るために生きなければならないのだから。』 ~キースの詩より~人もまた花だ。永遠に咲き誇る花などない。でも、だからこそ、美しくもありいとおしくもある。盛者必滅会者定離 この理は常に皆の傍に横たわっているといえるでしょう。会うは別れのはじめなり。バラの つぼみは早く摘め時は過ぎゆく今日 咲き誇る花も明日は枯れる“今を生きろ” 我々は死ぬ運命なのだ今を生きろ 若者たちよ すばらしい人生をつかむのだSeize the day追伸私のために尽力してくださったKさん、ありがとうございました。あなたに感謝の意を伝える場がここしかないことをもどかしく思います。心から感謝いたしております。
2005/08/27
コメント(1)
-
ミュージックバトン
ぷにぷにから渡されました、ミュージックバトン ・コンピュータに入ってる音楽ファイルの容量・・・150GB ・今聞いている曲・・・妖怪あんださんのチャットルームにて Spoonful/Cream ・最後に買ったCD・・・先週の木曜に十字屋で買った Dexter Gordon 『I Want More』 『It's You Or No One』 『Strings & Things』 『Montmartre Summit 1973』 (Jackie McLeanとの共演) 『King Neptune』 『Billie's Bounce』 『Love For Sale』 大人買い ・よく聞く、または特別な思い入れのある5曲 1.Bill Evans Trio/Days Of Wine And Roses エヴァンスはなくなる直前のラストトリオが好きだ。 いにしえの”黄金のトリオ”の良さも認めた上で。 2.Dexter Gordon/As Time Goes By 映画『ラウンドミッドナイト』より テクニック的には枯れて見るべきものはないが、 思いを込めて吹くとこうも美しくなるのかという例 3.RUSH/Tom Sawyer もう一度見たいと願う数少ないバンド ロックトリオの様式美の局地 4.The Eagles/Wasted Time 様々な思い出と共にある曲 5.ARB/Daddy's Shoes 指を鳴らせ!トラブルキッズは今もトラブルキッズのまま。 ・バトンを渡す5人 1.PIEさん(楽天広場)2.はるろりんずさん(楽天広場) 3.大島 筋ヱさん (ミクシ)4.KOETたん(ミクシ食い物つながり) 5.ともちゃん (ミクシ)ってーことでバトンタッチ
2005/06/20
コメント(2)
-
ご連絡
こんヴぁんわ。しばらく仕事が忙しくて日記は休んでおります。死んだわけではなく元気にしております。オンラインショップの店長なんかやるもんじゃありません…まだ、スピリットは切らしておりませんので、近く再開します。ではでは。ピケ拝
2005/06/19
コメント(4)
-
今日の音楽…綾戸智絵 LIVE 2005
綾戸智絵 LIVE 2005久々に楽天日記を書くぴけです。こんヴぁんわ。ここのところ忙しくしてたので随分と開いてしまいました。その間にネットショップの立ち上げとかでバタバタと。全然儲かっていないんだけどな…で、今日は久々の綾戸さんの京都ライブ。今日のステージに、数十年前立ったことあるんだよなー、ピアノで。もう今では指も満足に回らないけど。6時半、定刻どおりに開演。席はファンクラブ優先の6列目とベストポジション。幕が上がるとともに1曲目は定番の『Tennessee Waltz』日程発表時は出演者未定となっていたので誰が出るのかと思っていたが、ステージは綾戸さん一人。で、奥に段が作ってあったので、後でクワイアーも出てくるんだなと。彼女のゴスペルクワイアーの始まりはここ京都。今は本拠地を富山にもっているらしいが、最初はこの京都で始まった。多分、私が初めて綾戸さんの存在を知ったクリスマスのクワイヤーは、その始まりの頃だったのだろう。だから、京都での綾戸さんのコンサートは"帰ってきた"というイメージが私にはある。1曲目が終わった頃に3列目あたりの客が遅れて着席。で、目ざとくそれを見つけた綾戸さんはそれをいじりだす。『あんた、今のテネシーワルツ聴いてへんのぉぉ。可愛そうに。しゃーないな~』と再度テネシーワルツを。2曲目はみんなからのリクエストがあった曲との事。カーペンターズの『Cross To You』本人いわく『私、”ら~らららら~~”なんてスキャットあかんねん』といっていたが、いやいや良かった。照れてスキャット部では笑いを取っていたが。3曲目、彼女のオリジナルソング『Everybody Everywhere』会場の空気を暖めるアップテンポのノリノリな曲だ。この曲が郵貯のキャンペーンに使われたことにかけて「I Say」「You Say(郵政)」と掛け合いで客席と一体感を出してゆく。この"特殊な場"を作り上げてゆく彼女の才能はすごいと思う。その場に居るものを引き込んで行き自分の力に変える。4曲目はクラプトンの『Wonderful Tonight』をスローで。5曲目はこれも彼女のコンサートでは定番『Geogia On My Mind』この曲を聴くと、自分の芯の部分がわさわさとざわめく感覚を感じる。不可触な部分に触れる曲というのだろうか。MCで縫い目の無いシャツの話をしてたので「もしかして…」と思ったら、やはり次の曲は『Scarborough Fair』。この曲はスコットランドの民謡が元だといわれているが、歌詞にも2通りの解釈があり、意味はそれぞれ違う。詳細は長くなるので割愛。続いてスティービーの名曲『You Are The Sunshine Of My Life』を経てこれも定番『Leaving On A Jet Plane』で、彼女の本当の意味での始めてのオリジナルソングという『Get Into My Life』そしてスタンダードナンバー『Autumn Leaves』を。で、ここでやっとクワイヤー登場。が、この後はネタバレになるので、ここではここまでと。ここから2曲をクワイヤーとやり、最後は『夜空ノムコウ』でしめ。クワイヤーとの部分がよかった。思わず熱いものがこみ上げて、気がついたら涙を流していた。彼女にはいつも元気になるパワーを貰う。以前は観客が片手(5人)なんてところで彼女の歌と漫談を聴いていたんだよなー。 今回はステージを降りて客席の方まで来たけど、以前はそれよりも近い距離で歌っていた。 ロイホーとかラブリーで。 帰ろうとする客に『帰るな!あんたら損するでぇ!』とかいいながら。 でも、距離は遠くなってもおばはんから伝わってくるものは相変わらず同じだなと。 時々変な標準語が入るのはご愛嬌ってとこで。さて、また明日からも頑張るか…
2005/04/22
コメント(3)
-
今日の音楽・・・Consecration(1980)
■Consecration / Bill Evans久しぶりに楽天日記を。博多出張1泊2日を2回とかバタバタしてたもんで。以前の仕事で部下が失敗したのでシブチンになったのか、取引先から渡された切符は全部自由席…う~むむむ。で、先日手に入れたこのアルバムのLP盤を今夜は。ようやく10枚全部聴くことが出来た。 このエヴァンス死の1週間前のドラマ、過去に何度もいろんな形で発表されてきた。 私が持っている音源では 1.『CONSECRATION The Last』アルファミュージック/2枚組みCD89年発売 2.『CONSECRATION2』アルファミュージック/同年に追加で発売された未発表音源8曲 3.『CONSECRATION The Last Complete Colection』アルファミュージック/同じく同年末に発表された全68曲コンプリート盤 4.『CONSECRATION The Final Recording2 Part2』マイルストーン/02年に発表された、ピッチ調整盤 と4つ持っている。 1と2は3のコンプ盤で“そのもの”が入っているので必要ないのだが、売りに出すのももったいないので。 4は97年にピッチ調整されて再発されたものを20bit化して発売。(国内版のみ20bit) で、今回LP盤を。 このLPはアルファから90年に発売されたされたもの。 ピッチ調整後の盤と比べると、若干音に落ち着きが無いような気もするが、音質的にはこちらの方がいいかな。 マスターテープのヒスノイズは仕方がないか。 ラファロ、モチアンとのトリオをビル・エヴァンスの代表作として推す人が多いが、私はこのラストトリオが一番好だ。 なぜ、滅びる寸前の肉体がここまで素晴らしい音を出せるのだろうか? 過去に何度もここに書いてきたことの繰り返しになるが、皆がよく知るラファロ、モチアンとのトリオとはかなり違う音だ。あの頃の繊細な和声感覚は影を潜めてる。曲に対するアプローチの姿勢も違う。70年代ポリリズムに活路を見出した彼が、そのテクニックを失った末に見せたもの。失ったと言い切ると語弊があるか。テクニックに頼り切るでもなく、頃合よい表現力を見出したというかな。そもそもポリを連発するようになったのはコントロール力の衰えともいえる。ポリを連発するのが少々耳に付く70年代中盤を経て、各声部間のコントロールがすばらしい輝きを見せる70年代後半のほんのわずかな時間。ただ、手放しで評価するわけではなく、その複雑な展開性から演奏のクオリティはあがったけど、音楽の質的に言うと下がったものもあるし、肉体の衰えから来るものもある。 薬の常用による肉体的な衰えからくるものは隠しようが無い。 手が動いていない、ディスコードやミスタッチが散見される等々… でも、それらが全体的なクオリティの低下につながっていない。 生々しいまでに感情をあらわにしたピアノ、そのエヴァンスの音に絶妙のタイミングで反応するクリエイティブなベース、トリオの推進役として引っ張ってゆくドラム。 日を追うごとに肉体は加速度的に衰えを見せ、徐々にイマジネーションはきらめきの度合いが薄れてゆく。 エヴァンスソロのパートにそれがよく現れている。 それでも、このトリオの演奏には自分の心をぎゅっとわしづかみにして離さないものがある。 毎日カジュアルに聴くにはちょっと重いものがあるが、この演奏はいい。 凄くいい。 袋小路で迷い迷った末に出会ったこの演奏、この演奏の先にあるエヴァンスを見たかった…
2005/03/16
コメント(0)
-
今日の音楽・・・I Still Have Dreams(1979)
■I Still Have Dreams / Richie Furay振り返っても仕方がない、過去よりも今がすごくいい、未来は明るいに違いない、本当にそう思える日はくるのだろうか?負け惜しみでもなんでもなく。ウエストコースト路線で続いてみる。昨年のイーグルスのコンサート以来、自分としてのルーツに帰ろうとしているようだ。自然な流れとして。もともとこのひとはフォーク畑の人なので純然たるウェストコースト路線とは違うか。レコード会社が主導して作り上げたバンド、サウザー・ヒルマン・フューレイ・バンドが崩壊したのち、ソロ活動に移行してゆく。アサイラムレーベル(=デビッド・ゲフィン、後のゲフィンレーベル創始者)が“第二のCS&N”を作ろうとして組織したサウザーヒルマンフューレイは名脇役を3人集めてスーパーグループを作ろうという単純ないかにもアメリカンな発想の元に作られたバンドだった。世の中そうはうまく行かない。期待されたほどの商業的成果は得られなかった。ソロ活動を始めて、音楽は以前と比べて明るくなったように思う。ソロ第1作のあたりは宗教色を感じさせる作品が多かったが、この3作目ではそれらのカラーはあんまり感じられない。(70年代中頃にリッチーはキリスト教に帰依した)このポップ感覚が本来の彼が持つものか。その中にも挫折感を感じさせるものがある。60'sの高揚の後の無というのだろうか。リアルタイムでこの時代に聴いていない私にはこれ以上は語れないかな。その時代のその空気の中であったからこそ、意味を持つものがある。1曲目『Oooh Child』から軽快に。音の作りもいい。それまでのリッチーの交友人脈から路線を変更して、実力のみで選んだと思われるバックの面々の力か。ポコ時代のカントリー色は彼の持ち味ではなかったのだと感じさせられる。『Lonely Too Long』はラスカルズのヒット。『Island Love』や『I Was A Fool』『I Still Have Dreams』のメロディーだけを聴いてると、ソウル色が感じられるが、歌いだすと一転ウエストコースト本流に。どことなくブルーアイズドソウルな香りが。『Come On』にはティモシーBやランディ・マイズナーのクレジットも。『I Was A Fool』では先のバンドでのメンバー、ジョン・デビッド・サウザーがハモっている。『Satisfied』でのローズマリー・バトラーのハーモニーのパートもいいな。宗教色の薄くなったこのアルバムで唯一その影を感じさせる曲だ。彼がキリスト教の考えを強く受けていることはこのアルバム発表のあとに起こった出来事でもよくわかる。01.Oooh Child02.Lonely Too Long03.Island Love04.Come On05.I Was A Fool06.I Still Have Dreams07.Satisfied08.Headin' South09.Oh Mary10.What's The Matter, Please?このアルバムの発表後、自らの力に限界を感じたのか、何かを悟ったのか、彼はコロラド州で牧師としての生活を始めました。82年に発売された4枚目のソロはクリスチャンレーベルから出されたものであり、97年に発売された5枚目も別のクリスチャンレーベルから出されました。もう彼がメインストリームに帰ってくることは無いだろうけど、それが彼のやりたいことならば、それもまたいいか…
2005/03/05
コメント(0)
-
1リットルの涙
今日、たまたま風邪を引いて会社を休んでました。で、昼間テレビをつけてたら徹子の部屋でこの本と映画のことが…かとうかずこさんが読み上げられた、木藤さんから黒柳さんへの手紙お母さんはこの映画に亜也さんを感じたと。上映予定館 ぜひぜひ、機会があれば。
2005/02/16
コメント(3)
-
今日の1枚…Natural Progressions (1977)
■Natural Progressions / Bernie Leadon & Michael Georgiades Band1月から久しぶりの楽天、今日は風邪引きで仕事は休みました。ネットショップの立ち上げ等で、毎日ばたばた。今まで基幹システムをメインに扱ってきた自分としては、webはまだまだ知らない事ばかり。新しいことをやるために時間をとりたいのだが、なかなか。自分が進むべき道についてももっと時間をとって考えたいのだが。流されることなく、虚心に自分を見つめてゆきたい。そこから生まれるものを力に変えて。今の自分が記憶の中に消え去るまでに。バーニー・リードン初期イーグルスを支えた男。当初、イーグルスはLAのカントリーロックバンドとして受け入れられた。それは結成までにフライングブリトー等のいろんなバンドで活躍してきた、バーニーの評価によるところが大きい。ペダルスチール、ストリングベンダー、バンジョーといったカントリーロックには欠かせない楽器をいくつも操るバイプレイヤー。60's幻想の幕引きとともに脱退した彼が友人、マイケル・ジョージアデスと組んだ作品がこのアルバムだ。2人が仲良くマーチンのギターを抱えているジャケがこのアルバムの性質を現しているともいえる。ジョージアデスが6曲、バーニーが4曲書いている。”これ”といえる1曲はないが全体的に流れる音のフレイバーが心地いい。何度も聴き返したくなる作品だ。バーニーにしては都会的に仕上がっているのは、マイケルの力か。自分はこのあたりの音楽が好きなんだなと再確認。先ずはマイケルの曲『Callin' for Your Love』アコギ、パーカッション、エレピの取り合わせがフリーソウルに通じる。元ジェリー・ガルシア・バンドのドラマー、ケンパーの音がいい。(このアルバムの時点では当然ジェリーガルシアバンドはまだ無い)ケンパーは4,5年前にボブ・ディランのバンドで来日していたはずだ。変わったところではフォーカスのアルバムにも彼がクレジットされている。アップテンポなナンバーが彼の持ち味だと思うが、このアルバムのようなけだるさの中でも存在感がある。落日の幕引きを連想させる『How Can You Live Without Love?』ハーモニーが心地いい。使っている楽器にしては、都会的なソフトロックを感じさせる曲。ケンパーのブラシが心地いい『Breath』ちょっとヘビーな『Rotation』軽快で、ウエストコーストの海岸沿いをオープンカーでドライブしてるようなイメージを連想させる『You're the Singer』ドラムのヘビーさが前面に出ている『Tropical Winter』と4曲、マイケルの曲が続く。このアルバムの中で一番のお気に入り『As Time Goes On』ウエストコースト・ロックの敗北の歴史を感じさせる歌だ。「We're happy now,we've finally found what we were looking for」というフレーズが好きだ。けだるげな『Sparrow』短3度上の音がキーになっていると感じる。ゆったりとしたロックンロールを聴かせる『At Love Again』はマイケルの曲だ。「Witchy Woman」を連想させるイントロの『Glass Off』L.Aの夕暮れの景色が見えてくるようだ。01.Callin' for Your Love02.How Can You Live Without Love?03.Breath04.Rotation05.You're the Singer06.Tropical Winter07.As Time Goes On08.Sparrow09.At Love Again10.Glass Off70年代のウエストコースト・ロックが好きな人にはオススメの1枚。バーニーの音がすごく心地よく感じる。マイケルがメインに出て、バーニーがその引き立て役に回っている感が強いが、彼が隠し味として生きている。バンドのレベルも高く、ウエストコーストのソフトロックを心地よく聞かせてくれる。裏ジャケでバンジョーを抱えるバーニーとそれを囲む友人たち。カントリーテイストが適度に効いたいい作品だ。”カリフォルニアの夢”が夢のまま、 テキーラ・サーキットの宴が終わりを告げたトルバドゥールでの1ページ、そんなアルバムだ。
2005/02/15
コメント(6)
-
今日の音楽・・・At The Village Vanguard August 17,1967 / August 18,1967(Part2)
■At The Village Vanguard August 17,1967 / August 18,1967 / Bill Evans Trio8月18日の音源はミドルテンポの『In a Sentimental Mood』から。この演奏はいい。ほどよく抑制されている。ポリリズミックなフィリー・ジョーの特徴がほどよく出て、いい感じに仕上がっている。そのままの流れで『California Here I Come』やはりこのトリオの持ち味はこういいテンポの曲か。『Emily』はお気に入りのナンバーだ。ラストトリオの演奏が一番好きだ。ここでの演奏はまたちがったアプローチを見せているが、トリオが補完しあったいい演奏だ。フィリー・ジョーが扇動的にひっぱる、『G Waltz』この曲はこの日4度演奏している。というか、このヴァンガード以外では記録として残されていない。彼のオリジナルだが、作品が気に入らなかったのか。『Wrap Your Troubles in Dreams』もこの日の演奏の方がいい。2ndセットに。『You're Gonna Hear From Me』はほぼ同じアレンジだが、こちらの方が心地いい。酒が進んでいるというせいもあるか。『On Green Dolphine Street』は初リーダー作直後にもフィリー・ジョーとのトリオで吹き込んでいるが、こちらの方がいい。透明感がある。フィリー・ジョーと一緒というと、薬の匂いが漂うが、この18日の音源は前日のものと比べるとよく仕上がっている。ゴメスには暴走を止めるだけの力がないので、走り出すとどうしようもないのだが、この日はそれ以前でとまっている。発表を前提とした録音ということが効いているのか。バラードナンバーが多いと、もっと耳についたかもしれないドラミングもこれくらいならOK。August 18,1967 Disc1(1st Set)01.In a Sentimental Mood02.California, Here I Come03.You're Gonna Hear from Me04.Alfie05.Gone With the Wind06.Emily07.G Waltz08.Wrap Your Troubles in Dreams (And Dream Your Troubles Away)Disc2(2nd Set)01.In a Sentimental Mood02.California, Here I Come03.You're Gonna Hear from Me04.Alfie05.Gone With the Wind06.Emily07.G Waltz08.Wrap Your Troubles in Dreams (And Dream Your Troubles Away)09.On Green Dolphin Street(3rd Set)10.G Waltz11.You're Gonna Hear from Me12.Wrap Your Troubles in Dreams (And Dream Your Troubles Away)13.Gone With the Wind14.Emily15.G Waltz『GETTING SENTIMENTAL』での闇雲な疾走等、フィリージョーにはいいイメージがないのだが、ここでのものはいい感じだな。フィリー・ジョーが疾走するのをわかっているから、エヴァンスがバラードナンバーを控えたというのもあるだろうが。
2005/01/05
コメント(0)
-
今日の音楽・・・At The Village Vanguard August 17,1967 / August 18,1967(Part1)
■At The Village Vanguard August 17,1967 / August 18,1967 / Bill Evans Trioこんヴぁんわ。お正月でずいぶんと太ってしまったピケです。(-_-;)お正月で見ようと思っていたDVD、全然見れませんでした。ロギンスのグランドキャニオンライブとエヴァンスのモノクロ映像くらいで。まあ、ボチボチ見ながら整理していこう。この2枚組み2SETは以前に書いたLP『California Here I Come』に収録されているものをベースに単発では作品化されてなかったと音源を追加して、新たに編集しなおしたものだ。『California Here I Come』としては9月にヴァーヴからCD化されており(国内盤は発売されていない)、元からのLPとあわせて私の持っているものはダブリまくり。まあ、鉄錆BOXはなかなか出して聴く気になれないし(手が汚れる)、この2枚組みに解説を書かれている杉田氏のものもなかなかGOODなのでそれはそれでいいか。LPのレビューのときにも書いたと思うが、元となった『California Here I Come』は、死後2年経った82年の発表。この作品だけ長くCD化されなかった理由は謎だ。ま、特に理由などないのかもしれないが。生涯最長のパートナー、エディ・ゴメスと、そのキャリアを通じて一番多く共演しエヴァンス自身も好んだというドラマー、フィリー・ジョー・ジョーンズ。フィリー・ジョーとはクスリ友(苦笑)ということもあり、長く続いたのだろうか。確かこの演奏のあとも、薬の治療のためにトリオから離れたはず。61年の奇跡とも言える演奏と同じ、1日3Set。ラストトリオのこの地での演奏は2Setとなっているが、これはやはりクスリからくる体力の消耗が原因か。1stセットは『Happiness Is A Thing Called Joe』から。この曲はこの演奏以外、記録として残ってないはず。ちょっとアップに『In a Sentimental Mood』フィリー・ジョーは少々にぎやか過ぎる感もあるが、それによってエヴァンスの普段は見せない面が現れているともいえる。ダメ男『Alfie』この前年にマイケル・ケイン主演の映画用の曲としてバカラックが作ったもの。『Gone With the Wind』は「風とともに去りぬ」といった方がわかりやすいか。フィリー・ジョーのダメな一面が。空中分解寸前まで突っ走りすぎ。晩年の疾走感とは違い、全くコントロールされていない。スリリングというよりははらはらする。『Turn Out the Stars』はまだ抑制下か。『Polka Dots and Moonbeams』ももう少ししっとりとした感じが私は好きなんだが。『Stella by Starlight』は逆にこういう展開も面白いか。いつもどおりピアノから始まる『Emily』程よく抑制されてトリオがうまく機能している。『Wrap Your Troubles in Dreams』はエヴァンスとフィリー・ジョーの息が合ったいい例だ。2小節ごとのやり取りの後、1小節ごとに進化し、エンディングを迎える。August 17,1967 Disc1(1st Set)01.Happiness Is A Thing Called Joe02.In a Sentimental Mood03.Re:Person I Knew04.California, Here I Come05.Alfie06.Gone With the Wind07.Turn Out the Stars08.Polka Dots and Moonbeams09.Stella by StarlightDisc2(2nd Set)01.Very Early02.You're Gonna Hear from Me03.Emily04.Wrap Your Troubles in Dreams (And Dream Your Troubles Away)05.'Round Midnight06.On Green Dolphin Street07.If You Could See Me Now08.I'm Gettng Sentimental Over You(3rd Set)09.You're Gonna Hear from Me10.G Waltz11.California, Here I Come12.Emily13.Alfie14.Wrap Your Troubles in Dreams (And Dream Your Troubles Away)18日分は明日に書こう。
2005/01/04
コメント(0)
-
今日の1枚・・・Seven(2004)
■Seven / 綾戸 智絵年末ジャンボ、まだ夢見ていたいから確認してないピケです。こんヴぁんわ。正月はのんびりと。この連休が終わったら、4日以降はほとんど休めないかもしれないから、今のうちに。年末の掃除時に電源系統も小細工をしてみたのでいろいろなジャンルのものを聴きながら効果を試してみた。もう一度極性を調べて全てアースを取り直して、メセニーのギターの透明感が増したように思う。アコースティックリヴァーヴの機器を買うかと考えていたのだがこれでしばらくいって見よう。心なしかエッジも立ちはっきりとした音になった。中高音の立ち上がりが心地いい。PC音源用のウーファーをステレオにまわしたりいろいろ試してみたんだが、もう少しかな…いいエンジニアリングの音源を聴くと、もっと上を追求したくなる。久しぶりに2日連続でアップして古いものを整理してたら、自動巡回の方々の足跡がぺたぺた。全部消してしまいたいものだ。アフィリエイトばかりで中身が全然ないサイトを、ワザワザ足跡をたどっていってみてもな。綾戸さん、デビュー7周年。初めて知った、北山倶楽部でのクリスマスライブからもう10年ほど経つ。やはりナマで聴きに行きたいのだが、なかなか。『今日出るよ』という情報は入るのだが、なかなか予定が合わず、公式なライブしか行けない。ツアーを見に行っても、新譜からの曲しか聴けずリク出来ないが、まあ仕方がないな…前作『Time』からほぼ半年。相変わらず忙しい中で精力的にレコーディングを行っている。スタジオの関係で原人江川さんたちがバックにいなくなったのがちょっとさびしい。パワフルなおばはん、「今度CDつくってん!」「今度デビューするでぇ!」 今まで数多くのサプライズを届けてくれた。ジョン・ビーズリープロデュース第3作目の今作では、いきなり1曲目が『Born To Be Wiid』(ワイルドで行こう)カナダのロックバンドステッペンウルフのHIT。こりゃまたサプライズ。気持ちよいブラスに載せてあっけらかんと。続いて『I Can't Stop Loving You』を黒っぽく。2度目の吹き込み『Tenessee Waltz』この曲はムカシからライブで何回も聴いたなあ。その時々により形は変わっているが。珍しいところでスティーリーダンの『Do It Again』都会的なこの曲をコテコテ調なアレンジで。ナベサダさんのオリジナルナンバー『My Dear Life』オリジナルはリトナー、グルーシン等GRPオールスターズといった面々だ。ヴォーカルバージョンも何人かの方であったな。ちと軽さが足りないな。雲の上を歩くような軽快感がこの曲の持ち味だと思うのだが。ちと、味付けがおせち料理的。う~むペドロ&カブリシャスか『Was Ich Dir Sagen Will』(別れの朝)オーストリアの作曲家、ウド・ユルゲンスの作だということをはじめて知りました。イーグルスのナンバー『Desperado』う~ん、ちょっと無理が。この曲はいろんな人がやっているが、平井堅のは逆に軽すぎるし・・・リンダ・ロンシュタットくらいがいいな、やっぱり。内容はいろんな解釈もあり重いのだが、もうちょっと軽めがいいと思う。『When The Saints Go Marching In』久しぶりにおばはんのスキャットにクチトロンボーン。陽気に行進ってカンジがおばはんらしくっていい。『I Fall In Love Too Easily』このアルバム唯一のスタンダードナンバーか。レディデイ、エラ、そしてシナトラ御大などいろんな人が歌っている。歌なしでもチェットやマイルスが。映画『Weigh Amchor』劇中で歌うシナトラが初演か。シカゴブルースの名曲『Troubled In Mind』最後はストーンズの曲、『Angie』で。1.Born To Be Wiid2.I Can't Stop Loving You3.Tenessee Waltz4.Do It Again5.My Dear Life6.Was Ich Dir Sagen Will7.Desperado8.When The Saints Go Marching In9.I Fall In Love Too Easily10.Troubled In Mind11.Angieう~ん、全体的なまとまりがすこーし足りないかと。安楽な座に甘んじることなく、新しいピークを目指しているのはわかるんだけど。ぴりぴりとした緊張感や新たな音楽を作り出そうとする熱い意欲があるだけに、もったいない。大好きなだけにどうしても期待が大きくなってしまうのは仕方がないか。
2005/01/03
コメント(0)
-
今日の音楽・・・The Gram Parsons Anthology(2001)
■The Gram Parsons Anthology / Gram Parsonsこんヴぁんわ。ずいぶん久しぶりの楽天です。忙しかったのやらいろいろで2ヶ月ほど放置してました。その間にも来て頂いていた方には、素直に感謝感謝です。書きたいこと、言いたいことはいろいろあったけど、忙しかったのと精神的に書く気になれなかったのと。止めるつもりはありません。どんなペースであれ継続してゆきます。ここが理想郷ではないと言うことは初めからわかっている事。”幻滅した”と去ってゆく方もおられますが、私はそうはしない。執事さん、楽天広場というスペースやそこに集う人々がどうであれ、あなたには残っていただきたい。久しぶりのレビュー、また意外だと言われそうだがカントリーロックの始祖とも言える人物、グラム・パーソンズ(以下GP)。私が彼を知ったきっかけはイーグルスから。バーニー・リードンが歌う「My Man」が彼のことだと言うことを知り、そこからGPというアルバムだけ聴いてみた。もうその頃には彼はこの世にいなかったが。以下、「My Man」の一節をI once knew a man,a very talented guyHe'd sing for the people and people would cryThey knew that his song came from deep down insideYou could hear it in his voice and see it in his eyesAnd so he traveled aloneリードンはGPとはフライング・ブリトー・ブラザーズでの盟友関係だった。この曲が発表される前年に亡くなったGPへの追悼。この追悼の曲を最後にイーグルスのカントリーロック色は失われていった。補足しておくと、GP自身はイーグルスのことを批判していた。”バブルガム的だ”と。だが、逆の見方をするとイーグルスはGPのフライング・ブリトーやポコの失速を見て自分たちはその轍を踏まないようにしただけとも言える。ただ、その方法は結論としての敗北がありき、と言ったものだったのかもしれない。私は80年代の、俗に"80's"とよばれているものも好きだけど、その敗北の歴史を知った上での70年代のロックの方が好きだ。カントリー系でもトム・ウェイツを聴く事をおしゃれだと勘違いして聴いている人は多いみたいだけど、GPを聴くのがおしゃれだと思う人はいないようで、日本では無名な存在のままか。本国でもカントリーにロック世代の感覚を移植しようとする彼の感覚は長く正当に評価されなかった。その"理解されない苦悩"が彼を死に至らしめたのか。さて、アルバム。先ず結論。ライノのコンピは期待を裏切らなかった。GPというアーティストの軌跡をたどるいいコンピだ。安直にHITだけを集めたと言うのではない、企画したもののGPへの思いが感じられる。インターナショナル・サブマリン・バンド、バーズ、フライング・ブリトー・ブラザーズを経てソロでキャリアを終えた彼の重要な部分をチョイスしている。先ずはインターナショナル・サブマリン・バンドのアルバム『Safe At Home』から6曲。軽快なナンバー『Blue Eyes』は後にザ・バーズのアルバムでも取り上げる。”いかにもカントリー”というほのぼのとした、いい曲だ。『Do You Know How It Feels (To Be Lonesome)』はその後ブリトーのアルバム『The Gilded Palace Of Sin』でも歌っている。邦題『僕の淋しさを知って』これはその名のとおりGPの心情を歌ったものなのか。重厚な音のつくりの『I Must Be Somebody Else You've Known』これ結構好き。続いてザ・バーズの『Sweetheart Of The Rodeo』から5曲GPはバーズに雇われてたはずだけど、作品はGPの意向が濃い。録音もGPの強い希望でナッシュビルで行われた。(カントリーの聖地)作品は全体的にカントリー色が強い。特にここに選ばれているナンバーはそうだ。このコンピにはディランの作品が選ばれていないから当然ともいえるが。全編ストリングベンダー(ペダルスチールとギターの親戚ってかな)が印象的。牧歌的な『Hickory Wind』から深いストーリーを持つ『One Hundred Years from Now』まで、名盤からのチョイスは難しかっただろうが、ベストに近いと思う。いずれバーズについては別途書いてみよう。次にフライング・ブリトー・ブラザーズの『The Gilded Palace Of Sin』から8曲。これは彼らのファーストアルバムだ。カントリーロックといえばやはりこのブリトーの名ははずせない。あくまで”雇われメンバー”だったGPがバーズ脱退後に作ったバンドだ。トラブルからバーズを脱退したGPの安息の地だったのだろうか。バーズの作品との比較としてはロック色が強い。誤解を招かないように書くと、カントリーロックとして。クリス・ヒルマンとのハーモニーがいい。『Christine's Tune』はバーズのファンクラブ会長であったクリスティン・ヒントンの歌。この曲のリリース後に事故で命を落としたそうだ。この曲がブリトーのテーマともいえる、重要な曲だ。後のポコ、イーグルスはこの曲の影響が濃いように思う。私は。サンフランシスコのヒッピームーブメントとは対照的にL.Aには精神性のようなものがなく、それを強く求めているように感じる。だからこそのカントリーロックなのかもしれない。『Do Right Woman, Do Right Man』にはデヴィッド・クロスビーがコーラスで参加。この曲のアレンジのセンスがいい。流石GP。スチールギターの使い方一つでこうも変わるものか。『Wheels』は都会から田舎への道か。GPとヒルマンのハーモニーがいい。コステロが後にカバーした『Hot Burrito #1』こっちを後から聴いたけど、オリジナルの方がやっぱいいわーヒルマンいわくこれはGPと彼女の破局の歌らしい。そういった意味でもコステロの歌がかなうわけがない。『Burrito Deluxe』から6曲。このアルバムからバーニー・リードンが参加する。が、GPの転落はここから始まったともいえる。ヒルマンいわく、レコーディングの後半には顔も出さなくなってしまっていたらしい。アンサンブルの出来としてはこのアルバムの完成度は前作よりも高い。『Older Guys』のうねりのような力は面白い。ハーモニーが綺麗な『Cody, Cody』はなんだかCS&Nのナンバーのようだ。バーニーが入った効果が一番現れている。『Wild Horses』はミック・ジャガーとキース・リチャーズが書いた歌だ。カントリーが好きなストーンズの二人が書いた曲を親友のGPが歌ったもの。GPソロ『GP』から8曲。ブリトーを追われたGPはエミール・ハリスとの活動によって復活を果たす。エミール・ハリスはGPによって見出された。で、バックにはプレスリーのバンドメンバー等、GPのやりたかった音楽を演奏できるメンバーがそろった。プロデューサーは敬愛するマール・ハガードに依頼したが、グラムの飲酒癖を理由に拒否。で、そこに現れたのが失意のイギリス時代の友人リック・グレッチ。フィドルの音色がいかにもって感じの『Still Feeling Blue』。そこに乗る2人のハーモニーがいい。『We'll Sweep Out The Ashes In The Morning』での二人が入れ替わるところも。まだメインとして張るだけの力量がなかったエミールの使い方を心得ているGPによって、彼女の魅力が引き出されている。まだ完全に飲酒癖からは立ち直ってないが(永遠に立ち直れなかったか)GPは体調的にはいいようだ。かなりのお気に入り『She』ディープサウスに置き去りにしたものへの郷愁…ハレルヤ!!『Live1973』から3曲。これは『GP』リリース後のツアー音源。『Drug Store Truck Drivin' Man』はバーズ時代のGPの作品だが、バーズがこの曲を録音したのはGP脱退後。GPの死後発表された『Grievous Angel』から10曲。このアルバム、もうGPはボロボロだったと思うのだが、声の調子はいいという評価だ。いやいや、これは体調ではなく心から来るものだろう。自らが望んだ音を、望んだバンドで出来るという。エミール・ハリスの存在感は前作よりも上がっている。それまでのヒルマンやリードンとのハーモニーとはまた違い、カントリーロックに乗る女性ヴォーカルってのもいいと思う。ルーツミュージック定番のロードソング、『Return of the Grievous Angel』で幕を開ける。ピアノの使い方が効果的な『Brass Buttons』初期のイーグルスの音が好きな人にはこの曲なんかGPの入り口としていいだろう。彼女-亡き母が縫ってくれた真鍮のボタン…GPはどうしてここまで無防備になれるのか。ここまで自分をオープンにしてしまっては生きづらかっただろうに。悲しいエンディングを迎える『$1000 Wedding』。なんと感情的に無防備なことよ。この時代にGPが築きあげたものは、そこからの追求あってのものでありその核は誰にも真似できないということが、明確な形で残るという意味では今日的な意味はあると思うが。文化としてではなく歴史として生み出されたカントリーのイデオムから得たものをGPは別の表現領域まで広げていった。そして、そこから生まれた挫折感が、彼を死に至らしめた。1973年9月19日、ツアー先のホテルでドラッグのオーヴァードーズにより死去。1.Blue Eyes2.Luxury Liner3.Do You Know How It Feels (To Be Lonesome)4.I Must Be Somebody Else You've Known5.Miller's Cave6.Knee Deep in the Blues7.Hickory Wind8.You're Still on My Mind9.Christian Life10.You Don't Miss Your Water11.One Hundred Years from Now12.Christine's Tune (A.K.A. Devil in Disguise)13.Sin City14.Do Right Woman, Do Right Man15.Dark End of the Street16.Wheels17.Juanita18.Hot Burrito #119.Hot Burrito #220.High Fashion Queen21.Older Guys22.Cody, Cody23.Wild Horses24.Sing Me Back Home1.To Love Somebody2.Still Feeling Blue3.We'll Sweep Out the Ashes in the Morning4.Song for You5.Streets of Baltimore6.She7.New Soft Shoe8.Kiss the Children9.How Much I've Lied10.Drug Store Truck Drivin' Man [Live]11.That's All It Took [Live]12.California Cotton Fields [Live]13.Return of the Grievous Angel [Remix]14.Hearts on Fire15.Brass Buttons16.$1000 Wedding17.Love Hurts18.Ooh Las Vegas19.In My Hour of Darkness20.Brand New Heartache21.Sleepless Nights22.Angels Rejoiced Last Night GPは柩におさめられて、妹のいる故郷の南部に送られるのを待っていた。だが、彼が南部の地に送られることはなかった。彼が最も心を許した友人により盗まれた死体は、生前のGPの言葉に従い、ロスの東、ジョシュアツリー国定自然記念物公園にて荼毘に付されました。
2005/01/02
コメント(2)
-
あけましておめでとうございます
とりあえず、生きております。なかなか時間が取れないのとmixiの日記がメインになってきたこともあってこちらは放置気味ですが、今年もボチボチ書いてゆきますので、よろしくお願いいたします。ニューイヤーをファーガソンのハイノートで迎え気持ちも新たに。先ず新年1発目のレビューはグラム・パーソンズから行こうかと思っております。(予告)日本では評価の低いアーティストなので面白くないかも知れませんが、まあ自分の趣味なので付き合ってやってください。
2005/01/01
コメント(3)
-
イーグルス大阪ドーム
いって来ました。 大阪ドームはバビロンのストーンズ以来。 大正駅降りた時点で6時回ってたので走りました、ドームまで。 もう全力疾走で最後まで完走しました。 何人も抜き去ってやりました。 それだけでも今日の自分を褒めてやりたいです。 えらいぞ俺。 で、なんとか1曲目のロングランに間に合った。 うんうん、今日はドン・ヘンリーの声も出ている。 演奏曲目自体は東京と全く同じ。 しいていうと違ったのはジョー・ウォルッシュのノリ。 東京の時よりも乗ってた。 「わっさー!!」も連発。 でも、ウォルッシュが乗れば乗るほど、引いちゃう人が多かった気も。 ジェームス・ギャング時代のモノ、予習してませんね。 ウォルッシュは“人殺しと強姦以外は何をやってもいい”と言われてイーグルスに入った人なのであれでOKなんです。(本当か) ホテルカリフォルニアは東京では自分の聴き間違いかと思ったけど、やはりキーを下げてました。 今日も感じたから間違いないです。 『Tlake it to the Limit』も音は低かった。 ランディー・マイズナーのダラスライブ盤が一番ベストだと思います。 細かいこと言い出したらきりがないけど。 イーグルスはもともとライブバンドではなく、ライブとアルバムの演奏差はあんまりないからなー。 最後の『Desperado』ライターつけてる人の多かったこと。 やっぱ大阪、無法地帯。 携帯カメラ、バシバシ撮ってる人もいたし。 マナーは悪かったです。 自分が彼らの音楽を一番聴いていたころの思い出がよみがえりました。 よかったです。 でも… 高揚の後の挫折感に似た感情を感じてます。 無意味な万能感を感じていたあのころ。 帰りの電車でも、周りの人はいい音楽を聴いたあとの高揚感でニコニコしてたけど、自分はそうはなれなかった。 それが素直な心情です。 『イーグルス、最高でした!』と素直に言い切れない。自分はイーグルス現役最後の世代だから、70年代のイーグルスが敗北してゆく過程をリアルタイムでは体験していない。最後のほんのわずかな時間だけだ。でも…まあ、これが素直な感想です。
2004/11/03
コメント(5)
-
イーグルス 東京ドーム公演(10/30)
土曜日は午前中まで京都で仕事して、そのままのぞみにのって行ってきました、東京ドーム。ポールのコンサート以来かな。ストーンズの初来日の方があとだっけ。 まず、音響は最悪でした。 これちゃんと仕事してるか?ってくらい。 ロックのコンサートってこんなものかなー で、6時過ぎに開演。 先ずは『The Long Run』から ドン・ヘンリーの声、少しきつい。 出てないなあ。 ちなみにオリジナルアルバムでのサックスはデビッド・サンボーン。 この公演では演奏されなかったけど、『Sad Cafe』の哀愁を帯びたアルトがよかったなあ。 次はグレンのリードナンバー『New Kid In Town』 グレンのチェックのシャツ、変わらないなー。 この"New Kid"ってのはホール&オーツのことだ。 シニカルに音楽界の冷たさを描いた曲。 で、ここでグレンのMC 「FAREWELL 1ツアーに来てくれてありがとう」 別にフェアウェル2をやるわけではない。 彼ら流のシニカルなジョークだ。 グレンがピアノに移り『Wasted Time』 この曲は後期の名バラードだ。 リプライズは演奏ではない。 まあ、ほとんどの人がこの流れを理解してなかったかも。 このまま後期のナンバーを中心にやっていくのか?と思ったら、グレンがソロコンサートでも好んで演奏するナンバー『Peaceful Easy Feeling』を。 続いてティモシーB登場。 彼に対する暖かい拍手の多かったこと。 この日はティモシーの57歳の誕生日、とグレンが紹介する。 ロン毛でスリムというその容貌は変わらないなー。 もちろん『I Can't Tell You Why』を歌うそのファルセットも。 『One Of These Nights』 ここにドン・フェルダーがいないことが… ドン・ヘンリーとグレン・フライがイーグルス利権の全てを握っていることに反感を持っていたドン・フェルダーが離脱することは当然だったのかもしれないけど、残念だ。 『Lyin' Eyes』はイーグルスをよく知るファンには受けはよかったようだがあまり知らない人は…(笑) 次はドン・ヘンリーのソロ『The Boys Of Summer』 これは逆にイーグルス時代のファンからはあんまり受けなかったかも。 MTV大賞を取った曲なんだけどなあ。 ウォルッシュ登場『In The City』 このウォルッシュのバカっぽさがかっこいい。 『Already Gone』 う~ん、フェルダーのギターのイメージが… 今回のツアーはサポートメンバーの腕に頼る部分が大きい。 ってわけで第1部はここで終わり。 引き続き第2部ね~ん 01.The Long Run 02.New Kid In Town 03.Wasted Time (& Reprise) 04.Peaceful Easy Feeling 05.I Can't Tell You Why 06.One Of These Nights 07.Lyin' Eyes 08.The Boys Of Summer 09.In The City 10.Already Gone で、20分ほどの休憩のあと第2部開演。 先ずはグレン『Tequla Sunrise』 初期の名盤「Desperado」から。 う~ん、肝心のDesperadoはいつやるんだよーう。 グレンのソウルフルな魅力が見られる。 構成としてドン・ヘンリー→グレン・フライの繰り返しで、所々にウォルッシュとティモシーBのリードという感じ。 リユニオン後のアルバムから『Love Will Keep Us Alive』 これもあんまり受けよくないなー。 で、さらに新しい『Hole In The World』 これはこの間出たベスト盤にカップリングされてたんだけど、この秋に出るって話だった新譜はまだかな… 最後に新しいアルバムを作るって話だったけど。 中期の名盤から『Take It To The Limit』 やっぱ、これはランディ・マイズナーの曲だよなあ… マイズナーはこのリユニオンには全く関与してないから、このナンバーを演奏するか心配でした。 この曲は彼らのハーモニーの美しさが一番よく出ていたと思います。 その美しさがオリジナルのこの曲ではまだイーグルスに参加してなかった、ティモシーBの力による部分が大きかったのは皮肉なところで。 「グレンはソロのナンバーやらないのかなあ」と思ってたら、サックスのソロからすぐわかったこの曲『You Belong To The City』 でも、「え~、この曲なに~」って人は多かったなー。 派手なスライドギターで「おお!」 やっぱり『Walk Away』だ。 ウォルッシュのリード作少ないから、ジェームス・ギャング時代のものも。 ウォルッシュのバカさ、サイコー!! ステージ上のスクリーンにも『COOOOL』と。 わかるファンには盛り上がった1曲でした。 ちなみに、ジェームス・ギャングは開拓時代に実在したギャング団で、そのジェームス・ギャングにあこがれて同じ道を歩んだのがダルトン兄弟。 で、そのダルトン兄弟の一生を描いたコンセプトアルバムが「Desperado」だ。 で、そこに元ジェイムス・ギャングのウォルッシュが加わると。 なんか微妙なつながり。 なんでこの曲を入れたんだろうっていう『Sunset Grill』 この曲、ヘンリーのソロ作「Building The Perfect Beast」でもあんまりヒットしてなかったし。 う~ん、アンコールへの伏線か? 『Life's Been Good』なんかも意外な選曲。 確か、2枚組ライブ盤にも入ってたっけ。 ウォルッシュ、いくつギターを使う気だろうか… ドン・ヘンリーのソロ作から『Dirty Laundry』 次もウォルッシュソロで『Funk No.49』 この辺はあんまりコアではないファンはついてゆけてなかった。 次の大阪に行く人はジェイムスギャングとかも予習しておきましょう。 彼ら最後のナンバー1ヒット『Heartache Tonight』 これもグレンらしいいい曲だ。 ホーンセクションがいい味出していたなあ。 で、トリに『Life In The Fast Lane』 う~ん、これもなんで曲目に入ったのかわからない選曲。 で、これにて第2部終了 続きはアンコールへ。 11.Tequla Sunrise 12.Love Will Keep Us Alive 13.Hole In The World 14.Take It To The Limit 15.You Belong To The City 16.Walk Away 17.Sunset Grill 18.Life's Been Good 19.Dirty Laundry 20.Funk No.49 21.Heartache Tonight 22.Life In The Fast Laneで、メンバーは引っ込んだわけだけど、そりゃ当然あれもやるでしょうと。 で、再度出てきてやりました『Hotel Calfornia』 トランペットのイントロで、コードをわからない人には何の曲をやるか理解できなかったようで。 ウォルッシュが12弦を使うってウワサもあったけど、やっぱり無理だったようで、サポートメンバーが。 やはりこの曲はドン・フェルダーとウォルッシュのツインギターがあってこそだ。 そりゃー、この曲をやってくれて嬉しくないわけない。 でも、でも…と思ってしまう。 で、また全員引っ込む。 みんな、「アレまだじゃん」って感じで拍手はやまない。 で、全員再度出てくる。 特徴的なギター、 キタ━━━((゚ (∀゚ (゚∀゚) ゚∀) ゚))━━━!!!! 『Rocky Mountain Way』 ウォルッシュのソロ。 黄色いヘルメットかぶってノリノリ。 ああ、これジョーのノリだよなー。 で、ヘルメットにカメラが仕込んであって、いろんなことやるやる。 (あれ?この曲だったっけ?)ジョーはイイわー サービス満点。 で、ドン・ヘンリーのソロから『All She Wants To Do Is Dance』 この曲、なにがビックリしたかって、グレンのダンス(笑) もう、踊りっぱなし。 体力、凄いです。 で、また全員引っ込む。 当然、「アレ、まだだよねー」とファンは拍手止めない。 ここで帰る人も多数いたが、もったいない。 で、再々度登場。 「今日は本当にありがとう。古いナンバーなんだけど聴いて欲しい」 と、グレン。 『Take It Easy』 やっぱ、これこれー。 これがないとね。 で、一旦ライトが落ちピアノに当たる。 グレンが静かに弾き出す。 『Desperado』 ただ感動。 ずーっと口ずさんでました。 最後にドン・ヘンリーがマイクを向けてきて皆で合唱「You Better Let Somebody Love You~♪」 前回の来日時と同じ。 Encore 1 23.Hotel Calfornia Encore 2 24.Rocky Mountain Way 25.All She Wants To Do Is Dance Encore 3 26.Take It Easy 27.Desperado ドン・ヘンリー、かなり太ってました。 パンフの写真は修整か?って思うくらい。 スティックさばきも怪しかった。 他の3人がいい感じだったので余計に目立ってました。 ここにマイズナーが居たら、『Hearts On Fire』をはにかみながら歌ってくれただろうなあ、とかいろいろ思うことも。 グレンもマイズナーを思っていたようで、『Take It To The Limit』の時にも「ランディといっしょに作った曲なんだけど、今日はボクが唄うよ」と言ったり。ドン・フェルダーもしかり。久しぶりに「エアボーン」引っ張り出して聴いてしまいました。彼のスライドギターがあれば、演奏曲目も変わっただろうなあと。次の大阪も同じ曲になるかもしれないけど、東京ドームの音響よりは少しはマシになるだろうか…って新譜の話はどうなんだ~
2004/10/31
コメント(2)
-
こんヴぁんわ
台風のさなか、因島に意地で渡ったぴけです。とりあえず生きてます。ま、生存報告しておきます。
2004/10/21
コメント(2)
-
今日の1枚…Celebrate Me Home
■Celebrate Me Home / Kenny Loggins(1977)こんヴぁんわ。どうも仕事でバタバタしてるのとかで、楽天の日記更新は疎かに。その割にはまめにミクシィは更新してるが。こっちはレビューベースにしてるので、なかなか書く時間がないのもある(いいわけ)まあ、オープンな場所とクローズされた場所と使い分けてゆこう。こちらには書きにくいこともある。この間見たニュースで、日本IBMが営業部門の個人用デスクを廃止しだしたということがのっていた。(asahi.com、9月9日)自分専用の机はありません――。日本IBMは、営業部門の職場をそんな環境に転換し始めた。つい長居しがちな自分の「城」を廃止することで、顧客と社外で接する時間を増やしてもらうのが狙いだが、不必要な紙資料を減らす効果もあるという。 今年1月から試行し、9月から本格移行したのは箱崎事業所(東京都中央区)のメーカー担当の営業部門約900人が入る14階の1室。空間を区切る壁のない室内には4~6人掛けのテーブルが並ぶが、全部で300~400人分しかない。 ここで仕事をする場合は、どの机を使ってもよい。各テーブルに設置された電源とLANケーブルに、自分のノートパソコンを接続する。仕事を終えたら、広げた資料は必ず片づけ、保存する資料は各個人のロッカーに収納する。 試行期間の社員の反応は「顧客への訪問時間が約4割増」「社員間の会話が活発になった」などが多く、同社は05年末までに、箱崎事業所内にいる全営業担当者約5000人にこの仕組みを広げる。 「やはり、自分だけの空間があった方が……」という声もある。だが同社幹部は「仕事がないのに意味もなくパソコンに向かって座る時間が減るはずだ」と話している。 AS/400とかIBMの機器を仕事で使用している関係から、このことは聞いていたんだけど、自分ならちょと違和感あるなと。「落ち着かない」というようなことを、担当の方は言っていたが、まあ、そうだなあと。"自分(専用)の居場所がない"まあ、営業職で外に出てることが多いからといえば、それもそうだが。でも、自分の帰る場所が決まってないというのはどうも…帰る家に明かりがともっているのと、真っ暗な中に変えるのではやはり気持ち的に前者の方がいい。疲れ果てたときなど、その明かりに暖かさを感じることもある。我が家からこぼれる明かりを目指して家路をたどる、美しい景色じゃないか。そこは精神的、物理的に自分が落ち着ける場所だ。いかにも日本的な考えなのかもしれないが、出張から帰ってきて自分の机で誰かが仕事をしてたら、「どいてくれよ」と思ってしまう。自分の居場所があると安心する。いかに自分の仕事が会社の利益をかせぐメインであり、そこに存在の必要性を見出していても、身を置く場所がないとやはり安息はない。”グローバルスタンダード”というアメリカの基準が日本にも当てはめられるかといわれると否だと思う。日本人はウェットな生き物だし。生態として体を置く場所は必要だ。ドライな関係ばかりでは、高温多湿な国に生まれ、それを受け入れてきた人々には苦しいのではないだろうか。携帯メールが流行ったのは、そういうところも関係してると思う。近すぎず、遠すぎず。そういうしっとりとした関係が日本人には必要だ。この秋雨のように。今日は一日の最後にケニー・ロギンスを久しぶりに。アル・クーパーやニール・ヤング等この年代のものを最近よく聴く。これも自分の中のウェットな部分か。華やかさは少し足りないけど、いい音楽を聴かせてくれたケニー。今は家族を中心とした悠々自適な生活で、自分のやりたい音楽だけをやっている。華やかな表舞台に現れることはもうないだろうが、充足した生活だろう。比較的最近だが、「ティガームービー プーさんの贈りもの」という映画のエンディングの歌も暖かくてよかったな。ケニーの名をあげるとすぐにトップガンやフットルースを言われる方も多いが、70年代の作品こそケニーらしい。って、以前にケニーの作品のレビューを書いたときにも言ったか。ロギンス&メッシーナの頃のインプロビゼーションとは違ったスマートな魅力がこの頃の作品にはある。プロデューサー、ボブ・ジェイムスの影響か。深夜2時過ぎに一人聴く、「Celebrate Me Home」爽やかで、優しさに満ちたこの曲、これがケニーの魅力だな。もう帰って来ない、過去の”自分の日々”を思い出す。音楽には記憶と密接に結びつく作用があるが、この曲では特にそう思う。 1.Lady Luck 2.If You Be Wise 3.I Believe in Love 4.Set It Free 5.Why Do People Lie 6.Enter My Dream 7.I've Got the Melody (Deep in My Heart) 8.Celebrate Me Home 9.Daddy's Back10.You Don't Know Meさて、明日は日帰り出張か…
2004/09/26
コメント(2)
-
今日の1枚…Live In Paris Vol.1
■Live In Paris Vol.1/ Bill Evans Trio(Feb.6.1972)こんヴぁんわ。エイベックスとソニーがCCCD運用の方針を変更との事。エイベックス・プレスリリース もう一丁ソニーミュージックも追従の方向音楽ファンを泥棒扱いするCCCDがなくなるのはいいことだと思う。だが、逆の見方をすると、『だから輸入盤ではなく国内盤を買いなさい』という流れがさらに加速することになるのか。なんら明確な形での動きはないが、徐々に外堀から埋められているような。iーTuneが国内に参入して暴れまわったら、この障壁はどう変化するだろうか。自分の力でできることからやっていこう。日本の知財推進計画とは”産業界の都合を知的弱者である国民に押し付けていこう”ということに他ならないのでは。馬鹿にするなと怒鳴ってやりたい。文化庁のパブコメ募集私も提出するつもりで、書いてます。感情的になりすぎずに、自分の言葉で書いてみてください。自分の意見を。さて、ここのところラストトリオの音源ばかり聴いていたが、ゴメス、モレルのトリオでも。このトリオは世間的な評価が一番低いトリオかも。最終的にモレルがカナダ人女性と結婚し、ツアーに出れなくなったことでこのトリオは終わりを告げる。もともとエヴァンスは自らが共演者に求めることというのがあまり無く、演奏について相談を受けても『それでいい』としか答えなかったそうで。JAZZはこだわりのある演奏者が多いが、彼はそうではなかったらしい。だから、結婚という機会が無ければこのトリオはまだ後まで続いていたかも。はっきりいうとモレルの評価は私の中では高くは無い。ゴメスも。ジョンソンと同質なエレクトリックな音だが、似て非なるもの。想像性豊かなジョンソンのベースと比べると、ゴメスは劣る。この音源、私が持っているのは日本のNORMAが出したもの。ノーマは"24bit”とうたっているが、これは怪しい。他にもNormaのCDを持っているが、CDDBに接続してディスク情報を取得したら、West Windという別レーベルの曲情報があがってきた。このアルバムも元のCDを単純にコピーしたものではないだろうか。このときエヴァンスは肝臓障害からくる手の腫れに悩まされていたらしい。この腫れは、その後もずっと亡くなるまで彼を悩ますことになる。先ずはフランス語でのメンバー紹介。エヴァンスのゆったりとしたイントロから始まる『Re: Person I Knew』どうもゴメスの電気的な音が合わないように感じる。エヴァンスはひたすら自己表現の世界に入っている。それを引き出すという意味では、ゴメスは最良か。『Turn Out The Stars』はいつものフレーズで。音の洪水のようなイントロから、最後の瞬間的なブレイクまで。ラストトリオの壮絶な演奏ばかりを聴いてきた数日の後に聴くには、丁度いいかも。悪く言うと手クセのオンパレードかも。イマジネーションが一番衰退していた頃の演奏だとも言える。『Gloria's Step』のようなアップテンポな演奏ではモレルの遅れが目立つように感じる。これも、ラバーバラの推進力と比較してだが。『Two Lonely People』は、もう少し緊張感が欲しい。もう少しそれがあれば、曲の終わり部分も感動的になったものを。綺麗なモルデントから始まる『Waltz For Debby』この装飾はいい。モレルも充分にドライブする。『What Are You Doing The Rest Of Your Life』残された人生に何をするか…70年代に何度も取り上げたナンバーだ。Bill Evans(p)Eddie Gomez(b)Marty Morrell(dr)1.Introduction2.Re: Person I Knew3.Turn Out The Stars4.Gloria's Step5.Two Lonely People6.Waltz For Debby7.What Are You Doing書いてる間にウチのHPの足跡をたどって他にも行ってみたが、『ホームページ500アクセスに挑戦しています』って???なんかワケわかんない人多いな…まあ、私の目に見えないところで頑張っていてください。
2004/09/18
コメント(3)
-
再考CONSECRATION / LAST WALTS 3
連日の神戸行きもおわり。来週の出張まで少し余裕ができた。今週末は休めるか。9月15日、毎年この日の前後には現存する最後のエヴァンスの演奏をリピートして聴く。バートヘンニンゲンでの彼の誕生日のものや、ロニースコッツでのものも。Consecration(VICJ-61001~8)The Last Waltz(VICJ-60656~63)Bill Evans(p)Marc Johnson(b)Joe LaBarbera(dr)Recorded at Keystone Korner ,San Francisco ,August31-September7 1980ここにいたる流れとしては5月下旬から6月上旬にかけてのヴィレッジヴァンガード、7月下旬から8月にかけてのロンドン、ロニースコッツの2週間公演の、ベルギー、ノルウェー、イタリア、スペイン、ドイツのヨーロッパツアーがある。今日は2枚からランダムに聴いてみた。muse cafeさんのおっしゃってた、最終日の34Skidooとか。この曲は難しい。ポリフォニックに変化していて、それがコントロール力の低下から来るものだと感じる部分もある。ラバーバラがエヴァンスの持つスピード感を引き出している。ラバーバラの音の当て方がいい。両極端を強調し、その間の鍵盤を激しく行き来する。テーマをリハーモナイズする手法は変わらない。この最後の音源は今までもう何度も聴いているが、いまだに新しい発見がある。そしてここから始まる、来るべき彼の姿を見たかったとも思う…今日という日の最後に『Danny Boy』を。ひとりぼっちのエヴァンス。盟友ラファロを失い、涙をこらえてひとりたたずむかのような演奏”充分を超える孤独な演奏”と評したのは誰だったか。その孤独の中にも彼の優しさが見える気がする。指先に集中して、想いの全てをそこから放つかのような…それは愛であり、悲しみであり、人間としての複雑な感情が入り混じっている。彼にはマイルスのような帝王としてのカリスマ性やパーカーのような人間的なエピソードはほとんどない。 だが、それは彼が人間的につまらないということの証ではない。 彼の個性は音楽の中にある。 明確な形で。 『 どんな感情の呟きでも鍵盤に移せる 』 - Bill Evans 彼を知りたいと思う。 だから彼の音を求め、これからも聴いてゆく。なりたい自分になれるように。彼が信ずる音楽に忠実であろうとしたように、自分もそうありたい。 1980年9月15日、ルイジアナ州バトン・ルージュにて永眠享年51歳精神論をぶつのは好きじゃないんだが、やはり彼の音に対しては冷静になれないなあ。
2004/09/15
コメント(0)
-
再考CONSECRATION / LAST WALTS 2
すっかりなくなったと思っていたんだけど、自動巡回してる人ってまだいるのかな。ご苦労様。カウンターの数ばかり気にしてても仕方がなかろうに…今週は土日とも出勤で神戸まで通いに。遅くなりそうなので泊まった方が楽なのだが。1日くらい、泊まるかな。先週末は久しぶりにLPを引っ張り出して、何枚か聴いてみた。さらにヤフオクで何枚も買っているので棚にはどんどんLPが。週末に聞いた音源エヴァンスのリーダー作でMPSサンプラー盤Portrait In JazzHomewoodThe Canadian Concert Of Bill Evansあとはトニースコットのリーダー作で、ラファロ、モチアンのものSung Herosなんかも。それと平行して、キーストンコーナーの音源を順番に。ディスコード、ミスタッチ…『駄作なし』といわれたエヴァンスらしくないかもしれないが、その彼が見せる”死への情熱”が心を捉えて離してくれない。オーデュエンスのためでなく、ひたすら自分のために弾くエヴァンス。その姿はあの輝かしいファーストトリオの頃から変わらない。1961年の6月のビレッジヴァンガードでもオーディエンスは必ずしも彼の音に集中してはいない。皿の音をガチャガチャいわせるウエイター。馬鹿笑いするオヤジ・・・そんな中でも自分たちの音に集中して、すばらしい演奏を繰り広げた3人。そのスタイルは支えあう2人が違えども変わらない。聴衆の存在は彼らの中ではあってないものだったのではないだろうか。晩年のグールトが好んだスタイルを、ライブハウスにいながらにして身につけていたのか。あの独特な、ピアノの中に消え入りそうなスタイルで自らの音を聴きながら。音楽は彼にとって、自己を成立させるための唯一の手段だったのだろうか。だからこそあそこまで壮絶だったのではないだろうか。それは破滅といえるのか融合といえるのか私には未だわからない。ただ、この感情的に無防備な音が好きだ。この音源についてはどうも冷静に聴けないなあ。
2004/09/07
コメント(0)
-
再考CONSECRATION / LAST WALTS
高校時代、いっしょにインターハイを目指して戦った戦友から、約10年ぶりの電話。会わなかった時間を感じさせずに昔のような会話がすぐに始まる。最後まで果たせなかった夢。あと少し、足りなかった力。ほんの2,3会話を交わすだけでお互いのすごして来た時間がわかる。年内の再会を約束して、電話を終わる。9月…心をやさしく包んでくれる毛布が欲しくなる季節までもうすぐ。毎年9月になるとエヴァンスの命日を思い出す。習っていたピアノの先生が悲しんでたことや、いろいろと…なんの役にも立たないセンチメンタリズムを。今夜は最後の記録、キーストンコーナーでの音源を。短くも一瞬のうちに昇華したラストトリオのドキュメント。壮絶なる彼の最後の記録。8枚組BOXSET2つから、1980年8月31日の演奏から順番に並び替えて聴く。死を覚悟し、医者の診察を拒否してものめりこんだ、ラストトリオとの演奏。生々しい情感にあふれたピアノ…楽器をコントロールする力は落ちているとも感じるが、その生々しさが心を捉えて離さない。各声部間のコントロールがすばらしい。ウォーキングしているかのようなパートもある。きれいなスケールでプレイして、瞬間的な判断でブレイクさせる。どこでブレイクさせても成立できるように考えて弾いているのだろうか。衝動的なアプローチから瞬間的にそこまでもっていけるものか…そこに絡むクリエイティブなベースに、ぐいぐいとドライブさせてゆくドラム。彼を崇拝する二人のプレイヤーが彼に与える力も聞き逃せない。マーク・ジョンソンにとってこのトリオから得たものは大きかっただろう。完全な手放しで評価するわけではなく、その複雑な展開性から演奏のクオリティはあがったけど、音楽の質的に言うと下がったものもある。徐々にイマジネーションはきらめきの度合いが薄れ、最終日にはもう何もなくなってしまう。途中、もがき苦しむようなそれでも演奏を止めなかった。その末にあるものは彼なりの敗北宣言であったのだろうか。燃え尽きて、テクニックもとうに失せ、精神力だけで最後の一滴まで搾り出そうとするかのような演奏。彼のピアノは私の心を豊かにしてくれる。そして、ほんの少し優しくなれるような気がする。
2004/09/02
コメント(1)
-
眼光紙背に徹す…2
こんヴぁんわ。いろいろありで日記はしばらくのご無沙汰でした。その間も来て下さっていた方、すいませんね。いろいろとモチベーションが下がったり、多忙だったりで。おかげでいろいろと見つめなおす時間が出来ました。何事にも絶対はない。これは私の常々の行動の根底にあるもののひとつだが、そうもいかないときもある。進みたい自分、進めない自分…今という時間をいくつもつなぎ合わせてゆくと、先が見えてくるのだろうか。この15日はエヴァンスの75回目の誕生日だった。もし・・・もしが許されるならば、今の彼の演奏を聴きたかった。もう、とうにピークを過ぎ去った演奏であっただろう。彼自身が一番嫌った部類の演奏であったかもしれない。それでも、聴いてみたかった。自らのためだけに弾く、彼の姿を。かつてのテクニックを失った表現者としての姿がそこにはあるのかもしれないが。それでも・・・今月はいろいろCDを買い込んだ。ロック系ではRUSHの新譜を。JAZZではブルーノートが安かったので10枚ほど。あとはケイコ・リーのDVDがあったのでそれも。エルヴィンの追悼盤、パド・パウエル、デックス、ペッパー…数えてみたら30枚ほど。俗に言う『大人買い』かな?亞さん からいただいた本『1リットルの涙』ようやく読めた。亞さんに感謝感謝!この前の日記にも書いたが、自分が彼女の年の頃に、ここまでいろいろ考えていただろうか・・・10代の頃は自分の可能性が無限にあると錯覚していた。『私は何のために生きているんだろうか』この言葉、彼女が長くは生きられないことを自覚しての言葉だったのだろうか。今の自分に問われても、自分自身納得がいく答えは出せない。この本は『脊髄小脳変性症』という病に冒された木藤亜也さんの日記だ。映画化も決定しているそうだ。この9月に彼女の地元、名古屋で先行ロードショーのあと10月から全国で。単館上映ではなくロードショーと。最初からアンサーが与えられてるものではなく、自分で答えを出さなくてはならないものはなかなかヒットするというレベルまでは行かないかもしれないが、たまには何か”SOMETHING”を考えてもいいのではないだろうか。いや、考えないと人間どんどんアフォになる。話を本に戻そう。15歳、中学3年生で病気を発病した亜也さんは、16歳のときに自らの病気のことを知る。運動神経を支配する小脳の細胞が何者かによって働きが悪くなってくる病気で、100年位前に始めて見つかった病気だということを。彼女や母親の潮香さんたちは、その今できることを受け入れてがんばってゆく。今まで出来たことが出来なくなると事を受け入れるのは、言葉で言うほど簡単なことではないだろう。重いものが持てないなら、やめるのではなく、いる部分だけもって学校に行こう。通学が苦ならば、今度は母親が。お母さんも、出来ないことを受け入れて、そのできる範囲でできることを精一杯やるようにと決して過保護ではなく、彼女を見守ってゆく。長くなるが、一部抜粋____________________________________________________________________________________________________________________________先天的に目や体の不自由な人と違って、過去におやれたことがどうしても頭から離れない。どうして出来ないかと悩みも大きいし、感情が先だってしまう。だから、いつも精神との戦いから始まる。はたから見ていると機械的にラジオ体操しているような訓練も、実は精神との戦い、鍛錬だよ。亜也、結果はどうあろうと、今を悔いなく生きてこそ将来があるんじゃないかと思うよ。亜也はよく泣いているよく泣いている。そしてそんな亜也を見ているとかわいそうでならない。でも、現実、今置かれている立場をきちんと理解して、これからの亜也の人生を充実させていかないと。足を地面につけた生き方が、永久にできなくなるよ。お母さんや弟妹は、あなたがどうしてもできないことには、惜しみなく手を貸してあげる。でも、意見を言ったり、けんかをする時は、ポンポン言うでしょ。あれは亜也が人間的には何も違ってはいない普通の子であり姉であると思っているからなのよ。だから、精神を強くする愛の言葉と受けとめるのよ。他人にグサッとするようなことを言われても、耐えていけるように、これも訓練なんだよ。____________________________________________________________________________________________________________________________残酷なことかもしれないが、受け入れなければいけないことを、お母さんはちゃんと伝え、亜也さんはきちんと受けとめている。これ以上のことは誰にも出来ない。『Nobody Does It Better』自分の血を分けた母だからこそいえる言葉だ。そして亜也さんは精一杯、"ベストをつくした"といえるようにがんばる。健常者と対等に勝負できるものを見つけようとして。物語なら、ここでハッピーエンドの大団円に向かって進んでゆくのだが、現実は…彼女は可能性をひとつずつ閉じてゆく辛い作業に挑まなくてはならない。なんと悲しいことよ。現実の残酷さに、なんともいえない虚脱感のようなものを感じさえもする。考えないと生きて行けないからと考えようとするも、その可能性すら閉じられてゆく。"自分で考えて”養護学校行きを決めたかったと。周りの何気ない言葉からも考えることを見つける彼女の感覚はすばらしい。障害を抱えたから発達したのではなく、それまでの彼女の生きてきた道がそれをさせたのだろう。そして自分の病気にはまだ治療法はないという残酷な現実を受け入れる。こう、言葉だけで書くと簡単な1文で終わってしまうが、最後の可能性を閉じる言葉だ。それでも彼女はあきらめない。自分にできることは何かを考え、そして精一杯生きてゆく。『お母さん、もう歩けない。ものにつかまっても、立つことができなくなりました』そして、20歳で彼女の日記は突如終わる。この本の題ともなった彼女の言葉__________________________________________________________________________________________私は生れ変わりました。身障者であっても知能は健常者と同じであると思っていました。着実に1段づつ上った階段を、踏みはずして下まで転げ落ちた、そんな感じです。先生も友達もみな健康です。悲しいけどこの差はどうしようもありません。私は東高を去ります。(注:彼女が1年間だけ通った高校。その後養護学校に転校)わたしは身障者という重い荷物を、ひとりでしょって生きていきます。こう決断を下すのに、少なくとも一リットルの涙が必要だったし、これからは、もっともっといると思います。__________________________________________________________________________________________人は何か外的なきっかけがあれば変われるものだと思う。変わることはなかなか難しいことだが。この、亜也さんの日記から何を得るか。答えはその読んだ人の数だけあると思う。バラの つぼみは早く摘め時は過ぎゆく今日 咲き誇る花も明日は枯れる“今を生きろ” 我々は死ぬ運命なのだ今を生きろ 若者たちよ すばらしい人生をつかむのだSeize the day
2004/08/23
コメント(3)
-
つれづれなるままに…
こんヴぁんわ。この前、ケースを変えたときにCPUファンも変えたのだが、そのファンの効果がないくらいにCPU温度が上がっていろいろと悩んでたのだが、グリスを塗りなおして再度セットしたら、約30度で安定。今まで60度を越えていたのは自分の取り付けがまずかったせいと。CANOPUSのFirebird R7S、結構いいです。2年前の7月発売のファンなので今なら1,000円程度でショップに売っている。私のPen4 2.6Cにはこれくらいで十分かな。「もう少しだけ冷やしたい」って人にはこれでいいだろう。あまり冷却ばかり追及するとノイズが気になってくるし、チャット以外にもPCで音楽を聴くこともあるので。グラフィックボードはRADION9600PROの256MB。ゲームなんて全然しないので宝の持ち腐れ。以前は仕事で会社のサーバーにもつないだりしてたけど、今は接続してないのであまりスペックは必要ないのだが。ATA133のボードを増設してHDDは6本駆け、Sirial-ATA、SCSIも併用。マザボがGIGABYTEのエントリーモデル的なものなので、Sirialをつなげると排他制御になり、IDEをひとつ殺さないといけないのが難点だが。サッカー日本代表、アジアカップ優勝。中国人の反日サポーターが取り上げられているが、ユーロ2000のクロアチアVSユーゴスラビアの試合と比べるとまだマシ。まあ、比較の対象にはならないが。その背景も違うし。クロアチアはザグレブ。マクシミル・スタジアム。プラーヴィ(ユーゴの選手)はこの国にとってはこれ以上はないほどの”悪者”その中での2-2の引き分け。中心人物はもちろん、ピクシー。先日、来日したレアル・マドリードのフォワードだったこともある、ミヤトビッチも。『ヘイ、ミヤト。お前のペ●スだって俺はくわえることが出来るぜ』(自主規制)なんて応援歌があるくらい、愛された男。まあ、セルビア語は世界で一番汚い言葉だし・・・セルビア民兵によるコソボの虐殺は確かに事実だ。でも、それがNATOの空爆後に行われたことも事実。”虐殺を止めるための空爆”という大義名分は成り立ってなかったのだ。拡大するECに、拠点を持って対応したかったアメリカのエゴか。作られた悪、セルビア人はそれでも自分たちの民族に誇りを持っている。その彼らが見せる文化としてのサッカーが私は好きだ。亞さんから2冊の本をいただいた。『命のハードル』と『1リットルの涙』ありがとうございます。仕事でばたばたしたりいろいろなことでモチベーションが下がりがちなのだが、明日感想を書いてみるか・・・自分が16の頃。こんなにしっかりと物事を考えていただろうか。ただぼんやりと、モラトリアムの闇を見るともなしに眺めていただけ。ウチはある意味火宅であった。その中で生まれたものもあり、自らの起こした事で永遠に失ったものもありで。そんないろいろを経験して自分は変わった。人は何か外的なきっかけがあれば変われるものだと思う。変わることはなかなか難しいことだが。この本はそんな背中を押す手になる本かな。亜也さんのストレートな感情を読み進むうちにそう感じた。『私は何のために生きているの?』亜也さんだけでなく、誰もが自分に求める答えだ。「お金のためだけではない」とか、「家族のため」という答えはすぐに出てくるが、本質的な答えはすぐには出てこない。『なんのために生きたか?』なら答えは出そうだが。私は日々を生きる。そういえる今に感謝。
2004/08/09
コメント(1)
-
今日の1枚・・・Closing Time
■Closing Time/Tom Waits(1973)こんヴぁんわ。著作権法改定による輸入CD規制に断固反対のピケです。自分が忘れないためにも何度も繰り返そう。iPod mini 、出たと思ったら即完売。買おうかどうしようか迷っているのだが、通勤に長時間かかるわけでもなし、モバイルHDDとしてはノート用の80GBを使っているので特にどうしてもってことはない。新しい東芝のコスミオってノートも欲しいし。AVノートの考え方がソニーとはまた違うところにあるようで。他にも今のメインスピーカー、NS1000Mのパーツ取り用にもう1セット程度のいいのを買おうかと。探してると、ウーファーを変えたばかりというコンディションのを見つけた。これもチェックだな。JBL4312Mk2とかも気になるが、自分の好みYAMAHAで行きたい。JAZZ=JBLというのもよく聞くが、YAMAHAでもいいじゃん。アンプはONKYOでもいいじゃん。ハーマンやOTTOを使ってきたけど今はこれ。ピュアオーディオマニアからは相手にされないメーカーだけど、ハイエンド機メーカーばかりじゃオーディオの未来はない。こういう普及価格帯でがんばるメーカーは応援したい。そのONKYOが久しぶりにピュアオーディオアンプとCDプレーヤーを作った。スピーカードライブ能力がいいという好意的な評価もあるし、ちょっと気になる。いまさらCD専用機ってのもいいと思う。(変な言い方)CDの実力を今の技術で引き出してみよう、贅を尽くすでもなくエントリーユーザーにも買える価格帯でという姿勢がいい。機会があれば日本橋あたりで試聴してみたい。先日、たまたまつけたNHKの教育TVで平忠彦さんが。もう10年近く見てなかったがずいぶん老けたなあ。彼が現役を引退して、筑波サーキットに帰ったあの日…皆で暖かく「おかえりなさい」と迎えた日のことが。当時、同じ場所で走っていた仲間の大半はもう降りてしまった。若くして鬼籍に入ったやつもいるし。つまらないミスで。自分ももう降りてしまったが。今はあそこに戻りたいという欲望もなくなった。今週も週末はゆっくり休み。…でも会社からの問い合わせは何件も入るが(汗)昨日は昼間、台風で風雨がきついので、家でLPのリッピング作業を。また、ダブリ買いを数枚発見(涙)まあ、音源は同じでもモノラル盤だったり、高音質盤だったりなのでOKとしよう。望外のものとは別に、ダブリ音源をわざと買ったものも数枚。20bitK2シリーズのCDとか。カルロス・クライバーも鬼籍に入られたとか。近年はクラシックの最前線からは離れていたので、どうだかは知らないのだが、あの魅せる指揮がもう見れないのは残念。酔いどれ詩人、トム・ウェイツ。真夜中の詩人。昔大好きだった、ARBの凌さんが最後のツアーで歌った『I Wish I Was In New Orleans』トム・ウェイツを聴くと、昔ARBキッズだった頃の自分を思い出す。カットアップするバロウズも。らもさんもトムが好きだったなあ。イーグルスのものも有名な『Ol' 55』このトムのものがオリジナルだ。声の渋さがなんともいえない。うめくようなヴォーカル(笑)水溜りでおぼれて死んでしまいそうな男の歌う、心の声。恋なんて憂鬱だとうそぶいて歌う『I Hope That I Don't Fall in Love With You』でも、最後は君に惚れたと吐露する、情けない男。いやいやかっこいい。男にはその心情がわかる。長い月日がたって昔の恋人に電話をかける『Martha』なんともいえない歌だ。『Grapefruit Moon』のメロディの美しいことよ。言葉にするとくさくてかっこ悪いけど、この音はいい。『Closing Time』そのタイトルが似合う曲。音楽を言葉に置き換えることなどできないなと。自分のつたない表現力ではこの曲を言葉にすることは出来ない。01.Ol' 5502.I Hope That I Don't Fall in Love With You03.Virginia Avenue04.Old Shoes (& Picture Postcards)05.Midnight Lullaby06.Martha07.Rosie08.Lonely09.Ice Cream Man10.Little Trip to Heaven (On the Wings of Your Love)11.Grapefruit Moon12.Closing Timeさて、飲みに出かけるか。ぶらぶらと、夜の街へ。
2004/08/01
コメント(0)
-
今日の1枚・・・The Return of Art Pepper: The Complete Art Pepper Aladdin Recordings
■The Return of Art Pepper/Art Pepper(1956.8)こんヴぁんわ。さて、昨日の続きだが本当に高音質を求めるなら、今のPCの状況ではドライブは外付けのSCSIが一番。ATAPIだと信号ラインがすべてマザーボードに入ってしまうし、USBはさらにCPUパワーを食うため不安定なPC電源ではクオリティの高い電圧を保てない。ATAPIドライブを外付けにするキットはあるが、わざわざSCSIに変換してくれるものなんてなさそうだし。今のニーズを考えれば外付けケースはUSB2.0しかないのは仕方がない。レガシー機器はもう枯れ行く規格だという声もあるが、PCオーディオやFAではまだまだ必要。よって、YAMAHA CRW-F1のSCSIモデルをオークションで探すことにする。1年前に買っておけばよかったと後悔しきりだが。最高の音質にしたいと思っているわけではないが、手が届く範囲の費用でそれができるなら、もう少し上を目指してみようかと。久しぶりに聴いたLPで、CD盤では消えていたドラムのブラシの音がしっかりと出ていたのを再確認したところから音への欲求がふつふつと。なんにでもはまりやすいタチで、バイクや車にはまっていた頃はレースまでやってみたり。で、それと平行してレース仲間に進められたラジコンにはまって…自分では「違う!」というのだが、他人から見れば立派な”おたく”か。今日は体調が悪く半日仕事を休んでしまった。参加していたサッカーやバスケの社会人リーグを引退してからはどうも運動不足で、肩こりからの偏頭痛がひどい。なんとかせねば。破滅型天才、アート・ペッパー。ジャズ界きっての麻薬狂。この作品は彼の絶頂期の演奏。この年の春まで1年間ほど麻薬のために刑務所生活を送ったあとの復帰作だ。バックを支えるメンバーはウエストコーストコネクションといったところ。私の持っているこのCDはコンプリート盤と称して「コレクションズ」という盤から5曲追加したもの(11~15曲目)アートのサックスはその演奏の背景が見えるようでぞっとするときもある。”そこはかとない翳りのある情感”という評を見るが、いやいや。もっと深いものだと思う。01.Pepper Returns02.Broadway03.You Go to My Head04.Angel Wings05,Funny Blues06.Five More07.Minority08.Patricia09.Mambo de la Pinta10.Walkin' Out Blues11.Pepper Steak12.You're Driving Me Crazy13.Tenor Blooz14.Yardbird Suite15.Straight Life今、ニュースで中島らもさんの死去を知った。今夜は彼の分まで酒を飲もう。彼の作品は、らりってるままに書いたものや、ビート系のものまでほぼ全部読んだなあ。いまだ開かれないドア。不浄の左手、二度と迎えない朝。合掌
2004/07/27
コメント(4)
-
今日の1枚・・・The Amazing Bud Powell -The Scene Changes
■The Amazing Bud Powell -The Scene Changes/Bud Powell(1958)こんヴぁんわ。久しぶりの休みの週末をぐうたらと過ごしたピケです。久しぶりの休みなのでオークションで落札したLPをCDに焼く作業を行った。使用ソフトはONKYO CARRYON MUSIC VERSION 4.00使用メディアはVICTOR。太陽誘電製の63分メディアが今ではほとんど手に入らなくなってきているので仕方がなく。このメディア、気に入っていて最近はこれを使うことが多い。音楽を少しでもいい音質で聴こうと思うと低速での記録が欠かせないが、一般的に売られている高速対応メディアでは低速は切り捨てられていることが多く、少し高くなるがこういうメディアが必要になる。CDドライブのオーディオケーブルにも気を使って、ちゃんとシールドされたものを使っているが、今はPCアンプ経由で音を出しているのであまり意味がなくなった。わざわざM-AUDIO社のサウンドカードを入れているものの勿体無いな…DTMとかいろいろとする人も増えてきてるが、そもそもCDの音を原音と考えることには異議あり。ウォークマンの音をベースとして考えれば、それも普通なのかもしれないが、いい音っていうことが軽視され過ぎていると感じる。i-Podにしても「音楽が聴こえます」程度にしか思えないのだが…上に書いたメディアにしても、音楽用としての明確な規格はあるのだろうか?オレンジブックPart2以外には、自分が調べた限りではなかったが。音楽用としての規格をちゃんとした上で、セキュアCDなどを導入してちゃんと著作権料についても考えるというなら納得できるが、今のCCCDは納得できない。何度も言うが。普通のオーディオ機器でも再生できないかもしれないものを販売しておいて、売上が下がったといって泣き言を抜かして悪法を作って救済してもらうなんざ、何をかいわんや。ミリオンセラーを連発していたほんの数年前に短いわが世の春を謳歌して何もしてこなかったツケが今来ているだけのこと。CDプレーヤーは累計12億台、CD-ROMドライブは15億台出荷されているらしいが、その中で再生できる機器、出来ない機器があること、それを当然とすることはおかしい。そりゃ売れなくなって当然だ。DVD-AUDIO、SACD等いろんな高音質規格があるが、CDもまだまだ可能性がある、というか音は悪くなってきているように思う。ドライブ自体も高速・マルチ対応ばかりをウリにしているが、いい音で聴きたいと思ったら、バッファローやIOなんかのへなちょこドライブを使っていてはダメ。私はYAMAHAのCRW3200を使っているが、民生用でせいぜい許せるのはYAMAHAかPLEXTORくらいか。しかしこのYAMAHAも今は撤退しているかも。AudioMASTERいいと思うんだけどな。このドライブの外付けタイプが欲しいのだが探してみるか。いろいろと試してみたがPCの電源ユニットが近くにある限りノイズは減らない。電源から離してドライブを搭載しようとすると、今度は山のように搭載している磁気ドライブ群からのノイズが(汗)少しピアノを弾きに。即興で音をトップからずらして左手の和音をぶつけてみたり。指はまったく回らなくなったのと反比例して自分の音が出せるようになった気がする。動きはたどたどしくて、ある意味なみだが出るくらいだが。気分を入れ替えて音楽に。これは後期のパウエルトリオだ。1958年12月の録音。電気ショック療法で全てのイマジネーションを失ったといわれている、精神病院での療養のあと。この頃の作品は評価しない方も多い。抜け殻だと言って。事実、ミスタッチも散見されるだが最も売上的には成功した作品であろうことも事実。有名なナンバー『Cleopatra's Dream』から。日本人好みのマイナー調の美しい曲。最近、NHKで番組をやっている某女性ピアニスト(コンポーザーか?)が、この演奏を評して「どこが良いのかわからない」と言ったとか。寺島靖国氏もこのアルバムのアート・テイラーの演奏を評して「ブラシに哲学がない」といったらしいが、それはあくまで氏の個人的所感によるものなのだろう。私は2曲目の『Duid Deed』への入りの数音の重さが好きだ。ジャケどおりの全体的に青みがかったイメージを作り上げている。確かにどうも進行が単調な気もするな…まあ、そう悲観的に捉える必要もないとは思うが。人は変わりつづけるものであり、この変化も許容できる範囲かな。01.Cleopatra's Dream02.Duid Deed03.Down With It04.Danceland05,Borderick06.Crossin' The Channel07.Comin' Up08.Gettin' There09.The Scene Changes10.Comin' Up (Alternate Take)さあ、明日からもがんばるか。
2004/07/25
コメント(0)
-
今日の音楽・・・Alone(Again)
■Alone(Again) / Bill Evans(1975)こんヴぁんわ。3週間ぶりの休みの週末をぐうたらとすごしている、ピケです。舞踏家の大野一雄氏がまだ現役と知りびっくり。体の不自由を表現に上手く取り入れ、踊るその姿は一般的な踊りの概念を超越した存在だ。不自由であるからこそ出来る表現とは・・・氏の指先に宿るもの、どこのそれだけの力が眠っているのか。日常と乖離したその表現は一度見る価値はある。何も感じなければそれまでだが。仕事の山を越したと思ったら、トラブル発生。対応でここ数日はバタバタ。自分はこんなにもレベルの低い人間を部下に使っているのかとがっかり。おまけに私でなければ対応できない仕事も発生して、昨日は赤穂まで。オークションの落札代金を振込む時間が取れなかった(涙)ヤフオクで違法コピーのMP3を出品してるのを見た。こんなことをするやつがいるから、余計な法案が出来るのだ。さて、6月のCDの生産実績がRIAJ(社団法人 日本レコード協会)から発表になった。社団法人 日本レコード協会 で、前月までとの対比。大幅売れ行きダウン。邦楽:前年比73%(シングル:前年比68%・アルバム:前年比75%)累計でも前年比95%。。洋楽も売上の低落傾向に歯止めが利かない。さて、6月って何があったっけ…よーく考えてみよう。輸入権の創設以外に何か理由はあるだろうか。あれで頂点に達したヘビーリスナーの反感の結果がこれということではないだろうか。この結果をよーく考えて欲しい・・・さて、今日は久々にエヴァンス。『Alone』の続編だ。60年代の『Alone』から70年代のこのアルバムになって、音も演奏もずいぶん変わった気がする。レーベルの差、録音地の差、いろいろな条件の重なった結果か。これも先日LPで買いなおした。LPのほうがそこら辺の音の違いがよく表れている気がする。この作品ではYAMAHA製のピアノを弾いている。この年の9月、彼は父親になった。このアルバムはそういう充実した時間の中で作られた。誰だっけなYAMAHAの名物調律師・・・ここで気に入って、こののちグールトにもYAMAHAのピアノを勧めたんだっけ。いくつもの表情を見せる、『The Touch Of Your Lips』左手のインスピレーション…ソロの左手は普段と使い方が違うようだ。右手の装飾をするだけでなく、左の動きは大きい。別に単調だからクリシェを使うわけではないようだが。『Make Someone Happy』休みなく動き続ける右手に左手の出す音が、軽く当たる。時には左が先導して転調に入り、またあるときは右の動きにあわせる。テーマを幾重にも積み重ねて構築した、ジュール・スタインの劇中歌『People』この13分は必要な時間だ。このエヴァンスのメロディーの出し方が好きだ。右手の音を聴いて瞬時に左手を動かすのだろうか。綺麗な修辞…ひとりぼっちの彼の姿を思い描く。01.The Touch Of Your Lips02.In Your Own Sweet Way03.Make Someone Happy04.What Kind Of Fool Am I05.People明日は何しようかな…
2004/07/24
コメント(0)
-
今日の音楽・・・Bruckner Symphony No.8
■Bruckner Symphony No.8 / 朝比奈 隆 NHK交響楽団(2000)こんヴぁんわ。久しぶりの日記更新。山鉾巡行もおとついで終わり、祇園祭も一段落。おとついは、神幸祭のあるのを忘れてそれの真っ只中をぶらぶらとサンボアまで歩いたので人ごみでかなり汗をかいた。まあ、その分ぺルノーが美味しくなったと思っておこう。来週の還幸祭は会社のビルの横にお旅所があるので夕方は会社から見れる。ムカシはこの還幸祭で御神輿を担いだこともあったな。(通称”あとのまつり”。あとの祭りという言葉はこのお祭りが、17日の巡航に比べて寂しいところから来ている。ムカシは山鉾巡行は17日と24日に別れていたのだ。)今年も祇園祭は仕事で明け暮れた。例年通りに。今の仕事をしている限り、これは変わらないだろうな…毎日、いろんな音楽を聴いてはいるものの、日記を書く時間はなかなか取れない。毎日更新することに特に意味を感じてないので、まあいいか。今夜は久しぶりに朝比奈先生のブルックナーを。先生の大阪フィルや京響は何度か聴かせていただいた。近くにあるコンサートホールの柿落としとか。先生のブルックナーはいつも違う。そのスコアの書き込みが伺える。そもそもブルックナーは出版譜によってバラバラで同じものがないといえる。この解釈の幅が愛される理由であり、過小評価の理由でもある。ブルックナーの後期の交響曲は音の響きが美しい。この8番が一番好きだ。その中でもコーダが一番。この盛り上がりがなんともいえない。大音量で聴きたくなるなあ。もっといいシステムで。明日一日頑張れば、仕事もひと段落。今週は週末休めそうだし、頑張るか。
2004/07/19
コメント(0)
-
今日の音楽・・・Jazz At The Plaza Vol.1
■Jazz At The Plaza Vol.1 / Miles Davis(1958)こんヴぁんわ。昨日はは久しぶりに休めたピケです。昨日は朝からイノダへ。コーヒーだけ先ずは頼んで、後でビーフカツサンドを頼むつもりだったのだが、なんだか暑さで食欲がないのかそのまま帰宅。この前買った靴がちょっと合わなかったので、広げてもらいに持ってゆく。薄いイタルデザインのを買ったのが間違いだったかな。バーゲンで思わず新調したスーツに合わせたのだが。久しぶりに楽天を徘徊してみた。主に音楽系と思しきところを。自分のHPも見直して反省々。聴き方、感じるものなんざ人それぞれ。それを無理して言葉にしようとしているわけではなく、感じるままにまあぼちぼちと行こう。マイルスのリーダー作を取り上げるのは初めて。どうもまだよくわかりきれてないと感じるので書きづらい。理解してないと書けないわけではないのだが。マイルスとエヴァンス、この2人がともに歩んだ時間は1958年から59年にかけてのほんのわずかな時間だ。いや、それがわずかかそうでないかかは2人のみぞ知る、というところか。58年というその時期が重要なのかもしれない。期間ではなく。このアルバムはアルバム化を目的としたものではなく、もとはコロムビアレコードが主催したJAZZパーティーの実況録音。先ずは『Straight, No Chaser』から。帝王はテーマを取らない。トレーン、キャノンボールだけ。ソロのトップを取るがエヴァンスは最初の2,3コーラスでバッキングを止める。簡単な4ビートだがかすかに聞える音が耳を引く。トレーンのシーツオブサウンドがコンボを転進に導こうとする。最後はエヴァンスがしめる。『My Funny Valentine』ジミー・コブのドラムが少し重い。ミュートの中から現れるマイルス。メロディックに聴かせるようでもあり…全てが過ぎ去り過去形になった今だから、わかる部分もあり。エヴァンスの美しさは既にこの時期にも散見される。最後をまとめるは『Oleo』『Five』の萌芽が見える。エッジの立ったエヴァンスの音がいい01.Straight, No Chaser02.My Funny Valentine03.If I Were A Bell04.Oleo今日から祇園祭の歩行者天国が。明日はその人ごみの中を帰らないと・・・
2004/07/14
コメント(0)
-
今日の音楽・・・On The Border
■On The Border / Eagles(1974)こんヴぁんわ。今週来週と土日もずっと出勤のピケです。ストレスが溜まるとまたCDの衝動買いに走ってしまいそうだ。去年はなんだかんだで200枚くらいは購入したが、今年もそのレベルかも。節度を持って買っているつもりなのだが。私は基本的に音楽は流通しているものを購入する。エヴァンスの音源のみはオークションを利用するが。前にも書いたが、ファイル交換などもってのほか。レンタルも利用しない。こういうと『いやなヤツー』と一言で片付けられてしまいそうだが。これが普通だと自分では思っている。買うのはオリジナルアルバムを。ベスト盤は極力買わない。どうしてもオリジナルが手に入らないって時などは買うが。他の楽天のHPにもあったようだが、私のところにも怪しげなアクセスが。なんのデータ取りだ?『東計電算』先日、ずっと家に眠っていたスピーカーが知人に引き取られていった。もうここ6年ほどずっと眠ったままだったから、使ってもらえるならまあいいかと。基盤も腐ってないようで、まだ使えそうとのこと。今の国産スピーカーは退化してるといってもいいほどだから、20年ほどムカシのNS500でも十分だろう。さて、今日もイーグルスを。このアルバムは途中でプロデュースがシムジクに変わった。元のプロデューサー、グリン・ジョーンズはイーグルスのメロディアスな側面を引き出したがったようだが、メンバーは荒々しいロックに魅力を感じていたようだ。その方向性の違いから、プロデュースをビル・シムジクに変更する。この流れはその後のバーニー・リードンの離脱を生む原因ともなる。レコーディング中に参加していたドン・フェルダーがそのままメンバーに。アルバムのライナーには『イーグルスはウエストコーストに於いて現在も最爽快で、尚且つ、プログレッシヴなゴキゲンなロックグループなのだ!』と書かれている。なんだかなー(苦笑)しかも、”も最”なんて誤植もしてるし。まだまだワカゾーだったんだな、天辰保文。いきなりのドン・フェルダーのギターがいい『Already Gone』やっぱり今度の来日ではこのギターが聴けないってのはな…ジョー・ウォルッシュもいいんだが。ジョン・デビッド・サウザーとドン・ヘンリーの作品、『You Never Cry Like Lover』次作「One Of These Nights」に通じる部分がある音。少しにがーいラブソング。というかハッピーエンドはこのアルバムには歌われていない。過ぎ去ってしまった恋愛、言い換えると消え去ってしまったロックスピリッツを歌っている。スピリッツを失ったロックは二度と私には微笑みかけないと・・・グラム・パーソンズに捧げられた『My Man』バーニー・リードンらしいカントリーフレイバーあふれるいい曲だ。ドン・ヘンリーのリードヴォーカルにしては珍しくR&B色の強いナンバー『On The Border』ムカシ、ディーンというタバコのCMで使ってたのを耳にしたことのある『James Dean』ジャクソン・ブラウン、ジョン・デビッド・サウザー、グレン・フライの3人によるロックンロールナンバー。今度の来日公演では演奏されないだろうな、こういうのは。こういうノリノリも当時のウエストコーストの醍醐味だったと思うのだが。アル・パーキンスのスティールギターにのるハーモニーがいい、『Ol'55』元はトム・ウェイツの作品だ。これをイーグルスの作品と勘違いしてる人もいるが、前年にアルバム「クロージングタイム」でトムが歌っている。はにかんだ笑顔が印象的なランディ・マイズナーの作品『Is It True?』泥臭いドン・フェルダーのスライドギター、『Good Day In Hell』BTOに代表されるサザンロック的なフレイバーがちょと。この曲のギターで、グレンはドン・フェルダーに惚れ込んで、イーグルスへの参加を要請する。最後は初の全米ナンバーワンHIT『The Best Of My Love』ドン・ヘンリーが持つ”言葉に対する愛情”が一番よく出ている曲じゃないだろうか。終わってしまった恋愛の相手に対する愛情…そのまま”終わってしまったロックスピリット”に対象を置き換えられる。邦題、”至上の愛”とは言いえて妙。去っていった恋人を、何の打算もなしに今も愛する。「No Never」だということは判ってその上で。至上であり、永遠でもある愛情。マンションから飛び降りをしたどこかの俳優が吐く、言葉だけのラブアンドピースなどとは本質的に違う。01.Already Gone02.You Never Cry Like Lover03.Midnight Flyer04.My Man05.On The Border06.James Dean07.Ol'5508.Is It True?09.Good Day In Hell10.The Best Of My Love祇園祭の混雑が始まっているなあ・・・さて、明日もぼちぼちと・・・
2004/07/11
コメント(1)
-
今日の音楽・・・Eagles
■Eagles / Eagles(1972)こんヴぁんわ。おとついから忙しく気合モードのピケです。ちょと気になる話だが、日本輸入禁止のCDが出たそうな。“始まりは、いつもソニー”って謎工氏のコピーは笑った。昨日はなんとかイーグルスの東京公演のチケットゲット。席はどこになるかわからないが。仕事でずっと出先におり、ネット環境のないところなので知人に頼んだが、昼間はサイトにまったくアクセスできず。なんとか帰宅後に予約を取れて一安心。イーグルスは一番お気に入りの洋楽アーティストだ。エヴァンスとどちらが好きかと聞かれると、どちらかな・・・ザ・バーズやフライングブリトーといった先達のあとを受け、ウエストコーストという地域ロックの最後のランナーとして幕引きを受け持った。ウエストコーストの頽廃を自嘲気味に歌うホテルカリフォルニアばかりが代表として紹介されるけど、どうも違和感がある。文学青年、ドン・ヘンリーの詩はそう簡単に『いい』と言い切れるほど単純ではないと思うのだが。イーグルスは本国アメリカでも受け入れられたのと同様、もしくはそれ以上に嫌われた。彼らのアルバムに対する評価も、必ずしも好意的なものでなかったと記憶している。彼らがあまりにも卓越した存在で成功しすぎていたから嫌いだ、というような文を何かで読んだ記憶がある。”南カリフォルニアの典型的なロックバンド”というスタイル、地位は彼らにとってプラスにもマイナスにも作用したのか。イギリス文学に傾倒していたドン・ヘンリーとケルアック的人生観を持つグレン・フライ。その2人がメインになって作り上げた曲は、表面的な明るさの裏にいろいろな意味を持っていた。ホテル・カリフォルニアとは、それまで彼らが歌っていたものは幻想であり既に崩壊していたということの告白といえるだろう。その告白を終えたときから、彼らは解散への道を歩んでいたのだろう。今夜は久しぶりに彼らのファーストを聴いてみた。この14年ぶりのリユニオンに始まった、長いツアーの終わりを前にして。彼らの音楽は自分の記憶と密接に結びついている。今まで経験したことの様々なシーンを思い出す。高揚感のあとの挫折もあれば、万能感にあふれていた頃のこともあれば…今夜は疲れからか少し酔い過ぎているようだ。明日のためにそろそろ寝るか・・・
2004/07/08
コメント(2)
-
イーグルスが来る!
ずいぶん遅い話だが、このことを今日教えてもらって、一日ウキウキ。帰ってからも『First』から順番に聴いてみたり。おそらくイーグルスとしては最後の来日。これは行かないと後悔する。来日が決まっただけでこんなに浮かれてる自分ってなんだかなーとにかく、予定をあわせて東京も大阪も行くか。10月が待ち遠しい。でも、ドン・フェルダー首にしたままなんだよな~4人で来るのかな。とりあえず今日はそんなこんなで。
2004/07/05
コメント(1)
-
今日の音楽・・・Affinity
■Affinity / Bill Evans(1978)こんヴぁんわ。祇園祭関連の仕事で毎年この時期はバタバタ。ロクに落ち着いて音楽を聴いたりも出来やしない。毎年のことだが、7月はこんな調子だ。MPSサンプラー盤がようやく手元に届いた。箱入りの3枚組みLP、程度はまあいいほうか。56,000円…同時に落札した8,000円のLPが安く感じるな(笑)たった1曲のエヴァンスのために出す金額ではないかもしれないが、満足している。”エヴァンス馬鹿”OKOK。馬鹿になりきれるものを私は持っている。全世界で200枚限定とも言われているこのLP、今回手に入ったのは偶然。忙しくしていてしばらくチェックしていなかったヤフオクを久しぶりに見たところ、落札期限まであと1日のこのLPを見つけたのだ。即、1発目の入札、軽く50,000円上限で。。で、翌日の夜10時過ぎが期限だったので1時間くらい前からチェックしていたところ、狙っている人が2人、入札。で、残り10分を切ったところで再度入札して、あとは10分間が過ぎるまでの時間の長かったこと・・・リーダー作5枚、サイドメン約20枚いつになったら揃えられるかな。そう簡単に揃えられても面白くないが、まだ自分の知らないエヴァンスを聴いてみたいという願望のままに進んでみよう。このアルバム、今まで一度も取り上げてなかったか…一時はよく聴いていたのだが。カシオペアの野呂さんもこれをよく聞くということが、以前ジャズ批評誌の別冊に載っていたな。”イージーリスニング”と軽く見るジャズマニアもいるだろうが、こういうポップ路線もいい。”ハーモニカおじさん”トゥーツ・シールマンスとの共演。マーク・ジョンソン、エリオット・ジグムンドとの、この時期のレギュラートリオにマルチリード奏者ラリー・シュナイダーと、前述のハーモニカおじさんが加わる。トゥーツとの絡み、そこに加わる隠し味としてのシュナイダーが丁度いい。「ジャズ界でハーモニカを演奏するのは彼だけなんだ。」「そして私は彼が音楽とメロディに向ける全体的な感覚が大好きなんだ。彼がハーモニカでそれをどうやるのかは、きっと誰にも判らない。その答えを見つけようとするのはもうやめたよ」とはエヴァンスの科白だ。ポール・サイモンの曲『I Do It for Your Love』この曲は以前にポールと仕事をしたことがあるトゥーツが、この曲がエヴァンスのピアノに合うと考え選曲したもの。二人の濃密な時間…エヴァンスのアコースティックピアノがつむぐハーモニーは、ただただ綺麗だ。美しい。3曲目は再びアコースティックに戻って、スローに『This Is All I Ask』もう酒を飲まなきゃやってられない。部屋の照明を暗く。夜の闇の中にそのまま消え去ったかと思ったら、再び目の前に出現する二人。『Days of Wine and Roses』酒とバラの日々は過ぎてゆくこの杯に注いでくれどうぞなみなみ注がしておくれ花に嵐の例えもあるぞさよならだけが人生だテーマを吹くトゥーツのハーモニカは様々な感情を思い起こさせる。悲しみのようでもあり、愛のようでもあり、暖かな視線のようでもあり。トゥーツのあとを受け、ラリーが。このラリーが音を引き締めてくれている。甘さばかりでは酒は美味しくない。ソロイストのバックをコンピングで受けるエヴァンス。ただただ美しい。この美しさはどこから来るものだろうか。彼の胸を去来するものはなんだったのであろうか。これ以上は出来ないくらいに贅肉をそぎ落とした音で、ここまでのものが伝えられるのかという驚き。この音楽を聴けることに感謝。涙もろくなるのは酒のせいだけではない。まもなく滅びようとしている男の肉体が最後の輝きを放ちだしている。この音楽を伝えきれない自分の文のつたなさがもどかしい。ローズとそのエフェクターが効果的な『Other Side of Midnight (Noelle's Theme)』「カクテルピアノだね」と自嘲的に笑うシニカルなエヴァンスが見えるような。いやいや。エフェクターに頼るでもなし、ここまでスローなのにメロディを見失わせないこの表現の深さはなんともいえない。新たな『Blue in Green』の姿。フレーズの置き換えが彼のこの時期の重要な命題だったのか。『Body and Soul』この時間が永遠に続くかのような錯覚。永遠などハナからないと判っているはずなのに。この濃密な時間が永遠に続いて欲しいという願望か。01.I Do It for Your Love02.Sno' Peas03.This Is All I Ask04.Days of Wine and Roses05.Jesus' Last Ballad06.Tomato Kiss07.Other Side of Midnight (Noelle's Theme)08.Blue in Green09.Body and Soul”POP路線”と侮るなかれ。私はまだまだ彼の音を理解しきれてない。理解などとは無駄な努力か。聴くたびに違った側面が見えてくる。そのトリップをまだまだ感じたくて彼の音を探す。自分の中の深い部分からの願望として。
2004/07/04
コメント(0)
-
今日の音楽・・・The House Of Blue Lights
■The House Of Blue Lights / Eddie Costa Trioこんヴぁんわ。おとついはオークション落札でそのまま祝杯をあげ続けたピケです。(照)本当は今夜にも聴けるはずだったのだが、仕事が忙しかったため、商品の配達指定時間に家に帰れず。(号泣)再配達は週末かな・・・今週までは日曜も休めそうだし。来週からは祇園祭関連のイベントで土日も出勤。もうここ数年続く、毎年のことだが。祇園囃子の練習の音も聞こえてきて、京都はもう夏が近い。PCまわりはひとまず一段落か。6月はCDもオークションも買いすぎたので、7月は少し控えよう。私はファイル交換は使わない。欲しいものは正当な対価を払って買う。著作権に関して、アーティストの権利を守るのは当然のこと。レーベルが悪だからと、守らなくていいというものではない。だが、悪法には断固として反対する。アメリカで上院に提出された『誘発法』、まさかこのままのものが成立するとは思えないがアメリカ人って何を考えてるやら・・・エヴァンスのリーダー作コンプリートまであと5枚(サイドメンのものはまだ持ってないものが多い)そこに近づきたいという思いの中からこそ生まれてくる充足感。それは自己満足という名前でもあり人に誇るものでもないが、今回の1枚は本当にうれしい。MPSサンプラー盤に入っているエヴァンスの演奏は『Turn Out The Stars』ただ1曲のみだが、それでもうれしい。今週が仕事のヤマだが、早く週末にならないかな・・・エディ・コスタ。31歳で夭折したピアニストだ。ヴァブラフォンも演奏し、エヴァンスとの共演もある。このアルバムはその彼が残した最高傑作ではないだろうか。彼のピアノは絶品なのだが、レーベルは彼をヴァイブラフォン奏者としてサイドメンで起用したかったらしく、ピアノの作品はあまり残されていない。1957年、ダウンビート誌でピアノ・ヴァイブの両部門で新人賞を取ったときの台詞、「新人賞を貰ったことは、死神に接吻されたような気分だよ」その5年後の自動車事故で、その接吻は現実となる。先ずはアルバムタイトル『The House Of Blue Lights』から。重いイメージを連想させる左手の音。ずいぶんと重い音の作り方だ。中低音域を多用するからか。このパーカッシブなプレイが彼の持ち味なんだろうな。『My Funny Valentine』でも、そのパーカッシブなプレイは生きている。左手の使い方がキー。定番的なこの曲の演奏方法とは少し違うと感じる。ヴァイブ奏者なのでもう少し軽い音を作るのかと思ったが、そうではないようだ。『Diane』も左手のバッキングが印象的だ。ベースはウェンデル・マーシャル、ドラムはポール・モチアン。この2人との相性もいいようだ。特にマーシャルが。リズムのない中からテーマが突然出現するようなイメージがある『When I Fall In Love』ゆったりとした流れから最後はアップテンポに、『What's To Ya』01.The House Of Blue Lights02.My Funny Valentine03.Diane04.Annabelle05.When I Fall In Love06.What's To Ya少し余裕がないな…7月は下旬までこのまま過ぎて行ってしまいそうな。
2004/06/30
コメント(0)
-
今日の音楽・・・L.T.D Live At The Left Bank
こんヴぁんわ。今日、パーツ店で聞いて、ウチのマザーボードではシリアルATAは排他的接続になるということを確認。要はIDEをとるかシリアルATAを取るかしかこのマザボでは道がない。最上位機種ならもうひとつROMがついていて、排他しなくても制御できるそうなのだが。RAIDの板をもう1枚入れるかとも考えたが、PCIにこれ以上ボードを刺すと不安定になりそうだし。外付けのケースが余ってるのでそれに入れて、USBでつなぐか。とりあえず、ファンの音を消すために、マウントにラバーシールを入れ、ケースにはウレタンを張ってみた。これでだいぶん静かになったと思う。さて、日記を書いている間にうれしいことがひとつ。探していたLPをオークションでゲット!!もう、ずっと探していたものだったので非常にうれしい。一人大騒ぎで、祝杯なんかあげたりして。会社帰りにサンボアでひっかけてきたところなのに。いや、非常にうれしい。本当にうれしい。MPSサンプラー盤、56,000円也。杉田さんのディスコグラフィーには8万円超と書かれていたので、少しは安く手に入った。でも、また2chでさらし者になりそうな予感も・・・とりあえず、TOPページの『探してます』からは外しておこう。今日買ったデックスのレビューを書こうと思ったのだが、祝杯でヘロヘロなので書けるかどうか。とりあえず、一旦アップしておこう。書けるようだったらまたのちほど。
2004/06/28
コメント(2)
-
今日の音楽・・・Secret Messages
■Secret Messages / Electric Light Orchestra(1983)こんヴぁんわ。再セットついでにATA133のHDDをひとつ、シリアルATAに換装。ページングファイルの設定やレジストリを変えたのでこれでもう少し早くなるだろう。HDDの容量は全部あわせて700GB以上はあるな。もともと刺していたIDE0のHDDが認識しなくなったのだが、BIOSを適当にいじっても解決せず。来週以降にマニュアルをちゃんと読みながらやろう。あわせて地上派デジタルも対応するかと考え中。放送のコピー制御なんてバカなことをやっているから、それに対応できるようにしないと。おそらくはDLLの書き換えで対応できると思うのだが、ソースコードをスターリングで調べてってのも面倒だし。なんか”悪い使い方も出来ますよ”デコーダーを買って対応するかなあ。民放はCMがあるからただで見れるのだ。ここら辺は話が複雑になるのだが、権利者はスポンサーだ。この”地上波デジタルのコピーガード”ってのはどう考えてもおかしい。理論が破綻している。時間が出来たら、自分なりにまとめてみるか。もう過ぎてしまったが、6月25日この日は奇跡ともいえるエヴァンスのファーストトリオの演奏がビレッジヴァンガードで行われた日だ。あのアルバムについて今年も書いてみるかと思ったが、忙しくて断念。1961年の奇跡とも言える演奏から、44年か・・・このままの流れで行ったら7月前半はあんまり日記が書けそうにない。まあ、適度に流しながら行こう。メロディメイカー、ジェフ・リン。PIEさんも書いてくださっているが、奥田民生がモロにパクってるのは、有名な話。2001年に出た新譜「ZOOM」のライナーには奥田民生とPUFFYが文を寄せているし(笑)『アジアの純真』のレコーディングの際にはずっと聴いていたらしい。80年代に入り彼らの音はストリングスが衰退し、キーボードを重視したものに変わってゆく。その転機となったのが大ヒット作「ディスカバリー」(1979)か。このアルバムは80年代に入りプロデュース業が忙しくなってきたジェフが自分自身のための表現として作り上げたものと言えるだろう。彼のソロという色合いが非常に強い。このあと、ドラマーのべヴはブラックサバスに、リチャード・ダンディはソロプロジェクトにと別々の道を歩んでゆく。いきなりレッドアラートの緊急発進を連想させるような『Secret Messages』シンセが少し後退しギターが出てきている。このメロディの作りこみ、やはりジェフの才能はすばらしい。『Loser Gone Wild』もシンセを使ってはいるが、メインはギターか。以前との比較だがロック色が強くなっていると感じる。『Bluebird』は重厚なつくりのバラードナンバーだ。以前の派手なサウンドは後退して、代わりに出てきたのがこの”ジェフがやりたかった音”か。『Rock'n Roll Is King』はシングルカットされてそこそこヒットした。結構ノリのいい曲だ。70年代の名曲『Hold On Tight』に通じるところがある、いい曲だ。最後は幻想的なシンセ『After All』で。当時はLp2枚組みでリリース予定だったものを曲を削って1枚で出していたが、CD化に際してボーナストラックという形で3曲追加された。ただ、残念なのは『Beatles Forever』という曲はここから削られたまま、いまだ発表されていない。一部の曲は、ベスト盤に追加されてるのだが。1.Secret Messages2.Loser Gone Wild3.Bluebird4.Take Me On And On5.Time After Time6.Four Little Diamonds7.Stranger8.Dancer Ahead9.Letter From Spain10.Train Of Gold11.Rock'n Roll Is King12.No Way Out13.Endless Lies14.After Allこのアルバムを、これからELOを聴くと言う人には薦めない。でも、ある程度の耳をもったわかる人には薦めてみたいアルバムだ。この後のジェフ・リンの活動のコーナーストーンとなったアルバムだし、その音楽的意味はある。トラベリングウィルベラーズ等のその後の活動はここから始まっている。さて、また明日からぼちぼち頑張るか。
2004/06/27
コメント(1)
-
今日の音楽・・・Secret Messages
■Secret Messages / Electric Light Orchestra(1983)こんヴぁんわ。メインPCのケースを夏に向けて変えてみたのだが、フロントオーディオポート等の接続がばたばたと。体調が悪かったのと仕事が忙しかったのもあり、日記の更新は後回しに。以前のケースは98年からずっと使っていたもので、PEN4の発熱を上手く排気するのも限界だったし、拡張に次ぐ拡張でベイもいっぱいに。12cm×1、8cm×4 ファンはこれで十分か。3.5、5インチのベイはあわせて12個あるがその内6つをHDDで。って6つもHDDがあるのは多すぎるか。素組みだが一応配線等はなるべくノイズを拾わないようにはああだこうだと。CPUは当分は2.6Cで行こう。さて、ELO。エレクトリック・ライト・オーケストラ。以前にも書いたと思うが、ジェフ・リンは最高の部類に入るメロディメーカーだと思う。2001年に15年ぶりにアルバム「ZOOM」を出したが、やはり彼らのピークは70年代から80年代の前半にかけて。出すアルバムすべてヒットし、”最多TOP40ヒット”でギネスに記録も残していたと思う。今では彼らの名前を知る人のほうが少ないかもしれないが。「世界最小にして最高のオーケストラ」と呼ばれたストリングスを多用した初期から、エレクトロニクスを多用した後期まで、隙のない音を作る。ああ、時間がないので続きは明日にするか…
2004/06/23
コメント(2)
-
今日の音楽・・・Go
■Go / Dexter Gordon (1962)こんヴぁんわ。今日の京都は暑かった。加茂川の河原でサックスをブロウする男が一人。初夏の空気に『The Chrismas Song』が乗っている。終わったところで少し話しかけてみる。前にも私が通りがかって、聴いていたのを覚えていたとの事。自分はどこにたどり着こうか…虚心に見つめたいという希いをこめて。一歩でも近づきたいという思いの中からこそ生まれるものもある。自分が今まで歩んできた道が徒労だったと知ることもあるかもしれない。それでも、行けば明日が今日になる。一人行く道にも力強い仲間はいる。その仲間は、実体ではなく音楽のこともあり、姿は様々だ。そのひとつの側面から音に近づけるよう、言葉を詠わせる。ブログが作るオープンソース的コラボレーション…思考や論理が詰め込まれたそれらを読んでゆくのは楽しい。例え自分にそのスキルがなくとも。私はライターではなく自分の思うがまま直感的に書いているだけなので少々言葉足らずなところもあり、反省する事しきり。中身が濃いところが増えた一方で、ないところもすごく増えているような。いや、そっちのほうが多いか。コラボレートに参加する人は一部で、見てるだけで何も言わない人が多い。データを羅列しておけばOKと、勘違いする人もいるし。とかいう私も、この楽天にHPを作っていることは自分にとってはある意味自虐的だ。(笑)さて、デクスター・ゴードン彼の訃報を耳にしてからもう10年以上の月日が流れる。デックスのサックスを聴くと、なぜだか安心してしまうところがある。ああ、デックスだよな、と。このすっきりとしたブロウが心に染み入ってくるようだ。50年代に一度は頂点を極めたあとに麻薬禍に陥り、すべてを失う。そして60年代に入り、ようやく彼は帰ってくる。麻薬のことから、酒場で営業するためのライセンスがなかなかおりずヨーロッパに渡ることになるのだが、その直前に吹き込んだのがこのアルバムだ。この作品を彼の最高傑作だと推す声も多い。国によるコントロールを避けるだけがその渡欧の理由だったのではないが、ヨーロッパに渡ってからのデックスは自由な空気の下、いい作品を何枚も残した。今の文化庁の役人にいってやりたい。コントロールの強化は文化の発展には一切寄与しないと。まあ、私はエヴァンスほどはまだデックスを聴きこんでないので、どれが最高傑作なのかは判らないが。デックスのサックスは絶対的な確信を持って私に問いかけてくる。だが決して声高ではない。それがこの自然な演奏に一点の曇りもなく吹ききるデックス、このワンホーンがいい。『Cheese Cake』は文句なしにかっこいい。曲よしアドリブよし、といったところ。よく言われる言葉だが、男性的なブロウという彼の魅力的な側面が見える。2曲目はそれと対になる側面、官能的なバラード。『I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry』サックスはここまでエロっぽくないとだめだよなと一人納得。この題を意訳すると、『涙乾くまで』といったところか。テーマをブロウするデックス、この時39歳(だったはず)、いろいろと自身の経験と重ね合わせているのだろうか。この作品を吹き込むまでにいろいろと積み重ねてきたものがあるだろう。実体験として知ってこそ、表現できるものもある。ソニー・クラークのピアノもスマートな感じでいい。『Love For Sale』なんかクールでいかしているなあ。ビリー・ヒンギスって他には何に参加してたかな。地味な感じなんだけどいいな。『Where Are You』は私はロリンズの方が好きかな。授業終了のチャイム(笑)から始まる『Three O'clock In The Morning』常に自然体であった、デックスのいいブロウ。Dexter Gordon (ts)Sonny Clark (p)Butch Warren (b)Billy Higgins (ds)01.Cheese Cake02.I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry 03.Second Balcony Jump04.Love For Sale05.Where Are You06.Three O'clock In The Morningさて、またリハビリしながらぼちぼち頑張るか。
2004/06/20
コメント(1)
-
今日の音楽・・・Kootch
■Kootch / Danny Kortchmar (1973)こんヴぁんわ。毎日リハビリで首をつってるピケです。まあぼちぼちとやっていこうかと。この日記もリハビリのほうも。昨夜もリハビリ帰りで久しぶりに先斗町のほうに出てみたが、歩いているだけで暑い暑い。何かを探してるんだけど、探し物が何かわからないので時間がかかる。見つからないのは、本当は探す気がないからだろう。ずいぶんとすっ飛ばして、もう夏になったかのようだ。感覚は加速しても明日は明日でしかなく、1年後ではない。明日になれば今日という日が昨日になりいつもと同じ順番で変わってゆくだけだ。判ってはいるつもりでも、錯覚する。70年代、ビートルズの解散で幕を開け、ジミ・ヘンドリックスの死やオルタモントの悲劇を経て、イーグルスの解散で楽日を迎える。その中で、先日のメイスンと同様、70年代の名盤と呼ばれる作品にはクーチの名前がよく見られた。ジェームス・テイラーとのフライング・マシーンやキャロル・キングと結成したThe Cityとかジョー・ママとか。東海岸でそのキャリアをスタートさせた彼が西海岸に渡るきっかけとなったのは、ジェームス・テイラーのドラッグ禍によるものからか。で、L.Aに渡りキャロル・キングとシティを。で、このバンドもキャロルのツアー嫌いのため(だったと聴いたはず)、解散。でその後はソロ活動に移ったジェームス・テイラーやキャロル・キングの作品やライブに参加していたが、彼もソロデビューすることになりこのアルバムを吹込む。彼の好んだファンキー路線のままに。ギターだけでなく、ベースやドラムといったリズム全体のコントロールも彼がやっている。うーん、器用貧乏とはこのことを言うのだろうか。ニューオーリンズを思わせる『Put Your Dancing Shoes On』から。カリプソ的な響きを持つ2曲目と3曲目。『Got To Say So Long』のようなゆったりとした時間の流れる曲もいいな。『For Sentimental Reasons』は唯一彼の作品ではなく、スタンダードと化した名曲から。ナット・キング・コールの歌が有名なナンバーだ。70年代流のスタンダード新解釈といったところだろう。私はこの3曲目と4曲目が好きだな。カーティス・メイフィールドばりにソウルフルな『You're So Beautiful』『My Mind Made Itself Up About You』からはどんどんブルージーになってゆく。シャープでブルージーなギターだ。「まあ、とりあえずやってみようぜ」と語りかけてくるような。01.Put Your Dancing Shoes On02.Up Jumped The Devil 03.Got To Say So Long04.For Sentimental Reasons05.Burnt Child06.You're So Beautiful 07.My Mind Made Itself Up About You08.Don't Jump Salty09.Come Strollin' Now70年代のカリフォルニアサウンドといってしまえば簡単なんだが、クーチにとってカリフォルニアとはただの場所でしかなかったのかもしれないな。シンガー・ソングライター(死語?)としての彼の力量をいかんなく発揮した快作。さて、新しく買ったDV機器の設定をするか…
2004/06/19
コメント(1)
-
今日の音楽・・・Certifield Live
■Certifield Live / Dave Mason(1976)こんヴぁんわ。松下竜一氏が亡くなられたそうで。佐高信さんの話から彼のことを知ったのだが、やさしさのある反権力、という姿勢を持った人でした。合掌今日も仕事を早めに終わって、首のマッサージへ。しばらく収まっていたのだが、ここ数日また痛む。10代の頃からバスケやレースで無理していたのが、筋肉が落ちるとともに出てきた。運動不足だな…レイカーズは、ピストンズに完敗。エゴむき出しでチームがまとまれなかった結果だな。ピストンズとのNBAファイナルといえば、88-89シーズン、ジャバ最後のシーズン。あの年もスリーピート(3連覇)確実だといわれながら負けたんだっけ…バイロン・スコット、マジック・ジョンソンのガードコンビが怪我で戦列を離れ、スターターはウォージー、グリーン、ジャバにあとはクープ、リバースだっけな…こんなくだらないことばっかり、なんで覚えているかな…今日も仕事帰りにいつものレコード店をふらふらしてる内に、いつものように10枚ほど。不買運動ってのではないんだけど、買うソフトを年間100枚程度に減らしていくかな。十分吟味した、本当に欲しいものだけに。ムカシのテープの買いなおし等はテープからCDに焼くでもして。ムカシコンサートで隠れて撮った音源なんてのもちらほら。当時『来日してない最後の大物』といわれていたBOSSの京都府立体育館、デビュー15周年だったかのクイーン、トム・ペティと来日してたディラン等々。デイブ・メイスンも当時来日していたはずだが、行ってなかったな。その後メイスンはしばらくソロで活動したあと、90年代末には何を考えたかマック(フリートウッド・マック)に入ったり。当時のマックにはデラニー&ボニーの娘も入っていたけど、マクヴィーだけしか見るものがなかったような。メイスンがいる必然がなかった。このアルバムはトラフィック脱退後(何度か脱退・再加入を繰り返していたらしいが)のライブアルバム。もともと彼がアメリカとイギリスを行ったり来たりしていたことが脱退の原因だったらしいが、そのアメリカとの往復が彼の音楽性を広げたといえるだろう。ってか、すっかりアメリカナイズされてるけど。で、クラプトンから誘われてデレク・アンド・ドミノスに参加したり、ジョージ・ハリスンのソロに参加したりといろんなところで活動していた。70年代の名盤といわれるアルバムのクレジットを見たら、かなりの確率でメイスンの名前があると思う。他にもグレッグ・オールマンとの活動とかもあるし、ここでは書ききれない。このアルバムはメイスンとしては2枚目のライブ盤だが、前作は移籍後に前にいたレーベルが意趣返しに出したもので、本人の望んで出したものとしてはこれが初。76年L.A.でのライブ。自らが出そうとして出しただけあって、演奏もいい。『Feelin' Alright』から”泣きのギター”の真骨頂発揮か。これはトラフィック時代の作品だ。いかにも70年代サウンドといった感じの『Pearly Queen』このギターソロがいい。イーグルスのカバー『Take It To The Limit』メイスン・バンドのヴォーカルハーモニーは本家にも負けるとも劣らない。これ、結構いいな。アコースティックなものでしっとりと聴かせたあとは、ちょとソウルフルに『World In Changes』。『Goin' Down Slow』のブルースを経てアップテンポに『Look At You, Look At Me』充実した演奏。バックのメンバーもいい。サイドギターのジム・クリューガーとキーボードのフィニガン。クリューガーはこのあとボズ・スキャッグスのバンドにも居た(同時進行かも)01.Feelin' Alright02.Pearly Queen 03.Show Me Some Affection04.All Along The Watchtower 05.Take It To The Limit06.Give Me A Reason Why 07.Sad And Deep As You08.Every Woman09.World In Changes 10.Goin' Down Slow11.Look At You, Look At Me 12.Only You Know And I Know13.Bring It On Home To Me14.Gimme Some Lovin'70年代のカリフォルニアサウンドを上手く消化したいいアルバムだ。さて、もっと書き込みたいのだが体調もあまりよくないのでこれくらいに。
2004/06/17
コメント(1)
全205件 (205件中 1-50件目)
-
-
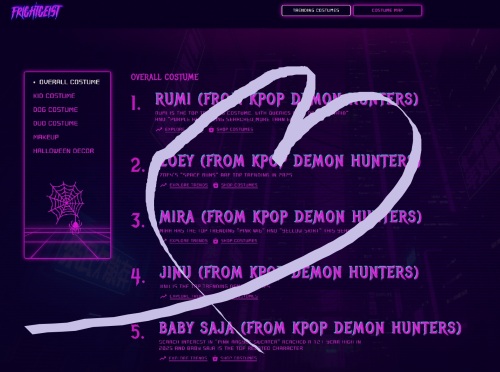
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【森戸知沙希・佐藤優樹・小関舞・譜…
- (2025-11-14 07:10:04)
-
-
-

- ラテンキューバン音楽
- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…
- (2025-10-16 12:29:53)
-








