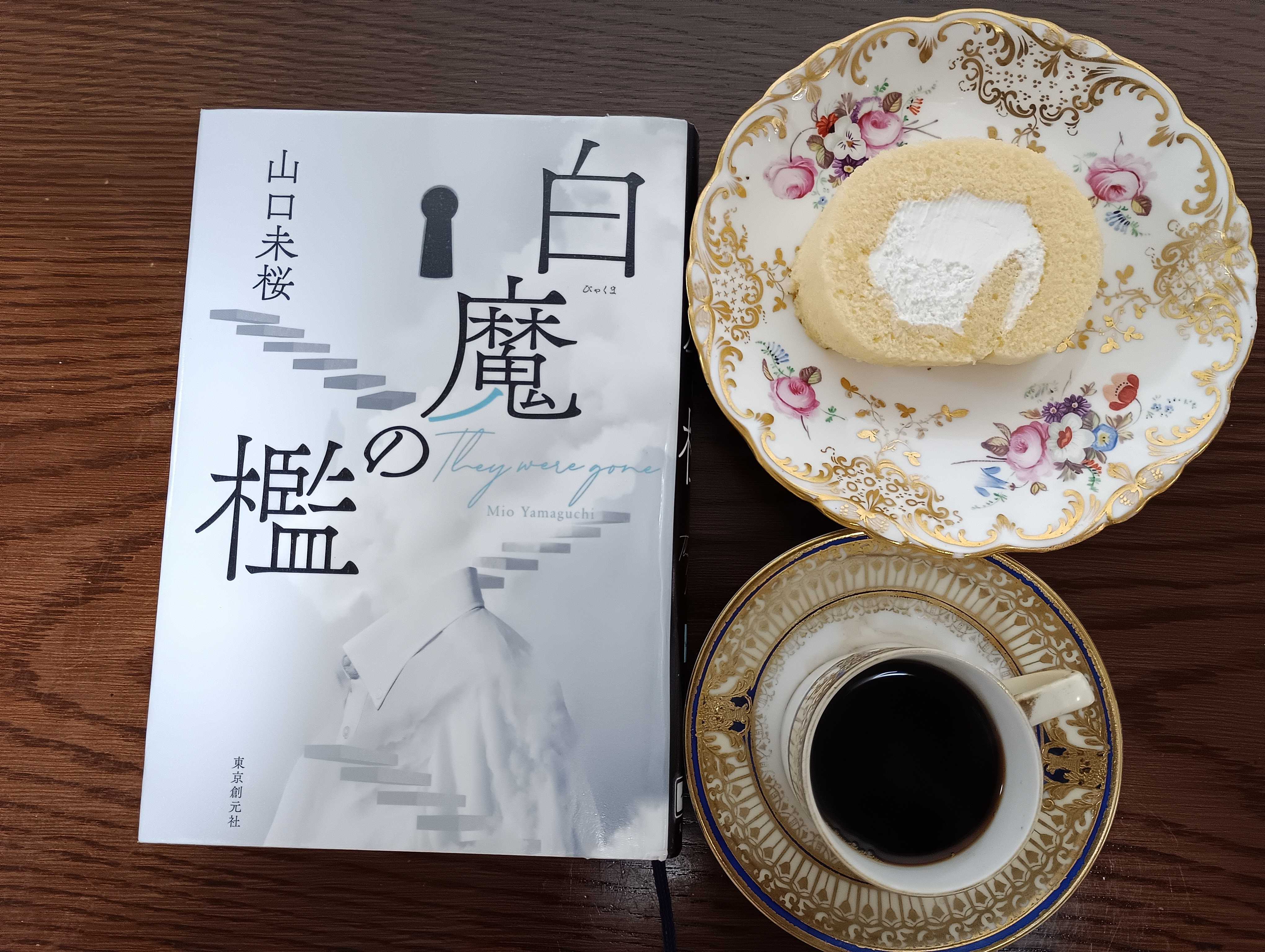2013年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
国債価格と消費税増税
A氏:先週末で25日から4日間続いた朝日新聞の「けいざい深話」欄の「黒田日銀の半年」が終わったね。 一番、興味があったのは、初日掲載の「トラウマ 国債急落」と題して、黒田東彦日銀総裁が、消費税増税の予定通りの実施を強く主張している記事だね。私:金融政策を独立して担当する日銀総裁が、政府の担当分野である財政運営に口出しするのは極めて異例だという。 その黒田日銀総裁を走らせたのは、半年前の就任直後に味わった「国債価格の急落」というトラウマだと報じている。A氏:4月に大手銀行が国債を売り始めると、市場に疑心暗鬼が広がり、国債価格は急落し、0.5%の長期金利が5月23日には一時、1.0%に達した。 これに懲りたんだね。私:当時、日銀は市場の動機を調べ、対策として国債の買い入れの小分けをはじめた。 最後の手段は、大手銀行の首脳のもとに国債売りをしないように、電話による「圧力」だったという。 それでなんとか切り抜けた。A氏:消費税増税を延期すれば、日本は財政再建の意思がないとして、国債が売り始められ、また国債価格が暴落する恐れがある。 トラウマの再来を懸念したんだね。私:黒田総裁は、消費税増税で腰折れすることがあれば、さらに金融緩和をすると発言しているという。 日銀の幹部でさえ「これは実験だ」という声は根強いという。 そして、米国同様、金融緩和は、いつかは「出口」を決めなくてはならない。 カギを握るのは経済成長だ。 「民間企業の爆発」で「プロダクト・イノベーション」は起こるのか。 黒田総裁にとっても予断は許されないようだ。
2013.09.30
コメント(0)
-
9月29日の朝日新聞書評
私:毎日曜日の朝日新聞にはいくつかの選ばれた本の書評が載る。 これらは4頁にわたる読書欄にあるが、いろいろなコーナーに分かれている。 まず、「ニュースの本棚」というのは最近のニュースに関する本の紹介だね。 今週は、伊勢神宮と出雲大社に関する本を数冊とりあげている。A氏:今年は、伊勢神宮の20年に一度の遷宮と60年に一度の出雲大社の遷宮が重なる記念すべき年だね。私:出雲大社の祭神は大国主神(おおくにぬしのかみ)で、神社は壮大な社殿で、本殿の高さは40メートルあったようだ。 山陰を中心に東は北陸や信濃まで及んでいた出雲王国の栄光を長くとどめるモニュメントのようにみえるという。A氏:明治に国家神道が整備されると、全国の神社は伊勢神宮を頂点にランク付けされ、出雲大社は否応なく、その下位にランクされるね。私:天皇や皇族の参拝も出雲大社より伊勢神宮のほうが多くなる。 三種の神器の一つとされる八咫鏡は伊勢神宮内宮の神体とされ、分身が皇居の宮中三殿の一つである賢所に安置されるようになる。 しかし、伊勢神宮の遷宮では、この八咫鏡を実際に見た天皇は誰もいないという。A氏:「昭和天皇独白録」によると昭和天皇は 「敵が伊勢湾付近に上陸すれば、伊勢熱田両神宮は直ちに敵の制圧下に入り、神器の移動の余地はなく、その確保の見込が立たない、これでは国体護持は難しい」 と述べ、降伏を決断させたという。私:原爆でもなく、ソ連参戦でもなく、「見えない鏡」が「ポツダム宣言」受諾を決断させたということになるね。 一応、数冊紹介された中から、中公新書の「伊勢神宮」を図書館に予約した。 本格的な書評コーナーのほうで興味を持ったのは、「忘却のしかた、記憶のしかた・日本、アメリカ、戦争」という本だね。 ジョン・W・ダワーの著だ。A氏:ピュリツァー賞を受けた占領下の日本社会を描いた有名な「敗北を抱きしめて」を書いた日本学者だね。 このブログでも2006年に読書記録を6回にわたりまとめているね。私:評者は、この良書を、イラク戦争で日本占領経験を引き合いに出した米国当局は読んでいないという。A氏:ブッシュ大統領は、最初、イラク戦争を正当化するため、イラクは敗けた後は、日本のような安定した民主国家になるだろうと言っていたからね。私:ダワーは、イラクは日本に似ていないと指摘している。 事実、戦後のイランは未だに混乱状態だ。 米国当局の日本の勉強不足だね。 むしろ、国連に反して単独で中東に攻め入った米国こそ、満州事変から15年戦争の泥沼に入った日本に似ているという。A氏:日本で戦争責任があいまいになった原因も、天皇の責任を不問に付した米国の占領政策にあり、責任という言葉は空疎なものになるという。私:また、ダワーは、日本人は戦前の侵略と残虐行為をみとめることができずにいる、という見方が米国でも広がっているが、米国は原爆を残虐行為として認めておらず、日本人の「歴史的忘却」を非難する資格はないという。A氏:日本を見ることが直ちに米国を、そして世界を見直すことになるということか。私:図書館に予約した。 理性をもって、日本をみつめているダワーの著書を読むのは、7年ぶりだね。
2013.09.29
コメント(0)
-
英語辞典に載った日本語KAIZEN
私:9月17日にトヨタ自動車最高顧問の豊田英二氏が100歳で死去した。 死去を報じたテレビ報道では、オックスフォード英語辞典に「kaizen」とあるのを示し、これがトヨタの「改善」からきていることで、氏のトヨタ生産方式の功労を讃えていたね。A氏:日本のものづくりの新しい方法が、日本語のまま、国際化して英語になったね。 昨日のブログの「デフレーション」の著者吉川洋氏のいう「プロセス・イノベーション」だね。私:トヨタ生産方式は最初、「かんばん方式」などと言われたが、トヨタの大野耐一氏が中心になって確立したシステムで、1960年代に確立するね。 そして、トヨタ以外の日本の自動車業界にも広がるとともに、自動車以外の製造業にも応用され、世界に拡大する。 トヨタはこの生産方式でコストも安いが品質も優秀な車を作り出すようになり、1980年代にはアメリカ車を追い越し、貿易摩擦にもなる。A氏:トヨタ生産方式には、「kaizen」だけでなく、いろいろな手法があるね。私:日本は、1990年頃のバブル崩壊後、不況に落ち込んだ。 その頃、テレビ朝日の「朝まで生テレビ」で、不況脱出が話題になった。 そのとき、当時自民党の国会議員が 「ヨーロッパには『セル方式』という革新的な生産方式がある。 これを日本でも導入し、不況脱出をはかったらどうか」 という発言があった。A氏:「セル方式」というのはトヨタ生産方式の1つの手法ではないの?私:そうなんだよ。 しかも、その「朝まで生テレビ」の出席者の誰一人として「それはトヨタ生産方式だよ」と間違いを指摘した人はいなかったね。 自分の国の強さである「プロセス・イノベーション」に無知なんだね。 当時、自信を失った日本産業界は、景気のいいアメリカに学ぶために、アメリカで流行していた「リエンジニアリング」と方法を取り入れようとしていた。 ところがこれも中身を見ると「トヨタ生産方式の焼き直し」なんだね。 当時、アメリカはトヨタという言葉を使うのを嫌ったのか、MITが「Lean production」という名称で本をだしているが、中身はトヨタ生産方式を説明しているんだね。A氏:逆輸入だね。私:ところで、俺たちが若い頃、日本企業はHowには強いが、Whatに弱いと言われていたね。 「何を作るか」に弱く、それを「どのように作るか」に強い。 前者が「プロダクト・イノベーション」、後者が「プロセス・イノベーション」にあたるね。 トヨタ生産方式は20世紀末に日本が作り出した代表的な世界的「プロセス・イノベーション」だった。 日本はHowのトヨタ生産方式という「プロセス・イノベーション」で高度成長期に国際競争に勝ってきた。 Whatは欧米任せで、日本はHowで勝ってきた。 しかし、この「プロセス・イノベーション」の方法は今は、新興国に移ってしまった。A氏:残念ながら、この間に「プロダクト・イノベーション」が日本には生まれなかったようだね。私:いや、俺は先日、このブログで新書「『東洋の魔女』論」をアマゾンの「当日配送」で買った話を書いたが、この「宅配便」というサービスは、「当日配送」を含め、日本での「プロダクト・イノベーション」だと思うよ。 1971年にヤマト運輸の社長になった小倉昌男氏は、76年1月20日「電話1本で集荷・1個でも家庭へ集荷・翌日配達・運賃は安くて明瞭・荷造りが簡単」というコンセプトの新サービス商品「宅急便」を誕生させている。 これは多くの雇用も吸収してきた。 今ではさらに、朝収穫した京野菜をその日の東京都内のレストランに出すことも、大阪の主婦が都内の高級スーパーで注文した食材を夕食に使うこともできることを狙っている。 このため、配送センターを各所に投資している。 日本全土に「当日配送」を拡大しようとしている。 そうなると消費者の生活は様変わりするだろう。A氏:昨日の吉川洋氏は、今のデフレの究極の原因は、日本の「プロダクト・イノベーション」の欠如だという。 アベノミクスの第3の矢の経済成長戦略は、日本が従来、不得意としたWhatである「プロダクト・イノベーション」でないとだめだね。 「宅急便」やアメリカのシェールガスのような。私:安倍晋三首相のいう「民間の爆発」は「プロダクト・イノベーション」の爆発であるべきだね。 そうすれば、雇用も吸収できる。
2013.09.28
コメント(0)
-

「デフレーション」吉川洋著・日本経済新聞出版社13年1月刊
私:図書館に予約して待って借りたのだから、何かの書評を見て借りたと思う。 何の書評を見たかは記憶にない。 ブログに記録すべきであった。 この本は、やや専門的な本で経済学の数式まで登場する。 多くの経済学者の学説が登場する。 そこで理解できる範囲のポイントだけ読んでまとめることにしたよ。 まず、日本のデフレが、金利ゼロ下でのデフレであるということだ。 これは金融市場では初めてのことだという。 この日本の特殊条件を知らないで、欧米の経済学者がなぜ、もっと金融緩和をしないのか疑問視したことがあったという。 A氏:金融緩和が生ぬるいというわけだ。 私:しかし、その後、その特殊性に気付き、新しい学説が進んだという。 著者の吉川洋氏は、「デフレの正体」で藻谷浩介氏が「日本の生産年齢人口の減少がデフレの原因である」というのに反対だね。 著者は、生産年齢人口の減少が「需要」にマイナスに働いているというが、高齢化で家計貯蓄率が低下しているという。 高齢化により社会全体の消費性向は上がっているという。 A氏:年寄りのほうがカネを使うのかね。 私:それとこの20年間で、欧米と日本の大きな違いは名目賃金の動きだという。 欧米は上昇しているが、日本は極端に下がり続けている。 先進国で名目賃金が下落しているのは日本だけだという。 A氏:終身雇用の崩壊や派遣労働の増加などの日本の雇用構造の変化が影響しているのかね。 企業のブラック化かね。 私:大企業の正社員も下がっているという。 名目賃金が下がり始めたら「本格的なデフレ」だという。 その低下傾向は、1998年からだね。A氏:アジア通貨危機、日本長期信用銀行、北海道拓殖銀行などが破綻するなど、日本経済がマイナス成長になった年だね。 1998年は自殺者が今までの2万人台から3万人台に一挙にジャンプした年でもあるね。 私:吉川氏は、デフレに陥るほどの日本経済の長期停滞を招来した究極の原因は、「プロダクト・イノベーション」の欠乏だという。 グローバル経済における国際競争、円高の下、日本企業は一貫して「1円でも安く」コストダウンを図るべく「プロセス・イノベーション」に専念してきた。 A氏:新しい製品やサービスを創出する「プロダクト・イノベーション」でなく、働く工程の「イノベーション」ということか。 それは、賃金もコストだから「プロセス・イノベーション」でさがり、雇用も減るね。 私:著者は、経済の成長にとって最も重要なのは、「新しいモノやサービスを生み出す雇用創出型」の「プロダクト・イノベーション」だという。米国のシェールガスのような新しい「プロダクト」の創出だね。 アベノミクスの3本目の矢は、その期待に沿えるだろうか。 この本は、1930年代の大不況から、日本のこの20年間のデフレまで、経済学者のいろいろな考えが変わってきていることをまとめているが、まさに百家争鳴だね。 著者は、本の最後に、「デフレと金融政策をめぐる論争は、混迷する現代マクロ経済学の反映である」と書いている。 「混迷する現代マクロ経済学」が、この本を読んだ読後感だね。
2013.09.27
コメント(0)
-
JR北海道の保線問題
私:JR北海道の線路の保守放置問題は報道の突っ込みが甘いね。 こういう問題の原因をすぐに組織の体質にするのは、間違った問題追及だね。 対策は体質改善というわけのわからない結果になるのが落ちだ。 俺が、昔、ある工場に行ったとき、ある現場できちんと作業計画が作られていないので、「なぜ、きちんと作っていないの?」とそこの課長に聞いたら、その課長が「それはうちの体質です」と答えたね。 俺はすぐに「あなたが体質だよ」と言ったね。A氏:JR北海道の社長も記者会見で、 「なんでこうなっているのかわからない。 体質かもしれない。 体質改善の必要がある」 というような他人事のようなこと言っていたね。私:記者は社長に「そういうあなたの体質でしょう」とすぐ切り返すべきだね。 それに、多くの保線工事をしていない箇所を数字で抽象化するから、具体的な原因がわからないね。 線路だけでなく、火災や車両の部品脱落など、車両点検の問題もあるようだね。A氏:国鉄民営化のとき、赤字体質のまま、民営化したのが、原因だという説もあるね。私:これも「体質」原因説と同様に抽象的だね。 現場作業の進め方にどう現れているか、具体的に捉えないのは共通している。 問題線区を数でまとめるのでなく、一つの線区でいいからとりあげ、その線区に行くことだ。 そして具体的にどういう保線計画で、ある期間、何名で、何時間、どの保線工事を行ったのか、やっていない線路はなぜ、とばしたのかなど、線区長に徹底的に聞けばいいことだ。 それをいくつかやれば、そこから、作業の進め方でいくつか共通点が具体的に出てくるだろう。 それから真の体質が分かる。A氏:しかし、脱線事故を起こして、人身事故がなかったことは、不幸中の幸いだね。私:見方によっては、手抜きの悪知恵が現場にあったのかもしれないね。 それも具体的に現場作業の進め方を掴まないとなんとも言えないね。A氏:新レールの基準が間違って使われていたこともあるね。私:それも書類が変わっているはずだし、現場のチェックシートも変わっているはずだ。 そのへんは、現場の書類の管理など、ファイルを見て問題の原因を確認すべきだね。 問題は、社長や幹部は謝るだけで、個々の工事の放置を現場感覚で把握していないことだ。 だから、回答が抽象的で、他人事のようになる。 まず、社長はどこでもいいから、いくつかの現場にとんで、保線工事を観察してから、そこの線区長とじっくり、最低1時間、保線作業のことで話すことだね。 本社の人間やお偉いさんからは、その後で聞くべきだね。 そうすれば、彼らのいいかげんさも正確に理解できるだろうがね。A氏:もう、国の監査が入っているね。私:書類審査だけでなく徹底的に現場主義で監査してもらいたいね。 そして、それに基づいて現場作業管理の具体的な再発防止策を提示してもらいたいね。
2013.09.26
コメント(9)
-
シリア内戦の変化
私:今日も朝日新聞朝刊の国際欄では「シリア 引き裂かれる市民」としてシリア内戦を報じているね。 英軍軍事専門誌によると、反体制派の戦闘員約10万人のうち、アルカイダ系は約1万人、その他のイスラム過激派は3万から3万5千人で、反体制派の半数を占めるという。A氏:本来、反体制派は「シリアでの民主的政権」が目的だが、イスラム過激組織の目的は「厳格なイスラム法に基づく国づくり」だね。 目的がまったく違う。 だから、反体制派内の抗争が始まっているという。私:アサド大統領は17日、米テレビのインタビューで 「これは内戦ではない。 反体制派の8割から9割はアルカイダ系」 と述べ、「テロとの戦い」の立場を強調したという。 「アサドか、過激派か」との踏み絵を内外に迫っている。A氏:早くから君はシリアに関心を持ち、君の「シリア知的街道」は昨年から続いてきたね。「『地図で読む世界情勢』第2部・これから世界はどうなるのか」、「シリア内戦 世界の発火点になる前に」、「シリア・アサド政権の40年史」その1・その2・その3・その4・その5、「シリア内戦とアラブ原理主義の反政府軍の一派」、「シリア旅客機、トルコ空港に強制着陸」、「シリア機強制着陸問題・その後」、「シリア内戦・代理戦争化」、「シリア攻撃と化学兵器使用の真偽」、「シリアの米国の攻撃と化学兵器使用」、「アサド大統領に対するオバマ大統領の方針転換」私:シリア内戦は、今は米ソ対立になってきたね。 プーチン大統領は、シリアの化学兵器破棄で、米国の勝手な軍事支配に釘をさしたね。 今後の展開はどうなるだろうか。
2013.09.25
コメント(2)
-
「出口を阻む投機マネー・米金融緩和」22日朝日新聞社説
私:一時下がった株価が先週また大きくあがったね。 短期間で大きくアップダウンしたね。A氏:FRBが金融緩和の拡大ペースを落すという予測から、一時、株安、円高が始まったというわけだね。 新興国から投資が逃げ出す。私:長期金利も上がりだした。 緩和終了を見込んだ投機マネーの動きが原因だと社説は言う。 そこで先週の17日から18日の連邦公開市場委員会(FOMC)で緩和の拡大ペースを落とすという市場の期待を裏切り、現状維持を決めた。 理由は景気回復が本格的でないためという。A氏:途端に、ニューヨーク株が値上がりし、日本の株式もその影響で株高、円安にもどったね。私:以前、クルーグマン教授が、米国の失業率がよくなったからといって、過去の良き時代の失業率と比較にならないとしていたね。 雇用の増加も鈍く、住宅部門の回復も勢いがない。 そこで、FRBが金融の量的緩和策を終わらせる「出口戦略」へと踏み出す寸前で、立ち往生を強いられたと社説は言っている。A氏:同様に日銀の「出口戦略」も難しいだろうね。 それにしても投機マネーというのはどうしようもないね。私:ところで、来年1月に任期が切れるバーナンキFRB議長の後任人事が来週にはきまりそうだね。 最初、オバマ大統領が考えていたラリー・サマーズ元財務長官が辞退して候補から外れることになった。 その結果、FRB副議長のジャネット・イエレン氏が選ばれそうだね。A氏:イエレン氏はクルーグマン教授が推薦しているね。 選ばれれば、初の女性FRB議長になるという。私:イエレン氏はクルーグマン教授によれば、金融緩和派だというから、「出口戦略」は先になるかもね。 それを予測してまた投機マネーが動く。 どうしようもないね。。
2013.09.24
コメント(2)
-
「TPP・インドネシアから見える『壁』」22日朝日新聞「ザ・コラム」欄・有田哲文編集委員筆
私:有田氏はインドネシアを訪問してこの記事を書いている。 TPPの首脳会合が10月にAPECの機会に合わせ、インドネシアのバリ島で開かれる。 しかし、インドネシアはTPPに参加していない。A氏:インドネシアは人口2億4千万人。 東南アジアの大国で環太平洋にどっしり位置しているね。 なんでTPPに参加していないのだろう。私:中国と東南アジア諸国連合(ASEAN)との間で結んだ自由貿易協定(FTA)で懲りたようだね。 このFTAが発効した2010年以降、農産物、食品、繊維製品などの中国からの輸入がどっと増え、インドネシア企業はえらい目にあったという。 農民の収入も落ちた。A氏:だから、大国との垣根を低くするのはコリゴリだというわけか。私:さらにTPPはそれぞれの国の制度にも口を出そうとする。 ISD条項だね。 インドネシアのような発展途上国にとっては不利なものが目立つという。 最たるものが知的財産権の扱いだという。 TPPでは政府が国有企業を支援することによって、外国企業のじゃまをしてはいけない。 日本の日本郵政のかんぽ生命保険が槍玉に上がったが、資源開発や銀行など140もの国有企業があるインドネシアはその比ではない。A氏:知的財産権や国有企業の問題は実際のTPP交渉でもマレーシアなどが反発し、火種になっており、このままでは先進国と途上国の対立となるね。 そもそも、世界貿易機関(WTO)が壁にぶつかったのは、先進国と途上国の利害が鋭く対立したからだ。私:それがダメだから先進国、とりわけその真ん中にいる米国がぐいぐいとルール作りをする仕組みがいいのか、そこにムリはないかと有田氏は、インドネシアの現状を見て指摘しているね。 TPP交渉は、途上国を含め広い産業範囲をカバーするだけに、交渉は簡単ではないね。 日本でも榊原英資氏のように「TPP敗戦」だという人もいるからね。 また、太平洋戦争のように敗けるとわかっていて戦争をしないように願いたいね。A氏:国民皆保険のような健康保険制度は問題になる。私:国民を保護する国家の権限と利益追求のグローバル経済の対立かね。 「国滅びて、グローバル企業残る」とならないように祈るのみだね。
2013.09.23
コメント(0)
-

「『東洋の魔女』論」当日到着
【送料無料】「東洋の魔女」論 [ 新雅史 ] 私:今日は日曜日なので朝日新聞はいつもの通り書評がある。 今週、興味を持ったのは「『東洋の魔女』論」だね。 書評の評者は日本大学教授で経済学者の水野和夫氏だね。A氏:君はファンだね。私:水野氏は、「永続敗戦」の読書感想を自分のブログで書いていたが、次のように書いてあった。 「書名以上に、本書の内容は刺激的である。 読んだあと、顔面に強烈なパンチを見舞われ、あっけなくマットに仰向けに倒れこむ心境になった。 こんな読後感は初めてだ」 これで俺はこの本を読む気になって、図書館に予約して待ってから借りて読んだ。 読後の記録はこのブログので6回にわたって書いた。 たしかに、「永続敗戦」はショッキングな本であった。 ところで話は「『東洋の魔女』論」だ。 今朝の朝日新聞の書評では、はじめから次のような水野氏の文章が出てきた。 「本書の途中でページをめくることができなくなった」 とある。 要するに涙のためだね。 最後に今の経営者にぜひ一読を薦めたいとある。A氏:スポン根論ではないんだね。私:書評の見出しに「紡績業通して語る日本戦後論」とあるように、日本の経営論だね。 朝、新聞を読んで、すぐ、インターネットで図書館を検索したら「なし」。 アマゾンを検索したらあり、すぐに注文すれば「当日配送」するという。 そのうち、図書館も買うだろうから、それまで待つ手も考えられた。 しかし、水野氏が涙して読んだとあるし、「永続敗戦」のこともあったので早く読みたい。 新書版で903円で安い。 思い切って買うことにした。 インターネットでアマゾンに発注したのが、午前8時ちょうどだね。A氏:何時頃着いたかね。私:今日、午後7時頃、ヤマトの宅配便で届いたね。A氏:まさに「当日配送」だね。私:しかも、配送料無料だ。 今週の日経ビジネスでは特集で「物流大激変・ヤマト、アマゾン『超速配送』の舞台裏」を扱っている。 その中に、「当日配送」に密着した記事が載っているね。 化粧品「オルピスの当日配送だ。 注文が朝の6時24分。 埼玉県加須市のオルピスの流通センターで包装。 ここを出てヤマト運輸の埼玉ベース店に到着。 後はヤマト運輸の東京ベース店、南東京ベース店、上目黒センターへと積み替えられ、目黒のエリアのセールスドライバーの車に積まれる。 この注文をした記者の目黒の自宅には17時51分に着いた。A氏:その日経ビジネスの特集と、当日配送で到着した「『東洋の魔女』論」と読みたい本と雑誌が集中したね。私:読書の秋になったとは言え、他に急いで読書中の本もあるので、ちょっと多忙だね。
2013.09.22
コメント(0)
-
初秋の自然公園ウオーキング・セミの鳴き声減る
1週間前の台風1過の後、急に朝晩の気温が下がり、本格的な秋到来の気配を感じた。 台風一過後、空は青く、秋晴れの快晴が続いたが、数日間、午後からの用事が続き、自然公園ウオーキングができないでいた。 今日、ようやく午後から時間がとれた。 2時半、家を出る。 家に余分にあったお茶のペットボトル1本を持って出かける。 上は下着にTシャツだ。 森に入るまでは、日陰を選んで歩く。 秋とはいえ、まだ、直射日光に当たると暑い。 森に入って気がついたことはセミの鳴き声が減ったことだ。 あまり気にならなくなった。 湿度が低く、カラッとしているせいか、喉があまり渇かない。 前回の真夏のウオーキングではペットボトル2本を空にしたが、今回は1本で十分だった。 違うものである。 いつもの通り、2時間、12000歩。 汗は十分にかいたので、シャワー後、入浴。 身につけたものは洗濯機。 全部、着替えしてサッパリする。 今年の猛暑の疲れなのか、涼しくなってからすこし体がだるい。 考えてみれば、もう9月の下旬である。 歳のせいか、日のたつのが速い。
2013.09.21
コメント(0)
-
アサド大統領に対するオバマ大統領の方針転換
A氏:今朝の朝日新聞では、シリアの首都ダマスカスの生々しいルポを報じているね。私:俺が注目したのは、「視点」という囲み欄で、東京外国語大学教授青山弘之氏の記事だね。 「反体制派の弾圧 進む恐れ」と題している。 確かに、オバマ大統領がアサド政権の化学兵器の廃棄により、シリア攻撃をやめたことは、アサド政権の正当性を否定してアサド大統領の退陣を要求した路線を転換したと言えるね。A氏:化学兵器の廃棄までの管理責任が生まれたアサド政権を邪魔する勢力、すなわち、反政府勢力に、これで米国はあからさまに支援ができなくなったね。私:化学兵器廃棄を米国がのんだことで、アサド大統領は米国とシリア反体制派の切り離しに成功したという。 今後は、アサド政権は反体制派の弾圧を有利に進められる。A氏:シリアが化学兵器全廃で優等生の振る舞いをしているのは、狙いはイスラエルにあるという。 イスラエルは中東で唯一核兵器を保有し、化学兵器使用禁止条約を批准していない。私:そのイスラエルのならず者ぶりを浮き彫りにし、自国シリアの問題をうやむやにする狙いがアサド大統領にあるという。A氏:なるほど、アサド大統領はそれで、今回の化学兵器廃棄による米国の攻撃回避を「外交の勝利」と言っているんだね。私:中東問題は複雑だね。 複眼的な視点が必要だね。
2013.09.20
コメント(4)
-
シリアの米国の攻撃と化学兵器使用
私:シリア政府軍が化学兵器を使用したとのことでオバマ大統領は、すぐにでもシリア攻撃をする宣言していたが、次第にトーンダウンしてきたね。 イギリスは不参加だし、国内の世論もよくない。 世論を見て議員もあまり積極的でない。 オバマ大統領は、議会の承認を得て攻撃を開始する意図であったが、ズルズル延びていた。A氏:そこへロシアがシリアの化学兵器の廃棄という提案をしてきた。 これに乗っかっていくことでオバマ大統領はうまく面子をつぶさないですみそうだね。私:シリアは米国の攻撃を避けられたので、「外交の勝利」としているようだ。 しかし、シリアは化学兵器は「蜂の一刺し」作戦用だから。簡単に放棄するだろうか。 ところで化学兵器廃棄問題であいまいになりそうなのは、「シリアが本当に化学兵器を使ったのか」という事実だ。 これが、ハッキリしない。 しかし、国連調査団の報告を待たず、米国は独自ルートで、シリアの政府軍が使用した証拠を得たとして、攻撃を急いでいたね。 一方、ロシアは化学兵器の使用は反政府軍が使ったという。 米国が攻撃開始をもたもたしているうちに、国連の調査報告が出たが、サリンが使用されたことは事実だが、政府軍か反政府軍が使用したかは明確でないらしい。A氏:今朝の新聞では、国連調査団の報告書を詳細に分析した関係者は「アサド政権側が使った」との見方を固めているという。 関係者は誰かは明らかでない。 米国が明確な証拠があるなら、国連の査察と一致するはずだが、これが明確でないね。ね。私:以前、プーチン・ロシア大統領は「今は、内戦は政府軍に有利になっているのに、なんで政府軍がわざわざ化学兵器を使う必要があるのか」と言っていたね。 2,3月前、国連調査で反政府軍が化学兵器を使ったというニュースがあったね。A氏:今日の夕刊でアサド大統領が18日に米国のTVインタビューで、化学兵器の使用を否定しており、反政府勢力の「卑劣な犯罪」だとの見方を示したという。 米国が証拠の一つと主張する被害者のビデオ映像も「偽造だ」と退けたという。私:シリア報道では外国報道を含め、シリア政府非難には捏造が多いという過去の事実もあるからね。 どうも、シリア政府軍が化学兵器を使ったという確たる証拠が明示され、関係者がそれを共有化していないようだね。 諜報合戦みたいだね。 化学兵器廃棄とは別に早く真実を知りたいものだね。
2013.09.19
コメント(2)
-
よくわからない汚染水の流れ
A氏:君が昨日とりあげていた福島原発事故の汚染水問題を今朝の朝日新聞でとりあげているね。 昨日、国際原子力機関(IAEA)の年次総会の特別報告会で、スロベニアの規制当局関係者が「汚染水がたまる問題は事故の当初からあったことなのに、なぜ、2年間も解決策が探られてこなかったのか」と指摘したと報じていたね。 今朝の朝日新聞の記事はその回答みたいな記事だね。 要するに、東電は2年前に汚染水対策を検討していたわけだ。 しかし、約1千億円かかるということで、躊躇したようで、政府も認めている。私:東電の柏崎原発の再稼働で社長が新潟県知事に了解を求めに行ったとき、知事に安全対策が不十分なことをつかれ「カネか安全か」と言われたことが底辺でつながっているね。 カネで汚染水対策が後手に回ったということを今朝の新聞は報じている。 1千億円で躊躇して、2年たち、かえって高く付きそうだね。A氏:朝日新聞は、5頁では1頁つかって、地下水と汚染水の流れと対策をイラストに描いてるね。 しかし、まだ、ピンと来ない説明だね。私:まず、元の地下水は毎日1000トンだということはわかる。 事故前は井戸「サブドレン」で地下水を汲み上げ海に流していた。 そうしないと水圧で建物が浮いてしまうためだ。 これが事故で動かせなくなった。A氏:そのため、原発建屋に1日400トンの地下水が入り込んで放射能に汚染されて汚染水となる。 これを汲み出して、タンクに入れているということになる。私:新聞記事は、坑道の汚染水にふれているが、これは日常の地下水の流れと別だろう。 話を基本的な流れに集中すべきだね。 新聞記事だと元の1日1000トンの地下水のうち、400トンが建屋に流れ込んで400トンの汚染水になるというのが基本的な流れだね。A氏:問題は建屋のどこがから地下水が侵入しているかが、放射線量が高く建屋に近づけないので、建屋への地下水の流入防止方法がわからないということだね。私:だから、建屋の地下水防水でなく、毎日1000トンの地下水を迂回させるのが対策の基本発想だね。 地下水の流れという自然の複雑な動きとの戦いとなるね。 「想定外」と言わないことだね。 しかし、2年前にカネがかかるとして、2年間放置して、オリンピック招致で火がつき、慌てて政府が正面に乗り出している。 一種の外圧:オリンピック外圧によるものだ。 日本は本当に原発事故を反省しているのかね。 2年間モタモタしている間に、汚染水タンクからの漏れによる地下水汚染という別の地下水汚染が出てしまったね。 これも地下水相手のやっかいな問題だね。 原発の「永続敗戦」はまだ続いているね。
2013.09.18
コメント(4)
-
汚染水対応の遅れ
A氏:今日の夕刊で、昨日開会した国際原子力機関(IAEA)の年次総会で、日本政府はフクシマの問題の現状説明で独自の報告会を開いたという。私:いろいろ専門家から質問があったらしいね。 その中でスロベニアの規制当局関係者が 「汚染水がたまる問題は事故の当初からあったことなのに、なぜ、2年間も解決策が探られてこなかったのか」 と指摘したとあるね。 日本政府がこの指摘に対してどのように答えたのか、新聞は報じていないが、日本としては致命的なところをつかれたね。A氏:汚染水対策で政府が全面に立つというが、「責任をとるのは誰なのか」という質問には的確に答えられなかったようだね。私:総会に出席した山本一太科学技術担当相は記者会見で「状況はコントロールできている」と強調したという。 安倍晋三首相のオリンピックのプレゼンの「アンダー・コントロール」に合わせた政治的な説明だね。 考えてみると、スロベニアの人の指摘のように、事故の当初から汚染水対策は並行して手を打つべきだったね。 「原子力村」はフクシマの事故で、呆然として、全体的な視野を失ったんだろうね。 失敗したら、失敗後の処理もきちんと科学的に行うべきだね。A氏:真の科学者でないからフクシマの事故を起こし、事故後も真の科学者でないから、処理も行き当たりばったりだね。私;メルトダウンした原子燃料を冷却するに水がいる。 しかし、その冷却水は汚染される。 理想は、この水を循環させれば、タンクに貯める必要はない。A氏:それができないのは、地下水が炉に侵入し汚染されるからだろう。私:この地下水が、「津波」のように「想定外」の動きをしている。 それを甘く見たね。 汚染水問題は福島原発事故の「永遠敗戦」を反映しているようだね。
2013.09.17
コメント(2)
-

映画「桐島、部活やめるってよ」吉田大八監督
私:この映画の原作の朝井リョウ氏の小説は、2009年大学在学中の20歳のときのもので「小説すばる新人賞」を受賞している。A氏:君がブログでその原作の「桐島、部活やめるってよ」をとりあげているね。私:映画は「第36回日本アカデミー賞」の作品賞、監督賞、編集賞の3部門で最優秀賞を獲得した。 話題賞の作品部門も 受賞しており、同作に出演した女優の橋本愛さん、俳優の東出昌大さんの2人は 新人俳優賞に輝いている。 ツタヤのDVDを家人がやっと借りられたので見た。 ツタヤのDVDで映画を見るのは初めてだね。 10本ぐらいあるコマーシャルを飛ばし、ようやく本命に到着。A氏:原作は、4人の高校生の独立した独白だというね。私:桐島というのはバレー部のキャプテン。 それが突然姿を消すというだけは、4人の独白の中では一貫しているね。 一貫したストーリーがないし、独白なので小説は内面の心理描写だけだ。 映画ではどのようにまとめたのか、興味があったが、なるほどというまとめ方だね。 独白している4人とも高校2年の同じクラスだが、関連して同じクラスの生徒も多く登場する。。 映画は原作をかなり変えている。 しかし、桐島が登場しないのは、原作と同じだね。 現代の高校生の学校生活をナマで見聞できたね。 女子学生のセリフはちょっと若者語的で聞き取りにくかったね。 俺の高校時代は男子校だったから、ちょっと雰囲気は違っていたね。 今、タイムトンネルで、このような現代の高校の教室に行ったら、呆然と立ちすくむだけだね。 イヤホンで音楽を聞き、コンビニで軽い食べ物を買い、DVDを借りて映画を見るという生活は俺たちの高校生活では予想もできなかったね。A氏:1964年の東京オリンピックが「欧米へのあこがれと劣等感を抱く敗戦国の日本が誇りを取り戻すためのイベントだった」ように、俺たちの高校時代は、その東京オリンピックに向けての時代だったからね。 高度成長に向けて社会は走っていて、考えて見れば、俺たちの高校時代はなんとなく社会に目標があったね。 俺たちの頃は、部活も野球くらいだったから、ほんの1部だね。 放課後は、グランドの片隅でグラブなしのテニス軟級ボールの草野球をよくした。 男子高校のせいか、時代のせいか上、中、下のカーストみたいなものもなかったと思うね。私:しかし、まぁ、なんとか言いながら、この約50年で「成熟」た社会」になったんだね。 少子高齢化社会にもなった。 A氏:今の高校生は俺たちの時代と違う「成熟社会の悩み」があるのだろうね。 社会も一致した目標はない。私:俺たち高齢者には、孫が高校生になったら、この映画や原作は今の高校生活の生徒の内面を知るにはよい参考にはなるだろうね。 小学校は乙武洋匡氏の「だいじょうぶ3組」、中学校は奥田英朗氏の「沈黙の町で」、高校はこの「桐島、部活やめるってよ」と、偶然、この3作で現代の学校生活の実態を知ることができたね。
2013.09.16
コメント(0)
-

「対書対論・消費税」日経ビジネス9月16日号
【送料無料】消費税のカラクリ [ 斎藤貴男 ] 私:来年からの消費税増税導入はほぼ決定だろうね。 ところで、今週の日経ビジネスの対書・対論は、その消費税をとりあげている。 消費増税反対の斎藤貴男著「消費税のカラクリ」と消費税増税賛成の熊谷亮丸著「消費税が日本を救う」とだね。 サブタイトルは、斎藤氏の方は「弱肉強食構造を強化する」とあり、熊谷氏のほうは「消費課税は世界の常識」とある。 「消費税のカラクリ」のほうは、逆進性などの観点とは別な視点から、消費税が不公平な税制であるカラクリを明らかにしているという。A氏:特別な視点とはどういうものだね。私:価格転嫁の問題だね。 中小企業・零細企業・独立自営業は顧客との力関係で、消費増税分を価格に転嫁ができないか、それ以上の値引きを強いられる。 企業利益は悪化する。 もう一つは「輸出戻し税」だ。 輸出は消費税が適用されないため、その仕入れに払った消費税は還付される。 輸出大企業が下請けに還付分以上の値引きを強いることによって、「輸出戻し税」は事実上、「輸出補助金」として機能しているという。 消費税増税で大企業は利益を拡大させるが、零細事業者は壊滅する。A氏:消費税増税は、弱肉強食の構造を一層拡大させるということわけだね。 【送料無料】消費税が日本を救う [ 熊谷亮丸 ]私:一方、増税賛成派の熊谷氏の方は、財政再建が必要だというオーソドックスな賛成論だね。 消費税のメリットとして税の補足可能性、安定性など常識的な点を上げている。 世界的な潮流も「所得課税」から「消費課税」に重心が移っている。 こういう国際標準から逸脱した税制を採用すると、企業や国民の海外脱出を起こす原因になると警告しているという。A氏:デメリットである逆進性はどうかね。私:短期的なデメリットとして認めている。そして、給付付き税額免除や所得税の累進性の強化、相続税の負担増など、歳入歳出構造全体で対応すべきと主張しているという。A氏:「輸出戻し税」のカラクリはどうかね。私:輸出戻し税は、正当なカネであり、批判論は「大企業(金持ち)がたくさんお金をもらえて羨ましい」という俗物根性に過ぎないと一蹴しているという。 オーソドックスな増税賛成論だが、国債価格暴落の危険性や社会保障制度改革などのリスク面を含めて主要な論点が網羅されているという。 日本経済再生論としても読み応えがあると好評だね。 一応、図書館に予約した。 零細企業の価格転嫁問題については、両者で対論がほしい問題だったね。
2013.09.15
コメント(0)
-
集団的自衛権論再燃
私;第1次安倍晋三政権のとき、集団的自衛権の新解釈が問題になったが、急遽、政権が変わり、福田、麻生政権に移った。 同時に集団的自衛権論も棚上げになった。 それが第2次安倍政権となって本格的に取り上げられだしたね。A氏;昨日のテレ朝の報道ステーションに公明党代表山口那津男氏が登場して、集団的自衛権の新解釈のことを聞かれていたね。 山口氏はこの問題でアメリカの要人と接触し、帰日したばかりだった。私:公明党は現行解釈の維持派だね。 しかし、与党であるだけに、新解釈を推し進める安倍首相との関係が難しいね。 テレビでは、この問題は国民の理解が必要だから、2、3年はかかると言っていたね。 この日のコメンテーターの寺島実郎氏も、新解釈に反対で、NATOの集団自衛権行使でも、国ごとに参戦が議会承認などで異なり、実際には意味が無いと言っていたね。A氏:今朝の朝日新聞の「問う・集団自衛権」欄では、軍事ジャーナリスト田岡俊次氏が「タカ派の平和ぼけ危険」と題して、集団自衛権の解釈変更には反対だね。私:田岡氏は、日中関係の変化とアメリカの国内事情から、米国にとって日本の集団的自衛権は無意味で、日本は一人だけ泳ぐのが遅い水泳選手がターンを終えた他の選手たちと反対方向に泳いでいるようなものだという。A氏:北朝鮮は核は使わない。 それは自滅であることを知っているからだ。 日中関係は尖閣問題は「棚上げ」で互恵関係回復が妥当な落とし所だという。私:首相は中国包囲網を作ろうとしているようだが、米国、韓国、豪州は加わらず、成功しないだろうという。 安全保障のポイントは敵を減らすことで、あえて敵を作るのは愚の骨頂で、タカ派の平和ぼけは本当に危ないとしている。 日中、日韓の国交不安定は、そういう環境下で当分進むだろうね。
2013.09.14
コメント(4)
-
オリンピックと文化交流活動
私:昨日、なんとなくNHKのテレビをみていたら、オリンピックの解説をしていた。 それを見て、改めて知ったのは、オリンピックはスポーツの国際交流だけでなく、文化交流も目的としているのだね。 開催地が、その国の文化も発信することが重要な目的だね。 その趣旨にそってロンドンオリンピックのときは、多くのイギリス文化に関するイベントが行われ、多くのアーチストも参加したという。A氏:1964年の東京オリンピックのときは、歌舞伎がメインテーマになったね。私:今朝の朝日新聞の「2020東京五輪・号砲ニッポン」シリーズは4回目で、今日でこのシリーズ欄は終了だが、タイトルは「文化も『成熟』の契機」とあるね。 オリンピックと文化交流との関係にふれているね。 1964年のオリンピックは「欧米へのあこがれと劣等感を抱く敗戦国の日本が誇りを取り戻すためのイベントだった」と作家の奥田英朗氏はいう。A氏:この欄は俺も読んでいるが、今回の東京五輪のキーワードは「成熟」だという。 「未来の幸せを目指すのでなく、現在を楽しむ時代で、7年後の五輪に向けて変化するとしたら、量的な成長でなく、質的な成長が必要」だという。私:「成熟」の具体的な形として政府や自治体が強くアピールしてきたのが「文化国家」としての日本だ。 しかし、国の予算に占める文化予算の割合はわずか0.1%。 韓国は0.8%、フランスは1%強。 日本は文化大臣もいないし、政治家の芸術への理解もまだまだ低いという。A氏:その中で文化庁は20年度までに予算を倍増するという。 そして、日本を国外から文化人が集まった、唐の都・長安のような「文化芸術交流のハブ(結節点)」にする構想をまとめたという。私:五輪は世界中から来た人たちに日本ブランドを記憶してもらうよい機会。 同時に日本人にとっては自らの文化の多様性を再発見するきっかけになるという。A氏:3日前のこのブログの「英語を社内公用語にしてはいけない3つの理由」に出てきた「わび「さび」のようにだね。 アメリカ人のジョブズ氏やドーシー氏のほうが、日本文化の「わび「さび」の考えを自分のデザインに活かしているのに、日本人はあまり、関心がないようだね。 20年の五輪を機に、再度、日本文化の良さを確認し、東京五輪で多くのイベントを行うべきだね。 クールジャパンも東京五輪を追い風に、日本文化を対外にもっと積極的に広めるべきだね。 東京五輪を機に、日本は英語に支配され、英語文化圏にまきこまれるなんていう敗北主義を捨てるべきだね。 「成熟」した文化を発信する五輪とすべきだね。
2013.09.13
コメント(6)
-
日韓ビール合戦記
私:意外なことに、今年の夏の日本メーカーの国内ビール消費は昨年より少ないという。 昨日のテレビで報じていた。A氏:今年の夏は記録的な猛暑だったのにね。私:ゲリラ豪雨など、豪雨が災いしたようだ。 しかし、輸入物の缶ビールは価格も安く、120%増の売上で、しかも韓国産が中心だという。 味も悪く無いという。 ところが、その肝心の韓国で逆転現象が今夏起きたという。A氏:逆転現象?私:韓国では、日本産ビールが売上を伸ばし、70%増というから、倍近い伸びだね。 韓国人は、韓国ビールは水っぽいが、日本ビールはうまいという。 日本のビールメーカーは来年夏は韓国市場を狙うだろうね。A氏:昨日の日中の政府関係の冷え具合と、中国の民衆の冷え具合が違っていたが、日韓関係も似ているね。私:日韓の政府関係も冷えきっており当分出口は見えないね。 民間の交流はもっと盛んになるだろうが。
2013.09.12
コメント(0)
-
「愛国日本品不買運動」のその後
私:ちょうど1年前に日本は尖閣諸島の国有化を決めた。 すぐに中国では、デモが起きたが、日本製品の不買運動もはじまった。A氏:これから始まった日中政府間の悪化はそのまま、続いていて、未だに出口が見えないね。私:日経ビジネスでは、この1年間の一般の中国人の日本製品に対する姿勢を4回に渡り調査しているね。 4回目は今年の8月にやっている。A氏:相変わらず、嫌日かね。私:4回の調査では、次第に日本製品を買うようになってきている。1年前は63%ほどあった不買者が、先月の4回目の調査では、33%と減っているね。A氏:政府と違い民衆は日本への理性的な目をとりもどしてきたのかね。私:ただし、地域と業種によって回復率が大きく違うね。 大連、上海、広州、武漢、北京は平均以上の回復だね。 しかし、南京、西安、成都などは回復が遅い。A氏:ここは過去の日中戦争の経緯から反日感情が強いところだね。私:業種によっても回復が違う。 キャノン、ソニー、ニコンなどは支持率が高い。 小売も卸売もいい。 問題は自動車だね。 中国の自動車市場全体が2ケタのペースで伸びているのに、トヨタ、ニッサン、ホンダなど日本車は前年割れだという。 苦戦している。A氏:乗用車は、乗り回すと「俺は愛国者でない」と外部に宣伝しているようなものだからだろうね。私:今後、また変な問題でも出ない限り、民間の方は対日感情は改善されるだろうが、それでもこの1年、民間でも「反日の基礎票」が2~3割いる。 この層に対する日本企業のきめ細かい努力が必要だと日経ビジネスは指摘しているね。A氏:今朝の新聞広告で、週刊文春で「中国の76%が『自国の歴史教科書は嘘』衝撃データ公開」「『尖閣は日本の領土』という『ウィキペディア』に愕然とした若者」とあるね。私:中国のネットメディアがネットで調べたものらしいね。 民衆は本音は政府のいうことをあまり信用していないね。A氏:日中関係も政府レベルは悪化傾向だが、民間レベルはもっと改善の余地があるね。私:それにしても、韓国はいやらしいことを平気でやる国だね。 日本からの水産物を放射能があるからと輸入禁止にした。 しかも、タイミングをオリンピック評価委員会の前を狙った。 明らかにオリンピック東京開催の妨害だね。 今は、あてが外れて目も当てられないね。
2013.09.11
コメント(2)
-

「英語を社内公用語にしてはいけない3つの理由」津田幸男著・阪急コミュニケーションズ11年7月刊
【送料無料】英語を社内公用語にしてはいけない3つの理由 [ 津田幸男 ]私:新刊ではない。 なにかの雑誌を読んで知って、興味を持って図書館に予約した。 新刊でないのですぐに借りられた。 著者の津田幸男氏は筑波大学院教授で、専門は英語支配論、言語政策、国際コミュニケーション論だという。A氏:3つの理由とは何かね?私:第1に「日本語・日本文化の軽視」 第2に「社会的格差・不平等の助長と固定化」 これは要するに英語ができるか出来ないかによる格差・不平等だね。 第3は「言語権の侵害」 言語権とは「自分の母語を使う権利」だという。 この3つを書いて、楽天とユニクロの社長に直接手紙を出したという。 しかし、返事は来なかったという。A氏:しかし、グローバル化で英語の使用は拡大しているね。私:著者は国語の専門ではないようだが、日本語の良さ、日本文化のよさを失うべきでないとしているね。 これは英語により日本語滅亡論にはよく出てくる般論だね。 面白かったのは、次の文章だね。 「禅仏教により広まった『わび』『さび』の精神も日本ではないがしろにされています。 これも復活しなければなりません。 今の日本では「わびしい」「さびしい」はマイナスの意味しかありません。 しかし、『わび』も『さび』もその根本にあるのは「日本型エコロジー精神」です。 『わび』も『さび』も「何かが不足している」という情緒をあらわしているからです。 そしてその「何かが不足している情緒」を1つの「美」として形作ってきたのが日本の伝統文化です。 日本の俳諧の伝統がそれを生み出してきました。 『わび』と『さび』という欠乏の状態を「美」に変えたのが日本の芸術です。」A氏:なんで『わび』『さび』を特に取り上げたのかね。私:実は、今週の日経ビジネスを読んでいたら偶然「わび」「さび」が出てきたんだよ。 今週の特集は「スクエア・インパクト」で、ツイッターの創始者ジャック・ドーシー氏がスクエアというベンチャー企業を起こし、スマートフォンなどで端末決済できるようにして、自営業者や中小企業は無料同然で大企業と同じ武器を手にすることができるようにした「決済革命」をとりあげている。 ドーシー氏は、シリコンバレーでは「ポスト・ジョブスに一番近い男」と期待されている天才だ。A氏:そのITの天才と「わび」「さび」はどういう関係があるの?私:彼は、「わび」「さび」を英語で書いた1冊の本を新入社員研修で渡す。 「両極端の要素に中にある『美』。 そのバランスこそが大事ということを社員に学んでほしい」 という。 彼はインタビューに答えてさらに言う。 「『わび』『さび』は両極端の対比の中で美しさを見出すことと、とらえている。 暖かさと冷たさ、素朴なものと近代的なもの、居心地の良いものと無機質のもの。 面白いのは、2つの対照的なものの間に「美学」があるということだ」 ドーシー氏は、アップル社の故ジョブズ氏を尊敬しているという。 ジョブズ氏も禅に魅せられ、京都を頻繁に訪れた。 日本の美意識から多くのインスピレーションを受けたという。A氏:アメリカの先端を行く情報機器のデザインの「美学」に「わび」「さび」の「美学」が使われているとはね。 英語問題で日本語の被害者意識だけでみるのは視野が狭いね。私:この本の著者は徹底した英語と日本語を敵対するものという視野の狭い視野で考えている。 それでは敗北あるのみだね。 ジョブズ氏やドーシー氏のように補完し合うべきものに発想を変えないと、敗北主義で終わるだけだね。 日経ビジネスは、俺にとってグッドタイミングでドーシー氏の「わび」「さび」をとりあげてくれたね。
2013.09.10
コメント(7)
-

「いま、憲法改正をどう考えるか・『戦後日本』を『保守』することの意味」樋口陽一著・岩波書店13年5月刊・その4
A氏:「家族」についての自民党草案はどうかね。私:「『家族』は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 『家族』は、互いに助け合わなければならない」 とある。 「個人」が消え、「家族」の中の「人」になり、「『家族』が社会の自然かつ基礎的単位」となっているのは、現行憲法の社会観の逆転だね。 天皇を頂点にした「村社会」的な意識が強い日本には「個人」は向かないと見たのかね。 「敗戦」に向けての最後は、「個人」の立憲政治も消えて「村」の大政翼賛会になる。 「和」は「和して同ぜず」でなく「個人」無き金太郎飴になる。 だから、敗けると知っていて、開戦する。 戦争が始まると「戦陣訓」になる。 天皇のための「玉砕」となる。 「人間意思の自由、思想の自由」という近代的思想の一欠片もない。 その近代思想の相手と近代戦を戦ったのだから、当然、「敗戦」だ。 技術の最先端の原発まで「原子力村」となり、安全性を心配する「個人」を追い出し、最後は、フクシマで壊滅する。 「敗戦」の流れとまったく同じだね。 「個人の尊厳」軽視は「ブラック企業」にも現れている。 考えると、自民党の憲法草案は「永続敗戦」の産物だね。A氏:国民が権力を縛る憲法から国民が尊重への義務を追う憲法という転換。 なんだか、教育勅語も一緒になっている感じだ。 明治憲法ですら教育勅語は別だったのに。私:「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」が「のみ」が削除され「婚姻は両性の合意に基づいて成立し」に変えられている。 これも現行憲法より「個人」が曖昧となるね。A氏:考えてみれば、西欧は一神教のもとに「個人」という意識が強い。 その思想に接した夏目漱石など明治の知識人がそれまで封建的なムラ意識が支配的な日本における西欧の「個人」で苦闘してきた。私:「敗戦」を「終戦」にせず、もう一度、天皇を頂点とする家族主義を国家のあるべき姿とするのか、それとも「個人」の尊厳を中心に置くのか、考えるべきだね。 自民党の草案は9条だけの問題でないことがよく理解すべきだね。 まぁ、一言で言えば、自民党草案は「永続敗戦」の憲法的産物だね。 9条問題にめくらましを食わされてはダメ。 憲法改正問題の検討には「永続敗戦」から脱した幅広い見識が問われている。
2013.09.09
コメント(4)
-

「いま、憲法改正をどう考えるか・『戦後日本』を『保守』することの意味」樋口陽一著・岩波書店13年5月刊・その3
私:現行憲法での天皇は明治憲法の「政治を総覧」する立場から「国政に関する権限を有しない立場」へと一変した。 治安維持法の保護法益とされ、大審院の判例で示されていた法的意味の「国体(万世一系の天皇君臨し統治権を総覧)」は変わったが、天皇への尊崇・敬愛という意味での「国体(憧れの天皇)」は変わらないというのが当時の政府答弁であった。 それに対して、当時、憲法学者の宮沢俊義氏は「ポツダム宣言」受託によって「わが国の政治体制上の根本的な改革」「革命」もたらされたという。 この彼の見解は「八月革命」論と呼ばれるという。 新憲法の草案を見たある専門家は、「国民主権」「基本的人権」「法の支配」という言葉が、わが国の憲法に書き込まれるようになったのを見て、「鮮烈な感動、声をあげて喜びたいほどの開放感」を味わったという。 しかし、、「国体護持」を実現したかたちでの敗戦は、敗北という外見に反して、革命が起きそうな事態を天皇制国家の支配層が排除した華々しい勝利にほかならないと「永続敗戦」では言っているね。A氏:その後、警察予備隊の発足など冷戦と逆コースで憲法の立場も変わってくるね。私:今までのことを念頭に2012年の自民党「改正草案」の中身に入ろう。 まず、天皇を元首と変えているが、中身が変わらないようなので、なれてきている象徴でも同じようなものであるという。 明治憲法の名称にもどりたかったのだろうか。 この天皇の項に「国旗、国歌、元号」が入る。 これらは天皇・皇室という制度と関連させていこうという方向がみられるという。A氏:戦争放棄は安全保障となり、国防軍が明記される。私;表現の自由、信教の自由と政権分離、労働基本権は、書き方が微妙に変わっている。 これが、具体的な適用のとき、近代憲法を逆転させる意味を持っていると指摘している。 例えば、現行憲法では「表現の自由」の規定だけであるが、自民党草案では、追加として「公益及び公の秩序を害してはならない」と例外事項を並行的にならべている。 そういう例外事項は裁判等に譲るべきで、そうしないと、この例外が当たり前になり、表現の自由と同じレベルの重要性を帯びる恐れがある。 こういう「自由や権利には制約があるよ」という例外事項の並行的な追加が、信教の自由と政権分離、労働基本権にあるという。A氏:書いている人の意図が密かに爆弾を仕掛けているようで怖いね。私:前文は全面的に書き換えられている。 「長い歴史と固有の文化」「天皇を戴く国家」「国と郷土」「家族や社会全体がお互いに助けあって」という言葉が登場している。 自民党草案は、明治憲法のとき、森有礼が唱えた「天賦人権説」は放棄し、「これに基づく規定を全面的に見直す」というものだね。 それから、現憲法の「個人」が家族の一員である「人」に置き換わる。 「個人」と「国家」でなく、家族や社会全体の中におかれた「人」だからこそ「和」がなりたつというわけだ。 「個人」でなく、「家族」をもとにするというのが、安倍晋三首相が「日本をとりもどす」というときの日本像なんだろうね。明日は、その点についてもっと掘り下げてふれよう。
2013.09.08
コメント(4)
-

「いま、憲法改正をどう考えるか・『戦後日本』を『保守』することの意味」樋口陽一著・岩波書店13年5月刊・その2
私:昨日、「憲法押し付け論」、「短時間作成論」、「改定実績ゼロ論」による現行憲法の批判は、実は「中身検討棚上げ」で共通していることをあげた。 どの条文が戦後70年経って問題なのかの個別の条文の議論が9条以外はあまりないね。 当時、憲法学者の宮沢俊義氏は「ポツダム宣言」受託によって「わが国の政治体制上の根本的な改革」「革命」をもたらされたと言ったという。 この彼の見解は「八月革命」論と呼ばれるという。 すなわち、「ポッダム宣言」の要求は、敗戦国日本の新憲法の中身に介入しているね。 「ポツダム宣言」10項の「民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除し、言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重を確立する」という内容。 12項の「平和的傾向を帯びかつ責任ある政府の樹立」という内容。 10項の「民主主義的風潮を強化しあるいは復活」ということについて、明治憲法の作成からこの本ははじまっているね。A氏:明治憲法の作成には、できるだけ諸国の知恵に学んでいい憲法を作るため欧州の憲法を参考にする方針があったね。 イギリス、フランスとわたり、最後にドイツが日本にあっているだろうとドイツ憲法を主に参考にしたという。 その意味では明治憲法は先進国の西欧憲法の「押し付け」だとも言える。私:だから、当時、憲法など日本帝国の法制度の設計者のひとりである井上毅は当時「立憲政体の主義に従えば、君主は臣民の良心に干渉しない」と言っている。 また、伊藤博文は「憲法は第1に君権を制限し、第2に臣民の権利を保護するにある」と言う。 当時の文相・森有礼は「臣民の財産及び言論の自由は人民の天然所持するもの」という「天賦人権説」を唱えている。A氏:それが「立憲主義」なんだね。 そして、それから120年たった、今、自民党の憲法改正案では、「立憲主義」を捨てようとしているね。 これは改憲、護憲の正反対の立場に立っている森、樋口教授は、この明治以来の「立憲主義」の放棄をしている自民党案を両氏とも批判しているね。私:しかし、西欧の「立憲主義」が日本に定着するまでには時間がかかるね。 明治の学者の間にも論争があり、「憲法は国固有の国体、政体のものなので、一切、外国の事例や学説にこだわってはならない」という帝大の憲法学者穂積八束氏もいた。 当時、森鴎外も「立憲政治」の行く手を憂慮し 「外観を変更しても風土と気候と、すべて眼に見えないものが、人間意思の自由、思想の開放には悪意を持っているらしい」 と洩らしているという。A氏:しかし、「立憲政治」はその後、進んでいき、「立憲政友会」「立憲民政党」などの政党ができ、選挙も行われるね。 1918年(大正7年)に成立した原敬内閣は、日本初の本格的政党内閣だね。 しかし、もう一方の「人間意思の自由、思想の自由」は後退していくね。 そして、最後には「立憲政治」まで後退させるね。 何故だろう?私:明治憲法が施行された1890年に同時に「教育勅語」が出されている。 これによって「君主は臣民の良心に干渉せず」とはならなくなった。 道徳の根源は天皇となり、その「感情」が議会政治とは別の次元で、学校教育と兵役という2つの義務教育によって臣民の中に深く打ち込まれた。A氏:そこで「ポッダム宣言」の「民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除し、言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重を確立する」となるのか。 特に軍国主義の10年は暗黒だったからね。 当時は、天皇のために命を捧げることが臣民の道だった。 明治初期に芽生えた言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重などはきれいに消えていた。私:明日は、現行憲法の話に移ろう。
2013.09.07
コメント(0)
-

「いま、『憲法改正』をどう考えるか・『戦後日本』を『保守』することの意味」樋口陽一著・岩波書店13年5月刊・その1
私:この本との出会いは、このブログで日経ビジネスの8.12-19合併号「本」欄をとりあげたのが発端だね。 ここでは、憲法改正派の慶応大学小林節教授の著書「白熱講義!日本国憲法改正」と護憲派の樋口陽一東大名誉教授著「いま、、『憲法改正』をどう考えるか」を対比させていた。 しかし、細かい点は改正点のほうはふれていて、護憲論理にはふれていなかったので、この両論の対比のを1頁で行う試みは失敗だったね。A氏:ところで、憲法改正は安倍晋三首相の祖父である岸信介元首相以来の政治的課題だね。 その間、左派が3分の1以上を占めたり、ねじれ国会などになったりで憲法改正は政治課題の中心にならなかったね。私:もともと「押し付け」憲法のGHQ案では、議会は一院制だったのを日本側が要望して2院制にしたという経緯がある。 これがねじれの原因になり、自分で自分の首を締めるとは歴史は皮肉だね。 それが、ねじれ解消の安倍政権でいよいよ憲法改正に取り組むとなる機会はきた。 最初、とっかかりとして、改憲の提案をやりやすくするというので96条の改定提案権を3分の2以上を、半分にするという提案があったが、反対が多いようで、安倍政権はひっこめたね。A氏:改憲で意見が正反対の小林氏、樋口氏両氏ともにこの安倍政権の96条改定は反対しているね。 憲法は容易に変えるべき性質のものではないとしている。私:この裏には、憲法が発布以来、70年にもなろうというのに、改訂ゼロだというあせりがあるね。A氏:改定少ないのはおかしいとして、ドイツが50回以上変えたとか、他国との比較が出るね。私:しかし、これは憲法の構成の違いによるようで、それを理解しないと間違いの元になる。 他の諸国で改正の回数が多いとされるその内容を見ると、統治の仕組みの手直しが大部分であり、基本権条項を中心とする憲法の基本規格には手を加えていないという。 ドイツでは「人間の尊厳」をはじめとする条文のいくつかを改正不能とする規定があり、ナチス体験を教訓として、憲法秩序の防衛が強調されているという。 フランスは「共和制統治形態」の改正を禁止しており、1789年人権宣言17条が一言一句そのままで違憲審査の基準とされているという。A氏:他国の憲法改正の件数を比較して、公平な議論をするにはまずそれらの改定内容をよく理解する必要があるね。 改定件数の小学校の算数レベルの数字比較問題にしてはダメだね。私:それから、大衆受けしやすい論理が「押し付け憲法」から「自主憲法」へということで憲法改正の必要性が叫ばれることだね。 岸政権が発足したのが1956年だが、この頃から、一貫して言われているね。 これも論理的にはおかしなことで、「押し付け」だから内容が粗悪で、「自主」だから内容が良いということはすぐに直結しないね。 「押し付け」のほうがよく出来ていて、「自主」のほうが粗悪だとも言える可能性もある。 「押し付け」論は中身の議論を「棚上げ」して、被害者意識に訴える感情的な討議方法だね。A氏:GHQのスタッフが短時間で作り上げたというが、これも短時間で作成したから質が悪く、時間をかけるほど質がいいとういう直結発想も、論理的に合わないね。 短時間に集中してやったから質がいいということもあるし、ダラダラ、時間をかけても内容がよくないこともある。 これも「中身棚上げ論」だね。私:当時、国際政治的には、天皇制を廃止させようとする極東委員会に先手を打って、天皇制を維持しようとしたマッカーサーが、迅速に憲法作成で既成事実をつくるために作業を急いだね。 それに新憲法の内容は、次の「ポツダム宣言」の趣旨にそったものでなくてはならない。 4項.日本帝国を破滅の淵に引きずりこむ非知性的な計略を持ちかつ身勝手な軍国主義的助言者に支配される状態を続けるか、あるいは日本が道理の道に従って歩むのか、その決断の時はもう来ている。 10項 日本政府は、日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする。 12項 連合国占領軍は、その目的達成後そして日本人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を帯びかつ責任ある政府が樹立されるに置いては、直ちに日本より撤退するものとする。 詳細は明日からにしよう。
2013.09.06
コメント(0)
-
ゲリラ豪雨とゲリラ竜巻
私:テレビは、ゲリラ豪雨とゲリラ竜巻の報道がほとんどを占めているね。A氏:全国的に拡大してきたね。 みのもんたの番組では「天変地異」と言っていたね。 それほど、かってない異常気象だね。 地球温暖化のせいだという学者もいる。私;しかし、横浜は長い間晴天で雨がなく、逆に雨がほしいと思っているくらいだ。 3日前、週間天気予報で、4日頃から雨が連続して降るという。 そこで、一昨日は晴天だったがこれが快晴の見納めと思い、例の2時間の自然公園ウオーキングに出かけたよ。A氏:ゲリラウオーキングか(笑い)。私:ウオーキングに出かけるとき、気温は高温警報が出ていたから、午後3時、少し日が傾きかけてから出かけたよ。 森は相変わらず、蝉の声の大合唱だが、道にもう死んだセミが腹を上に死んでいるのをよく見かけたね。 蝉の寿命は地上で2週間か。A氏:横浜は、昨日は、雲が多かったが、雨は期待した程ではなかったね。私:夜、ザーッと来たがすぐやんだね。 雨量が少ないね。 むしろ、驚いたのは午前中の地震だね。 横浜は震度4だから、かなり揺れた。A氏:ゲリラ豪雨、ゲリラ竜巻に加えて大地震が来たらどうしようもないね。私:それこそ、天変地異だね。 こういうニュースは東京オリンピックの招致に関係しないのかね。 原発の汚染水が世界では関心になっているようだが。 横浜も、今日、やっと雨が少しパラツイた。 明日はもう、天気は回復するが、土、日は雨になりそうだ。 ゲリラ豪雨、ゲリラ竜巻にはご勘弁願いたいね。
2013.09.05
コメント(0)
-

「沈黙の町で」奥田英朗著・朝日新聞出版13年2月刊
【送料無料】沈黙の町で [ 奥田英朗 ]私:この本は、3月3日の朝日新聞書評に掲載されていたので、図書館に予約した。 この小説は2011年6月から2012年7月まで朝日新聞に連載したものだが、単行本のとき多少加筆訂正したという。A氏:何がテーマの小説かね。私:中学生のいじめ問題だね。 いじめ問題に正面から取り組んだ貴重価値のある小説だね。 図書館に貸出を申し込んでから半年近く待って、俺の順番に来たので図書館に行った。 そしたら、受取カウンターにこの本が出てきた時は驚いた。 ドサッと置かれた本は510頁の長編だ。 この暑い夏に読みきれるとかとちょっと不安になったよ。 しかし、読みだすと、一種のミステリー風の著者の話の旨さに引きこまれ、4日ほどで読了した。A氏:どういう「いじめ」なのかね。私:舞台はある地方都市だが、そこの裕福な家の一人っ子が「いじめ」の対象となる。 いかにも「いじめられそうなタイプ」として描かれている。 この子が、死体で発見される。 それは「肝試し」というのがあり、校舎の2階屋根から、すぐ下の大樹の太い枝にとびつくというものだ。 原因は、それに「いじめられっ子」が飛びつきミスをしたのではないかということだが、死体の背中につねられて皮下出血をしたおびただしい跡があるのが警察でわかり、「いじめ」が表面化する。 その子は中学2年でテニス部に属していた。A氏:ムリに肝試しを強要したのかね。私:警察は、それを視野に生徒たちの捜査を開始する。 話は、警察、学校、新聞社、生徒の保護者と多くの人物が生き生きと描かれて登場する。 小説では、それらの人物を2種類に分けて描写する。 一つは人物の内面心理まで入った描写。 1つは外面的な描写。 内面描写は、事件担当警官、担任教師、新聞社の若い女性記者、母子家庭の保護者、被害者の母親、いじめと直接関係ない同級生の女生徒、新任の若い検事などに限られている。 しかし、授業以外の中学生の学校生活を細かく捉えているね。A氏:いじめられていた本人の内面描写はないの?私:それが問題かもしれないね。 それと担当主任が生徒の人間関係や「いじめられている子」に関心がうすい気がしたね。 生徒と担任の関係についての話が少ないような気がしたね。 担任教師はテニス部の顧問だが名ばかりで、テニス部の練習は生徒まかせで見ていない。 乙武洋匡著「だいじょうぶ3組」ような教師と生徒の密な関係の話がほしかったね。 生徒たちは、この子がいじめられていることを知っているが、近くに接しているはずの担任教師、そのいじめられっ子の親は案外気がついていない。 話の進め方は小説としては面白いし、最後の3頁くらいで読者を驚かす形式だが、いじめ問題にはあまり深い掘り下げはないね。A氏:いじめ問題の根絶はやはり、学級制度の廃止かね。私:そこまではこの本は問題提起はしていないね。 小説のうまさには感心したがね。 猛暑を一時的に忘れることができたね。
2013.09.04
コメント(0)
-
「猛暑の夏 ピンチがみせた底力」3日朝日新聞社説
私:今朝の社説は、出だしはよかった。 今年の猛暑は異常で、平均気温2度以上上回り、統計をとりはじめた1961年以降の最高記録を塗り替えたという。 熱中症で救急搬送された人は5万3千人を超え、少なくとも87人がなくなったという。 社説は、ここまでは今年の猛暑の異常さを数字で示してよかった。 ところが、これから以降、数字は消える。 だから内容に説得性がない。A氏:俺も読んだが、暑さに一矢報いた痛快な出来事に話題が移っているね。 これが、社説タイトルの「ピンチがみせた底力」だというわけだ。 まず、四万十市の観光客を集めた例を上げているが、ここは鮎漁が被害にあったデメリットを上げていない。私:次に企業や家庭の節電熱を上げていて、これが今年の夏の電力不足を補ったというような書き方だね。 ここにくると数字で示せる話なのにデータがない。 今夏の電力需要量は昨年に比較して、どのくらいだったのか。 供給電力量はどのくらいだったのか。 そのうち、原発や火力の比率はどうだったのか。A氏:それがなくて節電の話ばかりだね。 JR西日本が省エネ効果の高い車両に切り替えているとか、デパートやオフィスが照明をLEDに切り替えているとか、家庭のエアコンも故障したのを機に高くても省エネ型に買い替えているとか、中小企業も節電に努力しているとか、ピンチはチャンスだというわけだね。私:俺のところのエアコンは故障しなかったから、この猛暑で昨年以上にエアコンはバンバン使っているよ。 電力会社は、原発停止で、その代わりの電力は火力発電だろうから、火力発電で猛暑を乗り切ったんではないかね。 だから、電力料金値上げとなっている。 そういう実態は数字がないから社説の主張の正しさがわからない。A氏:節電で、今年の猛暑を乗り切ったという内容にとれるね。私:昨年の夏と比較した消費電力量と比較すれば節電効果は簡単にわかるだろうね。 節電で乗り切ったというなら、昨年と電力消費量が減ったことを示す数字を示すだけでいいのではないかね。 データがなくて主張するというのは、主観的な印象だけでこわいね。 間違った世論を誘導しやすいね。
2013.09.03
コメント(0)
-
汚染水漏れ 点検ずさん
A氏:君が「永続敗戦」の例で、一昨日とりあげた原発事故による汚染水のトラブルが今朝の朝日新聞に大きく取り上げられていたね。 新聞1面ではタンク間をつなぐ配管からも漏水を発見とあるね。私:38面では「汚染水漏れ 点検ずさん・1日2回、タンク1基あたり15秒」と大きな見出しで報じている。 千基あるタンクを2人でやるから、一人で500基の点検。 これを2時間でやると1基あたり約15秒だね。 これは大きな防護服を着て大変な歩行スピードが要求されるね。 これであの大きなタンクをきちんと点検できるのかね。 これを1日2回やるわけだ。A氏:東電ではこれまで、10人程度でやっていた担当者を今日2日から増やし約60人体制にするという。私:これもおかしな話で、本来、きちんとやるなら、60人ほど必要な点検を、今まで10人でやっていたことになる。 誰が最初の10人を決めたのかね。 危機感がないね。 「永続敗戦」だね。 人数の計算も逆だね。 まず、1基あたり必要な点検時間を決めるのが当たり前だ。 例えば1基あたりの点検時間が、異常な場合の線量測定などを含め、1分かかるとする。 500基だと500分、約8時間だね。 一人の労働時間は1日フルで8時間なら、1日2回の点検だと千基では4人となる。 しかし、保護服の脱着などで実際に作業できるのが2時間なら、4倍の16人となる。 必要点検人員が、最後に計算結果で出るのが常識だ。A氏:問題は1日2時間しか点検作業をしないことだね。 8時間労働として残り6時間は何をしているのだろうか。 防護服の着替えだろうか。 その点も新聞は報じてもらいたかったね。私:今日からは1日4回点検するという。 それが60人だという。 これもどういう計算なんかね。 どこから、人を急に集められるのかね。 ところで、福島原発の仕事は危険を伴うが、作業そのものの難易度は高くないうえに、単価が高い。 「フクイチ(福島第1原発)バブル」だという。A氏:人手不足だね。私:しかし、中抜きの多い多層下請けだね。 原発事故に伴う雇用も汚染されている。 汚染水処理には東電任せではダメで、政府が乗り出すというが、まず、シッカリ計算をしてもらいたいね。 放射能が減衰するまで、何十年で、その間、何トン汚染水が発生し、現状のタンクは何基になり、その土地は何ヘクタールになるのか。 海まで汚染水がいかないようにするには、地下水の動きの調査を含め技術的にどういう方法を追加して行うのか。 そのカネは概算どのくらいかかるのか。A氏:すでに溶接型のタンクからも水漏れがあるという。 今回、タンク間をつなぐ配管からも水漏れがあったという。私:「原子力村」のような傲慢な技術力を反省して日本に未だある「謙虚な優秀な技術力」を結集して対応してもらいたいね。 成功すれば世界も日本の技術力を見直すだろう。
2013.09.02
コメント(0)
-
シリア攻撃と化学兵器使用の真偽
私:シリア問題に興味を持ち始めたのは昨年10月だ。 それまで、シリアは俺にとっては謎の国だったね。 しかし、世界の紛争の中心地になるのではないかという予感があった。 A氏:それから、君のブログの「シリア知的街道」が始まるね。 「シリア内戦 世界の発火点になる前に」、「シリア・アサド政権の40年史」その1・その2・その3・その4・その5、「シリア内戦とアラブ原理主義の反政府軍の一派」、「シリア旅客機、トルコ空港に強制着陸」、「シリア機強制着陸問題・その後」、「シリアの近未来・『アルカイダ化』迫る現実」、「シリア内戦・代理戦争化」 と続くね。私:特に「シリア・アサド政権の40年史」はシリア問題を理解するに重要な基礎知識となって、今、直面している米国のシリア攻撃を理解するのに役だっているね。 ところで、シリアは、「シリア・アサド政権の40年史」その3にあるように、第4次中東戦争ではエジプトとともに、イスラエルと戦うが、エジプトは裏切ってイスラエル側につくね。A氏:そこで、シリアはいくらロシアの支援があると言っても米国の支援があるイスラエルには不利だ。 そこで考えたのが「蜂の一刺し作戦」で、ミサイルの弾頭に化学兵器をつける。 世界中に金銭でこのような軍事技術を供与してくれるのは北朝鮮しかない。 そこで、金日成当時の北朝鮮との関係が始まるね。 1994年の金日成の葬儀にはアサド大統領(現大統領の父親)は、北朝鮮大使館に弔問に出かけている。 A氏:「シリア・アサド政権の40年史」その4によると、2007年9月6日深夜、シリアのアル・キバル村の施設が何者かによって爆撃された。 米国の報道機関は、シリアが北朝鮮の協力により建設中だった原子炉をイスラエルが爆撃して破壊したと報道した。 広島、長崎の原爆被害のイメージが強いのかイスラエルは核兵器にものすごく神経質だね。 しかし、シリアは、これは捏造だとした。 この問題の真相は未だに明らかでないようだ。 私:今度のシリアの化学兵器の使用も事実はまだ、よくわからない。 「シリア・アサド政権の40年史」その4、その5でもふれていたが、今のシリア報道では外国報道を含め、シリア政府非難には捏造が多いという。 米国が、イラクの大量破壊兵器の保持のデマに迷わされたようなことにならないように慎重さが必要だね。 もっとも、イラクのときは大量破壊兵器問題がなくても、ネオコンのフセイン憎しが先にあったようだがね。。 当時、ネオコンはイラクの次はシリアだという話もあったくらいだ。 ネオコンではないオバマ大統領の決断はどうなるかね。
2013.09.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1