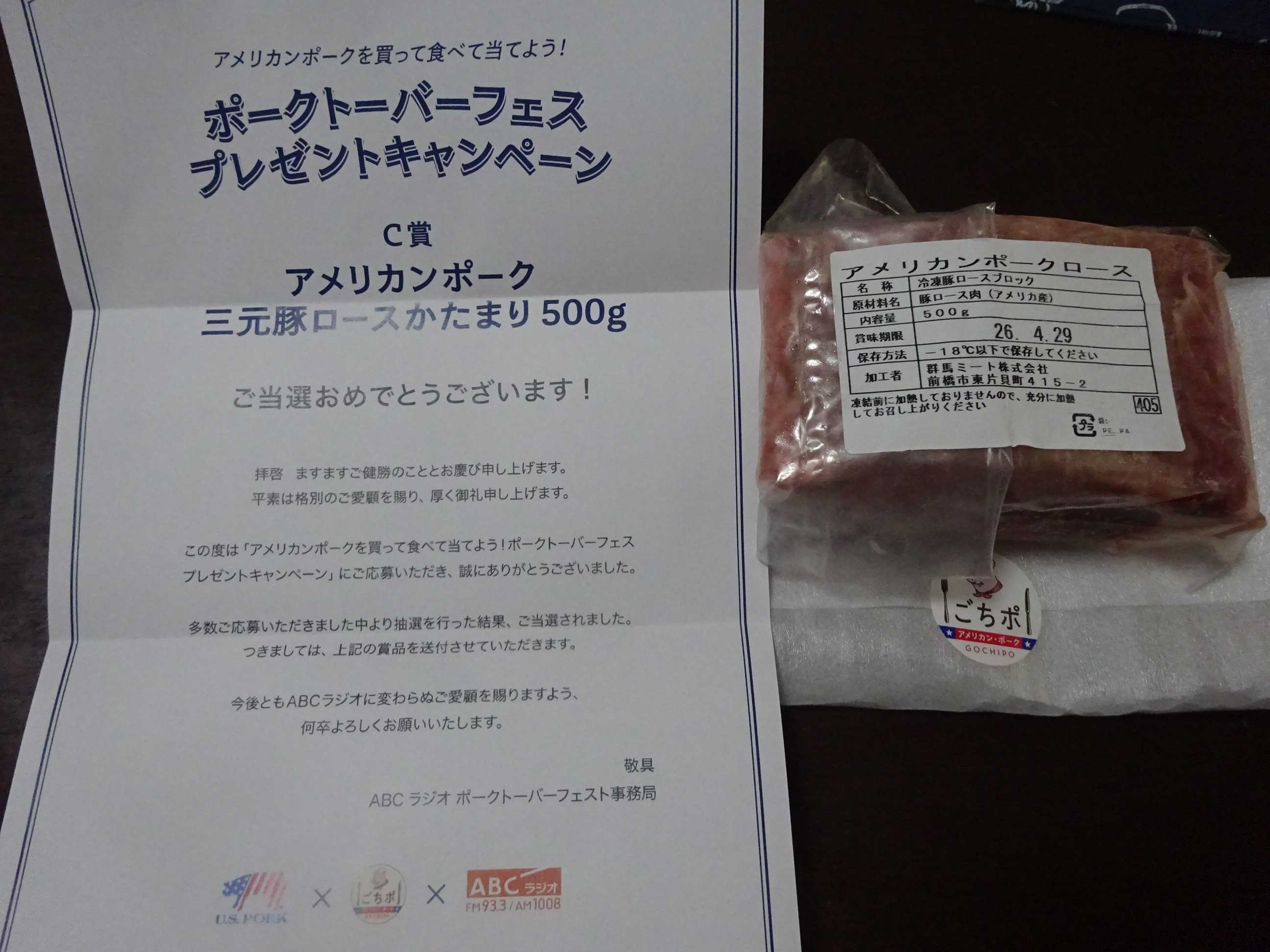2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年08月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
感即動
人は、感じたら動く。「感即動」とは、「感じたら、すぐに動く」という意味だけではない。「感じさせることで、人は動く」という意味がある。感じさせなければ、人は動かない。理性で説得しても、人は動かない。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。
2006年08月30日
コメント(0)
-
最高の出逢いとは
最高の出逢いとは、自分を最も輝かせてくれる人との出逢いです。人生は、出会いによって作られる。人との出会い。物との出会い。出来事との出会い。いろいろな出会いにより、道が決まっていく。学生の頃、ある教科の先生にあこがれて、その教科が好きになり、いつの間にか先生になりたいと思った人。天体望遠鏡を買ってもらったことで、毎日、星を眺めているうちに天文学の道を歩み出した人。自己や病気という出来事との出会いで、医者になった人。心の底から興味関心好奇心が湧いてきて気がついたらその道を歩んでいた。最初は興味も関心もなかったけど、縁あってある会社に入社したことにより、一所懸命仕事に取り組んでいくうち、興味関心が湧いてきて、知らず知らずにその道の専門家になることもある。縁は、自分から求めて作れるものではない。人智を超えた「計らい」によって与えられるものである。今、自分の目の前にある問題から逃げずに努力を続けることが、縁を呼び寄せます。自分のしたいことがわからない。そんな時は、今与えられている仕事に全力を尽くす。必死にやってみる。そこから、新しい道が見えてくることがある。考えているだけではダメ。とにかくやってみる。必死でやってみる。必死でやっていると、新しい出会いも生まれるもの。
2006年08月28日
コメント(0)
-
18年 思風塾全国大会のお知らせ
思風塾の会員以外の方もご参加いただけます。現在思風塾は、全国で30ヶ所。今回は、「思風塾ひろしま」の主催で、開催されます。広島は、芳村思風先生が、21世紀日本の使命の中で、「日本は、世界平和のための盟主にならなければいけない。なぜなら、世界唯一の被爆国としての体験をしている。被爆地広島から、今世界平和を発信することに意味がある。」と話されています。広島市民は、原爆を落とされたことに対する怒りや恨みを、投下したアメリカに向けるのではなく、「2度と同じような体験をする人が出ないように、戦争のない世界にしなければいけない」と怒りや恨みを「平和」へのメッセージに変えています。その広島で、「愛」とはなにか?「平和」とはなにか?について、芳村思風先生が2時間たっぷりとお話いただく予定です。年末にむけてお忙しい時期とは思いますが、ご参加宜しく願いします。 思風塾全国大会 in 広島テーマ「愛と平和」講師:芳村思風~平和発信の都市広島で、「愛」を考える時間をもってみませんか?日時:平成18年11月25日(土)11:00~12:00 平和公園・原爆資料館見学( 14:00~17:00 芳村思風先生講演17:15~18:00 塾生実践報告・講評・質疑応答18:30~20:30 記念パーティ ※ 講演会からの参加もOKです。会場:広島東急イン730-0029 広島市中区三川町10-1TEL 082-244-0109参加費:講演会・・・・・・・・・・5,000円 記念パーティ・・・・・8,000円(「感性論哲学の世界」・「遷都論」書籍含む)ゲスト:行徳哲男先生 岡部明美先生お申し込み・問い合わせ思風塾全国会事務局TEL 03-5755-1471FAX 03-5204-9236
2006年08月25日
コメント(0)
-
教育とは・・・
教育とは、命の中にあるものを引き出すこと。教育とは、学ぶことを喜びとさせること。教育とは、成長する喜びを味わわせること。どんな子どもにでも天分・素質がある。同じ顔の人はいない。ひとりひとりの顔が違うと言うことは、自分しか出来ない能力があることの証明。理性能力は、他人が作ったものを覚えて使う能力。潜在能力は、理性を超えた能力。潜在能力引き出し方は、天分発見の方法
2006年08月23日
コメント(0)
-
そうだよね。わかるよ。
人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。
2006年08月22日
コメント(0)
-
経営者は、お客さまのために仕事はするな
経営者の仕事は、会社を経営すること。会社は、社員で成り立っている。経営者は、社員のために存在する。社員のために仕事をする。社員は、お客様のために仕事をする。経営者は、社員と家族の生活のために働くという姿勢を常に示さなければいけない。経営者は、顧客のために仕事をしてはいけない。どの会社の社員よりも、自分の会社の社員を幸せにすることが一番の喜びでなければならない。会社がよりよい方向に変化していることを、常に社員に実感させる行動し、結果を目に見える形で示すことが大切である。「社員のためになら死ねる」という経営者の元にしか「社長のためなら死ねる」「この仕事のためになら死ねる」という社員は育たない。経営者の5つの問い・利益の出る仕組みを作り続けているか?・よりよい方向性への変化を作り出し続けているか?・出てくる問題を乗り越え続けているか?・感性から湧き出した理念を大事にしているか?・本業を通して、会社と社員を発展成長させているか?
2006年08月20日
コメント(0)
-
円熟ではなく角熟をめざす
角熟人間は、出会いによってつくられていくもの。出会いによって、自分の持っている潜在能力が引き出され長所となって現れる。長所は、自覚的に作られるものではなく、出会いによって決まるものです。出会いは、行動することで生まれてくるもの。人間は、長所半分・短所半分。長所をつかんだら、その能力をいち早くよりずば抜けたところまで伸ばすのが、本当の自分をつかむ近道。長所を伸ばすことによって、それをずば抜けたものとして、その結果、「短所が、味に変わる」これを「角熟」という。人間は、まるくならなくてもいい。人間は、まるくならないということを前提に角張ったまま熟していく生き方を理想とします。
2006年08月19日
コメント(0)
-
誰も、この苦しみを、この気持ちを、わかってくれない。
誰も、この苦しみを、この気持ちを、わかってくれない。誰も僕の事を本当にわかってくれない。この思いは、誰の胸にも、死ぬまでつきまとうものである。人間は、本質的に、根本的に誰でも、皆、さみしいのである。孤独なのである。しかし、又、人間はこの誰にも理解されない心をかかえて人と共に生きて行かなければならない存在である。そこで人間は、人と共に生きる為に人に語りかけ、話しあい、理解しあえるよう努力するのである。いや、努力しなければならないのである。なぜなら、みんな同じ人間であるからだ。この、孤独である人間が互いに理解しあおうとし、その為に全人類に共通する真実を求め、それを手がかりに助け合って生きようとする努力、これこそが他ならぬ哲学なのである。主義主張で対立する事が哲学なのではない。
2006年08月18日
コメント(0)
-
時流独創の精神
時流独創の精神 6つの問い1.自分の心を本当に納得させるものを理屈ぬきに追い求めているか?2.固定観念・先入観念から自分を解放しているか?3.自分の使命は何であるかを知っているか?知ろうとしているか?4.命から湧きあがる欲求・欲望・興味・関心・好奇心を持っているか?5.現実への異和感を大切にしているか?6.有機的統合能力を磨いているか?”問い”について感性論哲学では、「問い」(といかけ)がたくさんあります。「時流独創の精神とは・・・」=「~である」ということなのですが、「問い」の形にする事により、実行できているかどうかを自分で確認することを習慣づけるためです。これは、「答え」を持つことは大切なのですが、その答えに縛られないためです。答えに縛られると、他の答えを排除する、否定する、説得しようとする・・・そこから対立が始まります。答えを持ちながらも、よりよい答えを求め続けること。違う答え・考え方から、自分の答え・考え方を進化発展させること。そのために「問い」の形になっています。
2006年08月17日
コメント(1)
-
愛は感じるもの
真実の愛は、努力してつくっていくもので、その努力に愛の価値があるのです。相手のために払った努力の量と質が愛の重みを決定するのです。そして、その努力を愛と感じるのが、人間の愛であると言えるのです。愛は感じるもの。感じなかったら愛ではありません。また、愛を感じさせることによってしか、愛は存在し得ないものです。
2006年08月16日
コメント(0)
-
新しい倫理観
【新しい倫理観】●「偏見をなくそう」から、「偏見はなくならないし、誰でも持っている」自分も偏見を持っているいうことを強く自覚して生きる●「我を捨てましょう」から「我を捨てれば人間ではない」自分の自我を成長させる生き方をする●「物欲を捨てろ」から「物欲を人間的な品格のあるものにしよう」欲が歴史を作っていく。●「足るを知る」から「より高度な足るを知る」へと昇華させていく。とらわれずに、求める姿勢。不完全であることを自覚し、「足らざるを知る」ことも大切●「短所をなくせ」から「短所はなくさず、長所を伸ばして、短所を味に変える」短所があるから人間である。短所があるから謙虚になれる。短所の自覚がない人は、傲慢になる。
2006年08月15日
コメント(0)
-
新しい時代
今、まさに一つの時代が終わろうとしている。二十世紀の理念に生きた巨星が、一人また一人とその輝かしい時代に別れを告げて去って行く。世界の文明は、あらゆる分野において危機に直面しており、深まり行く混迷の中で人々は不安に包まれている。終焉とはさみしい言葉である。喜びは短く、悲しみは長い。喜びは努力しなければ得られないが、悲しみは努力なしにやって来る。人生とは、その大半が苦から楽への、悲しみから喜びへのプロセスである。人間の価値は、このプロセスそのものにどれ程の生き甲斐を見い出し得るかにかかっている。世界は、今後、苦しい不安定な動乱期を経験しなければならないであろう。しかし、それは決して悲しむべき時代ではない。むしろ、動乱期こそ最も素晴らしい時代である。すべてのものがそこから生まれ、あらゆる新しいものがへの可能性をはらんだ生き甲斐のある時代世界中の若人が待ちに待った、夢多き時代がやってきたのである。
2006年08月13日
コメント(0)
-
哲学とは・・・
誰も、この苦しみを、気持ちを、わかってくれない。誰も俺の事を本当にはわかってくれない。この思いは、誰の胸にも、死ぬまで付きまとうものである。人間は、本質的に、根元的に、誰でも、皆、さみしいのである。孤独なのである。しかし、また、人間は、この誰にも理解されない心を抱えて人と共に生きて行かなければならない存在である。そこで、人間は、人と共に生きる為に人に語りかけ、話し合い、理解し合えるように努力するのである。いや、努力しなければならないのである。なぜなら、みんな同じ人間であるからだ。この、孤独である人間が互いに理解し合おうとし、その為に、全人類に共通する真実を求め、それを手がかりに助け合って生きようとする努力、これこそが他ならぬ哲学なのである。主義主張で対立する事が哲学なのではない。哲学とは、助け合って生きるための学問である。宗教の違い、人種の違い、考え方の違い、価値観の違い、文化の違い、風習の違い、・・・様々な違いを受け入れる。説得しようとするから、対立が起きる。正しさを主張するから、対立が起きる。お互いいいところを取り込んでお互いに成長する。
2006年08月12日
コメント(0)
-

愛とは・・・
愛とは短所を許し補い、長所と関わる力である。古来より、「愛」は、文学の中でしか扱われていなかった。学問として体系化されていない。感性論哲学では、愛を実力としてとらえ、成長させるものとして考えています。愛とは感じるもの 愛とは信じること愛とは許すこと愛とは肯定すること。理屈を超えた肯定の心愛とは認めること愛とは相手の成長を願う心情新しい精神文明の核となるもの愛は理屈を超える力。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者と共に生きる力愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。相手のために努力できるということが「愛」があるということ。相手のために努力できないのは「愛」がないということ。人間を愛するということは、不完全な存在(長所半分・短所半分)を愛するということ。短所を許すことから、人間の愛が始まる愛は人間関係の力である。人間関係の基本は愛。結婚は恋の墓場であり、愛の始まりである。人間を愛するというのは不完全な存在を愛するということ。不完全とは、どんな人間でも長所半分・短所半分。愛するとは許すこと。相手の短所を許し、長所を見つけてほめて伸ばしてますます好きになる。長所が伸びたら短所は人間の味に変わる。自分と同じ考え方の人しか愛せないのは、偽者の愛。それは自分しか愛せない愛である。愛は本来、他者を愛するために存在する。愛とは 命の能力である。命は愛によって生み出され、育まれ、満たされる。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。愛するとは、相手から学ぶこと。相手のために努力できるということが「愛」があるということ。相手のために努力できないのは「愛」がないということ。人間を愛するということは、不完全な存在(長所半分・短所半分)を愛するということ。包容力は、愛。今、一番人類に必要とされている能力芳村思風先生が、愛について話された言葉を集めてみました。(ちょっと同じ言葉がいくつか重なってしまいました)
2006年08月11日
コメント(0)
-
人生の3つの問い
感性が問い、理性が答え、体で実現する。感性論哲学では、「問い」を大切にしています。最も大事な問いは、「人生の問い」といわれます。 人生の3つの問い ・将来どんな人間になりたいか ・将来どんな事をやりたいか ・将来どんな生活をしたいか答えを持つことは、大切なこと。この3つの問いに理性できちんと答えを出す。しかし、もっと大切なことは、実行すること。行動すること。やってみて、再び問う。これでいいのか。問い続けること。「なぜ私は、生まれてきたか?」「誰もが、その人でなければ出来ない大切なお役目を持っている。そのことで時代を一歩勧めるために生まれてきたのです。新しい歴史を作るために生まれてきたのです。」
2006年08月10日
コメント(0)
-
生きるとは
生きるとは 人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。人間において生きるとは、何のためにこの命を使うか、この命をどう生かすかということである。命を生かすとは、何かに命をかけるということである。だから生きるとは命をかけるという事だ。命の最高のよろこびは、命をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。その時こそ、命は最も充実した生のよろこびを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。君は何に命をかけるか。君は何のためなら死ぬことができるか。この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である
2006年08月09日
コメント(1)
-
年代別教育論
年代別教育論A.0~3歳 赤ちゃんの心に、本当に安心して生きていったらいいんだ という安心感と信頼感をしみこませる。 生きる事の原点である信じる力を傷つけずに維持する。 スキンシップを通じて子供に充分な信頼感と安心感、 愛を感じさせる。B.3~6歳まで(第一反抗期) 行動力と自制心(倫理観・善悪正邪の区分の基礎)を創る ことを目的に教育する。C.6~10歳まで(善悪正邪の区分) 子供が主体的に人間的判断をするための土台となる 大人の持っている常識としての善悪正邪の区分を しっかり教え込む。D.10~13歳まで(過渡期) 親は、先生を批判したりけなさず、先生を誉めて好きにさせる。E.13~15歳まで(第二反抗期) 何か質問されてもすぐに答えず、一緒に調べたり、 どのようにすれば答えが出るか、その方法を教え一緒に考える。 この時期に必要なことは、主体性と責任感の二つを作ること。 人格に目覚める頃だから、子供の人格を認めて接することが大切。F.15~20歳まで(自分で自分を教育する) 「自分で自分を教育することを教える。 目的を与えることが大切で、 「将来どんな人間になりたいか」 「将来どんな仕事がしたいのか」 「将来どんな生活がしたいのか」 を問い、考えさせる。G.20~30歳まで 30歳までの人間には、大宇宙の偉大な進化の力が働いている。 「個性を磨きだす」 「常識で考えるのではなく、常識を考える」 「自分に与えられた使命を自覚する」 ことによって創造力を湧き出させる。東京思風塾ホームページ
2006年08月04日
コメント(0)
-
教育論概論
教育の方法は、感性を人間化させるために手段能力として理性を使うことである。教育の理念は、育てるために教えるということである。教が育を越えてはならない。人間らしい心を創る最も本質的なものは、価値を感じる感性である。教育とは教育とは今出来ないことをできるようにすることです。自らの力で、「出来た!」「わかった!」という喜びと感動を味あわせることが、何よりも大切なのです。1.「教が育を越えてはならない」 引っ張り出すために教えるのであり、能力を開発するために 教えるのだから、教が育を越えてはならないのです。 その人間が持っている資質・素質を歪めないで引っ張り出してあげる。 あるものを引っ張り出した上げるために、教えるということを 方法・手段として行うということを忘れてはならない。 社員教育でも、自分が教えようとしていることに対して、興味や関心を持たせるということが大切なのである。すべてを教えて、それを習得させて、暗記させてそれでそれをその通りにやらせるのは機械を作る方法であって、人間をつくる方法ではありません。人間をつくる方法というのは、興味や関心を引き出してあげて興味や関心をもちだしたら、自分で勉強をはじめるという状態に持っていってあげること。それが教育者の腕であるのです。大切なことは、興味・関心・好奇心・欲望を呼び覚ますために教えるという行為をするのだということです。だけども残念ながら、今日それがなされていない。その結果、何がしたいのかわからないという、そういう青年ばかりが社会にでてきてしまっているということになってしまっているのです。2.理性という能力を関心や欲求を呼び覚ますために使って教育する大切なのは、育て方。問題を与えて、子供に考えさせるシステムは、間違っている。問題というのは、子供の中から出てこなければなりません。遊びも大事な教育方法のひとつです。自由奔放に遊ばせて、その遊びの中から自分がいろいろ創意工夫してやっていくということが出来るようになっていくのです。遊びの中で、問題にぶつかった時、それを「どうしたらいいのかなぁ」と思って、創意工夫することが、知恵をつくるのです。社員教育でも、「社長の好みの人間をつくるための教育」「自社にあう人間にするための教育」では、画一化された人間しか会社に存在しなくなります。経営者にとっては不都合でも、基本だけはきっちり押さえて、あとは自由奔放にその社員の能力を引っ張り出し、その出てきた能力にふさわしい仕事を与えることも経営者の仕事です。教えなければいけないのは、知識ではありません。意味や価値や値打ちや素晴らしさ・・・どこにおもしろさがあるのか、どこが素晴らしいのか、それが出来たときどんなふうになるのか、知識ではなく、意味や価値や素晴らしさを感じることを教えるのです。興味や関心や好奇心を湧き上がらせることが出来ればあとは放っておいても自分で求めはじめるのです。3.自分がそのころどうであったかということを思い出しながら教育する。4.子供は、空なる気を吸って育つ人間は、空気を吸って生きています。空気とは、空なる気なのです。目に見えないのです。気とは、感性です。空気を吸うとは、目に見えない感性を吸っているということ。意味や価値や値打ちは、感じるもの。教育においていちばん大事なものは、言葉ではないのです。一番大事なものは、空間がというものが与える、意味や価値や値打ちなのです。それは、目つき・表情・態度です。子供は、お父さん・お母さんが、自分に対してどんな目つき・表情・態度で接してくれているかが、最大の意味や価値や値打ちをもつのです。言葉にふさわしい目つき・態度・表情で子供に接する事が大切なのです。言葉は理性です。目つき・態度・表情は、完成です。感性はウソが言えません。そして、空間はまさに感性の海なのです。理屈を越えた雰囲気というものをつくるのは、目つき・態度・表情なのです。感性だからこそ伝わるのです。5.教育する側の生きる姿勢大切なことは、親や教師や教える側の生きる姿勢です。生きる姿勢とは、どういう問題意識をもってその人が生きているのかということ。父親とはいったい何なのか、母親とはいったい何なのかそういう「自分自身の存在への問い」を常に自分で持ちながら生きているかということ。このような姿勢が非常に大切な問題です。子供は、親の背中を見て育つということもそのひとつです。お父さん・お母さんが、どういう生き様、どういう気持ち態度で、人生を生きているかということです。経営者であれば、経営者自身がどういう意識、どういう自覚を持って生きているかということが、非常に大きな教育効果をもっています。人間の存在そのものが、無意識のうちに他人に対する教育的効果をもち、社風をも作っているのです。自分で自分を律する、自分の哲学、生き様、立居振舞言葉使いが、自然に全体に対して、教育効果をもっていて、ものすごく大きな教育力・感化力を発揮しているのです。<明日は、0歳から30歳までの実践論です>東京思風塾ホームページ思風塾ホームページ
2006年08月03日
コメント(0)
-
感性論哲学は、実践哲学
「感性論哲学は、実践哲学です!」「感性論哲学は、実践哲学です。現場の経営に活かせなければ意味がない。哲学は、破壊の学問。哲学は、パンクです。現状に異和感を感じ、現状を破壊し、新しい物を構築する。哲学は、自分自身の芯を作るもの。セミナーを受講した後どう動くかが大切。セミナーを受けるだけなら、お金のムダ。」常に「これでいいのか?」と問い続ける。 変化が、成長を作り出す。すべてを固定させる必要はない。自社の理念もその役割を果し終えたとき、進化発展させなければならない。固定させなければいけないことはない。変化しなければ、生きているとは言えません。生きているとは、変化していること。経営者・リーダーは、変化を作り続けることが仕事。どんな小さなことでもいい変化させる。朝、会社に行けばカーテンが替わっている。階段にスベラーズが貼ってある。机に花が活けてある。社員の誕生日・奥さんの誕生日に社長から花束を贈るようにする。社員のために、社員が働きやすいように会社を変化させ続ける。社員は、お客さまのために働く。経営者は、社員のために働くこと。哲学は、考える学問ではない。自分の考えの芯をつくるもの。実践に活かせなければ意味はない。感性論哲学は、実践哲学。現実の中から違和感を感じとり、問題を感じ取る。出てくる問題を乗り越え続けること。問題がないことを望んではいけない。問題がないとは、成長がないこと。問題がないことが、幸せではない。しっかりした芯を持っていれば、多少のことでは考えは、ぶれない。乗り越えていける。セミナーで学んだこともすべてを取り入れる必要はない。感性論哲学も自分にとって必要なところだけを学んで、取り入れればいい。考えは、変えなくていい。変えてはいけない。取り入れて、自分の考えを成長させること。大切なことは、実行すること。実践すること。変化を作り出すこと。現状から1歩でも進むこと。
2006年08月01日
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1