2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年12月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
感動・感即動
人は、感じたら動く。「感即動」とは、「感じたら、すぐに動く」という意味だけではない。「感じさせることで、人は動く」という意味がある。感じさせなければ、人は動かない。理性で説得しても、人は動かない。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。
2006年12月27日
コメント(1)
-
問いをもつ
理性は答えを出す力感性は問う力感性が問い、理性が答える答えを持つことは大切もっと大切なのは、「これでいいのか」と問い続けること答えに縛られないこと縛られると、違う考え方の人を説得しようとする違う考え方の人と対立する感性論哲学は、どんな考え方・意見も否定はしない相手の考え方・意見のいいところ、自分の考え方にないところ、を取り入れて、自分の考え方・意見を成長させる。・・・・・・先生からこの話を聞くまでは、答えを出すことが一番大事だと思っていた。自分の考え方・意見と違う考え方・意見を説得しようとしたり、否定したりしていた。ディベートで勝ち負けを競っていた。勝つだけではダメなこと・・・人間関係の破綻はすべて競争意識から始まっていた負けず嫌いが功を奏したこともあったけど、いい面ばかりではなかったいつも勝ち負け、他人との比較をしてきた先生は、こんなこともおっしゃっている。「感性論哲学もすべて受け入れなくてもいいんですよ」自分の気に入るところ、合うところだけを取り入れたらいいんですよ。すべてを取り入れたら、自分がなくなりますよ」
2006年12月27日
コメント(0)
-
天はオレを大人物にしようってか?
問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。<「にげたらあかん!」/font>
2006年12月26日
コメント(2)
-
人間教育の本道 2
●子供の問題行動への対処方法1.子供は、悩みを持っても大人に相談しないということを知る。大きな悩みであればあるほど相談しない。人間は自分で乗り越えないと、命が成長しないということを本能で知っている。日常と違うところを見つけたとき、変化の原因を探す努力をする。自分では解決できないけど、心の底では早く誰かに自分の気持ちを理解して欲しいわかって欲しいと願っている。しかし、親が聞いても、子供は「なんでもない」と答えてしまう。子供の小さな変化を見つけ、理解してあげることが大切。2.反抗しない子が、いい子ではない。反抗する子どもが、正常だと理解すること。親に反抗しながら、自分を作っていく。親離れ・子離れの時期。反抗することが悪いことではない。反抗しない子供は、いつまでも親離れできない。両親を愛している、両親が好きな子供であればあるほど、親のために我慢しているということを理解してあげる。従順で素直であることは、ストレスにもなる。我慢していることに対する感謝の気持ちを伝えて子供の気持ちを理解して接してあげる。反抗は、新しい時代を作る行動。否定するだけでなく、理解しようとする努力も必要である。明治維新も古い体制・慣習を壊そうとした若者の行動の成果。当時の権力者から見れば、反社会的な行動だった。社会的にも批判されることが多い。そういった犠牲の上に新しい時代が作られる。反抗を恐れないことも親の愛。子供のために自己犠牲的な努力ができる覚悟が必要。子供を守る・成長させることが親の喜び。相手のために努力できることが、愛。真実の愛とは、相手のために自己犠牲的努力を喜びとできること。これが究極の愛の形である。反抗させながら、それにどう対応していくか、反抗を喜ぶような対応。「まだまだ子供だと思っていたのに、そんなことまで考えるようになったのか」と反抗を成長として認めてあげる。その考え方を成長させるために子供と関わる。子供の考え方のレベルが低い・間違っているとは捉えず、子供が望む方向への出会いや勉強の方法を考える、お金を出してあげる。ムリに自分の考えと同じ方向へ引き込まない。親の考えが正しいという判断はしない。価値観を押し付けない。3.ぐれた子供や悪いことをした子供にそれをやめさせることは、かえって悪くさせてしまう。子供は、悪いことをしているという自覚がある。「悪いことをしてはいけない」というだけではだめ。なぜそんなことをしなければならないのかという原因を知る。その心情をまずわかってあげる努力をすること。結果に至るプロセスを理解することにより、どう対応すればよいかを考える。
2006年12月25日
コメント(0)
-
人間教育の本道 1
人間教育の本道『教育は、国家盛衰の要。起業消沈の因。一家存亡のカギを握る大事業である。』人間における最も価値ある仕事は、人を育てること。子供を立派な人間に育てること。企業においても社員を有能な社員に成長させることが、企業発展のカギである。経済は、資本主義経済から人格主義経済へ変わらなければならない。教育力が低下している。父権の失墜。母性の喪失。育児本能が衰退している。●今、なぜ教育の問題がでてきたか。1.分業による教育のアウトソーシングの原因父母が教育の現場に携わらなくなってしまった。解決策 ・職住接近 ・起業が夫婦で採用し、会社内に託児所を作る社会・企業のあり方を変えていく必要がある。社会構造の転換が必要。2.理性を成長される教育により、本能が衰退していた。 ・母性本能の衰退 ・育児本能の衰退本能は、遺伝的に決められたことしかできない。理性は、よりよいことを考える力。理性が成長すると本能は、じゃまになる。理性が成長することにより、本能が衰退するのであれば、本能よりももっとすばらしい力を人間の力で文化として作っていく。3.科学の発達により、あらゆる問題を客観的に見る力がついたために、自分と切り離して見るようになった。対象と一体になる。理屈抜きの愛の精神がなくなってきた。自分の子供に対しても、他人の子供のように批判的に見るようになってきている。子供がいることにより、自分が遊べなくなったと感じる人が増えている。母乳で育てると、体系が崩れると嫌がる。命の一体感がなくなっている。・子供が万引きでつかまった。警察で父親が言った言葉。「おまえがそんなことをしたら、おれは会社や近所での立場がなくなる」と子供を責めた。この父親は、子供の事ではなく、自分のことしか考えていない。・子供がウソをついた。「ウソをつくことは悪い!」と責めるだけではダメ。「子供が、ウソを言わなければいけない状況に自分が追い込んだ。もっと早くそんな気持ちを気づいてあげられなかったおとうさんを許してね。ごめんね。」と言えるかどうか。そして、「だけど、ウソはいいことではないんだよ。この次同じようなことになったときは、お父さんに話して欲しい。一緒にその問題を乗り越えられるようにしていこう」と必ず付け加えなければいけない。甘やかすだけではいけない。4.時代の大きな変化により大人が子供たちに与えようとしていることと、子供の心が求めている内容が一致していない。教育が無力化している。子供たちが先生の教えることに興味を示さない。子供が知りたいと興味・関心をもつことを学校では教えていない。自分本位な相手に対する接し方。相手のことを「わかっているつもり」で接している。未来は子供たちの手の中にある。子供たちに迎合するのではなく、未来を作るために、未来を与えるための教育とは何かを考える必要がある。5.子供の反抗を許さない・抑える・恐れる意識が大人にある。子供は、親・先生に反抗しながら、自分を確立していく。大人に従順なだけでは、新しい歴史は作れない。反抗させながら、子供と一緒に成長していくのが教育である。反抗を恐れては、真の人間教育は成り立たない。大人の考え・価値観を一方的に押し付けて、それに従わないと×をつける。反抗を許さないことが、家庭内暴力や構内暴力につながる。
2006年12月24日
コメント(0)
-
そうだよな、わkるよ
人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。
2006年12月23日
コメント(0)
-

愛とは
愛とは短所を許し補い、長所と関わる力である。古来より、「愛」は、文学の中でしか扱われていなかった。学問として体系化されていない。感性論哲学では、愛を実力としてとらえ、成長させるものとして考えています。人間を愛するとは、不完全な存在を愛すること。どんな人間にも長所が半分あり、短所も必ず半分はあります。自分にも短所はあるのです。人間を愛するということは、その人間の長所・短所すべてを愛するということ。お互い半分ずつ嫌な所を持っている。だからこそ、お互い許しあって、生きていかなければいけないのです。相手のために努力できるということが、「愛している」ということ。相手のために努力し続けることが、「愛がある」ということです。短所があることを認めて許すこと。その上でお互いの長所を見つける努力をし、ほめあうことで成長していく。愛とは、人間と人間を結びつける力。愛の目的は素晴らしい人間関係をたくさん作っていくことです。感性論哲学の講義の中で出てくる「愛」についての言葉を集めてみました。よく似た表現が重なっているかもしれませんが・・・愛とは感じるもの 愛とは信じること愛とは許すこと愛とは肯定すること。理屈を超えた肯定の心愛とは認めること愛とは相手の成長を願う心情新しい精神文明の核となるもの愛は理屈を超える力。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者と共に生きる力愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。相手のために努力できるということが「愛」があるということ。相手のために努力できないのは「愛」がないということ。短所を許すことから、人間の愛が始まる愛は人間関係の力である。人間関係の基本は愛。結婚は恋の墓場であり、愛の始まりである。人間を愛するというのは不完全な存在を愛するということ。不完全とは、どんな人間でも長所半分・短所半分。愛するとは許すこと。相手の短所を許し、長所を見つけてほめて伸ばしてますます好きになる。長所が伸びたら短所は人間の味に変わる。自分と同じ考え方の人しか愛せないのは、偽者の愛。それは自分しか愛せない愛である。愛は本来、他者を愛するために存在する。愛とは 命の能力である。命は愛によって生み出され、育まれ、満たされる。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛するとは、相手から学ぶこと。包容力は、愛。今、一番人類に必要とされている能力
2006年12月22日
コメント(0)
-
夫婦の愛の10か条
●夫婦の愛の10か条 男女の愛は、「この人のためなら死ねる」という心情 親子の愛は、「どんなことがあっても子供を信じぬく力」 この二つの愛の交差するところが、夫婦の愛である1.家庭も人間的成長のための道場である 家庭の中で、自分を人間として磨いて成長していこうとする意識が大切。 子供が生まれて、父親母親になれる。 子供が悪いことをして、父親としての役割を学ぶ。 夫婦げんかを通して、相手の気持ちを学ぶ。2.どうせするなら心をこめて 惰性に流されないこと。3.共通体験、共同体験を積み重ねる努力 同じ体験や一緒に何かをすること。4.夫婦と言えども、元は他人 夫婦の仲にも節義、節度をわきまえた関係性であること。5.家庭とは、理屈抜きに信じ合い、許し合って生きる場である 家庭は、不完全な人間が安心して帰れる場所でなければならない。 理屈で責め合えば、地獄。理屈を持ちもまない。 理屈を超えた愛を作る場である。 6.結婚という決断に人生をかける 「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。 「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。 捨てる勇気のこと。 オレ、私には、この人しかいないという気持ちが大切。7.子供の存在を強く意識すること。子はかすがい。 子供がいるから、父親母親になれる。 子供のことを思えば、問題も乗り越えられる。 親としてのあり方を自覚させてくれる。8.セックスは人生の三分の一の重みを持つ重要課題 セックスは、人生の1/3の重みを持つ課題。 仕事1/3・生活1/3・セックス1/3 セックスとは、単なる性交渉ではなく、男女のふれあい・命のふれあいのこと 抱きしめることの大切。相手の欲求を満たす努力が必要。9.理念への問いをお互いに持つ 理念とは、夫・妻とは、いかにあるべきか? 父親・母親とは、いかにあるべきか? 真剣に人生を歩き始めた時、命のそこから湧いてくる問いを問い続けること。 10.人生には、失敗の人生はない 人生は、体験の連続。体験とは、真実を語る力。 体験は、やった人間しかわからないものを教えてくれる。 体験には、マイナスがない。 体験の数だけ、幅ができる。 体験の数だけ、重みができる。 体験の数だけ、厚みができる。 体験こそ人生の宝である。最高の愛の形とは 父性愛 母性愛 男性は、父性を極める。 女性は母性を極める。 男は、万物の父となれ。 女は、万物の母となれ。
2006年12月21日
コメント(3)
-

幸せとは・・・
幸せは感じるもの。幸せを求めている間は、幸せにはなれません。今あることに幸せを感じられるかどうか。「悩み」「苦しみ」「問題」がなくなることを願っている人は、一生不平不満を言い続けなければいけない。「悩み」「苦しみ」「問題」がなくなることが「幸せ」になることではない。問題や悩みがあっても幸せ。問題や悩みがあても、当たり前と自覚するだけでも幸せに近づける。問題や悩みは、嫌だ・なくなって欲しいと思ったとき、そこから逃げてしまう。では、「問題から逃げずに、乗り越えていくためにはどうするか」1.今、自分が、おかれている状況を客観的に見る 問題を感じるのは、感性、 乗り越えるために理性を使う。自分の悩み・問題には、「どうしようもできない。もう死ぬしかない」と思いつめるような事でも、「死にたい」という人の悩みには、「死ぬ気になれば何でもできる。」とアドバイスできる。2.理性を使って、ものごとの意味や価値やすばらしさを考える「自分の周りに起きる出来事は、すべて自分にとっていいこと」だと思う。「運もツキも解釈力の問題」これは、「いいことだ」と思うといいことになってくる。問題から逃げず「苦しみ」「悩み」尽くしたとき、自分自身の中で母なる宇宙のエネルギーが目覚める。母なる宇宙のエネルギー = 潜在能力眠っていた潜在能力のスイッチがONになる。問題や悩みは、必ず答えがある。今ある能力では、どうにもならないだけ。なんとかしようと努力することで、成長する。今ある能力でなんとかなることばかりだと、問題も苦しみもなにもない。でもそれが幸せとは、限らない。完璧な人間はいないから、全く問題がないことは、ありえない。問題がない、問題に気がつかないことは、成長もないということ。それもまたつまらない人生ではないだろうか。
2006年12月20日
コメント(2)
-
命には、命より大切なものがある
「このためなら死んでもいい」「この人のためなら、命をかけても守る」、「この仕事になら、命をかけて取り組める」と思えるものと出会ったとき、命は最も激しく燃え上がり、最高に輝くのです。「この人のためになら死んでもいい」と思うくらい人を愛さなければ、本当の意味での愛のすばらしさを味わえない。相手からも「この人のためになら死んでもいい」と思ってもらえるような人間になるための努力を続けることも大切です。仕事でも、「この仕事のためになら死んでもいい」と思うくらいでなければ、本当の意味での仕事の醍醐味を味わっていない。理屈を越えたものであり、命の底から湧き上がってくるものです。理性で考えるものではありません。健康のことを忘れて何かに必死に取り組んでいるとき一番健康である。命は、知らないうちに病気を治していることもある。命には、命より大切なものがあるのです。・・・・・・・・・・・初めてこの講義を聴いたときは、意味がわかりませんでした。「命より大事なものがある」というのがピンとこなかったのです。家族のためなら、火の中にであっても何も考えず飛び込んでいくだろう。仕事のためにそれができるだろうか・・・今与えられた仕事や人間関係は、仮に自分のやりたい事でなくてもいろいろな縁が重なって与えられたものである。上司が嫌だから・・・好きな仕事じゃないから・・・と別のところに道を求めると、同じような問題が人と場所を変えてやってくる。今与えられたところで、必死になって取り組んだとき、新しい道も開けてくる。一所懸命にやっているかもしれないけど、必死にやっているか。
2006年12月19日
コメント(2)
-
真・善・美
感性の本質とは何か?感性の最も根本にある能力は、「感受性」ではなく、「求感性」(ぐかんせい)です。求感性とは、自分が生きていくために必要な情報を自ら積極的に求めて感じ取ろうとする働きのこと。感性の働きは、平衡作用=ゆらぎ・カオス・ホメオスタシス感性が、理性によって人間化されたものを「知的感性」といい、この知的感性こそが、私たちの心です。感性が良くて、理性が悪いのではありません。理性が、有限かつ不完全な能力であることを知ることが大切です。理性とは、よりよいことを考える能力。感性の3作用1.調和作用・・・善・・・人間関係や環境との調和・2.合理作用・・・真・・・目的を実現する為の最適な方法を模索する働き3.統一作用・・・美・・・全体を1個の命としてまとめ上げる
2006年12月18日
コメント(0)
-
あきらめたらあかん!
16日の東京思風塾のテーマは、「感性論哲学の体系」だった。今テーマで、これほど深く話されたのは、初めてだそうだ。「感性論哲学のすべて DVD18巻大全集」最後の収録だった。今まで、感性論哲学の全体系を書かれた本は無い。感性論哲学も、芳村思風先生自身も進化発展の途中だからだ。27歳で学生結婚。結婚に反対の両親からの仕送りがストップされた。子供が出来、生活費に困る毎日が続いた。夜中から、朝の5時までパン工場で、出来上がったパンをトラックに積み込む仕事をした。帰って、2~3時間寝て、9時に学校へ。午後は、さまざまなアルバトをした。そんなことが、何年も続いたとのこと。それでも20歳のとき、先人が作っってきた哲学に違和感を感じ、「感性」を研究しようと決めたことを貫き通したかった。哲学は、考えるだけの学問ではない。「どうしたら幸せになれるか」それを実践するための学問である。28歳の時、「人間の本質も、宇宙の本質も感性である」と気づく。命には、命より大切な目的がある。なぜなら、このためになら死んでもいいという物にであったときに命は最高に輝くから。苦しんで苦しんで、苦しんで、それでもなおあきらめずに必死になってやっていたとき、命のそこから湧いて来るものがあった。命は自分で作ったものではない。宇宙から与えられたもの。宇宙は母なる命。命を生かそうとする宇宙の力は、苦しんで、苦しんで、苦しみぬいた時働き出す。今でも講演の時、芳村思風先生は、メモやノートを見ることがない。与えられた時間、与えられたテーマで2時間でも3時間でも話をされる。ときどき沈黙の時間がある。初めて講演を聞いた人は、大抵ビックリする。長いときは、1~2分の沈黙が続く。話を考えているのではないらしい。湧いてくるのを待っている。本位サインを頼んだ時もそうだ。時間があるときは、じっと相手の顔を見たまま動かない。そんな時、何人も書かれた言葉を見て涙を流している。私と芳村思風先生の出会いのときもそうだった。その人にほんとうにピッタリの言葉が書かれる。感性論哲学は、頭で考えた哲学ではありません。実体験を通して得てきたものです。行徳哲男先生は、こう紹介された。「芳村思風先生には、他の講演者の方と違ってはなやかさはまったくない。それでも年間300回以上の講演をされている。いぶし銀のような凄みがある。芳村思風先生の謙虚な人柄はもちろん、何よりもすごいのは、話されている事と行動に寸分の違いも無い。実践者である。これからの日本を変えていくのは、「感性論哲学」しかない」34歳の時、「感性論哲学の世界」という本を自費出版。以来感性論哲学を語り続け、先生ご自身も、感性論哲学も今尚進化発展しています。一回聞いたから知っているではなく、実践できているかどうか?芳村思風先生は、「その問題は、こうすればいい」というような答えは与えてくれません。それぞれ状況は違うし、能力もちがう。乗り越えるのは、自分自身でしかないから。でも、お話を聞いているうち、ヒントや、キッカケそして何よりも勇気を与えていただけます。来年は、ぜひライブで芳村思風先生のお話を聴いてください。まとまりがなくなってしまいました。このお話は、「感性論哲学のすべて」DVD18巻大全集の最後の18巻に収録されます。発売は、来年2~3月の予定です。1~9巻は、発売中です。
2006年12月17日
コメント(0)
-
本物の人間とは
本物の人間とは、次の3つの条件を備えている。1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持つ。2.より異常をめざして生きる。3.人の役に立つ存在になる。そして、これを目的に努力することによって、人間は、本物の人間として、の格を持つことができる。これは、「問い」の形にして、常に自分自身に問いかける。1.不完全である事を自覚し、にじみ出る謙虚さを持っているか。2.より異常をめざしているか。3.人の役にたつ存在であるか。答えは、一つではない。答えを持つことは大切。もっと大切なのは、その答えに縛られないこと。縛られると他を排除しようとしてしまうから。人間は不完全だから、完璧はありえない。まだまだ努力・成長しなければいけないという気持ちが、謙虚さにつながる。今日12月16日は、東京思風塾です。1回だけの参加もOKです。今回のテーマは、「感性論哲学の体系」13:00~20:00です。一つのテーマを徹底的に掘り下げてお話していただけるのは、東京思風塾だけです。今日のテーマでのお話は、今まで出初めてのテーマです。体系については、話せれた事はありません。沖縄・福岡から、北は福島・長野と全国各地から30名以上の方が集まります。一度ライブで聞いてみませんか?東京思風塾思風塾ホームページ
2006年12月16日
コメント(0)
-
最高の出会い
最高の出逢いとは、自分を最も輝かせてくれる人との出逢いです。人生は、出会いによって作られる。人との出会い。物との出会い。出来事との出会い。いろいろな出会いにより、道が決まっていく。学生の頃、ある教科の先生にあこがれて、その教科が好きになり、いつの間にか先生になりたいと思った人。天体望遠鏡を買ってもらったことで、毎日、星を眺めているうちに天文学の道を歩み出した人。自己や病気という出来事との出会いで、医者になった人。心の底から興味関心好奇心が湧いてきて気がついたらその道を歩んでいた。最初は興味も関心もなかったけど、縁あってある会社に入社したことにより、一所懸命仕事に取り組んでいくうち、興味関心が湧いてきて、知らず知らずにその道の専門家になることもある。縁は、自分から求めて作れるものではない。人智を超えた「計らい」によって与えられるものである。今、自分の目の前にある問題から逃げずに努力を続けることが、縁を呼び寄せます。自分のしたいことがわからない。そんな時は、今与えられている仕事に全力を尽くす。必死にやってみる。そこから、新しい道が見えてくることがある。考えているだけではダメ。とにかくやってみる。必死でやってみる。必死でやっていると、新しい出会いも生まれるもの。
2006年12月15日
コメント(0)
-

生きるとは
生きるとは 人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。人間において生きるとは、何のためにこの命を使うか、この命をどう生かすかということである。命を生かすとは、何かに命をかけるということである。だから生きるとは命をかけるという事だ。命の最高のよろこびは、命をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。その時こそ、命は最も充実した生のよろこびを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。君は何に命をかけるか。君は何のためなら死ぬことができるか。この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である芳村思風なんどもなんども読み返した。行き詰まったとき迷ったとき苦しいときどうしていいかわからなくなったときこれだ!これしかない!と思っても、うまくいかなくなると「ほんとうにこれでいいんだろうか?」と迷ってしまう。このためになら死ねるこの人のためなら死んでもいいそんなことに出会えたとき自分の命が震え出す。それは、一生かけて探し続けなければいけないものかもしれない。
2006年12月14日
コメント(1)
-
人生の3つの問い
感性が問い、理性が答え、体で実現する。感性論哲学では、「問い」を大切にしています。最も大事な問いは、「人生の問い」といわれます。 人生の3つの問い ・将来どんな人間になりたいか ・将来どんな事をやりたいか ・将来どんな生活をしたいか答えを持つことは、大切なこと。この3つの問いに理性できちんと答えを出す。しかし、もっと大切なことは、実行すること。行動すること。やってみて、再び問う。これでいいのか。問い続けること。「なぜ私は、生まれてきたか?」「誰もが、その人でなければ出来ない大切なお役目を持っている。そのことで時代を一歩勧めるために生まれてきたのです。新しい歴史を作るために生まれてきたのです。」東京で芳村思風先生の勉強会が2ヶ月に1回開催されています。土曜日の1~8時までと長時間ですが、ひとつのテーマをこれほど長く話されることは他ではありません。●「12月16日(土) 東京思風塾のご案内テーマは「感性論哲学の体系」体系については、ほとんど講義されることはありません。ぜひこの機会にご参加ください。
2006年12月13日
コメント(0)
-
この哲学から日本の復活がはじまる
「この哲学から日本の復活がはじまる 上下巻」 鈴木繁伸・芳村思風共著 株式会社マネジメント・ブレーン刊 価格1500円+75円 1999年の4月【本の目次】■上巻□はじめに□第1章・・・21世紀日本の使命□第2章・・・脱近代の理念と新しい価値観□第3章・・・時流、独創の精神と経営について□第4章・・・脱近代の人間性□第5章・・・感性論哲学の基本原理□第6章・・・人生哲学の基本原理□第7章・・・実現するべき自己の発見□第8章・・・成功への階段を登る□おわりに■下巻□はじめに□第9章・・・愛の実力をつくる□第10章・・本物の人間とは、何か□第11章・・人格論□第12章・・境涯論□第13章・・感性論哲学とは、どのような哲学か□第14章・・教育論□第15章・・感性論哲学の興亡の原理□おわりに【上巻】■感性論哲学は、深い歴史観を基に、人生観、世界観を語り、教育、政治、経済、社会、文化の各分野の本質を明らかにして、未来への理念を指し示しています。・・・この感性論哲学の理念を軸に、国民1人1人がその生き方や夫婦、家庭の在り方を考え、新しい教育や経営の在り方を創っていけば、その変化は日本から世界に及び、人類の人間性は飛躍的に進化、発展していくと確信しています。私は特に中小企業の社長の方に、この哲学を軸にして、自分の言葉で社員に目標や理想を語っていただきたいと熱望しています。なぜなら、今の若者を本当に蘇らせることができるのは、実は顔の見える身近にいる会社のトップである中小企業の社長しかいないからです。(はじめに)■日本人は新しい時代を創る民族ではなく、新しい時代の過渡期を担う民族であるという自覚を持つ必要があるのです。・・・日本人には第二のギリシア人、第二のルネッサンス人になるという自覚が必要なのです。(P16)■「カオス」とは「秩序を模索する働き」です。・・・全ての存在は、「秩序を模索する働き」を持って存在しているのです。(P19)■最新の量子力学の宇宙観では、宇宙は、真理や法則によって動いているのではなく、一瞬一瞬新たなる秩序を模索しながら生きていると考えるようになってきました。宇宙の最終的な姿や物質の最小単位も「カオス」または「ゆらぎ」である事がわかってきました。この事から永遠に変わらない本質はなく、事実は変化し続けている。つまり「真理は1つ」ではなく、「真実は無限」なのだ、というふうに世界の考え方が変わってきたのです。(P34)■感性論哲学の基本的な考え方は、我々が「俺」「私」と言っている実体は感性であり、実感と本音こそ偽りのない自分そのものだ、ということです。そして、感性論哲学は人間や生命の本質も宇宙の究極的実在も感性であり、それゆえ感性は人間と生命と宇宙を貫く窮極的原理であって、感性が精神を創り、感性が肉体を創る、という全く新しい人間観を創りました。(P36)■感性論哲学は、「人間性の陶冶と金儲けを一石二鳥でやる」という方法です。自分の仕事を通して自分を鍛えていくのです。全ての職業は、原理的に言って、その職業に従事する人間を、人に喜んでもらえるような仕事の仕方ができる能力と人間性を持った人間に鍛え上げる、という道場としての価値を持っています。そうでなければ、職業として成り立たないからです。この意識で人間が労働し始める事によって、人間の価値観が変わり、明らかに、我々人間は資本主義経済、キャピタリズムから脱却できるのです。このような新しい労働観を原理におく事によって、資本主義経済ではない新しい経済システムが誕生するのです。(P42)■平等に代わる新しい時代の理念として、感性論哲学では「和道」という言葉を掲げます。全世界のこれから何百年間かにわたる人類の新しい理念として、平等に代わって「和道」の理念を掲げるのです。(P49)【下巻】■愛は努力して創っていく芸術であり、文化です。世間では「結婚は墓場だ」と言われますが、その意味する所は、結婚は「恋の墓場」であるが、「愛の始まり」である、と理解しなければならないのです。(P16)■どうすれば人間が人間を信じて、信じ抜いていく生き方が可能になるのでしょうか。そのためには理性と感性の協力が必要になります。まず、理性を使って、人間は信じられないものだと認識する必要があるのです。なぜなら、理性的に考えれば、人間は不完全な存在であり、不完全であるが故に失敗をしたり、罪を犯したり、嘘を言ったり騙したり、裏切ったりするものです。人間がそういう不完全な存在であると事をまずは理性的に十分認識する事が大切です。 そして、人間が不完全で信じられないものである事を本当に理性的に認識した人間はどうなるか、と言いますと、嘘を言われた場合、それが人間なのだと思うのです。騙された場合にも、それが人間なのだ、という理性的認識を持てるのです。しかし、人間は決して嘘を言いたいのではなく、裏切りたいわけでも内のです。人間は不完全であるが故に裏切らなければならないような状況に追い込まれてしまい、心ならずも裏切る行為をしてしまう事がありますが、それが人間の人間たる故の弱さなのです。 だから、この事を感性にまで落とし込めば、人間は嘘を言いたくて言うのではないのだから、その人間の心を信じよう、という事になるのです。人間が人間を信じるとは、そういう事なのです。信じるのは、理性ではなく、心です。感性です。信じるとか、願うとか、祈ると言った事は、感性の問題なのです。故に、人間が人間を信じる為には、どうしても感性にまて、心にまで、その原理を落とし込まなければならないのです。(P24)■人間の本質を理性と考えると、人間が人間に話をする場合に、相手の理性に対して話をする、という意識で話す事になります。これを説得の論理と言います。説得の論理は、権力構造にはまりこむ論理です。だから人間は説得されると、「説得されたくない、権力構造にはまりたくない」と反感を覚えるのです。 感性論哲学では、人間の本質は感性であり心であるのだから、人間が人間に話す時には、自分の心(感性)を使って相手の心(感性)に向かって、相手に分かってもらうように話す(命の語りかけ)事になります。それを納得の論理と言います。納得の論理とは、人間に話すという事を自分の心を使って空いての心に向かって話す事だと考える論理です。心を使うとは、願いと祈りを持って話すことであり、相手の心に向かって話すとは、分かってもらえるように話す事です。(P34)■より以上を目指して生きる生き方は、人間的魅力の源泉でもあり、生きがいもそこから出て来ます。生きがいを失った人間は、必ず目標を失った人間です。生きがいを回復させるには、どんな事でもいいから、より以上を目指して生きる事です。すると、徐々に生きがいが戻ってきます。何か1つの事に打ち込んでいる人間の姿には、何かしら人を惹きつける魅力があります。原理的に言って、より以上を目指して生きるという姿勢からしか人間的魅力は出てきません。(P60■人間性における成長(新しい気づきの積み重ね)
2006年12月12日
コメント(0)
-
意志の力 愛の実力
「意志の力 愛の実力」 芳村思風講演著 コスモ教育出版刊 本体価格 【本の目次】□はじめに□序章 感性論哲学への道□第1章 この命を何の為に使うか□第2章 真実の自己とは何か□第3章 成功への階段を登る□第4章 21世紀のキーワード、愛を育てる□第5章 真実の愛とは何か■会社であるならば、もっとよりよい会社の在り方を考える、もっとよりよい経営の在り方を考える、そのもつとよりよい会社の在り方を考えるということが会社における人生観の哲学であり、もっとよりよい経営を考えることが会社における人生観の哲学である。だから本当に会社の成長は、発展、幸せを願うならば、経営者は哲学なしには経営はできません。確固たる信念を持って会社を成長させていくためには、なにらかの意味での哲学というものを経営において持っていなければ、着実に確実に会社を成功の方向へ、幸せの方向へ、勝利の方向へ導いていくということは不可能であります。哲学がなかったら、その時々に起こってくる様々な変化、現象に振り回されてしまって、その場しのきぜの対応しかできないのです。哲学を持つことによって我々は、現象に振り回されることなく真実を見つめながら生きていくという、そういう生き方が可能になってくる。だから、たとえ自分達が今やっていることが、現実には、この現在の時点においてはあまりよい効果が出る方法でなくても、この方法の積み重ねが10年先の我が社の繁栄を築くんだという信念があって、初めて経営はできるんです。今という時点に適合することばかりを考えていたのでは、常に時代の後追いであって、真に先見性のある経営はできません。今に対応するということは、何かが起こってからしか行動できないということですから。結局は事後処理的な、後追い的な経営しかできない。しかし、本当の経営は、常に10年の計、20年の計、30年の計、50年の計、100年の計を持って現在を考える。現在にどう対応するかということも、50年先を見通して現在の経営をする、そういうものが経営の基本ですから。単なる事後処理型で、こういう事態が起こった、そこでそれにどう対応したらいいのか、というのはもう経営じゃない。そこには理念がない。哲学がない。とにかく哲学という学問は、常に物事の理念を追究する。そういう意味で哲学は、自分を取り巻く外的環境をよりよい方向へと変えていく外的変革の学としての世界観の学としての側面と、同時に自分の生き方をよりよいものに変えていく内的変革の学として、人生観の学としての側面を持っております。(52,53P)■繰り返しますが、命には命より大切なものがあります。それは「愛」と「意志」です。個々から愛することができるものと、人生を賭けて意志することができるものを、人間は持たなければなりません。そして、そのために生き、そのために命を使うのです。そこに人生における最高の喜びがあるのです。(90P)■真実の愛は、努力してつくっていくもので、その努力に愛の価値があるのです。相手のために払った努力の量と質が愛の重みを決定するのです。そして、その努力を愛と感じるのが、人間の愛であると言えるのです。愛は感じるもの。感じなかったら愛ではありません。また、愛を感じさせることによってしか、愛は存在し得ないものです。(98P)
2006年12月11日
コメント(0)
-
感性論哲学の世界
●「新しい思想・感性論哲学の世界」 芳村思風著 思風庵哲学研究所 刊 本体価格 2625円 芳村思風先生の第1作目。この本を渋谷の大盛堂に頼み込んで、置いたことがキッカケで行徳哲男先生に出会う。今年で、出版30年。■学問や文化を根底から支えている原理の正当性を問い正す事は、哲学が全人類に負っている重大な使命であり責任である。今や世界は弁証法的対立の時代ではなく、根元的統一の基盤を要求しているのである。【本の目次】□目次□序論 ・序文・前章命題□本文・第一章 感性の確立・第ニ章 感性の構造・第三章 世界観・第四章 現代哲学との対話・第五章 一般的命題□西洋思想史年表□註□あとがき□さくいん■21世紀の世界は、20世紀を築いた原理の延長線上には存在しない。21世紀を築く巨星の条件は、原理的創造への意欲と情熱である。新たなる世界は、新たなる原理を要求する。感性論哲学は、哲学における21世紀の新しい原理である。(2p)■思惟と身体との統一は、感性を媒介にして初めて現実的なるものとなっている。そこで、最も現実的な意味において、「私」とは、感性において統一されて在る「身体と思惟」の有機的全体性なのである。(29p)■我々は、感性なしに思惟を現実的なものとして考える事はできないが、思惟なき感性を現実的なものとして考える事ができる。感性は、その作用において思惟作用を前提としない。それ故に感性は、存在においても作用においても思惟から独立した存在である。(31p)■感性は、すべての感官を通して与えられる感覚や表彰を感受して、それを統一統合し、感性という世界における1つのまとまりある全体的経験を形成する。(34p)■能動的なる感性としての「直観」という能力は、認識論的な表現であって、これを存在論的な能力として考えた場合には、「意志」と名付けられ、実践的な能力となる。(39p)■意味は関心によって呼び起される。意味とは関係である。関心とは、能動的な心の働きであり、感性における直観の能力において発現する作用である。我々はすべて、混沌たる意味世界の中に、関係あるものとして生まれて来、そして無意識の内にも、関係を持って生きている存在である。それ故に我々は、無意識の内に根源的に意味づけられているのである。我々は意味の大海の中に、意味を持って生きているのである。生きるとは、このように、根元的意味づけられているという事の意味を自覚する事である。使命とは、この意味の自覚から出発するのである。何等の関係なしに存在しているもまのは、この世界の中には何一つ存在しない。すべてのものは、意味と使命を持って存在しているのである。(43p)■人間が思考し始めるのは、言葉を発音する事ができる時期と同時である。最初の思考は、言葉とその言葉に含まれる対象的内容とを統一する作業から始められる。そして、このすべての過程が、人間の社会における人間同志の共同生活において進められるというごく当り前な平凡な事実が、人間が、人間らしい人間になるという事に、大きな意味を与えているのである。「人間」はこの意味において、本質的に社会的な存在なのであるということができる。(53p)「感性論哲学の世界」(2,500円+送料500円)在庫あります。ご希望の方は、ご連絡ください。(サイン入りです)
2006年12月10日
コメント(0)
-

人間観の革正
芳村思風先生の本の紹介です。感性論哲学の全体を知るうえでは、一番わかりやすい1冊です。平成19年の東京思風塾では、この本をテキストに講義と参加者による先生との問答を中心に進めていく予定です。また、感性論哲学の実践している方々と思風先生の対談も予定しています。●「人間観の革正」 芳村思風著 致知出版刊 価格 2750円+138円 ■君は何に命をかけるか。君は何の為になら死ぬ事が出来るか。この問いに答える事が、生きるという事であり、この問いに答える事が、人生である。【本の目次】□まえがき□第一章 脱近代の理念 ・数万年単位で起こっている3つの変化 ・数千年単位で起こっている3つの変化 ・数百年単位で起こっている諸々の変化□第二章 脱近代化の人間性 ・理性への批判 ・理性と感性の関係 ・知恵の活用 ・人間性の進化 ・生き方の変革 ・感性的な判断力□第三章 感性の本質と構造の働き ・人間観の革正 ・感性の本質 ・感性の働き ・感性の構造 □第四章 感性が精神と肉体を創造する ・感性が肉体を創造する ・感性が精神をつくる ・人間性の体系□第五章 感性と宇宙 ・宇宙の摂理 ・人間の使命 ・人類の運命■「人間の本質は感性であり、宇宙の本質も感性なんだ。宇宙を支える感性が自分の命を支えており、私の本質である。だから、私とは宇宙なんだ」という感性と宇宙のつながりを自覚できれば、どんなに大きな生き方ができるかを考えてもらいたいと思います。 座禅やヨーガはが目指す悟りの世界とは、まさにそういう境地です。座禅やヨーガは感性と宇宙の原理に気づいていないために、実践的な修業によって、そういう心境に至ろうとしています。しかし、この原理を知れば、修行などしなくても「私とは宇宙である」という自覚へと自らを高めていくことができるのです。 そのために必要なのは、理性の力によって感性を成長させることです。理性の力を借りて感性と宇宙との係わりを知ることによって、人間とはそういう感じ方ができる感性をつくることができます。そして、宇宙と自分の命が一体化するという実感を持つことができるのです。すべては宇宙の摂理の働きによって創造されたものだから、宇宙にはムダなものは何一つ存在しません。そうなれば、どんなものとも対立しないで、すべてを活かし切り、全部を呑み込んでいげるようになります。■自分が意識しなくても、自分の存在なり声なりは、全宇宙に影響を与えています。「俺が生きている」というだけで、それが全宇宙に影響を与えている。「俺の一挙手一投足」が全部の人間に影響を与えているということです。 そういうことを敏感に理解する人間は、吉田松陰やイエスのように、わずか2、3年で時代を変え、世界を動かすような影響力を持つことができるようになるのです。「俺の一挙手一投足が周りの人間に影響を与えている、自分の存在が周りの人間を動かしている」と感性で感じられる状態になってきたら、常人にはないような影響力が出てくるのです。■ただし、間違ってはいけないのは、感性から湧いてくるものをただむやみに実現すればいいのではない、ということです。理性が感性や欲望の奴隷になってしまっては野獣です。大事なのは、どのように理性を使ってそれを他人に迷惑のかからない方法で実現するかと考えることです。この構造が大事です。■理性とは、客観性と普遍性の能力です。したがって、理性的に考えるとは「みんなにとってどうか」と考えることです。社会、人類、国家など、自分を包み込む、より大きなものを視野に入れながら、自分の中から湧いてくる欲求を実現しようとすることです。 ここに偉大なる人間の仕事が始まるのです。単に命から湧いてくるものをそのまま自己中心的にぶつけるのではなく、湧いてくるものを理性を通して表現するところに人間的な行動があるのです。理性は客観性と普遍性の能力であるがゆえに、それを使って考えると、そこに「みんなにとってどうなのか」という社会性・人類性が芽生えることになります。ゆえに、理性を通して表現することによって、命から湧いてくるものは「志」となり、「使命」になるのです。■人間のなかで働いている感性は大宇宙の根源とつながっているゆえに、人間の命には大宇宙から湧き上がってくるエネルギーが存在するのです。それを表現しているのが、感性から湧き上がってくる欲求・欲望・興味・関心・好奇心・悩み・苦しみ・問題なのです。 そこにこそ、常人を超えた仕事をさせる力の源があります。感性から湧き上がるエネルギーを原理にせず、理性で考えた計画や目標を実現しようとすると、人間はその目標や計画に縛られ、支配され、堅苦しい不自由な生き方となり、本当のやる気が湧いてきません。命から湧いてくる力の助けが得られないので、平凡な人間の生き方になってしまうのです。こうした構造が人間にはあるということを知って下さい。■大事なのは、現在自分がぶつかっている問題や悩みなどをどう理解して、宇宙の根源から湧き上がってくる感性のエネルギーと結び付けるかです。■いろいろな現象が天のサインなのです。すべてが何かしら自分に使命を与えようとしているという意識で現象を眺めることのできる人間だけが、自分に与えられた本当の使命を感じることができるのです。 誰もがイエスや吉田松陰のような大きな仕事をしなくてはならないとというわけではありません。しかし、「感性と宇宙」の関係から人間の生き方を考えるならば、どんな人間にも宇宙大の生き方ができる可能性があることを、もっと真剣に考えなければならないと思います。■宇宙との構造的な連関性を自覚することを通して、感性と宇宙の関係をどういうふうに自分の人生のなかに生かしていくかを考えてもらいたいと思います。そうすれば、どんな人間でも、大宇宙きから湧き上がってくるエネルギーを自分の人生の生き方の土台に据えて、単に人間的な力ではない、大いなる何かの力に支えられながら生きていくことができるのです。 もっともっと感性の声に耳を傾け、命から理屈抜きに湧き上がってくるものを大切にしてもらいたいと思います。そういうものに根ざした生き方をすることによって、自分でも驚くような人生が始まるのです。
2006年12月09日
コメント(0)
-
信じて、信じて、信じぬく
人間は、信じられないものであることを自覚する。 ウソも言う。裏切ることもある。失敗もする。 罪も犯す。 「信じられないものを、信じると決断する」 矛盾を内包する真実を生きる。 だまされても傷つかない心を持つ。 人間だから、ウソをつくことも、 裏切ることもある。 だまされても、裏切られても、 自分ひとりだけでも信じられるかどうか。 簡単にできることではない。 だまされたら、腹が立つ。 裏切られたら、悲しい。 それでも、一度信じた人を信じぬけるかどうか。 簡単に出来ない。相当の覚悟がいる。 理屈では考えられないことをできるかどうか。 理屈では考えられない決断が、 最高の愛の世界を作る。 矛盾を内包した真実の世界を生きる。 子どもがウソをついたとき、 「お父さんが悪かった。」と 子どもに謝り、抱きしめることが出来るかどうか。 ウソをつかなければならない状況を自分が作ってしまった。 そう思えるかどうか。 「でもウソをついてはいけない」と子どもを叱るのは、 その後。 「人間は不完全である」を知る。 これを知り、実践していくとはどういうことか。 だまされたり、裏切られて相手を責めるのは、 人間に完全を求めている。 意識せずにそうなってしまうこともある。 人間が不完全であることを認め、 不完全を許した時、 人間の最高の愛の姿がそこにある。 信じて、信じて、信じぬく力を持つ。
2006年12月08日
コメント(2)
-
人生の3つの問い
感性が問い、理性が答え、体で実現する。感性論哲学では、「問い」を大切にしています。最も大事な問いは、「人生の問い」といわれます。 人生の3つの問い ・将来どんな人間になりたいか ・将来どんな事をやりたいか ・将来どんな生活をしたいか答えを持つことは、大切なこと。この3つの問いに理性できちんと答えを出す。しかし、もっと大切なことは、実行すること。行動すること。やってみて、再び問う。これでいいのか。問い続けること。「なぜ私は、生まれてきたか?」「誰もが、その人でなければ出来ない大切なお役目を持っている。そのことで時代を一歩勧めるために生まれてきたのです。新しい歴史を作るために生まれてきたのです。」歴史は、その時代に生まれてきた子供たちが作ってきた。「近頃の若い者は・・・」という言葉が出てきたら、時代の流れに沿っていないということ。明治維新もITの時代も「地がごろの若い者は・・・」と言われていた人たちが作ってきた。
2006年12月07日
コメント(0)
-
時流独創の精神
時流独創の精神 6つの問い1.自分の心を本当に納得させるものを理屈ぬきに追い求めているか?2.固定観念・先入観念から自分を解放しているか?3.自分の使命は何であるかを知っているか?知ろうとしているか?4.命から湧きあがる欲求・欲望・興味・関心・好奇心を持っているか?5.現実への異和感を大切にしているか?6.有機的統合能力を磨いているか?”問い”について感性論哲学では、「問い」(といかけ)がたくさんあります。「時流独創の精神とは、~である」ということなのですが、「問い」の形にする事により、実行できているかどうかを自分で確認することを習慣づけるためです。これは、「答え」を持つことは大切なのですが、その答えに縛られないためです。答えに縛られると、他の答えを排除する、否定する、説得しようとする・・・そこから対立が始まります。答えを持ちながらも、よりよい答えを求め続けること。違う答え・考え方から、自分の答え・考え方を進化発展させること。そのために「問い」の形になっています。
2006年12月06日
コメント(0)
-
感即動
人は、感じた動く。「感即動」とは、「感じたら、すぐに動く」という意味だけではない。「感じさせることで、人は動く」という意味がある。感じさせなければ、人は動かない。理性で説得しても、人は動かない。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。
2006年12月05日
コメント(0)
-
一灯照宇の志
一灯照宇の志一灯照隅という言葉がある。「古人言く、径寸十枚、これ国宝に非ず。一隅を照らす、これ則ち国宝なり、と」 最澄「天台法華宗年文学生式」『魏王が言った。「私の国には直径一寸の玉(ぎょく)が十枚あって、車の前後を照らす。これが国の宝だ。」斉王が答えた。「私の国にはそんな玉はない。だが、それぞれの一隅をしっかり守っている人材がいる。それぞれが自分の守る一隅を照らせば、車の前後どころか、千里を照らす。これこそ国の宝だ」と。』 湛然の著「止観輔行伝弘決」安岡正徳さんの言葉によく「一灯照隅」が出てくる。 「賢は賢なりに、愚は愚なりに、一つことを何十年と継続していけば、必ずものになるものだ。別に偉い人になる必要はないではないか。社会のどこにあっても、その立場立場においてなくてはならない人になる。その仕事を通じて世のため人のため貢献する。そういう生き方を考えなければならない。」たとえ一本のロウソクでも身の周りを照らせば明るくなる、それを万人が照らせば「万照」、ことごとく世界を照らせば「遍照」。全ての始まりは常に小さなところから。ひとつの灯火が片隅を照らす。その灯火が次の灯火を点け、また次の灯火を点ける。そして多くの灯火が全国を照らし、ひいては地球を照らす。さらに宇宙を照らすという志を持て!芳村思風先生が、サインを求められた時によくかかれる言葉です。
2006年12月04日
コメント(0)
-

勝つことよりも大切なこと
勝つことよりも大切なことは、共に力を合わせて成長すること。正しいか正しくないか、勝ち負けで判断しようとすると、対立が出来る。説得しようとする。相手のいいところから、少し学ぶ。まず相手を受け入れる。人間は、必ずどこか欠けたところがある。完璧ではない。勝ち負けのゲームをやめたとき、受け入れ、共に成長できる。
2006年12月03日
コメント(1)
-
一道一徹
「一道一徹」…一つの道を貫き通す芳村思風先生が、本にサインした言葉。あまり書くことのない言葉ですが、時間があるときは、本を持ってきた人をじっくりと見て、浮んできた言葉を書かれます。書かれたサインを見て、涙を流した人を何人も見ました。「よくサインに書かれる言葉」この命なんのために使うか愛するとは、相手から学ぶこと責め合うのではなく、愛し合って生きる命には、命より大切なものがある。それは愛と志である問題は成長させるために出てくる限界への挑戦!不頼独行いつも目に愛の光を!勝つことよりももっと素晴らしいことは、力を合わせて成長することあなたは、どんなサインをいただきましたか?
2006年12月01日
コメント(5)
-
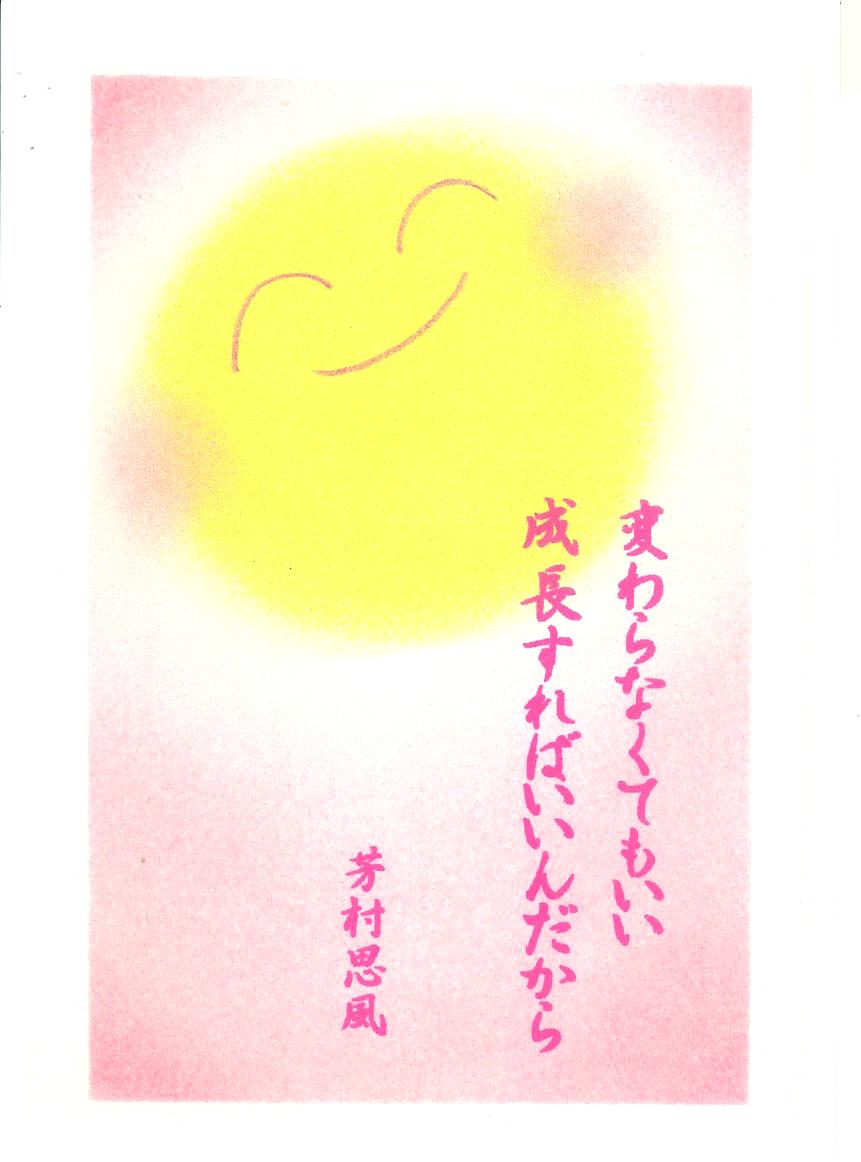
変わらなくてもいい成長すればいいんだから
変わらなくてもいい成長すればいいんだから勝つことよりももっとすばらしいことは、共に力を合わせて成長することこの命なんのために使うか!愛とは、短所を許し補い、長所と関わる力です真実の愛とは、考え方の違う人間と共に力を合わせて生きて行く力です。人生は、どの道を選ぶかではない、選んだ道から出てくる問題を乗り越え続けることができるかどうかです考え方ではなく感じ方が人間を決定する。逃げたらあかん!問題は貴方を苦しめるためではなく成長させるためにあるのです思風先生の言葉がポストカードになりました。上の9つの言葉と、「生きるとは」の詩を加えて、10枚組み 1,000円(税込)芳村思風「風の言葉1」初回製作分100セットは、完売しました。現在芳村思風「風の言葉2」を作成中です。好きな言葉があれば教えて下さい。
2006年12月01日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-19 16:55:20)
-
-
-

- 株式投資でお小遣いを増やそう
- 11/1/(火)日経平均はどう?下がる…
- (2025-11-20 14:47:13)
-







