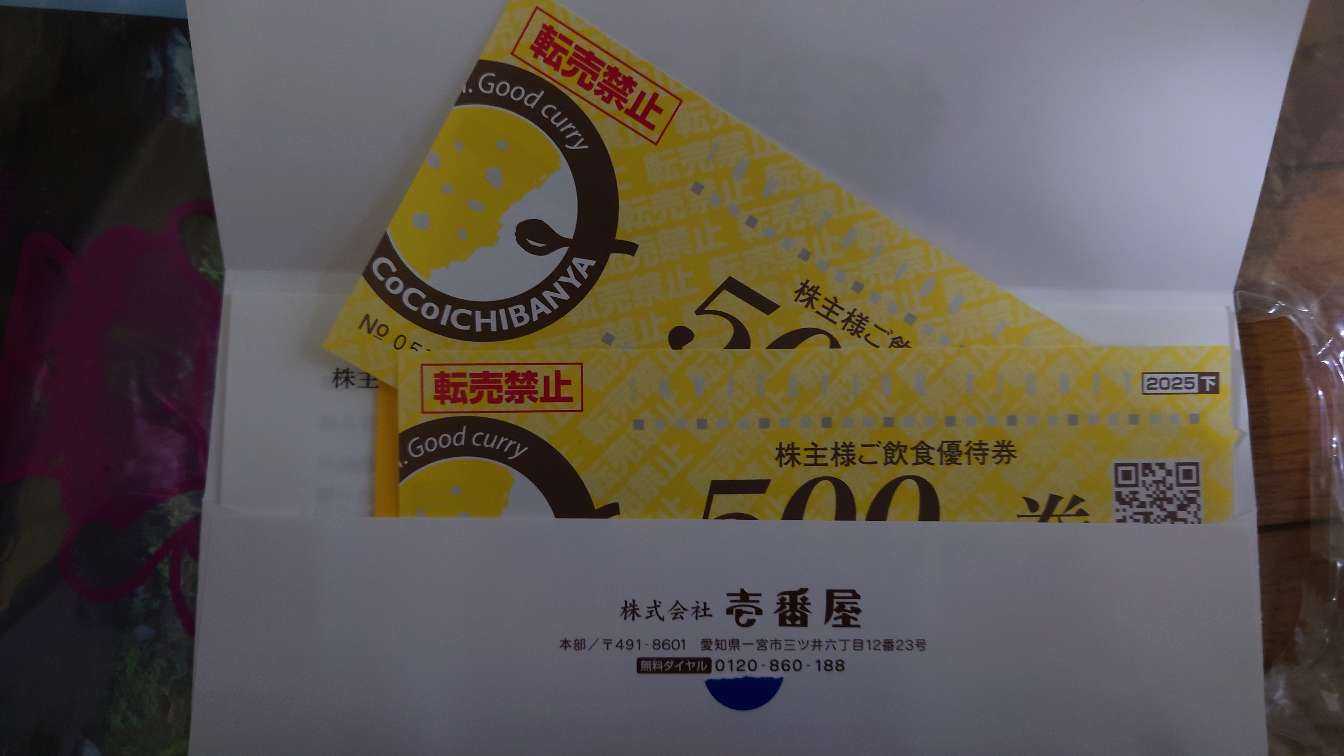2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年02月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
感動させうる人間とは
人は、感じたら動く。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。
2006年02月24日
コメント(4)
-
天はオレを大人物にしようってか!
問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。
2006年02月23日
コメント(1)
-
感性論哲学の歴史観(3大パラダイムシフト)
現代は、歴史的な大転換期にさしかかっています。3つの大きな流れがあり、それが今、同時に新しい流れに変わろうとしています。A.数万年単位のパラダイムシフト 1.地球時代から、宇宙時代へ 2.タテ型社会から、ヨコ型社会へ 3.弱肉強食から、適者生存へB.数千年単位のパラダイムシフト 1.西洋の時代から、東洋の時代へ (理性原理から、感性原理へ) 2.文明の対立から、世界文明へ (地域文明から世界文明へ) 3.二元論的人間観から、一元論的人間観へC.数百年単位のパラダイムシフト 1.政党政治から、脱政党政治へ。そして合議政治へ 2.資本主義経済から、脱資本主義経済へ。そして人格主義経済へ。 3.民主主義から、脱民主主義へ。そして互敬主義社会へ。 4.理性文明から、脱理性文明へ。そして感性文明へ。 5.物質文明から、脱物質文明へ。そして精神文明へ。
2006年02月22日
コメント(0)
-
純粋感性とは・・・
感性論哲学では、宇宙の本質のことを「純粋感性」と定義しています。それは、宗教では「神」であり、「気」を呼ぶ人もあり、筑波大学の村上和雄名誉教授は、「サムシンググレート」と呼ばれている物です。感性論哲学では、さらにその本質を「求感性」という働きでとらえています。世界は、エネルギーの海と言われているように、すべてはエネルギーで充満しています。そのエネルギーが動き、偏り、とどまり、散り、渦巻き、拡散し、収束し、波うちといろいろな様相を呈しているのが現状です。静止しているのではなく、動きながら、バランスを取りながら、動的平衡作用が働いています。感性には、3つの作用があります。「調和作用」 「合理作用」 「統一作用」「調和作用」・・・空間バランスや形をよりよくする作用「合理作用」・・・時間バランスや時間的速度追求や論理性に働く作用「統一作用」・・・とりまとめて新しい平衡状態をとる作用※まだまだ勉強不足で、わかりやすく表現できませんでした。
2006年02月21日
コメント(2)
-
大和心
大和心とは、大きく和する心。日本には、世界の食卓がある。世界の音楽がある。世界の文学がある。世界の宗教がある。世界の言葉がある。世界各国の違った文化・宗教・言葉を取り入れて、尚かつ進化させる力が日本人にはある。これは、日本人にしかないもの。漢字は、日本に伝わり、カタカナ・ひらがなと発展した。今では、英語やフランス語も取り込んで進化している。仏教は、インドから始まり、東南アジアや中国を経て、日本で集大成されている。外国まで行かなくとも、東京で世界中の料理が楽しめる。違いを理由に排除するのではなく、そのいいところを取り込んで、日本古来のものと融合し、さらに発展させていく力が日本人にある。
2006年02月17日
コメント(1)
-
歴史観
感性論哲学的10の歴史観1.歴史は風土と民族と国家と思想を変えながら進んでいく。2.すべての存在は、存在することへの必然性をもって存在している。3.すべての存在は、存在することへの必然性を実現しきった時、 完成され衰退していく。4.一度完成された形式に到達したものは、保守化して時代に取り残され衰退する。5.一度歴史的使命を終え、潜在能力を出し切ったものは、 2度と歴史の主役にはなりえない。6.人類は、人類としての潜在能力を出し切ったとき衰退する。7.世界歴史を動かす力は2つある。それは因果律と自由律である。8.時代を興す原理は、また時代を滅ぼす原理でもある。9.不安を解消し、安心を実現することを目的に歴史が創られる。10.時代欲求や時代感情(時代感性)が歴史の方向を決定する。※各項目の解説は、ぜひ各地の思風塾や書籍で
2006年02月15日
コメント(0)
-
人生は出会いによって作られる
人生は、出会いによって作られる。縁は、自分から求めて作るものではない。人智を超えた「計らい」によって与えられるものである。今、自分の目の前にある問題から逃げずに努力を続けることが、縁を呼び寄せます。・・・・・・・・・芳村思風先生と行徳哲男先生の出会い。昭和51年11月。34歳の時、「感性論哲学の世界」という本を自費出版した。どこの出版社でも取り扱ってくれない。東京の大きな書店を回り、4~5冊ずつ置いてまわった。「代金も利益もいらないから、この本を置いてください」「もし売れたら店長のお小遣いにしてください。」2,500円の本だ。いくつかの書店で平積みにしてくれたそうだ。その中の1件に、渋谷の大成堂という書店があった。本を並べた翌日。行徳哲男先生が何気なく、その本屋に立ち寄って、「感性論哲学の世界」を手にした。「考え方ではなく感じ方が人間を決定する」行徳先生は、扉に書かれたこの言葉を見て、衝撃が走ったそうだ。自分がやろうとしていたことの裏づけが、その本に書かれていた。今までやってきたことに間違いはなかった!そう確信したそうです。その日のうちに、連絡を取り、翌日には、東京から、三重県鳥羽市まで駆けつけた。「その日から私の人生は変わりました」先人の哲学者の研究という象牙の塔の世界から離れ、20代で、「感性論哲学」を考え出した。もちろん受け入れられるはずがなかった。34歳の時書いた「感性論哲学の世界」は、自分の考えを一人でも聞いて欲しい。ただそれだけの気持ちで、本屋さんに置いてまわった。行徳先生が、実業の世界へと結び付けてくれた。感性論哲学を人生に活かす。感性論哲学を経営に活かす。多くの経営者の方が、感性論哲学との出会いで「自分の中に1本の芯ができた」と話されています。「いろいろな問題や悩みはあるけど、少しくらいの事では、動揺しなくなった。」そんなお話をよく聞きます。「行徳先生がおられなかったら、今の自分はありません」一人でも自分の考え方を知ってもらうだけでいい、と自費出版の本を配ってまわった芳村先生。1冊の本と出会って、すぐに行動した行徳先生。うまくまとめられませんでした。感性経営問答塾の中で、芳村思風線ご自身が「出会いと縁」について、ある方の質問に対して答えられたお話です。
2006年02月14日
コメント(0)
-
生きるとは
生きるとは 人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。人間において生きるとは、何のためにこの命を使うか、この命をどう生かすかということである。命を生かすとは、何かに命をかけるということである。だから生きるとは命をかけるという事だ。命の最高のよろこびは、命をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。その時こそ、命は最も充実した生のよろこびを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。君は何に命をかけるか。君は何のためなら死ぬことができるか。この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である・・・・・・・思風塾で参加者の方に、先生の言葉で一番好きな言葉はなんですか?と聞いたとき、最も多いのがこの「生きるとは」だ。「日めくり」の中にも入れたかったけど、全文を載せなければ意味がないような気がしたので入れなかった。「命には、命より大事なものがある」命を賭けても、守りたい人と出会うこと命を賭けても惜しくないものと出会うこと命を賭けても惜しくない仕事と出会うこと
2006年02月10日
コメント(0)
-
使命とは・・・
降りかかる苦難の中に使命あり初めて芳村思風先生の講義を聞いたとときに本にサインしてもらった言葉。ある事情で、うつ状態に近い日が3ヶ月続いていた。家から出るのは、コンビニへ弁当開に行くだけ。誰とも話もしない日が、2週間くらい続いていた。そんな時、以前務めていた会社の取引先の社長からの電話がきっかけだった。何もしていないなら、東京まで来ないか。「芳村思風先生という哲学の先生の講座があるから。」哲学?芳村思風先生?哲学には、全く興味はなかった。でもこのままじゃいけない・・・ただそれだけで、東京に来た。講義を聞いても、よくわからなかった。芳村思風先生の第一印象は、やさしそうな方。講義の中で、ひっかかる言葉がいくつかあった。チョッと勉強してみようか。軽い気持ちだった。本を買って、サインをお願いした。先生が、黙って私の顔を見つめる。長い沈黙・・・・3分以上続いた。急にペンを取り、先生がかかれた言葉が「降りかかる苦難の中に使命あり」涙が止まらなかった。先生には、自分の状況を何も話していない。先生は、私の顔を見て、言葉が湧いてくるのを待たれていたそうだ。それから、サムシンググレート・シンポジウムのお手伝いをさせていただくことになった。それまでは、高速道路をアクセル全快で走っていた。車が故障して、高速道路から降りた。スピードを落とすと、いろいろな物が見えてきた。全速力で走っていたら、見えなかったものが見えてきた。全速力で走っていたら、出会えなかった人たちとの出会いがあった。芳村思風先生との出会いと、この言葉で、人生が変わりました。
2006年02月09日
コメント(1)
-
出逢いとは・・・<日めくりができるまで>3
ほんとうの出逢いとは、自分を最高に輝かせてくれる人との出逢いのこと自分も人を輝かせる人になり、人を輝かせる人と人をつなぐ人間になること。<昨日からの続き>印刷屋さんを探しながら、絵と文章の校正を続けていた。なかなか見つからない。そんなある日、友人のコクーンというバンドのコンサートに出かけた。2枚目のCDの発売記念コンサート。終わったあとのパーティで、またまた面白い出会いが・・・。出会いというより、再会だった。妻が若い頃(???)務めていた会社の取引先の方だった。印刷会社の方だった。今は退職されているけど、当時の部下の方に連絡してくれるとのこと。翌日早速連絡をとって、打合せ。後は、価格だけ。1週間後、見積書が届いた。「!」やっぱり・・・1000部では採算が取れない。2000部で何とか、発送費やその他を含めて、定価2000円ならできる。でも・・・2000部売れるのだろうか?それに個人での取引なので、印刷開始と同時に半額、印刷上がりで残金の支払という条件付。今準備できるお金は、半分だけ。2回目の支払を少し延ばしてもらっても足りない。どうしよう・・・ここまで来て、一番大きな問題がでてきた。悩んだあげく、両親借りることにした。この年になって、まだ心配をかけるようで心苦しかった。見本を持って、大阪に帰った。「絶対に年あけに返すから・・・」黙って貸してくれた。しばらくしてから、妻が電話したときこう言っていたそうだ。「あんなにうれしそうな顔をしているのを、久しぶりに見た。それにあなたがついているし・・・」40歳も過ぎているのに、頼れる両親がいることをほんとうに感謝した。10月末、印刷が出来上がった!宅配便で50ケース。箱を開けて、手にとったときの感激は、絶対に忘れない。先生もとても喜んでくださった。電話やメールで出来上がったことを知らせた。毎日のように入る注文の電話・FAX・メール・・・12月始めには、2000冊完売。何とか借金も返済できた。追加発注しなければいけないことになった。1,000部追加発注。利益は、そのまま追加印刷分になってしまうけど、うれしいかった。なによりも、思風先生がいかれる先々で「日めくりができました」と宣伝していただけたこと。先生が昨日どこに行かれたかがわかる。講演の翌日同じ地域からのFAXが届いた。先生のおかげで、自己表現をさせていただいた。いろいろなところから、うれしい話を聞かせていただいた。そこからまた新しい展開も始まりそうだ。「私の言葉だけでは、誰が作っても一緒。あなたにしか出来ない物を作りなさい」と言って、他からの依頼を断ってまで、待ち続けてくれた芳村思風先生、絵の描き方を教えてくれた江村信一さん、お金を貸してくれた両親、販売はじめ、いろいろな面で助けてくれた妻、販売に協力いただいた全国の思風塾の方々、日めくりを買っていただいたたくさんの方々ほんとうにたくさんの人に助けられていることに感謝しています。・・・・・・・・芳村思風先生の一日一語なのに、長々と3日間にもわたり、自分の事ばかり書いてしまいました。出会いに感謝です。
2006年02月08日
コメント(0)
-
出逢いとは・・・<日めくりができるまで>1
ほんとうの出逢いとは、自分を最高に輝かせてくれる人との出逢いのこと。自分も人を輝かせる人になり、人を輝かせる人と人をつなぐ人間になること。<日めくりが出来るまで>「芳村思風先生の日めくり」は、先生の講演会の休憩時間一緒に参加していた方と話がきっかけでした。「あの言葉ずしんときたよね」それだけで、お互いどの言葉かわかるくらい衝撃的な言葉でした。その時、「先生の本は難しいから、あんな言葉を集めて日めくりを作ったら、もっとたくさんの人にわかってもらえるんじゃないかな」哲学?感性論哲学?そんなもの興味ない経営には役立たないそういう方にもぜひ、聞いていただきたい。女性にも、子育て中のお母さんにも若い方にも・・・そんな気持ちで作り始めました。「先生の言葉で、日めくりを作りませんか」先生にお願いしたとき、おっしゃった言葉に感激した。「私の言葉だけなら、誰が作っても同じです。あなたが絵を添えてくれるなら、いくらでも私の言葉を使ってください。」直ぐに製作取りかかった。先生の講演には必ず参加し、本を読み、講演テープを聞きまくった。言葉は、31すぐに選べた。絵が描けない。31枚、言葉に合わせて絵が描けない。何枚も描いたけどピンと来ない。半年が過ぎた頃、別のところから、「日めくりかカレンダーを作りたい」との話が先生のところにきた。「今、東京で日めくりを作ってくれていますので、それを待ってください。」先生がそう答えて、断ってくださった。それを聞いてあせりがでてきた。でもやっぱり絵が描けない。絵のテーマすら決まらない。描いては破るそんな日がまた半年続いた。そんなある日、また素晴らしい出逢いがあった。(続きは明日)
2006年02月06日
コメント(0)
-
人間として本物とは何か No.3
3.人の役に立つ人間になっているか 人の役立つことを喜びとする感性をもつこと=愛人のために尽くして喜ばれることに喜びを感じる愛は誰にでもある社会的存在としての人間には、人の役に立てることを喜びと感じる感性が必要。●人間は社会的な存在。 「自分の価値は他人が決定する」 社会の原則は自分の価値は他人が決めるということ。 自分がどれだけ凄いかを語ってみても自己満足。 他人から評価されてなければ意味がない ⇒社会の中で本物というためには、 人の役に立てることを喜びとする感性を成長させなければならない●人の役に立つ人間になる●人に必要とされる人間になる 職業とは、その職業に従事した人間を、 人に喜んでもらえるような仕事の仕方ができる人間性と能力を持った 本物の人間にそだてあげるもの。 プロとは、お客さまにも、一緒に仕事をする仲間にも喜んでもらえるような 能力と人間性を持っている人のこと。 プロとして、「さすが」といわれるような仕事の仕方ができ、職業を通して、 人間と社会の実態のおそろしさやすばらしさを命の痛みを伴った体験をして、 人間性と能力を成長させる。 相手が喜んでくれるまで、結果を出すまでやり続けるのがプロ。 結果を出して初めてプロと言える。
2006年02月05日
コメント(0)
-
人間として本物とは何か No.2
2.より以上をめざして生きているか命から湧いてくる問題意識をもち「より以上」を求めて生きること成長意欲をもつ1.「より以上を求めていきる」ことで人間は成長する 人間は完全にはならない→完全になることを求めてはいけない →完全にはならないことを自覚し、「より以上」を求める生きること大切2.「より以上」を求めて生きるための原動力は「欲」 欲をもってはいけないというのは宗教の世界。 人間には肉体がある。 欲がなければ死んでしまう。煩悩を活かしきって生きる。3. より以上を求めて生きるには「、よりよく」をめざす理想がなければならない 理想を頭で考えてはいけない。 欲求としての理想を持たなければいけない。 頭で考えた理想は命を苦しめる。 欲求として出てきた理想こそが命を喜ばせる。4. 理想をもって生きるには、自分の身に降りかかってくる問題、悩みが必要 問題も悩みもなくならない。 問題や悩みを乗り越え続けること。 問題や悩みがないことが幸せではない。
2006年02月04日
コメント(0)
-
人間として本物とはなにか NO.1
人間として本物になるための3つの問い1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持っているか2.より以上をめざして生きているか3.人の役に立つ人間になっているか・・・・・・・・・・・・・・1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持っているか ・不完全性の自覚とはなにか 「人間は神でもなく、動物でもない」 神は完全・絶対的 完全になろうとしてもなれない(人間は神ではないから) 動物は不完全性を理解していない 「不完全な人間と」して人間らしく誇りを持って生きる時代 ・「神」は存在するのか? →感性論哲学では、「神」という言葉が存在することは認める。 「神」が存在するかどうかは問題にはしない。 宗教は、「神は存在する」という前提から始まる。 しかし聖書も「はじめにことばありき」から始まる。「目に見えるものの背後に、目に見えないものが存在する」ことを 確信することから、「目に見えないものを大切にする心」が生まれた。 ⇒謙虚さがにじみ出てこそ初めて本物になれる ※謙虚さを持つためには A.人間は長所半分・短所半分と自覚する 短所は「活人力」になる。長所で、だまって人を助ける。 自分にも短所があることを自覚することで謙虚さを持てる 短所がなくなると人間でなくなる。なくなることはない。 短所があるから謙虚さが生まれる 短所を出ないように意識することが人間性を高める B.謙虚な理性を作る 理性は合理的に考えるすばらしい能力であるが、 合理的にしか考えられない有限・不完全な能力である。 理性は正しい判断はできるが、完全ではない。 理性を「よりよい」ことを考えるために使う夢・理想を作り出す力。 謙虚だけではだめ。それを裏付ける自信を持つ。自信だけでは傲慢。
2006年02月03日
コメント(0)
-
人間の格とは
人間は人格を持って生まれてくるのではない。人間は生まれた後に努力して人間としての格を獲得して人間になるのである。人格の柱は理性ではない。頭のよい人間が人格者であるとは限らないからである。人格の柱は、人間の存在的本質である感性である。人格となった人間性は作為的ではなく、命の底から自然にあふれ出て、感性的に表現されるものである。
2006年02月02日
コメント(0)
-
本物の人間とは
本物の人間とは、次の3つの条件を備えている。1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持つ。2.より異常をめざして生きる。3.人の役に立つ存在になる。そして、これを目的に努力することによって、人間は、本物の人間として、の格を持つことができる。これは、「問い」の形にして、常に自分自身に問いかける。1.不完全である事を自覚し、にじみ出る謙虚さを持っているか。2.より異常をめざしているか。3.人の役にたつ存在であるか。答えは、一つではない。答えを持つことは大切。もっと大切なのは、その答えに縛られないこと。縛られると他を排除しようとしてしまうから。人間は不完全だから、完璧はありえない。まだまだ努力・成長しなければいけないという気持ちが、謙虚さにつながる。今週土曜日 2月4日は、東京思風塾です。1回だけの参加もOKです。今回のテーマは、「人間として本物とは何か」13:00~20:00です。一つのテーマを徹底的に掘り下げてお話していただけるのは、東京思風塾だけです。沖縄・福岡から、北は福島・長野と全国各地から30名以上の方が集まります。一度ライブで聞いてみませんか?東京思風塾思風塾ホームページ
2006年02月01日
コメント(0)
-
本物の人間とは
本物の人間とは、次の3つの条件を備えている。1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持つ。2.より異常をめざして生きる。3.人の役に立つ存在になる。そして、これを目的に努力することによって、人間は、本物の人間として、の格を持つことができる。これは、「問い」の形にして、常に自分自身に問いかける。1.不完全である事を自覚し、にじみ出る謙虚さを持っているか。2.より異常をめざしているか。3.人の役にたつ存在であるか。答えは、一つではない。答えを持つことは大切。もっと大切なのは、その答えに縛られないこと。縛られると他を排除しようとしてしまうから。人間は不完全だから、完璧はありえない。まだまだ努力・成長しなければいけないという気持ちが、謙虚さにつながる。今月の東京思風塾のテーマは、「人間として本物とは何か」です。このテーマで、1時間少しの講義を5回。詳しく徹底的にお話いただけます。今週土曜日 2月4日は、東京思風塾です。1回だけの参加もOKです。今回のテーマは、「人間として本物とは何か」13:00~20:00です。沖縄・福岡から、北は福島・長野と全国各地から30名以上の方が集まります。一度ライブで聞いてみませんか?東京思風塾思風塾ホームページ
2006年02月01日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1