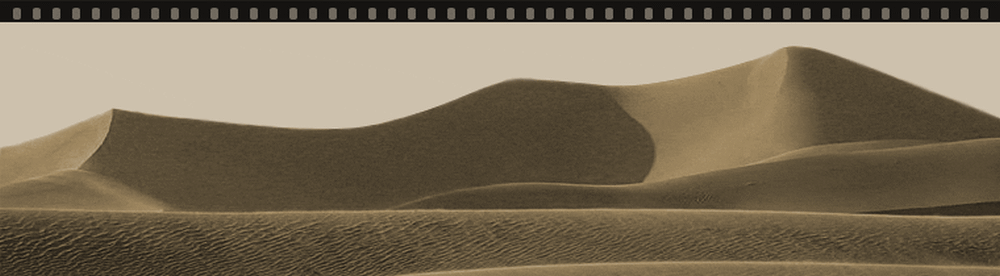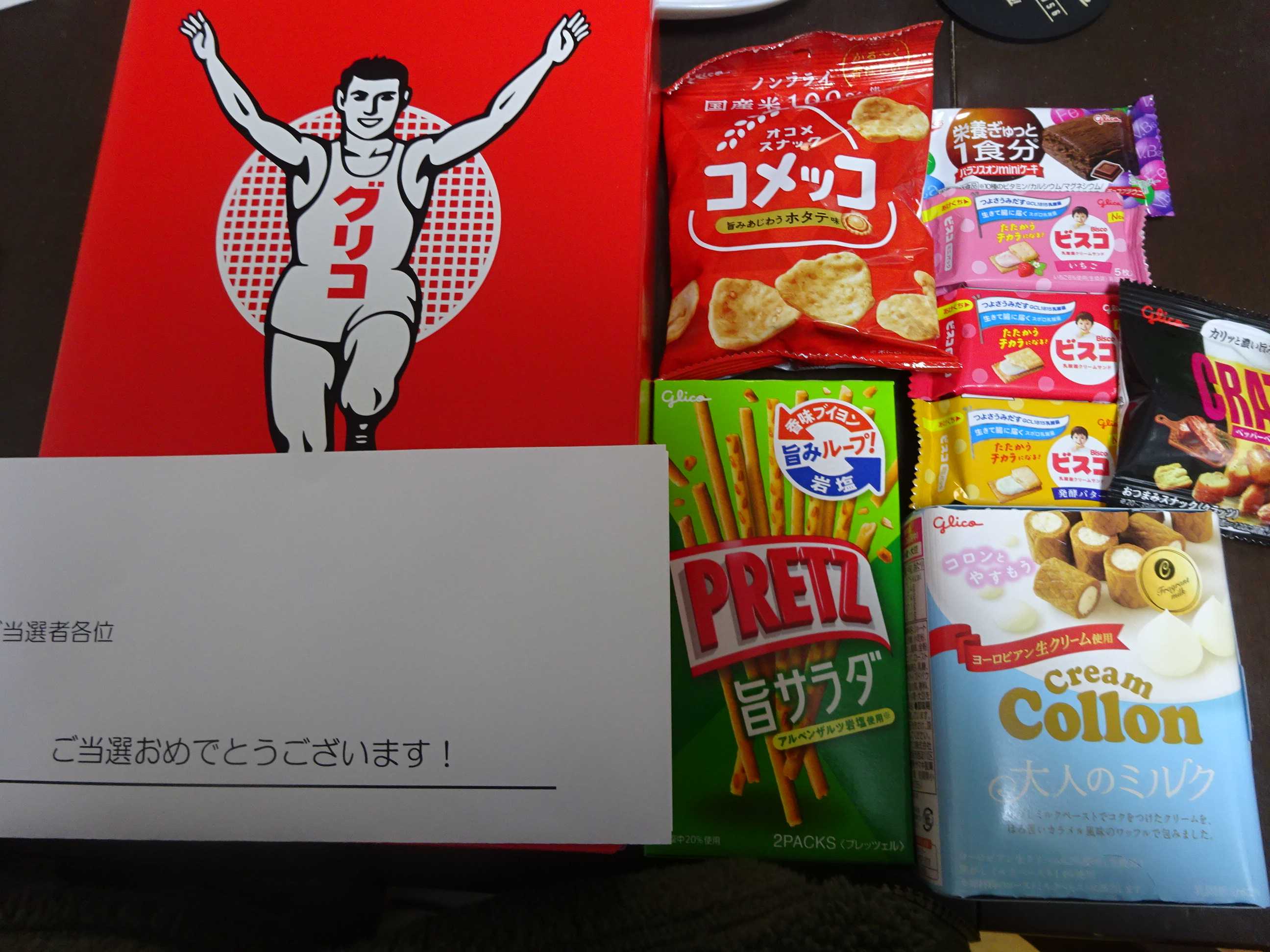2008年04月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

きょう(4・28)は、神田香織の講談サロン「香織倶楽部」第1回発表会に行ってきました。
プロの講談師ではなく、趣味で講談をやろうとする一般人のための講談教室の生徒さんたちの発表会です。会場は上野広小路亭。開演直前に着いたのですが場内は既にほぼ満員。かろうじて空いていた座椅子に着きましたがデブにはつらい体勢でした。7人の生徒が登場。中には、師匠の神田香織さんと3人並んで講じた生徒もいました。落語を聴くのが好きな私ですが、もし、自分でやるとしたら落語ではなく講談だと思っていました。5月末から第2期が開講するそうですが、受講するかどうかは、まだ迷っています。
2008.04.28
コメント(2)
-

昨夜(4・27)は、第20回の古今亭菊之丞独演会でした。
来場者は102人。 演目は「崇徳院」と「花見の仇討ち」毎回、着実に来場者は増えています。ところがデータを入力していたAccessファイルが破壊され、完全な修復が出来なかったために、一部のデータが欠損してしまい、第18回の来場者数の確認ができませんでした。 第16回(1/21) 64人 第17回(7/29) 84人 第18回(10/17) ?人 第19回(1/27) 95人 第20回(4/27) 102人毎回、着実にお客さんが増えていますので、お陰様で、黒字になってきました。「累積した赤字」が消える目途も立ってきたので、「そろそろ出演料を上げたいね」と世話人同志では話し合っています。
2008.04.28
コメント(0)
-
昨日(4・21)は、奥さんと「東西若手落語家コンペティション2008」に行ってきました。
「東西若手落語家コンペティション2008」の会場は都内・内幸町ホール。ここは落語会にはちょうど良い大きさで、好きな会場です。2008年度・第1回の出演者と、その演目は下記の通りです。(演目の後ろの数字は所要時間です) 林家染左 時うどん(23) 三遊亭天どん 反対車(20) 立川談修 家見舞い(25) 桂阿か枝 千早ふる(19) 古今亭朝太 粗忽の釘(24)審査員は会場のお客さんです。入場するときにプログラムと一緒に投票用紙を渡されました。プログラムには<投票権>として下記のように書かれていました。観客の投票権は、5人の演者すべての演目を聞いた場合にのみ有効とする。途中入場、及び、退席はいずれの場合も無効とする。このルールは納得できます。司会の林家いっ平は「居眠りしたお客さんも投票権を失います」と言って笑いをとっていました。後半の出演者も「きょうのお客さんは最後まで絶対に帰らないからやりやすいや」と言って、笑いをとっていました。理解できないのは。1枚の投票用紙(A4サイズ)の上下に、同じ5人の出演者の名前が印刷されていたことです。プログラムには<選出方法>として下記のように書かれていました。印象に残った方のお名前を上段に一人、下段にも別の方を一人、計二人お選び下さい。(○が1つのみ又は3つ以上ある場合、同一の方に○のある場合は無効票とします)司会は「昨年とはこの辺りのルールが変わりました」と言うだけで、なぜ、このようなルールになったのかについての説明はありませんでした。会場を出てから、この主旨に気づきました。「動員票の効果を薄めるため」なのです。「一人だけに○をつける」方法だと、できるだけ多くのフアンを動員できる噺家が有利になってしまいます。これは、とくに関西の噺家には不利になってしまいます。今回のルールのように「別の人にも必ず1人○を付けさせる」ことにすれば、どんなにフアンを動員しても、その数だけ、別の噺家にも票が行くことになるのだから、ある噺家がフアンを動員したからといって、それで自分だけが特に有利になるわけではありません。ライバルへの投票が増えるのが嫌だからといって「1人だけの○」は無効票になってしまうのです。私も、奥さんも、投票した人は同じでした。立川談修と古今亭朝太です。二人とも優勝の予想は朝太で、その通りの結果になりました。もうネットのニュースで流れています。通常の落語会とは違った緊張感と楽しさがあったので、次回も聴き行こうと決めました。
2008.04.22
コメント(0)
-
きょう(4・17)は一人で「立川流広小路寄席」に行ってきました。
お目当ては立川談笑さんです。ほかに「いつかは聞いてみたい」と思っていた人が2人いたので、わわわざ、この落語会を聞くためだけに飯能から上野まででかけたわけです。自宅を出るのが少し遅れて、前座と立川談奈、立川志らべの3人を聞き逃してしまいました。ぎりぎり談笑さんの出番に間に合いました。お客の入りは9割ほど。小ネタでしたが、きょうの談笑さんも楽しませてくれました。与太郎と対峙している叔父の店主の、その目の動きで、与太郎が掃除をしている情景を感じさせてくれました。何度も聞いているネタなのに、演者が違えば、楽しませてくれるのが落語の良さであることを実感させてくれます。この後、殆どの出演者が「きょうは凄いお客の数ですねぇ、普段はこんなに入っていないんですよ」と言っていましたが、はっきり言って、大半のお客は「談笑さん目当て」ではないでしょうか・・・他の出演者は下記の通り。桂文字助 立川龍志 立川吉幸 立川志遊 立川談幸 立川ぜん馬もう、私の中では、立川流一門でのベスト3は、<立川志の輔・立川談春・立川談笑>です。
2008.04.17
コメント(0)
-
昨日(4/13)は、地元と瑞穂町の地域寄席2ヶ所をハシゴしました。
最初に行ったのは、我が家から徒歩5分ほどのところにある能仁寺。飯能駅からはやや遠い(徒歩20分くらい)ので、みなさん、車で来ているようです。大きな寺院なので駐車場は充分にあります。ここでも了解を得て、<有望若手応援寄席>のチラシを配らせていただきました。少し小雨が残っていましたが、大きな軒下でしたので濡れずに手渡しできました。ポスターやチラシ、お寺のwebサイトには<国際チャリティー寄席>と書かれていて、入場は無料ですが、<ご寄付を募ります>と明記されていました。廊下に置かれていた募金箱に1000円入れました。(ホント!)受付では来場者全員に袋に入ったお菓子とペットボトルのお茶が配られました。ということは、聴きながら飲食してもいいのでしょう。私も、そうさせていただきました。会場の本堂はほどよく満員。飯能市内にはお寺がかなりたくさん有るのですが、落語会が開催されるのは「年に1回有るか無いか程度」なのです。出演者と演目は下記の通りです。 三遊亭遊雀「牛ほめ」 翁家喜楽 太神楽曲芸 中入り 三遊亭遊雀「天狗裁き」挨拶に立たれたご住職の話によると「初めての落語会」とのことでした。お寺の本堂は、落語会の会場としては悪くないと思いますので、もっと増えていくことを願っています。会場を出て、我が家を素通りして徒歩でJR八高線の東飯能駅へ急ぎました。次に行く「みずほ寄席」の会場は、二つ目の箱根ヶ崎駅ですが、駅からはけっこう歩く(20分)のです。会場の瑞穂町福祉会館は地元の人以外にはわかりにくい場所にあります。前回も迷って、何度も人に道を尋ねましたが、今回も駅から会場までの間で2度も訊ねてしまいました。コピーしたGoogle地図を持っていてもわかりにくいのです。「みずほ寄席」については、2007/12/24にも書き込みましたが、今回で2回目です。前回は和室でしたが、「来場者からは椅子席の希望が多かった」ということで、今回は全員椅子席の部屋でした。出演者は、当初、古今亭菊之丞さんの予定でしたが、風邪をひいて喋れないとのことで急遽、春風亭柳朝さんに代わりました。「代演」でもお客さんから不満が出ないのが落語会の良さでもありますね。これは主催者として安心できる要素です。出演者と演目は下記の通りです。 古今亭志ん坊「道灌」 春風亭柳朝「悋気の独楽」 中入り 春風亭柳朝「鮑のし」古今亭志ん坊は、前座になってまだ1年だそうですが、かなり上手いし、落ち着いていましたね。私が、柳家三三、入船亭扇辰、春風亭柳朝、古今亭菊之丞、三遊亭好二郎を初めて聴いた時は、彼らはすでに二つ目でしたが、この「志ん坊」という前座さんは、私が前座として聴いた噺家さんの中でピカイチです。と思っていたら、帰宅してたまたま読んだ落語関係のブログにも志ん坊はうまい」と書き込まれていました。これからは『東京かわら版』でチェックして古今亭志ん坊をおっかけてみようと思いました。帰りも途中の十字路で進むべき方向に自信が持てずに立ち往生していたとき、近づいてきた人に「箱根ヶ崎の駅に行く方向はどちらでしょうか?」と訊ねたら、「私も駅に行きますから一緒にどうぞ!」と言われました。若い女性だったので「えっ?!」と驚きましたが、「落語の会場にいらしてましたよね」と言われて納得。私と同じように主催者のSさんから誘われた方で、帰る方向は違っていましたが、電車が来るまで「落語談義」で話しが弾みました。これも地域寄席の良さでしょうね。
2008.04.14
コメント(4)
-
地域寄席を重視している噺家さんとの共著もいいなぁ・・・
『地域寄席の楽しみ方』という本は、地域寄席を主催する人の視点(つまり私)と、地域寄席に出演する噺家さんの視点と、各地の地域寄席を楽しみにしているお客の視点という<三者三様の視点>で書かれていたほうが、読む人にとっては面白いでしょう。地域寄席を主催者の視点で、読む人が期待するのは、主催者の<建前と本音><開催までのプロセス>、そして<苦労したコト・楽しかったコト><主催者のメリット・デメリット><運営上の工夫と失敗><これからの夢と計画>などでしょう。地域寄席に出演する噺家さんの視点で、読む人が期待するのは、<出演者としての建前と本音><出演するようになった経緯><地域寄席での嫌なコト・楽しみなコト><寄席との違い><地域寄席全体への期待と懸念>などかもしれません。地域寄席を楽しみにしているお客の視点で、読む人が期待するのは、<各地の地域寄席ガイド><地域寄席の種類と違いの解説><行きたくなる地域寄席・二度と行きたくない地域寄席><地域寄席の開き方>などかもしれません。これを、全部、私一人が書いても、あまり面白くないかもしれません。そこで、誰か、地域寄席を重視している噺家さんとの<共著>というのも面白いと思っているのですが・・・・
2008.04.11
コメント(0)
-
当ブログの目的は『地域寄席の本』にするコトです。
実は、私が、当ブログを始めた目的の一つは、「地域寄席のことを書いた本を出版したい」ということでした。私はいままで9冊の自著がありますが、いずれもビジネス書ばかりで、落語関係の本は一冊も書いたことはありません。(私の自著9冊を知りたいかたはAmazonで 小久保達 と検索して下さい)私自身の<落語家ファン度>を相撲番付になぞらえて自己評価すれば、もちろん、横綱大関クラスでもなければ幕内上位クラスでさえありません。しかし、だからと言って、序の口や三段目クラスでもないでしょう。東京都板橋区で生まれ育ったので、小学6年生の時から池袋演芸場や、日比谷の東方名人会に通っていたし、いまでも都内の寄席や落語会には年に20~40回くらいは出かけ、自分でも地域寄席を毎月主催しているのだから、幕下上位か十両中位くらいには相当するのではないかと自負しています。それでも、そんな私が「地域寄席の本」を書いて、どこか名の知れた出版社から出版してもらおうと考えたのですから、無謀と言うか、厚かましいと言うか・・・・やや妄想に近いのかもしれません。しかし、すべての<企画>は、まず<妄想>から始まるのです。妄想ですから、勝手に、タイトルだけは浮かんできたのです。ズバリ! 『地域寄席の楽しみ方』です。あるいは『地域寄席入門』とか、『いま、なぜ、地域寄席が増えているのか?』という案も捨てがたいですね・・・
2008.04.10
コメント(0)
-

きょう(4/2)は、三三さんがトリを取る鈴本演芸場上席夜の部に、奥さんと行ってきました。
少し早めに上野駅に着いてので、公園口の改札から駅を出て、花見客で混雑する上野公園の中を通り、不忍池の辺を歩いて、鈴本へ。記憶では、昨年の柳朝さんの襲名披露興業の時は、きょうと順番が逆で、寄席が終わってから夜の上野公園の桜を見ながら、公園口の改札から電車に乗ったのを思い出しました。三三公式サイトから、割引券のプリントを持参したので、当日2800円の入場料が2200円。二人で1200円もお得ですから、途中のコンビニで買ってきたイナリ寿司とオニギリ代になりました。開演前は、会場の了解をもらって、ロビーにあるチラシコーナーに「有望若手応援寄席・飯能」のチラシを置くことができました。会場の入りはほぼ半分。出演者は下記の通りでした。 林家たい木「寿限無」 桂才紫「代書屋」 太神楽曲芸・和楽社中 古今亭菊志ん「松竹梅」 柳亭市馬「長屋の花見」 漫才・ホームラン 橘家文左衛門「桃太郎」 入船亭扇遊「一目上がり」 奇術・伊藤夢葉 三遊亭白鳥「新作」 曲独楽・三増之助 柳家三三「宿屋の仇討ち三三さんの初日のネタは「ねずみ穴」だったそうです。明日(4/3)の鈴本演芸場は休演で、「新にっかん飛び切り落語会」だそうですが、そこでは三遊亭好二郎さんと一緒のようですね。できれば、「三三・好二郎ふたり会」なんてのが実現すると面白いと思うのですが・・・・
2008.04.02
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1