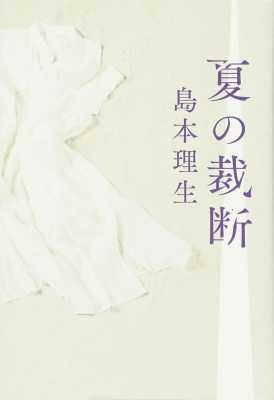2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年09月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
金城哲夫の沖縄芝居6
明日からしばらく東京なので、今日のはだらだらエッセーになると思う。 さて今日はぼんやりとネットで尚巴志のことを調べていた。特に重要な点は、金城以前に尚巴志がどのように描かれてきたのか、という点である。ところが無いのである。もちろんネット検索だけで本気調査ではないので、結論づけるのは早計であるが、なかなか見当たらない。組踊は第二尚氏の宮廷で演じられたものだから、第一尚氏のスーパーマンぶりはまずいのかもしれないが、娯楽を旨とする近代沖縄芝居なら何度も題材に上がっていてもおかしくない。ところが例えば昭和初期に渡嘉敷守良が書いた「今帰仁由来記」などは時代は重なっているのだが今帰仁城が滅びたあとの話で、尚巴志は出てこない。 尚巴志というのは私の知る限りにおいて、琉球史上最大の英雄である。おもろに「鬼鷲」とうたわれ、実質一代で小さな地域の按司から、三山統一に至り、琉球王国の基礎を築いた。その業績は2位が誰かわからないほどの、ぶっちぎりの一位である。しかも誕生時の予言とか他にも興味深い要素があるので素材としては悪くないはずである。平田大一の「翔べ!尚巴志」の宣伝文に本来ならば偉大なる王として宣揚されなければならないはずの彼の偉業が、現在の沖縄で語られていないのはいったい何故か…。と書いてあるのだが、答えは教えてくれないw。しかも現在のみならず、ずっとほとんど描かれてこなかった可能性がある。その一方何度も語られるが非業の死をとげた護佐丸と阿麻和利である。現在尚巴志で検索するとローカルなハーフマラソンがまず上がるし、尚巴志×組踊だと平田大一、尚巴志×沖縄芝居にいたっては、私が2、3日前に書いたこのブログが一番上でヒットしてしまう>< 金城以降の作品は少なくとも2つある。先に挙げた「翔べ!尚巴志」=「鬼鷲~琉球王尚巴志伝」(完全に同じなのかは未確認)。その前、1995年に沖縄ローカルで「琉球風雲児 尚巴志物語」という人形劇が放送されたようである。金城の作品を含めると、この三作には共通点がある。それは東京である。 金城については言うまでもない。「琉球風雲児 尚巴志物語」の作者は小澤公平という人で東京出身、沖縄アクターズスクールの立ち上げの時沖縄に来た人である。また平田氏は大学時代を東京で過ごしており、その経験がなければこれほど自由に古典を改変する発想が得られたかどうかといった感じである。要するに東京でなくともいいのであるが、外からの視点がないとなかなか尚巴志を取り上げないのではないか。ちなみに最近大城立裕が「今帰仁落城」という新作組踊を書き、これには尚巴志がでてくるが、完全に今帰仁サイドからの物語である。 この程度の勉強で仮定というのもなんなんであるが、「テンペスト」で描かれたみたいに長い第二尚氏の時代、尚巴志がタブーであったのか、琉球王は家康や秀吉よりむしろ天皇に近く、そもそも描くことがいけなかったのか(だとすると「首里城明け渡し」もだめだよなあ)、そもそも伝統的な沖縄文化においては尚巴志みたいな100戦100勝のキャラクターは馴染まなかったのか、なんとなく最後のが近いような気がするが、それはもうちょい勉強しないと何とも言えない。
Sep 20, 2012
コメント(0)
-
金城哲夫の沖縄芝居5
今日は「風雲 琉球処分前夜」を読んだ。この作品の初演は1972年の4月であり、本土復帰の1ヶ月前のことである。まさに「復帰前夜」になぜ琉球処分なのか、ということなのだが、読んでみるとわかった。琉球処分には今なおいろいろな解釈があるが、「風雲 琉球処分前夜」ははっきりと大和派の宜湾親方のサイドに立ち、琉球処分に肯定的である。清との関係を守ろうとする頑固派の亀川親方は、完全に琉球士族の既得権益の擁護者という扱いになっている。 宜湾親方対亀川親方の二項対立にすると、どちらの言い分も相対的になってしまうので、宜湾朝保の進歩主義を支えるのが、主役の大里朝輝である。これは現時点では全くの架空と思われる。よく似た名前には摂政だった大里朝教がいるが、キャラクター的に全く関係ないと見るべきだと思われる。 注・こういう書き方をすると、私がとっくの昔に琉球処分の関係者を知っていたと誤解されてしまうが、宜湾や亀川は大城立裕の「小説・琉球処分」を読んだから知ってるだけであって、大里朝教など10分前に調べて初めて知ったのである。 さてキャラクターの方の大里朝輝の方であるが、彼は農民出身なのであるが、進歩的な宜湾に能力を認められ取り立てられたという設定である。(実際に宜湾がそんな事をしたのか、現時点では知らない。いずれ調べる)そして大里が守旧派士族の前で、士族の傲慢と農民の解放を訴える場面が芝居の見せ場になっている。これにより「琉球処分」は農民解放という側面が強調されることになる。 この作品は金城哲夫の沖縄芝居を考える上で、最も重要な作品だと思われる。1,沖縄芝居の史劇の中で最大のヒット作とされる山里永吉の「首里城明け渡し」という先行作品がある(今はまだ読んでいない。また山里の脚本と実際の上演とに微妙な差異があるらしく、ここは結構大変)。今年の12月には「首里城明け渡し」もまた上演されるらしく、これは行かねばなるまい。2,2年前の1970年には大城立裕「小説・琉球処分」を原作とする「琉球処分」が新劇として上演されている(この事実を知ったのも今日)。大城と金城とは大変親しかったので、見ている可能性は濃厚である。さらに「小説・琉球処分」そのものの影響。「小説・琉球処分」の読み直しは結構大変である。3,既に見たとおりの内容から、金城は復帰を良い意味での第二の「琉球処分」と考えていた、もしくは期待していた可能性が濃厚だと思われること。4,現在「第二の琉球処分」というと悪い意味で使われることがほとんどである。「琉球処分」の受容史も考え直さなくてはならない。そのためにはまずこの作品の同時代評を確認する必要がある。5,進歩主義者金城哲夫という側面がかなりくっきり表れていること。これと復帰後の金城の苦悩との関連。 というわけで、ここはかなり宿題が多いのであるが、今回直近の目標は「虎!北へ走る」を良く理解することなので、宿題は宿題として先に進む。
Sep 19, 2012
コメント(3)
-
金城哲夫の沖縄芝居4
ここらで年表。どんな作品研究でもやらなければいけないというものではないが、やはりあったほうがいいと思う。1969 昭44 金城円谷プロ退社、帰沖。上原も退社、フリーに。 佐藤ニクソン会談72年返還を合意 沖縄基地内でガス漏れ事件(7)、米軍毒ガスを撤去と発表 アポロ11号月面着陸1970 昭45 大阪万博、70年安保 「佐敷の暴れん坊」初演7月1971 昭46 4月2日~昭和47年3月31日 「帰ってきたウルトラマン」金城「毒ガス怪獣出現」(6/11) 「佐敷の暴れん坊」再演「潮」旗揚げ公演、7月。 「一人豊見城」12月。 1972 昭47 沖縄本土復帰(5月15日)。浅間山荘事件「成長の限界」(ローマクラブ) 「泊気質 ハーリー異聞」2月。 「風雲 琉球処分前夜」4月11日〜14日。1973 昭48 第四次中東戦争、オイルショック小松左京『日本沈没』光文社 「虎!北へ走る」「潮」三周年、7月3日〜7日。1974 昭49 ゴジラ対メカゴジラ(東宝)1975 昭50 海洋博 開会式・閉会式の演出担当。 「王女の恋」9月6日、7日。1976 昭51 金城没 2/26(37才)1977 昭52 「泊気質 ハーリー異聞」再演、10月9日、10日。1978 昭53 「一人豊見城」再演、「潮」8周年。11月18日〜22日。
Sep 18, 2012
コメント(0)
-
金城哲夫の沖縄芝居3
金城の沖縄芝居は数が少ないので当然全部読むのであるが、今日は特に優先順位の高い「佐敷の暴れん坊」を読んだ。これは「虎!北へ走る」の前編であると同時に、金城最初の沖縄芝居である。 昨日の記述には一部間違いがあり、初演は1970,7,1~3。「宮城亀郁謝恩の夕べ」再演が1971,7,17・18 「劇団『潮』旗揚げ公演」である。 物語は若い頃の尚巴志(虎寿金)が、単なる暴れん坊から徐々に成長し、最後に暴虐な大里按司を倒すという単純明快なものであり、派手な立ち回りが何度もある娯楽性の高い作品である。*「虎寿金」というのは伝承によれば北山王、攀安知の5男である。なぜこの名称を尚巴志の幼名に用いたのか不明。*「三良」という友人は既にこの作品にも登場しており、やはり北村三郎が演じている。金城が北村のために創作した人物というのは、多分あっている。*尚巴志は若い頃、持っていた刀を異国人の大量の鋼と交換しそれを農民達の農具に転用した、という伝承があるが、この作品では鋼を大里按司の武器に転用される、と書き換えている。*尚巴志登場の場面ではトマトをかじっているなど、非常に自由な創作態度。*途中で育ての親と恋人が殺されるのだが、これは勝利を盛り上げるための要素であり、「虎!北に走る」の王妃のような、暗いエピソードはない。
Sep 15, 2012
コメント(0)
-
金城哲夫の沖縄芝居2
今日やったこと。 まず「虎!北へ走る」の脚本を読んだ。この作品は三山時代、尚巴志の北山攻略をモチーフにしたものである。難攻不落の今帰仁城をいかに攻略するかを縦軸に、二人の女性が横軸として関わってくる。思ったこと感じたこと。(これらは全て調べる以前の思いつきであり、具体的な根拠はないものも。生きるのもあるし捨てるのもあります。しかし読書メモは非常に重要です。) 冒頭の冷害は沖縄の物語としては異色。ウルトラセブン「零下140度の対決」との関連。 そもそも沖縄に冷害なんか起こるのか。 タイトルはこれまたウルトラセブン「ウルトラ警備隊西へ」と似ている。 三国志の影響? 尚巴志は平和主義者として描かれている。劉備みたいな感じ。 敵の豪傑、本部平原を味方につける方法が呂布と貂蝉の話に似ている。 実質的な国王が平民のふりをして忍び込むあたりは水戸黄門ちっく? 王妃のキャラがすごい。さつきさんこれを演じるのか!芝居全体から言うとスパイスのようなものかもしれないが、金城作品では異例の存在のような気がする。 北山王、攀安知が単なる敵キャラに終わっていない。彼が悪い王になったのは、夫婦の不幸な過去のせいだと解釈せざるを得ない。これは痛快娯楽劇であるはずのこの作品に暗い影を落としている。※初読の印象をメモしてから図書館へ。3冊借りてきた。1、『金城哲夫の世界(沖縄編)』 これは沖縄時代の金城作品のバイブル。今回改めてよくできた本だなあ、と思った。 わかったこと。「虎!北へ走る」の初演は1974、7、3。劇団「潮」3周年記念公演。演出は金城自身が行っていた。3年前の旗揚げ公演で好評だった「佐敷の暴れん坊」の続編ということになっている。その時の舞台監督は今回の方言翻訳を行なった北村三郎氏。また北村氏は当時「三良」の役で出演している。この人物は現状金城の創作と思われ、「三郎」からとったのかも。他に平良とみや旦那さんの平良進なども出ている。2、大城立裕『琉球の英傑たち』 これは尚巴志のことを簡単に知るため。攀安知が民を思わない王であったことや、今帰仁城が要害であったことが増長の理由だったなど、基本的に大枠は同じであることがわかった。王妃についてや冷害についての記述はない。この程度でいいような気もするが、機会があったらもう少し詳しい歴史書見るべきかも。3、大野道夫『沖縄芝居とその周辺』 みずほ出版2003、9、1。 これは広く沖縄芝居を理解するため。組踊と違って沖縄芝居は近代に入ってあらわれた大衆芸能であるため、体系的な研究というのはあまりない。この本も悪い本ではないのだが、個人的な思い出話などが多い。また「です、ます」調なので読みにくい。 沖縄芝居については、金城以外の作品をもう少し見るほうが先決かも。 夏休みだし、初日としてはまあまあ進捗した。
Sep 14, 2012
コメント(0)
-
金城哲夫の沖縄芝居1
まず告知沖縄新作芝居「虎北へ走る」2012、12,22(土)。23(日)。国立劇場おきなわ脚本 金城哲夫演出 幸喜良秀翻訳・演技指導 北村三郎尚巴志 嘉数道彦尚忠 宮城茂雄浦添按司 宇座仁一 (他) 全部で30人以上も出てくるので(他)としたが、その中に大野ゼミ卒業生の天願雄一、他ゼミだが日文(国文時代?)卒業生の伊良波さつきさん、が出ます。あ、あと準主役の宮城茂雄君も狩俣ゼミの卒業生ですよ。 で、これについて書くことになったのだが、金城哲夫については多少知っているのだが、沖縄芝居についてはお寒い限り。ちょうど今卒論を書いてる4年生、テーマを決めたばかりの3年生と大差ない。 そこでまた勉強の実況をしていきます。
Sep 13, 2012
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1