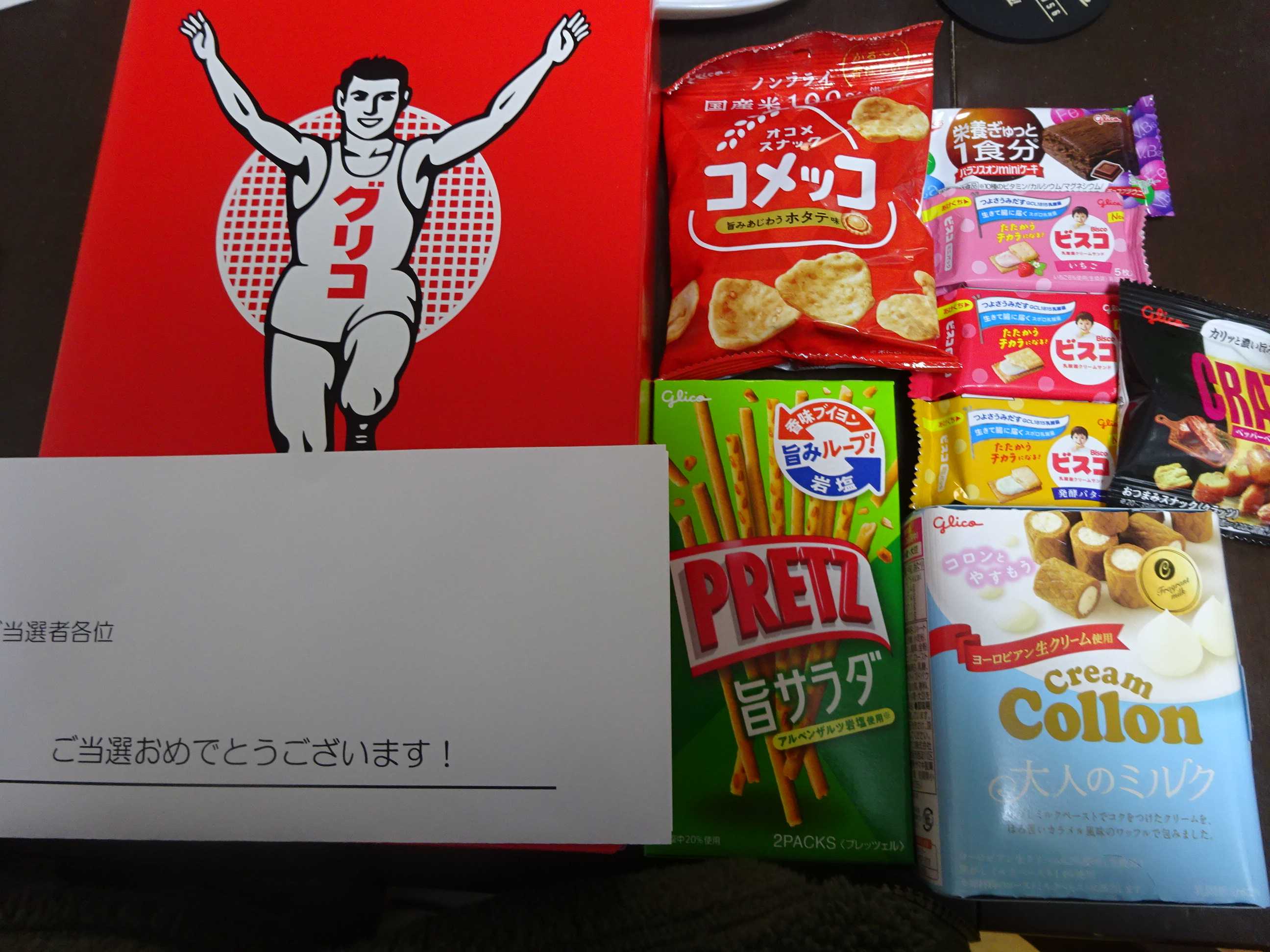2005年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
実は90%の削減が必要なです。
2月16日に京都議定書が発効されました。日本は1990年比で二酸化炭素の排出量を6%削減する必要があります。また日本では二酸化炭素の排出量が1990年比で8%も増えてしまいました。したがって合計14%の二酸化炭素を削減しなければなりません。ところで14%削減すれば地球温暖化は防げるでしょうか。実は14%削減だけではまだまだたりません。大気中の二酸化炭素濃度を360ppmに安定させれば温暖化は防止できます。そのためには地球全体で今の二酸化炭素の排出量を60~70%削減しなければなりません。排出量の多い先進国ではそれ以上の削減が本当は必要なのです。では日本はどれくらい削減する必要があるのでしょう。京都大学の松岡護教授(環境工学)によると…。「日本は80~90%を削減しないといけない計算になる。 たいへん厳しいが、達成しないと国内でも悲惨な影響を受けることになる。 あと半世紀、できるだけ早く、本格的に取り組む必要がある」(2005年2月16日「讀賣新聞」)「悲惨な影響」とは例えば昨年公開された映画「デイ・アフター・トゥモロー」のような状況です。温暖化により海水の循環が止まると赤道一帯の熱が高緯度地方に伝わらず氷河期のような寒冷化が急激に起こる。英国のサウサンプトン海洋学センターによると、「十分な温暖化対策をとらなかった場合、今世紀末までに30%の確率で海水の循環が止まるという結果」(同紙)が出たそうです。14%削減は「十分」ではないですが、大きくて小さな第一歩と言えるでしょう。
2005.02.28
コメント(0)
-
ドッジボールの投げ受けは低学年までに身につけておきたい技術である。
腰および左肩の痛みが少しずつだが和らぎつつある。2人の娘と愛犬ゴロウの散歩に出かける。2人のドッジボールの投げ合い受け合いを見て随分うまくなったと感心する。女の子だがドッジボールの投げ受けはある程度できていた方がいい。片手で投げてしっかり受け取れるという技術は小学校低学年まででしっかりと身につけさせていきたい。夜はご近所のTさんご夫婦を招いてお食事会。おでんを中心に美味しい料理が並ぶ。この日の酒は「英勲」だ。2日続けて豪華な夕食となる。
2005.02.27
コメント(0)
-

伝統的な日本料理を堪能する。
一宮さん宅で行われたお食事会に誘われた。伝統的な日本料理が盛りだくさんに振る舞われる。ビールは「エビスビール」。清酒は、濃厚「春鹿」・すっきり「やどりぎ」・あっさり「半蔵」といったほんまもん。 1日1食の我が人生の今宵の1食はとてもとても豪華絢爛なのだ。お腹一杯食べてもお腹が出なくなった我が体質は同時に酒に敏感に反応する。たのしい食事中3回ほど数分間眠ってしまうのである。最後は焙りたてコーヒーを飲む。いやはやほんとうにごちそうさまでした。
2005.02.26
コメント(0)
-

特別授業 「一杯のコーヒーから地球が見える」
一宮唯雄さん【*1】の特別授業を行う。1時間目は、薬としてのコーヒーの歴史をひもとき、健康食品としてのコーヒーにまつわる面白話をくりひろげる一宮さんの講義を聴く。一宮さん作詞の歌「おいちーおいしいコーヒー」を歌のお姉さん(田中さん)が披露する場面もあり、子どもたちは楽しくコーヒー学習ができる。2時間目は家庭科室へと場所を変えコーヒー焙煎を体験する。簡易焙煎器「焙りたて名人」を使い子どもたち全員が生豆を焙煎するのである。ものの5分とたたぬうちに香ばしい焙煎豆のできあがりだ。「あま~い香りがする」と言う子らもいる。朝日新聞・毎日新聞・日本食糧新聞・サンテレビ・ミニコミ誌「ザ淀川」といった報道関係者の方々【*2】が取材するなか子どもたちは実に生き生きとコーヒー焙煎を楽しんでいる。市販のコーヒーと自分たちが焙煎したコーヒーと飲み比べる。断然自分たちで焙煎した焙りたてコーヒーの方がおいしい。【*3】「食品栄養学上、コーヒー本来の正しい賞味期限は、焙煎後約『豆で7日、粉で3日、たてて30分』」という一宮さんの言葉に納得するのだ。なぜ今回このような授業を企画したのか。子どもたちは環境学習「ECO発信」の真っ最中である。特に今は社会科で「森林を守る」学習もしているところだ。・コーヒーなどの換金作物による森林破壊・「先進国と発展途上国」といった「南北問題」・生産国を支援する公正貿易(フェアートレード)また家庭科では「正しい食生活」の学習もしている。・食の安全性・食品表示・簡便さに流されない手作りの良さそういった様々なことに気づくきっかけを与えてくれる特別授業だからである。まさに「一杯のコーヒーから地球が見える」である。【*1】NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」代表。お気に入り参照。【*2】「取材依頼は1週間前までに」等等といった取材規制が今年度から設けられ、取材を見送った方々もいて、恐縮することが少なくなかった。【*3】「おいしい」と言った子がほとんどだが中には当然「苦い」という子もいた。豆の量を調節してやや薄目のコーヒーにした方が子どもには飲みやすいだろう。その他。焙煎から始まるコーヒー作りの手順は1時間目に行う。時間的ゆとりをもってコーヒーを飲みつつ一宮さんの面白話を聞く。
2005.02.25
コメント(2)
-

椎名誠さんのECO的話を聞く。
椎名誠さんの話を1時間ほど聞く。といってもこれは基調講演という場での話だ。椎名さんによると世界には大きく分けて3つの種類の川があるという。1 アマゾン川・メコン川・ガンジス川2 日本の川3 スコットランドの川(スペイ川)詳細はシーナ兄貴の近著『メコン・黄金水道をゆく』(集英社)をぜひ読んでほしい。ほかにも「エネルギー」や「水不足」といった環境問題の話をシーナ兄貴独自の視点で語ってくれた。私は図解的書き留め(メモ)をしながら話を聞く。当然、話の後の質問あらかじめ考えている。ところが。「時間がきました。話を終わります」そう言って椎名さんは舞台を後にした。司会の方が「もう一度、拍手を」と言ったとき、すでにもう椎名さんはいないのだ。う~ん、椎名さんらしいなと思う。「それでは15分ほど休憩を取ります」と司会者。15分もあるのなら質問の時間を取ってくださいよ、と強く思ったのである。実はシーナ兄貴を我が家にお招きしようと準備をしていたのだ。1 事前に手紙を出す。(A4の紙7枚)2 京都は伏見の酒蔵で「やどりぎ」を買う(兄弟の盃用)3 ハガキを出す。4 基調講演での質問を用意する。(今日明日の旅のご予定を聞く)5 焙りたてコーヒーを用意する。6 オルター食材を買いそろえておく。7 つれあいが特製の鍋料理をつくる。8 「エビスビールあります」9 みのおエフエムの方をお招きする。(その他約数十種類)兄貴なら電話連絡なしでもひょっこり来てくれるだろう、と思っていたのだが…。まあ今日は雨がひどいから…。などと自分に言い聞かせ、連れ合いが作ってくれた特製鍋とエビスビールを少々飲んで夜7:45には眠ってしまった。ひょっとして夜中に兄貴が来るかもしれないと思いつつ…。
2005.02.24
コメント(0)
-
毎晩、足がつる原因がわかった。
寝ているときに足がつる。「こむらがえり」というやつである。余談だが学生の頃まではこれを間違って「コブラがえり」と言っていた。以前はラグビーの試合後などに足がつったりした。寝ているときに足がつることもたまにあった。しかし最近は毎晩のごとく足がつるのである。少し前までは足がつるとアイタタタと言って素早く起きストレッチなどをした。それでも治らないから痛みがやむまで部屋中を歩き回ったりもした。ところがもうそんなことさえも面倒くさくなり足がつってもじっとそのまま痛みに耐えて寝ている今日この頃である。この痛みは気持ちいいんだ、ああ気持ちいいと自分に言い聞かせながら寝るのである。するとおそらく数分後には痛みも消えて知らぬ間にまた眠れるのだ。安全な食べ物ネットワーク「オルター」代表の西川英郎さんを講師に招き特別授業を行う。豆腐の試食を通して食の安全を考える授業である。オルター使用の豆腐数種類と市販の豆腐数種類を用意して子どもたちに「◎○△×」と4段階で味の評価してもらう。西川さん曰く「この子たちの舌が心配」といった結果となる。授業後、校長室で西川さんに食や健康に関することを1時間ほど聞く。毎晩、足がつるのはなぜなのか、という質問もする。「肝臓が悪い」(つづく)
2005.02.23
コメント(4)
-
オルター食材でイチゴ付きの紅茶時間
そうじをしっかりやったら後で美味しいイチゴと紅茶をいただこう。3時間目、子どもたちにそう呼びかけた。別にお菓子でつるわけではない。これはれっきとした家庭科の学習なのだ。教科書にも掃除の後に「ティータイム」などと書いてある。「クリーン作戦」後「ティータイム」で「トーク」しようというわけだ。あえて英語を使うのがいやなので先の文は次のように訂正する。掃除徹底活動後苺付紅茶時間会話をしよう。なんだか漢字が多いが要はそういうことだ。紅茶・ヨーグルト・イチゴ・黒糖、すべてオルター【*】使用のもの。子どもたちはこのイチゴのうまさに相当感動していた。私も食べたが甘くてしっかり食感のある堂々たるイチゴに感動したのである。【*】お気に入り参照。
2005.02.22
コメント(0)
-
地球温暖化特集の「9月号」が手に入る。
雑誌「ナチュラルジオグラフィック」の9月号をぜひ手に入れたい。地球温暖化特集で最新の情報や写真資料が方にあるようだからだ。ところが私がお世話になっている箕面駅前の「木下ブックセンター」で注文したところ、すでに出版社では在庫切れだった。売れる雑誌なら増刷してくれてもよさそうなのだがそうはいかない事情もあるのだろう。これは昨年の話である。今年に入り省エネルギーセンターの方から「紀伊国屋」など大手書店では取り寄せ可能という情報をいただいた。よし、と思い、まずは曽根駅前の「ブックファースト」に行く。ところがここでも出版社が在庫切れのためとりよせできませんとのこと。残念だが、とても愛想のいい店員さんで好感が持てたのが救いである。しばらくしてから梅田にある「紀伊国屋」で注文をする。1週間たっても連絡がないので、梅田に行くついでに再度「紀伊国屋」に行く。「すいません。ご連絡したのですがお留守だったみたいで…」と言われ、やはりここでも在庫切れ。う~ん、取り寄せ可能のはずだったのだがどうしたことだ、と思いつつ店を出る。数日後、今度は梅田の「旭屋」に行く。「少々お待ちください。調べて参ります」お、ここは何と「ナショナルジオグラフィック」のバックナンバー常設店ではないか。期待をふくらまし店員さんを来るのを待つ。「お客様、申し訳ございません。昨日まではあったのですが…」期待していただけにがっくりである。まあ省エネセンターによる取り寄せ可能情報はやはり正しかったのは確認できた。その後、梅田にある「ジュンク堂」「ブックファースト」と大手書店を歩いてまわるがどこも、「申し訳ございません。在庫切れです」である。ああ、とうなだれて帰宅したのが昨日の話。酒蔵見学の後で少々ふらつきながら帰宅したあの日である。本日インターネットで「9月号」を手に入れようとしたところ、バックナンバー常設店が「旭屋」の他にあることが判明。梅田にある「ブックファースト」だ。さっそく、電話をかけて在庫確認をする。「9月号ですね。少々お待ちください。 ……はい。あります」おお、よしよし、即注文である。梅田には「ブックファースト」が3店あるので、どこの店かを確認する。すると昨日わたしが行ったところと同じ店ではないか。「ええ、昨日行ったら、在庫切れです、って言われましたよ」「あ、そうですか。申し訳ありません」まあここは怒らずに、「9月号」が手に入ることを確認できたのでよしとしよう。そういう大らかな気持ちにもなるのである。しかし、2番目に訪れた「ブックファースト」曽根店のあの愛想のいい店員さんがなぜ、この「ブックファースト」梅田店がバックナンバーの常設店であることを教えてくれなかったのだろう。まあ若い店員さんでもあったからそこまではしらなかったのだろう。知っていたらあの愛想のいい店員さんなら教えてくれたに違いない。これまた大らかな気持ちになるのである。まあともかく明後日には念願の「9月号」が手にはいるのだ。これからの本探しはやはりインターネットも活用すべきだと確信した次第。おはようございます。原田誉一です。日曜日やや酔っぱらいながら梅田の書店を探し回りました。というのも紀伊国屋で注文していたのですが、在庫切れだったのです。旭屋→ジュンク堂→ブックファースト、どこも在庫切れ。ところが一昨日ブックファーストにバックナンバーがあることを発見しました。明日取りに行く予定です。
2005.02.21
コメント(0)
-

五感で直に感じる現場の香り・小さな音・気温
【写真1】アルコール発酵の様子を見ながら三井さんの解説を聞くのんきさん 【写真2】カップ持参で試飲会に挑む(のんきさん・私・三井さん)京都は伏見にある酒蔵に行く。清酒「英勲」で有名な齋藤酒造の酒蔵だ。【*1】「現場でしか分からない香り・小さな音・気温など、 肌で感じてください」社長のこの言葉を素早く書き留める。その後、工場長の説明・ビデオ鑑賞・酒蔵見学とつづき、お待ちかねの「利き酒会」。持参カップを持って数種類の清酒と勝負。もう感動的にうまい。体内の細胞にスーと染み渡り数時間後少々酔っぱらい気分になってしまう。「今日はここのお酒を買えると言うことですが、今後どのようにすれば買うことができるでしょうか」もうろうとなりながらも話の最後には質問もするのである。購入できた大小合わせて5本の酒をカバンに入れ千鳥足で何とか無事帰宅する。【*1】お気に入り参照
2005.02.20
コメント(0)
-
間違えてもそこには意味があるのですね。
最近よく「意味」という言葉を意識するようになった。たとえば国語の授業では次のような発問を考えたりする。「『洪庵のたいまつ』にはどういう意味が込められていますか」「文章全体を通してみると、第1段落にはどういう意味があるのですか」国語はもちろん他の教科などでも応用可能な発問も考える。「今日の授業はあなたにとってどんな意味がありましたか」「意味を問う」ということは、実に応用範囲が広い。先の発問でいうと、「主題」や「段落の役割」が問える。それ以外に、原因・理由・背景といったことにも思考が及ぶこともある。また文章(テキスト)から自分の価値観を形成することにも役立つ。客観的に考えていたことを主観的にとらえ治す作業ができるということでもある。幅広く考えることもでき、また奥深く思索できる。昨日アイヌプロジェクトの催しに参加した。開始時刻を間違えて1時間半も早く会場である「街山荘」に到着。おまけに開始時刻が30分以上も遅れたので合計2時間以上待つことになる。夜7:30には「街山荘」を出るつもりだったが、開演が7:30を過ぎる。しかし2時間以上もムダな時間・意味のない時間をすごしてしまったかというとそうではない。その間、いろんな方とお話しすることができた。初めて合う人・数年ぶりに合う人・親しい方と有意義な時を過ごせたのだ。開始時刻をまちがえ、一見ムダな意味のない時を過ごしかに思えたが、有意義な意味のある時を過ごすことができたのだ。そして今日2月19日(土)鶴見緑地にある大阪市環境学習センター「生き生き地球館」に行く。環境学習発表会という催しに参加するためだ。5年生の子どもたちがかいたECO発信の掲示物も持参する。これは宅配でも送れたのだが、当日この催しの発表者として参加することなっていたので、持参することに決めた。しかし、私が発表者として参加する催しは19日(土)ではあるもののそれは3月19日(土)の催しであった。前日それに気づいてアッチャ~と思った次第。こんなことなら、宅配で送れば良かったと思ったが後の祭りである。しかも「生き生き地球館」は大阪市の施設だから逓送便でも送れることにも後で気づきさらにアッチャ~化したわけだ。交通費往復540円と数時間を費やして行くことになる。ムダな意味のないお金や時間を使ってしまったのかた少々がっかりしそうになったが、考え直す。これにも何か意味があるのだろうと。用意されていた掲示板に子どもたちのECO発信を貼ってから帰ってもよかったのだが、会場では何やら誰かの講演会が行われている。せっかくだから聞いてみようと中に入る。200人ほど入れる会場に30人ほどの人がまばらに講師の話を聞いている。何だか寂しい講演会だなあと思いつつ一番左端の後ろから4番目の席に着く。講師は京都精華大の山田国廣教授(環境社会学)。演題は「地球の環境は一人じゃ守れない」だ。寂しい会場内だが山田先生は元気はハツラツに話している。わたしは、講演後質問するつもりで話を聞こうと書き留めながら聞く体制を作る。「総合学習」で講師の方を招いて特別授業を行っているが、子どもたちにはよく「講師の方の話が終わったら質問するように」と言ってもいる【*1】。質問するつもりで話を聞くことで主体的な聞く構えができ理解も深まるのだ。山田先生の講演後、司会者が「質問のある方は…」と言うとすぐに挙手をする。マイクをもらい質問したのである【*2】。「生き生き地球館」を出て駅へと向かう途中、教え子に会う。私が担任している5年1組の男のとそのお兄ちゃん、そしてお母さんも。教室に掲示したあった今日のこの催しのチラシを見て参加したのだという。うれしいではないか。「先生が質問されているのも聞きましたよ」とお母さん。いやはや少々恥ずかしい気もしたがこれまたやはりうれしい。2月と3月をまちがえはしたが、やはりこれにも意味はあったのだ。福島大学の飯田史彦さんは『生きがいの創造』(PHP研究所、2003年)で次のように言う。「すべてのことには意味がある」(206頁)「意味が現象に優先する」(362頁)「人生では、まず全てのことに意味(学びの材料)が存在し、その意味を実現化するために最適な現象を生じてくれる」(362頁)そういう意味でも「意味を問うこと」にも意味があるのですね。【*1】ところがなかなか子どもたちは質問をしない。はずかしいというのが大きな原因のようだ。またどういう質問をしたらいいのか分からないという子も多い。そこで質問の仕方や質問の例を教えた。・質問の仕方 1 話を聞く前に予め質問を考えておく。 2 話を聞きながら質問を書く。 3 質問は?と聞かれたらすぐ手を挙げその間に質問を考える。・質問の例 「いつからそのようなことに興味を持たれたのですか」 「お話の中に出てきた○○についてもう少し詳しく教えてください」 「○○さんは子どものころどんなことをするのが好きでしたか」【*2】「今日はどうもありがとうございました。 先生に2つご質問します。 1つ目は、冷蔵庫の電源を切っても故障しないかと言うことです。 私は箕面に住んでいるのですが、先日の寒い日、家に帰り、ビールを冷やそうと冷蔵庫を開けたところ、冷蔵庫の中の方が暖かかったんですよね(笑)。 ビールは冷蔵庫ではなく外で冷やしました(笑)。 このように冬に冷蔵庫を使うのはもったないない。 できれば電源を抜きたいのですが、故障が気になります。 2つ目の質問は、蛍光灯の電源をつけたり消したりしすぎると逆に電気を消費するのではないか、ということです。(以下省略)
2005.02.19
コメント(0)
-

特別授業「森が死ねば海が死ぬ」
【写真1】特別授業後、子どもたちからサイン責めに合う釜中明さん 【写真2】アイヌプロジェクトの演奏(街山荘)
2005.02.18
コメント(2)
-
来週あたりの予定を見てやりくりせねば。
知人から電子便(メール)が届いた。来週あたり我が家に行きたいという。了解、と思い、予定表を見てムムと唸ってしまう。ゆっくりと話す時間がなかなか作れそうにないのだ。どうしよう…。もちろん平日は学校で仕事である。う~ん…。ちなみに来週あたりの予定は次の通り。18日(金)釜中さん授業「森が死ねば海が死ぬ」映画「木霊」観賞後 『アイヌ・アート・プジェクト』音楽と舞踊(街山荘)19日(土)環境教育マッチングフェア(生き生き地球館) 大阪教育サークルはやし例会(街山荘)20日(日)三井さんと酒蔵見学(京都伏見「英勲」蔵元齊藤酒造株式会社) 環境市民団体15%クラブ例会(生涯学習センター)21日(月)教育指導最終評価分科会22日(火)オルター食材でお茶菓子を味わう(家庭科) 生活指導部会 23日(水)西川さん授業「豆腐の試食から食の安全を考える」24日(木)琵琶湖の環境を考えるシンポジウム(朝日生命ホール) 椎名誠さんご招待(?)25日(金)一宮さん授業「一杯のコーヒーから地球が見える」26日(土)青年フェスタ(箕面観光ホテル)小田さん講演 環境(ECO)的予定がやはり多い。
2005.02.17
コメント(0)
-
「温室効果ガス 日本9割削減必要」(「9割」は誤植ではありません)
京都議定書が本日発行された。日本は二酸化炭素を1990年比で6%削減しなければならない【*1】。今日の讀賣新聞の第18面、「どうなる地球 衝撃の破局的災害予測 温室効果ガス 日本9割削減必要」文字通り「衝撃」的な内容である。9割とは90%である。日本は90%の削減が必要というのだ。松岡譲・京都大学教授(環境工学)によると、映画「デイ・アフター・トゥモロー」【*2】のような「シミレーション結果もありうることが示された」。「日本は80-90%を削減しないといけない計算になる。 たいへん厳しいが、達成しないと国内でも悲惨な影響を受けることになる」 本来この記事は18面でなく第1面に大きく報じられるべき内容であろう。6%削減なんてホントはじめの第一歩にすぎないが、動き始めたことに意味がある。【*1】1990年以降増加した8%を合わせると今後14%削減する必要がある。【*2】昨年7月に書いた下記の電子便を参照ください。地球温暖化で、南極の巨大な棚氷が崩壊。棚氷は海で溶け、海水の塩分濃度を低下させる。すると海流の流れが変わり、大気に異変をきたす。予測困難な異常気象の始まりである。ソフトボール大の雹(ひょう)が頭上から人々を直撃。巨大な竜巻が人や車、そして高層ビルまでも吹き飛ばす。急激な海面上昇で、海水が一挙に町を飲み込む。大気の異変が進行し、今度は恐ろしく急激に気温が下がる。町を飲み込んだ海水はもちろん、建物や人々が凍りつく。北半球の多くの国々が極地のごとき氷の世界へと一変する。「そのときあなたはどこにいますか」これは今上映中の映画「デイ・アフター・トゥモロー」の話。なんだ映画の話か、と思わないで下さいね。深刻な地球温暖化の影響はもうすでに始まっているようです。佐賀県では竜巻が起こりました。車までもが飛ばされるほどの竜巻です。雹が降ってきたところもあるそうです。死者14名、浸水家屋25000棟以上の被害をもたらした新潟・福島豪雨では、世界最強の海流・黒潮の大蛇行が関係しているとの指摘も(2004年7月17日「讀賣新聞」)。地球温暖化の授業を毎年やっていますが、今年ほど現実味を持ってやった年はありません。おそらくそういった傾向はこれからも続くようで恐いです。今日はめずらしく一人で家の留守番。つれあいと娘2人は「デイ・アフター・トゥモロー」を見に行きました。今宵は家族で「地球温暖化」について語り合うことになるでしょう。
2005.02.16
コメント(0)
-
3回目のECO発信が終わり…
5・6時間目を使い5年1組・2組のECO発信交流会をする。学習発表的なECO発信は今日で3回目となる。1回目は学級の友達および教職員対象に研究授業で行ったECO発信(1)。2回目は保護者対象に学習参観で行ったECO発信(2)である。1回目・2回目ともなかなかのできのECO発信であったことはここにも以前書いたとおりだ。このままいけば3回目はさらに素晴らしいものになると大いに期待していた。しかし今ひとつ物足りなさを感じてしまったのだ。交流会後、教室にもどり子どもたちに次の質問に答えてもらう形で紙に書かせる。1、今日のECO発信、全体的に見て、どうでしたか。2、なぜそう思ったのですか。(理由)3、どうじてそうなったのですか。(原因)4、今後どのようにしていけばいいですか。(対策)5、あなたの今日のECO発信はどうでしたか。6,書き漏らしたことなど、今日の感想を書いてください。ほとんどの子が「1」で良くなかったということを書いた。あえていえば今日は「失敗だった」。しかし失敗からも大いに学んでほしい。5年1組で学習できる日は後26日である。
2005.02.15
コメント(0)
-
冒険家・大場満郎さんの地球縦回り世界一周の旅第2弾が始まるのだ。
『南極からのメッセージ』(NHK出版)を読んでいきなりオオと唸る。冒頭に次の記述があるからだ。「北極、南極をたった一人で歩いて横断した大場満郎さんは、南極大陸について次のように語ってくれた。『あまりにも大きくて自分の力だけではどうしようもないというか、とてつもない存在感がありますよね。あまりにも大きくて『変なやつ』というあだ名をつけましたよ』」(同書3頁)いきなりあの大場さんが登場している。しかも同書64頁には大場さんの文章が掲載されてある。「人の気持ちを原点に戻す南極の自然」という15頁にも渡る文章だ。これを読むと南極大陸単独横断のすさまじさがじわじわつたわる。そして大場さんの人となり、生き方といたものまでじわ~としみてくる。ああ、もっと早くにこの本を読んでおけばと後悔する。この本は2年前に購入していたのだが読んだのが昨年12月である。その年の7月に実は大場さんが本校で2回目の特別授業を行ってくれた。【*1】その後、みのおエフエムのタッキー地球レポートという番組で「冒険家・大場満郎さんと語る地球縦回り世界一周の旅」を2人で収録したのであった。そのときまでは「すごい人だなあ」と思っていたが、この本を読んでさらに「ものすごい人ではないか」と驚愕したのである。そうか大場さんとはこれほどまでにものずごい冒険家であったのだと再認識した次第。その大場満郎さんが今月16日にカナダに向かう。地球縦回り世界一周の旅の第2弾がいよいよ開始される。この日は京都議定書発効の重要な日でもある。16日は京都議定書発行日という話を子どもたちに今日したが、大場さんのことはまだ話していない。明日は大場さんの話をしようと思う。もちろん『南極からのメッセージ』を紹介しながら。【*1】お気に入りの「地球縦回り…」参照。1回目の特別授業の様子を紹介してあります。
2005.02.14
コメント(0)
-
今年度5年生の「総合学習」をまとめる.
今年度5年生の「総合」の3本柱は「基礎学習」「環境学習」「発展学習」である。「基礎学習」では、学力の基礎である「読み書き計算」を中心に、「名文音読」「先習い漢字学習」「百問わり算」を行った。また各教科の補習的授業も必要に応じて行い基礎学力の定着化を図った。「環境学習」では、「世界に向けてECO発信」を主題とし学期ごとに次の学習段階を設けた。すなわち1学期「知る」、2学期「調べる」、3学期「伝える」である。まず地球温暖化など環境問題の現状を「知る」。つぎに環境文庫の本などを使い自分で環境問題に関することを「調べる」。そしてその現状や防止方法などを「伝える」。つまり「ECO発信」である。「発展学習」では、教科の発展的内容はもちろんそれにとらわれない内容までも幅広く学習できる授業を試みた。「冒険」「パントマイム」「世界」「漫才」「カレー」「健康」「報道」「家」「食」「コーヒー」といった現場で活躍されている方々10名を講師に招いて行った特別授業に子どもたちは多くの刺激を受け様々なことを学ぶことができた。また週1回のパソコン学習により子どもたちのパソコン技能は確実に向上した。「基礎学習」「環境学習」「発展学習」が相互に関連し合い、3学期の「ECO発信」がとても充実したものになった。環境に視点をおいた地球の現状を訴えたり、環境先進国の取り組みを紹介したりといった内容を、パントマイムや漫才といった表現方法を取り入れて発信したり、ホームページで発信したりできた。もちろんそうした表現活動ができるのも土台となる「基礎学習」がしっかりしてきたからにほかならない。 4月 ○ 朝の学習 ・先習い漢字学習 ・百問わり算 ・名文音読 ○ 図解による書き留め(メモ)を始める ○ 環境授業「オゾン層と紫外線」(学習参観) ○ 大場満郎さんとの交信(グリーンランド~日本)計7回5月 ○ 3色ボールペンによる読解を始める6月 ○ 環境授業「地球温暖化」 ○ 特別授業1「エコロマンのエコロジーマイム授業・省エネ編」 講師…パント末吉さん(笑って伝えるメッセンジャー) ○ 特別授業2「地球スライドショー 前半 北極・アジア・南太平洋」 講師…松本英揮さん(究極のエコロジスト 宮崎大・鹿児島大非常勤講師) ○ ラジオ関西取材「新東三国小学校の環境学習」7月 ○ 特別授業3「地球縦回り世界一周の旅・グリーランド縦断報告」 講師…大場満郎さん(冒険家)9月 ○ 環境文庫開設(環境に関する本200冊以上を教室に常設)10月 ○ 特別授業4「地球スライドショー 後半 アメリカ・ヨーロッパ」 講師…松本英揮さん(究極のエコロジスト 宮崎大・鹿児島大非常勤講師) ○ 特別授業5「漫才で伝えよう」 講師…平川幸男さん(漫才師 漫才コンビ「Wヤング」) ○ 特別授業6「カレーから始まる国際理解・インド」特別授業7「インド・チキンカリー実習」 講師…サニー=フランシスさん(DJ タレント) ○ 環境授業「電気を使い過ぎる生活」 ○ 特別授業8「歯医者さんが語る〈食と健康〉」 講師…豊田裕章さん(歯科医)11月○ 特別授業9「エネルギー問題」 特別授業10「地球温暖化とケナフ」講師…落合雅治さん(ジャーナリスト 大阪ケナフの会代表)12月○ 社会見学(読売新聞社 サイエンス=サテライト) ○ 環境授業「新エネルギーと省エネルギー」1月 ○ 特別授業11「未来の新エネルギー」講師…落合雅治さん(ジャーナリスト 大阪ケナフの会代表) ○ 研究授業「ECO発信(1)」2月 ○ 参観授業「ECO発信(2)」 ○ 交流授業「ECO発信(3)」 ○ 特別授業12映画『木霊』鑑賞と「山が死ねば海が死ぬ」 講師…釜中 明さん(NPO「いい家塾」代表) ○ 特別授業13「豆腐から食の安全性を考える」 講師…西川栄郎さん(安全な食べものネットワーク「オルター」代表) ○ 特別授業14「一杯のコーヒーから地球が見える」 講師…一宮唯雄さん(NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」代表)3月 ○ タッキー地球レポート「ECO発信」(みのおエフエム)
2005.02.13
コメント(0)
-
今まとめている途中です。
今年度5年生で行った「総合的な学習の時間」を今まとめている。基礎学習・環境学習・発展学習の3本柱の「総合」。まだ途中だが結構やっていることに改めて気づくのである。明日にでもここに掲載できればと思う。
2005.02.12
コメント(0)
-
この3連休でやるべきこと
3連休の初日なのだが目覚めたのが2:30。午後ではなく午前2:30である。前日午後8:30には寝ていたのだがそれにしてもこれは早い。まだ当然ながらまだ真っ暗で部屋の気温は8℃である。それでもエイヤと起きて服に着替え、いつものように焙りたてコーヒーを飲み「さてと」とこれからするべきことを頭の中で整理する。3連休ではあるがやるべきことやりたいことが山積みなのだ。というわけで、この3連休のうちやるべき事を忘れぬうちに書いておこう。・研究機用の原稿(今年度の5年生の取り組みをまとめる)・3つの特別授業の準備・本を5冊読むこと・畑の土を整理する・2つ目のホームページによる著書の紹介・娘たちと遊ぶこと・机上整理まだまだあるのだがこれ以上はここに書いても仕方ないものがほとんどだ。やはり「研究紀要の原稿」が今のところ手強い感じがする。休みなのに仕事とは、と思うのだが楽しくやりたいものだ。
2005.02.11
コメント(0)
-
椎名誠さん、ぜひ我が家に来てください
作家・椎名誠さんに手紙を送る。内容はズバリ「我が家に来てください」だ。椎名さんが2月24日(木)に来阪する【*1】という情報を先月末に毎日新聞で知った。毎日新聞社主催の「水辺と生き物」【*2】というシンポジウムで椎名さんが基調講演をするという。弟分の私としては兄貴の来阪と聞いてじっとしてはおられないではないか。何しろ日本全国の海を見に行ったり、世界各国の川・海・山・街などをあちこち旅に出ることが多い兄貴である。したがって、めったにない来阪なのだ。それに先週よんだ兄貴の本【*3】にある「余市」と「煎りたてのコーヒー」という言葉にオオと唸ったのだ。「余市」は北海道にある兄貴のカクレ家(別荘)の近くの街。そこから車で30分の小樽にる「海猫屋」という料理店では「煎りたてのコーヒー」を出すそうだ。つまり、・「余市」→「よいち」→「誉一」(私の名前)・「煎りたてのコーヒー」→「焙りたてコーヒー」【*4】といった我田引水的類推単純思考でもってオオとなった。しかもだ。2月24日(木)という日は我が家で最もいい食材および酒が準備できる日なのである。オルター【*5】からの新鮮で安全な食材が届くのが毎週水曜日。2月20日(日)は三井さんと酒蔵見学会【*6】に行き銘酒「英勲」を手に入れることができる。そして当日までにはエビスビールも用意できる。「エビスビールあります」だ。さらに、翌25日(金)には本校で「一杯のコーヒーから地球が見える」【*7】の特別授業を行う。先ほどの「煎りたてのコーヒー」と結びつくではないか。兄貴は旅の途中ひょっこり小学校に立ち寄ることも少なくない。新大阪から車で7分ほどにある本校だからひょっとして兄貴の来校もあるかもしれない。条件は全て整った。あとは兄貴からの返事を待つだけだ。【*1】2005年1月28日付「毎日新聞(夕刊)」より【*2】副題「琵琶湖の環境を考える」 場所・朝日生命ホール(大阪市中央区高麗橋4-2-16) 応募方法・FAX(06-6346-8665)住所・名前・年齢・職業・電話番号・希望人数を書いて申し込む。入場無料。【*3】椎名誠『小魚びゅんびゅん荒波編』(講談社、2004年)141頁「余市」、147頁「煎りたてのコーヒー」。【*4】今年出版予定の本の主題でもある。【*5】「安全な食べものネットワーク・オルター」。お気に入り参照【*6】1月20日の日記「【秘】また参加したい環境ECO旅行と食・酒の会」参照。【*7】NPO「一杯のコーヒーから地球が見える」お気に入り参照。
2005.02.10
コメント(2)
-
ここ数日の流れるような国語の授業
ここ数日下記のような流れで国語の授業を行っている。私があれこれ指示を出さなくても子どもたちは流れるように勉強する。教科書の文章は司馬遼太郎の「洪庵のたいまつ」だ。適塾の創設者・緒方洪庵の伝記である。・名文音読(芥川龍之介・走れメロス・徒然草・日本国憲法・いろはかるた)…5分・百問わり算…5分・先習い漢字試験(40~50問)…5分・答え合わせ…2分・全文一斉音読「洪庵のたいまつ」…13分・前時の図解を回し読み(回し見)…3分・本時の場面を帳面1ページに図解する…12分ここまでいたるには、徹底音読・図解の仕方・3色ボールペンの使用法などなどいくつかの学習事項が土台となっている。来週からは話し合い・読解問題をへて試験を行う。子どもたちは果たしてどれくらい力がついたか。楽しみである。
2005.02.09
コメント(0)
-
1日1食は体にもいいし地球環境にもいいECOなる行動なのだ
去年の今頃は確か体重94kgであった。それが今は78kgである。1月1食を正しく実践してきた結果である【*1】職場で4名の方から、「原田さん、やせたね~」としみじみ言われた。昨日は、「これ娘が着ていたのだけど」と上着やズボンまでいただいた。自分ではほとんど服を買わない人生を歩んでいるので、ありがたくちょうだいするのだ。1日1食だと以前はこんなことをよく言われた。「食事の回数を減らすより回数はそのままで量を減らせばいい」「相撲取りは1日2食だから太るのだ」「朝食を抜くのは健康によくない」「抜くのなら夕食を抜くべきだ」そう言われながらも1日1食で、その1食を夕食で貫く。夕食は1日のうちで最も至福の時間であるからこれを抜くことは断じてできないのだ。家族団欒である。最近はもう先のような事はもうほとんど言われなくなった。1日1食(夕食)の結果16kgやせた事実があるからだろう。朝・昼をぬくということは、それだけエネルギー消費を抑えることにもなる。食料・燃料などなど。食事ひとつとっても今や日本は「輸入してまで食べ残す不思議な国」なのだ。全国民が朝・昼をもし抜いたら単純に60%のエネルギー削減も可能かもしれない。まあ現実にはあり得ないかもしれないが。しかしそれでも私はこれからも1日1食の我が人生を貫くのだ。【*1】1月1日の日記参照。
2005.02.08
コメント(6)
-
角の取れた丸みのある美味しいコーヒーができました。
数年前に購入していたセラミック製の濾過器をドリッパーに使う。すると何かいつもと違う口当たりになる。角が取れた丸みのある、あえて言えばトロンとした感じだ。それでいてコーヒー本来のうま味が味蕾にしっとりとしみわたるのである。一宮唯雄さん【*1】にいただいた「焙りたてや」のトラジャスペシャルと「島珈琲」【*2】のマンデリンを1:1の割合でブレンドする。どちらも簡易焙煎機「焙りたて名人」でそれぞれ別々にやや深入り加減で焙煎後数時間ねかせたものだ。いやあ、実にうまかった。めったに「おいしい」と言わない連れ合いも素直に「おいしい」と言う。焙りたてコーヒーを毎日飲んでいる珈琲通の落合さんもしみじみと「ああ、おいしいね」と言いおかわりまでしてくれたほどだ。この新鮮な焙りたてコーヒーを朝のむとその日一日がぜんやる気といったものがじわじわとわいてくるのを最近とみに感じるのである。【*1】NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」代表。「お気に入り」参照。【*2】「お気に入り」参照。
2005.02.07
コメント(0)
-

明石家のんきさんの「省エネ自然派家屋」訪問
2月16日に京都議定書が発効される。これからますます省エネをはじめとするECOなる行動が重要になってくる。ということで明石家のんきさんが「省エネ自然派家屋」の我が家を訪問しECOなる行動を取材する。まず電気代が月1500円ほどの我が家の省エネ術を公開。ムダな待機電力をなくすため電源はコンセントから抜いておく。これが基本。電気使用量が一目で分かる省エネナビも紹介。雨水タンク「天尊水」による雨水利用。生ゴミ堆肥化装置「グリーンエコ」で土育て。ガス使用量5分の省エネ調理など。取材そっちのけで思わずかなりつっこんだ話しもしかけてくるのんきさんであった。『のんきが行く~京都議定書発効、省エネ生活を学ぶ』は今月21日放映される予定である。
2005.02.06
コメント(0)
-
意外にも娘たちは「グリンチ」を支持しているのである。
きのう「グリンチ」を途中で打ち切り素早く寝たので今日も3時半には目が覚める。8時には箕面駅前の接骨院に行こうと思う。その前に貸しビデオ屋に「グリンチ:を返しに行こう。そう思い、8時前にビデオを持って家を出ようとしたところ、娘たちが「グリンチ」を見たいと言う。「グリンチ」を昨日の続きから再生し素早く接骨院へと向かう。運良く一番に診てもらう。またもや素早く帰宅し「グリンチ」を貸しビデオ屋に返却する。娘たちに聞くとどうやら「グリンチ」は面白いらしい。「マスク」や「ベートーベン」以上という。なになにそんなに面白いのであれば見ればよかったと思うのであるが再度105円を出して借りる気にはやはりなれない。そこで今夜は昨日の「グリンチ」打ち切りをはらすべく「ゴンゴ」を借りた。今から見るのだが、果たして面白いか否か。
2005.02.05
コメント(0)
-
寒い部屋でもストーブを消して家族であったかになる方法。
金曜日は「映画の日」だ。帰りに貸しビデオ屋「ツタヤ」で1本借りる。「当日返却」なら105円で借りれる【*1】のだ。「当日返却」といっても翌日の朝10時までに返せばいいのである。金曜日はテレビでも夜に映画を放映するが見る気がしない。テレビ宣伝(コマーシャル)が煩わしいからである。いいところで宣伝の画面に切り替わる。時間のムダ。子どもたちにも教育上精神上発達上有害無益なことこの上ない。もともとテレビを見ること自体に問題が多い。教育士・岸本裕史さんも著書『見える学力、見えない学力』(大月書店)で「テレビ十悪」を書いているほどだ。そうは言うものの子どもたちにとってやはりテレビは魅力的ではある。したがって我が家ではテレビの視聴時間は1日1時間と定めている。もちろん私は全くと言っていいくらいテレビは見ない。うちのテレビは部屋の隅に追いやられている。おまけにアンテナを設置していない。【*2】あまり心地よくテレビを見る環境にはなっていないのだ。それでもやはり映画は見たい。できれば家族そろって一緒に楽しめる映画をじっくり見たい。【*3】いつも朝3時半起床なので夜9時には寝てしまう。帰宅するのが夜7時ごろだから、ゆっくり映画を見ている暇はない。でも金曜日は特別だ。次の日は休みである、といった精神的安堵感がありゆったりくつろげるのだ。そこで金曜日は我が家の「映画の日」と相成ったわけである。さてここらようやく本題だ。家族で過ごすときは仕方なく石油ファンヒーターを使っているが【*4】、家族で映画を見るときはこれを消す。すると室温は10℃を切るようになる。もっともこれをつけていても室温は15℃である。この状況でもって2時間もの間どうやって映画を見るのか。しかも寝間着姿である。まずジャンバーなどの上着を着る。次に私・娘・娘・連れ合いの順にソファーに座る。そして布団にくるまるのである。これで完璧。室温がたとえ1ケタでもわれわれ4人はあったかなのだ。テレビ・ビデオ・蛍光灯の3つの電気を使用している分、せめて暖房にかかるエネルギーは省きたい。それになによりも家族4人が文字通り身を寄り添って映画を見るなんていいではないですか。これも我が家のECO発信(エコ発信)である。ちなみに本日の映画は「グリンチ」。今ひとつ期待はずれだったので途中で打ち切り4人とも素早く10時に就寝。先週見た「オーロラの彼方へ」は面白かった。幼稚園の娘には難しかったようだが、過去と現在の親子の交信という着想がスルドイと思った。【*1】大阪人の私は日常「ら入り言葉」は使わない。あえて「ら入り言葉」を使用するといったことも極力さけている。したがって「借りられる」でなく「借りれる」と書く。【*2】職場の「神戸先生」手製の簡易ケーブルアンテナで民放3社のチャンネルは映る。日によってはとても鮮明に写るときもありびっくりするくらいだ。【*3】1月5日の日記「何方か、最低条件3つを満たし腹の底から感動できる映画を教えてください」参照。【*4】1月30日の日記に引用した、「ライブタウン」の原稿「今もっとも欲しい温暖化防止の切り札4点」参照。
2005.02.04
コメント(0)
-
ECO発信(エコ発信)をラジオでも
ラジオ大阪の方から電子便をいただいた。「五重丸」なほのぼの親子を紹介して欲しいとのこと。ちょうど今ECO発信(エコ発信)の最中である。しかも2月16日に京都議定書が発効される。これはもうねがってもない機会だ。ECO発信(エコ発信)をラジオでもできる。そしてもう1つ。みのおエフエムの「タッキー地球レポート」でもECO発信ができそうだ。13分間の番組で子どもたちが「環境メッセージ」を発信する。できるだけ多くの子どもたちにECO発信(エコ発信)をしてもらいたい。
2005.02.03
コメント(0)
-
第2回目の環境授業・ECO発進(エコ発進)を終える
5時間目の学習参観で第2回目の環境授業・ECO発進(エコ発進)を行う。第1回目の環境授業・ECO発進(エコ発進)の反省点をふまえかなり進化発展した内容である。言葉遣いも適切で大阪の子らしい話しっぷりだ。よくもまあ短時間のうちにあれだけの台詞を覚えたなあと感心する。毎日継続している「名文音読」の効用もあるかもしれないが、それよりも子どもたちの「やろう」という意欲の方が強いからだろう。予め質問を書いて発表を聞くようにしていたので、発表後も活発に意見交換ができた。下調べもよくできていたので「わかりません」という言葉はあまりでない。子どもたちになりにその場で受け答えができていたのにも関心関心である。参観後の学級懇談会では8名ものお母さんが参加してくれた。ここ数年でかなりの参加率である。たいがい最後の学級懇談会というのは参加される方が少ない。学級担任としては最後の学級参観こそ多くの方に参加していただきこの1年間の子どもたちの成長ぶりをお互い喜び合いたいと思っているのであります。そういう意味で昨日の学級懇談会は短時間で充実したものになったと思っている。きのうの学級懇談会でこの「原田誉一の電脳掲示板」のことをお知らせした。もしこれをお読みのお母さんがいらっしゃったらぜひ一言二言「コメント」をお願いしますね。第3回目の環境授業・ECO発進(エコ発進)は2組の子らとの交流となる。
2005.02.02
コメント(0)
-
第2回目のECO発信に向けって発進
3時間目に第1回目のECO発進の反省会を行う。面白くてよくわかる発表であったことをまずほめる。研究等議会でも他の先生方からいただいたお褒めの言葉も紹介する。次に改善点を子どもたちに聞く。「声が小さかった」子どもたちも分かっているのだ。そして私から5つの改善点を話す。なるほどと子どもたちが思ってから昨日の日記を印刷し子どもたちに配って読む。第1回目のECO発進の改善点を記した日記である。これでさらに改善点を意識できただろう。その後、テーマ班別に分かれ第2回目のECO発進に向けた活動を始める。そのさい、きのう子どもたちが書いた質問・感想の用紙を各班に配る。これを参考に、調査や原稿の見直しが活発に行われる。第2回目のECO発進は明日の授業参観で行う。より進化発展したECO発進になること請け合いである。
2005.02.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1