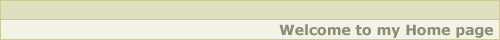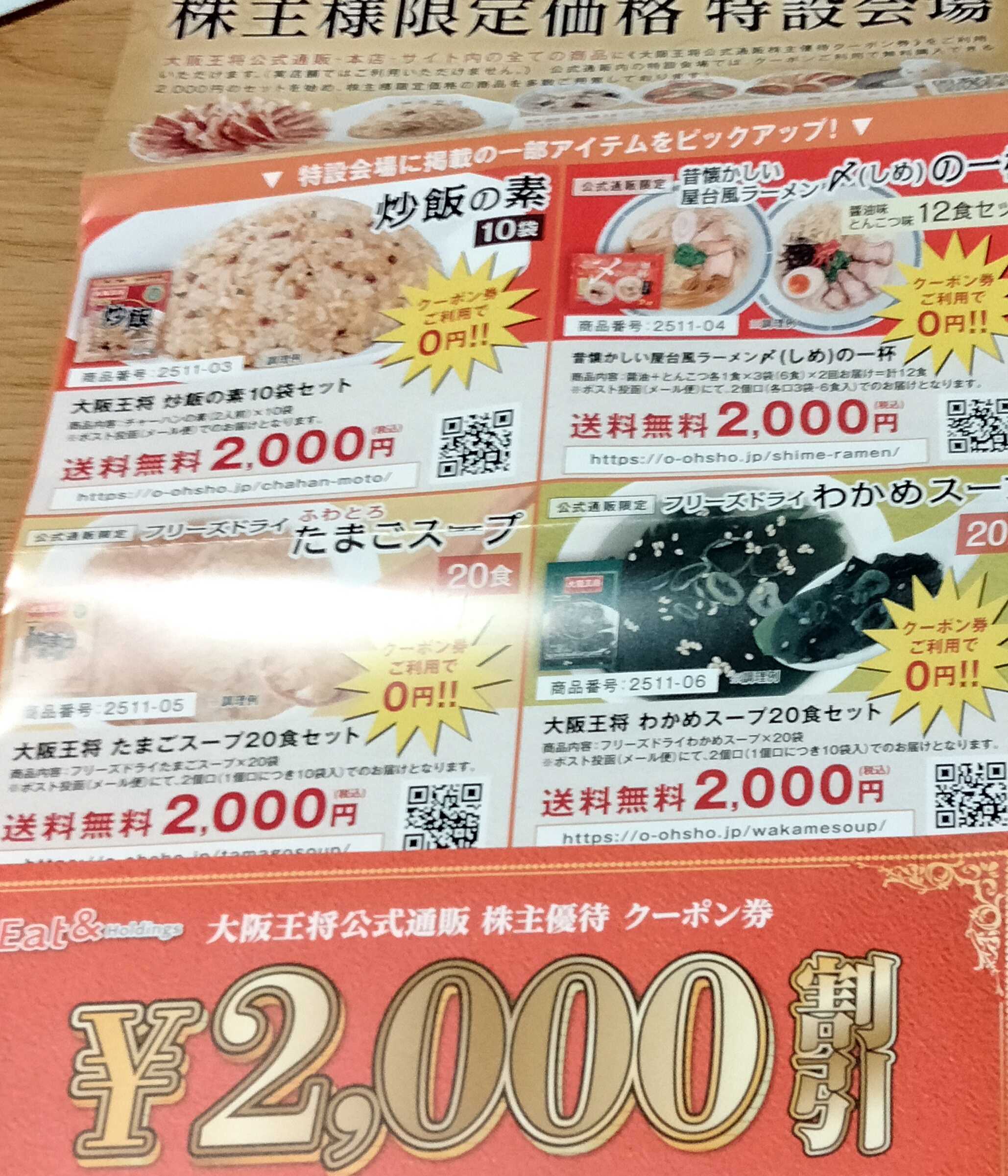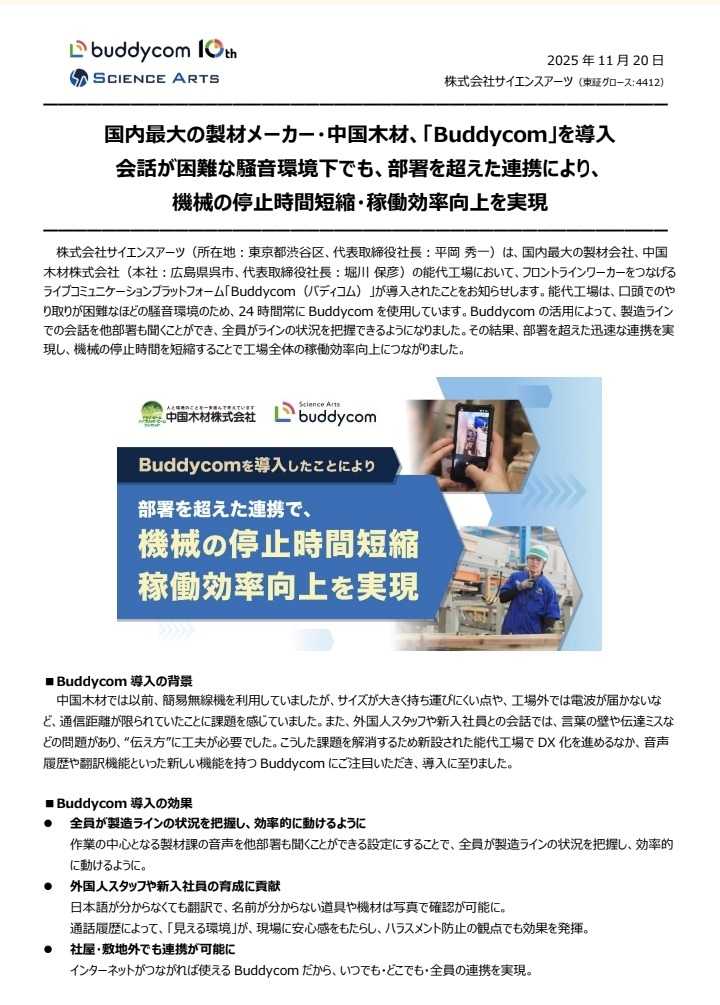全48件 (48件中 1-48件目)
1
-
人儲けの日に想う
10月6日は人儲けの日。人儲け。それは人生の基本。人儲け。それは真の儲け。人儲け。利益は仕事からやってくる。仕事は人からやってくる。はた(周囲)を楽にすることが、働く(はた・らく)こと。人儲け、人様のために働けるという幸せ。感謝される喜び。労働が朗働となり、人材が人財となる。サービスが先、金はアト。人様を助けるつもりで助けられている。助けようとし、お役に立とうとするその行動が、自分をふるいたたせ、生きがいを自分に与えている。助けることで助けられている。これは人儲けの醍醐味。人儲け。長い眼で見ると最良最高の投資。ただし、ポートフォーリオは大事です。
2004年10月06日
コメント(501)
-
●従業員満足 30 なぜ、今「従業員満足」なのか
・はじめのおことわり本日から、セミナープレイバックです。ワンテーマずつ、セミナーで話した順に出していきます。ただし、実際には図表を駆使して話をしていますので、実際のセミナーをテープ起こししたものとは表現が違っています。・本編開始 定義まずはじめに、従業員満足とは何かということなんですが。社員が喜んで本気になって働いてもらえるような満足。これを従業員満足とします。社員の福利厚生の充実というのも「従業員の満足」にはなりますが、社員の仕事の本気には直接つながってこないので、求めるものが違うだろうということで省略します。・時代が求めるそれで、最近特に経営に「従業員満足」が重要であると言われ始めました。従業員満足が大事ということは、江戸時代の頃からあったはずなのに、それはなぜ今、改めて言われ始めているかということなんです。皆様ご承知のように、インターネットなどの進展により、ものすごいスピードで、世の中は変化している。その変化に乗り遅れずに即時対応をお客様にしていくためには、現場主導でないと対応ができない。現場で本気になって当意即妙に切り盛りしてもらうためには、従業員満足を満たしてあげないといけない。もう、ピラミッド型の支配従属型ではおいつかなくなってきたのです。------------------------------補講その1定義について従業員満足は、個人のライフプランと会社の仕事の一致である、と定義するコンサルタントもいらっしゃいます。これは、具体的に制度を作っていく上での指針とするための定義です。今回の自分の定義は、会社にとって必要な従業員満足の姿を追い求める前段として、その本質を明らかにしたいと。そういう動機で定義しています。目的によって、定義の仕方は変わります。ほかにもいろいろな「従業員満足とは※※」というのがあって良いと思います。その2 江戸時代の従業員満足について江戸時代にも「のれんわけ制度」「無能な若旦那は経営に参画させず、現場の優秀なものに任せる」「家訓を浸透させる」など、現代でも参考にできる「従業員満足」と「経営の安定」を考慮した制度がすでにありました。
2004年08月06日
コメント(2)
-
●従業員満足 29 セミナーをやってみて
今日も、内容的には一回お休みです。今回は、昨日のセミナーの反省について。この「従業員満足」の連載は、今回のセミナーのために刺激を定期的に与えることを目的として連載してきたものです。そして、そのセミナーがついに終了しました。そこでつくづく思ったのは、聴衆の母集団により、興味のありどころが違う、という当たり前の事実でした。以前、一般向けと社労士向けに同じテーマをやったことがあって、食いつきの違いから感じていたことですが、今回もふたたび痛感しました。事前に気がつけよ>自分、というところです。もうこの一言で、どの程度成功したか、お分かりいただけたと思います(とほほ)良い勉強になりました。ちなみに、経営コンサルタントを相手のセミナーです。われながら少々無謀だったかも。でも、こちらもコンサルタントなので、なんとかこなすことはできました。お情けつきで、合格点ぎりぎりかな。特に、こちら側が勉強になったのが、「統計の嘘」について。こちらとしては、信頼できる出版社の信頼できる著者の著作物で、出典の明らかなデータについては、とりあえずそれを正しいものとして論を進めていったのですが、質問のときに、そのデータの正当性の論拠を求められて立ち往生しました。確かに、その姿勢がないと統計の嘘に乗せられて、だまされる可能性がある。ただ、逆にそれをつきつめると、「学問」になってしまい、非実用の知識になる恐れもある。枝葉を見て幹を見ないという愚です。この辺のバランスが難しい。先ほどの例で言うと、たとえばデータの正当性の論拠を見つけ出したとして、今度はその正当性の根拠となる情報が正しいという論拠は?こうなってくると、最終的には天国から著者を呼んでこいという話になりかねません。どこかで割り切らないといけない。「本が正しい」で割り切るか「本の情報の論拠まで」調べるか、もっと調べるか。立場によって違います。たとえば一般経営者だと「信頼できる本からの転載」でコンサルタントが聞き手の場合だと、本の情報の論拠まで。学者が相手だと、もっと深く、ということになりそうです。自分は基本的に社長の経営の意思決定のヒントになりたいという立場なので、出典が不透明でも、明らかに役に立つと直感できるものの場合、それを使うことにしています。経営と経営学は違う。ここを間違うとミスリードする、もしくは社長からあいそをつかされる。。。。ただしこの「直感」を養うためには、試行錯誤とシミュレーションが必要になります。うん、結局は量稽古です。あすからライブプレイバック編です。
2004年08月05日
コメント(0)
-
●従業員満足 28 番外編 いよいよ今日が本番
今日、セミナーをやります。この1ヶ月間「従業員満足」について毎日1テーマずつ書き続けたそもそものきっかけは、このセミナーの準備を忘れないようにするためでした。ただ、どなたががおっしゃるように、継続は力なりで、やり続けていくうちにわかってくることもあって、その意味では、実りの多い期間でもありました。また、さらに引き続き追求していきたいテーマでもあります。奥が深くて、有益で面白いからです。また、一連の書きこみの中で「従業員満足とは従業員の自我を慰撫すること」という結論を明示できたのは一番の収穫でした。これはもともと形にならないもやもやした状態で自分の中にあったものを、ここで書き込みをして、突込みを入れていただいたことにより、表現について自問するきっかけとなり、今回のような形にすることができました。しかも、ここの部分は、全体のへその部分に当たる重要なところなので、本当にありがたかったです。連載でいうところの「従業員満足の「4」と「6」と「4の2」です。おばか社長さん、ありがとうございました。おばか社長さんに「従業員の自我?社員にわがままさせ放題?そんなあほな。あんた、経営知らんやろ」という突っ込み(←そのように読み取りました)を警鐘として、そうではなくて伝えたいことは、「自我とはわがままではなくて、自意識」だと。さらに、某様からのご指摘によりその自意識とは「盲目の(=無条件、全方向に広げ続けようとする)関与意思」だということを表現するに至れたときには、ヤッタと思ったものです。この表現に到達するまでに、この楽天日記では、おばか社長さん、それから配信メール先からの某様。この2名のご指摘により、ここまでまとめあげることができました。某様の指摘は「自我とは、わがままではなく自意識(表層レベル)なんですね、集団とのかかわりという自意識が不景気だと少なくなるんですかね?」というご指摘でした。これまた、「あー自分の表現は範疇も内容も不足であった」と痛感させられました。この方への返信メールを書くべくまとめていくうちに、自分はこれを明示したかったんだ(=自我=「私の・・・」という意思関与=盲目的に過去現在未来に広がるということ)、というものが浮き彫りになってきました。そして現在につながっています。ですから、ご両人には、本当に感謝感謝です。それから、このセミナーの企画をたててくださったAさんにも感謝、感謝です。さて、今日はそんなわけで、具体的な「従業員満足」のヒントを提示するという意味においては一回お休みです。明日からは、今日のセミナーのための準備内容をもとに、セミナーで話しをした内容を中心に、それぞれ大体800字程度にまとめて出してみようかなと考えています。要するに、セミナーで話したこと、あるいは話す準備をしたことで気がついたことなどを連載形式でお伝えしようというものです。実はこの企画、すでに今日しゃべる内容が不完全であることに気がついてしまっているので、気がひけたりもするのですが、現段階の自分自身の等身大の足跡ということで、あえて今日のセミナーの内容に即することにしました。それと、ビジュアル資料も充実しているのですが、(→13ページ)、これについては、生セミナーとの差別化のために、あえて提示しないことにします。その分を文章でフォローしようと考えています。あさってから行います。明日は、セミナーの余韻です。
2004年08月04日
コメント(0)
-
●従業員満足 27 ゲーム感覚を取り入れる
・今日のポイント今日のポイントは、「競争心を刺激する」「ゲーム感覚を演出する」です。ゲーム感覚で競争を演出すると、楽しく参加できますし、それが業務上の必要性から発生してますので、堂々と誇れます。また、優勝水準が、業務上必要なレベルをはるかにこえるものになっていても、迷惑になるわけでもありません。むしろ、競技者のトップの水準が高いということは、相対的に、底辺のレベルが底上げされるとということ。実は新の狙いはこちらです。ゲーム感覚でトップの水準を、競わせることによって上げていく。すると、それ以外の層も、自分ももう少し技量子向上させてみようという気になります。あわゆかば出場してみようかとも。・実例 吉野家実は、牛丼の吉野家がこれをやっていました。社内で牛丼選手権を開催し、決まった時間内に決まった分量のごはん、肉、たまねぎ、汁を過不足なく丼に盛り付けるという、素朴な戦いでした。しかし、地区大会、全国大会があるので、結構大掛かりです。テレビでやっていたのですが、優勝者の技はすごかった。神業というか、ゴットハンドというか、人間ってここまでできるようになるの?という内容でした。7秒くらいでぱたぱたぱたと作ってしまい、それが数グラムとちがわない正しい目分量。たまねぎの量の配分も適性だし、汁の多さも多からず少なからず。人間の精密さというのは鍛えると相当なものになります。・お祭り感覚優勝者や上位者は、それをプライドとして励みにしてさらに技量を向上させようと努力する。それは本人にとっては面白い仕事です。しかもその姿勢は、職場の周囲にも良い影響を与える。いっぱいの丼を盛り付けるときに、真剣さという妖気があたりを支配するからです。管理しないで管理する、いわば空気管理ですが、その極意とも言うべき真剣さの伝播。これが仕事をゲーム化して競わせることによって、自主的に発生してくる。非常に参考になるお話です。老婆心で付け加えておきますが、賞罰で、歩合制のノルマのような賞罰の与え方になると、陰惨になりがちです。わっしょい感覚、お祭り感覚、ゲーム感覚。楽しくハレの舞台で遊ぶ感覚。この浮遊感覚を取り込むことが、必要です。「面白 真剣 役に立つ」様な工夫が必要です。
2004年08月03日
コメント(0)
-
●従業員満足 26 成長を妨げる要因
仕事の報酬仕事の報酬は、仕事。これは従業員満足を考えるときの鉄則です。仕事の達成を通じての成長実感が、一等級の大きな従業員満足の要素となることに間違いありません。実はあまり大きな声ではいえないのですが、従業員の成長を抑止している大きな要因の一つが、「上司」。認めたくないことですが、事実です。ひとつには「部下の依存心理」もうひとつには「権力というおもちゃをもてあそぶ上司」に原因があります。依存という魔性管理職は、かつてそれなりの業績を上げてその結果の昇進があって管理職になるというのがほとんどの場合です。ですから、それなりに仕事をさばく能力はあり、部下の仕事がまだるっこしく感じて、ついつい「俺に任せろ」。部下も、自分が失敗して上司から怒られるよりも、適当に上司をヨイショして、自分の責任範囲の仕事に良い結果がでたほうが良いので、ついつい上司に下駄を預けてしまう。成果を部下に譲った形にして、あたかも教育をほどこした「良い上司」であるかのように自分自身を勘違い。しかし実際には部下は仕事を実質的には経験していないから、部下は成長しません。権限という魔性もうひとつは、上司に与えられる「権限」。権限を持つと、人は指示や命令を出すようになります。命令どおりに部下は動くため、この体験が増えれば増えるほど「部下は、上司の命令で動く存在である」と実感し、これが繰り返されるうちに、やがて「うちの部下は指示待ち人間が多い」「甘い顔を見せると手を抜く」「自分の指示や命令がないと一定の成果を挙げられない」と、思い込むようになってきます。実はこれらは一種の勘違いです。ですが、これを妨げる者がいないため、結果として社内の人材が不活性化していきます。「うちの会社には、ろくな人材がいない」本気でそう思ったときは、この病状が進行してしまっているときです。従業員をろくな人材にしなかったのは、上司の責任です。人材は、いつでもどこでもそれなりに存在します。ただ、それを人材として発掘することのできる人が少ないだけです。発掘できず、芽をつぶし、それに気がつかないでいる人が多いのです。
2004年08月02日
コメント(1)
-
●従業員満足 25 マズロー理論の修正
「従業員満足」を考えるときに、欲求はなぜ起きるのか、どのように起きるのかの考察は重要です。それを知るために、ハーズバーグやマズローなど、いくつかの学者の理論を参考させていただいています。ところが日常の現場と、実験室のような純理論とでは、乖離が生じることがある。企業の現場で理論を使用するためには、この乖離の修正が必要です。マズローの5段階欲求説は欲求説関係の代表的な理論ですが、この理論も日常の現場で語るためには修正が必要です。今日は、このお話しをします。マズローの5段階欲求説はあまりにも有名ですが、同時に日常で使用するには修正が必要です。修正は「低位からの不可逆性」の部分です。「不可逆」といのは、生理欲求が満たされた後に、安全欲求が起こり、それが満たされた後に、集団所属欲求が起き、同様に、優越欲求、自己実現欲求の順番に、前段階が満たされた後に次への欲求起きる。その逆にはならない、という意味です。しかし、究極の極限状況を想定する場合は別として、日常の状況を良くするための理論という意味においては不適切です。これについては実は、アルダファの「存在・関係・成長」論があって、修正されています。こちらのほうが実用的。これは、「個の存在」「人間関係」「人間的成長」の要素が、基本欲求としてあるという理論です。そしてこれらは同時並行に存在することもあり、お互いに補完関係にもある、という認識です。わかりやすさのためにケーススタディをあげます。経理に配属された新人。体育会系で、フットワークの軽さと人間関係力の構築が得意という、バリバリの営業マン系。彼が配属されたのは、なんと経理。しかもどんよりしているという評判のお局の巣窟だった経理。彼は自分の得意分野の能力を発揮できず、「成長」させることもできない。しょうがないからこれを補完しようという心理から、職場の「人間関係」構築に意を注ぐようになる。ところが世代が違い、性格が違い、相性も悪い。どうもうまくいかずぎくしゃくする。しょうがないから「生活費を稼ぐために仕事をしているんだ」と割り切って、仕事にいそしむようになった。これがたとえば公認会計士をめざす新人で、職場の上司がその熱心さを認めて、あげていたら?あるいは、人間関係がウマが合う状態で、楽しい職場だったとしたら?このように「個としての存在・人間関係・能力の成長」の何処が突出していてもいいし、どの部分もある程度は満たされているし、ある程度は不満。そして極端にどこかの要素が少ない場合には、ほかの要素で補おうとする。これが現実の姿です。(ちなみに、マズローの「生理・安全」「所属・優越」は、アルダファの「存在」「関係」にそれぞれ対応します)マズローの提唱した、5種類の欲求要素は重要ですが、日常の職場の問題を考える上では、究極の状況を想定しないので、「不可逆」の部分については注意が必要です。
2004年08月01日
コメント(0)
-
●従業員満足 24 衛生要因としての賃金
内容は、昨日の続きです。衛生要因としての賃金について、もう少し考察します。・衛生要因とは水や空気がなければ生きてはいけません。少ししかなければ、大変。ストレスの原因にもなります。しかし仮に、水や空気をあり余るほど潤沢に用意してもらっても、特別にうれしくありません。実は、外部(=環境)から受ける刺激(=衛生要因)は、大なり小なりこのような性質を持ちます。つまり、外部から受ける刺激は、基本的に自分の意思で制御できないので、必要な分だけは確保したいけれど、確保したらあとはどうでもいいよという、受動的な反応になります。そのほうが精神衛生上良いからなのでしょう。実は、賃金も、この「外部から受ける刺激」なんです。・成果主義のうまくいかない理由成果主義・業績主義のため、一部のスターにドンと出し、その原資は、本来ほかのメンバーへ充当されるはずだった分からやりくりする。このやりかただとどうなるでしょうか。お金をたくさんもらったスターは、労働意欲がなくなります。なぜなら自分の人生の経営資源で、相対的に少ない「時間」を大事にしたくなるためです。これを「ハングリー精神がなくなる」といいます。また、ほかのメンバーは世間相場より低い金額をもらうことになるので、全体が不平不満で充満します。やる気のなさが横行します。スターは職場に顔を出さなくなり、その他のメンバーは顔を出しても労働意欲が低い。これではなんのための新人事制度導入だか、わからなくなります。これなら、まだ年功序列主義のほうがいいということにもなります。(ただし年功序列主義復古を推奨しているわけではありません)・年功序列主義下での成果主義実は年功序列主義も一種の成果主義です。一生涯を賭けて成果を比較するという感じの成果主義。だからすぐにはそれほどの差がつかない。ただし、今の少しの差が、将来の差につながる。今の賃金の差は「額の差」ではなく、出世スピードの上昇度の「角度の差」です。ですから、たとえばまったくおなじ同期で諸条件も一緒の者の給料を比較したときに、月給がたった千円違うという事実があれば、それは将来、課長と部長の差になってあらわれるかもしれないという暗示になります。千円違うという小さな事実は、将来の待遇の違いという想像により、ものすごい効果を生み出します。将来の役職の差、役職により使える会社の福利厚生サービスの質の差、役職間の賃金の差、退職金額の差、役職定年制の適用年齢の違い、関連会社への再就職の条件の差などなど、総合すると、莫大な違いになります。それが年功序列制度下の賃金制度では「千円」で表現できるのです。つまり、小さな金額で、大きく差別化することができるのです。もちろん、年功序列制度には、右肩上がりの賃金という、現代では致命的な欠陥があるので推奨はしてません。ただ、一部の製造業などには、現在でも最適な手法です。
2004年07月31日
コメント(2)
-
●従業員満足 23 従業員満足の基本 ハーズバーグ
従業員満足を考える上で、非常に参考になる一里塚があります。それはハーズバーグの「動機付け要因・衛生要因」の考え方です。・要因「動機付け要因」とは、従業員の心の中の要因で、いわば内的要因です。この要因がなくても、社員のヤル気を阻害するものではないが、その要因があれば、社員のヤル気がもりもりでてくるものです。具体的には「達成」「承認」「責任」「仕事そのもの」などです。「衛生要因」とは、環境要因の意味で、従業員を取り巻く外的要因のことです。この要因がたっぷりあっても、社員のヤル気が増えるわけではないが、その要因がないと社員のヤル気がたちまちなくなってしまうというものです。具体的には「経営方針」「賃金」「上司とのコミュニケーション」などです。・使い方環境要因は、世間相場であればいいやと割り切るのが賢明です。非常に立派に対処しても無駄になる可能性が高いです。逆に動機付け要因は、できるだけ満たしてあげるようにいろいろと工夫するといいです。衛生要因の中で特に大きいのが「経営方針」です。確かに、がんばれといわれても、何に対してどのようにがんばったら、がんばったことになるのか、不明であれば従業員のストレスはたまりまくりです。かといって緻密細密に詳細を極めてもらっても、それに比例してヤル気がもりもり沸いてくることもありません。うざったいだけです。ということで、経営方針についてはラフに、社員に示してあげることが重要になります。もうひとつ重要なのが「賃金」。実は衛生要因なんですね。これはものすごい指摘だと思います。要するに、「賃金は世間相場よりも低いと、どんどん社員のヤル気はなくなってく」「しかし世間相場よりもどどーんと出してあげても、カエルの面に水で、それほどの効果がでない」という意味なんです。動機付け要因は各社で工夫をするといいでしょう。「役割と責任を明確にした上で」「仕事をまかせて(=仕事そのもの)」「達成させて」「それを承認してやる」というメカニズムについて、いろいろと気配りをすると、それらが成果と菜って報われるということです。
2004年07月30日
コメント(4)
-
●従業員満足 22 賃金15年周期説 その3
昨日は、時代とともに賃金制度が変遷し、その原因には、現場の不満が慢性的にあるため、というお話をしました。本日は、では、なぜどのような制度をとっても、慢性に不満はなくならないのかについて、お話します。囲碁から発生した言葉で、「岡目八目」というのがあります。これは、ギャラリーのほうが盤面のことを8目ほど強い(=よく見通せる)というところから、他人のことはよく見えるという意味で使われます。評価について言うとかならずこれがあります。いいかえると、自分については皆、盲目です。なぜでしょうか。囲碁だけではないのかもしれませんが、対局を見ていて「自分よりプレイヤーが弱いと思ったら、同じくらいの実力と思え」「自分と同じ強さだと思ったら、自分より実力があると思え」「自分より強いと思ったら、めちゃくちゃ強いと思え」ということを教わりました。実際その通りです。このずれは、外から見えない相手の部分についての評価を過小評価してしまうためでしょう。自分については、内部についても含めて自己評価しているからです。これをうぬぼれといいます。この「うぬぼれ」による自己評価と、周囲からの客観的な評価との間には、多少のずれがあるのが普通です。さて、おたがいに、自分は90点、相手は80点だと思っている二人がいたとします。二人の実力はともに80点。評価の制度が精密になればなるほど両者に対し、「あなたは80点ですよ」と説明する。すると、両者から「相手については当たっているけれど、自分については間違えている」と不満をちます。もし、さいころでどっちかを90点、残るほうを80点と、でたらめな評価したとしたら、どちらかか片方の同意は得られます。要するに、きちんと客観的に正しい評価手法を編み出せば編み出すほど、総すかんを食らい、でたらめ評価未満の評価を受けてしまうという、皮肉な構造になっています。で、この根本の部分を直そうとしないで、賃金制度の形のせいにするから、「じゃあ年功給(勤続年数に対して金を払う)を職能給(能力に対して金を払う)に変えよう」「職能給から成果給(実績に対して金を払う)に変えよう」「成果給から職務給(職務内容に対して金を払う)に変えよう」と、いろいろ理屈をつけては試行錯誤するのですが、効果があらわれないのです。
2004年07月29日
コメント(0)
-
●従業員満足 21 賃金15年周期説 その2
昨日は、賃金制度の流行は、およそ15年ごとに変わるというお話をしました。今日はその推定される理由についてお話します。賃金制度が変化する要因として、世の中の環境の変化(方向性の変化)があります。東京オリンピック・万博、石油ショック、バブル崩壊など。プラスマイナス数年のかなり大きな誤差はあるものの、環境が変化している。これが人事制度の変更意欲に大きな影響を与えています。これは、賃金制度を変化させる外からの要因です。もうひとつは、内からの要因。むしろ実はこちらのほうが強いのではないかと考えています。内からの要因。すなわち、各人の不満足が限界に来て改定にいたるという、いわば内部からの崩壊。15年といえば、22歳で入社した人は37歳。ちょうど、会社を自らの手で改革していこうかという年代です。15年というのは、一通り酸いも甘いもかみ分けて内部事情にも通じ、実力を発揮するポジションにつくのにちょうどいい年数です。仮説として、仮に、「賃金制度はどのような制度にしても、不満が残るというう客観的事実」と「今の賃金制度が悪いために不満が生じているのだと主観的に感じている」ならば、幻の理想の賃金制度をめざして約15年ごとに主流が変化していくという事実に対して説明がつきます。そして制度に対する不信の心理サイクルに追い討ちをかけるのが外部要因。内部要因だけでは、はじけきらないのですが、機は熟しているので外部要因をてことして、ポーンとはじける。つまり、機が熟すのに、約15年かかり、それをはじけさせる要因は必ずしも15年ごとには発生しない。しかし数年に1度クラスの大きさの変化であっても、それが卒啄の機(そったくのき)となってはじける。かなり茫漠としたもの同士のイメージでもありますが、このように考えてます。※次回は、ではなぜ賃金制度(特にその分配論拠である評価)が不満視されるのか、この原因に迫ります。
2004年07月28日
コメント(0)
-
●従業員満足 20 賃金15年周期説 その1
戦後の賃金の歴史を紐解くと面白いことに気がつきます。それはほぼ15年ごとに流行があるということです。数年の誤差はありますが、なかなか面白い現象です。まずは大雑把に過去を振り返って見ます。●1 1945年から1960年までこの時代は、焼け跡の日本をどう復興させるか、また、どうやって食べていくかということが主なテーマで、賃金的には「●生存給」のようなものです。もらえればありがたい、という時代。●2 1975年までこの時代は、オリンピック、万博に象徴されるように、高度経済成長から石油ショックまでの右肩上がりの時代。この時代は「●年功給」です。市場が作れば売れた時代だから、だれでも課長になれる時代でした。少々の矛盾は成長率の喜びに隠される、というある種幸せな時代でもあります。●3 1990年まで石油ショックから、債権大国日本、そしてバブル崩壊までの時代。石油ショックにより、成長は無限大ではないということを知り、地球の資源も会社のポストも限りがあるということに気がつきました。そこで横並び出世をさせないために、出世を間引く手段として「●職能給」が脚光を浴びます。内容は修正年功給ともいうべきもので、中小企業で一世を風靡しました。●4 2005年までバブル崩壊から現代まで。デフレ大不況リストラ時代です。もはや、右肩上がりの許されない時代。市場価格に連動した人件費の要求が企業に求められ始めた時代です。この時代は「●成果給」90年代の後半は、職能給から成果給に移行する会社があいつぎ、現代では半分以上が成果給になっています。ところが、これが不満の温床になっており、新たに経営を圧迫する。評価のものさしが不明確。評価をする上司の価値観にばらつきがある。また、人間としてのエゴがある。与えられる仕事が不公平だ。優秀な人材が満腹感から働かなくなり、それ以外の人材が、はらぺこのため手抜きをするようになった、などなど。どうもうまくいく様子はありません。※明日はうまくいかない原因についての考察です
2004年07月27日
コメント(0)
-
●従業員満足 19 任せる
松下幸之助が一代で松下財閥を築きあげた要因。いろいろ考えられますが、大きな理由のひとつとして世界に先駆けて事業部制を構築したことがあげられます。これは平たく言うと「任せる」ことですが、なぜこのシステムを発明したかというと、実は本人が病弱だったから。病弱でしんどいので、自分で全部は出来ないのでまかせた。それが任せられたほうのヤル気を刺激し、どんどん増殖していった。とこういうことです。じゃあ任せればうまくいくのかとこれを真似をすると、まあ、ほとんどは失敗におわります。目配り気配りに違いがあるからです。任せるというと、放任してしまう場合が多い。あるいは任せるとは名ばかりで細かいチェックをする。どちらもうまくいきません。このあたりのさじ加減はむずかしいのですが、やはり要所要所は押さえておかないといけない。で、どうやって押さえていたのかというと、どうも、連絡をまめにして、報告をまめに受けていた。そしてこちらのイメージする方針通りしているかどうかをチェックして、それをものさしにしていた。方針に沿って失敗するほうが、方針を無視して成功するよりも評価を高くする。ここに秘密があります。連絡には、交換手が電電公社にはりついていた当時から、電話をかなり使っていたようです。電話は即時性があって、移動が瞬時(=東京の人と話した次の瞬間に九州の人と話すなどが可能という意味)で、内容は話すだけだから時間に無駄がない。この利点を最大に活用していたようです。本人は無学(小学校中退、10歳から丁稚奉公。字も満足にかけない)という自覚があるから、周囲の人に尊敬の意を持って聴くことが自然にできた、体力がない自覚があるから(休眠結核の爆弾を抱えていた)、任せることが自然にできた。方針という背骨だけを押さえて、あとは任せる。背骨に沿った行動かどうかだけをチェックする。これが松下財閥形成のパワー源の基本的な構造だったのでしょう。社員の「自分の仕事」という意識を最大限にくすぐりつつ、方針の明示・方針に沿った評価により正しい方向にパワーを誘導するする。松下幸之助氏の足跡は、従業員満足をうまく引き出せれば、すごいパワーになるという生きた証明でもあります。
2004年07月26日
コメント(0)
-
●従業員満足 18 予算を与える
従業員満足を、ローコストで充填するためにはどうしたらいいか。この命題について、引き続き考えて見ます。以前、「従業員満足4の2」で述べたように、「『私の』という盲目的意思」を慰撫することが従業員満足の重要なポイントになります。この「私の」を満たすのは意思決定の主体になるとき、平たく言うと「自分で決める」のが満足度が大きい。そこで、今回の提言は、ずばり「予算を与える」です。何かをするとき、たとえば社内の環境整備とか、イベントを行うときなど、あるいは通常の備品購入でも。いずれの場合でも、目的を明示した上で、予算(=金額の上限)を与える。そして予算内での工夫を任せる。これが意外なほどの効果があります。何にどれだけ金を掛けるのか、それによってどれだけの効果を引き出せるのか。実行する側にすると、この工夫が楽しい。また、自分で意思決定をして実行した後、低コストで高効果が得られたときには、その価値が自分の功績になる。それが事実として周囲から認知される。これらがすべて自我を満足させる刺激になります。この刺激が、すなわち報酬。給料を上げたり地位をあげなくても、満足を与えることはできます。しかも本気の工夫がありますから、金の使われ方も生きたものになるというおまけつきです。ポイントは、目的を明示すること。何の実現のためにそれをするのか、これを理解させること。それと、NGの買い物など、やってはいけないことの明示。代用など、やっていもいいことの例示。それと小さいことについてとやかく言わないこと。ものによっては、中間報告をさせること。相談は乗ってやること。まあ、いろいろありますが「お釈迦さんの手のひらの孫悟空」のイメージです。押さえるところだけ押さえておいたらアトは自由に遊ばせる。これができるようになれば、初級管理職としても合格です。(ちなみに中級は、それに部下の実力向上(教育指導)、上級はさらに仕事の創造が必要です)。
2004年07月25日
コメント(0)
-
●従業員満足 17 仕事の意味
・3種類の感覚有名な話なのでご存知の方も多いと思います。恐縮です。レンガを積み立てて建物を作っている作業員に「あなたは、今何をされているのですか」と聞いてみると、最初の作業員は「ご覧の通り、レンガを組み立てて、壁を作っているところです」。次の人は「町の教会を作っているところです」、そして3人目の人は「歴史的事業である○○教会の大伽藍の基礎を作っているところです」最初の人は、アルバイト感覚。次の人はサラリーマン感覚。3人目は経営者感覚。同じ仕事を同じようにやっているようでも、やっているときの面白さや、やりがいの度合いが違います。またこれは、仕事のできばえにもかかわる問題なので、できるだけ、後者の方に従業員を誘導する必要があります。・従業員満足の簡単な充填方法ではどうすれば、アルバイト感覚側から、経営者感覚側に動かすことができるか。一つの解決法があります。それは仕事についての情報を提供することです。今、自分たちがやっていることはどういう仕事の一部で、全体としてはどういう意義のある仕事なのか、そしてそのうちのどの部分を任されて、その意味はどのようなものなのか。これを伝えてあげることです。すると、単純作業のように見えた仕事が、実は周囲に支援を与える重要な役割を担っているということに気がついたり、あるいは大方針に沿う形で、今の自分の仕事を工夫してさらに全体最適に向けて仕事を加工していくことができます。そしてその仕事は「単純作業」の仕事ではなく「重要な仕事の一部分」を担っているという埃を持つこともできます。・ある実例覇気のなかったある女子事務員に、役職者が話しかけました。「自分たちの部門のしている仕事の社会的意義、役割の重要性」を語り、「君もそのメンバーの一員だ」と言い、「君の役割は自分たちの部門の荒くれ男を後ろから支援すること、それが部門の良い仕事のアウトプットにつながる」ことを話して「そのために何をしたらいいと思うか」を考えさせることにしました。その女性は、それまでそんなことは考えてみたこともなかっただけに、感激し、女性ならではの気配りを職場で発揮し始めました。その部門の空気も活性化し、生産性もあがりました。・何処の職場でももし、仕事の重要性を伝えてなかったり、全体像を伝えてなかったり、チームの一員だという自覚がなかったり、した場合には、即効性がある可能性があります。対処法も、期待する方向性を伝えた上で、自分に対処法を考えさせる。場合により対処法のアイデアの微修正を誘導する。この程度のことができるようなコミュニケーションは日ごろからとっておく。それだけで、かなり職場がいい方向にかわる可能性があります。意外と小さな躓き石が全体の流れを落としていることが多いので、虚心坦懐、初心にもどってチェックされることをお勧めします。
2004年07月24日
コメント(2)
-
●従業員満足 16 出入り自由
・「出入り自由」で人気アップある建設設計系の会社で、社員のスキルアップのための教育投資はするけれど、出入りは自由だと、一生会社にいなさいよとは言わないよ、という人事方針を打ち出しました。背景には、仕事の性質上、高い給料を払うことができないので、優秀な高給取りをつなぎとめておくことができないという台所事情があり、またそのため、ある程度人材が育つと退職していくという悩みもありました。そこで逆手を取って「出入り自由」を打ち出した。そしたら皮肉なことに、優秀な人材が集まりだしたという話があります。(情報源 最近の日経新聞)・会社の寿命と個人の寿命設計図屋さんは業務単価が決まってるので、しょうがないといえばしょうがないのですが、この考え方は業界の特殊事情を抜きにしても、今後も拡大していくでしょう。というのは完全に会社と個人の労働寿命が逆転したからです。長寿時代の現在では、労働寿命は20歳~70歳の50年間。会社の寿命は30年(それすらあやういという話も)だからです。昔は、寄らば大樹の陰が通用していましたが、山一證券の倒産を指摘するまでもなく、大樹も根が腐れば倒れるということがばれ始めてきました。現に今でも某財閥系製造業が今苦戦を強いられています。なまじ支えがあると、腐ってることに気がつきにくいものです。実は現代では情報化時代に軸足が移り、そのため世の中の変化が激しくなり、小回りの利く会社の方が生き延びやすくなったということと、スケールメリットが活かしにくい企業環境に変わってきたという背景があります。業界の将来も会社の将来もどうなるかわからない時代。確実に働く期間が延びてきた時代。そうなると会社の中でも出世よりも、会社を辞めても生きていける一生もののスキルのほうが重要になってきます。これが「出入り自由」の人気の秘密でしょう。・社員との新しい関係会社としても、この傾向を読むならば、今必要な職務については割高採用でもかまわないと考えるのが正解でしょう。それと、社員の技術アップへの投資。これは半分福利厚生という位置づけになります。これからの社員教育は社員が自由に自分の人生設計に合わせた教育を選び、その手助けを会社がするという形が望まれるでしょう。会社が押し着せるのではなく、支援するというスタンスです。全員一律の教育は望まれなくなっています。社員を会社に縛りつけないというスタイル。これもまた現代的な従業員満足の出し方であるといえます。
2004年07月23日
コメント(2)
-
●従業員満足 15 関心を持つ
数万人単位の人数の会社の場合、社長が名前を覚えてくれただけで社員が感動し士気が上がるということがあります。実際には、一生懸命名前情報を教えてくれる人がいるわけなんですけれど、名前だけでも直接にトップとコミュニケーションができると、下の立場の側としては、一気に「自我」が広がるのを感じるので、起きる現象です。もう少し小さい会社の場合、たとえば、お菓子の製造会社なんですが、従業員1600名のある会社では、社長が管理職兼務で基本的にマネジメントを全部見ている。全員から一言コメントを毎週もらって、それを毎週初半日かけて読む。この推移をみて、問題ある部署問題を抱えている社員をチェックし、人事の対処を行う。そういう会社があります。コツは、全体の1割の「?」というコメントを気にかけて、継続してチェックしていくことだそうです。だいたい問題予備軍が1割くらいで、あとの9割は「暑いですね」「がんばっています」みたいなものだそうです。コミュニケーションの工夫をすればここまでできる。ましてや、今は、メールでこれができる時代です。ある上場会社の社長は、メールで直訴をどんどん支える。読んで、必要なものをうち選んで返事を書く。簡単な返事はメール、複雑なものは電話。重要でないものは、秘書に指示して適当に。秘書を介在させたり、電話を使ったりすることで、かなりの量をこなすことができる。もちろん自分で全部メールしていたのでは時間が足りません。優先順位をつけ、発信の方法を仕分ける工夫は必要です。それにしても、かなりの対応ができる。この話をすると、メールを打てないという高齢の社長も大勢おられます。しかしメールを見ることくらいはできる。こういう場合は、発信を電話でどんどんするといい。これができるか面倒くさいと考えるかで、会社が発展するかつぶれるかに分かれるといってもいいくらいです。直接話ができる、自分の仕事の進捗状況に関心を持ってもらえる、何かのときには役に立ってもらえる。この安心感がさらに本気で仕事をしようという意欲につながります。自分はクーラーの効いた部屋でのうのうとしていて、部下が働かないと嘆いていてはいけません。大体そういう社長に限って、部下の動きを把握していない。自分の代わりに動いてもらっていることにまず感謝しなければいけない。給料を払ってるんだから働いて当たり前だ、と思うようではいけません。働くレベルにも、上中下があり、給料で上を要求することは不可能だからです。社員に仕事の「上」を要求するためには、まず社長が社員に「情」を出してやらなくてはならないのです。
2004年07月22日
コメント(0)
-
●従業員満足 14 一つの例証
・感想 夢仙人・さちこさん ちなみに私は500円でもいいから現金がいい。スパーのテレオペしてた時の大入り袋の100円が涙ちょちょ切れるほど感激もんだった。それだけでバカみたいに喜んで働いたさ。(7月20日8時10分) ・考察夢仙人・さちこさん、すてきなご感想ありがとうございました。さちこさんのうれしかった理由は何でしょうか。100円という大金がはいったから?それはないですよね。ではなにが?これは自分の存在、会社に貢献しているという自分の存在を会社が認めてくれた、その物証をもらったから。だからうれしかったのでしょう。その意味では、中の100円よりもそれを入れた袋のほうが、記念として価値があるかもしれないですね。・本気を引き出すこのように、経営者側からの、ありがたい、ありがとう忙しいのによくがんばってくれたね。というささやかなメッセージと少しのコストが、従業員の本気を引き出しています。この、本気を引き出すというところが重要で、仕事の出来を左右します。たとえばちょっとした笑顔とかさりげない心配りなどの、あるなしが、顧客のリピートオーダーの有無を決定します。そしてこの部分は、命令でうやれといわれてやれるようになるものではありません。以下に自主的な本気の貢献を引き出すか。難しい問題であると同時に簡単なことでもあります。人間は、ある意味鏡みたいなもので、自分だけよければいいという考え方をすると相手も同じようなリアクションを返してきます。感謝し、がんばりにたいして報いてあげたいと思うと、相手もそれに応じた活動をしたいと思うようになります。これが「士は己を知るものの為に死し、女は己を愛するもののために容姿を作る」といわれているゆえんです。古今東西、人間の機微はそれほどかわらないものなのです。労務管理は、この意味で人間心理学、組織心理学といえます。財務や数学のように割り切れるものではないのです。ここに労務管理の難しさと同時に面白さがあります。
2004年07月21日
コメント(0)
-
●従業員満足 13 ほめるタイミング
効果的に「ほめる」にはどうしたらいいのか、今回はこれを考えます。ほめられるときに一番うれしいのは、その場ですぐにほめられることです。なぜか。因果関係がわかりやすいから。これを応用したのが、餌付けを利用して行う動物のサーカス。クマだろうとアシカだろうと、猿だろうと、命令に従ったらほめてやってご褒美のエサを与える。これにより言葉の通じない動物に芸を仕込んでいます。これが可能なのは、賞罰をタイムリーに行っているからです。翌日叱ったのでは、動物はなぜ叱られたかがわからず、いじめられているのではないかと誤解します。しかし、実は、このメカニズムは人間も同じなのです。たとえば同じよい事をした人が二人いたとして、一人がその場で、もう一人が半年後に呼び出されてほめられる。どちらがうれしいでしょうか。愚問ですね。半年後では、感激もほとんどなくなってしまっています。しかし、この愚をほとんどの会社が行っているというと驚かれるでしょうか。実は、賞与がそれにあたります。半年間の努力による利益の配分還流というのが主旨ですが、いつのまにか感激のない「後払いの生活費」になってしまっている。これでは制度の形骸化であり、もったいないことなのですが、その原因はここにあります。タイムリーに与えるならば、原資は十分の一くらいで同じ効果を出せます。たとえば大入り袋のような形でタイムリーに支給するなど。ここでいろいろな工夫が出てきます。たとえば、タイムリーにほめ、「大入袋」は金銭ではなく点数で累積させておく。そして賞与時に、金額に換算する。これだけでも、タイムリー効果が現れます。ちなみに、ここで点数としておき、金額を不明瞭にしておくのがミソです。この期末にどれだけの利益がが出るかは、なってみないとわからないのですから、賞与原資額は不明にしておかざるをえない。点数の換金はその一部なのですから、当然不明です。なにも、金で支払わなくてもいい。いろいろなオプションが考えられます。会食、贈答品、観劇など、会社から感謝感激の印として出せるものなら何でもいいのです。
2004年07月20日
コメント(2)
-
●従業員満足 12 はげましのことば
・質問 Lost gardenさん やればできるは仕事ができたから言う言葉だとしたら、仕事をしている際にさらにやる気を起こさせるような言葉はありますか? (7月19日4時38分) すてきなご質問をありがとうございます。「仕事をしている際にさらにやる気を起こさせるような言葉」という意味で、「よい子・悪い子・普通の子」バージョンで考えて見ますね。いい言葉がなぜいい言葉なのかを知る上で、それ以外の言葉と比較するとよく見えてくると思いますので。たとえば納期が遅れぎみかも、という仕事について考えて見ます。・普通の言葉 「がんばれ」本当は良くない言葉です、がんばれってのは。でも、通常に使われてるので、まあ常識を加味すれば悪意のない言葉ということで、結果的に普通の言葉。なんで本来はよくないかというと、「がんばれ」というのは裏の意味として「お前は、がんばっていない」というメッセージがこめられているからです。そもそもがんばっていれば、がんばれという言葉は必要はないわけで、がんばっていないからがんばれ、となる。この意味でよくない言葉です。ただ、世間で通常に使われている「がんばれ」は「私はあなたを応援しています」という意味で使われており、発信側も受信側もその感覚で捉えているので、結果的には悪い言葉にはならずにすんでいる、ということです。発信者の心理的位置は「第三者」の立場です。・悪い言葉 「できた?」とか「いつできる?」「できた?」とか「いつできる?」は、悪い言葉です。仕事の納期に興味の重点があり、業務の遂行者には興味がないという言葉です。しかも、この言葉だと「もうできているはずなのに、できていないとしたらお前が悪い。サボっているからではないのか」という遂行者への非難の言葉が込められています。この場合、自分に責任のないことでも遂行者はできない不都合な理由を隠してしまいます。その結果その仕事が失敗に終わる可能性が高くなります。発信者の心理的位置は、「発信者」の立場です。自分が都合よくなるために周囲を操作するという意識です。・良い言葉 「何か、問題ない?」これは、納期より遅れている原因が、あなた(という人格)以外のこと(=外部要因、できごと)にある。それを除去する手伝いができないか(=応援している)、問題があったら相談してね。あなたが悪いのではなく問題が悪い。僕はその問題を取り除く味方、というメッセージになります。発信者の位置は、「受信者」の立場です。私はあなたを応援しているという意識です。このやり取りの場合、問題の予感を先出ししてくれるようになるので、トラブルの予防が可能になります。これが、さらに仕事をヤル気を起こさせる言葉の切り口です。・言葉より大事なもの言葉は、そのものよりも、日ごろの非言語コミュニケーションの積み重ねに意味があります。信頼のおける人の励ましの言葉はそのまま励ましとして伝わり、敵対する人の励ましは冷やかしに聞こえます。さらにヤル気にさせるためには、日ごろの愛情がポイントになります。
2004年07月19日
コメント(2)
-
●従業員満足 11 ほめ言葉
・難しい ほめ言葉賞罰の、一番手軽で安上がりだけれども難しいのが、この、ほめるということです。ほめるとはそもそも何か。ヨイショやベンチャラとは違います。「えらいね すごいね りっぱだね」ってなにがなんだか、わかりゃあしない。こういう馬鹿なほめ方をする人はさすがにいないと思いますが、確実に逆効果になります。馬鹿にしてるか馬鹿にされるか。いずれにしてもろくでもない。・やれば できるいいほめ言葉があります。「やればできるじゃない」。魔法の言葉です。これは、まずやればできるはずだという仕事を与える側の信頼が前提になっています。さらに、なかなかできていないという実態が続き、本人が一生懸命努力した、という状況があります。その上で、仕事をする側のレベルが上がったときに与えるほめ言葉です。これはものすごく効く。事前のしごきがきつければきついほど、効きます。仕事を与えられたほうは、まあ、最初はうらみますね。いくらがんばってもがんばってもだめだしされて、いい加減に嫌になる。嫌になるんだけれど、なにくそとやってるうちに、自分が自分でないくらいの、ある種取り憑かれたように仕事に入っていくときがでてくる。そのうち技量が上がって、満足できるかどうかは別として、明らかに新しい段階に何かが変わったという仕事のできばえのときがあります。ここで、ほめてやる。「やればできるじゃない」。・言葉の奥にあるものこの言葉には、仕事を与える側の信頼と期待が凝縮されています。そしてよくがんばったねというねぎらいの意味も。ということは、今まで厳しくダメだしが出ていたのは、眠っていた自分の高い水準を引き出すための産みの苦しみだったんだ、と、達成感と同時に、期待を受けていたという実感の両方を得ることができます。ほめるときには、ああだこうだと長々とほめるよりも、この一言のように、短いけれど深い意味が含まれているもののほうが深く心に突き刺さります。華道の剣山よりも、一本の縫い針のほうがはるかに痛いのと同じ道理です。ただし、言葉の奥にある信頼や期待が本物でなければ言葉の効果はありません。言葉とは、それ自身が何かをするのではなく、言葉で表すことのできないもの、ある種の実態、を象徴して具象化する道具だからです。あくまでも、信頼感が前提になります。
2004年07月18日
コメント(2)
-
●従業員満足 10 仕事の報酬
先日は、賃金を「稼ぎの報酬として支払いたい経営者」と「努力の報酬としてもらいたい従業員」の話をしました。今日は、これらの論議を一歩さかのぼってみます。稼ぎの報酬としての賃金、労力の報酬としての賃金、どちらでもいいのですが、共通するのは「仕事の報酬は賃金」という考え方です。しかし、果たしてそうだろうか。違うのではないだろうか。これが、今日のテーマです。仕事の報酬が、賃金でないとするならば、何が報酬なのか。仕事の報酬は、仕事。これが報酬です。仕事をする目的は、金を稼ぐということのほかに、面白さを求めるという要素があります。やりがいという面白さ、技量が上がるという面白さ、将来が楽しみになる面白さなど。経験が増え、実力がアップするという実感や、会社に利益をもたらし、頼られているという実感。仕事をしたという達成感など。これらがすべて報酬です。すると、仕事をしたという満足感達成感があり、仕事の経験が増え、勘がさえるとか視野が広まるなどの実力がアップする。次に同じ仕事をするときによりうまくできる。失敗を予防できる。その可能性が高い。つまり、仕事人としてのレベルがあがるわけです。仕事のレベルがあがるとそれに比例して、充実感も生まれる。生きがいであると同時に、自分が重要であるという実感のフィードバックでもあります。実は、これが報酬の本質です。「従業員満足4」および「従業員満足4の2」をごらんいただいた方には、すでにピーンとこられていると思います。いい仕事をすると、より高度な仕事のチャンスが生まれる。自己実現のチャンスにめぐり合える。これが本当の意味での仕事の報酬です。つまり仕事の報酬は仕事。より大きな、やりがいのある仕事。金や名誉は、これに後からついてくるものです。ここを見落とすと、不幸道へ歩んでしまうように思えます。
2004年07月17日
コメント(0)
-
●従業員満足 9 リストラ
・稼ぐ人現実問題として、稼ぎがなければ会社は給料は払えません。ところが会社の中は「働く人」だらけで、「稼ぐ人」は意外に少ない。特に中小企業の場合、稼ぐのは社長だけということもよくあります。社長の人事系の悩みの多くの部分もここにあります。実は成果主義にしたい、という発想には、経営者寄りの考え方を理解してくれよ、という切実な意味がこめられています。では、どうすればいいか。・リストラ基本路線は、「稼ぎ」に注力して、稼ぎにならない「働き」を最小限にする。要するにコストを下げて、利益を出す仕事の部分を最大化することです。正社員を増やさず、パートやアルバイトを多用する。あるいは、請負という形態を活用する。営業をしなくても集客できる段階的システムを作る。間接業務を外注化する、派遣等の労働力を活用する。などなど、やりかたはいくらでもあります。・心の傷やりかたはいろいろありますが、ひとつ気をつけなければいけないことがあります。それは、「従業員には心がある」ということ。この視点がないと、特に中小企業ではとんでもないことになります。リストラはうまくしないと組織の心に傷を残します。税理士さんは「人件費は損金」みたいな感覚ですから、ばさばさ切りたがる傾向にありますが、実際に切られた現場をみると、人身に後遺症が残っています。後遺症を払拭するには、10年かかります。また、整理解雇の4要件というのがあって、むやみやたらに解雇できないのが現状です。(たとえば、請負に業態変更させるのは解雇です)・コミュニケーション同じ方法をとるにしても、やり方によっては結果が大差です。ではどのあたりに気をつければいいのか。大ざっぱに言うと、コミュニケーションです。会社がそうする必要性を説き、異見があれば聞く。必要であれば調整策を盛り込む。これを段階的に行う。また、さかのぼって、入社時にとりかわす労働契約は重要です。この時点での説明不足は後々響きます。・バランスもう一つ重要なのは、バランス。経営にしわ寄せさせさせると倒産しますし、従業員にしわ寄せをさせると退職やトラブルの問題が発生する。もちろん労使が満足しても、反社会的組織活動であってはいけません。実際にはもっと細かいバランスが必要になります。たとえば賃金を改定するときに特定の層にしわよせだけをさせると無効になる。たとえば制度変更により減額される(損をする)人がでる場合には、その損をどのように補填するのか。この調整のしかたが重要なポイントになります。
2004年07月16日
コメント(0)
-
●従業員満足 8 賃金の意味
昨日は成果主義賃金についてのお話しをしました。それにしても「成果主義賃金制度にすればうまくいく」わけではないはずなのに、なぜ、あれほど成果主義制度は大人気なのでしょうか。実は、経営者にとって、魅力がある考え方だからです。実は、経営者と労働者とでは、給料に対する考え方が違います。見える景色が違うのです。・経営者(社長)と従業員(労働者・労働法)の観点の違い経営者にとって支給する賃金の論拠は「収入-経費」つまり、どれだけ「稼いだ」かです。一方、従業員にとって受給する賃金の論拠は「労働時間×時給」つまり、どれだけ「働いた」かです。この両者の感覚の違いが、サービス残業の強制の問題を引き起こしています。実は従業員から見て意外なのは、社長は払うものは払いたいと思っている。サービス残業を強いている社長さんでも、賞与は弾んでやりたいと考えています。これは、社長の立場では稼ぎ(利益実績)には報いたいと思うからです。もっとも、やらずぶったくりの社長さんでは、一緒に働こうとする人がいなくなるので、仕事ができなくなるため自然淘汰されるという事情はあります。一方、従業員の立場では、拘束された時間(働き)に対して報いてほしいと考えています。労働法も同じ考え方です。がんばったんだから、そのがんばりを見てほしい。このギャップはなかなか埋まらない。仕方がない部分もあります。従業員の場合、自分で求めて衝いた仕事ではなく、あてがわれた仕事だから、稼ごうにも稼ぎを見せることができない、という事情もあるからです。悪いことに(?)労働者の給料に関する権利は、労働基準法や最低賃金法などの労働法で守られています。しかし現実問題として、稼ぎがなければ、会社は給料は払えません。ない袖は振れません。そこで、会社を見渡してみると、「働く人」だらけで、「稼ぐ人」は意外に少ない。特に中小企業の場合、稼ぐのは社長だけということもよくあります。
2004年07月15日
コメント(2)
-
●従業員満足 7 成果賃金と年功賃金
・成果主義の賃金前々回は、賃金は衛生要因もしくは不満足要因である、たりないと比例して不満、しかし多くても比例して満足にはならないというお話をしました。実は、成果主義による賃金制度がうまくいかない理由の大きな部分がここにあります。成果主義は端的に言って成果をあげたら、成果に合わせていっぱい支給するし、成果が出なかったら、その出ない成果にあわせて少なく支給する、というものです。ここで、成果の上がっている少数派と、成果の出ない多数派に分けて考えます。まず、前者。優秀な人が成果をあげる。成果報酬を短期間でどーんと支払う。ところが、そのお金を儲けた人。あとは働こうとしない。どうしてかと尋ねると「生活に必要なお金を稼いだら、後は自分の時間としてエンジョイしたいんです。タイムイズマネーではなく、タイムイズライフです」優秀じゃない人は、成果が上がっていないからということで、賃金が下がった。下がったら、馬鹿らしくってやってられないよ、ってなわけで、内職アルバイトにひた走り。結局だれも仕事をしなくなった。極端な例ですが、賃金に比例してヤル気が起きて業績がアップして、という経営者の読みどおりには従業員は動かないし、従業員満足の「最大多数の最大幸福」はそこには存在しない、ということも、お分かりいただけると思います。・年功序列主義の賃金今はもう、すっかりなりを潜めた観のある年功主義賃金ですが、どうしてどうして、この、賃金と言う切り口から見る年功序列主義賃金は、なかなか味わいのある制度。年功序列制度の会社では、条件が同じもの同士の給料の金額が1円違うと、それは大変な違いを意味します。ほとんど横一斉同額アップが建前ですから。金額の差は、「出世の角度」の差を意味するので、大変なんです。たとえば角度が1度違うと、100メートル先には、線は結構乖離します。この差が、つまり出世の差。つまり今1円違うというのは将来トータルでイクラかの違いになることを意味し、この圧力が現在の給料にはねかえって生きてきます。つまり1円の違いは、たとえば将来の部長と部長代理くらいの差であるかもしれず、さらにはその後の退職時の年齢や子会社への再就職などの二次的待遇まで含めた差を意味するかもしれません。この1円の意味するものに対する共同幻想が、1円を1円でないものへ変えてしまいます。これがゼロベースの賃金(=過去をご破算にして、ゼロから積み上げて内訳を見積もって決める賃金)だと、同僚とたとえ10000円の違いがついても、まあご愛嬌みたいなニュアンスになってしまいます。すぐに取り返せるさ、てなもんです。成果主義賃金だから社員満足が達成できるというわけでは、ありません。もちろん、成果主義賃金制度を採択しても従業員満足を達成させることは不可能ではないのですが、それには別な仕掛が必要になってきます。・結論 成果主義制度が、従業員満足を引き出すわけではない。明日も、ひき続き賃金です。
2004年07月14日
コメント(2)
-
●従業員満足 4の2 「自我」についての補足
ちょいと予定を変更して、今回は「自我」についての補足をもう少しします。というのは、ここの認識がキーポイントであるにもかかわらず、意図が説明不足なために、逆に今後の理解の妨げになりかねないと考えたからです。以下は、ある方からメールで質問をいただいて、行った返答がベースになっています。●ご質問> さて、「自我」、この言葉の持つイメージを少し取り違えていたように思われる> のが、今日の話の内容です。この「自我」をくすぐりつつ(?)会社の目的とす> る所に誘導する、それが肝要なんでしょうね。> 最近余り聞かなくなった言葉に、「愛社精神」「ロイヤリティー」があります。> あの頃は日本経済も厳しい状況下にありましたが、皆輝いていましたね。正に> 「プロジェクトX」の時代でした。日本国家・会社・従業員皆の目標のベクトル> が合い、苦しくても先に明かりを見出しながら、皆頑張っていたんでしょうね。> 「自我」も先行きの見通しや安定感がないと上手く行かないものなんでしょうか?●回答・自我について自分の言っている「自我」というのは、結局「盲目的な意思」(=自分が”生き残る”ために必要な諸活動エネルギー)のことです。すべての生き物は自分の遺伝子を複製し、繁殖させようとする、本能よりさらに根源的な本能。いわゆる「利己的な遺伝子」。あの意思が原型です。たとえば、子供をほしがり、弟子をほしがり、名を残すこと(みんなの記憶に残ること)をほしがります。これは未来将来方向への「盲目的な意思」です。所有欲、独占欲、支配欲、自己重要感などは、現在方向への「盲目的な意思」。自己正当化(すっぱいレモンや甘いぶどうなど)、記憶の歪曲認知などは、過去方向への「盲目的な意思」。これらはすべて「『私の』という範疇」で示されるものです。・「『皆の目標のベクトル』が合い、輝いていたについておっしゃるように、「自我」をより大きなものに素直に没入して喜ぶことができたというのは、国が貧乏だったからですが、ある意味幸せなことでした。「富貴はともにせず」であり、豊かなる現代は、この意味において誠に寂しい限りです。没入する自我が大きい範疇のものであればあるほど(個人より会社、会社より国、国より人類など)、全体がスムーズに流れますので、犠牲的精神が尊ばれ、犠牲的行為に対して感動するのもこの理由によります。ただ自我の没入対象の範疇が大きくなりすぎると共感できなくなる部分も大きくなります。人類愛を正面から標榜するとうさんくさくなったり先ほどの例で「人類より全生命、全生命より、物質を含む全存在」なんてのは、ほとんどの人(あるいは全員?)から同意が得られないはずです。たとえば経営理念の浸透が重要とされるのも、このあたりの機微によるものでしょう。・ご質問の「先行きの見通しや安定感」について未来に不安があると、現在を守りで対処しようとする。これが活動を鈍くすることはあると思いますが、「自我」とはあくまでも「自分」を過去現在未来に対して拡大しようする「盲目的な意思」の活動意欲のことですので、自我自体が鈍くなるということはないはずです。ただ、どの方面に活動の食指を伸ばすのかが違ってくるのでしょう。いいご質問をいただき感謝しています。おかげさまで、伝えきれてなかったもやもやの部分が整理されました。今後ともお導きのほど、よろしくお願いいたします。
2004年07月13日
コメント(1)
-
●従業員満足 6 ちょっと補足+賃金
・幸せ=自我の拡大とは前々回は、幸せとは、自我の拡大の実感である。これを活用するのが人事制度を構築したり運用する際の要諦であり、へそだというお話しをしました。ここで、キーワードとなる「自我の拡大」について、わかりにくかったようなので、冒頭でもう少し補足します。自我の拡大とは、個人レベルでは、いままでみたされなかった欲望が満足されること、あるいは満足できるようになると予感すること。自分の能力や視野が今までよりも広がったと実感できること、あるいは予感すること。組織とのかかわりのレベルでは、所属を実感できること、組織(集団)の中で、存在を認知してもらうこと。組織の中でのなんらかの優越性を認めてもらうこと、実感できること。これらが、今までなかったのが増えたとか広がった、というのが「自我の拡大」です。・具体例たとえば、30年ローンを組んで家を新築する。すばらしい見晴らし、美しい内装、気に入ったレイアウト。確実に幸せです。それは自分の欲望が満たされたから。すばらしい家を所有したから。この時点で自我が拡大したからです。しかし、悲しいことに刺激はいずれ、慣れの中に埋没します。人のうわさも75日。75日というと、2ヵ月半。つまり、刺激が保つのは、せいぜい3ヶ月ということ。せっかくの新築の家の喜びも3ヶ月後は以前と変わらず食う寝るところの位置でしかなくなります。新築の喜びは3ヶ月、新築のローンは30年。・賃金実は、これと同じ構造なのが「賃金」です。がんばった、ほめられた。昇給した。うれしい。ところがこの昇給の喜びが1年持たない(へたすると、3ヶ月も持たない)。支出は、収入が増えると自然と増えてしまう。しかも給与が上がると社会保険料も上がる。税金も上がる。結局手取りに反映するのはそれほどではなくなります。実は賃金は衛生要因もしくは不満足要因といわれるもので、「足りないと、そのままストレートにその不満足が反映する」と同時に「充分を越えてあった場合でも、その多い部分は反映しない」という性質を持ちます。つまり、世間相場よりも少ないと、ぶつくさ文句のいいまくり、しかし、多く弾んでやっても、その割にうれしく思ってもらえない。なかなかやっかいなしろものです。今日はここまでです。明日は成果賃金と年功賃金についてです。
2004年07月12日
コメント(0)
-
●従業員満足 5 従業員満足の目的
・ある失敗事例都内の零細企業。アウトソーシングの事務処理系の会社で、割合にルーチン、そのわりに複雑で面倒な仕事が多く、とにかくマンパワーに頼らなくてはならないという会社がありました。当然、問題になるのが、人材のマンパワーをどうやって担保するか。これをどうするかについて散々悩んだ挙句、社長の出した結論が、「従業員満足が大事だ」・・・社長はさっそく、社員に対して、目標管理制度を実施することを宣言。その際に、各自自主的に目標を決めさせました。最終のゴールを明示して、個別目標を決めさせた上、面接をして管理していく方法をとりました。半年後、なんか妙に、会社に元気がありません。1年後、会社に元気が戻っていました。でも、以前の会社と微妙に何かが違う。。。実は、その1年間で、社員が全員入れ替わってしまっていたのでした。社長の話によると、従業員満足を最大限にするために、彼らの意見を尊重して目標を立てた。ところが、でてきた目標の水準は甘くて低いもので、しかも達成率もさらに低かった。そのうち、職場の空気がよどみはじめた。ひどかったのが、客先からのクレームの握りつぶしや仕事(オファー)の拒否。残業をしたくないのと、うるさいことを上から言われたくないため。もちろんまっとうな社員もいるのだが、少数派。そのため、まじめで優秀な人が一人ぬけ二人抜けしていった。なにしろ基本方針が「従業員満足」。従業員が満足するためには、仕事は邪魔。コミュニケーションも面倒くさい。最初はびくびく、そのうち段々堂々と。こうしてゆっくりと会社は腐っていった。ひょんなきっかけから、社長はこのことに気がついた。得意先からクレームの話を聞いてびっくりしたのだ。驚いた社長は、社員を集めて、方針を変更し、目標を作り直してあてがって、厳しく報連相を求めるようにした。すると、いっせいに社員が辞めると言い出した。最初から厳しかった社員環境と違い、最初ゆるゆるだっただけに、厳しさとのギャップに耐えられなくなったためであった。不幸中の幸いだったのは、社員思いの社長であることは社員も知っていたということ。そのため、少しずつ社員を入れ替える方式に賛成してもらうことができた。引継ぎも、なんとか行うことができた。新しいやり方である「厳しさ」の水準は下げなかった。あとから入ってきた人には普通の感覚で従ってもらった。そして1年後、全員が入れかわってみると、今の連中は、その「厳しい水準」を別に理不尽なものとも思わずこなしてくれている。最初からこうすればよかった。・失敗の原因「従業員満足」の達成を会社の目的にしてしまったのが失敗の原因でした。目的とするべきは「顧客満足」あるいは「会社の利益」。従業員満足は、手段です。会社の利益を上げるのが最終目的。そのために、手段として顧客満足の達成があり、顧客満足を達成する手段として従業員満足の達成がある。また、目標の達成の水準を具体的に測定できるものにしていなかったのも敗因です。「がんばる」とか「一生懸命」のような抽象的な文言は、目標として、あるいは結果の計測対象として、無意味です。自分としては一生懸命がんばった。それは事実ですが主観でもあり、客観的にはどちらともいえないあいまいなものです。この敗因はメジャーを準備しておかなかった会社側にあります。「一生懸命がんばる」ために何をするのか。1日30件新規顧客開拓のために電話をかければがんばったことになるのか。5件でもがんばったことになるのか、あるいは最低100件は必要なのか。。。。。具体的に基準となる数値を配備しておけば、これらについての問題は解消されます。・結論難しいことではありません。「従業員満足とは何か」「何のための、従業員満足なのか」「なぜ従業員満足は必要なのか」。こういう本質をつかむことなしに「従業員満足」を導入したために失敗したのでした。この件に限らず、洞察して本質を把握し、わかりやすい対処法をこつこつと実施していく。これが人事制度導入成功の秘訣です。※本日このネタを選んだ理由は、癒し太郎さんの日記を見たのがきっかけでした。明日は、従業員満足の最重要要素の一つである「賃金」について考察します。本日はここまでです。
2004年07月11日
コメント(0)
-
●従業員満足 4 幸せの本質は、自我の拡張の実感
・根源としての人間観本日は人間観のまとめとして、個人としての「人」あるいは組織人としての「人間」が、何について幸せを感じるか、ということについてお話します。ここを押さえると、経営に効果的な従業員満足とは何かを把握しやすくなります。少なくともひとりよがりの従業員満足システムの構築をせずにすみます。さて本日の本題です。実は、今日の話がこのシリーズ中で最大のへその部分になるのでよくお読みください。はい、では本日の本題。わたしたちは、何について幸せを感じるか。。。。。解答は「自我の拡張」です。・自我とは何かここで、自我とは何かについて、お話します。私の道具、私の仕事、私の会社、私の友達、私の子供、私の、私の私私・・・。道具や仕事などが大事なのではありません。大事なのは常に「私の」の部分です。この「私の」という範疇が、自我です。わがままや利己主義の意味でないということを、まずご理解ください。たとえば明日は国政選挙ですが、投票することにより「私の選択」で国が決まります。投票行為により、国政が自我の範囲に含まれます。そのため、不本意な結果だとしても、しょうがないと積極的な諦めができます。投票を棄権すると、自分には関係ない、というアナーキーな気持ちが生まれます。これは国政が自我と切り離されるからです。この意味で、白票投票と棄権とでは、大きな意味の違いがあります。日常も同様です。会議などで根回しをしないと「俺は聞いていない」といわれて意地悪をされる。これは根回しをしなかった相手の自我が満たされていないからです。あるいは社員旅行などで、高級コンパニオンを招いてのドンチャン騒ぎより、各部門に分かれて出し物を出し合う形式のほうが金がかからないにもかかわらず盛り上がるのは、各自が会に積極的に関与しているという実感があるためですが、言い方を変えると、その会の成立に対して、自分の自我を注入しているためといえます。このように、自我というのは厄介かつ重要なものです。そして、ここで、さらに重要なことを申し上げます。私たちは、自我が拡大するときや、その自我が慰撫されるときに喜び、幸せを感じます。また、これを傷つけられるとき、不幸を感じ、防御のために暴力を振るうなどの行為が出てきます。これが幸せの本質です。ここは重要中の重要なポイントですので、今から検証します。たとえば、野球ファンが自分の応援するチームの勝利に酔いしれる。子供の成長に没入して喜ぶ(俗にい言う親ばか)。会社の中で、自分が認められたと実感する。新しい能力が身についたと実感する。これらはすべて自我の拡大か、慰撫です。たとえば、ワールドサッカーの暴動などは自我を傷つけられる型です。幸せというとたとえば好きな異性と相思相愛。これは相手の中に自我を投影するようになる喜びです。その効果の意義の善悪はともかくとして、現象としては事実です。・自我をどう活用するか「自我の拡張」の推進、または押さえ込みや傷つけ、それらが「賞」であり「罰」となります。この認識が、人事系の制度構築や、コミュニケーション推進のコツです。部下育成と成長の指針であり、従業員満足への道しるべとなります。上司を説得し動かす秘訣であり、集団を動かす鍵です。そもそも、説得という言葉の意味は「説ク(返り点)得ヲ」。つまり相手の得を説くということ。相手の「得」とは相手の自我を傷つけず拡張できるという図のことで、説くとはそれを相手にわかるように示すことです。それは大義名分であり、利益の導入であり、明るい未来の予感、成功と賞賛のイメージ。さまざまな形をとりますが、煎じ詰めるとそれらはすべて「自我」の拡張か慰撫です。今日のお話は、へそのなかのへそであり、へそ過ぎてその重要性にピンと来ないかもしれません。そのくらい重要なことです。この辺の事情を解析するため、たとえばなしをします。たとえば大学受験。大学受験のノウハウはいろいろありますが、その虎の巻というか、へそ中のへそは、ただ一言「燃えよ」だったりします。開かれたヒミツとも言うべき性質のもので、教わるほうはピンと来ないわけです。奥義というのはすべてそのようなものです。弟子が熟してきて、あとひとつつきで開眼するだろう、その状態のときに、ポーンと背中を押してやる。その際の一言みたいなものです。要するに、受け止める側の機が熟していないと、受け止めることのできない言葉なのです。自我の拡張、という概念が、いかに人間の活動の広範囲をカバーしているかふりかえってみてください。古今東西の有象無象の事象から、自分の周辺および自分の過去現在の出来事およびその背景となる関係性。検証すればするほど、「自我」がいかにせつないほどからみついてきているか、行動の動機の根源をなしているか、ご理解いただけると思います。そして、これをつかむことが、人事系の仕事をする上で、特に重要になります。これを把握するため人事は「中国の古典」「戦国時代の歴史」「心理(宗教を含む)」を読めといわれます。人間と組織の本質の理解のためです。その太い背骨の部分が、しつこいよういですが「自我」です。・まとめ感情の動物であり、組織の中において、関係性と、自我の拡張と慰撫を限りなく求める動物。これが人間の本質特性です。この人間の性質に添った形で具体的にいろいろと処方箋をとっていくのが名経営であり、それを補佐するのが、コンサルタントです。ぜひ、おとといから本日にかけてのいわんとするところをお汲み取りいただき、自分の事例に置き換えて、検証されることをお勧めします。いろいろな有益な気付きがでてくることをお約束いたします。明日からは具体論に移ります。本日はここまでです。
2004年07月10日
コメント(8)
-
●従業員満足 3 「人間」は、自己重要感を求める社会的動物
・根源としての人間観従業員満足を考えるときに、まず従業員とは何かを考える必要があります。昨日は「人」について考えました。本日は、後編。「人間」について考えます。昨日も申し上げたように、「人間」は組織の一員としての特質です(人の間にいるから、人間)。・人間は、自己重要感を求める社会的動物人間にはさまざまな欲望(衝動)があります。たとえば食欲、性欲、睡眠欲。でも、これらの欲望は小さなもので、周囲への影響力は小さい。人間の社会的動物の部分である、「自己重要感」を求める欲求。これは非常に強く、かつ根深い。たいていの欲望は、ここから発しています。実は、経営人事の要諦中の要諦、へその中心部が、ここです。ここをおさえておけばそれほど的外れなことにはならず、また逆に、ここを無視しては、ほとんどでたらめなことになる。ここがポイントです。「自己重要感」というと、大げさですが、要するに、認知への渇望、平たい話が、認めてほしい、ということです。もう少し噛み砕くと、「知ってほしい、覚えててほしい、忘れないでほしい」ということ。重要人物であることを認めてほしいというばかりではありません。概念は、もう少し広い。マズローの5段階欲求で言うと、「食う寝るのレベルの欲求」→「存在の安全保障レベルの欲求」→「所属(愛情)レベルの欲求」→「認知(承認・尊厳・優越)レベルの欲求」→「自己実現レベルの欲求」のうちの4番目の欲求になります。赤ん坊から大人、老人まですべて「かまってほしい」ということです。余談ですが、マズローは「自己実現」の部分ばかりが誇張されていて、やや誤解されているようです。また、5つの階段をだんだん上っていくものではなく、並行したり、あるいは下の段階が満たされないでいても上の段階を先に満たすことがある、ということで、ここも誤解されがちなところです。この自己重要感(=認知)満足への欲求は、広く深い。名誉を求めたり、死後は自分では検証できないにもかかわらず、後世に名を知られたがったりというのもこの衝動によるものです。たとえば暴走族が目立ちたがったり、犯罪人が自己顕示したりするのも、この認知への渇望です。子供がかわいいというのも、自分の遺伝子を後世に認知させるという欲求の現れです。最も誤った方向にエネルギーが流れてはいるのですが。。。人事制度を構築するときには、このエネルギーを活用できるかどうかが重要なポイントで、その成否が決まります。労務管理は、論理的というよりは、心理的なものです。(※以上については、300人以下の中小企業を前提として話をしています。それを超える人数の集団についてはあてはまらないかもしれませんが、論の対象外とします)多くの従業員満足の問題の原因は実はコミュニケーション不全にあります。そして、コミュニケーションの問題は、認知の問題。制度の不全を直す前に、関係性の不全を直す必要があります。そして関係性の不全の主な原因は「自己重要感」の欠落です。ここを把握しておけば、具体的に何をしたらいいのかの対策がいくらでも見えてきます。この具体例については、また機を改めて記載します。・今日の結論 「人間は、自己重要感を渇望する」きょうはここまでです。
2004年07月09日
コメント(0)
-
●従業員満足 2「人」は、感情の動物
・根源としての人間観従業員満足を考えるときに、まず従業員とは何かを考える必要があります。それは「人」であり、「人間」です。「人」は、個人の特質。「人間」は組織の一員としての特質です(人の間にあるから、人間)。この2つについて、考えてみます。今日はその前編、「人」について考えます。・「人」は、感情の動物まず、人は「感情の動物」です。この洞察を最初に読んだのは、あの名著「人を動かす」でした。学生時代に紐解いたのですが、目からうろこの大ショックでした。その後、20年以上の人生を経て、その間の経験を加味してふりかえってみても、まさにその通り。鋭い指摘です。人はそれぞれいろいろな行動をする。その際に、いろいろ理屈をつけてその足跡を正当化する。けれど、最初に来るのは、「感情」です。理屈ではない。早い話が「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」。なぜ袈裟が憎い、とにかく憎い。屁理屈はあとからいくらでもくっつける。基本スタンス、価値観を支えるのはあくまでも、感情。「理屈(理性)」は、正当化するデコレーションツール。要するに、結局は、好きか嫌いか。あからさまに言うと角が立ちますが、本音です。・ある実例在職中のあるとき、自分は人事担当だったんですが、営業部長と話す機会がありました。「おう、人事か。いい人材を採ってくれよ」 「あのぅ、いい人材っていうのは、どんな人材なんでしょう」「そりゃあ、おれが使いやすい人材だ」 「使いやすい人材というと?」「文句を言わず、俺のしてほしいことを、どんどんてきぱきしてくれる人材だ」 「ということは、イエスマン?」「・・・・そうだ」優秀な人材云々といっても、これが現実です。だれでも、自分の思うとおりに働いてくれる人が好き。好きな人の点数が高くなる。どこの会社でも普通に見られる光景です。ごますりが良い悪いかを論じてもしょうがない。それが「人」だから。人は感情の動物だから、しょうがないです。関連してお話しすると、よく会社の社風を変えるような人材を求めるといいつつ、結局うまく改革がいかないというケースがよく見られます。ある意味これは当然なこと。そういう主旨で集められた「人材」は2通りのどちらかの選択しかありません。ひとつは「朱に交わって赤くなる」。もうひとつは、「去る」。このどちらかしかないのです。組織というのは保守的なもので、どうしても現状を維持しようとする。集団の意思としてどうしても現状を維持する。そのとき、改革を叫ぶのは異分子扱いであり、組織としては、取り込むか排除するかするしかない。まちがっても、従おうなどとは思わない。結局、改革は挫折するのが常道です。これを打破するには、頭をすげ替えるしかないのですが、これはまた別の話なので今日は割愛します。・今日の結論 「人は、感情の動物」きょうはここまでです。
2004年07月08日
コメント(4)
-
●新シリーズ 従業員満足 1なぜ従業員満足が重要か
●ご挨拶 新シリーズ「従業員満足」について諸般の事情により、少し突っ込んで「従業員満足」について調べたり考えたりすることになりました。その中途経過報告というか、プロセスをちょこちょことまとめてこの楽天日記に書いていこうと考えています。日記を読んでくださる皆さんから「それは間違いではないか」「俺はコウ思う」「これはこういう意味ではないか」「その文献はここにある」「これが参考になる」など、ご意見や示唆をいただければありがたいです。●序章 なぜ「なぜ従業員満足が重要なのか」を追求するのか従業員満足の重要性や要因や阻害要因などを研究することにより、経営者は「社員が生き生きと働く、風通しの良い、利益の出る会社」を作るヒントを得ることができるでしょう。社員は「自分の人生の生きがいを、会社の仕事に重ねて働くことがができる」ので、幸せになるでしょう。また、生き生きとした強い中小企業が日本中にでてくるようになれば、力強い日本の復活になります。いいことだらけです。その種をまきたい。これが、「なぜ従業員満足が重要なのか」を追求する主な理由です。また、経営コンサルタントの方(税理士、社労士、診断士含む)はご自分の仕事のヒントになるかもしれません。また逆に「何を浅はかなことを言ってるんだ」ということも多くあるでしょう。そのときには、どんどん突っ込んでいただければ、ありがたいです。私の勉強になります。実はこれを期待しています。ここでいくら恥をかいても、落とし穴の穴埋めができれば、業務の本番での助けになります。盲点や矛盾点に早めに気づいておきたいというのも一つの理由です。また、サラリーマンの現場から、こんな従業員不満足の原因があった(早い話が愚痴)という情報も楽しみにしています。それを解消するためには、あるいは予防するためにはどうすればいいのか、これを考えるきっかけになるからです。・想定するターゲット読者今シリーズの読者として、対象外なのは、物販系の個人事業主であろうと思われます。ただ、その方たちでも、会社や会社員に営業をかけるときには、敵を知る、という意味で、無意味なことではないと思います。話の種くらいにはなるでしょう。また、かつて会社員だった場合には、それを思いだしていただければ楽しんでいただけるかと思います。結局全部が読者ターゲットになりうるのですが、とりあえず、直接的に想定している読者層は、一般社員、管理職、経営者、および彼らの家族、広い意味での経営コンサルタントの皆さん、以上です。●本編 なぜ従業員満足が重要なのか・理屈は簡単いよいよ、第1回目は、「なぜ従業員満足が重要なのか」です。要するになぜ従業員満足シリーズをすることにしたのか、その動機を問うてるわけです。まず、会社は利益を上げ続けなければ、存続できない。利益を上げるためには、顧客満足を勝ち取って、定期的な財やサービスについてのご注文をいただかないといけない。顧客満足を勝ち取るためには、徹底した本気の従業員の業務行動が必要になる。その行動を実際にしてもらうためには、従業員が、会社のために本気で働きたいと思えるシステムを作っておかなくてはいけない。そのためには、従業員満足を研究する必要があるのです。・実際が難しいじゃあそのためにはどうするのがいいのか、というとこれがなかなか難しい。個人としての人間、および組織人としての人間。この価値観というか習性というか、こういうものを理解把握した上で、対処していかなければいけない。ところが、この「対処」が簡単ではない。・失敗例 成果主義賃金たとえば賃金制度の成果主義。がんばればお金いっぱいもらえるよ。ヤル気出してね。・・・・ところが、優秀な人はガボッと短期間でお金を儲けたら、あとは働こうとしない。どうしてかと尋ねると「生活に必要なお金を稼いだら、後は自分の時間としてエンジョイしたいんですよ。タイムイズマネーではなく、タイムイズライフですからね」ということで、優秀な人が働かなくなった。優秀じゃない人は、賃金が下がったから、馬鹿らしくってやってられないよ、ってなわけで、内職アルバイトにひた走り。結局だれも仕事をしなくなった。・失敗例 目標管理制度目標管理制度を導入しましょう。従業員のヤル気を大事にするために、従業員に目標を決めさせましょう。決めましたか?はーい。1日のうち半分遊んでいても達成できる目標をたてました。どんどん達成しています。目標を達成したのだから、ぼーなすをはずんでください。・・・テ、テメェぶっ殺されんど。・失敗例 ほめて育てる「いやあ、いい仕事をしてくれたね。たいしたものだ。がんばったね。どうもありがとう。」「・・・社長、本当にそう思ってるならボーナス弾んでよ。」「いや、ほかのみんなもがんばったから。なんだよ、口だけかよ、馬鹿らしいな、今度から手抜いてやろう」・ではどうすればいいのか失敗しないためには、具体的にどうすればいいのでしょうか。これらについては、次回以降、ボツボツとふれていくことになります。正しい従業員満足の方法とは何か、どのような方法があるのか。これらについて、考えていきたいと思います。その手始めとして、ベースとなる「基本的な人間観」から整理してみたいと思います。というわけで、次回は、「人間とはいかなる生き物か」について考察してみたいと思います。本日は、ここまでです。
2004年07月07日
コメント(2)
-
●人の心に花一輪添えられる人に 桂小金治(抜粋)
今回は、中休み。ちょっといい話のご紹介です。「思考が人生をつくる」とはいうけれど、では、その「思考」はどこで作られるのでしょうか。実は、小さい頃に、親の人生への態度を観て、その原型が作られるのではないでしょうか。そこで、今回は、その断片を拾ってみました。ハンカチをご用意の上、ご覧ください。「人の心に花一輪添えられる人に」タレント・桂小金治さんより、一部抜粋(全体の2/9くらい) ※↑クリックすれば全編を読むことができます。■『この赤飯にこたえるぞ』 うちへ帰って、ふと気がついたら、おやじが着物道楽だったんです。着物をたくさん持っていた。空襲の後の焼け残しの着物を3枚売った。着物でできる商売はないかな、そうだ、おやじはよく寄席へつれていってくれた、落語家は皆着物を着ていた、落語家になろうと決心をしたのが昭和21年、暮れも間近い寒い晩でした。新宿末広亭の楽屋をがらりと開けて、「落語家にしてください」と入っていったのですが、そう簡単には落語家にはしてくれない。「楽屋で働いていてごらん」。働くということは子供のころからおやじにたたき込まれています。僕のお父さんは、人に用事を言いつけられてから仕事をするやつは半人前、自分の目で、自分で仕事を見つけて、自分で動けるやつが一人前。僕は生まれて初めての楽屋で、目で見るものを仕事に変えて駈けずり回った。この姿を認めてくれたのが、関西出身の桂小文治師匠。「よう働くやつだな。わいの弟子にしてやるで」 この師匠の目にとまったのが僕の幸運の始まり。この師匠の目にとまるような男に育てておいてくれた、おやじのおかげです。桂小竹という名前をもらって、うちへ帰っておやじに報告したら、おやじは喜んで、「いい名前をもらったな。小さな竹か。大きな竹にすくすく伸びろと言うんだ。だけど竹には節があるぞ。節がないと雪に折れる、風に負ける。あの節は竹が自分でつけた。節をつけて強く生きていけ。おめでとう。お祝いに明日お赤飯を炊いてやろう」 うそをついた。「うそをつくなよ、人に迷惑をかけるなよ」と言いつづけていたおやじがうそをついた。お赤飯を炊くと言ったって、うちに米がないことは僕が一番知っていますから。当時お米は配給です。配給のお米はすぐに売ります。そのお金でふすまの粉、さつまいも、ジャガイモ、とうもろこしを買ってきて、食い延ばしをするのです。おととい僕が米を売ったばかり。1粒の米もないのに赤飯が炊けるわけがない。おやじは僕を喜ばせたい一心で、つらいうそをついたんだな。 せんべい布団にくるまって寝ました。翌朝、目が覚めたそのとき、いつものお膳の上に小さなお鍋が乗っている。何だろう。ふたを取ってみて驚いた。ぱーっと湯気がたって、おいしそうなにおい。1合そこそこのご飯が炊けていて、それに食紅が落としてある。まごうことなきお赤飯。それはもち米ではありません。小豆も入っていない。おやじは約束を守って、僕に赤飯を炊いて祝ってくれた。「父ちゃん、これはご飯じゃないか。うちに米がなかったろう。どうしたの」「おまえの門出を祝っておれができるのはそのくらいのことだよ。今朝、米屋の前へ行って掃き集めてきたんだよ。きれいに洗ってあるから、心配しないで食え」。この一言が僕の胸に突き刺さった。さんざん、何も知らずに僕は布団にくるまって、ぬくぬく寝ていた。おやじは暗いうちにそっと起き出して、ほうきとちりとりを持って米屋さんの前へ行ったんですね。 今、お米はきれいな袋に入って、1粒もこぼれないようにできています。当時はトラックに米俵を乗せて、米屋さんの前まで運んでくる。この米俵に手かぎを引っかけて、米屋の中に担ぎ込む。その途中で、俵のすき間からこぼれたお米が米屋さんの前に散らばって、コンクリートのすき間にでもはさまっている。おやじはほうきとちりとりを持って、暗い米屋さんの前で、お店の前に散らばっているお米をかき集めてくれたんです。1軒の店だけででは1握り、これだけの米を集めるのに何軒、何時間、どのくらいの道のり、この寒空の下を歩いてくれたのだろう。親ってありがたいものなんだな。胸がいっぱいになる。涙がぽろぽろこぼれて、ご飯が口に届かなかった。おやじは僕の顔をじっと見て、「しっかり食えよ、今朝、スズメの上前をはねてきたんだ。残すとスズメに叱られるよ」 僕はこのときに思いました。おれはこの赤飯にこたえるぞ。おやじの心に報いるぞ。あいつが落語を5つ覚えたと聞いたら、おれは10覚えよう。あいつが10回けいこをしたと聞いたら、おれは20回けいこをしよう。けいこ、けいこと歩みながら寄席に通った。■『おやじが守ってくれた』 我が子を奮い立たせるのは親なんですね。一生懸命楽屋で働いて、わずかのお給金をもらって、これをおやじに渡す。おやじは自分の稼いだ金とあわせて、少しずつですが、長野のおふくろのところに送り続けた。やがておふくろのところから、3畳2間、高さ6尺、小さな家の骨組みを送ってきてくれた。これを大工さんに組み立ててもらって、今日は板を1つ、今日は板を2つ、継ぎ足し継ぎ足ししてやっと一軒のうちができ上がって、前の3畳をお店に直して、おやじとおふくろが一杯飲み屋のまねごとをする。裏の3畳は親子4人、狭いながらも楽しい我が家。 一杯飲み屋と言ったって、3畳のカウンターとお客さんが3人座ったら、もう満員御礼、札止め。ろくな商売ができやしない。ところが、夏、かき氷屋を始めた。これが当ったんです。よしずを張り出して、場所を広げて、長いすを2つ置いて。手回しの機械で。懐かしいですね。今は皆電気でかき回すが、昔は手回しの機械の間に氷を挟んで、そして手で機械を回して氷をかいたんです。ところがこの機械は高くて買えません。苦し紛れに、氷をかくかんなを買ってきて、かんなで氷をかいていたら、あそこの氷は目が荒くておいしいよと評判が立った。人生何が幸いするかわからない。 2キロほど離れたところに製氷会社がある。ここへ行って、6貫目の氷を2枚買って、天幕に包む。背中に座布団をかって、うちまで運ぶ。冷蔵庫を買うお金なんてありませんが、おやじは知恵がある。二重の箱をこしらえて、間にかたくおがくずを詰めた。この箱が冷蔵庫のかわり。たった12貫目の氷です。寄席が終わって、僕がうちに帰ってくるころにはその氷はいつも売り切れている。その箱がからからに乾いているはずなのに、ある。1貫目の氷の塊が2つ残っている。「あれ、なんだよ。父ちゃん、氷が残っているじゃない。どうしたのこれ、売れなかったの」「売れすぎるんだよ。後から後からお客さんが来てくれるのに、氷が売り切れてしまって商売を休んでいるのはもったいないだろう。おれは今日、製氷会社に行って、6貫目の氷を2回運んだよ」 この一言は辛かった。2月の中ごろからおやじの体の具合がおかしくなって、病院へ無理やりつれて行って先生に診てもらった。先生は僕をかげへ呼んで、「お父さんの病気は肝臓ガンです。もう手遅れで手術はできません。無理をさせずに長生きさせてあげなさいね」。そう言われていたおやじが、あの重い氷を担いで2キロの道を行き帰りした。ああ、おやじに苦労をかけたな。そうだ、自転車が欲しいな。自転車があれば一度にたくさん楽に氷が運べる。自転車が欲しい、欲しいと思いながら寄席に帰った。 その自転車が近所の川端に捨ててある。当時は貴重品です。寄席が終わった帰りがけ、新宿マーケットの裏を通ろうとしたら、隅のほうに自転車が1台置いてある。透かしてみると鍵はかかっていないんです。あたりを見ると人影はない。自転車に近づいて、ハンドルを持って、かたんと動かしたらすーっと動いた。僕は思わずひらりとこれにまたがって、自転車泥棒をしたんです。500メートルほど離れたところに京王電車の踏み切りがある。ちょうど電車が通りかかった。目の前に遮断機が下りて、かんかんかんかん、ごーっと電車が通りすぎて行った。ああ、皆1日一生懸命働いて、まじめに我が家へ帰っていく。おれは1日働いて、帰りに人の物を盗んだ。えらい違いだ。返しに行かなければ。 人間の運命というものは30秒、1分で変わるもの、狂うものですね。今思えばあの遮断機がもう30秒後から下りたら、僕は下りかける遮断機の下をすり抜けて逃げていって、一生自転車泥棒の汚名を胸に隠して生きてこなければならなかったはずです。僕は運がいい。遮断機が僕を助けてくれたんです。僕は自転車に乗って、もとの場所に戻っていった。もとの場所には売り込みのおじさんがいて、自転車が盗まれたと大騒ぎしているところで、「おまちどうさまでした」「こらー」と、よってたかって殴られて、僕はそのまま淀橋警察署の留置場のご厄介になりました。翌朝、刑事さんが来て、「自転車の持ち主が、『盗む気があったらそのまま逃げて行った。途中で返してきたのは、一時の出来心。将来ある若者なんでしょう。2度と悪いことをしないようによく叱って、許してやってください』。この一言がなかったら、おまえは網走へ50年は行く運命だった」。そう叱られて、無罪釈放の身となって、うちに帰ることができた。 1晩もうちをあけたことのない僕がうちをあけたんですから、当然おやじは「ゆうべはどうした」。おやじの前でうそはつけない。実は、かくかくしかじか、自転車泥棒をし損なって、淀橋警察署のご厄介になりました。「ばか野郎」、おやじの鉄拳が飛んでくると思ったら、おやじはぐっと手をひざの上に置いて、目をつぶって黙っている。おやじの手がぶるぶると震えたと思ったら、突然涙がぽろっと流れた。おやじのほほを涙が流れ落ちた。おやじは僕の前に手をついて、「おまえにそんな気持ちを持たせたおれが悪かった。勘弁しろ」。おれはおやじに抱きついて、「父ちゃん、僕が悪かった。2度と悪いことをしないから許して」と泣きました。78年間今日まで、どうにか人様に後ろ指を指されずに生きてこられたのは、あのときのおやじの強さ、そして温かさが僕を守ってくれているんだろう。感謝しています。
2004年07月06日
コメント(5)
-
●完売御礼
6/22-7/5の原稿内容を某紙で連載することになったため、ここから削除させていただきました。(2004.07.22記)
2004年06月22日
コメント(11)
-
●勉強会。
面白い勉強会をやった。当日集まった同業36人が、各自5分以内で業務上のお役立ち情報を伝えあうというもの。ジャンルも多岐にわたり、切り口や価値観もさまざま。でもそれでいい。それがいい。たまに宣伝臭の強いやつもいる。でも5分だけ我慢すればいい。だから、気が楽。それに宣伝したいやつも、宣伝の前振りとしてのお役立ち情報を伝えないといけないから、実際の宣伝にはあまり時間を取れない。時間ピッタシを狙うやつ、あまりにも話したいことが多くて、資料だけ渡して資料の見方だけ説明して後は読んどいてというやつ。適当にお茶を濁そうと考えてきたやつ。やっててつらいのは自分の用意したネタが重なった場合。早い者勝ち。今回は、3人が一つの案件に重なった。しかし、さすが。2番目の人は1番目の人の話の裏話をし、3番目の人はそれに関連して、と、別の案件に話を切り替えていった。聞く方もスリリングだった。3時間で、36人が3~5分で話をするという状況。時間がないから結構無駄なく進む。あらかじめ資料を準備した人も大半で、当然消化し切れていない部分がでてくるがそれはそれで後で時間をかけて処理をすればいい。とにかく刺激になった。勉強になった。自分がこれから何をすればいいかを気がつくヒントをもらった。もらったものが多すぎて、まだ咀嚼し切れていない。こういうセミナーもいい。専門家同士が共通のネタの範疇で行う場合、いい。これが一人30分とかになると、無駄や遊びが入ってくる。問題意識の切り口のパターンも少なくなる。36人も発表すれば、誰かしらのネタが参考になる。だれもが何かの得がある。それに、どう見ても5分しか持たないぞという内容の発表でも、ごまかしが聞くから参加するのもそれほどしんどくないというのも、5分間スピーチのメリットか。是非またやってほしいと思った。ちなみに自分は、管理職と部下の効果的なコミュニケーションをとるためのチェックリストと、やる気を出す標語、それと部下指導のパターン化をするヒントを書いてあった本の紹介。一部声が裏返ったりしたが、伝えたいことは、とりあえず伝えられたように思う。その後、懇親会。酒飲みが酒に飲まれる。少しセーブしないとまずい。口が軽くなる。どこで敵を作っているかわからない。自戒しなければ。あと、かならず「自分は出さないが聞くだけは聞いて帰ろう」という身勝手なやつもいる。ちょっと腹が立つのだが、次回は何人いるかチェックしてやろうと思う。2:6:2の法則が成立から、検証してみたい。勉強会のもう一つの獲物は、気分の高揚。高揚というと大げさだが、確かにある。朝出かけて、勉強会をして酒を飲んで、夜、家に帰ってきて机の前に座る。朝よりもするすると仕事に入っていける自分を発見する。ファイトあふれる会合に参加すると、みんなの気合のエネルギーに染められるのかもしれない。気の交流があるのかもしれない。そういえば、つげ義春という暗い漫画家が、水木しげるの家に遊びに行って、彼が去った後に彼の座っていたいすに座ったら、妙に何もする気がしなくなってしまったという話があった。どんよりとした気で染めたのかもしれない。自分の体験だが、あるとき自分がガードレールに腰掛けていたときに、恋人に感じるようなあの独特なわきわきとした雰囲気を感じて、思わず背後をふりかえったら、男女のカップルが通ったすぐあとだった。「???」と思って彼らの背中を見ていたら、小さな入り口からすっとビルにはいっていった。ずいぶん遠慮深いものだと思って看板を見上げたらラブホテルだった。やはり、「気」というものはあるな、と実感した。そういえば、剣豪は殺気を感じることができたというし、宮本武蔵なんぞは、伝説では、自分の殺気を養生するために、関係ない人々、たとえば客間に呼ばれてお茶を出されたとすると、そのお茶を出した人に対して、「もし、今、彼女を一思いに殺すとしたらどこからきりつければいいか」みたいなシミュレーションを延々とやったのだという。あまり友達にはしたくない。昔は大変だったのだろう。ちょっと余談に走ってしまったが、気というのは、確かにあると思う。怒るときには本気で、ただし愛情を持って、という話は良く聞く。その愛情の水準を何で調べるか、この「気」を無意識のうちに推し量って察知しているのかもしれない。だから、「本気」が武器になるのだろう。●余談 名前昨日書いたように、楽天用の名前を変えた。文章を名前が束縛する部分がある。書きたい範疇、書こうという範疇が微妙に変化する。名前というのは、人格を持つということを改めて実感。今の名前は、職業的つっぱりは不用だし、きれいごとを言わなくてもいい、本音を語れる。それが気に入っている。書きたい文章の発想の思考回路も、名前を変えるとかわってくるようだ。まるで、その名前の人格が自分の中に潜んでいるかのように。ちょっと不思議な感じがする。
2004年06月21日
コメント(6)
-
きょうからは「ひであき」
●楽天日記のアクセスを増やす方法2週間近く日記を書いて、気がついた。アクセス数の多いのは、楽天を話題にした場合。共通項のない、ばらばら人間の集合体としては、唯一の共通項かもしれない。だから当然かも。たまたま楽天のネタをふったのは、初日と昨日の2日だけだったのだが,アクセスが100を超えたのもその二日だけというのはどういうわけだろう。まいった。楽天のネタを振らないと、読んでもらえないということだ。俺の日記が下手くそだからか。魅力がないからか。そうだ。うーんダブルまいった。要するにもっと精進しろということだ。気づかせてくれた楽天日記に、感謝しかない。でも、こんな感謝なら、できればしないですませたい。でも、栢野さんならこんな場合、するんだろうな、感謝。とにかく、アクセスを増やすために楽天の話題をこじつけて進展させてもしょうがない。つまらない。意味がない。そもそもそんなつもりではじめたわけじゃない。さて、では自分の初心とはなんだったのか。●商売の場から修行の場へ楽天日記を始めたとき(12日前)は、商売の下ごしらえとして使えればいいかなとおもっていた。そういう下心から、「コンサルひで」というペンネームではじめた。しかし、どうも勝手が違う。微妙な違和感の原因を探った。栢野さんのページも見た。じっと見た。ずっと見た。考えた。やがて気がつく。そうか、修行の場だ。楽天日記は。丸裸さらけ出しで自分をたたきなおして強くなる。そういう場だ。それが自分にとっての楽天だ。ここで有名になっても、忙しい中小企業の社長はみていない。お客さんがいるわけじゃない。でも、すごい人はわんさといる。変な人もいるが、まあ世の中だ。無名の実力コンサルタントもわんさといる。個人事業主も多い。社員のいない会社の社長だ。そのかわり、ゆめがある。熱い。めちゃめちゃ熱い。このパワーが楽天日記の魅力の一つだ。こうしておれは「コンサルひで」から本名の「西宮英昭」にかわった。●修行の場から遊びの場へしかし、相変わらず違和感は続く。どうも、浮いているのだ。自分ひとりが実名で、無用に肩肘を張っているように見える。場の空気を壊している?ふとそう感じた。身分を隠す必要はないが露出する必要もない。プロフィールに本名を書いておき、日記の交流ではいつものペンネームを使えばいいじゃないか。突然そういうことに気がついた。ここは、遊びの場なんだ。知的交流を楽しむ場なんだ。遅まきながら気がついた。楽天日記のすばらしい点、それは訪問のお互いの足跡がわかる点。お互いの日記を紹介したり、コメントしたり、自分のところで書いたりできる点。要するに、自由に言語コミュニケーションができる点。しやすいように環境が整備されている点。それならば、その環境を利用しないてはないじゃないか。そのためには、名前はペンネームに変える。交流を図る。どんどん自由に書いていく、自然にどんどんやっていけばいいのだ。どうも、久しぶりの超メディア登場ということで、びびった裏返しのツッパリで、対応が過剰になっていたようだ。自然体、自然体。自然体が一番だ。ということで、きょうから「コンサルひで」である「西宮英昭」は、「ひであき」になります。どうぞよろしく。
2004年06月20日
コメント(6)
-
●評価と報酬
●ずるい楽天日記楽天日記は、ずるい。それとも俺が馬鹿なのか。まあ、多分馬鹿なんだろう。何がって、楽天日記のカウンター。最初はぜんぜん気にしてなかった。ところがキリ番ごとにメールがくる。キリ番はだれですよ、次は○○番でお知らせしますよ、って、何回もいわれているうちに意識するようになり、気がつくと、「あと何人でキリ番だ」とか、「次のキリ番まであと何人だろう、くそなかなか増えないなあ」など。楽天マジックにはまってしまっていて、完全に馬鹿状態の、俺。●魅力に100倍の差?そのうちこんどは周囲が気になる「え?ボッキーさんとか、トップの人は、7千とか8千とか言う数字だって?1日のカウンターの数字?ありえない、うそだろう」何しろ1日のアクセスが100いかない自分。ちょろっと調べてみると、1分間に6人の訪問数。うう、単純計算で8千人を超えてしまう。確かにうそではない。すごい。めちゃくちゃすごい。おれより100倍も集客(?)してる。いったいこれは何なんだろう。HPを比較しても、もちろん面白かったり役に立ったりということはあるのだが、100倍以上も魅力が違うとは思えない。うーんなんなんだ。・・・なるほど、これが情報化社会におけるトップ総取りの現象なのか。妙に納得。いや、納得している場合ではない。せっかく書くのだから少しは注目されたい。誰にも読んでもらえないのはさすがに寂しい。さて、どうしようか。●道を外れる・・・こうして、本来中身を充実させるつもり、当初の目標の中小企業の社長さんだけに将来読んでもらえればいいコンテンツを作るつもり、的な加入時のイメージが、どんどんゆがんでくる。いつのまにかカウンターアップ目当ての企画を考えてしまいそうな自分がいる。いけない、そんなことではいけない。そう気を引き締めてミーハーな自分を押さえつけようとしているはずが、次第に逆転。まさに、ミイラ取りのミイラ。本末転倒、まずいだろう、自分。それにしても●認知という報酬この、楽天日記のカウンターシステムは、うまい。メールフォローも考え抜かれてる、いいシステムだ。結果が本人にフィードバックされることにより、ようしもっとがんばってやろう、という気持ちにさせられる。これって、動機付けの報酬としては非常に、うまい。企業においてもいえることだが、金銭だけが報酬ではない。認知されること、ほめられること期待されること。これらはすべて報酬である、というか、こちらの要素のほうが飽食の時代には、報酬としての価値が実は高い。この事実を盲点としているから、各種の人事評価制度がうまく回っていないのだ。●リアルタイムの報酬よーく考えよう~、お金は大事だよ~・・確かにそうだが、人はパンのみにて生きているわけではないのも事実。心の糧が大事なのだ。そしてその心の糧はリアルタイムであることが重要。後日集計を取って、あのときのご褒美ですといわれたって、感激は小さい。半年後に賞与金額でフィードバックされたって何それっ?てのがもらう側の本音。まあせっかくくれるんだから、もらっておこう。これでは会社は賞与のどぶ捨てに近い。動物でも、調教をうまくいかせるには、ご褒美としてのえさのやるタイミングが重要。人間だって動物なのだ。●楽天マジックの正体「認知という報酬」と「リアルタイムの賞罰」、これが動機付けの要因として非常に有効。そして、楽天日記のカウンターシステムは、まさにこれを体現している。金をかけずに、ランキングの発表や、メールによるカウンターお知らせシステムの運用によって、強い動機付けを参加者に与え続けている。現実に、延べ数で何人訪問したかということがリアルタイムでわかるということ、その情報自身が、受け止める側にとって、賞であり罰になる。注目されるとうれしいし、無視されると寂しい。このシンプルで根深いところをうまくくすぐっている。人数が多ければ、そして上位ベスト10とか何とかに名前が載ったら、誰しも人情で、もっと続けたいと思うだろう。名誉という、あるいは認知されたという報酬。だから何?って言われればそれまでなのだが、でも、すごい。実際には、人数が超がつくほど集まるようになれば、さまざまなビジネスのもとになる可能性がある。セミナーの集客にも有効だ。典型は栢野さん。彼はまさに楽天日記の大スター。そしてボッキー米谷さん。正直、楽天日記を始めるまで、ボッキーさんの事をぜんぜん知らなかった。●感想楽天日記が繁盛しているのは、上記に見られるように参加者の動機付けがうまいということ。もちろん、操作のしやすさや、足跡追跡のしやすさというのもそのフォローシステムとしてあげておかなければいけない。これもまた重要なアイテム。それにしても、人間心理をくすぐったうまいシステムだなあと、そしてそれにまんまとうかうかと乗せられている俺は馬鹿だなあと、ここ2週間弱ほどやってみて、非常に実感したことでありました。
2004年06月19日
コメント(4)
-
●目標管理の盲点と、その克服法-2
昨日の続きです。今回も、目標管理の盲点と、その克服法についてお話します。●復習昨日もお話ししたように、健康を強く維持するためのポイントは睡眠・運動以外では1 断食2 生食・全体食3 身体の力学的なひずみを治す4 呼吸をコントロールして、心身のバランスをとる5 摂取の質、量、時間帯に気を配るといわれています。今回は2以下について述べます●縄文食の勧め昨日も述べましたように、長い間の体を支えてきた伝統を生かす、これが健康の秘訣であると。日本人の場合、縄文食が健康の秘訣になります。今は亡きニュートンの編集長で東大の元物理学者(名前失念)の、紹介した健康法でもありました。縄文食がいいのだそうです。縄文食というと、玄米、小魚、木の実、海藻類です。これを海水天然塩を使って調理する。これが体にいいのだそうです。実際に、試してみると、成人病予防として非常に有効とされているアイテムのようです。●全体食の勧め次にお勧めなのが、全体食。昔はきっと食料不足のため、全部食べていたのでしょう。というのは、全体食をすると、体の栄養バランスが良くなることが多いからです。これも、縄文の太古からの大自然との関係が体に刻まれている証拠と見ていいでしょう。全体食。たとえばにがうりのゴーヤだったら、種も食べます。あれは意外とおいしい。ごま油に塩をひとつまみ入れて、それで炒めて食する。単に炒って塩を一振りという人もいます。いずれにしろおいしいというのが結論。体にもいい。たとえば大根。葉と皮と実をそれぞれ違った調理をします。実は通常の使い方。皮は、一口大に切って酢醤油につけて食べるとおいしい漬物になります。浅漬け。葉は、茎のところをみじん切りにして、そばつゆとおろししょうが(チューブのでOK)であえて食べます。さわやか系の風味が絶妙。全体食は体にOKですので。ゴミを出さないですむので、地球にも優しいし、無駄な部分がなくなるので、財布にもやさしい。いろいろな意味で、お勧めです。●お勧めの食べ物を一つ煮干と、だし昆布を一口大に切ったものを玄米黒酢につけておきます。これ、縄文食。全体食。おいしいです。いくらでもいけます。栄養価もヘルシーです。簡単です。安いです。お勧めです。あと単独で松の実もつまむとおいしい。ちょっと体調に優れないなあと感じ始めたらぜひお試しください。下手なさぷりや薬よりよほどいいです。医食同源です。昆布も煮干もだしをとる本体ですから、いい味出します。しかも両方とも酢でやわらかくなってるので、うまい。残った酢のエキスには、昆布と煮干のだしがいっぱいはいってるのでこれまたうまい。久々のヒットであります。●本当の贅沢食べ物の、そのおいしさを最大に引き出す、無駄な部分をできるだけなくす、活用して食べるという行為は、愛であり、社員に無駄な存在はないという、「労務管理の心」に通じるものがあると思います。全体食をできるということは、叡智を活用して日常を密度濃く生きる、味わいつくすことが食の部分でできているという意味で、本当の贅沢です。●体のゆがみを直すさて、話は変わって。。整体というのがあります。自分もやってもらったことがありますが、体が自由になったような気になります。人によってはかなりの効果が見込めると思います。日ごろ運動不足の人など、体のコリから血行不良になり、諸病状の温床になります。脳梗塞や心筋梗塞など、血のめぐりの悪さが原因で大きな病気になりますので、予防の意味でも必要です。病気にかかったときのための保険にかかるより、その金で、病気にかからないように、体に保険をかけるほうが、日ごろの気分もいいはずです。血の巡りを良くするカイロプラクティスは、体の骨をぼきぼきと痛くするのではないかと言う不安もありますが、そういう方は、痛くしない操体というものがあるようです。ここなんかいかがでしょう→操体の某癒養院、施術風景なんかいかがでしょう。新小岩ですが、訪問型なので、遠方の方も便利です。セルフアフターフォローのレクチャーも受けられるので、何回も通わなくても良くて経済的。・・・なんか宣伝ぽいな(笑)。実は、楽天日記上で知り合った方です。この方の考え方(=年を取ることが楽しみにできる日本にしたい)に共鳴したので、少し応援したいと思い、本人にナイショで告知してます。心の背骨がしゃんとしてる方なので、きっといい仕事をされる方でしょう。●呼吸をコントロールするこれについては、研究中ですので(というか実績としての、これだ!という実感がまだ、経験不足により、ないため)コメントを控えます。●摂取の量・質・時間帯寝る前は食べない、量は控えめに、質は縄文食で。はい、なかなか実行できてません。ついたべすぎで反省毎日です。これは自分の目標だな・・・・●結論健康は、公私の宝。今日は、以上です。
2004年06月18日
コメント(7)
-
●目標管理の盲点と、その克服法
今回は、目標管理の盲点と、その克服法についてお話します。●目標管理の盲点目標管理の盲点、それは健康管理です。普段、特に若い人があまり意識していないことですが、重要なことです。長い目で見ると、皮肉なことですが、この点、バランスが取れてるようです。つまり、無理して働きづめの人は、重い病気がきっちりと休養を与えてくれるのです。俺は強いんだとばかりに突っ走って何ヶ月も病床に伏せるパターンは、良く見てきました。労働時間の問題だけではありません、運動や食事なども重要なメンテンスアイテムです。これを意識して工夫する必要が、あります。体の調子がいいときと悪いときとでは、同じ努力をしても達成度合いや勢いのつき方が違うからです。●睡眠時間以外のお話し健康管理というと、睡眠時間や時間帯などが重要ですが、今回は触れません。今回は、そのほかについて述べます。健康を強く維持するためのポイントは、睡眠・運動以外では1 断食2 生食・全体食3 身体の力学的なひずみを治す4 呼吸をコントロールして、心身のバランスをとる5 摂取の質、量、時間帯に気を配るといわれています。今回は断食について述べます●断食の論拠たとえば足の裏、昔は当然裸足で駆け巡っていたわけで、大小の石等が常に足の裏を刺激していた。これを体は取り入れて、足のつぼとして現在に至る。つまり、長期にわたる大自然の環境との関係を体のメカニズムに取り入れてきてるのが人間(に限らず生物)の姿です。、人間の何万年単位での長い間の歴史に思いをはせると、食料の確保が積年の夢であり、目標であったと思われます。言い換えると、食料がなくなりかけるということは、日常良くあったことであるはずです。ということは、断食は体のリセットとして有効に働きかけるアイテムになっている思われます。実際、断食を1週間ほどする、何かしらの気づきがあるようです。●断食の効果自分は今までに1週間級の断食を2回やりました。独学でなので危険を意識しながらですが、無事にこなしました。そしてそれぞれからだの発する声を聞くことができたように思います。1回目の断食では、断食前はコーヒー好きだったのが、アフターでは緑茶好きになりました。2回目の断食では、風呂に微少塩分を入れると気持ちいいということを発見しました。これは風呂がまへの影響を恐れてすぐにやめてしまいましたが。断食をすると、その直後、肉体の健康状態について敏感になるという効果があるようです。●断食の注意実際に断食をする前に、ご注意。事前に1週間、本番1週間、事後に1週間の準備が必要です。事前はそばなどを食べる。量も徐々に減らしていく。事後は、おもゆなど、栄養の薄い負荷の小さいものから段々に体を慣らしていく。この調節が個人の意志では難しいので、道場に通うのが一般的なのでしょう。それと、危ないと思ったら、やめる勇気を持つことも重要でしょう。●体験と伝聞の違いものの本によると、断食中ものすごい歓喜があったり、体の悪いところが痛み出すなどの諸症状が出るようなことがかかれてましたが、そんなことはありませんでした。ただ、断食中に食料のにおいをかいだときに胃袋がぎゅっとあばれたのはびっくりしました。それと、断食を終えて最初の食事で、たまたまトーストパンバターツキを一口食べたら、心臓が、「激しい運動をした直後」のような動き方、すなわち「とくとくとくとくとくとくとくとく」と、ものすごい勢いでビートしだし、赤血球が全力で油を中心とした栄養分を全身に配達するべく走り回っていたのを覚えています。すごく怖かった。だって、運動もせず、息切れもせずに心臓が猛烈なスピードで動くという経験は生まれて初めてで、今のところそのときだけでしたから。どうやら「事後は、おもゆなど、栄養の薄い負荷の小さいものから段々に体を慣らす」のは鉄則のようです。明日は、断食以外のモノについて述べます。
2004年06月17日
コメント(4)
-
簡単で便利な問題解決の発想法
●ステップ1:ゴールを決めるなんでもいいから、自分の達成したい目標をできれば具体的に1つだけ設定します。何でもいいです。3年後の経常利益は何億円みたいなものでもいいし、友達100人できるかなでもいいです。とにかく最終ゴールを1つ決めてください。●ステップ2:そのためには?を自問するつぎに、その最終ゴールを達成するためには何が必要か。必要な要素を最大で8つ書いてください。できれば具体的に。●ステップ3:そのためには?×2を自問するつぎに、その必要な要素最大8つ達成するためにはそれぞれ何が必要か。必要な要素を合計最大で64書いてください。できれば具体的に。●ステップ4:そのためには?×3、×4、×5を自問する同様にそのためには・・・と、これまでと同様に×5までやってください。・・・実は、項目の中には膨らまないものもありますので、完璧には埋まらないはずです。それでかまわないものとしてください。できれば、あらかじめ時間を決めて書き始めるとゲームっぽくていいです。緊張感と集中力で結構かけます。それなりに項目数は出てくるはずですから、それでよしとしてください。完ぺき主義になる必要はありません。また、無理だし無意味です。ある程度かけて、この程度でいいだろうと実感できたらそれでOKです。8項目というのは、するすると出せる項目の限界で、×5というのは、ほぼこのあたりが出尽くしとなるからです。もちろんそれ以上増えてもかまいません、ここの目的は、アイデアを具体化してどんどん出すということです。・ステップ2~4のヒントエクセルを使うと便利です。あとで並べ替えたり抽出するときに便利ですテキストファイル&タブでもまあ役に立ちます1項目は1行で書き込みますアイデアを出すことが目的なので、少々ヘンな内容でもかまいません。・実例のイメージ例テーマ:友達100人作りたい____いろいろなところに顔を出す________習い事をする________ボーイスカウトに入る________奉仕活動をする________アルバイトをする____友達に紹介してもらう________ともだちとコミュニケーションを密にする____________ともだちの誕生日をDB化しておく____________お誕生会を開く ____________電話で連絡を取り合う____________メールを出す________________メールを出すためのイベントを仕掛けておく____家族親戚に紹介してもらう________お願いする________盆暮れに顔を売りに行く____先生に紹介してもらう____HPを使う________親しみやすいHPを作る________こまめにHPを変更する「そのためにどうするか」の問いの答えになるたびに、実際にはタブで段下げをしていきます。●ステップ5ひととおり、アイデアを出るだけ出すと、具体的にいつまでに何をしなくてはいけないか、茫漠と見えてきます。結構忙しいことがわかる。今度は、非現実的な案を排除して、よさそうなものから優先順位と納期をつけていきます。方法が茫漠としていたら、たとえばこうするという方法を付け加えます。ステップ5のヒント時間軸的には、遊びやゆとりを盛り込んでおきます。特に、自分との約束や家族との約束をきちんと盛り込んでおきましょう。それと、中間計画を立てる時間帯も加味しておく必要があります。目標にかかわる時間の目安は、全体の1/10~1/20くらいは必要でしょう。たとえば、1日単位の計画に30分、1週間単位の計画に3時間、1ヶ月単位に半日。年間計画に1週間、という感じです。そのぐらいは時間をかけても、その後のスムースさを考えると、必要経費な時間です。ステップ5のヒント2上記の作業を、みんなでわいがやしながら行うと、きっと文殊の知恵が生まれるでしょう。会社でやる場合には、一人がパソコンで書記をやり、それをプロジェクターで壁に映し出しながらワイがやします。テキストファイルとタブで、どんどん作っていく事が簡単にできます。黒板に描くと、間に入れたりするのが結構大変です。出来上がりも汚いので清書が必要になります。
2004年06月16日
コメント(2)
-
年金雑感
●貧乏人の子沢山年金問題の要因である「少子化」だが、世界の古今東西の歴史レベルで見ると、豊かさの証拠でもあるので、その意味では喜ばしいことだと思う。だいたい子沢山なのは貧乏国。将来への不安が子沢山になるのだろう。あるいは、生活のストレスが性欲につながって子沢山になるのかも。●制度を変えよう豊かで平和だと少子化が進むのならば、少子化で年金制度が行き詰って困るという問題は、むしろ慶賀するべき。よかった、よかった。豊かになった日本、おめでとう。こう歓迎するのが筋だろう。では制度の行き詰まりにはどう落とし前をつけるか?答え。制度を変えればいい。制度によって、世の中や生き物の生理が決まるのではなく、世の中の実態を損なわないように設計運用するのがあるべき姿。少子化だから子作り環境を整備しろってのは、官僚の傲慢。大自然の法則より、自分たちの設計図のほうが正しいのだと言ってる。●年金は国が胴元のねずみ講制度はどう見ても破綻している。世代間扶養という美しい建前の制度も、作られたのは人口構図がピラミッドの成立した時代。無限に底辺が広がるわけもない。だいたいにして前提がおかしい。未来永劫ピラミッド人口の前提で、官僚が何兆円も中抜きで食い散らかしているとなると、まるで国が胴元の世代間ねずみ講。こんな制度はいつかは破綻する。小手先の改造は破綻の先送り。国民年金を半分近くが支払っていないのは、すでにこのインチキ性を見破られているから。みんなが見破って誰も支払わないと、さらに破綻のエックスデイは前倒しになる。いや、すでに通り過ぎたのかも。●「官僚は間違わない」という考えが間違い結局、消費税のような形での収まりにしないとどうしようもない。その段階で、世代間扶養という建前は消し飛んでしまうが、それで失うものは官僚の面子だけ。そんなものはいくらでもはさんですてればいいのだが、なぜか国は(というか官僚は)すべての優先順位のいの一番に、これ(=官僚の面子を守ること)をもってくる。官僚は間違った判断をしない、という大前提のルールをそろそろ見直すときがきている。間違わないことが大事なのではなく、間違いに気がついたら直ちにこれを修正することが大事。ここを誤るとスリータイヤ自動車の経営者ような醜態をさらすことになる。●年金を話題にするときのご注意全国民が参加できるテーマではあるが、家庭で語るのは少々疑問だったりする。というのは、親子の立場が違えば利害関係が対立するから、真剣に話し合うと険悪な雰囲気になる可能性がある。この点少々注意が必要かもしれない。
2004年06月15日
コメント(2)
-
実用 目標設定5 「無意識」の落とし穴
●皮肉な体験個人で長期目標をもつということについて、ちょっと皮肉な経験があります。●非現実的な5ヵ年計画会社に入って10年近くたったある日、引越しのために物品の大整理をしていたら、ノートが出てきました。そのノートについては、すっかり忘れてしまっていたのですが、新入社員として入社した当時、無邪気に立てた5カ年計画でした。といっても内容はたった1ページ、しかも大きく数行しか書いていないという、たわいのないもので、「1年目200万円、2年目2千万円、3年目2億円、4年目20億円、5年目200億円」と毎年10倍に増やしていくだけの単純な、会社で達成したい売上の数字のなぐりがきでした。最初の数字が200万円なのは、1年目の当時、任された市場の過去の実績の平均が年間で200万円だったためです。6年目2000億円としなかったのは、さすがに非現実的すぎる(その会社の当時の売上を超えてしまう)と思ったためでした。冷静に考えれば、そもそもこの3年目以降の目標自体が非現実的なんですが。。。。ノートは最初の1ページにそれが大きく書かれており、あとは白紙のままダンボールの底に眠ってしまったものです。きっと、生まれてはじめて営業マンとしてテリトリーを任されたうれしさに、衝動的に思いつくまま目標を書いてはみたものの、自分もその非現実的な内容にあきれ、ダンボールに放り込んでしまって、そのままになってしまったものだったのでしょう。そのうちそれを書いたということ自身も忘れてしまいました。●皮肉な形で倍以上に達成されてしまったで、実績はどうだったか。「1年目500万円、2年目5千万円、3年目ほぼ5億円、4年目数十億円、5年目数百億」でした。思い出してぞっとしました。非現実的な目標を、倍以上でクリアしてしまっていたという事実に気がついたのです。ただし、この数字には、ちょっと説明が必要ですす。1年目は新人なので、売れない市場をあてがわれます。営業の練習をつみなさいということで。2年目から本当の仕事でした。3年目に、会社の事情で組織の組み換えがあり、市場単位で動いていたある仕事が、政策というか会社の管理の都合上、名目だけ自分のテリトリーとして管理することになり、名目的に自分の売上として管理することになりました。つまり、自分の労力や能力とは無関係。要するに、数字だけが自分のもので、その業務への実際にはまったくノータッチ、ということです。ルートセールスで、売上と成績はぜんぜん連動しませんので、こういうことが通常に簡単に行われていたのです。実力とは無関係の、あてがわれた数字です。4年目に、それまでの営業を離れて、商品企画部に異動になりました。で、既存機種の改善を担当したのですが、その機種の合計売上が数十億単位。次の年には全社の機種に絡んできてその総計は、数百億円。。。。もちろんこんな数値に営業マンとしての意味は、すでにぜんぜんありません。そして、6年目、関連会社に異動し、そこでは売上と関係のない人事の仕事をすることになったのです。つまり、目標を立てた5年間は、皮肉な形で「達成」され、目標をたてるのをやめたつもりの6年目が、ゼロ目標を立てたものとして、ゼロとして達成されていたのでした。自分の意思とは無関係で決まったはずの異動辞令は、実はこのノートが招いた、つまり自分がノートに殴り書きしたときの、その瞬間の行為の結果が招いた、いわば自己責任だったのではないか。理論理屈では説明のつかないこの事実に呆然とし、ぞっとしました。ノートを眺めながら、何か見てはいけない、この世のものではない、自分の運命を決めた恐ろしいものを見るような、不思議な気持ちでした。●深層意識のメカニズム実は、ものの本を読むと、こういうことは珍しくないようです。というか、深層意識というのはどうも、とんでもないパワーを秘めている。と同時にとんでもない形での実現をやらかしてくれる。(たとえば今回の例のように)。かなり非現実的な目標でも実現してくれる代わりに、どのような形で実現するかはわからない。必ずしもこちらの期待するようなストーリーとしては実現しない。さらには、その実現により、念じた本人が幸福になるか不幸になるかなんてことはぜんぜん頓着しない。こういう性質が深層意識のパワーにはあるとされています。こうしてみると、無意識を制御するというのは、簡単ではないようです。●別のケース実は、もう一回皮肉な目にあっています。在職中「自由がほしい、年収2千万円ほしい」が夢であり、目標でした。2000万円とは、当事社長の収入がそのくらいだと聞いていたので、じゃあ俺も同じだけ、と無邪気に考えたのです。で、在職中に社労士試験に合格したのですが、開業したらどういう仕事をいくらでできるのかなと、調べて、あっと驚いた。「相談業務・30分5千円」というのが社労士会で報酬として定められていたのですが、これをみて、あっと驚いたのです。当時、年間の労働は、残業も含めて2000時間が常識的でした。もし仮に年間2千時間を相談業務とすると、年収額で2千万円になります。つまり、社労士試験に合格することで、名目だけは「年収2千万円を達成」したことになってしまったわけです。もちろんこんなもの、机上の空論で、何の役にも、腹の足しにもなりゃしません。こんな達成のされ方かよ。ずいぶん皮肉だなあと、そりゃあないだろうと、苦笑いでした。ビジョン達成へむけての意識的努力をすることなく無意識にとどめておくと、まっとうな状態では達成できないと深層意識が判断し、それでも律儀にも達成しようとする結果、こじつけでヘンなものを引っ張ってくるのかもしれません。ですから、長期のビジョンを立てるときは、飛躍しててもいいけれども、そこからだんだん具体的にブレイクダウンできるものはブレイクダウンしていき、目標を常に見続け、見直し続ける。思いついた発想をどんどんメモする。実行できるものから実行していく。こういう一連の作業がどうしても必要なようです。これを書いたのを期に、初心にもどって、もう一度自分も長期ビジョンを立て直してみようと思った次第です。
2004年06月14日
コメント(3)
-
実用 目標設定4 長期ビジョンを持つ
●非現実的?10年後20年後の長期の計画を持ちましょう、先日、こういう話を社長さんにしましたら、そんなバカな事を考えてどうする、せいぜい3年後だろう。要するにそんな先の世間動向わからないし分析できないししても無意味だし、そんな無意味な状況予測の元で目標を立てたってしょうがない、膨大な作業が無駄に終わる。というようなことを言われてしまいました。●暗夜の一灯そこで自分がお話ししたのは、予測ができないからこそラッキーであり、長期の計画を立てるチャンスだと。予測がつくのなら、その範囲に縛られる。しかし予測がつかないということは、何をイメージしてもいいということ、自由に未来のビジョンデッサンを書くことができる。細かい内容はもちろん必要はない。必要なのは、経営の意思、社長のやるぞという気持ちの確定。そこからすべてが生まれる。と、まあそういうお話です。こんな話があります。真夜中、道に迷ったときに、行き着くべきゴールは暗夜の灯台のように一点光ってる場所があってそこを目指していった。行き止まり道に回り道。紆余曲折あったが、どうにかこうにかたどりついた。たどりついて振り返ってみると、意外と一直線に近い道を来ていた。本来の本当の道を知っていたら取ってこなかったろうあぜ道なども通っていた。結局本当の道ならこうだったというゴールとは違ってはいたものの、その道と比較してそれほど遜色のない新しいルーを通ってきていた。でも、それはあらかじめ知っていたら避けていたような危険な道も含まれていた。最終ゴールの一点、暗夜の一灯を脳裏に叩き込んでおくと、結果から振り返って意外とまっとうな道筋を得ることができる、こういう教訓です。この話は、「以前こんな出来事があった」的な雑誌上の雑談の取りとめもない一エピソードですが、目標設定とは何かを考えるたびに、非常に比ゆ的示唆的な話として自分の中で反芻され、いつの間にか深く印象に残るようになった話です。理屈でではなく、そういうものだという実感があるのです。●実例長期目標を持ち、それが人生やビジネスにいい影響を与える実例として、たとえば若くして日本IBMの常務になり、コンサルタントに転進した井上富雄氏とか最近では「一冊の手帳で夢は必ずかなう」の熊谷正寿氏などが有名です。井上氏はこの方面(=超長期目標を掲げましょうという啓蒙を本で個人に対して行った人という意味)でのパイオニア。人生25年計画、熊谷氏は15年計画を立ててどんどん実践していき、実績をあげている人です。企業でも、終戦直後の廃墟闇市だらけの時代にぶちあげたワコールの50年計画とか、戦前の松下幸之助氏の250年計画など。ラフでどーんと長期のゴールを示すことにより、自らを鼓舞し、グレードを上げ続けていくというのが目的です。実際、内容はおおざっぱです。というか細かくしても無駄に終わるわけで。たとえば国内のシェアを席巻する、海外進出する、海外シェアを席巻するということを10年単位での目標としておいてある。とにかく暗夜の一灯をともすことが重要です。●メカニズムたとえば10年後こうなっていたい、という長期ビジョンをぽんとワンフレーズおいたとします。すると「それを実現するためには何が必要か」ということを反芻するようになり、そのたびにブレイクダウンしたより具体的な目標を思いつくようになります。最初にビジョンがないと、出てこなかったであろう、このいろいろなアイデア。これがどんどん出てくるのが、たとえ非現実的であると揶揄されようとも長期ビジョンを持ち続けるメリットです。出てきたさまざまなアイデアを多く細かく具体的にしていき、一つ一つ実行していくと、いつの間にかゴールに引き寄せられている、その際に代替案や優先順位も、最終ゴール実現にふさわしいかどうかのチェックを受けるので、その行動についての回り道、無駄の可能性が、ビジョンを持たなかったときよりも小さくなります。●留意点実はその長期目標をとりあえず立てるということがなかなか難しい。茫漠としているし、仮に決めてもそれが本当に必要なのかとなると、切実感がない。この辺が難しいところです。しかしやはり、目標をたててみて、どうも違うなと思ったら考え直すにしても、とりあえず立ててみるのが、いいでしょう。うまくいかなくてもそれは「この方法ではダメだった」という調査だった程度に思って軽く受け流すことにして。何もしなければ何も始まりませんから。失敗は成功への一里塚ですから。それと、どんどん実行していくこと。社長さんのなかにも「アイデアは無限にある」という方はいらっしゃいます。しかし、人・金・時間、経営資源は限られています。何をしないであきらめるか、何からするか、何だけはしなくてはならないか。これをえいやあと決めて、やるべきことをどんどんやっていく。実行した計画は「計画」ですが、実行しなかった計画は「妄想」であり時間の無駄だからです。これは自戒の意味が強いです。はい。
2004年06月13日
コメント(3)
-
実用 目標設定3 (器を作る)
●書き出すメリットとはすべきことを書き出す大きなメリットのひとつは、茫漠たる不安や焦燥感から開放されることです。昨日も話しましたが、手書きでやると、自分の無意識への架け橋が強くなるため、実行実現のストレスが小さくなります。言い換えると目標達成の可能性が強くなります。●グルーピング化するさて、思いつきを書いた100枚の付箋。これをグルーピング化しましょうというところまで、昨日お話ししました。いわばKJ法でまとめましょうということですが、KJ法といっても深く考える必要はないし、難しく考える必要もない。要はどんどんアイデアを出し、類似をまとめ、茫漠としていた真実の自分の意思を明確に視覚化する、というだけのことです。どういうまとまりになればいいという結論があらかじめ見えていないのでこの場合有効です。今回の作業の目的には真実の自分探しの意味があるので、この手法をとりました。ここからいくつかのことが見えてきます。●ダブった付箋が意味するものまず、書いた内容で、同じ事を違う表現で書いてある複数の付箋があるはずです。これは、そのことを無意識のうちに自分が強く意識していることのボリューム化で、実行の優先順位をあげる価値があることを示しています。これが、仮に母集団が次20枚や30枚程度だと、そのときにたまたま勢いで連続して思いついたいくつかの項目が「これが俺にとっての重要項目なんだ」と勘違いしてしまう可能性が強いので、最低でも100枚は、ほしいといったわけです。また、これがたとえば1000枚になってしまってからこの作業をしようとすると、今度はその作業の煩雑さのために、作業が完了できない恐れがあります。多すぎず、少なすぎずの過不足ない数字の最低が100枚です。●現時点での自分の本質にフィットするグループの明示さて、実際に分類すると、多くのグルーピング、小さなグループがでてきます。それぞれのユニットに、テーマをつけます。これが、当面の自分の戦場を示唆しています。自分もこれを書くにあたって改めてやってみたのですが、現状の自分は「取り掛かり中の仕事」「情報の仕入れ(学習)」「人脈」「ツールの作成」「目標の設定」「生活のリズム」「趣味」「環境整備(掃除)」「IT」「終了事項」でした。実は、これが器です。器の内容は人によりさまざまです。計画立案の本などを見ると、6~10項目ぐらいを決めうちで書かれてることが多いです。たとえば「仕事・健康・家庭・趣味・金・人脈・心の安定」などです。最初からそれに入れていってもいいのですが、上記にやるグルーピングから入っていくほうが自分によりフィットした計画を立てることができます。よそゆきでない、借り物でない、自分だけのもの、無意識の自分が必要としている達成目標にぴったりフィットの、自分だけの目標設定、です。服でいえばオーダーメイド。既製品でないので、多少コスト(手間)がかかります。今度は、このグループの相互関係をチェックします。そして、今の自分にとっての重点優先項目グループを確認します。●いつごろやるかを決めるこれらの自分自身の欲望(目標)を視覚化した段階で、各テーマを時系列に整理しなおします。時系列といっても、緊急性の強いものは最初に除外していますので、ここに残ってるのは「抽象的なもの」か「いつまでにやらねばいけないというものではない」ものが残っているはずです。いったん付箋にして出てくるのを見ると、結構やることが多いようであいまい抽象的なとらえ方をしていることに気がつきます。それはそれでかまいません。この残っているものをみて、表現を具体化できそうな場合には、具体化しなおします。そしていつごろやろうかなという意思決めをします。●「重要」と「緊急」ここでちょっと余談。というか理解促進のために「重要と緊急」についてお話します。ご承知のように、目標・予定には4つの事象があります。「重要・緊急」「重要」「緊急」「重要でも緊急でもない」の4つ。このうち、「重要・緊急」「緊急」は、作業の最初に除外しているはずです。ですからここに残ってるのは、「重要」「重要でも緊急でもない」ですが、「重要でも緊急でもない」ものは、この際どうでもいい。無視します。すると、残ってる付箋リストは「緊急ではないが重要」なものになります。実は、これを処理するのが非常に、重要です。繰り返しますが重要です。本当に、重要です。計画のへそといってもいい。いつやってもいいと自覚しているものは、つい後回しになりがちです。しかし、実はそういうものが一番重要です。●ここで理解促進のために、質問を2つ。質問その1「緊急」と「重要」の二者択一、どっちを優先して処理しますか?正解は「重要」です。ここが小さな盲点。ここを押さえておかないと、忙しいのに成果が上がらないということになります。これは意外と正しい時間配分ができていない企業が多いです。少しでも多くのことをやろうとして、肝心なことに手が回らなくなってしまっている。これをバタ貧(バタバタするのに貧乏)といいます。忙しいのに利益が上がらない場合、振り返る必要があります。忙しいと仕事をしているような気になる。これがまずい。社員はそれでもいいかも知れませんが、社長さんは、まずいです。質問その2「重要かつ緊急」と「重要」どちらを重視して(強く意識して)計画を立てるといいですか?正解は、なんと、「重要」なのだそうです。恥をさらしますが、実は自分もこの盲点に引っかかっていました。「重要かつ緊急」の事項のほうを重大視するべきだろう、と思っていました。ところが、そうではなかった。「重要だが緊急でない」ことのほうが重要なんだそうです。「重要だが緊急でない」ことを先回りして段取っていくと、「重要で緊急」な出来事が減ってくる、つまり、仕事や状況に振り回されなくなってくる、だから、、、というものでした。計画の意味意図の本質を見た思いで、言葉がありませんでした。これを教えてくれたのは、「7つの習慣(キングベアー出版)」です。有名な売れ本ですが、名著でした。●最終整理さて、その「緊急ではないが重要であるもの」についてのリストの固まりが、今、あなたの手元にあります。ここからの作業としては、付箋をグループ内で時系列として4つにわけます。それは「今日する」「今日はしないが今週する」「今週しないが今月する」「目先しない(あとまわし)」です。で、すでにある「重要だが緊急ではない」付箋を、自分の意思で時系列に配置していきます。抽象的で付箋をはれないと感じたら、具体化・ブレイクダウンして新しく付箋を書き起こします。これで付箋の受入簿が「今日」「今週」「今月」「未定」の4つになり、さらに「未定」の中が項目別に分かれることになります。以後、思いついたものを付箋に書いたら、この受け入れ簿(ノート)に振り分けていきます。そして毎日終わった「今日」はdone帖になります。できれば、するべきことを採番してノート化し、それを付箋に転記して、その日するべきことを作っていくといい。というのは、採番ノートは、思考回路のアイデアノートになるからです。未来の思索のヒントにもなるし、精神程度の遍歴の日記にもなります。ある意味情けないのですが、何年かして、振り返ってみると「おお、すごいこと考えていたなあ、これをやってれば、今ごろはすごかったのになあ」ということに気がつくことたびたびです。そう、実は実行の継続こそが命であり、ここが一番難しいところです。それはさておき、将来結構有効に働く可能性の多いアイデアノートとなる可能性があります。また、未定の項目は、状況によりかわることがあります。どんどんかわってしまってもかまいません。とにかくやることを思いついたら書き出して、どのタイミングでやっていくかを次々と決めてやっていく。これで、短期中期までの目標管理実行についてのお話は終了です。長期目標については、明日述べます。
2004年06月12日
コメント(1)
-
実用 目標設定 2(書き出して分類する。とにかくはじめる)
目標設定の第2ステップ。書き出した目標欲望を分類してみる。実は、100個書き出すというのは、一人ブレーンストーミングです。100個でなくても、次のステップに移ります。でも、できるだけ少なくとも100個にするように並行して努力してください。なぜここで努力しておくといいかというと、アイデアが出しやすくなる癖がつくからです。それはさておき。今日は、次のステップです。とりあえず手元に100の目標欲望があるものと仮定してお話しします。100の項目を、今度はPostItなどに書き出します。そしてグルーピングしていく。グルーピングの仕方ですが、「今日すること」「今日はしないけれど今週すること」「今週しないけれど今月(特に特定の日)すること」をまず取りのぞいちゃって、その残りをグルーピングします。どんなグルーピングになるか。それは人によりそれぞれ違います。確実にいえるのは、そのグルーピングの種類とかカラーが自分の人生における興味対象性向方向性ということです。とりあえずそこに表出している対象イメージと格闘していくことになります。グルーピングのほうは、もう少し調理しなくてはいけないので、それと平行して、「今日すること」に全力を尽くします。項目はだいたい10もあれば充分でしょう。伝説では、6つでいいことになっています。ちなみに伝説というのは、100年近く前の海外(多分アメリカ)のあるコンサルタントに成功報酬方式で仕事の効率をあげてほしいといったら「明日するべきことを6つ書き出して優先順位をつけて、順番にやっていく」というアイデア一つを提供したら、百万ドルの報酬だった、という伝説です。ご存知の方も多いと思います。100個を書き出して、10個を今日実行する。まず、目先の1個に集中する。これの繰り返しです。1個実行すると、これすなわち小さな成功体験。これが小さな自信を生み、自己信頼を生む。それが次の成功体験を呼び込み、このサイクルをまわしていくうちにだんだんと渦が大きくなってくる。そのうち自分でも制御できないほど大きくなってきて、気がついたら周りを巻き込んでいて・・・ということのようです。まあ、それは先の話。実は、病的なほどに自信を失ってしまったり、やる気がなくなってしまったときの回復への糸口がこの方法(小さな成功体験を積み重ねる)です。頭の片隅においておくともしかすると南下の助けになるかもしれませんので、老婆心までに。ちなみに、目標を書き出すときは、手書きがいいようです。どうも、そんな感じです。パソコンのほうが、書く手間を省略できてよさそうなんですが、自分自身にしみこんでこない。手書きで目標を設定したほうが、実行実現度が高い、これは経験則です。推測ですが、目標や夢は、これを手書きで書くことにより、夢実現の道先案内人として自分にしみこませる、そういう効果があるようです。それとよく言われるのが、肌身離さずしょっちゅう目標を見ておくこと。これについては明日述べます。
2004年06月11日
コメント(2)
-
実用 目標設定(まず、アイデアを出す)
楽天日記開設記念。皆様に幸せつくりのお手伝いを企画しました。目標設定の最初の最初についてお話します。難しいことは抜きにして、とにかく100個、書き出してみる。やりたいこと、するべきこと、なりたい姿、ありたい状態。ほしいものなど、自分の希望や目標や欲望を、とにかくランダムでいいから書き出してみる。具体的でも抽象的でもかまわない。また、今日するべきことでも将来するべきことでも、あるいは日常するべきことでも気にしない。とにかく書き出す。書いて書いて、書く。すでに書いたことをさらに細かく書く。それでもいい。とにかくそうやって行動リストを100つくる。100というのは簡単そうで、意外に難しい。これを今日中にする。行動リストのアイデアには整理番号を振っておきます。ある程度書いて、前に書いたのを見てさらに類似をひらめいたら、それもまた新しい1つのアイデア、としてかまわない。最初はとにかく100集めます。なお、これは、いったん100集めた後、毎日10個とか、すこしづつ書き足していきます。たとえば1日10個として、3年間で1万。1万のアイデアを実現したらどうなるか。ものすごく違う自分がそこにいるはずです。そのスタートの一番重要な部分を勢いづけとともにやろうというのが、その方法を書いたのが、今日の日記です。よろしかったらおつきあいください。目標を設定する。誰にも見せるものではないので、目標は、せこい内容でも、反社会的な内容でもかまいません。ただし、犯罪行為はとりあえず禁止ということでお願いします。自分の未来の栄光・喜びは、そのリストの中から生まれてきます。想像しないことは実現しません。想像したことの一部が創造されて世の中を構築します。世の中のすべてのものは、もともと誰かの想像から始まっています。想像は創造の母体。まず、想像しましょう。数を膨らませると、創造へ向けてのドライブになります。栄光の未来を築くための第一歩。とにかく100の目標欲望の設定。ペンとメモを肌身離さず持っておくといいです。自分の場合はシステム手帳とボールペン。本を読んでても、メールを見ても、新聞を見ても、誰かと話してても、ふと「ピンと来た」その内容をまずメモる。メモした内容をじっとにらんで、それに派生する目標や行動を書き出す。これも番号を振っていい。実は、この作業で、自分を知るという意味が含まれています。次のステップは明日お話しします。
2004年06月10日
コメント(1)
-
楽天恐るべし
昨日1日で、100人以上のアクセスがあったようです。ありがとうございました。感謝、感謝です。それにしても、オンラインウエブの威力には、改めてびっくり。何の宣伝もしないのに、覗いてくれる人がこんなにもいるとは。現実の世界では、どんなに努力しても、1日に100人と名刺交換するとなると、異業種交流会とか、特殊な場合しか考えられない。しかも、肉体的・精神的・経済的な投資が結構かかる。そしてそのほとんどが、無意味に役立たずにておしまいとなる。ところが、このオンラインでは、ちょいちょいと独り言を書くだけで、100人の人が「あー、ひでは独り言を言ってるな」と理解を示してくれる。これってすごいことですね。面白いし、恐ろしい。100人の人が読むということは、たとえば雑誌での投稿ならその10倍の1000冊発行しているような雑誌である必要があるわけで、それを考えると、周知という点ではすさまじい破壊力を持ったメディアなんだなと、改めて実感します。あとは、業務への実際のインパクトがどれくらいあるのか、ということが要チェック事項ですけど。僕は以前、DMのちらしを撒いたことがあった。約3千枚。これをはがきでやったんだけれど、印刷代やソフト代も含めて20万円ほど投資したんだけれど、反応が、まったくなかった。正確には3件あって、2件が「迷惑だ」、1件が名乗らずに値段だけ聞いてガチャリ。誰も何も読まないわけではないのかということを確認しただけで終わった。もう金輪際DMの投稿なんかするものかと思った。それに比べると、すばらしい時代になったもんです。
2004年06月09日
コメント(0)
-
楽天日記になれるための練習 3
わけがわからないながらもやってみれば見えてくることもあるだろうと思い、目をつぶってスタート。みなさま。よろしくご指導をお願いいたします。本日最後は、削除の実験です。↓空白ならOK
2004年06月08日
コメント(5)
全48件 (48件中 1-48件目)
1