全3238件 (3238件中 1-50件目)
-
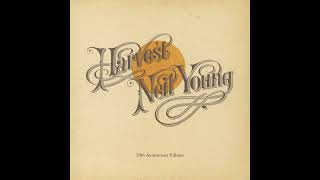
ニール・ヤング 「オールド・マン(Old Man)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その5) “秋を感じさせる”という個人的思い入れ(思い込み?)でニール・ヤング(Neil Young)の楽曲を取り上げてきましたが、今回の5曲目で一区切りです。最後は何と言ってもこの曲、「オールド・マン(Old Man)」です。初回に取り上げた「週末に(アウト・オン・ザ・ウィークエンド)」と同じアルバム(1972年の『ハーヴェスト』)に収録されています。「週末に」がアルバムのオープニング・ナンバー(A面1曲目)なら、今回の「オールド・マン」は、元来のLP盤のB面のオープニングのナンバーということになります。 イントロのギターを聴くと、何か凝った曲なのかなという印象を受けるかもしれませんが、歌が始まるとド直球の弾き語り風かつニール・ヤング節のナンバーです。 最後は、この曲のライヴでの演奏シーンです。第1回目の「週末に」と被ってはしまうのですが、その時にリンクを貼ったのと同じBBCライヴの演奏シーンです。ギターの弾き語り調がストレートに刺さってくるところ、そして何よりも若きニール・ヤングの声の伸びがお見事なライヴ演奏です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月13日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その4) 前回の「ザ・ペインター」が収録されているのと同じニール・ヤング(Neil Young)のアルバム(過去記事)から、もう1曲取り上げてみようと思います。「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」というのが、その楽曲です。ピアノ弾き語り風の、どちらかというと地味な曲なのですが、筆者的にはこの哀愁と寂しさの漂う感じが何とも言えない魅力になっているナンバーです。 この曲のライヴでの演奏もご覧いただきます。リリース当時の2005年、ライマン・オーディトリアムでの演奏シーンです。 鍵盤を前にしての演奏ですが、ギターを弾きながら、ピアノを弾きながら(さらにはハーモニカ演奏を披露しながらというパターンもあります)といずれも味わい深さを発揮できるのは、ニール・ヤングの魅力であり強みであるのだろうとあらためて思ってみたりします。[収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) 【中古】 プレーリー・ウィンド/ニール・ヤング プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月12日
コメント(0)
-
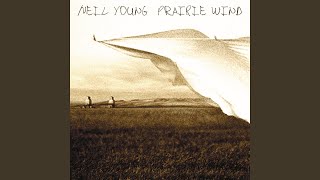
ニール・ヤング 「ザ・ペインター(The Painter)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その3) 秋という季節と絡めてのニール・ヤング(Neil Young)曲選の3回目です。前2回の曲から時は一気に進んで、2005年のアルバム『プレーリー・ウィンド』に収められた「ザ・ペインター(The Painter)」というナンバーです。 この曲が収録されたアルバムは、リリース年としては離れているものの、『ハーヴェスト・ムーン』(2005年)と並んで『ハーヴェスト』(1972年)の続編的内容と見なされる作品で、そういう意味では、楽曲の雰囲気も通底している部分があります。 続いては、発表当時(2005年)のステージの模様をご覧ください。アルバム収録のもとのヴァージョンと同様のまったりした雰囲気が魅力といったところです。 [収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 【中古】 【輸入盤】プレイリー・ウィンド/ニール・ヤング ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月11日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その2) 筆者の中ではなぜだか秋という季節と結びついているニール・ヤング(Neil Young)のナンバーの2曲目です。今回の楽曲は、彼の作品の中でも代表作として1,2位を争う(と筆者は思っている)名盤『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』に収録のナンバーです。 まずは、上記の盤に収められた表題曲「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」をお聴きください。 なぜ“秋”なのかという点については、結局のところ感覚的なものでしかないのですが、この“頼りなさげな”(もちろんいい意味で)が筆者にそう思わせるといったところなのでしょう。 今回は、後世のライヴ映像もご覧いただきたいと思います。1998年、ファーム・エイドでのステージの様子です。上記のヴォーカルの魅力(そしてハーモニカ演奏部分も実に魅力的です)が存分に発揮されています。 [収録アルバム]Neil Young / After the Gold Rush(1970年) アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ [ ニール・ヤング ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月10日
コメント(0)
-
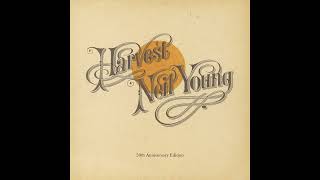
ニール・ヤング 「週末に(Out on the Weekend)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その1) 今夏の連日の猛暑もようやく収まってきて、少しは秋が感じられる日も増えてきました。そんなわけで、“秋の風を感じるニール・ヤング曲選”をお届けしたいと思い立ちました。ニール・ヤング(Neil Young)が必ずしも秋と結びつくというわけではないのですが、個人的にはそういうアルバムがあることをこちらの過去記事(『ハーヴェスト』)にも書きました。他のいくつかのニール・ヤングのアルバムでも、なぜだか秋とシンクロするものがあって、今回はそうした中から彼の楽曲をいくつかピックアップしていこうと思い立った次第です。 最初の曲は、上記『ハーヴェスト』に収録の「週末に(Out on the Weekend)」というナンバーです。アルバムのオープニング曲にしては何とものどかというか素朴なナンバーなのですが、筆者の個人的思い入れとしては、秋風が吹く山道をドライヴするのに最適な1曲だったりします。 もう一つ、ライヴ演奏もお聴きいただきたいと思います。発表当時(というか厳密にはアルバム発表の前年)の1971年、BBCライヴでの弾き語り演奏の模様です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月08日
コメント(0)
-

アルカンヘル・ウルバーノ 『レジェンダス(Leyendas)』
“都会の天使”によるメキシコのアーバン・ロック アルカンヘル・ウルバーノ(Arkángel Urbano)は、メキシコの4人組ロック・バンド。直訳すると“都会の大天使”というのは何ともベタな名前に思えるが、その演奏スタイルもメキシコの大衆層向けのベタなロックというもの。メンバーは、ロベルト・カルロス(通称ダニーロ、ヴォーカルとリズム・ギター)、セサル・クルス(ベース)、ホアキン・ガジョソ(リード・ギター)、ダビー・アルバレス(キーボード)、ウリシス・ロサード(ドラムス、パーカッション)という5人組である。メキシコでその手の盤を多く手掛けるデンバー・レコードから2015年にリリースされたのが、本盤『レジェンダス』である。 1.「ラ・ジョローナ」は、ややヘヴィメタル寄りのシリアスな演奏がビシッと決まっている好曲だが、夜な夜な聞こえる女性の泣き声というメキシコの民間伝承を表題にしているというミスマッチが面白い。収録曲全体を見ると、ブルース/ロック・ベースのメキシカン・ロックが中心で、筆者に刺さるナンバーとしては、3.「アモール・インポシブレ」(“かなわぬ愛”の意味)、8.「フリアン」、12.「ティエンポ・デ・トリウンファール」(“勝利のとき”)といった辺りだろうか。 他の収録曲の中には、若くして母となった少女に捧げた7.「ア・ウナ・ホベン・ママ」、メキシコシティ近郊の高山を表題にした9.「イスタックシワトル(白い女性)」、イエス・キリストの名と曲調が見事なミスマッチ(?)を醸し出す10.「エル・ラメント・デ・クリスト」(“キリストの嘆き”)のような曲がある。かと思えば、日本人的にはやや仰天の11.「ゲイシャ」(“芸者”)なんて曲も含まれている。中途半端なバラード調の演奏にのせて、“月のごときゲイシャ~、白い肌、君のことが忘れられない~”といったような歌と演奏(もちろん本人たちは大真面目)。こうした部分も、“何でもあり”の面白さということで楽しめばいいのだろう。[収録曲]1. La llorona2. Recuerdos3. Amor imposible4. El blues de la verdad5. La historia de un perdedor6. Flores negras7. A una joven mamá8. Julián9. Iztaccíhuatl (mujer blanca)10. El lamento de Cristo11. Geisha12. Tiempo de triunfar (David Severo Carmona)2015年リリース。 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月06日
コメント(0)
-

ジョアン・マヌエル・セラ― 『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』
カタルーニャ人シンガーが“文学を歌う” スペインはカタルーニャ出身のシンガー、ジョアン・マヌエル・セラ―(Joan Manuel Serrat)の19枚目のアルバムとして1985年にリリースされたのが、本盤『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』である。セラーの有名曲の一つ「カンターレス」は、スペインの詩人アントニオ・マチャードの詩に音楽をつけたものとして知られているが、実はこの曲が収録されたアルバム(1969年の『詩人アントニオ・マチャードに捧ぐ』)そのものがそういうコンセプトであった。これと同様に、マリオ・ベネデッティを題材としたのが、本盤ということになる。 マリオ・ベネデッティは、ウルグアイ生まれの小説家、ジャーナリスト、詩人で、軍政下の祖国からアルゼンチン、ペルー、キューバ、スペインへと逃れて亡命作家生活を送った。亡命生活の最後の時期に当たるのが、ちょうど本盤の頃であった。そのベネデッティの詩を題材にして音楽にのせてセラーが歌うというのが、このアルバムのコンセプトである。 表題曲の1.「エル・スール・タンビエン・エクシステ(南もまた存在する)」は、世界におけるいわゆる南北格差が歌われており、南米出身のベネデッティならではの説得力がある。どの曲に関しても、セラーの歌唱力が生かされているが、筆者の好みでは4.「アガモス・ウン・トラート(取引をしよう)」、5.「テスタメント・デ・ミエルコレス(水曜日の遺言)」、6.「ウナ・ムヘール・デスヌーダ・イ・エン・ロ・オスクーロ(裸の暗がりの女性)」、10.「デフェンサ・デ・ラ・アレグリーア(歓喜の擁護)」なんかがいい。8.「アバネーラ」は、キューバのハバナがテーマとなっていて、これもまたベネデッティの亡命生活から生まれたテーマである。 上述のような“文学的な”盤ながら、リリース年から翌年にかけて4曲もがシングルカットされている(発売順に6., 3., 7., 4.)。文学作品がポップやロックの曲に化けるというのは、日本語では想像しにくいかもしれないが、この辺りはやはりラテン語の流れを汲む文化圏の底力なのかもしれない。それと同時に、亡命生活にある作家の声を聴衆に届けようというシンガーとしてのセラーの心意気があって誕生した盤ということであろうか。[収録曲]1. El sur también existe2. Currículum 3. De árbol a árbol4. Hagamos un trato5. Testamento de miércoles6. Una mujer desnuda y en lo oscuro7. Los formales y el frío8. Habanera9. Vas a parir felicidad10. Defensa de la alegría1985年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月03日
コメント(0)
-

ポール・チェンバース 『ゴー(Go)』
ハード・バップ直球ながらオープンな雰囲気の盤 1935年、ピッツバーグ生まれでデトロイト育ちのポール・チェンバース(Paul Chambers)は、33歳と早くに亡くなったこともあり、リーダー作は決して多くはない。ブルーノート盤以外で目立ったものとして、今回取り上げるのが、1959年のヴィージェイ盤の本作『ゴー(Go)』である。 サイドマンとして数々の盤に出ているだけあって、メンツとしては、ある意味よくありそうな組み合わせ。アルト・サックスにキャノンボール・アダレイ、トランペットにフレディ・ハバード。リズム・セクションはピアノのウィントン・ケリーにドラムのジミー・コブおよびフィリー・ジョー・ジョーンズという、お馴染みの顔ぶれによる演奏である。マイルス・デイヴィス『カインド・オブ・ブルー』にメンツがそっくり?と思う向きもあるだろうが、それもそのはず。本盤の録音は1959年の2月。『カインド・オブ・ブルー』が同年の3月~4月なので、ほぼ同時期の録音ということになる。 本盤を一言で表すならば、直球のハード・バップ盤ということになるだろう。けれども、ブルーノート盤なんかに典型的なシリアスさに欠けるというのも、重要な特徴だと思う。言い換えると、弾けたりリラックスしたりという、“シリアス”の対極のような要素が演奏の随所で目立つ。それは、上記の『カインド・オブ・ブルー』と並べて聴いてみると一目瞭然だろう。 1.「オーフル・ミーン」は、冒頭からチェンバースのベースが弾け、キャノンボール・アダレイのサックスが奔放に駆ける。4.「ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ」は、上で述べた通りのオープンなリラックス感が特徴的。それに対し、5.「イーズ・イット」はもっとシリアスに迫ってくる演奏から始まるのだけれど、やはりどこかにオープンな雰囲気(途中の拍手なども含めて)を持ち合わせている。6.「アイ・ガット・リズム」も同様な特徴を持つと言えるが、個人的にはスピード感のあるこの演奏は、本盤中で特に魅かれるものだったりする。 ちなみに、筆者は通して聴いていないものの、1998年には未収録音源を含めたものが2枚組としてリイシュ―されている。[収録曲]1. Awful Mean2. Just Friends3. Julie Ann4. There Is No Greater Love5. Ease It6. I Got Rhythm[パーソネル、録音]Paul Chambers (b)Julian “Cannonball” Adderley (as)Freddie Hubbard (tp)Wynton Kelly (p)Jimmy Cobb (ds)Philly Joe Jones (ds)1959年2月2~3日録音。 【中古】 ゴー+1/ポール・チェンバース 下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、 バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月29日
コメント(0)
-

オリヴァー・ネルソン 『スイス組曲(Swiss Suite)』
ネルソンがまとめあげた熱狂のライヴ演奏 1971年6月18日、スイスのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでの熱演は翌朝5時まで夜通し続いた。その最後を飾った演奏の収められたのが、本盤『スイス組曲(Swiss Suite)』である。この演奏をまとめあげたのは、アレンジャーでアルト・サックス奏者でもあるオリヴァー・ネルソン(Oliver Nelson)であった。 ジャケットには、上記の通りのライヴ演奏盤である旨(“Recorded Live at the Montreux Jazz Festival”)に加え、“Featuring Gato Barbieri & Eddie ‘Cleanhead’ Vinson”とあり、2人の写真も載せられている。 LPのA面全部に当たる1.「スイス組曲」では、これら2人のうち、まず前者のテナー、次いで後者のアルト・サックスが躍動する。とくにガトー・バルビエリ(ガート・バルビエ―リ)の方は、この同じ日のライヴ演奏が『エル・パンペーロ』としてライヴ盤になっており、その演奏後の熱い雰囲気の中、そのまま熱演を奮っている。およそ27分のこの演奏では、これら2人のとにかく情熱的で激しいプレイをオリヴァー・ネルソン率いるオーケストラががっちりと受け止めているのだけれど、聴く側の観点としては、そんな細かいことを忘れてとにかく熱い演奏にのめり込めるのがいい。 アルバム後半(LPのB面)は、名曲2.「ストールン・モメンツ」で幕を開け、オリヴァー・ネルソン・オーケストラによる合計3曲の演奏が収められている。これらの演奏も、総じて熱く、熱気に満ちたものである。個人的に気に入っているのは、上記の「ストールン・モメンツ」。次いで、ラストを飾る4.「ブルースの真実(ブルース&ジ・アブストラクト・トゥルース)」のキレのよさが特に印象に残る。 [収録曲]1. Swiss Suite2. Stolen Moments3. Black, Brown and Beautiful4. Blues and the Abstract Truth[パーソネル・録音]Oliver Nelson (as, arr, conductor), Gato Barbieri (ts: 1.), Eddie "Cleanhead" Vinson (as: 1.), Charles Tolliver (tp, flh), Danny Moore (tp), Rich Cole (tp), Bernt Stean (tp), Harry Beckett (tp), Buddy Baker (tb), Bertil Strandberg (tb), Donald Beightol (tb),C.J. Shibley (tb), Monte Holz (tb), John Thomas (tb), Jim Nissen (bass trombone), Jesper Thilo (as), Michael Urbaniak (ts), Bob Sydor (ts), Steve Stevenson (bs), Stanley Cowell (p), Victor Gaskin (b), Hugo Rasmussen (b), Bernard Purdie (ds), Bosko Petrovic (ds, vib, tarabooka), Na Na (berimbau), Sonny Morgan (congas)録音:1971年7月18日(*7月19日午前) スイス組曲(ライヴ・アット・モントルー・ジャズ・フェスティヴァル) [ オリヴァー・ネルソン ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月26日
コメント(0)
-

ウディ・ショウ 『マスター・オブ・ジ・アート(Master of the Art)』
魅力が伝わるライヴ演奏盤 ウディ・ショウ(Woody Shaw)は1944年生まれのジャズ・トランペット奏者。フレディ・ハバートと並ぶ奏者と言っていいようにも思うのだけれど、正当に評価されてこなかったミュージシャンだと言える。本盤『マスター・オブ・ジ・アート(Master of the Art)』は、1982年と比較的新しい吹き込みなのだが、彼の魅力を存分に伝える好ライヴ演奏盤だと思う。 内容としては、レギュラー・クインテット(ウディ・ショウのトランペット・フリューゲルホーンのほかにスティーヴ・ターレのトロンボーンを含むクインテット)に、ゲストとしてヴィブラフォンのボビー・ハッチャーソンを加えたメンバーでの演奏。このヴィブラフォンもなかなかいい働きをしていて、2.「ダイアン」はその効果を実感できる1曲だったりする。 本盤全体を通じての筆者のイチオシは3.「ミステリオーソ」。セロニアス・モンクの有名な楽曲で、並行して展開するメロディというややこしさを見事に創造的な演奏に変えてみせている。時にマイルス・デイヴィスを彷彿とさせるスリリングさすら感じるというと言いすぎかもしれないが、筆者的にはそのくらいに魅かれるものがある。 都合5つのトラックが収録されているが、実際の演奏は1.~4.で、最後の5.はウディ・ショウの肉声によるインタヴューである。彼は本盤の吹込みから7年後の1989年、地下鉄ホームから転落するという事故により、左腕を切断し、その後の経過もよくなく同年に44歳で死去した。通常であれば、蛇足とも言われかねないインタヴュー音声だが、生前の貴重な証言として自身の音楽観などについて語っているものとなっている。[収録曲]1. 400 Years Ago Tomorrow2. Diane3. Misterioso4. Sweet Love of Mine5. The Woody Shaw Interview[パーソネル・録音]Woody Shaw (tp, flh), Bobby Hutcherson (vib), Steve Turre (tb), Mulgrew Miller (p), Stafford James (b), Tony Reedus (ds)1982年2月25日録音。 JAZZ BEST COLLECTION 1000::マスター・オブ・ジ・アート [ ウディ・ショウ ] [枚数限定][限定盤]マスター・オブ・ジ・アート/ウディ・ショウ[CD]【返品種別A】 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月23日
コメント(0)
-

オレハ・デ・バン・ゴッホ 『ディレ・アル・ソル(Dile al sol)』
成功を収めたデビュー盤 ラ・オレハ・デ・バン・ゴッホ(La Oreja de Van Gogh, 略してLOVG)は、スペイン北部バスク地方のサン・セバスティアンで結成されたポップ/ロック・グループ。メンバーは、アマイア・モンテーロ(ヴォーカル)、パブロ・ベネーガス(ギター)、シャビ・サン・マルティン(キーボード)、アルバロ・フエンテス(ベース)、アリツ・ガルデ(ドラム)の5人から成る。なお、ヴォーカルのアマイアはソロシンガーとして独立したため、2008年からはヴォーカリストがレイレ・マルティネスに変更となっている。 1990年代の末、彼らのデビュー盤となったのが、この『ディレ・アル・ソル(Dile al sol)』である。明るくド派手なポップかというとそうでもなく、ロック調かというとそんなこともない。丁寧で安定したバンド演奏とアマイア・モンテーロの個性のあるヴォーカルが適度なポップさを伴った楽曲となって並んでいる。いい意味で、ある種の“聴きやすさ”とヴォーカルの魅力が聴衆の支持に結びついたと言えるのだろう。 1.「エル・ベインティオチョ」は、彼らの最初のシングルで、いきなりヒットを収めたナンバー。このアルバムに収録されていてシングル発売されたナンバーは8曲もあるのだけれど、そのうちで最も大きなヒットとなったのが、2.「クエンタメ・アル・オイード」。こちらの曲の方は、スペイン国内のシングル・チャートで1位を記録し、スペイン・ポップスの代表的なナンバーの一つとして定着した。 6.「ドス・クリスタレス」は、演奏もヴォーカルも聴きごたえがある注目曲の一つ。表題曲の9.「ディレ・アル・ソル」は、テンポのよさと小気味よさが光る。12.「ソニャレー」は、軽妙なリズム感とヴォーカルのよさがうまく生かされた好曲。全体として、後のアルバムと比べるとまだ荒削りな部分も残されているものの、バンドとしての演奏力の高さに加え、アマイアのヴォーカルで聴き手が魅了されるというこのバンドの特徴はすでに明確に表われている。デビュー盤ということを考えると、完成度の高さが際立っているし、上に挙げた以外にも聴き逃がせない曲が多く、おすすめの好盤と言えるように思う。[収録曲]1. El 282. Cuéntame al oído3. Pesadilla4. La estrella y la luna5. Viejo cuento6. Dos cristales7. Lloran piedras8. Qué puedo pedir9. Dile al sol10. El libro11. La carta12. Soñaré1998年リリース。 ↓ベスト盤です↓ 【中古】 La Oreja De Van Gogh ラオレハデバンゴッホ / Lovg: Grandes Exitos / La Oreja De Van Gogh / BMG Import Argentina [DVD Audio]【ネコポス発送】 ↓LP盤です↓ 【輸入盤LPレコード】【新品】La Oreja De Van Gogh / Dile Al Sol【LP2023/4/28発売】 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月20日
コメント(0)
-

INDEXページ更新
ここ1カ月ほど滞ていましたが、INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもあり がたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月16日
コメント(0)
-

パブロ・ミラネス 『ディアス・デ・グロリア(Días de gloria)』
年齢を重ね、安定感と安心感に満ちた好作 パブロ・ミラネス(Pablo Milanés)は、1943年キューバ出身のミュージシャン。2022年に79歳で没している。シルビオ・ロドリゲスらとともに、キューバの新しいトローバ(ヌエバ・トローバ・クバーナ)を牽引した人物で、スペイン語圏の音楽界では実に人気の高い存在である。 1970年代以降、彼は数多くのアルバムや楽曲を世に送り出したが、2000年にリリースされた『ディアス・デ・グロリア(Días de gloria)』は、個人的にリリース直後から繰り返し聴いたこともあり、愛着のある作品の一つとなった。もう少し客観的な言い方をするならば、50歳代後半になったパブロが、以前と同様の安定感と安心感に満ちたパフォーマンスを見せた好作品ということになるだろうか。 おすすめの曲としては、まず表題曲の1.「ディアス・デ・グロリア」(“栄光の日々”の意)。この演奏は通常の弾き語り(アコースティック演奏)だが、アルバム末尾には“トリオ・ヴァージョン”(11.)なるものも収められている。2.「クアンド・ジェガス・アウセンテ・ア・ミ」(“君がいなくなってしまった時”)はテンポよく安定した演奏と歌唱がいい。5.「エン・サコ・ロト」(“破れた袋に”)はアコースティックながらラテンのリズムというキューバ人ならではの曲調が印象的である。 7.「ノスタルヒアス」(“郷愁”)は、いかにもパブロらしい回想的な詞と曲調の、個人的には気に入っているナンバーの一つ。9.「シ・エジャ・メ・ファルタラ・アルグナ・ベス」は、“もし彼女がいなくなったなら”、“もし彼女が私を愛さなくなったなら”、“もし彼女が歌うことを忘れたならば”、などと歌い、“僕がこの歌を書くことはないだろう”と締めくくるラヴソングとなっている。アルバムを締めくくるのは、上記の通り、表題曲のトリオ・ヴァージョンである11.「ディアス・デ・グロリア」。トリオと言っても、本盤全体を支配するアコースティック調を崩さない雰囲気の演奏で、こちらのバージョンも結構気に入っている。[収録曲]1. Días de gloria [acoustic versión]2. Cuando llegas ausente a mí3. Canto a victoria4. Deborah Winsky5. En saco roto6. Masa7. Nostalgias8. Éxodo9. Si ella me faltara alguna vez10. A dos manos11. Días de gloria {trio version}2000年リリース。 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月14日
コメント(0)
-

テレグラフ・アヴェニュー 『テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)』
サイケとラテンが融合した独自路線のロック テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)は、ペルーのロック・バンド。1969年、ワロ・カリーヨ(ドラムス、元ホリーズ)とボー・イチカワ(ギターとヴォーカル)の出会いに始まり、その後、ジェリー・ラム・カム(ベース)、チャチ・ルハン(ギターとコンガ)、さらにはベーシストがアレックス・ナタンソン(ベースとヴォーカル)に交代し、4人組の布陣が固まった。このメンバーで1971年にリリースされたのが、セルフ・タイトル盤の『テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)』である。なお、テレグラフ・アヴェニューというバンド名は、イチカワがサンフランシスコ滞在中の住処の通りの名前に由来する。 音楽的な方向性でいうと、“サイケデリック・ロック”に分類されうるのだろう。けれども、このバンドの面白いところは、ラテンのリズムが感じられるというところにある。カリフォルニアで触れたサイケを志向しているのだけれども、根はラテン。音楽を細かく分類するのは嫌いなのだけれど、“ラテン・サイケデリック・ロック”と言ってもいいような感じである。 注目の曲をいくつか触れておきたい。ラテンのリズムとサイケ音楽の融合という点では、3.「スイート・ホワットエヴァー」、5.「サンガリガリ」(←こう読むのでしょうか?)がその特徴をよく表している。他に6.「レット・ミー・スタート」は、楽曲自体もよくギターも効果的な好ナンバーで、こうした楽曲もよく聴くとリズムにラテンな部分が見え隠れするのは興味深い。アルバムを締めくくるセルフ・タイトル曲の8.「テレグラフ・アヴェニュー」は、コーラスが印象的で、どこか哀愁を漂わせるこれまた好曲である。ちなみに、CD化によって、現行の盤ではボーナス・トラックとしてもう1曲、9.「イッツ・OK」という曲が加えられている。[収録曲]1. Something Going2. Happy3. Sweet Whatever4. Lauralie5. Sungaligali6. Let Me Start7. Sometimes In Winter8. Telegraph Avenue9. It's OK [bonus track]1971年リリース。 【中古】米CD Telegraph Avenue Telegraph Avenue CD2007 Lazarus Audio Products /00110 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月11日
コメント(0)
-

ロバート・ラム 『マイ・ネイバーフッド(Life is Good in My Neighborhood)』
シカゴのオリジナル・メンバーによるソロ第二作 ロバート・ラム(Robert Lamm)は、テリー・キャスらとともに、ブラス・ロック・バンドのシカゴの創設メンバーである。彼は、1970年代のシカゴのソングライティングの重要な部分を担った。しかし、時の経過とともに、シカゴはAOR路線へと向かっていった。これによって、彼が曲を作らなくなったかというと、そんなことはなかった。バンドとしてのシカゴが“甘い”路線をとる中、彼は相変わらず自作曲を作り続けていた。そうした曲が日の目を浴びることになったのが、1993年発表のソロ・セカンド作『マイ・ネイバーフッド(Life is Good in My Neighborhood)』である。 アルバム表題の元になった1./11.「マイ・ネイバーフッド」は、シンプルかつ往年のシカゴっぽさを残す“ヴァージョンA”(トラック1.)と、少し肩の抜けた南国風な感じのする“ヴァージョンB”(トラック11.)が収められている。この表題曲のほかに前半で注目したいのは、3.「オール・ザ・イヤーズ」。往年のシカゴらしい曲調のナンバーで、シカゴのアルバムの中でも聴いてみたかったと思わせる1曲だったりする。5.「ジェシー」は、ラム節が生かされた曲で、シリアスでドラマチックな雰囲気がいい。 アルバム後半では、7.「タブラ」と9.「ホエン・ウィル・ザ・ワールド・ビー・ライク・ラヴァーズ?」が特にいい。前者は、シリアスなナンバーだが、曲の精度が高く、完成度もとりわけ高い。後者は、個人的にはアルバムいちばんの出来で、シカゴそのものといった雰囲気のナンバー。詞の内容も早い時期のシカゴを彷彿とさせるものだったりする。[収録曲]1. My Neighborhood (Version A)2. When The Rain Becomes3. All The Years4. Murder on Me5. Jesse6. Ain't No Ordinary Thing7. Tabla8. In This Country9. When Will the World Be Like Lovers10. My Neighborhood (Version B)1993年リリース。 【中古】CD ロバート・ラム マイ・ネイバーフッド WPCP5519 Reprise Records /00110 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月09日
コメント(0)
-

パティ・スミス・グループ 『ラジオ・エチオピア(Radio Ethiopia)』
完成度が高く、エネルギーに溢れた作品 パティ・スミス(Patti Smith)は、1945年シカゴ生まれ、ニュージャージー育ちのミュージシャン。“パンクの女王(クイーン・オブ・パンク)”と呼ばれ2007年にロックの殿堂入りしている。彼女は1975年にデビュー盤を発表し、これに続く第2作(パティ・スミス・グループの名で発表したアルバムとしては最初)となったのが、1976年の『ラジオ・エチオピア(Radio Ethiopia)』(なお、かつての邦盤タイトルは『ストリートパンクの女王』)だった。 彼女の作品の中ではロック色が濃い作品で、ジャック・ダグラスをプロデューサーに起用して商業的成功を狙ったものだったという。本盤最大の魅力は、何よりもパティのとんがり具合というか、前衛的・実験的なことも普通であるかのようにこなしていくパワフルさと実力にある。 アルバムは、ロック曲として完成度の高い1.「アスク・ジ・エンジェルス」から始まる。続く2.「エイント・イット・ストレンジ」や4.「ピッシング・イン・ア・リヴァー」に見られるうねりやアンダーグラウンド感にも、実は背後に安定感と完成度の高さが隠れているように思う。 本盤のハイライトは、アルバム表題曲の7.「ラジオ・エチオピア」。実際には「ラジオ・エチオピア」と「アビシニア」という曲のメドレーないしは組曲形式になっていて、12分超えの大作。既存の概念の打破、もしくは破壊と再構築という意味では、モダンジャズからフリージャズに行ってしまうぐらいの衝撃と吹っ飛びようである。とにかく熱く、しかし手が込んでいて、既存のスキームでは語れない“ロック”が展開されていると言えるように思う。 さて、こうしてこの人の作品を聴いていると、“パティ・スミスは女でありパンクである”という言い方は正しいのだろうか、という疑問が浮かび上がってきてしまう。彼女の音楽に耳を傾けると、“女である”ことも、“パンクである”ことも、ある種どこかで無意味化されてしまう。筆者としては、そんな気がどうしてもしてしまうのである。[収録曲]1. Ask the Angels2. Ain't It Strange3. Poppies4. Pissing in a River5. Pumping (My Heart)6. Distant Fingers7. Radio Ethiopia~Radio Ethiopia/Abyssinia1976年リリース。 ラジオ・エチオピア [ パティ・スミス・グループ ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年09月07日
コメント(0)
-

ソエー 『レプティレクトリック(Reptilectric)』
完成の域に達した推奨盤 21世紀に入ってから20年余年のメキシカン・ロック界でこれはというバンドを挙げるとすると、断然、筆者はソエー(Zoé)の名を挙げたい。このバンドは、1990年代に形成され、2001年のセルフ・タイトル盤でデビューした。 本盤『レプティレクトリック(Reptilectric)』は、前作(2006年)の成功に続いて制作された4枚目のスタジオ盤で、2008年にリリースされた。ソエーと言えば、2019年の『アストラン』でのグラミー受賞が知られるが、この作品と前作はラテン・グラミーにノミネートされていたし、11年のライヴ作もラテン・グラミーの受賞作となっていた。何が言いたいのかというと、この頃には既にソエーのサウンドは完成されたものになっていたということである。 実際、筆者的にも、これまでのところ上記の『アストラン』と並んで彼らの最高作と思っているのが本盤である。分野でタグづけするなら“ラテン・オルタナ・ロック”ということになるのだけれど、彼らにしかできない幻想的というか宇宙的なサウンド、ラテン系ロック独特のリズム感が演奏面の特徴になっている。そして、こうしたサウンド面の特徴だけが売りなのでなく、何よりも楽曲のよさが際立ち、この作品を特別なものにしている。 何としても聴き逃がせないナンバーとしては、まずは表題曲の1.「レプティレクトリック」。レオン・ラレーギ(ヴォーカル)がマヤの預言者の本に着想を得て思いついた造語で、古代神ケツァルコアトルを連想させる詞になっている。5.「ポリ」は初恋をテーマにした楽曲であるが、センチメンタルな感じは全然せず、浮遊感のあるサウンド、シンプルながら馴染みのいいメロディ、独白的な詞と三拍子揃った好ナンバー。なお、これら1.と5.はシングルとしてリリースされた。 長くなってきたけれど、他にどうしても外しがたい曲としては、3.「ソンブラス」、4.「ノ・アイ・ドロール」、政治批判的な7.「ネアンデルタール」、10.「ウルティモス・ディアス」。全編通じて好曲が並び、挙げだすときりがない。ソエーのアルバムとしてだけでなく、ラテン系ロックの作品としても名盤リストに入るべき作品だと言えるように思う。[収録曲]1. Reptilectric2. Nada3. Sombras4. No hay dolor5. Poli6. Resiste7. Neandertal8. Fantasma9. Luna10. Últimos días11. Babilonia2008年リリース。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年09月04日
コメント(0)
-

カルラ・モリソン 『アモール・スプレーモ(Amor supremo)』
成功を収めたセカンド作 2009年にシーンに登場したカルラ・モリソン(Carla Morrison, 英語読み風にカーラ・モリソンと書かれたりもするが、スペイン語の名前なのでカルラという読みが正しい)のセカンド・アルバムが、この『アモール・スプレーモ(Amor supremo)』という盤である。アルバムの表題は“至上の愛”という意味で、2015年にリリースされた。本盤には、60分を超える全13曲が収録されている。前作同様、アルバムはラテン・グラミーにノミネートされ、シングル曲がオルタナ部門で受賞を果たした。 ファースト作のところ(参考過去記事)にも書いたのだけれども、彼女の作品には、現代社会に生きる孤独感みたいなものが滲み出ている。そういう意味では、本セカンド作も同じ流れの中に位置づけられるものと言えるだろう。ファースト作と比べて変化しているのは、音作りの進歩で、作り込みの度合いが格段にアップしているように思う。 アルバムの収録順に注目したい楽曲を見ていくと、まずは、1.「ウン・ベソ」。彼女の独自の楽曲の世界が存分に発揮された1曲だと思う。3.「ベス・プリメーラ」は、ラテン・グラミーのオルタナ部門で受賞曲となったナンバー。4.「アスカル・モレーナ」は“ブラウン・シュガー”を意味する表題とは裏腹に、甘くないシリアスさが魅力。7.「デブエルベテ」は、私的にはイチオシの楽曲の一つで、いい意味でのこの“不安感”がカルラ・モリソンの魅力だと感じる。13.「トド・パサ」は、セカンド・アルバムにして堂々とした完成度が感じられる好曲だと思う。[収録曲]1. Un beso2. Flor que nunca fui 3. Vez primera4. Azúcar morena5. No vuelvo jamás6. Cercanía7. Devuélvete8. Mi secreto9. Tierra ajena10. Yo vivo para ti11. Tú atacas12. Mil años13. Todo pasa2015年リリース。 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年08月31日
コメント(0)
-

ロス・ラヴキルズ 『ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)』
骨太のメキシコ大衆ロック・バンドによるセルフ・タイトル作 ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)は、2010年に結成されたメキシコのロック・バンド。詳しい情報に関しては、よくわからないことだらけなのだけれど、結成まもなく出された最初の盤が、セルフ・タイトルのこの『ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)』ということのようだ。バンド名の“Lovekills (Love Kills)”は、かのフレディ・マーキュリーの楽曲を思い起こさせるが、それと関係があるのかどうかもよくわからない。 メンバーは、ロべ・マルティネス(Robe Martínez,ギター&ヴォーカル)、マルセロ・メンドーサ(Marcelo Mendoza, ベース&ヴォーカル)、ラウリオ・ルイス(Raulio Ruíz, ギター)、ロッド・ビエイラ(Rod Vieyra, ドラム)という4人構成で、メキシコシティを起点に活動しているという。とはいえ、このデビュー時点では、マルティネスとメンドーサはいたものの、残る2人の名はなく、キケサン(QuiqueSan, ギター&コーラス)なるメンバーがクレジットされている。また、バンドが当初結成されたのはメキシコ北部のコアウィラ州トレオンとのことで、本盤も同地でレコーディングされている。 本盤は、デビュー作といっても、7曲入りのミニアルバムと呼べるヴォリュームのもの。プロデュースを担当したのは、マウリシオ・テラシーナ(Maurizio Terracina)というメキシコ/イタリア国籍の音楽プロデューサーである。メキシコ・ロック界では知られた人物で、独立系のバンドなどのプロデュースを積極的に行ってきたプロデューサーである。実際、1曲1曲の仕上がりの精度の高さは、このプロデューサーの力量に負う部分が大きいのではないかという気がする。 注目曲としては、1.「トゥ・シレンシオ(あなたの沈黙)」の端正で重いサウンドがいい。2.「ブスカンド・カリフォルニア(カリフォルニアを探して)」は、国境を越えてカリフォルニアでの新たな人生を目指すというベタなテーマだが、サウンド面ではベタにはならず、しっかりとした演奏に仕上がっているところに好感が持てる。4.「エウフォリカ」は1.と並んで骨太のサウンドでしっかりと聴かせる好曲。さらにハードな楽曲としては、やや実験的な6.「アウトデストルクティーバ(自爆的)」がいい。硬派な演奏とガラスの向こう側から歌っているかのようなヴォーカルの組み合わせというのは、なかなか決まっていると思うのだけれど。[収録曲]1. Tu silencio2. Buscando California3. No te olvido4. Euphorica5. Inocente6. Autodestructiva7. Zombie2010年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月28日
コメント(0)
-

L.A.ガンズ 『“砲”(L.A. Guns)』
ロサンゼルスの熱きHR/HMシーンの立役者 ガンズ・アンド・ローゼズが2つのバンドの元メンバーの融合によって成立したということはよく知られている。その2つのバンドというのは、L.A.ガンズとハリウッド・ローズだった。ハリウッド・ローズの方は1989~90年に再結成されたものの、作品リリースはなかった。他方、L.A.ガンズの方は、早々にガンズ・アンド・ローゼズを離脱したトレイシー・ローズが中心となって再興され、アルバムを発表していくことになった。 トレイシー・ローズを中心に実力者揃いのメンバーはデビュー前から注目され、1988年に発表されたのが、ファースト作となるセルフ・タイトル盤『L.A.ガンズ(L.A. Guns)』(邦盤では『“砲”』)であった。“L.A.メタル”という括り方がなされることもあるが、文字通り“L.A.(ロサンゼルス)”の名を冠する彼らは、1980年代後半、西海岸発のHR/HMの立役者の一人といえそうな勢いを持っていた。 1.「ノー・マーシー」は、スピード感のある重くかつ軽快な演奏が魅力。2.「セックス・アクション」は、リリースされて聴いた当時から特に印象に強く残っているナンバーで、この不良っぽさも彼らの大事な持ち味の一部分である(ヒットはしなかったものの、その当時にはシングルとしてもカットされていた模様)。4.「エレクトリック・ジプシー」(こちらもシングル化された)は、たたみかけるような演奏が筆者的にはお気に入り。 7.「クライ・ノー・モア」は、小休止的なギターのアンサンブル風の小品で、じっくり聴かせる名曲の8.「ワン・ウェイ・チケット」のイントロ的な役割も果たしている。アルバム終盤をきれいにまとめようという感じではなく、勢いづいたままの10.「シュート・フォー・スリルズ」、11.「ダウン・イン・ザ・シティ」で終えているのも、若々しいと言えばそれまでかもしれないが、筆者としては好感が持てる。全体として、若さがほとばしり(そう考えると、L.A.の表記のピリオドが“ガイコツ”なのも、今となっては微笑ましい)、西海岸のメタルシーンを反映したお手本あるいはモデル的な作品。そんな風な感想を個人的には持っているアルバムだったりする。[収録曲]1. No Mercy2. Sex Action3. One More Reason4. Electric Gypsy5. Nothing to Lose6. Bitch Is Back7. Cry No More8. One Way Ticket9. Hollywood Tease10. Shoot for Thrills11. Down in the City12. Winters Fool(日本盤リイシュー時のボーナス・トラック)1988年リリース。 “砲" [ L.A.ガンズ ] 【輸入盤CD】【新品】L.A. Guns / L.A. Guns 【K2017/11/3発売】(LAガンズ) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月24日
コメント(0)
-

マロ 『マロ(Malo)』
ホルヘ・サンタナのバンドによるラテン・ロックの好盤 マロ(Malo)は、カルロス・サンタナの実弟であるホルヘ・サンタナ(Jorge Santana,2020年に68歳で没)を中心とするバンドであった。前身のバンドであるマリブスのメンバーと別のバンドのメンバーを混合する形で、1970年代初頭にマロは誕生した。ホルヘ・サンタナ(ギター)のほか、アルセリオ・ガルシア(ヴォーカル、パーカッション)、パブロ・テジェス(ベース)、アベル・サラテ(ギター)ら計8人から成り、通常のロック・バンドの編成に含まれる楽器以外に、管楽器(フルート、トランペットなど)や打楽器(コンガ、ティンバルなど)がフィーチャーされているのが特徴である。1972年、このバンドの最初のアルバムとして発表されたセルフ・タイトル作が、本盤『マロ(Malo)』であった。ジャケットのデザインには、メキシコ人画家ヘスス・エルゲーラによる、アステカの擬人化された神話の作品が使われている。 メキシコ生まれのホルヘは、サンフランシスコのラテン系の多い地区(ミッション地区)で育ったという。同じく中心人物の一人アルセリオはプエルトリコ系、パブロはニカラグア生まれでティーンエージャーの時の移住者であった。まさしくそうした西海岸のラテンのストリートの雰囲気に、実兄のカルロス率いるサンタナが切り拓きつつあったジャズやラテンを含みインプロヴィゼーショナルな新たなロックのスタイルがうまく融合した成功例だったと言えるのではないだろうか。どの楽曲も短くキャッチーにというよりは、個性が強く長い尺(収録曲はいずれも6~7分を超える)で、しっかりと聴かせるナンバーが並ぶ。 本盤の収録曲のうち、最も知られているのは、5.「スアベシート」であろう。哀愁漂うメロディに軽いラテンのリズム、そして英語の詞を聴かせるというスタイルがチカーノやラテン系の人々に受け入れられたのだろう。これと同じく、ラテンの若者たちに人気を博した曲として、4.「いとしのネナ」も収められている。詞が英語とスペイン語の両方であること、音楽的には、サルサのようでもあり、ソウルのようでもあり、でもやっぱりロックであるというのが印象的なナンバーとなっている。 ほかに、個人的好みに基づいた本盤の聴きどころとしては、まず、1.「パナ」が挙げられる。ラテンの雰囲気が緊張感ある演奏とともに展開されるというのがいい。2.「さよならを言うだけ(ジャスト・セイ・グッドバイ)」は、シリアスなギター演奏が聴きどころ。6.「平和(ピース)」は、プログレッシヴな雰囲気の楽曲で、ヴォーカル、トランペット、ギターそれぞれの鬼気迫る演奏が9分を超える長尺の中でじっくりと堪能できる。[収録曲]1. Pana2. Just Say Goodbye3. Café4. Nena5. Suavecito6. Peace1972年リリース。 【中古】 マロ MALO/マロ 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月20日
コメント(0)
-
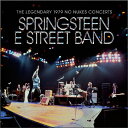
ブルース・スプリングスティーン&E・ストリート・バンド 『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』(2/2)
当時の勢いと熱気が満載のライヴ盤(後編) (前編からの続き) アルバム収録曲をざっと見ていきたい。1枚目の冒頭3曲は、『闇に吠える街』を代表する楽曲が並ぶ。1.「暗闇へ突走れ」はライヴで見せ場へとなっていったレパートリーで、2.「バッドランズ」と3.「プロミスト・ランド」はそれぞれ元アルバムのA面・B面のオープニング曲である。続く2曲は、リリース直前の『ザ・リバー』からのナンバーで、表題曲4.「ザ・リバー」でじっくり聴かせ、5.「愛しのシェリー」で盛り上げる。そして、1枚目の終盤は、サード作『明日なき暴走』所収の6.「涙のサンダーロード」、ファースト作収録の7.「ジャングルランド」という、じっくり聴かせる代表的楽曲が連続する。 2枚目に移ると、最初の2曲はこの時点のレパートリーの中で特に盛り上がるナンバーが並んでいる。セカンド作収録の1.「ロザリータ」は、12分という長さを感じさせず、むしろメンバー紹介なども含めてこれだけ盛り上げて楽しませるにはこの時間が不可欠といった演奏を披露している。 2.「明日なき暴走(ボーン・トゥ・ラン)」は、若いころの彼の代名詞的ナンバーで、上記サード作のタイトル・トラック。3.「ステイ」は、モーリス・ウィリアムスとゾディアックスの1960年の全米No.1ヒット曲。続く4.「デトロイト・メドレー」と5.「クォーター・トゥ・スリー」は、ライヴでのお得意のレパートリーである。前者は「デヴィル・ウィズ・ザ・ブルー・ドレス・オン」、「グッド・ゴーリー・ミス・モーリー」、「シー・シー・ライダー」、「ジェニー・テイク・ア・ライド」という、1960年代をスプリングスティーンのバンドらしくカバーしたロック・メドレー。後者は、ゲイリー・US・ボンズの1961年の全米No.1ヒット曲のカバーである。アルバムを締めくくる6.「レイヴ・オン」は1958年のバディ・ホリーのヒットでも知られるナンバー。このように、2枚組の本作の終盤にかけての演奏は、ライヴでしか味わえないスプリングスティーンのパフォーマンスを楽しむことができる。[収録曲](Disc 1)1. Prove It All Night 2. Badlands 3. The Promised Land4. The River5. Sherry Darling6. Thunder Road 7. Jungleland(Disc 2)1. Rosalita (Come Out Tonight) 2. Born to Run 3. Stay4. Detroit Medley: Devil with the Blue Dress On~Good Golly Miss Molly~C.C. Rider~Jenny Take a Ride 5. Quarter to Three6. Rave On1979年9月21日(I: 6-7, II: 1-2, 4, 6)、同22日(1.-5, II: 3, 5)録音。2021年リリース。 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ノー・ニュークス・コンサート 1979(完全生産限定盤/DVD付)/ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 【送料無料】[枚数限定][限定盤]THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERTS (2CD+DVD) 【輸入盤】▼/ブルース・スプリングスティーン&Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2025年08月17日
コメント(0)
-
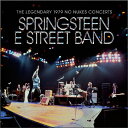
ブルース・スプリングスティーン&E・ストリート・バンド 『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』(1/2)
当時の勢いと熱気が満載のライヴ盤(前編) アメリカン・ロック界の大御所、ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)の若き日のライヴで、40年以上の歳月を経て2021年にリリースされたのが、本盤『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』である。 21世紀に入った頃からだろうか、巷では、いわゆる“蔵出し”ライヴ系のリリースが溢れるようになった。そうした古い音源のリリースには、正直なところ、玉石混交という感が否めない。けれども、いざリリースされて聴いてみた時、何十年か前のライヴでこれほどに感動したのは、どちらかと言うと珍しい例だったというふうに記憶している。 収録されているのは、2枚組で全13トラック。音源には、ボブ・クリアマウンテンによる新たなリミックスが施されている。このライヴの前年(1978年)にリリースされた『闇に吠える街』と1975年の出世作『明日なき暴走』、そしてライヴのレパートリー曲が中心となっている。その一方で、リリース目前の『ザ・リバー(ザ・リヴァー)』に収録されることになるナンバーからも2曲が披露されている。 E・ストリート・バンドの息の合った絶妙の演奏は、これ以前のライヴでもよく知られているし、スタジオ作ながら『ザ・リバー』にも顕著である。また、後にリリースされた大部なライヴ作『ザ・ライヴ』(1975~85年の音源)の時期を考えると、すでに完成された演奏力が存分に発揮されていることもうかがえる。その演奏に加えて、ゲスト陣も目を引くもので、ジャクソン・ブラウンにトム・ペティ、さらにはローズマリー・バトラー(参考過去記事)なんかが参加している。 そのようなわけで、ライヴ・パフォーマンスの質が高かった(けれども1984年以降の『ボーン・イン・ザ・U.S.A.』の妙な熱狂はまだ訪れていない)時期の、優れた演奏が堪能できる盤であると、全体としては言えるだろう。 長くなってきたので、いったんここで稿を改めて、後編に続けたい(曲目等の情報は後編を参照)。 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ノー・ニュークス・コンサート 1979(完全生産限定盤/DVD付)/ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 『ノー・ニュークス・コンサート 1979 (2CD+Blu-ray)【完全生産限定盤】 [ ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド ] 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2025年08月16日
コメント(0)
-

バッド・カンパニー 『ストレート・シューター(Straight Shooter)』
デビュー盤からの勢いを維持したセカンド・アルバム バッド・カンパニー(Bad Company)は、1970年代前半、フリー(参考過去記事(1) ・(2) ・(3) )での活躍を経たポール・ロジャース(ヴォーカル)、サイモン・カーク(ドラムス)らが結成したバンド。他のメンバーは、元モット・ザ・フープルミック・ラルフス(ギター)、元キング・クリムゾンボズ・バレル(ベース)という面々だった。 1974年発表に発表されたこのバンドのデビュー盤は、見事なセールスを記録し、全米チャート1位、英チャート3位を記録した。そして、続く翌年の本盤『ストレート・シューター(Straight Shooter)』もそれに劣らぬほどの成功作となり、英米ともに3位のヒット作となった。 冒頭の1.「グッド・ラヴィン」と2.「フィール・ライク・メイキン・ラヴ」はともにシングルとしてもリリースされたナンバー。前者はこのバンドらしい端正なロック・ナンバー。後者はなかなかの好曲で、全米のシングルチャートで10位となった。 他に筆者が気に入っているナンバーを少し挙げておくと、4.「シューティング・スター」は適度な肩の力の抜け具合がいい。無論、ハードな楽曲がよくないという意味ではなく、本盤の収録曲中でそうした方向性で頭一つ抜けているのが5.「ディール・ウィズ・ザ・プリーチャー」だと思う。全体として言えるのは、ハードな楽曲と少し控えめな楽曲がうまく配されている点と、ポール・ロジャースによる楽曲のよさが目立つというのが、本盤の特徴ということになるのかもしれないと感じる。[収録曲]1. Good Lovin' Gone Bad2. Feel Like Makin' Love3. Weep No More4. Shooting Star5. Deal with the Preacher6. Wild Fire Woman7. Anna8. Call on Me1975年リリース。 【中古】英LP Bad Company Straight Shooter ILPS9304 ISLAND /00260 次のブログランキングのサイトに参加しています。 時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月14日
コメント(0)
-

INDEX更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも ありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年08月11日
コメント(0)
-

ロッド・テイラー 『ロッド・テイラー(Rod Taylor)』
詩人/シンガーソングライターによる幻の1枚 ロッド・テイラー(Rod Taylor)は、1947年ノース・キャロライナ州生まれのミュージシャン。1970年代に入ると西海岸に移り、ミュージシャンとして活動するだけでなく、詩集を出版したりもしている。そんな彼が唯一残した作品が、1973年発表のセルフ・タイトル盤『ロッド・テイラー(Rod Taylor)』である。 1971年に設立されたアサイラム・レコードにとって、トム・ウエイツの次に契約した13組目のアーティストが、このロッド・テイラーだったという。日本では“第2のレオン・ラッセル”の触れ込みで発売されたらしいが、日本国内どころかアメリカでもさっぱり売れなかったようである。 確かに、売れなくても仕方なかった地味さがある。失礼ながら、名前からして地味だし、アルバムもやや陰気なセルフ・ポートレート写真で、淡々と歌を伝えるシンガーソングライター然とした雰囲気が醸し出されている(とはいえ、後述のメンバーを含む演奏自体は、必ずしも地味というわけではない)。全曲が次作で、プロデュースはチャック・プロトキン(ボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンの作品のプロデュースでも知られる)が丁寧に仕事をしている。演奏面では、ライ・クーダー(ギター、マンドリン)、ジェシー・エド・デイヴィス(ギター)、ジョニ・ミッチェル(バッキング・ヴォーカル)など、なかなか豪華なミュージシャンたちがサポートしている。 いくつかの曲をあげながら、アルバムを見渡しておきたい。オープニングの1.「アイ・オウト・トゥ・ノウ」は、ひたむきに詞を紡ぐシンガーソングライター的な楽曲。2.「クロスローズ・オブ・ザ・ワールド」は、南部風の泥臭さを伴うナンバーで、こういった曲は案外、筆者の好みだったりする。5.「メイキング・ア・ウェイ」は、どこかレオン・ラッセル風のテイストで、こういう楽曲でうまく火がついていたならば、ひょっとして売れたのかもと思わないでもない。ピアノをバックにした7.「危険な生活のブルース」も、同じくレオン・ラッセル風と言えるかもしれない。12.「ザ・ラスト・ソング」は、デビュー盤の締めくくりにこのタイトル(“最後の歌”)はどうかという気がしないでもないが、楽曲としてはなかなかの好曲。 1970年代初頭、何人ものシンガーソングライターが現れては消えていった。テイラー自身も述べているように、その中では最も成功した口だったのだろう。その後、少しの活動歴があったようだが、テイラーの名は音楽史の表舞台には残らなかった。とはいえ、アルバムという形で残された本盤は密かな1枚として聴き継がれていくことだろう。[収録曲]1. I Ought to Know2. Crossroads of the World3. Railroad Blood4. Double Life5. Making A Way6. Sweet Inspiration7. Livin' Dangerous Blues8. Something Old9. Man Who Made It Fall10. Lost Iron Man11. For Me12. The Last Song1973年リリース。 【中古】CD ロッド・テイラー ロッド・テイラー AMCY2901 ASYLUM /00110 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月10日
コメント(0)
-

ジョー・ペリー・プロジェクト 『熱く語れ!(Let the Music Do the Talking)』
エアロスミスのメンバーによるプロジェクト盤 ジョー・ペリー(Joe Perry)は、1950年米国出身のギタリスト。スティーヴン・タイラーの欠かせないパートナー(これら2人のコンビは“トキシック・ツインズ”と呼ばれる)で、ロック・バンド、エアロスミスを牽引してきた。そんなペリーがソロ・プロジェクトを動かしたのは、1980~83年のことだった。タイラーとの確執からエアロスミスを脱退し(後に和解してバンドに復帰)、計3枚のアルバムをジョー・ペリー・プロジェクト(Joe Perry Project)の名義で発表した。 本盤『熱く語れ!(Let the Music Do the Talking)』はその第1弾で、1980年にリリースされた。上記の3枚のアルバムの内では最も売り上げを伸ばした(全米47位)アルバムである。大部分の曲(共作も含めると全曲)がジョー・ペリーのペンによるもので、彼以外のメンバーは、ヴォーカルにラルフ・モーマン(ただし、ペリー自身がリード・ヴォーカルという曲も複数ある)、ベースにデヴィッド・ハル、ドラムにロニー・スチュワートといった布陣だった。 1.「熱く語れ!」はアルバムの表題曲。この曲名およびアルバム名の原題を直訳すると、“音楽に語らせよ”。結局のところ、音楽に語らせるのは演奏者なのだから、演奏者が“熱く語って”も一緒なのかもしれないが、実際にこの曲を聴いてみると、確かに“音楽が語りだしている”という風に思える(ちなみに、この1.はエアロスミスのアルバム『ダン・ウィズ・ミラーズ』でも演奏されている)。1.と並んで見事な演奏で音楽に語らせていると思えるのは、3.「ディスカウント・ドッグズ」。とにかくジョー・ペリーのギターがカッコよく炸裂する。 アルバムにはジョー・ペリーがヴォーカルを担当する楽曲も収められている。筆者の好みに照らしてのその中でのベストは、10弦ギターを使用しての7.「ザ・ミスト・イズ・ライジング」、次いで4.「シューティング・スター」といったところか。また、インストルメンタル・ナンバーも1曲収められている。5.「ブレイク・ソング」がそのナンバーだが、短い楽曲ながら、ジョー・ペリーがこれでもかとギターを聴かせるという演奏に仕上がっている。 アルバム終盤の8.「レディ・オン・ザ・ファイアリング・ライン」、9.「ライフ・アット・ア・グランス」まで演奏の勢いは衰えず、特に9.のリズムに乗ったスピード感は、聴いた後にスッキリした感じになる。全米チャートで47位どまりだったとのことだが、記憶の狭間に埋もれさせてしまうのはもったいないと好作だと個人的には思う。[収録曲]1. Let the Music Do the Talking2. Conflict of Interest3. Discount Dogs4. Shooting Star5. Break Song6. Rockin' Train7. The Mist Is Rising8. Ready on the Firing Line9. Life at a Glance1980年リリース。 【中古】 熱く語れ!/ジョー・ペリー・プロジェクト 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月07日
コメント(0)
-

ジャッキー・バイアード 『ハイ・フライ(Hi-Fly)』
ピアノ演奏の多彩ぶりが発揮された盤 ジャズ・ピアノ奏者のジャッキー・バイアード(ジャキ・バイアード,Jaki Byard)の3枚目のリーダー作に当たる『ハイ・フライ(Hi-Fly)』は、彼が残した吹き込みの中でもベストのものと言われたりする。このバイアードという人は、“多彩多芸なピアニスト”とも評される。さまざまなスタイルのジャズ・ピアノを取り込んだ演奏がこの人の特徴であり、しかもトランペットやサックスも演奏できるというマルチな演奏者でもあった。 本盤は、ベース(ロン・カーター)とドラムス(ピート・ラロカ)との3ピースというシンプルな構成ながら、確かにバイアードのピアノの多彩さが際立っている。そうしたピアノ演奏を可能にしているのは、残る2人の安定感というのはもちろんなのだけれど、個人的にはロン・カーターのベースがとりわけいい味を出していると感じる。以下、収録曲のうちで、特に注目したい演奏をいくつか取り上げてみたい。 まず、表題曲の1.「ハイ・フライ」はランディ・ウェストンのペンによるナンバー。ピアニストであるウェストンらしい楽曲をバイヤードらしく解釈して弾きこなしていて、派手さはないが、好演奏と言えるように思う。バイアードの自作曲は3曲(2.,4.,5.)が収められているが、なかでも意欲的で実験的なのは5.「ヒア・トゥ・ヒアー」。どういう展開の演奏になっていくのか、聴いていて飽きない。さらに注目したいのは、7.「ラウンド・ミッドナイト」。演奏そのものの幅と奥行きが感じられると言えばよいのだろうか、三次元的な深さが感じられる演奏になっている。このディメンショナルな広がりとでも言えそうなものが筆者は気に入っていて、この7.から次の8.「ブルース・イン・ザ・クローセット」への流れは本盤の聴きどころとも言えるように思う。[収録曲]1. Hi-Fly2. Tillie Butterball3. Excerpts from "Yamecraw4. There Are Many Worlds5. Here to Hear6. Lullaby of Birdland7. 'Round Midnight8. Blues in the Closet[パーソネル、録音]Jaki Byard (p), Ron Carter (b), Pete La Roca (ds)1962年1月30日録音。 【中古】 ハイ・フライ/ジャッキー・バイアード(p),ロン・カーター(b),ピート・ラロカ(ds) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月04日
コメント(0)
-

エロール・ガーナー 『グレイテスト・ガーナー(The Greatest Garner)』
ガーナー初期の、控えめで味わい深いトリオ盤 左利きで、楽譜を読めず、並外れた音に対する感性を持つというエロール・ガーナー(Erroll Garner)。彼のピアノは、確かにくせがあるけれども、多くの人を魅了してきた。本盤『グレイテスト・ガーナー(The Greatest Garner)』は、1949から50年にかけてのトリオ演奏が収められたもので、時期としては、有名曲「ミスティ」(関連過去記事)や代表盤『コンサート・バイ・ザ・シー』よりも前の、彼の最初期に当たるものである。 収められた演奏は、バラード系のおとなしめの楽曲が中心。エロール・ガーナーのピアノの味わいを落ち着いてじっくり楽しむという趣の盤と言える。2つのセッションの音源となっていて、トリオの面々は過半の演奏では、ベースがレナード・ガスキン、ドラムスがチャーリー・スミス。他方、いくつかの曲では、ベースがジョン・シモンズ、ドラムスがハロルド・ウィングとなっている(詳細は下記のデータを参照)。 個人的に気になる演奏をいくつか見ておきたい。1.「今宵の君は(ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト)」は、テンポよくガーナー節が展開される。2.「ターコイズ」は、キラキラとした幻想的な、ある種ガーナーらしいというのとは異なる雰囲気を楽しめる。これと似た方向性を持つ演奏としては、7.「スカイラーク」や9.「フラミンゴ」、さらには10.「夢(レヴェリー)」が挙げられる。他方、彼らしいピアノのリズム感を楽しめる楽曲も複数あるが、おすすめは6.「アイ・メイ・ビー・ロング」や12.「捧ぐるは愛のみ(アイ・キャント・ドゥ・エニシング・バット・ラヴ)」。“ビハインド・ザ・ビート”と表現される彼の左手の動作とその効果は、ツボにはまると中毒性がある。なお、現行のCD盤では、後から吹き込まれた方の1950年5月のセッションの未収録曲がボーナス曲として追加されており、それら4曲の演奏も本来の12曲に劣らない質の高い演奏であることがうかがえる。[収録曲]1. The Way You Look Tonight2. Turquoise3. Pavanne4. Impressions5. Confessin'6. I May Be Wrong7. Skylary8. Summertime9. Flamingo10. Reverie11. Blue and Sentimental12. I Can't Do Anything But Love[パーソネル、録音]1~4, 7, 9~12:Erroll Garner (p), Leonard Gaskin (b), Charlie Smith (ds)1949年7月20日録音。5~6, 8:Erroll Garner (p), John Simmons (b), Harold Wing (ds)1950年5月12日録音。 【中古】CD エロール・ガーナー(p) グレイテスト・ガーナー WPCR27374 ATLANTIC 未開封 /00110 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月01日
コメント(0)
-

グレイト・スペックルド・バード 『グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)』
カントリー・ロックの好盤 グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)は1969年に結成されたカナダのカントリー・ロック・バンド。フォークないしはカントリーのデュオだったイアン(ヴォーカル、ギター)とシルヴィア(ヴォーカル、ピアノ)のタイソン夫妻(Ian & Sylvia Tyson)を中心に、エイモス・ギャレット(ギター、ヴォーカル)らが参加したバンド(メンバーは随時変化したが、本盤録音時にはエイモス・ギャレットに加えて、スティール・ギターにバディ・ケイジ、ドラムにN.D.スマート、ベースにケン・カルマスキーという布陣)だった。なお、バンド名は、カントリー歌手のロイ・エイカフの楽曲名に因む。このバンド単独の名義でリリースされた唯一の盤がこのセルフタイトル作の『グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)』であった。権利の関係で入手困難が続いたため、“カントリー・ロックの幻の名盤”と呼ばれていた盤である。プロデュースはトッド・ラングレンで、彼にとって初めて他のアーティストのアルバム・プロデュースを担当した作品となった。 そのようなわけで、カントリー・ロックの歴史を語るうえで必ずしも王道とは言えない作品だが、カントリー・ロック作品としてかなりの好盤であることは間違いない。ザ・バーズやバッファロー・スプリングフィールドといったバンドがムーヴメントを起こしたり引っ張って行ったりしたのに対し、このグレイト・スペックルド・バードの活動は儚かった。そんな彼らの演奏は、シリアスさの一方で、どこかしらのどかさや楽しさが感じられるように思う。それは、おそらくは、このバンドがカントリー音楽の先にこの音楽をとらえていて、新たなことをやるという気負いよりも、どちらかというと各々のメンバーの特徴を出しながら楽しんで演奏するという雰囲気が強かったせいではないかと想像してみたりする。 注目曲をいくつか見ておきたい。まず、1.「ラヴ・ホワット・ユア・ドゥーイン・チャイルド」は、イアンのヴォーカルとエイモス・ギャレットのギターが中心となって醸し出すスリリングな空気感がたまらない。3.「トラッカーズ・カフェ」はシルヴィアのヴォーカルが前面に出たいかにもカントリー調のナンバーで、リイシューのCDには、ボーナストラックとして、ライヴ・ヴァージョン(13.)が収められている。 アップテンポでノリのよい6.「ブラッドショット・ビホルダー」は、イアンのナンバーで、テンポよいドラムと小気味よいギターが印象的。10.「リオ・グランデ」は、イアンとエイモス・ギャレットの共作で、楽曲そのもののよさが光る。アルバムを締めくくる12.「ウィ・セイル」はカントリー・バラードとでも呼べばいいだろうか。スローで合唱風のナンバーで、目を閉じるとメンバーたちの姿が浮かんでくるような1曲である。[収録曲]1. Love What You're Doing Child2. Calgary3. Trucker's Cafe4. Long Long Time to Get Old5. Flies in the Bottle6. Bloodshot Beholder7. Crazy Arms8. This Dream9. Smiling Wine10. Rio Grande11. Disappearing Woman12. We Sail13. New Trucker's Cafe -live-(CD追加トラック)1969年リリース。 【中古】CD グレイト・スペックルド・バード グレイト・スペックルド・バード CDSOL7194 /00110 【中古】 グレイト・スペックルド・バード/グレイト・スペックルド・バード 下記のランキングサイトに参加しています。お時間の許す方は、 バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年07月29日
コメント(0)
-

ブラック・サバス 「パラノイド(Paranoid)」ほか
オジー・オズボーンよ、永遠なれ… つい1週間ほど前に書いた記事(過去記事はこちら)に続き、またしても訃報です。ブラック・サバスのヴォーカリストで、自身のバンドでも活躍したオジー・オズボーン(Ozzy Osbourne)が2025年7月22日に亡くなりました。パーキンソン病を公表していたものの、今月初旬に引退ライヴのステージに姿を見せたばかりだったのですが、それからわずか17日後のことで、享年76歳でした。 オジー・オズボーンといえば、まずはブラック・サバス(Black Sabbath)での活動が思い起こされます。1970年にデビューし、同年のセカンド作では大きなシングル・ヒットも残しました。まずは、彼らの代表曲の一つで、同セカンド作のタイトル・チューンでもある「パラノイド」をお聴きください。 続いては、ブラック・サバスを脱退後、ソロで自身のバンドを率いての活動期の楽曲から、個人的に印象に残っているものを一つ。1983年発表のアルバム『月に吠える』の表題曲で、同盤からの第1弾シングルとなった曲で、「月に吠える(Bark at the Moon)」です。 もう1つ、ブラック・サバスの上記のアルバム所収のナンバーで、往年のプロレス・ファンにも懐かしいナンバーです。アニマルとホークからなるザ・ロード・ウォリアーズの入場曲としても使用された「アイアン・マン(Iron Man)」です。同じタイトルということもあり、コミック作品の『アイアン・マン』の映画でも使用されました。ライヴのステージでのオジー・オズボーンの雄姿をご覧ください。 アルコール・薬物の問題や、コウモリ食いちぎり事件など世間を騒がせたり破天荒な行動が注目されたりするミュージシャンでもありましたが、いまは安らかに眠らんことをお祈りします。R.I.P.追記: 上でプロレスの話題にも触れましたが、続いてハルク・ホーガンが鬼籍に入りました。同様にご冥福を心からお祈りします。[収録アルバム]Black Sabbath / Paranoid(1970年)Ozzy Osbourne / Bark at the Moon(1983年) 【輸入盤CD】【新品】Black Sabbath / Paranoid【K2016/8/5発売】(ブラック・サバス) Ozzy Osbourne オジーオズボーン / Bark At The Moon: 月に吠える 【CD】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年07月26日
コメント(0)
-

スティーヴィー・ニックス 『ロック・ア・リトル(Rock A Little)』
実力に裏打ちされたサード作 フリートウッド・マックへの加入によって、『ファンタスティック・マック』(1975年)以降のこのバンドの躍進を支えた重要人物が、スティーヴィー・ニックス(Stevie Nicks)だった。“歌姫”とか“妖精”とか呼ばれるものの、こうした形容は、バンドのお飾り的な“顔”という意味ではなく、ヴォーカリストとしての力量を称えるものと捉えたものと考えるべきであろう。 1985年発表の『ロック・ア・リトル(Rock A Little)』は、フリートウッド・マックが各メンバーのソロ活動を活発化させた時期の作品である。大きなヒットとなった『麗しのベラ・ドンナ』(1981年)から数えて、スティーヴィー・ニックスのソロ・アルバムとしては3作目に当たる。 ジミー・アイオヴィンら複数のプロデューサーを起用しているが、全体的に1980年代特有のきらびやかなサウンドが展開されている。聴きどころとしては、シングルとして全米4位を記録した7.「トーク・トゥ・ミー」。それから、同じくシングル・カットされて米国で16位となった1.「アイ・キャント・ウェイト」。いずれもリスナーのツボを押さえた楽曲で、スティーヴィー・ニックスのヴォーカルの魅力が全開のナンバーだと思う。 他に個人的にいいと思う曲をいくつか挙げておくと、アルバム表題になっている2.「ロック・ア・リトル」、オーストラリアのみでシングル発売された5.「インペリアル・ホテル」、8.「ザ・ナイトメアー」。あと、アルバムの最後を飾る11.「誰かあなたに(ハズ・エニワン・エヴァー・リトン・エニシング・フォー・ユー?)」。この曲は、シングル・カットされたものの、大きなヒットとはならなかったのだけれど、アルバムの中で聴くと存在感の大きいスロー・ナンバーだ実感する。[収録曲]1. I Can't Wait2. Rock a Little (Go Ahead Lily)3. Sister Honey4. I Sing for the Things5. Imperial Hotel6. Some Become Strangers7. Talk to Me8. The Nightmare9. If I Were You10. No Spoken Word11. Has Anyone Ever Written Anything for You?1985年リリース。 【中古】CD Stevie Nicks Rock A Little CP325098 EMI, Modern Records /00110 ロック・ア・リトル【CD、音楽 中古 CD】メール便可 ケース無:: レンタル落ち 【ご奉仕価格】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年07月25日
コメント(0)
-

INDEXページを更新しました
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。1か月以上、更新していませんでしたが、この間の記事へのリンクを追加しています。INDEXページへは、下記リンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つ でもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月21日
コメント(0)
-
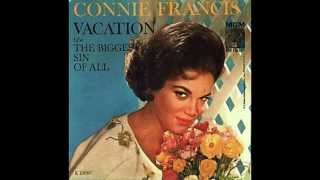
コニー・フランシス 「ヴァケーション(Vacation)」「可愛いベイビー(Pretty Little Baby)」ほか
稀代の女性シンガー、追悼 コニー・フランシス(Connie Francis)が亡くなったと報道されました。骨盤骨折での入院から容体が悪化し、本年(2025年)7月16日に87歳で逝去したとのことです。往年の偉大なる女性シンガーの追悼ということで、今回は彼女の曲をいくつか取り上げたいと思います。 彼女の代表曲と言えば、個人的には断然これというナンバーから。1962年に発表されたヒット曲、「ヴァケーション(Vacation)」です。 この曲は、日本でもいろんな人によってカバーされて知られていますが、なんとその日本語詞でコニー・フランシス本人が吹き込んだというヴァージョンも存在しています。余談ながら、イタリア語と日本語の発音が似ているせいかとは思いますが、イタリア系の彼女にとって、日本語の詞は歌いやすかったと本人も述べていたそうです。 続いては、1958年のヒット曲、「間抜けなキューピッド (Stupid Cupid)」です。往時の若きコニー・フランシスの映像とともにお楽しみください。 もう1曲、アメリカではアルバム収録曲の一つに過ぎなかったのですが、日本では超有名曲となった「可愛いベイビー(Pretty Little Baby)」です。 この「可愛いベイビー」が日本で有名になったのは、本邦でカバーされてヒットしたためにほかなりません。いろんな日本のシンガーがこの曲をカバーしていますが、やはり有名なのは中尾ミエによるものでしょう。そのようなわけで、最後に、中尾ミエによる「可愛いベビー」(“ベイビー”ではなく“ベビー”という表記になっています)をお聴きください。 コニー・フランシスのご冥福をお祈りします。R.I.P. 定番ベストセレクション::ヴァケイション~コニー・フランシス [ コニー・フランシス ] SINGLES COLLECTION (3CD) 【輸入盤】▼/CONNIE FRANCIS[CD]【返品種別A】 【輸入盤CD】【新品】Connie Francis / Absolutely Essential 3CD Collection【K2017/8/4発売】(コニー・フランシス) 輸入盤 CONNIE FRANCIS / 20TH CENTURY MASTERS : MILLENNIUM COLLECTION [CD] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月20日
コメント(0)
-

リッキー・マーティン 「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ(Livin' La Vida Loca)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その30) 1千万アクセスということで、ここまで29曲を紹介してきましたが、今回で30回の区切りです。最後は、景気のいいダンサブルな曲で締めたいと思います。 アメリカ領プエルトリコ出身のリッキー・マーティン(Ricky Martin)は、少年時代から芸能界で活躍しており、やがてメキシコを拠点にソロの歌手として成功を収めました。そんな彼の代表曲と言えば、このナンバー、「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ(Livin' La Vida Loca)」です。まずは、ビデオクリップをご覧ください。 この曲がヒットしたのは1999年のことでしたが、続いては、もう少し後のライヴでのパフォーマンスをご覧ください。2007年のライヴですので、リッキー・マーティンは30歳代半ばといったところでしょうか。相変わらずノリのよさとキレを見せています。 よく知られているように、この曲は、郷ひろみがカバーして本邦でも大きなヒットとなりました。カバー曲としてのタイトルは「GOLDFINGER '99」で、彼の長いキャリアの中でも上位のヒット曲となりました。 ここまでの30回にお付き合いくださった方に心より感謝いたします。次からは通常の更新に戻ります。[収録アルバム]Ricky Martin / Ricky Martin(1999年) 【中古】 【輸入盤】Ricky Martin/リッキー・マーティン 【中古】 【輸入盤】Best of Ricky Martin/リッキー・マーティン 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月18日
コメント(0)
-

シカゴ 「素直になれなくて(Hard To Say I'm Sorry)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その29) さて、今回は1980年代前半、シカゴ(Chicago)の有名曲です。1969年にデビュー盤(過去記事)を発表し、作品を積み重ねていった彼らは、やがて音楽的方向性を変えていき、AOR的なヒット曲を放つようになっていきました。そうした趣向を典型的に示すナンバーで、彼らの代表曲の一つともなったのが、全米1位ヒットとなったこの「素直になれなくて(Hard To Say I'm Sorry)」でした。 プロデューサーのデヴィッド・フォスターの起用がこの成功を産んだわけですが、この後、シカゴはバラード路線のヒットを連発していくことになりました。もう一つ、この曲のライヴ演奏の様子もご覧いただきましょう。1984年の映像です。 ちなみに、曲の最後がシングルとはずいぶん違ってしまっていますが、これは、元のアルバムでは次の曲(「ゲット・アウェイ」)が一続きのものとして収められており、それが再現されているためということだったりします。 最後にもう一つ、年齢を重ねた後世のピーター・セテラもご覧いただきましょう。2017年の音楽祭のステージでの「素直になれなくて」です。 [収録アルバム]Chicago / Chicago 16(ラヴ・ミー・トゥモロウ)(1982年) ラヴ・ミー・トゥモロウ(シカゴ16) [ シカゴ ] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月17日
コメント(0)
-

エルヴィス・コステロ 「グッド・イヤー・フォー・ザ・ローゼズ(A Good Year for the Roses)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その28) 今回はエルヴィス・コステロ(Elvis Costello)が歌うバラード曲です。デビュー当初は、パンクやニューウェーヴ、“怒れる若者”といったイメージが強かった彼ですが、年齢とキャリアを積み重ねていくなかで、柔らかくしっとりした歌を聴かせるという魅力も姿を現しました。 「グッド・イヤー・フォー・ザ・ローゼズ(A Good Year for the Roses)」は、1981年に発表されたアルバム『オールモスト・ブルー』に収録された楽曲です。シングルとして全英チャートで6位というヒットとなったナンバーです。 このナンバーのステージでの演奏の模様も見ていただきましょう。元のリリース年からは30年ほどの時を経た、円熟のコステロの姿をご覧ください。 ところで、この曲が収められた上記のアルバムは、“カントリー&ウエスタンが含まれています”という注意書きがついており、そうした方向に寄ったアルバムでした。実際のところ、この「グッド・イヤー・フォー・ザ・ローゼズ」という曲も、コステロのオリジナル曲ではなく、カバーでした。元は、ジェリー・チェスナットが作者で、カントリー歌手のジョージ・ジョーンズ(George Jones)が1970年にアメリカでヒットさせた曲でした。そのようなわけで、ジョージ・ジョーンズのヴァージョンもお聴きください。 [収録アルバム]Elvis Costello / Almost Blue(1981年) 【輸入盤CD】【新品】Elvis Costello / Almost Blue (エルヴィス・コステロ) 【中古】米CD Elvis Costello エルビスコステロ Almost Blue CK37562 Columbia /00110 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月15日
コメント(0)
-

エドガル・オセランスキ 「シン・ティ(Sin ti)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その27) さて、少しトーンダウンして落ち着いたナンバーを今回はお届けします。1975年、メキシコシティ出身のシンガーソングライター、エドガル・オセランスキ(Edgar Oceransky)のナンバーです。オセランスキは、1990年代末に今クルーで受賞するなど頭角を現し、トローバやバラード系の楽曲をヒットさせているアーティストです。 そんなオセランスキの2018年の楽曲で、「シン・ティ(Sin ti)」です。スペイン語の詞ですが、“君なしに”とか“君なくして”といった意味の表題で、同年発表の『エスカルラタ(Escarlata)』というアルバムに収録されています。 さて、この曲のステージ上での演奏もご覧いただこうと思っていろいろと見ていたら辿りついたのが以下の映像です。いつ、どこでのものかはよくわかりませんが、スタジオライヴ風の演奏の模様です。 [収録アルバム]Edgar Oceransky / Escarlata(2018年) ↓ライヴ盤です↓ 【輸入盤CD】【新品】Edgar Oceransky / #Eometropolitan2019 (w/Blu-ray)【K2020/1/24発売】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月14日
コメント(0)
-
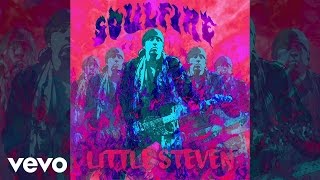
リトル・スティーヴン 「ソウルファイアー(Soulfire)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その26) ブルース・スプリングスティーン関連のアーティストの楽曲をもう一つ取り上げます。リトル・スティーヴン(Little Steven)は、スプリングスティーンが率いるE・ストリート・バンドのメンバーですが、1980年代から自身のアルバムもリリースを重ねてきました。そんな彼のソロ当初からのバンドであるディサイプルズ・オブ・ソウルとの名義で2017年に18年ぶりの新作として発表したアルバム(参考過去記事)の表題曲「ソウルファイアー(Soulfire)」が今回のナンバーです。 上述のアルバムは、他のアーティストへの提供曲などを自身で演じるというものでした。今回の曲「ソウルファイアー」は、元々は2011年にデンマークのバンドに提供したもの(同バンドのメンバーとの共作)でした。そのバンド、ザ・ブレイカーズ(The Breakers)のものと聴き比べていただきましょう。アレンジはさほど変わらないのですが、上の本人によるヴァージョンは、やはりリトル・スティーヴン節が炸裂といった趣になっていますが、このザ・ブレイカーズの演奏もなかなかよくて、しっかりロックしているといった印象です。 余談ながら、このリトル・スティーヴンという人は、本当に才能に富んだ人なのだなと思います。スプリングスティーンのバンドのギタリストという、ギター奏者としての能力だけでなく、作詞作曲とヴォーカルも担当する自身の活動、そして何よりもプロデュースなど音楽全体を作り上げる能力が抜きんでているんだとつくづく感じさせられます(ついでながら、TVドラマ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』では、役者としても成功しました)。 さて、もう1本の映像です。リトル・スティーヴンによるライヴ演奏のシーンもご覧ください。 [収録アルバム]Little Steven & the Disciples of Soul / Soulfire(2017年)Little Steven & the Disciples of Soul / Soulfire Live!(2018年) 【輸入盤CD】【新品】Little Steven / Soulfire Live (Digipak) 【K2018/8/10発売】(リトル・スティーヴン) ↓LP盤です↓ 輸入盤 LITTLE STEVEN / SOULFIRE [2LP] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月13日
コメント(0)
-

ニルス・ロフグレン 「ビコーズ・ザ・ナイト(Because the Night)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その25) 「ビコーズ・ザ・ナイト(Because the Night)」と言えば、パティ・スミスの1978年のナンバー(過去記事)として知られているかと思います。この曲、実は、ブルース・スプリングスティーンが作りかけにしていた原曲を基に、完成していなかった歌詞部分をスミスが書いて共作となってパティが有名にしたというものでした。そのようなわけで、ブルース・スプリングスティーンもこの楽曲を頻繁にライヴで演奏しています。 でもって、今回はスプリングスティーンのバンド(E・ストリート・バンド)のメンバーであるニルス・ロフグレン(Nils Lofgren)のヴァージョンを取り上げます。なぜニルスが?と思う方もいるでしょうが、実はスプリングスティーンのライヴで、この曲がニルスのギター・ソロを聴かせる場面として定着しています。まずは、スプリングスティーンが歌っている「ビコーズ・ザ・ナイト」のライヴでのニルスのソロのシーンをご覧ください。 ただギター・ソロを見せ場にするだけでなく、「ビコーズ・ザ・ナイト」は、ニルスの持ち歌にもなっています。以下は、ニルスがヴォーカルも担当してこの曲を披露し始めた頃と思われる映像です。E・ストリート・バンドの同僚であるマックス・ワインバーグ自身のバンドとの共演で、スプリングスティーンもゲストとして参加しているライヴの1コマです。 さらに、もう一つ。今度は、ニルス自身のバンドでこの曲を披露しているステージの様子もご覧ください。すっかりニルスの“持ち歌”と化していて、完成度の高い演奏の動画です。 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月12日
コメント(0)
-

レインボー 「シンス・ユー・ビーン・ゴーン (Since You Been Gone)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その24) 元ディープ・パープルのリッチー・ブラックモアが率いたレインボーは、様式美的なハードロックから次第にポップな方向を意識していきました。そんな中、当時のファンには衝撃の変貌ぶりだったなどと言われたりもする「シンス・ユー・ビーン・ゴーン (Since You Been Gone)」は、よくも悪くも彼らを代表する曲の一つとして知られるようなヒットになりました。 ちょうど時期的には、ロニー・ジェイムス・ディオが脱退し、新ヴォーカリストとしてグラハム・ボネットが参加した時期の楽曲でした。シングルとしてはイギリスで6位というヒットとなり、アルバムとしては、ボネットが参加した唯一の作品である『ダウン・トゥ・アース』に収められています。 その後、グラハム・ボネットはレインボーを去り、やがて自身のバンドであるアルカトラスを結成しますが、そこでもこの曲はボネットの“持ち歌”となって披露されていきました。1984年、若きイングヴェイ・マルムスティーンがギターを担当した「シンス・ユー・ビーン・ゴーン」をご覧ください。イングヴェイはフライングVを使用していて、見事なプレイを披露していますが、この1984年の日本(中野サンプラザ)での公演は、アルカトラスのライヴ盤としてアルバムになっています。 ところで、この曲、世間ではレインボーの代表曲と思われていますが、彼らのオリジナル曲というわけではありません。元々はラス・バラード(同じくレインボーの「アイ・サレンダー」もこの人が作った曲だったりします)の楽曲で、それをレインボーがカバーしたというものでした。そのようなわけで、ついでにラス・バラードのものもお聴きください。 [収録アルバム]Rainbow / Down to Earth(1979年)Alcatrazz / Live Sentence(1984年)Russ Ballard / Winning(1976年) ダウン・トゥ・アース/レインボー[SHM-CD]【返品種別A】 アルカトラス / LIVE SENTENCE FEAT.GRAHAM BONNET AND YNGWIE J MALMSTEEN (2 DISC DELUXE EDITION)(CD+DVD) [CD] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月11日
コメント(0)
-

ボン・ジョヴィ 「ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー(Born To Be My Baby)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その23) 突然、思い出して聴きたくなった曲です。今回は、とあるボン・ジョヴィ(Bon Jovi)のナンバーを取り上げます。 1986年発表の『ワイルド・イン・ザ・ストリーツ』とそこからのシングル曲(参考過去記事(1) ・(2) )のヒットでスターダムにのし上がったボン・ジョヴィは、続く1988年のアルバム『ニュージャージー』でも快進撃を続けました。 同盤からはシングル曲のヒットが相次ぎ、ボン・ジョヴィ人気は留まることを知りませんでした。そんな中の1曲が、今回の「ボーン・トゥ・ビー・マイ・ベイビー(Born To Be My Baby)」です。全米ビルボードのチャートで3位のヒットとなりました。 続いては、ライヴ演奏の場面もご覧いただこうと思います。1つめは、1990年、日本の東京ドームでのライヴ・ステージの様子、そして、もう一つは2000年のチューリッヒでのライヴの1コマです。 [収録アルバム]Bon Jovi / New Jersey(1988年) ニュージャージー +2 [ ボン・ジョヴィ ] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月10日
コメント(0)
-

ロセンド 「アグラデシード(Agradecido)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その22) 続いては、スペインのロック・シンガー、ギタリストの楽曲です。ロセンドことロセンド・メルカード(Rosendo Mercado)は、1970年代後半から1980年代前半にかけてレーニョというバンドで活躍後、1985年からソロで活動を始めました。その最初のソロ作に収められ、ヒットしたナンバーが今回の「アグラデシード(Agradecido)」で、彼の代表曲の一つです。 スペインにおけるロックの確立期に活躍した人物ですが、過去のいろんな写真や映像を見るにつけ、いつもギターを持った姿が決まっているという印象があります。そんな彼のこの楽曲のライヴ・ステージ上での模様もご覧ください。2011年のライヴの映像です。 ところで、少し前に紹介したミゲル・リオスのアルバム(参考過去記事)にロセンドと共演したものがあります。まさにこの「アグラデシード」をリオスがカバーし、ロセンドがレコーディングに参加したという経緯のものです。映像は動かないものしかないのですが、よろしければこちらのテイクもお聴きください。 [収録アルバム]Rosendo / Loco por incordiar(1985年) 【輸入盤CD】【新品】Rosendo / Mi Tiempo Senorias (w/DVD)【K2019/12/6発売】 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月09日
コメント(0)
-

ソダ・ステレオ 「デ・ムシカ・リヘーラ(De música ligera)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その21) 大阪で万博をやっているから世界各国を巡るというわけではないのですが、今回はアルゼンチンのロック・バンドのナンバーです。ソダ・ステレオ(Soda Stereo)は、1982年に結成され、1984年にデビュー盤を発表しました。中南米のロックないしはスペイン語ロックの分野で先駆的な成功を収めたバンドです。 今回の曲は、「デ・ムシカ・リヘーラ(De música ligera)」というナンバーです。1990年のアルバムに収録された曲で、同盤からのファースト・シングルとして人気を博しました。 この曲は、ラテン系ロックの定番曲として定着しました。ソダ・ステレオは1997年に解散しました(ただし後に再集合してのライヴの機会はありました)が、解散時の“ラスト・コンサート”で最も盛り上がった瞬間がこの曲だったと言います。そのようなわけで、その“ラスト・コンサート”でのこの曲の映像もご覧ください。 [収録アルバム]Soda Stereo / Canción animal(1990年) 【輸入盤CD】【新品】SODA STEREO / CANCION ANIMAL 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月08日
コメント(0)
-

フラヒル 「アベニーダ・ラルコ(Avenida Larco)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その20) 前回はフランスのアーティストでしたが、今回は遠く海を越えてペルーの楽曲です。ペルーの都会にいると、街中でやたらと1980年代洋楽を耳にするような気がするのですが、現地では、地元のロック音楽も着実に展開していたわけで、今回はそうしたペルー出身のロック・グループの有名なナンバーを取り上げたいと思います。 フラヒル(Frágil)は、1970年代後半にリマで形成されたロック/プログレッシヴ・ロック・バンド。1981年にデビュー盤をリリースしています。そのデビュー盤のタイトル曲で、今ではペルーのロックの古典的ナンバーとなっている「アベニーダ・ラルコ(Avenida Larco)」が今回のナンバーです。まずは、この曲のビデオクリップをご覧ください。 このフラヒルというバンドは半世紀近くの時が流れた現在でも存続しているとのことです。後世のライヴ映像を、ということで、2014年のリマでのライヴの演奏シーンをご覧ください。 [収録アルバム]Frágil / Avenida Larco(1981年) 【中古】ブラジルCD Fragil ? Avenida Larco RSLN027 Rock Symphony /00110 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月06日
コメント(0)
-

セルジュ・ゲンスブール 「ユア・アンダー・アレスト(You're Under Arrest)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その19) 唐突ですが、フランス人アーティストによる楽曲です。セルジュ・ゲンスブール(Serge Gainsbourg)は、1928年生まれのアーティストで、音楽のみならず映画でも活躍したマルチな人物でした。音楽面だけを見ても、ジャズ、シャンソン、ロック、ポップスにまたがる多彩な音楽性を発揮したアーティストでした。彼は1991年に62歳で没しましたが、生前最後のスタジオ作となった『囚われ者』(1987年)に収録され、シングルとしてもカットされた「ユア・アンダー・アレスト(You're Under Arrest)」が今回の曲です。まずは、アルバム収録のものをお聴きください。 続いては、この同じ曲のライヴ・ステージの様子をご覧ください。リリース翌年の1988年、パリでのライヴ映像です。ちなみに、この年にゲンスブールは、生涯で唯一となった来日公演も果たしています。 [収録アルバム]Serge Gainsbourg / You're Under Arrest(囚われ者)(1987年) 【輸入盤CD】【新品】Serge Gainsbourg / You're Under Arrest (セルジュ・ゲンスブール) 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月05日
コメント(0)
-

マーティ・ペイチ 「私は御満足(It's All Right with Me)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その18) ジャズを続けます。ピアノ奏者にして優れた編曲者のマーティ・ペイチには、そのジャケット写真から、通称“お風呂”と“踊り子”という有名なアルバム(参考過去記事(1) ・(2) )があるのですが、今回はその“踊り子”の方に収録されている楽曲です。『ブロードウェイ・ビット』に収められた「私は御満足(It's All Right with Me)」をお聴きください。 この曲を含むアルバムは、12人編成のビッグバンド風の演奏が特徴なわけですが、そのエッセンスとも言えるのが、この演奏ではないかと思います。 この曲は、元々は映画『カンカン』でフランク・シナトラが歌ったナンバーなのです。そのような楽曲ということもあって、幾多のジャズ・シンガーもこの曲を歌っています。今回は、個人的にこれがおすすめということで、エラ・フィッツジェラルド(Ella Fitzgerald)による「イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー」をどうぞ。 [収録アルバム]Marty Paich / The Broadway Bit(1959年録音) 【中古】 ブロードウェイ・ビット/マーティ・ペイチ(p、arr),フランク・ビーチ(tp),ステュ・ウィリアムソン(tp、v−tb),ジョージ・ロバーツ(tb),ボブ・エネヴォルセン(v−tb、ts),ヴィンス・デ・ローザ(fhr),アート・ペ マーティ・ペイチ / THE BROADWAY BIT + I GET A BOOT OUT OF YOU [CD] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月04日
コメント(0)
-

アート・ペッパー&ジャック・シェルドン 「ある恋の物語(Historia de un Amor)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その17) さて、今回はジャズです。アート・ペッパー(Art Pepper)の晩年の作品から、「ある恋の物語(Historia de un Amor)」です。1980年、トランペット奏者のジャック・シェルドンを含むクインテットでのセッションで吹き込まれた演奏で、この曲名を表題にしたアルバム(『ある恋の物語』)や、同じセッションの別の曲を表題にしたシェルドン名義のアルバム(『エンジェル・ウィングス』)に収められています。 この時のセッションでは、アルバムに収録されなかったものの、ジャック・シェルドンによるヴォーカル入りヴァージョンも存在したようです。そのヴォーカル入りヴァージョンもお聴きいただきましょう。 シェルドンのヴォーカル自体は案外いい感じなのですが、いかんせん、スペイン語が劇的にヘタクソです(苦笑)。まあ、それはご愛嬌といったところなのかもしれませんが、日本語のまったくわからない外タレが頑張って英語訛りの日本語で歌ってるアレと同じ感じになってしまっています。結局のところ、メキシコの曲であることをあまり感じさせないヴォーカル抜きのヴァージョンの方が、このセッションの吹き込みとしては成功していると言えるのではないでしょうか。 お耳直しと言っては何ですが、この曲のオリジナルもついでにお聴きいただきたいと思います。メキシコだけでなく、いろんな国のアーティストがカバーしていますが、本家本元の作詞・作曲者であるカルロス・エレータ・アルマラン(Carlos Eleta Almarán)による1955年のシングル曲として発表されたヴァージョンをお聴きください。 [収録アルバム]Art Pepper with Jack Sheldon / Historia de un Amor(1980年録音)Jack Sheldon & His West Coast Friends / Angel Wings(1980年録音)Art Pepper / Presents West Coast Sessions! Volume 5: Jack Sheldon(2017年リリース) 【輸入盤CD】【新品】Art Pepper / Art Pepper Presents West Coast Sessions 5: Jack【K2017/9/29発売】(アート・ペッパー) 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月03日
コメント(0)
-

ハート 「いつわりのストレンジャー(Tall, Dark Handsome Stranger)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その16) 今回は、アン・ウィルソンとナンシー・ウィルソン姉妹を中心としたバンド、ハート(Heart)による楽曲です。このバンドの作風を代表しているかというと必ずしもそうは言えなさそうなのですが、勢いがあってノリのいいロック・ナンバーです。 「いつわりのストレンジャー(Tall, Dark Handsome Stranger)」というこの曲の邦題は、1980年代臭のするタイトルですが、そこはご愛嬌(笑)。ともあれ、発表当時の元のヴァージョンをお聴きください。 さて、この曲のライヴでの演奏をと思ったのですが、ステージの様子が映っている動画でこれはというものが意外と見当たりませんでした。いろいろと聴きながら、動かないものの、演奏内容がよいものとして、以下をお聴きいただきたいと思います。1995年、ラスヴェガスでのライヴとのことです。 [収録アルバム]Heart / Brigade(1990年) ブリゲイド [ ハート ] [枚数限定][限定盤]ブリゲイド/ハート[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年07月02日
コメント(0)
-

スティング 「ラシアンズ(Russians)」
1000万アクセス達成記念~いま聴きたいナンバー(その15) スティング(Sting)は、スチュワート・コープランド、アンディ・サマーズとのザ・ポリスでの活動後、1980年代半ばからソロ活動を始めました。その最初の第一歩となったのが、『ブルー・タートルの夢』というファースト・アルバムでした。同盤からは、いくつかの曲がシングル・カットされて衆目を集めましたが、その一つが、今回の「ラシアンズ(Russians)」という曲です。 この曲、実はずっと昔の動画貼り付けができなかった頃に一度取り上げています(参考過去記事)、今回は動画付きでご覧いただければと思います。 映像からもわかるように、冷戦真っただ中といった内容の曲です。詞にも“ソヴィエト”、“フルシチョフ”、“レーガン”、果ては“オッペンハイマーの死の玩具(核兵器)”なんてことばが出てきます。最後は“ロシア人も我が子を愛していることを望む”と言っていますが、時代は巡り巡って、現在、ロシアは侵略戦争真っ最中。こんなことを言うと不謹慎かもしれませんが、リメイクしたらもう一度ヒットするんじゃないかとすら思ってしまいます。 さて、この曲のライヴ・ステージ上での演奏の様子もご覧いただきましょう。2010年、ベルリンでのステージの模様です。 この頃、スティングはロシアでもこの曲をステージで披露したりしているのですが、上記の通り、ここ数年はそれが難しそうな世の中になってしまいました。東西の対立が再び“昔話”になり、スティングがロシアで再度この曲を披露できる日が少しでも早く来ることを願うばかりです。[収録アルバム]Sting / The Dream of the Blue Turtles(ブルー・タートルの夢) (1985年)Sting / Fields of Gold: The Best of Sting 1984-1994 (1994年) ブルー・タートルの夢 [ スティング ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年07月01日
コメント(0)
全3238件 (3238件中 1-50件目)











