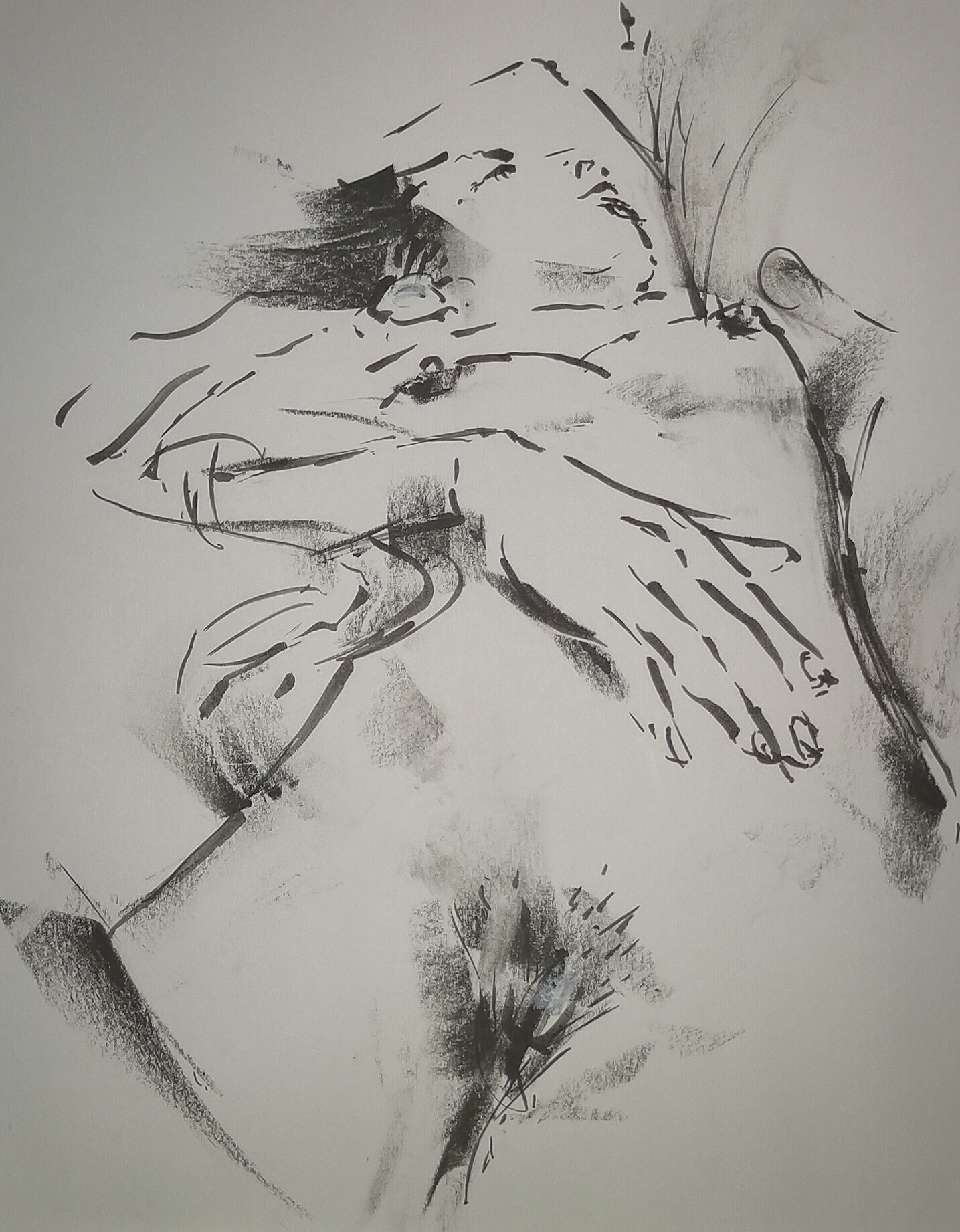2014年01月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
最悪の場合、どんな事態があり得たか
電力業界、自民に原発新増設促す 「模範解答」配布安倍政権が策定を進めるエネルギー基本計画の閣議決定を前に、電力会社などでつくる電気事業連合会(電事連、会長=八木誠・関西電力社長)が自民党議員に原発の必要性や新増設を訴える文書を配っていたことが30日、わかった。同党が計画内容について行った党所属国会議員へのアンケートについて、原発推進の立場で答えるよう促す内容。原発新増設は政権の方針も超えており、業界が自らの利益を前面に押し出した形だ。朝日新聞が入手した電事連の文書によると、エネルギー需給の基本方針として「原子力が重要な電源であるとの位置づけを明確化する」と強調。「原子力発電を一定程度の規模を確保する」として、「そのための新増設・リプレース(建て替え)の必要性を明確化する」とした。安倍晋三首相は新増設について「現在のところまったく想定していない」としている。再稼働についても、文書は「安全の確認された原子力の再稼働を効率的かつ迅速に行う」と明記。核燃料サイクルも「着実に推進する」としている。---喉もとすぎれば暑さわするる、なんて言葉がありますが、いくら何でも、今から原発の新・増設というのは、あまりに無茶苦茶な話です。さすがに、あの安倍でさえも、原発新・増設はまったく想定していないと言っている(言わざるを得ない)のが現状です。福島第一原発の事故で放出された放射性物質の量は、チェルノブイリ原発事故の1割前後と見積もられています。実際に原子炉内に溜め込まれていた放射能のうち、放出された割合は2%前後と推定されています。チェルノブイリの場合は、原子炉内の20~60%の放射能が放出されたと推定されています。ということは、福島第一原発も、事故の成り行きによっては、もっと多くの放射能が放出されてしまうことだってあり得たわけです。福島原発の4基の原子炉に溜め込まれていた放射能の総量は、チェルノブイリのそれの、おおむね2倍程度でした。ということは、もし事故の規模がチェルノブイリと同程度になった場合、放出された放射能量はチェルノブイリの2倍(実際の事故の20倍)となった可能性があるわけです。東日本大震災の直後、政府内で検討された最悪事態のシミュレーションが、後に公開されています。福島第一原子力発電所の不測自体の素描 平成23年3月25日近藤駿介結論として、以下のように記述されています。水素爆発の発生によって追加放出が発生し、それに続いて他の号機からの放出が続くと予想される場合でも、事象のもたらす線量評価結果からは現在の20kmという避難区域を変える必要はない。しかし、続いて4号機プールにおける燃料破損に続くコアコンクリート相互作用が発生して放射性物質の放出が始まると予想されるので(略)50kmの範囲では、速やかに避難が行われるべきである。その外側の70kmの範囲ではとりあえず屋内退避を求めることになるが、110kmまでの範囲においては、ある程度の範囲に土壌汚染レベルが高いため、移転を求めるべき地域が生じる。また、年間線量が自然放射線量を大幅に超えることを理由に移転を希望する人にそれを認めるべき地域が200kmまでに発生する。(容認線量に依存)続いて他の号機のプールにおいても燃料破損に続くコアコンクリート相互作用が発生して大量の放射性物質の放出が始まる。この結果、強制移転を求めるべき地域が170km以遠にも生じる可能性や、年間線量が自然放射線量を大幅に超えることをもって移転を希望する場合認めるべき地域が250km以遠にも発生することになる可能性がある。これらの範囲は、時間の経過とともに小さくなるが、自然(環境)減衰にのみ任せておくならば、上の170km、250kmという地点で数十年を要する。要するに結論として、最悪の場合は強制避難の対象が半径170km以上、希望者の避難を認める対象が250km以上に達する可能性がある、と踏んだわけです。戦慄すべき事態です。福島第一原発から東京(大手町)までの距離は、おおむね220kmです。だから、東京のほとんどが任意避難の対象となります。北関東や新潟、仙台などは強制避難の対象。避難者総数は、何と3000万人です。このシミュレーションを見た菅首相は、後にこう述懐しています。「いったい、天皇陛下はどこへ移せばいいのか、国会は、各省庁は・・・・・・そんなことを考えた。はたして政府機能は維持できるのか。内閣はどうするんだ。戒厳令がないのにそんな避難ができるのか。それに選挙は今後どうやればいい。GDPはどこまで落ち込み、失業率はどのくらいになるのか。そもそも日本の1/3が使えなくなって北海道と西日本とに分断されたら、国家として統治できるのか。国家の自滅だ。そんなことをずっと考えていたんだ。3000万人が避難を強いられるようになったら、避難途中で病人やお年寄りが数十万人単位でなくなるかもしれないとも思っていた。」(講談社文庫「メルトダウン」大鹿靖明 P188-189)この想定は、事故がチェルノブイリ級の事態まで発展した場合には、決して杞憂ではすまなかったはずです。もしこんな事態にまで至っていたら、「日本終了」じゃないけれど、国家として破滅的な事態に至っていたことは間違いありません。。そして、原発が稼動している限り、原発が大地震に襲われて、そのような最悪の事態が発生する可能性は否定できません。例えば浜岡原発や柏崎刈羽原発がそのような事故を起こした場合も、日本は破滅的な事態に至るでしょう。追加燃料代が国富の流出だとか、電力会社の赤字がどうとか、そんなレベルの話など、3000万人避難生活に比べたら、実に小さな話だと、私には思えます。
2014.01.31
コメント(0)
-
それで少子化を解決することなどムリ
年頭にあたり 「あたり前」を以て人口減を制す□埼玉大学名誉教授 長谷川三千子新年早々おめでたくない話--どころか、たいへん怖い話をいたします。このままでゆくと日本は確実に消滅する、という話です。日本の人口は昨年の10月1日で1億2730万人となりました。すでに8年前から減少に転じて、今のところ毎年20万人ほど減り続けています。だからといって何が怖いのか、と首をかしげる人も多いでしょう。戦後急に増えすぎた人口がもとに戻るだけではないか。毎年20万人減れば百年後には1億そこそこの人口になってちょうどよいのではないか--そう考える方もあるでしょう。しかし、そういう単純計算にならないというところが人口減少問題の怖さなのです。今の日本の人口減少は飢餓や疫病の流行などでもたらされたものではありません。出生率の低下により、生まれてくる子供の数が減ることによって生じている現象です。子供の数が減れば、出産可能な若い女性の数も減ってゆく。(中略)単純に、人口不足の国が人口過剰の国から人間を調達するなどということはできません。またもし仮にできたとしても、人口の3分の2を海外から調達している日本を、はたして日本と呼べるでしょうか? わが国の人口減少問題は、わが国が自国内で解決するほかないのです。ではいったい、この問題をどう解決したらよいのか? 実は、解決法そのものはいたって単純、簡単です。日本の若い男女の大多数がしかるべき年齢のうちに結婚し、2、3人の子供を生み育てるようになれば、それで解決です。実際、昭和50年頃まではそれが普通だったのです。もちろん一人一人にとってそれが簡単なことだったというわけではありません。いつの時代でも子育てが鼻歌まじりの気楽な仕事だったためしはないのです。しかし当時は、私も近所のお母さんたちもフーフー言いながら2、3人生み育てていた。それがあたり前だったのです。もしこのあたり前が、もう一度あたり前になれば、人口減少問題はたちまち解決するはずです。ところが、政府も行政もそれを大々的に国民に呼びかけようとは少しもしていない。そんなことをすると、たちまち「政府や行政が個人の生き方に干渉するのはけしからん」という声がわき起こってくるからです。でもこれは全くおかしな話です。というのも、以前のあたり前を突き崩し、個人の生き方を変えさせたのは、まさに政府、行政にほかならないからです。たとえば平成11年施行の「男女共同参画社会基本法」の第4条を見てみますと、そこでは「性別による固定的な役割分担」を反映した「社会における制度又は慣行」の影響をできるだけ退けるように、とうたわれています。どういうことなのか具体的に言えば、女性の一番大切な仕事は子供を生み育てることなのだから、外に出てバリバリ働くよりもそちらを優先しよう。そして男性はちゃんと収入を得て妻子をやしなわねばならぬ--そういう常識を退けるべし、ということなのです。実はこうした「性別役割分担」は、哺乳動物の一員である人間にとって、きわめて自然なものなのです。妊娠、出産、育児は圧倒的に女性の方に負担がかかりますから、生活の糧をかせぐ仕事は男性が主役となるのが合理的です。ことに人間の女性は出産可能期間が限られていますから、その時期の女性を家庭外の仕事にかり出してしまうと、出生率は激減するのが当然です。そして、昭和47年のいわゆる「男女雇用機会均等法」以来、政府、行政は一貫してその方向へと「個人の生き方」に干渉してきたのです。政府も行政も今こそ、その誤りを反省して方向を転ずべきでしょう。それなしには日本は確実にほろぶのです。---ネット中では、この文章が結構話題になっているようです。何しろ、かのNHKの経営委員の意見ですからね。私に言わせれば、論者の名前と記事のタイトルを見ただけで内容が予想でき、かつその予想をまったく裏切らない中身だな、と思いますね。結局、この人の言いたいことの根本は、「女性の一番大切な仕事は子供を生み育てることなのだから、外に出てバリバリ働くよりもそちらを優先しよう。そして男性はちゃんと収入を得て妻子をやしなわねばならぬ」という部分なのでしょう。しかし、そんな価値観に回帰して、出生率が向上することなどあり得ないと、私は確信しています。そもそも、「男性はちゃんと収入を得て妻子をやしなわねばならぬ」って、そんなことは日本の経済状態や雇用環境に左右される問題であって、個人の努力で何とかなる問題ではありません。それとも、長谷川が日本社会のために給料のよい仕事をたくさん提供してくれるのでしょうか。長谷川は、昭和50年(1975年)頃までは既婚女性の大半が専業主婦だった、という思い込みがあるようですが、それは事実に反します。歴史的に見て、専業主婦は江戸時代以前の一般庶民には、まず存在しませんでした。いたとすれば、武家、それもある程度裕福な人に限られたでしょう。貧乏武士は、妻だって働かなければ喰っていけなかった。専業主婦が増加したのは、明治以降、いや、実際にはもっと新しい時代かもしれません。基本的に、農家で妻が農作業に携わらない、なんてことはあり得ませんから。検索したところ、興味深い資料に行き当たりました。既婚女性の労働この3ページ目(紙面上は171ページと書いてある)に、有配偶女子就業率(全国)というグラフが載っています。つまり、既婚女性の就業率です。これを見ると、実は長谷川が思い込んでいる1975年は、既婚女性の就業率が谷間のように一番落ち込んでいた時期であることが分かります。長谷川の頭の中では、おそらく1975年頃までの日本はずっと専業主婦が多く、それ以降専業主婦が減ったということになっているのでしょう。しかし実際は、専業主婦がどんどん増えて、そのピークが1975年、それ以降は再び減少している、ということなのです。そして、その1975年でも、25歳から34歳までの既婚女性(その当時は、まずたいていは小さな子どもを抱えていたはずです)の就業率は1/3を超えていたし、1940~50年代には、5割に近かったのです。また、同じ資料に、別の興味深い統計が載っています。6ページ(記事中には174ページとある)に、地域別の就業率が載っています。全国平均が5割を越えている中で、実は東京、大阪などの大都市圏の既婚女性の就業率は、全国平均以下です。一方、既婚女性の就業率が全国平均より高いのは、山形、福井、鳥取、島根、富山などとなっています。さて、一方合計特殊出生率を都道府県別に見ると、どうでしょうか。2011年の数値ですが、こちらのサイトにグラフがありました。全国平均が1.39(2012年は1.41)に対して、既婚女性の就業率が一番低い方から順番に、大阪1.30、奈良1.27、神奈川1.27、東京1.06、埼玉1.28と、合計特殊出生率は全国平均以下です。一方、既婚女性の就業率が高い方から順番に、山形1.46、福井1.56、島根1.61、富山1.37、鳥取1.58です。富山だけは合計特殊出生率が全国平均を下回りますが、それ以外はすべて全国平均以上です。なお、合計特殊出生率が突出して高い沖縄は、既婚女性の就業率はほぼ全国平均並です。したがって、この数値からは、長谷川の思い込みとは逆に、むしろ既婚女性の就業率が低い地域ほど女性は子どもを産まない、という結果になっています。もっとも、この資料からは別の結果も読み取れるでしょう。大都市圏ほど合計特殊出生率が低い、都市化されていない地域ほど出生率が高い(既婚女性の就業率も同様の傾向)ということです。ということは、東京や大阪などの大都市から人を追い出して、地方に住まわせれば出生率は上がる、かもね。でも、中国の文革時代の下放じゃあるまいし、どんなトンデモな政治家でも、今の時代に都市の住民を無理やり田舎に移住させる、なんてことはやらないし、できるはずもありません。「人口不足の国が人口過剰の国から人間を調達する~ことはできません。」とあります。確かに、出生率の高い国から移民を受け入れることは解決策にならないことは事実です。でも、その理由が「はたして日本と呼べるでしょうか?」というのは、なんの理屈にもなりません。少子化問題を論じるのに、この底の浅さは何なのかなと思います。出生率の高い国から移民を受け入れることが解決策にならないのはなぜかと言うと、諸外国の例から見て、たいていの場合は移民の出生率が最初は高くても、やがて、元々の住民と同水準まで低くなってしまうからです。(唯一の例外は米国のヒスパニック系)男女共同参画社会基本法についても何か書いていますが、これは、行政が主導して「性別による固定的な役割分担」を変えたのではなく、社会のなかで「性別による固定的な役割分担」が変わってしまった現実に、遅ればせながら行政が対応した、ということにすぎません。この法律が制定されたのは1999年ですが、先の資料が示すように、それより20年も前から既婚女性の就業率は上昇し続けているのですから。「実はこうした性別役割分担は、哺乳動物の一員である人間にとって、きわめて自然なものなのです。」というのも、およそ事実に反する非科学的な話です。私の知る限り、哺乳類で(いや、別に哺乳類に限らないのですが)、エサ取りはオスだけがやる、メスは子どもの世話だけに専念する、なんて動物はいません。だいたい、人間のような一夫一妻という家族構成をとる動物は、鳥類には非常に多い(ただし、繁殖期以外は「夫婦」はバラバラで、したがって繁殖期の度にパートナーが変わるのが一般的)ですが、哺乳類では多数派とはいえません。とりわけ、人類に最も近い動物である類人猿には、人間と同じような一夫一妻の「夫婦」を常時維持している動物はいませんから、人間の家族の形を哺乳類一般に当てはめて、「自然」とか「自然ではない」なんてのは、そもそも無意味な話です。人間に最も近いチンパンジーとボノボは、複数の雌雄同士が群れをつくり、いわば乱婚の状態です。ゴリラは一夫多妻。じゃあ、人類の「自然」にあわせて乱婚や一夫多妻にしますか?あり得ないことでしょう。産経新聞が、イデオロギーを優先して粗雑な論文を掲載しがちなのは、今に始まった話ではないけれど、こんなのがNHKの経営委員で、しかも名誉教授の肩書きを持っているというのだから、呆れてしまいます。
2014.01.30
コメント(6)
-
なおる病気と治らない病気
三鷹ストーカー:被告と面会“自分勝手な特有思考”記者に ◇警察庁 治療に重点東京都三鷹市の女子高生殺人事件で、殺人罪などで起訴された元交際相手の池永チャールストーマス被告が勾留先の立川拘置所で毎日新聞の取材に応じた。池永被告はストーカー行為や殺害の理由について「復縁ではなく、連絡を取り続けたかった。彼女の死を考えると楽になった」などと述べた。こうした発言に象徴されるストーカー加害者の心理を巡っては、刑罰だけでは再犯を防げないとの指摘があることから、警察庁は来年度から加害者の治療に向けた研究に乗り出す。今月24日に面会に応じた池永被告は、丸刈りが少し伸びた髪形で上下ジャージー姿。質問に一つ一つ言葉を選びながら答えた。女子生徒に電話やメールで執拗に連絡を取った理由について、復縁目的ではないと強調。ストーカー行為は犯罪と認識していたとした上で、「(連絡が途絶えて)すべてを手放すのは勇気がいる。連絡の強要はした」と話した。こうした説明について、加害者治療に実績のある精神科医の福井裕輝さんは「ストーカー加害者は相手に対する愛情と憎しみが共存し、感情を整理できない場合が多い。池永被告にも同様の傾向がうかがえる」と指摘する。自分を拒絶して苦しめる相手を不幸に陥れることで心の痛みを和らげる−−という自分勝手な思考は、ストーカーに特有という。(以下略)ーーー確かに、ストーカーから殺人にまで至るような状況というのは、心理状態としてまともであるはずがない。ただし、殺人なんてものは、犯罪を犯す瞬間には誰だって冷静ではなく、何らかの異常心理状態にあるのではないでしょうか。全く冷静な状態で殺人を犯す人がいるとしたら、そういう人が一番恐ろしいでしょう。何はともあれ、治療に重点という方向性は間違っていないと思うのですが、では実際にどうやって、どの程度治療できるのかというと、なかなか難しいのではないかと思います。こういう人は、広い意味ではある種の人格障害の一種でしょう。ただ、人格障害は、障害であって障害ではない。それに付随して他の病名が付いていれば別ですが、それだけでは精神障害の手帳も取れないし、責任能力も問題なしと見なされます。犯罪を犯して、人格障害のみを理由に心神耗弱などで無罪になった例は、多分ないはずです。障害であって障害ではない、病気であって病気ではないものを治療するといっても、本当にできるのかな?って、思ってしまうのです。治すことがまったく不可能、ということはないでしょが、あるレベルを超えると、立ち直るのはかなりむつかしいと思わざるを得ません。異常な心理に捉われている人は、自分が異常だとは思っていない場合が多いのです。人格障害を精神病呼ぶことが適切かどうかは分かりませんが、精神病の一種と考えれば、病識(自分が病気との自覚)がないということになります。病識がない人を治療するほど、難しいことはないと思うのです。「あなたは異常だよ」と言われて、そのとおりだと自分を客観視できるようなら、そもそもストーカーなどやらない。いっときの気の迷いなら、ハッと目が覚める、ということはあるかもしれません。しかし、殺人にすら至るようなレベルのストーカーは、もっと根の深い、人格面での問題がある可能性が高いように思います。人格障害とは違いますが、依存症も治すのがむつかしいと言われます。覚せい剤の常習犯なんて、治療しなければならないことは誰でも(本人も理屈では)分かっているはずです。バックアップ体制もないわけではないけれど、治せない。覚せい剤で何度も何度も逮捕を繰り返している人がいますね、有名人でもいます。アルコール依存も同様です。アルコールは、違法薬物ではなく、飲酒自体は法に触れないだけに、いっそう難しいかもしれない。このブログでも何度か取り上げたことがありますが、かつて中川昭一という政治家がいました。麻生内閣の財務相で、記者会見中に泥酔して醜態を晒して辞任に追い込まれて、後に死去しました。あれは、明らかにアルコール依存症です。騒動が起きたときに調べたら、中川昭一には酒にまつわる武勇伝、いや醜態が山ほどあった。多分、あれが政治家ではなく一般のサラリーマンだったら、とっくの昔に退職に追い込まれていただろうと思われるレベルです。彼は、何度かアルコール依存の「治療」も試みたようです。現役の国会議員で、閣僚経験もある人物ですから、当然、最高レベルの治療を試みたはずですが、治らなかった。現職の議員という立場を続けながら、飲酒の機会を断つことは、所詮不可能だったのだろうと思います。よく言われるのは、依存症は、「底付き体験」つまり、周囲の人間に縁を切られて、助けてくれる人もいない、依存対象の物質(酒であったり薬物であったり)を買うお金もない、という状態まで追い込まれないと、本気で治療しようという気にならない、という話です。(異論もあるようですが)もっとも、実際には、どん底まで落ちてもなお、治療に取り組めない人などゴロゴロいますけ。仕事を失い、友人も家族も失い、住む家すら失ったら、そのさきにはもう死しかない。だから、でしょうか。アルコール依存の死亡率は、癌より高いといわれます。中川の場合、金持ちだから、経済的な面では、なかなか底を付かなかった。その前に自分の命が底を付いてしまったわけです。人格障害の場合も、「治療」の難しさは依存症と同じようなものでしょう。性格がねじ曲がっている人だって、そんな性格に生まれてきたかったわけではない、という意味では、かわいそうな状況だとは思いますけど、だからと言って、現実にそういう人に「かわいそう」という感情をいだけるほどには、私も聖人君子ではありません。では、どうしたら良いのか、というと、なかなか妙案は思い浮かびません。結局、当面は被害者の側が対策を取るしかないのだろうな、と考えざるを得ないのが現状です。
2014.01.29
コメント(2)
-
内向き愛国主義者の手前勝手な理屈に納得する外国はない
橋下市長発言要旨「朝日や毎日のような主張を言えば政治的中立害さない、というのはおかしい」「民主党はもうちょっと歴史を勉強したほうがいいんじゃないですか。籾井さんが言っていることはまさに正論ですよ。その通りですよ。あの主張に反論なんかできる人なんていないと思いますよ。僕が言い続けてきたことと全く一緒です。あの意見について、まぁ朝日は毎日、メディアは大誤報やってくれて、主語とかすっとばして、正当化したとギャーギャー言っていたが、籾井さんの言っていることは僕がずっと言い続けてきたことで、あの点についてきちっと反論できる人はいないと思いますよ。もっとね、皆さんも含めてね、歴史を勉強しないといけないし、今この時期、この状況になってね、中国や韓国のこの状況をみて、歴史というものが外交戦争に使われているということもある。日本は今までそういうことやってこなかった。日本の外交官もそういうこと言わずに、とにかく相手の気を害さないようにとやってきたが、中国もね、それなりの力を持ってきて、今までのアメリカ一極の世界秩序の中で我慢するような状況でなくなったときには、歴史については主張してきますよ」「安重根の問題だって、韓国の主張だって中国の主張だって、彼らの主張でそういう主張あると思うが、日本であんな主張認められませんよ。歴史は当事者によって主張や認識が違うのはあたりまえ。だから自衛戦争だと言っても相手方から見たら侵略だし、相手が侵略と言ってもこっちからしたら自衛だということもある。でも僕はサンフランシスコ講和条約を結んだ以上は、世界から侵略戦争と評価されること、言われることについては日本の政治家として受け入れざるを得ないが、その他の歴史問題については、今までのように黙っていたらいいなんてそんなことやってたら、外交戦争に敗北しますよ」「どれだけ中国や韓国が今、世界でプロパガンダやっているんですか。今まで日本人は相手の気持ちを害してはいけないということで「言うな」「言うな」となりましたが、慰安婦問題は最たるもの。きちっと言わないといけない。日本人として。認めるところは認め、反省するところ反省する。世界から不当な評価受けるようなことについてはしっかり言わないと」「アメリカ人もヨーロッパも、完全に勘違いしている。僕が言っているのは、世界の、国際社会においては価値観は多様化している。一定の価値観を押しつけたって理解はしてくれない。でも世界共通の物差しは、フェアかアンフェアか。慰安婦問題はアンフェアです。日本だけを袋だたきするような世界の態度はアンフェだと言えばいい。戦争は悲惨だし、二度とやってはいけないが、そういう状況の中で、似たり寄ったりのことはどの国だってやっていたし、戦争と性の問題は、どの国だって抱えてきた不幸な歴史なんですよ。そういうことは二度と繰り返さない、今の価値観においてはそんなことあってはならない。だけど、日本だけが不当に袋だたきされているのは何故かというと、日本人が主張してこなかったからだ」「慰安婦問題について、どういう問題なのか。河野談話の問題点とかきちっと言わなかったから。籾井さんの言っていることは至極正当で、民主党はもっと歴史を勉強すべきだし、自民党の方から批判が出るのは非常に残念です。こういう問題になって必ず出てくる政治的中立性ですよ。出ましたよまたこれ」「政治的中立性ってね、だいたい何か発言したら政治的な価値観は必ず含まれるものでね。メディアからしたら、毎日、朝日にしたら、籾井さんとは慰安婦問題で反対意見だから、ああいう発言をしたら政治的中立性を害するというが、朝日や毎日のような考えだったらあれも政治的な見解ですよ。ひとつのね。籾井さんの考え方も政治的な考え方。僕の考え方も政治的な考え方。もっと言えば、慰安婦問題について、世界から袋だたきにあっても良いという主張も政治的な考え方」(以下略)---ひとことで言って、「馬鹿」ということに尽きます。「歴史の勉強をしろ」というのは、最近ネットウヨクがやたらと言いたがるけれど、橋下も同じことを言い出したのは、ネットウヨクと同じメンタリティの持ち主だから、ということでしょうか。学ばなければならないのは、自分たちのほうだろうが、と思います。朝日は毎日、メディアは大誤報やってくれてなどと言っていますが、橋下の問題発言を報じた各マスコミの、具体的にどこが誤報なのかがさっぱり分かりません。当時、橋下の発言要旨と、各紙の報道内容を見比べて、どこをどう見ても誤報など何もなかったというのが私の結論です。いったい何が誤報なのか安重根の問題だって、韓国の主張だって中国の主張だって、彼らの主張でそういう主張あると思うが、日本であんな主張認められませんよ。これは、まったく逆立ちした主張です。韓国は、別に日本に対して安重根を英雄と認めろとか、日本国内に記念碑を建てろと言っているわけではない。韓国が中国に記念碑を作ることについて、日本が文句を言う資格があるのか、という問題です。「日本で」あんな主張が認められないことを、何で日本の外にまで強いることができるのか。アメリカ人もヨーロッパも、完全に勘違いしている。私の見るところ、「みんなが完全に勘違いしている(私は勘違いしていない)」というのは、たいていの場合はお前一人が勘違いしているのに、その自覚がないだけ、というのが実態です。米国だってヨーロッパだって、別に親中国親韓国でもない。しかし、従軍慰安婦の問題に関して日本のネットウヨク系の主張に同意することはない、なぜなら、そのような主張は非常識だからです。似たり寄ったりのことはどの国だってやっていたし、戦争と性の問題は、どの国だって抱えてきた不幸な歴史なんですよ。そういうことは二度と繰り返さない第一に、戦争と性の問題は、どこの国だって抱えてきた、ということ自体は事実です。ただし、従軍慰安婦のように、前借金で女性を縛って、軍人に対して性的奉仕をさせる、しかもそれを最前線にまで持ち込む、ということを組織的におこなった国は、日本とナチスドイツくらいです。第二に、自国の非を問われているときに、「よその国だって」などという言い方をするのは、そのような「不幸な歴史」を二度と繰り返さない熱意に対して疑いを抱かれても仕方のない態度でしょう。殺人犯が裁判のときに、「あの殺人事件の犯人は逮捕されていない、あの殺人事件の犯人は死刑にはならなかった」などと言い立てたとすれば、それを真摯な反省の態度だと考える人は、まずいないでしょう。だいたい、「米軍は風俗産業を活用しろ」などということを口走るような人物がもしも軍の司令官だったら、従軍慰安婦のような愚行をまた繰り返しかねないと、私は真剣に危惧しますね。日本だけが不当に袋だたきされているのは何故かというと、日本人が主張してこなかったからだいいえ、違うでしょうね。日本だけが袋だたきされているとすれば(不当に、とは私は思わないが)、それは前述のとおり、一般論的な軍隊と性に関する難しい問題は普遍的に存在するにしても、強制売春という行為を第二次大戦期に行ったのが日本とナチスドイツくらいだったからでしょう。実際問題として、橋下が思うような「事実」を、右翼連中がワシントンポストに意見広告として出した結果、どうなりましたか。明らかに逆効果になって、米国下院の「慰安婦に対する日本政府の謝罪を求める決議」の採決を促す結果になったし、それ以外の国々からも次々と同様の決議が出ています。主張してこなかったからではなく、異常な主張をしたから袋叩きにあっているだけのことです。結局のところ、橋下は、国内で受けのよい言辞を弄して支持を集める術には長けている。しかし、その姿が国外からどう見えるかについては、まるで意識がない。「主張」云々に関しても、その主張を世界がどう受け取るかというところへの意識がない。「日本の立場」なるものを叫べば外国から理解されるという勝手な思い込みにすがり付いているばかりです。まさしく国内でしか通用しない理屈を振りかざす、内向き愛国者の典型です。そのような内向き愛国者が結局国を滅ぼした過去の失敗を、再び繰り返すことだけはやめて欲しいです。
2014.01.28
コメント(0)
-
尊厳死
「尊厳死」 法制化の動き 安楽死とどう違う? 賛否は?末期ガンなどに侵され、回復する可能性がない患者の意思に基づいて延命措置を施さない「尊厳死」を法制化する動きが出ています。超党派の国会議員でつくる「尊厳死法制化を考える議員連盟」は、患者が延命措置を望まない場合、医師が人工呼吸器を取り外すなど延命措置を中止しても法的責任を問わない「尊厳死法案」を、今の通常国会に議員立法で提出する方針です。尊厳死とは具体的にどのようなもので、どうして法制化する必要があるのでしょうか。尊厳死と似ている言葉に、「安楽死」があります。安楽死とは、肉体的・精神的苦痛から患者を解放するため、薬物投与などで人為的に死を早めることを言います。それに対し、尊厳死は、病などにより「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置を中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることを指します。本人の意思に基づくのが「尊厳死」わかりやすく言えば、第三者の意思が介在するのが「安楽死」、本人の意思に基づくのが「尊厳死」です。現在、日本には尊厳死について明確に規定した法律が存在しません。患者本人や家族の意向を受けて延命治療を中止した医師は「殺人罪」に問われる可能性があるため、医療現場では患者らが尊厳死を望んでもやむなく延命措置を続ける傾向が強いとされています。こうした事態を解消するため、尊厳死を法制化する動きが出ているわけです。東京新聞(1/12付)によると、「尊厳死法制化を考える議員連盟」が提出を予定している法案では、末期ガンなどに侵され、適切に治療しても患者が回復する見込みがなく、死期が間近と判定された状態を「終末期」と定義。15歳以上の患者が延命措置を望まないと書面で意思表示し、2人以上の医師が終末期と判定すれば尊厳死を認め、医師は刑事、民事、行政上の法的責任を問われないと定めています。また、意思表示の撤回はいつでも可能とし、本人の意思が確認できない場合は「法律の適用外」としています。賛成・反対それぞれの理由は尊厳死は、死生観に直接関わる問題だけに、法制化の動きには賛否両論があります。中日新聞(2012/11/27付)は、「生きていれば年金が入る、と自分たちに都合のいい延命を患者に強いている家族もいる。尊厳死法案は、自己決定による終末期医療を支援するもの」という、尊厳死法案の実現を求めている日本尊厳死協会東海支部の青木仁子支部長の声を伝えています。一方で、反対論も少なくありません。北海道新聞(2012/10/24付)は、「法案は死ぬ権利を認めるもの。医療提供を受けなければ生きられない社会的弱者に、死の自己決定を迫る危険性がある」という、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者らでつくる「日本ALS協会」の反対意見を伝えています。ほかにも、「人の死に国家が介入すべきではない」「延命措置の中止は命の軽視につながる」といった批判も強く、法案の成立は見通せない状況です。---以前に、安楽死について記事を書いたことがあります。薬物投与などで積極的に「殺す」行為である安楽死は、現実的に日本で認められる可能性は少ないのだと思います。しかし、積極的な延命治療を行わない、という尊厳死の場合は、「本人の自発的な意志に基づくのなら」という前提の上ですが、一概に否定されるべきものではないように思います。以前の記事にも書きましたが。父の最期を見て、私は思いました。激しい痛みに耐えて、その病気から治る(完治とはいわないまでも、ある程度までは)ならば良いのですが、末期がんなどというものは治りません。確実に死ぬ。その死をちょっと先に延ばすためだけに、痛みに耐え続けるのは、現時点での感覚としては、私は嫌です。もちろん、本人の意思に反してとか、治る見込みがあるのに、ということはあってはなりません。けれども、治る見込みがない、あとは痛みに苦しむだけ、という状態で、「死ぬ権利は認めない」というのは、「もっと苦しめ」というのと同じことです。もっとも、現実には、あからさまな行為まではしないにしても、本人(意思表示ができれば)と家族の意向があれば、あまり波風が立たない程度のレベルでは、あまり必死な延命治療は行わない、という程度のことは、結構どこの病院もやっているのではないでしょうか。例えば、老衰や末期がんの人が心臓が止まったからといって、AEDを使うことはないし、呼吸が止まったからといって人工呼吸を施すこともないでしょう。(少なくとも私の父の場合はそうでした)ただ、おそらく本人と家族の意思が相反する場合、特に本人は延命措置を望まない、家族は延命措置を望んでいるという例の場合に、あとで問題が生じやすいのではないか、という気がします。そのあたりをきちんと整理して、本人の意思が優先というルールを確立することは必要でしょう。まあ、容易に結論の出ない問題であることは確かです。
2014.01.27
コメント(2)
-

かぐや姫の物語 再論
ある意味どうでもいい話ですが、竹取物語について、改めて調べているうちに、ちょっと引っかかったところがありました。先の記事に書いたように、かぐや姫に求婚する5人の貴族のうち3人は実在の人物、残りの2人も、モデルと思われる人物が特定されています。で、彼らはみな飛鳥時代(7世紀後半)に活躍した人物です。竹取物語は、平安時代の890年代から10世紀半ばまでの間に書かれているそうなので、200年以上前を舞台にした物語として書かれていた、ということになります。実際、物語の書き出しは、「今は昔」となっています。ちょうど、現在の小説家が江戸時代を舞台に小説を書くような感じです。ところが、高畑監督の「かぐや姫の物語」は、明らかに平安時代を舞台にしています。飛鳥時代と平安時代では、貴族の衣装は相当違います。かぐや姫が着ている十二単(女房装束)や、男の貴族が着ている、なんという名前か忘れましたが、貴族の服装は、いずれも平安時代以降のものです。彼らが住んでいる寝殿造の邸宅も、確か平安時代以降の建築様式だったはずです。↓ 7世紀後半頃の貴族の女性の服装↓ 7世紀後半頃の貴族の男性の服装もっとも、「百人一首」に出てくる持統天皇(春すぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天のかぐ山)の姿は、たいていの場合十二単で描かれています。これはネット上で探した画像ですが、うちの実家にある百人一首も同様です。時代考証的には、明らかにおかしい。↓ かぐや姫の物語の衣装作品作りに当たっては、舞台背景や関連する事柄などを徹底的に調べると言われる高畑勲監督が、このことに気が付かなかったわけがありません。ストーリーに関しては徹底的に原作に忠実な一方、服装など時代考証上の年代設定については、あえて原作の「物語上の年代」ではなく「物語が執筆された年代」に合わせたわけです。きっと、理由があってのことなのでしょう。飛鳥時代より平安時代の衣装は現在にある程度残っているので、大方の観客にとってある程度見慣れているけれど、飛鳥時代の衣装では見慣れなくて親しみがわかないから、でしょうか。百人一首の持統天皇の服装が十二単になっているのも、同じような理由かも知れません。平安時代以降の服飾に関しては、かなりの程度資料が残っていますが(天皇家が、結婚や即位の礼の際に着用する服装も、基本的には平安時代から続く伝統に基づいている)、飛鳥時代の服飾は、よく分からない面が多々ある、ということも理由のひとつでしょうか。実際のところはどうなんでしょうね。
2014.01.26
コメント(4)
-
NHKの会長が、こういうことを言い出すとは
NHK籾井新会長「従軍慰安婦、どこの国にもあった」NHK新会長の籾井勝人氏は25日の就任会見で、従軍慰安婦について「戦争をしているどこの国にもあった」と述べた上で、日本に補償を求めている韓国を批判した。従軍慰安婦問題を取り上げた過去のNHK番組に関連し、この問題に関する見解を問われ答えた。籾井氏は会見で放送法の順守を繰り返し語った。放送法はNHKを含めた放送事業者に「政治的公平性」を義務づけている。籾井氏は従軍慰安婦問題について「今のモラルでは悪いんですよ」としつつ、「戦争をしているどこの国にもあった」としてフランス、ドイツの名を挙げた。「なぜオランダにまだ飾り窓があるんですか」とも述べた。飾り窓はオランダなどにある売春街を指す。さらに「会長の職はさておき」とした上で、韓国についても「日本だけが強制連行したみたいなことを言っているから話がややこしい。お金をよこせ、補償しろと言っている。しかしすべて日韓条約で解決している。なぜ蒸し返されるんですか。おかしいでしょう」と批判した。その後、記者から会長会見の場であることを指摘されると、発言を「全部取り消します」と話した。NHKの海外向け国際放送については、尖閣諸島、竹島という領土問題について「明確に日本の立場を主張するのは当然。政府が右ということを左というわけにはいかない」と述べ、政府見解を積極的に伝える考えを強調した。また、籾井氏は特定秘密保護法について「世間が心配していることが政府の目的であれば、大変なことですけど、そういうこともない」「あまりかっかすることはない」と述べた。---安倍政権の肝いりで選ばれたNHK会長ともなれば、こういう人物なのではないか、という予想はしていましたが、まったくその予想どおりの人物だった、ということのようです。従軍慰安婦について「戦争をしているどこの国にもあった」というのは、確かにそのとおりではありますが、「だから日本は悪くはない」という意味でそれを言っているとしたら、話になりません。殺人犯が、「殺人を犯したのは私だけではない」などと言ったところで、「だから何?」としか言いようがないのです。国についても「日本だけが強制連行したみたいなことを言っているから話がややこしい。」私は、韓国の主張について、詳細に検討はしていませんが、日本が強制連行した、とは言っていますが、日本「だけ」がしたと、本当にそういっているのでしょうか。ドイツに比べて日本は反省が不十分である、ということは言っています。しかし、それは逆にいえば、ドイツも日本と同様のことを行ったという事実認識の前提の上での話です。まして「なぜオランダにまだ飾り窓があるんですか」なんて発言は、論外の話です。従軍慰安婦は、戦前の日本の公娼制度も全般的に同様ですが、前借金で縛って売春行為を強要する事実上の人身売買です。だから、性的奴隷であったと非難されているわけです。近年のヨーロッパ諸国では、売春が合法化される傾向がありますが、そこでは、当然のことながらこのような人身売買行為は排除されています。人身売買が伴わなければ売春を公認してよいのか、というのはなかなか難しい問題ですが、少なくとも前借金で縛る人身売買と同列には論じられません。日本の公共放送の会長という地位についた人間が、就任記者会見でこんなことを放言する、当然世界中にその放言内容が報じられるわけです。韓国にも中国にも、米国にもドイツ、フランス、オランダにも。日本のネット右翼は、こういう放言を聞いて溜飲を下げるかもしれないけれど、日本以外の国で、このような発言が好感を持って迎え入れられることはない。ドイツだってフランスだって、オランダだって、こんなことを言われれば少なくとも気分は良くないに決まっています。もちろん米国もそうでしょうし、韓国や中国はいうまでもありません。「明確に日本の立場を主張するのは当然。政府が右ということを左というわけにはいかない」と言っているそうですが、その「日本の立場」というのが「従軍慰安婦は捏造だ、南京大虐殺は捏造だ、大東亜戦争は正義の戦争だ」などというたぐいのものだとすると、主張すればするほど、日本の異常性を際立たせて、世界の中で立場を孤立させる事態を招くことになるのは間違いありません。国内でしか通用しない内向き愛国主義を振りかざして、国外の反感を買うことが「日本の立場を主張」なのでしょうか。太平洋戦争時の日本は、明らかに「愛国者」たちが道を踏み外して、日本を破滅に導きました。彼らは、主観的には愛国者でしたが、結果においては、日本にもっとも害悪をもたらしたのは、明らかに、自称愛国者の連中でした。このまま行くと再び自称愛国者たちが、日本を破滅に導いてしまうのではないか、という危惧が、ここ最近急激に増大しつつあるように思えます。
2014.01.25
コメント(8)
-
ネット調査がいかに当てにならないか
以前に、ネット上の人気投票が、実際の世論の動向とはかけ離れているということについて、記事を書いたことがあります。ネット上の「真実」しか見えない人たちそして、また新たなネット人気投票伝説が現れました。田母神氏、断トツ本命!? 都知事選アンケートで異変 8割以上の票集め東京都知事選のアンケートで異変が起きている。ラジオNIKKEIのニュース番組「マーケットプレス」のホームページで15日から、主な立候補予定者の名前を挙げて、「東京都知事にふさわしいのは誰?」と聞いたところ、何と、元航空幕僚長の田母神俊雄氏が、8割以上の票を集める1位となっているのだ。アンケートでエントリーされているのは、田母神氏をはじめ、舛添要一元厚労相、細川護煕元首相、前日弁連会長の宇都宮健児氏、発明家のドクター・中松氏=本名・中松義郎=の5人。「その他」「関心なし」という選択肢もある。18日午前8時時点で、田母神氏が83・15%(6835票)とトップで、事実上の2強とみられる舛添氏や細川氏、それ以外の候補を大きく引き離している。---支持率85%だそうです。圧倒的じゃないですか。何が圧倒的かって、実際の世論との乖離の激しさが、です。どう考えたって、田母神が85%もの得票を得ることはない、これは断言できます。というか、もし田母神がそんな支持率を獲得するような世の中になったら、私は真剣に亡命を検討するかもしれません。でも、実際はそんなことはあり得ません。その半分の得票だって取ることはできません。そもそも、このネット調査に回答した人が、都知事選に投票権を有する有権者かどうかも、定かではありません。ネット「世論」と現実が、どれだけ乖離しているか、また一つの証拠が積み重ねられた、という感じです。とはいえ、脱原発を掲げて立候補した細川は、「あとだしじゃんけん」がむしろあだになっているような感じで、小泉の応援があっても、それほど支持は伸びていないようです。当選どころか、宇都宮候補より票が取れるのかどうか、というところみたいです。ということは、結局は舛添が優勢ということなのでしょうか。私自身は、宇都宮に入れるか細川に入れるか、現在のところは宇都宮候補に傾いています。
2014.01.24
コメント(4)
-

かぐや姫の物語(大幅に追記)
実は、高畑勲監督の「かぐや姫の物語」を見ました。以下、ネタバレですが、そもそも竹取物語の筋と結末は、誰でも知っていて、話の筋はまったく原作どおりなので、ネタバレもなにもありませんね。もっとも、童話としてのかぐや姫はともかく、「竹取物語」をちゃんと読んだことはなくて、細部はうろ覚えで「こんな話だったっけ」というところもありました。いやー、切なかった。ひょっとしたら、目の付け所がずれているかもしれないけど、うちの子が新生児のときのこと、3歳くらい、5歳くらいのときのことを思い出してしまった。何だか、物語の中の他人の子どもに見えなかったのです。実に、子どものことをよく観察している。翁が「都に出る」と言い出すあたりが、ちょうど今のうちの子くらいの年でしょうか。一番最後、月からの使者がかぐや姫を迎えに来るシーンはグッときました。(ここを詳細に説明すると、本当に未見の人へのネタバレになってしまうので、避けますが、月からの使者によって皆が眠らされそうになった一瞬、あるきっかけで翁と媼が意識を取り戻して、かぐや姫に駆け寄る、そのあたりが、実にもう、泣かせどころを計算していたのかって感じです)将来うちの子が独立して家を出て行くとき、こういう気持ちになるのかな、なんて思いました。かぐや姫と違って、二度と戻ってこないわけじゃないし、記憶を失うわけでもないけど。子どもを、家族を大切にしなくちゃ、なんて思ってしまいました。まあ、今でも大切にしているけど。月からの使者がやってくる場面の音楽が、ある意味ではとてもミスマッチなのですが、強い印象を残します。高畑監督は、あえて感情をかきたてる音楽は排したそうです。「月の世界は悩みも悲しみもない、だから悲しげな音楽はいらない」というような趣旨(手元にソースがないのでうろ覚えですが)のことを書いています。「人間界の感情とは超越した世界からやってきた人たちの音楽」という感じです。上記はニコニコ動画からの引用ですが、YouTubeには映画で使われたBGMそのものはアップされていないようです。その代わり、ピアノで弾いた動画が見つかりました。ピアノだけで聞くと、意外にも宗教的な印象を受けます。(私は、ですよ。他の人がどう感じるかは分かりませんが)白地の多い背景も、最初ちょっと違和感を感じたけど、しばらく見ていると、逆に味があるという気になりました。ネット上で評価を見ると、酷評している人も少なくないようです。確かに、エンターティメント性は乏しいかもしれない。子どもが見て楽しめる作品ではないかもしれませんし、私のように、自分の子どもと重ね合わせて見てしまうのと、子どもになんか興味がない人が見るのでは、感じ方が違うのかもしれません。前述の、クライマックスシーンの音楽も、評価は分かれるようで、あの場面であの音楽はわけが分からない、という感想も聞きました。でも、私にとっては、かなり記憶に残る傑作です。かぐや姫の罪と罰、というのが話題になっているようで、キャッチフレーズになっていた割に、何が罪と罰だったのか、よく分からない、という意見もあるようです。私は事前情報ゼロで見に行ったので、罪と罰がキャッチフレーズになっていること自体知らなかったのですが、月に帰ると、地球でのことは楽しかったこともつらかった事もすべて忘れさせられてしまうというのは、それ以上ないくらい残酷な罰だと、私は思いましたね。すべての記憶を失うというのは、事実上死と同じことです。人生には楽しいこともつらいこともある、よいものも悪いものも、清らかなものも汚らわしいものもある、それが人生であり、生きるに値するものだ、と、高畑監督がそう訴えたかったのかどうかは分かりませんが、私がこの作品から感じたメッセージはそんな感じでした。それにしても、です。お歯黒や黛を嫌がり、上流階級の公達と、姿も見ないうちに結婚を決めることを嫌がるかぐや姫の考え方は、一見すると現代的な解釈に感じられますが、実はそうではないようです。原作でもかぐや姫は「よくもあらぬかたちを、深き心も知らで、あだ心つきなば、のち悔しきこともあるべきを、と思ふばかりなり。世のかしこき人なりとも、深き志を知らでは、あひがたしと思ふ」(美男子でもなく、本音も知らないまま、浮気でもされたら後で後悔するだろうと思います。恐れ多い人といえども、本音を知らなければ結婚などできません)と言い、それに対して翁は「思ひのごとくも、のたまふものかな。」(本音をズケズケいう人だ)と応える。というやりとりがあります。ということは、です。男と女の関係についての考え方は、少なくとも本音の部分では、1000年前も現在もたいして変わらない、ということなのでしょう。建前は違うかもしれないけれど、一皮剥けば中身は同じ、ということです。そして、当時の人もそれを当然のごとく認識していたのでしょう。そりゃそうです。男女の関係というのは、社会情勢とか思想などによって多少左右される部分はあるにしても、本質的には、そう変わるものではないでしょうから。竹取物語のことなんて、今まで真剣に調べたこともありませんでしたが、この作品から興味をもって、調べてみました。日本最古の物語、とされていますが、その原点は現存していないそうです。ただ、10世紀に書かれた、ほかの文献に「竹取物語」への言及があることから、少なくともそれ以前には世に出ていたことは確かで、遅くとも10世紀半ば、おそらくは890年代頃に書かれたものと推定されているそうです。執筆者は不明ですが、貴族社会のことや仏教、民間伝承についてよく知っていることから、貴族階級の中でも学問のある男性と考えられています。物語の中でコケにされる5人の公達のうち3人(阿倍御主人、大伴御行、石上麻呂)は実在の人物であり、車持皇子は藤原不比等、石作皇子は多治比嶋をモデルにしているといわれます。中でも藤原不比等の車持皇子は、蓬莱の玉の枝の偽者を作った挙句、その代金を踏み倒す、一番卑劣な人物として描かれていること(原作では、さらに卑劣なことをやっていますが、高畑監督は、そこまでは描いていません)から、作者は藤原摂関政治に対してかなり反体制的な考え方の持ち主と推定されているようです。月から来たかぐや姫、なのですから、よく考えてみれば物語の元祖であるとともに、SFの元祖とも言えるかもしれません。そして、いかにもな科学技術の結晶である宇宙船で宇宙人が飛来するSF小説や映画より、かぐや姫を迎えに来た一行の方が、「異世界からの使者」という印象を強く与える気もします。宮崎駿の「風立ちぬ」も素晴らしかったけど、「風立ちぬ」と「かぐや姫の物語」のどちらを選ぶかと言われたら(もちろん、どちらも選びたい)、私はかぐや姫をとります。
2014.01.23
コメント(0)
-

ラテンアメリカ、ドロボー体験
強盗:中南米ご用心、神出鬼没 遭遇時は抵抗せず南米エクアドルで昨年末に日本人夫妻が被害に遭った強盗殺人事件から間もなく1カ月。犯行の手口は、中南米で頻発する「特急誘拐」だったと見られている。6月開幕のサッカーのワールドカップでは多数の日本人がブラジルを訪ね、中南米各国にも立ち寄ると予想される。中南米で特に多い手口にはどんなものがあるのか。「ブラジルなどでは東洋系は総じて金持ちというイメージが広がっている。特に日本人旅行者は服や仕草が違い、目をつけられやすい」。邦字紙「サンパウロ新聞」編集局次長で、3度路上強盗に遭った松本浩治さん(48)はそう警告する。まず空港に到着すると、預けた荷物の中身が盗まれていることがある。高級ブランドのスーツケースは特に狙われやすい。成田空港や関西空港では搭乗前、有料で荷物を透明フィルムで何重にも巻いてくれる。開封に手間取りそうな荷物はそれだけで狙われにくくなる。市内へのタクシーは、空港の案内所が紹介する正規登録の車に乗るのが鉄則だ。運転手が強盗と共犯で、客を一時的に誘拐し金品を奪う「特急誘拐」を避けるためだ。空港を出たタクシーに目をつけ、信号で停車中にバイクで横付けして窓を割って荷物を奪う「窓割り泥棒」もいる。荷物は足元へ置くようにしたい。サンパウロでは銀行などで大金を両替した人が、店舗から出た途端にひったくりに遭う例が多い。銀行員や警備員が強盗と内通し、両替した人の身なりを伝えているとされる。このためブラジルでは、銀行内での携帯電話使用を禁じる法律ができたほどで、クレジットカードの利用が奨励されている。服装や所持品にも注意が必要だ。欧州の高級ブランド品は普及しておらず、それらを持てばすぐ観光客とばれる。貴金属、高級腕時計は外し、女性は薄化粧が基本。男性の帽子も目立つ。スマートフォンは富裕層の証しなので、街中でむやみやたらに撮影しない。歩きスマホはもってのほかで、簡単にひったくりに遭う。観光中にケチャップを服にかけたり小銭を落としたりして気をそらせた隙(すき)に荷物を取る古典的な窃盗や、集団で囲んで羽交い締めにする「首締め強盗」が日中、人通りの多い場所で発生している。サンパウロでは昨年1〜11月、届け出があっただけで1日平均500件の強盗、700件の窃盗事件が発生。強盗犯は拳銃を所持するため、抵抗せず財布を差し出すしかない。メキシコでは昨年9月、日本人出張者がホテルの部屋にかかってきた電話で「麻薬カルテルの者だ。言う通りにしないと部屋に行って殺す」と脅され、プリペイド携帯電話4台分の代金の振り込みを強要される恐喝事件が起きた。犯人は無作為に電話しているので、切ればいい。最も注意が必要なのは、無論夜の街。6月14日に日本−コートジボワール戦があるブラジル北東部レシフェは売春が盛んな都市だ。北東部は同国で最も殺人事件が多く、治安の悪い土地柄。試合終了は深夜なので、事前に旅行代理店を通じてホテルまでの足を確保しておくのが無難だろう。サンパウロの日系旅行代理店社長、吉原正浩さん(50)は、日本から24時間以上かけて中南米を訪ねる観光客に、到着空港で気を緩めないよう助言する。「空港での置き引きが最近、非常に増えている。貴重品入りのカバンを盗まれると、旅の出だしから身動きが取れない。ホテルに着くまで緊張を持続させて」と話す。---私は、ブラジルに行ったことはありませんが、中南米はメキシコ3回と南米3回(ペルー・ボリビア・チリ・アルゼンチン)の合計6回行っています。そして、強盗にはやられたことがないけど、ドロボーくんには2度やられています。一度目は1989年、ボリビアのオルーロのバスターミナルでニセ警官にボディーチェックされて、現金を取られました。もっとも、その時はニセ警官と思ったけど、あとから考えると案外本物だったりして。このときは、私服警官のような2人組が、身分証明書を見せて、犯罪捜査とか言って、身体検査をしたわけです。私の前にもう1人身体検査をされた奴がいましたが、おそらくそいつも一味だったのでしょう。財布や腹巻の貴重品をチェックして、それらを確かに私のカバンに戻したように見えた(警戒していたので、指先を注視していた)のでした。しかし、「警察のオフィスにいくから歩け」と言われて、2~3歩歩いたところで振り返ると、二人組はかき消すようにいなくなっていた。あっと思ってカバンの中を調べると、戻したように見えた財布が入っていない。やられた!って思いました。あの指使いは、まさしく手品師そのもの。このときの被害総額は270~280ドルくらい。当時のレートでは4万円以上です。ただ、取られたのは米ドル現金のみでした。トラベラーズチェックは漢字でサインしてあったので、現金化できないとあきらめたのでしょう。日本円の現金も取られなかった。ボリビアでは円をドルや現地通貨(ボリビアーノ)に両替するのが難しいからです。あと、靴に隠してあった100ドル紙幣は発見されなかった。なので、そのあとも旅を続けることが可能でした。2度目は1996年、メキシコの地下鉄ですりに会いました。これは、広い意味では強盗の一種といえなくもありません。地下鉄に乗る際、やけに多くの乗客(実はスリ団)に取り囲まれて、もみくちゃになったのです。その瞬間、メガネを弾き飛ばされた。そのめがねは、飛びついて取り戻しましたが、そのまま地下鉄に乗ったら、あれだけ大勢いたはずの客が、誰も乗ってこない。あ、スリ団だったのか、とその瞬間に気がついた。かばんはガッチリとガードしていたので取られなかったのですが、ポケットの財布がなくなっていました。そのときの被害額は日本円にして3000円か4000円くらいでしたが、クレジットカードが財布の中に入っていなかった。理由は忘れましたが、財布からクレジットカードだけ出してポケットに裸で突っ込んでいたのです。そのため、財布だけすられてクレジットカードはポケットの中に残っていた。あれが取られていたら、使用停止の連絡とか、いろいろ厄介だったはず。不幸中の幸いではあったものの、メキシコで地下鉄に乗る時にクレジットカードは持ち歩くべきではなかっった、と反省しました。その当時(1996年)は、まだ携帯がなかった時代ですが、今だったら、メキシコで地下鉄に乗る時に携帯は持っても良いか、持たない方が無難か、やっぱり持たない方が無難だろうなあ。メキシコでも地下鉄と市内路線バス、流しのタクシーは、ヤバイのだけど、私はかなり使いました。独身の時の一人旅はほとんど地下鉄ばっかり。空港やバスターミナルへの行き来など、重い荷物を持っているときだけしかタクシーは使いませんでした。実は新婚旅行(メキシコ)でも地下鉄と流しのタクシーは使いました。幸い、我々の新婚旅行では、変なトラブルには会わなかったけど。上記の、実際に被害を受けた2回以外に、狙われながら逃げ切ったことも何回かあります。2001年、ボリビアのラパスでであった手口は、私の横を、ある男が走り抜けて行くのです。その瞬間、なぜか私の目の前にお財布を落としていく。そうしたら、なぜかそこに別の男が現れて、その財布を拾い上げて、私に見せるわけです。結構な厚さの札束が入っている。「あいつ、落として行ったよ、山分けしちゃおうぜ」みたいなことを言うのです。だけど、どこからどう見たって怪しさ満点の状況で、さすがの私でも、頭の中は危険信号がチカチカと点滅。「カンケーないから」と無視して、その場を歩み去りました。「山分けしよう山分けしよう」としつこく追いかけてくるので、完全無視。最終的には、偶然制服警官とすれ違ったので、それ以上私を追いかけることをあきらめたようです。あとで知人に聞いたら、「それは典型的な手口だよ」と言われました。「山分けしよう」と言われて、うっかりその財布に手を出すと、「落とし主」が舞い戻ってきて「オレの財布から金を取った」と難癖をつけて、私をボコボコニしてカネを巻き上げる、という筋書きだそうです。そのとき、後で思い当たったのは、狙われる直前に写真を撮っていたことです。一眼レフのでかいカメラで。獲物捜しをしていたドロボーくんには、いいカモが来たって思われたでしょうね。ただ、ドロボーくんたちの手口が、さすがに稚拙すぎた。これも同じときですが、街中で、「私は困っている」という人に話しかけられたことがあります。「私は、ヒカ(JICA)で働いているんだけど、母親が病気で治療費が払えなくて何とかかんとか・・・・・・(結論)お金をくれ」という趣旨。JICAの名を出すんだから、私が日本人と当たりをつけて話しかけたのでしょうが、「これは詐欺か実話か」って考え込みましたが、結局は「私はただの旅行者で、あなたに何もしてあげられません、ごめんなさい」と言ってその場から逃げました。同じ旅行のとき、前述の、「典型的な手口」と教えてくれた知人に誘われて、その知人の知り合いの結婚式に出て、演奏したことがあります。結婚式の場所はボリビア・ラパスのダウンタウンで、ラパスより一掃治安の悪い、エル・アルトでした。帰路は夜です。タクシーの通るハイウェイに出るまでの間、その知人曰く「ここはすごく治安が悪いからね、気をつけて。一緒に演奏した××さん(地元在住のボリビア人)、前歯がないでしょう。彼、ここで強盗に殴られて、前歯全部折られちゃったんだよ。今日の新郎のお兄さんも、このあたりで強盗に身ぐるみはがれているから」ヒーー、地元のボリビア人でもやられちゃうのかよ、と思いながら、彼と、もう1人のボリビア人と3人で警戒しながら歩きました。前歯を折られたら、笛吹には致命傷ですからね。中南米で外を歩く時は、やっぱり常時どこか神経を研ぎ澄ましている必要があります。デイパックは必ず前に回しますし。それと、通常は外に出歩くときは盗まれて決定的に困るものは持ち歩かない。これに限ります。引用記事にあるケチャップ強盗は、25年前からある古典的手段ですね。当時はマヨネーズ強盗でしたが。シャンプー強盗だったり、そのほか色々な類似の手段は耳にします。私自身はやられたことはありませんけど。空港で航空会社職員や税関職員が荷物を抜きとる話も、よくありました。はっきり言って、ラテンアメリカでは制服を着て権力を持っている人たちが一番信用ならなかったりします。(権力はあっても給料が安いので、よからぬ手段で元を取ろうとする)だから、冒頭のニセ警官も、ニセではなく本物の警官である可能性が、大いにあり、なのです。私の場合は、バックパッカー(ザックで旅行)ですから、荷物に頑丈な鍵など付けようもないのですが、どうやらバックパッカーはたいして金目のものなど持っていないと思われているようで(実際、金目のものをバックパックに入れたことはない)、空港で荷物を抜き取られる類の被害にあったことはありません。しかし、まあそんなこんなはあるけれど、メキシコ、南米、また行きたいよーーー。
2014.01.22
コメント(4)
-
「固有の領土」という硬直した領土観
尖閣・竹島は「固有の領土」=中高指導解説書に明記検討-下村文科相下村博文文部科学相は14日の閣議後記者会見で、沖縄県の尖閣諸島と島根県の竹島について、中学校と高校の教科書編集や指導の指針となる学習指導要領の解説書に「わが国固有の領土」と明記するよう検討していることを明らかにした。 解説書は約10年ごとに行われる指導要領の改定に合わせて変更されるのが通例。現在の解説書は小中が2008年、高校が09年に公表されており、途中での見直しは異例という。 下村文科相は「将来を担う子どもたちが日本の領土を正しく理解することは、極めて重要なことだ」と説明した。---1週間前の報道ですが、自民党政権が学習指導要領に尖閣諸島と竹島を「日本の固有の領土と書け」と言っているそうです。4年も前のことですが、「固有の領土」なる言葉のおかしさについて、記事を書いたことがあります。固有の領土なんてものはない改めて調べてみましたが、そもそも「固有の領土」なる言葉には、国際法上の定義はないそうです。「固有の領土」の定義とは何でしょうか?固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に立たないことは明白です。---スローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎない、とは手厳しいですが、実際のところそのとおりでしょう。「固有の」なんて前置詞を振りかざすのは、尖閣・竹島・北方領土以外では見たことがありません。「東京は日本の固有の領土である」とか「本州は日本の固有の領土である」なんて言う人はいない。すなわち、「固有の」という単語が、領土問題を抱えている場所で、自国の立場を主張するためのプロパガンダ用語に過ぎないということです。「固有」を手元の岩波国語辞典で調べてみると、「1他から与えられたものではなく、もとからあること。2そのものだけにあること。特有。」とあります。尖閣諸島という島々は、この世に世界に二つとはない、という意味では、確かに「固有」ではあるでしょう。が、しかし、その意味では、固有ではない島、固有ではない土地なんてものがあり得るのか、ということになります。この世に固有ではない土地なんて、どこにもないわけです。したがって、「固有ではない領土」なんてものはあり得ないのだから、無意味に過剰な表現と言わざるを得ません。一方、「元からある」という定義に注目すれば、尖閣であれ竹島であれ、北方領土であれ、物理的には太古の昔からそこにあった(たぶん、人間の歴史より古くから)ことは確かでしょうが、「日本の領土」という意味では、元からあったものではないことは明らかです。2000年近い日本の歴史の中で、尖閣諸島や竹島が日本の領土になったのはいつのことですか、せいぜい百年余り前のことにすぎません。また、沖縄(琉球というれっきとした独立国だった)が日本に服属したのは17世紀、正式に日本の領土になったのは明治以降のことです。北海道も、室町時代以降にやっと道南に日本の支配が及ぶようになった程度です。東北地方ですら、日本の支配権が及んだのは平安時代以降のことです。領土も国境線も、時代とともにいくらでも動くことがあります。そもそも国家というもの自体が興亡を繰り返してきたわけです。絶対不変の国境線などというものは、あり得ない。そんなことはちょっとでも世界史を学べばすぐに分かることです。尖閣諸島や竹島、北方領土は日本の領土であると主張する、という政府の立場は分かります。私も尖閣諸島は日本の領土であると思います。ただし、北方領土は、歯舞・色丹の2島のみ日本の言い分に理があり、国後択捉にかんしての主張は無理筋であると思っています。竹島についてはよく分かりません。いずれにしても、です。「日本は尖閣諸島を実効支配している」というのは事実です。「尖閣諸島は日本の領土だと政府は主張している」のも事実です。しかし、「尖閣諸島は日本の『固有の』領土だ」というのは、事実というよりはプロパガンダです。いくらて゜゛も変わりえる領土と国境線を、絶対不変のものとみなすのは、硬直思考の一種であるように、私には思えます。学校教育を、事実を教える場ではなく、そのような硬直思考のプロパガンダの場にしよう、ということなのでしょうか。
2014.01.21
コメント(4)
-

カネで人の心は買えない、ということか
<名護市長選>稲嶺市長、移設反対派では過去最高の得票数米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題を争点に、今回で5回目となった同県名護市長選を制した稲嶺進市長は、移設反対派の候補としては過去最高の得票数・得票率で再選した。移設を巡り政府や政権与党と対立した候補が当選したのも初めて。逆に、自民推薦で敗れた末松文信氏は移設容認派として過去最低の得票数・得票率となった。それだけ政府・自民党に対する有権者の反発が強かったといえる。移設問題を争点とした市長選は1998年から始まり、移設容認派が3連勝。反対派が勝ったのは前回10年の稲嶺氏が初めて。この際、稲嶺氏は1万7950票(得票率52.3%)を獲得。それまでの反対派候補の中で最も票を集めたが、今回はさらに上回る1万9839票(同55.8%)を得て、末松氏に4155票の大差をつけた。また、容認派が当選した3回の選挙は、政府・自民党と候補者が連携。前回の市長選は「最低でも県外」を掲げた民主党政権下で実施され、稲嶺氏と政権の方針は一致し、同党も稲嶺氏に推薦を出した。今回は「辺野古推進」の自民党政権下で、移設を巡る稲嶺氏と政権のスタンスは真っ向から対立した。関係者によると、稲嶺氏は革新系政党の推薦を受けたが、保守系の企業や商店主の他、女性や若年層などからも幅広く支持を獲得。「市民をカネでつろうとする高慢な政府・自民党への反発があり、保革の共闘態勢となった」と分析する。稲嶺氏は20日の記者会見で「1996年の普天間返還合意以来、今回ほど争点がはっきりした市長選はなかった。推進、反対とはっきり分かれたので有権者にとってわかりやすかった」と指摘し、「市長の権限をきちんと行使したい」と改めて移設阻止の決意を語った。---私は、沖縄に行ったこともないので、当ブログではあまり「稲嶺応援!」みたいなことは書きませんでしたが、当選することを願っていました。この結果には万歳を叫びたいと思います。ところで、この選挙で、稲嶺市長再選の最大の「アシスト」となったのは、一説によると自民党の石破幹事長だ、というはなしです。「名護に500億円基金」石破氏、市長選でアピール自民党の石破茂幹事長は16日、沖縄県名護市で市長選の応援演説に立ち、名護市の地域振興に向けて500億円規模の基金を立ち上げる意向を明らかにした。「名護が発展することで沖縄も飛躍的に発展を遂げる。安倍政権として全面的に支援し、国、県、市が協力して新たに500億円の名護振興基金をつくる」と述べた。沖縄の経済振興を政権が後押しする姿勢をアピールし、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設を推進する狙いとみられる。19日投開票の市長選で党推薦候補を応援するため現地入りした。(以下略)---実に分かりやすい利益誘導です。しかも、それを告示後の選挙期間中に一陣営の応援演説で表明するのだから、いくら何でも露骨すぎます。札束で頬を叩いて、「欲しければ投票しろ」というのに等しい行為で、ほとんど買収まがいと言ってもいい。こういう発言は、人間のプライドをいたく傷付けるものです。結果として、冒頭の引用記事にあるように、移設反対派の得票は史上最多で、賛成派の得票は史上最低となったわけです。カネで釣る利益誘導主義は明白に拒絶されたわけです。カネで人の心は買えない、ということでしょう。で、選挙負けたとなると、さっそく振興基金500億円見直し 石破氏、名護市長選うけ沖縄県名護市長選で選挙期間中、500億円の振興基金構想を表明した自民党の石破茂幹事長は20日、米軍普天間飛行場の同市辺野古への移設反対を訴える稲嶺進氏の再選を受けて、「稲嶺進市長から言及がない以上、どうするか申し上げることは適切ではない。市長から伺い、しかるべく対応をする」と述べ、ゼロベースで見直す考えを示した。(以下略)---そりゃもちろん、稲嶺市長が「500億円の振興基金をください」などと言うわけがありませんから、そうなるのも当然でしょう。ただ、選挙に負けた翌日には白紙撤回というのでは、「あれは有権者の歓心を買って投票誘導するための手段だった」と自ら認めているようなものです。ひとことで言って、じつに醜悪であり、みっともない言動と言うしかありません。ちなみに、500億円を宣伝する怪文書(発行責任者の名も記載されておらず、選挙期間中なので、違法チラシになります)もばら撒かれたそうです。
2014.01.20
コメント(3)
-

西穂高・谷川岳リバーサルフィルムの写真
12月末に登った西穂高独標と、先週の水上温泉・谷川岳の写真ができましたので、アップしました。まずは西穂高独標。といっても、先に書いたように、天気が悪かったので、写真は多くありません。西穂丸山付近での撮影です。ガスの向こうにかすかに霞沢岳が見えます。同じく、西穂独標および西穂高岳本峰までのピーク群が、かすかに見えます。これは12月30日の写真で、これでもまだ、翌31日よりは天気は多少マシだったのです。翌日は、ほとんどマトモな写真は撮れませんでした。31日、西穂山荘からロープウェー方面への下り、樹林帯の中です。さて、続いて、1月11日、上越線水上駅で撮影した、蒸気機関車D51の写真です。機関車はまだ連結されていませんが、牽引される客車です。いわゆる「旧型客車」です。これもかなりの年代物です。一番手前のスハ42 2234は、1954年7月製造なので、今年60年。その他の各車もほぼ同年代に製造されています。しかし、この時代の客車は頑丈に作られている(その代わり重い)ので、それ以降製造された軽量客車より長持ちしています。この日は、客車はスハフ42+オハ47+オハ47+オハニ36という4両編成でした。フィルムカメラ時代の写真撮影時の露出の鉄則は、白っぽいものは標準より露出をプラス補正、黒っぽいものはマイナス補正です。でも、山の写真は撮り慣れてますけど、蒸気機関車の写真ははじめて撮るので、感覚がよく分かりません。マイナス1補正で撮ったら、黒くて潰れてしまい、やっぱり標準露出のほうがきれいに写ります。考えてみれば、機関車本体は黒いけど、その周辺は雪で白いですからね。それでもまだ暗部は潰れています。プラス補正くらいにすればよかったかな。激しい降雪です。機関室付近。鉄道省鷹取工場昭和15年とあります。後のJR西日本鷹取工場(2000年に廃止)の製造なんですね。しかし、でかいボイラーがあるとは言え、この吹きさらしの機関室は寒いだろうなあ。(そして、夏は暑いだろうなあ)続いて、翌1月12日の谷川岳です。朝7時前後、宿の部屋からの撮影です。前日が上記のような天気だったので、こんな晴天になったのはびっくりでした。ちなみに、同時に撮影したiPad miniの写真は、こうです。こういう写真は、露出補正のできないiPad miniでは、どうにもなりません。暗いほうに露出があってしまい、遠方の山は白く飛んでしまいます。何度か試したのですが、どうにもなりませんでした。こういう部分は、やっぱり「値段なり」の撮影機能なんですね。ズームもないし。前述のとおり、フィルムカメラの時代は、白っぽいものは露出はプラス補正をかけないと、適正な明るさになりません。しかし、ではプラス補正すればよい写真になるのかというと、そうとも言い切れません。天神平から少し登ったあたりからの谷川岳の写真です。確か露出補正プラス1で撮影したように記憶しています。これでも、まだ実際よりやや暗く写っています。一方、露出補正なしで標準露出のままで撮影したのは↓です。日没直前か、というくらい暗く写っています(実際には午前10時頃です)が、その反面、雪面の微妙な陰影がよく見えます。露出をプラス補正した写真は、明るさは実際の風景に近い(それでも暗いけど)代わりに、陰影の細部は白く潰れてしまい、のっぺりした写真です。雪山の撮影は、明るさが本物の風景に近ければ描写が潰れてしまい、細部の描写がきれいに見えると、全体に暗い写真になる、なかなか二律背反で難しいものです。この2枚の写真の中間あたりで折り合いが付けば、一番良いんでしょうが。私自身の好みでは、どちらかと言うと下の写真の方が好きです。ただし、私自身の肉眼でも、ここまで陰影が深く見えていたわけではありません。むしろ、写真を見てはじめて、「こんなに陰影が深かったのか」と気がついたくらい。山の写真撮影は、日中の時間帯より夜明け直後や日没直前の方がよい写真が撮れます。日差しの角度が浅いので、山の斜面に影が多く、自然な状態でも陰影がはっきりしやすいからです。とはいえ、家族旅行なので、夜明けの時間から山に入っている、というわけには行きません。夕方には雲が出てしまい。日が翳って陰影がなくなっていました。では、iPadでは・・・・・と思ったら、同じ場所ではiPadでは写真を撮っていなかったようです。比較的近い位置での撮影が↓そこそこに明るく、陰影の描写もそこそこ。まさに上記の2枚の写真の中間あたり、という感じです。なお、現在のデジカメは、どこをどう改良したのか、雪の写真でも露出補正なしで、適正な明るさに写ります。だから、露出補正できないiPad miniでも、山の中でとった写真はちゃんと撮れていますし、2011年に購入したコンパクトデジカメ(これは露出補正できるカメラですが)も同様です。ほどほどに標準的な写真を撮るなら、コンパクトデジカメに限ります。天神尾根に出てからは、ひたすら尾根筋を登っていくだけです。上州武尊山じゃないかと思うのですが、その場で地図とコンパスで確認しなかったので、よく分かりません。かなり上部まで登ってきました。これも、何枚かとった中では、標準露出で暗めに写っている写真が一番きれいでした。やはり天神尾根の上部(まだ山頂ではない)から万太郎山、仙ノ倉山、平標山方面を撮りました。手前の尾根は、雪面に亀裂が入っています。尾根筋の雪庇といい、いつ雪崩になっても不思議はなさそうな。ああいうところには近づいてはいけません。登ってきた道のりを振り返って。天神平のスキー場が小さくなりました。標高差600mというのは、1日の行程としては短いほうですが、それでもこうやって見ると、よく登ってきたな、と思います。山頂に着きました。オキの耳(1977m)から、トマの耳(1963m)を振り返ります。トマの耳まで引き返して、オキの耳を撮りました。雪庇がかなりせり出しています。間違えてああいう上に乗ったりすると、雪庇を踏み抜いて転落、ということになってしまいます。それにしても、スキーかスノボかわかりませんが、とんでもないところにシュプールがついています。通常の登山だと、あんな場所は雪崩が怖すぎてとても近づく気になれないのですが、スキーだと大丈夫なんでしょうか。そんなわけないですね。ただ危険地帯通過の所要時間が非常に短かい、ということはいえるのかもしれません。余談ですが、天神尾根には、スノーボーダーもかなり入っていました。しかし、スキー場も含めて、スノーボーダーばかりで、スキーはかなり少なかった。私自身は、スキーは数えるほどしかやったことがなく、しかも、もう20年以上ご無沙汰していますけど、今は、スキー人口よりスノボ人口の方がはるかに多くなっているんようです。肩の小屋まで降りてきました。ここから山頂(トマの耳)は、目と鼻の先です。この時期は無人で、屋外のトイレも撤去されていました。このあとの時間帯は、次第に雲が増えて、天神平に戻ってきた頃には曇りになってしまったのですが、ここまでの時間帯だけでも、こんな晴天に恵まれたのは、充分に幸運でした。
2014.01.19
コメント(2)
-
センチメントなのはどっちか
石原元都知事、細川氏らを批判 「ただのセンチメント」日本維新の会共同代表の石原慎太郎・元東京都知事は17日、23日告示の都知事選で細川護熙(もりひろ)元首相と小泉純一郎元首相が連携して脱原発を訴えることについて「物事を複合的に考えることができないのは愚か。類は類を呼ぶ体たらく。電力は経済の血液だ」と批判した。都知事選で支援する田母神俊雄・元航空幕僚長の事務所開きで述べた。石原氏は「小泉君という単細胞の元首相が言い出した。原発問題が都知事選のシングルイシュー(単一の争点)とは軽率な話だ」と語り、「原発を全廃すると何がどうなるか議論せず、ただのセンチメント(情緒)」と指摘した。---前の記事にも書きましたが、私自身が今回の選挙で誰に投票するかはまだ決めていませんが、少なくとも確定しているのは、田母神と枡添には投票しない、ということです。細川に投票するか宇都宮に投票するか、今のところは宇都宮に傾いているので、細川には投票しないかもしれません。なんといっても、政策の発表を延期延期というのはいただけない。討論会から逃げていることもいただけない。が、それはそれとして、原発推進派の細川攻撃の激しさを見ると、やっぱり原発推進派から見て一番脅威に感じられるのが細川陣営(実際には細川自身より、支援する小泉のほうでしょうが)なのだろう、という気はします。票は投じないかも知れないけど、立候補表明自体は、大いに評価したいところです。で、石原が脱原発派を口汚くののしるのは今に始まった話ではなく、以前からのことですが、「物事を複合的に考えることができないのは愚か。」という言葉は、むしろ石原自身をはじめとする原発推進派にこそ当てはまるんじゃないかと思います。「原発がなければ電力が維持できない」「電力がふんだんに使えないと経済が維持できない」という硬直した思考に凝り固まって、物事を複合的に考えることができていないのは、原発推進派のほうでしょう。国内の原発は、2012年5月から7月までと、昨年9月以降現在までの通算6ヶ月間、すべて停止しています。2012年から昨年9月までの間だって、稼動していた原発は関西電力大飯原発の2基230万kwあまりにすぎません。だから、もう約2年間、「ほとんどの原発が止まっている」状態が続いています。節電シフトなどの取り組みは、2011年夏にはいろいろと行われましたが、それ以降は工場の土日シフトのような類の大規模な節電は行われていません。しかも、去年も一昨年も、夏はかなりの猛暑、特に昨夏は観測史上に残る暑さでしたが、電力不足に陥ることはありませんでした。電力供給が明らかにもっとも危機的だったのは、もちろん、何の努力もなく余裕で足りた、などと言うつもりはありませんし、こんご半永久的に化石燃料に頼り続けるべきとも思わないけど、とにかく現状は電力が足りていることは間違いない。結果的にみて、日本中で節電意識が定着したため、例えば東京電力管内で見てみると、昨年あれほどの猛暑で、なおかつ節電の数値目標はもはや設定されていないにもかかわらず、最大電力は5093万KWで、5000万KWを超えた日は2日間しかありません。震災以前に比べて、1000万KWくらい電力の消費は減っています。どう考えても、情緒的なのは原発推進にしがみつき続ける石原らの方であるように、私には思えます。
2014.01.18
コメント(0)
-

消えた機関車たち
先日、水上駅で蒸気機関車に遭遇したことについて、ちょっと書きましたが、動いている蒸気機関車を私が見たのは、子どもの頃京都の梅小路機関車館で、動態保存の蒸気機関車が構内を展示運転するのを目撃して以来のことです。あれはいつのことだったか、はっきりとは覚えていませんが、小学校低学年の頃か、あるいは幼稚園児だったかもしれません。(おぼろげな記憶では、家族旅行で京都には、2回いったような気がする)旧国鉄から蒸気機関車が(動態保存を除き)消滅したのは、本線上の列車牽引は1975年12月、入替作業は1976年3月のことです。その時、私は小学校2年。つまり、私が梅小路機関車館で蒸気機関車に夢中になっていた頃、まだ北海道では現役の蒸気機関車が生きていたようです。そういえば、父に昔、「お前が生まれた後も、まだ蒸気機関車はこのあたりを走っていた」などと言われたことがあります。改めて調べてみると、各線の蒸気機関車最終運転日を調べたホームページがあることを発見しました。確かに首都圏の各路線でも、1969年から70年頃までは蒸気機関車が走っているんですね。ただ、その時私は1歳か2歳。見てはいたのかもしれませんが、さすがに覚えていません。私がよく覚えているのは、貨物用電気機関車EF15。戦後製ではあるものの、茶色のボディにデッキ・従輪つきの、いかにも古めかしい電気機関車ですが、私が小学生の頃、いや中学生くらいまでは山手線の貨物線をごく当たり前に走っていた。その姉妹機の旅客機EF58(外観はEF15とは全然違って、とても優美で大好きな機関車でした)も、これは旅客機なので山手線は走っていなかったけど、上野駅あたりでは、当たり前に見かけました。いつの間にかEF15もEF58も、完全に消滅しています。祖母が横浜の戸塚に住んでいたので、横須賀線(その当時、東海道本線は戸塚には停車しなかったし、東戸塚駅はまだなかった)で何度も祖母の家に行きましたが、その際にはEH10型電気機関車もよく見かけた。黒塗りで、2両をで1編成の貨物用電気機関車でしたが、これもいつの間にか消えてしまった。やはり動態保存機はありません。↓EF15型電気機関車↓EF58型電気機関車↓EH10型電気機関車蒸気機関車は動態保存機があるけれど、それより後に登場したEF58(蒸気機関車に匹敵するくらい人気のある機関車でしたが)は、保存機は何両かあるものの、いずれも当初は運転されていたものの、そのうちに動態を維持できなくなり、今は動いていません。ずっと昔にEF55型電気機関車の引退の話を書いたことがあるのですが、EF55も、1960年に引退した後、1980年代に整備されて動態復元したのですが、結局機器の劣化などで2009年を最後に動態を維持できなくなりました。考えてみると蒸気機関車は、多くは戦前戦中の製造です。先日水上で見たD51 498号機は1940年製造だそうです。一方、EF58は戦後の製造だから、たいていの蒸気機関車より新しい。にも関わらず、動態保存はできなかったわけです。電気機関車の方が、古くなった際の機器の修復などが難しい、ということなのでしょうか。今では、電気機関車が牽引する旅客列車自体がほとんど残っていません。「夜行列車」「食堂車」「急行列車」にくわえて、「客車列車」もまた絶滅寸前です。貨物列車では、2軸貨車が、ほぼ絶滅。無蓋車、有蓋車など、要するにタンク車とコンテナ車以外の貨車がほとんど消滅。何というか、旅情をそそるようなものが、すべてきえてなくなりそう、ということです。
2014.01.16
コメント(0)
-
脱原発知事選で何が悪い
都知事選 脱原発主張に利用するな東京都知事選を「脱原発」で戦おうと、細川護煕、小泉純一郎の両元首相が連携を確認した。17日に正式に出馬会見する細川氏は「原発問題は国の存亡にかかわる」と話し、小泉氏は「原発ゼロでも日本は発展できる」との認識を共有できたとして細川氏への応援を表明した。2人に共通するのは、都知事選をてこに「脱原発」の世論を一気に拡大する狙いだろう。だが、原発というエネルギー政策の根幹を決めるのは国の役割である。どうしても「原発ゼロ」を実現したいなら、今一度国政に打って出て問うべきだ。他にも多くある都政の課題を脇に置き、「脱原発」に都知事選を利用するのはおかしい。小泉氏は「今回の知事選ほど国政に影響を与える選挙はない」として、原発ゼロか、再稼働容認かという、2グループによる争いだと言い切った。小泉氏は首相時代、郵政民営化という単一テーマで衆院を解散し、大勝利を収めた。都知事選でも同様の展開を描いているのだろう。だがあの時は、あくまでも国政課題の民営化問題を総選挙で問うたのであり、都知事選で「脱原発」を掲げることと、同一視はできない。昨年、国内原発の「即時ゼロ」を唱えた小泉氏は、高レベル放射性廃棄物を埋める最終処分場が決まっていないことなどを理由に挙げた。だが、原発を即時ゼロにして、首都東京が消費する電力をどうまかなうのか。細川氏も、脱原発に至る道筋を語っていない。国家の最高指導者を経験した両氏が、現実的な解決策を示さないまま、「脱原発」ムードをあおる無責任な姿は見たくない。一昨年暮れの衆院選で、脱原発派の民主党や日本未来の党は大敗した。代替エネルギーの普及に見通しが立たない段階で、「原発ゼロ」などの急進的な主張は、国政レベルで広がりを持ち得ないことが示された結果だ。安倍晋三政権は「原発ゼロ」路線を見直し、安全性が確認された原発の再稼働を進める努力をしている。原発活用で安定的な電力供給を確保できてこそ、都民の生活を守り、経済を支えることができるはずだ。候補者には、現実に立脚した政策論争を聞きたい。---私自身が誰に投票するかは、現時点では未定です。細川を支持しているわけではないし、もともとは票を投じるつもりもありませんでした。ただ、こういう意見を見てしまうと、原発推進派にとっては、よほど細川が(というより、そのバックにいる小泉が)脅威なんだなと思うわけです。それほど原発推進派の脅威になるなら、票を投じてみても・・・・・・、しかし、いくら反原発に舵を切ったとはいえ、あの小泉がバックのいる候補者に票を投じるのは・・・・・・、と、現在考え込んでいるわけです。ま、私自身が誰に票を投じるかは別にして、脱原発を掲げる候補者が選挙で有力候補になるのは(当然すればいうまでもなく)よいことではあります。というわけで、例によって産経の社説(主張)です。「原発というエネルギー政策の根幹を決めるのは国の役割」とあります。それは事実ですが、地方自治体がそれに発言してはいけない、などということはありません。もちろん、都知事の政策は原発問題だけがすべて、ではないことは事実です。私も、脱原発問題のみではなく、それ以外の政策も考慮して、誰に投票するかを決めようと思います。ただ、それを決めるのは候補者と有権者であって、産経新聞ではない。「脱原発なんて都政の課題じゃない」と多くの有権者が思っているなら、細川候補や宇都宮候補は負けるでしょう。しかし、勝つにしろ負けるにしろ、どういう政策を掲げるかはそれぞれの候補者の自由です。産経も、そんなに脱原発が嫌なら、「都知事選だ脱原発など主張するな」などと言うのではなく、原発推進派の候補を支援すればいいだけの話なのです。「だが、原発を即時ゼロにして、首都東京が消費する電力をどうまかなうのか。」ともありますが、現にまかなっているじゃないですか。「一昨年暮れの衆院選で、脱原発派の民主党や日本未来の党は大敗した。代替エネルギーの普及に見通しが立たない段階で、「原発ゼロ」などの急進的な主張は、国政レベルで広がりを持ち得ないことが示された結果だ。」民意というのは永久不変じゃないので、一昨年の衆院選で脱原発派が負けたからと言って、脱原発の是非をもう一度民意に問うことに何の問題もありません。だいたい、選挙結果は選挙制度(小選挙区制)にも左右されます。脱原発派は、戦術的には負けましたが、原発推進派が得票の過半数を制したわけではないのです。誰に票を投じるかはともかくとして、都知事選における、原発是非を巡る激しい論戦を多いに期待します。
2014.01.15
コメント(4)
-

どんな服装で山に登るか
旅行から東京に帰ってきてから、何だか無茶苦茶寒いですね。職場なんか、室内温度にムラがあって、私のいる席は夏は温かく冬涼しい(笑)、いや、夏暑くて冬寒い場所で、なかなか厳寒状態です。え、水上温泉や、まして谷川岳の方がよほど寒いだろうって?もちろん気温のデータの上ではそうです。でも、実際の体感温度はどうでしょうね。一昨日の谷川岳なんて、途中までは暑くて暑くて、汗だらだらかいていました。ちなみに、その時の気温は、正確には不明ですが、谷川岳天神平スキー場のツィッターによると、12日朝7時の気温は-7.5度、今朝(1月14日)朝8時は-9.5度、午後3時は-8度となっています。私が天神平から谷川岳に登っていた時間の気温は分かりませんけど、-3~4度くらいでしょうか。山頂は天神平より650メートルほど高いので、気温の低減率(高度100メートル上がるごとに気温は0.6度下がる)から言うと、-7~8度でしょうか。でも、寒くないのです。厚着をしているから、でしょうか。私が冬山登山の際に来ている服は、だいたい下記のとおりです。左側はゴアテックスの雨具です。先日アイゼンを引っ掛けてズボンに穴をあけてしまったことで分かるように、素材の厚さとしてはペラペラです。だいたい、夏山用の雨具だし。その右側に3枚重ねで並べているのが、その下に着ている服です。下に着るものから順番に、上から並んでいます。長袖Tシャツ、長袖シャツ(タートルネック)、フリース(らしきもの)です。ちなみに、ゴアテックスの雨具と、長袖Tシャツ(肌着)は登山用品店で購入したもので、それなりの値段でしたが、その上に着るタートルネックの長袖シャツと、オレンジ色のフリース(らしきもの)は某大手スーパーで買ってきたもので、それぞれ値段は1000円くらいです。重要なことは、素材に綿が含まれていないことで、それがクリアできればどこで買ったっていいのです。で、12月末に西穂高独標に登ったときは、このすべてを着込みました。去年2月に八ヶ岳の赤岳に登ったときもそう。しかし、今回の谷川岳では、オレンジ色のフリースは、天神平についた時点で脱いでしまいました。暑くて着てられないことが、容易に推測できたから。つまり、長袖シャツ2枚の上に夏用のゴアの雨具という3枚重ねです。まあ、長袖「シャツ」と言っても、それぞれかなの厚手の生地ではありますが。その前、2012年に硫黄岳に登ったときも、2枚目のシャツはこれとは別のものですが、やはりシャツ2枚の上に夏用の雨具でした。その時は、硫黄岳は猛烈な強風、気温はおそらく-15度以下だったはずです。さすがにその時は、登っていてまったく暖かくはありませんでしたが、寒くて震える、ということはありませんでした。今回の谷川岳では、前半はフリース抜きでも暑くて汗ダラダラ。ただ、さすがに山頂付近は天神平より一段と気温が低いことと、山頂近くは斜度がそれほどきつくないため、汗ダラダラということはありませんでしたが。ちなみに、下半身は、ズボンとその上にゴアテックスの雨具のズボンという2枚重ねです。あ、もちろんその下にパンツをはいてますけど(パンツだけは綿製です)。以前は、ズボン下(ももしき、かな)を履いていたこともありますが、暑い、きつい、蒸れる、歩く邪魔、というわけで、全然使っていません(ただし、かさばらないものなので、持ち歩いてはいます)。まして、厳冬期登山用の分厚い上着とオーバーズボン(結構高価なもので、冬の八ヶ岳で2回くらい使いました)なんて、たとえ-15度の冬山といえども、暑くて着ていられないわけです。これらは、やたらとかさばるので、もって行くこともありません。※なお、これらの服装はあくまでも私の自己流なので、冬山のベテランから見てどうなのかは分かりません。職場の同僚と何回か一緒に冬山に登ったときに「普通のゴアテックスの雨具の方が楽だし寒くないよ」と教えてもらって、それ以来こういう服装なのですが、厳冬期の雪山に夏用の雨具で登っている人は、あまり多くないことも事実です。こうやって見ると、全部長袖、という点には留意すべきでしょうが、東京での日常生活とたいして変わらないのです。特に、フリースを省略して、シャツ2枚と雨具、というときは、日常生活より薄着でさえあります。なのに、何で寒くないかというとまず、冬山では帽子と手袋を欠かさないこと、これが大きいのだと思います。帽子は、スキー帽のような暖かいものですし、手袋は内側はウールの手袋(化繊のときもある)、外側にゴアテックスのシェルという2枚重ねです。そして、靴は冬山用の登山靴に、これまた厚い生地のロングソックス。その上にロングスパッツといういでたちです。↓手袋と帽子↓登山靴とロングスパッツ(スパッツは、現在使っているものはこの写真とは違います)やはり、手先足先の冷たさというのは、体感温度に大きな影響を与えるように思います。というか、谷川岳の山頂で手袋を外していたら、5分ほどで指がしびれてきました。30分の素手でいたら、かなり深刻な凍傷になるでしょう。もう一つは、ゴアテックスの雨具は風を通さない、ということです。私は、日常生活ではセーターを着ることが多いですが、セーターは保温性はありますが、風を通すので、風がある時は寒い。でも、ゴアテックスの雨具は生地はペラペラでも、風をシャットアウトするので、強風でもあまり体感温度が変わりません。だったら日常生活でもゴアテックスの雨具を着ればよいのですが、さすがにこの原色の雨具を日常生活で着るのはね・・・・・・。そして、最後に登山は坂を歩き続けている、つまり平地でのランニングに近い運動をしているので、体が温まっている、ということなのでしょう。
2014.01.14
コメント(0)
-

快晴の谷川岳
この三連休、家族旅行で水上温泉に行ってきました。で、その合間に私は谷川岳へ。初日は、3時頃水上駅に着いたところ、天気は雪。その雪の中を、なぜか多くのカメラマンがカメラをかまえて待ち構えています。実は、電車が水上駅に着く前から、沿線に、カメラを構えた人だかりができていたので、これはひょっとしたら、と思ったら、案の定、SLの復活運転「SL新春レトロみなかみ号」でした。水上駅には、まだ使用可能な転車台が残っているので、高崎から水上の間は、よく蒸気機関車の運転が行われているようです。我々が水上駅に着いたのは、ちょうどSL列車の折り返し時間帯だったようで、運良く蒸気機関車の機回し作業を目撃することができました。しかし、行きの電車内で子どもがiPadを散々使ったために、水上駅に着いた時点で、電池の残量がほとんどなし。動画撮影中にバッテリーが切れてしまいました。なので、連結のところまでしか撮影できませんでした。それにしても、カメラマンの数の多さに仰天しました。特に、水上駅から高崎方面に2~3分歩いたところに、何十人もの人が、すごいカメラとすごい三脚を構えて、ズラーッと並んでいました。蒸気機関車が好きな人って、多いんですね。書くいう私も、元鉄道ファンなので、かつての血(笑)が騒いで、撮影してしまいましたが。で、この日はこんな悪天候で吹雪でした。これでは、翌日も晴天は期待できないかな、と思いきや、翌朝は快晴。谷川岳が「のぼってください」と呼んでいるかのような天気になりました。谷川岳の登山ルートはいくつかありますが、積雪期に私が登れる、となるとロープウェイを使って天神尾根を登るルートしか無理です。これは、天神平のロープウェイ終点の状況です。朝9時半少し前頃、まだまだ晴天です。ここからしばらくは、スキーコースの脇を上ります。アイゼンとワカンの両方を持って行ったのですが、トレースがちゃんとついているので、アイゼンでいいだろうと思って歩き始めたら、トレース上でも、ズボズボと雪にはまって、なかなか進めません。そこで、途中からアイゼンからワカンに付け替えたところ、快調に歩いて行ったのですが、途中で一ヶ所、ワカンではちょっと厳しい場所があったのです。そう言えば、去年もここを抜けるのはちょっと大変だったような。そこで再びアイゼンに付け替えて、あとは全行程アイゼンで歩きました。天神尾根の稜線に出る少し手前から、谷川岳の全貌を撮影しました。過去2回谷川岳に登りましたが、いずれも山頂部がガスに覆われていて、今回初めて全貌の写真が撮れました。同じ場所から。去年は、1月と8月に谷川岳に登っていますが、8月は、ロープウェイ終点から山頂まで、2時間もかかっていません。 標高差600メートルで、日帰りの荷物だから、私の足だと1時間半くらいが標準なのですが、雪に足を取られながら歩くと、とてもそんなペースでは歩けません。先ほど触れた、ワカンからアイゼンに履き替えた場所以外は、厳しい部分はまったくないのですが、時間はかかりました。最初のうちは、汗ダラダラでした。だいぶ登ってきました。白と青の世界。去年は、このあたりからガスにまかれて視界ゼロでしたが、今回はずっと晴天。さすがに、このあたりまで登ってい来ると、気温も下がり、雪も締まっていて、アイゼンだけでもあまりもぐりません。汗も、さすがにこのあたりではかかなくなりました。頂上直下に肩の小屋があるのですが、登りではここは素通りして山頂に急ぎました。(もっとも、この時期は肩の小屋は閉鎖しているようです)そして山頂到着です。まず、1963mのトマの耳。しかし、ここも素通りして、もう一つのピーク1977mのオキの耳を目指します。トマの耳からオキの耳に向かう途中です。オキの耳に着いたのは1時過ぎだったので、登りの所要時間は3時間半か4時間近かったようです。オキの耳からトマの耳を撮りました同じくオキの耳より、万太郎山、仙ノ倉山、平標山方面一ノ倉岳、茂倉岳方面トマの耳には何人か人がいましたが、オキの耳には、私がついた時点では誰もいませんでした(トマとオキの間で2人の登山者とすれ違いましたが)。たった一人で山頂を独り占め。さっそくケーナを吹きましたが、その前もしばらく写真撮影で素手だったので、吹き始めた時点で既に手は痛みに近い冷たさを感じ始めており、「コンドルは飛んでいく」を1曲吹いたら早くも限界。時間的にも少し遅いし、朝方には快晴だった空も、この時間になると少し雲が出てきたので、下山にかかりました。まずは、登りでは素通りしたトマの耳に立ち寄ります。ここには何人か登山者がいたので、記念写真など撮っていただきましたが、ガスがかかってきたため、更に下って、やはり先ほど素通りした肩の小屋に立ち寄ります。もっとも、前述のとおり閉鎖中でしたが。トイレがあるかと思ったら、小山閉鎖期間中は撤去されているようです。ここでカップめんを食べたのですが、これがちょっと失敗。保温ポットでお湯を持ってきた(普通の感覚でいえば、まだ充分な熱さだったと思います)のですが、カップめんの方が冷え切っているため、注いだお湯も一挙に冷める。3分待つ間に更に冷える。結局、随分ぬるくなったカップめんを食べるはめに。まあ、それでも人肌よりは暖かかったですが。ここからの下りは、あっという間。天神平のスキー場までもう少し、というところで、再びケーナを取り出しました。そこまで降りてくると、山頂よりは気温も高く、ここでは3曲か4曲吹きました。その場所から、下ってきた天神尾根を振り返ります。同じ場所から。万太郎山か、その手前の尾根の川棚ノ頭か、私にはちょっと分かりませんでした。で、このあと天神平に戻ってきたのは3時半前頃。そのときには、天気は曇りになっていました。(雲が高いので視界はありましたが、日差しはない)その後、夜には雪が降り始め、今朝も吹雪でした。2泊3日の日程で、初日と3日目は雪、私が山に登る日だけ快晴、という奇跡のような天候。年末に北アルプスで吹雪かれた分を取り戻した感じです。例によってリバーサルフィルムでも撮影したので、後日そちらも公開します。特に、蒸気機関車D51は、iPadでは動画しか撮影しておらず、写真はフィルムカメラでしか撮っていません。(蒸気機関車は撮影したことがないので、明るさの補正がうまくいっているかどうかは、プリントしてみないと分かりませんが)
2014.01.13
コメント(2)
-

記憶に残る小説
このブログで、書評というのはあまりやったことがありません。 「メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故」(講談社文庫 大鹿靖明著)と、「福島原発の真実」(平凡社新書 佐藤栄佐久著)を取り上げたことがあるくらいです。私は、おそらく読書家と言われるような人に比べれば、さほど本を読んでいないし、特に最近は重厚な本より新書ばかり読んでいるような傾向もあります。そんな私でも、特に強い印象の残る小説が、何冊かありますので、順不同に紹介しようと思います。「所有せざる人々」アーシュラ・ル・グィンアーシュラ・ル・グィンと言えば、スタジオジブリがアニメ化したゲド戦記(アニメはあまり評判がよくなかったけど)が有名です。あれは児童文学ですが、児童文学ではない一般向け小説(主にSFが多い)も数多く書いています。それらの一つで、「ハイニッシュ・ユニバース」というシリーズに属する作品です。人類が、遠い将来宇宙に広がっていき、あちこちの星で、人類とよく似た知的生物の高度文明と遭遇する時代の物語りです。(それらの知的生命体は、古い時代に地球人類と枝分かれした遠い親戚同士であるらしいことが、いくつかの作品で示唆されています)「所有せざる人々」は、ある連星の片方には豊かな物質文明を誇る人々が住み、もう片方には、エコロジー的な生活を指向する人々が住む、そんな星の物語です。ただし、エコロジー生活をする人々が住む星は、惑星アレナス(スペイン語で砂の意味です)と名付けられ、荒涼とした星で、自然はあまり豊かではなく、むしろ、物質文明を謳歌する星(惑星ウラス)の方が自然が豊かなのです。その惑星アレナスから、ウラスに、一人の科学者が渡ります。この科学者が故郷アレナスで送ってきた生活と、ウラスに渡ってからの出来事、つまり過去と現在が交互に登場する手法が取られています。同じく、「ハイニッシュ・ユニバース」に属する1冊、「闇の左手」もお勧めです。両性具有の種族が暮らす星に渡ってきた、地球人の外交官が、その星の国家間の争いに巻き込まれて、逃避行を繰り広げる話です。「泥流地帯」/「続・泥流地帯」三浦綾子三浦綾子の小説も大好きです。何しろ、旭岳に登った際、帰路に旭川で三浦綾子記念文学館に寄ってしまいました。旭川に行く機会があったら絶対に、って思っていましたから。最初は、たまたま「銃口」を舞台化した演劇を見る機会があって、それで読み始めたら、はまってしまったのです。もっとも、その「銃口」の原作は、なかなか手に入らなくて、だいぶ後になって読みましたが。三浦綾子の代表作は何と言っても「氷点」でしょうし、これも好きですが、1冊だけ挙げるとすれば、「泥流地帯」と「続・泥流地帯」です。(泥流地帯は、完全に物語の途中で終わっており、続・泥流地帯と併せて、はじめて一つの物語になります。個人的には、タイトルは、「続」ではなく、「上下」にした方が良いいような気もしますが)これは、十勝岳の大正噴火(噴火によって積雪が一挙に溶融、火山泥流となって上富良野の町を襲い、140人以上の死者が出ている)を描いた話です。貧しくつらい生活の開拓移民ながら、何とか心豊かに、少しずつ生活の安定を掴み始めていた主人公の一家、貧しさと、親が酒乱であるに、遊女に身を落としたヒロイン、2人とも、十勝岳の噴火によってすべてを失い・・・・・・以下はネタバレになりそうなので、書くことはやめておきます。三浦綾子の小説は、とにかくみんな好きですね。前述の「銃口」「天北原野」「海嶺」なども印象に残っています。北海道の人なので、だいたいの小説は北海道が舞台です。「海嶺」は違いますが。三浦綾子記念文学館周辺は外国樹見本林になっています。「氷点」の舞台として出てくる場所です。撮影は2003年8月です。「エバ・ルーナ」イサベル・アジェンデイサベル・アジェンデは、かのサルバドル・アジェンデの従兄弟の娘に当たります。アジェンデというのは、バスク系の苗字で、スペイン語圏でもあまり多くはなく、どちらかというと「名門」というイメージです。チリで雑誌編集者をしていましたが、アジェンデの親族であることから、クーデターの数年後にベネズエラに亡命します。その後彼女は夫と離婚してしまい、米国人と結婚して今は米国在住です。おそらく、現在ラテンアメリカではもっとも人気のある小説家だと思います。半分くらいの作品は日本語に訳されています。処女作となった「精霊たちの家」は非常に面白い作品であると同時に、多少難解なところもあるのですが、その後の作品はどちらかと言うと大衆文学の分かりやすさで書かれています。「エバ・ルーナ」は彼女がベネズエラに住んでいたころ、ベネズエラを舞台にして書いた小説です。貧民出身で、親に先立たれた孤児のエバ・ルーナと、オーストリア出身のジャーナリスト、そして武装闘争を行う左翼ゲリラ、非常にワクワクする冒険劇です。そしてもう一つ、「パウラ、水泡なすもろき命」これも傑作です。ただ、これは小説というよりは自伝です。アジェンデの娘・パウラは、28歳のときに、ポルフィリン症の発作を契機にしてこん睡状態に陥ります。(今にして考えると、これって限りなく医療ミスの匂いがしますが)こん睡状態が続いている間、「もし彼女が目を覚ましたとして、途方にくれないように」と物語るために書いた、アジェンデ自身の自伝です。しかし結局、パウラは意識を回復することなく、1年後にこの世を去ります。その部分の描写は、(日本語訳で読んでいますけど)非常に美しく、胸が締め付けられるようです。「武揚伝」1・2・3・4佐々木譲「ベルリン飛行指令」で佐々木譲の小説を始めて読み、この人にもはまりました。でも、中でも印象に残っているのが「武揚伝」です。幕末の歴史といえば、たいてい維新の志士が正義の味方で、徳川は老残の旧体制の権化。しかし、佐々木譲はあえて、五稜郭に逃げ込んだ旧幕府軍を正義とする視点で小説を書いています。おそらく、歴史的事実としては、「蝦夷共和国」の実情は先進的なものではなく、徳川残党の苦し紛れの策に過ぎなかったのだろうと思います。が、佐々木はあえてそこに、明治政府がその後進んでいく対外戦争と侵略の歴史とは違う道の日本、いや、違う道の北海道(佐々木も北海道の出身ですね)という夢を、小説に託したかったのでしょう。それにしても、坂本竜馬や、幕府側としては人気のある勝海舟をあえて小物や嫌なやつに描く発想はすごいな、と思います。その代わり、函館で死んだ土方歳三は、えらくかっこいい描き方。ま、実際残っている写真を見ると、今の感覚でも、男の私から見てさえ、確かに「いい男」だと感じますが。他にも、「これは」という小説はいくつかあります。気が向いたら、また紹介するかもしれません。
2014.01.11
コメント(2)
-
戦争をしたい自民党
自民方針案「靖国参拝受け継ぐ」明記 「平和国家」削除自民党は8日、2014年の党運動方針案を決めた。「靖国神社への参拝を受け継ぐ」と明記し、党の憲法改正草案を説明する対話集会を開いて改憲の機運を高めることを狙うなど、保守色の強い内容となった。19日の党大会で正式決定する。靖国参拝について、当初案では「不戦の誓いと平和国家の理念を貫くことを決意し、靖国神社の参拝を受け継ぐ」と例年通りの記述だった。だが、7日の総務会で「靖国神社は不戦の誓いや国家の平和を祈るところではない」などの異論が出た。一方で「自衛隊員にもしものことがあった場合、靖国神社に奉る覚悟を示すべきだ」と表現を強めるよう求める声も出たため、総務会での了承は見送り、石破茂幹事長に一任された。最終的に「不戦の誓い」と「平和国家」の文言を削除し、「日本の歴史、伝統、文化を尊重し、靖国神社への参拝を受け継ぎ、国の礎となられた方々に対する尊崇の念を高め、感謝の誠を捧げ、恒久平和への決意を新たにする」との文言に落ち着いた。憲法改正については、「党是である憲法改正の実現に向けて、党全体として積極的に取り組む」と踏み込んだ内容にした。---昨年末、安倍が靖国を参拝したとき、安倍は「恒久平和への誓い」なる談話を発表しています。その中で、「日本は、二度と戦争を起こしてはならない。私は、過去への痛切な反省の上に立って、そう考えています。戦争犠牲者の方々の御霊を前に、今後とも不戦の誓いを堅持していく決意を、新たにしてまいりました。」なんてことを言っていた。そのような思いを表明する場として靖国はふさわしくないと思っていたら、何と自民党内でも「靖国神社は不戦の誓いや国家の平和を祈るところではない」という意見が出たそうで。まったくそのとおり、ではあるのですが、だから靖国参拝をやめる、というのではなく、「不戦の誓い」と「平和国家」の方をやめる、というのですから、こりゃもうあきれ果てた話です。結局、安倍の言う「恒久平和への誓い」が、まったくその場しのぎの口からでまかせでしかなかったことを、こうして自民党自らが証明してしまったわけです。挙句の果てに、「自衛隊員にもしものことがあった場合、靖国神社に奉る覚悟を示すべきだ」などという意見まで出たそうで。いったいどの政治家がそんな暴論を掃いたのかは知りませんが、それは、戦争をやってもよいんだ、戦争で死者を出してもよいんだ、という意思表示に他なりません。それにしても、です。自衛隊員を靖国神社に奉る「覚悟」とは、いったいどんな覚悟なんでしょうか。自分自身が靖国神社に奉られる(つまり、死ぬ)覚悟なら、まだ分かります。しかし、自民党の国会議員が戦場に行く可能性など、まずありません。自分自身には命の危険のない立場の人間が、自衛隊員に戦地に行けと強いるだけで、靖国神社に奉る「覚悟」とはね。覚悟ってのは随分軽薄ものなのだなと呆れてしまいます。自分自身が命の危険を冒すのでなければ、どれだけ勇ましいことをいうことだって平気ではあるでしょう。こういう、人の痛みを理解できない政党は、そのうち本当に戦争を引き起こしかねない、今ほどそういう危惧を強く抱いたことは、これまでにありません。週刊新潮の最新号に、靖国参拝「安倍総理」を暴走させるFacebook「いいね!」という記事があります。週刊新潮と言えば、都会の保守オヤジの代弁誌みたいなものであり、毎号反中国、反韓国の記事が書き連ねられている右翼週刊誌ですが、そんな週刊新潮ですら、思わずたじろいでしまうくらい、「ネット世論」の空気は異常、ということのようです。しかし、昔から独裁者は周囲をイエスマンで固めて道を誤るものです。安倍第一次政権も、「お友達内閣」などと揶揄されていましたが、これも同じでしょう。そして今回は、フェイスブックの「いいね」という擬似世論のイエスマンに囲まれて、ご満悦でいるようです。何というか、本当に日本の将来は暗い、と思ってしまいます。
2014.01.10
コメント(2)
-
安楽死
ベルギー最高齢アスリートが安楽死、シャンパンで乾杯して旅立つベルギーで「最高齢アスリート」として親しまれてきたエミール・パウウェルスさん(95)が安楽死を選択し、家族や友人約100人とシャンパンで乾杯をした後に旅立った。7日のベルギーのメディアは、前日の6日に自宅で家族や友人、スポーツクラブの仲間たちに囲まれ、微笑みながら乾杯しているパウウェルスさんの姿を伝えた。フラマン語の現地日刊紙ヘット・ラーツテ・ニウスによると、パウウェルスさんは6日、「後悔はしていないし、死への恐怖感はまったくない。わたしの人生の中で最高のパーティーだ。友人全員に囲まれて、シャンパンと共に消えていくのが嫌だなんて人がいるかい? 」と語った。「注射薬を持って医師が来たとき、わたしは満たされた人生を送ったと思いながら、この世を去る」パウウェルスさんは末期の胃がんのため、この数か月間は寝たきりになっていた。昨年3月に行われた高齢者欧州選手権の屋内60メートル走で優勝したのが、アスリートとして残した最後の大きな成績だった。ベルギーでは2002年に安楽死が合法化され、12年には1432件が報告された。現在は安楽死の対象を、12歳を超える子供にも拡大することが検討されている。---私の父は、膀胱ガンが最後は全身に転移して、亡くなる前の1ヶ月あまりは、そりゃもう本当に大変でした。ガンもいろいろで、それほど苦しまずに亡くなる方もいるようで、医師には「死ぬならガンで死ぬのが良い」と言う方もいるそうですが、私の父の場合は、本当に苦しんで苦しんで、苦しみぬいて死んだ。いろいろな鎮痛剤や、おそらく麻薬の類の痛み止めも使ったはずです。でも、苦しみから解放されることはなかった。一時は利いても、だんだん利かなくなる。苦しみぬいて生還できるならともかく、末期がんの場合、苦しみぬいた挙句、その先には死しか待っていません。同じ死ぬなら、こんなに長く苦しみたくない、早く殺してくれ、と父が思ったかどうかは分かりませんが、口に出してそんなことをいうことはありませんでした。もっとも、最後は、譫妄(ガンによる、ある種の認知症的な状態)が出て、正常な判断力はなくなっていましたが。若い頃はとてつもなく頭の良かった父だけに、その最後の姿はなんとも・・・・・・。四十数年の結婚生活で、楽しいことも大変なことも随分いっぱいあったのに、母は、夫のことで何気なく思い出してしまうのは、いつも最後の苦しんでいた姿ばかり、と言っていたことがあります。父の闘病生活は1年ちょっとでしたが、本格的にどうにもならなくなったのは、再発が分かって以降の最後の1ヶ月でした。1ヶ月だったから、まだ何とかなったけれど、あの苦しみが更に何ヶ月も続いたとしたら、本人もさることながら、周りの負担も限界だったかもしれません。母は病院に何回も泊り込んだりしていましたが、そのとき70歳でしたから、よく体力が保ったものと思います。幸い、あれから約5年、母は今も元気ですけどね。安楽死は、日本ではまったく認められていません。医の倫理とか、「厄介な患者」に死を強要しかねない可能性とか、いろいろと問題があるのは分かります。ただ、私も父の死の直前の姿を見て、これほど苦しみぬいている父が、その状態のままで生きながらえてほしいとは、さすがに思いませんでした。それは生者の都合であって、死に行くものがどう考えているかは分からないけれど、いかに考えても、あの状態で生きていることが本人にとって苦痛以外のものであるとは思えませんでした。でも、日本ではまだまだ安楽死というのは社会的な合意が得られないのでしょうかね。引用記事のエミール・パウウェルスさんは、最近数ヶ月は寝たきりだったそうですが、昨年3月には60メートルそうで優勝だそうなので、その時点ではピンピンしていたわけです。94歳くらいまでピンピンしていて、最後の数ヶ月だけ寝たきり、そして自らの意思で人生に終止符を打つ、充実した人生だったんでしょうね。家族や友人約100人とシャンパンで乾杯というのは、事実上の生前葬でしょう。
2014.01.08
コメント(4)
-
これじゃ少子化するに決まっている
子どもを電車に乗せてはダメ?大人が寛容にすべき?年末年始も賛否を呼んだ公共交通機関のマナー 年始から、一部のツイッター上で議論となっていたのが、電車に子どもを乗せる際のマナーについて。昨年も漫画家のさかもと未明氏が飛行機に子どもを乗せるのは子どもにとっても負担が大きく、周囲の迷惑になるという内容を書いた雑誌記事がネット上に転載され、「炎上」するという出来事があった。新幹線の乗降客の多い年末年始の時期に再び持ち上がったこの話題。公共交通機関でのマナーについて、世間の人々はどう考えているのか。車内で泣く子ども「舌打ち」ぐらいはしてもいい?Twitter上のつぶやきをまとめているTogetterの「子供が車内で騒いでいたら 舌打ちぐらいはしてもいい?」というトピックを見てみよう。ことの発端は1月5日。NPO法人フローレンス代表理事の駒崎弘樹氏が「今、新幹線で後方の席の子どもが泣いてて、隣の席の女性がうるせーな、って言いながら舌打ちしたんだけど、そういう人は新幹線自由席じゃなく、車で移動すべきだ。公共交通というのは、老若男女、色んな人が乗るもの。公共圏は、我々が当事者意識と寛容によって生み出すものだと思う」とつぶやいた。これに「舌打ちくらいいいんじゃないかと思ったりするwww」と反応したのが堀江貴文氏。しばらく2人のやり取りが続き、どちらもフォロワー数が多いこともあって、さまざまな意見が噴出した。また、乗車マナーの話題とは少しズレるかもしれないが、混雑に見舞われた新幹線車内で「立っているお年寄りをグリーン車に乗せるべき」とツイートしたアカウントが、「金を払っていないのにグリーン車に乗せろという主張はおかしい」といった反論を受けて「炎上」するということもあった。(参考:『超混雑だった東海道新幹線の乗客が「立っているお年寄りをグリーン車に乗せるべきだ」とツイート→炎上』)年末年始の時期は家族連れの移動が多く、子どもや高齢者の利用が普段より多いと推測される。公共の場である電車で、社会的弱者である存在と接することが普段より多い時期とも言えるだろう。どちらもこの時期ならではの話題だったという印象だ。(以下略)---以前に、さかもと未明という漫画家(というより、極右文化人)が、飛行機の中で泣き叫ぶ子どもにブチ切れて、着陸直前の機内で席を立ち、「飛び降りる」と叫んで走り出すという騒動が報じられたことがあり、その件に関して記事を書いたことがあります。子は泣くもの子どもは泣くものです。こりゃもう、人間は息をするもの、というのに等しいくらい絶対普遍の原則です。乳児が泣かなかったらやばいですよ。まあ、そういうことを、人はみんな子育てをしたとき初めて体感して、寛容になっていくものなのかもしれません。ただ、例えば幼児が駄々をこねて金切り声を挙げるような場合(3~4歳くらいが多いかな、当然、乳児はそういうことをしない)、それが至近距離だったりすると、さすがに「うるさい」と思うことはあります。うるさい、というか、物理的に耳にキーンと来る。そういう時は、多分顔をしかめているんじゃないかと思います(その瞬間の自分の表情を正確に把握しているわけじゃないけど)。口には出しませんよ。しかし、耳が耐えられる以上の音量が飛び込んできたとき、思わず顔をしかめることも、人間の生理現象としてやむを得ないことだとは思います。というわけで、堀江貴文が「舌打ちくらいいいんじゃないかと思ったりするwww」と言ったそうですが、私も、まあ舌打ちくらいは仕方がないかなって思います。そこまでなら、まあ生理現象のようなもの、ともいえますから。ただ、その子どもが何歳くらいでどの程度の泣き声で、その親がなだめようとしていたのか放置していたのかなどの詳細が分からないので、確たることは言えませんけど、私の直感では、そこで「うるせーな」と声に出してしまう人に、ある種の危うさを感じてしまうのです。そっちの方がマトモじゃないような・・・・・。いや、それもある種の偏見かもしれませんけどね。それはともかくとして、こういうことに関しては、お互いが寛容になるしかないだろうと思うわけです。堀江貴文は、売り言葉に買い言葉なのだろうけど、子どもに睡眠薬を飲ませろ、みたいなことまで書いている。私はどうも、その種の向精神薬を子どもに飲ませるというのは承服できないのです。医学的にどうなのかは分かりませんし、年齢にもよるでしょうが、乳児だったら、例えば風邪薬(あの眠くなる成分は、ごく弱いとはいえ向精神薬的なものだと思う)だってどうかと思います。子どもの泣き声程度にそこまで不寛容な社会で、いくら少子化対策などと言ったって、そりゃ無理でしょうと思ってしまいます。子どものわがままを何でも聞いてやれ、などとは言わないけれど、少なくとも泣き声くらいはね。その後段、「立っているお年寄りをグリーン車に乗せるべき」とツイートしたアカウントが炎上というのは、そのアカウントは有田芳生参議院議員の娘のアカウントなのだそうですが、1月3日の有楽町での火災で新幹線が何時間もとまってしまった間に、とりあえず空席のグリーン席をお年寄りなどに開放したら、という提案だったようです。結果的にその提案は断られたようですし、彼女もそれ以上強硬に主張したわけでもなさそうです。JRの立場としては、いくら非常時でもグリーン券を持たない乗客をグリーン車に座らせたくはないだろうし、こういう回答は仕方がないだろうとは思います。ただ、こんなことで炎上というのはまったく不可解です。結局のところ、在特会などのネットウヨクに強硬姿勢をとる議員の親族だから、ということで、ネットウヨクがたかってきて暴れた、ということなのではないかと思えます。これもまた、不寛容さが招いた騒動、というところでしょうか。
2014.01.07
コメント(4)
-

またまた凄まじい社説
原発再生元年 核燃サイクルで活路開け 再処理工場の稼働が急がれる異例の年始といえよう。平成26年は、原子力による電力供給が「ゼロ」で明けた。国内50基の原発が昨秋以来、すべて停止しているためである。昨年7月、原発の新規制基準が施行され、第1陣として北海道、関西、四国、九州の電力4社が、計12基の原発の安全審査を原子力規制委員会に申請した。半年が経過し、審査の完了した原発は1基もない。牛の歩みを思わせる緩慢さだ。電力会社への資料提出の求め方などに手際の悪さがあるのでないか。規制委は外部とのコミュニケーションを密にして的確な審査を円滑に進めるための改善努力が必要だ。≪断層調査の予断を除け≫原発の再稼働が1日遅れるごとに、50基合計で毎日100億円の国富が消えることを忘れてはならない。社会は、時間を軸に回っている。規制委も健全な時間感覚を身につけなければ、適切な規制を行えない。規制委の指示に従い、電力会社は津波やテロなどに対する大規模な工事などを集中的に実施したではないか。規制委も速やかな審査で応えるべきである。規制委が安全審査を終えないと、原発は再稼働に進めない。安全性が確認された原発を順次発電に復帰させ、電気代の再値上げを回避したい。景気浮揚には安定した電力供給が不可欠だ。完成の域に達している日本原燃の再処理工場(青森県六ケ所村)の安全審査も、着実に進めてもらいたい。原発で使い終えた燃料を再利用する核燃料サイクルは、資源に乏しいわが国の活路を開くエネルギー戦略だ。再処理工場では、使用済み燃料からプルトニウムとまだ使えるウランを取り出し、不要な核分裂生成物をガラスで固める。昨年5月、ガラス固化体製造にも成功した。だが、昨年末に核燃料施設用の新規制基準が施行され、それに基づく安全審査を待たなければ完成できなくなった。再処理工場の完成が遅れると、国内各原発の燃料貯蔵プールの収容能力を超えかねない。規制委は、再処理工場など複数の原子力施設が立地する下北半島の地下構造を調査しようとしているが、中立性の維持された調査と判定が望まれる。これまでに手がけてきた原発敷地内の断層調査は、はかばかしい進展を見せていない。活断層を発見したいがために、「見たいものが見えてしまう」ような予断を含む調査は、決してあってはならないことだ。原子力を他のエネルギーと同列に扱う考えがあるなら、明確な誤りだ。非核保有国で唯一、日本に再処理が認められているのは、日米原子力協定があってのことである。30年を満期とする協定の期限が4年後に近づいている。再処理工場の操業開始が遅延すると協定の継続も危うくなろう。それでは、日本のエネルギー安全保障が根底から崩れかねない。≪最終処分場にもめどを≫最終処分場の候補地選定も急がれる。小泉純一郎元首相が言うように「原発即ゼロ」にしても、高レベル放射性廃棄物を含む使用済み燃料は、すでに大量に発生している。最終処分場を造らずに済ませることはできないのだ。これまでの市町村側が手を挙げる応募方式から、政府が地質的に適した候補地域を全国的に広く示した上で、複数地点に申し入れをする方式に転換する方針も昨年示された。これ以上の先送りは許されない。現世代の責任として取り組みを進める道を探りたい。フィンランドとスウェーデンでは困難を克服して進んでいるではないか。これとは別に、東電事故で発生した福島県内の放射能汚染土壌などを30年間保管する中間貯蔵施設の建設も急がれる。福島の復興促進のためにも欠かせない。1月中に閣議決定されるエネルギー基本計画においても、原発はエネルギー需給構造の安定性を支える基盤となる重要なベース電源として位置付けられる。太陽光や風力発電への期待も高いが、再生可能エネルギーだけでの電力生産には限度がある。現代社会は、大量のエネルギーの土台の上に構築されている。それを忘れれば、日本の先進国としての存続さえ危うくなる。理性あるエネルギー再建に向かう出発の年としたい。---例によって例のごとく、ネトウヨ新聞、いや産経新聞の社説です。産経の社説がトンデモなのは今に始まった話ではないけれど、これはまたすごいレベルの社説です。現在すべての原発が停止中であるということは、その分だけ原発事故の危険性が減っている、ということで、望ましいことだと私は思っています。ただ、私自身は、何度か書いているように、原発全廃のタイムスケジュールが確定すれば、それまでの間に限って、危険度の高い原発を除き原発を稼動することに反対ではありませんが。いずれにしても、危険度の高い原発については、再稼動することには反対です。「断層調査の予断を除け」これまで、散々「予断」で「安全だ、安全だ」と危険に目をつぶってきたのは、原子力ムラであったわけです。そのツケが来ているに過ぎない話であって、今の時点で「安全だ安全だ」と言って安易に安全審査を通すとしたら、その方が異常なことです。「規制委の指示に従い、電力会社は津波やテロなどに対する大規模な工事などを集中的に実施したではないか。」とありますが、どうなんでしょうか。例えば、一昨年、いったん再稼動された多い原発の場合、津波対策の工事は、日程が決められた、というだけで、実際には何も行われてはいなかったにも関わらず、再稼動されてしまいました。その後、現在では堤防のかさ上げだけは完成しているようですが。他の原発の進捗状況はどうなっているのでしょうか。「原発で使い終えた燃料を再利用する核燃料サイクルは、資源に乏しいわが国の活路を開くエネルギー戦略だ。」という主張にもびっくりです。核燃料サイクルは、明らかに破綻しているからです。「夢の核燃料サイクル」を実現するはずの高速増殖炉は、実用化できる可能性がまったく見えません。核燃料サイクルの見通しがまったく立たないにもかかわらず、使用済み核燃料の再処理を(国外に委託して)どんどん進めてしまった結果、日本は使いきれない大量のプルトニウム在庫を抱えてしまっている、それが現状です。プルトニウムは核兵器に材料になるので、大量の在庫を持たないことが国際公約なのに、在庫が増えてどうしようもないの。それでやむなくはじめたプルトニウム減らしの策がプルサーマル、つまり通常の軽水炉でプルトニウムをウランに混ぜて使用するやり方です。しかし、プルサーマルには多くの問題があります。ごく大雑把な言い方をすると、プルサーマルではプルトニウムのごく一部しか消費できない上に、何度も再処理することができず、核燃料の節約にはあまりならない、しかもコストが非常に高い。もちろん、事故のリスクも高まります。つまり、極論すれば、プルサーマルというのはプルトニウムを減らさなければならないからやっていることであって、リサイクルという意味は限りなく小さい。リサイクルとは、リサイクル品に活用の手段があって初めて成り立つのであって、リサイクル品の使い道がなくて汲々としているようでは、リサイクルとして成り立っていないのです。であれば、使い道に苦慮するプルトニウムの抽出などする必要がない、いやしないほうがよい、というのが論理的な帰着です。最終処分場についても、相変わらずの主張です。「政府が地質的に適した候補地域を全国的に広く示した上で、複数地点に申し入れをする方式に転換する方針も昨年示された。」そうですが、「地質的に適した候補地域」がこの日本で果たして見つかるのかどうか、いささか疑問の余地ありです。「フィンランドとスウェーデンでは困難を克服して進んでいるではないか。」そもそもフィンランドやスウェーデンと日本では、地盤的な条件がまるで違います。スウェーデンなんて、天然の洞窟をそのまま利用して地下鉄駅が作られたりしています。これほど強固な地盤の国と、日本のような軟弱地盤の国を同列において、「同じにやれ」というのは「バカですか?」という以上のコメントを思いつきません。もちろん、人口密度もまるっきり違います。そもそも、私は最近知ったのですが、かのフィンランドのオンカロですら、実は同国にある4基の原発の半分の高レベル廃棄物しか貯蔵できないのだそうです。フィンランドですら、「困難を克服」はできていない、ということになります。まあ原発推進で凝り固まっている新聞(産経新聞が狂っているのは、そこだけの問題ではないですが)は、もうどうにもならないな、という感じですね。
2014.01.06
コメント(0)
-

取らぬ狸の皮算用
リニア輸出:政府、米に5000億円融資提案安倍晋三首相が昨年2月、オバマ米大統領とワシントンで会談した際、ワシントン−ボルティモア間に超電導リニア新幹線を導入する構想について、総工費の半額を国際協力銀行を通じて融資する意向を伝えていたことが分かった。日本政府関係者が明らかにした。総工費が約1兆円と見込まれるため、日本政府は首相が再訪米した昨年9月までに、5000億円規模の融資を米側に追加提案した。実現すれば日本政府の対外融資で最大規模になる。JR東海はリニア新幹線の特許技術の無償提供を米政府に申し入れ、首相はリニア新幹線導入を「日米同盟の象徴」と位置づけ、昨年2月の日米首脳会談で実現を提案した。しかし、融資に言及したことについては両政府とも公表していない。米国のリニア新幹線構想は、ワシントン−ニューヨーク−ボストン間(約730キロ)の3都市を結ぶ。このうちワシントン−ボルティモア間(約60キロ)を早期開業区間としている。現在、この区間は約1時間かかるが、リニアを導入すると15分程度に短縮できる。首相は昨年9月の訪米時に講演した際も、リニア新幹線について「日本では東京と名古屋間で開業に向けた準備が進んでいる。その前に、まずはボルティモアとワシントンをつないでしまおう」とアピールした。日本政府関係者は「大統領は前向きだ」と話し、2014年11月の米中間選挙前にも判断する可能性があると見ている。ワシントン−ボルティモア間は東京−名古屋間(約286キロ)より大幅に短いため、14年中に計画が具体化すれば、27年開業予定のリニア中央新幹線を追い抜き、世界初になるとの見方もある。(以下略)---何と言うか、壮大すぎて腰を抜かしそうな話です。だって、当の日本自身、まだリニアモーターカーを実用化はしていないのです。リニア中央新幹線については、以前に記事を書いたことがあります。狭い日本、そんなに急いでどこへ行くそのリニア中央新幹線が名古屋まで開業するのが、JR東海の計画では2027年、13年後の話です。工学的な技術の面では、これまでの実験で確立されているのでしょうが、実際の建設、運行のノウハウ、採算性などについては、まったく未知数です。そんなものを今から売りに出して、しかも5000億円も融資する、というのです。何だか、取らぬ狸の皮算用、という気がしてならないのです。しかも、相手は米国です。車社会であり、なおかつ民間航空が非常に発達している米国ですから、採算の見込みは日本の中央新幹線より更に厳しいことは明らかです。リニア新幹線↓別の記事には、こんなことも書かれています。日本のリニア技術をアメリカに提供へ 車社会に変革を起こせるか?日本の超伝導リニア技術をアメリカに提案していた安倍首相は15日、米リニア関連会社TNEM社一行と面会し、輸出に向けた意見交換を行った。TNEM社は、ダシュル元米連邦上院議員や元州知事、元長官などの有力者で構成されており、アメリカのリニアを代表するリーディングカンパニーである。ワシントン―ニューヨーク間の北東回廊に超伝導リニアシステム導入を進めるため、ロビー運動をしている。ニューヨーク・タイムズ紙は、安倍首相はボルチモア―ワシントン間の40マイル(約64キロ)に、リニアの走行路と推進システムを無償で提供することを申し出している、と報じている。なお、アメリカへのリニア技術提供については、今年2月に開催された日米首脳会談でもふれられていた。【アメリカ鉄道の実情は】アメリカで最も速い高速列車は、最高時速110マイル(約176キロ)で、通常は平均時速80マイル(約129キロ)で運転されている。対して日本のリニアは時速315マイル(約507キロ)だ。現行で最も速いアセラ・エクスプレスは、ワシントン―ニューヨーク間(約370キロ)を、3時間前後で結ぶ。リニア導入により、わずか1時間で到着することが可能になる、とニューヨーク・タイムズ紙は報じている。エポック・タイムズ紙も、ニューヨークの交通渋滞を避けることができ、大変魅力的な交通手段の一つになり得るだろう、と報じている。他方、リニア導入にかかる莫大な費用に対しては懸念を示している。アムトラック(全米鉄道旅客公社)は、ニューヨーク―ワシントン間の費用は1100億ドル(11兆円)にのぼると試算している。TNEM社の資金5000万ドルでは全く及ばないと指摘する声もあるという。(以下略)---総工費11兆円もかかる大事業を行うには、米国の鉄道産業の経営基盤(技術的な基盤も)はあまりに脆弱です。引用記事にあるアセラ・エクスプレスというのは、フランスの高速新幹線TGVをベースにしたものです。アセラ・エクスプレス↓フランス・TGV(TGVにもいくつかタイプがある中で最新型)↓引用記事には「最高時速110マイル(約176キロ)」とありますが、Wikipediaの記述によれば、場所によっては最速240km/h出すようです。ワシントン―ニューヨーク間の所要時間は最速で2時間47分とあります。本家フランスのTGVは最速320km/h出ます。日本の新幹線も、のぞみは東京-名古屋間を1時間40分で結ぶので、ほぼ同じ距離のワシントン―ニューヨーク間より1時間も速い。(こだまが2時間40分台なので、アセラ・エクスプレスとほぼ同じ速さ)何故こんな差が出るかというと、フランスのTVGや日本の新幹線は高速新線を建設しているのに対して、米国のアセラ・エキスプレスはすべて在来線を走っているからです。いくら車両が高速でも、線路が古い在来線ではスピードは出せません(日本でも、在来線を改軌したミニ新幹線の速度は遅い)。で、高速新線を建設すればもっとずっと高速で運行できる、なんてことは最初から分かりきっていることですが、そうは言っても、そんな新線を建設する資金は、アムトラックにはないのです。ない袖は触れないから仕方がない。というのが米国における鉄道産業の現状です。そこにいきなりリニア新幹線と言ったって、5000億円融資しても、総工費11兆円が10兆5千億円になるだけです。そんな建設費が負担できるくらいなら、アセラ・エクスプレスのための新線がとっくに建設できているはずです。というわけで、限りなく実現性が低い、投資したとしても回収不能の可能性が限りなく高い話であるように思えます。ワシントン−ボルティモア間だけ先行開業というのは、まるで上海トランスラピッドみたいな話です。上海トランスラピッドは距離30kmほどで、延伸の動きも当面はないようで、技術見本市の域を出ない状況です。60kmを現状1時間、リニア新線なら15分というのは、それほどのインパクトでもありません。山陽新幹線の小倉-博多間は実距離で56kmで所要時間16分です。60kmでも17分か18分でしょうから、専用軌道の新幹線よりさほど速いわけではない。上海トランスラピッドの採算性は報じられていないようですが、建設費の回収まで考えれば、黒字とは思えません。ワシントン−ボルティモア間も、それと同じことになるでしょう。まあ、記事にあるようにその部分の建設費を日本がプレゼントするなら、純運行経費だけなら赤字にはならないかもしれませんが。いや、しかしそもそもリニア新幹線というのはJR東海の所有物であって日本政府の所有物ではないはずです。その特許技術の無償譲渡とか、JR東海も随分気前が良いものです。その気前の良さの裏にあるものの方が問題かもしれません。JR東海は、今のところリニア中央新幹線を自己資金で建設すると言っています。しかし、「お国のため」に特許技術を無償で米国に譲渡するということは、「その代わり、国も中央新幹線の建設費を負担してね」というバーター取引ではあるまいか。5000億より、そっちの建設費負担のほうが大きいかもしれない。まあ、「まさか」というよりは「やっぱり」という感じの危惧なのですが。※写真の出典は、すべてWikipediaです。また、アセラ・エクスプレスの所要時間を、当初誤ってボストン-ニューヨーク間で計算していたため、ワシントンDC-ニューヨーク間の所要時間に訂正しました。
2014.01.05
コメント(4)
-
暴走し続けるネット世論
春香クリスティーン、靖国参拝に「ヒトラーの墓参り」発言 ネット鎮火せず、朝鮮日報も追随安倍晋三首相の靖国神社参拝をめぐる、タレント・春香クリスティーンさんの発言が物議を醸している。問題となったのは、参拝当日の2013年12月26日にテレビ番組で行った「もしもドイツの首相がヒトラーのお墓に墓参りをした場合、他の国はどう思うのか?」という発言だ。12月28日には韓国大手紙「朝鮮日報」の日本語版でも「靖国参拝:日本のタレントの発言で物議」と報じられ、いまなお火はくすぶっている。■抗議コメントはすべて削除春香さんは12月26日の「情報ライブ ミヤネ屋」(よみうりテレビ系列)にコメンテーターとして出演した。この日のトップニュースは安倍首相の靖国参拝で、近隣諸国との関係悪化を懸念する論調で番組は進められた。司会の宮根誠司さんは「やっぱり隣国ですから、中国・韓国の歴史認識ってのは一致させたいのが理想」だとしながら、南スーダンでの内戦などを例にだし、春香さんに「隣同士で仲の良い国がどれだけあるのか」と問いかける。それに対して春香さんは、「海外でよくこの問題と比べられるのが、『もしもドイツの首相がヒトラーのお墓に墓参りをした場合、他の国はどう思うのか?』という論点で議論されるわけですけれど、まあ難しい問題ですよね」と答えた。あくまで春香さん個人の意見ではなく、海外で「靖国参拝」と「ヒトラーの墓参り」が同列に扱われることがあると紹介したのみだったが、発言の一部がひとり歩きした結果、多くのネットユーザーから「英霊に対する侮辱」や「事実誤認がある」などと反発を浴びることとなった。すぐさまネット上では批判がうずまき、春香さんのブログやツイッターは「炎上」した。ブログには抗議コメントが殺到したが、そのいずれも即座に削除されたことが火に油を注いだ。26日以降、現在まで春香さんはブログ・ツイッターなどで発言をしていない。ネット掲示板「2ちゃんねる」では29日の現在もなお、「ヒトラーとか極端な例を挙げる必要ないからな」「『靖国参拝する日本人、外国人観光客、海外要人はヒトラーの信奉者も同然』と言ってるようなものだ」などと、発言に対する批判が高まっている。(以下略)---靖国神社は「墓」ではない、ということは言えますけど、それはあまり本質的な問題ではないでしょう。靖国神社を巡る問題は、二つに集約されると思っています。ひとつは、靖国神社それ自体が侵略戦争に積極的に加担する存在であり、なおかつ現在でもなおそのことに対する反省がない、ばかりか侵略の歴史を賛美し続けていることです。そして、もうひとつは、A級戦犯という戦争責任者を祀っていることです。A級戦犯は、日本が無謀な戦争に突入して破滅に至ったことについての大きな責任があります。侵略戦争ということと同時に、それによって日本自身が破滅したことの責任者でもあります。もちろん、A級戦犯として処刑された人たち「のみ」に全責任がある、と言うわけではないし、A級戦犯の選定や罪の重さにいい加減なところはあるのは事実ですが、だからと言ってA級戦犯として処断された人たちが、たいして罪のないあわれな被害者、というわけでは断じてありません。文脈を見る限り、彼女は「靖国参拝とヒトラーの墓参りは同列だ」と言っているわけではなく、「諸外国からは同一視されるので難しい問題だ」と言っているように見えます。そして、彼女の危惧はまったく正しいと、私は思います。1985年、米国のレーガン大統領はドイツ公式訪問中に、ドイツのコール首相とともに、ビットブルク軍人墓地を訪問しましたが、その際、この墓地の埋葬者に武装SS隊員49名が含まれることが発覚し、大問題となりました。結果としてレーガンはこの墓地を訪問したのですが、同時に強制収容所跡地も訪問することで決着しています。もちろん、この墓地の埋葬者の中で、武装SSの戦没者はごく一部でした。また、武装SS所属兵士というだけで、具体的な戦争犯罪への関与が明らかになっている者がいたわけでもありません(戦争犯罪に関与がした部隊の所属兵士が埋葬されていることは確認されたが、その戦没者個人が関与したかどうかは不明)。いうまでもなく、ナチスや武装SSの高官や含まれていたわけでもありません。それでも大問題になった。もし、そこに、ヒットラーとまでは言わないまでも(ヒットラーには墓はない)、ナチスやSSの高官が埋葬されていたとしたら、訪問がありえなかったことは明らかです。このことから考えても、A級戦犯だけを祀っているわけではない、という種類の言い訳や、A級戦犯はヒットラーとは違う、という種類の言い訳が、国際社会で通用するはずがないのです。だからこそ、米国も、事前に国務長官と国防長官が千鳥が淵に参拝し、事後には「失望した」という強い反応が出てきたわけです。それにしても、です。こういうごく常識的な意見に憤激して、ブログやツィッターに、脊髄反射的でワンパターンな批判を殺到させてしまう人たちの神経というのは、どうなっているのかな、と思います。※本人のブログやツィッターに寄せられたコメントは削除されているそうですが、2ちゃんねるやそのまとめサイトなどで、彼らの言い分はいくらでも見ることができます。最近、日本の世論は急激に右傾化していて、私などは空恐ろしさを感じているのですが、それにしたって、世間一般の世論は、ネット上ほどまでは右傾化していません。世論調査でも、靖国参拝に対しては(賛否がかなり拮抗していますが)反対のほうが多い。しかしネット上でだけはネット右翼の声がでかくて、そうでない意見は、口にすれば叩かれる、とばかりにますます小さくなっていく。そして、勇ましいネット上の国士連中に媚を売るような首相が、勇ましいことを言う、こんなことでは、日本はどこに行ってしまうのかなと危惧せざるを得ません。
2014.01.04
コメント(10)
-

おせち料理
独身の頃は、新年にかけて山登りに行っていたり、あるいは友人の家に泊まりに行ったりして、1月1日に家にいなかったことも度々ありましたが、結婚してからは、家庭内の不和の種になりかねない(笑)ので、山登りに行っても必ず12月31日には帰宅して、新年は家で向かえるようにしています。で、1月1日は、毎年私の実家でおせち料理を頂いています。と言っても、手作りしたものは、全体の半分しかありませんが。自分で撮った写真ではなく、母がたまたま撮った写真をもらったので、これ1枚しかありません。一番手前(タラバカニ)は、弟が買ってきたものです。その奥の皿はコハダの粟漬、カブ、カズノコ、大根とにんじんのなますなど、その奥の重箱は、伊達巻、紅白かまぼこ、昆布巻、栗きんとん、田作り、一番奥の重箱は煮しめ(やつがしら、しいたけ、にんじん、ごぼう、高野豆腐、たけのこ、蓮根、こんにゃくなど)。その左隣は我が家から持っていったもので、おせちのように重箱に入れてありますが、中身はオードブルで、おせちと言うより「おせち風」です。それ以外に、黒豆と焼き豚があります。ま、いろいろありますけど、母が実際に料理したのは、一番奥の重箱の煮しめ類(と雑煮)だけです。あとは、買ってきたものを寄せ集めてあります。もっとも、最近は全部セットになったものを買ってくる人の方が多いかもしれません。そもそも、おせち料理など食べないという家も少なくないようです。分からなくはありません。おせち料理の起源はいろいろあるのでしょうが、本質的には、お正月から手の込んだ料理はしたくない、というところが大きな要素を占めているのでないか、という気がします。つまり、事前に作っておくもので、その場で作るものではない、したがって暖かい食べ物ではない、ということです。暖かいのは雑煮だけです。味も、酢の物や甘辛系(駅弁などに多い)が多く、私は好きですけど、飽きやすい味と言えなくもない。しかも、いわゆる日本料理一般と違って、おせち料理なんてお正月にしか食べないものです。煮しめは1年中食べますけど、伊達巻やカズノコ、こはだの粟漬は、お正月食べなければ、まず1年中食べることはない(そもそも、それ以外の時期は売っていない)。そう考えると、今のかたちのおせち料理は、ひょっとすると絶滅危惧種に近い存在なのかもしれません。我が家だって、母は今75歳ですから、自分でおせち料理を準備できるのも、あとせいぜい数年だろうと思います。母がリタイアしたとき、じゃあ相棒がおせち料理を準備するかというと、どうでしょうね。ある意味で、食品業界流通業界が、季節商品としてキャンペーンをしている(バレンタインとかホワイトデーとか、土用の丑の日とか、最近急に出てきた恵方巻とかと同じ)ことで維持されている存在、とは言いすぎでしょうか。いや、そもそも1年の初めに親族全員が顔を合わせて食事する、という風習自体が消えかかっているかも知れません。前述のとおり、私も独身の頃には新年から家を空けていたことが度々ありましたから。
2014.01.02
コメント(2)
-

今年もよろしくお願いします
昨年は、安倍政権の下で右翼的、国家主義的な動きが露骨に現れた1年となりました。よかったのは、経済が比較的好調だった点ですが、これがどこまで続くのかは疑問の余地は多いにあります。多くの論者は「アベノミクスは偽薬である」と言っています。私の個人的願望としては(仕事の上の都合も含めて)、アベノミクスでも何でもいいから、好景気が長く続いて欲しいのですが、現実には金融緩和(日銀が円を市中にばら撒く)と財政出動(国債をどんどん発行)に支えられた「好景気」が持続可能であるようには、どうも思えません。今年は果たしてどんな年になるでしょうか。多くの人にとって平和で幸せな年であって欲しいと願っています。いや、年の初めに限らず、いつだって、そう思わないときはないんですけどね。---話はまったく変わりますが、昨日西穂独標を目指した際、雨具のズボンにアイゼンの歯を引っ掛けて、穴を開けてしまいました。膝下までは硬い生地のスパッツをつけているのですが、新雪の急斜面をズボズボと登っていたとき、どうしても足を大きく上げて登っているので、何かの拍子にスパッツより上まで足を上げて、それで引っ掛けてしまったのです。アップにすると、こんな感じです。ザックリと穴が開いています。生地の裏面まで、完全に貫通しています。凶器はこれです。↓12本歯のアイゼンの、どの歯で引っ掛けたかは分かりませんが(引っ掛けたときの感覚では、多分前歯ではないと思う)、これで引っ掛けて小さな穴一つだけで済んだら、むしろ幸運かもしれません。一歩間違えたら、もっと派手に大きく裂けたり、もっとひどければ、その下のズボンまで切って、太ももむき出し、なんてことも、なくはないかも知れません。で、この程度の穴なら、リペアシートで修理することにしました。写真で見れば分かるとおり、実は以前にも傷をつけてしまったことがあり、そのときリペアシートを貼り付けて修理しています。その傷は、2011年12月に上高地でつけた傷で、そのときは貫通はせず、表面を破いただけでした。で、リペアシートを貼り付けた後、2年間この雨具を使っています。この間、雪山には6回登り、無雪期に雨に降られた山行も1回か2回ありましたが、まったくはがれる気配もありません。厳密に言えば、これを貼ってしまえばゴアテックスの透湿性は失われるはずですが、面積が極小なので、あまり問題はない。これです。登山用品店で購入したものです。その時は雨具を修理してもらうつもりでお店に持っていったのですが、どういう経緯だったかは忘れましたが(修理代が高額だったのかな)、結局修理には出さず、これを買って帰ってきてしまったのです。結果として、それで正解でした。修理完了。穴が貫通しているので、裏面にも貼りました。多分、実用的にはこれで問題ないはずです。ただ、リペアシートはこの色しかなかったので、見た目は、ちょっとつぎはぎだらけですね。最初に傷つけたときは、購入からまだ2年あまりしか経っておらず、「そんなにすぐ買い換えられないよ!」と思ったのですが、今はもう4年以上になります。次に穴をあけてしまったら、買い替えの考え時でしょうか。もっとも、前の雨具は10年以上使いました。最後は、生地が汚れて目詰まりして、透湿性がなくなったことと、縫い目にガタが来ていたかも知れない(確証がないが、縫い目付近が一番濡れたように思う)ことで、新しい雨具に買い換えました。が、実は今も台風の中を出勤するときは、この引退した雨具を使っています。台風では傘は役に立たないし、自宅から最寄り駅まで、最寄り駅から職場まで、せいぜい15分程度の歩行距離なので、その程度なら蒸れることも浸水することもないからです。それを考えると、やっぱりこの雨具も、4~5年でお払い箱、というわけには行かないな。あと3~4年は使いたい。最悪、ズボンのみ買い換える手はありますが。それにしても、厳冬期でも夏山用の雨具でまったく問題ないのですが、アイゼンの歯を引っ掛けるとこへの耐久性は、生地がペラペラなだけに皆無に等しいことを痛感しました。厳冬期用の分厚いウェアを持ってはいるのです。冬の八ヶ岳で2回使いましたが、もうカンベンです。まず、重くてかさばる。そして暑い。マイナス15度とか20度の暴風雪の中と言えども、歩いている限りは夏用の雨具で寒いと感じたことはありません。厳冬期用のウェアじゃ、暑くて暑くてかなわないのです。もちろん、シベリアのマイナス50度の吹雪の中だったら話は別でしょうが。※この記事を書くにあたって、山の道具の寿命を色々調べていたら、ダウンのシュラフ(寝袋)の寿命は、メンテナンスに気を使っても最長10年という記述を発見して驚愕。私のシュラフは、もう15年使っています。(ダウン9割・フェザー1割)今年も使ったし、去年はゴールデンウィークの涸沢で使った。以前より保温性が落ちた感覚はないです。しかも、使った後陰干しする以外は何もメンテナンスをしていないのに。
2014.01.01
コメント(8)
全27件 (27件中 1-27件目)
1