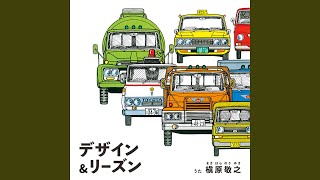2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年08月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
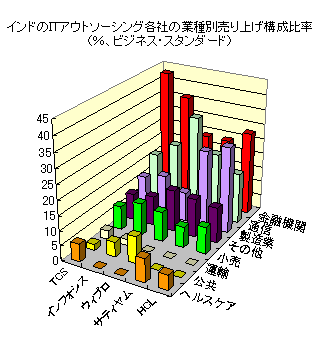
第99回 インドのITアウトソーシング業界とサブプライム問題
今日のまとめ 1. サブプライムの問題は主にインドのBPO企業に悪影響を与えている 2. 一方、ITアウトソーシング企業への影響は殆ど無い 3. 中・長期の展望は明るい■インドに飛び火した米国のサブプライム問題 米国のサブプライム・ローンの焦げ付きの問題で去年の末から今年8月30日までに大小合わせて143社の住宅ローン業者が倒産しています。倒産した業者の大半は比較的規模の小さい企業ですが、その中には比較的規模が大きく、インドにBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の業務を外注していた業者もあります。このため一部のインドのBPO企業に業績予想の下方修正を余儀なくされるところが出てきています。BPO企業全体の売上高に占める住宅ローン業者の割合は約7%程度であると言われています。また、証券業、商業銀行などを含めた金融サービス業全体では35%程度です。■BPO企業への影響 今回、一番影響を受けているのは中堅のBPO企業です。具体的にはWNS(ティッカー:WNS)、エクセル・サービス(ティッカー:EXLS)、アイゲート(ティッカー:IGTE)、エンファシスなどです。このうちWNSは8月16日に業績ガイダンスの下方修正を発表しました。顧客のひとつである米国の住宅ローン業者、ファースト・マグナスが事業に行き詰まりBPO契約をキャンセルしたのがその原因です。ファースト・マグナスはWNSの売上高の約5%を占める顧客でした。WNSは2008年度の売上高ガイダンスをこれまでより1600万ドル低い2.86億ドル~2.91億ドルに修正しました。WNSは今回のガイダンス下方修正の前日に決算発表のカンファレンス・コールを開催しており、その翌日に早くも前日に示したガイダンスを下方修正するという不手際で投資家の信頼を失う結果となりました。WNSのもうひとつの顧客であるインディマック・バンコープ(ティッカー:IMB)も住宅ローンに関連する業務を行っていますが、こちらはWNSのライバルであるエクセル・サービスへも業務を外注しており、エクセル・サービスの売上高の約5%を占めています。なお、インディマックはサブプライム・ローンを扱っていません。このほかのBPOということになると最近 IPOされたジェンパクト(ティッカー:G)が気になりますが同社は先日の決算カンファレンス・コールの中で住宅ローン業者向けの売上高は今年1500万ドル程度を予定しており、そのうち800万ドルは既に入金しているので残りは700万ドル程度だと説明しました。つまり同社の総売上高の1%に満たない数字です。■ITアウトソーシング大手への影響 さて、BPO企業の状況は上に述べた通りですが、ITアウトソーシング企業はどうでしょうか?。ITアウトソーシング企業の顧客には住宅ローン業者はあまり名前を連ねていません。ただ、ウィプロ(ティッカー:WIT)やインフォシス(INFY)は小さなBPO 部門を持っており、大変僅か(売上高で1%以下)ですが今回の問題の影響を受けると思われます。いずれにせよ実際の収益に対するネガティブな影響よりも投資家心理に対する悪影響の方が遥かに大きいと思われます。また住宅ローンという業種に限らず、金融サービス業全般ということで見るとITアウトソーシング各社にとって金融サービス業はたいへん重要な顧客です。 これらのことから目先はインドのIT関連株に対する投資家のセンチメントが悪化するのは避けられないと思います。■中・長期の展望 さて、目先は兎も角、中・長期的な展望を考えると今回の下げは必ずしも悪いことばかりとは言えません。それは今後米国で住宅ローンの審査が厳格化し、ペーパーワークが増えると生き残った業者はアウトソーシングを増やす必要があるからです。実際、ドットコム・バブルが弾けた後、業績が悪化した投資銀行はコスト圧縮の為、財務モデルの維持などの比較的付加価値の低い業務をインドにアウトソースしました。それから今回のサブプライムの問題がインドに飛び火する直前まではインドのITアウトソーシング企業にとって一番頭の痛い問題はルピー高でした。しかし今回の世界の株式市場の急落でルピー高にはどうやら歯止めがかかったように見受けられます。各社の業績にとってみれば住宅ローン業者の問題よりこの為替の問題の方が深刻です。そのルピー高圧力が和らいだということは或る時点でバーゲン・ハンターが出動してくる可能性があるわけです。
2007年08月31日
-
第98回 中国本土の個人投資家の外国株投資解禁
今日のまとめ 1. 本土の個人投資家のH株買いだけでなく国際機関投資家の参戦にも注意 2. A株はマルチプル・コントラクションをおこす 3. H株のバリュエーションは若干底上げが期待できる 中国国家外貨管理局は8月17日に中国本土の個人投資家の外国株投資を今後順次解禁してゆくと発表しました。今日はこの発表が持つ意味について考えてみたいと思います。■香港上場株からスタート これまで中国本土に住む個人は一年間に5万米ドルまでしか外貨に換えることができませんでした。このルールは今後も維持されます。今回の措置は外国株式を買う場合に限って現行の枠にとらわれずに上限金額を設定せず購入を許すというものです。今回対象となる外国株はいまのところ香港市場に上場されている株に限定されています。香港市場に上場されている株と言った場合、やはり中国本土の個人投資家にとって馴染みのある中国企業に先ず物色の矛先が向かうと考えるのが自然でしょう。つまりH株やレッドチップということになります。将来はこの可能投資範囲は徐々に広げられてゆく見込みです。■完全な自由化ではない さて、実際の手続きですが中国本土の顧客は中国銀行の全国の支店に口座を開設することを許されます。そこから中国銀行の天津支店経由で香港市場へ注文がつながれるわけです。このように窓口を限定するということは中国政府にとってお金の流れを把握しやすいという利点があります。特定の企業の特定の窓口だけを通じて解禁するというやり方は中国のような政治体制の国でしか考えられないことです。窓口が限定されているという意味では今回の発表は完全な自由化とは言えません。■QDIIは実質的にその役目を終える しかし個人投資家の立場からすればこれまで施行されてきたQDII(Qualified Domestic Institutional Investors)プログラムより今回は一段と自由度が増したと評価できると思います。QDII制度は厳格な外国為替制度を維持しようとする国が採用する暫定的な制度です。そこでは極めて制限的でかつ煩雑なペーパーワークを金融機関に課し、その金融機関がスポンサーする形で投資信託などを通じて個人投資家に海外へ投資させるわけです。これは喩えて言えば「団体旅行でのみ海外への渡航を許可する」というルールなのです。つまり旅行社に与えられた枠の中で指定された期日に出発する感覚ですね。これに対して今回の外国株投資の解禁は言わば「個人旅行を解禁する。但し予約は特定の旅行社で行うこと。」という感じです。これなら団体行動に拘束される窮屈はありません。一般にお金は「自由な方へ、自由な方へ」と流れるものです。すると新制度で香港株が自由に買えるようになるとQDIIは早晩廃れると考えた方が良さそうです。(但しこれは個人投資家の取引に関してのみ。機関投資家は今後もQDIIを利用すると予想されます。)■株価は本土からの資金の到来を一足先に織込みにかかる さて、今回の措置でどのくらい中国本土の投資家が資金を香港に持ち出すのでしょうか?。未だ発表直後ですのでこれを予想する事は難しいです。敢えて言えば余り巨額の資金は一度には動かない気がします。ただ、実際の資金の移動が限られているだろうという事と、それが今後のH株やレッドチップ、さらに中国本土のA株の株価形成に影響を与えないということとは別問題です。事実、今回の発表後の過去数日間の各指数の動きを見れば既に影響が出ていることが分かります。具体的にはA株の株価の上値は重く、H株やレッドチップ株の値動きは軽快だということです。これはどうしてかというと今回の発表直前の時点で中国本土のA株と香港のH株との間には約55%近い乖離があったからです。本来同じ株でありながらA株の方がH株より遥かに割高に買われていたわけです。その理由はこれまで中国国内の投資家は海外への送金を制限されており、割高と知りながらもA株を買わざるを得なかったからです。■長期的には中国株の種類はひとつになる 中国本土の個人投資家が香港に上場されているH株やレッドチップを買えるようになるということは長い目で見ればこれまでA株、H株、レッドチップなどといろいろな種類に分かれていた中国株の分類が将来的には廃止の方向へ向かうことを暗示しています。これは世界の機関投資家にとって重要な意味を持ちます。その理由はいろいろな種類に分かれていたものが統合されると全体としての流動性が増し、機関投資家が日頃参考にしている運用のベンチマークにおける中国株への配分比率が上昇することが考えられるからです。すると機関投資家としてもベンチマークについてゆくために中国株を買い増す必要が将来的には出てくるはずです。■不自然な株価形成は次第に過去のものとなる さて、中国本土の個人投資家の投資戦略も今回の発表を機に今後変化してゆくことが考えられます。例えばこれまではH株を香港で出している企業が本土で上場すると上場初日にいきなり50%も高い値段で取引されるというケースが多くありました。しかし今後はそういう非効率な株式の売り出しの方法を中国政府はやめてしまう可能性もあると思います。私がそう考える理由はH株やレッドチップで既に取引されている会社をA 株で本土に上場するということはいろいろな歪曲の原因となってしまうからです。皆さんはH株がA株市場に上場されたとたんに爆騰するのはその会社にとって良いという風にお考えかもしれませんが、これは厄介な問題を引き起こします。なぜなら仮に新株を香港市場におけるH株の実勢価格に近い株価でA株としてオファーしたとして、そのIPO後、株価が急騰した場合、「その株に対する需要が旺盛であったにもかかわらず安く値決めしすぎた」という批判を受ける可能性があるからです。そういう批判をかわすため若しA株IPOのときに高めの価格設定をすると逆に中国本土の個人投資家からは「なぜ我々だけ不当に割高な値段でIPOを買わないといけないのだ」という不満が出るでしょう。新株ではなく政府の持ち株を売り出す場合はこの問題はさらに輪をかけて政治的に微妙な問題になります。これらの問題はいずれも一物二価で本来同一の証券に二つの全然違う値段がついてしまっていることからくる歪曲なのです。■今回の改革の背景 中国政府が本土の個人投資家に香港の株を解放するもうひとつの理由は人民元高の圧力を人民銀行だけの力で抑え込めなくなってきていることの表れでもあります。8月12日に発表された中国の7月のインフレ率は+5.6%と過去最高の水準でした。豚肉をはじめとする食品の価格の高騰が原因です。人民銀行はインフレを抑制するために金利を繰り返し引き上げていますが人民元の相場をある一定の範囲内に押さえ込もうとすると輸出代金の人民元への転換のニーズに対して、ドルを買い、人民元を売り向かう役目をしなければいけません。それははからずも中国国内のマネー・サプライを増加させてしまうことになるのです。これを債券の売りオペなどのステリライゼーション(不胎化)により中和させることに躍起になっていますが、穿った見方をすれば、どうやら人民銀行ひとりだけで相場に立ち向かうのは限界に近づいたという風にも取れるでしょう。■H株の新しい妥当水準を求めて さて、中国本土のA株の平均PER(株価収益率)は現在過去12ヶ月の実績EPS(一株当たり利益)に基づいて約45倍、向こう12ヶ月のEPSでは34倍程度で取引されています。一方、H株のPERは過去12ヶ月の実績ベースでは約22倍、向こう12ヶ月では17倍程度で取引されています。A株の水準が高いのはあくまでも「他にお金をもってゆくところがない」という事情から生まれた、きわめて人為的な好需給に助けられた部分が大きかったです。従って今後A株のPERは国内投資家の資金が香港市場へと抜けてゆくことを考えると徐々に緊縮(マルチプル・コントラクション)を起こすと考えた方が自然です。従ってH株のバリュエーションとA株のバリュエーションが鞘寄せするとして、その折り合い地点は両者の中間点ないしはより現在のH株のバリュエーションに近い方だととりあえず考えておいた方が良さそうです。これはH株のEPS成長率を考えても大体確認できることです。即ちH株のEPS成長率は2008年が約25%、2009年が約17%成長と見られています。香港のH株は今後本土からの継続的な資金流入などの株価下支え要因がありますからEPS成長率よりもプレミアム、つまりPEGレシオ(PE to Growth Ratio)にして1倍以上で買われることは十分考えられます。
2007年08月23日
-
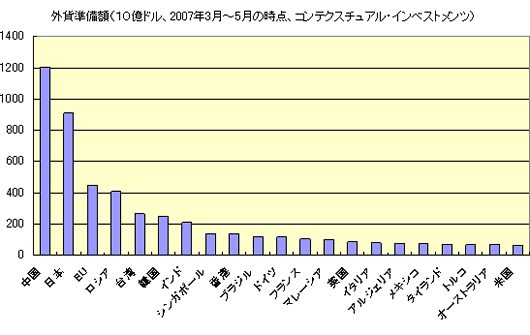
第96回 投資戦略の見直し:リスク許容度の低下は一時的問題に過ぎない
今日のまとめ 1. 投資家のリスクに対する許容度が下がったのが資金引き揚げの原因 2. 住宅ローンの問題はあくまでも米国の問題でありBRICsは関係ない 3. BRICsの経済運営はきわめて手堅く通貨暴落などの危険はない 4. BRICsはファンダメンタルズが良いのでいずれ資金は戻ってくる■リスク許容度の低下 これまでサブプライム(信用力の低い借り手)に限定されてきた米国の住宅ローンの問題が信用力の高い借り手にまで及んできているという認識が広がっています。このため米国の資本市場ならびに株式市場は波乱の展開になっています。投資家のリスクに対する許容度が下がった為、海外市場からもとりあえず資金を引き揚げようという市場参加者が相次ぎBRICsのマーケットも荒れ模様です。しかし米国とBRICsでは経済のファンダメンタルズに根本的な違いがあります。■住宅ローンの問題がなぜ米国経済にとって重要か? 住宅セクターは米国のGDPの15~20%程度を占めていると言われています。しかし実際には住宅市場の動向が米国経済に与える影響はそれ以上に大きいです。なぜなら米国の消費者には持ち家が値上がりした含み益をホーム・エクイティー・ローンなどの形で取り崩し消費に回す態度がすっかり定着しているからです。つまり住宅価格は米国の消費動向を左右する重要な要因なのです。米国経済の過去10年間の実質成長部分の91%は消費でした。ということは消費がおかしくなるとアメリカの成長そのものがあやしくなるということを意味します。米国の株式市場が荒れるのも頷けます。■収入以上の生活をしてきたアメリカ人 アメリカの長期金利は1979年の第2次オイルショック以降、基本的にはずっと右肩下がりで下がってきました。このような好ましい金利環境では金融機関は色々な新しい金融サービスを消費者に提案し易いです。クレジット・カードやホーム・エクイティー・ローンはその例です。こうして金融サービスの消費者への浸透が進むと消費者は自分の収入以上の生活を享受することが当たり前になります。住宅ローン問題がアメリカの国民を不安にさせているのには自分たちがすっかり借金に依存する体質になってしまっているからです。今回の住宅ローン問題は過去20年続いてきた借金漬けの成長路線が終着点に来てしまったことを示唆しています。別の言い方をすれば米国経済は今後の成長のロードマップを最初から描きなおす必要に迫られているということです。■BRICsの消費者 一方、BRICsの消費者はこれまで銀行サービスとは全く縁がありませんでした。ですからアメリカ人のように借金漬けではありません。むしろ近年になってはじめて住宅ローンやオート・ローンなどの金融商品が出現したという段階です。つまり経済の中で消費者が占める割合というのはこれから伸び始めるところなのです。BRICs各国経済が今後内需の比重を高めながら安定的に成長できる余地が大いにあることは容易に理解できます。■経済のファンダメンタルズの明暗 これまでなら「米国がクシャミをすればBRICsは寝込んでしまう」という喩え通り米国の変調はBRICs を直撃したと思います。しかし今回は「サブプライム問題どこ吹く風」でこれらの国の経済は好調です。そのひとつの理由は上で見たような「新しい消費者」がBRICs各国でちからをつけてきており内需が好調だからです。さらにこれまでは米国だけに依存してきた輸出に関しても変化が出てきています。即ちBRICs同士での交易がどんどん伸びているという事です。それでは通貨に関してはどうでしょうか。エマージング諸国の多くは極めて高い水準の外貨準備高を維持しています。 BRICs各国は健全かつ保守的な経済政策を励行しており公的債務の削減にも努めてきました。その結果、むしろ日本や米国の方が問題を抱えているように見えます。 こういう状況ではBRICsの通貨を売り崩すことは困難です。勿論、最近のマーケットの荒れを反映してエマージング・マーケットの債券と米国財務省証券との金利差(EMBIスプレッド)はこのところ70ベーシス・ポイントほど拡大しました。しかしこの程度の金利上昇はかんたんに乗り切れると思います。■持続可能な経済成長 むしろBRICsの経済は下のリーディング・インディケーターのチャートからもわかるように世界の経済の牽引車の役割を果たしています。 企業収益も引き続き好調でBRICsの足下の業績予想は上方修正されています。 それではBRICsの株価水準についてはどうでしょうか。下のチャートはBRICsの投下資本利益率と株価純資産倍率を比較したものです。これで見ると BRICsは米国や日本より資本効率の良い経営をしていることがわかります。例えばロシアの投下資本利益率は日本より高いにもかかわらず株価純資産倍率は日本より割安です。このように現在のBRICsの株価純資産倍率は投下資本利益率に照らして考えると十分に正当化できると思われます。 結論として現在のBRICs市場の荒れは単にリスク許容度が低下した世界の投資家が慌てて資金を引き揚げていることから起こっているのだけれどもBRICsのファンダメンタルズはたいへんしっかりしているので嵐が収まればまた資金は戻ってくると考えられます。
2007年08月02日
全3件 (3件中 1-3件目)
1