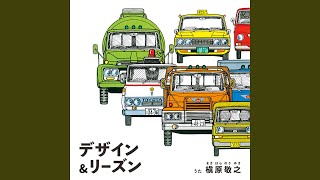2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
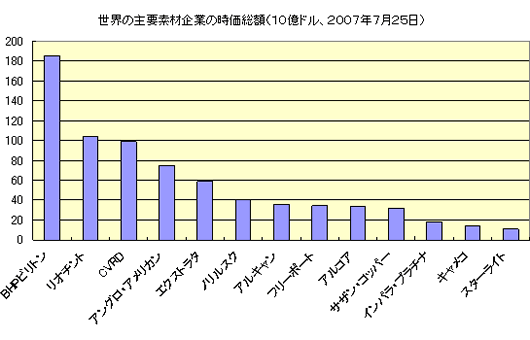
第95回 世界の素材セクター(その3)
今日のまとめ 1. 素材セクターはM&Aの嵐の渦中にある 2. 一握りのグローバル企業の寡占が強まっている国際的な業界再編の動き いま世界の素材産業は大きな業界再編の嵐に巻き込まれています。最近起こったM&Aの代表的なところをまとめると次の表のようになります。買収企業被買収企業エクストラタ・ノルリルスクライオンオアフリーポート・マクモランフェルプス・ドッジランディーンリオ・ナルセアランディーンユーロジンクCVRDインコエクストラタノーランダノーランダファルコンブリッジCVRDカニコリオチントアルキャン 僅か一年足らずの間にこれだけ多くのM&Aが起こる背景には一体何があるのでしょうか。 先ず素材各社は市況の高騰でどこも空前の利益を上げています。しかし新規の鉱床を発見するのは難しいですし現在生産を続けている鉱床はだんだん深くなり採掘コストは漸増しています。このため各社とも長期に渡る資源の確保が急務となっています。手っ取り早い方法は会社ごと買ってしまうやり方です。また、昨今の好景気で鉱業の会社はどこもキャッシュが余っており下手をすれば買収のターゲットにされてしまいます。それを防ぐには自らが買収企業として他社を呑み込み、その際、負債を背負い込めば他企業からつけ狙われる危険が減ります。今なら比較的低利で借り入れが可能ですしどんどんキャッシュが入ってくるので借金の返済も迅速に行えます。利払い負担が軽減すれば利益もぐんぐん伸び更に株価が上がるでしょう。このような好循環が買収ブームを煽っているわけです。この結果気がついてみると巨大コングロマリットに世界の鉱山がどんどん吸収され、ごく一握りのグローバル企業が世界の資源を支配する構図が出来上がりました。 これらの企業の多くは多国籍企業であり世界の多くの地域に鉱床を持つと同時に世界中の顧客と商売しています。つまり「これはどこの国の企業だ」という風に国籍を特定することは極めて困難なのです。逆の見方をすればこれらの企業の全てがBRICsの勃興がもたらす素材ブームの恩恵を直接蒙っている企業だと言えるでしょう。大手三社の去年の部門別利益構成は次のようになっています: なお、リオチント(ティッカー:RTP)は最近、アルキャン(ティッカー:AL)の買収を発表しています。ですから今後アルミニュームの比率が高まると思われます。同様にCVRD(ティッカー:RIO)はインコを買収しましたので今後ニッケルの比率が高まると思われます。アルコア(ティッカー:AA)はアルキャンに買収提案していたのですがリオチントがより良い条件を提示したためアルキャンに逃げられてしまいました。そのため今度は逆にアルコア自体が M&Aのターゲットになるのではないかと見られています。フリーポート・マクモラン(ティッカー:FCX)はフェルプス・ドッジを買収した際に負債を抱え込んだので今は買収のターゲットとは看做されていません。サザン・コッパー(ティッカー:PCU)はミネラ・メヒコと合併しメキシコとペルーに特化した銅のピュア・プレイとなっています。キャメコ(ティッカー:CCJ)は最近注目を集めている原子力発電の分野を代表するウラニウムの業者です。同社はカナダ、サスカチュワン州のマッカーサー・リバーに世界最大のウラニウム鉱山を所有しています。同社のウラニウム鉱床は純度が極めて高くユニークな資産です。しかし最近は出水などの鉱山の操業上の問題が度重なり投資家の落胆を誘っています。さらに同社のウランは長期契約を履行するためにスポット価格の半値程度で売られています。ウランは国家安全保障上の重要な資源ですからキャメコは外国資本が1社で15%以上の株式を取得することを禁じています。インドのスターライト(ティッカー:SLT)はインド最大の非鉄金属の企業で銅、亜鉛、アルミニュームが中心です。インドはBRICsの中でも特にインフラストラクチャーへの投資が遅れており今後大きな成長が期待できる市場です。
2007年07月30日
-
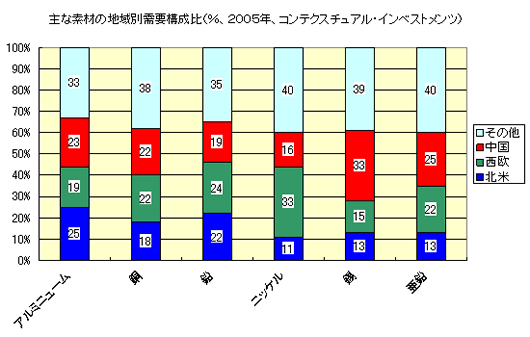
第94回 世界の素材セクター(その2)
今日のまとめ 1.素材のセクターはグローバルな視点から分析する必要がある 2.近年の好景気で需給は引き締まっている 3.全ての工業向け金属の価格が高騰している BRICs経済が需要構造に与える影響素材の需要と経済の発展段階は密接な関係があります。例えば錫や亜鉛は比較的発展途上国からの需要が高いです。一方、鉛、アルミニューム、ニッケルは先進国からの需要が高いです。 こうした違いはどうして出るのでしょうか。その答えは各々の素材の用途にあります。錫はブリキやハンダに使われます。また亜鉛はトタン板を作るのに使われます。これらの製品はどちらかと言えば発展途上国で多く消費されます。一方、鉛の消費の8割は車のバッテリー向けです。アルミニュームは航空機や自動車などの輸送機器、建設、アルミ缶などに使われます。ニッケルはめっきやニッケル・カドミウム電池、リチウム電池、ステンレス鋼などの製作に使用されます。これらの製品はどちらかと言えば先進国が主な市場です。銅は建設、製造業、輸送機器、カーペットや靴下などの商品と多岐に渡る用途があります。特筆すべき点としては中国における銅の消費の約半分は電線に使われているという点でしょう。世界銀行によると1980年から2000年にかけての高所得国(アメリカ、EU、日本など)と発展途上国の年間平均GDP成長率はそれぞれ2.9%と3.4%でした。つまり両者の成長のスピードには余り差異は無かったのです。しかし近年は発展途上国が持続的に高所得国の成長率を大きく引き離しています。 注:発展途上国(*)というのは中国とインドを除いた数字世界銀行ではこのような発展途上国の高所得国に対するアウトパフォーマンスは今後も長期に渡って続き、結果として発展途上国が世界経済全体に占めるシェアは着実に上昇してゆくと予測しています。 錫や亜鉛は鉱業に携わる業界人の間では「プアーマンズ・メタル」、つまり「貧乏人の金属」という風に形容されることもあり、長年、先進国では需要が低迷していました。それらの金属が今、力強く復活し、活況を呈している背景には上に見たような世界経済の成長の軸足が発展途上国にシフトしていることが深く関係しているのです。BRICsの中でも先頭を走る中国は今どんどん高所得国へ追いつこうとしています。従って中国の場合はむしろアルミニュームのような「リッチマンズ・メタル」に注目しないといけないのかも知れません。下の図は10年前と比較してアルミニュームの一人当たり消費量がどう増えたかを示したグラフですが中国の伸びが顕著ですね。先進国の場合、一人当たりの消費量は20キログラムを超える国が多いです。中国の場合も当然、いずれそういう水準に到達すると思われます。例えば航空機はアルミニュームがふんだんに使われている製品の典型例ですが下のグラフは世界の航空機発注に占めるBRICsのシェアを示しています。実に世界の需要の37%がBRICsから来ているわけです。 このようにBRICsはこれまで主に先進国が中心となって消費してきたメタルに関してもどんどん消費しはじめています。つまり全ての素材の需給関係にインパクトを与えているわけです。これは素材メーカーにとっては新しい操業環境であると言えるでしょう。このような現実に対応するべく各社は買収合併などを繰り返しており、世界の素材業界は今、戦国時代に突入しているのです。
2007年07月18日
-
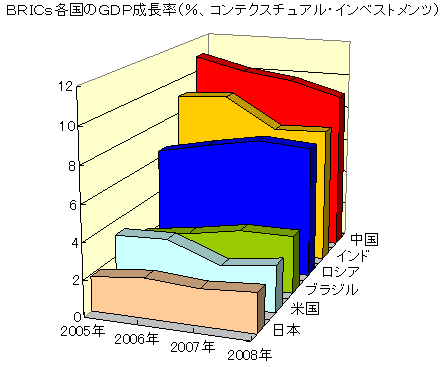
第93回 世界の素材セクター(その1)
今日のまとめ 1. 素材のセクターはグローバルな視点から分析する必要がある 2. 近年の好景気で需給は引き締まっている 3. 全ての工業向け金属の価格が高騰している■グローバルなセクター 素材のセクターは昔からグローバルな視点による分析が欠かせないセクターでした。分析の対象となる商品が世界中どこでも比較的均質であり、大量に輸送するのに適していること、生産者の採掘コストが決定的に重要であることなどがその原因です。BRICsの台頭による需要の底上げで素材セクターが歴史的に持ってきたこうしたグローバルな色彩は最近一層強まっていると言えます。これまでの先進国中心の消費からBRICsを中心とするエマージング諸国へ需要の中心がシフトするのに伴って最近では素材のセクターはあたかも成長産業のような様相を呈しています。そういう認識は正当化できるのでしょうか。この問題を次の三つの角度から考えてみたいと思います。 1. 景気循環的な視点 2. BRICs経済が需要構造に与える影響 3. 国際的業界再編成の動き■景気循環的な視点 世界の経済はドットコム・バブル崩壊、9・11同時テロ、それに続く米国のイラク進攻という一連の悪いニュースを消化した後、2003年頃を境に景気拡大サイクルに入りました。ここ数年の世界の経済成長は過去最高のペースに近い、極めて高い成長を記録してきました。 今はその好景気がどれだけ持続するかという点が世界の投資家の主な関心事です。インフレ懸念から世界各国が政策金利を引き上げてきたこと、更に米国では住宅市場が調整局面に入っていることなどから今年はじめの時点では世界経済はある程度の減速を余儀なくされるという見方が優勢でした。しかし直近のデータでは意外に世界の経済は底堅い動きとなっています。下に示したのはOECDのコンポジット・リーディング・インディケーターです。リーディング・インディケーターは主に短期での景気の先行きを占う指標として使われます。これで見るとOECD全体(紫色)として景気の拡大が維持されていることがわかります。また、中国のリーディング・インディケーターは極めて高い水準で高止まりしています。さらにブラジルやロシアの指数もここへきて上向いています。 このように今の世界経済は主にBRICs諸国の経済が好調であることから好景気が持続していると考えて良いでしょう。こうした好景気を受けて素材の在庫は段々取り崩されつつあります。下のグラフは各素材の在庫を消費量で割った数字です。今、仮に供給がストップしたとすると在庫を完全に使い切ってしまうのに何週間かかるかを計算したものです。こうして見ると在庫消費比率は全体に右肩下がりであり需給関係が引き締まっていることを感じさせます。 このような経済環境を背景に各素材の価格は下のグラフにみられるように過去4年の間に79%から295%も上昇したのです。
2007年07月17日
-
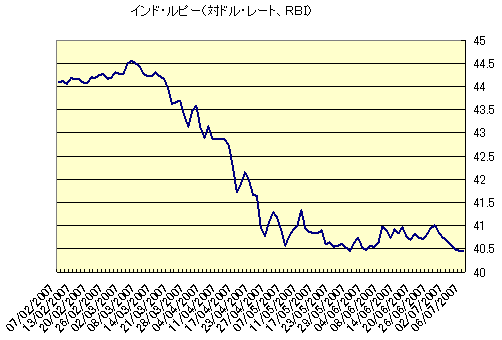
第92回 インドのITアウトソーシング業界の近況
今日のまとめ 1. 最近のルピー高でインドのIT各社の株は冴えない 2. アナリストのコンセンサス予想はまだ下がる余地を残している 3. ルピー高でもインドのIT企業の国際競争力は余り落ちない 4. ADRのプレミアムはかなり縮小した■間近に迫った決算発表 このところ中国の産業セクターについて書いてきましたが、今日は暫くぶりにインドのITアウトソーシングのセクターを取り上げたいと思います。その理由は今週から同セクターが決算シーズンに突入するからです。インドのITアウトソーシングのセクターに対しては最近、悲観論が増えています。その理由はインド・ルピーがこのところ強含んでおり、これが各社の業績の足を引っ張ると考えられているからです。 上のチャートは2月以降のインド・ルピーの対ドル・レートです。数字が小さくなればなるほどルピー高であるという風に読みます。 さて、投資家の立場からすればルピー高が各社の決算に与えるインパクトが既にどれだけ株価に織り込み済みか?ということが気になります。このところインド・ルピーはずっと43.5から47のレンジで推移してきました。しかし4月にサポート・ラインである43.5付近を割り込み新しい水準を模索する展開になっています。このルピーを巡る新しい展開は未だ各社の業績のガイダンスには反映させていません。例えばインフォシスの例を示すと前回の決算のカンファレンス・コール(4月11日)で提示されたガイダンスでは為替レート=43.10を用いていました。つまりガイダンスの依拠する為替レートより今のマーケットは6%ほどルピー高になっているわけです。為替が1%動くことによる営業マージンの減少は各社によってばらつきがありますが、大体、20ベーシス・ポイントから50ベーシス・ポイントくらいの悪影響を受けます。それをもとに各社の6月期決算のマージンを試算したのが下のグラフです。 インフォシスの場合、6月決算のEPSに対する為替のインパクトは1から2セント程度であると思われます。いま、『ヤフー・ファイナンス』でインフォシスのコンセンサス予想を見ると6月期のコンセンサスは90日前に比べて1セント下がり40セントに、9月期も同じく1セント下がり44セントとなりました。ですから、ことインフォシスに関する限り為替絡みの悪材料はある程度織り込まれたと考えられます。反面、その他の銘柄はアナリストの予想数字は殆ど下方修正されていません。 さて、株価の方を見るとインフォシスの場合、2月の高値から現在までに約13%程度調整しています。いま仮に今年一年に渡って現在のルピー高の悪影響が続くと想定すれば今年度のインフォシスの通年のEPSにとって4から5セント程度の悪影響が出るわけですからそれを現在の同社のPERである28.4倍で掛け算してやると株価にして$1.42程度の減少要因となってもおかしくありません。2月の高値は引値ベースで約60.5ドルですから理論的には為替の悪影響を織り込んだ株価水準は59.1ドルという計算になります。すると今の株価($52.59=7月6日引値)は為替のインパクトを必要以上に大きく織り込んでいる可能性があるわけです。 ルピー高になってもインドのITアウトソース企業の国際競争力は余り落ちないと思います。なぜなら米国などインド以外を本社とするITアウトソーシング企業も最近はインド企業への対抗上インドにオペレーション拠点を置く企業が増えており、各社のコスト構造は似通ってきているからです。インドではITの人材がだんだん不足してきており人件費の上昇プレッシャーがあると言われています。しかし各社の従業員当たりの粗利益額の推移を見ると意外に安定的に推移しています。このことは各社がコスト増をちゃんと価格に転嫁出来ていることの表れだと思います。従って最近のルピー高によるインドのIT企業のコスト増も同様に顧客に価格転嫁できるに違いないと思われます。 以上を総合するとインドのIT関連株の最近の低迷は過剰反応のような印象を受けます。或いはインドのIT株がこのところ冴えない展開だった理由は、増資やIPOが相次ぎ需給関係が悪化したことも影響しているのかも知れません。以前はADRで取引されているインドのIT企業の株は本国市場の株価に対してかなりプレミアムがついていました。しかし最近ではそのプレミアムが随分縮小して殆ど苦にならない程度の水準となっています。
2007年07月09日
全4件 (4件中 1-4件目)
1