2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年05月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
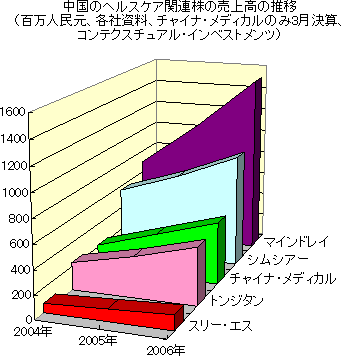
第87回 中国のヘルスケア・セクター(その3)
今日のまとめ 1. ヘルスケア・セクターへの投資は個別銘柄の選別が鍵となる 2. 技術力、経営者の見識、財務力などでADR上場銘柄が抜きん出ている中国の薬品株に投資する際のポイント 中国の薬品株に投資する場合、ただ漫然と最も規模の大きい企業から順番に株を買えば良いという考えは通用しません。なぜなら大手製薬会社の多くは旧政府系企業で経営が非効率なところが多く、それらの企業は一般に低収益体質ですし、企業統治(コーポレート・ガバナンス)面でも問題があるところが多いからです。折から中国のヘルスケア市場は営業倫理の向上キャンペーンの影響で目下の経営環境はかなり厳しいです。さらに医療を庶民の手に届き易くするために政府は承認カタログにおける価格改定を繰り返し、薬価の値下げを試みています。これらのことから中国の製薬業界は今後強烈な淘汰の時代に入ってくると予想されます。このため薬効面で卓越した商品を多く抱えた企業、全国ネットの営業組織が完備されている企業、近代的経営で企業統治がしっかりしている企業、資本市場へのアクセスがしっかり確保されておりチャンスと見ればどんどんM&A(買収・合併)で業容を拡大してゆける企業、などの条件を満たした企業を選ぶ必要があるのです。中国の医療機器株に投資する際のポイント 上に述べた薬品株を買うときの注意点の多くは医療機器株を買う場合にもあてはまります。ただ異なる点としてはこれまで高価な医療機器は外国製品の輸入に頼ってきたのですが国内メーカーが力をつけてきており政府も割高な外国製品を退け、国内メーカーを後押しする政策を進めている点です。この結果、中国の医療機器メーカーにとってはビジネス・チャンスが広がっていると言えるでしょう。技術力という点でも外国企業との技術力の格差は製薬業界ほど大きくなく、事実、輸出市場にどんどん出てゆこうとしている企業も散見されます。グローバルな視点をもった経営者 中国の薬品会社や医療機器メーカーに共通する「隠れた財産」があります。それは欧米の最高峰の教育機関で教育を受け大手の製薬会社やバイオテクノロジーの会社や医療機器メーカーで研究開発に従事した人材がどんどん中国に帰国しており、彼らが中国のヘルスケア市場に新風を吹き込んでいる点です。この人材の層の厚さは注目に値します。そういう新しいタイプの経営者は自分の会社の株式を公開する場合もADR市場を選びます。別の言い方をすれば技術力や経営の質の面でトップ・クラスのヘルスケア企業の多くはADRでしか買えないということです。スリー・エス・バイオ(三生制葯、ティッカー:SSRX) 同社はバイオテクノロジーの企業です。同社の主力製品はEPIAO(イーパイオ/益比奥)で、アムジェンやキリンのEPOに類似した、腎性貧血症患者に対する赤血球増殖剤です。このカテゴリーでの同社製品のマーケット・シェアは36%で首位です。現在、同社のEPIAOは肝臓障害、キモセラピー、手術後の赤血球補給の3つの用途に対して使用が認められています。直近の決算ではEPIAOは前年比+12.7%で成長しています。次の製品がTPIAO(ティーパイオ/特比奥)でこれはTPOに類似した、キモセラピーに絡む血小板障害を治療する薬です。直近の決算ではTPIAOは前年比+227%で成長しています。同社は上記2つの薬を含めて全部で6つの薬を販売中、ないしは開発中です。同社は売上規模的には上のグラフに見られるようにまだ小さいですが今年から来年にかけての売上成長は60%以上が見込まれています。今年のコンセンサス予想に基づいたPERは23.6倍、来年の予想に基づいたPERは14.6倍です。トンジタン(同済堂、ティッカー:TCM) 同社は漢方薬と西洋薬を作っています。同社の主力薬は「シェンリン・グーバオ」です。シェンリン・グーバオは骨粗ショウ症(骨が砕けやすくなる病気)の薬です。2900万人の中国人が骨粗ショウ症に罹っているといわれ、中国の人口が高齢化すると今後さらに患者が増えることが予想されます。直近の決算でのシェンリン・グーバオの成長率は前年比+76%でした。同社はこの他にも10種類の漢方薬と37種類の西洋薬を製造販売しています。それらの商品ポートフォリオは老人の罹りやすい病気に重点が置かれています。同社の売上成長は大体+35%程度と見込まれます。問題点としてはシェンリン・グーバオの原料費が比較的激しく上下することでこれが収益予想をむずかしくしています。同社は積極的な買収戦略を展開し、中国の製薬業界におけるコンソリデーター(統合主体)になるものと予想されます。今年のコンセンサス予想に基づいたPERは14.8倍、来年の予想に基づいたPERは13.3倍です。シムシアー(先声、ティッカー:SCR) 同社はジェネリック薬を中心とする製薬会社です。中国ではファースト・ツー・マーケット(初めて登場するジェネリック)薬に対しては5年間を最大限とする「モニタリング期間」と呼ばれる独占販売期間が設けられます。シムシアーは主にそれらのブランデッド・ジェネリック薬を中心に営業展開してゆきたい考えです。同社の成長の軌跡を辿ると:2002年 ザイリン 「再林」(抗生物質)2004年 インタイチン 「英太青」(関節炎)、アンチ 「安奇」(抗生物質)2006年 ビチン 「必存」(心臓発作)、ビチ 「必奇」(下痢)2007年 アンドウ 「ENDOSTAR」(抗がん剤) と矢継ぎ早に新製品を出しています。売上成長、利益成長が年々着実に出せるようにどんどん商品のラインや企業を買収してゆく積極経営を展開しています。同社はR&D面では精華大学と協同しています。同社は未だIPOされて間もないためコンセンサス予想は出揃っていません。しかし大まかに言えば売上成長で35%程度が予想できると思います。一方、PERは今年のEPS予想(コンテクスチュアル・インベストメンツによる)に基づいて約23.5倍です。チャイナ・メディカル・テクノロジーズ(ティッカー:CMED) 同社は癌の治療に使われる高密度焦点式超音波治療法(HIFU)と血液や尿の検査に使われる電気化学発光免疫測定法(ECLIA)の2つの医療機器を作っています。中国政府の統計によると中国人の死因の首位はガンです。HIFUは前立腺ガンや肝臓ガンなどの治療に使われるそうです。シー・メドのHIFUは所謂、ノン・インヴェイシブ、つまり治療すべき箇所の近くを切開したりする必要の無い設計となっており、ターゲットとなる肝臓癌、腎臓癌、乳癌、前立腺癌などの箇所を瞬時に60℃から70℃の加療温度に熱することが出来ます。治療に際して特別な麻酔は必要ありませんし、皮膚のやけどや不快感などもありません。HIFUの機器は他のメーカーも出しているのですが、ノン・インヴェイシブ型の製品は同社だけです。また、病院の評判ではシー・メドのHIFU装置は他社の競合商品より安全性、信頼性の面で優れているという評判です。現在の出荷実績は約150台(去年の売り出し目論見書の時点で)です。中国政府の統計によると中国には約18000の病院があり、そのうちHIFUが導入可能な大病院は1000程度です。シー・メドの二つ目の製品はECLIAで、米国や欧州では普及しているテクノロジーですが、中国ではまだ使われ始めて間もない製品です。シー・メドのECLIAは糖尿病、成長に関する疾病、血瘤、SARSなど27種類の検査項目に関して応用可能な検査装置です。また、同社のECLIA装置は低価格であるため、大病院でなくても予算的に無理なく購入できるという優位性があります。シー・メドは北京大学の大学病院と密接な協力関係にあり、同社のHIFUならびにECLIA装置は北京大学が開発した技術の開発・販売権を獲得し、製品化されました。同社はまた米国のジェネラル・エレクトリック(GE)が大株主であり、それが同社の信用を高めていると言えるでしょう。同社の問題点としては売掛金が多いことで、直近の四半期決算では売掛金回収に要する日数は約140日でした。同社の売上高は約+40%、利益は約+20%で成長しています。同社株のPERは今年のコンセンサスEPSに基づいて19.3倍、来年の数字に基づいて15.8倍程度で取引されています。マインドレイ・メディカル(ティッカー:MR) 同社は中国最大の医療機器メーカーです。マインドレイの主力製品は患者モニター装置、血液や尿の検査装置、超音波診断装置、麻酔装置などです。製品のデザインから製造まで全部自社でこなしています。売り上げ高の約10%程度を R&Dに使っていることからも、同社が研究開発に真剣に取り組んでいることがわかります。国内の他のメーカーの製品と比べると性能面で優れたプレミアム商品に位置づけられています。一方、外国製品に比べるとほぼ同じ性能の製品であると同時にマインドレイ社の製品の方が廉価な価格設定になっています。また、外国の製品に比べて価格性能比に優ることから海外での販売展開にも力を入れています。全体の売り上げに占める海外比率は約44%です。同社の顧客の大半は病院や診療所です。これまでの納品実績は約25000の病院や診療所と取引があります。中国の医療機器市場はディストリビューターを通じた販売が主体であり、ディストリビューターは比較的事業規模の小さい業者が乱立しています。このため、多くのディストリビューターとの関係を維持しているということが参入障壁となります。マインドレイ社は1950に上るディストリビューターと商売しており、その販売網は中国随一です。さて、リスク・ファクターですが、先ずディストリビューターに依存する販売形態のため、機器の営業に際してのキックバックなど不正商取引に巻き込まれるリスクがあると思います。また、ディストリビューターの倒産などの信用リスクも考慮されるべきでしょう。また、医療機器は日進月歩で技術が進歩しているので競争力のある新製品の開発に遅れるとマーケット・シェアを落とすリスクがあります。さらに海外進出は販売網の確立などに費用を要します。思うように売り上げが伸びない場合、収益悪化要因となります。製造に関しては急激な需要増に生産が間に合わず商機を逃すというケースが過去にありました。競合という面では主に外国のメーカーは事業規模の面でも技術力の面でも歴史が長い分、有利です。また、同社の売り上げのうち、トップ5の製品が全体の売り上げの38%を占めており、特定の人気商品に対する依存度が比較的高い点も注意する必要があると思います。同社は当面の国内売上成長予想を25~30%、海外売上成長予想を60%程度と見込んでいます。従ってこれらを合計した全社売上成長予想としては40%程度が期待できるでしょう。同社株は今年のコンセンサスEPS予想に基づいたPERで44.5倍、来年で32.4倍で取引されています。
2007年05月28日
-
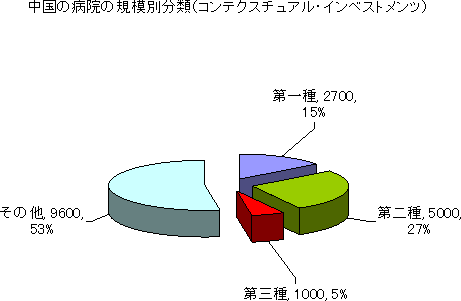
第86回 中国のヘルスケア・セクター(その2)
今日のまとめ 1. 中国では薬は主に病院で処方される 2. 薬価統制があり価格改定は頻繁に行なわれる 3. 新薬開発コストは大変低い 4. 中国の製薬業界は零細企業が乱立している中国の病院ならびに薬局事情 中国の病院は政府によって第一種から第三種、さらにその他の4種類に分類されています。このうち一番規模の大きいのは第三種で普通、大学病院のような教育施設に付随しています。第二種病院は地方都市の総合病院などです。この第二種病院に限って民営化が許可されています。さらに第一種というカテゴリーがあるのですが、これは特定疾病分野に特化した専門病院などです。第一種病院の特徴は予算規模が大きく専門医も沢山抱えている点です。 中国では米国のように医薬分業にはなっておらず処方薬については病院内の薬局で購入するのが一般的です。上のグラフの第二種病院だけが現在民営化を許されており、民間企業の病院が現れ始めていますが今のところ大部分の病院は国有です。それらの国有病院において薬が処方される際、その病院の承認リストに載っている薬に限って処方してよいことになっています。それぞれの病院が承認リストを作成するにあたっては労働社会保障省(MLSS)が選んだ薬のカタログの中からそれぞれの地方政府が独自の承認リストを作成するという方式が取られています。MLSSのカタログに収録される薬はティア1とティア2に分類され、ティア1に分類された薬は必ず地方政府の承認リストに含まれることが義務づけられています。さらにティア1に分類された薬は100%保険で払い戻しが効き、患者の自己負担はありません。ティア2に分類された薬は地方政府の裁量で承認リストに載せるか載せないかを独自に判断することが出来ます。ティア2に分類された薬は80~90%保険が利き、差額が患者の自己負担になります。このことは中国で処方薬を製造している製薬会社にとってMLSSのカタログに収録されるということが売上伸長の為にたいへん重要になることを意味します。しかし実際にはどの薬がカタログに採用されて、どの薬が落選するかは運・不運による面が多く、製薬会社にとって不確実性が高いと言えるでしょう。さて、処方薬ではなく店頭(OTC)薬に関してみると、こちらの方は主に薬局で買われてゆきます。中国人は軽い症状なら病院へ行かず薬局で店頭薬を買って済ませてしまう人が多いです。中国の薬局は零細企業が多く市場はたいへん細分化されています。 中国には昔から漢方薬が存在することは皆さんもご承知だと思いますが中国では漢方薬は西洋薬と全く分け隔てなくカタログに採用され、病院で処方されています。漢方薬は中国国内で消費される全ての薬の中で約30%程度を占めており、今後もこの比率は安定的に推移すると考えられます。製薬業界の監督当局 中国の製薬業界を監督しているのはSFDA(China State Food & Drug Administration)です。中国国内で薬を製造したり販売したりするためにはSFDAから承認を受けることが必要となります。新薬はSFDAから承認されることが必要ですが、ひとたび承認されて売り出された薬は5年間モニタリング・ピリオド(監視期間)が義務付けられます。この5年間の間は政府がその新薬が安全であるかどうかなどを観察するために設けられた期間です。重要な点としてはひとたび或る新薬がモニタリング・ピリオドに入ると全く同様の薬効を持つと思われる類似薬に関しては新薬承認申請書類を受け付けないし、外国の製薬会社の薬の輸入承認や中国国内における生産も受け付けないという点です。つまりモニタリング・ピリオドは言葉を替えて言えば独占販売許可期間であるという風に考えても良いでしょう。薬の製造に関する規定としてはSFDAが承認した品質基準(GMA=Good Manufacturing Practice)をクリアした工場でのみ生産が許されます。薬価統制について MLSSの承認カタログに収録された処方薬ならびに店頭薬の末端価格は薬価統制の対象になります。具体的には薬の値段そのものが政府によって決められる場合と、最高価格の上限を政府が定め、後は製薬会社の判断で自由に価格を決められる場合の2種類のケースがあります。薬価の改定は比較的頻繁にあり、最近では年2回くらいのペースで薬価が引き下げられています。全ての薬が薬価改定の対象になるというわけではなく、どの薬が対象になるかは薬効や市場のニーズなどを勘案して決められるようです。一括購入 地方政府はその管轄下にある病院の薬を仕入れるに際して競争入札で大量買付けするケースがあります。この入札で決められた落札価格がその年の実質的なカタログ定価になります。この定価は1年間有効です。製薬会社としてはこれらの地方政府ごとの応札事務を代理店に任せるわけにはゆきません。代理店販売網に加えて自前の営業組織を維持する必要があるのはこのためです。新薬開発 中国国内で新薬を開発する際の典型的な研究開発費用はひとつの新薬あたり約590万ドル程度であると言われています。これは米国の平均的新薬開発費用(8億ドル)に比べると大変低い数字です。これは製薬会社の研究スタッフの給与水準が米国のそれの10分の1以下であること、さらに臨床試験に要する費用が安いことなどがその主な理由です。零細製薬会社の乱立 中国の製薬業界は歴史的に新規参入が比較的容易であったことなどから2004年末の時点で4700社もの企業が乱立しています。従って比較的小さい市場のパイを沢山の会社が奪い合っている構図になっています。中国で最大級の製薬会社でも国際的な比較で見るとその業容は大変貧弱です。このことは今後中国の製薬業界は統合の嵐に晒されることを暗示していると思われます。実際に企業の買収のみならず商品群の買収は頻繁に起こっており、買収による成長を標榜する企業は市場のパイそのものの成長率より遥かに早いペースで急成長しています。医療サービス業界の不正腐敗の粛清 近年中国の医療サービス業界は医療機器の購入や薬品の一括購入に際するわいろなどいろいろな不正腐敗がはびこっていました。中国政府はこの事態を重く見て営業倫理の粛清に乗り出しました。その結果、去年から今年にかけてはヘルスケア・セクター全体で営業活動が一時的に止まったりするなどの影響が出ました。この粛清は一応峠を越えたように見えますがまだ終わったと決まったわけではありません。一時的な営業の停滞はこのセクターの業績に対する不透明感を増し、その結果として薬品株や医療機器メーカーの株はどちらかというと敬遠されてきたと言えます。
2007年05月21日
-
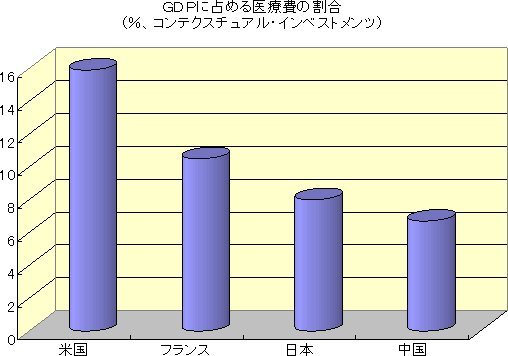
第85回 中国のヘルスケア・セクター(その1)
今日のまとめ 1. 医療支出はまだまだ伸びる余地がある 2. 1980年代から始まった自由化・民営化は失敗に終わった 3. 地方における医療サービスは壊滅的打撃を受けた 4. その是正の為に中国政府は医療支出をガンガン積み増している医療の充実は中国政府の最重要課題 1980年代に中国政府はそれまで政府主導で行なっていた医療サービスの自由化・民営化に踏み切りました。この結果、優秀な医師はより高い所得を目指して大都市に出てしまい、農村における医療は壊滅的な打撃を受けました。今、中国政府はこの過ちを正すべく地方における医療サービスの充実を国家の最優先プロジェクトに据えて取り組みはじめています。このことはわれわれ投資家にとっても大きなチャンスが生まれることを意味します。 まだまだ伸びる余地がある医療支出先ず主要国のGDPに占める医療費の割合を見ると米国はGDPの16%と飛びぬけて高いです。一方、中国は6%強でありまだまだ今後この割合が上昇すると考えられます。中国の医療費負担比率 下のグラフをみると1986年を境に赤で示した国家の医療費負担が急減し個人の負担が増えています。これは中国における医療の自由化の結果です。 現在の中国の健康保険制度では、サラリーマンの場合、典型的に会社が給料の10%程度を医療保険の積立金として負担し、本人は5%程度を積み立てます。疾病にかかった場合、薬代や医療費の一部はこの保険から支払われるのですが、この医療保険の補償額は全く不十分で医療費の実費の大部分は本人負担になってしまいます。地域格差 中国の一人当たりの医療支出を見ると都市と地方の一人当たりの医療支出には下のグラフに見られるように大きな格差があります。 地方における医療支出が少ないのは田舎の人が都会の人に比べて健康だからではありません。地方では所得が低すぎてお医者さんにかかることが出来ないのがその理由です。優秀なお医者さんはどんどん都会へ出てしまいました。中国政府はこのまま地方の農家を見捨てる政策を続けるとたいへんなことになるという危機感をもっています。医療保険制度の拡充 次に掲げたグラフは中国の国民医療保険基金の増加をしめしたものです。 中国の国民医療保険基金は年率約28%で成長してきました。しかし現在の1800億人民元という総額は世界の水準からみると全く話にならない僅かな金額です。そこで中国政府は先の全人代で政府の医療支出を前年比+87%増額すると発表しています。当分、中国の医療が世界の水準にキャッチアップするまで中国政府は医療支出を増やすものと考えられます。
2007年05月16日
-
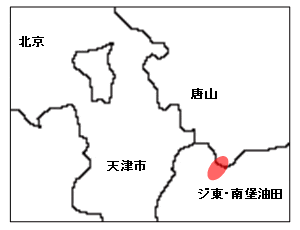
第84回 ペトロチャイナの新油田発見について
今日のまとめ 1.ジ東・南堡油田は大慶油田に次ぐ規模である 2.渤海湾の絶好のロケーションに位置している 3.石油鉱床構造は効率的な生産を容易にするものと思われる 4.同社株のビジネス・リスクは軽減される 5.ペトロチャイナの今後の投資計画は「内向き」になる 背景 5月3日にペトロチャイナ(中国石油天然気:0857、ADRティッカーはPTR)が新油田を発見したと発表しました。同社のニュース・リリースの内容から判断するとこの新油田の規模はかなり大きいです。この油田の発見はペトロチャイナの将来の生産計画(プロダクション・プロフィール)やコスト構造、さらに今後の投資計画などに大きな影響を与えそうです。従って今日はこの新油田について考えてみたいと思います。 会社側の発表 ペトロチャイナの発表によると今回発見されたジ東・南堡(Jidong/Nanpu)油田は唐山に近い渤海湾の沿岸地域に位置し(地図参照)、油田は内陸、浅瀬、沖合いにまたがっています。埋蔵量に関しては:と発表されています。石油鉱床は4箇所の油層を含み同油田は高品質で採取効率の高い油田になるだろうと主張しています。油層の平均の厚みは80~100メートル、油層の深度は1.8~2.8キロメートルで鉱床構造は採掘に適しているとのことです。ペトロチャイナの油田ポートフォリオの中での新油田の位置づけ さて、それではこの新油田はペトロチャイナにとってどれだけ重要な発見なのでしょうか?。今回発見されたジ東・南堡油田の確認埋蔵量は上の表にあるように4.05億トンです。ジ東・南堡油田は「高品質である」という記述があることからAPIグラビティー(原油の等級のことを指します。ペトロチャイナの全社平均は34です)が38だと仮定するとトン→バレルの換算率は7.55ですので: 405 (million ton) × 7.55 = 3,057.75 (million barrel) となります。つまり30.58億バレルということになるわけです。ペトロチャイナ全体の確認埋蔵量(Proved, developed & undeveloped reserve、但し原油のみ)は2005年の時点で115.36億バレルでした。新油田の確認埋蔵量を合算した新しい総確認埋蔵量をベースに計算するとジ東・南堡油田は全体の20.95%を占めることになります。これは大慶油田(ペトロチャイナの新総確認埋蔵量に占めるシェア=30.13%)に次いで2番目に大きな油田ということになります。(なお、なるべく現実的、且つコンサーバティブな試算をするために推定埋蔵量、予想埋蔵量、天然ガス確認埋蔵量は計算から除外しました。ウォール・ストリートのアナリストが同様の計算をする場合でも慣例から考えて、多分、それらの数字は全て無視すると思います。) 次にジ東・南堡油田の確認埋蔵量(30.58億バレル)を加えて世界の主要石油会社の石油ならびに天然ガスの総確認埋蔵量を比較してみると下のグラフのようにペトロチャイナ(226.13億BOE)がエクソン(220億BOE)、ルクオイル(201億BOE)を抜いて世界第1位となります。(但し天然ガス主体の企業であるガスプロムは石油会社ではないという判断から比較の対象から除いてあります。) ペトロチャイナのストーリーがどう変わるか? 次に今回の発見でペトロチャイナ株の銘柄としてのストーリーがどう変わるかについて考えてみたいと思います。ペトロチャイナ株は今回の新油田発見のニュースが出るまでじり安を辿る展開でした。これは主力の大慶油田の生産が徐々に落ち込み始めている事が原因であることは「第七十九回 中国の石油業界 (2007年3月22日)」のレポートで紹介しました。ペトロチャイナは現在、原油生産の約4割を大慶油田に依存しているのですが含水量(water cut)が89.78%と極めて高く、生産量が今後つるべ落としに減り始めることが懸念されています。直近の決算でコストがオーバーランした理由のひとつは汲み出しても汲み出しても水ばかり出るので生産コストが嵩んでしまったことによります。従って「早く代わりになる油田を発見しないと大変なことになる」と投資家の不安は高まっていました。その点、今回発見されたジ東・南堡油田はただ単に規模が大きいだけでなく操業条件や品質の面でも期待が持てます。 ジ東・南堡油田が本格的に生産に入るのは未だ数年先のことだと思いますので当面はペトロチャイナの株主は同社の不安定なコスト構造を我慢する必要があるでしょう。しかし会社側の「採取効率が高い」という発表を額面通り受け止めれば、今後同油田の全社生産量に占める比率が高まるとともにペトロチャイナの収益は安定度を増すと考えられます。つまりジ東・南堡油田の発見は単にペトロチャイナの埋蔵量が伸びたということだけではなく、同社のビジネス・リスクを軽減し、収益力を引き上げる可能性があるということです。 さらに国内でこのように有利な巨大油田が発見されたことで、今後の油田開発費用の割り振りとしては政治的リスクの高いアフリカなどを徐々に後回しにし、比較的リスクの低いジ東・南堡油田を本格的に立ち上げることに向けられると予想されます。
2007年05月07日
全4件 (4件中 1-4件目)
1










