2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
第71回 もうひとつの中国株式市場
今日のまとめ 1.ADRも中国株投資の定番のひとつ 2.中国のニュー・エコノミーを買うなら断然ADRが良い 3.中国企業は同一競争条件の確保の為に敢て敷居の高い米国市場に上場する 4.企業はコンパラブルズ(比較対象)企業の居る市場で上場したがる 5.新しいアイデアを具現化するためにはタイムリーな資金調達が不可欠 6.国籍ではなく、技術評価が鍵を握る案件もある 今日からいよいよBRICsの最後の国である中国の株式について書いてゆくことにします。このレポートは『ADRを使ったBRICs投資』という表題ですから主にADRを中心に紹介してゆきます。そこで今日は中国株をADRで買う意義について考えてみるところから始めましょう。 もうひとつの中国株式市場皆さんは中国株にはH株、レッドチップ、B株など色々な種類があることをご存知だと思います。ADRという形で米国のニューヨーク証券取引所やナスダックで取引されている中国株も立派な中国株です。いや、これからはむしろH株やレッドチップなど皆さんが日頃慣れ親しんだ種類の中国株に加えてADRも中国株投資の定番のひとつとして投資範囲を広げることをお勧めします。その理由はADRでしか取引できない中国株が幾つも存在し、しかもそれらの少なからぬ企業が今後の中国を代表する成長株になる可能性を秘めているからです。折から北京オリンピックを来年に控えてこれまでの重厚長大から次の経済の成長段階に合わせて今後は消費関連や内需株、サービス業などのセクターに投資の軸足をシフトすべきだという意見が最近しばしば聞かれます。しかし、それらのセクターの企業はアメリカで上場されている場合が多いのです。例えばインターネットのセクターは中国の広告業界の成長に投資する際に好適な投資対象なのですが、その殆どはナスダックで取引されています。「中国のグーグル」というあだ名がつけられているバイドゥ(BIDU)というサーチ・エンジンの会社の名前を皆さんも聞いたことがあると思います。また、広告の会社ではフォーカス・メディア(FMCN)という銘柄がナスダックに上場しています。太陽電池は最近注目を集めている業界ですが、サンテック・パワー(STP)をはじめとする中国の有力な太陽電池関連株は殆どがアメリカで取引されています。さらに語学学校のニュー・オリエンタル・エデュケーション(EDU)やビジネス・ホテルのホーム・インズ&ホテルズ(HMIN)などもADRでしか買えません。中国の医療機器の業界は将来国際的にもかなり競争力を持ちうると予想されますが、この重要なセクターを代表するマインドレイ・メディカル(MR)やチャイナ・メディカル・テクノロジーズ(CMED)などの銘柄もやはりADRです。さらにアムジェン(AMGN)を彷彿とさせるような中国初の本格的バイオテクノロジー会社、スリー・エス・バイオ(SSRX)も近日ナスダックに上場する予定になっています。乱暴な言い方をすれば、これらの「ニュー・エコノミー」的な業種に投資しようと思えば香港や本土市場だけを見ていては埒があかないわけです。 伊達や酔狂でアメリカに上場するのではないそれではこれらの企業はなぜわざわざアメリカで上場することを選んだのでしょうか?。外国企業がADRを出す動機としてしばしば最初に挙げられるのは懐の深い米国の投資家層にアプローチすることで、本国市場では到底ムリな大型の資金調達が可能になるという事です。確かに昔、エマージング・マーケットの企業が最初にアメリカでADRを出した頃はこういう議論が当てはまりました。例えばペルーの金鉱株にミナス・ブエナヴェンチュラ(BVN)という会社があるのですが、彼らがリマ取引所で大型の資金調達をしようとしても国内市場が未発達ですからそれはムリな話なわけです。しかし、こと中国企業に関する限り最近では香港市場や本土市場の厚みが増しているのでわざわざアメリカまで資金を調達しに来る必要は無くなっています。実際、去年は中国の大手銀行が相次いでIPOしましたがいずれも香港で上場しました。大量の資金を調達するという視点に限って言えばもはやアメリカの市場は「用無し」なのです。むしろアメリカ市場は株式上場を計画する世界の企業からはどちらかといえば敬遠されはじめています。その理由はサルベインズ・オックスレー法などにより規制が強化されているからです。確かに米国に上場すると監査費用や弁護士費用、インベスターズ・リレーションズ費用などが高くつくし、投資家からの訴訟リスクも高いです。つまり、アメリカで株を上場するのは楽ではありません。そんな不都合を敢て甘受してまでADRを出すからにはよほど切迫した理由が必要です。同一競争条件の確保 それではそんな苦労をしてまでなぜ中国の企業は米国でADRを出すのでしょうか?。その狙いは同一競争条件を確保するという点にあります。例えばグーグル(GOOG)は今、虎視眈々と中国市場への参入を狙っているわけですが、中国でのNo.1サーチ企業はバイドゥです。バイドゥは潤沢な資金力を持つグーグルからの攻勢に対抗してゆかなければなりません。ところがアメリカではインターネットの会社は大変高い株価収益率(PER)の初値設定でIPO出来ます。高株価でIPO出来るということは発行株数を抑えても十分な資金調達が出来ることを意味しますから資金調達コストは低いと言えます。若しバイドゥが香港でIPOしたとすると香港の平均的株価収益率は米国のそれにくらべて低いですから初値設定も低くならざるを得ません。この場合、資金調達コストは割高になるわけです。如何に廉価な資本を引っ張ってこられるかというのが企業の競争条件のひとつであることを考えれば迎え撃つバイドゥの側でもナスダックで上場し、ライバルよりハンデを負わないようにすることがどうしても必要なわけです。この意味で最近、ナスダックにIPOしたマカオのカジノ、メルコPBLエンターテイメント(MPEL)が香港ではなくアメリカで資金調達したのは英断だったと思います。何故ならマカオではラスベガス・サンズ(LVS)やウイン・リゾーツ(WYNN)などの米国勢が今大挙して押しかけていて物凄い勢いでカジノやホテルを建設しているからです。彼らは米国市場で高い株価水準で資金調達していますからそれに対抗するにはメルコPBLもなるべく有利な条件で株式を発行しないといけないのです。 類は友を呼ぶこのように比較の対象となるライバル企業のことを投資銀行家の間ではコンパラブルズ(比較対象)と呼びます。インターネットやバイオテクノロジーや代替エネルギーや医療機器の企業にADRを出すところが多いのは、そもそも中国や香港にコンパラブルズとなる企業が無いからです。逆の見方をすれば今後もこれらの業種の企業はアメリカでIPOされる可能性が高いわけです。上場のタイミングに対する考え方の違いまた、企業の成長過程のどの段階で株式市場から資金を調達できるか?というタイミングの面からの考察も重要です。アメリカのナスダックなどの場合、IPOしようとする企業がちゃんと利益を出しているかどうかに関しては特別気にかけません。眼前にあるビジネス・チャンスをモノにするために今が株の出し頃だと思えば、売り上げ面や利益面で未だちゃんと格好がついていない企業でもIPO出来るのです。その代わり、先に述べたようにディスクロージャーなどの点では厳格なルールが適用されます。これに対して日本やアジアの株式市場はこれまではどちらかといえば実績主義でちゃんと企業として格好がついていることを重視する傾向がありました。(今は新興市場などが整備されつつあるのでこの点での考え方は変わりつつあります。)インターネットや代替エネルギーやバイオテクノロジーのような、ニュー・エコノミーの企業にとってはタイム・ツー・マーケット、即ち新製品や新サービスを発想してから世に問うまでの時間をいかに短縮するかで勝敗が決まってしまいます。ですから彼らはアイデアを具現化するための資金調達もテキパキ出来ることが競争上絶対必要になるのです。 投資家層の洗練度売り上げや利益がちゃんと出ていない企業が株を出す場合、その会社のビジネスがちゃんと軌道に乗るかどうかの判断は格段に難しくなります。これが先端技術などの分野になれば投資家の側でちゃんとになるわけです。この点で米国の株式市場は世界の市場をぐるっと見回してみてもダントツに洗練されています。つまり「違いの判る」機関投資家が米国にはちゃんと存在するわけです。別の言い方をすればその会社のビジネスが先端技術になればなるほど、その会社の国籍などはどうでも良くなるわけです。 中国の未来を背負って立つような優良企業が場合によっては本国の市場ではなくADRでデビューする理由がご理解頂けたでしょうか?
2007年01月29日
-
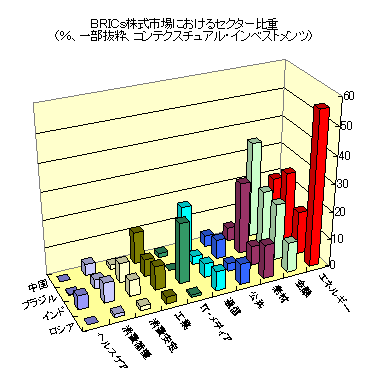
第70回 2007年のBRICs市場の展望(その3)
今日のまとめ 1.BRICs株式市場は特定業種への偏りが激しい 2.ロシアはエネルギー・セクターが突出している 3.インドはITとヘルスケアの比重が相対的に高い 4.ブラジルは素材の比重が相対的に高い 5.中国は金融セクターの重要性が飛躍的に伸びた 6.一般にITやヘルスケアは高い株価収益率が付与されている 7.一般にエネルギーは低い株価収益率に甘んじている 8.今後伸びる業種はまだ株式市場では重要な比重を占めていない BRICs市場のセクター構成今日はBRICs市場の今年の展望をセクター構成面から考えてみましょう。BRICsの株式市場は米国や日本のそれに比べ特定業種に比重が偏っています。そこでBRICs株式市場の今年の展開を占うにあたってこのセクター構成の偏りを頭に入れておくことは欠かせません。さて、各国のセクター構成比を考えるにあたって先ず直面する問題は「どのベンチマークに準拠するか?」ということです。普通、先進国の株式市場においては例えば年金のような性格の資金の場合、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)指数をベンチマークに採用する機関投資家が多いです。しかしBRICsの場合、そもそも年金は未だこれらの市場を投資対象に組み入れていないところが多く、その意味においてMSCI指数の影響力は限定的です。MSCI指数はフリー・フロートと言って機関投資家が自由に株式市場で売り買い出来る浮動玉の多寡が各銘柄の比重を決める上で重視されます。このためロシアの資源株などは実際の時価総額構成比率に比べて極端に軽い比重しか付与されていません。BRICs株式市場の主だったプレーヤーがヘッジファンドなどの株価指数にあまり頓着しない投資家であることを考えると投資ユニヴァース(範囲)の把握に際して時価総額や売買代金などのファクターもある程度重視すべきだと考えます。さらに去年の例ではロシアや中国の場合、エネルギー株や銀行株に大型のIPOが相次ぎ、それぞれの国の株価指数の構成変更がマーケットの変化の早さに遅行するという現象が見られました。これらの要因を加味しながら弊社独自のディスカウント・ファクターを用いて再構成したBRICs市場におけるセクター比重が下の図です。上のグラフから読み取れる点を幾つか整理したいと思います。先ずロシアは特にエネルギー・セクターの占める比重が突出していることが目を引きます。インドの場合、IT、ヘルスケアなどが他のBRICs各国に比べて突出しています。ブラジルで特徴的なのは素材の占める比率が高い点です。中国では金融が最も重要なセクターです。現在のこうしたセクター構成を1年前の姿と比べてみるとその変化の大きさに驚かされます。具体的には中国では銀行株の大型IPOが相次いだおかげで金融セクターの比重が激増しました。またロシアではロスネフチのIPOやガスプロムの持ち株構成のリストラクチャリングによりエネルギー・セクターへの偏向が一層強まりました。 業種と株価収益率(PER)の関係一般に株式市場の投資家は特定の業種の成長性や収益予想のブレの大きさなどを考慮しながら「これが妥当だ」と感じる株価収益率(PER)水準のイメージを知らず知らずのうちに固めてゆくものです。当然、成長性が高いと目される業種については株価評価は高くなるのが普通ですし、収益予想が立てやすいビジネスほどより高い株価評価が付与されます。下のグラフは弊社によるBRICsセクター別の利益成長予想とセクター別株価収益率を示したものです。一般にIT・メディアやヘルスケアは高い株価収益率が付与される場合が多いです。最初のグラフと見比べると、今、インドはIT・メディアやヘルスケアの占める比重が高いです。このためインド市場全体の株価収益率はどうしても押し上げられる傾向があります。逆にエネルギーは付与される株価収益率が低いため、エネルギーの比重が特に大きいロシア市場は見かけ上割安に見えるわけです。今後BRICsにミドルクラス(中流階級)が出現するにつれて消費やヘルスケア、メディアなどの分野は高い成長率を維持するものと思われます。従ってそれらのセクターの株価収益率は高止まりすると予想されます。今一度一番上の「BRICs株式市場におけるセクター比重」のグラフに戻ってみると消費、ヘルスケア、IT・メディアなどの分野はまだまだ株式市場で重要な位置を占めるに至っていません。5年とか10年という長期で考えた場合、それらのセクターが全体に占める比重が増えてゆくと予想されます。なお、例えば中国のインターネット関連や医療機器など将来高い成長が見込まれる分野の一部は中国のH株やレッドチップ市場ではなく、ADRで取引されている場合が多い点を断っておきたいと思います。それらの銘柄は上のセクター比重のグラフには反映されていません。 セクター比重と商品市況や金利の関係さて、去年の夏から世界の原油市場はザックリとした調整局面を迎えています。上に掲げたグラフからもわかる通りBRICsにとってエネルギーは最も重要なセクターです。今年のBRICsの株式市場のパフォーマンスを占うに際して原油価格の動向がひとつの決め手になってくることがおわかりいただけると思います。国別で言えばロシアやブラジルは原油や素材の市況が低迷する局面では下値リスクが大きいと言えます。反対にインドはヘルスケアやIT・メディアなど株価収益率の比較的高い業種を多く抱えています。金利上昇局面ではそれらの銘柄は特に調整幅が大きいと一般に考えられていますので注意が必要です。
2007年01月15日
-
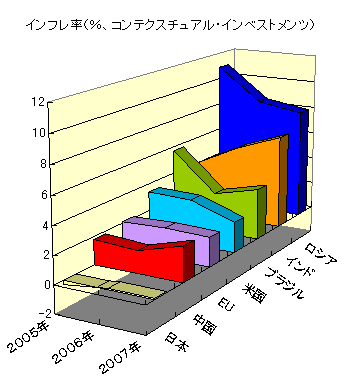
第69回 2007年のBRICs市場の展望(その2)
今日のまとめ 1.インドのインフレ悪化が懸念される 2.北京オリンピック後の事を考慮しながら相場に取り組む 3.ロシアではプーチン大統領の08年の任期終了が大きな不透明材料となる 4.インドの州議会選挙は財政問題再燃の契機になる可能性がある 5.BRICs株式市場は先進国の金融市場の変化に今後も振り回される 6.急激なドル安はBRICs株安を誘発する可能性がある BRICs株式投資を巡るリスク前回の記事でBRICs各国経済は2007年も絶好調を継続するであろうこと、企業収益も順調に伸びると思われること、株価のヴァリュエーションはインドを除けばリーズナブルな水準であることを述べました。つまり基本的にはBRICsには強気の姿勢で臨めば良いわけです。しかし、それではBRICs株式への投資にリスクが全然無いか?といえばそれはそうではありません。そこで今日はリスクについて考えてみたいと思います。インフレーション下のグラフは弊社の予想する各国のインフレ率です。中国は2.5%、ブラジルは3.7%、インドは6.8%、ロシアは8%を予想しています。この中で特に問題になるのはインフレがどんどん悪化しているインドです。これまで世界の投資家はインドで進行中のインフレに対して比較的寛容でした。その理由はインドは原油を輸入に依存しており、去年後半は原油価格が下落基調だったことからいずれインフレ・プレッシャーは緩和するだろうという認識が広まったためです。確かに昨今の原油安でインドは随分助かりました。しかしエネルギー・セクター以外の部分を見るとインフレ・プレッシャーは引き続き高いと見るべきでしょう。特にインド経済のバックボーンをなしているITアウトソーシングの分野では優秀な人材が払底しはじめており、賃金上昇圧力があります。より広い人材プールから採用することを強いられることによるIT労働力の質の低下が感じられます。一方、中国のインフレは非常に低い水準を維持しており、一見、何ら問題無いように見えますが、不動産セクターへの投機資金の流入などにより住宅コストは上昇圧力に晒されています。このことは消費者物価指数には反映されていないことに注意を払うべきです。こうしたインフレ・プレッシャーを背景にこのところインドや中国では矢継ぎ早の引き締め政策が打ち出されています。こういう時は投資家は余り調子に乗り過ぎないことが肝心です。それからこれはBRICs全般について言えることですが内需が好調な理由のひとつは金利水準が比較的低く、消費者がクレジットで住宅や自動車を購入しやすくなったことによります。したがって金利の上昇はこれらの国々の歴史の浅いコンシュマー・クレジット・ブームに水をさす結果になりかねません。 北京オリンピック次にBRICsの行事予定表に絡んだ投資戦略について少し考えてみたいと思います。先ず中国では2008年にオリンピックを控えています。これが投資家にとって目先の大きな目標であることは今さら指摘するまでもありません。北京周辺では今、建設ブームになっています。オリンピックに関連した建設需要で新たに追加されたフロア・スペースは平たく並べたとするとマンハッタンの5倍の面積になると言われています。中国政府は オリンピック開催時には北京上空の空気が澄んでいるようにするため、2007年中に殆どの建設工事を完了するよう指導しています。このように人為的に設定された期日をめがけて誰もがまっしぐらに邁進している場合は、「その後どうなる?」ということをちょっと頭の隅で考えながら行動するべきだと思います。通常、このように将来或る好材料やビッグ・イベントが必ず来ることが決まっている場合、株式市場は約2年前からそれを織り込みにかかると言われています。その意味ではオリンピックに向けてのラリーは既にスタートしていると考えるべきですし、オリンピックまでは相場の基調は強いと考えられます。その反面、「相場は知ったら、しまい」という諺がある通りオリンピックが終わったら株式市場が調整局面に入る可能性があることは否定できません。今の中国を東京オリンピック当時の日本と比較することは様々な条件が異なるのでナンセンスなことかもしれませんが、東京オリンピックが終わった後の日本を思い起こしてみると証券不況が来て山一證券に日銀特融が発動されたり、それまで見て見ぬふりをしていた公害問題に対してついに国民の不満が爆発したりしました。つまりオリンピックの後は社会の変革期だったわけです。 ロシアの政治カレンダー一方、ロシアにとっても2008年には大きなイベントが控えています。こちらは現職のプーチン大統領の任期が2008年3月に切れるという事です。ロシアの憲法では大統領が連続して務められる任期は2期までです。憲法改正が無い限り(そしてプーチン大統領がこれまで表明したところによると改憲の意思は無いことになっています)プーチン大統領はクレムリンを去らねばなりません。プーチン大統領が余りにも行政手腕に長けていたので、この後、誰が来ても世界の機関投資家にプーチン大統領と同じレベルの安心感を与えることは難しいと思います。このため2008年の任期満了を前にロシアの持ち株を処分する投資家も出てくるのでは無いでしょうか?。それから大統領選挙の前哨戦として07年12月にはデュマ(議会)の選挙もあります。大方の予想ではプーチン大統領の支持母体である統一ロシアが過半数を制すると見らえています。いずれにせよ2008年はロシアにとってむずかしい年になる可能性は否めないわけですからロシア株に投資するなら早めに決断し、大統領交代のときまでにはポジションを整理するくらいの用心が必要かもしれません。 インドの政治カレンダーインドでは2007年の3月から一部の地域で州議会選挙がはじまります。これは2008年にかけて順番にインド各地で展開する行事であり、そういう意味ではクライマックスはありません。この過程でインドの国民が現政権にどれだけ満足しているかが或る程度明らかになると思います。前回の選挙では事前の予想を覆し、コングレス党が当時の与党のBJPを退けました。経済好調に自信を深めていたBJPの「輝けるインド」という選挙のキャッチフレーズに対して多くの有権者が冷淡だった理由は農村と都市市民との格差拡大などの問題があったためです。現在、インドの経済は引き続き絶好調ですが、格差の問題は余り改善していません。インドの政治の体質からして選挙の時期はどうしても「ばら撒き」政策に流れやすいです。しかしインドは赤字財政体質であり、国際機関投資家はそうした人気取りの政策に対しては厳しい目を向けると思われます。 先進国の金融市場にも注意BRICsに投資するに際して、先進国の金融市場全般のリスクについても一応目配せしておく必要があると思います。これまで既にBRICsの株式や投信に投資したことのある人なら思い当たるでしょうがBRICsの株式市場が急落するのは必ずしもBRICsそのものに問題があるときではなく、先進国の金融市場が変調した場合であることが多いからです。BRICsの株式は世界の過剰流動性のゲームの一番先端の部分であるとも考えられ、それゆえに先進国の信用市場が微妙に変化しただけで怒涛のような売り物に晒されたりします。その先進国の信用市場ですが、このところ凪のような平静な状態が続いています。現在の景気サイクルは所謂、ミッド・サイクル・コレクションと称される景気拡大局面での踊り場的な段階にさしかかっています。このことから考えるともう少し荒れて然るべきなのにこれまでのところ世界の市場は極めて安定的に推移しています。それ自体は歓迎すべきことですが、心配なのは投資家の心の中にコンプレーセンシー(リスクを甘く見る態度のこと)が忍び込んできている点です。ドル安とエマージング市場現在の国際資本市場では日本をはじめとする金利の比較的低い国でレバレッジをかけた信用を調達し、それをエマージング市場などの比較的金利面で魅力のある市場に投入するというキャリー・トレードが常態化しています。これらの国々の金利見通し、ならびに為替が安定している場合にはこういうポジションは引き続き維持されるでしょう。しかし何かの拍子に例えば急激にドル安に振れたとすると国際機関投資家はポートフォリオのリスク・エクスポージャーを一斉に落としにかかると思います。BRICsの株式はそういうシナリオ下では真っ先に痛手を蒙るカテゴリーです。
2007年01月10日
-
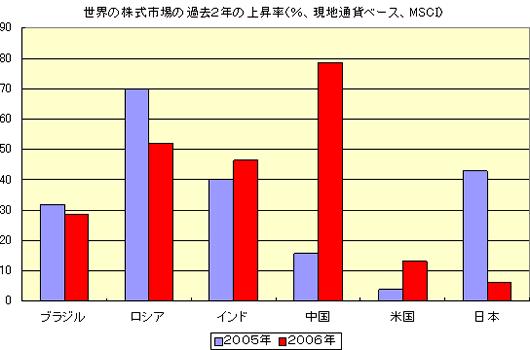
第68回 2007年のBRICs市場の展望(その1)
今日のまとめ1.BRICsにとって去年は大変良い年だった 2.07年もBRICsのGDP成長率は高水準が予想される 3.同様に企業収益成長率も高水準が予想される 4.インドを除けば株価収益率でみた株価水準はそれほど高くない 5.インドが割高なのは投下資本利益率の高さが投資家から評価されている為 2006年の相場を振り返る2006年はBRICsにとって大変良い年でした。下のグラフは過去2年間の主要市場の株価上昇率です。 2006年のBRICs株式市場を振り返ると唯一、ヒヤッとさせられたのは5月から7月にかけての急落局面でした。しかしこの急落はBRICsのファンダメンタルズが悪化したために起こったのではなく: (1)日本の量的緩和政策の終焉と (2)それに呼応して世界の投資家が向こう見ずなキャリー・トレードのポジションを一斉に落としたこと の2つの外的要因が直接の引き金となった、極めて一時的な調整でした。その後のBRICs相場は危なげない展開でした。今年も去年に引き続き米国や日本における流動性の動向がBRICsの株価形成に大きな影響を与えると考えられます。 2007年のGDP予想夏の米国連邦準備制度理事会の利上げ打ち止めの決定以降、投資家の懸念は米国経済の減速にむかっています。そこで2007年の各国のGDP成長がどのくらいになるか?の予想ですが、コンテクスチュアル・インベストメンツLLCでは下のグラフに見られるようなシナリオを立てています。中国は9%、インドは7%、ロシアは7.3%、ブラジルは3.5%を予想しています。先進国各国のGDP成長率は若干2006年より下がる見通しですが、グラフからもわかる通りBRICs全体としては相変わらず高水準の成長が維持される見通しです。(なお、中国とインドの予想数字に関しては弊社の数字よりもっと強気で見ているエコノミストが多いと思います。) 企業収益予想次にBRICs各国の純利益成長率に関してですが、弊社では下のグラフのような予想を描いています。 中国は13%、インドは20%、ロシアは15%、ブラジルは25%成長を予想しています。ひとことで言えば2007年も企業業績は順調に伸びるということです。なおBRICsの企業収益の予想は大きく外れる場合が多いのでこれらはあくまでも大体の目安と考えてください。このことは市況産業の占める比率の高い国について特にあてはまります。例えばロシアの2006年の純利益成長に関して2005年の時点で上のグラフに見られるように40%近くも成長すると予想していたエコノミストは誰もいなかったと思います(私自身はマイナス成長になることを覚悟していました=つまり全く間違っていたわけです)。なぜロシアの予想数字がそこまで大きく外れたかと言えば、それは原油価格が06年前半に急騰した展開を読みきれなかったからです。 BRICsの株価水準さて、次にBRICsの株価水準に関してですが、最初に見たように各国とも素晴らしい株価上昇を見た割には例えば株価収益率で見たBRICsのヴァリュエーションは去年と比べてもそれほど高くなっていません。これは企業収益が着実に伸長してきたことに助けられているわけです。 上のグラフで見てもわかるとおり、ブラジルや中国に至っては過去10年の平均PERより現在のPERのほうが割安なくらいです。去年の中国の株式市場の好調ぶりを見ると「あれはバブルじゃないか?」と決め付けたくなりますが、少なくとも株価収益率という尺度で見る限り11倍程度のPERの市場をバブルと呼ぶことには少々無理があると思います。反面、インドは過去10年の平均PERより大幅に割高になっているのはもちろんのこと、過去最高値の水準まで来ています。インドの株価評価が飛び抜けて高いのはインド企業の経営効率が大変高いことと無関係ではありません。下のグラフは投下資本利益率と株価収益率を比較したものです。投下資本利益率とは融資や社債、株式など、投資家から託された資本でもってどれだけ利益を稼いだか?の指標です。これで見るとインド企業は授けられた資本を活用して利益を生むのが特に上手いことがわかります。これは長い間インド企業は資本市場へのアクセスが限られており、なけなしの資金を無駄にしない態度がしっかり身についていることによります。
2007年01月04日
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- まち楽ブログ
- 山城ガールむつみさんの「北条五代特…
- (2025-11-20 23:23:43)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 日経平均株価、先物上昇、サイバー株…
- (2025-11-21 00:00:02)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- ファジーについて考察します。
- (2025-11-20 07:39:53)
-







