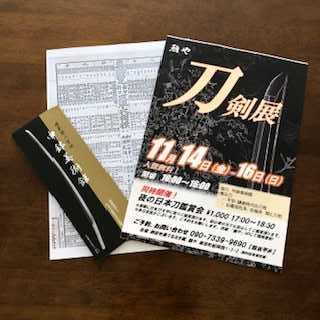2025年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

設備より躯体性能(断熱性、耐震性)を 優先
おはようございます、紙太材木店の田原です。日中は暖かくなってきましたから昨日は油断していて29度・・・薪ストーブのおかげですが、室温調整が微妙なこの頃です。さて、2月も終わりですが1月、2月の電気料金はどれくらいでしたでしょうか?2月分の請求はもう少し先と思われますが一般的に1月より少し安くなる傾向があります。1月はお正月休みで家にいる時間が多くなりますし、夜更かしすればそれだけ電気を使うことになります。それに2月は28日しかありませんから1月より3日少ないのも関係しているでしょう。紙太材木店では付加断熱を10年ほど前からしていますが5年ほど前までは太陽光パネルは予算に余裕があれば設置。パネルより先にすることは、断熱性を上げる事。Ua値で言えば0.3程度までは断熱性優先とお話してきました。と言うのもパネルは後からでも容易に設置できますが、住まいの断熱性を上げることは後からの工事では費用も掛かりますし、住ながらとなるとストレスも多く難しいものがあります。北海道では外壁側からの断熱改修もありますからストレス的には軽減されても費用的にはそれなりにかかります。2017年から2020年までの4年間の太陽光パネルの設置率は50%弱ほぼ半数の方が設置してました。それが2021年以降は、100%の方がパネルを設置されています。蓄電池の設置はまだありませんが、電気代については上がることはあっても下がることはありません。FITでの買取金額はまだしばらく続きますが、価格的には減少傾向です。エネルギー価格上昇に対する住まい手側の対抗手段の順番は1 断熱性を0.3程度まで確保2 太陽光パネル3 蓄電池この順番です。蓄電池は価格的にこなれていない感がありますが、近い将来にはどの家庭でも設置の方向に行くと思われます。紙太材木店の住まいのオーナーさんの年間のエネルギー代の収支はUa値0.3前後夫婦+子供2人30坪前後パネル容量4~5Kw平均すると、自家消費買電、売電で年間で+5700円となります。10年間は売電がありますが、その後は売電単価が安くなりますから収支としてはマイナスになるでしょう。そのマイナスがどれくらいになるか?FIT終了後の売電単価を厳しめに見て6円買電単価を40円とすると年間のエネルギー収支はマイナス90.000円ほどになります。住まいの性能とパネル設置容量で異なりますが、Ua値0.3前後でも上記のような収支になります。断熱性を優先した住まいと断熱性よりパネル容量を優先した住まいでは、かなり違いが出るんじゃないでしょうか。くれぐれも、設備より躯体性能(断熱性、耐震性)を優先してください。蓄電池の出番はFIT終了後のその頃でも遅くはありません。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月28日
コメント(0)
-

実施設計をすると住まい手には見えてくるものがある
おはようございます、紙太材木店の田原です。日中が暖かくなりました。朝は氷点下ですけれど・・・おかげで、午後から薪ストーブはお休みですが今日はどうなんでしょうね。昨日はご契約前の最終打合せでした。建物の仕様はその前の打合せで確認してありましたから、金額の確認です。設計契約をして頂いたのが昨年の7月末ですから、ほぼ7か月の打合せ期間ということになります。設計契約をしていただく前にプラン作成をしてそのプランに基づいて概算の金額をお伝えしていますが、7か月の実施設計の間には住まい手の方の最初に考えていたことが変化していきます。設計が詳細になればなるほどより具体化すればするほど当初は遠くから森を見ていたけれど、どんどん近づいて木を見る枝を見る芽を見るそんな感覚でしょうか。実施設計をすると住まい手の方には見えてくるものあるんですね。家を建てると言うことは住まい手の方が経験したことの無い購買活動です。つまり、何もないものを買うことになります。自動車やTV、冷蔵庫、スマホ、靴、服どれも目の前にあって形になっていて金額も明示してあります。素材や性能、機能、色や形もどれも分かっていて買うか買わないかを決めてきました。でも住宅は何もありません。しかも一つ一つのパーツを全て自分で決めていかなければなりません。大手のHMや規格住宅であればこの三つから選んでください。色はこの二つしかありません。それは取付できません。うちの会社では取扱いできません。仕様決めの打合せは3回までで全てパソコン上で行います。それでコストが安くなり、自分でも満足できるならそれでいい方も多くおられます。住まいを商品として考えるなら単に自分達の世代だけが住むのだから安ければ安いほどいい住宅価格が高騰していく中、それは一つの考え方としてあるでしょう。決められた選択肢の中から選べば金額の変動はありません。紙太材木店の場合、設計契約前の概算金額と詳細設計をした後の金額とでは3~4%ほど上振れした変動があります。選択肢を限定して決めてしまえば変動は少ないと思いますが、気持ち的にそうしたくないんですね。なので最初に伝えておきます。詳細打合せをしていくと過去のお客様の例から3~4%上振れしますと。次回の打合せでご契約、着工は4月以降になりますから基準法改正後となります。岐阜市一日市場北町の家GX志向型住宅Q1.0住宅 レベル4長期優良住宅耐震等級3(許容応力度計算)BELS ☆5設計住宅性能評価建設住宅性能評価紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月26日
コメント(0)
-

住まいの省エネ性は Ua値や断熱性能等級ではなく 冷暖房負荷で判断するのが基本
おはようございます、紙太材木店の田原です。朝は氷点下の日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。2月も今週で終わり。日中は暖かくなる予報ですが朝晩の冷えはまだしばらく続きそうですね。建築知識ビルダーズの編集長の木藤さんがFBで自邸が75m2以下の為、長期優良住宅の基準に満たないことを嘆いて(怒って)ました。75m2の広さは平屋の場合にかかる制限です。もちろん2階建てにも広さの制限があって、その場合1階は40m2以上という規定があります。最近は平屋ブーム。来月断熱、気密の見学会を行う可児の家Cの分譲地でも6宅地の内4軒は平屋。NHKのクローズアップ現代でも平屋が取り上げられていましたが、平屋がブームな理由の一つに2階建てに比べ階段がない、廊下が少ないなのでその分の費用が掛からないなんてことを挙げていました。同じ面積なら基礎も屋根も2倍になることはスルーしてましたから、建築屋から見れば??な内容でしょうか。Ua値や断熱性能等級を基準にすると価格の事は別にして平屋でも気になることはありませんが、暖房負荷や冷房負荷を基準にすると年間の暖房費や冷房費は2階建ての方が南面からの日射を利用できれば圧倒的に有利になります。もちろん、設計の工夫や冷暖房負荷の計算が出来なければ絵にかいた餅ですが・・・平屋ありきのプランでは冷暖房負荷の違いも分かりませんし、設計者が提案しない場合もあります。前回、4月の基準法改正で構造計算や省エネ計算の義務化で相当混乱が予想されるとお伝えしましたが実は、平屋はその対象外何故なのか?この平屋ブームの火付け役は?分からないことが多くありますが住まいの省エネ性はUa値や断熱性能等級ではなく冷暖房負荷で判断するのが基本です。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月24日
コメント(0)
-

2025年 基準法改正の意味
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日の朝は冷えましたね。名古屋でマイナス2.2度こちらではマイナス5.1度でした。外トイレの蛇口も、この冬初めて凍りました。子供の頃は蛇口が凍らないように、寝る前に洗面室の蛇口の水を(井戸水)少し出したままにしておくのが普通でした。朝の冷え込みは随分緩くなりました。昨夜、建築士会の理事会で4月の基準法改正の話しが出ました。今月末に行政や民間の確認検査機関を招いて研修を行うのですが、事前打合わせに行った研修委員長の話では縦割り行政そのもの・・・混乱が相当予想されるようです。長期優良住宅や性能表示、あるいはBELSを標準的に取得している工務店や設計事務所は、何か特別なことをすると言った影響はありません。上記の各種の認定を取るために、構造計算や省エネ計算も当たり前に行っているからです。今月の新建ハウジングに2024年の11月に過去3年以内に住宅を新築した人のアンケートがあります。(n=600)長期優良住宅の取得率は41.8%内訳は全国展開のHMが53.7%地域の工務店が26.8%長期優良住宅の取得率はここ数年上記のような数字で変化はありません。つまり、6割は長期優良住宅の基準に達していなことになります。家余りの現在。今後も更に増えていくと予想される空き家。どんな対策を取る必要があるのか?ここ何年も笛や太鼓で、あるいは補助金で優良な住宅の割合を高めようとしても4割に張り付いた長期優良住宅の割合は伸びることはありませんでした。なんとしてもその割合を高めるそれが、今回の建築基準法改正です。一次的な混乱があろうがついてこれないHMや工務店があろうが優良な住宅を建てれない業者には退場してもらう。良い悪いは別にして、国の方針はそのようです。気をつけなければならないのはこれから家を建てる方。家が完成すると完了検査を受けて、検査済み証と言うものを発行してもらう必要があります。完了検査を申請する時、各種の書類や写真を添付するのですがそれがどう変わるのかまだ何も発表はありません。書類が不備であれば写真が無ければ完了検査は受けられませんし、検査済み証も発行されません。長期優良住宅の認定も検査済み証の添付が条件です。住宅会社の依頼先は十分検討する必要があります。検査済み証が無くて困るのは、住宅会社ではなく家を建てた方なのですから。基準法の改正は今後は優良な住宅しか建てさせないという国の固い決意の表れと見ることができます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月21日
コメント(0)
-

活字で勉強したい方向け Replanの 「鎌田紀彦のQ1.0住宅デザイン論」
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝はマイナス4度と冷え込んでいます。昨夜10時頃まで薪ストーブを焚いていた事務所も、今朝は15度まで下がっていました。最近、断熱改修のご相談をたて続けて受けました。以前と違うのは相談者が断熱や断熱リフォームの事を勉強されていることです。気流止めと言っても理解されている方は実務者を除けば一般的にはほとんどおられませんが、既にご存知でした。You TubeなどのSNS上では家づくりでの様々な情報が動画で溢れていますから、スマホさえあれば隙間時間でも知識を広げることが可能です。そんな時代ですが、活字で勉強したい方にお勧めなのがReplanの「鎌田紀彦のQ1.0住宅デザイン論」新住協の前代表理事で日本の高性能住宅を牽引されてこられました。新住協の総会が年に一度開催されますが、毎回鎌田先生が基調講演をされます。その講演内容のダイジェスト版と言っていいでしょうか。総会は年に一度ですが、3か月に一度寄稿されてますから変化の速い最近の住宅業界にタイムリーな内容となっています。相談された方もこのReplanで勉強されたとかその鎌田先生のセミナーが3月18日にウィンクあいちであります。内容は1.省エネ基準等級6~7 Heat20 G2~G3 そしてQ1.0住宅レベル1~4 どのレベルで造ればよいか2.高性能住宅をエアコンで、 ローコストに快適な冷暖房するにはどうする。3.ローコストな断熱・耐震改修~ 住宅の一部を断熱改修するにはどうする、 マンションを断熱改修するにはどうする。会場とZOOMがあります。時間は午後1時から5時までの4時間濃い内容ですので、新築やリフォーム、断熱改修をお考えの方は必見ですね。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月19日
コメント(0)
-

工事中の見学会では何を見るのか
おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は3月並みの暖かさでしたが、今週一週間ほどは寒気が居座るとか。まだまだ寒い日が続きそうですね。さて、前回お伝えした可児市で工事中の住まいの見学会は3月9日(日) 10:00から開催します。Q1.0住宅 レベル4許容応力度計算 耐震等級3レベル4と言うのは国の省エネ基準住宅の暖房消費エネルギーの10%以下であることを示しています。自然温度差は12.4度で、今まで紙太材木店で建てた住宅の中では一番良い数字です。立地は南面道路で日射を遮るものは何もない恵まれた条件です。写真でわかるように総二階で南面の窓を大きく取っています。自然温度差が12.4度もあるのは窓の大きさと建物の断熱性が関係しますが、もう一つ関係するのはガラスの日射侵入率。従来の日本のサッシのガラスは断熱性が良ければ日射侵入率が悪い日射侵入率がよければ断熱性が悪い相反する性質を持ってました。今回南面で使用したのはシャノンのESクリアという断熱性も良く、日射侵入率も良いガラス。自然温度差が12.4度と言うのは、今日の日中の最高気温が10度と予報していましたが何も暖房しなくても日射があれば12.4度プラスして部屋の中は22.4度になることを表しています。実はこのESクリア北海道、東北限定のガラスで、残念ながらこちらでは販売していません。関東以西ではESスーパークリアと言うガラスが出ています。断熱性はいいのですが日射侵入率がESクリアより劣ります。ガラスの違いで自然温度差がどれくらい違うかあまり意識されていないと思いますが、ESスーパークリアで計算すると自然温度差は約0.6度違います。なんだ、0.6度かと思われるかもしれませんが付加断熱を3センチ厚くすると自然温度差が同じになります。たかがガラスと言っても馬鹿になりませんね。限られた予算を最大限有効に使うことが大切です。単にUa値を上げるだけでは、有効に使ったことにはなりません。単にUa値をよくする事よりも暖房費や冷房費が下がることの方が、住まい手に取っては大切なはず。この住宅は一種の全熱交換式の換気扇は使っていません。それでも、暖房消費エネルギーはレベル4まで持って行けますし、自然温度差は12度を越えます。建物が完成した後の見学では表面的な事しか見えません。工事中の見学は、機会があればどんな工夫がしてあるか自分の目で見ることができます。他人任せHM任せではなく、自分自身の目で見ることが大切です。断熱材はどうやって入っているべきか気密シートはどう張られているか窓はどのように設計したらいいか付加断熱はどこまでしたらよいか換気や空調はどう考えればよいか換気は一種の全熱交換でなければならないのか結露計算はどうされているのか日射の遮蔽はどうするか台風対策は防犯カメラはetc可児市 工事中見学会構造、断熱、気密etc3月9日(日) 10:00~16:30お申し込みはこちらから>>紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月17日
コメント(0)
-

暮らし易さや 住み心地の良さは 見えないところに
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は風が強くて寒い一日でした。あれだけ風が強いと隙間風を体感できた方もかなりおられるのではないでしょうか。なんだか部屋の空気が動いているようなとか何処からかわからないけど明らかに冷たい空気が入ってきている・・・トイレの換気扇が逆回転している・・・勝手口の上げ下げ窓の隙間からジャロジーから etc強風が吹いているので明らかに隙間風がと分かりますが、実は強風でなくても隙間があれば気がつかないだけで外気は室内に入ってきています。出典北海道住宅新聞記事(有)北欧住宅研究所 川本清司以前、漏気量の記事で第三種換気の時の表を解説しましたが一種換気の場合は上記のようになります。表は北海道なので内外の温度差30度温度差換気が出ていますが、東海地方だと内外温度差は20度くらいでしょうか。東海地方の平均風速は過去の気象庁のデータから3.5m/s前後です。表から分かることは隙間が大きければ大きいほど、風が強く吹けば吹くほど内外の温度差が大きければ大きいほど家の中から逃げていく暖かい空気が多い反対に言えば外の冷たい空気が入ってくることになります。台所の換気扇お風呂の換気扇トイレの換気扇x2か所多くの場合これらは換気計算のルートとは別物です。そこに上記の漏気量が加わります。熱交換率〇〇%だからと言っても、家全体での換気量から見ると実際に熱交換している割合は皆さんが思っているより遥かに少ないものになります。だからと言って熱交換が意味のないものではありません。その効率をより高めるための設計上の工夫や施工の精度が、家づくりには求められます。ある意味暮らし易さや住み心地の良さは見えないところにあります。3月9日(日)に可児市で工事中の住まいの断熱、気密の見学会を計画しています。詳細は後日お知らせしますが、見えないところを見たい方や自然の力を使った窓の設計や空調設計の基本を見てみたい方は、見学にお越しください。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月14日
コメント(0)
-

目で見るコールドドラフト
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝はマイナス3度。名古屋もマイナス1度と報じてましたから東海地方はかなり寒い朝となりました。事務所の机の横には窓がありますが、ガラス面から冷気が滝のように下りてきます。少し分かり難いかもしれませんが写真の右側から水蒸気を出しています。左側に行くにつれ下側に下がっています。この冷気が窓面を伝って下りていくのをコールドドラフトと言います。一般的にこのコールドドラフトを防ぐには根本的にはサッシの性能を上げガラスや枠の断熱性を上げることですが、既存の家の場合このガラスの室内側にもう一つサッシを取り付ける事でも可能です。ガラス面で発生する冷気以外の細かな隙間から入ってくる隙間風も内側にサッシをつけることでかなり抑えることができます。サッシの外側にシャッターがあれば、夜間はそのシャッターを閉めることでも抑えることができます。また、厚手のカーテンやプチプチ(気泡緩衝材)取りつけることでも可能です。ただ、根本的には内窓の設置や高性能サッシへの交換でしょうか。既存のサッシの場合、サッシ自体の気密性についてはほとんど考慮されていないと言っていいでしょう。多くの日本の家では、サッシの断熱性が低いことでコールドドラフトが発生し、気密性が低いことで冷たい隙間風が入ります。自分の家は10年ほど前に建てた家だから大丈夫と思ってるかもしれませんが、寝室で親子4人川の字で寝ていて朝起きた時にサッシに結露が見られるようなら換気が不足してるかサッシの断熱性が不足しているかその部屋の断熱性が低いかどこかに問題があります。断熱改修には様々な手法があります。寒いからと単に断熱材を入れるだけでなく、寒さの根本的な要因を取り除く必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月12日
コメント(0)
-

寒いほどエアコンが頻繁に止まる デフロスト対策
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も粉雪が降っています。空はどんよりとした雪雲で、予報通り晴れるのか気になります。今シーズン一の寒波普段雪の少ない所や最近積雪の無かった地域でも雪が積もったり・・・日中でも10度を下回ったり何度も氷が張ったりとここ1週間ほど寒い日が続いてますがストレスなく暖かく過ごされているでしょうか?最近はエアコン一台で暖房できますの家があります。温度差20度でUa値で計算して2.8KWだからOKという乱暴な計算で煙に巻いているようです。これは家から逃げていく熱よりエアコンから得られる熱が大きければ暖かいとして宣伝しているのですが、エアコン暖房で忘れていけないのはエアコンは寒いと止まる・・・運転を止めます。デフロスト運転と言います。暖房運転をすると室外機に霜が付きますが、そのままだと霜は氷に成長してしまいます。(もちろん動かなくなります)その前に霜を融かす必要があって融かしている最中がデフロスト運転デフロスト運転で霜を融かしている時は暖房運転をお休みしてます。ここ1週間ほどなんでエアコンがこんなに頻繁に止まるんだ?故障か?でもしばらく放っておくと動きだすから何なんだ?エアコンが動いている時は部屋は暖かいけどエアコンが止まると忍び寄るような寒さが・・・頻繁にエアコンが止まって寒いから設定温度を上げると、更に頻繁に止まる悪循環デフロスト運転のその対策はなんと寒いのに設定温度を下げる事・・・でも、残念ながら設定温度を下げてもデフロスト運転の頻度が下がるだけで無くなるわけではありません。エアコン一台なんていうHMの宣伝文句に固執せず、もう一台エアコンを設置して2台使いが賢明ですが、燃費は悪くなりますが寒冷地用エアコンの設置でも大丈夫です。もう一つ、室外機の霜の発生を押えることは設計上の工夫ですることができます。これが燃費を抑えれて暖かくストレスなく過ごせる方法で、体も懐も温かく過ごせます。方法は簡単で暖かい空気を室外機にぶつけて霜の発生を抑えること。なので住まいの設計時に対策を取っておく必要があります。抜本的に暖かさを確保するには既に住んでいる場合は・寒冷地用エアコンに替える・もう一台エアコンを設置して 2台使いをする・他の暖房器具と併用する・断熱改修をする高性能な住宅を建てているところでも、デフロスト対策まではなかなか教えてくれません。新築検討者は慎重に考える必要があります。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月10日
コメント(0)
-

KKBでスタイルのある家づくり
左から木又、桂山、大木、田原、清水、大沢、関尾(中央の頭は勝部)おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日、一昨日とKKBの研修でした。二日目は名駅に朝8時15分集合なので私は近場と言うこともあり家に帰ったのですが・・・岐阜県の道路は雪で大渋滞。雪の影響は愛知県の犬山まででその先は大丈夫と予想していたのですが、犬山まで行くのに予想以上の時間がかかってしまいました。結局、名古屋まで2時間かかりましたが、早めに出ていたのでなんとか大丈夫でした。二日目はイシハラスタイルさんの建てた家の見学です。私は午後から所用があったので午前の2軒を見学しました。2軒とも1年ほど前に完成し、既に入居されてます。2軒とも住まいをとても大切にされており、丁寧に暮らされてるのが分かりました。会社の社名通りスタイルのある家づくりをされています。先日も広島でKKBの建てた家を見学しましたが、会社のHPの写真で実例集を見るのと実際に訪れて見るのでは感覚的にはその情報量は何十倍も違います。使ってある素材や材料職人の手仕事、技量設計者の工夫etc大手のHMの建てた家を見ても参考になるものはあまりありませんし、これはと、思わず写真を撮りたくなるようなこともほとんどありませんが、KKBに参加している工務店の家の見学は見ているだけでも楽しいですし参考にもなります。新築を検討されている方は一度そんな見学会の機会があれば覗いてみてください。住宅展示場にあるHMの家との違いが如実に分かります。住宅展示場は既に何軒ものHMの家が建っていますし、訪問するのも地場の工務店の見学会より敷居が低く感じられますから、工務店の見学会に比べれば訪問しやすい環境にあります。だからと言って住宅展示場ばかり行っていては、違いがわかりません。一生に一度の家づくりなのですからセンスのいい工務店の見学会にも是非一度足を運んでみてください。合板フローリングにビニルクロス工業製品の枠やドアそれらを使うだけが家づくりではありません。工務店はその工務店独自のスタイルのある家づくりをしています。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月07日
コメント(0)
-

入れればいいわけでは無い、壁や床の断熱改修
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は雪。それほど積もっているわけではありませんが、細かな雪が深々と降ってます。午後はKKBの集まりが名古屋でありますから早めに出かける必要がありそうです。先日、断熱改修の相談を受けました。20年ほど前に建てられた住まいです。契約では床下に断熱材があるはずでしたが、余りの寒さに確認したところ床下に断熱材が入ってなくて数年前に入れたとのこと(建てた業者はすでに倒産)壁の断熱材は20ミリほどのスタイロフォームが放り込んであります。放り込んであるというのは、固定されてあるのではなくただ、入れてあるだけと言う意味です。壁の厚さは105ミリそこに20ミリの断熱材ですから85ミリの隙間ができます。もちろん、壁の気流止めなんてありませんから床下の空気はその壁の85ミリの隙間の空気と一体です。更に言えば壁の隙間の空気は在来工法の構造上、1階の天井裏の空気と繋がっています。天井裏の空気は2階の壁の空気とも繋がっていて、それは屋根裏の空気とも一体です。在来工法の大壁の家はたとえ断熱材が入っていても、壁の中いっぱいに充填されていなければ床下から屋根裏まで一体の空気になります。その空気と室内を仕切るのは12ミリのプラスターボードと張ってあるビニルクロスだけ・・・もちろんコンセントや照明のスイッチが壁についていれば、そのわずかな隙間から冷気が室内に入ってきます。壁を板張りにすれば、乾燥して収縮した板同士の隙間から更に冷気が入ってきます。部屋を暖房して暖かくすればするほど、暖かい空気が室内の天井近くの隙間から逃げていき、出ていった暖かい空気と同じ量だけ冷たい空気が室内に入ってきます。いくら暖かくしても部屋は15度以上にはならず、ひざから下は更に温度が低い。日本の少し前の住まいを暖かくするには、断熱性を上げることと壁の中の通気を止める事の二つをする必要があります。しかし、壁の断熱性を上げるには外か中の壁を取り除いて断熱材を入れるしかありませんが、それはにはお金も時間もかかります。次善の策が壁の通気止め、気流止めです。床の断熱材を厚くすることも有効ですが、床の合板に密着させる必要があります。床の断熱材は一般的にスタイロフォームのように硬質系の断熱材が使われますが、床合板の裏側に密着させて取りつけます。断熱改修などで後から取り付ける場合はどうしても隙間が出来て、効果が半減してしまいますから密着させるには工夫が必要です。壁の断熱材にしても床の断熱材にしても入れてあるだけではNG。基本的には室内側の壁や床に密着している必要があります。壁の場合それが出来なければ、気流止めで壁の中の空気が対流しないような工夫が必要です。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月05日
コメント(0)
-

Ua値や断熱性能等級より冷暖房費を意識すべき
おはようございます、紙太材木店の田原です。週末は名古屋で完成見学会でした。見学に来られた方と話していて気になることがありました。これは以前から危惧していたことですが、ほとんどの方がUa値や断熱性能等級を意識されています。最近では旭化成ホームズのへーベルハウスが断熱性能等級6(Ua値0.46)を標準化という報道や他の大手のHMも断熱性能等級の上位のシリーズを出してきてますから尚更かもしれません。でも住まいの温熱環境でUa値が0.26とか断熱性能等級7で双六でいうアガリかと言うと、そうではありません。新住協でもパッシブハウスでも重視するのは暖房費がいくらかかるのか?冷房費がいくらかかるのか?その家で生活するとどれくらいエネルギーが必要なのか?住まい手にとっては等級や数値よりも実生活ではそちらの方が意味を持つはずです。一般の方は等級が上がれば数値が良くなればそれと連動するように暖房費や冷房費が下がると思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。なぜなら等級やUa値に、日当たりのよさやによる暖かさや換気の熱交換の効果などは考慮されないからです。住まいの立地条件は様々で日当たりが良ければ等級やUa値を上げるより、日射の有効利用や制御する設計の方が建築コストを抑えたり冷暖房費を下げることができるからです。Ua値や等級は冷暖房費を下げる上でのベースとしては必要ですが、QOL(生活の質)の向上を考えるとそれだけでは十分ではありません。これから新築を検討される方は断熱性能等級やUa値だけを見るのではなく1年間その家で生活したら冷暖房費はいくらかかるか?調理や家電まで含めたエネルギーコストがどれくらいかかるか?そちらも同じように意識していただけるとHM選び工務店選びのひとつの武器になります。同じ土地で同じUa値、同じ断熱性能等級でも住まいの設計次第で冷暖房費は大きく変わってきます。紙太材木店インスタグラムこちらから紙太材木店HPこちらから
2025年02月03日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1