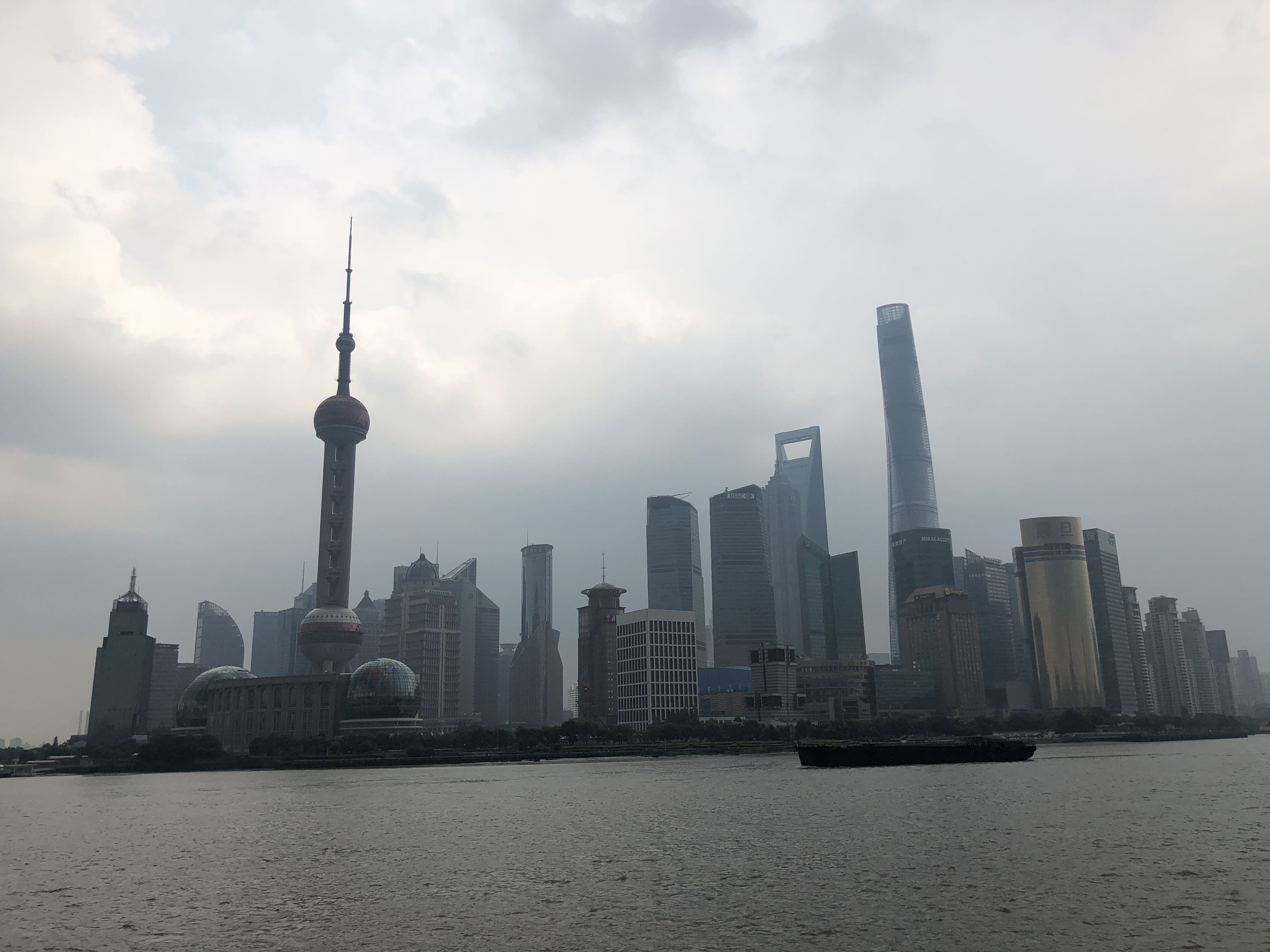PR
カレンダー
コメント新着
キーワードサーチ
「仙台育英 日本一からの招待」という本です。
須江監督は、仙台育英高校野球部を率いて、2022年の夏の甲子園で優勝しました。
東北勢の史上初めての優勝ということで、大きな注目を集めました。
仙台育英高校に限らず、東北勢は何度も甲子園での優勝まであと一歩、というところまで勝ち上がりました。
かつては雪国のハンデ、という言葉もありましたが、時代は変わり、強いチームが各県から生まれています。
しかしながら、なかなか優勝旗は白河の関を越えませんでした。
その間に、北海道は駒大苫小牧が、北陸は敦賀気比が優勝し、優勝旗は北海道や北陸に渡りました。
そんな時代を経て、初めて東北に優勝をもたらした須江監督のチームビルドは、気になっていました。
野球に限らず、高校生の部活動は指導者によるところが大きいので、どのような方なのか、どんな考えで選手と接しているのかなど、興味を持っていました。

仙台育英日本一からの招待 幸福度の高いチームづくり / 須江航 【本】
高校野球のあり方は昔から大きく変わり、坊主頭でないチームも増えました。
仙台育英、慶應と、坊主頭でないチームが、2年連続で夏の甲子園を制することになったのも、大きな変化だと思います。
かつては、監督が厳しく指導し、時には鉄拳制裁などもあり、型にはめ、全て監督の指示で試合をするようなチームばかりだったと思います。
しかしながら、監督の指示や指導の通りにやるだけでは、自分たちで考える力が付きません。
極端なチームでは、全てノーサインで戦うチームも出てきました。
選手がさまざまな状況から自主的に判断し、それをプレーできるようにしていくには、大変な時間や反復が必要だと思いますが、実際にプレーをするのは選手ですので、咄嗟の時に自分たちで判断し、やれるようにしなければなりません。
須江監督の本の中には、選手に考えさせる機会をたくさん与えていくと共に、監督との信頼関係を構築し、お互いに何でも話し合える環境を作っていたことがわかるフレーズがたくさんありました。
また、競争を高めて、ギリギリまでベンチ入りメンバーは決まらないことや、選手の基礎体力やプレーヤーとしての必要な力を数値化し、誰が見ても納得できるように見える化して、ロジカルに指導しているという話もありました。
さらには、上級生が誰よりも一生懸命に練習する、率先してグラウンド整備をする、地域のために貢献する、などという姿勢を見せることで、下級生も自然と同じように振る舞っていく、ということは、非常に納得しました。
これを須江監督は、「チームの文化を作ること」と表現しておられます。
スポーツに限らず、会社、組織において、この「文化」というものはとても大きいと、私も実感していました。
良い文化のある組織は、いろいろな意味で強い組織だと思います。
文化を作ること、を改めて振り返って考え、何年経っても変わらない文化を持っていくことの大切さを学びました。
是非、皆様にも手に取っていただきたい一冊です。