2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年11月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
退院しました
ついに退院し、シャバの生活に戻りました! 10週間ぶりに一緒に暮らすようになった2歳2ヶ月の娘は 「おかぁちゃん、もうあんよいたくない?」 「もうなおった?」 などといいながら(おしゃべりが進歩してる!)、ペタペタと私を触り、歓迎してくれた。その後はべったりと私に甘え、離れるのを嫌がり、生まれて以来初めてというくらい、私に付きまとっている。今まで祖父母と3人で生活できていたとは思えない変貌ぶりだ。大変だけれど、これまで本人なりに我慢していたのだろうから、これも仕方ないかなと思っている。 本来、人工股関節を入れた人は、脱臼の恐れがあるので、脱臼の危険がある姿勢をしがちな、床に座ったり立ったりすることは、退院から1ヶ月くらいはあまりすすめられないという。でも、子供の世話を少しはしないといけないからと、安全な立ち座りのやり方を習ってきたことが思いきり役に立っている。 せっかく慣れた保育園に行く時も泣いていた娘も、もう私がどこかへ行ってしまうことはないと安心したのか、保育園へも泣かずに行くようになり、少し安定してきた。 今、私の重点課題は、自分のリハビリと娘を安心させることかな。
Nov 29, 2010
コメント(4)
-
入院の成果
今回、2ヶ月病院にいなければいけないとわかった時は、そんなに入院!?と、正直愕然とした。 小中学生の頃の入院と比べれば期間は約半分だから、短いといえば短いのだけど、あの頃とは背負うものが違うというのか、周りへの影響は大きい。 困ったな…。と思っていたのだけれど、ふと、この機会にできることをやろう!と考え直した。 そしてその成果は… まず読書。約30冊の本を読んだ。勉強になるものから笑えるもの、話題の作品まで、いろいろ楽しむことができた。 つぎはタイ文字。前々から覚えたいと思っていたのを、この機会に本で学習。歩くようになってからは疲れて頭を使いたくなくなり、なかなか進まなくなったので道半ばだけれど、基本的なところや、構造は少し理解できた。 そして編み物。娘が生まれてから、2年ほどほとんどしていなかったかぎ針編みで、娘のベスト、カーディガン、ポシェット、指人形3体、自分用のカバンができた。 こんな感じであれこれやっていたので、幸いあまり退屈することなくすごせた。 そして肝心の脚は……。 弱った筋力が回復し、強化されるまでは、本当の仕上がり具合はわからない気がするけれど、長さのちがいがほとんどなくなったので、立っているときの安定感が改善された。また、前に書いたように、開きがよくなり、靴下がはけてさらに爪切りまでできるようになったのにはおどろいた。そして何よりも痛くなくなったのはうれしい。 私の場合、年齢や症状の進行度合いからいえば、必ずしも人工関節をすぐに入れる必要はないとのことだった。でも、通常人工関節を選択する高齢の人よりも、求める活動量は大きいはずだから、生活の質を考えれば関節の置き換えを選択してもいい時期も違うのではないかと思う。どちらにしても本人の意思次第だと思うけど。 とにかく、予定されていたことをすべてしてもらい、よい関節を作ってもらえたのは大収穫だ。あとは筋力アップをがんばろうと思う。
Nov 18, 2010
コメント(4)
-
ついに!
入院からもうすぐ10週間。杖を2本使った歩行は少しずつ長く歩けるようになり、少しなら1本でも歩けるようになってきた。 そしてついに退院の許可が! 19日に退院できることになった。退院後はしばらくの間、娘とともに実家で過ごす予定。 両親がいるので家事も育児も急にやらなければいけなくなるわけじゃないけど、家の生活は今よりずっと体力がいるはず。さて、どうなるか…。
Nov 17, 2010
コメント(4)
-
裁判長!死刑に決めてもいいすか
裁判傍聴人として知られた北尾トロ氏の裁判傍聴記第3弾である。 裁判員制度スタートの少し前に、もし自分が裁判員だったらという視点で裁判を傍聴したもので、裁判を通した人間観察が面白く、犯罪の話でありながらつい笑ってしまう前の2冊とはかなり趣も異なる。 趣も異なるけれど、「勉強になる」度合いもかなり違う。タイトル通り、今回は自分が裁判員だったら、死刑という結論を下せるのかということがテーマなので、裁判を追うだけではなく、北尾氏が死刑や裁判員について考えた記録が含まれている。それは法律のど素人であれば誰しも疑問に思いそうなことで、私は大変勉強になった。 さて、もしも私が、この本に出てくる事件の裁判員だったら…。 結論は出せなかった。ずっと前に、永山則夫氏の「無知の涙」を読んでから思っている、死刑ってなんだろうという疑問がさらに深まった感じだ。 それから、この本に出てくる杉並親子強殺事件の容疑者は、発達障害、精神障害を否定されている。この本にはその精神鑑定のところが専門用語が多すぎて概要しか理解できなかったとのことで詳細は省略されている。心理学をかじっている私はそこをもう少し知りたかったなと思った。 ! そこでふと思った。裁判員制度の意味って、そういうところにあるんじゃないかな。 異なる背景を持った市井の人々が集まれば、同じ事件の同じ記録を目にしても、気になる場所や感じ方はずいぶん違うはず。そういう、プロにはない視点を入れることが大切なんじゃないかな。 折しも、裁判員制度初の死刑判決が出たという。裁判員になるってどういうこと?死刑ってなんだろう?そんなことを考えたい人は是非一読を。
Nov 16, 2010
コメント(0)
-
靴下がはけた!!
手術からもうすぐ8週間。最初はスリル満点という感じだった松葉杖歩行も、まだ実用レベルとは言えないものの、かなり安定したので、いよいよ松葉杖よりも短い、ロフストランドという杖(私が以前から使っている杖)を2本使って歩く練習を始めた。これもまだたどたどしいものの、思ったよりはすんなりと、できるようにはなった。 そして、大きな変化をし始めているのが、関節の動きだ。手術前の調子がよかったときよりも、大きく開くようになったのだ。 人工股関節を入れた人が一番気をつけなければならないのは、脱臼だ。関節を入れ替えて3ヶ月くらいは、まだ不安定なので、深く曲げ、内股になると、関節が脱臼することがあるのだという。そのため、そういう姿勢になりそうな動作は禁止されていたり、やり方が決められていたりする。 その一つが靴下の脱ぎ履き。必ず足をひろげ、あぐらのような感じで足を引き寄せてしなければならないのだ。 手術前にこれを聞いた時、 「そんなの、絶対無理!」 と思った。股関節の曲がりが悪いから、足を引き寄せるのも難しいし、開かないし、そんな格好をして靴下をはいたことなどなかった。だから、いくら手術したといっても、それは無理と思っていたのだ。 ところが、先週くらいから、だんだん骨もついてきているのでと、足を引き寄せてあぐらのように開く動作をやってみると…。 もちろん、あぐらの姿勢まではできないけれど、思ったよりも開く!それからはかたくなってしまったひざを曲げる訓練に加え、足を開く訓練もすることにした。すると、その姿勢で親指がちょっと触れるようになったのだ。 これはもしかして靴下が自分ではけるのでは〓 試しにやってみると、おお〓ちゃんとはけるじゃない〓 今も私は前に書いた白い弾性ストッキングを24時間はいている。でもこのごろは、薄いそのストッキングだけでは足が寒くなってきた。ちょうどいいタイミングで靴下がはけるようになって、よかったー。
Nov 5, 2010
コメント(9)
-
かぎ針編みのこどもカーディガン
家事のない入院生活は、本当に時間がある。この時とばかり編み物と読書にいそしんでいる。 いや、リハビリもがんばってますよ。もちろん…。 新作はこども用のカーディガンだ。ブティック社の「編んであげたいキッズニット」という本で偶然見て、ぜひ編みたいと思い、本と同じ色の毛糸を買った。でも、本はパーカーだったのを、フードなしにアレンジしてみた。 残念ながら写真にはあまりうつらなかったけれど、首周辺の、玉編みを並べてで作ったぶどうのような模様ねところを編むのが楽しかった。 本に載っていた、大人用も私好みだったんだけど、大人用は編むところが多いから飽きそう…。編み物好きなわりに根気のない私。
Nov 4, 2010
コメント(2)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇
- 専業主婦ケチ子、ふるさと納税のサバ…
- (2025-11-28 10:47:23)
-
-
-
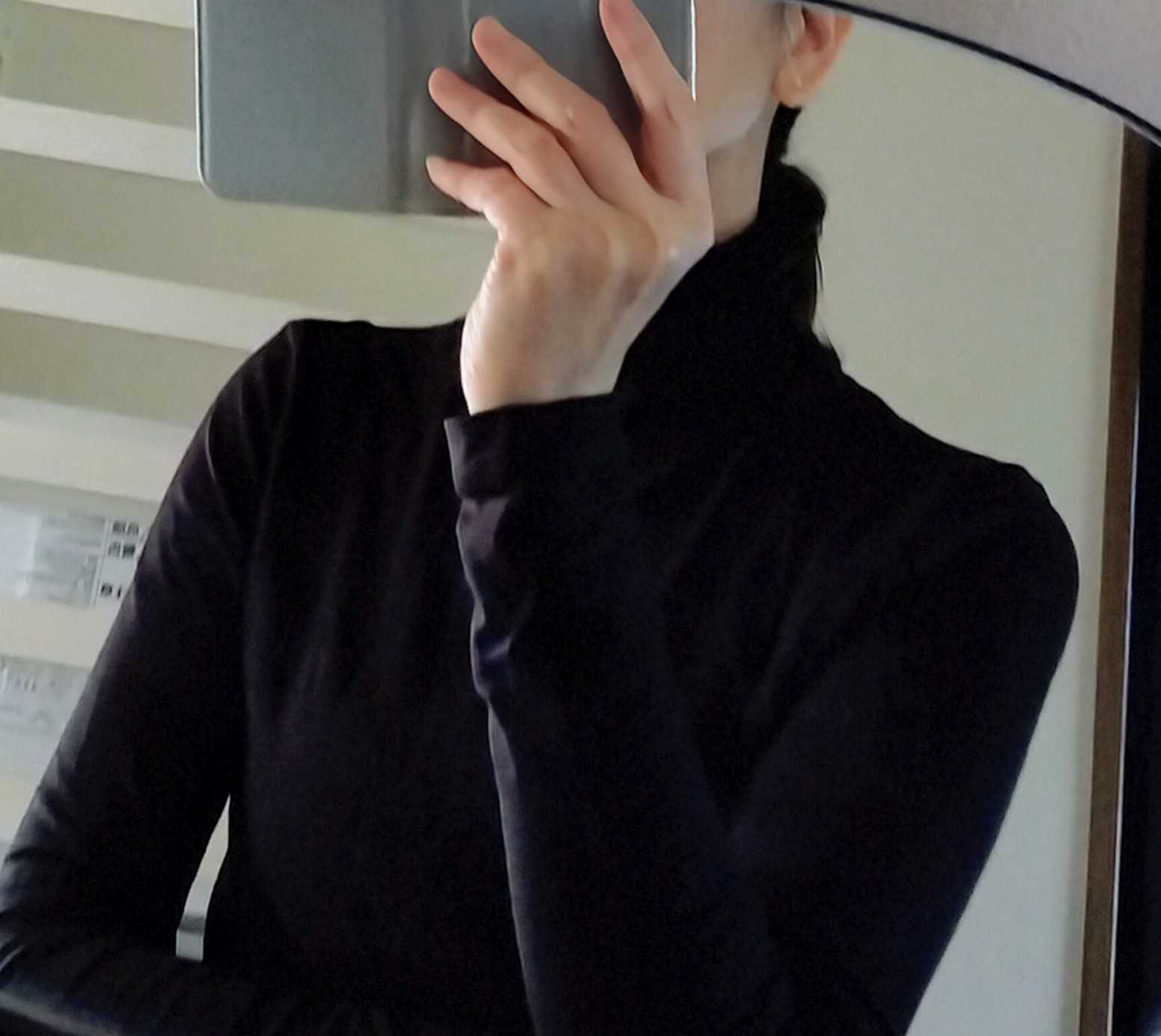
- φ(._.)主婦のつぶやき☆
- 【少ない服で暮らす】冬を乗り切る!…
- (2025-11-28 15:31:52)
-
-
-
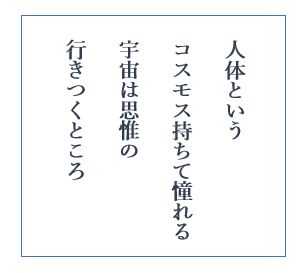
- 日記を短歌で綴ろう
- 〇☆〇星や宇宙は悠久としての憧れ
- (2025-11-28 11:06:35)
-







