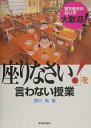

先日、「学び合い」研究をされている 西川純
先生を知りました。
著書を2冊、ネット経由で買いました。
今、読みかけています。
僕はまた、いい本にめぐり合いました。
線を引きまくっています。
ページの端を折りまくっています。
タイトルからして興味をそそるのですが、内容は、僕が心から共感・納得できるものでした。
読みかけの本をブログで紹介することはそんなにないのですが、
西川先生の著書は、ネット書店の在庫がそんなにありませんので、
興味ある方に少しでも早く注文してもらおうと思って書いています。
僕がネットで注文した時は、在庫切れがほとんどで、
買えた本も在庫数冊でした。
(状況は変わっているかもしれませんが・・・。)
詳しくは、いろいろ言いたいことがありますが、まずは著者名と書名だけ。
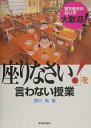
「座りなさい!」を言わない授業
~落ち着きのない子,大歓迎!』
(西川純、 東洋館出版社
、2004、1800円)
以下、楽天ブックスより抜粋転載。
============================
【目次】(「BOOK」データベースより)
学級崩壊?/きっかけ/ 学び合いは学ぶ必要があるか?
/ 教師の役割
/ 立ち歩きを育成する授業
/実践
/ 立ち歩きは悪か?
/グループの構造/個性とは?/オッカムの剃刀
【著者情報】(「BOOK」データベースより)
西川純(ニシカワジュン)
2002年上越教育大学教授。2003年博士(学校教育学)。
教科を学ぶ児童・生徒・学生・大人の姿から、よりよい学びの姿を探る。
その方法は、 徹底的に学びに密着
丹念に記録し、労力を惜しまず分析する
。
最近は、 学習者同士の学び合いに着目
し、
異学年における学び合い
、 授業中の「じゃれ合い」
を研究している。
============================
この本を選んだ僕自身は、
・自分は教えすぎる。教師の言葉が多すぎる。
・もっともよい授業は子どもの表現が多い授業。
・教師は教えずに、子ども同士が学び合うことで相互に高まり合い、
成長する。
・「障害」のある子どもを教師が個別で取り出してマンツーマンで教えることは
本来望ましくない。
どのような子どもも、子どもの中で、学び、育つ。
・お仕着せの「教育」はよくない。
と考えています。
以上のような考え方に、西川先生の本は合致します。
そのため、非常に賛成できるご意見や、勉強になる研究結果が満載であると感じられました。
ちょうど昨日の研究授業でも、
授業の冒頭で子どもたちが立ち歩いて自由に意見交換することを
担任の先生が促されているシーンを見ました。
また、子どもの自己決定・自己選択を促されているシーンも見ました。
授業の最後に、子どもが授業の感想を発表しました。その中に、僕が「すごい!」と思えた発表がありました。
すごいのは教師ではなく、子どもである、ということを具体的に周囲に示せる教師になりたいと思います。
☆以下のブログランキングに参加しています。
応援していただける方のクリックをお願いします!(^0^)
![]()
![]() ブログ王ランキング
ブログ王ランキング
-
「学校というところは勉強しに来るところ… 2024.05.28
-
「思考を過去や未来に飛ばすべからず」 … 2024.05.26
-
近兼拓史『80時間世界一周』 2024.02.22
PR
Category
カテゴリ未分類
(57)生活をよくする
(204)共に生き、共に育つ
(174)たのしいべんきょう
(146)体育
(12)本の紹介
(176)音楽♪
(275)道徳 等
(12)問題解決
(104)考え方
(146)個人的な日記
(161)話し合い・話す・聞く
(36)特別支援教育
(188)小学校
(78)阪神間 地域情報
(36)PC・デジタル関係
(328)教材・教具
(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸
(15)旅行(温泉含む)
(75)環境保護・エコ
(26)仕事術
(74)英語学習
(26)作文・書くこと・漢字
(20)よのなか(社会)
(47)いのち
(27)人間関係・コミュニケーション
(90)子育て
(33)算数
(11)地震・防災
(16)心理・カウンセリング・セラピー
(30)読む・音読・朗読
(9)エクセルでのプログラミング
(21)北播丹波 地域情報
(4)教員免許
(2)教育改革
(34)休校期間お役立ち情報
(21)映画 等
(15)創造性をはぐくむ
(5)プレゼン
(12)通級
(2)健康
(3)ゲーム
(1)Keyword Search
Free Space
※過去の「読書メモ」のリストを作成中。
<ICT活用>
Wordの音声入力が進化していた!
GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」
GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。
GIGA スクール以後の、今後の方向性について
<特別支援教育>
オリジナル標語
自傷行為のある子への取り組み
「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える
運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう
<「今日行く」ユースフル>
駐車場検索のやり方
三宮格安駐車場
♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク
<「教育」ユースフル>
教材・教具
携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)
※リンク※
★にかとまのホームページ ※NEW
にかとま情報局
エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ
にかとまの音楽のページ
Calendar
Comments




