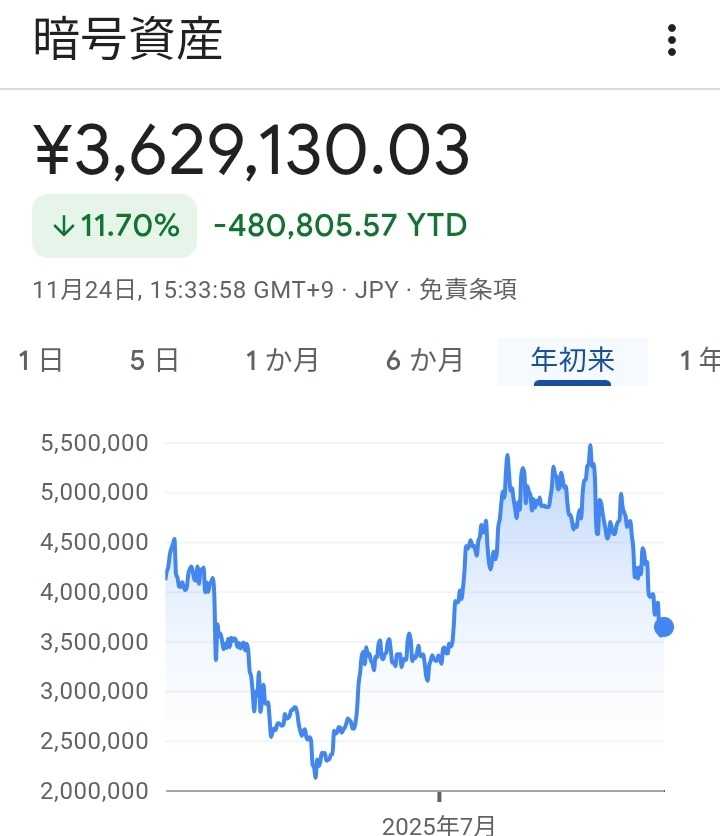2010年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
密教の読み方・・・2
・ 私は仏教(釈迦仏教 上座部仏教 道元仏教)も、密教もともに大好き。マルクスもなるほどと思えるようなった・・・弁護士の故・遠藤誠さんは自分は「シャカマル主義」だと書いていますが、なるほどいい言葉を思いついたものだと思います。(はじめての宗教シリーズ般若心経の本 学研)・ 釈尊の言葉が一番正しく後世に伝わっているとされるのが「ダンマパタ」(法句経)別名「仏教の論語」ほかの経典と趣が違い、人生訓集・・・一つ一つはごもっともなんですがね、「法華経」なんかに比べて、物語性に乏しい・・・一時は「小乗」と軽視され、世渡り術のノウハウに過ぎないと見向きもされなくなった時期もあったそうな。でも、熟読すると中々深い・・・釈尊はまじないとか、占いとか、宗教儀式には無頓着というか、意味がない、場合によっては有害だ!とまで考えておられたようですなあ。そういう意味では、道元禅師も同様。ユダヤ教に対するキリストさま同様でありましょう。 ・ 「法句経」108この世にて功福をえんとてあるは犠牲(いけにえ)をそなえあるは火に供物を献ずること一年(ひととせ)つくすともそのすべての功徳は正しき人々を敬礼(きょうらい)するものの (正しき人々とは、仏陀になった人々のこと)四分の一にも およばざるなり ・ これは正に、釈尊による密教(当時のゾロアスター教)批判ですわな。 ・ 法句経102にはこういうことが書かれている無益の句より成る百の詩(うた)を口に諳ぜんよりききて心のしずかなるべき一法句(ほっく)を誦(ず)せんことはるかにもまさる ・ さて、釈迦仏教と密教は違うのは、違うみたいなんだけど、じゃあ密教は偽物なのか??私はそうじゃないと考えています。密教は、大脳生理学や心理学にもリンクしていくんですが、やはりすごい秘法であると確信しています。大脳(ミクロコスモス)を宇宙(ミクロコスモス)にアクセスさせるのですから・・・
2010.03.31
コメント(0)
-
雷天大壮・・・2
・ こんな時、トップがもし傲慢な態度で部下たちに接するならば、次卦澤天カイ(崩壊)へ至る時・・・・ では、ミドルリーダーはどうすればよいのか?・ 「礼」の心で、問題解決にあたる・ 「礼」の本来の意味は、「自己制御」・・・これはただ引っ込んでいるのではない。中庸のバランスで打つべき時は打って出る、退くべき時は己の利益は放棄しても退く・・・という積極的な受けの姿勢
2010.03.30
コメント(0)
-
雷天大壮・・・1
・ 来年度の職場における業務状況並びに人事環境の易占の結果・ バブル期・・・表面泡立つも空虚なる時・ 下位の者の【陽】の勢いのみ強く、それをうまく束ねることができなくなる状況・ 過ぎたるは、及ばざるが如し・・・共同事業も温度差あり・・・大きく成功を狙うと崩壊の道へ
2010.03.29
コメント(0)
-

密教の読み方・・・1
釈迦の読み方・ 増原良彦著・・・ですがこの方ペンネームは「ひろさちや」さん・・・というとお分かりの方、増えそうですね。・ 私はお釈迦様も好きだし、密教も好きです・・・特に不動明王が好きです。・ ところがどうも、お釈迦様(釈尊)は、密教的なことは禁止されていたようなのです・・・すると、密教って仏教じゃない???の
2010.03.28
コメント(3)
-

「時」に中る・・・3
・ 人生は選択の連続です…しかも、選ばないで、迷っているだけでは、先に進まないだけでなく、むだに命が減っていく。・ ためらわずに矢を射る!その指針の一つに、「易経」の理論的研究は役だっています。・ 君子はうらなわず…諸行無常の「時」の変化を、見取る・読み解く「観察眼」「直観力」「洞察力」を、実際の出来事をとおして、学んでいかなければならないのではなかろうか…と最近、思うようになってきました。易経(上)
2010.03.27
コメント(1)
-
「時」に中る・・・2
・「時」の変化を、私なりにイメージするとこういう感じです・ 全体的には警察の射げき訓練場のような的のイメージ 1 的は、年末宝くじのように回転式で、白・灰・黒(吉・普通・凶)の3色 2 的は交通標識みたいなんだけど、レール式で絶えず動いている 3 動き方は、スピードや向きが絶えず変化している 4 しかし全く不規則という訳でもなく、動き自体はゆったりしている 5 一見不規則に動いているけど、長期的に見ると、何か規則性はありそう (春夏秋冬は変化するが、・・・去年・今年・来年・・・という長期展望に立つと同じような変化をくり返している) 6 めんどうなことにたまにアクシデントが起きる(警察射げき場のテロリストのような感じで) 7 しかし、アクシデントも危険そうなところで起きることが多いので、予測不能というわけでもない感じ 8 的を射る制限時間があって、射ることを拒否することはできない。3色のどこかを射らなければならない・ こんな感じで、人生や森羅万象の変化ってあるんじゃないかな?と、イメージしています。どうかなあ?
2010.03.26
コメント(0)
-
「時」に中る(あたる)・・・1
・ 易経で重んじられることは、「時」の変化を見取ること。・ 「時」には3つの要素がある 1 時 時間・期・タイミング・兆し 2 処 環境・状況・場 3 位 位置・立場・人間関係・社会的地位・ この3つの要素を見取って、即時即場で適切な判断、対応や出処進退が出来るのが君子(リーダー)の必須条件である・・・これを時に中る・・・時中(じちゅう)という・ 中庸の中も中るで時中と同じく。適当・真ん中・まあまあ・平均・漏れなく・・・ということではなくて、出るべき時は出る・・・強く、弱く・・・退くべき時は退く・・・徐々に、脱兎の如くに・・・というように変幻自在、融通無碍なる、ツボにはまった判断・行動を「中る」という。・ 組織の「春夏秋冬」がつかめない、状況把握ができない、自分の立場が分かっていない・・・この時処位のどの要素が欠けてもリーダー失格。・ しかし、リーダー役なのに・・・あんはん、どうなってるん?という疑問符のつく「リーダー」の多きことよ・・・自己利益だけだあ~の「利~駄あ~~」って人もいたり、よく分かっていない支離滅裂気味の「離~舵あ~~」って人もいたりと・・・
2010.03.25
コメント(0)
-

ユーハイムのチョコバームクーヘンとエスプレッソ珈琲と…
リーダーのための「易経」の読み方・ 今、書類作成中・・・締め切りは25日夕方まで・・・あと24時間少々(大学の卒論思い出すわあ・・・今の状況)・ 調子出なくなったんで、おやつタイム中・・・チョコのバームクーヘンは中々いいですわ・・・チョコ成分には「恋愛」と関連する物質が入っているそうな^-^だから恋に恋する乙女ってチョコ好き多いのだそうな。私は妖怪人間・猫又であって、乙女なオトメンではないが^-^(もっとも職場では、「あんたはオバメン」と言われているが^-^)・・・バターにはドーパーミンを放出させるような物質が入っていて・・・あっ・・・効いてきたわ、頭ん中スイッチ・オン!・ せっかくドーパーミン出てきたから、今日はこれまで!
2010.03.24
コメント(0)
-

疲れの正体は?
図解・病気を治す自然治癒力の高め方最近睡眠時間もずれ 疲れなかなかとれず・・・
2010.03.23
コメント(0)
-

40歳からの仕事術を読んで
40歳からの仕事術・ 「戦略」とは・・・目標達成のための有限な資源の最適配分・・・のこと・ 有限な資源とは体力・気力・時間・お金・注意力など・ 何をやるか・・・ではなく、何をやらないか。何を捨てるか。優先順位をつけて、お尻から(ゴール地点から)計画を考えて、仕事や勉強をしていかなければならない。・ 今・ここで・自分が・・・なすべきことを判断したら、あとは一心不乱に課題に切りかかるように集中することが肝心・・・時に中る「時中」・・・「中庸」(ツボにはまる)とは、決して真ん中で、平均的で、無難でよい!・・・というわけでなはい。
2010.03.22
コメント(0)
-

ピアノ発表会終了^^
・ 終わった~ほっとしました。出来は、自己最高に出来た練習と比べ、4割ですね・・・まあね。その10割つ~のも、「ひよこ組」レベルよりやや上くらいなんだけどね^^「が~ん」ときて、舞台上では3・5割かな?と感じたが、ビデオみたら4割くらいまでは付けてあげたいな・・・と率直に思いました。(註)師匠いわく。大抵の人は発表会では、自己最高の練習レベルの6~7割くらいになるそうな。緊張するからマイナスになる。ひよこ組たちは幼児なので緊張は少ない。だから、ひよこ組以上は1練習方法を工夫して、2練習の絶対量も増やして、という2つのアプローチが必要なのだ・・・とにかく練習での最高値を上げなさいと・・・そうすると・・・本日は落第ですわなあ^^・ 25年来、お世話になっているお寿司屋さん(71)が、この3月いっぱいで卒業(廃業)・・・今朝ピアノ弾きにでかける直前に、玄関先で出会ったら「3日くらい前に決めたんだけどさ・・・」「え!」・・・まあ、兆しは感じてたんだけど、残念というか、寂しい猫又です・・・この方がいるから、今日の私がいるというレベルの「人生のキーパーソン」のお一人であります。公私にわたってのお付き合いで、ある意味、「親」みたいな方。私にとって「参謀役」「後見人」な方。・ 早速、ピアノの打ち上げにその寿司屋さんへと出かけました。私にしては、珍しくお銚子(熱燗)1合・・・も、飲んでしまいました。夕方4時半から10時まで貸切になって、長居してしまった・・・24歳くらいの私の若かりし写真も発掘され、懐かしく・・・へえ~結構やせてたな(元々小太りなんだけど・・・おいおい、じゃ今は・・・^^)(註)元大酒呑みで25年前はこのお寿司屋さんで一人で一升瓶をというお馬鹿もしていました・・・引退してスイーツ男子(47)。今ではスイーツバイキングなんか普通に行ってます^^「砂糖中毒」「カフェイン中毒」です。・ 終わりっていうのは、誰にでも来るんだけど・・・寂しいです。・ いま北海道は札幌の一部地区を除き、シャッター通りです。札幌市内でもそういうシャッター通り地区があるんですがね・・・一体この国はあと10年経ったらどうなっているんでしょうかね?一体日本のもっていた資本はどこへ行ったんでしょうかねえ?私自身はアンチ唯物論派ですが、最近「マルクス」について、ちょっと勉強始めてみました。「資本論」はなんか難しいけど、ここらの本から読み出してみました。ナニワ金融道ゼニのカラクリがわかるマルクス経済学
2010.03.21
コメント(3)
-

上座部仏教との出会いから・・・3
法句経・ 上座部仏教は、日本における「道元禅」に似ているのだろうなあ・・・と、日頃から感じています。(曹洞宗・・・とではなくあえて「道元禅」と書かせていただきます。曹洞宗僧の方には申し訳ございませんが)・ 釈尊自身は経典を残してはおりません。キリストさまも聖書を書いてはおりません。これは文書化していないということ。弟子が編纂したものが後世に伝わったものが、現在印刷物として、我々が目にしている「経典」である。このことに、まず気が付くべきであると考えます・・・言行録、随問記ですわなあ。・ 釈尊ならばこんな時、どうされるだろうか?キリストさまならどうおっしゃるだろうか??と・・・想像力を働かせながら、自分の頭(顕在意識)で考え、心(潜在意識)で判断し、言葉や体で表現していく・・・そして、自分以外の全ての人・生き物・ものに評価してもらって、己を正していく・・・こういう作業が、実は本来の「宗教」なのかなあ?と、思えるようになってきました。・・・「生活禅」とでも名付けましょうか。・ ものづくりの仕事をされておられる方ならば、自分の仕事の良し悪しに対して、「もの」が応えてくれる感覚・・・分かっていると思います。材料など「もの」や、道具も、言葉を介さずに大いに語ってくれますね
2010.03.20
コメント(2)
-
上達って奴は・・・2
長い引用になって恐縮ですが、これ正に私が伝えたい「上達」についての正鵠を射る内容なので使わせていただきます。「高原現象」にあって大切なのは、よき師匠と出会うこと・・・そして、よき師匠の教えて下さることを素直にやり続けること・・・これに尽きますでしょう。「守破離」とは言いますものの、初心者特に年齢がいってからの初心者は、師匠の教えを素直に聞いて実行する「守」も段階がずっとずっと続くかもしれないけど、それしか方法はなさそうです。http://nedwlt.exblog.jp/8213125/NED-WLT 酒井穣のパーソナル・ブログ より引用直感では、技能(スキル)の習得というのは、学習の量に比例していると思われます。しかし現実の技能の習得に当たっては、学習する内容も方法も正しいのに、その効果が見られない状態におちいる期間ができるのが普通です。これを心理学では特に「プラトー現象」と言います。プラトー(Plateau)とは高原や高台のことなので、そのまま日本語で「高原現象」とも呼ばれます。このプラトー現象というのは、どこか「スランプ状態」と似ているように思われますが、スランプ状態というのは、通常は既に高いレベルにある技能者が本来の力を出せなくなるようなときのことを指すのに対して、プラトー現象というのは、これから力を付けようとしている成長過程にある人(特にビギナーを抜けつつあるレベル)に見られる現象のことであり、基本的にスランプとは似ていても異なるものです。プラトーにあるときは精神的には辛い期間にあたるものの、その後に続くさらなる飛躍の準備期間(土台の形成)として位置づけることができ、「歯を食いしばって超えるべき壁」という意味で理解するのがよいと思われます。何事においても、ちょっとした停滞を自らの成長限界としてしまうのは気が早いかもしれないということです。プラトー現象という言葉は、語学の修得や受験勉強などの文脈でよく登場するのですが、勉強という文脈にとらわれず、キャリア、宣伝効果やダイエットにも、これとよく似た現象が見られ、プラトーという言葉が使用されることがあります
2010.03.19
コメント(2)
-
上達ってやつは・・・
・ 上達ってやつは・・・不規則な幅と高さでできている階段のようなものだ・・・練習して毎日、練習した分だけ目に見えて上達できれば「励み」になるのに、そうはならない・・・練習しても上達しない・・・しかし練習しないと上達しない・・・寝不足しながら練習してやっと「あれ?なんか少しうまくなった??」と思う日が来る・・・しかしそれはいつか分からない・・・諦めて投げ出した翌日がそのポイント日であったのに・・・というような事って多いのかもしれない。「諦める一歩あとに上達があったりしてね」・ 21日地元のホール(700人収容)でピアノ発表会・・・小学生に混じって参加・・・キャサリン・ロリンのショパンのためのマズルカって曲を弾きます。簡単だけど、私にとっては難曲であります。・ キャサリンロリンについて(全音の資料より)キャサリン・ロリンは、アメリカの女性ピアノ教育者で、あのギロックの教え子であり、親友でありました。彼女は現在も、指導者として後進の育成に取り組んでいます。彼女の作品は数多くありますが、いずれも難易度は初級から初中級のものが中心で、ブルクミュラー25の練習曲と同程度とお考えください。中でも、特に親しまれている曲集は「ピアノの叙情詩」で、使われている音域(特に左手のアルペジオ)が広く、ペダルも必要条件となり、小学生の高学年~大人向けの作品となっています。女性の作曲家ならではの美しく、それでいてとっても親しみやすい曲ばかりです。特に大人の女性に人気がありますが、もちろん男性にも支持されています。とても美しい旋律でいて、比較的簡単に弾くことのできる『キャサリン・ロリン』の世界を貴方も体験してみませんか?!
2010.03.18
コメント(4)
-
上座部仏教との出会いから・・・2
・ なるほどと思ったことは「祈らない」或いは「祈り方が違う」ということ。・ 御利益を祈るのではなく、生きとし生けるもの全てに対して、「ありがとう」「いただきます」「しあわせになって下さい」という慈悲の心で祈る・・・これが上座部仏教の祈りに対する基本的な考え方・実践である・・・と解釈しています。
2010.03.17
コメント(0)
-

上座部仏教との出会い・・・1
仏教は心の科学・ 私淑するお一人・・・Aスマナサーラ長老(スリランカ上座部仏教)の著書はどれも読み応えがあります。・ 上座部仏教は、仏教徒は祈らない・・・という立場であります。そういう意味では、大乗仏教やキリスト・ユダヤ・イスラムなどと一線を画しております。信じるものは救われるという価値観の方々からすると、全く悪魔とも見えるでしょうか???私は道元禅と上座部仏教って結構にているかな?と感じております。・ お釈迦様のお開きになった仏教って、本来哲学・・・生命哲学だったのかもしれませんね。
2010.03.16
コメント(2)
-

マインドマップとの出会いから・・・4
ザ・マインドマップ・ この本の120~127ページにかけて、2つから1つを選ぶ意志決定法について書かれています。・ 読んでみて易占と通じるなあと感じます。占いというと適当、偶然みたいなイメージをもつのが一般的かと思います。・ 私は何か判断する場合、選択する場合でも、最終判断で悩んだ時は、結果的に「占う」しかないと思っています。選択肢Aでも選択肢Bでも5分5分だから、自分の頭では判断できない・・・つまりここまで分析して、悩んで、選ぶことができない・・・ということはどちらでもよい(或いはよくない)ということですから、コインでもなげてどちらか選べばいいわけです。・ その時、頭の中に浮かんだすべてのキーワードを全て速射法でマインドマップに書き出して、まずは今までの知識・経験をフル稼働させて、自分の頭で考え尽くすことが大切です。これは易占であっても同様で、卦から連想される単語・絵をイメージと連想で広げていって解釈するわけです。・ 大抵は描いて「見える化」した段階で、考えはまとまるので、マインドマップは「自分で考える易占」とも言える感じです。
2010.03.15
コメント(2)
-
マインドマップとの出会いから・・・3
・ 私がマインドマップを使っていて、「あ!これいけるな!」と感じている利用例は 1 TO DO メモ 2 日記 3 悩み解決「自問自答」 4 作品のデザイン 5 読書メモ 6 スピーチ原稿 ・・・ です。 1~6は順位ではありません・ 最近、やってみて新発見は、易とマインドマップってすごく相性がいいということに気が付きました。こうやって「見える化」しておくと、時の推移と易の結果とを、反省して分析し直すこともでき、中々勉強になります。・ 私にとっての「易経」観は、「当たるも八卦・・・」の占い本というだけではなく、変化の書、時の書・・・という視点からも、研究している・・・そういう立場です。・ 義理易というのかな・・・キーワードから現状に照らし合わせて、連想を広げていき、解釈をする・・・これをやってみると、ここがマインドマップと実に相性がいいんですねえということに気付いたわけです。カラーでいっぱい絵も描いていくので、楽しみながらできますよ。ついつい時間が経ってしまう。
2010.03.14
コメント(3)
-
マインドマップとの出会いから・・・2
・ 脳の中で、ものを考える時、例えば「りんご」・・・どう考えてますか?・ り・ん・ご・・・或いは林・檎と頭の中に、いきなり文字が出てくる方、中々いないでしょう。「いや、いや、普通に文字で考えていますよ。」という方いたら大したものです。・ 一般的には、絵しかもカラーで考えますよね。イメージ(心象)で。もう一つはアソシエーション(連想)です。りんごのイメージから、り・ん・ごや林檎という文字を連想したり、赤や緑、黄色を連想したり、アダムとイブを連想したりと、一人一人が様々な連想を広げていきます。しかも、文章では無く、絵と単語というイメージで、放射状に思考は広がっていき、また同時に収斂・収束されていく。・ その頭の中のデザインを、マインドマップをとおして「見える化」しているわけ。従来の方法に比べ、脳に対するストレスが小さく、考えることがとても楽しくなるツールです。
2010.03.13
コメント(0)
-

マインドマップの出会いから・・・1
勉強が楽しくなるノート術マインドマップが本当に使いこなせる本・ 2001~2年頃、発想を広げて・まとめる・・・そして関連付け連動させる方法として、マッピングの研究をしておりました。その時は「イメージマップ」という言い方で、付箋紙に思いついたことを書いて、放射状(くもの巣状)にして仮に貼り付け、全体が完成した段階で、貼り付けた位置を変えたり、書き加えたりしてポートフォリオをつくったもんでした。・ しかし、2年間そのプロジェクトに取り組んだ、時間・労力の割には「イメージマップ」法は効果的ではなく、定着も今一歩・・・手ごたえがなかったです。・ ところが、これは全くの偶然なんだけど、ネットサーフィン中「ドラゴン桜」から「マインドマップ」にたどり着きました。2008年1月のことでした・・・以来、広げて・まとめる(拡散・収束)思考がとても楽しく、苦にならなくなりました。「イメージマップ」とは似て非なるものであると思います。
2010.03.12
コメント(0)
-
城を頼る者は
・ 城を頼る者は、城を捨てられない。 (織田信長の言葉)・ 城に限ったことではなく、人間は頼りにするものや人、力を中々捨てることはできないんでしょうなあ・・・私もそういう人間ですわ。・・・執着ですわな。・ 城を、カミサン・親・子・人のふんどし・・・体力・気力・健康・・・腕力・暴力・・・金・借金・・・土地・家・家門・家名・・・名誉・地位・コネ・会社・・・学歴・知識・主義・主張・宗教・・・インターネット・携帯電話・・・と様々言い換えることが出来ます。これ、形違うけど、結局「欲」ですわ・・・広い意味での「欲」・・・「欲」は全部ワルモノじゃないからね。・ この欲をいかに自己コントロール(広い意味での「礼」「節」)していくべきか・・・生まれたら必ず死ぬんだけど、いい「生き様」・「死に様」ができるか・・・信長さんは身をもって、歴史の中で説法しているんでしょうなあ・・・南無
2010.03.11
コメント(0)
-
もし人間が・・・
・ もし、人間が未来永劫に生きられるとしたら、恋愛も勉強も、子供を産むこともいつでもいいとなってしまう。・ 人間は、死があるからこそ、生きている間に出来るだけ有意義にすごそうと努力するのだ。(青木雄二の言葉)
2010.03.10
コメント(0)
-

金も また ・・・ 哲学
青木雄二金言集 知人が本を整理・処分していた時、ごみ用ボール箱に落ちていた本。それまで、青木雄二はどうも苦手でしたが、この拾ってきた本をとおして、青木氏の発想や観察眼にとても共感できるようになった。因みに3月10日の言葉は・・・金は借りるもんやない。稼ぐもんや。これは基本の基本。
2010.03.09
コメント(0)
-
なかなか 疲れる
・ なかなか疲れています。・ 自分の頭の上の蝿を払うことはなかなかできない。しかし、人の頭の上の蝿なら十分払うことができる。だから、お互いもちつもたれつ・・・やさしく、協力し合って「払い合う」ことが、幸せへの第一歩なのではないかと思います。そこが即・極楽、そこが即・天国。・ われよし、人よし、みんなよし・・・Win-Win理論・・・近江商人の真髄
2010.03.08
コメント(0)
-
集中と多動
・ ドーパミンは、快感、意欲、興奮を増進させる脳内ホルモンですが、セロトニン(脳の活性化、心の安定をもたらす働きのある脳内ホルモン)が不足していると、ドーパミンの働きが押さえきれないのだそうです。(冬期になると日照時間が減って、セロトニンが不足しやすい環境に陥りがちです。)・ さて、セロトニンが出てこないと、脳内物質のバランスが取れなくなる。そこでその調整のために、体を動かす必要があるのだそうな。手っ取り早いのが、手遊びや貧乏ゆすり、きょろきょろする、体をさする・・・などの多動症状を起こす方法。武者震いっていうのもそうなのかなあ?動いているとセロトニンが段々出てくる。・ ですから、子どもの場合、「静かにしなさい。」と言って、無理矢理、椅子に縛り付けるが如くするのは逆効果である。積極的に動かした方がむしろ脳が活性化し、落ち着いて考えることができる。しかし、授業中自由に動かしておくわけには行かない。そこで座学だけでなく、間に例えばノート丸付けタイムを設けて、教室内を公然と歩いてもいい時間を挟み込む・・・多動症状が目立たなくなるような形態の「授業の工夫」をすればよい・・・そうな。逆転の発想ですわな。・ 古の哲学者・宗教家はみんな歩いて哲学したらしい。体を通して、理屈を超えて直感的に理解・体得してたんでしょうな。京都の「哲学の道」なんかいいですね。・ 大人の場合、子ども時代よりは多動症状は目立たないですが、それでもやはり、絶えずそわそわとした印象を与える方いますわ。貧乏ゆすりは幼少期の多動症状の生き残りみたいもんですな。・ 文武両道と言いますが、極端に「武(スポーツ)」の達人になる必要もないけれども、簡単な運動(歩く・縄跳び・ラジオ体操)、家内労働、日曜大工、ピアノ、書道など・・・体を動かす活動は、脳内物質のバランスをとって、脳の活性化を促すようです。日照時間の短くなる冬、セロトニンも不足するので、スキー&温泉・サウナなんていうのも、理にかなっていますわ。
2010.03.07
コメント(0)
-
どこに 心をおくべきや
・ 集中と散漫・・・その心の状態は、紙一重。・ 何かに集中すると、その見ているもの、聞いているもの、やっていることにのみ全神経が行ってしまう。勿論そういう状態は学ぶ時には大切。授業中、集中して聞かないと叱られますわな。フロー状態に入ると、ものすごい力を発揮することは、体験的に何度も学んでいます。締切日は魔力をもっていますね。追われるから、力が発揮できる。・ しかし。集中するということは、同時に、視野が狭くなるわけだ。すると、周りの状況が目に入らなくなる。これでは危険で自動車の運転はできない。前しか集中出来ないと、横や後ろ、時に上からの状況の変化に対応できない。・ ピアノなんかでも言えるかも。集中と散漫・・・正と負、陰と陽・・・変化して絶え間なきや・ 昔の剣豪や忍びの者たちが、一対多で切り結んだ際、一人で戦う者はどこに神経を置いたのだろうか???考えるとわくわくしますわな。
2010.03.06
コメント(0)
-
練習の時にあっても・・・
・ 今日、ピアノレッスン日であった。一人で練習していると、「おお。結構いけるかも。」と大いなる錯覚に浸れるのだが。先生がそばで聞いていると思うと、どこか一音ミスっただけで、もう・・・だめです・・・別に叱られるわけでもないのですがね。・先生いわく。一人で練習する時であっても、いつも誰かに見られているというイメージトレーニングが必要なのです。
2010.03.05
コメント(0)
-
一陽来復
・ その道を反復し、七日にして来復する(易経・・・地雷復)・ 物事には春夏秋冬のような陰陽の道を反復する法則と転換点が必ずある。その法則性を知り、目に見えない兆しを観る目を養おうとするのが易経である。・ 「易経」一日一言 人生の大則を知る 竹村亞希子 著 到知出版社 12月21日分より
2010.03.04
コメント(0)
-
三寒四温 兆しと萌し
・ 春分の日が過ぎて・・・3月3日にもなった・・・というのに、雪です。まあすぐに溶けてしまいますがね。・ いつも思うのですが、北海道では春分になったからと言って春は姿を現さない、夏至になったからとて夏は姿を現さない・・・不思議・・・北海道の地面と海があったまるまで1ヶ月くらいかかるのかなあ?・ 最近、知ったこと。目に見えないけど変化が始まった・・・これが兆し、それがほんのちょっと。土のスキマから出てくるか来ないか・・・土が盛り上がっているかな?くらいの変化の始まりを萌しと書くのだそうな。
2010.03.03
コメント(0)
-

易経について学ぶ
易経に出会って18年くらい経つのですが、中々難解でちょっと放っておいたのですが、最近いい本に出会いました。おかげで非常にすっきりした形で、頭が整理されてきました。勿論、深遠ですから一生ものではありますが。「易経」一日一言
2010.03.02
コメント(0)
-
面白き・・・
面白き ことも無き世を 面白く 高杉晋作の辞世の句 全くその通りで…日々の心のもち方にこそ、生きる楽しみを見出す鍵があるものですね。
2010.03.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1