2025年11月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
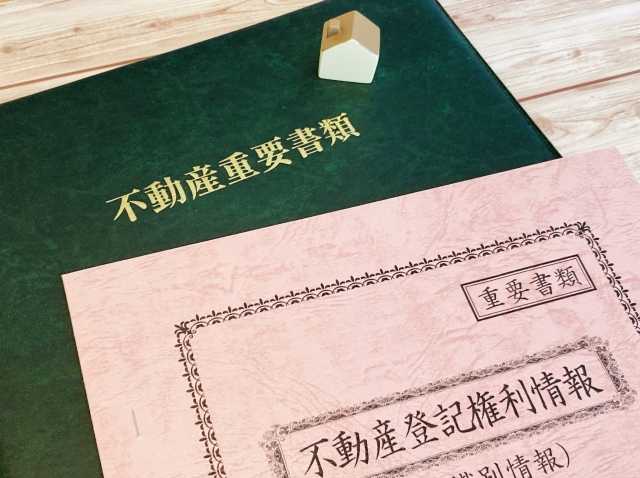
マイホーム購入時、夫婦で共有?お得?
マイホームの名義、どうしていますでしょうか?夫婦で共有名義にするとお得って聞いた事ある方もおられるかもしれません。今回は、FPとしてマイホーム購入時夫婦共有名義のメリット・デメリットについて簡単にお話したいと思います。 夫婦共有名義にする最大のメリットは、税金の控除額が増える事です。夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での節税効果が期待できます。また、将来家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例を夫婦それぞれが利用でき、最大6,000万円まで控除可能です。もう一つのメリットは、高額なローンが組める事です。夫婦の収入を合算して審査を受けることで、一人でローンを組むより借入可能額を増やせる場合があります。逆にデメリットとしては、手続きが煩雑になる事があげられます。不動産の売却や大きなリフォームには、共有者全員の同意が必要です。それぞれ同意文書の作成など手続きが増えます。また、関係変化した場合のリスクもあります。離婚時には財産分与でトラブルになりやすく、どちらかが亡くなった際の相続関係も複雑化する可能性があります。あと、登記費用などが単独名義の場合より多くかかることがあります。 さて、今回はマイホーム購入時に夫婦で共有名義にするメリット・デメリットについてお話しました。税金の控除や住宅ローンの借入額で利点がある一方、手続きの煩雑さや将来的な関係悪化の際に問題が生じる可能性があるんですねぇちなみに、出資額に応じた持分で登記しないと、贈与税が発生する可能性もあります。例えば、夫の方が多く出資しているのに、半分ずつの登記だと、差額は贈与とみなされる為、贈与税が発生するって訳です。夫婦それぞれの収入や購入するマイホームの金額など総合的に考えて選択しましょう。
2025.11.15
コメント(0)
-
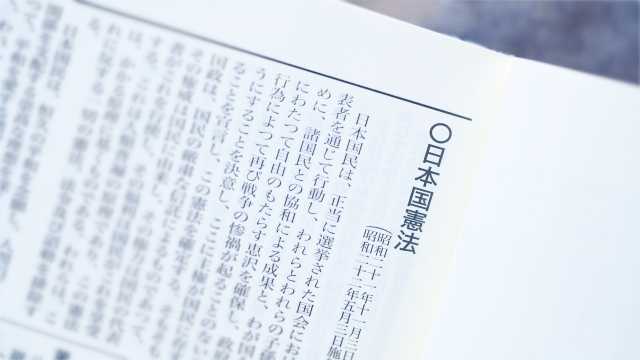
公共の福祉?具体的には?
前回、憲法中の「公共の福祉」について記事を書きました。今回は、「公共の福祉」の具体例について簡単にお話したいと思います。 公共の福祉とは、簡単に言うと「個人が持つ権利を、社会全体の利益や他者の権利を侵害しない範囲で認める」という考え方です。個人の自由や権利が尊重されるべきですが、それが他人や社会全体に迷惑をかける場合には、一定の制限が加えられることがあります。「表現の自由の制限」例としては、他者を誹謗中傷したり、デマを拡散する発言は規制されることがあります。これは表現の自由が、他者の名誉やプライバシーを侵害する場合には制限されるためです。また「プライバシーの権利の制限」例としては、犯罪防止のために設置される防犯カメラは、個人のプライバシーと社会の安全を維持するという目的のバランスを考慮して運用されています。そして「喫煙の自由の制限」例としては、「喫煙の自由」と「嫌煙権」のように、異なる個人の権利が衝突する場合に、公共の福祉によって喫煙が制限されることがあります。 さて、今回は「公共の福祉」の具体例をお話しました。公共の福祉は、私たちの日常生活から社会の仕組みまで、さまざまな場面で個人の権利と社会全体の利益のバランスを取るために用いられているんですね~。ちなみに、公務員のストライキ権の制限(公務員は原則ストライキ権ありません)も「公共の福祉」の一つと考えられています。火事になった時、消防士が「自分ら今、ストライキ中です」とか言われたら困っちゃいますもんね。
2025.11.09
コメント(0)
-
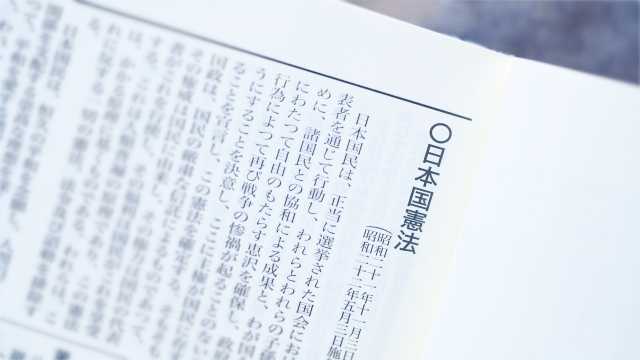
憲法にある公共の福祉って、何?
明日は、年に一度の行政書士試験です。私も受験の際に「憲法」を勉強しました。皆さん、日本国憲法、読まれた事ありますでしょうか?その中に「公共の福祉」という言葉があります。今回は、憲法中の「公共の福祉」について簡単にお話したいと思います。 「公共の福祉」とは、主に日本国憲法において、基本的人権を制約する根拠として用いられる概念です。憲法12条、13条、22条、29条にこの言葉が明記されており、人権は無制限ではなく、一定の制約を受けることを示しています。憲法第12条では、保障する自由と権利は、国民の努力によって保持されるべきものであり、濫用せず、常に「公共の福祉」のために利用する責任があるとしています。第13条では、すべての国民は個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は、「公共の福祉」に反しない限り、最大限尊重されると規定されています。これは、「他人に迷惑をかけない限り」において人権が尊重されることを意味するとも解釈できます。第22条では、「公共の福祉」に反しない限りで、居住、移転、職業選択の自由が保障され、外国移住や国籍離脱の自由も侵されないとされています。第29条では財産権は不可侵であるとする一方で、その内容は「公共の福祉」に適合するように法律で定められ、公共のために用いることができると規定されています。 さて、今回は日本国憲法にある「公共の福祉」についてお話しました。人は皆、自由なんだけど、それは「公共の福祉」に反しない限り(みんなのため、周りに迷惑をかけてはいけない)って事なんですね。ちなみに、「公共の福祉」って言葉は日本国憲法から登場しています。大日本帝国憲法では、「法律の留保」という形で権利の制限をされていました。法律の留保=法律の範囲内でって意味です。
2025.11.08
コメント(0)
-

NISAやiDeCo?どうやってやると?
前回、老後資金の準備でNISAやiDeCoが良かよって記事を書きました。今回は、FPとしてNISAやiDeCoのやり方について簡単にお話したいと思います。 NISAやiDeCoを活用した資産運用の手順は、以下のステップで進めるのが基本です。まず、証券会社や銀行でNISAまたはiDeCoの専用口座を開設します。口座開設は、手数料が安く、取扱商品が豊富なネット証券が良いと思います。次に、毎月いくら積み立てるかを決めます。NISAは年間投資枠、iDeCoは所得に応じた掛金の上限額の範囲内で、無理のない金額を設定しましょう。続いて、投資する商品を選びます。初心者の方には、世界中の株式などに幅広く分散投資できる低コストの「インデックスファンド(投資信託)」がおすすめです。全世界株式(オールカントリー)や米国株式(S&P500)に連動するものが代表的です。商品と金額を決めたら、自動で毎月買い付ける「積立設定」を行います。一度設定すれば、あとは基本的に放置プレイで構いません。短期的な価格の変動に一喜一憂せず、長期的な視点でコツコツと資産を育てていく「長期・積立・分散」が成功の鍵となります。 さて、今回はNISAやiDeCoのやり方についてお話しました。投資はギャンブルではありませんので、相場が上がった下がったで売り買いをしません(←これやるとギャンブル)。一定額をコツコツ積立てましょう。ちなみに証券会社の選択については、過去の記事にも書きましたが、「SBI証券」か「楽天証券」がお勧めです。特に初心者の方には、操作方法や画面の見やすい「楽天証券」を紹介しています。ご自身の環境に応じて選択ください。
2025.11.03
コメント(0)
-

老後資金の準備、どうすればいいと?
人間いつまで働けるか分かりません。老後資金の準備されていますでしょうか?今回は、FPとして老後資金の準備について簡単にお話したいと思います。 老後資金の準備で最も大切なのは、まずご自身の「ものさし」で必要な金額を把握することです。一般的に「2,000万円必要」などと言われますが、これはあくまで平均的なモデルケースに過ぎません。具体的には、まず「ねんきん定期便」などで将来の公的年金受給見込み額を確認します。次に、ご自身が送りたい老後の生活をイメージし、毎月の生活費を予測します。この「予測支出」から「年金収入」を引いた不足額に、老後年数(例:25年~30年)を掛け合わせたものが、ご自身で準備すべき目標額の目安となります。準備方法としては、税制優遇が大きなメリットとなる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や新NISA(少額投資非課税制度)の活用が基本です。これらを利用し、「長期・積立・分散」を意識して、投資信託などでコツコツと資産を育てていくのが効率的です。ご自身の年齢やリスク許容度によって最適な方法は異なりますので、まずは現状把握から始め、早めに計画を立てて実行に移すことが重要です。 さて、今回は老後資金の準備についてお話しました。備えあれば憂い無し、安心した老後を迎える為にも準備が必要ですね。ちなみに、老後準備の資産運用、当たり前ですが若ければ若い程有効です。投資は長期になればなる程、複利の力が働き、利益が増大しリスクが減少するからです。
2025.11.02
コメント(0)
-

保険の見直し?どうやってすると?
保険の見直しされていますでしょうか?今回は、FPとして、生命保険や医療保険の見直しについて簡単にお話したいと思います。 生命保険や医療保険の見直しと最適化は、ライフステージの変化に合わせて行うのが基本です。具体的には以下の手順で進めます。まず、現在加入している保険の「保障内容」「保険期間」「保険料」を保険証券で正確に把握します。次に、今の自分や家族にとって本当に必要な保障額(必要保障額)を計算します。これは、万が一の際に必要となる生活費や教育費などの総支出から、遺族年金などの公的保障や貯蓄を差し引いて算出します。現状の保障内容と算出した必要保障額を比較し、保障が不足していれば増額や新たな保険への加入を検討し、逆に過剰であれば減額や解約を考えます。例えば、子どもが独立すれば大きな死亡保障は不要になる一方、自身の医療や介護への備えは手厚くする必要があるかもしれません。医療の進歩により入院日数が短期化しているため、日帰り入院や通院を保障するかも重要な確認点です。最終的に、保障内容と無理なく支払える保険料のバランスを考え、複数の保険商品を比較検討して最適なプランを選びましょう。 さて今回は、生命保険や医療保険の見直しについてお話しました。今の自分の状況に応じてどの保険がどのくらいの保証必要かを考え、最適化しましょう。ちなみに、相談する人は、保険会社や代理店でも良いですが、幅広い選択肢から中立的なアドバイスが欲しい場合や、家計全体を見てほしい場合はファイナンシャルプランナー(FP)をお勧めします。
2025.11.01
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 株主優待コレクション
- ペコちゃんのツインほっぺを購入しま…
- (2025-11-16 00:00:05)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 大阪万博は黒字ではない赤字です!運…
- (2025-11-16 07:29:59)
-






