全264件 (264件中 1-50件目)
-

【セコムパスポートfor G-ID行政書士電子証明書の更新方法】
※今回の記事は、行政書士の先生向けの内容となっております 当事務所では、セコムパスポートfor G-ID行政書士電子証明書を使ってPDFファイルに電子署名を行っています。(電子定款・契約書等)今回、証明書の期限が来た為、更新手続きを行いました。その際の作業について、私自身の備忘録としてココに残します。もし、更新手続きでお困りの先生がおられましたら、参考にして頂ければ幸いです。なお、新規の設定に関しては、2024年2月22日の記事にて記載しておりますので、併せてご参照ください。 SignedPDF署名機能の環境設定を更新1.上部のメニューから「プラグイン」→上の「%menu%の場合」→「SignedPDF…」をクリック (説明書と違う+バグなのか「%menu%の場合」が2つあり上を選択)2.環境設定の画面「署名用鍵管理」の「証明書ストア」をチェック(たぶんチェックされてます)3.その下の「パスワード変更」をクリック4.パスワード変更画面で、新旧パスワード枠を入力(PINコードの事、新旧それぞれのPINコードを入力)してOKをクリック5.その下の「証明書ストア管理ツール」をクリック6.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「初期化」を選択7.その下の「パスワード」にPINコードを入力してOKをクリック8.「証明書ストアを初期化しますか。」とメッセージが出るので「はい」をクリック9.「証明書ストア管理ツール ログイン」画面のメニューで「参照」を選択10.「パスワード」に(新しい)PINコードを入力してOKをクリック11.「証明書ストア管理ツール」画面の「証明書情報」の「追加」をクリック12.「証明書インストール」の「参照」で証明書ファイル(cert.p12)を選択13.「追加する証明書のパスワード」でPINコードを入力、「インストール」をクリック これで更新完了し、電子署名できるようになるはずです。私の場合、「PDF印影情報」は触らず、前のままの自身の職印画像で署名ができました。
2025.11.29
コメント(0)
-

相続不動産の分割方法?どんなんあると?
相続で不動産がある場合、どのように相続人の間で分ければよいのでしょうか?今回は、相続不動産の分割方法について簡単にお話したいと思います。 まず、「現物分割」があります。これは、相続人の中から特定の人が不動産をそのまま相続する方法です。 現金や預金など他の遺産と組み合わせて、相続分を調整することが一般的です。ただし、不動産は現金のように均等に分けるのが難しいため、公平性に欠ける場合があります。土地の場合、分筆して物理的に分割することも可能ですが、建物は分筆できないため、注意が必要です。次に「代償分割」。これは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、その不動産を相続しない他の相続人に対して、自身の財産から金銭(代償金)を支払って調整する方法です。特に、相続人の一人が不動産に住み続けたい場合に有効な方法です。ただし、代償金を支払う相続人にはまとまった資金が必要となります。次に「共有分割」。これは、不動産を売却したり分けるのではなく、相続人全員の共有名義にする方法です。各相続人が持分を分け合って所有します。この方法は公平に見えますが、将来的に不動産の売却や管理などで全員の合意が必要となるため、トラブルの原因になることがあります。最後に「換価分割」。これは、不動産を売却し、その売却代金を相続人全員で分け合う方法です。現金を分けるため、公平性が高く、相続人間のトラブルになりにくいのが大きなメリットです。誰も利用しない不動産を分割する際に適しています。 さて、今回は相続不動産の分割方法についてお話しました。分割方法はいくつかありますが、状況に応じて選択する事になります。ちなみに、「等価分割」を選択する場合、売却前に故人から相続人への名義変更(相続登記)が必要になります。売却代金を分け合うにもかかわらず、売却の手間を省く目的で便宜的に相続人代表者の単独名義に相続登記することは、原則として認められません。また、換価分割には譲渡所得税がかかるため、予め専門家に相談する事をお勧めします。
2025.11.24
コメント(0)
-

相続不動産、評価方法の対立?
不動産の評価方法、いくつかある事ご存知でしょうか?相続の際、不動産の評価方法でもめる事もあります。今回は、相続不動産の評価方法について簡単にお話したいと思います。 遺産分割において、不動産の評価方法をめぐり相続人間で意見が対立することは少なくありません。誰が不動産を相続し、他の相続人にいくら支払うか(代償分割)を決める際、この評価額が直接影響するためです。例えば、長男と次男が実家を相続するケースを考えます。長男はそのまま実家に住み続けたいと希望し、次男は法定相続分に相当する現金(代償金)を求めました。ここで対立が生まれます。長男は、支払う代償金を抑えるため、固定資産税評価額や路線価といった比較的低い「相続税評価額」を基準にすべきだと主張します。一方、次男は、実際に売却した場合の価値に近い「時価(実勢価格)」で評価し、より多くの代償金を受け取るべきだと主張します。この評価額の差が、兄弟間の深刻なトラブルに発展するのです。この問題を解決するには、まず第三者の専門家である不動産鑑定士に鑑定を依頼し、客観的な時価を算出することが有効です。鑑定評価額は公平な基準となり、当事者双方の合意形成を助けます。また、複数の不動産会社から査定を取り、その平均額を参考にすることも一つの方法です。 さて、今回は相続不動産の評価方法についてお話しました。相続人それぞれの利害関係で主張が異なってきます。場合によっては、専門家など第三者を交えて話し合う事も必要かもですね。ちなみに、話合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では中立な調停委員が間に入り、最終的には審判で裁判官が評価方法を決定します。感情的な対立を避け、客観的な指標をもとに冷静に話し合うことが重要ですね。
2025.11.23
コメント(0)
-

相続不動産の意見対立、どうすればいいと?
相続財産の中に不動産があるってケース多いですよね。その際、相続人の間で意見の対立があるとどうしたら良いでしょう。今回は、相続不動産の意見対立について簡単にお話したいと思います。 不動産の売却では、現金化を急ぎたい側と、思い出の家を売りたくない側とで意見が対立し、トラブルに発展することがあります。特に、親から相続した実家をめぐり、兄弟間で意見が割れるのは典型的な例です。一方は固定資産税などの負担から早く売却したいと考え、もう一方は親との思い出が詰まった家を手放したくないと感じることで、対立が深刻化します。このような問題を解決するには、いくつかの方法が考えられます。まず、代償分割という方法があります。これは、売却に反対する側が、売却したい側の持ち分を現金で買い取るものです。これにより、家を残したい側の希望を叶えつつ、売却したい側は現金を得ることができます。次に、すぐに売却せず賃貸に出すという選択肢もあります。家賃収入を分配することで、目先の現金化ニーズに応えながら、将来的に売却のタイミングを改めて検討する時間的猶予が生まれます。また、リースバックという手法も有効です。これは、不動産を一度売却して現金を得た後、買主と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法です。ただし、売却価格が市場価格より低くなる可能性や、家賃が発生する点には注意が必要です。 さて今回は、相続不動産の意見対立についてお話しました。いずれの方法をとるにせよ、感情的な対立を避け、弁護士など第三者の専門家を交えて冷静に話し合うことが、双方が納得できる着地点を見つけるための鍵となります。ちなみに、この様な不動産トラブルを含めて相続が発生してからでは解決の難易度が上がります。そうならない様に、早めに準備する事をお勧めします。
2025.11.22
コメント(0)
-

不動産共有の場合、相続するとどうなると?
前回、マイホームの夫婦共有についてお話しました。では、その共有名義の不動産、相続の時どうなるのでしょうか?今回は、共有不動産の相続について簡単にお話したいと思います。 不動産が夫婦で共有名義の場合、一方が亡くなった際の相続は、亡くなった方の持分のみが対象となります。例えば、夫婦で2分の1ずつの持分であれば、亡くなった夫の2分の1の持分が相続財産となり、妻が所有する残りの2分の1は対象外です。相続が発生すると、まず遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合は、生存している配偶者や子などの法定相続人全員で遺産分割協議を行い、亡くなった方の持分を誰がどの割合で相続するかを決定します。協議がまとまると、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。その後、法務局で不動産の持分を新しい所有者に移す「相続登記」の手続きを行うことで、名義変更が完了します。 さて今回は、共有不動産の相続についてお話しました。共有名義の不動産を相続する場合、生存している配偶者が自動的に亡くなった方の持分を全て相続できるわけではないんですね~。ちなみに、遺産分割協議の結果、他の相続人(例えば子など)が持分を相続するなどした場合、不動産の共有者が増え、将来的に売却やリフォームなどを行う際に、共有者全員の同意が必要となり、手続きが複雑化するリスクがあります。このような事態を避けるため、生前に遺言書を作成しておくなどの対策が考えられます。
2025.11.16
コメント(0)
-
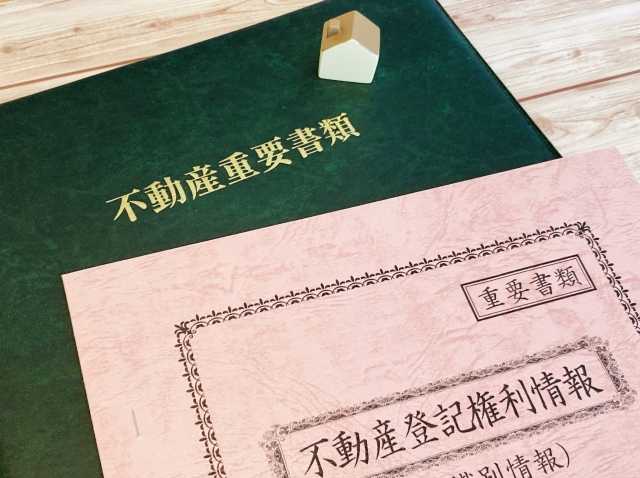
マイホーム購入時、夫婦で共有?お得?
マイホームの名義、どうしていますでしょうか?夫婦で共有名義にするとお得って聞いた事ある方もおられるかもしれません。今回は、FPとしてマイホーム購入時夫婦共有名義のメリット・デメリットについて簡単にお話したいと思います。 夫婦共有名義にする最大のメリットは、税金の控除額が増える事です。夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での節税効果が期待できます。また、将来家を売却する際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例を夫婦それぞれが利用でき、最大6,000万円まで控除可能です。もう一つのメリットは、高額なローンが組める事です。夫婦の収入を合算して審査を受けることで、一人でローンを組むより借入可能額を増やせる場合があります。逆にデメリットとしては、手続きが煩雑になる事があげられます。不動産の売却や大きなリフォームには、共有者全員の同意が必要です。それぞれ同意文書の作成など手続きが増えます。また、関係変化した場合のリスクもあります。離婚時には財産分与でトラブルになりやすく、どちらかが亡くなった際の相続関係も複雑化する可能性があります。あと、登記費用などが単独名義の場合より多くかかることがあります。 さて、今回はマイホーム購入時に夫婦で共有名義にするメリット・デメリットについてお話しました。税金の控除や住宅ローンの借入額で利点がある一方、手続きの煩雑さや将来的な関係悪化の際に問題が生じる可能性があるんですねぇちなみに、出資額に応じた持分で登記しないと、贈与税が発生する可能性もあります。例えば、夫の方が多く出資しているのに、半分ずつの登記だと、差額は贈与とみなされる為、贈与税が発生するって訳です。夫婦それぞれの収入や購入するマイホームの金額など総合的に考えて選択しましょう。
2025.11.15
コメント(0)
-
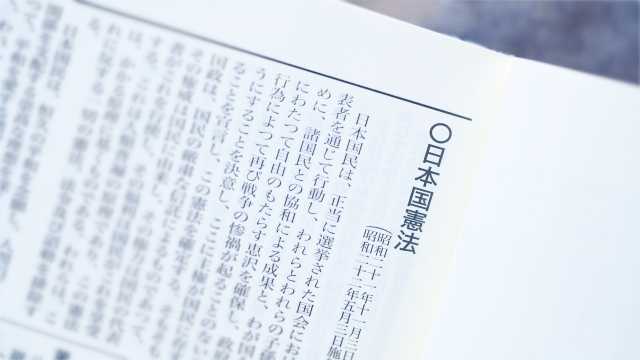
公共の福祉?具体的には?
前回、憲法中の「公共の福祉」について記事を書きました。今回は、「公共の福祉」の具体例について簡単にお話したいと思います。 公共の福祉とは、簡単に言うと「個人が持つ権利を、社会全体の利益や他者の権利を侵害しない範囲で認める」という考え方です。個人の自由や権利が尊重されるべきですが、それが他人や社会全体に迷惑をかける場合には、一定の制限が加えられることがあります。「表現の自由の制限」例としては、他者を誹謗中傷したり、デマを拡散する発言は規制されることがあります。これは表現の自由が、他者の名誉やプライバシーを侵害する場合には制限されるためです。また「プライバシーの権利の制限」例としては、犯罪防止のために設置される防犯カメラは、個人のプライバシーと社会の安全を維持するという目的のバランスを考慮して運用されています。そして「喫煙の自由の制限」例としては、「喫煙の自由」と「嫌煙権」のように、異なる個人の権利が衝突する場合に、公共の福祉によって喫煙が制限されることがあります。 さて、今回は「公共の福祉」の具体例をお話しました。公共の福祉は、私たちの日常生活から社会の仕組みまで、さまざまな場面で個人の権利と社会全体の利益のバランスを取るために用いられているんですね~。ちなみに、公務員のストライキ権の制限(公務員は原則ストライキ権ありません)も「公共の福祉」の一つと考えられています。火事になった時、消防士が「自分ら今、ストライキ中です」とか言われたら困っちゃいますもんね。
2025.11.09
コメント(0)
-
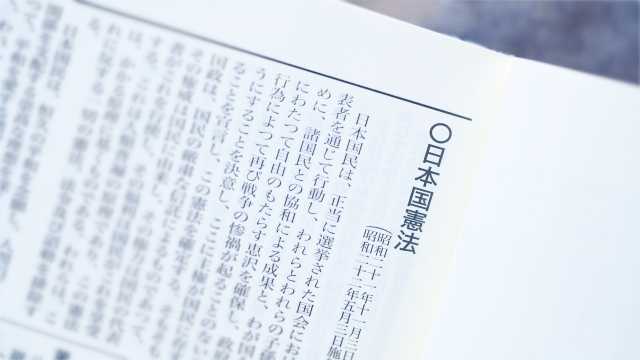
憲法にある公共の福祉って、何?
明日は、年に一度の行政書士試験です。私も受験の際に「憲法」を勉強しました。皆さん、日本国憲法、読まれた事ありますでしょうか?その中に「公共の福祉」という言葉があります。今回は、憲法中の「公共の福祉」について簡単にお話したいと思います。 「公共の福祉」とは、主に日本国憲法において、基本的人権を制約する根拠として用いられる概念です。憲法12条、13条、22条、29条にこの言葉が明記されており、人権は無制限ではなく、一定の制約を受けることを示しています。憲法第12条では、保障する自由と権利は、国民の努力によって保持されるべきものであり、濫用せず、常に「公共の福祉」のために利用する責任があるとしています。第13条では、すべての国民は個人として尊重され、生命、自由、幸福追求の権利は、「公共の福祉」に反しない限り、最大限尊重されると規定されています。これは、「他人に迷惑をかけない限り」において人権が尊重されることを意味するとも解釈できます。第22条では、「公共の福祉」に反しない限りで、居住、移転、職業選択の自由が保障され、外国移住や国籍離脱の自由も侵されないとされています。第29条では財産権は不可侵であるとする一方で、その内容は「公共の福祉」に適合するように法律で定められ、公共のために用いることができると規定されています。 さて、今回は日本国憲法にある「公共の福祉」についてお話しました。人は皆、自由なんだけど、それは「公共の福祉」に反しない限り(みんなのため、周りに迷惑をかけてはいけない)って事なんですね。ちなみに、「公共の福祉」って言葉は日本国憲法から登場しています。大日本帝国憲法では、「法律の留保」という形で権利の制限をされていました。法律の留保=法律の範囲内でって意味です。
2025.11.08
コメント(0)
-

NISAやiDeCo?どうやってやると?
前回、老後資金の準備でNISAやiDeCoが良かよって記事を書きました。今回は、FPとしてNISAやiDeCoのやり方について簡単にお話したいと思います。 NISAやiDeCoを活用した資産運用の手順は、以下のステップで進めるのが基本です。まず、証券会社や銀行でNISAまたはiDeCoの専用口座を開設します。口座開設は、手数料が安く、取扱商品が豊富なネット証券が良いと思います。次に、毎月いくら積み立てるかを決めます。NISAは年間投資枠、iDeCoは所得に応じた掛金の上限額の範囲内で、無理のない金額を設定しましょう。続いて、投資する商品を選びます。初心者の方には、世界中の株式などに幅広く分散投資できる低コストの「インデックスファンド(投資信託)」がおすすめです。全世界株式(オールカントリー)や米国株式(S&P500)に連動するものが代表的です。商品と金額を決めたら、自動で毎月買い付ける「積立設定」を行います。一度設定すれば、あとは基本的に放置プレイで構いません。短期的な価格の変動に一喜一憂せず、長期的な視点でコツコツと資産を育てていく「長期・積立・分散」が成功の鍵となります。 さて、今回はNISAやiDeCoのやり方についてお話しました。投資はギャンブルではありませんので、相場が上がった下がったで売り買いをしません(←これやるとギャンブル)。一定額をコツコツ積立てましょう。ちなみに証券会社の選択については、過去の記事にも書きましたが、「SBI証券」か「楽天証券」がお勧めです。特に初心者の方には、操作方法や画面の見やすい「楽天証券」を紹介しています。ご自身の環境に応じて選択ください。
2025.11.03
コメント(0)
-

老後資金の準備、どうすればいいと?
人間いつまで働けるか分かりません。老後資金の準備されていますでしょうか?今回は、FPとして老後資金の準備について簡単にお話したいと思います。 老後資金の準備で最も大切なのは、まずご自身の「ものさし」で必要な金額を把握することです。一般的に「2,000万円必要」などと言われますが、これはあくまで平均的なモデルケースに過ぎません。具体的には、まず「ねんきん定期便」などで将来の公的年金受給見込み額を確認します。次に、ご自身が送りたい老後の生活をイメージし、毎月の生活費を予測します。この「予測支出」から「年金収入」を引いた不足額に、老後年数(例:25年~30年)を掛け合わせたものが、ご自身で準備すべき目標額の目安となります。準備方法としては、税制優遇が大きなメリットとなる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や新NISA(少額投資非課税制度)の活用が基本です。これらを利用し、「長期・積立・分散」を意識して、投資信託などでコツコツと資産を育てていくのが効率的です。ご自身の年齢やリスク許容度によって最適な方法は異なりますので、まずは現状把握から始め、早めに計画を立てて実行に移すことが重要です。 さて、今回は老後資金の準備についてお話しました。備えあれば憂い無し、安心した老後を迎える為にも準備が必要ですね。ちなみに、老後準備の資産運用、当たり前ですが若ければ若い程有効です。投資は長期になればなる程、複利の力が働き、利益が増大しリスクが減少するからです。
2025.11.02
コメント(0)
-

保険の見直し?どうやってすると?
保険の見直しされていますでしょうか?今回は、FPとして、生命保険や医療保険の見直しについて簡単にお話したいと思います。 生命保険や医療保険の見直しと最適化は、ライフステージの変化に合わせて行うのが基本です。具体的には以下の手順で進めます。まず、現在加入している保険の「保障内容」「保険期間」「保険料」を保険証券で正確に把握します。次に、今の自分や家族にとって本当に必要な保障額(必要保障額)を計算します。これは、万が一の際に必要となる生活費や教育費などの総支出から、遺族年金などの公的保障や貯蓄を差し引いて算出します。現状の保障内容と算出した必要保障額を比較し、保障が不足していれば増額や新たな保険への加入を検討し、逆に過剰であれば減額や解約を考えます。例えば、子どもが独立すれば大きな死亡保障は不要になる一方、自身の医療や介護への備えは手厚くする必要があるかもしれません。医療の進歩により入院日数が短期化しているため、日帰り入院や通院を保障するかも重要な確認点です。最終的に、保障内容と無理なく支払える保険料のバランスを考え、複数の保険商品を比較検討して最適なプランを選びましょう。 さて今回は、生命保険や医療保険の見直しについてお話しました。今の自分の状況に応じてどの保険がどのくらいの保証必要かを考え、最適化しましょう。ちなみに、相談する人は、保険会社や代理店でも良いですが、幅広い選択肢から中立的なアドバイスが欲しい場合や、家計全体を見てほしい場合はファイナンシャルプランナー(FP)をお勧めします。
2025.11.01
コメント(0)
-

親が亡くなり、1人に相続させるって遺言書!どうすればいいと?
故人の意思を実現させる遺言書。認知症では無い場合、その遺言書は有効となります。そんな遺言書に「特定の1人に全財産相続させる」ってあったらどうすれば良いでしょう?今回は、そんなケースについて簡単にお話したいと思います。 特定の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言書が出てきた場合でも、他の相続人が遺産を全く受け取れないわけではありません。兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)には、法律で保障された最低限の遺産の取り分である「遺留分」があります。遺留分を侵害されている相続人は、多くの遺産を受け取った人に対し、侵害された額に相当する金銭を請求することができます(遺留分侵害額請求)。例えば、相続人が配偶者と長男、次男の3人で、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとします。この場合、配偶者と次男の遺留分が侵害されています。 ・法定相続分: 配偶者1/2、長男1/4、次男1/4 ・遺留分: 配偶者1/4、長男1/8、次男1/8つまり、配偶者と次男は、自身の遺留分(それぞれ総遺産の1/4と1/8)に相当する金額を長男に請求することができるとです。まずは当事者間で話し合い、解決しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停でも合意できなければ、地方裁判所で訴訟を起こすことになり調停でも合意できなければ、地方裁判所で訴訟を起こすことになります。 さて、今回は、特定の1人に全財産相続させるって内容の遺言書が出てきたケースについてお話しました。他の相続人には、「遺留分侵害額請求権」があるので、後々争いにならない様に、遺留分を考慮した遺言書の内容にしないといけないですね。ちなみに、「遺留分侵害額請求権」は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年(もしくは相続開始から10年)で時効となるため、注意が必要です。
2025.10.26
コメント(0)
-
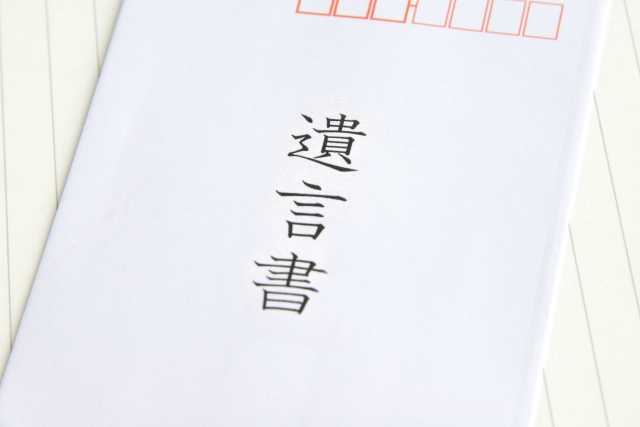
認知症の親が亡くなり、遺言書が出てきた!どうしたらいいと?
認知症だった親が亡くなり、遺品整理してたら遺言書が出てきたってケース。無くはないですよね?今回は、そんな場合どうしたら良いかについて簡単にお話したいと思います。 遺言者が認知症だった場合、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。重要なのは、遺言書作成時に遺言者に「遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)」があったかどうかです。まず、相続人全員で遺言書の有効性について話し合います。全員が遺言を無効とすることに合意すれば、遺産分割協議によって財産の分け方を決めることができます。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。ここでも合意に至らなければ、「遺言無効確認訴訟」を地方裁判所に提起し、裁判所に法的な判断を仰ぐことになります。無効と判断されやすい例として、遺言書作成時の診断書で重度の認知症と診断され、長谷川式認知症スケールなどの点数が極めて低く、ほとんど交流のなかった第三者に全財産を譲るなど不自然な内容の場合などがあります。逆に、有効と判断されやすい例として、認知症の症状が軽度で、長年連れ添った配偶者や介護をしてくれた子に財産を多く残すといった、合理的で単純な内容の場合などがあります。 さて、今回は認知症の親が亡くなった後、遺言書が出てきたケースについてお話しました。相続人全員の意見がまとまらない場合、最終的には裁判になっちゃいます。裁判では、医師の診断書や介護記録、遺言内容の合理性などが総合的に考慮されるんですね。ちなみに、争いになる場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。紛争性のある案件は、弁護士の独占業務となるからです。
2025.10.25
コメント(0)
-
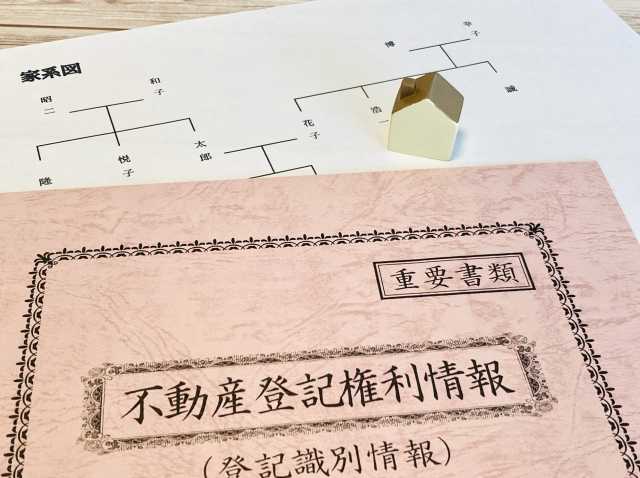
相続登記、具体的にどうやると?
前回、相続登記について記事を書きました。今回は、相続登記の具体的な手続きの流れについて簡単にお話したいと思います。 まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集して相続人を確定させます。同時に、対象不動産の登記事項証明書と、登録免許税の計算に必要となる固定資産評価証明書を取得します。相続人が複数いる場合は、誰が不動産を相続するかの遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成して全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。最後に、これらの書類と作成した登記申請書を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。申請後、不備がなければ1~2週間程度で登記は完了し、新たな権利証である登記識別情報通知書が交付されます。 さて今回は相続登記の手続きについてお話しました。不動産の取得を知った日から3年以内に行わないと10万円以下の過料が科される事があるので早めに処理したいですね。ちなみに2024年から義務化された相続登記ですが、それ以前の相続の際登記していなかったものも義務化の対象です。親世代ならまだ分かるかもしれませんが、それ以前の相続だったりすると書類を揃えるのも大変です。確認しておきたいですね。
2025.10.19
コメント(0)
-
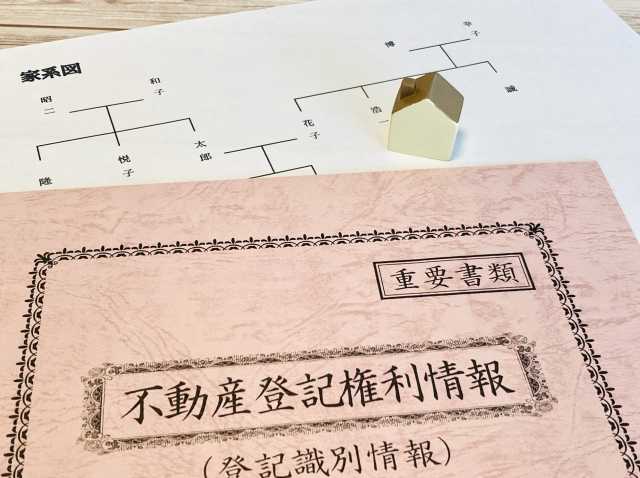
不動産の相続登記?義務?
相続の際、不動産(土地・建物)があると相続登記が必要ってご存知でしょうか?今回は、相続登記について簡単にお話したいと思います。 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を故人から相続人へ変更する手続きのことです。これまで任意でしたが、所有者不明の土地問題を解消するため、2024年4月1日から義務化されました。この法改正により、相続で不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。この義務は過去に発生した相続で、まだ登記がされていない不動産にも適用されます。つまり、「祖父から父に相続された土地やけど、登記しとらんちゃんね」ってな昔の相続でも該当します。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きを放置すると、過料の他に不動産の売却や担保設定ができないだけでなく、次の相続が発生した際に権利関係がより複雑になるリスクがあります。義務を果たすため、戸籍謄本などの必要書類を集めて法務局に申請を行う必要があります。 さて、今回は相続登記についてお話しました。遺言書があれば早いですが、そうでない場合、出来るだけ早めに遺産分割協議をまとめて誰が不動産を取得するのか決めて、相続登記する必要がありますね。ちなみに、遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を履行することも可能です。
2025.10.18
コメント(0)
-

消滅時効?って何?
以前、「取得時効」について記事を書きました。他人の物(主に土地など)であっても、一定期間、所有する意思を持って、平穏かつ公然と占有し続けることで、その物の所有権を取得できる制度でしたよね。今回は、逆に権利が無くなる「消滅時効」について簡単にお話したいと思います。 消滅時効とは、債権などの権利を持つ人が、一定期間その権利を行使しない場合に、その権利を消滅させてしまう制度です。これは、「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方に基づいています。対象となるのは、貸したお金を返してもらう権利(債権)などです。なお、土地や建物などの所有権は、放置していても消滅時効にかかることはありません。時効が完成するまでの期間は、原則として以下のいずれか早い方が適用されます。 ・権利を行使できることを知った時から5年 ・権利を行使できる時から10年が、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、この期間が20年となります。例えば、交通事故などでの人的傷害の場合、損害および加害者を知った時から5年、または不法行為(事故)の時から20年の時効期間となります。被害者保護の観点から時効期間が長く設定されているんですね~。 さて、今回は「消滅時効」についてお話しました。長期間にわたって「権利を行使しない」人の権利は、社会の安定のために消滅させることになっているんですね~。ちなみに、「権利を行使しない」とは、単に請求しないだけでなく、法的に意味のある手続きを取らない状態を指します。つまり、口頭や普通郵便での請求ではダメで、「裁判上の請求」や「内容証明郵便での催告」などが必要となります。
2025.10.13
コメント(0)
-

時効の更新と完成猶予って何?
前回、民法改正による時効制度について記事を書きました。今回は、その際に出てきた「時効の更新」と「時効の完成猶予」について簡単にお話したいと思います。 2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「時効の中断」「時効の停止」という用語は、それぞれ「時効の更新」「時効の完成猶予」へと改められました。「時効の完成猶予」とは、時効の進行を一時的にストップさせる制度です。時効期間が満了しそうになっても、特定の事由が発生した場合、その事由が終了するまで(または一定期間)、時効が完成しなくなります。例えば、内容証明郵便などで支払いを請求(催告)すると、その時から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。ただし、催告を繰り返しても猶予期間は延長されません。「時効の更新」とは、それまで進行していた時効期間がリセットされ、新たにゼロからカウントが始まる制度です。例えば、債務者が借金の存在を認める(例:一部を返済する、支払猶予を願い出る)と、その時点で時効は更新されます。 さて、今回は「時効の完成猶予」と「時効の更新」についてお話しました。「完成猶予」は一時停止、「更新」はリセットという明確な違いがあるんですね。ちなみに、口頭での約束も法的に有効となります。なので、「支払います」と口頭で言ったら、「時効の更新」が認められる為、そこから時効がスタートする事になります。
2025.10.12
コメント(0)
-

2020年民法改正?時効制度が変わったと?
皆さん「時効」ってご存知でしょうか?「それはもう時効だよ~」とか言ったりしますよね?今回は、2020年民法改正で変わった「時効」について簡単にお話したいと思います。 2020年4月1日に施行された改正民法により、時効に関するルールがいくつか変更されました。まず、消滅時効期間の統一です。飲食店のツケや工事の請負代金など、職業別に細かく定められていた短期の消滅時効が廃止されました。新しいルールでは、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」に統一されました。次に、用語の変更です。これまで使われていた「時効の中断」「時効の停止」という言葉が、より適切な「時効の更新」「時効の完成猶予」に改められました。そして最後に、生命・身体の侵害による損害賠償請求権です。人の生命または身体が害された場合の損害賠償を請求する権利については、被害者保護の観点から時効期間が長く設定されました。 さて、今回は2020年民法改正による「時効」についてお話しました。消滅時効は、「知った時から5年」「権利行使できる時から10年」なんですね。ちなみに、人の生命または身体が害された時の損害賠償請求権の時効期間は、「不法行為の時から20年」と長く設定されています。
2025.10.11
コメント(0)
-

葬式費用、相続財産から控除できると?
相続税を計算する場合、相続財産を算出しますよね。その際、葬式費用を差引けるってご存知でしょうか?今回は、相続財産から控除できる葬式費用について簡単にお話したいと思います。 相続財産を計算する上で、遺族が負担した葬式費用は遺産総額から差し引くことが認められています。ただし、税法で控除の対象となる「葬式費用」は具体的に定められているため注意が必要です。対象となるのは、主に以下の費用です。 ・遺体の捜索や、病院から自宅などへの搬送費用 ・葬儀、火葬、埋葬、納骨といった儀式そのものにかかった費用 (仮葬と本葬の2回行っても認められます) ・お通夜など、葬儀の前後に発生する通常避けられない費用 ・常識の範囲内のお布施など、葬儀に関連する謝礼これらの定められた費用を正確に把握し、適切に計算に含めることが大切です。 さて今回は、相続財産から差引ける葬式費用についてお話しました。(基礎控除を超えた)相続財産が少なくなると相続税が少なくなるのでお得ですよね。ちなみに、香典返しや、墓地・墓石の購入費用、初七日や四十九日といった法事に関する費用は、葬式費用とは見なされず、相続財産から差し引くことはできません。ごっちゃにならない様に気を付けましょう。
2025.10.05
コメント(0)
-

相続税の基礎控除?どうやって計算すると?
皆さん、相続税の基礎控除の計算どうやるかご存知でしょうか?今回は、相続税の基礎控除について簡単にお話したいと思います。 相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税の申告や納税は一切不要です。基礎控除額は、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」の計算式で算出します。この計算式にある「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、その他に子供、親、兄弟姉妹の順で相続権が移ります。例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人となる場合の法定相続人は、妻と子供2人の合計3人です。3,000万円 +(600万円 × 3人) = 4,800万円となります。この4,800万円が、基礎控除額となります。したがって、亡くなった夫の遺産総額(預貯金、不動産、有価証券などを合計した金額)が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。もし遺産総額が4,800万円を超える場合は、超えた部分が課税対象となり、相続税の申告が必要になります。 さて、今回は相続税の基礎控除についてお話しました。法定相続人の数によって基礎控除額が変わるので、まずは法定相続人を確定させる必要があるんですね。ちなみに、被相続人からの贈与は過去7年分、相続財産としてカウントされます。よって、「わーい、控除額ギリギリセーフ!」と思っていても、贈与があるケースでは相続税が発生する可能性があるんですね~。申告しない場合、延滞税や加算税で多額の税負担となる可能性があり、最悪財産を差し押さえられる事にもなりかねません。超注意です。
2025.10.04
コメント(0)
-

知らないと損をする?「時効の援用」
前回、取得時効の記事を書きました。今回は、その際にも登場した「時効の援用」について簡単にお話したいと思います。 「時効の援用」とは、時効が完成したことによって利益を受ける者が、その利益を享受する意思を相手方に表示することです。例えば、借金の返済義務がなくなる債務者が、貸主である債権者に対して「時効が成立したので支払いません」と主張すること等を指します。時効期間が経過しても、自動的に権利が消滅したり取得できたりするわけではありません。これは、時効の利益を受けるかどうかを当事者の意思に委ねるためです。したがって、時効の効果を確定させるためには、この「援用」という手続きが不可欠となります。援用の方法に決まった形式はありませんが、後々のトラブルを避けるため、「言った、言わない」の争いを防ぐ証拠として、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付するのが最も確実な方法です。 さて、今回は「時効の援用」についてお話しました。時効が成立しても、「はーい、自分、時効を援用しま~す」って意思表示しないと利益を得る事ができないんですね。ちなみに、時効期間が経過した後に、債務の存在を認めるような行為(例:借金の一部を返済する、支払猶予を申し出る)をしちゃうと、時効の利益を放棄したとみなされ、時効の援用ができなくなる可能性があります。気を付けましょう。
2025.09.28
コメント(0)
-

他人の土地も自分のものに?「取得時効」って何?
皆さん、取得時効って聞いた事ないでしょうか?民法162条にその規定があります。今回は、「取得時効」について簡単にお話したいと思います。 取得時効とは、他人の物であっても、「①所有の意思をもって」「②平穏かつ公然と」「③一定期間占有を続けること」で、その所有権などの権利を取得できる制度です。 ①所有の意思をもった占有であること: 所有者として振る舞う意思(自主占有)が必要です。 ②平穏かつ公然の占有であること: 暴行や脅迫によらず、占有を隠していないことが求められます。 ③一定期間の占有が継続すること: 時効期間は、占有を開始した時の状況によって異なります。自分のものだと信じ、そう信じることに過失がなかった場合(善意無過失)の場合、10年。他人のものだと知っていた(悪意)か、知らないことに過失があった場合の場合、20年で「取得時効」が成立します。 さて、今回は「取得時効」についてお話しました。典型例としては、隣地との境界を誤って長年使用していたケースなどがあります。ちなみに、時効期間が経過しても自動的に所有権が移るわけではありません。時効による利益を受ける者が「時効の援用」という意思表示をすることで、正式に権利を取得できるとです。
2025.09.27
コメント(0)
-

相続の際の借金、どうやって調べる?
相続の際、超重要なのは、故人の借金の有無です。借金があるのか?あるならどのくらいか?分からないと怖いですよね。今回は、故人の借金調査について簡単にお話したいと思います。 相続財産の調査において、故人が隠していることの多い借金の発見は特に難しい問題です。まずは故人の部屋などを確認し、ローンの契約書や利用明細、督促状といった書類がないか探してみましょう。より確実に調査するには、JICC(日本信用情報機構)やCICといった個人信用情報機関に、故人の信用情報を開示請求する方法が有効です。これにより、金融機関や消費者金融からの借入状況などを網羅的に把握できます。調査の結果、プラスの財産よりも明らかに借金が多いことが判明した場合は、「相続放棄」を検討する必要があります。相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要なため、速やかな調査と判断が重要です。 さて、今回は故人の借金調査についてお話しました。本人が遺言書や財産目録を作成していない場合、財産調査において借金の部分は超重要です。その大きさによっては3ヶ月以内に相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引継ぐ)を選択しないといけないからです。ちなみに、法定相続人や遺言執行者などが開示請求する場合、本人確認書類のほか、法定相続人であることを証明する書類(法定相続情報一覧図の写しなど)が必要となります。
2025.09.23
コメント(0)
-

相続の際の預貯金や有価証券、どうやって調べる?
相続の際、被相続人(故人)の財産ですが、多くの場合、預金として銀行にあるって事は想像できますよね。ただ、株などの有価証券がどのくらいなのか?財産目録が無い場合、調べないといけません。今回は、預貯金・有価証券の調査方法について簡単にお話したいと思います。 故人が遺した預貯金の調査は、まず預金通帳を探すことから始めます。通帳を基に、取引のあった金融機関の窓口で「預金残高証明書」の発行を申請すれば、相続開始時点での正確な資産額を把握できます。もし通帳が見当たらなくても、クレジットカードの利用明細や通販の支払い履歴などが、引き落とし口座を特定する手がかりになる可能性があります。心当たりのある金融機関に直接、口座の有無を照会することも有効です。また、株式や投資信託などの有価証券を保有していた場合は、取引のあった証券会社や金融機関に連絡を取り、資産価値を証明する「評価証明書」の交付を依頼しましょう。「証券会社が分からん」って場合、郵便物で「取引残高報告書」や「配当金の支払通知書」などで確認できます。 さて、今回は預貯金や有価証券の調査方法についてお話しました。被相続人の財産がどのくらいあったのか?正確に把握しなければなりません。預金のみならず、有価証券の残高も証券会社に証明書を発行してもらわないといけないんですね。ちなみに、証券会社が不明で、故人の遺品から手がかりが見つからない場合、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、故人が口座を開設していた証券会社や信託銀行などを調べることができます。
2025.09.22
コメント(0)
-

相続の際の不動産、どうやって調べる?
相続の際、被相続人(故人)の財産の内、不動産があるってケースありませんでしょうか?自宅等は分かりやすいですが、その他の不動産って何がどのくらいあるのか、知っておかないとわかんないですよね。今回は、相続の際の不動産の調査方法について簡単にお話したいと思います。 被相続人が所有していた不動産の相続調査では、まず物件の特定とその評価額の把握が不可欠です。調査の第一歩として、故人の自宅から「権利書」や「固定資産税の納付書」といった関連書類を探します。特に固定資産税の納付書を手がかりに、市区町村役場で「名寄帳」を請求すれば、所有不動産の全体像を明らかにできます。物件が特定できたら、法務局で権利関係が記された「登記事項証明書」を取得します。次に、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を入手し、不動産の価値の目安を確認します。 さて、今回は相続の際の不動産調査についてお話しました。何をどのくらい持っているのか?あらかじめ遺言書等で分かっていると調査もスムーズですね。そういったものが無いと、役場での調査等が必須となり、相続人の負担となります。慣れない作業は専門家に相談する事も選択肢です。ちなみに、これらの手続きを自身で行う際は、相続人であることを証明するための戸籍謄本や身分証明書が必要となります。何度も役場に通う事の無いよう忘れずに準備ですね。
2025.09.21
コメント(0)
-

相続の際の財産目録、何を記載する?
相続の際、被相続人(故人)の財産がどれだけあるか分からないと分配のしようが無いですよね。そこで必要となるのが、財産目録です。今回は、財産目録に何を記載するのかについて簡単にお話したいと思います。 財産目録には、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額などを記載していきます。そういった「プラスの財産」だけでなく、借金や税金、未払の治療費などの「マイナスの財産」もきちんと調べて、記載しておく必要があります。たとえ被相続人が遺言書を書いてくれている場合でも、財産目録が用意されていない場合は、やはり財産をきちんと調べて、財産目録を作成するようにしましょう。なお、財産目録は法律で作成を義務付けられている訳ではありません。しかし、遺産分割協議や相続税対策などの場面では、財産目録の有無によって、手続きの進行や結果に大きな差が出ることがあります。 さて、今回は財産目録についてお話しました。遺言書で財産目録と共に分配方法も記載されていると相続人の労力は激減します。やはり遺言書は作成しておくに越した事はありませんね。ちなみに「財産目録」、書式についての決まりがある訳ではないので、相続人全員が分かりやすいようにまとめておけばいいかなぁと思います。
2025.09.20
コメント(0)
-

特別な遺言の証人、どんな人がなると?
一般危急時遺言などの特別な方式の遺言、証人が必要となります。その証人はどんな人がなるとでしょうか?今回は、特別な方式の遺言の証人について簡単にお話したいと思います。 一般危急時遺言を作成するには、3人以上の証人の立ち会いが必要です。そして、誰でも証人になれるわけではなく、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。具体的には、民法第974条に「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。」と記載があり、 1.未成年者 2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人は、証人になる事ができません。これらは「その他の特別方式の遺言」にも適用されますつまり、遺言の内容によって直接的な利益を得る可能性のある人や、遺言者に近い親族は、証人から除外されるんですねぇ。 さて、今回は特別な方式の遺言の証人についてお話しました。このように証人に厳しい条件が課せられているのには、遺言者本人が自分で書くわけではなく、証人の1人が遺言者の口述を筆記するという特殊な形式をとるためなんですね。ちなみに、一般危急時遺言の証人を選ぶ際には、親族以外の第三者に依頼するのが一般的です。司法書士や行政書士といった専門家が証人になることもあります。
2025.09.15
コメント(0)
-

特別な方式の遺言?他にあると?
前回は、特別な方式の遺言として「一般危急時遺言」について記事を書きました。今回は、それ以外の特別な方式の遺言について簡単にお話したいと思います。 特別な方式の遺言として、「一般危急時遺言」以外に、以下3つあります。まず、「難船危急時遺言」。これは、船舶の遭難などで死の危険が目前に迫っている場合に作成できる遺言です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言の趣旨を伝え、証人の1人がそれを筆記し、各証人が署名・押印します。飛行機が遭難した場合も含まれると解されています。次に「一般隔絶地遺言」。これは、伝染病による隔離や服役中など、交通が遮断された場所にいる人が作成する遺言です。この場合、死亡の危急は要件とされていません。作成には警察官1人と証人1人の立会いが必要で、遺言者、筆者、立会人、証人全員の署名押印が求められます。最後に「船舶隔絶地遺言」これは、長期間の航海などで陸地から離れた船舶内にいる人が作成する遺言です。こちらも死亡の危急は問いません。船長または事務員1人と証人2人以上の立会いのもとで作成し、関係者全員の署名押印が必要です。 さて、今回は「一般危急時遺言」以外の特別な方式の遺言についてお話しました。いずれも通常の方式で遺言を作成できない特殊な状況下で認められる「特別な方式の遺言」です。ちなみに、これらの特別な方式の遺言は、遺言者が通常の方式で遺言できる状態になってから6ヶ月間生存した場合は、その効力を失います。「通常の遺言ができるんだったら、そうしてね」って事です。
2025.09.14
コメント(0)
-

臨終間際に作成する遺言?そんなんあると?
通常は、自筆証書遺言や公正証書遺言などで遺言書を作成します。でも病気や事故などで急に死が迫った時、「あ~遺言書作っとらんやった~」って言っても後のカーニバルですよね。今回は、そんな時作成する遺言について簡単にお話したいと思います。 病気やその他の理由で死亡の危急に迫られた人が作成できる、特別な方式の遺言として「一般危急時遺言」という特別な方式の遺言があります。通常の遺言方式が取れない緊急時に認められている遺言です。作成には、3人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝え、それを筆記してもらう必要があります。筆記された内容は、遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させて確認を取った後、証人全員が署名押印することで遺言が成立します。ただし、この遺言は、作成から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じません。また、遺言者が回復し、通常の方式で遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存した場合、この遺言は無効になります。 さて今回は、「一般危急時遺言」についてお話しました。利用されるケースは滅多に無く、あまり知られてはいませんが、知っておくと万が一に備える事ができるかもですね。ただ、こういった方式を取らなくて良い様に、元気なうちから遺言書を作成しておく事をお勧めします。ちなみに、遺言書は15歳以上であれば誰でも作成は可能です。これは、法律上、15歳になれば「意思能力」が備わっていると判断される為です。
2025.09.13
コメント(0)
-

株式会社と合同会社の設立費用は?
前回、株式会社と合同会社の違いについて記事を書きました。今回は、両者の設立費用について簡単にお話したいと思います。 株式会社と合同会社の設立にかかる法定費用を比較すると、合同会社の方が大幅に安く抑えられます。費用の大きな違いは、「登録免許税」と「定款認証手数料」の2点です。まず、登録免許税ですが、これは会社を登記する際に納める税金です。株式会社の最低税額が15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。どちらも資本金の額の0.7%ですが、最低額が異なるため大きな差が生まれます。次に定款認証手数料です。定款は会社のルールを定めた重要な書類で、株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要があります。これに資本金の額に応じて3万円から5万円の手数料がかかります。一方、合同会社はこの定款認証が不要なため、手数料はかかりません。 さて今回は、株式会社と合同会社の設立費用についてお話しました。自分ですべて手続きを行った場合、最終的に株式会社は約22万円以上かかるのに対し、合同会社は約10万円で設立可能なんですね~。また上記費用に加えて、定款を紙で作成した場合は、株式会社・合同会社ともに4万円の収入印紙代が必要です。が、電子定款を利用すればこの費用は不要になります。ちなみに、電子定款には、ICカードリーダーや電子署名ソフト等が必要となります。弊所では、「セコムパスポート for G-ID行政書士電子署名」にて電子定款作成が可能となっております。行政書士の先生で「電子署名だけやってくれん?」とのご依頼も喜んでお受け致します。
2025.09.07
コメント(0)
-

株式会社と合同会社?どう違うと?
最近は会社を立ち上げるハードルも下がって、法人を設立される方も増えてきました。その際、株式会社にするか、合同会社にするかを選択しなければなりません。今回は、株式会社と合同会社の違いについて簡単にお話したいと思います。 株式会社と合同会社は、どちらも法人格を持つ会社形態ですが、その仕組みや特徴にはいくつかの違いがあります。最も大きな違いは「所有と経営」の関係です。株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)が分離されており、株主は出資額に応じて議決権を持ちます。 一方、合同会社は出資者(社員)と経営者が同一であり、原則として出資者全員が経営に携わります。このため、合同会社は意思決定が迅速に行えるという利点があります。また、設立費用は合同会社の方が安く抑えられます。株式会社の設立には最低でも15万円の登録免許税と定款の認証手数料がかかりますが、合同会社は登録免許税が最低6万円で、定款認証も不要です。それと、株式会社には役員の任期があり、再任手続きや登記費用が発生しますが、合同会社には役員の任期がないため、これらのコストがかかりません。株式会社に義務付けられている決算公告も、合同会社では不要です。そして、株式会社の利益配分は出資比率に応じて決まりますが、合同会社では定款で自由に利益配分を決められます。 さて、今回は株式会社と合同会社の違いについてお話しました。一般的に、株式会社の方が社会的信用度が高いとされてて、資金調達や人材採用の面で有利になる場合があるんですね~。ちなみに、合同会社は比較的小さな会社で、株式会社は大企業というイメージはありますが、Appleやアマゾン、Googleの日本法人は、合同会社です。米国企業は、効率重視って事と、上記3社だと信用度は問題ないって事ですかね~。
2025.09.06
コメント(0)
-

死因贈与契約と遺言書の違いって何?
前回、「死因贈与」についてお話しました。「死んだらあげるよ」って言う死因贈与と、遺言書、何が違うと?って思っちゃいますよね。今回は、死因贈与と遺言書の違いについて簡単にお話したいと思います。 「死因贈与契約」と「遺言書」の最も大きな違いは、前者が贈与者と受贈者の「双方の合意による契約」であるのに対し、後者は遺言者の「単独行為」である点です。このため、死因贈与契約書には両者の捺印が必要ですが、遺言書は遺言者のみで作成できます。相続人の合意は不要ですよね。死因贈与のメリットとして、契約書を当事者双方が保管するため、遺言書のように発見されないリスクを低減できます。また、「生前の介護」や「ペットの世話」を条件とする「負担付贈与」が可能な点があげられます。この場合、受贈者が生前に負担を履行すれば、贈与者は原則として契約を撤回できません。一方、遺言は(本人が生きている限り)いつでも撤回可能です。 さて今回は、死因贈与契約と遺言書との違いについてお話しました。内容を秘密にしたい場合は遺言書で、負担付贈与などを使いたい場合は死因贈与など、状況による使い分けができるんですね。ちなみに、不動産を「死因贈与」した場合、「遺言」による相続と比べて不動産取得税や登録免許税が高くなることがあります。税金面では不動産の場合違いはありますが、どちらで財産を取得しても贈与税ではなく相続税の対象となります。
2025.08.31
コメント(0)
-

「死んだらあげるよ」って口約束、有効?
家族の「私が死んだら、この土地あげるよ」って口約束、あるかもしれません。その様な場合、法的に有効なのでしょうか?今回は、被相続人の「あげるよ」って言葉が法的にどうなのかについて簡単にお話したいと思います。 まず、単なる口約束でも全く持って意味が無いかと言うと、そうでもないです。それは、「私が死んだら、この土地をあげるよ」と被相続人が意思表示をし、言われた本人も合意すれば、「死を原因として効果が発生する『贈与契約』が成立する」ためです。これを「死因贈与」と言います。しかし、「本人がそう言って、自分は合意したとって!」と主張するだけでは、死因贈与契約があったと認められる可能性は低いです。その場合、「死因贈与の契約書」があれば、法的に有効と認められ、他の相続人とのトラブルも回避できます。円満な相続の為にも、死因贈与を行う際は、書面で死因贈与契約書を作成し、お互いに署名&押印して保管する事をお勧めします。 さて、今回は被相続人の「あげるよ」が法的に有効かについてお話しました。単なる口約束でも有効とはいえ、それを証明する人や書面が無い限り、認められる事は難しいんですね。ちなみに、契約書が無くても、相続人全員が、死因贈与契約に納得し、遺産を譲ってくれれば死因贈与契約の内容を実現する事ができます。遺言書が無い場合、相続人全員での遺産分割協議(話合い)となる為です。
2025.08.30
コメント(0)
-

お墓を受け継ぐ?法律の規定は?
両親が亡くなり、お墓が残る事ってあり得ますよね?その場合、法律ではどの様に扱われるのでしょうか?今回は、お墓を受け継ぐ際の法律について簡単にお話したいと思います。 ご先祖様を祀るためのお墓や仏壇、家系図などは「祭祀財産」と呼ばれ、特別な財産として扱われます。これらは一般的な遺産とは異なり相続財産には含まれないため、相続税の課税対象外となるのが大きな特徴です。この祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀承継者」といい、お墓の管理や法要などを主宰する役割を担います。祭祀承継者は相続人の中から選ばれることが多いですが、親族以外でもなることができます。承継者の決定は、故人の指定が最優先され、指定がなければ慣習や家庭裁判所の判断で決まります。祭祀承継者は、お墓の維持管理費などを負担することになりますが、その負担を理由に遺産を多く受け取ることは認められていません。 さて今回は、お墓を受け継ぐ際の法律についてお話しました。お墓などを受け継ぐ「祭祀承継者」は、故人の指定(遺言書等)が優先で、それが無い場合は最終的に家庭裁判所が決めるんですね。ちなみに、祭祀を行うことは法律上の義務ではなく、承継者の意思に委ねられており、引き継いだ祭祀財産を処分することも可能です。なので、後にトラブルとならない様、あらかじめ話し合っておく事が重要ですね。
2025.08.24
コメント(0)
-

連れ子に相続?できると?
再婚相手の連れ子、自身が歳を取ってゆくゆくは財産をその子にと考えるのは普通ですよね。ただ何もしなければ法律上の相続権はありません。では、どうすれば財産を残してあげられるのでしょうか?今回は、連れ子の相続について簡単にお話したいと思います。 主な方法は以下の3つです。 ①養子縁組をする最も確実な方法で、連れ子は法律上の子となり、実子と同じ法定相続人としての権利を得ます。これにより、法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えるといった節税メリットも期待できます。ただし、実子がいる場合はその相続分が減るため、将来のトラブルを避けるためにも、家族間で十分に話し合い理解を得ておくことが重要です。 ②遺言書を作成する(遺贈)養子縁組をしなくても、遺言書に「連れ子に財産を遺贈する」と記すことで財産を渡せます。この場合、連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」となります。注意点として、他の相続人には遺留分(法律で保障された最低限の相続分)があるため、これを侵害すると後に金銭を請求される可能性があります。また、養子縁組をしていない連れ子への遺贈は、相続税が2割加算される場合があります。 ③生前贈与をする生きている間に財産を贈与する方法です。年間110万円までなら基本的に贈与税はかかりませんが、それを超える額には贈与税が課されます。また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象になることがあるため注意が必要です。 さて今回は連れ子に財産を残す方法についてお話しました。どの方法が最適かはご家庭の状況によって異なります。ちなみに、連れ子がいる場合の相続はトラブルになりやすい傾向があります。ですので予め、専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を選択することが大切です。
2025.08.23
コメント(0)
-

行方不明の家族の相続、どうすればいいと?
通常、人は亡くなると相続が発生します。が、行方不明の家族の場合、生死が分かんないですよね?今回は、行方不明の家族の相続について簡単にお話したいと思います。 相続人が生死不明の場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできず、法的な手続きが必要です。主に「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があります。生死不明の期間が7年未満の場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任された管理人(弁護士など)が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、管理人が遺産分割協議に参加するには、別途家庭裁判所の許可が必要です。申立てから選任までは約1〜3か月かかります。生死不明の期間が7年以上の場合は、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。戦争や災害などの危難に遭遇した場合は、その危難が去ってから1年以上で申し立て可能です。失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したとみなされ、残りの相続人で遺産分割を進めることができます。 さて、今回は、行方不明の家族の相続についてお話しました。「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があるんですね。ちなみに、どちらの手続きをとるにせよ、まずは戸籍を取り寄せ相続人全員を確定させることが重要です。これらの手続きは複雑なため、専門家に相談し、状況に応じた適切な方法を選択することをお勧めします。
2025.08.17
コメント(0)
-

胎児も遺産相続できると?
人の権利義務発生は、「出生と同時」が基本です。ただ、出産予定の胎児の相続権はどうなるのでしょうか?今回は、胎児の相続権について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、胎児も遺産を相続することができます。その根拠は民法第886条に定められています。この条文では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されており、相続が開始した時点(被相続人が死亡した時点)で生まれていなくても、法律上、相続人としての権利が認められます。ただし、この権利が確定するためには「生きて生まれること」が絶対的な条件となります。民法の同条第2項で、死産だった場合には相続権は適用されないと定められているためです。母親の体から完全に露出した後、少しでも生きていれば相続権は有効となります。その胎児の相続分は、すでに生まれている子供と同じです。胎児がいる場合、その存在を無視して行われた遺産分割協議は無効となり、やり直す必要があります。そのため、通常は胎児が無事に出生するまで遺産分割協議を待つのが一般的です。 さて、今回は、胎児の相続権についてお話しました。本来、人の権利能力は「生まれた瞬間」から発生するんですが、相続だけは例外なんですねぇ。ちなみに、胎児は、本来相続人となるはずだった親が先に亡くなっている場合に代わりに相続する「代襲相続」や、遺言によって財産を受け取る「遺贈」の対象となることも可能です。
2025.08.16
コメント(0)
-

ペットの将来を託す?負担付遺贈って何?
自身亡き後、残されたペットのお世話、心配ですよね?今回は、残されたペットの将来を託せる「負担付遺贈」について簡単にお話したいと思います。 「負担付遺贈」とは、遺贈者が受遺者に対し、財産を譲る代わりに一定の義務を課す遺贈のことです。例えば、飼い主が亡くなった後、残されたペットの世話をしてもらうことを条件に、特定の人へ財産を遺すっていう事も可能です。当たり前ですが、ペット自身は財産を相続できません。なので、信頼できる人に飼育費を含めた財産を遺贈し、間接的にペットの将来を守ってもらう必要があるんですね。この制度の利点は、信頼する個人に法的な形でペットの世話を託せる点にあります。しかし、注意すべき点も存在します。まず、世話の負担が重いと判断された場合、受遺者が遺贈そのものを放棄してしまう可能性があります。そのため、事前に相手の合意を得て、遺す財産とペットの生涯にかかる費用のバランスを考慮することが大切です。さらに、財産を受け取ったにもかかわらず、約束通りに世話をしないリスクも考えられます。この対策として最も重要なのが、遺言で「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、受遺者が義務を果たしているかを監督し、問題があれば是正を求めたり、家庭裁判所に遺言の取消を請求したりする権限を持ちます。 さて、今回は「ペットの将来を託す?負担付遺贈」についてお話しました。ペットは相続できないので、信頼できる人に託すしかないとですねぇ。ちなみにこの他にも、生前に契約を結ぶ「負担付死因贈与」や、より柔軟で確実性の高い「ペット信託」という選択肢もあります。どの方法が最適か、専門家と相談して決めることをお勧めします。
2025.08.15
コメント(0)
-

読みにくい字で書かれた遺言書、大丈夫?
遺言者自身が一人で書ける「自筆証書遺言」。全文を自筆で書かなければなりません。もし、読みにくい字で書かれていた場合、法的に有効なのでしょうか?今回は、読みにくい字で書かれた遺言書について簡単にお話したいと思います。 判読不能な文字や不適切な保管状態(破損やインクに滲み等)の自筆証書遺言は、その部分が無効になるリスクがあります。特に日付が読めない場合は、遺言書全体が無効になる可能性もあるんです。これは、日付は必須事項だからです。こういった規則があるのは、遺言者の意思が確認できないが故の、相続人の間のトラブルを防ぐためです。このリスクを回避する方法として、以下の3点があります。 ①公正証書遺言の作成:公証人が作成するため、様式の不備や判読不能といった問題がなく、原本は公証役場で保管されます。 ②法務局の遺言書保管制度の活用:自筆の遺言書を法務局が保管する制度で、申請時に様式のチェックが行われ、紛失や劣化のリスクを低減できます。 ③第三者による確認:親族や行政書士などの専門家に遺言書を読んでもらい、内容を確認してもらう方法ですが、遺言の内容が他者に知られることになります。 さて今回は、読みにくい字で書かれた遺言書についてお話しました。せっかく遺言書を書いても無効になっちゃうと残された人が困っちゃいますよね。そういったリスクを回避する上記方法をお勧めします。ちなみに、第三者の確認で、行政書士に頼む場合、内容が他に漏れる事はありません。行政書士には厳格な守秘義務が課せれているからです。 ※行政書士法第12条
2025.08.14
コメント(0)
-

コンセント、差込み向きあるって本当?
皆さん、コンセントの差込む向きが決まっているってご存知だったでしょうか?今回は、法律から離れて、コンセントの差込みの向きについて簡単にお話したいと思います。 ご家庭にあるコンセントを見てください。2つ並んだ内、右の穴が少し小さくなっているのが分かると思います。この少し小さい穴の方が「プラス」で、縦長の穴が「マイナス」です。正しく差し込む事で、発生する電磁波を抑えたり、機器の性能向上するなんて言われています。が、実際は、逆に差し込んでも、電磁波が増える事(人体への影響)も電気代が変わる事も無いそうです。でも「向きがあるなら正しく差込みたい!」って方もおられると思います。では、どの様に差し込めばよいのでしょうか?電源プラグの種類によりいくつか見方があります。 ①電源プラグの線に文字が書いている:この場合、文字が書いてある方がマイナス ②電源プラグにアース線がある:アース線が出ている方がマイナス ③電源プラグにアース棒がある:アース棒を上にして向かって左がマイナス ④電源プラグに記号の表記がある:「W」や「℗」の表記がある方がマイナス ⑤電源プラグに何もない:この場合はどちらに差し込んでもOK さて、今回はコンセントの差し込む向きについてお話しました。現状日本におけるコンセントの差込む向きは決まっているものの、逆にしても全く問題はない様です。ちなみに、音にこだわる方は、オーディオ機器のコンセントへの差込む向きを正しくしているとの事です。音が違うようです。鈍感な私は、たぶん違いは分からないんだろうなぁw
2025.08.13
コメント(0)
-

相続土地国庫帰属制度?漢字多!
中国語ではありません。「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した不要な土地の所有権を、一定の要件のもとで国に引き渡すことができる制度です。今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について簡単にお話したいと思います。 「相続や遺贈によって土地を取得したっちゃけど、田舎だし売ったり活用したりとかできんっちゃんね」って事ありませんでしょうか?そのまま持ってても固定資産税とかかかるだけで負担になっちゃいますよね?そんな時に使えるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度が出来る2023年4月27日までは、不要な土地を手放すには相続放棄しかなく、その場合は預貯金などの他の財産もすべて手放す必要がありました。が、この制度により不要な土地だけを切り離して手放すことが可能になりました。ただし、建物がある土地や抵当権がついている土地など、この制度が使えない土地もあります。それと、「審査手数料(1筆あたり14,000円)」や「負担金(原則20万円)」など費用もかかります。 さて、今回は、相続等により取得した不要な土地を国庫に帰属する制度についてお話しました。そのまま相続すると自身の子どもや孫に負担をしうる場合、国庫に帰属するのも一つの手ですよね。ちなみに、制度が出来た2023年4月27日以前に相続した土地でも「相続土地国庫帰属制度」の対象となります。なので、「もう相続したのが20年前っちゃんね」って方も使えます。申請の代理が出来るのは、「弁護士」「司法書士」「行政書士」となります。
2025.08.12
コメント(0)
-

六法全書って何?
皆さん、六法全書ご存知でしょうか?「聞いた事ある」って方がほとんどかと思います。今回は、その「六法全書」について簡単にお話したいと思います。 六法全書、一言でいうと、日本の主要な法律を集めた書籍で、法律家や学生が使う「法律の辞書」のみたいなものです。言葉的には、「六法」と「全書」に分けられます。「六法」とは、法律の土台となる「憲法」・「民法」・「商法」・「刑法」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」の6つの基本法を指します。「全書」とは、「六法に加えて、実務でよく使われる重要法令も収録した総合版」という意味です。つまり日本の法律全部が載っている訳ではなく、「六法」以外の例えば「税法、労働法など」の重要法令が収録されています。この「六法全書」用途に応じて様々な種類のものがあります。例えば、弁護士などが使う「判例付き六法」は、法律の条文だけでなく、関連する重要判例の要旨も掲載されていて、むちゃくちゃ分厚くて重いです。逆に、判例を省略して条文だけをコンパクトにまとめた「ポケット六法」などもあります。私も行政書士試験の勉強で「ポケット六法」使っていました。 さて、今回は「六法全書」についてお話しました。法律の専門家や学習者にとって、仕事や勉強を進める上で欠かすことのできないツールなんですねぇ。ちなみに、「六法全書」毎年改訂されます。法律の改正は頻繁に行われる為、それに対応する必要があるんですね。
2025.08.09
コメント(0)
-

遺言書の訂正、どうやると?
前回、遺言書の書き間違いについて記事を書きました。では、書き間違えた遺言書の訂正はどうすれば良いのでしょうか?今回は、遺言書の訂正について簡単にお話したいと思います。 当たり前ですが、遺言書の訂正は自身が存命していないと無理です。そして、遺言書の書き間違いを訂正する方法は、民法第968条で厳格に定められています。この方式に従わない訂正は無効となり、訂正前の内容が有効とみなされます。まず、間違えた部分を二重線などで消し、どこを訂正したかが分かるよう訂正箇所を明確にします。次に、変更した旨を付記(遺言書の末尾や余白に「〇字削除、〇字追加」など、どこをどのように変更したかを書き加え)して、そこに署名します。 最後に、訂正した箇所(二重線を引いた場所の近くなど)に、遺言書で使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。以上の方式を誤ると訂正が無効になるだけでなく、遺言書全体の有効性が争われる可能性もあるため、慎重に行う必要があります。 さて今回は、遺言書の訂正についてお話しました。正しい方式で訂正しないと無効になっちゃうので慎重に行わないといけないんですね~。ちなみに、修正液や修正テープ等の使用は不可です。また、訂正箇所が多い場合や、内容が複雑になる場合は、訂正を重ねるよりも全文を書き直す方が安全です。そもそも正しい方式での訂正は手間ですので、思い切って書き直すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
2025.08.03
コメント(0)
-

遺言書の書き間違い、どうなると?
故人亡き後、遺言書を発見。でも間違った記載の場合、どうなるとでしょうか?今回は、遺言書に書き間違いがあった場合どうなるのか、簡単にお話したいと思います。 遺言書の書き間違いは、作成者が亡くなった後では修正できないため、非常に深刻な問題を引き起こす可能性があります。特に手軽さから選ばれがちな自筆証書遺言は、手書きで作成するため書き間違いのリスクが高く、細心の注意が必要です。もし遺言書に誤りがあると、その遺言書が無効になったり、不動産、預貯金、有価証券、自動車などの名義変更が金融機関や法務局に拒否されたりする危険性があります。特に、預金口座番号の1桁の間違いや、登記簿通りに記載されていない不動産情報など、細かい部分での誤記がトラブルの原因となりがちです。名義変更ができない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、故人の意思を反映させるために作成した遺言書が無意味になってしまう可能性があります。 さて今回は、遺言書の書き間違いについてお話しました。細かい事ですが、少しでも間違いがあると遺産分割がスムーズに進まない事もあり得ます。作成する際は、無効な遺言書にならない様、注意しましょう。ちなみに、亡くなる前までは、書き間違えた場合に法律で定められた方法で訂正できます。が、少々面倒ですし作成段階で誤記や記入漏れがないよう、慎重に確認することが重要です。
2025.08.02
コメント(0)
-

自分で作る遺言書、何に注意する?
遺言書、作成するのにルールがあるってご存知でしょうか?法的要件を満たさなければ、遺言書は無効となってしまいます。今回は、自分で作る遺言書(自筆証書遺言)の注意点について簡単にお話したいと思います。 自筆証書遺言は、全文を自身の手で書く事が法的な有効性の大前提です。その為、パソコンやワープロで作成されたものは、正式な遺言書とは法的に認められず、無効となります。その他、以下の注意点があります。 ・作成日は、何年、何月、何日と正確に記載 ・署名は必ず実名、フルネームで記載 ・必ず押印(認印でも可、母印は有効の判例があるが避けた方が無難) ・相続人の名前だけでなく、続柄や住所などを併記した方が確実この様に記述の仕方などに色々な決まりがあります。書き方が分からない場合や、無効になるか不安な場合は専門家に相談しましょう。 さて、今回は自分で作る遺言書(自筆証書遺言)についてお話しました。「自筆」証書と言われる通り、全て自分で文字を書かないと無効になるんですね~。※2025年現在ちなみに、自筆証書遺言書で、唯一パソコンやワープロでの作成が認められているものに「財産目録」があります。財産が多岐に渡る場合など、自筆すると大変ですからね。ただし、その「財産目録」の用紙には、署名・押印が必要となります。
2025.07.27
コメント(0)
-

遺言書作成前の準備?どんなんすると?
遺言書作成って大事ですよね。でも何から取り掛かれば良いか分かんないですよね。そこで今回は、遺言書作成前に準備する事について簡単にお話したいと思います。 遺言書で『誰に何を遺すか』を明確にするためには、まずご自身がどのような財産を持っているのか、その全体像を明らかにする必要があります。具体的には、土地や建物といった不動産、預貯金、株式や投資信託などの有価証券という様なプラスの財産はもちろんのこと、ローンや借入金といったマイナスの財産も全てリストアップする必要があります。こうすることで、財産の全体像が明確になり、遺産の分配を具体的に検討できるようになりますし、相続人が後々困らないように、財産の把握漏れや予期せぬ負債の存在を防ぐことにも繋がります。また、財産のリストアップと並行して、法律で定められている相続人(法定相続人)が誰になるのかも正確に把握しておく事も重要です。状況により、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などが該当します。法定相続人を特定することで、遺言がない場合に誰にどの程度の財産が渡るのかが分かります。その上で自身の意思を遺言にどう反映させるかを考えます。例えば、「特定の人に多く渡したい」とか、「法定相続人以外の人にも遺したい」などの希望がある場合、具体的に検討する基礎となります。(遺言書が無ければ、法定相続人全員での遺産分割協議となります)また、法定相続人には『遺留分』という最低限保障される権利がある場合があり、それを考慮した遺言内容にするためにも、まずは誰が法定相続人なのかを知ることが不可欠です。 さて、今回は遺言書作成前に準備しておくことについてお話しました。自身の財産について、何が、どのくらいあるのか?自身が亡くなった時、法定相続人は誰になるのか?分かっていないと的確な遺言書が作成できないって事になります。ちなみに今は書店などで「エンディングノート」が数百円くらいから売られています。その財産一覧などの項目でまとめると抜けもれなく自身の財産が把握できます。遺言書作成の前に「エンディングノート」を書いてみるのも良いかもですね。
2025.07.26
コメント(0)
-

次の国政選挙って、いつ?
昨日、参院選の投開票日でした。皆さん投票には行かれましたでしょうか?予想通り与党は過半数を維持できませんでした。これで衆議院に続き、参議院でも与党単独で法案を通す事ができなくなりました。ただ、そうは言っても、最大議席を有しているのは与党・自民党です。なぜなら、今回改選されたのは、参議院の半分124議席だけ(衆議院465議席、参議院248議席、計713議席)だからです。では、次の選挙っていつ?ってお話になると思います。今回は、次の大きな国政選挙がいつになるか?について簡単にお話したいと思います。 今回2025年7月20日に行われたのは参議院選挙です。参議院は任期6年ですが、半数が3年毎に改選されます。となると、次の参院選は、2028年7月となります。参議院は解散がない為、このスケジュールは動きません。しかし、衆議院は違います。衆議院は、昨年2024年10月27日に選挙が行われました。任期4年なので、任期満了による次の選挙は2028年10月26日までに行われます。その前に、首相が衆議院解散を決めれば、すぐにでも選挙が行われます。 さて、今回は、次の国政選挙はいつ?ってお話をしました。参議院は間違いなく、2028年7月まで選挙はありません。が、衆議院は解散による選挙が任期の2028年10月を待たずして行われる可能性があるんですね。ちなみに、参議院は半分ずつ3年毎に通常スケジュールで選挙を行う為、「通常選挙」と言い、衆議院は全員をいっぺんに選挙する為、「総選挙」と言います。
2025.07.21
コメント(0)
-

投票日当日、やっちゃダメな事あると?
本日2025年7月20日は、参議院議員通常選挙の投票日です。私も投票してきました。ところで、この投票日当日のNG行為があるってご存知でしょうか?今回は、選挙投票日当日のやっちゃいけない事について簡単にお話したいと思います。 選挙の公正を期すため、投票日当日には公職選挙法で禁止されている行為があります。選挙運動は投票日の前日までと定められており、投票日当日の選挙運動は全面的に禁止されています。違反した場合、1年以下の拘禁または30万円以下の罰金が科される可能性があり、選挙権や被選挙権が停止されることもあります。超厳しいですね。でも、「別に選挙運動とかしてないし」って方もおられると思います。が、ビラやポスターを配布したり、街頭演説を行う事だけが選挙運動ではありません。特定の候補者や政党への投票を呼び掛ける事(口頭もしくはSNS投稿)も該当します。なので、SNSに「〇〇候補に投票しよう」とか「比例は〇〇党へ」といった投稿したり、過去の選挙運動に関する投稿を再投稿(リツイートやシェア)する事も違反となる可能性があります。また、自身が投票した候補者名や政党名を書いた投票用紙の写真をSNSにUPする行為も、特定の候補者や政党への投票呼びかけとみなされる可能性があるため注意が必要です。 さて、今回は投票日当日にやっちゃいけない事についてお話しました。投票日当日は、選挙運動がガチで禁止されています。そして選挙運動とは、SNS投稿なんかも含まれますので、知らずに法律違反をする事が無い様、知っておく事が重要ですね。ちなみに、「選挙に行こう」とか「投票に行って来たばい」といった、特定の候補者や政党への投票を依頼しない、投票参加を呼びかける投稿は問題ありません。
2025.07.20
コメント(0)
-

投票率低いとどうなる?
皆さん、明日は、いよいよ、参議院議員選挙の投票日です。三連休の真ん中に設定された投票日、思惑に抗い投票しましょう。そういう策略で投票率が低いとどうなるのでしょう?今回は、投票率が低いとどうなるか?について簡単にお話したいと思います。 投票率が低いということは、国民の一部の意見しか政治に反映されないことを意味します。これは、投票に行く人が多い特定の世代や集団の意見が重視され、その結果、その層に有利な政策ばかりが実現しやすくなります。例えば、高齢者の投票率が高く、若者の投票率が低い場合、年金など高齢者向けの政策が手厚くなる一方で、子育て支援や教育といった若者向けの政策が後回しにされる可能性があります。→現在、これ。また、投票率が低いと、政治家は「どうせ投票に行かないだろう」と考え、国民全体の利益よりも特定の支持団体の利益を優先するようになります。→現在、これ。 さて、今回は、明日の参院選を前に「投票率が低いとどうなる?」についてお話しました。投票率の低下は、単に「政治への関心が薄い人が多い」という問題にとどまりません。それは、民意が適切に政治に反映されなくなり、特定の世代や集団に不利益が生じ、ひいては社会全体の活力が失われることにもつながりかねない重大な問題です。「投票したい政党がないっちゃね~」って場合も、投票する事が重要です。少しでも自身の考えに近い政党へ投票しましょう。一人ひとりが投票に行くことで、健全な民主主義社会を維持し、より良い未来を築く事につながるとです。
2025.07.19
コメント(0)
-
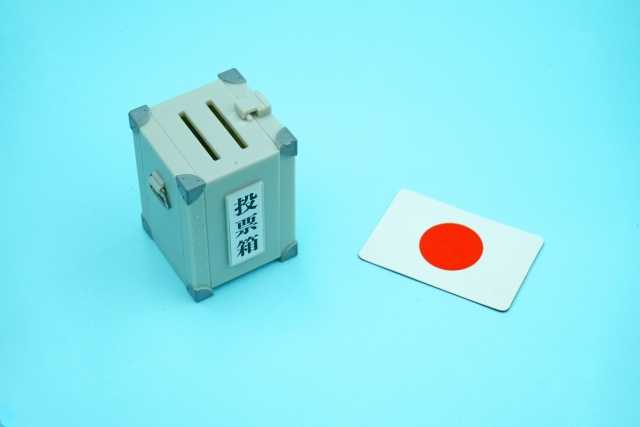
投票率?!低い原因は?
7月20日(日)いよいよ我々の将来を決める選挙が行われます。自身と子どもや孫など大切な人の生活に大きな影響を与える大事な選挙です。組織票を持つ与党が投票率を下げる為にわざわざ三連休の中日に設定した参院選。必ず投票に行きたいですよね。そんな投票率ですが、なぜ低いのでしょうか?今回は、選挙の投票率の低い原因について簡単にお話したいと思います。 日本の投票率が低い原因は、単一のものではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると思われます。まず個人の意識=政治への無関心(教育にも原因)や政治不信(生まれた時から不景気な若者など)があります。これは、戦後教育やマスコミの影響が大きいと言えます。次に、選択肢の不在・魅力の欠如=選挙戦では各党良い事しか言わない(差が分からない等)や、有権者を引きつける魅力的なリーダーの不在(マスコミの報道のしかたも問題)があったりもします。結局、若年層が選挙に行かない事で政治が「高齢者向け」となり子育て世代の施策も「やってます感」を出して終わりみたいな事になっちゃいます。これらの要因は独立している訳ではなく、相互に関連し合っています。政治不信→政治への無関心→「1票では何も変わらない」→投票に行かなくなる→投票率の高い高齢者向けに手厚い政治→更なる若者の投票離れ→政治不信みたいな負の連鎖がこれまでの流れかなと推察します。 さて、今回は投票率の低さについてお話しました。投票率の低迷は民主主義の基盤を揺るがす問題です。本来ならば、政治側から投票しやすい環境を整える必要があるはずです。・・・なのに三連休の中日って・・・ちなみに、今回の参院選、与党が過半数を割り込むと、衆議院に続き参議院でも与党が主導権を失い、現在の増税路線・国民所得軽視の政策が変わる可能性が高くなります。みなさん、選挙に行きましょう。
2025.07.13
コメント(0)
全264件 (264件中 1-50件目)
-
-

- たわごと
- ヱスビー食品優待、「鶏だし炊き と…
- (2025-11-30 05:29:46)
-
-
-

- 徒然日記
- ANTI NORMAL L/S Tee【Black x Yello…
- (2025-11-29 21:04:58)
-
-
-

- 写真俳句ブログ
- 何に見えるかな? (@_@)
- (2025-11-29 22:34:15)
-







