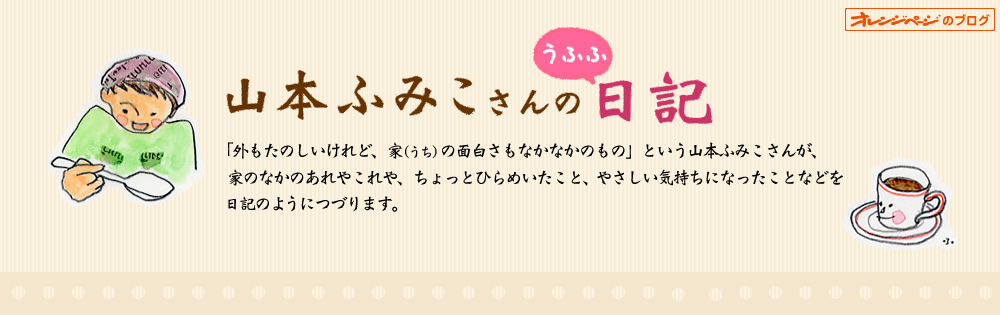2008年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

やっぱり、焼き茄子? ——8月のブログ(4)
■「メガネ、メガネ」 老眼がわかったのは、年上の友だちの老眼鏡をかけてみたのが、きっかけだった。くっきりと、よく見えること。 そのとき、わたしは38歳。 幼いころから、目だけ(ほんとうに目だけ)よかったために縁のなかったメガネをかけられるのが、うれしかった。メガネは、期待したほど似合わなかったが、ずり落ちてきたメガネを、片手でくいっと持ち上げる仕草は、うふふ……と、思った。知的な女の気分で、「くいっ」とやる。 老眼は、ぐんぐんすすんだ。 最初は、メガネなしでも読むことも書くことも、それなりにできたのに、3年もたつと、それがむずかしくなる。これは、メガネというより、わたしの目なんだなあと、思わされる。 メガネ歴約10年。 この10年は、わたしにとって、そのままメガネ探し歴となる。「メガネ、メガネ」と、メガネを探しまわる。全部で4つ持っているというのに。ときには、頭の上にメガネをのせながら、探している。 メガネなしでは、文字と、事の細部が見えなくなったことは、ある意味、わたしを育ててくれた。 ものを見るということは、視力でははかれないことを知る。 切実にメガネを探しながら、不便の値打ちを知る。 そして。 メガネをかけなければ、見えない汚れや曇りに向かって、「見ぬもの清し!」と言い放つ、きょうも。 ■ 手帖からの伝言 「珍紛漢紛」という名前の、手帖を持っている。 毎年、暮れになると、同じ小さな帖面を1冊もとめて、表紙に、このコトバを書きこむ、小さく。「ちんぷんかんぷん」。 子どものころから、この境地にいることが多かった。そういうわけで、もっとも慕わしいコトバである。 初めて出合ったコトバ。いいなあと思う、本の一節。異国の料理の名前。知りあったひとの名前と住所。切符の買い方。読みたい本の題名。——を、書く。 何年か前の「珍紛漢紛」を、何気なく開いて、どきっとする。 「自分が与えるものを、受けとる」 ことになってるんじゃないか、この世は。 と書いてある。 ■ 焼き茄子 夏から秋にかけて。気がつくと、台所のこころは、茄子を追っている。 茄子は油、いろいろな香辛料、魚、肉、チーズのような存在とも相性がよく、どんな国の料理の舞台でも、すましていい役をもらっている。 が、やっぱり焼き茄子かなあ、と思う瞬間がある。 焼き上げて、熱いうちに、あちち、あちちと言いながら、少し跳ねながら、茄子の皮をむくときの気持ちは、筆にも舌にも尽しがたいものが、ね。 〈焼き茄子〉 茄子を皮ごと、網で焼く。熱いうちに皮をむき(布巾や菜箸を使って、気をつけて!)、食べやすい大きさに(縦に)さくか、切るか、する。 熱いところを食べてもよし。冷やしてもよし。おろししょうがと、しょうゆで。※わたしの好みは、酢じょうゆをかける、です。※ 〈焼き茄子の味噌汁〉 この焼き茄子を、椀に置き、上から味噌汁を注ぎます。とき辛子を添えて。 この3つが、わたしのまわりで、わたしと一緒にうろうろしてくれる老眼鏡です。もうひとつ、100円ショップでもとめたメガネが、コピー機のところに置いてあります。いまのところ「老眼」だけで、ほかの症状はでていないので、市販の「老眼鏡」(の、度のきついもの。+2,5かな)で間に合っています。
2008/08/26
コメント(18)
-

ズッキーニとの出合い--8月のブログ(3)
■ 真夏の記憶 8月になると、戦争を考える。 自分が戦中戦後の渦中になかったという意味で、また、身近に戦争で命を落としたひとがいなかったという理由からも、太平洋戦争はわたしには遠い。 原爆投下、敗戦、米軍進駐の記録番組。慰霊祭や平和を考える集会——そういうことを通してはじめて、戦争を思おうとし、考えようとしている。 学校に長い夏休みがあり、職場や商店にお盆の休暇があり、その影響でいろいろな場面が変則的になる8月の裾は、やはり戦争がにぎっているのだと思う。 8月になると、読んでおきたくなる本が、書架から身をのりだしてくる。トルストイの『戦争と平和』もそのなかのひとつで、ことしはどうしても、また読みたいとつよく思わされている。 いろいろな事情を考えあわせると、読みはじめは8月の後半になりそうだが、それでも必ず、と、本とゆびきりをする。 ■ 風 数年前、扇風機を買いに走ったことがある。 それまで使っていたものを、家人たちにひとことの相談もなく、中国人の留学生にあげてしまったので、あわてて買いに出たのだった。 おおっ、頑丈な上、姿もいい。 この扇風機に、決めた。 「これ、ください」というわたしの言い方が切羽詰まっていたのだろうか、「お持ち帰りですか?」と、たたみかけて問われる。 持って帰れるんだな、とひとり合点し、「持ち帰ります!」と勇んで答えたまではよかったが、持ってみればかなりの重量だ。 店のひとは、近くに駐車してある自家用車までの距離を測ってそう言ったのかもしれないと、あとから気づく。 まいったな……。 駅前までかつぎ、バスにひきずり上げ、乗客になってからも嵩張る箱に引け目を感じ、最寄りのバス停に降り立ったときには、いろんな意味で玉の汗をかいていた。 という二人三脚の記憶のせいでもないだろうが、この扇風機とは、いいつきあいがつづいている。 扇風機がつくる風には、格別なものがある。 ■赤茄子やズッキーニのこと 子どものころ、祖母から、初めてトマトを見たときの話を聞いた。 祖母とトマトの出合いは、昭和のはじめの頃らしかった(北海道函館市)。 当時のひとは、トマトを「赤茄子」と呼んだ。「赤いけど青くさくて、おいしいなんて、最初は全然思えなかった。それをいまは、夏にトマトがないなんて、考えられないでしょ? 不思議よね」 トマトはこの国に馴染んだが、その後も、品種改良はつづいている。 わたしが子どものころ食べたトマトは、いまより酸味がつよかった。そうそう、冷やしたトマトに砂糖をかけて、食べたこともある。 トマトに、水菓子として珍重される部分があったということだ。なつかしいな、あれ。 大人になってから初めて食べた野菜として、ズッキーニ、アーティチョーク、アボカドなどがある。そういえば、ゴーヤも初めて食べたのは、20歳代のおわり、沖縄本島でのことだった。 それぞれとの、出合い——果たしてこれを自分は好きなのだろうかと、しばらく思いめぐらすようなこともあったのだ。出合いから、自分で扱うようになるまでには、また、それ相応の隔たりがある。 とくにズッキーニには、なかなか手が出なかった。 相手を、はかりかねていた。ふれあってみれば、飾り気のない、さっぱりした気質の持ち主だと、すぐ心づくのだけれども。 ズッキーニの塩づけズッキーニ…………………………………………長めのもの2本塩…………………………………………………………小さじ1弱レモン………………………………………………………… 適宜 ① ズッキーニは、厚さ5mmの輪切りにする。② これをボウルに入れ、塩をふる。③ あがってきた水もそのままに、冷蔵庫で冷やす。④ レモンを添え、食べる間際にしぼる。※2日のあいだに食べきるのを、目安に。 これが、扇風機です。身長は、142cm(123cmまで、下げることができます)。扇風機は、偉大だなあと、思わされています。 フウセンカズラの「風船」が、茶色くなりました。ほら、窓に、夏の雲がうつりこみました。 「風船」のなかの、種。このハートの模様に、思わず顔が……、ほころびます。
2008/08/19
コメント(27)
-

玉ねぎのちから——8月のブログ(2)
■昼寝 関東地方この夏いちばんの暑さ、という予報を聞いてしまったので、今朝小学生の子どもに、「きょうは、友だちと、うちのなかで遊んだらどう?」 とすすめる。 わたしの仕事部屋を冷房を効かせて貸しだした上に、おやつにアイスクリームを付ける。サービス満点だ、まったくのところ。 わたしは、居間で、汗をだらだら流しながら仕事をしていたが、昼過ぎ、涼しい部屋が妬ましくなり、3人の小学生のなかに割りこむ。「ここで、30分昼寝させておくれ」 そう言ったなり、枕に頭をのせ、たちまち眠る。 眠っているあいだに、こんがらがっていたものがほどけて、考えの筋が立っていた。 ■ さらし玉ねぎ 友だちが、「若いころの汗と、汗の種類が変わってると思わない?」と言う。「え?」 一瞬、何のことだかわからずに、聞き返す。 昔に比べて、汗がべたべたしているような気がするんだそうだ。 言われてみると……そうかもしれない。 「いやだなあ」と、つぶやきながら台所に行くと、そこで、玉ねぎと目が合う。(玉ねぎを食べよう)。 玉ねぎを食べると、さらさらになるのは血液だったか……。でも、何だか玉ねぎのちからは、汗をもさらさらにしてくれそうな気がする。 やおら、玉ねぎを刻む。 水にさらして、レモンをしぼり……。 けずり節としょうゆをかけて食べるもよし。 マヨネーズ(辛子を効かせて)をかけるもよし。 さらし玉ねぎのごまサラダ材料玉ねぎ…………………………………………………2個レモン(しぼり汁)…………………………………適宜ハム(または蒸しどりをさいたもの)、ピーマン、 きゅうり、にんじんなど ……………………各適宜〈ソース〉すりごま(白)、塩、こしょう、辛子をマヨネーズに混ぜる。 ① 玉ねぎを薄切りにし、水にさらす(何度か水をかえる)。② 玉ねぎをボウルに上げ、、しぼって、レモン汁をかけておく。③ ハム、ピーマン、きゅうり、にんじんはせん切りに。④ 材料の〈ソース〉であえる。 ■ ワンピース 昨夏、一度も着なかったワンピース。 今年も着ないような気がする。このワンピースをもとめたときのことを思いだしながら、じっと見る。 丈を少し切って、パンツの上に着るというのはどうだろうか……。 こういうことを思いつくと、うれしくなって、後先を考えずに、つまり具合のいい丈なんてこともあまり考えずに、いきなり実行。 じょき、じょき、じょき。 裾をまつる。完成。(いいかも、これ)。 新しいチュニックを1枚、手に入れた気分だ。 以来、外を歩いていて、ふと気がつくと、「あのワンピース、あれは切れる」とか、「いいチュニックになる」 という目になっている。 玉ねぎ、刻みに刻みました。刻みながらも、さらさら感が指先から伝わるみたいでした。 ゴーヤの実がなりました。うれしくて、うれしくて。こんなふうに、なるんですね。ただいま(8月9日現在)6.2cm。気がつけば、花もいっぱい、小さな小さな実もどっさり。すごいなあ……。ゴーヤ祭りだっ。
2008/08/12
コメント(20)
-

おいなりさん——8月のブログ(1)
8月のブログ、短いエッセイの連なりを、お届けします。小さな花束のつもりで……。 ■月代り 自分の調子——からだにも、こころにも——に「周期」のようなものがあるとしたら、それは、甘んじて受けるしかないのだろう。 「周期」を思わされるのは、不調のときだ。 ああ、いつになったら、ここを抜けだせるだろうか、と、気分は不調に浸りきっている。まるで、初めてそれを経験するひとのように、うろたえる。 いつも同じ調子では生きられないことも、だからこそ不調からだって、いつかは抜け出せることも、経験上、よく知っているのに。 もしかしたら……、うろたえたいのかもしれない。 なくはないのかもしれない、そんな指向が。 だとしたら、月代りのいま。 一抜けた(——不調からも、うろたえからも)! ■はがきに、字 メールのやりとりをしていても、こころの底に、澱(よど)むものがある。 伝えきれない何か。 受けとりそこねている、何か。 「暑中お見舞い申し上げます」 につづけて、二言三言手で書くだけで、気のすむことがある。 何だろうかな、これは。 ■これだったのか……。 ずっと待っていた。 待っているそれが、何なのかわからなくて、あれだろうか、これだろうかと、もやもやする。 いま、わかった。ああ、わたしが待っていたのは、これだったのか、と。 久しぶりの夕立。 うれしや、夕立。 ■おいなりさん 夏は、当てがはずれると、そのあとが大変だ。 ほおっておくと、すぐに、わるくなる。 たとえば、日常からはぐれた少年少女。 たとえば、食べきれなかったご飯。 少年少女は、自力で日常にもどるしかない。時がかかっても、それはきっとできるのだ。それに……、わるくなりかけた日日は、じつは、案外わるくない。味が出る。 ご飯のほうは、わるくなると、もう、味や趣致なんぞとは言っていられない。そうなる前に、手を貸さないと。 夏、気がつくと「おいなりさん」の皮を煮ている。ご飯救済のために。 おいなりさん(の皮)油揚げ(ひらきやすいものを)………………………………10枚だし汁(昆布だけでもよい)…………………………… 2カップ砂糖………………………………………………………… 大さじ4しょうゆ…………………………………………………… 大さじ4みりん……………………………………………………… 大さじ1 ① 油揚げは半分に切って、袋になるようそっとひらく。② これを湯通しし、絞っておく。③ 鍋に材料のだし汁と調味料を煮立て、油揚げを煮る。煮上がっても、さめるまで、そのままおく。(④ 油揚げに、酢飯を詰めれば、出来上がり。) ※ 材料の砂糖に、黒糖を使うと、味がこっくりします。※ 時間があるときに、おいなりさんの皮を煮ておくと(冷凍もできます)、重宝します。※ 酢飯 油揚げ10枚の「皮」で、2合ほどのご飯が包めます。 ほんとうは、昆布と酒を加えてご飯を炊きたいところですが、 このたびは、残りご飯を使うので、すぐに調味液(ご飯1合あたり、酢大さじ3、 砂糖小さじ1、塩小さじ1/2——一度弱火にかけ、さます)を混ぜます。 酢飯に、ごまや、ちりめんじゃこ、生姜の甘酢漬け(みじん切り)、 ひじき(煮ておく) などを混ぜても、ひと味華やぎます。※ 調味は、おいなりさんの皮(わたしのは、甘め)も、 酢飯(わたしのは、すっぱい)も どうか、それぞれの味をみつけてください。 おいなりさんというのは、自分の味の生かせる存在だと思うんです。 2階居間に面したベランダにグリーンカーテンを。南西の窓辺には、フウセンカズラを。 南東の窓辺には、ゴーヤを。
2008/08/05
コメント(32)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2025-11-13 21:04:35)
-
-
-
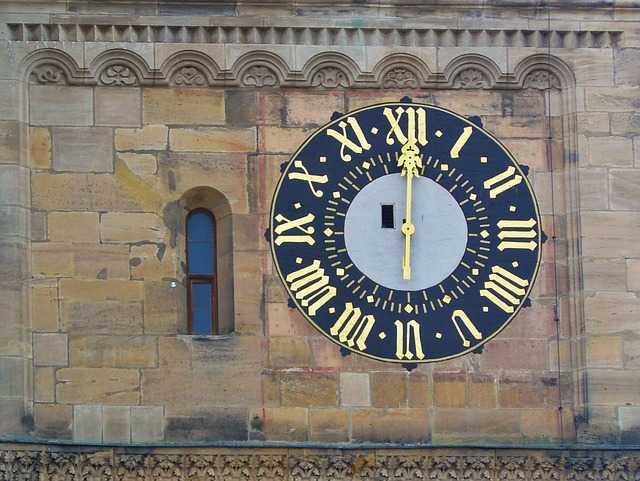
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- 今日のお出かけ ~
- 梅田阪急百貨店のクリスマスショーウ…
- (2025-11-19 00:00:07)
-