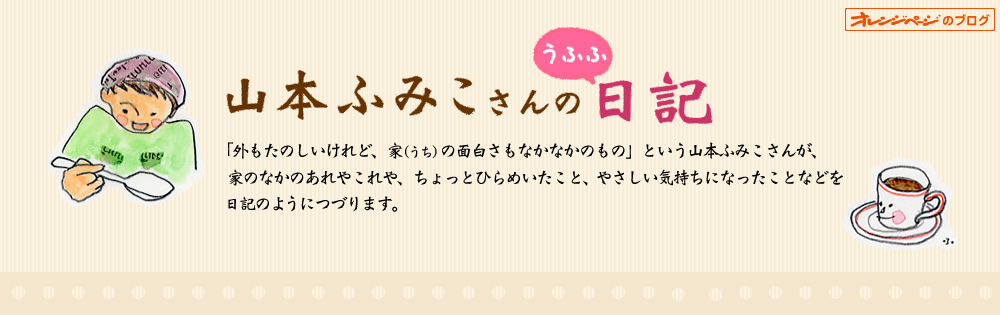2008年04月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

励ましていたはずが、励まされる……。
皆さんにも、こんな経験、あるでしょうか。 最近、わたしに起こったこと、ちょっと聞いていただこうかな、と思います。 * ああ、もう、終わりかな、と思った。 最近は、ずっと崖っぷちにいた。 ここで、かなり長いあいだ踏みとどまっていた。 つよい風でもひと吹きすれば、すぐさま、ころがり落ちてしまいそうで、かなりチカラを入れて踏ん張っていたのだった。 わたしを踏ん張らせたものは、この数年友だちだった彼女の、魅力だと思う。 彼女から受ける刺激が、わたしには新鮮に感じられた。いつも、少しちくちくしたが。 しかしながら、一昨日のわたしは……、「皮を剥かれた白うさぎ」だった。剥くのも、そこにすりこまれた塩も、みんなコトバでのこと。 わたしが、ひとには決してしないと決めていることが、あとから、あとから、降ってくる。「これは、もう刺激という域を越えている……撤退」 と密かにこころを決め、決めた現場から、終電で帰る。 撤退。 友だちだった彼女からの。 深夜、ぼんやりしながら、駅からの道をふらありふらありと歩く。 ひとりで、もう少しのあいだ、ぼんやりしたかった。 「あのひとのところへ」 そう思いつくやいなや、気持ちがゆるむ。 あ、わたし、泣いてる。 道端の電灯が、泣き顔を照らすのなんかは、平気。この際だ、ちょっと泣こう、そう思っていた。 「あのひと」とは、こぶしの大木。 今年の3月この項にも書かせてもらった(「春愁」)、あの、こぶしの木なのだ。 春先、ほんの少ししか蕾をつけず、その蕾も硬いままで、ほとんど咲かなかった。わずかに花と呼べそうなそれも、薄紙を、くしゃっと小さくまるめたような花だった。 あのときわたしは、この木に向かって、「がんばって」と声をかけた。花も咲かせないこぶしが、心配で、祈るような気持ちだった。 それからひと月半のあいだに、幾度かこぶしを見舞ったが、この日ばかりは、見舞いどころか、すがる気持ちで訪ねた。 弱っている者同士、より添いたかった。「どうしてこんなに悲しいんだろう」 と言って、泣きたかった。 こぶしは、クログロと茂っている。 葉っぱがクログロとして見えたのは、深夜のせいで、昼間見上げたなら、青青と見えるだろう。 こぶしのほうは、再生を果たしていた。 ううっと小さくしゃくり上げながら、目を見張る。木を仰ぐ。 励ましていたはずが、励まされている……。 なんともいえない気持ちで、家に帰る。 来年、花を咲かせて見せてくれるかどうかということまでは、わからないにしても。 ともに、寿命の尽きる日まで、と想う。 * わたしは、いまはもう元気です。 こぶしや、友だちや、近しいひとびとの存在のおかげで。 こんな話を、静かに読んでくださる皆さんのおかげで。 ふ ほうら、こんなに葉っぱが……。 「すっかり元気になりました」とはいえない状態のはずですが、ひとつの再生を果たしているこぶし。……励まされます。 軍手が、こぶしの柵に、こんなふうにひっかけてあったんです。この木のお医者さんが、昼ごはんに出かけたのじゃないでしょうか。軍手にむかって、「よろしくお願いします」と。
2008/04/30
コメント(31)
-

「残す」ということ。
「こんなもの、捨ててしまいなさいよ、」 「どうして、」 「あんたが持っているには、ふさわしくない、高いの、安いの、というこ とではありませんよ、僕がいやなんだ、」 「あなたのものでもあるまいし、」 「……そんなことは萬萬ないけれど、もしもだね、あなたの亡いあとに、 誰かが、この道具を見るとしよう……そうすると、あなたの持っている いい品まで、下る……」 多江は、どきりとしました。 いきなり、引用で気を引こうなどとは、我ながら、狡(こす)いことだ。 これは、「中里恒子」著作の、『時雨の記』(文春文庫)の一節である。 書架のなかの単行本も文庫本も、カヴァの背がいつしか擦れて、「時雨の記」という題名さえ読めないほどの有様は、この小説を好んでくり返し読んだことをあらわしている。 恋、というと、『時雨の記』に登場する壬生と多江のあいだに通う、気を許し合いながらも、ゆるみのない浄らな慕情を連想する。 一昨日、「中里恒子」について調べる必要があって、久しぶりに『時雨の記』をとり出す。そうなることを怖れてはいたが、やはり気がつくと、その場に坐りこみ、読みふけっているのだった。 掲出のくだりまできて、はっとした。 これまで幾度となく、とくに若いころには、大きくうなずきながら読んだ場面だ。ものの持ち方、選び方を、おしえられていたのである。 しかし、いまのわたしに響くのは、壬生の台詞のなかの、「あなたの亡いあとに、」というところ。 いつごろの頃からだろうか。 親しいひとたちの記憶のほかは、自分の持ちものをできるだけ残したくない、と考えるようになっている。 わたしの、母方の祖父母も、ほとんどものを残さなかった。およそ値打ちのあるもの、祖母の着物や装身具、祖父の鎌倉彫りの作品——これらは、わたしがものごころついたときには、すでにたくさんはなかった。 母によると、「差し上げてしまうのよ、どんどん」とのことだった。(どんどん……) あれは、祖父母が亡くなって、数か月が過ぎたころのことだ。 とうとう、ふたりの終の栖(すみか)を手放すことが決まる。 わたしは、祖父母の家に忍びこむつもりで、でかけて行った。 忍びこむなどとは、こそ泥のようだが、わたしにとっても拠所だった家が、手の届かぬものになる前に、ただ、もう一度だけ、という気持ちだった。それで、とつ然、訪ねたのだった。行ってみたら、顔見知りの大工のおじさんがいた。 玄関の引き戸に。台所の壁に。カナリアの小屋のあった板の間に。ごはんを食べた居間のあたりに。そして、祖母の着物をはおってひとり遊んだ奥座敷に。 ——触れる。 ——「さよなら」と「ありがとう」を言う、こっそり。 台所の棚の隅に、新聞紙にくるまれたものをみつける。そっと開くと、祖父母が好んで使っていた、切り子のコップがふたつ出てきた。(これ、もらっていいかな、わたしが) 誰にも黙って、コップをふたつ、持ち帰る。 わたしには、祖父母と共に過した時間の記憶だけで、じゅうぶんだけど、このコップがあることは、うれしい。 このコップで酌み交わしながら、大事なひとたちに祖父母の話を聞いてもらう。 このコップを眺めるうち、考えるようになっていく。 残すものは、こういうものを少しだけ、と。 祖父母愛用の、切り子のコップです。 切り子といっても、ざっくりしていて、それが洒落ているように、わたしには見えます。
2008/04/22
コメント(8)
-

「豪速球はやめてね」の巻
「ね、松坂大輔投手の球の早さを体験してみない?」 3年くらい前、友だち夫妻と、バッティングセンターに行ったときのこと。 友だち「夫」が、かるい調子で言ったのだ。 だから、わたしもかるく答える。「してみる、してみる」 飛んでくるボールの早さを目一杯早い目盛りに合わせると、それが、松坂投手の投げる球の早さ(時速150km)になるのだそうだ。 これが、速い。 目にもとまらぬ、ということばがあるが、あんまり速くて、ボールなんかなかったことになるほどだった。 へぼ打者のわたしは、空振りに次ぐ空振りである 「もう一歩前に出て振ってごらんよ」 友だち「夫」は元高校球児で、強豪早稲田実業高校を破って、あと1勝すれば甲子園、というところまで勝ち進んだ、「時のキャプテン」。言うこと、聞いてみようじゃないの。 それで、1歩前進。 ボールが飛んできた。 グキッ。 にぶい音。 バットを握る右手親指にボールが当たったのだ。痛い、というより、親指の芯がじぃぃぃぃぃぃぃぃぃんとする。 素人のおばちゃん打者が、松坂投手の豪速球に手を出そうとすることが、まちがいだったみたいだ。 それから10日あまりは、親指が腫れて、右手がつかいものにならなかった。まわりの誰もが、まったく同情してくれなかったことは、言うまでもない。 以来、ボールやバットから、ちと遠ざかることになったが、さきごろ、ボールとの再会をはたす。「久しぶりだね」「無沙汰は、互い」 このボールは、深夜、夫とわたしの寝室に投げこまれる。「寝ているところにボールが投げこまれるなんて話、聞いたことないぞ」 と夫は、ぐずぐず言っている。「聞いたことのない話でもなんでも、うちには投げ込まれるのよ」 どういうことかって? よくぞ聞いてくだされた。 社会人になった長女は週日のほとんど、また、アルバイトに励む次女も、週のうち2回は、うんと帰宅がおそくなる。終電になることも少なくない。自分で決めた仕事なのだし、そこはそれ、「がんばりなさいよ」という話だが、心配なことにはかわりない。 帰ってくるまでは、まんじりともできない。 というのはうそで、早いときは九時、おそくも十時にはふとんに入って、ちょっと本を読んだかと思うと、たちまち眠ってしまうというのが、わたしだ。心配でもなんでも眠ってしまい、夜半過ぎ、はっと目がさめる。「あの子たち、帰ってきてるかしら」 そうして、眠い目をこすり、半分寝ているからだをひきずって、子どもらの部屋のある3階まで行き、そっとそれぞれの部屋をうかがう。すでに寝息をたてているのをたしかめて、やっと安心するというわけなのだ。 3階までのぼっていくあいだに、心身ともに目覚めてしまう。ここで起きてしまうのは、いかにも早すぎるし、ふたたび眠るのには手間がかかる。なんとも中途半端なことである。夜半過ぎの困惑……だ。 そこで思いついたのが、ボールだった。 帰りが深夜になるときには、寝室——猫の「いちご」が出入りするので、扉は軽くしめてあるだけ——の、アタシが寝ているあたりに、ボールを投げてちょうだい。そうすれば、ふとめざめたとき、起き上がらずにアナタたちの帰宅をたしかめられるからね。ボールにイニシャルを書いておいたからね、ちゃんと投げてね。 投げる力がつよ過ぎて、ボールの勢いに目覚めさせられたり。顔に当たって「ぎょっ」としたり。 しかし、いまでは、投げるほうも投げられるほうも慣れて、具合がいい。夜中、自分がかけている茶色の掛け布団カヴァの上に、黄色いのと黄緑のと、2つのボールがころがっているのを見ると、心からほっとする。 サインは、「豪速球はやめてね」である。 このボールが、わたしの安心のしるし。 こうして、やすむ前に、寝室の扉のノブにかけておきます。
2008/04/15
コメント(20)
-

「ごはん、食べにおいでね」の箸
「家族水入らず」というコトバがあるが、わたしの気持ちのなかには、それが、ない。ないことはないのかもしれないが、そういうことは言わずに暮らしたいと思って、言わずに暮らしてきた。 昨日も深夜、末の子が寝ぼけ眼で、わたしの枕元にやってきて、「追いだされたから、泊めて」と言う。 どうやら、長女が、終電に乗りそこねた友だち2人を連れて帰ってきて、蒲団が足りなくなり、ひとりを末の子のベッドに寝かせたものらしい。やれやれである。 しかし、ほんとうは、こういう展開をわるくないな、と考えている。 あの家に行けば、寝床くらいはみつけられる、と思ってもらえるのが、うれしいのだ。 姉さんたちが勝手に泊まっていくのなんかは、もう慣れっこだが、もっと小さいひとが、親御さんの仕事の都合で、何日かつづけて泊まるようなときには、こちらもちょっと身構える。身構えるといっても、身構えていることを気取られないように身構えるという程度のことだが。 ふだん通り騒がしくしていれば、まあ寂しい思いをさせてしまう心配もなかろうが、こういうとき、わたしは自分とふたつの約束をしている。 ひとつめは、小さいお客さん(仮にハッパチャン)の名前をいちばん最初に呼ぶこと。「ハッパチャーン、ごはんですよー」という具合。 この家に暮らしているひとを呼ぶのは、そのあとだ。 もうひとつは、ハッパチャンのお箸を用意すること。「これ、ハッパチャンのお箸だから、おぼえてね」と、箸を紹介する。こうしておくと、ハッパチャンは、お膳立てを手伝ってくれるときにも、「これが、ふんちゃん(わたしだ)ので、これが上のお姉さんので、これが、わたしの」という風に、みんなと同じ感覚で食卓につける。んじゃないかな。 ときどき、お泊まりの小さいひとが帰ってしまったあと、末の子どもと目を合わせ、「なんか、久しぶり」「うん、久しぶり」と言い合って、ぎゅっと抱きあうことがある。 だけどね……。 何もかもを、あとまわしにされたこの家の子どもが、ひがんだり、ふくれることは、一度もなかった。もっとも、わたしにしたところで、ほかのことで、子どもがしょんぼりしているときにはわかってやりたいと思うが、この種の文句には、耳を貸さないつもりでやってきた。 うちに「自分の箸」を持つひとがふえたので、紙で小袋をつくり、お名前を書いて、専用のひきだしにしまっている。 このひきだしをあけるたび、自分たちが、一緒に愉しくごはんを食べる仲間をもっていることがひと目でわかる。 ありがたいなあ、としみじみ思う。 「また、ごはん、食べにおいでね」 「ごはん、食べにおいでよ」の箸の一部です。 こういう、「袋貼り」みたいな内職が大好きです。型紙と名前つけのシールを、箸と同じひきだしにしまっています。これさえあれば、同じ長さ、幅の袋がつくれるってもんです。 箸のほかに、茶碗もそれぞれに用意できるといいんですが、そこまでは、なかなかね……。ときには、家の者たちが、ごはんを食べに来てくれたひとに合わせ、みんなでそろいの茶碗を使うことがあります。これが、その茶碗です。(ふたも付いてます)。
2008/04/08
コメント(13)
-

「たれ幕屋」でございます。
近しいひとにうれしいことが訪れると、すぐ「お祝い、お祝い」という気持ちになる。世知辛いこの世にあって、そうたびたび訪れるわけではないよろこびごとを、きっちり祝っておかなくては、という思いもある。 季節の行事や、家の者たちや友だちの誕生日、就職のほか、「逆上がり記念」とか「一輪車記念」、「おじいちゃん、おばあちゃん、いらっしゃい」という祝いもある。 自分の分だけでなく、身近なよろこびごとをかき集めるかのような勢いで、祝おうとしている。おっつけ、うちの食卓で祝うことになるのだから、たいしたことではないが、ひとの慶事のお相伴にあずかるときのうれしさは、格別なものがある。 「今週末、リョウヘイの壮行会やるから」 と発表する。「今晩、アイバチャンのお誕生日会します。7時までには帰ってきてください」 と貼り紙をする。 そういうとき、手の空いている者たちが、「じゃ、つくっちゃいますか」と言いながら食卓に集まってくる。 紙、鉛筆、色鉛筆(DERMATOGRAPH)をとり出して、食卓にならべる。 誰かが、紙1枚ずつに、「遼」「平」「、」「板」「前」「修」「業」「が」「ん」「ば」「れ」「!」と鉛筆で下書きをする。 誰かが、それをなぞりながら、マジックインクで太字に仕上げていく。 そうして文字とバックの色塗りがはじまる。 これをするあいだ、「何て書こう?」と相談するほか、ほとんど打ち合わせもなく、作業はどんどんすすむ。この作業風景、すごく好きだ。 お祝い=たれ幕つくり。いつの頃からこうしてきたかは忘れたが、誰かのお祝いをする、というとき、掃除や料理にとりかかる前に、家の者たちはいきなり「たれ幕屋」になる。 これができてしまえば、お祝いの会の準備の半分はできたようなものだ。「遼平、板前修業がんばれ!」「アイバチャン お誕生日おめでとう」 これさえできていれば、料理なんかはふだん食べているものに、飾り気と面白みを少し加えればいい、という気持ちになる。 さて、きょうは長女23歳の誕生日。 3月30日という、年度のどん詰まりに生まれたので、本人はどこかで苦労をしたかもしれないが、芯のあるいい女になった。と、思う。 娘ではありながら、姉さんみたいでもあり、友だちでもあるひとが、すぐ近くで育ったことを、しみじみありがたく想いながら、「たれ幕屋」になる。このたびは、末娘とふたりの「たれ幕屋」。 みんなで食卓を囲む。 たれ幕の前で、記念写真を撮る。 ——そういうのが、わたしが考える、祝い。 こんな感じに、がしがし色を塗ります。DERMATOGRAPHは、大好きな文房具のひとつです。 「たれ幕」といっても、小さな看板(?)の連なり……。こういう仕事だけは、みんな、すごく早いです。がーっとはじめて、ばーっと描いて、すっと終わる感じ。どの仕事(勉強)も、そうだといいんですが。
2008/04/01
コメント(11)
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
-

- handmadeのある暮らし。
- ☆木の紙でつくる箸置き☆
- (2025-10-15 19:03:58)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2025-11-13 21:04:35)
-
-
-

- 収納・家具・インテリア情報
- 部屋にぴったり!四角のサイドテーブ…
- (2025-11-17 21:22:40)
-