2006年09月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

【「駅すぱあと」とピラミッドの関係は!?】「駅すぱあと」風雲録
「駅すぱあと」風雲録「ぱぴるす」「ナイル」――懐かしい統合ソフトたちである。ヴァル研究所は、これらのソフトの開発元、というより、運賃・経路検索ソフト「駅すぱあと」のメーカーといった方が分かりやすいかもしれない。本書は、ヴァル研究所の設立から今日に至るドキュメンタリーである。ソフトウェア・ビジネスの基本は自社製品であると思う。しかし、食いつないでいくためにはお金が必要だ。そんな厳しいビジネス社会にあって、ヴァル研究所の社員たちは、自社製品を創り、育て、死に際まで看取った経験を持つ。その苦労は並大抵のものではなかっただろう。出向をさせない社風、規模拡大より顧客を大切にする姿勢――どれをとっても、普通の会社できないことばかりだ。55歳で急逝した創業社長は、エジプト関係の膨大な量の書籍を所有していた。これらは、ピラミッド研究で有名な早稲田大学の吉村作治教授に寄贈されたという。ただ者ではない。■メーカーサイト⇒日経BP出版センター 「駅すぱあと」風雲録■販売店は こちら
2006.09.30
コメント(0)
-

【技術者としてかくありたい】田中耕一という生き方
田中耕一という生き方2002年にノーベル化学賞を受賞した田中耕一さんの評伝である。修士号も博士号も持たない無名のサラリーマンがノーベル賞を受賞したということで、たいへんな話題になった当時を思い起こす。いまは落ち着いて仕事に没頭できているだろうか。あらためて田中さんの言葉を読むと、普通であることがいかに素晴らしいことかを想起させられる。筆者が最後に、「小学校のときクラスに必ず1人はいた、日本人みんなの思い出のなかにいる懐かしい“あのタナカくん”」(202ページ)と表現しているが、まさにその通りである。成績がトップなわけではなく、スポーツができるわけでもなく、ルックスが良いわけではない。かといって、友だち付き合いが悪いわけでもない。そんな“タナカくん”がノーベル賞を受賞したことで、日本人の誰もが、まるで友だちがノーベル賞を受賞したかのように感じたのではないだろうか。その“タナカくん”だが、生後間もなく母が亡くなり、養父母の手で育てられたという。大学へ入る前にそのことを知らされて葛藤したこと、その影響もあって大学では1年留年してしまったこと、第1志望の会社に入れなかったことなど、人知れぬ苦労があったようである。それでも、地道に努力を重ね、サラリーマンとして会社につくし、妻を大切に想い――だからこそ、なおのこと身近に感じるのかもしれない。同じ技術者として、会社と対立をした青色発光ダイオードの発明者、中村修二さんへの配慮も忘れない。おそらく、“タナカくん”にとって、ノーベル賞は1つのイベントに過ぎなかったのだろう。“タナカくん”は科学者ではなく技術者である。毎日、コツコツと技術を磨き、社会に貢献できることが“タナカくん”の誇りなのだと思う。技術者として、かくありたいと、あらためて肝に銘じる次第である。■メーカーサイト⇒大和書房 田中耕一という生き方■販売店は こちら
2006.09.28
コメント(0)
-

【大学病院でミステリーの掛け合い漫才!?】チーム・バチスタの栄光
【大学病院でミステリーの掛け合い漫才!?】チーム・バチスタの栄光チーム・バチスタの栄光これがデビュー作となるミステリー作家だが、本業は医師。舞台となる大学病院の描写は、非常に写実的である。それとは対照的に、登場人物がコミカルだ。ストーリーは、ミステリーの王道である逆転に次ぐ逆転の展開。それが陳腐にならないのは、舞台と登場人物の描写のアンバランスさのおかげだろう。スターウォーズを背景にして名探偵コナンをやっているような感じである。主人公は私と同じ年齢で、仕事は昼行灯。しかも一人称で書かれているものだから、時間を忘れて読みふけってしまった。後半部分は、アイザック・アシモフのミステリーSF「鋼鉄都市」に登場する刑事イライジャ・ベイリとロボット・ダニール・オリヴォーの掛け合い漫才を彷彿とさせる。文句なく楽しめる作品だ。■メーカーサイト⇒宝島社 チーム・バチスタの栄光■販売店は こちら
2006.09.23
コメント(0)
-

【高熱でガンが治る!?】体温免疫力
体温免疫力前半部分では免疫のメカニズムが図入りで説明されている。これは理科の教科書よりわかりやすい。さすがは専門家である。ただ、のっけから「どうやら鳥は、体温が41C以上ないと空を飛べないようです」(17ページ)とあり、ぶっ飛んでしまった。かなりアレゲな本である。「現代医学は、近年急速に発達したといわれていますが、それでも治せない病気や、原因がよくわからない病気は枚挙に暇がありません」(82ページ)――これはまったくその通りだと思う。その流れで、かゆみは血流が良くなっている証拠なので放っておけばよい、というのもわかる。後半部分で、次第にアレゲになってくる。高熱で癌が「スパッとがんがなくなる」(110ページ)とか、「五十肩のほんとうの原因」は「いつも片側だけを下にして寝ているため」(139ページ)とか――他の場合、他の原因を無視した主張が並び、気をつけていないと著者の論法に巻き込まれてしまう。一線を超えてしまった専門家の著作として、興味深く読ませてもらった。■出版=ナツメ社■販売店は こちら
2006.09.19
コメント(0)
-

【次のデジカメを買う前に読むべし】デジタルカメラのしくみ
デジタルカメラのしくみデジカメの機能・性能が体系的に整理されている。すでにデジタルカメラを利用しており、2台目、3台目の購入を検討している方、いま所有しているデジカメで最高の画像を撮影したいという方にお勧めする。デジカメの歴史や、デジカメを構成する部品――レンズ、シャッター、撮像素子(CCDやCMOS)、メモリカード――の原理・方式の解説からはじまり、デジカメ内部でのソフトウェア処理の目的、JPEGやRAWの原理、Exif・DCFといったフォーマットの形式など、デジカメの機能・性能の細かいところまでよくまとまっている。これを理解できれば、「なぜデジタル一眼が求められるのか」の理由も分かるし、強いてデジタル一眼でなくても良い場合があることも分かる。デジカメのカタログ・スペックの読み方も変わってくるだろう。■メーカーサイト⇒日経BP出版センター デジタルカメラのしくみ■販売店は こちら
2006.09.16
コメント(0)
-

【動いているものを、止まって撮る】デジタルビデオ・メイキング
デジタルビデオ・メイキングデジタルビデオの機材の選び方から、撮影、編集、公開方法に至るまで、具体的にわかりやすく解説されている。「動いているものを、止まって撮る」(94ページ)というのが、ビデオ撮影の基本ポリシーだと思う。とくに子どもの撮影をする場合は、相手が勝手に動いてくれるので、こちらは不動の構えで撮影に当たるべきである。もっとも、子どもが大きくなってくるにしたがって運動量も増え、フレームアウトしてしまうことがあるわけだが、その辺は子どもの常日頃の行動を観察し、フレームのセッティングを考慮しなければならない。いずれにしても、行き当たりばったりで撮影するのは難しいということだ。■メーカーサイト⇒アスペクト デジタルビデオ・メイキング■販売店は こちら
2006.09.07
コメント(0)
-
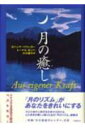
【月のリズムはトンデモか!?】月の癒し
月の癒し本国ドイツで300万部を売り上げたそうであるが、いわゆるトンデモ本である。どのような原因で月が身体に影響を及ぼすかは、一切書いていない。けれども、今日は満月だから何をやろうとか、今日は新月だからやめておこう、という自然のリズムを取り入れることはいいことだと思う。少なくとも、朝夕を無視し、四季を無視し、ひたすら原子時計が刻むタイムスケジュールに追われる生活よりは人間的であると思う。■メーカーサイト⇒飛鳥新社 月の癒し■販売店は こちら
2006.09.02
コメント(0)
-

【5色の氷がカクテルを照らす】アイスキューブ
アイスキューブ光るアイスの正体は――LEDである。電池と保冷剤が入っており、何度でも使える。アルコールが薄まることもない。しかも、常時点灯、点滅など3種類の発行パターンが用意されている。光の色は、グリーン、レッド、イエロー、ブルー、レインボーの5色。電池は交換できない。カクテルに入れてみてはいかが?■販売店は こちら
2006.09.01
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- 大好き!デジカメ!
- 10年以上昔のコンデジに復活の日を
- (2025-11-12 07:20:04)
-
-
-

- パソコンニュース&情報
- ブラウザChromeの新機能 "ページを音…
- (2025-11-03 10:02:13)
-
-
-

- アイフォン・アイポッドの必需品
- スティーブ・ジョブズの死に際に発し…
- (2025-07-14 03:41:24)
-







