2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年09月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
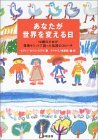
あなたが世界を変える日
1992年の6月11日、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで、国連の地球環境サミットが開かれました。そこで、カナダ人の12歳の少女セヴァン・スズキが、世界各国の首脳を前にして、わずか6分間のスピーチをしました。その言葉は、人々の強い感動を呼び、世界中をかけめぐり、いつしか「リオの伝説のスピーチ」と呼ばれるようになりました。あなたはこのスピーチを聞き、何を思いますか?(できれば、ぜひ一度、声を出して読んでみてください。)「あなたが世界を変える日」 セヴァン・カリス=スズキ著 (学陽書房)こんにちは、セヴァン・スズキです。エコを代表してお話します。エコというのは、子ども環境運動の略です。カナダの12歳から13歳の子どもの集まりで、今の世界を変えるためにがんばっています。あなたたち大人のみなさんにも、生き方を変えていただくようお願いするために、自分たちで費用をため、カナダからブラジルまで1万キロの旅をしてきました。今日の私の話にはウラもオモテもありません。なぜって、私が環境運動をしているのは、私自身の未来のため。自分の未来を失うことは、選挙で負けたり、株で損したりするのとはわけが違うんですから。私がここに立って話をしているのは、未来に生きる子どもたちのためです。世界中の飢えに苦しむ子どもたちのためです。そして、もう行くところもなく死に絶えようとしている、無数の動物たちのためです。太陽のもとにでるのが、私はこわい。オゾン層に穴があいたから。呼吸をすることさえこわい。空気にどんな毒が入っているかもしれないから。父とよくバンクーバーで釣りをしたものです。数年前に、体中ガンでおかされた魚に出会うまで。そして今、動物や植物たちが毎日のように絶滅していくのを、私たちは耳にします。それらは、もう永遠に戻ってはこないんです。私の世代には、夢があります。いつか野生の動物の群れや、たくさんの鳥や蝶が舞うジャングルを見ることです。でも、私の子どもの世代は、もうそんな夢をもつこともできなくなるのではないか?あなたたちは、私の歳ぐらいのときに、そんな心配をしたことがありますか?こんな大変なことが、ものすご勢いで起こっているのに、私たち人間ときたら、まるでまだまだ余裕があるような、のんきな顔をしています。まだ子どもの私には、この危機を救うのに何をしたらいいのかわかりません。でも、あなたたち大人にも知って欲しいんです。あなたたちも良い解決法なんて持ってないっていうことを。 オゾン層にあいた穴をどうやって防ぐのか、あなたは知らないでしょう。死んだ川にどうやってサケを呼び戻すのか、あなたは知らないでしょう。絶滅した動物をどうやって生き返らせるのか、あなたは知らないでしょう。そして、今や砂漠となってしまった場所に、どうやって森をよみがえらせるのか、あなたは知らないでしょう。どうやって直すのかわからないものを、こわし続けるのはもうやめてください。ここでは、あなたたちは、政府とか企業とか団体とかの代表でしょう。あるいは、報道関係者か政治家かもしれない。でも本当は、あなたたちも、誰かの母親であり、父親であり、兄弟であり、おばであり、おじなんです。そして、あなたたちの誰もが、誰かの子どもなんです。私は、まだ子どもですが、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知っています。そうです、50億以上の人間からなる大家族。いいえ、実は、3千万種類の生物からなる大家族です。国境や各国の政府がどんなに私たちを分けへだてようとも、このことは変えようがありません。私は子どもですが、みんながこの大家族の一員であり、ひとつの目標に向けて心をひとつにして行動しなければならないことを知っています。私は怒っています。でも、自分を見失ってはいません。私はこわい。でも、自分の気持ちを世界に伝えることを、私はおそれません。私の国でのむだづかいは大変なものです。買っては捨て、また買っては捨てています。それでも物を浪費し続ける北の国々は、南の国々と富を分かちあおうとはしません。物がありあまっているのに、私たちは、自分の富をほんの少しでも手ばなすのが怖いんです。カナダの私たちは、十分な食べものと水と住まいを持つ恵まれた生活をしています。時計、自転車、コンピューター、テレビ、私たちの持っているものを数えあげたら何日もかかることでしょう。2日前にここブラジルで、家のないストリートチルドレンと出会い、私たちはショックを受けました。ひとりの子どもが私たちにこう言いました。「僕が金持ちだったらなぁ。もしそうなら、家のない子すべてに、食べものと、着るものと、薬と、住む場所と、やさしさと愛情をあげるのに。」家もなにもない一人の子が、分かちあうことを考えているというのに、すべてを持っている私たちが、こんなに欲が深いのは一体どうしてなんでしょう。これらの恵まれない子どもたちが、私と同じくらいの歳だということが、私の頭をはなれません。どこに生まれついたかによって、こんなにも人生が違ってしまう。私がリオの貧民街に住む子どもの一人だったかもしれないんです。ソマリアの飢えた子どもだったかも、中東の戦争で犠牲になるか、インドで物乞いをしていたかもしれないんです。もし戦争のために使われているお金をぜんぶ、貧しさと環境問題を解決するために使えば、この地球はすばらしい星になるでしょう。私はまだ子どもだけど、そのことを知っています。学校で、いや幼稚園でさえ、あなたたち大人は私たち子どもに、世の中でどうふるまうかを教えてくれます。たとえば、争いをしないこと、話し合いで解決すること、他人を尊重すること、散らかしたら自分で片付けること、他の生き物をむやみに傷つけないこと、分かち合うこと、そして欲張らないこと。ならばなぜ、あなたたちは、私たちにするなと言うことをしているのですか。なぜあなたたちが今、こうして会議に出席しているのか、どうか忘れないで下さい。そして一体誰のためにやっているのか。それは、あなたたちの子ども、つまり私たちのためです。みなさんはこうした会議で、わたしたちがどんな世界に育ち生きていくのかを決めているんです。 親たちはよく「だいじょうぶ。すべてうまくいくよ。」と言って子どもたちをなぐさめるものです。あるいは、「できるだけのことはしてるから」とか、「この世の終わりじゃあるまいし」とか。しかし、もうこんななぐさめの言葉さえ、使うことができなくなっているようです。お聞きしますが、私たちこどもの未来を真剣に考えたことがありますか?父はいつも私に不言実行、つまり、何を言うかではなく、何をするかでその人の値打ちが決まる、と言います。しかし、あなたたち大人が、やっていることのせいで、私たちは泣いています。あなたたちはいつも私たちを愛していると言います。しかし、言わせてください。もしそのことが本当なら、どうか本当だということを、行動でしめして下さい。最後まで私の話を聞いてくださって、ありがとうございました。この本にはまだ続きがあります。ぜひ手にとってお読みになっていただければ、みなさまお一人お一人の心の中にこの話の続きが湧き上がってくることでしょう。ぜひ一人でも多くの(大人の)方にお読みになっていただきたいと思います。そして、ご自分の子どもや、みなさまの周りに居る子どもたちにも読んでもらいたいです。そして、一緒に環境問題について話し合ってみていただきたいです。子どもたちは、どのようにとらえ、どのように感じているのか。それを、大人たちは、どのように受け止め、どのように行動で示すのか。素敵な人との出合いに感謝します。素晴らしい本との出合いに感謝します。ありがとうございます。
2006/09/28
コメント(14)
-
知らないことを知ること、それが世の中を変える第一歩。
昨日まで仕事の関係で三日間ほど勉強に行ってきました。その中で、環境ジャーナリストの方の講演を聴いた時、久しぶりに衝撃を受けました。一体、自分は今、何をしているんだろう.....。9年前、食品業界の裏側を垣間見て、とんでもない社会の実態に気がついた。そして、今の仕事にご縁し、すばらしい人たちと出会い、たくさんの本を読み、多くの学びをいただいてきた。地球の環境のこと、食の現場のこと、農業のこと、学校教育のこと。そして、政治、経済、宗教、文化などあらゆることに関心が向くようになった。それまで無知・無関心だった僕は、スポンジが水を吸うかのように、いろいろな知識や経験を、スーッと身に付けることができた。あの頃は..........。自分で言うのもおかしいが、そこには光り輝いていた自分があったように思う。輝きがあったかどうかは別としても、一生懸命で、そこには情熱があった。では、今の自分はどうであろう。ぬるま湯にどっぷりと浸かり、小手先だけの気持ちの篭ってない仕事ぶりではなかっただろうか?周りの雰囲気に流され、仕事の惰性に流され、あの頃の情熱を失ってしまっていた。1000日修行と題し、自分を改めようと取り組んでは見たものの、あっという間に挫折状態。現実は、目先の日々の売り上げの増減に囚われ、仕事の喜びすら無くしてしまっていた。仕事=志事、そして、仕事=人生。そんな想いの中で続けてきた事業に、少し自信を無くしていた。信頼していた仲間や、信じていた恩師たちが、お金に狂っていく姿を見るうちに、人間不信に陥りかけていました。どんなにすばらしいことを言っても、所詮お金がすべての人間たちなんだ...と。でも、思ったんです。もしかしたら、神様は「私自身の姿を、鏡(仲間、恩師)に映してくれた」のかも知れない、と。そう、偉そうなことを言いながら、お金に執着してるのは”自分”ではないのか!?他人を軽蔑する前に、自分自身の姿をもう一度よく確認する必要がある、そんなことに気がつきました。カッコつけた言い方ですが、「何のために生きているのか」、そんな問いを自分に投げかけながら、今の自分の姿を恥ずかしく思いました。地球の環境が、今どれほどひどい状態になっているのか?私たちは、真実から目を背けようとしています。いえ、背けながら生きているのが現実でしょう。所詮は、他所の国の出来事、自分たちにはとりあえず関係ない。温暖化? オゾンホール? ダイオキシン? 環境ホルモン?テレビも最近言わなくなった?そうではないんです。地球を取り巻く環境は、深刻の一途をたどっています。人類の滅亡?そんなマンガのような話、信じれませんよね?しかし、絶対にあり得ない話と、何を根拠にあなたは言うのでしょうか?私自身、信じたくはありません。でも、ここ数年の身の回りで起こる環境の変化を冷静に捉えた時、そして、国連などの国際機関の調査結果の報告を、真剣に考えたとき、大抵の方なら、何かを感じていただけるはずである。もしかしたら.....えっ!?.....と。そう感じても、「自分には何もできない。」、それが99.9%の方々の意見でしょう。問題が大きすぎると、自分にできる問題ではないと、あきらめてしまいがちですが、そうではなく、知らないことを知ることが、世界・人類を救うことになる。初心に返って、勉強し直します。そして行動を起こします。それは、必ず人のお役に立てると確信して、自分のできることを、自分に与えられた使命として、コツコツと行っていきます。また、一人でも多くの共感し合える人たちと、生きる喜びを分かち合いたいと思います。地球の環境という大きな視点で想いをめぐらせた時、人間関係、金銭トラブル、身の回りのイザコザ、仕事のこと、病気のこと、老後のこと、家族のこと、etc.....。今はご自身にとって夜も眠れない深刻なことでも、地球規模で物事を考えた時、自分がどれほどちっぽけなことでクヨクヨしているのか、本当に馬鹿らしく思えることでしょう。今日、今、ここから、新しい自分の出発です。がんばってみます。みなさんもご一緒に。ありがとうございます。
2006/09/23
コメント(2)
-
本当の豊かさとは?
先日も触れましたが、佐藤一斎の「言志録」について、小田全宏氏の著書「日本人の真髄」の中にこんな一文がありました。分を知り、然るに後に足るを知る。貧しい人と言うのは、自分の分もわきまえず、大きな欲望を持つ人である。人間にとって理想を言えば、物質的にも、精神的にも両面で満たされた人であろう。しかし、そういう人はなかなかいない。金持ちになればなるほど、強欲になり心が貧しくなる人が少なくない。と。また、貧富を4つのパターンに分けておられます。1つは、お金があって心も豊かな人(富む人)。2つ目は、お金があっても「足りない」と常に思っている人(貧しい人)。3つ目は、お金は少ないけれども、豊かに思っている人(清貧の人)。4つ目は、本当に貧しくて心も貧しい人(極貧の人)。仏教の言葉に、「少欲知足」というものがあるそうです。欲を少なくして、足るを知る。足るを知れば、心の豊かさを体現することができるでしょうとのこと。「欲」がなければ、成長などしないとよく言われたりしますが、ここで言う「欲」は、「目標」や「希望」などに使われる意味合いのものではなく、ただ単に自己満足のにのための「我欲」に対する、「欲望」を意味するのだと思う。足りない、足りないという人の心というのは、ほとんどの場合、他との比較であり、自分とは、人生もモノの価値観も、全く違う人々を見て、ただただうらやましく思い、あれも欲しい、これも欲しいと思う、そんなところでしょう。違いますか?自分は自分、他人は他人。物質的な「欲」を満たそうと思うと、キリがないと思います。手に入れても、手に入れても、ますます欲しいという欲求が増すものではないでしょうか。大金持ちほど、欲を出しすぎて最後はすべてを失っていたりしませんか。それよりも、自分の心を満たしてくれるものは何か。自分とは?生きるとは?なんて、考えてみたとき、今の自分は、今の自分に満足できる存在なのでしょうか?外に欲求を向けるのではなく、内側に欲求を向けたとき、おもしろい自分に出会えるのかもしれません。よく、自分との戦いとか、自分との挑戦、なんて言うじゃないですか。そんな方々は、必ず自分と対話することをされています。自分との対話。なんか、宗教くさいことばかり申しましたが、私は特定宗教とはなんら関係ございませんのでご安心を。それでは、また。
2006/09/19
コメント(2)
-
細木数子も...。やっぱりテレビは腐ってる。
人は、往々にして、金や権力を持ち、他人からチヤホヤされ始めると、我を見失い始める。(いや、本性を見せ始めると言った方がいいのだろうか?)この度ようやく死刑が確定したAのような新興宗教の教祖や、今日のニュース記事に出ているような、恐怖を煽り立てて人からお金を巻き上げるエセ占い師H、現在裁判中のHのような法の抜け道と称し詐欺で荒稼ぎをしたベンチャー企業家、八百長でチャンピオンになるようなボクサーKは論外として、少なくとも、彼らの出発点には、”真実”があったと思う。そして、彼らを狂わせて行ったのは、”欲”の一文字ではないかと思う。その根底には、コンプレックスというかカルマというか、何か満たされることのない何かが存在していたのだと思う。斉藤一人氏が、著書「地球が天国になる話」の中で、コンプレックス、劣等感について話されていますが、人は生まれながらにして周囲の何かしらの要因によって劣等感を持たされているということを説かれています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、よろしければご一読下さい。今日はこれ以上触れません。あっ、で、今日は何を言いたかったかと言いますと、私は細木数子のような人間が嫌いだと言うことです。(苦笑!)だいたい、親からもらった名前を何の権利で変えさせるんですか?私の言うことを聞かなければ、死にますよ!なんてことを言う人間にまともな者はまず居ません。(これはそこらへんのインチキ宗教団体と同じです。)人生のアドバイスをする立場の人間は、必ず相手に勇気と希望を与えなければなりません。それを、このままではあなたは終わってしまうと、切り捨てるようなことを言うものは100%偽者です。なぜなら、そこに”愛”がないからです。時々、女子高生や最近の若者に、日本古来の奥ゆかしさ的なことを説教し、まともらしいことを言っている時があるけれども、一時はすばらしいと思ったこともありましたが、今思えば、ただ本を売りたいだけかと、思います。こんな腐った女を、バンバン使うテレビ局の気が知れない。どんなアホが見ていようとも、とにかく視聴率があがってスポンサーが喜べばそれで良い、そんな風にしか感じない内容である。この前の、Kのボクシング世界戦など、番組の構成はひどいものであった。あれ以来、あのチャンネルは、見る気がしない。結果、Mもんたの暑苦しい顔も見ることがめっきり減った。インターネットが通信の世界を変えるのは、もう秒読み段階だと思うが、その前にテレビで稼げるだけ稼いでおこうというところだろうか?利権にまぶりつく醜い拝金主義者たち。テレビに日本は、日本人は侵されていく。情報操作というものの恐怖を感じる日本人は少ないのかもしれない。細木数子さん猛抗議でDVDボックスから削除…「トップキャスター」第3話 今年4月期にフジテレビ系で放送された“月9”ドラマ「トップキャスター」が、1話分を丸ごと削除した形で11月15日にDVDボックス化されることが17日、分かった。削除されたのは、占い師の細木数子さん(68)を思わせるキャラクターが登場する「第3話」。放送直後、細木さん側が抗議し、フジが謝罪していた。DVD化にあたり特典映像がつくのは今や当たり前だが、1話そっくり削除という措置は極めて異例だ。 オンエア時は11話あったドラマが、DVDでは「全10話」になっていた。 「トップキャスター」は今年4~6月にかけて放送された1話完結スタイルのドラマ。天海祐希(39)がスクープを連発するニュースキャスターに、矢田亜希子(27)がアシスタント役を演じ、平均視聴率18・3%を記録。 問題の「第3話」は5月1日に放送された「恋愛運ゼロの逆襲」。人気占星術師・宮部天花(黒田福美)とキャスターの椿木春香(天海)が番組内で対立。逆ギレした天花は、春香の運勢は最悪だと言い放ち、改名をしないと運勢が変わらないなどと要求した。しかし、春香らのその後の取材によって、天花に家をだまし取られたという被害者がいることが分かり、占いもインチキだったことがバレる-というストーリーだった。 フジでバラエティー番組「幸せって何だっけ カズカズの宝話」(金曜・後7時57分)に出演している細木さん側は、自らを思わせる占い師が“悪役”で登場したことに猛抗議。抗議を受けたフジ側は謝罪した上で、パッケージ化などの際には配慮することなどを約束して和解していた。 関係者によると、ドラマ制作サイドは「第3話」もDVDに収録するよう要望したが、同局の“政治的判断”によって削除が決まったという。DVD化の際には未公開映像などの特典がつくことはあっても、1話分がまるまる削除されるのは前代未聞。フジ広報部では「今回の件で改めてコメントすることはありません。また再放送の際にどうするかはまだ決まっていません」としている。 (スポーツ報知) - 9月18日12時34分更新
2006/09/18
コメント(1)
-
歴史的和解?
お盆休みに中学時代の友達と一杯やりました。彼らとは、年に1、2度は酒を飲むのですが、その集まりが実にすばらしい。(と、思う。)だいたいスタートはお決まりのメンツ5~6人で始まるのですが、酒が進むにつれ、「あいつも呼ぼう、こいつも電話しよう」と、数時間後にはその店の部屋では入りきれない人数になるのです。前回の時は終わり頃には20人は十分越えていたと思う。ちょっとした同窓会である。(男ばかりであるが...^_^;)私は、高校になってから、中学時代に過ごした町からは引っ越したために、仲間とは少し離れた所に住んでいましたが、突然の思いつきの呼び出しに、これほどの人数が集まることがうれしくてたまりません。今年で38歳。中学を卒業して、もう23年が経つ。白髪まじりのおっさんが、当時と変わらないテンションで盛り上がる。いや、当時はこんな風にはお互い話ができなかったかな?(なんせ私たちは危ない?人々でしたから.....^_^;)38にもなると、お互いもう立派な大人で、もう当時のことは懐かしい笑い話である。何十年ぶりかに会っても、こうして何事もなかったかのように、溶け合うことのできる友がいて、本当に幸せだと思います。実は、今回は、少人数で飲んだのだが、歴史的和解???が生まれました。(苦笑!)お恥ずかしい話なのですが、実は中学卒業前に、あるやんちゃな同級生を、当時やんちゃな僕は、ボコボコにしてしまったのであります。(反省!)それ以来、同窓会があっても、飲み会があっても、彼の姿を見ることはなかったのですが、今回の飲み会で、「Y」を呼ぼう!という話の流れになり、あせる私を尻目に「Y」に電話。「どんな顔して会ーたらええんじゃ~!!!」と、慌てふためくのもつかの間、「Y」登場。私の第一声。「おー!!!久しぶり~。あの時はすまんかったの~。」(冷汗!)握手でお互いの再会を祝うも、何かぎこちない「私」。「Y」はどう思っていたかは分からないけど、お互い、久しぶりの再会を喜べたのではないかと、照れ臭いながらミョーに喜ぶ私。いやいや、懐かしい友に会って、うれしくない奴はあまり居ないと思う...。たぶん。(^_^;)友としか味わうことのできない独特の時間がある。その懐かしさの中に、自分の歴史を見るようで、自分の存在が確認できるのかも知れない。確かにそこには友としか味わえない空間がある。ちょっと前にブログにつづった、昔の歌の歌詞。ひとりまたひとり 友は集まるだろうひとりまたひとり ひとりまたひとり何とも心に沁みる素敵な歌詞である。そしてもう一つ。その仲間の一人が、長年付き合った彼女との結婚を決意し、それまで彼のポリシーとも言える、長い髪をばっさり切り落とし、音楽フリーター?をやめ、就職を果たしたのである。(音楽フリーターと言っても、岡山じゃ超有名らしい。)これには感動した。大切なもののために、一つの道を選ぶ。身近な者の出来事であっただけに、とてもうれしかった。ちかちゃんと言うとても素敵な彼女で、本当に幸せになって欲しいと思う。かんちゃん、がんばろうな!応援するで!と言うことで、最近あった、心温まる?エピソードでした。そんなこんなで、同窓会企画がモッコリ浮上したのかもしれません。がんばって成功させたいと思います。
2006/09/15
コメント(0)
-
懐かしい友に会えるかも!「この指とまれ!」
この度、中学校のときの同窓会をすることになりました。先日、数人のメンバーでイッパイやりながら打ち合わせ、いや? 打ち合わせをしながらイッパイ?いやいや? イッパイやるついでに打ち合わせ?(そもそも居酒屋で打ち合わせすること自体間違い? ^_^;)まぁ、とにかく、どうするよ? と、集まったわけでありますが、その席で、こんなおもしろいサイトを教えてもらいました。「ウェブ同窓会 この指とまれ!」全国の様々な同窓生が参加できるウェブサイトで、地域から自分の卒業した学校などを検索していくと、参加者(登録者)の名前がボヨヨォ~ンっと出てきます!そこには、見覚えのある名前がチラホラと。中にはめちゃくちゃ懐かしいやつの名前も出てたりするのでケッコー感動的です!まだ、使い方がよく分からないのですが、とりあえず登録して転校する前の小学校・卒業した小学校・中学校・高校・大学までちょっと欲張って登録してみました。そっ、そこには~!!!なっ、なんとぉ~!!!.........。(ここから先はご想像にお任せします。(^^♪)ウェブを通じてメールもできるらしいので、”嫌われてたり””忘れられたり”してなければ、数十年ぶりのコミュニケーションがとれるかもしれない!!??いやいや、俄然たのしくなってきちゃいました。(*^^)vと言うことで、この「ゆびとま」、お勧めいたします。同窓会やって、青春の1ページを思い起こしてください。ハイハイ!今年のお正月はみなさんで同窓会やりましょう!
2006/09/14
コメント(0)
-
夜回り先生の話 ~笑顔あふれる町づくり~
夜回り先生 水谷修先生のお話の中で、講演の最後にこんなエピソードをお話くださいました。ある中学校で、薬物予防の講演に行った時、講演終了後、一人の生徒さんが質問をされたそうです。「先生、私たちに悪や薬物の魔の手がこないようにするにはどうしたらいいのですか?」先生は、このように答えられました。「お前いい質問だなぁ。それはね、笑顔だよ。笑顔があふれる家庭や学校、地域に、薬物や悪なんかくるものか。」すると、もう一度その生徒さんから質問が。「どうしたら、笑顔があふれるようになるんですか?」先生は、例え話を交えながら、こう話されました。「それはね、挨拶だよ。家族や友達はもちろんのこと、道ですれ違った人や、町であった人たちと、おはよう、こんにちは、元気かぁ、と声を掛け合うことだよ。 」と。その講演の後、その中学校では、卒業までの1ヶ月の間、「クラス対抗あいさつコンクール」というのを始めたそうで、どのクラスが一番多くあいさつをしたかを競う競争をしたそうです。「今日は学校に来るまでに、50回あいさつしたぞ。」とか、「俺なんか、駅の改札で来る人みんなにあいさつして300回だ。」と言う風に。そして、しばらくして、学校宛に一通の手紙が届いたそうです。その内容は、ご近所の身寄りのないお年寄りが、一人寂しく生活する中で、朝掃除をしていると、通学途中の生徒さんがみんな「おはよう!」と声をかけてくれる。時には、ごみを運んでいると、「おばあちゃん、持ってあげるよ。」と、ごみを捨てるのを手伝ってくれたりした。それが、まるで孫でもできたようで、うれしくてうれしくて心に花が咲いたように温かい気持ちにさせていただいた。本当にありがとうございました。と言うものでした。水谷先生が生徒さんにおっしゃったことが、現実のものとなったのです。本当にすばらしエピソードだと思いました。明るいあいさつというものは、本当に気持ちの良いものです。私も、犬の散歩の際に、学校帰りの子どもたちや、すれ違う方々にできるだけ声を掛けるようにしています。中には、返事が返ってこない場合もあります。でも、きっと声を掛けられた子どもには、何かが伝わっていることと思います。そう信じています。私も、不意にすれ違いざまにあいさつをされた時に、とっさに声が出ない時があります。でも、声を掛けられた方の立場としては、何か心温まる思いが湧いてきます。そうですよね。良い地域社会を作るのに、そんなに特別なことは必要ないのかもしれません。日々のあいさつや、声掛けというものを大切にするだけでも、笑顔あふれる、心豊かな街づくりはできるのかもしれませんね。おかしな話ですが、あいさつって、やってみると、案外勇気が要るのもです。私も始めはそうでした。返事が返ってこなかったりすると、一人恥ずかし思いをしたりしてました。でも、こうして子どもたちに良い地域社会を残そうと目的をもって取り組んでみると結構がんばれるものです。そしてそれは次第にごく当たり前のように、自然にできるようになってきます。そうした大人の姿を見て、子どもたちも同じようにあいさつをするようになります。それは、本当にほほえましく、町の人々の心に、ポッと暖かい灯を灯してくれます。日ごろのあいさつや声掛け、本当に大切なことだなと思いました。
2006/09/12
コメント(8)
-
夜回り先生 水谷修先生
昨日、夜回り先生こと”水谷修先生”の講演を再び聴く機会が持てた。(前回の感想はこちらと、こちら。)今回は、女房・子供を引き連れ、家族全員で参加させていただいた。前回とほぼ同じ内容のお話であったが、その真剣な生き様に、改めて胸が熱くなった。その話の中で、福山市の薬物汚染の状況を聞き、これほどまで酷いものかと絶句する思いであった。広島市内での暴力団取締り規制の反動が、東へ流れてきており、しまなみ街道を経由して、四国から流れてくる勢力と混ざり、今、福山エリアが最も暴力団による、薬物汚染、売春、武器流通等の中心地として危険度が高まっているらしい。だが、こうした子供たちへの危険性は、福山だけでなく、全国的な広がりをみせているらしく、今の子供たちが、どれほどひどい環境にさらされているのか、子供を持つ親としてはぜひ時間をとって真剣に考えてもらいたいと思う。”麻薬(薬物)”と聞いて、「うちの子に限って...。」と思っている親が9割以上であろう。しかし、子供たちの世界では、かなりの割合で、その名前を耳にした経験があり、中には同級生の子が使用しているという場合もごく当たり前のようにあるという。”リストカット”と聞いて、「当然、我が家には無関係。」と思われる親がほとんどであろう。しかし、リストカットをしている子供が”いない学校”は、もう日本中に”無い”と言われているそうだ。当然、このような話を聞いても、ほとんどの人は実感として湧いてはこないであろう。それが普通である。しかし、現実に、これほど多くの子供たちが、悩み苦しみ、自らの命を絶とうとしている。他人事では済まされない現実がある。明日は我が身であるという覚悟が必要な時代である。私たち大人が、どうのようにこの現実に向き合うか、問われている。子供たちの明日を、日本の明日を、今、真剣に考えなければならない、そのことがどれほど重要なことか、理解できる大人が一人でも増えることを水谷先生は、その命を削りながら訴えて全国を講演されておられます。子どもの非行と聞いて、「そんなもの大人になったら治るよ。」と思っている大人の方、今は、ひと昔とは非行の”ありよう”が違うようです。私たちは、放っておかれても大人になるにつれて自然に社会に戻ってこれたかもしれません。しかし、今の子どもたちは、薬物にその体を蝕まれ、また、売春によりHIV(エイズ)のような死に至るような病気をもらうこともあるのです。それらは、子どもたちの責任でしょうか?いいえ、決してそんなことはありません。私たち大人が、子どもたちを非行に走らせないだけの愛を持って、子どもたちと接していなかったことが、そもそもの原因ではないでしょうか。その自覚すら感じられない大人が、今の日本社会を作りました。日本という国は確かに”物質的には”世界トップレベルで恵まれた国です。しかし、マザーテレサが来日した時に言った、「日本という国は本当に物質的には豊かな国です。でも精神的には貧しい人たちです...」という言葉が表すように、あまりに他人に対して無関心で冷たい人になってきました。それは、他人だけでなく、わが子に関しても言える事なのかも知れません。水谷先生の本の中に、こんな一節がありました。「子どもというのは、受けた愛の数が多ければ多いほど非行から遠ざかり、受けた愛が深ければ深いほど非行に入ってもその傷は浅い。」子どもに対する真の愛とはどのようなことか、今一度、大人として、社会の一員として、深く考える必要があると思いました。
2006/09/11
コメント(3)
-
佐藤一斎 「言志四録」
少く(わかく)して学べば、則ち(すなわち)壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち(すなわち)老いて衰えず。老にして学べば、則ち(すなわち)死して朽ちず。何年か前に、小泉首相が取り上げたことで有名になった言葉ですが、佐藤一斎という徳川時代の儒者の残した「言志四録」という書物の中の一節で、要は、生涯学び続けることの大切さを説いた言葉である。人は、歳をおうに連れて、勉強をしなくなる。だんだんと自分の持つ固定観念の中で、自らの世界観を持ってしまう。自分を無知な存在として、謙虚に学ぼうという向上心が薄れてくる。現実は自らの日常生活に追われ、それどころではないという人が大多数である。一方で、自己啓発書や宗教などに溺れ、頭でっかちになり、大人物気どりのバカもいる。どちらかと言うと、私なんぞはこちらの”勘違いバカ”の部類に入るのだが、こちらも低レベルで、どちらかと言うと逆に口だけ達者でやっかいな存在かもしれない。(苦笑!)こうして見ると、やはり、謙虚な学びと現実社会の中で真剣に生きるバランスを持った人が、誰からも信頼を得ることのできる 「人物」 であることは一目瞭然である。日本に生まれ、これほど豊かな時代に育ち、なぜそんなに悩み苦しむ必要があるのか?そこには常に他との比較の中で、”自分を卑しめる自分”が存在するのではないだろうか?自分の生き様を貫くだけの強い心。今の学校教育、社会生活の中には、こうした人間を学ぶという分野が無い。今日、様々な自己啓発に関する本が販売されるようになり、良く売れているということはそれだけ学びを求めている人が増えたと言うことなのか?それとも、ただがむしゃらだけでは生きていけないこの時代に、生き方の質というものを求める人が増えてきたと言うことであろうか?いずれにせよ、時代は「物質中心」から「精神中心」に確実に移り始めている。「モノの時代」から「心の時代」に変わったと言える。こういう時代だからこそ、「言志四録」のような、生き方の真理を説いた書物にスポットライトがあたるのかもしれない。「人間学」とよく言われるが、要は「自分を作る」ために「いかに生きるか」ということを学ぶ学問であり、それは、先人たちの歩んできた道を知ることであり、優れた人物の生き様から学ぶということである。今世の中は、大資本を持った企業のみが”勝ち組”と評されているが、リストラ、自動化、派遣社員の多用等により、「人を育てる」ということが失われている。多くの企業はそれに気づきつつも、業績向上のために、まだまだ転換できずにいる。このままでは、手遅れになる。人を育てることをやめ、教育にお金をかけることをやめ、このままでは必ずや日本という国は滅び行くであろう。その時にあわてなくてもよい自分を作ることが、今各々に必要な時代であると思う。あせらず、あきらめず、こつこつと自分を作ってきた人が、最後には多くの人を救える存在として生き残るのだと思います。
2006/09/08
コメント(4)
-
日木流奈君の詩
ボクが戦ってきたのはだれだろう他人に嫉妬したり比較して優劣を競ったり外に評価を求めたり絶対的価値は自分の中にあるというのにボクは相対的なものばかり求めていた戦う相手を外に求めていた間はボクの進歩は止まっていた挑む相手を自分の中に見つけたときボクは永遠という時の中で天に向かって歩むことを許されたのだこの詩は、日木流奈君という重度の脳障害を持った少年が書いたものである。現在彼は15歳だと思うが、これまでにも何度かテレビでも放映され話題となったことがある。歩くこともできなければ、しゃべることも、書くこともできない。文字盤を指差しながら自分の思いを伝えるしか方法がない。それでも、唯一の趣味であるという読書の中から、驚くほどの知識を得、自らのメッセージとして人々に感動を与えている。「絶対的価値は自分の中にある」人々がこの言葉の意味に気づいたとき、大きな前進を始めるのではないかと思う。まさに、「天に向かって歩むことを許される」のだと思う。人生で起こる出来事にはすべて意味がある。私たちは、不幸な状況やつらい立場に立たされた時、嘆いたり悔やんだり、時には人を羨んだり憎んだりする。頭の中では、様々な自己啓発の言葉を知っていても、なかなか「頭では分かっているのだが...」という域を出ることができない。そのために天は私たちに気づきのためのチャンスとして、様々な試練を与えられるという。それらの苦難や試練を、否定して生きるのではなく、受け入れることができた時、人は飛躍的に前進し、そこからまた新たな展開が始まる。と、私の好きな神渡良平先生の本にありました。結局、人生とは、自分の心のおきどころひとつということですね。「絶対的価値は自分の中にある」すばらしい言葉です。
2006/09/07
コメント(2)
-
2:6:2の法則
2:6:2の法則と言うものがあります。人間を始めとし、生き物が集団を作ると、その内の2割が生産性の高いすばらしい働きをし、真ん中の6割は何となく周りに引っ張られるように働き、残りの2割は、あまり役に立たない存在であるというもの。 微生物の世界にもこの2:6:2の法則が存在します。善玉菌と呼ばれる人間の健康にとって大変役に立つ”良い菌”が2割、悪玉菌と呼ばれる病気や腐敗の原因となる”悪い菌”が2割、そして日和見(ひよりみ)菌というどっちつかずの菌が6割、という比率です。この絶妙なバランスの中で、自然界は成り立っています。 この中の日和見菌、どっちつかずと言いましたが、正確には強い方の味方。善玉菌の勢力が強くなると、善玉菌の働きをし、悪玉菌の勢力が強くなると、悪玉菌の働きをするという、何ともズルイ奴ら。 でも、よくよく考えると、人間界もまさに同じですね。ほとんどの人は、勢いのあるものや、流行り廃りに流されて生きているだけです。それをズルイとは言いませんが、もっと確固たる自分を持たなければ世の中を良くする事はできないのかも知れませんね。 私は、今の日本社会が悪い勢力、悪い風潮に呑み込まれて行っているように思えてなりません。6割の日和見勢力(自分の意見を持たない人々)が、赤信号みんなで渡れば...という感じで、「どーせ俺一人が頑張ったって世の中変わりはしねーよ!」「なんで俺ばっかり我慢しなくちゃいけないんだ!」、という否定的、かつ、あきらめ的な感覚を持ち始めてしまっているのではないかと危惧しています。 しかし、その反対に、本当に世の中を良くしようという人々が、2割を超えたら、その6割の日和見が味方してくれるのではないかと思うのです。過半数、5割以上を変えようとするから、果てしない不可能のような目標に思えるかも知れませんが、2割程度が目標であれば、やれる気がするのではないでしょうか。 少し話の角度を変えてみますが、これは、健康の話でも言える事なのです。2割の健康体をがっちりガードできれば、8割の健康状態が作れると言えます。例えば、腸の中は微生物がいっぱいです。ビフィズス菌や乳酸菌が優勢な腸内環境であれば、栄養の吸収、老廃物の排泄がしっかりできとても健康的でいられるでしょう。しかし、食事のバランスが悪かったり、運動不足であったり、薬に頼った生活をされていると、たちまち腸の中は悪玉勢力が強くなり、様々な病気を生み出す原因となります。パーフェクトにしようと思おうから無理が出て、それが逆にストレスになったりするのではないでしょうか。2割の健康をしっかりと維持するための食事のバランスと、生活のリズムを考えてそれを目標に健康づくりを心がけられれば、無理なく続けられるのではないでしょうか。継続は力なり!(私が言っても説得力に欠けますが...^_^;)健康でなければ、強い意思は生まれてきません。強い意志を持たなければ、周囲を動かすことはできません。周囲を動かすことができなければ、世の中を変えることは不可能です。って、そんな大それた事をする必要はありませんが、一人でも多くの方々が、健康な体と、健康な心を持つことが、結局は世の中を良い方向に導いていくのではないかと思います。そのためには2割、そう、2割の自分を磨くことを目標にがんばってみてはいかがでしょうか。そのくらいなら、継続することができ、実現させることができるのではないでしょうか。2割の自分が変わることで、周りも(6割?)変わります。自分が変われば、周りも変わる。 ↑ ↑ ↑ ポチッとな。なんだかかなり強引な話のまとめとなりましたが、今日はこの辺で。
2006/09/06
コメント(0)
-
西郷隆盛の言葉
先日読んだ本で感じたこと。上に立つ者、下に臨みて利を争い、義を忘るるときは、下みなこれに倣い、人心たちまち財利に走り、卑吝の情日々長じ、節義廉恥の志操を失い、父子兄弟の間も銭財を争い、相讐視するに至るなり。かくの如くなり行かば、何をもって国家を維持すべきぞ。(西郷南洲遺訓 16条より)(訳)上に立つ者が下に対して利益のみを争い求め、正義を忘れるとき、 下の者もまたこれにならうようになって、みな私財に奔走するようになる。 卑しくけちな思いが日々増長し、節義廉恥の操を失うようになる。 親子兄弟の間も財産を争い敵視するようになる。 こうなったら、何をもって国を維持することができようか。これは、西郷隆盛が、幕末の儒者・佐藤一斎が著した「言志四録」を元に自らの学びとして書き記したものの中の一節ですが、世の中の真理をよく表していると感心した。いつの時代も、私利私欲に我を見失い、目先の欲望のままに行動する人間はいる。公務員、政治家、会社の代表、グループのリーダー等々、自分のおかれた”公的”立場というものを考えず、自らの欲望に従って、その特権を”悪用”する。そんな人々が実に増えてきたように思う。”公(おおやけ)”の立場という自覚を、また、その生き方を、人の上に立つ人々が持てなくなって来ている。明治維新の頃には、「この国をどうするか」という命題に、多くの「志士」たちがその命を捧げた。今、そんな「人物」が、日本にいるだろうか?話は変わるが、戦後アメリカが、二度と日本を立ち上がれなくするために行ったとされる「日本弱体化計画」というものがある。その中に、「3S政策」というものがあり、その内容は「セックス、スポーツ、スクリーン」の三つだそうだ。セックスにおぼれさせ、スポーツに興じさせ、テレビで洗脳する。まさにこれが本当であれば、アメリカの思う壺に完璧にはめられていると思うのは、私だけではないだろう。特に、メディアの情報操作はひどいの一言である。今のテレビは、見れば見るほど”バカ”を増やすものばかりだ。(と言っても、私もそのバカの一人であるのだが...^_^;)日本は今、取り返しのつかないところまで来てしまっているのかもしれない。自分の身の回りにも、不道徳な大人たちがウジョウジョしている。犯罪は、加害者よりも被害者の方が、精神的ダメージをひきずりやすいと言うが、まさに今の社会は、悪意に満ちた勢力が強くなりすぎ、その勢いに多くの人々が呑み込まれていっているように思えてならない。それが犯罪であろうが何であろうが、「やった者勝ち」の世の中である。そんな世の中が続くはずがない!そう信じながら、今夜も一杯の焼酎を片手に、負け犬の遠吠えなり。(こんな私でゴメンナサイ。切腹~♪ .....ふっ、古すぎ?^_^;)
2006/09/04
コメント(2)
-
生まれ来る子供たちのために
生まれ来る子供たちのために作詞 : 小田和正演奏 : Bank Band多くの過ちを 僕もしたように 愛するこの国を 戻れない もう戻れないあの人が その度に許してきたように僕はこの国の明日をまた想う広い空よ僕らは今どこにいる頼るもの何もないあの頃へ帰りたい広い空よ僕らは今どこにいる生まれ来る子供らのために何を語ろう君よ愛する人を守りたまえ大きく手を広げて子供たちをいだきたまえひとりまたひとり友は集まるだろうひとりまたひとりひとりまたひとり真っ白な帆を上げて旅立つ船に乗り力の続く限り二人でこいでいくその力を与えたまえ勇気を与えたまえ何となく借りた「Bank Band」のシングルCD「to U」。そのカップリングの中に入っていた一曲。昔大好きだった、小田和正ひきいるオフコースの曲。私が、中学生くらいの頃の曲だった。もう25年以上も前の曲だ。懐かしさの前に、言葉に出来ない感情が込上げてきて、涙が溢れた。何だろう?この気持ちは?当時はこれほど深く心に響いてはいなかっただろう。今、自分の無力さに言い知れぬはかなさを感じ、またその一方で、多くの友の心の温かさを心の底からありがたく想う。ひとりまたひとり友は集まるだろうひとりまたひとりひとりまたひとり僕は一人ではない。心安らぐひとときをともに出来る友がいることを、本当にありがたいと思った。そして、その友のためにも、この国のためにも、僕を産み育ててくれた両親のためにも.....、そして愛する子供たちの未来のためにも、大人としての果たすべく義務はなんであろう、と、再び失望の中に希望の必要性を強く心に感じた。出来ることは人それぞれ違うけれども、子供たちが夢を描ける世の中を作る努力を私たち大人があきらめてしまってはいけない、そう、ふと感じた今日でした。長い間、さぼってしまい反省していますが、あえて今日、誰にもお知らせすることなくまた、できることから一つずつ始めてみようと思います。温かく見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。皆様の温かいお気持ちは、痛いほど感じておりました。心より、深く深く感謝申し上げます。ありがとうございます。
2006/09/02
コメント(3)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2025-11-13 21:04:35)
-
-
-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇
- 【ウエルシア・ウエル活】WAON POINT…
- (2025-11-16 06:00:05)
-
-
-
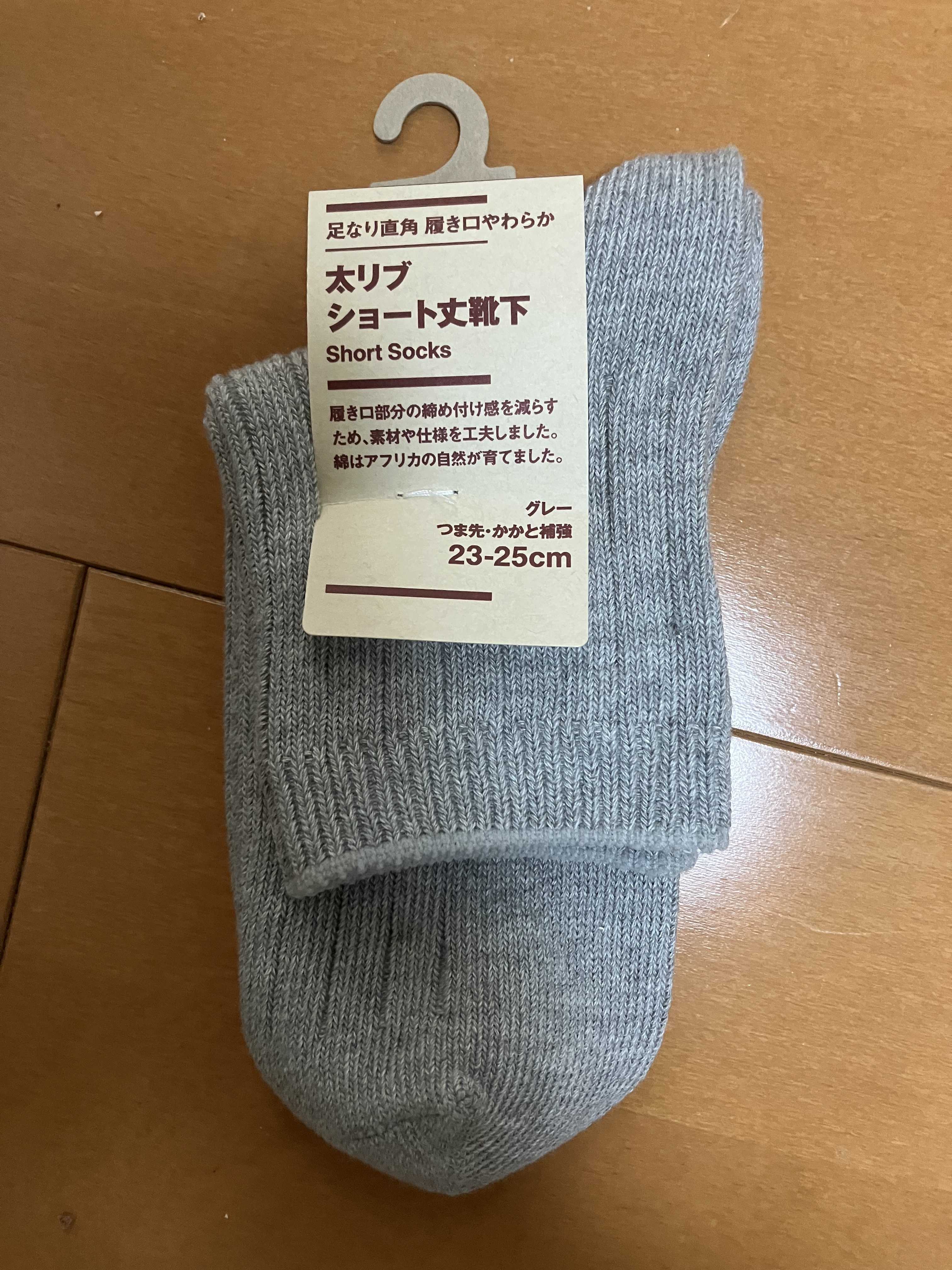
- 大好き無印良品
- ローソンで無印良品の靴下
- (2025-11-18 01:07:07)
-







