2016年09月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

偐万葉・ビッグジョン篇(その33)
偐万葉・ビッグジョン篇(その33) 本日は、シリーズ第268弾、偐万葉・ビッグジョン篇(その33)と致します。 <参考>過去のビッグジョン篇はコチラから ビッグジョン氏ブログはコチラから 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌22首並びに歩麻呂が詠める歌2首鼻ぐりの 塚はわれ見ず 成親と 細谷川の 歌碑にまぎれて (勘ぐり家持) (注)成親=なりちか。藤原成親。平重盛の妻・経子の兄。後白河院の側近。平 家打倒の陰謀・鹿ヶ谷事件で逮捕、備前に流され、其の地で死亡。 細谷川=ほそたにがわ。岡山市の吉備津神社近くを流れる小川。古今集など に歌われる。 まがねふく 吉備の中山 帯にせる 細谷川の 音のさやけさ (古今集1082) (鼻ぐり塚) 歩麻呂が追和せる歌1首ああブログ インターネットの 世は狭し 君もブロ友 我もブロ友 (注)上の歌は偐家持の下記歌(「偐万葉・ビッグジョン篇(その32)」所収) に追和せしもの。 ああ大和 はつ夏の風 光降り 此処もコクリコ ナガミコクリコ (与太野晶子) (本歌)ああ皐月 仏蘭西の野は 火の色す 君も雛罌粟(こくりこ) 我も雛罌粟 (与謝野晶子「夏より秋へ」)しかじかと 我はききたり 君が言ひ しかれどこのしか すべりたりしかと (注)鹿5頭を詠める歌な恋ひそ あはぢしまにも つぎつぎて のちもあはむと あふひの咲けば (タチアオイ)会津嶺(あひづね)に あふひの花の 今咲けど またもあはめや 昔の人に (本歌)梨棗(なつめ) 黍(きみ)に粟つぎ 延(は)ふ葛の 後も逢はむと 葵(あふひ)花咲く (万葉集巻16-3834)チューリップの 花のやうなる パプリカの たははにとれて 面目もあり (畑の歩麻呂) (パプリカ)神々の 遊べる庭に 咲く花と われも遊ばな 蝶ともなりて (蝶家持)かなかなと かなしき声の ひぐらしの 声を聞きつつ この日暮らさな (偐蝉丸)わが背子は 荒地の山に 山菅の 花を見つつや 今か行くらむ (本歌)愛(かな)し妹を いづち行かめと 山菅(すげ)の 背向(そがひ)に寝しく 今し悔(くや)しも (万葉集巻14-3577) (注)山菅=ヤブラン (ヤブラン) (荒地山)道の辺に 咲く芹見つつ わが来れば わが田は人参 咲く花ぞこれ (交野王) (本歌)あかねさす 昼は田賜(た)びて ぬばたまの 夜の暇(いとま)に 摘める芹子(せり)これ (葛城王 万葉集巻20-4455) (注)葛城王=橘諸兄(橘の姓を賜って臣下に降下する前の名) (芹) (人参)秋待ちつ 君に見せむと わがかきし 韓藍(からあゐ)の花 これにしあれり (偐智麻呂) (本歌)秋さらば 移しもせむと わが蒔きし 韓藍の花を 誰か採(つ)みけむ (万葉集巻7-1362) (注)韓藍=鶏頭のこと。二寸余の かぶと虫にも 夫婦(めをと)愛 あるものならし 寄り添ひ死にし (偐虫麻呂) (カブトムシの死骸)願はくは いつにてもよし ぴんぴんと 生きてころりと 死なましものぞ (難行法師) (本歌)願はくは 花の下にて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 (西行 山家集77)愛宕山と 比叡の山と あひし時 立ちて見しかや 甘南備の人 (枚方天皇) (本歌)香具山と 耳梨山と あひし時 立ちて見に来し 印南国原 (万葉集巻1-14 天智天皇) (注)あひし時=争った時 (愛宕山と比叡山遠望) 歩麻呂が贈り来れる歌1首夜を込めて 書いたブログで あるとても よに間違いの あるはゆるさじ (本歌)夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言 後拾遺集940 枕草子131段 小倉百人一首62) 偐家持が追和せる歌1首夜をこめて 書きしブログも 蝉丸の かみしもたがへ 咳ではゆるさじ (咳家持)飛鳥路の 秋は壱師の まづ咲きて 来よと白雲 われさしまねく (明日香村の彼岸花)歩麻呂には うまくもあらぬ はなかつみ かつ食ふ人に よりてはうまし (中臣郎子) (本歌)をみなへし 佐紀沢に生(お)ふる 花かつみ かつても知らぬ 恋もするかも (中臣女郎 万葉集巻4-675) 陸奥(みちのく)の 安積(あさか)の沼の 花かつみ かつ見る人に 恋ひやわたらむ (古今集14-677) (注)万葉集、古今集に登場する「はなかつみ」については、ハナショウブ、カ タバミなどと並んでマコモだという説もある。 (マコモダケ)たんぽぽの 咲く花五つ 蕾三つ 仮名のと四つで 豊能なりけり (マンホール麻呂) (豊能町のマンホール)さはぞひに さはにぞなれる さはぐるみ くるみなのれど みはたべられず (着ぐるみ) (注)さはぐるみ=沢胡桃 (サワグルミ)われきくに すもももももも ももといへ すももはぷらむ ももにはあらじ (桃谷駅長) (プルーン)日の下に 咲かぬ花かも 月下美人 夜目にしさくや ひとまどふらし (日下町三丁目自治会) (注)さくや=「咲くや」と「昨夜」の掛詞。 日下=東大阪市の地名。われも恋ふ 秋野の尾花 藤袴 栗に憶良の 歌添ふよしも (注)われも恋ふ=吾亦紅(ワレモコウ)を掛けている。君が屋の 戸口が花は 指折りて かき数ふれば 四種(よくさ)と栗か (家中憶良)(本歌)秋の野に 咲きたる花を 指折りて かき数ふれば 七種の花 (山上憶良 万葉集巻8-1537) (「秋彩」)(脚注)掲載の写真はビグジョン氏のブログからの転載です。
2016.09.30
コメント(6)
-

ビロードモウズイカ
今日、偶然に、或る花の名前が判明しました。 過去の記事で、名前不明で掲載したであろう写真の説明文を訂正しようと、当該記事を探したが、見当たらない。どうやら、記事に掲載したと思ったのは、小生の「思い違い」で、名前が不明なので、記事にはしなかったようでした。 その花の写真はフォト蔵にはアップしていたので、ブログ記事にしているものと勘違いしたのでした。ということで、遅ればせですが、その花を記事アップすることとします。 その花というか、植物は、昨年の10月28日~30日に富士吉田、山中湖などを銀輪散歩した折に、何度か道端で見掛けたものでありました。この銀輪散歩の記事は昨年の10月28日から11月2日まで5回にわたって記事にしていますが、富士吉田の駅周辺を散策した折と山中湖へと向かう銀輪の道で見掛けたのでありました。 それは、こんな植物でした。 名前はビロードモウズイカ。耳慣れぬ名前。 どんな漢字かと調べると「毛蕊花」でした。(ビロードモウズイカ・Wikipedia) Wikipediaには「ビロードモウズイカ(学名:Verbascum thapsus)はヨーロッパおよび北アフリカとアジアに原産するゴマノハグサ科モウズイカ属の植物である。アメリカとオーストラリア、日本にも帰化している。ビロードモウズイカは、大きな葉のロゼットから伸長した長い花穂に黄色い小花を密集し、高さ2メートル以上にもなる毛深い二年生植物である。」とある。 上の写真も、下の写真も、生憎と霧雨のような雨が時々降りかかるという気象条件にあったため、葉が小さな水滴に覆われて白っぽくなっていますが、そういう状況でなければ、白っぽい毛に覆われてはいるものの、もう少し緑色っぽいものであっただろうと思います。(同上) 上は根から葉が出たばかりの状態。ロゼット葉である。 成長するとロゼットの中心から花茎が伸びて、花穂を付ける。 花の写真がないので、Wikipediaから転載して置きます。 (ビロードモウズイカの花・Wikipediaから借用) 気になっていたものの、殆ど忘れかけていた植物の名が偶然ネットで判明したので、ちょっと愉快な気分、ということで記事にしてみました。 まあ、皆さまには関わりなきことでありますが・・(笑)。
2016.09.29
コメント(4)
-

ホットケーキからチョコレートケーキへ
先日(26日)の第181回智麻呂絵画展で、コフキタケの絵が登場しました。 その絵は、当ブログの8月7日の記事に掲載の写真からの絵であることも申し上げました。 このキノコの名前が、コフキタケ(コフキサルノコシカケ)であるのかどうかは、定かではありませんが、一応、コフキタケとして居ります。 このキノコのその後の状態を写真に撮っていますので、智麻呂氏がこれを絵にして下さったのを契機に、これをご紹介申し上げることとします。 (智麻呂画のコフキタケ) (モデル写真のコフキタケ) 上右の写真は8月7日の撮影で、記事では「ホットケーキ」か「どら焼き」みたいと評しましたが、その後は、こんな風に変貌しています。 なお、このキノコの生えている場所は、東大阪市の花園中央公園の片隅です。 (2016年8月12日の状態) 周囲に茶色の粉を飛散させ、地面や草を茶色に染めていますから、コフキ(粉吹き)タケで間違いないだろうという、まことにいい加減な小生の推定であります。 (2016年9月8日の状態) その後、雨にも打たれて、粉は流れてしまったようです。色も茶褐色と濃くなっています。ホットケーキがチョコレートケーキに変貌したという次第。 (2016年9月21日の状態) 更に色が濃くなり、ブラックチョコへと変わりつつあるようです。 幸いに、公園管理のお方も、草刈はしても、このキノコはそのままに残して下さいましたので、今後も観察が可能であります。今後も観察を続け、どのように変化して行くのか、見届けたいものと思っています。閑人の われにしあれば コフキタケ 移ろふ色の いかにとや見む (茸家持)
2016.09.28
コメント(11)
-

第181回智麻呂絵画展
第181回智麻呂絵画展 一昨日の若草読書会で智麻呂邸にお伺いした折に、新作絵画6点を撮影しました。在庫分5点とを併せ、全11点の作品が揃いました。よって、本日は第181回智麻呂絵画展を開催することと致します。 今回の家持館長お薦め作品は、「蓮の実」と「月下美人」でありますが、どうぞご自由にご覧下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは、お薦め作品その1の「蓮の実」であります。 智麻呂氏はこの実を描くに当っては、かなり苦闘されたようで、何度もデッサンをやり直して居られましたが、このように見事な絵となりました。(蓮の実) この蓮の実は、ご友人の友〇さんからご提供を受けたものであるとお聞きしたかと思いますが、智麻呂氏にとっては初挑戦の画題。そういうこともあって最初はご苦労されたようでありますが、仕上がってみれば、いい味が出ているかと。 先日、知人が茹でたという蓮の実を口にする機会がありましたが、美味いものでは全くない。仏様が蓮華に坐して居られるという極楽のB級グルメもどうやら大したものではなさそうです(笑)。 以下の4点は当ブログ掲載の写真から絵にされた作品です。(コフキタケ) 上は、8月7日の記事「ホットケーキみたいです。」に掲載のコフキダケであります。(ヒマワリ) 上のヒマワリは8月6日の記事「墓参・ヒマワリの咲く道」に掲載の写真からの絵です。(住吉大社・反り橋) 上は、8月25日の記事「銀輪渡船巡り」に掲載の写真からの絵です。(長浜城) 上の長浜城は8月13日の記事「岬麻呂旅便り192・関ヶ原戦場跡と城めぐり」に掲載の写真からの絵です。 この写真は、ヤカモチ撮影のものではなく、友人の岬麻呂氏撮影のものですから、もし著作権がこの写真について成立するならば、その模写の頒布も亦著作権法上の問題を生ずることになりますが、岬麻呂氏がこれを問題とするお方でないことは明白。従って、そのような野暮な検討はするまでもないこと。そのまま当絵画展に展示させて戴くことといたしました(笑)。 さて、次の「美人画」が、お薦め作品その2であります。(月下美人) 美人と言っても月下美人のこと。一応「見返り美人」のポーズを取っているようにも見える処が愉快であります。 この花は夜に咲いて、朝方には萎んでしまうという難儀な花。ひろみの郎女さんがご自宅で育てられているこの花。開花したのを見届けて、暗くなった午後7時か8時かに、わざわざ智麻呂邸に自らご持参、お届け下さったものであります。 となると、手早く絵にしないといけない。翌朝に描こうなんぞということは許されない。智麻呂氏はササーっと手早くスケッチされ、色付けされたのでしょう。いいタッチの絵になっています。夜目遠目 傘の内こそ 美人とふ 月下も夜目の 内にあるらし (鵜の目鷹の目) 次は秋らしい絵です。 (秋の香) 秋の香りをお届けせむと、東京のリチ女さんが智麻呂ご夫妻に送って下さった、立体式の切り絵紙細工(実物写真:右)の絵であります。(バナナ) 上のバナナは、智麻呂氏がデイサービスに通って居られる施設「アンデスのトマト」で頂戴したバナナであります。「トマトのバナナ」という何やらややこしいことになりますが、画面をはみ出さんばかりに力強く描かれました。 下の絵はエビネ。 これは上の蓮の実を下さった友〇さんが、花の絵を描く参考にと下さった南九州えびね園の花のカタログと言うかパンフレットと言うか、図鑑風の小冊子に掲載の各種のエビネの花から、緑神という名の品種を絵にされました。(エビネ・緑神) 次は、何やら絵本の挿画のような絵でありますが、上記の施設「アンデスのトマト」で、施設の方が「智麻呂さん、これを絵にお描きになったらどうですか。」と差し出して下さった絵を模写と言うか、写生された絵であります。 これも、元の絵に著作権というものが存在するのであれば、些かの問題も無きにしも非ずですが、偐万葉的絵画展ということで、大目に見ていただきましょう。(栗鼠と団栗)(樫の実) 最後の樫の実も、当ブログの8月6日の記事「墓参・ヒマワリの咲く道」に掲載の写真からの絵です。 以上です。今回は、食欲の秋というに、デザートなど美味しそうな食べ物の絵がありませんでした。蓮の実とモンキーバナナ、ドングリでは、猿や栗鼠でもあるまいし、ちょっといただけませんですな。まあ、今回は「芸術の秋」に徹した展覧会ということでご容赦賜りたく(笑)。 本日もご来場下さり、ありがとうございました。
2016.09.26
コメント(10)
-

若草読書会・句集「晏」を読む
本日は智麻呂邸若草ホール・午後1時集合にて若草読書会。 若草読書会の中心メンバーの凡鬼さんこと岩出くに男氏が句集「晏」を出版されたことは、当ブログの6月9日の記事で紹介済みであるが、今日はこの本を取り上げることとしました。各メンバーが同句集から予め選句(概ね5句)したものについて、作者自らに、その句の意味や句の背景、作句の経緯などを解説して戴こうという趣向であります。 出席者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻(お孫さんの3歳のリラちゃんも同伴)、小万知さん、祥麻呂さん、ひろみの郎女さん、香代女さん、偐家持の9名。選句を寄せて戴いた、偐山頭火さん、槇麻呂さん、リチ女さんは都合により欠席でした。和麻呂さん、和郎女さんやれんげの郎女さんも他用にて欠席。いつもより少な目でした。 始めに、小万知さんがご用意下さった花束と読書会メンバー有志からのお祝品を贈呈し、凡鬼さんの今回の句集出版を、遅ればせながら、お祝させていただきました。 (句集「晏」) さて、各自が選んだ句は以下の通りであります。 選句者からの選句についての簡単な感想などを述べていただいた後、作者自身の口からそれぞれの句についての懇切な説明があり、凡鬼俳句の世界に楽しく浸ることができました。 〇祥麻呂選句 坊ちやんと子規に会ふ旅のどけしや ルカ伝に惹かれる言葉あたたかし 語り部は皆老いたるや敗戦日 クリスマスキャロルも若き日の思ひ 霜柱平和憲法崩れさう〇偐山頭火選句 孟嘗君鶏鳴狗盗裘 〇ひろみの郎女選句 桃源に住まふ心地や春の夢 秋の日の届かぬ奥に釈迦三尊 春光やステンドグラス色滲む ナナハンの男紫陽花見てゐたり 器量よき猫の子すぐに貰はれて 〇小万知選句 五線譜を引いてやりたし蝌蚪の国 捩花や生くるに少し疲れあり (捩花・智麻呂画) (烏瓜・智麻呂画) 手繰られることを待つかに烏瓜 あるかなきかの風教へ小判草 立ち入りの禁止看板蛇犯す 〇香代女選句 ひそやかな世代交代夏落葉 散る紅葉残る紅葉を促せり 立ち止まり讃美歌を聴く聖夜かな 散りて咲く芙蓉は日々に新しく (芙蓉) 風が澄み水澄み深くなるこころ 〇恒郎女選句 深夜まで黒澤映画寒昴 平等が唯一の掟蝌蚪の国 五線譜を引いてやりたし蝌蚪の国 一匹となりてくつろぐ金魚かな 象の耳ぱたぱた春を知らせをり 〇偐家持選句 木槿咲く奥の細道結びの地 饒舌な男黙れと亀の鳴く 山椒魚つらつら見るに几帳面 はんざきの泰然自若悟り顔 チューリップ好きな人みな楽天家 在りし日の父に似てきし端居かな 義仲寺の手強き秋の蚊に会ひぬ (義仲寺) 〇景郎女選句 散りきって思惟の時なる桜かな 落鮎の龍宮まではとどかざり 仲秋や物みな影をふかめをり 客膳の一品として冬菜摘む 好好爺ならず反骨着ぶくれて 桜桃忌青春の日の苦き澱〇リチ女選句 山姥もコロポックルも霧の中 〇槇麻呂選句 好好爺ならず反骨着ぶくれて 管鮑の交はりのごと桜草 不器用に生きて古希越ゆ破芭蕉 (象潟・蚶満寺の芭蕉) 京舞妓そっと押しやる流し雛 青春の香りと黴の匂ふ書架 末つ子も嫁に行くとや桃の花 洞窟の闇何も応へず沖縄忌 声だかに正義語るな開戦日 クリスマスキャロルも若き日の思ひ 湖北には美男の仏かいつぶり 椰子の実はなき浜なれど春の波 凡鬼さんの講話が一段落した処で。栗ご飯やその他のご馳走、酒・ビールなども出て雑談、歓談。午後6時頃にお開きとなりました。 次回の開催は、11月26日(土)午後1時から、と決まりましたが、テーマは未定です。偐家持としては、恒郎女さんと智麻呂さんの美しい歌声を聴かせていただくことを中心として、みんなで歌う「若草歌声喫茶」でどうかと思って居ります(笑)。
2016.09.24
コメント(8)
-

「生前葬」と言う名の個展ーー家近健二個展
昨日(21日)は、古くからの友人(と言っても大先輩であるが)である画家・家近健二氏の個展に出掛けて参りましたので、その紹介です。 「家近健二個展(燈台、山、卵、花・・そして出会いたい風景などなど)」という案内ハガキを頂戴したのは先月の下旬のこと。会期は9月16日~21日であったが、所用や台風絡みの雨などの所為もあって、漸く最終日の21日になってお伺いすることが叶いました。 氏のお孫さんの「りんごさん」が通りがかりで当ブログの2012年9月26日記事「殉展そして近隣散歩」を見付けられてご訪問下さり、コメントを戴くという愉快なことが先月29日にあり、そのコメントでもこの個展のご案内がありましたので、これはもう是非ともお訪ねしなくてはならなかった、というものであります。 会場は、上本町6丁目の上本町ギャラリー。 銀輪家持、この日も足はマウンテンバイクでありました。自宅から会場までは自転車で40分余程度である。午前10時からの来客の応接を済ませた後、11時過ぎに自宅を出発、会場のあるカリヨンビル前到着が11時45分頃。隣のパチンコ屋さんの駐輪場に自転車を駐輪させていただき、ビル1階のレストランCARILLONで昼食を済ませて、会場へ。 (上本町ギャラリー) (アプローチ階段) 家近氏からの案内状には「上町台地にあって、文化の発信源でありつづけている上本町ギャラリーが、この秋(11月)をもって40年の歴史に幕をおろそうとしています。」とあり、ここでの同氏の個展はこれが最後となります。そういうこともあってか、それとも氏ご自身の別なる思いがあってのことかは存じ上げぬが、アプローチ階段を上がりかけて目に飛び込んで来たのは、「生前葬」と言う名の個展、という文字と旧約聖書・ヨブ記の言葉。ヨブが自分の息子、娘たち全てが死んでしまったことを知った時に神に向かって言った言葉。 「わたしは裸で母の胎を出た。また裸でかしこに帰ろう。 主が与え、主が取られたのだ。主のみ名はほむべきかな」 キルケゴールは、その著作「反復」の中で「ヨブよ、ヨブよ!おお、ヨブよ!あなたは、あの美しい言葉のほかに、『主があたえ、主が取られたのだ。主のみ名はほむべきかな』という言葉のほかに、ほんとうになにもいわなかったのですか。あなたは、七日七夜のあいだなぜ黙っていたのですか。」(9月19日の項)と書いていることなどを思い出しながら、突然のことなので、どう身構えてよいのやらも定まらぬまま、「生前葬」の会場へと向かいました(笑)。勿論、供花、香典の用意もない(笑)。 会場内は、色彩の氾濫。様々な絵が所狭しと並べられていました。 撮影してもよいか、会場に居られた家近夫人にお尋ねすると、「どうぞ、どうぞ。」ということであったので、やたらシャッターを切りまくりました。 家近氏は、次々とご来場になる皆さんへの応接に取り紛れて居られましたので、ご本人の許諾を得て居りません。著作権法上は、いささか問題ありということになりますが、偐万葉風見切り発車であります。 会場の雰囲気をお伝えすべく、ランダムに写真を並べることとします。 家近氏は「何と言ってテーマもないのがテーマ。雑多に並べてある。」というようなことを仰っていましたが、「生前葬」にテーマなどあるべくもない、と言うものでしょう。生前葬と言うに不謹慎に、小生も雑多に撮影することとしたのでありました。 以下、個別の作品の写真を並べてみます。作品番号は、小生が写真を撮った順番の番号で意味はありません。それぞれの絵にタイトルなども付されていませんので、絵を解釈する手掛かりもありません。 そもそも、絵は「解釈」するものではなく「感じる」ものなんでしょうから、タイトルなどというものは本来は不要なんでしょうが、絵画展などに出展する場合にはタイトルを付すことが必要なようです。審査員の先生方の「解釈」を容易にするために必要なのかとも思いましたが、審査員同士で絵の評価の意見交換をするときなども絵に名前が付いていないとややこしくなるという実務上の必要性ですかね。(作品1) 小生の目を惹いたのは、この絵。 落ちた帽子を拾おうとしているのか、身体を前屈したら帽子が脱げ落ちたのか、或は祈りの所作であるのだろうか。老人の窮屈そうな身体の動きが何やら気になりました。これでは絵の鑑賞ではありませんですな(笑)。 (作品2) (作品31) 左は自画像でしょう。生前葬だから「遺影」とは言わない。「現影」ですかな。 右の少女は何となく家近夫人の面影に似ていますから、お嬢さんの幼い頃、或はお孫さんの幼い頃の面影を重ねて居られるのでしょうか。幼くして亡くなった野花ちゃんのことなども思い出される絵でした。 次は家近氏らしいモチーフの絵。 卵の絵をよく描かれるが、卵や卵的なもの、卵のような形というのは氏の絵にとっては重要なモチーフのようです。 (作品30) (作品21) (作品22) (作品17) (作品19) (作品10)(作品11) 灯台の絵が多いのが今回の個展の特長でしょうか。 「灯台の絵が多いですね。」と申し上げると、抽象芸術的なものでは親しみを感じにくいだろうから、より多くの人に親しみを感じて貰うための絵である、というような趣旨のことを仰っていましたが、お説の通り、小生などはこういう絵の方がいい。 しかし、氏の遊び心は、これを普通のカンバスに描くのではなく、戸板に描くという処に現れている。一種の襖絵となったり、屏風絵となったりもするのである。(作品3) (作品12) (作品8) (作品34) (作品23)(作品5)(作品29) (作品4) (作品6) 単なる景色では飽き足らず、何やら霊のように浮かび上がる像。景色が現実なのか、人物が現実なのか、それは見る人の感じ方次第。 (作品20) (作品27) こういう絵を見ていると、能を連想する。 シテは決まって幽霊であり、この世のものではない。 芸術というのは、夢想・幽界と現実がないまぜになった世界・「あはひ」で成立しているように思うから、両者をどのように組み合わせ繋ぎ、そこに独自の意味・世界観や独自の感じ・雰囲気を表出し得ているかが、創作の妙ということなんでしょうが、創作は他者への発信でもあるから、見る側の共感というものも大切ですな。 (作品24) (作品25) 京の町家の空に白狐。越後の村上でしょうか。降り積む雪の道行く人影の頭上に巨大な鮭。こういう絵も好きですな。(作品16) これは何処のお寺でしょう。東西に塔があるから當麻寺でしょうか。 門にうずくまっている人影は旅の僧侶でしょうか。 となるとますます「能」のそれでありますな。 ワキ「これは旅の僧にて候・・」 (作品13) (作品32) 光琳、北斎、若冲などを想起する絵。絵からはみ出した鯛。恨めしそうな擬人化された目が諧謔であることを告げていますが、こういう絵も色々にもの思わせて楽しいですな。 次は、花の絵。 (作品14) (作品15) (作品33) (作品7) (作品9) (作品26) (作品18) (作品28) 額のガラスに反射して、撮影者である小生の姿や天井の照明灯が写り込んだりして、お見苦しい写真もあったかと存じますが、それは撮影条件の悪さにて、撮影者のカメラワークの所為ではありませぬ故、ご寛恕賜りますように。 帰途は、布施のヒバリヤ書店に立ち寄って、若草読書会用の買い物を済ませ、八戸ノ里駅近くまで帰って来た処で雨。雨具の用意はしていましたが、ザックから雨具を取り出して着るのも面倒と若江岩田駅近くで喫茶店で雨宿り。小止みになってから再出発。午後4時頃の帰宅となりました。<参考>中之島の後、心斎橋ー油絵個展 2009.5.25. ガリラヤの風 2011.11.30. 殉展そして近隣散歩 2012.9.26.
2016.09.22
コメント(8)
-

90万アクセス通過・ウリカエデとコキア
本日、外出先から帰宅してブログ管理ページを覗くと、総アクセス数が90万を超えていました。 (9月21日午後4時35分現在のアクセス数) どうやら午後3時頃に90万アクセスに到達したようです。 いよいよ、100万の大台突破が近くなってまいりました。 今のペースだと11月下旬頃がその時期となりそうです。 2007年4月29日にブログ開設ですから、9年7ヶ月で100万ということになりますが、遅いのか早いのかは何とも言えませぬ。しかし、2日に1回のペースでコツコツと飽きもせずブログ更新を続けて来たこともさることながら、何と言っても、さしたる取柄もない当ブログをご訪問下さる皆さまのお陰であり、有難く感謝申し上げます。 <累計アクセス数の推移> 10万 2011.1.11. 20万 2012.12.31. 30万 2014.11.7. 40万 2015.6.2. 50万 2015.10.11. 60万 2016.2.3. 70万 2016.5.27. 80万 2016.7.22. 90万 2016.9.21. 例によって、アクセス数90万突破というだけでは、小生個人の関心事に過ぎぬことでありますので、銀輪散歩で見掛けた植物の写真などを掲載して色を添えさせていただきます。(ウリカエデの実) この木は、先日(17日)の日記「銀輪花散歩・秋づけば」の記事の末尾に載せた「この実、何の実」の木と向かい合って生えていました。 実を見てカエデだろうと見当を付けたものの、葉が普通のカエデと形が違う。トウカエデという名前が浮かび、それだろうかと調べてみると、それとも葉が違う。ネットで色々あたってみた結果「ウリカエデ」だと結論づけたのでありますが、もし間違っているようでしたら、ご教示いただくと幸甚に存じます。 (同上) (ウリカエデの葉) 三裂の葉は、若い葉にはあるが、殆どの葉は卵形である。似た木にウリハダカエデというのがあったが、これは葉が全て三裂のようです。(同上 三裂の葉と卵形の葉)(ウリカエデ) (同上) ついでに、コキアの写真も掲載して置きます。 まだ、色づいていませんが、もう少し秋が深くなると、赤くなって美しいアキコさんになります(笑)。 (コキア)<参考>ブログの歩み関連記事はコチラ
2016.09.21
コメント(3)
-

偐万葉・ウーテイス篇(その4)
偐万葉・ウーテイス篇(その4) 本日は、偐万葉シリーズ第267弾、偐万葉・ウーテイス篇(その4)とします。ウーテイス氏はタイ北部にご在住の日本人。2013年3月8日に当ブログをお気に入りにご登録下さったのが交流のきっかけですから、3年半のお付き合いになります。 (その3)を2014年4月30日にアップして以来のウーテイス篇にて、久々のこととなります。 <参考>過去の偐万葉・ウーテイス篇はコチラ。 ウーテイス氏のブログはコチラ。 偐家持がウテ麻呂に贈りて詠める歌17首しゃくやくの はなゑがきたる ひのくれて すがらにまたむ なつのよのつき (にせともまろ) (芍薬の 花描きたる 日の暮れて すがらに待たむ 夏の夜の月) (第160回智麻呂絵画展より転載) (本歌)くれなゐの 牡丹咲く日は 大空も 地に従へる こゝちこそすれ (与謝野晶子) 春の夜の 波も月ある 大空も ともに銀絲の 織れるところぞ (同上)うるはしの やまとことのは たづぬれば まづはまほろば あをがきなるや (にせやかもち) (麗しの 大和言の葉 尋ぬれば まづはまほろば 青垣なるや) (本歌)倭(やまと)は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠(こも)れる 倭しうるはし (記紀歌謡) 散りぬべき 時知らずして ちとせ超え 花とも咲かず 人にも非ず (大伴ガラシャ) (本歌)散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ (細川ガラシャ)昨日(きそ)も明日も 虚仮(こけ)けふの今 こそよしと はしゃぎ杉田る 玄白言へる (過ぎた言白) (注)ウテ麻呂より杉田玄白の歌なりと「過ぎし世もくる世も同じ夢ならばけふ の今こそたのしかりけれ」のコメントありたるにつき、返したる歌。 タイの夜の 月照る庭に 飲み交はす われはデラシネ きみもデラシネ (偐ウーティス) たれにしも あらぬ名なりと 言ふ君の 憎まれ口も 楽しからずや (なのりそ家持) (注)ウーティスという氏のハンドルネームはタイ語で「誰でもない」という意 味だそうです。 ※タイ語というのは小生の思い違いでギリシャ語(uutisu)であるという ことが、過去の記事を遡って、判明しましたので、追記訂正します。 時々は 杉樽琴も あるなれど 削除宝刀 われにしあれば (伝家家持) (注)杉樽琴=過ぎたること いにしへに ありけむ人も 月見つつ 添はぬ心の とどめかねけむ (栗本月麻呂) (本歌)いにしへに ありけむ人も わが如か 三輪の桧原に かざし折りけむ (柿本人麻呂 万葉集巻7-1118) 吉野山 梢の花を 見し日より 心は身にも 添はず成にき (西行 山家集66) (写真提供:偐家持) われのこと きみはなに知る さかしらに これと決めるは をこと言ふなり ウテ麻呂の戯れ句に偐家持が付けたる脇句 古池や 蛙飛び込む 水も涸れ (ウテ麻呂) 芭蕉も枯れて 句もままならず (蛙家持) ゴーギャンは タヒチの女 智麻呂は 若草の花 おのがまにまに敷島の 大和のことは さほどだに なけど蕨の 蕎麦の恋(こほ)しき (偐ウテ麻呂) 散るときし 散るにしあれば 散るまでは 散らずありけり きみはもわれも 喜里川の 里やきりきり ひぐらしの 鳴く夕影の 風のかそけき (注)喜里川=東大阪市東部にある地区名 かなかなと かなしき声に ひぐらしは 日暮れ惜しみて 鳴くものならし (注)下二句は、初案「日暮れ惜しむや 里の夕かげ」を修正。 かなかなと そのひぐらしの われなれば 富も栄華も 吾が事に非じ 美しき もの見しときは 美しき 心になりて 人みなやさし美しき 言ぞ尽くさむ 美しき 言にし人も 愛を知るらむ (カナブン)※ウーテイス氏のブログより転載 (本歌)恋ひ恋ひて 逢へる時だに 愛(うつく)しき 言(こと)つくしてよ 長くと思(も)はば (大伴坂上郎女 万葉集巻4-661)
2016.09.20
コメント(1)
-

銀輪花散歩・秋づけば
まだまだ銀輪散歩には暑い気候ですが、木陰などを吹き抜ける風はひんやりと心地よく秋のそれである。ということで、銀輪散歩の道すがらの花も秋模様なのであります。(萩) 秋と言えば、やはり萩ですね。万葉人が最も多く詠んだ花は萩ですから、万葉人はこの花を心から愛したということであるのでしょう。 2009年8月29日の日記に萩の万葉歌を34首掲載していますが、141首もあるので全部を記載するのはハギではなくホネです。 <参考>萩の花 2009.8.29. 上の写真では、萩の背後にススキも写っていますが、人によっては、萩よりもススキ(尾花)の方にこそ秋を感じるということもあるでしょう。万葉人にもそういうのが居たようです。人皆は 萩を秋といふ よしわれは 尾花が末(うれ)を 秋とはいはむ (万葉集巻10-2110)(人は皆、萩のよさが秋だと言う。たとえそうだとしても、私は尾花の穂先のよさこそが秋だと言おう。) さて、皆さんは、ハギ派、ススキ派どちらでしょうか? (同上) ところで、これも萩なんでしょうか。花の感じは萩ですが、葉が普通の萩とは違っています。 ということで、ハギモドキということにして置きます。 (萩に似て非なる花か・不明)<追記>小万知さんからメドハギであるとご教示いただきました。 正真正銘のハギの一種。ハギモドキなどとこの花に失礼な ことを申し上げてしまいました。 なお、メドハギについては、万葉集(巻20-4493)に登場 する玉箒(たまばはき)だとする説もあるようです。 一般にはコウヤボウキのこととされていますが。 始春(はつはる)の 初子(はつね)の今日の 玉箒 手に執るからに ゆらく玉の緒 (大伴家持 万葉集巻20-4493) メドハギ・Wikipedia 次はイタドリ。(イタドリ) イタドリ、つまりスカンポです。この花もよく見ると結構美しい。万葉で「壱師の花」は「ヒガンバナ」とするのが多数説かと思うが、このイタドリだという説もある。確かにこのように咲いているのを見ると、イタドリ説も捨てがたい気になる。路の辺の 壱師の花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻を (万葉集巻11-2480)(路の辺の壱師の花のようにはっきりと人みんなが知ってしまった、私の恋しい妻を。) (同上) 万葉の秋の花の代表が萩なら、現代の秋の花の代表と言えばコスモスでしょう。撫子の花を少女の笑顔に喩えたのは大伴家持。 コスモスの花にも同様の趣があるので、ナデシコをコスモスに置き換えても歌として成立しますね。石竹花(なでしこ)が 花見るごとに 少女(をとめ)らが 笑(ゑ)まひのにほひ 思ほゆるかも (大伴家持 万葉集巻18-4114)コスモスの 花見るごとに をとめらの 笑まひの匂ひ 思ほゆるかも (偐伴家持) (コスモス)野辺見れば 撫子の花 咲きにけり わが待つ秋は 近づくらしも (万葉集巻10-1972) この歌もそのままコスモスに置き換えてもよさそう。野辺見れば コスモスの花 咲きにけり わが待つ秋の 近づくらしも (偐伴家持) (同上) コスモスの花は見下ろして撮影するよりも、大空をバックに、下から見上げて、出来たら逆光で撮影した方が「秋」らしい写真になる。 (同上)(ノブドウ)野葡萄の 色づく見れば 銀輪の この道にして 秋にあるらし (銀輪家持) (同上) まだ、色づき始めたばかりであるが、ノブドウの実も秋支度である。 (同上) ノブドウの色づき始めた道を行くと、ヨモギも花穂を風になびかせて立ち騒いでいるのでありました。(ヨモギ) 「蓬生」と言えば、ヨモギの茂った荒れた屋敷のこととなるが、これは平安朝になってからのこと。 万葉では、大伴家持の長歌(万葉集巻18-4116)に「・・ほととぎす 来鳴く五月(さつき)の あやめ草 蓬かづらき 酒宴(さかみづき) 遊び慰(な)ぐれど・・」とあって、端午の節句に、アヤメとヨモギを髪飾りにする習俗があったことがうかがわれる。香りの強いヨモギは、その香によって邪を払う力があると信じられていたのである。ヨモギ餅・ヨモギ団子もその名残であろう。 まあ、花穂を付けてしまっては、餅にも団子にも使えないでしょうが、空を背景に風に吹かれて花穂を揺らしている様は、ヨモギらの祝祭、とでもいった雰囲気。隣の葦は「アッシにはかかわりのねえこってござんす。」と知らん顔でありますが。(葦) 葦で、小生の好きな万葉歌と言えば、季節はもう少し先のことになるが、これでしょうか。葦辺行く 鴨の羽がひに 霜降りて 寒き夕へは 大和し思ほゆ (志貴皇子 万葉集巻1-64)(葦辺を行く鴨の背に霜が降り、寒さが身にしみる夕べは、大和のことが思われてならない。) 一昨日(15日)の記事にバッタや蛾と共に登場した花、ミヤコグサ。本日は花としてお伴はなしで登場であります。(ミヤコグサ)吹く風も 秋の色なり みやこ草 行きて咲く見む 長堤の道 (偐家持) (同上)名にし負ふ 花にしあれど みやこぐさ みやこを遠み いたづらに咲く (偐家持)(本歌)采女(うねめ)の 袖吹きかへす 明日香風 京(みやこ)を遠み いたづらに吹く (志貴皇子 万葉集巻1-51)(同上)(葛)萩の花 尾花葛花 瞿麦(なでしこ)の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花 (山上憶良 万葉集巻8-1538)と憶良が秋の七種の花として挙げたうちでも、萩、ススキに次いで3番目に挙げられている葛花。それにしては、花そのものが詠われることは、上の1首のみで「ま葛原」、「はふ葛の」と這い広がる蔓の様や、「葛葉」「葛の根」と葉や根の方を詠う歌ばかりなのである。 花単独で歌となることのなかった葛花であるが、繁る葉の陰に見え隠れしながら咲いている花はなかなかに美しいのである。萩のように小さく咲くのではなくまとまってどちらかと言うとぼってりとした感じで咲くのが、万葉人の好みには合わなかったということでもあるか。 (同上) (同上)(同上・花と実) 葛の実は、花以上に歌にはなりそうもないご面相であるから、実を詠った歌がないのは首肯できるというものである(笑)。 (同上・実) 真葛原の葛の葉の隙間から顔を覗かせているのはノイバラの実。 万葉では「うまら」である。芋も「うも」と発音したから、古代の「う」が何処かの時代から「い」に取って代わられたのであろう。道の辺の 茨(うまら)の末(うれ)に 這(は)ほ豆の からまる君を 別(はか)れか行かむ (丈部鳥(はせつかべのとり) 万葉集巻20-4352)(道の辺のイバラの先にはう豆のつるがからまるようなあなたを置いて、私は別れて行くのか。) (ノイバラの実)(チカラシバ 別名ミチシバ)立ちかはり 古き都と なりぬれば 道の芝草 長く生ひにけり (田辺福麻呂歌集 万葉集巻6-1048)(この実、何の実?) さて、ことのついでに気(木)になるこの実も掲載して置くこととしましょう。 何だか、よく知っている木のような気もするのだが、名前が出て来ない。元々知らないのかも知れないから、思い出そうという努力はしない、というのがヤカモチ流。しかし、気になる(笑)。来年の花咲く季節まで待つしかありませぬかな。 (同上) 本日は、銀輪花散歩、万葉花散歩でありました。
2016.09.17
コメント(14)
-
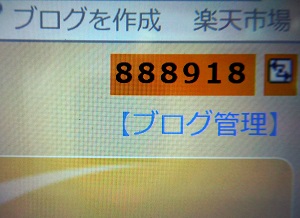
888888アクセス・ダルマさんが並んだ
本日午後4時半頃に888888アクセスを通過したようです。 8並びの見立ては「ダルマさんが並んだ」であります。 「ダルマさんが転んだ」は子どもの遊びと言うか、10を数えるための替え歌的なものであるが、「ダルマさんが並んだ」も丁度10音であるから、その遊びに使えそうですな。 尤も、関西では、「ダルマさんが転んだ」ではなく、「ぼん(坊)さんが屁をこいた」でありました。子どもの頃、誰もがそう言うものと思っていたが、東京の親戚の子どもだったか、東京から近所の家に遊びに来ていた子どもであったか、記憶が曖昧になっているが、彼が「ダルマさんが転んだ」であると言うので、「ぼんさんが屁をこいた」よりも上品で、所謂「標準語」なるアクセントと相俟って、東京というのは何でも「上品に」乃至は「気取って」言うのであるか、と子ども心にも思ったりしたのでありました(笑)。 <参考>ゾロ目アクセスの推移 2011年 3月18日 111111件 2013年 8月 2日 222222件 2015年 2月22日 333333件 2015年 8月 9日 444444件 2015年12月15日 555555件 2016年 5月 5日 666666件 2016年 7月10日 777777件 2016年 9月15日 888888件 さて、そのダルマさんの並びの写真を撮ろうと思っていましたが、気が付けば既に30件ばかりオーバーしてしまっていました。 どうやら、ダルマさんが転んで、ぼんさんが屁をこいたようで、下掲写真の如く二人ばかり行方不明であります。 そこで、8ということで、ハチ(蜂)の写真でも掲載して置くことといたしましょう。クマバチです。(クマバチ) (同上) (同上) クマバチが5匹で、8(蜂)6匹には届かず。 ミツバチ1匹の応援を頼んで、何とか数合わせであります。(ミツバチ) 蜂の写真を掲載したついでに、バッタと蛾の写真もオマケします。(ミヤコグサとバッタ) バッタの仲間でしょうが、正しい名前は存じ上げません。 同様に、下の蛾も、名前は不明。蝶なのか蛾なのかさえも小生には判然といたしませぬが、一応「蛾」として置きます。 その蛾がとまっている黄色い花はミヤコグサ。京都に多く見られるからこういう名が付いたそうだが、本当だろうか。(ミヤコグサと蛾) (同上) 中秋の名月もオマケで追加して置きます。(中秋の名月)
2016.09.15
コメント(12)
-

ガガイモの実
ガガイモの実。初めて目にしました。 何だろうと写真に撮りながら、近くに居た男性に、これ何だかご存じありませんか、と尋ねたが「分らん。」とのことでした。 花の方は以前見たような記憶があるが、名前が思い出せない。帰宅して、過去のブログ記事を辿ると、「ガガイモ」であるということが分った次第。 2012年8月23日の記事では、ガガイモと知ってでもいたかのように書いているが、ネットで調べてそれと知ったのだろうか。大相撲の関取・臥牙丸は知っているが、草花のガガイモは知らなかった筈(笑)。 <参考>処暑なれど 2012.8.23.(ガガイモの実) 上の<参考>として掲載している2012年8月23日の日記でも書いているが、少彦名はこのガガイモの実を二つに割って作った船に乗ってやって来たそうだ。確かにこの実は、弾けて二つに割れると、一寸法師サイズの神様にとっては格好の船になるというものではある。(同上) ガガイモの実は何のへちまという感じだが、花はよく見ると可愛い花ではある。(ガガイモ)(ガガイモの花) (同上) ガガイモは、名前を思い出せなかったが、こちらエノコログサは、間違いようもない。筈であったが、アカエノコログサという名が思い浮かんだものの、そういうエノコログサはなく、ムラサキエノコログサまたはキンエノコロということになりましたが、どうやらキンエノコロのようであります※。植物の名前は難しいと言うかまことにややこしい。※の文章は、当初ムラサキエノコログサとしていましたが、何か色が違うと思って いました。その後キンエノコロというエノコログサがあることを知り、その画像 を確認するとキンエノコロに間違いないことが判明しましたので本文を訂正しま した。(2016.9.18.)(キンエノコロ) 風が吹くとエノコログサの穂がなびく。秋の風である。(同上) アップで撮った上の写真を見て初めて気がつきましたが、針毛の間に小さなピンクの花らしきものが見える。これが、エノコログサの花なんでしょうね。これも初めて目にしました。(普通のエノコログサ)(ブタナの絮) ブタナの絮、綿帽子も風を待ち受けている。 新しい生命を運ぶ営み、未来への旅立ちである。(葦原)(同上) 葦原を風が渡って行く。 葦原の中ツ国は、わが国の神代の呼び名。 この国には葦原が似合う、と言うべきか。 暫く、ブログ更新をサボっていましたので、本日見掛けた植物の写真で取り敢えずの更新、手抜き更新であります。
2016.09.14
コメント(8)
-

クヌギとコナラ
8月28日の日記で、コナラの木に「クヌギ」という名札が掛けられていたことを記しましたが、それがこれです。 <参考>青雲会囲碁大会・秋の気配 2016.8.28.(「クヌギ」と書かれている「コナラ」の木) 確かに、コナラとクヌギはよく似た木であるから、花園中央公園のこの名札について小生も長らく疑うということもなく来ました。 しかし、先日、見上げると実はコナラのそれであったという次第。(クヌギ)(コナラ) 花園中央公園の桜広場の一角に、コナラとクヌギが並んでいる場所がある。ホットケーキみたいな茸が生えている切株のスグそばがその場所。 こちらは、何の木とも表示はないのであるが、上の2枚の写真を見比べて戴いてもお分かりのように、殆ど区別がつきません。葉の方も下の2枚の写真のようによく似ています。クヌギの葉の方がコナラのそれよりも幾分細長く大きいのであるが、別々に見て区別できる人はそんなには居ないでしょう。 (左:コナラの葉、右:クヌギの葉) しかし、実は一目瞭然。全く違う。 友人の小万知さんは、コナラの実はベレー帽を被っている、と仰っていましたが、それに倣うなら、クヌギの実はアフロヘアーのカツラを被っていると言うべきでしょうか。 (左:コナラの実、右:クヌギの実)(コナラの実とクヌギの実) コナラもクヌギもシイタケの原木になるほか、薪炭その他様々に利用され、古来から生活に密着した樹木である。そういうこともあってか、コナラもクヌギも万葉に登場する。〇コナラの歌下野(しもつけの) 三毳(みかも)の山の 小楢(こなら)のす まぐはし兒ろは 誰(た)が笥(け)か持たむ (万葉集巻14-3424)(下野の三毳山に生えるコナラのように美しいあの子は、どんな男を夫として、その笥を持つのだろう。)〇クヌギの歌紅(くれなゐ)は 移ろふものぞ 橡(つるばみ)の 馴れにし衣(きぬ)に なほ及(し)かめやも (大伴家持 万葉集巻18-4109)(紅色は華やかだけれど、すぐに色褪せるもの。地味なつるばみ色に染めた衣にどうして及ぶことがあろう。) コナラは、若い可愛い娘の比喩として使われているのに対して、クヌギ(つるばみ)は(それで染めた衣のことであるが)、古女房の比喩として使われているところが面白い。(クヌギの実) クヌギは「国木・クニキ」の転訛だとも言われている。 (同上) クヌギの実の落ち方も、アフロヘアーのまま落ちる奴、ヘアーはそのまま残し丸坊主で、つまり「実(身)一つ」で落ちる奴とそれぞれであるが、どちらが正規の落ち方なんだろうか(笑)。上の右の写真の実は蓋の中で反転しているから、この後は丸坊主で落下するのだろう。それに対して左の写真のように蓋を付けたまま落ちている奴もいる。発芽ということで言えば、丸坊主で地面に落ちた方が有利かとも思うが、これはどちらにせよ「ドングリの背比べ」に過ぎないのかも知れない。
2016.09.10
コメント(29)
-

健人会・しるもしらぬも逢坂の関
本日は健人会の集まり。昨年同様に石山寺近くの料亭「新月」にて12時からの昼の宴会。いつもは自転車持参で付近を銀輪散歩してから「新月」に向かうのであるが、前日の大津の天気予報は、午後からかなりの雨ということであったので、電車で行くこととする。出発直前に天気予報を確認すると雨は夕刻または夜になってからのようであったので、自転車に切り替えることも可能であったが、大事を取って、電車としました。結果的には、自宅に帰り着いた午後5時半まで雨には遭遇しなかったので、自転車でもOKであったのでしたが。 銀輪散歩ではなくても、少しは何処かに立ち寄ってみようと選んだのが「逢坂の関」。と言っても、逢坂の関跡の正確な場所は分かっていない。京阪電車の大谷駅の少し先、国道1号の脇に「逢坂山関跡」の碑があるので、それを訪ね、併せて蝉丸神社も訪ねることと定めて、家を出ました。 JR山科駅で下車、京阪電車に乗り換え京阪山科から大谷駅へ。大谷駅到着が9時36分。無人の駅改札を出て旧道を東へと行く。緩やかな坂道を上って行くと直ぐに蝉丸神社である。(蝉丸神社) 蝉丸と言えば、この歌。誰でも知っている歌。これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも 逢坂の関 (蝉丸 小倉百人一首10) 後撰集(1090)や素性法師集などでは第三句が「わかれつつ」となっているが、百人一首で「わかれては」と「書かれては」、知るも知らぬも逢坂の関なのである。 パロディ好きの小生なんぞは、「これやこのゆくもかへるも風邪ひけばしるもしらぬも逢坂で咳」などと言いたくなる歌なのである。 蝉丸さんは伝記などはよくわからない。今昔物語巻24では、宇多天皇の皇子・式部卿敦実親王の雑色(雑役をする身分のいやしい男)で、逢坂山に住み、盲目で琵琶にすぐれていたとあり、謡曲「蝉丸」では、延喜帝(醍醐天皇)の第4皇子で、生まれつきの盲目であったので出家した、とある。(同上) 人影は無く、ミンミンゼミが鳴いているばかり。 蝉丸神社に蝉であるから、これでいいのだ。 (同上・本殿)(同上・由緒) 走井餅と言うと、今は石清水八幡宮の鳥居前の店で売られているが、発祥の地はこの地なのである。 <参考>水無瀬銀輪万葉(下) 2010.10.25. 大谷駅の改札を出て、旧道に出た角の家の前に、元祖走井餅本家の碑がある。 (元祖走井餅本家の碑) (大谷駅) 蝉丸神社から更に行くと国道1号に出る。そこに逢坂山関跡碑がある。ここから、峠の向こう側の長安寺までの間の何れかの位置に逢坂の関はあったとされるが、正確な場所は不明だという。これでは、どの辺りで「咳」をしていいものやら、である(笑)。(逢坂山関跡碑) 関跡の碑の前では丁度工事中にて、脚立のようなものとかポリバケツなどという無粋なものが碑の前に置かれていて、写真のムードを著しく損ねるのでありましたが、是非に及ばず、そのまま写真に撮りました。 関跡の碑の近くには「大津絵販売之地」という真新しい石碑が建っていましたが、逢坂の関付近で旅人に大津絵を土産として売っていたのでしょうな。これやこの ゆくもかへるも 大津絵は 買ふも買はぬも 逢坂で売り (六兵衛はん) (大津絵販売之地碑) (大谷駅) さて、ここで小生は大いなる勘違いを犯してしまいました。 先程訪ねた蝉丸神社を上社と思ってしまったのでした。 現地の案内図をいい加減に眺めていて、関蝉丸神社上社、関蝉丸神社下社とあるのを見間違って、蝉丸神社上社・同下社と思い込んでしまったのでした。蝉丸神社を蝉丸神社上社、関蝉丸神社下社を蝉丸神社下社と思い込んだという次第。その結果、蝉丸神社と関蝉丸神社下社との中間にある関蝉丸神社上社を訪ねないまま、大谷駅へと引き返してしまったのでありました。 電車で次の駅の上栄町駅まで行き、下車。 長安寺の前を通って、国道1号に出て、少し戻った処、逢坂山への上り口に当たる位置に関蝉丸神社下社がある。これを蝉丸神社下社と思い込んで見て回っていたのでありましたが、その誤解に気付いた以上は、蝉丸神社、関蝉丸神社上社・下社という正しい区分で紹介し直さないといけないと、記事を修正して居ります。下社から国道1号の坂を5~600m上った処に関蝉丸神社上社があるのだが、上記の誤解をしたままの小生は、それを知る由もなしでありました。あらためて後日訪ねることと致しましょう。(関蝉丸神社・下社)(同上) この神社も踏切を渡ってお参りすることとなる。 このような神社、結構あるものです。小生の記憶に残るものでも、数か所ある。(同上)(同上・本殿)(同上・謡曲「蝉丸」と関蝉丸神社)(同上・時雨燈籠)(同上・本殿) 本・拝殿を囲むように回廊がある。ひと回りしてみた。 (回廊) (同上) 境内の奥、少し小高い処に小町塚なるものがありました。(同上・小町塚) 境内には、沢山の句碑がありましたが、名のある俳人のものではないようです。 (末社・貴船神社)(関の清水) (境内のサネカズラ) 再び、上栄町駅に戻り、浜大津経由で終点の石山寺へと向かう。 京阪石山駅で乗車した一人の男性が小生の向かい側の座席の右端に腰を下ろされました。小生は視界の端でそれを捉えてはいましたが、窓外の景色に気を取られていました。ややあって、「あれっ」とその男性。その声にそちらに視線をやると、草麻呂氏でありました。現役時代、一緒の部署で仕事をしたこともある人物にて、健人会の幹事役をしていただいている人物。はからずも同じ電車になったのでありました。 午前11時10分頃に終点の石山寺駅に到着。そこから、ぶらぶらと歩きながら草麻呂氏と、本日の会場である料亭「新月」へ。(新月)(同上) 既に田〇氏が到着して居られたので、我々は二番乗り。 三人で部屋へと上がる。 三人で雑談を楽しんでいるうちに、鯨麻呂氏、杉〇氏、平〇氏、徳〇氏、正〇氏、木〇氏、竹〇氏、関〇氏、生〇氏、森〇氏、岡〇氏が来られ、最後に今〇氏が来られて、本日の出席予定者15名全員が揃い、平〇氏の乾杯の発声で、開宴となりました。 宴会中の写真もありますが、顔を消すなどの修正が面倒なので割愛です。(同上) 正午開宴から午後3時の中締めまで、飲んだり、食ったり、喋ったり、笑ったりの愉快な時間。あっという間に過ぎました。 締めのご挨拶は杉〇氏、鯨麻呂氏の一本締めで、元気な次の再会を期して解散となりました。しかし、一同、料亭からJR石山駅まで送迎バスで向かい、石山駅構内の喫茶店に立ち寄って、更に暫しの雑談・歓談を楽しみましたから、実質的な解散は石山駅ということになりました。
2016.09.07
コメント(14)
-

墓参の道すがら
このところ、ゆえあって遠出の銀輪散歩もままならず、ブログのネタも途切れがち。偐万葉シリーズでつないでいましたが、昨日は恒例の墓参(本来は9月2日にすべきであったのですが、2日、3日が不都合となり、4日になりました。)でありましたので、その道すがらのことなどを記事にして置きます。(墓地からの眺め)※フォト蔵の大型写真で見るにはココをクリック。 我が家の墓は生駒山系の山の西麓の高みにある。もう、何度となく墓参のことを記事にしているので、ブロ友諸氏その他以前からご訪問戴いて居る皆さまには先刻ご承知のことかと存じますが、上の写真のような眺望にて、大阪平野が一望であります。 そのため、自宅からは徒歩15分程度の距離ながら結構な急坂を上るので、この時期は汗、汗なのである。 さて、墓参恒例の寺の門前の言葉はこれ。(今日の言葉) われわれは、大なり小なり人に迷惑をかけ、大なり小なり人のお世話になり生きている。そのことを自覚するだけで、世の中の景色が違ったものに見えて来るというものであります。樫の実の ひとりになくば われらみな 他に迷惑を かけるほかなし (偐団栗) (注)樫の実の=「ひとり」「ひとつ」などに掛かる枕詞。(樫の実) 道端の樫の木にドングリがなっていました。樫にもアラカシ、シラカシ、ウバメガシなどと色々種類があるようですが、ヤカモチにはこれが何の樫であるのかまでは分かり兼ねることであります。 そして、ナツメの実も。既に少し色づいている実もある。秋ですね。(棗・ナツメ) 道教では、棗を久しく食すると神仙になれるとされる。 「続日本紀」聖武天皇の神亀3年9月15日の条には「内裡(うち)に玉棗(しぼ)生ひたり。勅して、朝野の道俗らをして玉棗の詩賦を作らしめたまふ。」とあり、同27日の条には、「丈人一百十二人玉棗の詩賦を上(たてまつ)る。」とあり、内裏に棗の実がなったので、聖武天皇は棗の詩賦を作って奏上せよと勅を出している。棗の実は神仙の薬と考えられていて、これが実ること自体が瑞祥と見られていたのであろう。 それはさて置き、万葉集には棗の歌は2首ある。玉掃(たまははき) 刈り来(こ)鎌麻呂 室(むろ)の樹と 棗(なつめ)が本(もと)と かき掃かむため (長意吉麻呂(ながのおきまろ) 万葉集巻16-3830)(注)玉掃=コウヤボウキ 室の樹=ネズ (玉掃を刈り取って来い、鎌麻呂よ。室の木と棗の下を掃除したいので。)梨棗(なしなつめ) 黍(きみ)に粟つぎ 延(は)ふ田葛(くず)の 後もあはむと 葵(あふひ)花さく (万葉集巻16-3834)(梨、棗、黍に粟がついで実り、つるをはわせのびる葛のように、後にもまた逢おうと葵の花が咲くよ。) 道すがらに見掛けた花はケイトウとタマスダレ。 (ケイトウ) (タマスダレ) 見掛けた虫は、ショウリョウバッタ。 (ショウリョウバッタ) 毎度代わり映えのせぬ墓参関連の道すがら・お粗末日記でありました。
2016.09.05
コメント(8)
-

偐万葉・閑人篇(その10)
偐万葉・閑人篇(その10) 本日はシリーズ第266弾、偐万葉・閑人篇(その10)とします。 ふろう閑人氏は、偐万葉では「京閑麻呂(みやこのひままろ)」と名乗っていただいて居ります。 <参考>過去の偐万葉・閑人篇はコチラから。 ふろう閑人氏のブログはコチラから。 偐家持が京閑麻呂に贈りて詠める歌21首芥子菜の 花芽摘まむと わが来しに 盛りと花の 淀の長堤われはもや 蝶にあらねば 芥子菜の 花に埋もれつ 蕾ぞ摘みし (淀川堤の西洋芥子菜) 米もまた 野菊のごとも 知らざれば なにともかとも 言ふを知らざり (見猿家持) (映画「米」) かし農園 ならぬかかしの 農園に ふえてかかしの をかしかりける (案山子家さんま)伊賀の春 たけてかかしの あれやこれ かかし農園 いぶかしをかし (伊賀の貸家三間) (伊賀のかかし農園) アホサギと われをな呼びそ 雨降れば 川面波立ち 狩もかたかり (雨野青鷺) (鴨川のアオサギ) 「男ひとり」 「女ひとり」(偐六兵衛作詞 みずにかく作曲) (永六輔作詞 いずみたく作曲)京都七条智積院 京都大原三千院恋に疲れぬ女が一人 恋に疲れた女が一人茶色の帽子を斜めに被り 結城に潮風のすがきの帯が巻のスカート靡かせて 池の水面に揺れていた京都七条智積院 京都大原三千院閑な男が写真に撮った 恋に疲れた女が一人(注)偐万葉掲載に当り「恋に疲れた」を「恋に疲れぬ」に修正した。京都七条智積院 京都栂尾高山寺外国人の女が二人 恋に疲れた女が一人共に銀髪の大股歩き 大島紬につづれの帯が足音たてた石畳 影を落とした石畳京都七条智積院 京都栂尾高山寺閑な男が写真に撮った 恋に疲れた女が一人 (智積院) 歩み記す ブログの記事の 途切れ間を 埋める狙いが 記録ともなり (ブログ家持)八雲立つ 出雲八重垣 八重なせる 三瓶の山を めぐり吾が行く (三瓶之男命)(本歌)八雲立つ 出雲八重垣 妻(つま)籠(ご)みに 八重垣作る その八重垣を (須佐之男命) (三瓶山)五十嵐(いからし)の 川の上(へ)に咲く 姫小百合 後(ゆり)にも来ませ 君待つらむぞ ははきより たねのこぼれて ははきぐさ めぶくもうれし たけたてかけつ (ふろう仙人)(注)ははき=ほうき(箒) ははきぐさ=ホウキ草 (ホウキ草・コキア) 庭掃きて コキア芽吹くを 見つけたり 色づく秋待つ はつ夏の朝 (ふろう掃人)今日だけは 京都七条 智積院 ひとひとひとぞ 青葉の祭 (偐閑人)端正な 寺の構へに 気おくれて まだふみもみぬ 寺智積院 (智積院) 百日紅 咲きてクマゼミ 鳴きたれば 梅雨明け宣言 今ぞなすべきこれやこの にはにしなれば そのみめの よきもわろきも これこそゴーヤ (苦瓜家持)みめよしも わろしもにはの わがゴーヤ つけてもにても またよしのかな (苦瓜家持) (ゴーヤ)山桃は 雄株なるらし 蛙手(かへるで)を 広げ待つとも 実にならじかも (右近の楓)(注)山桃=ヤマモモ。雌雄異株。 蛙手=かへるて・かへるで。カエデのこと。今は「楓」の字を当てるが、 万葉の頃は「楓」はカツラの雄株(ヲカツラ)を指し、雌株(メカ ツラ)が「桂」とされた。 (左近の楓、右近の山桃)茸生(お)ふる 桜木見れば 病(やまひ)えて 老いてゆくらし かくしかひとも (偐茸持(にせたけもち)) 暑過ぎる 墓参の帰り 盆にどち 来たりて共に 呑めば嬉しも (缶詰王)(本歌)新しき 年の始に 思ふどち い群れてをれば 嬉しくもあるか (道祖王 万葉集巻19-4248) (缶詰ビアパーテイー) 隠れ家の 古き障子を 貼り替へむ わが待つ秋を 迎へむがため (偐閑麻呂) (障子の貼り替え)朔日(ついたち)に 剥がし終りぬ 障子紙 弓張月の 日までに貼らむ (偐貼麻呂)(注)掲載の写真はふろう閑人氏のブログからの転載です。
2016.09.03
コメント(8)
-

阿波踊り
少し前のことになりますが、智麻呂邸に第180回智麻呂絵画展の記事を印刷に打ち出したものをお届けした後、銀輪にて近隣散歩した際に見掛けた「阿波踊り」を紹介して置きます。阿波踊りと言えば夏の風物。9月になってしまいましたので、ちょっと「ときじく」の感が否めませんが、そこは偐万葉、季節感のズレやいい加減さはお手の物ということで、お許しいただくことと致しましょう。(阿波踊り) 何処という当てもなく銀輪を走らせていて、京橋、鴫野駅近くまで来た時に、何やら賑やかなお囃子の音。見ると阿波踊りである。 どういうお祭り、イベントなのかは知らないが、自転車を停めて、暫く見物させていただきました。 (同上・女踊り) 人垣の間から覗いていると、地元の世話役のように見えた男性が「どうぞ、どうぞ」と、もっと奥に入って見なさい、と言って下さったので、遠慮なく人垣の切れ目まで行って、撮影させていただきました。(同上・男踊り) (同上)(同上)(同上・鳴り物) この後、天満橋を渡って、囲碁例会の折の昼食場所としてお世話になっている「れんげ亭」の前にさしかかると、店の前で店主の「れんげの郎女」さんが店の前の道路に打ち水をされていました。日曜日とあって、お店は夜の営業。丁度開店の準備をされている処でした。顔が合って「あら、あら、今日は何ですの?」「まあ、散歩です。」となって、お店に招じ入れていただき、冷えたミネラルウオーターをグラス一杯ご馳走になり、一休み。開店準備のお邪魔をしてはいけないと、話もそこそこにおいとま致しましたが、冷えたコーラのペットボトルとお知り合いからのお土産だというお饅頭と煎餅を持って行けと、差し入れを頂戴してしまいました。何とも厚かましい客であることだ(笑)。夏の日に 銀輪せむと 来しわれぞ れんげの水に しばし憩へり (道辺黒人)(本歌)春の野に すみれ摘みにと 来しわれぞ 野をなつかしみ 一夜寝にける (山部赤人 万葉集巻8-1424) この後、大阪天満宮を廻って帰途に着きましたが、此処でも阿波踊りをやっていました。人が多くて、撮影はいたしませんでしたが、阿波踊りは人気が高いようですな。この踊りの所作は、どんなリズムでも合う気がする。<参考>近隣散歩関連記事はコチラから
2016.09.01
コメント(10)
全16件 (16件中 1-16件目)
1










