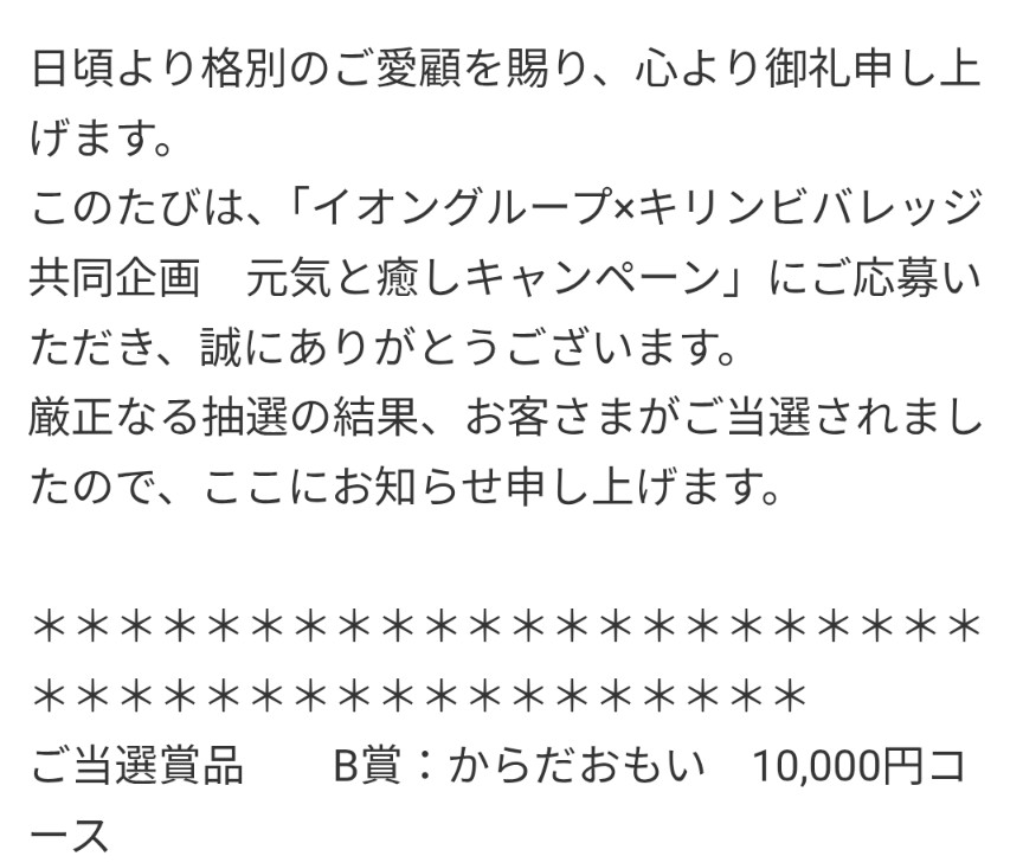2016年06月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

龍田から斑鳩の里へ(その2)
(承前) 上宮遺跡公園を出て法隆寺へと向かう。 すでに正午を過ぎていたので、国道25号沿い、産直市場「めぐみの郷」の向かいの「信州そばサガミ法隆寺店」に入って昼食。 昼食を済ませて、法隆寺南大門前到着が午後1時12分。(法隆寺・南大門)※法隆寺・Wikipedia 南大門前には修学旅行の小学生たち。何処から来たの、と尋ねると、愛知県の白木小学校、と一人の女の子が教えてくれました。 <参考追記> 白木小学校で検索したら、この小学生たちの法隆寺での写真がありましたので 追加でご紹介して置きます。法隆寺1、法隆寺2、法隆寺3 法隆寺は小生は何回目かの訪問になるが、久々のことなので伽藍配置もよく分からず、さて、何処から見て回るかと言っているうちに西院伽藍の前を素通り、東大門に来てしまった。門の向こうに八角形の建物。東院伽藍の夢殿である。(同・夢殿) 夢殿の東側が中宮寺。先に中宮寺に立ち寄る。 現在、中宮寺のご本尊、半跏思惟像は東京国立博物館へ出張中(特別展 日韓国交正常化50周年記念 ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像ー2016.6.21~7.10.)にて、本堂に鎮座ましますはそのレプリカとのことで、拝観は無料であった。 (中宮寺・本堂 南西側からの写真)※中宮寺・Wikipedia(中宮寺の会津八一歌碑)みほとけの あごとひぢとに あまでらの あさのひかりの ともしきろかも (会津八一) (注)ともしきろかも=「ともし」は「羨ましい」又は「心惹かれる」の意。 その連体形に接尾語「ろ」と詠嘆の助詞「かも」が付い たもの。「心惹かれることだなあ。」 本堂は南向きに建っているから、東側の開口部から、堂内の御仏に朝の光が射し込んだのであろうか。国宝の仏像に日光が射し込むというのも考え難いから、朝のお勤めの燈明の光が顎と肘とを静かに照らしている、という光景でしょうか。 再び、東大門から西院伽藍の方へと戻る。 鏡池の畔にあったのは、正岡子規の句碑。 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 (正岡子規) この句は1985年(明治28年)10月26日に奈良旅行の際に子規が句帳に書きとどめたもので、同年11月8日の海南新聞で発表されたのが初出。1985年9月6日の海南新聞には「鐘つけば銀杏散るなり建長寺」という夏目漱石の句が発表されているから、子規は漱石のこの句が頭のどこかにあって、柿食へば、の句を作ったのではないかなどとも言われているということは、以前の若草読書会で凡鬼さんから教えて戴いたことである。 この時、子規の体は死の床まで彼を苦しめることとなるカリエスの最初の兆候を左腰骨に感じていたのであってみれば、この句に何やら寂しさ、悲しさのようなものも感じなくもないと言うものである。司馬遼太郎の「坂の上の雲」ではこのように描かれている。 十月十九日、子規は漱石とも別れて松山を発った。帰京するつもりであったが、まっすぐにはもどらず上方のあちこちを見ようとおもった。広島から須磨まできたころ、にわかに左の腰骨のあたりが痛みだし、歩行もできなくなった。子規の晩年をくるしめたカリエスがここで症状を露わにしたのだが、子規はこのときはさほどの重症とはおもわず、痛みのうすらぐまで須磨で保養し、やがて、大阪と奈良にあそんだ。 大和路をあるき、法隆寺まできて茶店に憩うたとき、田園に夕のもやがただよっていかにも寂しげであった。 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 という句は、このとき心にうかぶままを句帳にとどめたものである。 (法隆寺境内の正岡子規句碑と会津八一歌碑) 西院伽藍の西側にあったのは会津八一の歌碑ちとせあまり みたびめぐれる ももとせを ひとひのごとく たてるこのたふ (会津八一)(法隆寺・西院伽藍の五重塔) どうやら、今回の散策は斑鳩三塔がその目的であったようですから、西院伽藍に入って五重塔をじっくりと眺めなければならないと言う次第。 中でもこの塔は、十年一日の如く、どころか1300年を1日の如く建っている塔なのであるから(笑)。(同・大講堂 左:五重塔、右:金堂) 下の写真は大講堂側から眺める金堂と五重塔ですが、カメラレンズの悪戯か、1300年1日の如くあるべき塔が左に傾き「斜塔ポーズ」を取ったのでありました。(同・大講堂側から見る金堂と五重塔と工事中の中門) 小生の心を読んで、余り受けなかったことを感じたか、直ぐに元の通りの直立姿勢に戻りました。1300年或は1400年もの直立不動は疲れると言うモノ。時にストレッチもしなくてはならないのでしょうね。ちとせあまり みたびめぐれる ももとせの 直立不動 かたもこるらむ (粟津八二) (同・五重塔、左・南側からの眺め、右・北側からの眺め) 法隆寺を出て、西隣の藤の木古墳にも立ち寄る。(藤の木古墳)※藤の木古墳・Wikipedia (同・墳丘測量図) 藤の木古墳の北隣の畑にはコスモスの花が咲き始めていました。 はやも秋の風を感じさせもする眺めです。 会津八一さん風に詠えば、いかるがの さとのコスモス さきそめて かぜにゆれそよ あきちかみかも (粟津八二)(注)さきそめて=咲き始めて かぜにゆれそよ=風に揺れそよ。「そよ」は「そよと吹く風」の「そよ」 と、「そ(代名詞)」と「よ(助詞)」が複合した感動詞 の「そよ(まったくその通りです。)」とを掛けている。 あきちかみかも=秋近みかも。「形容詞+み」は「~なので」「~だから」 の意。秋が近いからだなあ。でしょうか。(藤の木古墳北隣のコスモス畑) 藤の木古墳を出て、法輪寺へと向かう。 はい、斑鳩三塔の2番目法輪寺三重塔です。 (法輪寺・三重塔)※法輪寺(奈良県斑鳩町)・Wikipedia(法輪寺の沿革) 法輪寺境内にも会津八一の歌碑がありました。(法輪寺境内の会津八一歌碑)くわんのんの しろきひたひに やうらくの かげうごかして かぜわたるみゆ (会津八一)(注)やうらく=瓔珞。宝石などを連ねて編んだ、仏像の頭・首・胸などにかけた 飾り。(法起寺・講堂)※法起寺・Wikipedia(同・聖天堂)(同・三重塔) 法起寺三重塔です。これで、法隆寺、法輪寺、法起寺の斑鳩三塔巡り完了です。 ひろみちゃんは、この三塔が一緒に撮影できる撮影ポイントを探し求めて居られたようで、法輪寺の方にそれを尋ねて居られましたが、かつては自転車道の高みから撮影可能な場所も存在したが、今は建物が建て込んで、そのような場所はないとのことでした。 法起寺境内の池には、睡蓮が花を咲かせていましたが、荘厳な有難き雰囲気にて、花萼も黄金色を帯びているようなのでありました。(法起寺境内の池の睡蓮) そして面白かったのはこの羊歯。 小万知さんが最初に気付かれたのですが、確かに奇怪な葉です。 寺の方にシシヒトツバという羊歯だと教わりました。(同・シシヒトツバ)※ヒトツバ・Wikipedia シシヒトツバ (同上) 普通は左のようなんだろうが、成長するにつれて右のように先端が「枝分かれ」、いや、葉だから「葉分かれ」と言うべきか、二股、三股に分かれて、奇怪な面相になるという面白い植物である。通常の茎というものを必要としなくなった植物が枝分かれというシステムを葉の方に応用したということでしょうか。そもそも、通常の草花の茎と葉の関係をシダ植物に当てはめるのは無理ということですかね。(同・ノキシノブ) シシヒトツバの隣に生えていたノキシノブもよく見ると先端が二股になっている。シシヒトツバの真似をし出したのだろうか。 ブロ友のウーテイス氏は植物にも「意思」があるという考えをお持ちですが、このノキシノブも隣のシシヒトツバを見ているうちに、「ワシもあんな風にやってみたい」と念じて、遂にそれを成し遂げたのがこの姿なのかも知れませぬな。のきしのぶ ししひとつばの ごとあれと 念じてつひに 葉をや分けたる (忍家持) これにて斑鳩の里散策終了。帰途は西名阪道路経由、途中SAで珈琲ブレイクのあれこれのお喋りを経て、小万知さんを錦織公園付近までお送り申し上げてから外環状道路で、瓢箪山駅近くまで。そこで解散でありました。駅近くに預けてあったMTBで自宅へ。銀輪万葉とは言え、銀輪を走らせたのはこの部分のみでありました。<完>
2016.06.28
コメント(10)
-

龍田から斑鳩の里へ(その1)
本日は、若草読書会のメンバーの小万知さんと「ひろみの郎女」ことひろみちゃん8021さんと3人で法隆寺など斑鳩の里へ出掛けて参りました。 ひろみちゃんのマイカーに同乗してのもので、銀輪ではないのですが、わがブログのカテゴリーには、ドライブというのがありませんので、「銀輪万葉」のカテゴリーで記事アップすることと致します。 午前9時待ち合わせで、ひろみちゃんと合流。彼女の車で、外環状道路を南へ。錦織公園近くで午前10時待ち合わせで、小万知さんと合流。沢田交差点を右折、東へ。石川橋で石川を渡り、近鉄大阪線河内国分駅前からR25に入り、大和川沿いに走り、JR三郷駅手前の橋を渡って、先ず訪ねたのが「磐瀬の杜」。鏡王女の歌碑を見るためです。(磐瀬の杜) この磐瀬の杜や鏡王女の歌碑は2009年9月6日の日記にも採り上げているので、記事や写真は重複する部分もありますが、再度掲載して置きます。(鏡王女歌碑)神奈備の 磐瀬の杜の 呼子鳥 いたくな鳴きそ 我(あ)が恋益さる (鏡王女 万葉集巻8ー1419)(神なびの磐瀬の社の呼子鳥よ。そんなにひどくは鳴かないでおくれ。わたしの恋の思いがつのるから。) (注)神なび=神のおいでになるところ。 呼子鳥=カッコウのことと思われる 鏡王女は額田王の姉ともされる女性であるが、天智天皇に寵愛された後、藤原鎌足に下賜されるという現代風には悲しい運命の女性。この歌の「あが恋まさる」の相手は、鎌足では勿論なく、天智天皇のこととする方がしっくりするが、夫鎌足の死後に作った歌であり、鎌足を偲んでの歌であろうとする説が有力のようです。 ひろみちゃんも小万知さんも天智さんの仕打ちには「怪しからん」という反応でありましたので、深くは立ち入らぬが無難と男の本能が働きました(笑)。 もう1首、磐瀬の杜を詠った歌が万葉にはある。 志貴皇子の歌である。こちらは、無難な歌であります。 なお、「磐瀬の杜」の所在については諸説あって何処とも定まっていない。神奈備の 磐瀬の杜の ほととぎす 毛無(けなし)の岡に いつか来鳴かむ (志貴皇子 万葉集巻8ー1466)(神奈備の磐瀬の杜のほととぎすは、毛無の岡には、いつになったら来て鳴くのだろうか。) (注)毛無の岡=法隆寺北方の毛無池の辺りの岡とする説もあるが不明。(龍田大社) 磐瀬の杜を出て、龍田大社に向かう。小万知さんが龍田大社には行ったことがないとのことなので、ついでに立ち寄ることとしたもの。 ひろみちゃんと小生は先月1日に此処に来ているのであるが、その折の記事では、この神社などはひろみちゃんにブログ記事アップを譲り、小生ブログ記事では割愛しました。で、今度は小生の方でアップせよ、というのが彼女の意向。 しかし、小生も過去に何度も訪問して居り、記事にもアップしているので、それらに譲ることとします。 <参考>見まくの欲しき瓊花そして墓参 2016.5.2. 平群ー竜田川ー大和川ー龍田大社ー竜田越え(その2)2009.9.4.(拝殿右側の高橋虫麻呂歌碑) 上の歌碑の歌は高橋虫麻呂の長歌であるが、上記<参考>の2009年9月4日の記事に、その全文と現代語訳を掲載していますので、それをご参照下さい。 で、ついでにと、これまた5月1日に見た沈下橋を小万知さんにもご覧戴こうと明治橋を渡って大和川左岸の道を行くが、途中から自転車・歩行者専用道にて車は進入禁止。運転席隣の偐家持さんは銀輪専門なので、車のナビをするのは時に不適な場合があります。今回は、その例で、大和川沿いの自転車道を離れて迂回コースに入った途端に方向感覚が狂ったようで、ちと方向違いの迷路に陥るというハプニングもありました。しかし、途中2回、郵便配達の男性とガソリン・スタンドの女性社員とに道を尋ねるなどして、何とか迷路を脱出。沈下橋に無事到着しました。(大和川の沈下橋)(同上) 目的地は法隆寺、法輪寺、法起寺の斑鳩三塔なのであるが、その前に上宮遺跡公園に立ち寄ろうと、御幸大橋で大和川を渡り、富雄川右岸の堤防上の道を北上する。 これまた自転車道にて、本来は車が走るべき道ではなかったよう。しかし、何とか走り抜けることが出来て、上宮遺跡公園に辿り着くことができました。(上宮遺跡公園) 上宮遺跡公園や手前の成福寺跡の一帯は、聖徳太子が晩年を過ごした飽波葦垣宮のあった場所ではないかとも言われている。(成福寺跡) <参考>飽波葦垣宮跡 奈良の寺社・成福寺 飽波葦垣宮(上宮遺跡掘立柱建物群発掘説明板) 2009年5月に中学時代の恩師井〇先生の墓参をした帰りに自転車で富雄川を下って来て、たまたま目に入って立ち寄ったのが、この公園を知った最初であるが、その時と少し様子が変わっていました。 <参考>墓参と銀輪行 2009.5.24.(聖徳太子像) この聖徳太子像は当時はなかったかと。また、会津八一の歌碑の歌も別の歌に碑板が変わっていました。 犬養万葉歌碑の歌、聖徳太子の歌、その返歌、在原業平の歌などは以前のままなので、上記<参考>の2009年5月24日の記事をご参照下さい。(犬養万葉歌碑)(聖徳太子歌碑)(聖徳太子への「飢え人の返歌」の歌碑)(在原業平歌碑)(会津八一歌碑)いかるがの さとのをとめは よもすがら きぬはたをれり あきちかみかも (会津八一) 本日はここまでとします。続きは明日に。 (つづく)
2016.06.27
コメント(8)
-

岬麻呂旅便り190・世界三大花木ジャカランダ
先日、友人の岬麻呂氏から旅便りが届きましたので、ご紹介申し上げます。 今回の旅の主目的は、旅便りのタイトルから推測するに、世界三大花木のひとつ、ジャカランダの花を見ることにあったのでしょうか。 <参考>世界三大花木 小生は、この花、見たことも聞いたこともないので、初めてそれと知る花であるのだが、同氏のご自宅近くにはこの木があるとのこと(下掲写真)。(ジャカランダの木) ※ジャカランダ・Wikipedia(ジャカランダの花) ジャカランダというのはノウゼンカズラ科キリモドキ属の植物だそうで、色は違えど花の形はノウゼンカズラに似ている。葉はネムノキやアカシアに似ている。キリモドキという名は花の色が桐のそれに似ているからでしょう。 自宅近くでも見ることのできる木の花を見るために日南海岸まで出掛けるなどとは如何にも岬麻呂らしき風流でありますが、モドキとあらば万葉モドキ・家持モドキの偐家持も見に行かぬでもないですかな(笑)。尤も、モドキはこの世に数々ありますれば、モドキを訪ねる旅はキリもなきこととなる惧れもないではないと言うべきか。(日南海岸のジャカランダの森)(旅・岬巡り報告190) 「日南海岸沿いR220は、岬と入江がくりかえす風景がお気に入りだったが、近年トンネルや橋が整備され、便利さと引き換えに趣が減少。往年の観光人気ない。」とは岬麻呂氏の評であるが、以下、同氏のご説明により、送付されて参りました写真をご紹介して置きます。(JR西大山駅と黄色の郵便ポスト) 西大山駅・Wikipedia※JR日本最南端の駅・西大山駅 背景の山は薩摩富士ともいわれる開聞岳。知覧飛行場(現在は資料館)が近く、終戦直前の特攻隊はこの山を訓練の目印にした。(青島の郵便ポスト) 青島・宮崎市観光協会※青島 青島神社参道の左側に黄色いポスト。右側には青島亜熱帯植物園がある。大温室はメンテナンス休館中であった。(青井阿蘇神社)青井阿蘇神社・Wikipedia※青井阿蘇神社 熊本県・人吉市の中心部にある国宝の茅葺神社。相良氏の創建。(五木村)五木村・Wikipedia※子守唄の里五木 熊本県・八代市と人吉市を結ぶR445の途中にある五木村。幼い子供が人吉などに子守の年季奉公に出され、家恋しさに唄われた民謡。歌碑は名優森繁久彌氏の筆による。写真中央に子守のブロンズ像がある。(関之尾の滝)関之尾滝・Wikipedia※関之尾の滝 霧島神宮の南東がすぐ宮崎県との県境で都城市。関之尾甌穴で有名、その流れが滝になっている場所。前日の大雨の影響で水量多く飛沫でカメラレンズがすぐぬれる。<参考>岬麻呂旅便り関連記事一覧はコチラから
2016.06.25
コメント(12)
-

富良野・麓郷の森の木力工房からの贈り物
先日、富良野・麓郷の森の「木力工房」から贈り物が届きました。 当ブログ読者なら、「木力工房」ではお分かりにならなくても、偐万葉・ふらの篇でご承知の、ブロ友furano-craft氏と言えばお分かり戴けるでしょう。 furano-craft氏からの贈り物が届いたのであります。 それは、こんな桐箱に入っていました。 (木力工房からの贈り物) 桐箱の中に入っていたのは・・・。 斧と丸太。薪割りのオブジェでありました。(木力工房からの贈り物・斧のオブジェ) この作品は、furano-craftさんが、ご自身のブログで過日ご紹介されていて、面白いと小生が協賛の歌を作ったばかりでありましたので、このように目の前に現実に立ち現れることになろうとは思いもよらぬことで、まさに「ビックリポン」でありました。 <参考>この作品・斧のオブジェが掲載されている同氏のブログ記事 今日は雨・・・黒い森のなかで 2016.6.9. この作品に寄せた偐家持の歌が掲載されている当ブログ記事 偐万葉・ふらの篇(その7) 2016.6.12. (同上) furano-craftさん、素敵なプレゼント。 本当にありがとうございました。<参考>過去の偐万葉・ふらの篇はコチラ。 furano-craft氏のブログはコチラ。 同氏開設の木力工房・富良野麓郷庵(富麓庵)のHPはコチラ。<追記> 下記の偐山頭火さんのコメントから、箱に入った状態の斧のオブジェの写真が掲載されていないことに気がつきましたので、追加で掲載して置きます。
2016.06.24
コメント(7)
-

銀輪花散歩・アザミからアメリカフウロまで
暫くブログをサボっていましたので、そろそろアップしなくては、と言う訳で銀輪花散歩であります。 先ずはアザミ。 アザミも色々と種類があるようですが、これはノアザミ。(ノアザミ) ※ノアザミ・Wikipedia (同上) アザミの咲く原に黄色く群生しているのはブタナ。 タンポポに似ているが、ずっと背が高い。タンポポモドキとも呼ばれるが、どちらにしろ、何やらお気の毒な名前である。 もっとも、「モドキ」というのは「偐」に通じる名であるから、当ブログとしては歓迎すべき花と言うべきかも知れない。(ブタナ、別名タンポポモドキ) ※ブタナ・Wikipedia (同上) 次はヒメジョオン。これはどこにでもある花。(ヒメジョオン) ※ヒメジョオン・Wikipedia(同上) ヒメジョオンを撮影していて、見上げると、クルミの実がなっていました。(オニグルミ) ※オニグルミ・Wikipedia (同上) 胡桃の実から、何となくブドウを連想したら、葡萄畑に出くわしました。出来過ぎた話ですが、実際にその通りなのだから仕方がない(笑)。(葡萄) (同上) 同じ実でも、コチラは赤い実。名前が分からない。スグリとかサンザシという名が頭に浮かんだが、どうも違うようで、よく分りません。と言うことで「赤い実の木」として置きました。(赤い実の木) ※キンギンボク・Wikipedia オオヒョウタンボク・Wikipedia <追記> 下記コメントで小万知さんより、ヒョウタンボク(瓢箪木)とご教示戴きました。キンギンボク(金銀木)とも呼ぶようで、Wikipediaではキンギンボクとなっていて、「ヒョウタンボクことキンギンボク」と記されているが、当ブログでは「キンギンボクこと、ひょっこりヒョウタンボク」と表現して置きます。 (同上) そして、白い花。これは睡蓮ですが、ヒツジグサ(未草)ですな。(睡蓮 ヒツジグサ) ※ヒツジグサ・Wikipedia (同上) ヒツジグサの隣にはびっしりと菱の葉が水面を覆っていました。(菱) ※ヒシ・Wikipedia(ミモザでしょうか?) ※オジギソウ・Wikipedia ギンヨウアカシア・Wikipedia そして、通りかかった民家の庭先で目にしたこの木。多分ミモザかと思うが、葉の色が独特で目を惹きました。(同上) 最後は、アメリカフウロの種が落ちた後の姿。 中央のポールに街灯のようにくっついている丸いものは何であるのでしょう。(アメリカフウロ) ※アメリカフウロ・Wikipedia(同上) 以上、些か手抜きの記事ですが、銀輪散歩で見掛けた花・植物を並べてみました。 最後のアメリカフウロは智麻呂邸を訪問した際に、同邸の前の公園に生えていたのを摘んで智麻呂さんにお見せしたものにて、銀輪散歩とは少し違うのですが、まあその辺は大雑把な当ブログ記事のこと、特に問題はないでしょう。
2016.06.22
コメント(14)
-

第177回智麻呂絵画展
第177回智麻呂絵画展 今日は朝から雨ですが、昨日、智麻呂邸を訪問し、新作2点を「仕入れ」て参りましたので、第177回智麻呂絵画展の開催といたします。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 最初の絵は唐招提寺の瓊花であります。(唐招提寺の瓊花) これは、当ブログの5月2日の記事に掲載の写真を絵にされました。 勿論、当絵画展初登場の花であります。(元の写真) 今の時期の花と言えば、やはり紫陽花ですね。 今回は2点の作品が出展されました。(紫陽花A) 紫陽花Aはデイサービスに行かれて描かれたものであったかと記憶します。また、紫陽花Bは、ひろみの郎女さんことひろみちゃん8021さんが先の若草読書会の折にお持ち下さったものであります。 紫陽花の絵はこれまでにも沢山描かれていて、この時期の定番の花であります。(紫陽花B) ※紫陽花が出ている過去の絵画展は次の通り。 第1回展、第4回展、第7回展、第34回展、第36回展、第37回展、第40回展、 第58回展、第59回展、第81回展、第82回展、第100回展、第101回展、 第120回展、第122回展、第143回展、第145回展、第161回展、第162回展 この時期に相応しいと言えば、このドクダミの花もそうではないでしょうか。智麻呂邸近くの道端に咲いていたものを写生されました。(道の辺のドクダミ) ※ドクダミが出ている過去の絵画展は次の通り。 第79回展、第102回展、第120回展、第122回展、第143回展、第161回展 次の花はカタクリ。少し季節遅れですが、小万知写真集から絵にされました。(カタクリ) ※カタクリの絵が出ている過去の絵画展は次の通り。 第79回展、第175回展 次も少し季節遅れですが、アネモネです。(アネモネ) ※アネモネが出ている過去の絵画展は次の通り。 第102回展 当ブログの4月29日の記事に掲載の写真を絵にされました。(元の写真) 次は、テントウムシとコガネムシとの愉快なニラメッコのシーンです。これも、当ブログの5月26日の記事に掲載の写真を絵にされたものです。(テントウムシとコガネムシ) ※テントウムシは初登場。コガネムシの出ている過去の絵画展は次の通り。 第105回展(元の写真) 次は、智麻呂さんらしからぬ絵と思いきや、お孫さんのナナちゃんが描かれた絵でありました。ナナちゃんの新しいコートでしょうか。智麻呂さんのアトリエに飾ってあったので、撮影したら、作者は智麻呂氏ではなくナナちゃんであったと言う次第。 撮ってしまったら、ナナちゃんの承諾も得ずに絵画展に出してしまうというのは、偐家持美術館の常套手段。今回も無断出展であります(笑)。(ナナちゃんの絵) ※ナナちゃんの絵が出ている過去の絵画展は次の通り。 第3回展、第91回展、第99回展、第103回展、第111回展 最後は、お決まりのデザート。今回は果物であります。 先の若草読書会にヤカモチ館長が差し入れた果物たちであります。 どうぞ、皆さまもご遠慮なくお召し上がり下さいませ。(果物) 以上です。 本日も、ご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。
2016.06.16
コメント(15)
-

珍客来たる
昨日、我が家に珍客がありました。 体長2cm余のコクワガタのメスでした。 夜のうちに我が家に侵入し、朝になって居間を這っているところを家人に発見され御用となったのでありました。まあ、「御用」と言っても、職務質問したり、家宅侵入で告発しようと言うのではなく、写真に撮らせて戴くというに過ぎぬもの。撮影後は庭の樫の木にお移り戴きました。 樫の幹に移された時は、前肢を踏ん張り、頭部を高く持ち上げて、周囲を警戒するかのように長らく固まっていましたが、やがて元通りに姿勢を低くし、そろそろと幹を上へと上って行き葉陰に隠れて見えなくなりました。自身の身の振り方は彼女自身で考えて戴くべしで、山に帰るなり、他家にまた侵入するなり、お好きなようにと言う訳であります。 小生が子供の頃は、裏山の山裾の林に入れば、カブトムシやクワガタムシがいくらでも捕れたものだが、最近は(捕りにも行かないけれど)先ず見かけない。昔は、夏になると電灯の明かりに誘われてカブトムシやクワガタムシやカナブンがよく迷い込んで来たものだが、そういうことも今では無くなっているので、今回の来訪は、何やら嬉しい珍客の来訪と見えたのでありました。(コクワガタ♀)(同上)
2016.06.15
コメント(12)
-

偐万葉・ふらの篇(その7)
偐万葉・ふらの篇(その7) 本日は偐万葉シリーズ第261弾、ふらの篇(その7)であります。ふらの篇は昨年の12月以来のこと。久々の登場であります。 北海道・富良野に移住し、頑張って居られるfurano-craft氏への一種の応援歌(のつもり)であります(笑)。 <参考>過去の偐万葉・ふらの篇はコチラ。 furano-craft氏のブログはコチラ。 同氏開設の木力工房・富良野麓郷庵(富麓庵)のHPはコチラ。 偐家持がふら麻呂に贈りて詠める歌23首あらたしき 年の始めは 申年に あればさるなど まづ作らなむ (偐猿丸) (元日の作品)麓郷の 森の神々 降(お)り来らし さはさは雪の 間なくし降(ふ)れば (偐雪丸) (麓郷の森の雪) 凍り道 しかと見ぬ鹿 しかたなし 滑り形無し 転ぶ蝦夷鹿 (鹿衛門) 蝦夷鹿も 車固めし 雪道は 時にアイゼン 欲しとやあらむ (鹿衛門) 近道も 滑り転びて おそまつの 雪の道行き 蝦夷鹿衛門 (ちかえもん) スライディング したるやいなや しかにきけ すべりてくるま よけてやあらむ (しかえもん)麓郷の 森に幾年(いくとせ) 住み住みか 都のてぶり 忘らえにけり (山森奥良)(注)初案「住み住みて」を「住み住みか」に修正。(本歌)天ざかる 鄙に五年(いつとせ) 住(すま)ひつつ 都の風俗(てぶり) 忘らえにけり (山上憶良 万葉集巻5-880) 安倍の腹 さぐりてきけば かすかなる 記憶もなしの 言ひ逃がれかも (安倍不可麻呂)(注)初案「さぐりてみれば」を「さぐりてきけば」に、「記憶もなしと」を「記 憶もなしの」に、「言ひ逃げすかも」を「言ひ逃がれかも」に修正。(本歌)天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも (安倍仲麻呂 古今集406 小倉百人一首7) 男らは 白き息吐き 黙々と 雪かきすらし SLのごと 麓郷の 森にし生きる 冬とふは 日々これ雪との たたかひなるや(注)初案「たたかひなりき」を「たたかひなるや」に修正。 負けへんで 関西なまりに 言ひつつや 雪かき行く道 つくる背子かな われら今 ここに集ふは 用無しの 身となる春を 待つにはあらじ (除雪四天王プラスワン) (除雪四天王) 今しばし ありたきものと なごり雪 のこしつ冬は 去り行くらむか 去り行ける 冬が最後に くれる笑み やさしき言葉の ごとや雪降る (なごり雪) 音もなく 春の雪降る 窓越しに 森見つ何を 君つくらむや 北辛夷 咲く麓郷の 春たけぬ どれ下草を 明日は刈らなむ (蝦夷鹿麻呂) (キタコブシ) 延齢草 咲く麓郷の 木々の間に 月も真白く 昼寝やすらむ (蝦夷鹿麻呂) (延齢草) (昼の月)蝦夷鹿も 草刈時は 明日なりと 知りてやあらし 草を食(は)む見ゆ (蝦夷鹿麻呂) (蝦夷鹿) ひとはひと はやりすたりは きにとめず わがみちこれと ゆくひとぞよし 斧一閃 ぱっかり薪の 割れる音 なに迷ふこと あるやと言へり (閃家持) 薪割りの ごとや単純 明快に 生きる強さよ 風心地よし (薪家持) (薪割りのオブジェ)もののふの 八十(やそ)オコジョらが 居並べる アトリエもあり 麓郷の森 (偐家持)(本歌)もののふの 八十少女(やそをとめ)らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子(かたかご)の花 (大伴家持 万葉集巻19-4143)彫り彫りて 作れるオコジョ 手に取りて そばに置いてよ 愛(は)しきと思(も)はば (偐郎女)(本歌)恋ひ恋ひて 逢へる時だに 愛(うつく)しき 言(こと)盡(つく)してよ 長くと思(も)はば (大伴坂上郎女 万葉集巻4-661) (オコジョ)<脚注>掲載の写真はfurano-craft氏のブログからの転載です。
2016.06.12
コメント(12)
-

青雲会囲碁例会・鶴見神社
本日は、大学同窓会の囲碁サークルの例会の日。 会場の堂島まで、MTB(マウンテンバイク)で出掛ける。 今日は、中央大通りを避けて、吉田駅前で北に入り、あとはジグザグに適当に走っていると、徳庵橋の処で寝屋川にぶつかる。寝屋川左岸(南岸)の道を西へ。次の今津橋で寝屋川を渡り、一つ目の信号で左折し、道なりに走っていると、鶴見神社というのに出くわした。多分、初めて通りかかる神社の筈。少しご挨拶申し上げることとする。(鶴見神社) 祭神や神社の由来は下記<参考>をご参照下さい。 <参考>神社めぐり・鶴見神社、鶴見神社(大阪市)・Wikipedia(同上・本殿) 鶴見という名の由来は、下記にあるように、源頼朝に関連した伝説にあるようです。 横浜の「鶴見」も同じ伝説に由来するのだろうか。(鶴見の名の由来) 境内にある2本のクスノキ。地下で根が絡まり合っているとのことで「夫婦楠」と呼ばれているとのこと。 まあ、至近の距離に2本の大木があれば、地中で根っこが絡まったり、合体したりするのは普通のことで、珍しくもないのではないかという気もするのではありますが。(夫婦楠)(同上) 再び寝屋川沿いに戻り、今度は右岸(北岸)を西へ。JR京橋駅の前を通過して、いつものコースに入り、天満橋経由、裁判所前通過。いつもの喫茶店「なかおか珈琲」で昼食&珈琲。(喫茶店・なかおか珈琲) 昼食後、会場に行くと既に山〇氏と中〇氏が来られていて、碁盤・碁石の設営中。小生もお手伝い。その後、銭〇氏、若〇氏、田〇氏と今日が初参加の河〇氏がご来場。本日は全7名の出席でした。 小生の対局は、中〇氏に負け、銭〇氏とは2局連続して打って1勝1敗。ということで1勝2敗という成績でした。負けた碁は何れも終盤でアタリになっているのを見落としてというケアレスミスによるもの。今日は注意力散漫でした。「覗きにつがぬ馬鹿はいない」とは碁の常識であるが、「アタリにつがぬとは馬鹿も極まれり」というもの。こんな見落としをしているようでは勝てる訳がありませんな。
2016.06.11
コメント(4)
-

句集「晏」
友人の凡鬼さんが句集を出されました。 5日の若草読書会では出席者に各1冊ずつそれを頂戴いたしましたが、次回、9月24日の読書会では、この本を課題図書として、凡鬼さんご自身からお話をお伺いすることとなりました。 凡鬼さんの俳句は当ブログでもこれまでにいくつか掲載させて戴いていますが、こうして句集という形で拝見すると、あらためてその深い教養に感じ入ると共に同氏の物事に対する心の姿勢の真面目さと物事を見つめる眼差しのやわらかさとやさしさがよく感じられて、いかにも同氏の句であると思う次第。全329句、一気に読めてしまえる。同氏の手になる俳句は既に何千句かになっているとのことだから、第二句集もそのうちに出されるのではないでしょうか。 凡鬼さんの句は、予てより小生は「品がある」と感じていましたが、それは歴史や文学への深い教養と弱きものに心を寄せる視線の「やさしさ」とが織りなして出来上がる句であるからなのでしょう。 当ブログをご訪問下さるお方でご興味を持たれたお方は、是非、手に取りご一読下されば幸甚に存じます。ふむふむ、と同感できる句が沢山見つかり、心地よい気分になるのではないかと(笑)。 (岩出くに男第一句集「晏」)<参考>凡鬼さんの俳句が掲載されている当ブログ過去記事の主なもの。 凡鬼野菜2012 2012.7.19. 凡鬼氏の俳句 2009.11.4. 子規と漱石 2010.9.19. 第35回智麻呂絵画展 2009.6.3. 第60回智麻呂絵画展 2010.7.19. 第65回智麻呂絵画展 2010.10.20. 第87回智麻呂絵画展 2011.9.18. 俳句の話・若草読書会 2011.9.25. 第91回智麻呂絵画展 2011.12.18. 第99回智麻呂絵画展 2012.5.13. 煤逃げ墓参 2010.12.29. 柘榴 2008.9.15. メリークリスマス2013 2013.12.23. 第11回和郎女作品展 2012.1.29. (「晏」裏表紙)
2016.06.09
コメント(8)
-

偐万葉・ビッグジョン篇(その32)
偐万葉・ビッグジョン篇(その32) 本日は、久々の偐万葉シリーズ第260弾、偐万葉・ビッグジョン篇(その32)といたします。 <参考>過去のビッグジョン篇はコチラから ビッグジョン氏ブログはコチラから 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌22首生駒山の このてがしはの 両面(ふたおも)に 言ぞ込めつつ 駄洒落戯れ歌 (佞人家持) (本歌)奈良山の 児手柏(このてがしは)の 両面(ふたおも)に かにもかくにも 佞人(ねじけびと)の徒(とも) (消奈行文大夫(せなのぎやうもにのまへつぎみ) 万葉集巻16-3836) <訳:奈良山のコノテガシワが両面であるように、ああも言い、こうも言いと右往左往、佞人のやからよ。> おほなれる おほどの君も すべなかり いやこの頃の 越のサウルス (恐竜天皇)(注)おほどの君=男大迹天皇(おほどのすめらみこと)、継体天皇のこと。 (JR福井駅) ひったくりの 元祖なるかや わが手なる パンかっさらひ トンビ飛び行く(とびショック歩麻呂)お接待 受くる遍路の 身なるわれ けふはトンビに パンおもてなし (ひったくられ歩麻呂) (滝湖寺奥之院) ああ大和 はつ夏の風 光降り 此処もコクリコ ナガミコクリコ (与太野晶子)(本歌)ああ皐月 仏蘭西の野は 火の色す 君も雛罌粟(こくりこ) 我も雛罌粟 (与謝野晶子「夏より秋へ」) (ナガミヒナゲシ) 野豌豆 カスマもあれば 白花の 黄ばめるものは カシマなるらむ (鹿島建設)(注)カスマ=カスマグサ。カラスノエンドウとスズメノエンドウとの中間位の 大きさの野豌豆ということからカスマグサと呼ばれる。 カシマ=カラスノエンドウとシロバナカラスノエンドウの中間ということ で、カシマグサと洒落てみた造語。 (黄色い花のカラスノエンドウ) 光る海 見つつも行けば 伊豆の浜 やはらに砂の 押しかへし来る (伊豆の浜辺) (寝姿山) 寝姿を 背子には見せじ 下田なる 寝姿山は をみなにぞある 下田冨士 見つつもをらむ われひとり 姫踊子草の 咲けるベンチに (海端康成) 駿河なる 富士の高嶺は 天地(あめつち)の 分れし時ゆ 敷島の 大和の国の 鎮(しづめ)とも います神なり 古(いにしへ)ゆ 宝と人の 拝(おろが)める 神の山なり 草枕 旅行くわれも 赤人の はた虫麻呂の ごとあらむ 伊豆の浜道(はまぢ)を 越えぞ来て 千本三保の 松原の 道のこちごち 道の隈 仰ぎおろがみ わが旅の 無事をし祝(ほ)がむ 括りとすらむ 反歌伊豆の坂 わが越えくれば 富士の山 いや高々に 神さびにけり (海辺の可不可) (富士山)八重むぐら のせてブログの 主人(あるじ)言ふ やかもち来たり コメ書くらむと (徒歩歩家持)(本歌)八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそみえね 秋はきにける (恵慶法師 拾遺集140 小倉百人一首47) (ヤエムグラ) わびさびも わさびとぞ見ゆ 静岡の わさびづくしぞ わび茶はせんか (せぬの利休) (わさびづくし)白妙の 清き花愛(め)で 君や君 朴葉布(し)き折り 一献なさめや(本歌)皇祖神(すめろぎ)の 遠御代(とほみよ)御代は い敷き折り 酒(き)飲むといふそ このほほがしは (大伴家持 万葉集巻19-4205) (朴) 八千種の 花は見つれど どれもこれも それと知る名は いや少なきも(本歌)八千種(やちぐさ)の 花はうつろふ 常磐なる 松のさ枝を われは結ばな (大伴家持 万葉集巻20-4501) (エゴノキ) (源平小菊) もののふの 八十少女)らも おどろきの 白に黄色に かたかごの花 (注)初案「白に黄色の」を「白に黄色に」に修正した。(本歌)もののふの 八十少女らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 (大伴家持 万葉集巻19-4143)(注)八十少女=やそをとめ。多くの少女たち。 (白いカタクリ) (黄色のカタクリ) 花あれば われにはすぐる 馳走なり 酒は自前と 心得ぬれば (花歩麻呂)花あるも 酒ありてこそ 人生は 楽し愉快と 言ふべかりける (酒歩麻呂) ささゆりの さやにぞさける そのはなに さやにさやさや はつなつのかぜ (偐百合麻呂)小百合花 歩麻呂ともしも 朝なさな 往き来に見らむ 歩麻呂ともしも(本歌)あさ裳よし 紀人(きひと)ともしも 亦打山(まつちやま) 行き来(く)と見らむ 紀人ともしも (調首淡海(つきのおびとあふみ) 万葉集巻1-55)(注)ともし=羨し。うらやましい。 (ササユリ) 可も不可も なしとふ君が 玉葱の 今年もさはに なりたるぞよし (玉葱持)棚ぼたを 待ち勝ちヤカモチ 玉葱の ひとつもこの手で 育てたるなし (棚葱持) (玉葱)(脚注)掲載の写真はビッグジョン氏のブログからの転載です。
2016.06.06
コメント(10)
-

若草読書会・チェルノブイリの祈り
本日は若草読書会の例会でした。 出席者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼氏、祥麻呂氏、ひろみちゃん氏と小生の6名といつにない少人数となりました。ひろみちゃん氏は今回は初参加。同氏は小生の中学の同級生でブロ友にして、智麻呂絵画のファンでもあるということで今回からご参加戴くこととなりました。若草読書会としては、今年の新年会のれんげの郎女さんに続く新入生ということになりますが、このように新しい人がご参加戴けるのは有り難いことであります。 今回の発表者は祥麻呂氏。課題図書は、ベラルーシのノーベル賞作家、スベトラーナ・アレクセービッチ著「チェルノブイリの祈り」(岩波現代文庫)である。 この本は、1986年4月26日に起こった、ソビエト連邦(現、ウクライナ)のチェルノブイリ原子力発電所4号炉の爆発事故によって、被害を受けた住民や事故処理に当って被爆した多数の人々や被爆して発病し死んでいった人々の遺族の証言を収集したドキュメンタリーである。 放射能被爆というものの怖さについて何の知識もなく、その危険性についての情報を開示されることもなく、満足に線量計も与えられず、防護服の支給もなく、「お国のため」と事故処理に当たり、多量の放射線に被爆し発病し死んで行った人たちについての遺族の証言。病床にあって苦しむ人たちの証言。作者は自身の意見や感想を差し挟むことなく、膨大な人々の証言を積み上げることによって、あの事故が何であり、何が起こり、その時人々はどう動き、国家というものが何をしたのか、何をしなかったのか、ということを明らかにして行くという(ドキュメンタリーというものはそもそもそういうものなんであろうが)手法で、僕らの前に問題を、ものを思う素材を提示し、歴史的事実に対するイメージの喚起を促している。読み進んでいて楽しいものでは、勿論ないし、むしろ、出来るなら目を背けていたい現実ではあるけれど、フクシマを経験した僕らは、原子力発電に電力を依存して生きている僕らは、やはり読んで置かなくてはならない本の一つなのであろうと思われる。 原発の問題や国家権力の隠蔽体質や色々の角度から感想や意見が参加者の間で交わされましたが、それを「ドキュメンタリー」するほどの筆力もありませぬゆえ、詳細は割愛であります(笑)。 議論が一段落した処で、珈琲ブレイク。ひろみちゃん氏が持参下さった珈琲とお菓子、また本日欠席の小万知さんが差し入れて下さったお菓子を戴きながら雑談へと移行。その後、恒郎女さんがご用意下さった茶蕎麦を戴きました。 何でも、恒郎女さんがまだうら若き女学生であった時代、京都の蛸薬師の近くにあった蕎麦処「大文字」(今はもう廃業したかで無くなっている)の茶蕎麦が美味しくて、それを真似て作ってみた、という茶蕎麦でありました。 大文字か中文字か小文字か確かめてみようという憎まれ口をきいて箸を付けた小生でありましたが、なかなかに美味。勿論、小生は「大文字」の茶蕎麦なるものを存じ上げぬので、それと比べての判定は致しかねるのであるが、一応「大文字」の評価でありました(笑)。(アメリカフウロの種子) ひろみちゃん氏は、茶蕎麦の写真も撮って居られましたから、彼女の本日のブログを覗いて戴ければ、或は、その写真が掲載されているやも知れませぬ。 <参考追記2016.6.6.>ひろみちゃん氏の同ブログ記事 かくて、当方は、本の表紙の写真しかありませぬゆえ、拍子抜け、と評されるのも癪なので、アメリカフウロの写真を上に掲載して置きました。 これは、智麻呂邸の前の小さな公園の一角にて見つけたものであります。ヤカモチは未だ喫煙の悪癖から脱出できて居りませぬので、読書会の途中で抜け出しては、その公園で一服するということが常であり、本日も何度か脱出して公園へ、でありました。 勿論、読書会とも原発とも何の関係もない写真であります。読者への「おもてなし」という奴であります(笑)。写真ネタがないから、花のタネの写真で、という駄洒落でもあります。 なお、次回読書会は、9月24日(土)午後1時半~と決まりました。
2016.06.05
コメント(8)
-

墓参・花散歩・姫蔓蕎麦からアメリカデイゴまで
本日は、墓参と花散歩です。 墓参の道で最初に見たと言うか、撮影した花はこれ。(ヒメツルソバ・姫蔓蕎麦)<参考>ヒメツルソバ・Wikipedia この花はヒマラヤ原産で明治時代に日本に入って来たそうな。 咲き始めはピンクであるが、徐々に色が抜けて白色に変化する。 昨年10月の日記でも写真を掲載しているが、春にも秋にも花を付ける植物のようです。真夏には花を付けないとのことであるから、来月にはもう見られなくなり、9月か10月に再びお目にかかるということなのでしょう。来月以降の墓参の折に、その辺の処も観察してみることと致しましょう。春姫と 秋姫いづれ まさるとや 姫蔓蕎麦の 花咲くを見む (偐家持) (同上) そうでした。墓参は恒例の門前の言葉で始まるのでありました。 先月5月は、4月のそれと同じでありましたの割愛しましたが、6月はこれでした。尤も、5月の言葉が未だ切り替わっていない、という可能性もありますが。それはどうでもよいこと。(今日の門前の言葉) たとえ朝咲いて 夜散る 花であっても その中には 無限の いのちがある ―金子大榮 一瞬の中にも無限がある。 1日の命と1年の命と100年の命との間に本質的な差異はない。 それが「いのち」というものである。 わが「いのち」の残高も残り少なくなっているが、一瞬、一瞬の無限のいのちを生きているのであれば、残高の多少は問題ではないということでもあるでしょう。(南天の花) ナンテンの花は白い点々という程度のイメージでしたが、接近してよく観察すると、白い花弁がカタクリの花のように反り返って、中央の花蕊は鮮やかな黄色。花が散った後の実は未だ緑色で細長く先端に赤いものがくっ付いているのが面白い。この赤い色素がやがて実の表皮全体に沈着し、あの赤い実になるのでしょうか。 何れにせよ、ちょっとゴチャゴチャし過ぎて、花の風情を壊しているというのが難点でありますな(笑)。(枇杷) そして、枇杷の実。何やら微笑ましい姿です。今暫し 鳥なつつきそ 枇杷の実の 産毛の六つ子 葉裏にあれば (偐家持) (野蒜) ノビルの花はわが家の墓地の裏に咲いていました。 野蒜は春の若菜の一つ。万葉人も春野に出てこれを摘み食材とした。強い臭みには呪力があると考えられたようで、春の呪力を身に取り込むということであったのだろう。 古事記には、ヤマトタケルが足柄の坂本で坂の神の化身の白鹿に食べ残しの蒜を投げつけてこれを打ち殺している記事がある。<参考>足柄(あしがら)之坂本に到(いた)り、御粮(みかりて)食(を)す処於(に)、其ノ坂ノ神白き鹿(か)に化(な)り而来立(てきた)ちぬ。夵(しか)して、即ち其ノ咋(く)ひ遺したまへる蒜(ひる)ノ片端(かたはし)以(も)ちて待ち打ちたまへ者(ば)、其ノ目に中(あた)りて乃ち打ち殺したまひき。(古事記中巻<景行記>)(同上) 万葉集にも野蒜の歌が1首ある。即興の歌を作るのが得意であった長意吉麻呂が宴会の席で、酢・醤・蒜・鯛・水葱を詠み込んで歌を作れと所望されて即興で作った歌である。 醤酢(ひしほす)に 蒜(ひる)搗(つ)き合(か)てて 鯛願ふ 吾(われ)にな見えそ 水葱(なぎ)の羹(あつもの) (長意吉麻呂(ながのおきまろ) 万葉集巻16-3829)(棗の花) ナツメの花も咲いていました。 花とも言えぬ、小さな花ですが、花蜜はあるのでしょう。蟻が来ていました。 上の蒜の歌の次の歌にはナツメが詠われています。作者は同じく長意吉麻呂さん。今度は、玉掃・鎌・天木香(むろ)・棗を詠み込んだ歌を所望されたようであります。 玉掃(たまははき) 刈り来(こ)鎌麻呂 室(むろ)の樹と 棗(なつめ)が本(もと)と かき掃かむため (長意吉麻呂(ながのおきまろ) 万葉集巻16-3830) (同上) さて、最後はアメリカデイゴ。 これは本日の墓参の道で見たものではなく、先日1日の囲碁例会へ行く途上に通りかかった小学校の敷地に咲いていたものです。 これは流石に万葉集には出て来ませんな。(アメリカデイゴ)子どもらの 声をうれしみ いちしるく 咲きてやあらむ あめりかでいご (偐家持)
2016.06.04
コメント(6)
-

囲碁例会・腰掛石と鷺と花菖蒲
本日は囲碁例会。例によってMTBで梅田まで銀輪散歩である。少し早めに家を出たので、荒本交差点で定番の中央大通りを離れ、中央環状道路を北に行き、一つ北側の道を西へと走ることとする。第二寝屋川を渡り、路地を右に左にと走っていて出くわしたのが諏訪神社(大阪市城東区諏訪2丁目)。諏訪神社は各地にあるが、この諏訪神社は多分初めての訪問だと思う。この付近は囲碁の行き帰りや銀輪近隣散歩で結構走っているのだが、それでもこのように初めて出くわすという神社があるようです。(諏訪神社・大阪市城東区諏訪2丁目) 神社で多いのは、稲荷神社と八幡神社が横綱級でしょうか。春日神社、住吉神社、白山神社なども多いが、諏訪神社も多い神社の一つですな。(同上・拝殿)(諏訪神社由緒) 面白いのは、境内にある腰掛天満宮。祠の前の石が菅原道真が腰を下ろして休憩した石だそうな。太宰府に流される時に、道明寺に居た叔母・覚寿尼にお別れに行く際に、この神社の前を通ったので、立ち寄ってお参りされ、この石に腰を下ろして休まれたそうな。 この叔母との別れに際して、道真は「鳴けばこそ 別れも憂けれ 鶏の音の なからん里の 暁もがな」と詠んだこと、そのことから道明寺の里の人たちは鶏を飼うことを止めたということ、それを踏まえて、小林一茶が「暁や 鳥なき里の ほととぎす」という句を作ったこと、などは以前の日記で述べた。 <参考>銀輪散歩・白鳥神社、誉田八幡、道明寺天満宮 2013.10.19.(腰掛天満宮)(腰掛石) この腰掛石に触れると学業成就の願いが叶うらしいが、囲碁が強くなるようでもないから、触れずに置きました。(菅公腰掛石の由来) (注)上の説明文では「伯母」とあるが、覚寿尼は道真の父是善の妹とするもの に準拠して、本文では「叔母」と表記して置く。(6月2日追記) そして、もっと面白かったのが、神社の池(だろうと思うが)の亀。カメラを向けたら首を上に伸ばしてポーズしてくれました。これは外来種のミドリガメですかね。(亀も居た) 奥の方には亀の隣にアヒルも居ました。 何やら言葉を交わしているようでもありましたが、遠過ぎて聞き取れませんでした。(亀の後ろに家鴨も居た) 諏訪神社を後にして、適当に走っているうちに、JR森ノ宮駅の手前で再び中央大通りに出る。大阪城公園を横切り、日本経済新聞社ビルの前の橋で寝屋川を渡るいつものコースへ。この橋が京橋という名前であることに、本日気が付きました。(京橋)(京橋の説明板)(京橋の下を潜る水上バス) 土佐堀通りに出て西へ。天満橋で大川を渡り、いつもの「れんげ亭」で昼食。 会場の梅田スカイビル到着は12時26分。 中庭のワンダースクエアが何やら賑やかである。覗いてみると、この週末にかけて明日からか或は今夕からでも催されるのでもあるか、「ベルギービールウイークエンド2016」の設営準備中で、ステージでは外人の男性バンドが音合わせ・マイクチェックの演奏中でありました。(外人のバンドが音合わせ中) 中自然の森の前の半地下では「風鈴まつり」とかで、各種の風鈴を販売する屋台が並んでいて、チリリン、ヒャラヒャラと涼しげな音を立てていました。 風鈴は暑い夏に流行る疫病封じのためのものがその出発点らしい。「風鈴」という名で呼ばれるようになったのは、法然が「風鈴(ふうれい)」と呼んだことが最初で、これが後に「ふうりん」となったとのこと。 下の写真の右端の屋台が河内風鈴のそれで、そこに、上のようなことを書いた紙が貼ってありました。河内風鈴はわが地元の風鈴であるが、その工房の写真を以前ブログに掲載したことがある。 <参考>河内風鈴工房など近隣・銀輪散歩 2009.7.29.(風鈴まつり) さて、囲碁例会です。本日の出席者は福〇氏、竹〇氏、村〇氏、平〇氏と小生の5名。小生の対戦成績は、福〇氏、竹〇氏、平〇氏に勝って、村〇氏に負け、3勝1敗で、まずまずの成績でした。 帰途は中央大通りをひた走り、恩智川から花園中央公園に立ち寄って、暫し休憩でしたが、恩智川ではアオサギに出会い、公園では花菖蒲に出会いました。(恩智川のアオサギ)(花園中央公園の花菖蒲園)(同上)(同上)(同上)(同上) 朝の腰掛石は「石」ということで「碁石」に、帰途の鷺は、囲碁の戦いを「烏鷺の戦い」とも言うこと、花菖蒲は「勝負」に通じるということで、いづれも「碁」関連でありました。これをオチにして、いささか手抜きの本日の日記の〆とします。
2016.06.01
コメント(10)
全14件 (14件中 1-14件目)
1