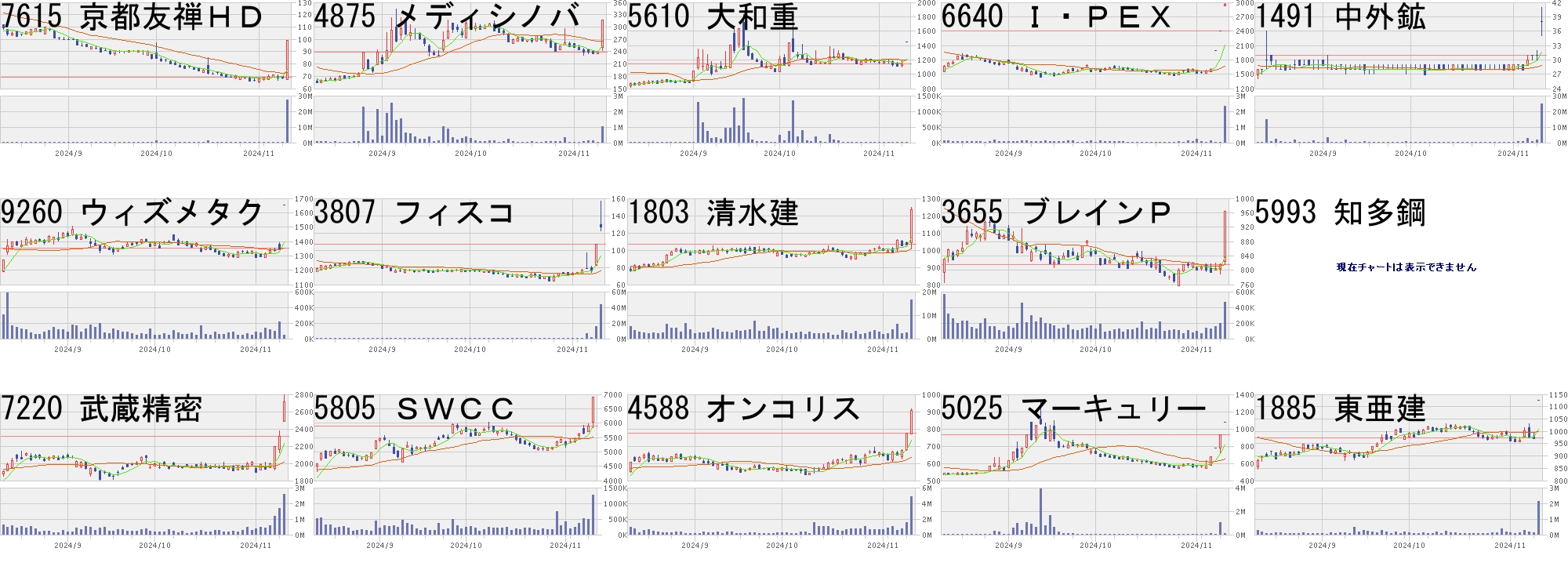[読んだ本] カテゴリの記事
全303件 (303件中 1-50件目)
-
「火星の人」(アンディ・ウィアー)を読んで
「火星の人」を読んだ。有人火星探査船で事故のため主人公マークはただ一人火星にとりのこされる。彼は植物学者でありメカニカルエンジニアでもあり、ありとあらゆる知識を生かして火星でのサバイバルを図る。NASAと連絡が着くまでは登場人物はマーク一人。そして技術的な説明が延々と続く。思うのだが、SF作家でそれほど深い科学知識を持っている人はあまりいないのではないか。知識があるとかえって書けないのがSFだろう。だから詳細な技術的説明も適当に読み飛ばしていた。まあ、古畑任三郎にでてくるファルコンの定理と同じようなものだと思って…。しかし、解説を読むと(途中で解説を読むという悪い癖があるので)、作者は宇宙開発に関心のあるプログラマーで15歳から国の研究所に雇われているのだという。となると、こうした技術的説明もそのつもりで読まなければならないのかもしれない。普通の人にとってはどっちでもよいことで、どのつもりで読んでも、理解しがたいものはさらっと読み飛ばすしかないのだが。というわけで、この小説の最初の部分はかなり退屈である。しかし、そのうち、NASAや仲間のクルーと連絡がつき、秘密裏に宇宙開発を進めていた中国の協力もあり、様々な困難を克服して地球への帰還を目指すという段になってがぜん小説らしくなる。そして最後は人間には互いに助け合うという本能があるという述懐で終わる。この小説でまず言いたいのは主人公は素晴らしい人物であるということ。これは聖人という意味ではなく、知力体力人に優れ、どんな困難にあってもポジティブ思考とユーモアのセンスをかかさないという意味である。翻訳も素晴らしくこなれた日本語で主人公の明るく剽軽な言葉遣いを上手く訳している。クルーたちも、これもまた優秀かつ素晴らしい人々で、皆、自分の危険をかえりみずに主人公の生還に協力しようとする。面白いといえば面白いのだが、一方で人間同士の葛藤とかそういうものがでてこないので、小説としてはものたりない。というよりも、こうしたものは通常の小説とは別の一ジャンルとしてみた方がよいのかもしれない。そしてまた、いいにくいのだが、科学技術というものは発展すればするほど人間の間の能力差を可視化する。主人公やその周辺の登場人物と一般人の間には天地ほどの能力差がある。そうした分断の中で、これからも、人間は「互いに助け合うという本能」(もしあるとしたら)を維持できるのだろうか。こうした分断がこれからは大きなテーマになりそうな気がする。なお、この小説は映画化され、日本では「オデッセイ」というタイトルで公開されている。ネット配信で映画の方も見たが、これは火星の風景の再現の迫力もあって、映画の方がはるかによい。小説を読むなら映画も併せてみることを薦める。
2024年11月04日
コメント(0)
-
更級日記を読んで
その昔、更級日記を読んだとき、文学好きの少女の等身大の日記という印象をもっていた。教科書に出ているのが、父の帰任にともなって京都に向かう旅日記風の記述だったり、源氏物語に夢中になっている記述だったりしたこともあったのだろう。いずれも少女時代の回顧である。実際には更級日記の記述は少女時代以降も続く。32歳で内親王の下に出仕し、33歳で橘俊通と結婚する。当時としても相当遅い結婚である。その間、高齢の父の常陸介任官、単身赴任、帰任後の引退、母の出家などもあり、作者は将来にかなり不安を感じていたのではないのだろうか。源氏物語の浮舟の境遇に憧れていたようなのだが、素晴らしい貴公子に人知れぬところに囲われていたいという夢をいつまでもみているわけにもいかない。宮仕えは辛いことや意に添わぬこともかなりあったようで、作者はやや内向的で仕事を器用にこなすというタイプではなかったのかもしれない。けれども、源資通との春秋の優劣論など和歌を通じての交流もあり、作者の学識や和歌の才能は宮仕えでも評価されていたのではないのだろうか。資通との交流は、物語めいていて、恋愛とは別物であっても、強烈な印象を残した。夫は下野守、信濃守に任官しているが、これにはいずれも同行していない。夫についての記述は少ないが、作者はひたすら子供たちを一人前にするのに必死になっており、夫が信濃から帰任して、すぐに亡くなったときも非常に悲しんでいる。悪い妻というわけではなかったのだろう。宮仕えは断続的に続けており、宮仕えの中で知り合った気の合う友人との交流を支えに子供が独立した後の日々を暮らす。更級日記の書名は晩年になって訪れてきた甥にあてた下記の歌による。月もいででやみにくれたる姨捨になにとて今宵訪ねきつらむ今、読んでも、やはり作者は等身大の女性という印象である。ただ実際にはこの作者は単に物語好きの文学少女、文学おばさんであるだけでなく、よわの寝覚めなどの数編の物語を書いており、いくつかは断片的に今日も伝わっている。そうだとしたら逆に不思議である。更級日記は晩年までの記述があるにも関わらず、物語を書いたことの記述は一切ない。そのあたり、あの紫式部日記には書きかけの源氏物語についての記述があるのに。
2024年10月22日
コメント(0)
-
「野菊の花」、「浜菊」(伊藤左千夫)を読んで
今まで名前は知っていても読んだことのない本はなるべく読むようにしている。「野菊の墓」は今の若者はどうかしらないが、我々世代なら多くの人が読んだ小説ではないかと思う。中学生の頃、国語の教科書の末尾にお薦めの本という頁があり、その中にもたしか紹介されていた。当時はこのお薦めの本というのはたいていはつまらないものだという変な思い込みがあり、それで今まで読まないできたのかもしれない。読んでみると、夕焼けに染まる畑の描写などかなり美しく、当時すでに歌人として名をなしていただけのことはある。政夫と民子のようやく恋といえるかいえないかのような関係も初々しく、この小説が長く愛され読み継がれている理由もわかる。この小説が発表されたのは明治39年だというのだが、この時代の農村の社会というものはどういうものだったのだろうか。政夫と民子との交際が禁じられた背景が、単に従姉で二歳年長ということだけだったのか、それとも、中学に通う政夫と手伝いのような民子との間の身分の差があったのか、どうもそのあたりがわからない。地域にもよるのかもしれないが、従姉との結婚や姉さん女房は戦前の日本でもさして珍しくなかったようにも思う。同じ作者の小説で「守の家」というのがあり、これは優しい守の娘が不幸な結婚をして早世してしまうという話で、なんとなく「野菊の墓」に似ている。年齢にもよるのかもしれないが、「野菊の墓」よりも「浜菊」の方が印象に残った。久方ぶりに東京から柏崎に友人を訪ねていくという話で、友人とは喧嘩をしたわけではないが、気持ちが隔たってしまったことを実感して寂しい心地で帰京するという話だ。もっとも主人公の方にも浜菊の想い出とともに友人の妹に多少惹かれているところがあった。柏崎に妻子をもち落ち着いている友人と主人公はいつのまにか別々のものの見方、別々の価値観にたつようになっている。多くの人がそうだと思うのだが、年賀状だけでつながっている昔の友人というものがいる。そうした友人ともし今会うとなるとちょっと怖いような気がするし、たぶん会うこともないだろう。もし会ったとしても、おそらくこの小説の主人公のように、互いの隔たりを実感し、より深く寂しい思いをするだけだろうから。
2024年10月21日
コメント(0)
-
「百年の孤独」(G.ガルシア・マルケス)を読んで
いつも思うのだが、ノーベル賞の中で自然科学系の賞と文学賞、そして平和賞は全く別のものと思った方がよいのではないか。業績を客観的に評価できる自然科学と異なり、文学の評価などは客観性がない。だいたいノーベル賞が発足して以降もトルストイは受賞していないし、その反面、政治家チャーチルの自伝が文学賞をとっている。今日、トルストイとチャーチルとどちらが読まれているのだろうか。日本でも川端康成と大江健三郎が文学賞をとっているが、この二人が大好きな作家だという人はあまり多くないのではないか。たいていの人は、川端や大江よりも、好きな作家や作品があるように思う。思うのだが、川端康成は作品に流れる日本的美意識が外国人に響いたのかもしれず、大江健三郎はヒロシマノートなど反核の思想が選考委員の共感を呼んだのかもしれない。それは反核というよりも、中国やフランスなどに核が拡散した以上、日本には核を保有してほしくないという欧米社会のメッセージのように思う。佐藤栄作のノーベル平和賞も今回の被団協の受賞も同様だろう。もちろんだからといって、文学賞や平和賞にケチをつける気などない。被団協は今回の受賞を契機になお一層世界全体に向けて反核のメッセージや思いを発信してほしいものだと思っている。中国やロシアも含め、国際社会が一体となれば北朝鮮の核を止めることができるかもしれないのだから。二度あることは三度ある…日本にはこんな諺もあり、恐ろしい。「百年の孤独」は1982年にノーベル文学賞を受賞しているが、これも、背景には中南米の土俗的風土に対する異国趣味があるのかもしれない。物語は魔術的リアリズムというらしいのだが、現実の中に4年間続く雨とか人間が突然空に吸い込まれると言ったような非現実要素が織り込まれたもので、少し違うのかもしれないが、阿部公房や別役実にも現実と非現実の融合といった要素はあるように思う。最初は、正直言ってなんてつまらない小説かと思った。架空の町を舞台にしたある一家の六代にわたる繁栄と滅亡を描いているのだが、共感できる登場人物はいないし、ぶっとんだ話が淡々と続いていくだけのようにみえた。しかし、物語が終わりに近づくにつれ、物語世界にある種の詩情を感じるようになり、読後感は悪くない。
2024年10月14日
コメント(0)
-
「ウは宇宙船のウ」を読んで
このタイトルは昔から知っていた。あまりにもダサいタイトルだと思ったからだ。しかし、作者ブラッドベリは詩情あふれるSFの名手で火星年代記は言わずと知れた傑作だ。そんなわけで、おくればせながら読んでみたのだが、あまりにも駆け足で読んだせいか、印象に残る話はなかった。これは作品が悪いというよりも、こちらの方にSFを受け入れる能力がどうやら減退してしまったせいだろう。年齢とともに読書傾向はかわるものだが、昔は「…ここはフォーマルハウト星系第7惑星」なんていう書き出しだけでも、わくわくしたのだが、今では舞台が火星だろうが、遠い未来だろうが、ああ、そうですかといった感じだ。この分野は特に読者の年齢を選ぶのかもしれない。しかし、SFというのは別に宇宙や未来を扱うものばかりではない。広い意味でのSFとなると、かなりの作品が含まれるだろう。となると、自分くらいの年齢向けのSFジャンルというのもあるのかもしれない。
2024年09月28日
コメント(0)
-
「二都物語」(ディケンズ)を読んで
この間のパリ五輪開会式を契機にフランス革命の解説などを見ているうちに、「二都物語」を読み返したくなった。ずっと昔に読んだ時には、フランス革命をあまり肯定的に描いていないと思ったが、あらためて読むと舞台はフランス革命後の恐怖政治の時代で、肯定的に描きようのない時代だ。小説のラストで20歳の貧しいお針子が処刑される場面があるが、実際、庶民階級の者もろくに裁判も経ないままで処刑された例があったという。血に対する熱狂が疑心暗鬼を生み、それがさらに次の犠牲を求めるという構図だったのだろう。まあ、小説の中の言葉なのだが、「処刑を見物しないことには共和派であるかいがない」という台詞がでてくる。斬首を多くの人々が熱狂して見物したわけである。革命というものは暴虐な王、贅沢三昧な貴族を処刑し、民衆の時代がやってきた、それで万歳という単純なものではない。教科書ではフランス革命は市民革命として習ったので、新興のブルジョア階級が革命を主導したような印象があるのだが、実際には貧窮した農民や下層民の暴動から始まり、革命後は王権の権威の源泉となっていた宗教を否定するなど、性格的には後年の社会主義革命に近いものだったのかもしれない。もっともこの小説は革命そのものを描いたものではなく、革命を背景に男女の愛を描いたものである。以前の日記にも書いたとおり、大衆文学と純文学の境界はよくわからず、ディケンズは文豪とよばれているので、作品は純文学かもしれない。ただ文学として登場人物の心理を考えた場合、恋のために自己犠牲を選ぶ主人公が人生をあきらめている理由がいまいちよくわからない。たしかに、病気や不品行をにおわせる記述はあるのだが、読んでいてあまり想像がつかない。小説が発表された当時の社会では共通のイメージがあったのかもしれないが、このあたりは具体的に書かず、影のある人物くらいにする方がかえってよかったのだろう。おそらく作者は物語の最後から構想をねったものと思われ、最初からいたるところに伏線がちりばめあっれている。筋を追うだけで手いっぱいだった初読に比べると、再読は伏線を踏まえて読む別の面白さがある。
2024年09月17日
コメント(0)
-
「寺山修司短歌論集」を読んで
図書館でなにげなしに手に取った本である。寺山修司の歌が前衛短歌というジャンルに分類されていることもここで初めて知った。短歌の歴史については、現代短歌だけではなく和歌までさかのぼると本当に長い。月がきれいだ、桜がきれいだ、世の中ははかない…こんな歌はたぶん残っていないものも含めれば何万回も何十万回も誰かに読まれているのではないか。花鳥風月、海や山、別れや恋の辛さなどは詠みつくされており、これ以上いったい何を詠むのだろうか。浅い想像かもしれないけど、こんな風に思った人がきっといたのだろう。そこで新しい短歌の流れが起こった。もちろんその一方で叙景を基調とするものや生活に根差したものも脈々と詠まれているのだが。この本には、そうした前衛短歌がいくつも紹介されているのだが、正直いってよくわからなかった。ちょうど現代美術をみたときのように、これってもしかしたら仲間内で誉めあっているだけでは…という気さえしてくる。ただ、中にはなんとなく雰囲気があって、いいなと思うものもないわけではない。ただ本書で紹介されていたなかでい印象にのこった歌は下記の二首でこれは特に前衛短歌というわけではないだろう。昏れ方の電車より見し橋脚にうちあたり海に帰りゆく水(田谷鋭)水銀の如き光に海見えてレインコートを着る部屋の中(近藤芳美)いずれも分類は叙景になるのかもしれないが、どこがよいのかというと説明にしくい。ただおそらくこうした光景を過去にみたことがあり、橋脚にうちあたった水が海に帰ることも、レインコートが部屋の光の加減で水銀のようにみえることも、考えたり感じたりしたことはあった。ただその一瞬に言葉にしなかったものが、歌人の言葉により、あらためてよみがえり、その情景が目に浮かぶのだろう。寺山修司の作品の中では、母は死んだり、駆け落ちをしたりしたことになっている。しかし、彼の死後、元気な母親が出てきても、驚いた人はすくなかったのではないか。随想や評論でふれる私的な話にはフィクションがあり、それも含めても彼の作品だということを皆知っている。随想にでてくる友達のトルコ嬢(当時の言葉)やヤクザの知合いもフィクションだろう。
2024年09月08日
コメント(2)
-
「土」(長塚節)を読んで
好きな小説、面白い小説ではないのだが記憶に残っている小説というものがある。長塚節「土」もそういう小説だ。全体のストーリーや登場人物の印象ではなく、細かな部分がいやに印象に残っているのだ。近所の家に風呂を借りにいく場面とか、自分の留守の間に家の醤油が減っていることを気にする場面とか…である。こうした細部の描写を積み重ねて、当時の貧農の生活の苦しさをこれでもかというほどに描く。もっともこれについては、読んだ時期が中学生くらいの頃ということもあったのかもしれない。あの頃はなんでも心に残るし、無駄にいろいろなことを記憶する。旺文社文庫という若草色の綺麗な表紙の文庫本が図書室に備えてあって、それでたしか読んだ。だからいつか再読したいと思っていた。夏目漱石はこの小説を絶賛して、「苦しいから読め」と書いている。農民の生活や風習が克明に描写されているが、たしかに読みやすい小説ではない。一文が長すぎるので、頁は文字でびっしりになっている。そしてところどころにやたらに長い自然描写がでてくる。それも、はっとする比喩や詩的な表現は少なく、平板な事実描写が延々と続く。主人公は卑屈で無学でさもしく、おまけに多少盗癖もある人物で、読者が共感するタイプではない。プロレタリア文学は1920年からとされているが、明治43年に新聞に発表されたこの小説も貧農の実態を描いたという意味で、プロレタリア文学の先駆ではないのだろうか。夏目漱石の絶賛の背景にも、当時の知識人の知らない貧農の生活実態を描くことの目新しさがあったのかもしれない。今のような情報社会ではなく、社会の格差分断も想像できないほどであった。漱石はこう書いている。余の娘が年頃になり、音楽会がどうの、帝国座がどうだのと言い募る時分になったら、余はぜひこの「土」を読ましたいと思っている。
2024年09月04日
コメント(0)
-
「暗殺」(柴田哲孝)を読んで
小説という体裁をとっており、人物の名前も変えてあるのだが、あの元首相暗殺事件を扱ったものというのはすぐにわかる。書いてあることのどこまでが本当なのだろうか。貫通しているわけでもないのに弾丸が遺体のどこからも発見されなかったとか、銃創は喉から胸に貫通しており、どうみても、高所から撃ったとしか思えないとか。このあたりはフィクションかもしれないのだが、あのニュースをきいたとき、多くの人が疑問に思ったのではないか。地をはうように生きてきた40歳そこそこの人間が手製の銃を作り、標的となった政治家の喉に弾を命中させることができるのだろうか。銃の訓練一つにも相当の場所と時間を要する。山奥で少し撃ってみたという程度で、あれだけの技量が身につくのだろうか。元総理は急所を撃ちぬかれ、周囲の群衆は誰一人かすり傷も負っていない。それくらい正確に標的を射抜いているわけである。たしかに、犯人には自衛隊員の経歴があり、武器の扱いに慣れているというはなしもある。しかし、自衛隊員だったのは、かなり昔のことであるし、そのくらいの経歴で、自作の銃を作り、標的を殺傷することができるとはとても思えない。だいたい元自衛隊員など何万人もいる。だから実は犯人は他にいる…という説は興味深い。もっとも、要人の暗殺で犯人は他にいる、あるいは黒幕がいるという話は、例えば伊藤博文にもあるし、ケネディにもあるので、わりと一般的なのかもしれない。ただ、この元総理暗殺事件であるが、それ以外にも不思議なことがある。それは、事件から二年以上もたっているのに、いまだに公判が開かれないことである。犯人はその間、ずっと世間から隔離されたままになっている。そしてあれほど騒がれた政治家と某宗教団体のかかわりについても、世間の関心が薄れたということもあるのかもしれないが、マスコミなどで全く触れなくなっているのも、逆にタブーになっているような気がする。例えば自民党の総裁候補について様々のメディアがとりあげているのだが、某宗教とのかかわりはどこも書かなくなっている。まあ、読み終わっても謎は謎のままに残るのだが、事件についてこんな見方もあるという意味では一読の価値はある。
2024年08月30日
コメント(0)
-
「市塵」(藤沢周平)を読んで
ダイナミックな「太平記」を読んだ後、すらすらと読める歴史小説を探して読んだのが「市塵」である。歴史小説には二種類あって、作者が自由に想像の翼を広げて書いたものと、資料を丹念に読み込んで読みやすくまとめたものとがあるように思う。新井白石の伝記となっている本書は後者だろう。資料も多いし、なによりも本人の著作も残っている。文章は藤沢周平なので非常に読みやすく、市井の儒学者だった新井白石が甲府藩に仕え、その後、藩主が将軍になるに伴いご意見番となって、家宣、家継の二代の将軍のご意見番として勤務した様子が淡々と描かれる。徳川時代を通じて、知恵者の側用人や御意見番が現れては消えていったが、将軍家をしのいだり、将軍家を棚上げにして権力をふるうような者はあらわれなかった。将軍吉宗の登場で、新井白石はご意見番を辞して儒学者としての著述生活に戻る。生類憐みの令などの綱吉時代の政策の否定に始まり、宣教師からの対外情報の収集、朝鮮通信使の礼遇の簡略化、通貨鋳造など、はでな施策や事件があるわけではなく、淡々と時代は移っていく。それにしても、あの太平記を読んだ後では、平和な時代のものはものたりない。それにしても、徳川綱吉は暗愚な将軍とされているが、このイメージは新井白石によるところもあるのかもしれない。最近では綱吉の再評価も行われているという。なにしろ「もし徳川家康が総理大臣になったら」でも徳川綱吉は入閣しているくらいなのだから。今度は今話題の「逃げ上手の若君」を見ようかな。
2024年08月26日
コメント(0)
-
「太平記」を読んで
「太平記」を読み終えた。軍記物語に分類されるのだが、「平家物語」とはずいぶん趣が違う。源平合戦を背景に滅びゆく平家の哀れを描いたのが平家物語なら、南北朝時代の動乱を背景に裏切り、卑怯、狡猾などそこに蠢く人間の実相を諧謔も交えて描いたのが「太平記」である。もちろん「平家物語」にも主君から立派な馬を賜りながら主君を見捨てて逃げる家臣が出てくるし、「太平記」にも楠木正成のような英雄的人物もでてくる。それでも、どちらに重点を置いて描いているかといえば、両者は明らかに違うように思う。また、「平家物語」が語り物らしく物語としての記述で一貫しているのに対して、「太平記」では人物名を羅列した箇所が多く、記録文学としての面もある。また、仏典や漢籍からの引用も多く、そうした挿話は後半になるほど多くなる。こうした挿話を読むのも、面白さのうちだろう。ただ、太平記は、平家物語に比べると読みにくい。これは、裏切り、寝返りはあたりまえの時代であるため、読んでいるうちにどちらが幕府方なのか、南朝側なのか、北朝側なのかがわからなくなってくるのである。私は、新潮日本古典集成で読んだが、これは注に適宜説明があるので、ずいぶん助かった。たしか、学校では応仁の乱で戦国時代が始まったと習った。しかし、「太平記」を読むと、室町時代初期からしょっちゅう戦闘があったようだ。鎌倉幕府を倒す戦いがあり、次には北条残党による中先代の乱があり、次には、建武の新政側と足利尊氏の戦いがある。このあたりまではわかりやすいのだが、室町幕府成立後は、高師直と足利直義の争いなど幕府内の争いが起きてくる。それどころか、互いに気に食わないくらいの理由での大名同士の争いまであるので、全く世の中は平和とはほど遠い。物語の終わりでは次第に南朝も先細りになっていき、世の中はようやく安定する様子をみせる。もっともこの時期になると南朝方の戦もどこか気が抜けていて緊迫感にかけている。湊川の戦いのような悲壮感ある戦はなくなっている。「太平記」という書名には平和な時代を希求するという意味があるのだろうけど、義満の小康状態を経て、やがて戦国時代が始まることを思うと、徳川の世になるまで、日本では長い長い戦争の絶えない時代が続いたのかもしれない。
2024年08月13日
コメント(0)
-
「太平記」(四)を読んで~あまりにもカオスな南北朝時代
「太平記」(四)を読んだ。知れば知るほどカオスな時代で、裏切り、寝返りは当たり前、ほぼ中心人物の足利尊氏さえ何を考えているのか不明で、いったい切腹の決心、出家の決心を何度やっているのだろうか。しかし、そうした絶体絶命の場にたってもなぜか強運で、いつのまにか幕府の創始者になっていたという感じだ。このあたり、天下統一を目指していた戦国時代の英雄や、日本の近代国家としての国づくりを考えていた幕末の偉人とは違う。南北朝時代は大河ドラマになったのは一回しかないのだが、この時代をドラマにしにくいのは皇室の扱いの難しさもさることながら、登場人物が何を目指していたかということの描きにくさもあったのではないか。この時代の人々は確固とした価値観があるわけではないのだが、武士の体面は非常に重視する。多くの人々が討ち死にする場面や集団で切腹する場面は何度も出てくる。合戦による死者の人骨が大量に見つかったというニュースがときどきあるが、それも南北朝時代のものが多いようである。京の都も何度も戦乱で荒廃し、足利義詮が一時的に南朝と和睦した時は、都を追われた北朝の官人でさえ、このままでもよいのでとにかく平和になってほしいと願ったくらいだ。いったいこの戦乱はいつまで続くのか…「太平記」という書名には、戦乱の終結の願いがあるのではないかというが、そのとおりだろう。戦国時代は応仁の乱で始まったというのが通説だったのだが、最近の研究では室町幕府というのは当初からそれほど安定した体制ではなかったという説もあるらしい。実際の権力の帰趨は、財力と兵力であり、究極的には、その領地を抑えている兵力であったのだろう。それぞれの地域ごとに、その場所を抑えている勢力があり、そうしたものが勝ち馬に乗ろうとして、ある場合には南朝方、ある場合には北朝方についていたというのがこの時代の実態であり、わかりにくさでもあるのだろう。
2024年08月04日
コメント(2)
-
「太平記」(三)を読んで
太平記を読む場合には常に登場人物がどちら側であるかを確認しておく必要がある。このあたり、平とか源とかいう登場人物の姓でどちら側かがわかる平家物語とは違う。登場人物がわかりにくいだけではない。南北朝の争いには大義がみえない。大義といえば錦の御旗なのだが、この時代にはなにしろ天皇が二人いる。大義がないので、世の中の大勢を見て、何度も寝返るのは普通のことになっている。こうした中で一貫して南朝方についていたのが、楠木正成と新田義貞だろう。新田義貞については、南北朝の争乱には源氏のなかでの新田と足利の争いという面があったので、一貫して南朝方であったのは当然だろう。しかし、新田と足利について、どっちが南朝でどっちが北朝かとなると、これは必然性がない。中先代の乱の平定後、新田義貞と足利尊氏はともに後醍醐天皇に双方を非難する書状を送っている。ここで後醍醐天皇は足利尊氏を朝敵としたのだが、もし、足利尊氏が後醍醐天皇側だったら、その後の歴史も変わっていただろう。楠木正成、新田義貞、足利尊氏についての記述を比べると、傑出した武芸の記述があるのは新田義貞だけである。しかし新田義貞にしても、一つの城の攻略にこだわって大局的な視点を欠いていたり、美女におぼれて攻勢の機会を逸したりと、人間的ではあるが、知略という面では楠木正成には及ばない。足利尊氏は野心家というよりは、戦況が不利になるとすぐに腹を切るだの、出家するだのと言い出し、京都での戦では挑発に乗り新田義貞と一騎打ちをしようとして部下に止められるなど、こちらも英雄的に描かれているわけではない。また、有名な稲村ケ崎の場面であるが、なんとなく、新田義貞が剣を投じると、潮がみるみるひいていき、鎌倉にわたったような想像をしていたのだが、実際には、剣を投じたその日の夜から潮がひいて遠浅となって馬で鎌倉に攻め入ることができるようになったとある。通常の潮の干満だったかもしれず、海など知らない新田の兵は潮が引いたのを神秘的にとらえただけかもしれない。太平記では、鎌倉時代末期からの、次々とうちつづく戦乱が描かれているが、建武の新政が乱脈をきわめ、恩賞が公平を欠き、武士たちが不満を募らせたあたりで、天下の大勢は、鎌倉幕府に次ぐ、新たな武家政権の誕生へと動いていったように見えてならない。特に倒幕に最も功績があり、自らも戦いの先頭にたっていた護良親王が、建武の新政発足後に岩屋に何か月も幽閉された後、足利直義によって殺害されたのをみれば、後醍醐天皇側にたって命がけで戦おうとはだれも思わないのではないか。それにしても護良親王の過酷な処分について後醍醐天皇はどこまで知っていたのだろうか。楠木正成とならんで早期に倒幕の兵をあげていた赤松則村が建武の新政後恩賞どころか司を取り上げられた理由はなんだったのだろうか。物語では語られない部分にもいろいろと興味がつきない。
2024年07月22日
コメント(0)
-
「太平記」(二)を読んで
「太平記」(二)を読んだ。この時代の騒乱はわかりにくい。源平合戦であれば源氏に属すること、平家に属することが戦いの理由であったし、主役はそのどちらかである。ところが、南北朝の騒乱となると、裏切り、寝がえりは普通のことで、そもそも天皇も二人いる形になるので、錦の御旗が唯一の勤皇というわけでもない。そしてその形勢も一進一退である。登場人物がいつのまにかあちら側についたりするので、まぎらわしい。鎌倉幕府が滅びた後、建武の新政が始まるが、恩賞は公平を欠き、後醍醐天皇側近の公家や寵姫の専横が始まる。楠木正成と並んで討幕の兵をいち早く上げた赤松円心は逆に守護職をとりあげられ、皇族中で最も功績のあった護良親王は征夷大将軍となったものの、讒言で失脚し、鎌倉に護送されて幽閉される。実父の後醍醐天皇は健在であったので、そこまでの措置というのがどうにも不思議だ。実際に幽閉されていたという岩屋が鎌倉にあるのだが、立ち上がることもできないほどの狭い土牢で、太平記にも、足利直義の命により殺害されたときに、長いこと座った姿勢しか取れなかったため、体が動かずに抵抗できなかったとある。背景には、自分の子を皇位につけたい寵姫の思惑があったことを匂わせているが、実際のところはどうだったのだろうか。その後、北条高時の遺児による中先代の乱がおき、足利尊氏が鎌倉に下り乱を平定した後、関東に権勢を振るうようになる。その後、足利尊氏は朝敵となり、新田義貞軍が討伐に向かう。最初は新田軍が優勢であるが、形勢は逆転し、都も危なくなったので、後醍醐天皇は御所を離れ、東坂本に移る。しかし、その後、後醍醐天皇方につく勢力が増えると、今度は足利尊氏が京を捨てて西国に下る。これだけのシーソーゲームが起きるのは、多くの勢力が寝返りを繰り返して優勢な方に着くために短期間で情勢が変わるし、世の中は落ち着かない。この間まで足利の二つ引き両の笠印をつけていた兵が線の中を塗りつぶして新田の紋に変えて今度は新田の兵として都を跋扈する。二筋の中の白みを塗り隠し新田新田(にたにた)しげな笠印かなそれにしても、大義の見えにくい時代なので、寝がえりする大将や降人となる武士も多い一方で、何百人単位での自害も行われる。不思議な時代としかいいようがない。
2024年07月10日
コメント(0)
-
鎌倉幕府の滅亡~太平記を読みながら
太平記で鎌倉幕府が滅亡にむかう過程を読んでいる。歴史は勝者によってつくられるので、現実の北条高時がここで書いてあるように闘犬と田楽だけに溺れた人物だったとも思えないが、世襲の常としてそれほど優秀というわけでもなかったのだろう。鎌倉幕府の体制がゆきづまり、つぎつぎと討幕の動きが起きてくるわけなのだが、幕府もその出先の六波羅もなすすべがない。日本史上の争いというのは、宗教とか民族といった決定的な対立軸がないので、大義というよりも時流によってどちらにつくかを決める傾向が強い。源平の合戦でもそうだし、はるか後の戊辰戦争もそうだった。特に、南北朝時代の対立は天皇まで二人いるので、特にこの傾向が強い。平家物語には無常観が根底にあり、栄華を極めた公達が、それぞれに悲劇的な最期をとげる様子が余韻をもって描かれる。それに比べると、太平記の登場人物はそれぞれがそれぞれの欲望で動いており、鎌倉方はもちろん後醍醐天皇方も美化されていない。嫋々と無常を謳うのではなく、争いから一歩ひいた皮肉っぽい知的な視線がある。そこが平家物語とは違う。太平記で英雄的人物として描かれているのは楠木正成だが、楠木正成が国民的英雄と扱われるようになったのは明治以降で、湊川神社も明治5年の創建のようである。現天皇は北朝系なのに、明治以降に南朝の中心の神格化が始まったのは不思議な感じがする。この時代は大河ドラマでもタブー視されていたというが、一度だけ扱われたことがある。局内では論争があったそうだ。ネット情報によると、楠木正成役には高倉健も候補になっていたそうで、高倉健なら昔ながらの英雄のイメージにぴったりだろう。ところが実際に楠木正成を演じたのは武田鉄矢であった。身分の低いゲリラ戦を特異とする土豪ならこっちの方がイメージにあうように思う。
2024年07月02日
コメント(2)
-
「太平記」を読んでいる~落首に笑う
「太平記」を読んでいる。以前、読んだとき、あまりにも面白かったので、もう一度読んでみたいと思っていた。鎌倉幕府崩壊から建武の新政とその瓦解を描いたもので、戦乱の時代を描いた書なのに、なぜ太平記とつけたのかが不思議だ。今、読んでいるのは幕府転覆の陰謀が行われた正中の変とそれにより誅殺されたものの哀話、それにつづく楠木正成の登場と、幕府軍の笠置攻めのあたりだ。この戦で抜け駆けの功名を狙った武士が二名ほどいて、いずれも敗れるのだが、その時の落首が秀逸でわらってしまう。最初に高橋又四郎と言う者が攻めていくのだが、さんざんに敗れる。この時の落首が木津川の瀬々の岩波早ければ懸けてほどなく落つる高橋次に小早川と言う者が攻めるがこれも敗れたので懸けもえぬ高橋落ちていく水に憂き名を流す小早川かなである。有名な五条河原の落書きもこの時代だし、この頃の落首落書きの水準はめちゃめちゃ高いように思う。源平もそうなのかもしれないが、日本の争いには理念とか宗教の争いと言った色彩はあまりない。後醍醐天皇と幕府の戦いも勤皇か武士かともいいにくい。なにしろこの時代は天皇に既に北朝と南朝があったのだから。勝ち馬に乗りたい様子見がほとんどなので、争いは長引かずに短期間で決する。だから壊滅的な被害もないので、古い木造建築や仏像なども比較的残っている。まあ、あせらずゆっくり読んでいこう。
2024年06月28日
コメント(2)
-
「枕草子」を読んで
「枕草子」を読み終えた。昔読んだときには伊周のイケメンぶりが強調されていた箇所が印象的で、極論すれば、その印象しかなかったのだが、あらためて読んでみると、その箇所は最後近くの宮仕え間もない頃の回想の段で、自分の局に退出するのを伊周が送っていく場面である。月が明るく、伊周の直衣が真っ白に見え、そこで伊周は「遊子なお残りの月を行く」という漢詩の一節を誦している。伊周の漢籍への造詣の深さがにじみでているわけだが、そんな様子を見て、「いみじうめでたし」というくらいに清少納言は感動する。中流貴族出身の清少納言にしてみれば、定子サロンは夢のような世界にみえたことだろう。おまけに伊周のような教養あふれる貴公子をみてしまうと、人がよい体育会系の元夫の橘則光などふっとんでしまう。ただ、清少納言がこの段を書いた時には関白家はすっかり没落して、伊周は戦々恐々と道長の機嫌をうかがって生きていた。なにしろ碁を打ってさえ勝ちを遠慮するくらいに縮こまっていたので、とてもかつてのさっそうとした貴公子の面影はない。なんという世の変転…しかし、それでも、かつてのあの月下の貴公子の姿だけは筆で残しておきたい。書いた時には、きっとそんな気持ちだったのだろう。枕草子が世に広まったきっかけは、跋文によれば、清少納言が私邸にいる時に、源経房が訪問し、その際に書いたものをうっかりと端近くに置いたままにしておいたのが、持っていかれてしまって世に広まったとある。それまでにも書き溜めたものは中宮や他の女房には見せていただろう。そもそも清少納言に紙を賜ったのは定子であり、そうであれば、当然あの紙にはどんなことを書いたのと中宮定子は聞いたはずであろうから。定子サロンの枠を越えて、枕草子が世にひろまったのは経房のせいなのだが、いったい彼が清少納言の私邸にまでやってきた理由はなんだったのだろうか。経房は道長とも非常に近い関係にあったが、いくら清少納言でも一女房の去就が政治的に意味を持つとも思えないので、まさか清少納言を道長方に引き入れようという思惑ではないだろう。単なる定子サロンでの話し相手なら、なれなれしすぎるし、男女の仲というのも考えにくい。このあたり、平安時代の貴族社会の感覚というのはわからない。枕草子の段は随想的部分、回想的部分などいろいろな分類ができるのだが、不思議なほどに作者個人について記載した箇所はない。清少納言は枕草子の中で、蜻蛉日記や更級日記の作者のように自身の人生は語っていないのである。多くは四季の風物や祭り、貴族社会での人物評、そして中宮を中心とする出来事や回想など、共通の話題がほとんどとなっている。それはちょうど現代のジャーナリストが私事を書かないのと同じようなことなのかもしれない。枕草子は一種のジャーナルとして当時の貴族社会で読まれ、後世に残っていったのであろう。
2024年06月22日
コメント(8)
-
「枕草子」を読んで~ものを書く幸せと慰め
世の中がいやになってしまってどこかに行ってしまいたい時でも、きれいな紙とよい筆とがあれば、本当に慰めになって「まあ、いいわ、もう少し生きていたい」と思うのよ…というのは昔清少納言が中宮の前で雑談の折にいった言葉である。今は良い時代で、WEBなんていう便利なものがあるので、いつでもいろいろなことを書くことができるのだが、紙が貴重品だった時代はそうはいかなかった。書くことが好きな人が紙と筆を手に入れた喜び…というのは今日では想像しにくい。しかし、思ったこと、考えたことをまとめてみたいというのは人間の根源的な欲求の一つなので、だからこそ、口承というものがあり、日本の場合には人々が口遊みやすくした短詩形式が発展した。文字ができてからは、その思いや考えを書き残したくなる。枕草子を読んでいると、作者がとにかく書きたいことを書いているという感じがするし、今だったらさしずめブログに書くような内容もある。こういう人って本当にいやよね、とかこういうのってわくわくするわよね、とかそんな文章である。枕草子には中宮定子が紙を送って来たという段があり、おそらくその時期に執筆が始まったのではないかと言われている。道隆が死去して長徳の変で伊周、隆家が失脚して関白家の家運が急速に傾いた時期である。この頃、清少納言はしばらく宿下がりをしていて、中宮が再度の出仕を促していた。宿下がりの背景は書かれていないのだが、政変の関係でどさくさがあった時期であり、いろいろな誤解もあったのかもしれない。明るく華やかな宮中絵巻のような枕草子だが、実際には、定子の属する関白家が急速に衰退していく中で、書くことで自らを慰め、また、それを周辺の人々も読むことで慰められて行ったのではないか。こういうのはいいわよね、とかいやよねとか言った軽い段もあれば、関白家が栄えていた時代の楽しい想い出を書いた段もある。また、今の暮らしの中でも面白いことや楽しいことを見つけて書いた段もある。実際には家運傾く中で、背いていく人や辛いこともあったのだが、そうしたことは書いていない。あえて書かなかったのだろう。ただ、一か所、定子の乳母が離れていくくだりがあり、こんな素晴らしい中宮様を離れるなんてどうしてできるのだろうか…と作者の筆致はここばかりは非難がましい。
2024年06月20日
コメント(10)
-
「枕草子」(上)を読んで
枕草子第百三十六段までを読んだ。だいたい真ん中あたりなので、感想を書いてみる。大きな部分を占める宮中生活の回想については、時系列に関係なく並べられており、しかも背景の政変などについてはほとんど記述されていない。そのため、ただ読んでいると楽しいことを思いつくままに書いたように見えるのだが、実際には道隆健在の頃の栄華の絶頂期から関白家の没落というように定子サロンをとりまく状況は激変している。栄花物語には関白家没落の後にも、並みの女房よりも面白い清少納言の相手をするのを楽しみに多くの男達が集まっていたという記述があったと思う。落ち目の関白家であっても、清少納言は必死にサロンをもりたてていたのだろう。百人一首でも有名な鳥のそら音の歌のやりとりも、この時期のことである。前半を読んだ中で印象的なものは雪の山の挿話である。定子のなくなる二年か三年前で、既に関白家は没落している時期のことである。雪が降った後で、大きな雪の山を作り、その雪の山がいつまで残るかについて定子と清少納言との間で賭けをした。ところがこの雪の山の庭に乞食の尼が侵入し、仏前の供物の残りをねだる。卑猥な歌を歌って舞うので、女房達はいつしかその歌詞にちなんで常陸介というあだ名をつける。権勢のある時期であれば、そんな乞食の侵入は考えられなかったであろう。また、この尼乞食というのは、本当に庶民だったのだろうか。この時代、出家というのは一定以上の階層に限られていたであろうし、貴族の女性であっても、しっかりした後見がなければ、小野小町の落剝伝説にあるように、困窮し流浪する可能性もあった。今昔物語には宮女が乞食同然で窮死する話もある。尼乞食の常陸介は道化として登場しているが、女房達の目にはもしかして明日の我が身かもしれぬという感があったのかもしれない。雪の山は結局は定子が賭けに負けるのがいやさに壊したという話になっており、これをそのまま読むと、単に定子が子供っぽい所業をしただけのことになる。しかし、そうではないだろう。雪山が壊れているのを見て清少納言がくやしがったということが書かれており、彼女自身も自ら道化役をやることで、サロンの雰囲気を明るくしようとしたのではないか。もちろんそれは定子も承知の上である。楽しく面白いことばかりを書いているようにみえる枕草子も、関白家が、政争に敗れ、没落していく背景を考えて読むと、どことなく物悲しい。ところで関白家の没落の決定的な要因となった長徳の変なのだが、ネットで見るとやはり道長の陰謀説がある。伊周と隆家が花山上皇に弓を射たという事件なのだが、秀才の誉れ高い伊周がこんな所業を主導するとも思えない。もしかしたら、伊周追い落としのために、道長と隆家が通じていたという可能性もあるのではないか。兄弟と言えども利害は同じではない。そして、その後を見ても、実際に弓を射たという隆家の処分の方が軽くなっている。
2024年06月17日
コメント(8)
-
「虞美人草」(夏目漱石)を読んで
当時、大評判だった文豪の作品、となると絶賛しなければならないのだが、どうも疑問が残る。ときおり入る漢文調の美文はいまどきこんなのを書ける人はいないなと思うし、各人物の造形もたしかである。しかし、両親を失い恩人の世話で進学した青年が大学で優等の金時計を貰い、英語を教えている富家の美女藤尾との結婚を考える。時は二十世紀初め、舞台は東京。文明の先端をすすんでいるつもりの主人公には、郷里の恩人すらも、遅れた田舎の住民、旧時代の人間に見え、できれば縁をきりたいと思っている。ところが恩人の方では主人公が自分の娘と結婚するものと期待しており、主人公と藤尾の仲が進展しそうになったときに、娘を連れて上京してくる。結局そのことは、「真面目になるため」主人公が恩人の娘を選んだことで藤尾が自殺をするという結末になる。当時は、貧しく優秀な若者を支援する代わりに、自分の娘を若者にめあわせるという人間関係がけっこうあったのだろう。正式な婚約ではなくとも、こうした場合、主人公には娘に誠をつくすことが倫理上期待されていた。そうだとしたら、藤尾と付き合った主人公の行動はかなり身勝手で優柔不断であり、驕慢な美女とされる藤尾はその犠牲者のようにみえる。そういえば、あの「舞姫」にしても、国費で留学した秀才が留学先で踊り子と深い関係になりながら、そのまま帰国した顛末をえがいたものなのだが、こんな身勝手な内容の小説が、いくら表現が巧みであるにしても、近代的自我の目覚めを描いた文学として評価され、教科書にまで掲載されているのがよくわからなかった。それはさておき、もう一つの小説を読む楽しみには、当時の世相を想像することがある。この小説では東京で開催された博覧会が大きな役割を果たしており、その記述も興味深い。当時の人々にとって博覧会というものはまさに文明の先端に触れることであった。また、主要な男性の登場人物はいずれも帝国大学卒業生なのだが、今の感覚ではずいぶんとのんびりしている。一人は博士論文の執筆中、一人は外交官試験受験中、そして一人はヒポコンデリーのような状況だ。帝国大学卒業といえば当時は稀少中の稀少で、それだけに学歴は大きな資産で就職をあせる必要がなかったのかもしれない。高等遊民と言う言葉がまだあった時代である。一方で女性は藤尾を除けば、いずれもつつましく受動的だ。今だったら、こうした小説が人気になるとは思えないが、明治と言う時代を知る上では、読んでみるのもよい。
2024年06月10日
コメント(2)
-
「もっと言ってはいけない」(橘玲)を読んで
世の中には言ってはいけないことがある。正確にはどこかでは言われているのだが、大きな声では言われていないということである。その一つ。人種によって知能の差があるという事実。人種によって脳容量に差異のあることは医学的に明らかになっているし、オリンピックやスポーツ国際大会を見れば人種によって運動能力に差のあることは多くの人が認める。それが知能となると、人種による差は大きな声では語られず、経済的背景や教育制度のせいになるのは不思議である。本書では、その「言ってはならない」人種による知能の差にかなりのスペースをさいている。内容はまあ、予想どおりなのだが、ただ、この人種の差というのは、あくまでも統計的な差異であるので、具体的に〇人種に属している誰かさんが△人種に属している誰かさんより、知的レベルが高いということはないのだし、数多くの天才的頭脳を輩出して学術の発展に貢献した民族があったとしても、その民族に属する任意の誰かさんが偉いということには全然ならないということはもちろんである。人種による知能の差があったとしても、それはヘイトを容認するものではない。次に男女による知能の差。これはどっちが優れているかではなく、一つは分散の違い、もう一つは分野の違いである。分散の違いというのは、あまり異論ないのではないか。要は極端なりこうとバカは男に多く、女は平均への集中が高いということである。ノーベル賞受賞者と犯罪者はいずれも男が多いが、これは女が差別されているわけでもなければ、男が差別されているわけでもない。また、男は空間的認知能力が高く、女は言語的能力が高いともいう。これも統計的傾向であり、個々人にそのままあてはまるわけではない。だから、理系に進む女性が少ないのをすべて昭和脳的偏見のせいにして、女子学生を入試で優遇するような動きはゆきすぎではないか。こうした人種による差異は知能だけではなくセトロニン濃度にもみられ、これが少ないほど真面目、几帳面、悲観的になりやすいという。東アジアでは、セトロニン濃度が遺伝的に低いという。もし、これが本当だとしたら、昨今、東アジアで特に少子化傾向が進んでいることも、これが背景にあるのかもしれない。悲観的かつ真面目だから教育熱心となり、教育費の負担も高く、受験競争も全員参加の激烈なものになりやすい。ケセラセラで愛する者同士一緒になって子供を無計画につくるなどもってのほか、きちんと結婚して良い子を生まないと家名の恥になる。こういう社会ではたしかに子供はなかなか生まれないだろう。
2024年05月29日
コメント(0)
-
「書道教授」(松本清張)を読んで
「書道教授」を読んだ。題名にある書道教授というのは主人公の銀行員が書道を習っている女性であり、年増だが奥ゆかしい魅力をたたえている。主人公には見合いで結婚した妻がおり、古本屋の色っぽい女房も気になり、さらに、その古本屋の女房に似た雰囲気のホステスとも親しくなっていく。このホステスがとんでもない疫病神で、主人公にしがみつき、次々と金をねだり、しまいには妻の実家から金を出してもらうことまで要求をする。よくある火遊びのつもりが深みにはまっていくというパターンなのだが、窮地に陥っていくいく状況は哀れでこっけいでもある。結局のところ、これは成功したかにみえた完全犯罪が破綻を迎えるという物語なのだが、冒頭にでてきた流行っていない呉服店の謎も回収されており、ややご都合主義にも見える点も気にならない。主人公の銀行員はどこまでも平凡な人間であり、こうした平凡な人間の平凡な日常と、犯罪とが地続きになっている分、ちょっと怖さがある。主人公をとりまく女性で一番活躍するのは前半ではホステス、後半では妻で、題名になっている書道教授の女性の出番はさほど多くないのだが、この女性こそが最も不思議な魅力を放っているようにみえる。この小説は「松本清張傑作短編コレクション」に収録されているが、他に収録されている短編の中には以前に読んだものも、いくつかある。ただ、一度読んだものでも、全く記憶に残っていないものと、逆に強烈な印象を残すものとがあるのが面白い。「巻頭句の女」は薄幸な女が強烈な印象を残すのだが、「カルネアディスの舟板」は読んだはずなのだが、ほとんど記憶になかった。いずれも面白い小説であることには違いない。
2024年05月27日
コメント(2)
-
「夜間飛行」(サン・テグジュペリ)を読んで
夜間飛行黎明期を舞台にした中編小説で、小説というよりも散文詩のような印象である。夜間飛行と言うのは今でいえば宇宙飛行に似ている。未踏の空間での絶対孤独の世界と言う意味で。そしてそこで目にする地上の光景や星や月も、今まで普通の人間が見ることができなかったものであることも共通している。飛行機の窓際に座り、はるか下で街が煌めくのを見たらきっと思い出す小説だろう。それにしても、現代では夜間飛行どころか宇宙に行った人も何人もいる。こうした人々の中で、文章と言う形で宇宙を伝えた人というのはどのくらいいるのだろうか。
2024年05月23日
コメント(0)
-
「歴史は予言する」(片山杜秀)を読んで
読みやすく面白い本である。そして随所に著者の博識があふれている。その博識というのは教養になりそうな知識ということではなく、同時代の人だったら知っているような、へえ、そうだったのか…という話である。もちろん著者はそんな時代に生まれていないのだが、そうしたことを知識として知っているだけでもなかなかのものであろう。世相、政治、国債情勢について縦横無尽に書いているのだが、別に右とか左とか上とか下とかの立場で書いているわけではない。そういう柔軟性がよい。一例をあげると柳田邦夫はベーシックインカムが好きという項目がある。ベーシックインカムは遠野物語の柳田邦夫とは結び付きそうもないのだが、著者によれば、日本人が我慢できる最低生活の水準の確定こそ柳田学の初動の志だという。農政官僚と民俗学はすぐに結び付きがたいが、そういう関心ももしかしたら多少はあったのかもしれない。現在のところは、あちこちで人手不足が叫ばれているが、今後は様々な分野で人間の仕事が機械に置き換えられていくのかもしれない。その結果、生まれる山のような失業者は、窮乏生活を求められ、ベーシックインカムで暮らすという未来図があるかもしれないという。著者はそんな未来を期待しているわけではないが、配達はドローン、タクシーは自動運転、事務はAIという時代になればそういう未来も本当にあるのかもしれない。一読して損はない本だと思う。
2024年05月16日
コメント(0)
-
「あの道この道」(吉屋信子)を読んで
少女小説のお手本のような小説である。舞台は戦前。嵐の日に生まれ取り違えられた二人の赤ん坊。一人は大金持ちの家の令嬢として育ち、一人は貧しい漁師の家の娘として育つ。取違物語はドラマにもよくあるのだが、現実にも赤ちゃん取違というのはないわけではない。物語ではたいてい貧しく育った方が主人公になっているので、こうした物語は主人公が貴種でありながら苦難の道を辿るという一種の貴種流離譚ともいえる。主人公が貧しい育ちにもかかわらず、気品があり美しく賢く、誰にも愛されるというのも貴種である故か。戦前は酷い格差社会であるので、こうした設定になるのだろう。金持ちの娘として育った側は最初こそ意地悪なのだが、これも、根っからの悪役と言うわけでもなく、登場人物全体に「いい人」が多く、その分、大団円に向けてすんなりと物語はすすむ。文体は非常に読みやすく、一気に読める。面白いのはサイドストーリーの温泉採掘の部分である。舞台は明らかに伊豆半島なのだが、温泉発掘に人生をかける親子がでてくる。家産を傾けても温泉発掘に打ち込む父と、その父の死後は模範青年のような息子が学業を辞めて遺志を継ぐ。伊豆半島には昔から知られた温泉もあるが最近発見された温泉もあり、その中にはこうした温泉発掘にまつわるドラマもあるのかもしれない。のも実際にいたわけであろう。
2024年05月13日
コメント(0)
-
「菊枕 ぬい女略歴」(松本清張)を読んで
「菊枕 ぬい女略歴」を読んだ。短編なのだが、読んでいて非常に重苦しい。女主人公ぬいに実在のモデルがいるということだけでなく、俳句の世界ということを別にしても、主人公の苦悩が、非常にありそうなものに思えるからである。ぬいはお茶の水女子高等師範付属女学校を卒業した才媛で、男並みの長身という女性にとっての難点を別にすれば際立っての美貌と文才にも恵まれていた。実際にモデルとなった女流俳人の写真をみても相当な美貌である。そして彼女は降るような縁談の中から美術学校出の青年を結婚相手に選ぶ。彼女が結婚相手に期待したのは「芸術家」であった。しかし、夫は田舎の中学校の美術教師になり、それで満足している。そういう結婚についての錯誤、夫への不満というのは、男から見ると身勝手であっても女性には時折ある。結婚前は男は自分の才能や将来性について多少盛ることがある。ぬいの夫も結婚前はもっともらしい芸術論をはき、それをぬいはうっとりと聞いていたのではないか。ぬいも後年俳人になるくらいなので、芸術的志向はある。田舎の美術教師の妻となったぬいは俳句を始め、頭角を現すことで、彼女にも新しい世界が開けるようにみえた。しかし、雑誌に自分の句が掲載されたところで、それだけで収入になるものでもない。俳人の多くは別に社会的地位のある職業についたり、そうした者の妻であったりする。俳句関係の交友が増えるにつれ、ぬいはますます「田舎の中学教師の妻」という身分に引け目を感じるようになる。今はそうしたことがどの程度あるのか知れないが、当時は夫の地位イコール妻の地位であった。ぬいが俳檀の巨匠にストーカーのようにつきまとったのも、巨匠を通じて自分に大きな世界が開けることを期待したのかもしれないが、それも拒絶される。表題の菊枕は菊の花をつめた枕を使うと無病長寿であるとされ、ぬいが師匠のために心をこめて菊枕を作るというエピソードによる。その後、ぬいは句作も衰え、精神を病んでなくなるのだが、このあたりはどこまでがモデルの実像で、どこまでが創作なのだろうか。ぬいは句想を得るために英彦山によく登っていたというのであるが、絵や写真と違い、俳句には元になるものがない。いくら山をみても山の俳句が浮かぶわけはない。一度、俳句で名声を得た人がそれを維持するというのはかなり大変なことのように思う。さて、一読してみると、この小説の主人公はぬいの夫の圭介ではないのか。俳句の会や旅行に行くぬいを経済的に支え、家事を行わないことにも文句もいわず、最後にぬいが夫のための菊枕を作ると、ようやくぬいが自分の下に戻ってきたとよろこぶ。妻の期待するような芸術家になれなかった夫の負い目かもしれないし、一種の嗜虐的な喜びかもしれない。こういう夫婦も世間のどこかにはいるのだろうか。
2024年05月09日
コメント(4)
-
松本清張のタイトルの妙「支払い過ぎた縁談」、「生けるパスカル」、「骨壺の風景」
森鴎外の三男を主人公にした評伝小説「類」に主人公は松本清張の小倉日記をテーマにした小説を読んで、その圧倒的な文才の差異に衝撃を受ける場面がある。これが評伝小説作家の創作なのかどうかはわからないが、いかにもありそうに思う。松本清張の短編傑作コレクションのうち、「支払い過ぎた縁談」、「死せるパスカル」、「骨壺の風景」を読んだ。最初の「支払い過ぎた縁談」というのは、アイディア自体は雑談の中からでも生まれてきそうなのだが、普通はこんなに面白い小説にはできない。昭和32年という当時の世相などまで想像させるし、登場人物の若い研究者にはなんとなく作者自身が投影されているような気がする。つっこみどころはあるのだが、ぐいぐいと読ませるのは作者の力量だろう。「死せるパスカル」も推理小説あるいは犯罪小説のようであるが、トリックについては、これだけのものでよくも…と思う。登場人物にはさほど共感できるタイプはいないし、主人公の画家は、佐藤愛子の「血脈」の佐藤紅緑を視点を移せばこうなるのかと思わせるほどである。けれどもこれも、先がきになり読ませる小説となっている。「骨壺の風景」は内容はほぼ作者の身辺に起きたことで創作の要素はない。祖母の骨壺を探すとともに、祖母や父母の人生を回想した内容である。似たような経験のある人はいるのかもしれないが、それを読ませる小説にできる人は稀有である。三作ともタイトルの妙ということで、並べられた小説なのだが、いずれも作者の読ませる文章の才というのを見せつけた小説のように思う。奇抜なトリックや特異な事件は扱っていないのに先が気になって頁を繰る手がとまらない。読ませると言えば、ときどきでてくる生き方指南のとうな新書も似たようなものだろう。自分ではまず買わないのだが、借りて読むことはある。知的生き方、幸福になる生き方、健康の秘訣などなどについてつづったものなのだが、多くは、それができれば苦労はないよといった内容で、読んだ後は時間を無駄にしたと思う。いってしまえば、金持ちになるには無駄遣いをしないことだとか、試験に合格するには一点でも多くとることといった類であろう。ただ、こうしたものがなぜ売れるのかと言えば、それは多くの場合、読ませる文章で書いてあるからだろう。文章というものは音色であり、内容というものは旋律のようなものなのかもしれない。音色がよければ心地よく最後まで聴ける。
2024年05月07日
コメント(0)
-
「塞王の楯」(今村翔吾)を読んで
戦国時代を舞台にした歴史小説である。ただ目新しいのは主人公を武士ではなく、石垣や鉄砲を作る職人としたことであろう。石垣が盾なら鉄砲は矛…この矛盾の解決の先に泰平の世が開ける。職人もまたそう信じて己の技術を磨いていく。歴史小説にはいろいろなタイプがあって、実際にあったかもしれない歴史的事実に即したものから、想像を飛躍させたファンタジー色の強いものまである。前者の中には頻繁に出展や根拠を説明しているものがあるが、はたして本作はどちらだろうか。作中で紹介されている石垣の技術や鉄砲の技術が、どの程度、歴史的な事実をふまえたものかどうかが気になる。そしてまた、この小説のように、殿が領民を守るために領民までが城に籠るなどということがどの程度あったのだろうか。領民、特に職人は、戦国時代の戦いの勝者にとっても金の卵を産む鶏のようなものであろう。関ヶ原の戦いでは農民たちは弁当をもって見物していたという話を聞いたことがあるが、おそらくそちらの方が事実に近かったのではないか。また、この小説では石垣を盾に見立てているが、実際の籠城戦では狙うのは建物本体であって、石垣を盾とするのは無理があるように思うし、砲を防ぐために即席で石垣を作るということも、本当にそんなことが可能だったのかとも思う。もっとも、どこまでが歴史的にありうることかなどと固いことは抜きにして、小説として読む限りでは面白い。歴史小説には、別の読み方もあり、現代に投影して読むという読み方もある。大津城の城主の京極高次は武将としては無能だが、部下を愛し愛される性格で、それが結果的に強さとなっている。戦国時代にこういうタイプがいたかどうかはともかくとして、現代のリーダーには、もしかしてこんなのもいるかもしれない。新機軸の歴史小説としては、読んでみても良いかもしれない。ただ、これは個人の感想で、人によって違うのかもしれないが、すいすいと読めるタイプの文体ではないようで、いっきに読めるという小説ではない。
2024年05月03日
コメント(0)
-
「書いてはいけない」(森永卓郎)を読んで
「書いてはいけない」(森永卓郎)を読んだ。ジャニーズのようにマスコミに強大な影響力を持つ者に対しては批判できない、財務省のような強大な勢力に反する言論は表に出ない…というのはおそらく実態だろう。ただ日航ジャンボ機の事故の真相についての記述は信じがたいもので、それだけで、大問題になりうる。戦後まもない時期に起きた闇の事件と同様、今の日本にも怖くて触れられないものがあるのかもしれない。さっと読める本だし、内容の強烈さは一読の価値はある。今のマスコミは書けないこと言えないことが沢山ある。そう思うとテレビの報道番組のコメンテーターのつまらなさもむべなるかなである。それなりの肩書の知的美女イケメンをならべて、チャンネルを回されない程度の時間でコメントを求めるのだが、おおくはもっともらしくありきたりなものにとどまっている。そりゃそうだろう。踏み越えて批判してはいけないものを批判し、触れてはいけないことに触れるとあっという間に降板する。あのショーンKでも十分務まる。マスコミについては、強力なスポンサー企業に対する配慮、情報源であり権力機関である政府に対する配慮、マスコミに影響力を持つ芸能事務所に対する配慮など、さまざまな配慮の中で報道を行なっている。特に政権の姿勢がマスコミに対してにらみをきかせるものであれば、報道できる範囲はますますせまくなる。日本の報道が委縮しているうちに、外国からの報道や批判で問題に火がつくなんてのは、日本の報道にとっては大変な不名誉だと思うのだが、そうした反省ははたしてあるのだろうか。そういえば、ある日本企業の現地子会社の提供したシステムに欠陥があり、700人以上の郵便局長が冤罪で訴追されるなんて事件がさる国であったようだが、これについても、日本では報道が少なかったが、これもスポンサー企業に対する配慮なのだろうなと思う。
2024年04月22日
コメント(4)
-
「名もなき毒」(宮部みゆき)を読んで
「名もなき毒」を読んだ。この毒にはいろいろな意味がある。無差別殺人犯の使う毒、シックハウス症候群の毒、さらには人間の中にあるまだ名のついていない毒。犯罪というものも、そうした人間の毒の噴出なのかもしれない。この小説には様々な人物が登場する。主人公の大企業の会長の娘(妾腹)と結婚したサラリーマン、トラブルメーカーの元バイト、元警察官の老探偵、売れっ子ライター、地域の世話役的な商店主と芸術家気取りのバカ息子などなど。ただ、そうした中で、これは読者によって違うのだろうけど、一番リアリティを感じたのは、体が弱く定職につけないでいるバイト青年だ。両親は家を離れ、寝たきりの祖母の介護をしながら、傾いた家に住み、楽しいことの何一つない生活を送っている。頼りなげで「何かしてやりたい」という雰囲気をもっているのだが、商店主も掃除をたのんで小金を渡す以上のことはしてやれない。この前の黄金茶碗窃盗男もたぶんこんな感じだったのだろうなと思う。そしてさらに思いつくのは佐藤愛子「血脈」の最終章の「暮れていく」に出てくる佐藤家の末裔だ。「血脈」では、よくこんなのを書いたなと思うほど佐藤家(自分の血脈)のどうしようもない人物ばかりを描いているのだが、先の世代のドラ息子達が、女と放蕩する、店をつぶすなどとアクティブなタイプが多いのに、最後の末裔の青年はぼやっとした無職青年で、無気力で何も考えていないという感じになって来る。こうした佐藤家の荒ぶる血が薄れていく様を「暮れていく」と表現したのだろう。豊かで平和な時代が長く続くとこうした「暮れていく」タイプが多くなるのかもしれない。ネタバレになるので、あまり書かないのだが、作中人物にももちろん毒を持っている人がいる。そのある者はその毒で自分をさいなみ、自滅していく。物語としての後味は良くないし、エピローグ的な個所は冗長で余計な気もする。ただ、これだけの長編にもかかわらず一気に読んでしまうあたりはさすがというものであろう。暇なときや通勤電車の中などにお薦めである。
2024年04月21日
コメント(2)
-
「数の悪魔」(エンツェンスベルナー)を読んで
実はこうした一般向けの数に関する本を読むのが好きだ。だいたいは図書館で借りるのだが、それは途中でついてゆけずにリタイヤした場合(こういうことは多い)も金銭的な後悔はなくてすむ。あの「博士の愛した数式」は小説も映画もいまだに傑作だと思っているし、ユーチューブにもこの分野の解説ははいてすてるほどあり、なかなか面白い。最近では、循環数やカプレカ数についての解説など興味深かったし、なんで今までこんなことも知らなかったのだろうかと思った。そういえばその昔、清水の次郎長が静岡で幕臣たちの生活再建の手伝いをしていたとき、旧幕臣の蘭学者から、月の満ち欠けの理由を説明され、なんで今までこんなことも知らなかったのか、長生きはするもんだ…と言ったとか言わなかったとか。まあ、それと似たようなものかもしれない。人間は数と言葉を使ってものを考えるものなのだが、言葉が自然発生的とはいえ、人間が作ったものであるのに対し、数というのは人間を超えたところに存在し続け、それを人間が発見してきたというところがある。だから非常に簡単な問題であっても、いまだに誰も証明できないというものもある。「数の悪魔」には興味深い話がいろいろとあるのだが、フィボナッチ数列とパスカルの三角形のあたりが面白い。一定の法則に従って数列を作ったり、三角形に並べていったりした場合、予想もしない別の法則が現れることがある。身近ですぐそこにある数というものにこれほど多くの不思議があるということに驚く。体裁は子供用の本になっているのだが、誰が読んでも良いだろう。
2024年04月16日
コメント(2)
-
「土屋文明」(内田 宜人)を読んで
図書館で衝動的に借りた本である。実は土屋文明と言う歌人は名前は知っていても、正直にいって彼の歌で好きなものがあるわけではない。この本でおびただしく引用されている彼の歌を読んでもそれはかわらなかった。土屋文明が短歌の世界で重きをなしたのは歌がすぐれているからというよりも、新アララギを主宰し、多くの弟子をかかえていたというその政治力にあるのではないか。ただ短歌のよしあしは受け手の感性によって違う。たぶん、自分の場合はたまたま土屋文明の歌と合わなかったというだけのことだろう。この本の面白さは土屋文明そのものよりも、筆者の眼を通して描かれる戦前から戦後の世相にある。特に、大東京発足や紀元二千六百年の時の街の様子などは興味深い。学校で紅白菓子を配り、花電車が走ったことなどは歴史の教科書にはでてこないし、紀元二千六百年という政府肝いりで作成された歌もあったがレコードはさほど売れず、筆者周辺では実際の祝賀ムードもさほどではなかったという。また、土屋文明が諏訪高等女学校の校長をやっていたときの教え子で昭和3年の共産党一斉検挙事件で犠牲になった伊藤千代子という女性についてもかなり詳細に書かれている。実際には校長と生徒の一人と言う関係にすぎなかったが、土屋文明は以下のような哀惜の歌をいくつか残している。芝生あり林あり白き校舎あり清き世ねがう少女あれこそ戦前という時代はいろいろな見方ができるが、思想弾圧によって犠牲になった人々が何人もいた時代であったことは忘れてはならないだろう。伊藤千代子の生涯については映画にもなっているようである。予告編「わが青春つきるともー伊藤千代子の生涯」 (youtube.com)
2024年04月14日
コメント(2)
-
「白い巨塔」(山崎豊子)を読んで
「白い巨塔」を読み終わった。医療と訴訟の世界を軸とした社会派小説で、その背景となった膨大な知識に圧倒される。この小説が出た昭和40年ごろにはまだ女流文学という言葉があり、女流作家と言えばなにか共通の作品世界があったと思うが、本作はそうした女流の枠をはるかにこえている。ただ、正直に言うと、最初の山である教授選のところではどうもこの作品テーマに興味がもてずにリタイヤしようかと思った。しかし、その次の山場である医療訴訟のあたりからはどんどん小説世界にひきこまれていった。主人公財前は手術した患者の診察を受持ちの医師にまかせ、海外出張に行く。このドイツ訪問の箇所は紀行文としても面白いのだが、その海外出張中に胃癌を手術した患者は肺癌で死亡する。これを遺族は胃癌の肺転移に気づかなかった財前の医療ミスであるとして訴訟を起こす。当たり前だが、損害賠償が認められるためには、医師に過失がありその過失と患者の死との間に因果関係がなければならない。手術時に肺癌の措置をしなかったことと、その後、短期間で起きた患者の肺癌死との間の因果関係を認めるのは難しいのではないか。癌は相当の期間を経て死に至る病であり、画像の見落としなどで早期発見の機会を逸したのとは違う。いくら患者遺族から見て医師が傲慢で手術後一回も患者を見なかったのが不誠実であったとしても、これだけでは損害賠償にはならない。非常に面白い小説なのだが、新進気鋭の弁護士がよくこんな訴訟を引き受けたとも思うし、調査や鑑定にも膨大な費用がかかるので、困窮する遺族が経済負担に耐えうるかも疑問である。同じ専門職でも医師は保険制度があるので貧しい農婦でも早期胃癌の手術ができるが、そんな制度のない法曹では弁護士費用や訴訟費用は遺族がすべて負担する。ただ、この小説、医療訴訟の控訴審の場面が一番面白い。訴訟では財前は肺転移に気づいていたという主張をする。そのために、部下の医師や看護婦に虚偽の証言をさせたり出廷を妨害するような工作をする。その財前の主張を原告側の弁護士らが覆していく。財前の主張の虚偽を暴く法廷場面が小説でもドラマでも最大の見せ場となっている。小説の流れでは、第二審は原告勝訴となるのだが、胃癌手術後に化学療法で延命できたはずであるので、患者の死を早めたことに損害賠償責任を認めたのはやはり無理があるだろう。当時は癌は今以上に不治の病であり、化学療法も緒についたばかりだったのだから。そしてまた、癌は患者本人に知らせないというのが常識だったので、たとえ死期が伸びたとしても、患者が経営する商店について自分の死後の準備をするとも思えず、商店の経営悪化や遺族の困窮が防げたとも思えない。この小説の最後については、こうした形の結末が一番すっきりするのかもしれないが、ややご都合主義の感じがしないでもない。ただ癌は患者本人には絶対に知らせないというルールが固く守られている点については、今日から見れば隔世の感がある。この時代には、癌の告知はタブーであり、癌を告知された高僧がショックのあまり気が狂ったという話がまことしやかに語られていた。
2024年04月09日
コメント(2)
-
「白い巨塔」(山崎豊子)購読中
「白い巨塔」を読んでいる。テレビドラマでやっていたのは知っていたが、実は見たことはない。ただ番組宣伝などでやっていた田宮二郎が多くの医師の従えて行う回診の場面が印象的だったので、病院などで回診をみると、つい「白い巨塔」を連想する。日本でもドラマや映画になっているが、韓国でも何年か前にリメイクされているので、どんな話かと思ったのだが、全五巻の内の第一巻を読んだ限りでは、それほどドラマチックな展開はない。大学病院の中の人間関係と教授選の舞台裏の話がメインで、どうもひきこまれない。医師といえば、病院では権力も名誉もある人々であり、その中で教授になるかどうかなんてそんなに重要なのだろうか…とついつい思ってしまう。主人公の名誉欲や上昇志向を理解し、同化しなければ、なかなか小説世界に入り込めないのだ。ただ第二巻の後半あたりからは医師の家族や患者をめぐる人間模様もでてきて、面白くなる。この小説が最初にでたのは1965年ということで、今にしてみると時代を感じる。医療分野では昔から女性も進出していて女医もいたはずなのだが、物語には女性医師は今のところでておらず、医師の夫人や娘達は専業主婦だったり、花嫁修業中だったりして、職業はもっていない。そういう時代だったのだろう。もっと変化を感じるのは、診断の場面で、レントゲン画像や胃カメラの映像から、病名を診断するのが重要な医師の能力となっている。今ならレントゲンや胃カメラ自体も進歩しているが、CTスキャンやMRIでより鮮明に人体内部を見ることができる。医師に求められる能力も機器の変遷とともに変わっているのかもしれない。
2024年03月13日
コメント(5)
-
「日本占領と敗戦革命の危機」(江崎道朗)を読んで
GHQ占領時代に以前から関心があった。日本近現代史の中で明治期と並ぶ大変革の時期なのに、あまりこの時代について書かれたものはないし、もちろん歴史の授業でもスルーされていた。ただ、昭和40年代かもしかしたら50年代くらいまでは、新聞の論調など「戦前の暗い時代を思い出す」というのがほぼ常套句になっていたし、なにか戦前の時代というのは余計なことを言うとすぐに特高というものがやってきて連れていかれるような怖ろしい時代だというイメージがあった。それが戦後の改革で民主主義というまぶしいものがやってきて、よい時代が始まったというわけである。ただその後、いろいろなものを読んだり聞いたりしてみると、もちろんそんな単純な話でもないとわかる。特に興味深いのはGHQの姿勢も一貫していたわけではなく、あの戦後まもない時期に計画されたゼネストをGHQ指令で止めたあたりから占領方針も変化した。それまではGHQは労組の見方と思われていたし、ゼネストも当然に支持されると思われていた。本書はこうした動きの背後に日本の敗戦革命を考える勢力と保守自由主義勢力の抗争があったとする。敗戦革命とは、戦後の窮乏や混乱に乗じていわゆる親ソ社会主義政権を樹立しようという動きをいう。ただそれもにわかに信じられない話だ。日本の占領は間接統治という形で行われ、その間接統治という形を得るためにも日本側の相当の努力があったというのは事実だろうが、その統治は連合軍の中でも米国主導で行われた。米国主導の中で親ソ社会主義政権の誕生と言うのも考えにくい。また、GHQの中に社会主義者がいたとしても、それと親ソはイコールではないだろう。ソ連は第二次大戦で膨大な被害を被った国であり、そこまでの影響力があったとも思えない。本書は、GHQの中に親ソ的な勢力があり、敗戦革命をもくろんでいたが、昭和天皇や吉田総理を中心とする保守自由主義勢力がそれを防いだと見る。その見方自体については疑問があるものの、これも占領期についての一つの見方として読めば興味深い本である。
2024年03月06日
コメント(10)
-
「源氏物語」を読んで
最初は少しずつ傍らに読むつもりだったのだが、読み始めるとたちまち続きがきになって読み進み、ノンストップのまま、ようやく「夢の浮橋」まで読み終えた。光源氏の本編では文章の流麗さや人物描写の鋭さに目を見張ったが、宇治十帖になると、本当にこれが1000年も前の小説なのかと驚く。この時代には素朴な英雄譚や伝奇物語が主流で近代小説がうまれるのははるか後のことだ。ところが宇治十帖では薫、匂宮、大君、中君、浮舟という五人の男女の心理が丁寧に描かれ、父八宮の死、大君の死、浮舟の登場と出来事が巻ごとに進行し、今の小説といってもよい趣がある。特に入水した浮舟の蘇生後を描いた「手習」の巻はそれだけでも独立した物語となっており、浮舟に想いをよせる中将、亡き娘がわりに浮舟を慈しむ尼君、天下の高僧として名高い僧都などが登場し、その中で、浮舟の出家の顛末がえがかれる。高度な文学的な鑑賞というのとは違うのだが、こうした物語はなんとなく既視感がある。中将の視点でみたらどうだろうか。亡き妻が忘れられずに妻の母である尼君をときおり訪ねている男がいる。その尼君の住む山里でふと美しい女を見かけ、彼女が忘れられなくなる。女は記憶を失っている様子で、どこの誰ともわからない。こうした物語はハッピーエンドにしろそうでないにしろ、今日でもドラマなどでよくあるのではないか。それにしても、この時代の出家とはどういう意味をもつのだろうか。源氏物語には出家する登場人物が多いし、その背景の事情もさまざまである。祈祷とか加持が、今の医療のような役割を期待されていた面もあるし、寺詣でが御利益を期待してという面もある。それとは別に、この世の苦しさを逃れる手段としての出家というのもあった。この世での栄華や幸せをあきらめるのと引き換えに後世の幸福を祈って出家し、精神の平安を得るのである。浮舟の身にしてみればいまさら世にでるわけにもゆかず、出家というのはしかたない選択だったのだろう。それにしても、出家後も兄弟と思ってほしい、後の生活の世話もしたい…と言う中将は誠実な男であり、浮舟も最初からこうした人に出あっていれば幸福になっていたのかもしれない。
2024年03月03日
コメント(2)
-
源氏物語「浮舟」の巻を読んで
更級日記の作者が源氏物語を読みながら大きくなったらきれいになるかしら、髪が伸びるかしらと思いながら夕顔や浮舟のような女性になることを空想する場面がある。その浮舟であるが、彼女は生まれた時からこの世の中に居場所のないような、それこそ浮舟の名のような寄る辺なき境遇の女性である。父親の八宮には生まれた時から拒絶され、継父の常陸守からは異人(ことびと)として疎外されて育つ。常陸守の実子でないことにより縁談が壊れてからは、常陸守の屋敷にも居場所がなくなり、中君のいる二条院、次いで母の用意した隠れ家に移り住むが、その後は、薫により宇治の別荘に匿われ、そこでたまさかの薫の来訪を待つ生活を送る。しかしそこに、二条院にいるときに浮舟に目をつけた匂宮もやってくるようになり、薫、匂宮、浮舟の三角関係が始まる。なぜこんなことになったのだろうか。浮舟が非常に軽視されている女性だったということがあるのだろう。源氏物語には様々な身分の女性がでてくるが、荒れた屋敷に住んで困窮していても、小路の小さな家に隠れ住んでいても素性だけはしっかりしていた。ところが浮舟は実の父に拒絶されており、その父も宮の中に数えられない八宮で既にこの世にいない。継父常陸守からは子供としての扱いをうけていないので、事実上、父親のいない女性である。さらに長い時期を常陸の田舎で育ったので管弦の道も教養も身についていない。遠慮して育ったせいか、物事を強く拒絶することのできない優柔不断な優しい性格なのだが、それはまた三角関係の中で薫にも匂宮にも決めかねるということになり、悲劇につながっていく。薫というと匂宮に対比して内省的な性格と解説されることが多いが、浮舟や中君、そして妻の二宮に対する態度は身勝手であるし、次から次へと想う女を変え、飽きたら姉一宮の女房に押し込むような匂宮に比べれば真面目というだけのことだろう。薫は、最初の頃は自分の出生の秘密に悩んでいた節もあるが、事実を知ってからは逆に露見を怖れているし、仏道に傾倒しているようでも、悟りを目指しているわけではなく、浮舟を失ってからも女一宮に今度は関心を向けている。ごく最近の言葉ではあるが、恵まれた中二病青年といった趣もある。このように薫にしろ匂宮にしろ、欠点が目につくのは、それだけ宇治十帖の世界が現実的だからであろう。光源氏を主人公にした部分では夢のような宴の場面が多く描かれたが、宇治十帖で描かれているのは貴族の普通の生活である。その意味で、宇治十帖の方がさらに近代文学に近いものだといえるのかもしれない。
2024年03月01日
コメント(2)
-
宇治十帖(宿木まで)を読んで
源氏物語を読み始めて止まらなくなっている(笑)。宇治十帖の宿木まで読んだのだが、たしかに宇治十帖と光源氏が主人公の本編とでは雰囲気が違う。光源氏の女君だけでなく、子供世代の女君が次々と登場し、それぞれの個性あふれる性格や恋が描かれる本編は、話のテンポが速く、舞台も桜の宴、藤の宴、女楽の合奏、香合わせ、胡蝶の船の宴と夢のような場面が多く、王朝絵巻の万華鏡と言った趣がある。これに比し、宇治十帖では主な登場人物は薫、匂宮、大君、中君、そしてこれからでてくる浮舟に限られる。匂宮が中君以外に結婚する夕霧の六君や薫が結婚する二宮は物語では気の毒なくらいに影が薄い。その分主人公薫の心理や行動が丁寧に描写されており、近代の文学により近いのは宇治十帖の方だろう。しかし、その薫の心理をみると…仏道に興味を持ち宇治の八宮邸に行って大君中君の姉妹をかいま見、大君にひかれる。八宮の死後、大君は薫を拒絶し、中君を薫へと望む。そのため中君を友人の匂宮と結び付ければ大君は自分に靡くと思い、匂宮と中君を結び付ける。匂宮の宇治来訪が途絶えたことなどの心労が重なって大君は亡くなり、中君は匂宮の二条院に移る。薫は中君と大君がいまさらながら似ているのに気付き、中君を匂宮に結び付けたのを後悔する。こうしたことを今の道徳でどうこういうのはナンセンスにしても、それにしても、身勝手な奴だと思ってしまう。大君が薫を拒絶する理由はいろいろと考えられるが、すでに女性の盛りの年齢を過ぎていることの引け目や健康不安、妻の死後上臈女房との間に子供を儲けながら仏道の妨げになるとして見捨てた父を見てきたことによる男性不信などの理由があったのかもしれない。光源氏もかなわぬ恋の相手に似ているとして10歳の少女を屋敷に連れ込むなどかなり身勝手なのだが、光源氏が、超人的な美を持つ道徳を超越した存在として描かれているため、そうしたものは感じない。ところが、薫や匂宮は、光源氏ほどの超人ではないために身勝手さが気になる。光源氏が主人公の部分と宇治十帖は別の作者という説が昔からあるようであるが、自然科学と違い、こうした問題は永遠にわからないのではないか。同じ作者であっても作品によって文体や雰囲気が違うことは珍しくない。だから別作者かどうかはわからないが、情報提供などで作品執筆を助けた人はいたように思う。源氏物語には膨大な古歌、漢籍、仏典をふまえた記述がある。また、作者がいったことのない須磨、明石や宇治の情景についての記述もある。結果的に小説家のアシスタントのような役割を果たした人がいても不思議ではない。
2024年02月25日
コメント(2)
-
「源氏物語」御法&幻~愛の物語の終焉
源氏物語にはいろいろな読み方ができるが、一つは母親の面影をもとめる光源氏の恋の遍歴の物語ともいえる。子供の頃に母親にそっくりだといわれる藤壺の女御を慕い、その気持ちはやがて恋に変わっていく。その藤壺に対する許されない恋心は、たまたま見出した藤壺とそっくりな面差しを持つ少女若紫に対する愛に投影され、若紫が成長するとともに、それは女性に対する愛へと変わっていく。若紫にしてみれば、10歳のときに二条院の屋敷に連れてこられ、光源氏を父のように兄のように思ってなついていたのだが、ある朝のこと、光源氏はさっさと起きてきたのに、若紫は全く起きてこない。布団をかぶったまま怒って泣いているのである。それでも実の父に対面し、裳着の成人の儀式をすませ、ようやく光源氏の想い人としての生活が始まるかと思ったとたん、今度は光源氏は須磨に移ることになる。せっかく名乗りをあげた実の父も嫉妬深い北の方に阻まれてなんの支援もできない中で、紫の上は女房達をまとめ、留守の屋敷をしっかりと守っていく。若紫は美しいだけでなく聡明な女性の紫の上に成長したのである。光源氏が都に帰還し、これからは光源氏の最愛の思い人としての生活が始まるかと思いきや、光源氏は明石に愛人をもうけ、姫君まで生まれていた。光源氏は姫君の将来のために姫を紫の上の下で養育してほしいという。姫君をひきとってからは姫君のかわいらしさに夢中になり、明石の上に対する嫉妬も和らいでいく。光源氏が須磨から戻って以降は、新しい女君がでてこない。玉鬘は養女格であるし、女三宮は朱雀院からの懇願である。紫の上は光源氏が最後にたどりついた女性であり、嫉妬に泣いたことはあっても、光源氏の最愛の女性としての地位はゆるがなかった。ただ女三宮の降嫁は衝撃で、子供も後ろ身もない立場の不安定さや今後は衰えていく容色の不安もあって、急に胸の痛みと高熱の出る病気にかかり、一時は生命さえも危うい状況になる。危機は脱したものの、その後は次第に衰えてゆき、出家の願望をもらすようになる。御法では仏事と紫の上の死を、幻では紫の上が去った後の光源氏の悲しみをえがいている。短い巻ではあるが哀切極まる部分でもある。源氏物語にはこれまでも女君の死が描かれてきたが、御法の紫の上の死は光源氏の出家につながり、ここで源氏物語の光源氏を主役にした部分は終わることになる。最晩年の紫の上は光源氏が朧月夜を訪れてもさほど嫉妬していない。なにか女三宮の降嫁以降、関心が仏道に移っていったようなところがある。御法では紫の上が仏道にも通じている様子がえがかれているが、光源氏の愛を争う世界から清浄な仏道世界への関心の移行は宇治十帖の終幕の浮舟の出家にも通じるように思う。
2024年02月19日
コメント(2)
-
「源氏物語」~夕霧
夕霧の巻はその前にも発端になるような箇所があるのだが、この巻だけで一つのまとまった話になっている。夕霧と柏木は極めて仲の良い友人であったが、死の直前の柏木の言葉を受けて、柏木の妻であった落葉宮を訪問しているうちに、しだいに落葉宮にひかれるようになり、ついに側室にするまでの顛末を描いている。柏木の死後、落葉宮の母が病気になったため、律師の祈祷を受けるために小野というところに母子ともに山籠もりする。夕霧はもちろんこの山籠もりの手続きも行い、小野にも何度も訪問する。夕霧という名はこの山里を訪問したときの歌に由来する。山里のあわれを添ふる夕霧に立ち出でん空もなき心地してこの頃には夕霧には既に落葉宮に対する想いがあり、ここに留まりたいという気持ちをこめた歌である。一方、落葉宮には柏木に愛されていなかった想い出があり、さらに容色が衰えた今となっては、軽々しく靡くつもりはない。その後、母が亡くなると、この山里に留まったまま、尼になりたいとまで思う。光源氏と女君の場合は、双方に思いがあるのだが、夕霧の落葉宮に対する想いはひたすら一方的である。だいたい最初から「世の中をむげに知らないわけでもないだろう」などというのはNGである。そして落葉宮を側室にした後で、恋などというものはちっともよいものではないと述懐するわけなのだから、このあたりは光源氏とはずいぶんと違う。もっとも夕霧の落葉宮への想いには柏木の遺言以外にも背景がある。夕霧は真面目で優秀な官吏なのだが、光源氏同様に音楽の才があり、風雅の道にも造詣が深い。これ以前の巻では、六条院の屋敷で女楽を聞いたり鈴虫の宴を楽しんだりするという夢幻のような世界と、所帯じみた雲居雁の様子が対照的に描かれている。雲居雁も子供の頃には大宮から琴の手ほどきを受けたが、その後は関心を失い、ひたすら子供の世話と家事におわれている。こうした場合、夫には妻に不満があるわけではないのだが、それとは別のものを別の女性にもとめるという心理があるのだろう。小野の山荘といういわば非日常の世界もかっこうの舞台となる。源氏物語は今の道徳とかモラルではどうかというのはあるにしても、夕霧と落葉宮、妻の雲居雁の悲喜劇は今に通じる中編小説のようである。なお、雲居雁が落葉宮の母からの手紙を奪い取る、源氏物語絵巻で有名な場面もこの巻の場面となっている。
2024年02月18日
コメント(2)
-
「源氏物語」若菜に見る人生のアイロニー
光源氏の栄華が「藤裏葉」の巻で絶頂に達した後、「若菜」で急展開となる。朱雀院が出家に際して後に残る皇女の行く末を心配して、なかばおしつけるような感じで光源氏に降嫁させる。女三宮である。ひたすら子供っぽく、知恵も伴っていないようなところがあり、それゆえ、院の心配はひとしおだったのであろう。故夕顔も「子めきてろうたし」と少女のような可愛らしさのある女性であったが、それは同時にコケティッシュな魅力になっていた。これに対して、女三宮は単に子供で、光源氏は当然に魅力も感じず、院への外聞をおもんばかって義務的に通うばかりとなる。ただ身分は皇女であるので当然に正妻となる。女三宮の降嫁は紫上にも衝撃を与える。あまりにも子供っぽい女三宮に光源氏の寵愛が移ることはないにしても、子供も持たず、確たる後ろだてのない紫上は寵愛だけが頼りである。そして年齢は40近くであり、今後は容色も衰えていくだろう。そうなったらいつまで寵愛が続くのだろうか、やがては「人笑いになるような」境遇になるのではないか。この頃から紫上は出家願望をもらすようになる。そんな精神的なストレスもあったのかもしれないが、急に胸の痛みを訴えて、一時は生命も危うい状況になる。光源氏は紫の上を二条院の屋敷に移して加持祈祷をさせたため、六条院は人のほとんどいない状況となり、そこに、柏木と女三宮の密通事件が起きる。この密通はやがて光源氏の知るところになり、女三宮は出家し、柏木は懊悩のはてに死ぬ。こうした顛末を女三宮からみたらどうであろうか。降嫁後に行われた光源氏40歳の賀は養女格の玉葛、紫上、秋好中宮、夕霧によってそれぞれ祝われ、女三宮は関係なかった。そして紫上の急病後は皆主だった人々は二条院に移っていった。この時、正妻とは形ばかりのものではないかという疎外感を、いくら子供っぽい女三宮でももったのではないか。そして密通発覚後は、光源氏は大仰には責めないものの、ねちねちと知っていることを匂わしていく。出家という形で逃げ出したくなったのも当然である。柏木の方の女三宮への執着の心理はいまいち今の感覚では分かりにくいのだが、当時の人は身分という概念に縛られており、身分の高い皇女との結婚を強く望むのも当時の貴族ではよくあることだったのだろう。それにしても密通というのは、宿命的な悲劇としか思えないし、その後の柏木の死の描写は両親は健在であっただけに哀切である。大きな物語の流れでいえば、光源氏の若い日の密通事件が、後年立場を変えて光源氏の身に起きるという皮肉、そしてそれによって、自分が密通を知っていながら知らないふりをしているように、父桐壷帝も密通を知っていたかもしれないということに思い及ぶ。自分が当事者となって、自分がその年齢となってはじめてわかるということも、人生には往々にしてあるものである。
2024年02月15日
コメント(2)
-
「源氏物語」紫の上と明石の上
平安時代の貴族社会では意外に離婚や再婚が頻繁に行われていたようである。そしてまた、一夫多妻も普通であったので、継母子関係というものもごくごく普通にあったのだろう。かの更級日記でも作者の母は継母で、その後、離別している。更級日記の作者と継母との関係は良好であったようなのだが、実際にはそうでない場合も多かったであろうし、落窪物語など継子いじめの物語も残っている。源氏物語でも、紫の上の父の正妻は「おおさがなもの」の悪役として物語に何度かでてくる。その一方で、源氏物語では、紫の上は明石の上の産んだ姫を大切に育てている。もちろん紫の上には明石の上に対する嫉妬はあったし、彼女の見事な筆跡をみたり、琴の上手の話を聞いたりしてすねる場面もある。けれども、もともと子供好きな性格で、姫をひきとってからは、姫のかわいらしさに、嫉妬もかなりおさまっていったという。妻が愛人の子供を引き取って愛育し、実母が子供のすぐ近くに住みながら我が子に会わないというのはどちらにも辛いはずの稀有なことであろう。昼ドラなら、それだけでも、継子苛めや子供をめぐっての争いなどのどろどろの話ができそうである。ただ、源氏物語の中で理想的な女性に描かれている紫の上と明石の上の間ではそんなこともなく、彼女らが初めて対面したのは、姫の入内準備のときである。二人はそれぞれに互いに対して光源氏の寵愛は当然だったという感想を持ち、後に姫が皇子出産のために里帰りしたときには、紫の上は乳児の世話を、明石の上はもっぱら湯の準備等を行う。光源氏が戯れに明石の上に赤ちゃんをとられてもよいのかというと、明石の上は、私はその方がよいと思っているので仲をさくようなことはいわないで下さいと返す。姫は実母が明石の上と知ってからは、ますます紫の上と睦まじくなる。愛情豊かな紫の上と、実母という確かさに裏打ちされているとはいえ一歩引く明石の上の賢さが、姫を中にして幸福な関係を築いているわけである。紫の上を桜に、姫を藤に喩える表現は,「若菜」巻にもでてくるが、明石の上は橘に喩えられており、紫の上の美しさにも気圧されないとしている。「あさきゆめみし」では百合となっているが、どちらにしても、外見の華やかさよりも内面の知性や品格がにじみ出ているような美ということだろう。
2024年02月14日
コメント(2)
-
玉鬘十帖
玉鬘から真木柱までの十巻を玉鬘十帖という。筑紫に下った夕顔の遺児の玉鬘が乳母とともに上京し、源氏の屋敷に引き取られた後、髭黒大将の北の方となるまでの顛末を描いたもので、後から執筆されたものという説もあるようである。本筋の方では女君たちは六条院の四季の屋敷や二条院に落ち着いて暮らしているので、さほどの変転はない時期である。ちょうどこの十帖が入ることで、明石姫が成長し、入内するまでがつながっていく。この玉鬘十帖は養女格として源氏の屋敷に入った玉鬘に、多くの男性が想いをよせ、文を寄越したりするのだが、それを光源氏が見て楽しむという難題婿のような物語となっている。まさか作者が違うということはないのだが、いままでに比べると、やや書き方の趣が違う。女君の美しさが詳細に描写されており、玉鬘については、山吹の花が露をふくんで光っているような美貌だとしている。この個所では紫の上の美貌についても、玉鬘との対で満開の桜の花が突然に現れたようだと表現されている。玉鬘の容姿は美そのものでは紫の上に一歩譲るが、そのかわりに明るい親しみやすさがあるというわけである。性格も母夕顔よりも「かどかどしさ」、つまり聡明さがあるとし、田舎育ちであるにもかかわらず、宮中に出仕し、内侍の職務もこなす。ただ、帝に気に入られそうになると、すでに髭黒の妻になっているということを考え、出仕を辞める。そして、訪れる前妻の息子達も可愛がり、訪問が許されない前妻の娘(真木柱)を残念がらせる。明るく聡明な田舎育ちの娘が都にでて幸福になる…今も昔も人々はこんな話が好きである。もっとも時代は平安時代、当時の幸福と今の幸福は中味が違い、玉鬘も当初は髭黒との縁は全く不本意だったのだが。源氏物語には対象的な女君がよくでてくるが、ここでも、もう一人、頭中将の姫と名乗り出た女君が出てくる。近江の君である。容姿はさほどの難はないが、ひたいが狭いという描写で、庶民的な田舎娘として滑稽に描かれている。平安貴族といっても、皆が寝殿造りの屋敷に住んでいたわけではない。貴族といっても中流以下は小さな家に住んでいることもあるし、作者も実際に近江の君のような女性にであったことがあるのかもしれない。玉鬘十帖でも、実直な髭黒や庶民娘近江の君、夫との不和のストレスからヒステリー発作を起こす髭黒の先妻、そしてねちねちと光源氏方への恨みを募らす先妻の母と登場人物がリアルに描かれている。
2024年02月10日
コメント(2)
-
源氏物語「須磨」&「明石」
源氏物語中で宇治十帖を除けば都以外が舞台になっているのは「須磨」、「明石」の二巻だけだ。作中には明石から見た淡路島の光景などもでてくるのだが、たぶん作者は須磨にも明石にも行ったことはない。古歌の情景などをもとに想像をもとに綴ったのだが、都とは趣のことなる海辺の情趣がそこはかとなく伝わってくる名文でさすがとしかいいようがない。一説によれば、紫式部が執筆をしたという石山寺と琵琶湖は近く、琵琶湖の情景を参考にしたともいうが、どうなのだろうか。須磨源氏という言葉があり、長編の源氏物語は「須磨」の巻あたりで脱落する人が多いという。たしかにここでは都人との別れや新しい生活の情景が描かれるほかは大きなドラマもなく、頭中将が訪れてくることくらいなのだが、こうした巻もよいと思う。次の「明石」の巻ではいよいよ明石の上が登場する。明石の上は「須磨」の巻で従者の良清が想いをかけている相手として紹介され、そこでは「勝れたるかたちならねど、懐かしうあてはかに、心ばせあるさまなど言いいたり」とされている。「明石」の巻では、実際に光源氏に逢うのだが、そこでは優雅で上品で六条御息所を思わせる女性として描かれている。田舎に流れてきた光源氏にとっては、都を思わせる女性だったのだろう。絶世の美女でなくとも、内面の知性や品性で、紫上にも気圧されないだけの魅力をもっていた女性である。源氏物語の読者層の多くは更級日記の作者のような中流貴族層だったし、作者自身もそうであった。田舎暮らしに辟易しながらも、上流の雲上人の生活に憧れもした。そんな少女たちにとってよき殿御にみそめられ、最後は中宮付きとして宮中に入ることになる明石の上のシンデレラ物語は大いに夢を書き立てたことだろう。明石の上こそが源氏物語の実質的なヒロインなのかもしれない。そしてまた実際、中流貴族の娘から最上層というのは全くないわけではなかった。藤原の兼家の妻で道隆や道長の母にあたる時姫は藤原傍流の出であったが、最高権力者の正妻となり、有力者となる子供を産んだ。自分ももしかしたら…と夢見ていた娘たちも多かったことだろう。
2024年02月05日
コメント(2)
-
源氏物語「賢木」&「花散里」
六条御息所は斎宮となった娘とともに野宮から伊勢に下る。この野宮にいる間に光源氏は六条御息所に会うのだが、彼女の直接の出番は意外に少ない。これも散逸した六条御息所との出会いを描いた巻があるのではないかといわれる所以だろう。ただその少ない出番でも、気品ある雰囲気は伝わってくる。なにしろ大臣の娘で天皇の弟の妻という、世が世なれば中宮になる可能性もあった女性である。それが光源氏との浮名が世に知られ、さらに生霊の噂まで出ているとなれば、都に身のおきどころもなく、伊勢にも下りたくなるだろう。やがて桐壷帝が死去し、右大臣方の皇子が帝位につくことで世の中の流れは変わる。左大臣は屋敷にこもりがちになり、光源氏を訪れる人もめっきりと減る。このあたりの世の中の変転は、実際に作者が見聞きした平安中期の権力抗争の様子が反映されていることだろう。桐壷帝の死後、藤壺の宮は史記の挿話を思い出して恐怖に震える。こうした中国の歴史の知識も教養ある女性の中ではかなり一般的になっていたことがうかがえる。弘徽殿の女御は気の強い政治的女性で、他の女君とは別カテゴリーなのだが、彼女の人物造形にも中国の史書が反映されているのだろうか。天皇が変わったのを機に弘徽殿の女御はいよいよ光源氏排除に動きだす。ここでちょうどよく起きるのが、光源氏と朧月夜の君との密会の露見なのだが、ここでも同じ右大臣の姫ながら冷徹な権力志向の弘徽殿の女御と恋愛に生きる朧月夜の君とが対照的に描かれる。その結果、光源氏は京を去り、須磨に向かうことになる。いよいよ都を離れる直前、わずかに交渉を続けてきた麗景殿女御の妹を訪ねるくだりが「花散里」の巻である。彼女との出会いは物語には描かれていないし、この巻もごくごく短く、しかも花散里の登場する箇所は数行にすぎない。そして巻名の由来となった歌も彼女自身ではなく姉の女御の歌となっている。人柄同様、物語の扱いも控えめなのだが、花散里はその後も登場し、六条院の屋敷の夏の院に住み、夕霧の母代わりをするなど重要な役割を果たしていく。ここでは花散里の容姿にはふれていないのだが、後に少年となった夕霧が花散里を初めて見る場面では、顔立ちがととのっていないなと思い、今まで美しい女性ばかりみてきて女性は皆美しいものと思っていたのだが、もともと優れていない容姿が盛りもすぎ、やせて髪も少なくなっているのが難点だなんて考える。源氏物語の登場人物は意外と美しい姫君ばかりというわけではない。花散里は容姿はいまいちなのだが、その後も何度も登場し、その控えめな賢さや家事の巧みさ、性格のよさなどの美点が次第に読み取れてくる。逆境の中でひさしぶりに訪ねていったのが花散里であったというあたりにも、彼女の変わらぬ暖かさが想像できる。
2024年02月04日
コメント(2)
-
源氏物語「花宴」&「葵」
源氏物語「花宴」では朧月夜君が登場する。紫の上があでやかで清純な昼の桜だとしたら、朧月夜君は妖艶な夜桜のイメージなのだが、この巻では朧月夜の容姿についての描写はない。夢のような花宴の夜に出あい、扇を交換して別れた女君ということで、その後の藤の宴のときにようやく右大臣の姫であるという素性が明らかになる。その後も朧月夜の君は光源氏の人生に関係していくのだが…。次の「葵」では、葵上の出産と死亡、そして紫の上との新枕が描かれる。有名な六条御息所の生霊の場面があるのだが、車争いに発する葵上と六条御息所、そして光源氏の三者三様の心理が生霊を作り出したような描写にもみえる。思うに紫式部は本当は生霊とかそうしたものは信じていなかったのではないか。光源氏は葵の上の声を聞いて六条御息所と思い、御息所は自分の衣服や髪に祈祷に使う護摩の匂いがついていると思う。いずれも主観である。ただこれも実際に生霊がとり殺したとも読むことができ、そうしてみると、怪奇小説の趣もある。それにしても、あらためて読むと葵上は隙がなく、とっつきにくいという描写ばかりで、死ぬ直前の光源氏を見送る場面以外ではあまり感情のよみとれる場面がない。むしろ光源氏になにかと気をつかう舅の左大臣や妻大宮の人の良いかいがいしさばかりが目立つ。葵上は兄の頭中将からみれば理想的な妻であり、容姿も端麗であり、また、親のない小さい女童をとりわけ可愛がっていたという描写もあるので性格も悪くなかったのだろう。ただ光源氏と結婚したときには光源氏が12歳で葵上は16歳、今でいえば高校生と小学生ほどの年齢差である。いったん「似げなくはずかし」と思い始めると、ぼたんのかけ違いのように、すれ違ったままになってしまう。それだけでなく、正妻という立場は光源氏の好き心を刺激せず、そのうちと思っていた節があったことと、葵上の側の感情表現の不器用さがあったことも大きい。なお「あさきゆみし」では葵上はやや子供っぽいわがままな女性になっているが、これは原作のイメージとは関係なく、あるいはこのくらいだったら光源氏と心を通わせることもできたのかもしれない。葵上の死後、紫の上(若紫)と新枕となるが、このとき、紫の上は15歳ほどになっており、結婚できない年齢ではない。若紫はかわいい幼女と出会い屋敷に引き取る巻であるが、この時期ではまだ、幼女を性愛の対象として見ているわけではなかった。
2024年02月03日
コメント(4)
-
末摘花と源内侍
若紫の巻の後には末摘花の巻、そして源内侍の登場する紅葉の賀の巻が続く。これらの巻では、若紫が光源氏の期待のとおりに聡明に育ち、藤壺宮は光源氏にそっくりの皇子を生むなどの本筋の変転もあるが、末摘花とか源内侍という個性的な人物も登場する。そしてまた、末摘花では零落した故宮の荒れ果てた屋敷、紅葉の賀では宮中の優雅な紅葉の御幸や舞楽というように場面も対照的である。末摘花は不器量な女性として容貌が詳細に描写されているが、驚くのは、光源氏が末摘花と空蝉を比較して「かの空蝉のうちとけたりし宵の側目はいと悪かりしかたちざまなれど、もてなしに隠されて口惜しうはあらざりきかし。(末摘花は空蝉に)おとるべきほどの人なりやは」と思っていることである。どっちもブ〇だが、空蝉はみのもてなしや心ばせで欠点をカバーしているという。以前は「わろきによれる」とだけ書かれた空蝉はそんなに不器量だったのだろうか。空蝉の方は一応天皇の後宮に入るようにと親は育て、夫の死後は先妻の息子が言い寄ったりもするので、いくらなんでもそんなに酷いわけがないと思うのだが…このあたりは光源氏の瞬間の心理をえがいているのか筆がすべったのか。ちなみに、末摘花と空蝉の容姿をみると、末摘花は背が高く痩せていて、象のような鼻とある。象のような鼻は人間にはいないので単に高い鼻というのなら、やせて背が高く鼻が高いのは現代ではさして難ではない。ただ赤い鼻というのはたしかに問題だ。空蝉は、眼がはれぼったく鼻筋も通っていないとあり、これは、今の基準でも、ごく一般的な不器量だろう。ただ、末摘花は不器量な上に、極端な引っ込み思案で気の利いた歌を詠むこともできない女性として描かれている。もっとも、困窮した生活では、きれいな用紙もないので、気の利いた歌のやり取りも期待できずに、零落した荒れ屋敷にひそんでいるしかなかったのかもしれない。これに対し次の巻に出てくる源内侍は出番は少ないがはるかに元気である。源内侍は数え年で57歳か58歳なので、今だってこのくらいの年で若作りはいるだろう。荒仕事をしない貴族は庶民に比べると若く見えただろうし、紫の上は43歳で亡くなるまで美しかったという描写もある。そう考えると源内侍も全くの老婆というほどではなかったかもしれない。だが年増は年増である。そうした年増が光源氏に思いをかけ、様々に誘惑?し、せまってくる。その一つがこんな歌である。君し来ばたなれの駒に刈り飼はんさかり過ぎたる下葉なりとも源内侍と光源氏がいるところに、頭中将が現れ、どたばたのうちに密会はおわるのだが、源内侍はちょいちょいとその後もでてくるようである。
2024年02月01日
コメント(2)
-
源氏物語若紫の巻を読んで
夕顔が忘れがたい女君として物語から去った後、光源氏は療養にでかけた北山できわだって可愛らしい10歳の少女に出あう。一緒に山寺に逗留している尼君にも似ているが、よくよくみると藤壺宮にもよく似ている。光源氏はその少女を手元におきたいと思うのだが、尼君は本気にしない。やがて尼君もなくなり、少女は父親に引き取られることになるが、そこでは継子として虐められるのは目に見えている。そんな状況で光源氏が少女を自分の屋敷である二条院に迎え入れるまでの顛末が若紫巻である。また、この巻では藤壺の懐妊(実は光源氏の子)という重要事態もおきており、藤壺に逢うことは、これからは完全に不可能になる。それだけに、藤壺によく似た少女を身近に置きたいという欲求は切なるものとなっている。源氏物語は高校の教科書に出てくるのだが、内容が内容だけに教科書向きの箇所はそう多くない。そのせいか、可愛い子供の出てくる若紫はたいていの教科書に載っているようなのだが、これも内容は10歳の少女に対する恋ともいえるものである。もっとも、少女若紫の方は全くの子供で、光源氏に対しても「お父様よりも綺麗」という印象しかない。雀の子を可愛がるなど、後年の子供好き世話好きという片鱗はあるのだが、それ以外は年齢よりも幼げで、才気あふれるイメージはまだない。二条院にひきとられた若紫は光源氏と親子のような、そうでないような不思議な関係になり、今後はどうなるか…ということで巻は終わる。この時代、貴族は人口のごくわずかだったというのだが、その貴族であっても、生活はかなり不安定だったようだ。若紫の母は按察使大納言なのだが、父を早くに失くしている。通ってくるようになった兵部卿宮も本妻に頭が上がらず、若紫の母もその心労が原因で早世する。だから若紫は父の庇護はあまり期待できず、頼みは祖母の尼だけという境遇だ。初めて物語にでてくるときも着古した着物を着ており、京の元按察使大納言の屋敷も荒れ果てている。次の末摘花の巻でも宮様の姫の末摘花が荒れた屋敷に古道具に囲まれた生活をしている様子が描写されており、この境遇は、光源氏の援助が途絶えていた後の蓬生の巻ではもっと悲惨になっている。平安の姫が優雅だったというのは恵まれた半面のイメージであり、今昔物語には宮様の姫がホームレス同然になる話がでてくる。あの清少納言にも晩年は零落したという説があるし、小野小町が乞食同然の姿で放浪したという伝説も真実味をもって受け止められていたのだろう。
2024年01月30日
コメント(0)
-
空蝉の巻、夕顔の巻を読んで
空蝉と夕顔の巻を読んだ。この頃、光源氏は17歳。まあ、源氏物語を教科書で読む高校生と同じ年代だ。この頃までに、光源氏に関係する女人は子供の頃からの憧れで永遠の女性である藤壺、正妻の葵上、手紙のやり取りをする朝顔の君、忍び歩きの相手六条御息所とすでに五人おり、これに空蝉、軒端荻、夕顔が加わる。そしてこの中で既に何人かの女性の性格が対照的にかき分けられている。小君も含めてドタバタの感のある空蝉の物語では、「わろきによれる」容姿だが慎み深く賢い空蝉と、美人だが騒々しく品のない軒端荻の対象。そして、夕顔の巻では上品で気づまりな六条御息所といとおしく可愛らしい夕顔との対象。夕顔には「ろうたし」という形容詞が使われているが、これは臈たけると同じ意味の上品で洗練されたというよりも、いとおしく可愛らしいの方の意味だろう。夕顔はどこがどうということもないのだが、小柄ではかなげな感じが心に沁みるというタイプとして描かれている。夕顔の花を所望した光源氏に扇に歌を書いて返した夕顔の君に娼婦性をみる見解もあるようだが、彼女の場合は、男性に対する依存心が強く、触れなば落ちんという風情があるように思う。そういうのを娼婦性というのであればそのとおりなのだが、打算的な女狐とは真逆で、心のままに、憧れる男性に依っていくというタイプなのだろう。扇の歌も素直に光源氏の美貌をたたえたもので、特段のひねりや技巧があるわけではない。心当てにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花光源氏は夕顔を廃屋となった屋敷に連れて行きながら、足が遠のいている六条御息所のことを思う。夢に女性が現れ、私が素晴らしいと思う女性のところには行かずに、こんな平凡な女性を寵愛するなんてと告げる。そして夕顔が息を引き取る時に同じ女が一瞬見える。これを六条御息所の生霊という見方もあるが、屋敷の怪ではないのだろうか。さらにいえば、光源氏の内心感じていた六条御息所に対するうしろめたさが夢になり、一瞬の錯覚になったように思う。こうしたものは、はっきりと生霊とするよりも、わけのわからない屋敷の怪とする方が、読者にとっての怖さが増す。夕顔は屋敷で急死し、遺体は惟光の機転で処理され、遺児の存在が示されたまま夕顔の物語は終わる。そして空蝉も夫とともに任地に下り、当面は小説の舞台から消えることになる。
2024年01月27日
コメント(2)
-
「輝く日の宮」(丸谷才一)を読んで
源氏物語が気になるせいもあって「輝く日の宮」(丸谷才一)を読んだ。作者の共同翻訳したジョイス「ユリシーズ」に似た章ごとに文体の変わる趣向もさることながら、こうした形式の小説もあるのかと改めて思う斬新なものとなっている。主人公は国文学研究者の女性。彼女の論考や学会等での議論、それも最初は芭蕉の東北行きの理由、次は源氏物語の失われた巻が論点になる。さらに冒頭では彼女が中学生の頃に書いた小説もどき、最後は失われた源氏物語の巻の現代訳?で終わる。これを横糸とすれば、縦糸として主人公の人生や恋愛の変転がある。主人公の教授への昇進、父親の死だけでなく、彼女は憂い顔の美人でもあり、同僚の学者との恋愛、次いで独身主義者を自認するビジネスマンとの恋愛模様もからむ。作者が最も力を入れた点、そして読者の興味関心はやはり、表題にもなっている源氏物語の失われた巻「輝く日の宮」だろう。源氏物語には失われたとされる巻があり、一つは「輝く日の宮」、光源氏の死を描いた「雲隠れ」そしてもう一つは宇治十帖の続編だという。「雲隠れ」はあまりにも悲しく出家する人が続出したので紛失させたという説もあるようだが、これはおそらく最初から書かれなかったのだろう。宇治十帖はたしかに続編がありそうにも思えるが、じゃあ、どういう内容かというと想像がつかない。巣守の君なるヒロインを主人公にした続編があるらしいという話もあるが、巣守というセンスもなんだし、紫式部の作ではないだろう。未完のようだが、宇治十帖はあれで完結しているとしか思えない。これに対して「輝く日の宮」の巻は藤壺の君との最初の逢瀬、六条御息所や朝顔君との出会いが描かれており、これは物語必須の場面であるから、もともと巻があったはずだという。小説中では、物語の謎を残すために藤原道長の判断であえて原稿から除かれたと推測する。世に出る前に道長のところで削られたのなら最初からなかったと同様ではないかとも思うのだが、最初からかかれなかったという見方もできるのではないかと思う。すべての女君について最初の出会いが描かれているわけではないし、最初の出会いが描かれている場合には夕顔、若紫など非常にその出会いが印象的なものになっている。何人かの女君、それも極めて高貴な女君との出会いについては読者の想像にまかせたとしても不思議ではない。源氏物語の一読者として桐壷、帚木…とよみすすんだとして、藤壺や六条御息所との最初の逢瀬の部分などが欠落していることに不満をもつだろうか。まあ、そのあたりはおしてしるべしという感じで、物語世界を楽しむのではないのだろうか。それはともかくとして、「輝く日の宮」は、論考中心のこんな小説もあるかという意味では面白く、源氏物語が好きな人には一読をおすすめしたい。
2024年01月18日
コメント(11)
全303件 (303件中 1-50件目)