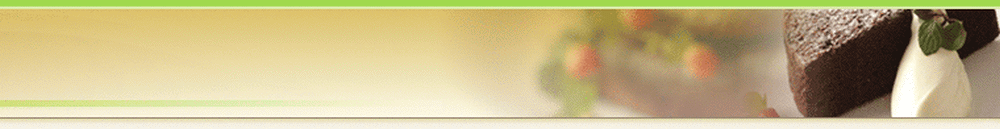PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
テーマ: 最近、読んだ本を教えて!(24304)
カテゴリ: 本
「狂った裁判官」(井上薫著 幻冬舎新書)を読みました。新書は文字が大きくかさばらないので、電車の中で読むのにちょうどよいです。
日本では刑事裁判では99パーセントが有罪になりますが、どうしてか?著者によれば、まず、検察が有罪になりそうな事件しか起訴しない。無罪になると、検察官の人事評価が減点になるのだそうです。そして、裁判官はというと、自分が無罪にして控訴されて上の裁判所で有罪になると、やはり評価が減点になるようです。裁判官も左遷されたくないし、裁判官の任期は10年で更新されないと退官することになるので、悪い評価はもらいたくない心理が働いてしまうということです。検察は上下一体だけれど、裁判官はひとりで判断しなければならないプレッシャーがある。裁判の前に判決文を書いている人もいるとか。
民事は和解が多いが、それは、裁判で勝っても相手に支払能力がなくてはもらえないので和解してもらえるだけもらうほうがよい、などの理由のほかに、判決起案をすべて書くとなるとかかえている件数をさばけないから、という理由もあるそうです。新しく受けた件数より解決した件数が少ないと「赤字」といって、能力がないように思われ、ネット上にも一覧表がさらされます。
もともと裁判官になるタイプは優等生で変わったことをしない行動パターンの人が多く、判例に頼りすぎるとも著者は批判しています。
人を裁くときには、本当にこれでよいのか、何度も書類を見直し、常に頭から離れない状況になるが、自分から志願したのではない一般人の裁判員にそれができるのだろうか?また、世間が「死刑に!」と騒いでいても、法に照らし合わせて無期懲役がふさわしければ無期懲役の判決を出すのが裁判官なのに、法律を知らない人が「世間の常識」で判断するようになっては、法ができる以前に戻ってしまう。8割がたの人がやりたくないという制度を作ることも民主的ではないし、裁判員制度は始まる前に廃止するべきである。
著者は判決理由にはよけいなことは書くべきではないとして、例に、小泉首相の靖国参拝によって精神的苦痛を受けたとして10万円の慰謝料を要求した裁判をあげ、原告に損傷はなく、損害賠償は認められないのだからそう書けば済むのであり、「違憲であるが」などはいらない、と主張しています。けれども、原告は10万円が欲しくて訴訟を起こしたのでなく、靖国参拝は違憲ではないかと訴えたかったのであり、日本ではこういう形でしか訴えることができないからそうしたのです。コスタリカのように、アメリカのイラク侵攻を支持するのは違憲だと一学生が訴えて裁判で認められ、有志連合のリストからコスタリカの名を削除させた、などということができる制度の国であれば、著者がいうことは筋が通っていると思いますが。
裁判所には国会で作った法や行政の処分が違憲ではないか、審査する権限もあるそうですが、それなら、安倍政権の教育基本法など審査するべきではないでしょうか。
日本では刑事裁判では99パーセントが有罪になりますが、どうしてか?著者によれば、まず、検察が有罪になりそうな事件しか起訴しない。無罪になると、検察官の人事評価が減点になるのだそうです。そして、裁判官はというと、自分が無罪にして控訴されて上の裁判所で有罪になると、やはり評価が減点になるようです。裁判官も左遷されたくないし、裁判官の任期は10年で更新されないと退官することになるので、悪い評価はもらいたくない心理が働いてしまうということです。検察は上下一体だけれど、裁判官はひとりで判断しなければならないプレッシャーがある。裁判の前に判決文を書いている人もいるとか。
民事は和解が多いが、それは、裁判で勝っても相手に支払能力がなくてはもらえないので和解してもらえるだけもらうほうがよい、などの理由のほかに、判決起案をすべて書くとなるとかかえている件数をさばけないから、という理由もあるそうです。新しく受けた件数より解決した件数が少ないと「赤字」といって、能力がないように思われ、ネット上にも一覧表がさらされます。
もともと裁判官になるタイプは優等生で変わったことをしない行動パターンの人が多く、判例に頼りすぎるとも著者は批判しています。
人を裁くときには、本当にこれでよいのか、何度も書類を見直し、常に頭から離れない状況になるが、自分から志願したのではない一般人の裁判員にそれができるのだろうか?また、世間が「死刑に!」と騒いでいても、法に照らし合わせて無期懲役がふさわしければ無期懲役の判決を出すのが裁判官なのに、法律を知らない人が「世間の常識」で判断するようになっては、法ができる以前に戻ってしまう。8割がたの人がやりたくないという制度を作ることも民主的ではないし、裁判員制度は始まる前に廃止するべきである。
著者は判決理由にはよけいなことは書くべきではないとして、例に、小泉首相の靖国参拝によって精神的苦痛を受けたとして10万円の慰謝料を要求した裁判をあげ、原告に損傷はなく、損害賠償は認められないのだからそう書けば済むのであり、「違憲であるが」などはいらない、と主張しています。けれども、原告は10万円が欲しくて訴訟を起こしたのでなく、靖国参拝は違憲ではないかと訴えたかったのであり、日本ではこういう形でしか訴えることができないからそうしたのです。コスタリカのように、アメリカのイラク侵攻を支持するのは違憲だと一学生が訴えて裁判で認められ、有志連合のリストからコスタリカの名を削除させた、などということができる制度の国であれば、著者がいうことは筋が通っていると思いますが。
裁判所には国会で作った法や行政の処分が違憲ではないか、審査する権限もあるそうですが、それなら、安倍政権の教育基本法など審査するべきではないでしょうか。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本] カテゴリの最新記事
-
小さなパン屋さんの思い出 May 7, 2021 コメント(5)
-
青山透子さん「遺物は真相を語る」 July 12, 2019 コメント(2)
-
「原爆の秘密 国内篇 天皇は知ってい… September 16, 2008 コメント(20)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.