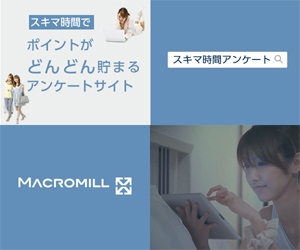カテゴリ: 霊魂論
ゲーテの自然科学論序説並びに精神科学(人智学)の基礎(GA1)
特注-記;神智学及び人智学における人間本質の階層
我々の通常一般世界での文化や宗教(*公教)の多くは、人間の構成を肉体を持つ身体と霊魂の二構成として捉え、その因子までを肉体と霊魂の二元論で考えます。対して、秘教や神秘主義的思想の多くは、「霊」と「魂」を分けて、霊・魂・体の三元論で考えます。ギリシャ哲学なかでも新プラトン主義やインド哲学などのいくつかの伝統では、更にもっと多くの階層的構造を基盤とします。とりわけ、それらを統合した近代の神智学、人智学では七階層で捉える傾向多くは好みます。ここではブラヴァツキー夫人に始まる神智学とルドルフ・シュタイナーの人智学における、人間本質の階層論について紹介します。プラトン、アリストテレスの階層論では、上位と下位は形相性の有・無で正反対の性質を持ちすが、究極的な神秘体験は、実体験からすれば「形」を感じないことが一般的です。そのような実体験を持っていた新プラトン主義のプロティノスは、プラトン哲学を継承しながらも、最上位の存在「一者」を「無相(無形相)」であるとしました。然し乍ら、「一者」が下位の秩序の根拠となり、固定する性質を持つ点は変わりません。プラトン以降のアカデメイアでは、様々な階層論がありましたが、クセノクラテスは「イデア」を「ヌース(霊的知性)」として捉えていました。それを受けつつ、プロティノスは、「一者/ヌース/魂」という階層を考え、それを定着させました。プロティノスは、「一者」から生み出された「ヌース」は、最初は「形相」を欠いた暗い素材的存在でしたが、「形相」を超えた「一者」を振り返って認識することで、光として「形相」を受け取り、形付けられると考えました。プロティノスの最上位の「一者」が「無相」であるなら、その点では、最下位の純粋な「質料」と同じです。つまり、この上下の極が同じで、この点で階層が対称となっています。ですが、最上位が「形相」の創造者、根拠であるのに対して、最下位は「形相」を受容者である点で、両者は異なります。新プラトン主義のイアンブリコスは、「ヌース」を、「存在/生命/知性」という三段階に階層化しました。これは、プロティノスが考えた、「認識対象/認識作用/認識主体(内容)」を捉えなおしたものです。といっても、ここには階層の上下対称性の考え方が潜在しています。新プラトン主義の大成者であるプロクロスは、それを理論化して、階層の上下対称性を、極だけではなく全体に広げました。プロクロスは、魂、限定すれば人間の魂、中でもプラトン言う魂の気概的部分を階層の中心にします。そして、アリストテレスの「動物/植物/無生物」の本質を、「知性/生命/存在」として捉えます。これは、イアンブリコスの「ヌース」の三階層の本質を、下位に折り返した形になっています。プロクロスの上下対象の階層論は、近代の神秘主義者であるシュタイナーの階層論にも見られます。プラトン、アリストテレスの階層論は、概念的(理念的)な知性を重視するものであるため、イメージや想像力、象徴をあまり評価しません。ですが、多くの神秘主義思想、特に魔術的な思想においては象徴的なイメージが重視されますし、啓示的な宗教でも、それらはヴィジョン(幻視)として与えられるものなので重視します。そのため、神秘プラトン主義でも、魔術に傾倒したポリピュリオスは、予言に関わる神的な想像力を重視しました。また、啓示宗教であるイスラム教の神秘主義哲学者も、それを重要しました。ペルシャ人のスフラワルディーは、イデア界に相当する恒星天と、動・植物魂に当たる惑星天の間に、神的・象徴的イメージの世界である「中間世界」を置きます。つまり、この象徴的なイメージ、創造的想像力の「中間世界」は、通常のイメージや想像力とは別のものなのです。そして、この位置は、「霊的知性(直観的知性)」の世界の下ではありますが、日常的な概念的思考やイメージの世界の上なのです。象徴的なイメージ、創造的想像力の段階を、上下対象の階層論に当てはめると、概念的意識の段階を中心にして、その下位のイメージの段階を、上に折り返した場所として考えることができます。これにぴったりと当てはまるのは、シュタイナーの「アストラル体」を折り返した「生命霊」でしょう。シュタイナーの階層論では、この段階は「霊視的」認識とも表現され、さらにその上は「霊聴的」、その上は「合一的」認識とされます。象徴やイメージ(心像)は視覚に限定されませんが、「中間世界」に対応するのは「霊視的」段階でしょう。視覚的なものより聴覚的なものを上にするのは、密教も同じです。密教では、聴覚的なマントラも視覚的な尊格の姿形(イメージ)も象徴性を持ちますが、マントラをより根源的なものとします。これは、マントラの方が視覚的イメージより形相性を脱しているからでしょう。例えば、密教の代表的な行法の「五現等覚」では、「虚空」から「光源(月輪)」→「放射光(日輪)」→「象徴的な音(種字)」→「象徴的な意味(三摩耶)」→「象徴的な視覚イメージ(仏身)」の順に観想して尊格を現します。つまり、形象的視覚よりも象徴的意味の直観、さらに聴覚、光の感覚をより根源的と考えます。もちろん、霊的感覚は、通常の日常的対象の感覚とは違うものなので、ここに書いたのは共感覚的な表現です。神智学におけるブラヴァツキー夫人はバラモン系のサーンキヤ哲学や、ヒンドゥー哲学の3シャリーヤ(三身)説、5コーシャ(五鞘)説などの階層論の影響を受けています。一方、シュタイナーは、神智学と共に、新プラトン主義のプロクロスの階層論の影響を受け、人間の本質を1904年の「神智学」、1906年の「神智学の門前にて」、1907年の「薔薇十字会の神智学」、1910年の「神秘学概論」などでまとめて述べています。
シュタイナーは、下記のように人間の9本質を考えます。
1 霊人(アートマ) :インツゥイツィオーン認識(合一的直観)
2 生命霊(ブッディ) :インスピラチオーン認識(霊聴的霊感)
3 霊我(マナス) :イマギナチオーン認識(霊視的想像力)
4 意識魂 :霊我と一体になった魂
6 感覚魂 :アストラル体と一体になった魂
7 アストラル体(魂体):夢の意識(動物的意識)、感覚・感情
8 エーテル体(生命体):睡眠意識(植物的意識)、形成力
9 肉体(物質体) :昏睡意識(鉱物的意識)
三分説では、1から3が「霊」、4から6が「魂」、7から9が「体」です。そして、4と3、6と7が一体なので、実質的には7本質となります。5が「自我」だと言う場合、この「自我」は日常的な「自我」ですが、目覚めた「自我」は、5と4が一体の「自我」と捉えられます。また、5の「自我」を中心にして、上下が対象の構造になっています。つまり、「自我」は7から9を感覚によって知覚しそれを言語化し、1から3を直観によって知覚しそれを言語化します。そして、7、8、9、8は、それぞれに、3、2、1が変化したものであるとも言うことができます。「自我」を3「霊我」で満たすと、それが7「アストラル体」を照らし、それによって「自我」が「アストラル体」を支配することで、そこに「霊我」が現れるのです。つまり、「アストラル体」を意識化して働きかけることで、その部分が「霊我」になるのです。こうして、「アストラル体」は変化していない部分と、変化した部分(霊我)から構成されるものになります。2と8、1と9の関係も同様です。この上下対称性は、ブラヴァツキー夫人の神智学にはありません。ただ先に書いたように、プロクロスときわめて類似しています。然し乍ら、シュタイナーがプロクロスについて語っているのを知りませんし、プロクロスには下位のものが上位のものに変化するという関係はないと思われます。「魂」は「体」を通した「体験(印象)」を「表象」に作り変え、それを「霊」に受け渡すと、「霊」はそれを「能力」に変換して成長します。また、シュタイナーは、「人間は思考存在であって、思考から出発するときにのみ、認識の小道を見つけることができる」と言い、「悟性魂」が行う「思考」を重視します。ですが、単なる「抽象的思考」は超感覚的認識の息の根を止めると言います。「生きた思考」が、超感覚的認識の土台を築くのです。超感覚的認識というのは、「魂」、「霊」の諸感覚で、それぞれ、魂的、霊的存在を直接、知覚します。思考を「生きた」ものにするには、外界に対して偏見を排して帰依する態度で、自分自身を空の容器にして、事物や出来事が自分に語りかけてくるように、外部のものに思考内容を作り出させることが必要です。シュタイナーは、霊界の法則が思考存在としての私自身の法則と一致している時、はじめて私は霊界の法則に従うことができると言います。そのような「魂」の中の不死なる部分、真・善を担うのが「意識魂」です。そして、「私」として生きる霊は、「自我」として現れるから「霊我」と呼ばれます。また、独立した霊的人間存在が「霊人」で、「霊人」に働きかける霊的生命力、エーテル霊が「生命霊」です。ちなみに、動物の「自我」はアストラル界に1つの種類の動物の1つの群魂という形で存在します。同様に、植物の「自我」は低次の神界に、鉱物の「自我」は高次の神界に存在します。シュタイナーの歴史観によれば、「太陽ロゴス」である「キリスト」が、ゴルゴダの秘跡で「地球霊」になって以降、「意識魂」を育てる時代になりました。シュタイナーは、ブラヴァツキー夫人と違い、アフラ・マズダをこの「太陽ロゴス」と同じものと考えます。シュタイナーはマズダ教(ゾロアスター教)に従い、神智学はより古いミトラ教に従っている点が、二人に大きな相違を生んでいます。シュタイナーによれば、睡眠時、「自我」と「アストラル体」は、「エーテル体」と「肉体」から離れます。また、夢を見る時には、「アストラル体」が、夢無状態より、より「エーテル体」と結びつきます。睡眠時の「アストラル体」は、宇宙的なアストラル界から法則を受け取り、それをエーテル体の建設に使います。死後の人間は、まず、「肉体」を脱ぎ、次に「エーテル体」を脱ぎ、最後に「アストラル体」を脱ぎ、それぞれの「死に体(態)」はやがて消滅します。アストラル体を脱ぎ捨てた後は、霊界を認識してその世界を体験しますが、また、地上世界にも働きかけて、それを変化させます。その後、やがて、霊界から流れてくる諸力を受けて、「新しく」アストラル体を形成し、再生します。
※エーテル体(エーテルたい、英: etheric body)は、神智学の『シークレット・ドクトリン』では、「魂の体、創造主の息」であり、ソフィア・アカモートが最初に顕在化した形態、7つの粗大順の物質(4つは顕在化し3つは未顕在)のうち最も粗大で塑性の物質であり物質の骨格であるとしている。アストラル光とも。初期の霊的世界において蛇として象徴されたものであり、ギリシア語の「ロゴス」に相当し、厳密にはアイテールとエーテルは異なるが、物質が存在する前は、現在のアーカーシャやアイテールと同様の「父であり母」であったと説明している。また、活力体、生気体 (vital body) とも呼ばれる。人智学で知られるルドルフ・シュタイナーは、生命体 (Lebensleib)、生命力体 (Lebenskraftleib)、形成力体 (Bildekr?fteleib) とも呼称しました。現代物理学いうところの、エーテルという言葉は19世紀の自然科学で提起された光を伝達する仮想上の媒質の名称として記憶されており、現在では不要な概念となっています。一方、シュタイナーは、エーテル体でいうところのエーテルは物理学とは関係のない別の意味の言葉として用いられていることを強調していることには注意が肝要です。。 (挿入参考文了)
参考画:霊人(Atman)

人気ブログランキングへ
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[霊魂論] カテゴリの最新記事
-
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタ… 2024年06月18日
-
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタ… 2024年06月17日
-
ルドルフ・ジョセフ・ローレンツ・シュタ… 2024年06月16日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
サイド自由欄
キーワードサーチ
▼キーワード検索
フリーページ
© Rakuten Group, Inc.