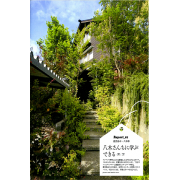PR
X
Free Space
設定されていません。
Calendar
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12
2023.11
2023.10
2023.09
2023.12
2023.11
2023.10
2023.09
Comments
御用邸のある町・三…
New!
jinsan0716さん
渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん
十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん
ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん
鹿児島のマンション… かごすまさん
Homeward Ultra-7さん
何を食べようかなぁ… hiro_0503さん
おひさまニコニコ ^… *Liko*さん
渡り鳥が結ぶ友和の… gusinさん
十人十色の情文スタ… 情報文化学科さん
ポンコツ山のタヌキ… やまもも2968さん
鹿児島のマンション… かごすまさん
Homeward Ultra-7さん
何を食べようかなぁ… hiro_0503さん
おひさまニコニコ ^… *Liko*さん
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 廃棄物・リサイクル
前回の記事に続いて、震災がれきの問題を論じます。まず、自民党の中で、震災がれきについて、もっともまともな意見を表明されている河野太郎氏のブログを紹介します。
続 震災がれき
2012年03月23日 20:43|自民党役職停止中|震災がれき
宮古市に震災がれきの視察に伺う。
震災がれきの二次仮置き場では、従事している約200人のうち地元の雇用は約170人。罹災証明書を持っているのは約20%。
主な業務は重機のオペレータと選別工だが、重機のオペレータは資格も必要なので、もともと建設業界などにいた人がほとんど。
がれきを選別する業務は、建設業界などを経験したことがない人が多く、ほとんどが一年契約。
がれきの選別は、コンベヤに載ってくるがれきを毎日八時間、選別する。なかなか雇用しても続かないそうだ。
広域処理するがれきも、選別までは地元で行うので、ここまでの雇用には広域処理も地元処理も影響はない。
理論的にはというのは、がれきは時間が経つと劣化するので、そうはならないからだ。
可燃物は、水分や塩分を含むようになったり、腐敗、発酵が進むと焼却には適さなくなり、コストはかかるが重油を足して燃やすか、さらにひどければ埋めるしかなくなる。しかし、処理をしていないヘドロのようになったがれきを埋めれば汚染のおそれがあるし、処理場の容量は限られているので、そう簡単に埋めるわけにはいかない。
再利用できる角材なども二、三年以上経過するとリサイクルには適さなくなる。
さらに、発酵熱による自然発火が昨年、数週間も続き、また、害虫の発生や悪臭もある。
宮古をはじめ今回の被災地は、山が海に迫っているところが多い。がれきの仮置き場になっているところは貴重な場所だ。宮古では、港湾施設と運動公園、野球場ががれきの仮置き場になっている。
処理が終わらなければ、こうした場所を利用することができない。
がれきは仮置き場に集められ、もう街中にはないのだから、がれきが復興を妨げているということはないなどと、したり顔して言う人はぜひ、被災地で復興にあたっている行政マンと直接、話をすることをお勧めする。
だから、地元で十年でも二十年でも時間をかけて処理すればいい、地元処理ならば雇用が増えるというのは、机上の空論だ。
放射能はもとより、粉塵、アスベスト、有毒ガス、水質汚濁などの検査は地元できちんと行われているが、規制値を大きく下回っている。
震災がれきを受け入れるとアスベストをはじめ有害物質がついてくると言う人がいるが、がれきは手で選別までしているので、言われなくとも現場ではきちんと調査して、安全を確認をしている、と現場の管理者の語気が強くなった。
ちなみに秋田県が昨日、県議会で報告した受け入れのための試験焼却のデータでは、宮古市のがれきの放射性物質の濃度は、キロあたり6ベクレル。
広域処理に加わるかどうかは、自治体に選択権がある。自分で処理できるなら、自分で処理すればよい。自分ではとても処理しきれないという時には、県にがれき処理を委託すれば、県が広域処理を行う。
たとえば岩手県では、大船渡などは地元の太平洋セメントの炉で燃やせるので、広域処理の必要がない。
陸前高田は、水産系の廃棄物を燃やすために仮設焼却炉の建設を当初考えたが、建設しているよりも大船渡の太平洋セメントの炉で燃やす方がはやいので、2011年6月から太平洋セメントで燃やしている。
岩泉町は、県にがれきの広域処理を委託し、宮古市、岩泉町、田野畑村などで一緒に処理している。
がれきの処理については、被災地の希望を聞いて支援が必要ならば支援するべきだ。地元で処理すれば雇用が生まれるなどと、よそで勝手に言ってみても、地元には迷惑だ。
がれきを広域処理するか地元処理にするか、被災地抜きに東京で議論しても意味はない。
続 震災がれき の引用は以上です。
現在の問題は、処理場が足りないという問題よりも、そもそも選別が追いつかないという問題のように思われます。選別の態勢を整えること、角材のリサイクル先を探すことなどのところを支援しないといけないのではないでしょうか。
河野氏は、その前の2012年03月14日のブログの 震災がれき Q&A その3 において、
Q 被災地に設置される焼却炉の能力はどのぐらいですか。
A 宮城県の震災がれきは、宮城県内の被災地を、
気仙沼ブロック
石巻ブロック
宮城東部ブロック
亘理名取ブロック
仙台市
に五分割し、まず、ブロック内で処理する、それができない分は県内処理、そして県内で処理できない分を県外にお願いするということになっています。
宮城県が受託した震災がれきの量は、量が確定していない気仙沼ブロックを除いて932万トン。
ブロック内処理量は471万トン、県内処理は117万トン、そして、県外処理量344万トン。
ブロック内処理をするために、焼却炉が設置されます。
石巻ブロックは5基、1500トン/日。
亘理名取ブロックは
名取に2基、190トン/日
岩沼に3基、195トン/日
亘理に5基、525トン/日
山元に2基、200トン/日
宮城東部ブロックは仙台市に場所を借りて、一ヵ所設置予定。
気仙沼ブロックは気仙沼市に二ヵ所、南三陸町に一ヵ所設置予定。
仙台市は、宮城東部ブロック用以外に、仙台市用に三ヵ所480トン/日。
この新設される焼却炉の処理能力は、相当に大きなものです。
たとえば私の地元と比べてみると、
人口 焼却処理能力
茅ヶ崎市 23万6千人 360トン/日
平塚市 26万人 294トン/日
これだけの焼却炉を被災地に新設して、それでも足りないものを県外処理しようということです。
と、宮城県では地元で相当に大きな処理能力を持つ焼却炉も新設し、各ブロック、そして県内でできる限りの処理をして、それでも足りない344万トンを県外処理にお願いするのだと書いています。
この河野氏のブログの記事(3月14日)の後、3月18日に細野環境・原発担当相が村井宮城県知事と会談して、「海岸防災林の盛り土に…震災がれき再利用で合意」したことが明らかにされています。
海岸防災林の盛り土に…震災がれき再利用で合意
細野環境相は18日、宮城県庁で村井嘉浩知事と会談し、津波から住民を守る海岸防災林を同県の太平洋沿岸部に整備するため、東日本大震災で発生した同県内のがれきを盛り土として埋め立て、再利用することで合意した。
震災のがれき処理に関し、政府が被災地での具体的な再利用策をまとめたのは初めて。
政府の計画では、仙台市から南側の仙台平野沿岸部の約50~60キロに防災林を整備する。その際、防災林を植えるための数メートルの高台をがれきを埋め立てて建設する。利用するがれきは、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の汚染の問題がないかどうか、環境省が安全性を確認する。事業は国直轄で行い、6月までに着手する。
(2012年3月19日 読売新聞)
遅きに失したとはいえ、政府も当然の策を検討せざるを得なくなったということがいえます。しかし、ということは、これだけでも県内で処理できるがれきの量がそれまで計算していた量と比べて相当変わってくる、ということがいえます。
さらに、「仙台市から南側の仙台平野沿岸部の約50~60キロ」だけではなく、宮脇昭先生が提唱するように、東北の太平洋沿岸約300キロにわたって、幅50~100メートル以上に防災林を築くとすれば、がれきは足りないくらいではないかと思われます。
河野氏の議論は、そのことについてはまったく触れられていません。そこからいきなり「県外処理=日本全国での広域処理」になっています。南相馬市の市長の考える復興計画などもあるわけですから、なぜ、まず現地、そして福島も含めた隣県、近県からその処理の可能性を探っていかないのか、いきなり九州・沖縄まで含めた日本全国にお願いするのか、その一番重要な点がまったく触れられていません。
「がれきの処理については、被災地の希望を聞いて支援が必要ならば支援するべきだ。」はわかりますが、地元で防災林という非常に有効な活用の仕方があるわけですから、はっきりいってやはりおかしいといわざるをえないのです。
続 震災がれき
2012年03月23日 20:43|自民党役職停止中|震災がれき
宮古市に震災がれきの視察に伺う。
震災がれきの二次仮置き場では、従事している約200人のうち地元の雇用は約170人。罹災証明書を持っているのは約20%。
主な業務は重機のオペレータと選別工だが、重機のオペレータは資格も必要なので、もともと建設業界などにいた人がほとんど。
がれきを選別する業務は、建設業界などを経験したことがない人が多く、ほとんどが一年契約。
がれきの選別は、コンベヤに載ってくるがれきを毎日八時間、選別する。なかなか雇用しても続かないそうだ。
広域処理するがれきも、選別までは地元で行うので、ここまでの雇用には広域処理も地元処理も影響はない。
理論的にはというのは、がれきは時間が経つと劣化するので、そうはならないからだ。
可燃物は、水分や塩分を含むようになったり、腐敗、発酵が進むと焼却には適さなくなり、コストはかかるが重油を足して燃やすか、さらにひどければ埋めるしかなくなる。しかし、処理をしていないヘドロのようになったがれきを埋めれば汚染のおそれがあるし、処理場の容量は限られているので、そう簡単に埋めるわけにはいかない。
再利用できる角材なども二、三年以上経過するとリサイクルには適さなくなる。
さらに、発酵熱による自然発火が昨年、数週間も続き、また、害虫の発生や悪臭もある。
宮古をはじめ今回の被災地は、山が海に迫っているところが多い。がれきの仮置き場になっているところは貴重な場所だ。宮古では、港湾施設と運動公園、野球場ががれきの仮置き場になっている。
処理が終わらなければ、こうした場所を利用することができない。
がれきは仮置き場に集められ、もう街中にはないのだから、がれきが復興を妨げているということはないなどと、したり顔して言う人はぜひ、被災地で復興にあたっている行政マンと直接、話をすることをお勧めする。
だから、地元で十年でも二十年でも時間をかけて処理すればいい、地元処理ならば雇用が増えるというのは、机上の空論だ。
放射能はもとより、粉塵、アスベスト、有毒ガス、水質汚濁などの検査は地元できちんと行われているが、規制値を大きく下回っている。
震災がれきを受け入れるとアスベストをはじめ有害物質がついてくると言う人がいるが、がれきは手で選別までしているので、言われなくとも現場ではきちんと調査して、安全を確認をしている、と現場の管理者の語気が強くなった。
ちなみに秋田県が昨日、県議会で報告した受け入れのための試験焼却のデータでは、宮古市のがれきの放射性物質の濃度は、キロあたり6ベクレル。
広域処理に加わるかどうかは、自治体に選択権がある。自分で処理できるなら、自分で処理すればよい。自分ではとても処理しきれないという時には、県にがれき処理を委託すれば、県が広域処理を行う。
たとえば岩手県では、大船渡などは地元の太平洋セメントの炉で燃やせるので、広域処理の必要がない。
陸前高田は、水産系の廃棄物を燃やすために仮設焼却炉の建設を当初考えたが、建設しているよりも大船渡の太平洋セメントの炉で燃やす方がはやいので、2011年6月から太平洋セメントで燃やしている。
岩泉町は、県にがれきの広域処理を委託し、宮古市、岩泉町、田野畑村などで一緒に処理している。
がれきの処理については、被災地の希望を聞いて支援が必要ならば支援するべきだ。地元で処理すれば雇用が生まれるなどと、よそで勝手に言ってみても、地元には迷惑だ。
がれきを広域処理するか地元処理にするか、被災地抜きに東京で議論しても意味はない。
続 震災がれき の引用は以上です。
現在の問題は、処理場が足りないという問題よりも、そもそも選別が追いつかないという問題のように思われます。選別の態勢を整えること、角材のリサイクル先を探すことなどのところを支援しないといけないのではないでしょうか。
河野氏は、その前の2012年03月14日のブログの 震災がれき Q&A その3 において、
Q 被災地に設置される焼却炉の能力はどのぐらいですか。
A 宮城県の震災がれきは、宮城県内の被災地を、
気仙沼ブロック
石巻ブロック
宮城東部ブロック
亘理名取ブロック
仙台市
に五分割し、まず、ブロック内で処理する、それができない分は県内処理、そして県内で処理できない分を県外にお願いするということになっています。
宮城県が受託した震災がれきの量は、量が確定していない気仙沼ブロックを除いて932万トン。
ブロック内処理量は471万トン、県内処理は117万トン、そして、県外処理量344万トン。
ブロック内処理をするために、焼却炉が設置されます。
石巻ブロックは5基、1500トン/日。
亘理名取ブロックは
名取に2基、190トン/日
岩沼に3基、195トン/日
亘理に5基、525トン/日
山元に2基、200トン/日
宮城東部ブロックは仙台市に場所を借りて、一ヵ所設置予定。
気仙沼ブロックは気仙沼市に二ヵ所、南三陸町に一ヵ所設置予定。
仙台市は、宮城東部ブロック用以外に、仙台市用に三ヵ所480トン/日。
この新設される焼却炉の処理能力は、相当に大きなものです。
たとえば私の地元と比べてみると、
人口 焼却処理能力
茅ヶ崎市 23万6千人 360トン/日
平塚市 26万人 294トン/日
これだけの焼却炉を被災地に新設して、それでも足りないものを県外処理しようということです。
と、宮城県では地元で相当に大きな処理能力を持つ焼却炉も新設し、各ブロック、そして県内でできる限りの処理をして、それでも足りない344万トンを県外処理にお願いするのだと書いています。
この河野氏のブログの記事(3月14日)の後、3月18日に細野環境・原発担当相が村井宮城県知事と会談して、「海岸防災林の盛り土に…震災がれき再利用で合意」したことが明らかにされています。
海岸防災林の盛り土に…震災がれき再利用で合意
細野環境相は18日、宮城県庁で村井嘉浩知事と会談し、津波から住民を守る海岸防災林を同県の太平洋沿岸部に整備するため、東日本大震災で発生した同県内のがれきを盛り土として埋め立て、再利用することで合意した。
震災のがれき処理に関し、政府が被災地での具体的な再利用策をまとめたのは初めて。
政府の計画では、仙台市から南側の仙台平野沿岸部の約50~60キロに防災林を整備する。その際、防災林を植えるための数メートルの高台をがれきを埋め立てて建設する。利用するがれきは、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の汚染の問題がないかどうか、環境省が安全性を確認する。事業は国直轄で行い、6月までに着手する。
(2012年3月19日 読売新聞)
遅きに失したとはいえ、政府も当然の策を検討せざるを得なくなったということがいえます。しかし、ということは、これだけでも県内で処理できるがれきの量がそれまで計算していた量と比べて相当変わってくる、ということがいえます。
さらに、「仙台市から南側の仙台平野沿岸部の約50~60キロ」だけではなく、宮脇昭先生が提唱するように、東北の太平洋沿岸約300キロにわたって、幅50~100メートル以上に防災林を築くとすれば、がれきは足りないくらいではないかと思われます。
河野氏の議論は、そのことについてはまったく触れられていません。そこからいきなり「県外処理=日本全国での広域処理」になっています。南相馬市の市長の考える復興計画などもあるわけですから、なぜ、まず現地、そして福島も含めた隣県、近県からその処理の可能性を探っていかないのか、いきなり九州・沖縄まで含めた日本全国にお願いするのか、その一番重要な点がまったく触れられていません。
「がれきの処理については、被災地の希望を聞いて支援が必要ならば支援するべきだ。」はわかりますが、地元で防災林という非常に有効な活用の仕方があるわけですから、はっきりいってやはりおかしいといわざるをえないのです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[廃棄物・リサイクル] カテゴリの最新記事
-
生ごみ分別収集は、リサイクル(資源化)… 2015.11.29 コメント(1)
-
ガベージ・マイレージという概念を提唱し… 2012.03.25
-
わが家はリサイクル率80%超 2012.03.24
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.