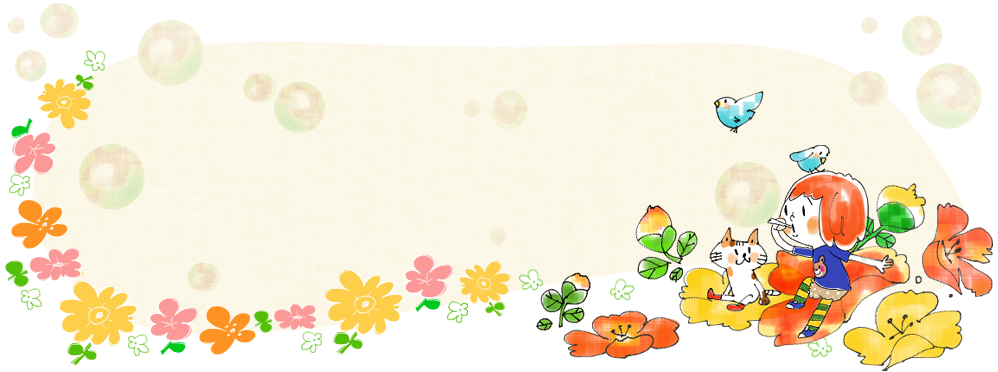カテゴリ: 短歌
6月18日(火)
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (26)
作歌机辺私記(94年11月)
「長塚節を」
七月末、宮崎まで講演に出掛けた。台風七号が南九州沖に滞ったまま動かず、その間、わずかに通う空路を頼るかのような旅であった。宮崎空港に伊藤一彦さんらが出迎えられ、そのまま青島の対岸に連れられた。台風の沖の曇りに打ち上げる潮のしぶきに濡れ、島に通う橋も行き来が絶たれていた。その対岸の浜の熱帯植物園に長塚節の歌碑があり、わかりにくい場所なのを伊藤さんが探し出してくれた。「とこしへ
に慰むる人もあらなくに枕に潮のおらぶ夜は憂し」の歌であり、歌碑の裏に一自由労働者が之を建つ、といった意味のようなことが彫られていた。死を前にして節はこのあたりを旅し、連日の時化に遭い、漁村の宿で呻吟している。日豊線など当時なく、乗合馬車と船との旅であった。来て見て作品の背後にあるものを実感とする。
そのこともあったわけではないが、歌会の席その他で、長塚節の歌あたりから読み直すことのすすめを、最近繰り返すことが多いのに気付いている。或いは、東京歌会でも出席者を前にそのようなことをいったのかもしれない。今、つづけているわたしたちの短歌の上に、一度、その原点であるべき何かに立ち返るために、或るいは、それを自分のうちに見定めることのために、という意味でもある。
創作とは、つねに限りない変化を求めていく営為であり、短歌もまたその例外であるはずはないが、同時に、その底に、短歌というものの原点、ないしは原型ともいうべきものを絶えず見据えておくことを忘れてはならないのであろう。何が短歌かという自らへの問いつづけでもある。それを見失うと、短歌という一定型詩型、一抒情詩型はとめどなく拡散し、糸の切れた凧のように風のまにまに飛び散ってしまうかもしれない。少なくとも自分のこととして、意欲的な作者ほどそれは自分のうちに知っておかなければならない。すなわち、繰り返せば、短歌がどのように多岐なひろがりを持とうとも、つねに、それが短歌であるという、何か原点であり原型であるものがあるはずなのである。その意味では、定型詩型というもの自体、まことの脆い、相互容認の上にある小文芸世界であるしかない。
その原点、原型をどこに求めるかは再びまた定めがたいが、わたしたちの場合、一応万葉集などの古典と思ってよい。しかしそれより、直接の実作のために、近代短歌のどこかに見ていくことがよく、さしあたり、わたしは今、長塚節あたりをじっくり読み、それを見定めておく必要をみなさんを前にして繰り返している。理由は、わたし自身の気持として、という以上はない。その上で、近代短歌を一つの歴史の継続としてしっかりと自分の内に畳み込んでおく作業が必要なのであろう。それをかってしてなかった人らの仕事の脆さを知って、ともいえる。(1994・11)
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (26)
作歌机辺私記(94年11月)
「長塚節を」
七月末、宮崎まで講演に出掛けた。台風七号が南九州沖に滞ったまま動かず、その間、わずかに通う空路を頼るかのような旅であった。宮崎空港に伊藤一彦さんらが出迎えられ、そのまま青島の対岸に連れられた。台風の沖の曇りに打ち上げる潮のしぶきに濡れ、島に通う橋も行き来が絶たれていた。その対岸の浜の熱帯植物園に長塚節の歌碑があり、わかりにくい場所なのを伊藤さんが探し出してくれた。「とこしへ
に慰むる人もあらなくに枕に潮のおらぶ夜は憂し」の歌であり、歌碑の裏に一自由労働者が之を建つ、といった意味のようなことが彫られていた。死を前にして節はこのあたりを旅し、連日の時化に遭い、漁村の宿で呻吟している。日豊線など当時なく、乗合馬車と船との旅であった。来て見て作品の背後にあるものを実感とする。
そのこともあったわけではないが、歌会の席その他で、長塚節の歌あたりから読み直すことのすすめを、最近繰り返すことが多いのに気付いている。或いは、東京歌会でも出席者を前にそのようなことをいったのかもしれない。今、つづけているわたしたちの短歌の上に、一度、その原点であるべき何かに立ち返るために、或るいは、それを自分のうちに見定めることのために、という意味でもある。
創作とは、つねに限りない変化を求めていく営為であり、短歌もまたその例外であるはずはないが、同時に、その底に、短歌というものの原点、ないしは原型ともいうべきものを絶えず見据えておくことを忘れてはならないのであろう。何が短歌かという自らへの問いつづけでもある。それを見失うと、短歌という一定型詩型、一抒情詩型はとめどなく拡散し、糸の切れた凧のように風のまにまに飛び散ってしまうかもしれない。少なくとも自分のこととして、意欲的な作者ほどそれは自分のうちに知っておかなければならない。すなわち、繰り返せば、短歌がどのように多岐なひろがりを持とうとも、つねに、それが短歌であるという、何か原点であり原型であるものがあるはずなのである。その意味では、定型詩型というもの自体、まことの脆い、相互容認の上にある小文芸世界であるしかない。
その原点、原型をどこに求めるかは再びまた定めがたいが、わたしたちの場合、一応万葉集などの古典と思ってよい。しかしそれより、直接の実作のために、近代短歌のどこかに見ていくことがよく、さしあたり、わたしは今、長塚節あたりをじっくり読み、それを見定めておく必要をみなさんを前にして繰り返している。理由は、わたし自身の気持として、という以上はない。その上で、近代短歌を一つの歴史の継続としてしっかりと自分の内に畳み込んでおく作業が必要なのであろう。それをかってしてなかった人らの仕事の脆さを知って、ともいえる。(1994・11)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[短歌] カテゴリの最新記事
-
島木赤彦「歌道小見」(抜粋:後藤)(1… 2024.06.28
-
歌集「未知の時間」(前田鐵江第一歌集)… 2024.06.28
-
近藤芳美「土屋文明:土屋文明論」より 2024.06.28
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.