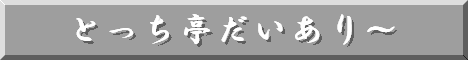全274件 (274件中 1-50件目)
-

アベレージ・ホワイト・バンド コンサート コットンクラブ東京2015
昨夜、アベレージ・ホワイト・バンドのコンサートに丸の内のコットンクラブに行ってきました。昨年も見たのですが、ヴォーカルに元タワー・オフ・パワーに在籍したことのあるブレント・カーターが定着したようで、今年はさらにパワーアップしたノリノリのコンサートでした。コットンクラブは初めて行きましたが、何となく肩がこらずに音楽が楽しめる良い会場でした。
2015年07月14日
コメント(5)
-

25年前のマーキーでのコンサート
昔私の所属していたバンドが、ロンドンのマーキーというコンサート会場で演奏した別の動画がアップされたので記録します。もう25年も前の出来事です。今思うと青春だったと思います。
2015年07月08日
コメント(4)
-

6月10日ボズスキャッグスコンサート渋谷オーチャードホール
6月10日の渋谷オーチャードホールのコンサートに行ってきました。相変わらず渋いコンサートをやってくれましたが今回はLoan me a dime.はやってくれませんでした。今回連れてきたギタリスト(志茂田景樹的な風貌)はすごくうまかったのでもっと聴きたかったのですが、彼がソロを取る場面が殆ど無かったのは残念でした。
2015年06月16日
コメント(2)
-

JDサウザーコンサート6月11日
6月11日JDサウザーのコンサートにビルボード東京に行ってきました。もう一人のイーグルスと言われている彼のコンサートは、とても素晴らしいステージでした。舞台はピアノ・ウッドベース・そしてJDのアコースティックギターのシンプルなセットアップでしたが、堪能しました。彼のハイトーンボイスが凄く曲にマッチしていて、正に彼のシンガーソングライターとしての力が十分に発揮されたステージでした。イーグルスとのコラボ「ニューキッズ・イン・タウン」「ベスト・オブ・マイラブ」「ユア・オンリー・ロンリー」などジャズのフレーバーを交えての正に癒されるコンサートでした。嫁さん曰く、ウエストコーストのシンガーソングライターの深さを思い知らされるステージでした。
2015年06月16日
コメント(4)
-
アル・ジャロウ イン ブルーノート東京 11月18日
遅まきながら11月18日にブルーノートにアル・ジャロウを見に行ってきました。ステージの中央部には高めのストールが2脚置かれているので、今年74才になったアルは疲れた時にそこに座って歌うものと思っていました。ステージが始まる前に足腰が及ばないので男性3人に抱えられて現れた彼を見て大丈夫かな?と不安になりましたが、ステージが始まるや足腰は危ないがあの声は健在でした。以前、10年ほど前にロンドンのバービカンセンターで彼のステージを見た時にジャズのリジェンドを見た!位にしか感じていなかったのですが、ブルーノートで見た彼は素晴らしかったです。最初の2曲は聴いていて感激で涙が止まらなかったコンサートは初めての経験でした。足はおぼつかなくステージ上のスツールに寄りかかりながら歌うのですが、彼の声そしてリズム感はまさに神がかりでした。さらにコンサートも後になればなるほど彼のエンジンもフル回転で本当に素晴らしいパフォーマンスでした。私の嫁さん曰く正に彼は神と交信できる数人の内の一人だと認識させられる貴重な体験でした。http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/al-jarreau/http://www.bluenote.co.jp/…/repo…/2014/11/19/al-jarreau.html
2014年12月07日
コメント(6)
-
平成26年1月2日Average White Band Live at Blue Note Tokyo
お久しぶりです。昨夜、アベレージ・ホワイト・バンドのコンサートにブルーノート東京に行ってきました。思えば十数年前にLondonのCamden TownにあるJazz Cafeという小さなコンサート会場(200人も入れば満員ぐらいの)で彼らを見たときはそれなりに良かったのですが(もちろんHamish Stuartも居なかったし)今回のライブは強力なサプライズが待っていました。コンサートが始まりメンバーがステージに登った時に、なんとなく見たことのある顔が一人混じっていたのだが思い出せない。曲が始まり彼がリードボーカルで歌いだしたときに、「あれっ?この声聞いたことがある。」ますます不思議に思いながら試行錯誤している内に、バンドは2曲目に突入その時に頭の中で確かアベレージ・ホワイトバンドに繋がりのあるバンドはTower Of Power!!!ひょっとしてBrent Carter?そうかも、いやまさか、でも似てる、うわっ!そうだそうに違いない。頭の中でこんな自問自答が行われながらもコンサートは進んでいった。私が、Brent Carterを知ったのはTower Of Powerの「Soldout」というアルバムでTOPファンの中にはあまり評価をしていない人たちもいるらしいが、私にとっては曲も演奏も素晴らしく大好きなアルバム中の1枚だと思っている。このアルバムの中で歌っているBrent Carterの声がまた素晴らしい!アベレージ・ホワイト・バンドにBrent Carterが加わったことで、さらにパワーアップしたライブはもういう事ありません。必見です!!!しいて言えば、あれだけ素晴らしいバンドのライブを聴かせるのだからブルーノート東京はもう少し音響を改善してくれるとありがたいです。
2014年01月30日
コメント(2)
-
Quasar gigs : At St.Maws ,Cornwall (その4)
夜も更け外の風も一層激しくなった頃、公民館の会場は隙間も無い程の人が詰めかけ会場は人の話し声と活気に満ち溢れていて私たちは外の風の音など殆ど気になら無くなっていた。開演の時間が間近に迫ると、我々メンバーの4人はいつもの様に舞台の袖に集まりお互いの手を繋ぎ精神を集中した後、掛け声と同時に舞台に出て行った。会場のアナウンスでバンド名を紹介した後で、一曲目が始まり会場の観客も楽しんでいるのが分かると我々の演奏にも一層のエンジンがかかる。演奏も一曲目の中盤位になったころであろうか、かなりの大きな音で演奏をしている我々耳にもハリケーンの風の音が聞こえ、公民館の窓の曇りガラスには木々の大きく揺れる影が移りこんで異様な雰囲気を醸し出していた。私は、演奏をしながら何となく不安な気持ちが心をよぎっているのを抑えきれなかった。その時、バチッと言う大きな音と共に会場の電気が消え、同時に舞台上で演奏をしている我々の音も生音であるドラムのリズムを除いて消えてしまい、行き場のなくなったドラムの音も止んだ。一瞬シーンとした真っ暗な公民館の内部、外ではハリケーンの風が我々をあざ笑うかの様にさらに大きな音で吹き荒れていた。公民館のスタッフが、非常用のライトを点けてくれたので会場は明るさを取り戻し再び人々の話声でざわめきだした。会場の停電は思ったより深刻らしく、スタッフの話によると現在回復の見込みは立っていないらしい。ステージの上では、トレーシーがドラムライザー(ドラムを乗せる台)の角に座り込み途方に暮れていた。そうこうしている内に、スタッフの誰かが私に「今、発電機を持ってくるのでちょっと待ててくれ。」と耳打ちをしてくれた。私は、トレーシーを元気づけるためにその事を伝えに彼女の所に行ったのだが、機械にあまり詳しくない彼女には具体的にその事がどういう意味なのか余り良く伝わらなかった様だった。暫くして、ジェネレーターが届き機材とステージライトに電気が供給され、キースが先程の停電で音響機材に影響が無かった事をそしてウエールズからこのコンサートの為に来てくれた照明担当のクライヴがステージのライトにを点検して問題無い事を確認した後、再び演奏を開始し無事コンサートを終えることができた。あの停電の後、誰かが機転を利かせてあの嵐の中をどうやって発電機を持って来てくれたのかは分からないが、その機転のおかげで大した時間のロスもなくコンサートを無事に終えることが出来たのもセントモウの人達のお蔭だった。翌日、朝起きてみるとハリケーンも過ぎ去り、普段の穏やかな漁港の景色を取り戻したセント・モウだった。我々は朝食を済ませるとしばらくトレーシーの家族と話をした後ロンドンに変える準備を始めた。トレーシーの家族にお礼と別れを告げる時に、デイブがシャーリーンに小鳥がする様にお互いの唇を突き出してお別れのキスをしているのが見えた。頬っぺた意外にするキスというものに慣れていない私は、ちょっと躊躇していたのだがシャーリーンが無邪気に唇を出したので何の抵抗もなくお別れのキスが出来たのは自分でも以外だった。今回は、トレーシーの生まれ故郷でのコンサートだったという事でもあり、ハプニングはあったもののセント・モウの人達の素朴な暖かさに助けられたような気がして、とても心が温まる数日間だった。私は、デイブの車の助手席にトレーシーそして後部座席に照明のクライブと一緒に乗り込みワイワイと話をしながらセント・モウを後にした。
2013年11月13日
コメント(2)
-
Quasar gigs : At St.Maws ,Cornwall (その3)
機材をトラックから出して公民館に運び込み、まずはドラムの場所を決めドラムを乗せるドラムライザーと言う木組みのセットを組み立てる。これは、いわゆるドラムを載せる台でステージよりも一段高い位置にあるので観客からもよく見えまたドラムの音自体もよい音で聴かせることが出来るためらしい。ドラムライザーを組み立てた後は、ディブがドラムやシンバルそしてそれらを取り付けるスタンドを箱から取り出す作業を手伝いながら、観客用のメインの大きなスピーカーをステージの両脇に設置をしモニタースピーカーを各パートの立ち位置に置き、それらをケーブルで繋ぐ作業である。こんな風にしてステージが段々と作られて行き、最後は自分のパートのギターのセッティングをしてステージの準備は完了である。ステージの準備が終わると、今度は音出しを兼ねたリハーサルであるがここでちょっとしたハプニングがあった。私は、通常コンサートの前は常にギターの弦を新しい物に張り替える。これは、音が良いという事ももちろんなのだが、バンドの楽曲の中にはギターの17フレットで1音半のチョーキング(弦を曲げて1音半高い音に持っていく動作)もあるので古い弦だと切れてしまい、私のギターは弦が切れるとギターの調律が大幅にくるってしまうのでそれを避ける為に切れにくい新しい弦を張っているのである。私は、ギターの弦を交換する際に一番細い1弦がブリッジのある部分に引っかかっていることに気付かずに調律をしてしまい、そのままリハーサルに入ってしまった。当然この事に気が付いていない私は、曲の途中で一弦をチョーキングしてピキッと言う音と共に一弦の調律が極端に低くなってしまい、曲を中断させざるを得なくなってしまった。私は、「Sorry! I didn't know but my first string was cought on the guitar bridge.」(ごめん、ギターの一弦がブリッジに引っかかっていたみたいだ。)と言うと、キースはすかさず「Oh Yah? That is a good excuse Toshi.」(え~そうなの?とっち、それはうまい言い訳だな。)と茶化すと、キースの皮肉屋なところが嫌いなトレーシーは「I know Toshi I trust what you've said.」(とっち、私は貴方の言っていることを信じるわ。)とキースをたしなめる口調で私に話しかけた。バンドのリハーサルは、いつもの様にこんな感じで特に機材の不調もなく無事に終了した。私は、ステージを下りると今朝私を朝食に呼びに来てくれたシャーリーが弟と遊びに来ていたので、まだ人が入っていないガラーンとした会場に3人でなるべく広い3角形状に座り、シャーリーが持ってきたボールをお互いに向けて転がし合いながら遊んでいた。ひとしきり遊んだ後、シャーリーが私と何かを話している時に彼女は私が無造作にボールを見ずに右手から左手に投げていたのが気に入ったらしく、「How did you do that ?」(どうやってやったの?)と言って私からボールを受け取ると同じようにやって見るのだが、彼女にとっては初めての試みなのでうまくボールをキャッチできない。私は彼女に、「You will be able to do it after a little practice.」(もうちょっと練習したら出来ると思うよ)と伝えた。夜も大分更けてきて、公民館は集まって来た地元の人達でにぎわってきた。私が、コンサート前の最終機材チェックをしているとステージの下から地元の若い男性が「Excuse me.」(ちょっと良い?)と私に声をかけてきた。私は、「Hi.What can I do for you?」(ハーイ、何か用?)と彼の所に歩いていくと、彼はにこにこと微笑みながら、「Are you any good?」(あなたはうまいの?)と聞いてきた。私は、同じように笑顔で彼に「Yes!I am very good!」(うんすごくうまいよ!)と言うと彼は「I'm fruttered !」(うれしいよ!)と言って私と握手をして会場の人混みの中に行ってしまった。夜も大分更けコンサートの開演が迫ってくる時間になると、外は大分風が強くなってきた様で公民館の中にもかなりの風の音が聞こえていた、地元の人たちの話ではどうやらハリケーンがこの土地に上陸したらしい、風の音は次第に大きくなると同時に私の気持ちにも一抹の不安が過っていた。
2013年10月31日
コメント(4)
-
Quasar gigs : At St.Maws ,Cornwall (その2)
我々の乗ったトラックは、セント・モウの町に入って行った。この村は、外海から大きく入り込んだ入り江になっておりそこには無数の漁船が停泊していた。殆どの家は、この地域でとれる石を積み上げて出来ており、その外側には胸位まで石を積み上げた頑丈な石垣がしっかりと家を守る様に積み上げていた。トレーシーの家に行くと、先に到着していたデイブとトレーシーが家の外に迎えに出ており、トラックを下りた我々に長旅の労をねぎらうと家の中に招き入れてくれた。我々は、トレーシーの家族としばし話をした後、別棟の寝室のある家に案内されそこでゆっくりと旅の疲れを癒すことができた。翌朝、目が覚めると私のベッドの前に10歳ぐらいの金髪の女の子とその弟らしき5歳ぐらいの男の子が立っていた。“Hi !、ハーイ””Who are you?(君は誰?)and what are you doing here?(ここで何をしているの?)と聞いてみたところ・”I'm Shirly and my mum told me to tell you 、your breakfast is ready.”(私はシャーリー、お母さんが朝ご飯が出来たからってあなたに伝えてと言われたの。)と答えたので、この子達が昨夜挨拶をしたトレーシーのお姉さんの子であることが直ぐに理解が出来た。私は、”Thank you shirly. I'm coming right away. Oh!By the way I'm Toshi.”(ありがとうシャーリー直ぐ行くね、あっ!僕はToshiっていうんだ。)と答えると。”I know,mum told me.”(知ってる、ママが教えてくれたもん)と言って部屋を走って出て行った。私は、着替えて別棟にあるダイニングに行くとデイブとトレーシーは既に朝食を取り家族と話をしている状態であった。私とキースは”Morning!”(おはようございます!)と言って部屋に入って行くとトレーシーのお姉さんが”Morning! Slept Well?”(おはよう、よく眠れた?)と言って、我々の為に座る場所を空けてくれて大きなお皿に目玉焼き、ベーコン(アメリカのベーコンと違いヨーロッパのベーコンはかなり塩辛いがこれが朝ご飯にはベストである)ソーセージ、焼きトマトそしてマッシュルーム等が所狭しと並んでいる、所謂English Breakfast(イングリッシュ・ブレックファスト:イギリスの典型的な朝食)を出してくれた。これにカリッとトーストした薄切りの食パンにバターを塗りそしてマーマレードを塗って食べ、非常に濃く入れた紅茶にたっぷりミルクを入れて飲むと一日の活力が全身に漲ってくる。食後、トレーシーの家族との談話がひと段落した後、今晩のコンサートの準備の為に村の公民館に向けて出発した。とは言っても、トレーシーの家から歩いて数分で行けるほどの近距離だったように記憶をしている。以前にも書いたことがあったとは思うが、QUASARは通常400~500人のコンサートならば場所さえあれば余裕でコンサートを開けるほどの機材を有している。難を言えば、まだバンドがローディを雇うほどの財が無い為にメンバーがコンサート会場で機材を運びセッティングをしなくてはならない。まあ、この様に自前の機材でコンサートが出来るのも、今思えばリーダーのキースが機材に明るいので常に自宅で機材のチェックをしてくれていて、いつ何時でも安心してコンサートが出来るようにしてくれているからなのである。
2013年10月29日
コメント(2)
-
Quasar gigs : At St.Maws ,Cornwall (その1)
最近台風の話題に事欠かないこの頃、何となく昔のことを思い出したのでその記憶をたどって思い出せる限りと思い書き始めました。時間のある時に思い出しながら書いていますので、頻繁には更新できないと思いますがよろしくお願いします当時、新生Quasarもかなりのライブの経験を積み、この頃になると私も曲のどの部分でエフェクターのペダルを踏み、ヴォリュームペダルを少しづつ上げて行ったり曲間では余計なギターのノイズを出さないようにミュートスイッチを踏んでおく事等、全ての動作を考えなくても自然に足が動く程になって来た頃の事だった。練習の後、例によってキースが、「みんなに知らせがある。次のQuasarのコンサート会場が決まった。場所はセント・モウ(St.Mawes:と書くのだが発音上最後のSは聞き取れないまたは発音しないのかもしれない:http://www.stmawes.info/st-mawes-village)コーンウォール(Cornwall)でトレーシーの生まれ故郷だ。」と発表をした。トレーシーの説明に寄ると、少し前に彼女が里帰りをした時バンドの話とコンサートの話を家族にしたところ、それじゃここでコンサートを開いたら良いという事になったらしい。「村を挙げてコンサートに協力をする、どうぞセント・モウに来てください。」と言われれば、こちらは願ってもない事であった。内容は、コンサートの前夜セント・モウに行き一晩泊めてもらい、次の日にゆっくりとコンサートの準備をしてその夜にコンサートを開く。コンサートの後は、もう一晩セント・モウに泊めてもらい次の日ゆっくり起きてロンドンに帰ってくると言う、通常の我々のコンサートでは考えられない程ゆったりとした優雅なスケジュールだった。トレーシーはデイブの車で一足先に里帰りをするという事で、コンサートの前前日にはセント・モウに向けて出発していた。私とキースはコンサートの前日にQUASARの機材が満載しているトラックに乗り込み、夕方近くになってゆっくりとロンドンを出発した。高速道路M4(イギリスの高速道路は殆どが高速料金を取られることが無いので便利である)で一路西に向かった。途中サービスエリヤで休憩し、食事やお茶取ったりして時間が経ってしまい。我々が目的地に近づいたのは夜もかなり遅くなっていた。ご存知の方もいると思うがイギリスの夏は日が落ちるのが極端に遅く、通常でも夜の9時~10時頃になってマリーゴールド色の夕焼けを経て夜の帳が下りる。我々の乗った車がセント・モウに近づく頃には、夜の帳が静かに下り雲一つない濃紺の空には満面の星が輝いていた。私は、車の窓ガラスの殆どを占めているその宝石箱をひっくり返したという喩がぴったりな景色に圧倒されしばし我を忘れて見とれていた。
2013年10月14日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 QUASARコンサート その2 TONYPNDY WALES 3
我々の乗った車は、カーディフを出て山道を暫く走ると昔炭鉱で栄えたトニーパンディに入った。キースは、更に車を走らせ坂道の多いこの街のとある公民館の様な建物の前で車を止めた。「Here we are !(さあ、着いた。)Let's get to work!(仕事に取りかかろう!)」と言って、車から出て行った。キースが車から出ると、彼を待っていたかの様に建物から年配の女性が出てきて親しく挨拶をし、何やら昔話の様な話が始まった。どうやら彼女はこの公民館の責任者で、キースは過去にバンドでこの会場に何回もお世話になっているらしく、お互い顔見知りになっているようだった。我々は、早速車から機材を下し始め公民館のスタッフの助けを借りて建物の中に運び始めた。建物の中の事は正直言ってうろ覚えなのだが、中に入ると1000人位は入るスペースがあり、その奥に高さ1,5メートル位のステージがあった。ここのスタッフは実によく働いてくれ、ステージの上にドラムライザー(ステージでは通常ドラマーが見えにくいのを解消するためと、ドラムの音を良く響かせるために一段高い台を組み立ててその上にドラムセットを組み立てる)を組み立てたりモニタースピーカーの設置を手伝ってくれた。ステージが組み終わった後、ちょっとしたサウンドチェックをしていると、今回ライトを担当してくれる生粋のウェールズ人クライヴという男性がライトのデスクを運んできた。彼は非常に明るい性格で我々ともすぐに打ち解けたのだが、彼の熟練したライトマンとしての技術には舌を巻いた。彼は、我々が会場に入る前にステージの上に自作のライトを取り付けていて、持っていた8チャンネルのライトのミキサーとそこについているジョイスティックみたいなものでステージの上に言いようのない神秘な空間を作り出してくれた。私は、リハーサルが終わった後にクライヴの所に行き「一人でこんな幻想的なステージライティングが出来るなんて初めて見たよ。」と話すと彼は「今回は予算が無くてこれだけだけれど、予算が多ければもっとビックリするステージにしてあげるよ。」と話してくれた。カーディフでのギター製作者もそうだったが、私はウェールズに来て以来この様に才能あふれる人達に出会えること自体、この国の音楽業界の層の深さに改めて驚かされる思いがした。コンサートの時間が近くなってくると、人気のなかった会場にかなりの人数が入りその熱気でムンムンとしてきた。時間が来ると我々4人はステージに出る前のスクラムみたいなものを組み、「いくぞ、オー!」みたいなことをやってステージに出た。我々の音楽は、ヘビーメタルの聖地であるこのトニーパンデイでも快く受け止められているようで観客はとても喜んでくれた。約2時間弱の演奏を終わり、ステージで機材の片づけをしていると隣で片づけていたドラマーのデイヴが「とっち、とっち!見ろよスゲエ美人がいる。」デイヴが示した方向には確かにそのままモデルの雑誌の表紙にしてもおかしく無い程の美人が2人丁度会場から出ていくところらしい。いま思えば、キャサリーン・ゼタ=ジョーンズの生まれ故郷なのだから不思議ではないのだが、首都カーディフから更に田舎に入った今は閉鎖されたこの小さな炭鉱町に、ロンドンでもなかなかお目に掛かる事のない垢抜けた美人が簡単に目に留まるとはさすがであった。まだ会場にはかなりの人数がコンサートの余韻を楽しんでいるところ、キースが会場の後ろの方から「とっち!ちょっと、こっちに来てくれ!」と叫んだ。私は、ステージから降りてかなりの人混みをかき分けなければキースの方に行けそうにないので、覚悟を決めて人混みの方に歩いていくと私の歩く方向に向かって人混みが2つに分かれモーゼの十戒に出てくる海が割れるシーンの様に私の為に通路を作ってくれた。私は、突然の光景に戸惑いながらもすんなりと人混みを通れた事を喜び、その奥にあるパブ(お酒を飲める場所)らしき部屋に入っていくと、その部屋は貸切になっているようで中央のテーブルに40歳前後のカップルを前にキースが楽しそうに話をしていた。キースは、私を見ると「とっち、ちょっと紹介させてくれ。こちらのカップルはQUASARが最初にここに来た時からのファンの方でとっちからもお礼を言ってもらおうと思ってね。」私は、「そうでしたか、それはありがとうございます。最初にQUASARを知ったのはいつごろなんですか?」等と楽しく話をしていた。暫くして女性の方が私に、「ちょっと、とっちさんにお願いがあるのですが」と聞いてきた。彼女は、私がどのような手をしているのか見せて欲しいという事だった。私は、お安いご用ですよと言って両手を差し出すと、彼女は私の手を取って繁々と見ながら「この手があの演奏をした手なのよね。」と呟くのを聞きながら私はこそばゆさを感じていた。演奏の後片付けも終わり、表に出るとこの会場の責任者の女性が見送りに出てきて「今日は、本当にありがとう。みんな楽しんで帰って行ったわ。」と言いながら我々一人一人と握手を交わした。我々は、手伝っていただいたスタッフの皆さんにお礼を言い、夜中の12:00過ぎに暗い夜道を一路ロンドンに向かって運転を始めた。途中高速道路のカフェで給油と休憩と遅い食事を取り、我々がようやくキースの家にたどりついた頃には既に朝の7時を過ぎていた。私は、機材車を下りキースからお茶でも飲んでいくか?と誘われたが、まだ彼のガールフレンドも寝ているだろうからと辞退をしてそのまま近くに駐めてあった自分の車に乗り込み家路に向かった。朝のラッシュアワーは大変な混みようだったが、私はそれとは反対の方向に走っていたので道はガラガラに空いていた。既にフル活動を始めているロンドン市内を横目で見ながら、家に到着し地区の大通りであるBROADWAYを行きかう車やお店を開ける準備等の朝の騒音を聞きながら家に入った。いつもの様にミルクティを作り、それを飲みながら頭の緊張をほぐしている内に眠気が催してきて眠りについた。
2013年03月21日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 QUASARコンサート その2 TONYPANDY WALES2
TONYPANDYのあるWALESと言う地域は、ロンドンから高速M4に乗り西に3~4時間行くとセヴァーンと言う大きな川にかかる橋がありそこを渡るとウェールズになる。ウェールズに関して興味のある人は下記のアドレスを見て調べてください。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA簡単に説明するとウェールズはThe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (イギリスの正式名称で、北アイルランド、スコットランド、イギリス、ウェールズの4つの連合国で形成されている。)形成されている4つの国の一つでイギリスの南西に位置し人種はケルト民族で、これは聞いた話だが彼らのルーツを調べると北欧のバイキングらしい。この地域の人達は、歴史上ローマ帝国に侵略されたこともあるのだろうが北欧系に多く見られる青い目で金髪の人が多いのも特徴だと言える。ウェールズの公用語はウェールズ語と英語で、一般にこの国は歌の国と呼ばれ声の良い人が多いのも特徴らしい。音楽の世界では、トム・ジョーンズ、メリー・ホプキン、ボニー・タイラー、ブレッド、マニック・ストリート・プリーチャーズ、ステレオフォニックス等。俳優の世界では、ティモシー・ダルトン、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ、リチャード・バートン、アンソニー・ホプキンス等は私でも知っている有名人だ。ウェールズの首都はカーディフ、ここは他の主要都市に比べるとこじんまりとした街だが、カーディフ城を始めとして歴史を感じる街である。今回我々は、トニーパンディーに向かう途中でこのカーディフでお昼をとりつつ一休みをした。昼食の後、一時間ほど自由行動となったので私は街を歩いていると楽器屋さんがあった。中に入って見ると結構大きな楽器屋さんで、広いフロアーに楽器が整然と置かれていた。私は、店の人に「フル・アコのギターを弾かせて貰いたい。」と頼み、片隅のコーナに設けてある試し弾きの場所でギターを弾いていると、新たにギターを持った人が私に近づいてきた。私は、次に試し弾きをする人だと思い席を譲ろうと立ち上がった。すると彼は、「No!No!You sit down.(いやいや、君は座っていて)」と言い「You don't want to play that 、you try this.(君は、そのギターは別に弾いてもしょうがない、このギターを弾いてごらんよ」と言いながら、有無を言わせず私の弾いていたギターを自分の持ってきたギターと交換した。私は、今まで見たことのないそしてメーカーのロゴマークの入っていないそのギターを弾いてみた。今になってみると、ギターの音は思い出せないが、その弾きやすさには驚いた記憶がある。そのギターは、白のグレッチの様なフルアコのエレキだったのだが、フレットの飾りなどはまだちゃんと貼り付けていなくてまだ試作品の様なギターだった。私が弾き終わると、先ほどの彼がやって来て「How is it?(どうだった?)」と聞いてきたので私は、「Yah! It's nice and easy to play.(うん!いいね弾きやすいよ)Is this for sale?(これは売り物なの?」と聞くと、ギターは売り物ではなく彼が試作品として作っている物で、彼は私に試し弾きをしてみてどう思うか感想を聞きたかったらしい。私はあの時、彼がいくら位であのギターを売るのか聞かなかったが、とても弾きやすく魅力のあるギターでお金があれば買ってもよいと思えるギターだったと記憶している。試作品のギターを弾かせてくれた彼にお礼を言って別れた後、私はキース達と待ち合わせた場所に行き再び車に乗り込み更にウェールズの奥深くにあるトニーパンディに向かった。
2013年02月23日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 QUASARコンサート その2 TONYPANDY WALES1
前回よりQUASARのコンサートで私が印象に残った思い出深い内容を書き始めたのだが、コンサートの順番ははっきり言って覚えていないので話が前後してしまうのはご了承ください。私がTONYPANDY http://en.wikipedia.org/wiki/Tonypandyという、ある地域の名前を耳にしたのはいつもの練習のあとだった。キースの話に寄ると、QUASARは過去に何回もこのウエールズの小さな村でコンサートを行いかなり人気があったらしい。加えてデイブの話では、ウエールズはへヴィメタルの聖地らしくオジー・オズボーン等もTONYPANDYで良くコンサートを開いていたらしいとの事だった。この頃までにはQUASARは、最初にNORFOLKまで行った時のバスは売り払い中型のトラック(良く佐川急便が使っているような少々大きめのトラック)にギター、ベースそしてドラムやPA機材を積んで移動するようになっていた。このトラックを買う時にちょっとしたエピソードがある。ある時、キースが私に「機材を運ぶトラックを見に行くんだけど、とっち一緒に来てくれないかな?」と言われ、当日キースと確かエレファント&カーソル(Elephant&castle)周辺だったように思うがトラックを見に行った時の事である。相手は、中年夫婦でやたらと我々に愛想が良く、その時のキースの服が白い縦襟のシャツと黒っぽいジャケットの襟を立てているので確かにその中年夫婦の言うように彼がVicar(牧師)に見えるのだが、最初にキースにあった時から夫婦はキースに「ねえ、あなたはVicarに見えるけど本当は牧師さんなのでしょう?その恰好は絶対に牧師に違いない。」といって聞かなかった。最初は、軽く否定をしていた彼もその夫婦が余りにもしつこく言うのでその内に面倒になってしまったのか否定をしなくなった。実際にトラックの売り買いの段階になってもキースの専門的な質問に、「我々は牧師様をだますようなことは一切できない。」等と言って来るので、結局そのトラックを買うことに決めてお金を払い車両の所有者を示す証明書を受け取り、2人でトラックに乗り込み家路に向かった。途中でキースが運転中に突然「くそっ、だまされた!」と言い出した。私は「どうしたの?」と聞くとキースは「あいつら俺にポンコツを売りつけやがった。」みたいなことを言いだした。彼の話によれば、トラックを運転してみて初めてこのトラックのコンディションがいかに悪いかが分かったらしいが、あの夫婦はキースを上手いことおだてて彼が試運転をしないでトラックを買うように仕向けたらしい。私は、キースの話を聞いて万能の彼をまんまとだませるあのような夫婦がいる事に、イギリスの詐欺社会の深さを知り驚いた、と同時にいつもクールなキースがだまされる事もあるんだという事実は珍しくもありそしておかしかった。その後、相変わらず万能の能力を持つキースは、あの欠陥だらけの車を一人でちゃんと乗れるように改造したのもすごいと思う。コンサートの日の朝、私はいつもの様に車でキースの家に行き寝ぼけ眼で入れてもらった紅茶をすすりながら彼の用意が出来るのを待っているとデイブとトレーシーがやってきた。機材をトラックに乗せて私はキースの運転するトラックに、トレーシーはデイブの運転する乗用車に乗り込みウエールズのトニーパンディに向かった。
2013年02月06日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 QUASARコンサート その1 MARQUEE
私が演奏していたころのQUASARのコンサートで書きたいことは沢山あるのだが、その中でもやはり私自信の個人的な思い入れのあるMARQUEEでのコンサートは、ロンドンでの一番の思い出だと思う。MARQUEEは、ロンドンでの音楽の登竜門であり、有名なバンドはBEATLES(彼らはリバプールから直で有名になった)以外のバンドは殆どと言って良いぐらいこのコンサート会場から出て行ったらしい。余談だが、つい最近1月24日付でYOU TUBEにその時の映像をアップしてくれた奇特な人がいたらしい、私は当時この映像の存在を知らなかったので今になってあの映像を見ることができるのはちょっと嬉しい。http://www.youtube.com/watch?v=qnOmQlzsrSo以前にも書いたことがあるのだが、このコンサートの時は残念ながらオリジナルのMARQUEEがあったWARDOUR STREET からCHARING CROSS ROADと言う場所に移ってしまった事であり、収納人数もオリジナルの場所は400人も入れば満員なのだが新しい場所は1200人と約3倍の収容人数になってしまった事であった。やはりオリジナルの場所には立ち見の観客がひしめき合い、熱気もさることながらステージのマジックが起きていたと思うのであのステージが無くなったのはさびしい限りである。その日、練習が終わるとキースが「みんなに話がある。いよいよQUASARがMARQUEEに戻ることが決まった。コンサートの内容はPENDRAGONとのジョイントコンサートだ。」以前にも書いたことがあるが、私が加入する前のQUASARはMARQUEEでのヘッドラインをレギュラーにつとめていた事もあったらしく。特にキースにとっては、何年か振りのMARQUEEコンサートになるらしく彼の嬉しさもひとしおだと思えた。私にとってもMARQUEEはロンドンに来て以来長年あこがれていたステージなので、自分がそのステージで演奏することになろうとは考えても見なかった。只、残念な事に演奏当日の私は、MARQUEEで演奏するという事で頭が一杯だった為なのかその日のことは殆ど覚えていない。演奏が終わってから、見に来ていたQUASARの最初のギタリストであるサイラス(イラン人)と再会を祝いグヮシッとハグしたことや、PENDRAGONの演奏を見ている時にQUASARの演奏が気に入った観客が、帰り際に我々に対して「イェ~!」と声をかけて行ってくれた事などは今でもはっきりと思い出せるのだが。もう一つ覚えているのは、当日会場の2階席にいた友人が、我々の演奏の時に彼の周りに座っているファンらしき人達がQUASAR(変拍子)の曲を一緒に歌っていたので驚いたと言っていた。私は、それを聞いて我々の音楽を実際に楽しんでくれている人達がいるのが、とても嬉しくそして有り難く思えた。残念ながらこの新しいMARQUEEもその後10年足らずで閉めることになってしまうのだが、我々も再びQUASARとしてこのステージに立つことは叶わなかった。
2013年02月04日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド その14
新生QUASARはそんな感じで始まり、キースはドラマーのデイブにコンサートの予約をどんどん取らせていた。キースの予定では、地方でのコンサートを手始めにどんどんファンを募り、最後に登竜門のMARQUEEでのコンサートにファンを総動員して音楽関係者を呼び、ショーケース的なコンサートを行うというものだった。只、最初の時点の新生QUASARのコンサートは悲劇的なものがあった。OXFORDでのコンサートでは会場が2階にあり、我々は全ての機材を狭い階段を登って2階の会場まで運ばなくては成らなかった。ここでバンドの持ち機材の説明をすると、所有している機材は小ホールや体育館位のコンサート会場は自前の機材で余裕でコンサートが出来るシステムPA(16chのミキサーや5つのモニタースピーカーそしてマイクやマイクスタンドそして縦・横1.5mほどのフロントスピーカーなど)を持っていて、会場は単に場所を提供してくれればどんな所でもコンサートを開くことが可能であった。これだけの機材を上記の様にバンドのメンバー4人で(内トレーシーは女性なので実質3人となる)コンサートの前に2階まで運ばざるを得なくなると体力的に少々きつい。加えてデイブとキースは其々の身長が180cmはあるので、コンサート用の大きなスピーカーを持って階段を上がる時等は身長が当時170cmの私にとっては結構苦労の種だった。その他にも、行ってみたら会場に観客が一人しかいなくて、殆どリハーサル状態のコンサートになってしまった事も今思えば面白い経験である。私がバンドで演奏していて困ったことは、イギリス人のバンドに東洋人がギタリストとして入っている事が気に食わないという人もいるらしく、演奏前に友達を連れてきてこいつは素晴らしいギタリストだからあいつ(私を指さして)の代わりに使ってくれと言いだす観客がいたり、演奏の途中で「俺にギターを弾かせろ、俺の方がもっとうまく弾けるぞ!」とステージに乗り込んでくる酔っぱらいもいた。もう一つ困ったことは、我々の音が通常のパブバンドと比較して格段に良いためにマイミング(弾いている振り)をしていると疑われることがあった。ある晩、コンサートの合間に観客の一人が私の前に寄って来て「レッド・ゼッペリンを弾いてみてくれ!」と言うので「今は、コンサートの合間に雑音が流れないように音を切っているので、ギターの音は出せない。」と言うと「そうだろうな。」と言って帰ってしまった。後で、その男の近くで彼の話を聞いていた友人が教えてくれたのだが、彼は私がギターを弾いている真似をしていると言っていたそうでコンサートの始めからずっと疑っていたらしかった。もう一つ思い出した事は、ある晩コンサートが終わってから一人の年配の人がビールを片手に私に話しかけてきた。「君は、日本人なのか?そうか。私はビルマの戦線で日本人と戦った事があるんだ。」すかさず私は「そうですか。それは私が生まれる前のことですね。そんな時代もあったのですね。」と言ってかろうじてその場の会話を逃げた経験も今思えば懐かしい思い出である。
2013年01月12日
コメント(2)
-
ロンドンでの体験 その2 プログレバンド その13
私は、たった今自分の足で踏んでスイッチを入れたエフェクターを見下ろした。すると、そのエフェクターの音量つまみがゼロを示しているのに気が付いた。すぐさま腰を落としてエフェクターの上に貼ってあるセロテープを剥がし、音量つまみをこれ位だったと思われる位置まで回し上げた後に次のギターフレーズを弾き始めた。幸いにもこの動作は、ドラムロールの間に行われバンドの変拍子のリズムから外れることなく再び音が出るようになり、観客にこの一件を気づかれるずに演奏をすることができたのだが、私の頭の中ではまだ「なんだ、なんだ?何が起こったんだ?どうしたんだ?」というパニック状態が続いていた。私は、とりあえずギターの音は出るようになった事だし、当面の問題は解消したので今は余計な事は考えずに引き続き演奏に集中することにした。演奏は一曲目の最後に差し掛かり、ギターのメロディーラインとシンセサイザーのストリングスが流れる箇所に来た時の事だった、私はギターを弾きながら何処からか不可解な不協和音が聞こえている事に気がついた。この事は後で知ったのだが、キース曰くキーボードのスティーブが使用しているムーグというシンセサイザーは、スイッチをオンにしてからその音が安定するまでは一定の時間がかかるらしい。キースは、スティーブにキーボードのスイッチを入れて置く様に再三アドバイスをしたにも拘らず、スティーブは忙しくてスイッチを入れて置く事を忘れていたらしい。その為、彼はキーボードの音程が不安定のままこのパートを演奏する結果となり、不協和音を出す始末になってしまった。一曲目が終わると、ヴォーカルのトレイシーが観客を相手に話をしている間、スティーブはチューニングに取り掛かりその後2曲目のUFOという曲の演奏が始まった。この頃迄には、私も先程の自分に降りかかったアクシデントの事はすっかり忘れてしまい、本来の演奏を楽しむようになっていた。UFOの演奏の最後に、その時の思い付きでエコーマシンを使いキーンという宇宙的な音を出したところ、観客が思った以上にその音に反応してくれ手を叩いたり歓声を上げたりして喜んでくれたのも私にとっては新鮮な驚きだった。ステージの進行も難なく進み、このコンサートの最後の曲となった。この曲は、私がこのバンドに参加して是非弾いて見たかった曲の一つで曲名はMISSION14、基本的なリズムは8分の15の変拍子で構成されているのだが、この曲は途中でいろいろな仕掛けがありキースがQUASARとして初めて作曲した曲らしい。私にとってこの曲は、とても思い出深いそしてキースの作曲能力が至る所で発揮された秀作だと思う。この曲の演奏途中で私がギターの早いフレーズを弾く箇所があり、キースがコンサート前に私に忠告していた「野外演奏は、冷たい風が手の甲を撫でると指が動きにくくなる」と言っていた事が実際に私の身に起こり、一瞬指が凍りついた箇所もあったのだが今思うと、私自身初めての野外演奏だった為に緊張した為に起きた現象だったのかも知れなかった。そうしている内にコンサートも無事に終わり、キースも新生のQUASARの初コンサートが無事に終えて安心したのか、満足そうに笑顔を見せながらステージを下りてきた。私はロンドンに戻ってから、キースに今回のコンサートで誰かが私のエフェクターに細工をしたらしい事を話して見たのだが、彼は別に驚く風でも無くこの業界ではその様な事件は良くある事でキース自身にも降りかかったある出来事を私に話し出した。それは、彼が1970年代にジョンメイオール・ブルース・ブレイカーズと言うバンドでベースを引きながらアメリカの西海岸を演奏旅行をしている時のことだった。キースがステージ前に飲んでいたお酒の中に、何者かが密かに眠り薬を入れたらしい。当然、彼はステージで演奏中に倒れそのコンサートは中止になり、キースはこの一件で理不尽にも責任を取らされバンドを首になった。同じ頃に、ニューヨークで演奏をしていたユーライア・ヒープと言うバンドのベーシストが演奏中に感電死という事故が起こり、西海岸で職を失くしていたキースにユーライアヒープからベースを持って直ぐにニューヨークに来るように連絡が入った。彼は、そのままニューヨークに行きホテルに着くや否やバンドからツアーで演奏する曲のテープを渡され、そのままホテル内に缶詰状態で曲を練習させられたらしい。キースは、その時の話を私にしながら当時を思い出すように「数日後、曲をマスターした後いきなりマジソンスクエア―・ガーデンズのステージに立たされた時は、正直足が震えたよ。あのステージは観客席がぐるりと取り巻いているので、俺がステージに出た丁度その頃殆どの観客がライターの明かりを付けているのがぐるりと見渡せて、思わずスゲェって心の中で思ったよ。」と静かに語るキースを見ながら私は、自分が今日受けた悪戯なんてほんの微々たる事の様に感じていた。その夜、キースとメアリアンにお休みを言って彼らの家を出る時、メアリアンが私に「今日はとっち良くやったわね、QUASARの前のギタリストが貴方が良いステージを見せたので腐っていたわよ。」と教えてくれた。私は、「そう、ありがとう。私も最初の野外ステージが結果的に楽しめて本当に良かったよ。じゃまた後でね。」と言って家路についた。私は、深夜の人気の無いロンドンの道路を、心地よい疲れを感じながら自宅のあるロンドンの北に向かって運転していった。当時、私が住んでいたマズウェル・ヒル地域はこの時間帯の路上駐車が困難で、いつもながら殆どの道路がぎっしりと車が駐車しており、なかなか駐車をするスペースが見つからない。ぐるぐると車を運転しながら、ようやく家から歩いて10分位の所に空いている場所を見つけて駐車をした後、人気のない夜道を用心深く歩いて家に入りふと時計を見ると時間は既に朝の3時を回っていた。私は、いつもの様にマグカップにたっぷりミルクを入れた濃いミルクティーを飲みながら、それまでの頭と体の緊張をゆっくりと解きほぐしてから眠りについた。
2012年12月28日
コメント(2)
-
ロンドンでの体験 その2 プログレバンド その12
前のバンドの演奏が終わり、いよいよ我々の番が来た。私は、先程運んでもらったギターのエフェクターの入ったバッグを受け取り、ステージに上がった。当時私が使用していたのは、ギターを歪ませるオーバードライブ、ディスト―ションそれから6弦ギターの音を位相を変えて12弦ギターの様に変化させるMXRのコーラスそして山彦の様に音を繰り返すエコーマシンそれからギターの音を音色を変化させずに継続的に伸ばすことが出来るコンプレッションサスティナー、そしてそれらの音量をコントロールするヴォリュームペダル等々、前日に其々のエフェクターを繋いでその音量や効果のかかり具合を慎重に測り、つまみが動かないようにその上からセロテープをしっかりと貼り付けたエフェクターを並べ始めた。その機材を見たステージエンジニアが「へ~!そんなに沢山のエフェクターを並べて全部使えるの?」と冷やかし気味に言いながらステージの私の前を横切って行った。この各ギターエフェクトをステージ上の演奏で踏むときは、曲によって2つや時には3つのエフェクトを同時に踏まなくてはならない時があり、この動きがタップダンスに見えるのでPedalboard (tap) dance(エフェクト板上の踊り)とも呼ばれているらしい。我々QUASARの曲は、以前にも書いたように曲によってギターの音色を頻繁に変えなくてはならないのが難点であり、長い曲であるMISSION14という曲などは数えてみると一曲で24か所も音色を変えなければならないという面倒な作業が含まれていた。さてステージで作業をしている私に、先ほど私に嫌味を言って行ったステージエンジニア(舞台音響係)とは別の担当者が私のギターアンプの設置場所について話しかけてきた。通常ギターアンプは演奏者の背後に置いてあり、前方に置いてあるバンド全体のミックスした音が流れてくるモニタースピーカーと自分の立ち位置によって全体の音を調整する。簡単に言うとギターアンプが後ろにあれば、前方のモニタースピーカーから流れてくるバンド全体の音の中でギターの音が小さくて聞こえなければ、演奏している自分の立ち位置を少し後ろに下がればギターアンプからの音をより大きく聞けるようになると言った事なのだが、私はこの時初めての野外ステージで感覚が狂ってしまっていた。何を思ったか、私はエンジニアの人に自分のギターアンプを前方にあるモニタースピーカーの横に置いてくれるように頼んでしまっていた。今思うと多分この時私は初めての野外ステージで演奏する事と、その日はバンドのサウンドチェックやリハーサルが無くいきなり本番だった為、そのステージが予想外に広かった事と自分のギターアンプが100ワットの出力しかないので、私の後方にギターアンプを置くと音が小さ過すぎて聴こえなくなるのでは無いかと不安だったのだと思う。とにかく、この位置では自分のギターアンプとバンド全体の音が流れてくるモニターアンプの音量のバランスを取ることができない事は後になって想像がついたが、エンジニアの人に既にこの様にセッティングを頼んでしまったからにはもう後戻りをすることは不可能だった。バンドのセッティングも終わり、いよいよ演奏開始である。ラジオ局の人のアナウンスで「さて本日の最後のゲストです。ここでクエーザーをお届けします。みなさん大きな拍手で迎えてください。いけ~!いけ~!」みたいな感じで最初の演奏ホワイト・フェザーと言う曲が始まった。演奏は順調だった。ギターの音が少々大きかったが、思ったよりは問題が無かったので少し落ち着いた頃演奏は中盤のギターリフから次のセクションに行くための高い音に変化するときだった。そのフレーズを弾く為にまずエフェクターのスイッチを足で踏み、弾いたのだが「音が出ない!」私は一瞬何が起こったのか判らずに体が硬直した。
2012年12月24日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド その11
我々は、その会場に入るまでは多分2~3000人位いやそれ以上来ているかもしれない、等と勝手な憶測で観客の人数を見積もっていたのだが、実際に会場に入ってみるとそこに来ていた人数は50人にも満たなかった。「なんだよ。どうなっているんだ?」とデイブが言い出し「まだ時間が早いんじゃない?」とトレイシ―が慰めると、キースが「ちょっと関係者に聞いてくる。」と言ってバスを出て行った。暫くするとキースが戻ってきて「さて、みんな聞いてくれ。ノーフォークのラジオステーションの責任者に聞いたところ、今回のコンサートの告知の報道に手違いがあったらしくニュースが行き渡らなかったらしい。彼らは私たちに出演料は払うが、このまま帰っても良いと言っているが、どうする?野外で演奏するのは、室内とは違って手が思うように動かなかったりする事もあるので、練習としても良い経験だと思う。」すると他のメンバーも「折角ここまで来たんだし、良いんじゃない?やってやろうじゃん」見たいな意見になっていった。加えてバスの外には我々のファンだという子達が何人か来ていて、我々がバスの外に出ると一人一人にサインをせがんできた。私はこの時生まれて初めてサインをせがまれる側になったのだが、いきなり頼まれてどうやってサインを書いたら良いのか分からなかったので、普通に銀行で書くサインを書いてしまった。コンサート会場に入って見るとステージでは既に地元のバンドが演奏をしていた、さすがにラジオステーション主催のステージらしくかなりしっかりした作りのステージで、機材やライトも見た目にはちゃんとしたものを使用していた。観客席となるスペースはかなり広いグランドで、コンサートに来た人数が約50人と言うのは残念だったが実際は2~3000人は軽く入る会場だった。私は、QUASARの出番が来るまでキースと会場内の出店でシェパーズパイ(牛挽肉又は羊挽肉とソースの上にマッシュポテトを乗せてオーブンで焼いたもの)を食べながらパイを作った叔母さんに「これって、全く母が作ってくれたような味ですね。」とキースが話しかけているのを聞きながら、先程彼がバンドの連中に話していた、野外演奏では指が思うように動かないと言った事が気になっていた。私は、思い切って「さっきキースがみんなの前で言っていた、野外演奏では思うように指が動かないという事だけれどもうちょっと詳しく教えてくれない?」と聞いてみた。彼は、「ああ、あのことね。野外で演奏すると以外に外気が冷えているのと、風が吹いたりして手の筋肉が硬直してしまうことがあるんだ。」きーすの説明を聞きながら私は、手の甲の筋肉がミシミシと音を立てて軋んで行くのを想像していた。そうしている内に、日は暮れてきて会場内に照明の光が入るようになった。会場には先程よりも人が集まってきたようだが、依然として200人にも満たない会場は見るからにスカスカの状態であった。私自身初めての野外ステージ、自分の弾くパートは決まっていてアドリブは許されない、リズムは全て変拍子のリズムで間違えるとなかなか演奏に戻れない、一曲の演奏時間が7~8分から長いもので15~6分の曲もあり、殆どの曲はエフェクターを踏んでギターの音色を変える個所が7か所から多くて24か所もある曲を演奏すると言う全て初めての経験なので、できれば余り観客がいない方が気が楽なのは正直な気持ちだった。無論観客が多ければそれなりにエキサイティングなコンサートになり、ステージに上っている者が多くの観客からエネルギーをもらえるという利点もあるという事は後に経験をするのだが、この時はそんな余裕は全くと言って良いほど無かった。最後のバンドが演奏をしている時、我々を関係者が呼びに来ていよいよ私たちの順番がやってきた。私は、ギターとエフェクターが入っている鞄を持ってステージに向かう途中、我々とバスで一緒に乗ってきた元ギタリストの仲間が後から追いかけてきて私の荷物を持ちたいと言い出した。私は、今までと打って変わったこの態度が少々気味が悪かったが、別に断る理由もなかったので鞄を渡して持ってもらうことにした。この時の一瞬の気味の悪さという感覚が、後でステージで演奏している時に事件として自分に返ってくる事になろうとは、私は夢にも思わなかった。
2012年12月23日
コメント(2)
-
ロンドンでの体験その2 プログレバンド その10
ノーフォークの野外フェスティバルに参加する日の朝、我々はキースの家に集まりバンドのバスに機材を乗せて会場まで行くことになっていた。このバスは以前にも見せてもらったことがあるが、お世辞にもツアーバスと言える代物ではない古ぼけた観光バスを改良してベッドと椅子机が備え付けられている。以前のバンドメンバーはこのバスで国中をツアーして回っていたらしいが、私が見た限りその車体は既に限界に来ていた。それでも、我々バンドメンバーやキースのガールフレンドそして私が入るまでギタリストだった元メンバー、そしてそのギタリストの友達件取り巻きが3人バスに乗り込んできた。キースが運転して総勢10人を乗せたこのバスは一路ノーフォークを目指して走り始めた。この元ギタリストの友達らしき3人、特にその中のボブと言う筋肉隆々の若者は、私がこの元ギタリストの代わりにQUASARに入ったことが気に食わないらしくこの道中で何かと私に突っかかってきた。私は最初は受け流していたのだが、そのうちに面倒くさくなり何となく力自慢らしい彼を冷かしてみたくなり、腕相撲の姿勢を取ると運転しているキースが「いいぞとっち!ボブをやっつけてやれ!」等とけしかけるのでみんなの注目の的になってしまった。私は、筋肉隆々のボブを見て最初から勝てるとは思わなかったが、成行き上みんなの見ている前で腕相撲の試合と相成ってしまった。この腕相撲と言うものは、最初に相手の腕を掴むと大体相手の力が分かり自分が勝つか負けるか即判断が付く物なのだが、この場合は何故か分からなかった。ボブは見かけは私の2倍位の隆々とした筋肉だが、彼の腕を握って見ると以外にもそれ程強そうには思えなかった。案の定初めの合図で力を入れると、腕はどちらにも倒れずに暫く真っ直ぐ立っているのだが、ボブは如何にもこんなもの軽い軽いという感じで見栄を張っているが目は笑っていなかった。(笑)暫くして私が渾身の力を入れようとすると、何を思ったか彼は自分の肘を周りに見えないように浮かして私の腕を巻き込んで倒してしまった。私は、「Cheating!(チーティング:反則だ)」と言うと「What!What?What did I do」(なんだ!なんだ!俺が何をした?)と言ってごまかし「そんなに言うなら、もう一度やろう!」とは決して言わなかった。そうしている内にバスのエンジンが急に止まってしまい、キースはバスを道の脇に止め車のエンジンを点検しながら修理をし出したのだった。その場所は、両側が植林されている田舎の国道の一本道で周りには全く何もなく便りはキースのエンジニアとしての能力だけだった。キーズは、こういうことに慣れているらしく小一時間も過ぎた頃にはエンジンを治してバスは再びコンサート会場に向かって走り出した。キースは再びバスを運転をしながら、「このバスは多分もう限界にきているので、これからは別の機材運搬用のトラックを見つけなければならないなあ。」と誰に言うともなく呟いていた。そうしている内にバスはコンサート会場のある野外のフィールドに入っていった。
2012年12月22日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験その2 プログレバンド その9
ある日私は、いつもの様に愛車(ホンダアコード1300CC程の中古だったと思う)でバンドの練習の為に当時スタジオのあったCLERKENWELL(クラーケンウエル:地図的にはロンドンの金融街:シティ・オブ・ロンドンにあるセントポール大聖堂から北西に車で5分程上ったところ)に向かった。この地域は、昼間は道路に市場が開かれているので賑わっているのだがバンドの練習がある18時頃には市場も終わり、既に屋台はたたまれていてその周辺には破れた新聞の端キレやら野菜の屑やらが一面に散乱していた。私は、車を駐車すると足早にその一角の中でも特に古いレンガ造りの建物に入り、長い廊下を反対側まで歩いた。そこから階段で地下に降りると、そこには私が最初にオーディションを受けたあのスタジオがあり、バンドはそこに常時楽器や機材をセッティングしてあり週に3~4回程あつまり練習をしていた。この頃は私もバンド練習に大分慣れてきて、あの難しいと思われた曲も卒無く弾ける様になってきていた。その日練習の合間の休憩時間に私は、キーボードのスティーブと一緒にフィッシュ・アンド・チップスの店で食べ物が出来るのを待っていると、スティーブが私の方を向いて「俺さ、とっちがバンドに入ってくれて良かったと思っているよ。これでバンドの足を引っ張る奴はいないからな。」と意味深な言い方をした。私は、訳が分からずに「ありがとう!」と返事をした。いつもは、ハンサムなのだが少々シニカルで神経質なあまり物を言わない彼が、この時はその素直な一面を一瞬私に見せたような気がした。スタジオに戻るとキースは我々一同を集めて「今度、NORFOLK(ノーフォーク:ロンドンから北東に車で2~3時間程行ったところ)の野外コンサートのメインとして我々QUASARがノーフォークのラジオステーションから招待を受けた。」と話し始めた。「初めてのコンサートが野外と言うのもちょっと大変だが、めったに経験できるものでは無いので出演した方が良いと思うけれど、みんなはどう思う?」キースはさらに「私が思うに、バンドは、ほぼ完成状態なので後はコンサートの場数を踏んで慣れて行く事だと思う。」と付け加えた。他の3人もみんな参加をすることに賛成したので、私がとやかくいう事ではないと思い私も賛成した。キースは「わかった。それじゃあ参加という事で返事をしておく。ここでみんなに言っておきたいことがあるけれど、いいかな?私は、みんなにQUASARのメンバーとして誇りと自信を持ってほしいと思う。QUASARは、他のミュージシャンが興味を持って見に来るほどのテクニカルな音楽を演奏している事を自負をして欲しい。わかったか?ではがんばろう!」と言うようなことを述べた。キースがこのようなスピーチをしたのは、後にも先にもこれ一回のみだけだったが、QUASARのメンバーとして結構自信を付けられたように思った。その日私は家に帰り、家の共同の入口ホールに一通の私宛の郵便物を見つけた。それは、失業保険からの支払いの小切手だった。私は、これでようやくバンドが軌道に乗るまでの金銭的な保証ができたという安心感と、QUASARで初めて演奏するそれも野外でという期待と不安が入り混じった気持ちでその夜を過ごした。
2012年12月21日
コメント(2)
-
ロンドンでの体験 その2 プログレバンド その8
さてバンドに入ったのはもちろん良かったのだが、まずはバンドに入ったことを私の会社の雇い主に報告をしないといけない。私は、会社に戻ってバンドのオーディションに受かったことを報告すると、残念ながら雇い主からは「それでは、仕事を辞めてもらうしかない。」という当然の言葉が返ってきた。私はそれまで会社の事務所兼アパートに住んでいたので、仕事をしなくなれば当然会社の事務所に住む権利を失う事となり、早速住む部屋を探さなくてはならなくなった。。今思うと、その時の私は入りたいバンドに入って音楽ができるという事だけで有頂天になり、仕事や住む場所を無くしたこと事態は正直言って大した打撃では無いと思っていた。コマーシャルのコーディネーターという仕事は面白い仕事であり、私にとって長年に渡りイギリスでの唯一の収入源だったのだが、この時の私は音楽をやりたいという願望の方が勝っていたらしい。(笑)早速私はLOOTという貸物件が載っている情報誌(新聞)を買い、貸物件を探してひたすらロンドンを走り回った。かなりの物件を探し回った後、私はロンドンの北部にあるマズウェル・ヒル(MUSWELL HILL)という地域の物件が載っていたのを見つけて出かけてみた。私は、このマズウェル・ヒルと言う地域に行ってみて、その丘から見降ろすロンドンの風景に一目で魅了された。丘の頂上を走るブロードウエイという大通りから、物件のある通りに下ると前方にはロンドンの街が一望に見渡せる壮観な眺めが広がり、その光景を見ていると何とも言えない清々しい気持ちになったものであった。その部屋は建物の2階にある20畳程の一部屋で、部屋を出てすぐ左側には20畳ほどの共同の台所があり、そこで料理や食事ができるようになっていた。私は、この物件がすぐ気に入りそのまま即エージェントに紹介料と月々の家賃の引き落としの手続きをしに行き、その日の内に部屋に入れる手配をしてもらった。同時に暫く仕事が無くなるので失業保険の申請をしに所定の事務所に行き、生活の金銭的援助を受ける手続きを済ませた。住むところが決まった私は早速コーディネーターの会社の事務所から自分の荷物を運び出し、長年親しんだケンジントン地域に別れを告げマズウェル・ヒルでの新しい生活を開始したのだった。それからの私の新しい日課は、週に3~4回のバンドのリハーサルとキースから他のQUASARの楽曲の伝授そして師匠のウィンストンに会に行ったり、友達とジャムセッションをしたりと何かと忙しい日々を過ごしていた。そんな毎日を過ごしていると時間の経つのは早いもので、気がつくとあっという間に3~4か月が過ぎ、その内に私の生活にある心配事が浮上して来て毎日を不安な気持ちで過ごす事になって行った。それは今まで仕事で貯めていた貯金が底をついて来ていて、気が付くと翌月の部屋代を払える金額がもう銀行に残っていないことだった。勿論この件は以前から気にはなっていたのだが、失業保険の手続きをした時に事務所の人から今までの仕事の経歴から見て援助を受けることは問題ないと言われて手放しで安心していたこともある。只私は、この書類の審査にどれだけ時間がかかるのかを甘く見ていたようだった。役所の仕事はどの国も時間がかかるらしいとは聞いていたが、イギリスのお役所の仕事はそれに輪をかけて時間がかかるらしかった。この審査さえ通れば部屋代と食事代は何とか保障されて、バンドが活動をするまで生活は安定する。私は、翌月の部屋代の支払いが銀行から自動引き落としになる日にちが迫る中、不安の胸中で手の中に残っている最後の全財産約50ポンド(約一万円)を握りしめていた。
2012年12月17日
コメント(4)
-
ロンドンでの体験 その2 プログレバンド その7
スタジオの中に入ると、そこにはキース、ドラムのデイブそしてキーボードのスティーブがそれぞれの楽器の前で談笑していた。私は、バンドのメンバーに挨拶をした後に持ってきたギターのケースを開き音出しの準備を始めた。部屋の中には、もう一人金髪の若い女性がいたのだが私は初対面なので挨拶は控えていたのだが、彼女は準備をしている私の所に来て「Hi!Nice to meet you. I'm Tracy」(ハーイ、初めまして、トレーシーです。)と挨拶をしてきた。私は、彼女が何者かわからないまま挨拶を交わし再びギター準備を始めた。私の準備ができると、キースが他のメンバーに合図をしてSeeing Stars Part2のイントロが始まった。私は、一年前にバンドで合わせた時とは違い、曲を熟知していたので演奏をしていて非常に楽しかった。演奏が終わるとキースは他のメンバーに「How was it?」(どうだった?)と演奏の感想を聞くとデイブは「Yah!It's OK,I guess」(ああ、いいんじゃない?と思うよ。)スティーブは「It bites!」(若者言葉では最悪だという意味でよく使われるのだが、彼のこの時の意味はお互いの楽器がかみ合うという意味で使われたのだと思う)するとキースは「OK,it's done then!」(オーケーこれで決まったな!)と言うと先程私に挨拶してきた女性に向かって「OK、Trace!This is it! Would you like to join us?」(オーケー、トレース!(トレーシーの愛称)これがバンドだ。参加する?)と聞くとトレーシーは「ええ、もちろん!」と返事をした。この瞬間私は、これが実質私の最終オーディションだった事、そして今私がQUASARのギタリストとして正式に受け入れられたことに初めて気が付いた。
2012年12月16日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド その6
キースと付き合い始めてから約一年が経った頃だったと思う。その頃私は、労働許可証の5年間を経て遂に念願のイギリス永住権を取得していた。その日私は、いつもの様にCMコーディネーターの会社に顔を出すと、会社の人から「とっち、キースという人から電話があったよ。」と声をかけられた。そこでキースに電話をしてみると、「ああ、実は今度バンドのギタリストが辞めることになってね。とっちが興味あるかと思って電話をしたんだ。」と話してくれた。私は「わかった!俺がやるから、そのポジションを他の奴にやらないで取っておいてくれ」と言ってすぐさまギターを持ってキースの家に行った。キースは、私がギターを持って家に入ると私に一年ほど前にやったオーデションの時のあの曲「Seeing Stars Part2」の続きを教え始めた。曲の構成、メロディやコード等、キースは今までバンドのギタリストに遠慮をしていたせいもあったのだろう、私には今まで話にさえ出した事も無かった。それからは暫くキースの家でQUASARの曲の講習を受け、家に帰ってそれを練習する日々が続いた。最初は、このバンドの曲(変拍子主体の曲)が自分自身弾くことができるか不安だったが、練習するに連れて「やれば出来るものなんだ!」という確信が持てるようになってきた。ある日私はキースに、ノーミスと言うリハーサルスタジオに来るように言われオリンピアと言う地域のの裏に行ってみた。ノーミスは、大きなオリンピア展示場の裏にある閑静な住宅地の中に余り目立たない様に建っていた。入口の受付でバンド名を言うと、部屋の位置と番号を教えてくれた。受付から中に入ると、まず黒塗りの箱にBAD COMPANYと白いペンキで書かれた木のケースが無造作に置かれていたり、何やら真っ白なセーターに白いズボンを履いた人がどこかで見たことがあると思えば、WHOのヴォーカルのロジャー・ダルトレイだったりなんかいきなり別世界に紛れ込んだ様だった。後で聞いた話だが、このリハーサルスタジオはかなり有名なところで、LED ZEPPELINの様な有名バンドもリハーサルに使っているところらしかった。私は、教えてもらった部屋の所まで行くとスタジオの重いドアを開け中に入って行った。
2012年12月15日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド 続き その5
キースの家に出入りするようになってからは、とにかく色んな人たちに会うようになった。当時、キースにはオーストラリア出身のメアリーアンというシンガーソングライターの彼女が一緒に住んでいて彼女のバンドメンバーや知り合いも出入りをするという大所帯だったが、家の間取りは12畳程の居間とベッドルームと6畳程の縦長のワークショップ、そして6畳程の台所とバス・トイレという間取りでメアリーアンの友達が来ているときは、私とキースはワークショップの部屋に入って彼のコンピューターで音楽を作る作業を見ながら話をするという日常が続いた。彼は、私に今までのQUASARの活動経過やバンドの批評が書いてある雑誌、そしてバンドのテープ(当時はカセットテープが主体だった。このテープにはあのFANFAREという曲も入っていたりライブの音源なども入っていた。)それから彼は自分で作成したバンドのポスターなどもくれたりした。キースがくれたバンドの経歴を見るとQUASARというバンドは、1979年に結成されて以来ロンドンの登竜門であるMARQUEEというコンサート会場でHeadline(ヘッドライン:メインアクト)を務めたこともあり、同じバンドサークルにはMARILLION(マリリオン)、PENDRAGON(ペンドラゴン)、PALLAS(パラス)、IQ(アイキュー)、TWELFTH NIGHT(トゥレフス・ナイト:シェークスピアの喜劇12夜からとった名前らしい)、SOLSTICE(ソルスティス:至る‐例Summer Solstice:夏至)等といういかにもプログレらしい名前のバンドがあげられる。ちなみに、私がバンドに入る数年前までは、このSOLSTICEというバンドのヴォーカルだったSUSAN ROBINSONがQUASARのヴォーカルだったように、お互いのメンバーがそれぞれのバンドを動いていたことも有る様にサークル内の活動は流動的だったようだ。例えば、この中のバンドがMARQUEEで演奏する時は他のバンドのメンバーが見に来ているなどのお互いの情報交換も頻繁になされていたようだった。ちなみにこれは、1985年にこれらのバンドがEMIより発売された「FIRE IN HERMONY」というコンピレーションアルバムでも、楽曲を持ち寄りお互いの力を合わせプログレを盛り上げようという動きが現れていたと思う。ある時、キースから「今度パットニーのハーフ・ムーンというVENUE(ベニュー:会場)でQuasarのコンサートがあるんだけれど来てみる?来るんだったら招待客名簿に名前を載せておくから」と誘われた。私は、あのアルバムをバンドがどうやって演奏するのかを見たかったので行ってみることにした。当日、バンドのコンサートが始まると会場にはVANGELIS(ギリシャの作曲者コンポーザー)のHEAVEN AND HELLの序曲が静かに流れ、それが終わるとQUASARの演奏が始まった。その演奏を聴きながら私は「このバンドでいつか演奏をしてみたい!」と強く感じた感覚は、今でも昨日の事の様に覚えている。
2012年12月14日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド 続き その4
オーディションの後2~3日してからキースに電話をしてみると、やはり遊びにおいでと誘ってくれるので彼が住んでいるところがどんな所なのか興味もあり行ってみる事にした。電話で教えてくれた彼の住所は、East End(イーストエンド)のDocklands(ドックランズ)という地域で、現在は高層ビルがたくさん並んでいるが私が最初に行った頃は再開発途上地域で、まだまだ、貧しくそして場所によっては結構危険な地域だった。キースが住んでいたところは、この地域にあるCouncil Flat(カウンシル・フラット:公営住宅)の21階だった。ロンドンは、当時高いビルはデビル(悪魔)が住むものと言って特に年配の人たちは住みたがらないらしいが、キース曰くドックランドで当時行われたジョン・ミッシェル・ジャー(当時有名だったフランスのキーボード奏者)などのコンサートは無料で見れる等の特典があったらしい。これは余談だが、公営アパートの不便なところは各アパートに2基付いているエレベーターが頻繁に故障をする。これは、ここに住んでいる家族の子供たちが落書きや悪戯をするかららしいが、役所もあまり頻繁に壊れるのでなかなか手が回らないらしかった。私もバンドに参加した後に何回かエレーベーターが動かないことがあり、階段で21階まで上る事が何回かあったが、この時ばかりは年配の人たちの言葉(高いビルは悪魔が住むところ)という意味を痛感したものだった。話を元に戻すことにしよう、キースが住んでいる建物に着いて私がタワーの(公営アパート)入口のベルを鳴らすと、彼がインターホンに出てきて、「入口を入ってエレベーターで21階まで上がって。」と言いと入口のドアの鍵を解除するブザーがなった。私は、ドアを押し開けて中に入るとその建物のホールは閑散としていて、壁には落書き床には新聞や雑誌の切れ端が散乱していた。前方には全体がアルミ箔をくしゃくしゃにしたようなデザインのエレベータ(ところどころが人為的に陥没している)があり、それに乗ってがたがたと不安な音を立てながら21階に上がった。エレベータを出ると正面にはドアを開けながらキースが待っていた。彼は、私を家に招き入れて白木で作られた頑丈そうなドアを閉めながら、「以前のドアは弱すぎて泥棒が蹴破って入ったので、最近防犯の為にこの分厚いドアに変えたんだ」と説明をしながら、私を奥のリヴィング(居間)に招き入れた。「Well,TEA!」(それじゃあ、紅茶にしようか?)と聞かれた私は「Yes,Please!」(お願いします)と答えた。ここで彼の住んでいる状況を説明すると、当時ミュージシャンや絵描き等下積みをしている人たちは殆どがこの様な公営住宅や倉庫等を利用して活動することがTRENDY(トレンディ:流行)だった。後にバンドに入ってから知った事だが、キースは結構裕福な家に生まれているらしく学校はパブリックスクール(名前はPublicだが、イギリスでは中高一貫の私立学校で、入学するのには頭が良くて家もかなり金持ちではないと入れないらしい、ちなみにアメリカではその名の通り公立学校という意味)を出ているらしかった。私たちは、紅茶(イギリスの場合紅茶というと必ずと言っていいほどにミルクティーで殆どがティーバッグを使用してかなり濃く出した紅茶とミルクを入れるが、そのティーバッグも日本の約3倍位は入っている大きなものである。)を飲みながら話をしたのだが、何せ30年近くも前の出来事であるのと、この後何回もキースと会っているので正直この時の会話は何を話したのかは覚えていない。今思い返すと、Quasarに入る前のこの時期が私にとってはキースとの一番楽しい時間だったように思える。
2012年12月13日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド 続き 3
オーデションも終わり、どうやら私が一番最後のギタリストだったらしい。彼らは、スタジオの楽器を片づけ始めた、メンバーの話によると当時EMIから新しいUKプログレバンドを紹介するアルバムを作成中で、彼らも1曲提出しなくてはならないので、その録音の為にスタジオを移動しなくてはならないらしい。楽器を片づけている彼らと雑談をしながら、私の頭にはある心配事が引っかかっていて、どうしても帰る前にはっきりと彼らに伝えようと思っていることがあった。前回の日記の最後に「私がオーデションで弾いた曲のタイトルが分かったのは随分後になってからだった」と記述したが、実はこれには私の労働許可書の問題が拘っていた。当時UK(United Kingdom)は、労働許可書を受理してから5年間はその職場で働くと永住権が申請できる。この永住権を受理してからは、私が何の仕事に就こうが自由になるのだが、私がQUASARのオーディションに行ったときはまだ労働許可書が下りてちょうど4年目で、自由に仕事を選べるようになるには後1年の労働実績が必要だった。私は、隠しておく必要はないと思っていたので、バンドのメンバーの前でキースにそのことを正直に話すことにした。キースは、「そうか、残念だけれど、我々はミュージシャンのユニオンに属している手前、まだ君をバンドに入れることはできない。」と言った後、「来年ならどこでも働けるんだろう?だったらまたオーディションにおいでよ!」と言葉を繋げた。私は、来年になってまたバンドのメンバー募集なんて虫の良い話は信じないので、早くうちに帰ろうと思いながら「All right!」と気のない返事をしたように思う。彼は、「そうだ、せっかくこうやって会えたんだから家に遊びにおいでよ!家に出入りをしていればバンドの様子もわかるし、メンバー募集の時もいち早くわかるだろう?」と言ってこの間電話をくれた番号に電話して遊びにおいでと誘ってくれた。バンドには入れなかったが、何となくこの時がイギリスのロック音楽業界のアングラ(アンダー・グラウンド)と呼んで良いものかどうかは分からないが、そのようなカテゴリーの世界に一歩足を踏み入れた時だったのかもしれない。
2012年12月11日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 プログレバンド 続きその2
先程スタジオのドアを勢いよく開けて出てきたキースとは打って変わり、彼は私にやさしい声で挨拶をしてから椅子に座り(正直言ってこの時彼と何を話したかは全く覚えていない)傍らに立てかけてあった12弦ギターを手に取ると、「私が弾くように弾いてくれる?」と言ってマイナーコードのアルペジオをワンフレーズ弾いた。私が同じように弾くと「いいね。じゃあ次はこれね」と言ってワンフレーズごとにコードを弾いていくのを同じように弾いてついていって、しばらくするとその曲の区切りらしいところまで辿り着いた。キースが「それじゃ、ここまで合わせてみよう」と言うとドラマーとキーボードが入って来た。「僕が、君が入るところに来たら合図をするから今弾いたとおりに弾いてみて。」というなりドラマーが何ともいえない複雑なリズムを刻み始めた。次に、キーボードがシンコペーションの効いたコードをかぶせると、いつの間に持ち変えたのかキースがベースで小刻みなそして別のシンコペーションの入ったフレーズを弾きだした。私は、ぞの複雑なリズムが描き出すサウンドの渦の中でしばし我を忘れて聞き惚れていると、キーズがここだと言わんばかりに頷きながらベースの高音部に指を走らせていった。私は、この初めて体験するリズムを体で拍子を取りながら先ほど教わったコードを弾きだした。初めてなので何となくぎこちない所はあるのだが、こんな感じなのだろうという感覚はつかめた。教わったところまで演奏が終わると演奏をストップして、キーズは「ここまで演奏ができたのは君が初めてだ。」と嬉しそうに話しかけてきた。私は、後にこの曲がSeeing Stars Part2という曲の冒頭の部分であることを知るのだが、残念ながらそれはかなり後になってからだった。
2012年12月10日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンド 続き1
以前にも私がQuasarに入る過程を書いたことがあった。初めてこのバンドのFANFARE:http://quasar.netne.net/noflash.html→Studio CD→Fire in the sky→Fanfareという曲を聴いたときは正直言って「失礼しました。」と会場を出ていきそうになった。その時、私はオーディションの順番待ちで何人かのギタリストたちとスタジオの外でドラマーのデイブがバンドの音楽を聴かせてくれたのだが、この曲を聴いた私の感想は「自分に弾くことができるだろうか?」という疑問だった。加えてその時、スタジオのドアを蹴破るように勢いよく開けて出てきた背の高いイギリス人が吐き出すように「全く、何にも弾けないじゃないか!!!」と呻いたときは本当に逃げ出したかった。残念ながら、これがキース・ターナーと私の最初の出会いだった。私は、逃げ出したい気持ちを抑えて何とか自分のオーディションの番まで持ちこたえて、スタジオの中に入るとそこにはオーディションを終えたギタリストがギターをケースにしまっていた。私は、彼に挨拶をすると彼は「君は何歳?」と率直な質問をしてきた。私は、「32」と答えると彼は驚いた顔をして私に「君はラッキーだね。」と付け加えた。私は彼に「君はいくつ?」と聞き返すと彼は、23歳のウエールズ人でこのオーディションの為に遥々ウエールズから電車で出て来たと教えてくれた。彼は、「グッドラック!」と言ってスタジオから出て行った。私は、ギターをアンプとエフェクターに差し込むと自分の番を待った。暫くすると先ほどスタジオから飛び出してきた彼が入ってきた。いよいよ私の番である。私は、自分の背中に冷たい汗が落ちるのを感じながら「ハーイ!」と彼に挨拶をした。
2012年12月08日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その2 プログレバンドQUASARとの出会い
私がロンドンに住んでいて楽しかったのは、やはり音楽活動をしていた時だったと思う。最初は、右も左もわからないまま知り合いの日本人ミュージシャンにくっ付いていたのだが、今になって思えばこの時に結構いろんなことを学んだような気がする。当時、自宅で音楽を作るなど考えてもみなかったので、ベイズウォーター駅付近に住んでいる日本人ミュージシャンのフラット(アパート)に行くのがとても楽しかった。ここには、クールなジャズギタリストの大ちゃんやブルーズロックギタリストで作曲家のゼロ、そしてそこには、マジシャンやいろいろな人たちが出入りしていた。私は、そこで作られたジャズ系の曲のサイドギターを録音したりして遊んで貰っていた。今思えば、私はこの時に自宅で録音をするという事を大分学ばせて貰ったような気がする。ある日、私が簡単なコードで歌を作りゼロに聞かせたところ録音しようという事になった。楽器類はヘッドフォンで聞きながら録音すればよいのだが、歌の段階になると防音設備のない普通のアパートで近所から文句が出ない訳がない。案の定、近くの部屋に住む大柄の中近東の叔母さんが文句を言いに来た。それに対抗したゼロは、あれだけまくし立てていた彼女を言い負かせてしまい、再び何事もなかったかのように録音を開始した。この時のことは、ロンドンに住み始めてまだ日が浅かったこともあり結構びっくりしたので、今でも鮮明に覚えている。結局この時代の彼らとの経験が、私を自然に音楽に向けた様に思える。それから何年かして大ちゃんは日本に帰り、ゼロはフランスに行き私は一人ロンドンに残った。私はなけなしの金を叩き4チャンネルの録音機を買い、一人でドラムやベースを録音し曲を作る毎日に明け暮れていた。私は、曲を作るために何回何回も同じフレーズを間違えないように弾いて録音していたことが、結果的にギターの上達につながったように思える。私は、同様にこの時期に友達からコマーシャルのコーディネーターにならないか?と誘われ、幸運にも仕事と労働許可書を2つとも手に入れる事になる。このコーディネーターという仕事は私に大変都合が良く、仕事が始まると3週間ほど時間を拘束されるのだが、それ以外は全く自由な時間を持てるのが嬉しかった。しばらくしてコーディネーターの仕事に慣れた頃、私は当時ニュー・ミュージカル・エクスプレス(だったと思う)という新聞の後ろのページに掲載している、ギタリスト・ウォンテッド(ギタリスト募集)というコラムを見てオーディションに行くようになっていた。最初は応募先に電話をして名前を伝えると、何処から来たの?と聞くので日本と言った途端に断ろうとする相手を説き伏せ、実際そのオーディションに行ってみるとこちらからお断りのバンドだったり、音楽はそっちのけで私に化粧をさせようとしたり、ギターの用意ができるとキーもコードも教えずにいきなりフュージョン系の演奏をして優越感に浸っている嫌味なバンドもあった。ちなみにこのバンドのボーカルは黒人女性なのだが、私の後の黒人ギタリストには懇切丁寧にキーとコードを教えていた。まあこんな風にいろいろなオーディションに行ってみたのだが、中には以前書いたこともあるピーターのような素晴らしいミュージシャンにも会えたのだから、まんざら悪い経験でもなかったように思える。ある日いつものように新聞のコラムを見ていると、ギタリスト求むUKプログレッシブ・ロックバンドという文字が目に入った。プログレ音楽が好きな私は、すぐにそこに書いてある連絡先に電話をしてみると非常に落ち着いた感じの声のイギリス人らしき人物が電話に出できた。私は、新聞のギタリスト募集の広告を見たんですが、オーディションを受けるにはどうしたらいいのでしょうか?と聞くと、彼は「僕らはプログレッシブ・ロックだけどいいの?良いんだったら何月何日の何時にクラーケンウエルの何番に来てくれる?じゃ待ってるから」と余り感情のない声で言った。「あっ、それから僕らのバンドの名前はクエイザー(QUASAR)って言うんだ。じゃ後でね。」と言って電話を切った。これが、クエイザーのバンドリーダーであるキース・ターナーとの最初の会話だった。
2012年12月04日
コメント(2)
-
ロンドンでの経験 その1 1980年代初期のロンドン
つい最近職場の人と話をしていて、イギリスから日本に帰ってきて早4年が過ぎたことに気が付き、本当に月日の経つのが早いことを実感している。今まで約30年近く住んでいたイギリスは、私にとってすごくエキサイティングでいろんな意味で勉強になった反面、数々の悪い経験もした。まあ、それも今になって思えばいろんな意味で勉強になったと思っている。音楽はもちろんのこと、BBCのドキュメンタリーを見ているだけでも、深く考えさせられる若者の麻薬問題(これは多分今でも変わらないとは思うが、1980年代当時とても深刻でテレビで良く取り上げられた問題だった。)や、はっとさせられるほどの色彩や何年も月日をかけて撮影された珍しい動物や昆虫そして植物などの生態の映像などなど、単に見ているだけではなくそれを見ている自分もさらに詳しく勉強したくなるような、そんな気にさせる番組が多かった。日本のテレビはそれなりに見ていて面白いのだが、考えさせられる番組というのが大変少ないのに気が付く、幾つかの優れた番組を除いてはトークショーやクイズ番組それなりに面白く作っているのだが、見ている我々は何も考える必要がない、クイズショーなどは確かに知識の面では広がるとは思うが殆どの題材は我々の日常には何の役にもたたない題材が多い。もう少しテレビを見ている側のことを考えてくれると、日常必要な知識やそれに関連した面白いプログラムができるのではないだろうか?そうすれば既にインターネットに移行してしまった視聴者もテレビに戻ってくるようになるかもしれない等と考えていると、話が大分横道にそれてしまった(笑)。さて1980年代初期のロンドンに戻ってみる、当時ロンドン市内のパブではバンドが演奏している場所が多く、ウエスト・ケンジントンの角にあるパブにポリスが出るらしいとか、ロンドンのバンド登竜門のマーキーでは、アイアン・メイデンというディープ・パープルをさらに加速したバンドが出ているとか、テレビではトップオフポップスでユーリズミックスが出てきたり、カルチャークラブがチャートを駆け上がったりトンプソン・ツインズやペットショップ・ボーイズ,スタイル・カウンシルやキュアー、ヘアーカット100やキュリオシティー・キル・ザ・キャットそしてデュランデュランやワム等々とロンドンの音楽市場は大変にぎわっていた。私は1970年代のバンドが好きだったので、当時はなんで1970年にロンドンにいなかったのだろうと嘆いていたのだが、今振り返ってみると1980年代もなかなか面白かったと思える。以前にも書いたことがあるが、1980年代初期の私は髪の毛を長くしていた事もあり、私服の刑事に職務質問をされたり鞄の中を探られたりする経験が少なからずあった。当時、ロンドンで東洋人が長い髪でいると何かと問題に巻き込まれやすいのか、アールズコート駅で5~6人の私服の刑事に取り囲まれたり、セントラルラインに乗っていて若い黒人の男が私の横に座ったかと思うと、すぐ立ち上がって歩いて行った後を見ると何かしら怪しい包み紙が隣に置いてあったり(勿論これは、後から追いかけてきた私服の刑事が持って行ったが)と何かと問題に巻き込まれる反面、当時黒系の洋服を好んで着ていたこともあり、ある時イタリアのレストランから出てきたイタリア人の小学生団体から「ブルース・リーだ!」と指を差される光栄な一時や、電車の中で3人組のティーンエージャーに絡まれそうになったりしても怖がりさえしなければ、その風貌から(東洋人で髪が長い、笑)相手の方が怖がって行ってしまう等とラッキーな助かり方をした経験もあった。
2012年12月01日
コメント(2)
-
ロンドンの生活と出会った人達(ニュージーランド生まれのコリン)
コリンに会ったのは、以前私の話にも出ていた語学学校の友人で香港から来た中国人ポール・サイミンの紹介だった。彼は、ニュージーランド生まれの中国人だ。ポールに言わせるとコリンは、生まれも育ちもニュージーランドの為に中国語はできないらしい。彼は、明るく躍動的なポールと比べるとコリンは年齢も上だし、私の目には穏やかでとても落ち着いて見える。何がそして誰が彼をここまで大人に育てたのかは解らないが、彼と居ると何故か気持ちが落ち着いて穏やかな気分になる不思議な魅力を持った人だった。コリンは、私に彼の発音がNative English(英語を母国語とする人)である為に「電話で話した後にその人と会ったりすると、私が中国人なの皆すごく驚くんだ。」と楽しそうに話していた事があった。ポールはと言うと、コリンのことを「中国人なのに中国語を話せないなんて。」と少々見下した感じで話していたことがある。これは、コリンの英語がNativeな為にポールが彼に少々嫉妬をした事で思わず出てしまった言葉だったのかは定かではない。このような事が直接の原因ではないとは思うが、我々三人が一緒に会うことは次第に減って行き結果的にポールとコリントは別々に会うようになっていった。ポールとは学生仲間なので、主に語学学校の中や学校がひけた後クラスメートや先生達と食事や遊びに行ったりする事が多く。コリンはというと、学生ではないのは解るが彼がどこでどんな仕事をしているのかも皆目解らない、いつもかなり古いブリティッシュ・フォード(英国フォード社)の乗用車に乗って夜遅く遊びに来ては、私をドライブに誘ってくれるといった感じだった。彼と行くところはCouncil Flat(カウンシル・フラット:公営住宅)等が多く、通常なら昼間でも近寄らない結構危なさそうなところが多かった。私は、目的地の近くの大通りに停められた車の中で音楽でも聴きながら待っているだけでコリンは15分~30分で用事を済まし車に戻ってくる。その後は、またドライブをして別の場所に移動をするといった具合である。彼と一緒に行ったところの何世帯かは家の中に入った事はあるが、彼はどうやってこんな色々な人達と知り合ったのだろう?と自然な疑問が湧くほど多種多様な人達だった。大学の寮に入っている中国人(これは解る)、首から数珠を掛けているイギリス人そしてミュージシャンや一見大道芸人風な人達など結構怪しげな人達も多かった。コリンのもう一つの特技は車の修理で、ドライブの途中で車が動かなくなった事があったが、かなり難しい故障でも2~3時間で直してしまった。どこでこんな事を覚えたか聞いてみると、ニュージーランドに限らず西洋では車の修理屋が頼りにならないので、若い時代に車を直す事を覚える人が多いらしい。そんなある日、彼は私の家に遊びに来ていつものようにドライブに誘う雰囲気でもなく椅子に座って雑談をしていた。コリンは、「突然なんだけどさ、とっち。俺、来週ニュージーランドに帰る事に決めたんだ。」と私に話を切り出した。私は「何かあったのかい?どうして急に決めたの?」みたいな事を聞き返したと思う。すると彼は「俺は、今まで同じところに長くは留まったことは無いんだ。ロンドンは居心地が良い分長居をしてしまったのだが、また旅に出たいと思う気持ちが強くなってきた。」みたいな事を話し出した。私は「飛行機の切符はもう買ったのか?」と聞くと、彼は楽しそうに「車で国境を越えながらニュージーランドまで帰る事にしたんだ。」と答えた。私には、この無謀なチャレンジとも言えるロンドンからあのオンボロ車(失礼)でニュージーランドまで運転をして帰るというコリンの計画は、当時想像もつかなかった。今から十数年前に、ねこ丸(嫁さん)から深夜特急という大沢たかお主演のテレビドラマを見たとき、その中で途中で知り合ったオーストラリア人のバックパッカーから3~5年かけて旅行をしているとか、主人公の大沢たかおが日本から乗り合いバスでロンドンまで旅行をするといったドラマを見たときに、コリンは30年前のあの時点でやろうとしていたんだと言う事がはっきりとわかった。彼は、その夜かなり遅くまで私と話をしてから、お別れを言って帰っていった。ポールの話では、コリンは翌週元気でニュージーランドに旅立ったそうで私にくれぐれもよろしくと言っていたようだ。彼とは住所も交わしていなかったし、もちろん手紙など来る事も無かったが帰る途中で仕事をしながらゆっくりと帰国しているコリンの姿を、あの深夜特急のシーンとダブらせながら時折想像してみたりもした。ひょっとしたら彼は途中で誰かと知り合って、未だに家に帰っていないのかも知れないと思う時もある。でも、まあそれはそれで幸せな事だろうと思う。
2011年07月05日
コメント(0)
-
ロンドンで出遭った人達(ジョン・バレット)
人の出会いとは意外に曖昧なもので、気がついたら知り合いに、あるいは友達だったということも間々あることである。当時、スタジオエンジニアだったジョン・バレットとの出会いもそんな感じで、彼とはどういう関係でいつどこで出会ったのか全く記憶が無いが、気がついたら知り合いになっていた。彼は、エンジニアはエンジニアでも、あのビートルズで有名なアビーロード・スタジオの録音エンジニアで、それまでそんなことを億尾にも出さない彼に私は本当なのかどうか聞いてみた。彼は「ああ、そうなんだ。知らなかった?今度案内してあげようか?いつが良い?」と至って気軽にあのアビーロード・スタジオに招待してくれた。私の返事はもちろん「イエス・スーン・プリーズ!(はい!近いうちに、お願いします)」である。アビーロード・スタジオはビートルズ以外でも数々の名盤を作り出してきたらしいが、私が知っている事でもう一つ有名なことがあった。それは、知る人ぞ知るあのピンクフロイドの名盤「Dark Side of the Moon(狂気)」が録音されたスタジオである。只、私にはその時彼にピンクフロイドの名前を出す事に躊躇があった。それは、ある友人の伝で、あるバンドへの誘いの電話を受けたことがあった。その電話の主は、「私は君のことを友人から聞いてオーデションに誘いたいのだけれど、君の好きなバンドの名前を教えてくれないか?」と聞いてきたので、私は胸を張って「ピンクフロイド」と答えた。すると電話の主は「ああそうなの、じゃあ我々のバンドとは趣向が違うのでだめだ」と一方的に電話を切られたことがあった。それ以来、好きなバンド名を聞かれた場合は「ああ好きなバンドね、いっぱいあってどれが一番好きなんて言えないな、君はどんなバンドが好きなの?」とまず相手の好きなバンド名を聞きだす事を学んだ。今になってみれば、自分自身あの頃の「ピンク・フロイド」に対する熱い想いが懐かしく思える。まあそんな理由もあり、私のピンクフロイドに関する当時の情熱の件は誰にも言わず、1人密かにあのアルバム「狂気」を録音したスタジオを見に行ったのである。ジョンは、アビーロードの歴史を順番に見せてくれるかのように、まず初期のミキシング機材が置いてある部屋を見せてくれた。その機材の色は、カーキ色に近かった様に覚えている、いわゆる戦時中のヘルメットや戦車の鉄板の色はこんなだったんだろうなと思わせるような色で、ダイヤル方式のつまみ自体もかなりの古さを感じさせるものだった、ミキシングデスク上の音を左右に揺さぶるパンなんかも摘みではなく立っているレバー式を左右に倒す方式で、いかにもアナログ色が満載の機材だった。また、この当時のアビーロード・スタジオの主な録音はポップ関係というよりはクラシック色の録音が盛んで、当時流行のフックト・オン・クラシック等もここの最新式のスタジオで収録されていたらしい。我々は色々な部屋を見ているうちに、かなり広めの収録部屋に行き当たった。ジョンは、「このスタジオは広いので、主にオーケストラの収録が行われる。」と説明してくれているが、私は「ここだ!」と思った。その時は、録音のついたてやその他の機材が取り払われてガラーンとした只の広い部屋だが、以前フイルムで「狂気」の録音がされているシーンを見たことがある私には、この部屋があのスタジオだということはすぐに解った。私は、1人興奮を抑えながら広いスタジオをゆっくりと歩き回った。この時ジョンは私に、当時ロンドンの音楽シーンに進出してきている新しいバンドや音楽の話を聞かせてくれていた。その筆頭は、まだ有名になる前のデュラン・デュランやグレース・ジョーンズ等のアルバムに付いて話していたのを覚えている。彼とは、その後も知り合いの日本人の家であったり、数はそれほどは多くは無かったが私の家にも時々遊びに来るようになっていた。そんなある日、私はある知り合いから、ジョンの事で大変ショックなことを聞かされた。それは、彼が末期の癌であり余命が何ヶ月も無いということであった。そのことを聞いたショックから立ち直れない数日後のある晩、彼は私の家を訪ねてきた。私は、ジョンにいつもと同じ様に振る舞っていた。すると彼は突然私に、「とっち、ちょっと相談なんだけれど。君は、僕が今付き合っている娘の事は知っているだろう?実は、その娘の他に可愛いスペイン人から告白されちゃって、困っているんだ。付き合うべきか、断るべきか迷っているんだけれど、とっちはどうしたら良いと思う?」と聞いてきた。彼が付き合っている日本人の女性は個人的には知らないが、何回か友人のところで顔を会わせた事がある程度でしか無かった。ジョンは、金髪で青い目の見てくれの良い好青年で性格も穏やかな事もあり、実際女性にはかなり持てると思う。私は、正直言ってこの質問には困ったが、しばし悩んだ挙句に「両方と付き合っても良いんじゃない?」と答えた。彼は「そうか、そう思うか?俺も迷ったんだけれど、余りにもそのスパニッシュが可愛いので付き合っても良いかな?なんて考えていたんだ。」と楽しそうに答えた。その夜、彼は遅くまで話をしてから家に帰って行った。その後、彼はパッタリと私の家に来なくなり、連絡も途絶えたまま数週間が過ぎた頃の事だった。友人の家で、以前ジョンの病気の事を教えてくれた知り合いに偶然会う機会に回り逢った。その知り合いは、こちらから聞く前にジョンの事を私に話しはじめた。ジョンは、その時末期の癌で苦しんでいて誰にも会える状態ではないという事であった。その知り合いは、ジョンにかなり近い友人らしくジョンも彼の不満をストレートにぶつけてしまうらしく「ホワイ・ミー?(何で俺が!)」と何回も叫ばれるのには困ったと零していた。それからまもなく彼が息を引取ったという知らせを受けた。今になって時々思うのだが、あの晩何でジョンが私のところに来て私にあんな質問をしたのか解らない。彼は私に「ガールフレンドが居ながら、そんな事を考えるなんて不謹慎だぞ!」と叱って欲しかったのだろうか?と時々考えてしまう事もある。また、私が彼の病気の事を知っているのかを確かめる為に、あんな質問をしたのかも知れないとも考える事がある。もしそうならば、私は彼の誘導尋問に見事引っかかってしまった事になるのだが、今ではそれも遠い昔の思い出に過ぎなくなってしまった。
2011年06月21日
コメント(0)
-
ロンドンの生活とであった人達(記録その1の3)
スクウァーターズ(Squatters):無断居住者私がロンドンに住み始めて初めて知った難しい言葉だった。この頃聞いた人の話であるが、ロンドンでは使用していない建物に入り込み自分達で中から鍵を取り付けて何ヶ月か住んでしまうと、オーナーでも彼らを追い出すことはできないという法律があったらしい。その後、このスクァーターズが余りにも増えすぎてしまい、彼らを取り締まるために法律が改善されたと聞かされたことがあるが今になってみると定かではない。私がその夜泊まりに来たのは、このスクァーターズの家であった。地面からみぞおち位の高さにある大きな窓が、その家の入り口だった。窓から家に入るのが不慣れな私は、まずギターケースを中に入れ窓枠に手を着いてから中に入った。中は電気が通っていないのか真っ暗だった。目が慣れてくると外からの月明かりで、青白くぼんやりと壁の枠や廊下らしき通路が浮き上がった私は、先ほどの日本人の女性に案内されて彼らカップルが住んでいる部屋に案内された。そこは蝋燭のみの光で照らされており、家具やその他の物は何もないがらんとした一部屋だった。そこには先ほどの金髪の彼が、床に座って微笑んでいた。我々は、再びお互いを紹介しあった。私は、もう彼らの名前は覚えていないが金髪の彼は、Irish(アイルランド人)で年は二十歳前後のケルティック(ケルト人)特有の青い目のハンサムな青年で、先ほどの日本人は彼のガールフレンドらしい。彼らは、私が今晩一緒に演奏していた男を良く知っていて、私が危ないことに巻き込まれない内に何とか私に知らせたかったらしい。我々3人が話していると、部屋に入って来て挨拶をしてまた出て行く人間が何人かいたのだが、日本人の彼女は私に「ギターを離さないでね。狙っているかもしれないから。」と忠告をしてくれた。そうしているうちに、金髪の彼氏は席をはずしてどこか他の部屋に行ってしまった。我々は、しばし日本の話しに花が咲いた。これも今思い返せば、彼氏の彼女に対する思いやりだったのかもしれない。遠く異国に住み着いた彼女に、同じ国から来た私と日本の話をさせてやりたい、と思った彼の思いやりだったのかもしれない。彼女は、しばし話日本の話しをした後ポツリと「私、日本に帰りたい。私の父は埼玉で学校の校長をしているの、どうやったら帰れるかな?」独り言のようにつぶやいた。私は、正直彼女に何と言葉を返したかは覚えていない。イギリスでの生活が、まだ始まったばかりの私にとってこの言葉はかなりショックだった。その後、この人達に会うことは一度も無かった。私は、時々30年以上たった今でも覚えているこの出来事は、ひょっとしたら夢で見たことで現実ではなかったのかもしれないと思うことがある。翌朝私は、そこを出て地下鉄のストックウェル駅まで歩き今度はちゃんと切符を買って地下鉄に乗り家路に着いた。その日、彼らの家からストックウェルの駅まで歩いている時の朝日の眩しさや、朝早く働く清掃の車の騒がしさはもう遠い昔の出来事となって記憶に残っている。
2011年06月13日
コメント(2)
-
ロンドンの生活とであった人達(記録その1の2)
私は「こんばんは、そうですよ。こんなところで日本の人に会うなんて奇遇ですね。」と答えた。すると彼女は私に小声で「突然なんだけれど、さっきあなたと一緒に演奏していたあの人は知り合いなの?」と聞いてきた。私はちょっとびっくりしながら「彼には昼間偶然街で会った時に一緒に演奏しないか?と誘われたのでここに来ただけで、私は彼のことは何も知らない。」と答えた。すると彼女は「彼は、あまり良いうわさのある人じゃないの、悪いことは言わないから彼と付き合うのは止したほうが良いよと彼が伝えてと言っているの」と先ほどの金髪の若い男性のほうを見た。彼は、私に笑顔を見せながら先ほど私と演奏をしていた彼を指差しながら「イエス、ヒーイズ・ノーグッド(彼は良くないよ)」と私に伝えた。私は、彼らにお礼を言って家に帰るために身支度を始めると、彼女は「これから私達も家に帰るのだけれど、彼があなたを家に誘えってうるさいの、どう?これからたいした所では無いけれど私達のところに遊びに来ない?」と誘われた。私は、断る理由が無いのとロンドンに住み始めてから今まで外泊をしたことが無いので、ちょっと外泊に興味が湧いた。もちろん日本人もいることが私の安心感をいっそう引き立てたのは言うまでも無いが、今晩一晩彼らのところに厄介になってみようと決心した。パブが終わってから、そこにいた10人程度の人数でチャーリングクロス通りのレスター駅まで歩き、そこから地下鉄の構内に入っていった。一緒に歩いている人達をよく見ると、彼らはこの辺りで良く見かける大道芸人や演奏をしているストリートミュージシャンだった。駅の構内に入ると彼らは、駅の改札にあるキセル防止用の鉄製の回転バーを駅員の目の前でいつものことのように平然と乗り越えた。明らかに無賃乗車だが、駅員は見て見ぬ振りをしている。驚いている私をその中の1人が後ろから押しながら、「ドント・ウォリー(心配しなさんな)」と私を改札の反対側まで押し出した。そこからチューブ(ロンドンの地下鉄は管・パイプのようなところを走っているのでこのような呼び方をしている。また地面下にあるのでアンダー(下)・グラウンド(地面)とも呼ばれる。なおアメリカなどで使われるサブ・ウエイはイギリスでは地下道という意味になります。)でノーザンラインを南に下りストックウェル駅まで行く間電車の中では宴会のような騒ぎで、その中でも年配のストリートミュージシャンが私の横で何気なく弾いていたシャドウズのギター曲の巧さは圧巻だった。ストックウェル駅に着いた我々は、駅を出る時も同様に改札を乗り越えた只この時は地元らしく何人かは駅員さんに挨拶をしながら出て行った。我々一向は、駅から5~6分程歩いたところでベニヤ板製の塀の隙間から入り大きな建物の庭に入った。庭に入った彼らは、その3~4階建ての大きな建物に近づき一階の大きなベニヤ板をはがしてそこから中に入って行った。私は、何が起こったのか理解が出来ずにしばし呆然とその場に立ち竦んでいた。すると先ほどの日本人の彼女が窓から上半身を出して、私に中に入るように手招きをした。
2011年06月11日
コメント(2)
-
ロンドンでの生活と出会った人達(記録その1)
以前にも述べたと思うが、私は音楽をするためにロンドンに行ったわけではなかったのだが、楽器やアンプを買い面白い人達に出会うと躊躇も無く出歩いて行った延長が、いつの間にか結果的に私をオーディションに行くことを決心させたように思う。只、今思えば、ロンドンに住み始めてから何もわからない最初のうち、結構「やばい」連中に会っていたように思える。今になって見れば経過は良く覚えていないが、何かの拍子に町で知り合ったミュージシャンに誘われて、トトナムコートロードの十字路付近の地下にあるパブで一緒に演奏しようと言うことになり、ギターを抱えてオックスフォード通り沿いからパブまで階段で降りていった。私はその時パブで何を演奏したかは全く覚えていないが、彼がギターを弾いて歌っているのに適当に合わせてギター弾いていただけだと思う。その頃のオックスフォード通りはとても華やいでいて、ライブハウス名門の100クラブ(ここは400人程度のライブハウスだが、1980年代に若い頃世話になったと言うことであのローリングストーンズが何の前触れも無く一夜限りのライブをやったことがあった。結果はご想像の通りオックスフォード通りは会場に入れない人達で溢れかえったそうである。)また、その通りからちょっと入ったデゥルリーレーンと言う通りにはロンドンの音楽の登竜門であるライブハウスのマーキーがあり(この会場は、当時ビードルズ以外は全てこの会場から有名になって行ったといっても過言でないほどに有名なライブ会場であった)。この時期ロンドンは、このほかにも色んなパブ(居酒屋と言おうか、まあお酒を飲むところである。)でバンドが演奏をしていたもので、私の住んでいたウエスト・ケンジングトンの角にあったパブでも当時有名に成りつつあったポリスが演奏する、と言う話まであったほど地域のパブでのライブは活動的であった。話がそれてしまったので元に戻すと、私はそのパブで演奏した後、そのパブのお客さんと話をしていたところ、若い金髪の男性が私に話しかけてきた。まだロンドンに住み始めて間もないこともあり、英語に自信の無い私にとって彼の発音は私にはとても聞き取りにくかった。すると彼は、人懐っこそうな笑顔を浮かべて何か言葉を言ってパブの奥のほうに消えていった。私には、その時の彼の言葉は「ちょっと待って!」と言ったように聞こえたのだが、もちろん空耳だと思った。すると彼は、パブの奥から1人の東洋人の女の子を連れてきた。彼女は、「こんばんは、あなた日本人でしょ?」と私に日本語で話しかけてきた。
2011年06月06日
コメント(4)
-
ロンドンの地下鉄(本当に強い人は、普通に見えることを彼らは知らない)
ロンドンで地下鉄に乗っていると、とにかく色々な出来事に出くわす事があった。ある駅から音楽集団が乗ってきて、ギター2台とアコーディオンでスパニッシュ風な音楽を演奏しながら車両から車両に移って行き、帽子を持ったお金を集める人がそれに続くといった半強制的に小銭を要求するグループ、また、ある駅からは1人の男が電車に乗り込んで来たと思うと「皆さーん、お忙しいところまことに申し訳ありません。私は現在失業中で、今日ご飯を食べるお金もありません。皆さんから、ほんの少しでも援助をいただけたらと思い、恥を忍んでお願いに上がりました。皆さんのご好意をお願いします。」と大声で説明をしてから(ご飯を食べていないのならあんなに元気な声を出せるはずが無いと思うのだが)帽子を持って車内を回るプロのベガー(物乞い)もいた。この連中は、無視をしていればお金を強制的に取る事も無く、もちろん地下鉄に許可を取ってやっているわけでは無いので彼らには弱みがあり、その為、人畜無害であった。また今はもう無くなったと思うが、一時期国鉄の沿線上などで何件か集団強盗が発生したこともニュースで何回か聞いた事があった。また、地下鉄に乗っていて全く知らない乗客から度々話しかけられることがあった。今ではその内容は殆ど覚えていないが、その乗客の殆どは北の人間だった。イギリスでは、一般的にロンドンから北の人間は温かく南の人間は冷たいと言われている。北は貧しいが、皆お互いに助け合って生きているので温かく、反対に南はお金持ちなので人を警戒するので冷たいという事が言われている。これを実証すると言うことではないが、一度早朝に南の方面で車が故障をしてしまった事があり、車を直して貰う為に近くのガレージまでヒッチハイクをしようと試みたが、何時間経っても行き交う車は止まってくれず近くの家から人が出てきても私達を見ると家に入ってしまうといった状況で電話も借りることが出来ずに途方に暮れていた時、ようやく一台の車が止まってくれて近くのガレージまで乗せて行ってくれた。この車を運転していたのが、何を隠そう北の人間だった。話を元に戻すが、こんな訳で北の人たちは地下鉄の中でも気さくに話しかけてくる。一度私が膝をたたいてドラムの練習をしていた時、「ドラムをやるのか?」と聞いてきたのがやはり北の人だった。北の人たち例えばビートルズで一躍有名になったリバプール出身の人達(イギリスの愛称でスカウサーと呼ばれる)のアクセントは日本で言うと、北関東(栃木・群馬など)で良く聞く尻上がりの発音に近いところがある。この日本とイギリスの北部の尻上がり発音の共通点は、どういう背景から来たのかは解らないが偶然とはいえ不思議である。昼過ぎのがらがらの地下鉄に乗っている時に、隣の車両から歩いてきた背の高い黒人が急に私の前で立ち止まり、私の隣に座った。すると、新たに隣の車両から現れた男女2人が私のほうに歩いてくると私の隣にいた黒人はいきなり立ち上がり、男女が来る反対方向に歩いていこうとした。その黒人が立ち上がった後に、テープでぐるぐる巻きにした小包が置いてあったのを私は見逃してはいなかった。すると、私の向かい側に座っていた男が間髪をいれずに立ち上がり、さっき黒人が座っていた私の隣の小包を手に取り、その黒人を連行しようとしていた男女に「オフィサー!これも持って行って。」みたいなことを言って包みを彼らに放った。後々でよく考えると、私はとんでもないことに巻き込まれていたかもしれなかったのだ。あの男女は刑事のコンビだった。あの時、私の向かいに座っていた乗客がその包みを刑事に放っていなかったら、きっとそれは私の持ち物だと思われただろう。中身はわからないが、よからぬものであったことは今、思うと想像がつく。その時は気がついていなかったようなことが、後から考えてみると非常に幸運なことだったりするものである、間一髪とでもいおうか・・・。今こうやって私のロンドンでの人生を振り返ると、色々なところで何か不思議な力に守られていたような気がする。私自身、迷信やミラクルパワーと言った現実にかけ離れた事は余り信じるほうでは無いのだが、こんなことを考えるのは寄る年並のせいなのであろうか?別なある日、ノーザンラインに乗っていたところ、3人の黒人が私の横に座ってきて、この間ぼこぼこにした東洋人の話をし始めた。その時、私の中で何かが「笑え!」と私に指示をしてきた気がした。それで、ふっふ、と笑ってみたところ、この3人は急に立ち上がってどこかに行ってしまったこともあった。また別な日、人気の無い通りを歩いていると、前からやってきた180cmをゆうに超える背丈の黒人がミラーのサングラスをかけたその顔を私に近づけ「俺は今、ムショから出てきたばかりで金が無いのだけれど貸してくれないか?」と聞いてきた。私は固まりながらも一歩後ろに跳びすさり、身構えた後で「ごめん、俺、金持ってないから」と言うと彼は私の肩を軽くぽんぽんと叩いてそのまま行ってしまった。私は、あの時は「もうだめだ!」と思っていたので、さすがにこれには唖然とした強烈な覚えがある。後に友人にこの事を話したときは、「最初の件はわからないけれど、後の件を聞くとあなたは誰かに守られている気がする。」と言われた事がある。聞くところによるとその友人は、母親が祈祷師をしていたと言うことでその友人も何回となく母親の助言で助けられたらしい。その血が入っている友人にこのように言われると、私の周りが急にご先祖さんでわいわいと守られているような楽しい気分になった。当時私は、髪が長く、通りがかったあるイタリアのレストランから出てきた子供の団体に「ブルース・リーだ!」と騒がれたこともある。その風貌から(と言ってもやつらは東洋人で髪が長けりゃ皆ブルース・リーに見えるらしい)強そうに見えたのかもしれない。これはその十何年か前にある新聞に載っていた小さな記事であるが、ロンドンの中心にあるピカデリーというホテルで、小柄の日本人が大男の物取りに襲われたらしい。通報を受けた警官が駆けつけると、鼻血で顔を真っ赤にした大男が警官に「助けてくれ!俺はこいつに殺される!」と叫んだそうな。この小柄の日本人、実は空手の有段者だったそうなというくだりの文章だった。実際、本当に強い人は、普通の人に見えることを彼らは知らない。(笑)
2011年05月10日
コメント(6)
-
地下鉄と刑事たち
ロンドンの生活の中で、私は時々とんでもないことに巻き込まれることがあった。まずは、ロンドンでまだ私が学校に行き始めの頃である。自宅のあるウエスト・ケンジントン駅から地下鉄に乗り、一つ目のアールズ・コート駅で電車を乗り換え、語学学校のあるパットニー駅に行く電車がホームに止まっていたので乗り込み電車が出発するのを待っていた時である。外から1人の男が電車の中に入ってきて私の前に立ち、「ウッデュー・マインド・ステッピング・アウト・サイド(外に出ていただけますか?)」と言って何か手帳のような物を私の目の前に差し出した。良く見るとそれは、彼の顔写真が写っている身分証明書のような物で、はっきりとは思い出せないがそこには「POLICE」と言うスタンプが押してあったように思う。いくら鈍い私でも、この状態が「すいません。今私は学校に行く途中でこの電車で行かないと学校に遅れるんです。」と断れる状態ではないのは一目瞭然である。私は、彼の後について電車を降りた。するとそこには、7~8名の私服の刑事が待っていて一斉に私を取り囲んだ。その中の1人が「ウッジュー・マインド・サーチング・ユア・バッグ?(貴方のかばんの中を拝見させて頂けますか?)」と言いながらその手は既に私のバッグの中に入っていた。彼らが何を探しているのかわからないが、私は彼らのなすがままである。私の周りは背の高い私服の刑事達がぐるっと取り囲んでいるので、多分プラットホームにいる人達には私の姿が見えない。バッグを見終わった刑事は、バッグから何も出てこなかったからなのか?少々苛ついた声で今度はロール・アップ・ユア・スリーブス(シャツの両袖を捲くり上げて)と言った。私が袖を捲り上げると、腕の上にある小さな赤い点を指差して「ワッツ・ジス?(これは何だ?)」と私に聞いた。私は彼にアイ・ドン・ノー・メイ・ビー・インセクト・バイト?(知らない。多分虫刺されじゃない?)と何気なく答えた。彼らは諦めたのか、私にお詫びの言葉も言わずに行こうとしたので私は「ワット・ワズ・イット・フォー?(なんの為のだったの?)」と聞いた。すると1人が私を振り返り「トゥ・プルーヴ・ユア・シチュエイション・ライト(君の立場を証明してやったのさ)」みたいな捨て台詞を吐いて行ってしまった。今思い返せばあの刑事たちは、私が麻薬の売人か何かと間違えたのだと考えられる。それが彼らの期待に全然添えずにお手柄も無く、完全な的外れだったので多分相当頭にきていたのだろう。これで彼らも、人間を格好で判断しなくなっただろうと考えると結構痛快である。しかし「私の格好は、そんなに変だったのであろうか?」と疑問に思うと結構いたたまれなくなった。
2011年04月28日
コメント(6)
-
ロンドンで剣道?
前回の日記の中で剣道の話が出たので、少しロンドンのサークル事情について書いてみようと思う。私はこの時期運動を何もやらないと体が鈍ってしまうので、良く体を鍛えるために家の周りのブロックを走っていたことがある。東洋人が運動着を着て道を走っていると、通りすがりの人にマーシャル・アーツ(格闘技)をやるのか?と興味深く聞かれることが少なくなかった。私が若かりし頃在籍していた中学の剣道部は強く、私の毎日の生活は剣道に明け暮れていた。高校に入ると、高校は余り剣道が盛んでは無かったのと、ちょうどその頃私が音楽とギターに熱中し始めたことも重なり、剣道部には在籍はしていたものの剣道には全然熱中出来なくて時々2年生の先輩に呼び出されては、練習に出るようにと怒られた事もあった。まあそんな訳で、私は日本の家に剣道の防具があることを思い出し、日本に里帰りをしたついでに剣道の防具をロンドンに持ってきた。今になっては、当時ロンドンでどうやって剣道をしている団体を探し出したか覚えてはいないが、多分アダルト・スクール(アダルトといっても日本で言うあのアダルトではなく、既に学校を卒業した人たちを対象にという意味の大人・アダルトである。)の紹介の本でFLOODLIGHT(フラッドライト)という物があったので、これを見て調べたのだと思われる。この本には、語学、スポーツ、音楽、歴史など色々な方面の習い事をする団体のことが出ていて何かを勉強したい人にとっては貴重な本だった。今思い返せば、私は週2回のペースで練習が行われているこのサークルで、ただ日本人だということだけで月謝も取られず優遇されていたように思える。約10人程度のサークルだが、日本の剣道クラブと違い先輩後輩のランク付けもなく、みんなで和気あいあいとして稽古をしていた。それでも練習の最中は、血の気が多いところが所々に見えてやはり日本の剣道のようにクールに対戦できないのはお国柄なのだろうか?中でも身長が180cmを有に超えるオーストラリア人のグレッグは、現役ラグビーの選手でもあり最初の切り替えしの時に全体重でぶつかって来たときには、こちらも全体重でぶつかって行っても体育館の片隅に飛ばされそうな程のパワーだった。このサークルの中の対戦相手でもっとも面白かったのは、ジョンというめちゃくちゃフィットな男である。彼は体が良く動くし運動神経も良いので、いつも対戦では引き分けになっていた。あるときこのジョンが、短い竹刀を作ったので2刀流で相手をしてくれないか?と持ちかけられた。私は、「ジョン日本では2刀流で剣道はしないんだよ」と言い聞かそうとしたが、彼は「MUSASHIは2刀流」といって聞かなかった。私は仕方なく生まれて初めて2刀流の相手と剣道をやった。まあ、これも日本では絶対にお目にかかれない代物で、以外に対戦していて面白かった。稽古の後で、我々はイギリス人の先生の前に一直線に並び今日の反省や連絡事項をするのだが、この時「来週七人の侍の映画をどこそこで上映する。見に行きたい人は後で私のところに申し出るように」と言う連絡事項が私にとっては壷にはまってしまった。その時私は何も言えなかったが、何故か厳つい彼らがメッチャ可愛らしかった。練習が終わるといつも彼らはお決まりのパブでビールで乾杯である。彼らが剣道をしている理由は、稽古の後でこのビールにありつけると言うのが一番らしい。またこの人たちはインテリで結構優しいところもあった。特にジョンは、あるクリスマスの前に「とっちはクリスマスはどうするんだ?」と聞いてきたので「別に何もしないけど」と答えた。すると彼は「クリスマスに1人でいるのは良くない、俺のところに来い」と言って無理やり彼の家に招待されたことがあった。彼の家族もとても暖かい人たちで、私はクリスマスイブから彼の家に泊りがけでご馳走をたらふく食べさせて貰ったことは今でも良い思い出である。私は、仕事も忙しくなった事もありいつの間にか剣道に行く時間がなくなってしまい、自然にあのサークルから足が遠のいてしまった。この時私は、日本の武道である剣道を通じてお互いの異文化を学ばせて貰ったと思う。ちなみにこのサークルはロンドンの西端で活動をしていた団体だったが、ある時ロンドンの中心にある大きな剣道の団体の道場に招待をされて稽古をしに行ったことがあった。その団体で剣道をしていた若い日本人に練習試合を申し込まれて対戦したところ、その素早い動きに舌を巻いてしまった。やはり日本の剣道は凄かった。
2011年04月26日
コメント(4)
-
公立の語学学校(その2)
以前にも書いたように、この公立の語学学校はさすがにカリキュラムもしっかりしていて一日3時間の授業を週5日間受け、最終的にケンブリッジ・ファースト・サティフィケイトの試験に受かった人はProficiency(熟練)というコースを受け、その後は大学へという行程が敷かれているらしい。私のクラスは、女性の先生が2人と男性の先生が1人の計3人が受け持ちで、女性の先生の1人Judithはおかっぱ頭、いかにも先生と言う容貌で発音に厳しく彼女から教わった事柄は大変多かったと思える。女性の先生の2人目Kathyは、金髪で青い目の若いアイルランド系の先生で、我々とは年が近い事もあり一緒に旅行に行ったりパーティをしたりして今思えば一番身近にいた先生だったのかもしれない。これは余談だがこの頃の私は、パーティで料理を作らされることが多く、マカロニサラダとトンカツ(モスリムの人には牛かつ)は特に評判が良かったが、多分今でも彼らはこれらの料理が「典型的な日本食なのだ!」と信じている。そして3人目、唯一男性の先生Roger、彼は多分その容姿からして間違いなくヒッピーの名残だと思われる。長髪でカラフルなシャツそして日本の数珠らしきものを首に掛けている。彼の話はめちゃくちゃ面白く、彼の授業が始まると生徒全員そのテンポの速いジョークに魅了され、時間の経つのを忘れてしまうようだ。彼は、その風貌からして日本の文化が好きらしく、授業中に日本のことを話す事がありその知識には驚かされたことも多々あったと記憶にある。クラスメートは、大体15人位だったと記憶している。その中でも特に仲が良い仲間は、イラン人で女性に手の早いアリ、大柄でやさしそうに微笑んでいるギリシャ人の男性マヌーサス、ちょっと小粋で歌うことが大好きな姉御肌のスペイン人ピリー、小柄でヒッピー風な愛嬌の良いスペイン人のローザ、この中で一番若くていかにも育ちの良いお坊ちゃん風なイラク人のハッサン、そしてお茶目なスイス人3人娘のポーリン、エリザベス、アナリーズ、そしてイラン人の賢いおばさんのシャケ、今でもこの人たちはしっかりと記憶に残っている。そうそう、この他に団体としてではなく、この頃一緒に遊びに行っていた中国人のポールを忘れてはいられない。彼の名前はポール苗字はサイミン合わせるとポール・サイミン、知る人ぞ知るポール・サイモンと一字違いの名前である。(関係ないか)彼は、当時まだ18歳ぐらいの礼儀正しい若者で、どういう過程で仲良くなったかは全然記憶に無いが、良く一緒に深夜のカンフー映画をオールナイトで見に行ったりした。その当時、学校の近くに映画館があったので深夜に2人で入ったところ、館内はカリブの黒人で満員になっていて、カンフー映画がカリブ人の間でこれ程人気があるとは知らなかった。その日映画館内で東洋人は我々2人だけという奇妙な経験だったが、物語の中で女優が男性に甘えたりするところを観客が真似をしたりして笑いを誘い、結構楽しく盛り上がっていたのは見ていてとても面白かった。ポールは当時カンフーを習っていて、格闘技の話のついでに剣道の竹刀で出来た痣がなかなか治らないと話をすると「打ち身にはこれが一番効く」といってタイガーバームと言う軟膏を紹介してくれたのもこの頃だった。彼はある時、カンフーの先生たちに私が剣道をやっていることを話したらしく、私に一度日本の剣道をやっているところを見学したいとポールを通じて頼んできた。ポールはカンフーの達人たちを、私がイギリス人に混じって剣道をしている体育館に連れて来て片隅に座り稽古が終わるまで我々を見学していた。カンフーの先生達は私に「貴方の動きは、カンフーに通じるところがあって面白かった」とコメントをして見学させてくれたことにお礼を言って帰って行った。私がこの公立語学学校に通っていたのは、通算して2年に満たないくらいだったと思うが、フランス・スペイン・ギリシャ・イランそして中国の人のしゃべる英語を聞き取れるようになったのは正にこの友人たちのお陰だったと思う。
2011年04月24日
コメント(2)
-
公立の英語学校
まだ、9月半ばなのに吐く息は白く厚着をして来たにも拘らず寒い。あのドイツ人らしき背の高い2人組みは、話をしながら歩いて体を温めているようで、私が到着してから2時間位は有に経つが相変わらず立ち止まらずに話し続けている。それでも時計が8時を回る頃には、チラホラと入学を希望する学生達が集まってきたが、到底定員には達する人数ではなさそうだ。9時に学校のenrollment(登録)が始まった時は、かなりの数の生徒が集まってきていた。そういえばこの時に、背の低い良くしゃべるギリシャ人のおっさん風の男にしつこく話しかけられちょっと困った記憶がある。彼とはその後も、学校の生徒たちと一緒にギリシャレストランに行った記憶があるので、その頃は生徒仲間だったのだとは思うが、それ以外の記憶が全く思い出せない。多分彼は、そんなに長くその学校には居なかったのかも知れない。結局この日は、学校に登録を断られるだけの生徒の数は来なかったようだ。登録の後に家に帰り、フローレンにこの事を話すと彼女がこの学校に在籍していた頃は授業料も今と比べて3分の一と格段に安く、その分生徒も多かったのだが授業料が高くなった今は勉強をしたくても金額が高すぎて払えない生徒が多くなったのではないか?との推測を話してくれた。今回私が登録をした金額は、1ターム(一学期)3ヶ月で90ポンドで私が学校を止める頃には一挙に270ポンドにまで上がったそうである。とにかくその日私は、学校の登録と授業料の支払いをを済ませ、クラスの振り分けを受けてIntermediate3(中級3)というクラスに入った。この学校は、Beginner-Elementary-Intermediate1-Intermediate2-Intermediate3-Proficiencyという6段階に分かれていて、私のクラスは中の上と言った所だった。以前にも書いたように日本人は、文法が得意なためにテストでは良い点を取ってしまう為に話す実力よりも上のクラスにされてしまい、後でクラスに付いていけなくなるケースが間々あるらしい。私は、余り素直に喜んでもいられない私の境遇を他の日本人生徒から聞いて困っていた。
2011年04月22日
コメント(2)
-
ロンドンでの生活と公立語学学校
ロンドンに住み始めた頃は、日本食には全然縁が無くとにかく狭い行動範囲の中で自分にあった食事を見つけることが先決だった。まずは家から一番近くの中近東の夫婦がやっている雑貨屋さん、ここではインスタントヌードルが買えた。銘柄は、中国製のDOLLSというインスタントヌードルでパッケージには簡単な漫画みたいな人形が描かれている。味は、ワンタンヌードル、チキン、ビーフ、そしてバーべキューだったと思う。最初は、ギターとアンプを買ってしまったので、「節約をしなくては!」と思い、2週間ほどインスタントヌードルだけで過ごして痩せこけてしまった。次に凝ったのはパスタだった。マカロニを買ってきて茹でて冷水で冷やし水を切り、ガラスの深い器に入れ、炒めたなす・ベーコン・たまねぎをその上にのせ、チーズを振りかけてオーブンに入れて焼く。表面がこんがりと焦げたら出来上がり。これもかなり気に入って何回も作ったが、あるときオーブンの中で熱のためにガラスの容器が割れてしまい、その後この料理は作れなくなってしまった。ちなみにガラスの容器のことは、大家さんには永久に内緒である。その次は何とかご飯が食べたくなり、学校の日本人から聞いてイタリアのプディングを作るためのお米をなべで炊いてみた。ちょっと甘い感じがするが、痩せても枯れてもお米である。これは結構いけていた。こんな感じで私のロンドンでの食生活は始まった。さて、話は再び語学学校に戻るが、8月の最後に私立の語学学校を終わり、9月の半ばからフローレンが教えてくれた公立の語学学校に行く予定をしていた。フローレンは私に「この学校はかなり人気があるので、受付の当日は朝早く学校の門のところに並ばないと定員オーバーで学校に入れない可能性がある」と教えてくれた。私は、彼女に言われたとおり受付の当日朝5時に起きて早めに受付に並ぼうと計画をした。ロンドンの九月は既に肌寒くなっていたのでしっかりと洋服を着込み、まだ薄暗いなか学校を目指し家を出た。学校に到着をしてから周りを見回すと、私以外の生徒は背の高いドイツ人らしき男が2人体を温めるために校門の前を話しながら行ったり来たりしていた。どうやら早すぎたようである。しかし、今更家に帰るわけにもいかず、校門のところに座って待っていることに決めた。
2011年04月20日
コメント(2)
-
買っちゃいけねぇ、でも・・・買っちゃった
このプライベートの学校には約1ヶ月間通ったが、何をやったのかは余り覚えていない。ただ一つ覚えているのは、授業中に私が自宅で夜寝ている時の事なんかを話している時だったと思う、ブランケット(毛布)と言うつもりで「バケット・ユー・ドント・ノウ・バケット?」何て言って先生を困らせたことがあった。(この時はクラスの後で自分の勘違いだった事が解り、非常に恥ずかしい思いをしたのでよく覚えている)その他はクラスで何があったかは全然覚えが無い。ただこの時、ロンドンで私の始めてのクラスメートであるイタリア人のチェザーリと友達になった。(しかし今はどういう過程で仲良くなったかは全然覚えていない)気が付いたら、お昼を一緒に食べに行ったり、学校が終わった後セント・ジェームス公園に一緒に行ったりして遊んでいた。その時期に撮った写真には、公園やポートベローのマーケット何かも写っていたチェザーリの友達のフランチェスカも写っていたので3人で遊びに行っていたようだ。チェザーリは、当時30歳位だろうか?いかにもイタリアの今で言うチョイ悪親父風で、いつも皮のジャケットを着ているイメージである。時折見せる、いたずらっ子のようなはにかんだ笑顔がトレードマークで、フランチェスかもこの笑顔で魅了したのかもしれない。たった1ヶ月だったが、お互いたどたどしい英語で話をしていたように思える、今は写真を見ても当時どんな会話をしたか殆ど覚えていないが、学校が終了し彼がイタリアに帰る前に「もし、将来とっちがローマに来ることがあったら、ここに電話をするように」と言ってメモをした紙切れを私にくれた。そこには、彼のフルネームと電話番号が書かれていた。その後、何年か経ってローマにいる彼を尋ねたのだが、彼のローマでの生活はびっくりするほどリッチだった。詳しいことは、翌年にユーレイルパスを使って語学学校で知り合った友達を訪ねてヨーロッパ旅行をする時に話をすることになると思う。この語学学校に行っている時に、一つ私がわくわくしたことがあった。それは、この学校のすぐ近くにDenmark Street(デンマーク・ストリート)という通りがあり、この通りの周辺一帯が楽器屋さんで埋め尽くされていた。これはもう私にとって、無料の遊園地みたいなもので毎日学校のお昼休みや授業が終わった後は必ず遊びに行っていた。私は、ロンドンに来るときに密かに自分で誓っていたことがあった。それは、ロンドン行くのは英語の勉強をする為に行くので、ギターを持っていくのは止めて勉強に集中できるようにしよう。この想いは、ある中古楽器屋さんにかかっていたギブソンの335を見たときに無残にも崩れ落ちた。当時日本ではやっていた、フュージョンミュージックで一躍有名になった、リー・リトナーやラリー・カールトンなどが弾いていたギブソンの名器335。その黒光りしたバディは、オールドの名に恥じない光沢を放っていた。しかし当時の私はアコースティックギターは解るが、エレクトリックギターに関する知識は残念ながらかじった程度のみであった。でも気持ちは「かっこいい、欲しい、買いたい」であった。当時の値段で599ポンド、一ポンドが700円~900円の時代である。でも幸か不幸かこの時の私はポンドの感覚が全く無い、私は日本から持ってきたお金をポンドに換金してそのお店に行き、その黒いギブソン335となぜかミュージック・マンの100Wのアンプを即買いしてしまった。これが私が生まれて初めて手にした、名のあるギターとアンプだった。
2011年04月18日
コメント(2)
-
とんだお昼の冒険
午前中の授業も終わり、お昼時間に外に出てみた。とりあえず、お腹が空いたのでどこか食べるところを探しに学校周辺を歩いてみた。先ほど出てきた地下鉄の駅前を通り過ぎ、トトナム・コートロードの交差点を右に曲がって数歩歩いたところに、ハンバーガー屋さんを見つけた。ここで思い切って中に入れば、その看板に出ているようなジューシーなハンバーグにありつけるが、ここで一つ大きな難題にぶち当たった。日本を出るときに何気なく空港で目に留まったエチケットの本、やはり外国に行くのにその土地の習慣を何も知らないで行くのも気が引けると思い買ってしまった。それは、サトウサンペイ氏の漫画で解りやすく海外の習慣や食事のエチケットそしてマナーについて面白おかしく解説してある本だった。その本に、外国ではレストランで食事をするときはチップを払う習慣があり、これを怠るとチップを当てにして一生懸命あなたにサービスをしたウエイターやウエイトレスを怒らせると書いてあった。そのページには、ご丁寧にチップを支払うことを怠った主人公がレストランのお客の前でウエイトレスに罵倒されている絵まで載っていた。さて現在私のおかれている立場だが、とりあえず入りたいレストランは見つかったものの、私の頭の中は「この人たち、チップはいくら払っているのだろう?」という疑問で一杯だった。そのレストランは、通りに面しているところがガラス張りなので、そこからレストラン内が良く見渡せた。中は結構広く、結構大き目のテーブルを真ん中に挟み3人がけの長椅子が両側に並ぶ6人掛けのテーブルが8組位あった。更に目を凝らすと右奥にレジのカウンターがあり、皆そこでお金を払っているようだった。お金を払っている人たちを見ていると、伝票をレジに渡してお金を払っているようだがその横に丸くて白いどんぶりみたいな物があり、会計を終えた人たちはそこに何かを入れてから店を出ているようだった。私はお客の支払う動作を店の外から何回も観覧しながら、お客はレジカウンターの丸くて白いどんぶりにチップを入れているらしいと確信がもてるようになってきた。その頃までには、私の空腹も限界に達しており、だんだん腹が据わってきた。とにかく中に入り、なるべくレジの近くに座って食べるものを食べてからチップの件を観察するように決めた。(ここまでで多分30分は考えていただろうと思われる)私は思い切ってドアを開け、中に入るとウエイトレスが近寄って来て私をレジからちょっと離れたところに案内した。言葉が出来ればレジの近くを希望することができたのだが・・・と残念に思いながら案内された席に座った。ここからレジのカウンターを見ると、外から見るよりはより近くで観察は出来るが客がチップをいくら入れているか?迄は判別が付かない。とりあえず、ウエイトレスにメニューの写真を指差しお皿にハンバーグと目玉焼きとソーセージそしてチップス(ジャガイモを短冊に切って油で揚げたもの)がのっているものそして紅茶を頼んだ。お腹が極端に減っていた私は、あっという間に全てを平らげて一息ついた。さてこれからが問題の支払いである。先ほどまで満員に近かった店内もお昼のピーク時が過ぎたためか、お客もチラホラいるだけでなかなか支払いにレジまで進んで行かない。私は、午後の授業がもうすぐ始まる時間であるため焦っていた。もうこれ以上は待てない!私は思い切って伝票を持ち立ち上がってレジに歩いていこうとすると、私の隣の席のお客が私の前に立ち上がりレジに歩いていった。お陰で私はその人がレジでお金を支払う一部始終を間近で見ることが出来た。その人はただ単にお金を支払った後、おつりの小銭のいくらかをどんぶりに入れただけだった。なんて事は無かったのである。後で分かった事だが、チップの本当に煩い国はアメリカであり、特にニューヨークはチップが生活を左右するらしいことが分かった。イギリスでは、心配したほどチップが煩い国ではないらしく、どうやらこれは私の取り越し苦労だったようだ。私は支払いを済ませ、急いで午後の授業に戻った。とんだお昼の冒険タイムだった。
2011年04月15日
コメント(4)
-
初めての語学学校
翌朝、私はフローレンの案内で地下鉄のウエスト・ケンジントン駅まで行きそこから地下鉄に乗った。(地下鉄と言ってもロンドンの西外れにあるこの駅は地上の駅だった。)私たちは、電車で7~8駅行ったところで乗り換えてトトナムコート・ロード駅に着いた。地下鉄の通路を出るといかにも中心地らしく、大きな建物が並びその1階はレストランやお土産やさん等のお店がぎっしりと並んでいる。目の前の大通りを赤い2階建てのバスが交通混雑の中を何台も連なって通り過ぎて行き、そして歩道は行き交う買い物客や観光客でごった返していた。フローレンは、駅を出たすぐ左側に私が目指す英語学校の看板を確かめると、「イッツ・ヒアー、オフ・ユーゴー・ゼン・アイム・ゴーイング・トゥ・ワーク・ナウ、シー・ユー・レイター」(ここだわ、じゃあ行きなさい、私は今から仕事に行くから、後でね)と言って人ごみに消えてしまった。私は、彼女は学校の中までついて来てくれるものと思っていたので、正直言って「えっ?」としばし呆然としていた。しかし、それはこちらが勝手に想像していただけで、事実彼女が仕事前に西も東も分からない私を地下鉄の乗り方を教えてここまで連れて来てくれ、その上に語学学校の場所を確かめてくれたただけで大感謝だった。ここからは一人なんだ、と気を取り直して学校の入り口の階段を上り、沢山の人が忙しそうに行ったり来たりしている2階の受付の前に立った。受付の女性は、もちろんこのアジア人がここに何しに来たかは分かっているので、私の名前を聞いて手に持っていたリストと照合した後、私を年配の先生のところに連れて行った。先生は、私の前に本を開いて絵が描かれたページを見せ「この絵の中に描かれていることを何でも私に伝えてください。」(もちろん、こんなにすらすらと彼女の言っている事が簡単に解るなら私がここにいる必要は無いのだが)みたいなことを言われたので、私は言われた通り「う~ん、マン・リード・ニュースペーパー、アンド、アイ・シー・キャット・ランニング」みたいなことを答えた。その結果、私はインターメディエイトというビギナーの上のクラスに入れられてしまった。正直言って、これは何か自分が思っていたよりも英語が出来たみたいで嬉しかった。(後で他の日本人の学生に聞いたところ、通常日本人は読み書きが出来るので話が出来なくても自分のレベルよりも高いところに行かされて苦労をするそうである。)そんな事とは知らずに案内された教室に入ると、そこには既に5~6人の生徒が部屋の中心に並べられた机の周りに座っていた。私は、以前にも書いたように、この値段が高い私立学校にはビザの関係上1ヶ月間だけ通い、9月からはフローレンが教えてくれた公立の語学学校に行く事になっていた。もちろん30年以上も前のことなのでこの学校のことは殆ど覚えていないが、この時の先生はなんとなく若くて威厳が無く単にアルバイトとして教えに来ているといった感じだった。無論このクラスの生徒は短期の留学生だったので、先生のほうからも余り腰をすえて教えられるタイプのクラスではなかったことは認めるが、このクラスでの勉強の意味は殆ど無かったと言える。しかし、このクラスは私にとって全くの無駄ではなかった。このクラスには、私がロンドンに来て初めてフローレン以外の友達が出来たのだった。
2011年04月13日
コメント(4)
-
ロンドンでの生活第1歩
その部屋はフローレンの部屋が通りに面しているのに対し、裏向きの小さな部屋だった。小さな部屋と言っても天井が高いので小さく見えるだけで、大きさで言ったら12畳ぐらいはあったと思う。部屋に入ってすぐ右には縦長の古い洋服ダンス、その奥には引きダンスそしてクッカー(電熱器使用の調理台)そしてその奥には縦1メートルぐらいの余り大きくない冷蔵庫があり、入って右側にはシングルベッド、その奥には今では使われていないのか板で塞がれている古い暖炉そして正面には上下にスライドする木枠の大きなガラス窓があった。窓の外には、大きな木がびっしりと葉をつけていてその先にある視界を遮っていた。私は、フローレンにお礼を言い早速自分の部屋に荷物を運んだ。そこは、今までいたフローレンの部屋とは雰囲気も全く違いシーンと静まり返っていた。私は、日本を飛び立ってから今まで雑踏の中で暮らしていたようなもので、久しぶりに味わう静寂にゆったりとした気持ちになっていた。ドアをノックする音がして半開きになっていたドアからフローレンが顔を出した。「カム・イン」と言うとフローレンは楽しそうに、「こんな近くに部屋が空いてて良かったわね。どう?部屋は気に入った?」と言いながら入って来た。私にとっては、ロンドンでただ一人の知り合いであるフローレンの真向かいの部屋に住めることは本当にラッキーだったとしか言いようが無い。私は言いたいことは山ほどあったが、現時点の私の英語力では「イエス・アイ・ライク・イット」と言うのが精一杯だった。彼女は、「グッド」と言った後で「リッスン、私はこれから仕事に行くけれど、明日あなたの学校に行く行き方を教えてあげるけど、学校は何時から?」見たいな事を聞いた。この学校は、当時フローレンの彼氏だったあの友達から、「イギリスは移民局がうるさいので帰りの飛行機の切符と語学学校に行くという証明書は必要だよ」と言う助言をもらい、一応一ヶ月の語学学校に行く手続きを日本でしていたのだった。語学学校の証明書を見ると朝10時と書いてあったので、「イッツ・テン・オクロック」と答えた。彼女は、「オーケー・アイ・ウィル・シー・ユー・アット・ナイン・ツゥモローモーニング」(じゃあ明日の朝9時に会いましょう)と言って部屋を出て行った。私は、しばらく部屋でゆっくりした後、買い物ついでに外に出てこの辺りを探索してみようと思いブラブラしてみた。すると私の家があるコモラロードと、大通り(確かノースエンドロードだったと思う)がぶつかったところに、古い電気製品を売っているところを見つけた。テレビっ子の私は、とにかくテレビだ!テレビが必要だと心に決め、テレビを買うには英語を話さなくてはならないことなど忘れて、店の中に入っていった。私は、いまだにあの時どうやってテレビが買えたのか思い出せないが、白黒の大きなテレビを買って自分で抱えて帰ったようである。家に帰ってからテレビを引きダンスの上に乗せ、電源をつないでスイッチをわくわくしながらスイッチを入れた。すると何から訳の分からないものが出てきた。それは幾重もの丸い輪の中心に女の子の顔が写っている。他のチャンネルに回しても同様の物が写っている。更に別なチャンネルに回すと、THEMESと書いてありバックに大寺院(今思えばセント・ポールだったと思う)が写っていた。どうやら、イギリスのテレビのチャンネル数は3チャンネルだけらしい。音を大きくしてみると、ピーと言う信号音がなっている。別なチャンネルは、バックにクラシックの音楽がなっているのでテレビが壊れているわけではないらしい。そうしているうちにテレビ番組が始まった。どうやらイギリスでは、テレビ番組とテレビ番組の間にこの音声信号を流して時間の調節を図っているらしい。私は、日本ではこのタイプの画面は全てのテレビ番組が終了した後にしか見たことが無いのでこれは正直びっくりした。考えてみればイギリスは、今でこそテレビのチャンネルが5チャンネルに増えたものの、私が行った頃は国営放送のBBC1とBBC2そして民放が1つしかなかったので、コマーシャルは1チャンネルしか無い為、こういった試験画面を見るのは珍しくなかったのである。
2011年04月12日
コメント(2)
-
ロンドンで初めて借りた部屋
翌朝、太陽が真上に昇ってから目が覚めた。私は既にお気に入りとなった例のバルコニーに椅子を出し、紅茶を飲みながら寝ぼけた眼で通りを眺めていた。ロンドンのからっと晴れた8月の空はすがすがしく、日陰では涼しいくらいだが日向に出るとぽかぽかと眠気を誘うくらいにちょうど良い暖かさだった。この頃のロンドンは、もちろん温暖化の影響がなく現在のように30度を越える暑さなど存在しなかった。1980年代のロンドンでは、「今年は夏が来ませんでしたね」と言った会話をした覚えが沢山あって、夏でも汗が吹き出るなんていう経験は殆ど無かった。紅茶を飲みながらしばらくバルコニーで日光浴を楽しんでいると、フローレンが外から帰ってきた。彼女は、平たい15cmぐらいの平たい缶詰のようなものを出して、缶切りで周りを開けながら、不思議そうに見ている私に「これはパイなのこうやって缶詰の蓋を開けてからオーブンに入れて焼くと中から膨らんできておいしいパイになるのよ」と教えてくれた。彼女は、オーブンにパイを入れると手際よくサラダを作り始めながら「あと30分ぐらいでできるからバルコニーでゆっくりしていていいわよ」みたいなことを言ってくれたので、お言葉に甘えて引き続き外の空気を楽しませてもらっていた。しばらくしてお昼の用意が出来、中に入ると先ほどの缶詰のパイが立派なパイと化してパンやサラダと共に食卓に並んでいた。食事をしながらフローレンは私に「実は、今日これからこの家の大家さんがここにやって来るんだけれど、彼に頼めば貸し部屋を紹介してくれると思うから一緒に会うといいわ」みたいなことを言ってくれた。(ここで再び説明するが、この頃の私は英語が全然出来ないので彼女がこんな言葉で言っていたなんていうことは書くことはできない。身振り手振りか英和辞典を使って会話をしていたことをご理解願います。mm)食事が終わり、しばらく話をしているとドアをノックする音が聞こえた。フローレンがドアを開けると、背の高い、年の頃なら60~70位の紳士風な男性がフランス語で何やら言いながら入って来た。フローレンも彼にフランス語で返しながら愛想良く話しているうちに、「急に英語で、リアリー?キャン・ウイ・ハブ・ア・ルック・アット・イット・プリーズ」みたいな事を言い出し、2人して部屋を出て行った。すると部屋の外から、フローレンの声で「とっち、カム・ヒア・アンド・ハブ・ア・ルック・アット・ジス」と言う声が聞こえたので部屋の外に出てみると、フローレンの真向かいの部屋のドアが開かれて大家さんとフローレンがその部屋に入っていた。「この部屋が空いているので、すぐにでも入れるんだって。。部屋代は週20ポンドで、毎週大家さんがとりに来るのでその時に払えば良いそうよ」と教えてくれた。私はすぐに20ポンドを彼に支払うと、彼はレントブックなる物に今週の分の判子を押してくれて私に渡し、握手をするとフローレンにまたフランス語らしき言葉で何か言ってから出て行った。部屋のサイズは狭いが小さな洋服ダンス・シングルベッド・椅子とテーブルそして電気クッカー(電熱器式の調理台に電熱器式のオーブンが付いたもの)そして冷蔵庫が付いていて必要なものは全てそろっていた。私がロンドンで初めての自分の城を手に入れた瞬間だった。
2011年04月10日
コメント(4)
-
訪英第一日目続き
どのくらい寝ていたのだろう?私は、ベッドから起き上がり薄暗い部屋の中で電灯のスイッチを探し歩いた。部屋の入口の横にスイッチがあったのでつけてみた。電灯を点けたときの最初の印象は、なんだか薄暗くボヤッとした明るさなのでなんとなく頼りなく感じた。日本で蛍光灯に慣れている自分の目には、ヨーロッパの電球の文化が初めはなんとなく馴染めなかった。今思えば、蛍光灯は確かに強い光で全てがはっきりと見えて便利なのだが、余りにも刺激が強すぎて目が疲れてしまう。ヨーロッパでもオフィスやデパートは蛍光灯だが、自宅に蛍光灯をつけている家はあったとしても数が少ないと思われる。取りあえず、フローレンが帰ってくるまでお茶でも飲もうと台所に行ってみた。お湯を沸かすのは電気やかん(ケトル)があり、お水を入れてスイッチを入れると中にある電熱器が異常なスピードでお湯を沸かしてくれる。このケトルがあるので、イギリスでは魔法瓶などを使用しなくても、短時間で必要なだけのお湯がすぐ沸く。これは誰に教わったのか今になってみると定かではないが、イギリスでは殆どの人は紅茶を入れるのにティーバッグを使う。このティーバッグがハンパな大きさではなく、多分日本の日東紅茶のティーバッグの3倍はあると思われるほど大きい。このティーバッグを背の高いカップに入れてお湯を注ぎ、お湯がかなり黒くなるまで(コーヒーかと見間違えるほどである)お茶を出しティーバッグを引き上げた後、紅茶が濃いベージュ色になるぐらいミルクをたっぷりと入れ、好みによって砂糖を入れて飲むのである。この紅茶の入れ方は初めてだがなかなかおいしく紅茶がいただけるので、それまでは珈琲派だった私が紅茶党に大変身したのだった。(しかし本当の理由は、この頃のイギリスでは珈琲といえば喫茶店のようなところでも、インスタント珈琲が出てくるのでおいしい珈琲はなかなか飲むことができなかった為である)。フローレンが仕事から帰ってきて、外に食事に誘ってくれた。全てがはじめての経験である私には、もちろん「YES!」である。今思い返すと、その時フローレンが連れて行ってくれた場所はフルハムロードのピッツア・エクスプレスだったと思う。ピッツア屋さんのチェーン店にしてはちょっと高級感を感じさせる店構えで、ピッツアもイタリア感覚の薄い生地のピザでとてもおいしい。私たちは、地下鉄でフルハム・ロードまで行きそこからお店まで歩いていったのだが、その途中で歩いていた2~3人の老婦人の一人が私に話しかけてきたらしい。私は、立ち止まり後ろを振り返ると、フローレンが立ち止まってその老婦人たちに何か説明をしていた。英語ができない私は、その会話に入っても仕方ないと思い、少しはなれたところで話が終わるのを待っていた。話が終わりフローレンは私のところに戻ると、先ほどの老婦人は私に道を聞きたかったらしいが、私が素通りしてしまったのでとてもびっくりしていたらしい。彼女は「彼は日本から着いたばかりで、まだ何も分からない。あなたをびっくりさせたことを許してあげてください」と弁護してくれたらしい。これは知らなかったにせよ、私がロンドンに着いて最初の思いもかけない失礼をしてしまったようだった。私はこの後レストランでどんな会話をしたのか全く覚えていないが、このときの日本の夏祭りの縁日を思い出させるフルハムロードの人ごみは、あの時食べたピッツアの味と共に約30年経った今でもはっきりと覚えている。家に帰るとフローレンは「今夜、私は友達のところに泊まるから、あなたはこの部屋に泊まりなさい。」と言って出て行ってしまった。私はロンドンでの最初の夜をこの素敵な部屋で過ごせる自分のラッキーさをフローレンに感謝して眠りに着いた。
2011年04月08日
コメント(2)
-
訪英第一日目
タクシーは、空港から3~40分程で私がロンドンで最初に住み着いたウエスト・ケンジントンという地下鉄の駅と同名の地域に到着した。道路の名前は確か50コモラロードだったと記憶をしている。タクシーの運ちゃんは、正確な場所を見つけるのが面倒らしく多分ここを10件ぐらい後ろに歩いたところだと思うと言って、私と荷物をタクシーから降ろした。タクシー料金を払う段階になって、運ちゃんは「16ポンド(シックスティーン パウンド)」と言ったのを「60ポンド(シックスティ パウンド)」と聞き間違えた私は、彼に20ポンド紙幣を3枚渡したところ、ちょっとビックリした運ちゃんは「ユー・ラッキー!(運が良かったな!)」と言って20ポンド紙幣を2枚私に返して、去って行った。いま思えば、あの頃の1ポンドは約700円~900円位の換算率だったとして、約42000~54000円もの大金を渡してしまうところだった。恥ずかしい話だが、為替もろくに知らずにロンドンに行きこんな目に会ったにもかかわらず、実際のポンドの貨幣価値が分かるようになるまでは暫くかかったように思う。その後も、何回かタクシーで空港からケンジントンまで乗ったことがあるが、16ポンドプラス2ポンドのチップで約18ポンドが正規の料金なので20ポンドを払っただけで済んだのは助かった。本当にあの運ちゃんで運が良かったと思う。さてタクシーを降りたところは、赤レンガの3階建てのビルが両側に並ぶ所謂居住地区で、目の前にはアラビックな叔父さんが煙草や食料品などを売っている雑貨店が一つ、私の立っている後ろはちょっと地中海の建物を思わせるような白いアーチが入り口になってその奥は石畳の道が続いていた。8月の太陽はまだまぶしいが、からっとした温度は日本で言う秋口の過ごしやすい日だった。その白いアーチの横には、真っ赤な公衆電話がまぶしい太陽の光を受けて鮮やかな色を放っていた。空港で既に公衆電話のかけ方に慣れた私は、早速そこからフローレンに電話をしてみた。「は~い、フローレン。アイム ヒア」みたいなことを言ったと思う。彼女は「ワット、ビルディングス・ユーキャンシー?」みたいなことを聞かれ(あくまでもこんなことを話したような気がする程度であるが)「アイ・シーリトル・ショップ」的なことを言うと、「アイ・シー・アイ・ノウ・ウェア・ユーアー・ドント・ムーブ・ゼアー(貴方のいるところは分かったので、そこを動かないでね)」と言って電話は切れた。数分後、「ハーイ、とっち。ナイス・トゥ・シー・ユー・アゲイン」と言いながらフローレンが足早にこちらにやって来た。私は、彼女に案内されてそこから50メートルほど歩いたところにある、50コモラロードに着いた。彼女は一つの家の中を分割して貸している通常ベッドシット(部屋の中にベッド・冷蔵庫そして調理場がついており共同のフロ・トイレが3階に一つ付いている)と呼ばれているところに住んでいた。これは全く一つの家を分割しているので、通常一階の部屋は居間として作られているので天井は高く大きな暖炉がついている。最もロンドンは1960年代にはスモッグを誘発するため暖炉で石炭を燃やすことが禁止されているので、殆どの暖炉は電気やガスを使っている為暖炉としての機能すなわち煙突は使用していない。話はそれてしまったが、フローレンの部屋は2階(イギリスでは1階がグランドフロアーで2階は1階(ファースト・フロアー)と呼ばれるが、彼女の部屋は元ベッドルームとして使用されていたと思われる。その厚いワインレッド色の絨毯が敷き詰められた部屋は、ダブルベッドを置いても十分なほどの空間があり、その奥には小さいながらも壁で仕切られた別のキッチンがある。キッチンの更に奥には道路側に面しているバルコニーがあり、ちょうどT字路に面しているこの建物から見える景色はまっすぐ正面に伸びる道路のために遮るものは何も無く、素晴らしい眺めを楽しめた。彼女は、私のためにパンとスープと人参を細かくシュレッドしたものに酢と胡椒で味付けをしたもの(フランスでは良くこれをサラダとして食べるらしい)を用意してくれた。食事をしながら、積もる話を身振り手振り、そして英和辞書を交えながらした後で、彼女は「私は、これから仕事に行くのでとっちは少し休んでね」といって外に出て行った。私は、まだ「ようやくイギリスに着いた!」という興奮から覚めない為か旅の疲れも殆ど無く、まだまだ眠る気にはなれなかった。彼女が仕事に行った後、暫くベランダに椅子を出して外の空気と風景を楽しんでいたのだが、急に睡魔に襲われ気がついたときには街燈の光が入る部屋のベッドの上で眠っていた。
2011年04月06日
コメント(2)
-
到着
さて、例のスリーピースのスーツで過酷な南回りの旅をこなし、よれよれになりながらもようやくたどり着いたヒースロー空港では、飛行機の大幅な遅れにより(後で聞いた話だがパキスタン航空は到着時間が遅れることで有名らしい、パキスタン航空のPIAは英語でPerhaps I Arrive.の略だと皮肉られているらしい)迎えに来てくれているはずだった例のフランス人の彼女フローレンはその辺りに姿は見えず。途方にくれた私はしばし空港のロビーで呆然としていた。取りあえず電話をしてみようと思い、持っていた日本円をポンドに換金。小銭を持って公衆電話のところまで行き、受話器を取り上げコインを入れようとするのだが、コインの投入口のところにバーのような金属があって、コインが入るのをふさいでいる。受話器を耳に当てて見るとツーという電話の音がしている。「あれ?お金も入れてないのに音が聞こえる、壊れているのだろうか?それとも、イギリスは公衆電話が無料なのかな?」等と自分に都合のよいことを考えていたが、取りあえずダイヤルを回してみた。何回か呼び出しのベルが聞こえた後、フローレンの声が「ハロー?」と聞こえた。私は「ハーイ、フローレン イッツ とっち」とすかさず答えた。しかし、電話口のフローレンはこちらの声が聞こえないみたいで、数回「ハロー」と言った後で電話を切ってしまった。さて困った、どうやったら電話がかかるのか、これが私にとってイギリスでの最初の試練だった。何回か受話器を取り、電話をかけようとしている私を見かねてそばにいた人が電話のかけ方を身振りで教えてくれた。それは、先ずコインを電話の投入口に乗せてそれからダイヤルを回し相手を呼び出し、相手が出たらコインを投入口に押し込めるとバーが開いてコインが投入口に入り相手と会話ができるといった内容だった。教えてくれた人にお礼を言った後で、再びフローレン電話をかけてみたところ、やっと今度は、電話がつながり彼女と話をすることができた、彼女は、空港で随分待ったが、飛行機が大分遅れたので一旦家に帰って連絡を待つことにした・・・みたいなことを言ったと思うが、なんと言ったのか正しくは全然覚えていない。その後、彼女はロンドンの黒いタクシーは信用できるからタクシーに乗って住所を見せれば問題ないから、タクシーでこちらまで来なさい、みたいな事を私に伝えた。英語も分からない私がどうやってこれを電話口で聞き取れたのか、今思えば火事場の馬鹿力というのは、こういう必死の状態の中で無意識のうちにでる力を言うのかもしれないと思う。私は、フローレンに言われたように黒いタクシーを捜して外に出ると「タクシー要らないか?」みたいな呼び屋が私に話しかけてきた。が、これはフローレンが言っていた白タクらしいので、首を横に振りながら黒いタクシーを捜して更に歩いていくと黒くて屋根の高いタクシーが何台も並んでいる場所にたどり着いた。その先頭のタクシーの運転手に行き先を書いた紙を見せると、運転手は私のスーツケースを運転席の横に乗せて私の為にドアを開けてくれた。目指すはロンドン市内!私は、長旅の疲れも忘れてタクシーの窓から流れるイギリスの風景を見ていた。これは余談だが、ヒースロー空港内のトイレに入った時のこと。用を足した後、トイレを出る時にイギリス人のおじさんが入れ替わりにトイレに入って来た。彼は、間に合いそうになかった為なのか、小便器のところに行くまでに自分のイチ○ツを既に社会の窓から出して手に握っていたのだが、その象の鼻のようなブツを目撃したことが、私にとってイギリス到着後の最初のカルチャーショックだった。(笑)しかしまあ、こんなどうでもいいことを覚えているという意味では、それほど必死でもなかったのかもしれない、とも言える。
2011年04月03日
コメント(4)
-
海外旅行に関しての初歩的なミス
さて、その初歩的なミスとは?私は、この時まで外国はおろか国内の旅行でも飛行機というものには乗ったことがなく、自分自身もあまり計画的な性格でない事も手伝って、飛行機なんて飛べば目的地に着くもんだとばかり思っていた。だから、飛行機のチケットは電車の切符と同じで乗る時には見せて、降りる時にも見せれば良いもんだとばかり思っていた。したがって、自分が乗る飛行機が、パキスタン航空というあまり喜ばれる航空会社ではないということも、そのルートがしかも南回りであり、ロンドンまでの行程がハンパではなく長いということも、全然知らなかった。その上に、いったん飛行機が空中に浮かべば、次に着くのはロンドンと信じて疑わなかった私は出発当日、成田空港でスリーピースのスーツに身を包み(今思えば、あの時の私の格好は完璧なピエロである)見送りに来てくれていた両親や姉や叔父、そして友達に別れを告げて空港内の通路を出発ゲートに向かって行った。以前にも書いたと思うが、出発ロビーで私が見た飛行機は、期待していたエアーフランスのような大型の飛行機ではなく、なんかこじんまりとしたプロペラ機の容姿さえ感じさせる機体だった。(もちろんこの時代に海外旅行がプロペラ機の理由はないのであるが、あくまでもこれは機体を見た私の第一印象である)以前にも「1979年8月、私はロンドンにやってきた」で書いたように、私はこのこじんまりとしたサエない飛行機でパキスタンのラワルピンディに行き、約7時間の休息後にやっとジャンポジェット機に乗り換え、ロンドンまで約36時間程の大冒険(海外旅行が初めての私にとっては文字通り)を敢行する羽目になったのである。この時の旅行自体、その時は大変なことばかりだったような気がしていたが、今思えば海外旅行が初めての私にとっては、北京からパキスタンのラワルピンディまでゴビ砂漠の上を飛びながら万里の長城を眺め、それから山間にある小さな村を眺め、それから雲の上に突き出た小さなエベレストを遥かかなたに見下ろした、とてもエキサイティングな旅行だった。多分、今同じ事をもう一度やれるか?と言われたら、今はあれこれ知ってしまっただけに、躊躇してしまうだろうと思う。今の方が格段に英語が喋れるし、旅行の経験が今とは格段に違うが・・・・・。やはり若さだったのだろうか?あの時は怖いもの知らずだったと言うか、怖いものなど弾き飛ばしてしまう若さと力が漲っていたように、いやいや「怖いもの」自体を知らなかったのかもしれない。
2011年03月31日
コメント(4)
全274件 (274件中 1-50件目)
-
-

- やっぱりジャニーズ
- 楽天ブックス予約開始!ドラマ「マウ…
- (2024-09-16 22:53:26)
-
-
-

- 気になる売れ筋CD・DVD
- 小室哲哉 billboard classics ELECT…
- (2024-11-28 11:04:30)
-