2024年04月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

社長・手塚治虫は、新劇の夢を追って辞めた社員に仕送りし続けた
前回のエントリーに登場した河井竜氏。(旧)虫プロ社員で制作進行担当だった。入社は(旧)虫プロ全盛期の1963年。彼には新劇の脚本と演出をしたいという夢があり、とうとう2年後のある日、社長の手塚治虫に退社を申し出た。演劇では食えないと、一度は思いとどまるよう説得した手塚社長だが、河井氏の決意は固い。最後は「わかりました! 立派な演出家になってください」と送り出した。劇団を作ったものの、すぐに食えるわけもなく、廃品回収業のアルバイトをする河井氏。すると(旧)虫プロの仲間が200キロもの動画用紙を提供してくれた。さらに河井を驚かせたのは、手塚社長から毎月現金書留が届くことだった。劇団の公演パンフレットには広告も出してくれた。だが、3年後、河井氏は病に倒れてしまう。結核だった。劇団はうまくいかず、お金も底をついていた。結核は法定伝染病。治療費は国から出るが、夢は諦めようと決意を固める河井氏。諦めた自分が、手塚社長から支援を受けることはできないと、「芝居で食っていけるようになったから、もう仕送りは結構です」と手塚社長に電話をした。「あ、そうですか、よかったよかった。河井さん、よかったですね。いっそうがんばってください」「長い間ありがとうございました。本当にありがとうございました」【中古】ブラック・ジャック創作秘話(4)-手塚治虫の仕事場から- / 吉本浩二時は流れ流れて2009年。まさみじゅん氏のブログで、河井氏とともに手塚邸の植栽の剪定に行った話を見つけた。ちょうど『誰も知らない手塚治虫―虫プロてんやわんや』が出版されたころだ。http://mcsammy.fc2web.com/MushuProOB/MushiProOB1.html高齢になった手塚夫人が植栽の管理が大変と聞いて、出向いたのだという。http://diary.fc2.com/cgi-sys/ed.cgi/mcsammy/?Y=2009&M=9&D=13
2024.04.30
-

医学博士・手塚治による手塚治虫診断は「誇大妄想的突発性錯乱症」
手塚治虫著『ぼくはマンガ家』によれば、彼は「誇大妄想的突発性錯乱症」なのだそうだ。それが事実であるということを、めちゃくちゃ汚い絵これまでにない個性的な作画で、あますところなくギャグにした不朽の迷作――それが『ブラック・ジャック創作秘話』だ。【中古】ブラック・ジャック創作秘話(2)-手塚治虫の仕事場から- / 吉本浩二これはホントに面白い。手塚漫画より手塚治虫のが面白いんじゃないかと思えるくらい、面白い。手塚治虫ファンじゃなくても面白い。まだ読んでない不幸な人は、すぐに読むべき。さまざまある手塚先生「錯乱の場」での中でも、もっとも意味不明で、Mizumizuイチオシのシーンは、これ。制作進行担当社員の河井氏に、「もう待てない」と言われて突発性錯乱症スイッチが入る手塚先生。社長なのに、「やめます!」と叫んで、机の下に逃げ込む。しかも頭だけ。行動が猫。ちなみに、この河井氏が(旧)虫プロを辞めたあとのエピソードは、手塚治虫がどれほど思いやりのある人間だったかを端的に示す例。そして、その厚意に応えて、河井氏が手塚未亡人のために取った行動も、素晴らしい。それについてはまた次のエントリーで。誇大妄想入った突発性錯乱の場は、こちら。冷静になったときの手塚先生の弁は、「編集の方から野放しにされたら、半分の作品も生まれなかったですよ」。で、「自由にしてくれ」と言われて、「分かりました!」と野放しにした編集者の原稿は、結局3回連続で間に合わず、その後その編集者が会社を辞めたと聞いて…自分のせいだと思ったとたん、怒涛の責任転嫁…言うことやることメチャクチャだ(苦笑)。ちなみに、なのだが、『神様の伴走者:手塚番1+2』に、その編集者とおぼしき人物のインタビューがあり、本人は「自分が会社を辞めたのは手塚さんのせいではない」と話している。もともとやりたかったことが別にあったからだそうで、本人は手塚治虫含めて周囲の人たちが「手塚番をしながら3回も連続で原稿を落としてしまったので、会社を辞めたんだ」と思っていたことも知らなかった。お次は、のちに松本零士となる松本晟少年の証言から。このシーンには、夜中の「メロン」「ケーキ」「スイカ」などのバリエーションあり。テレビのドラマでも採り上げられて、かなり有名になっているエピソード。さらに…完全に少しイカれたおっさん…手塚治虫「正史」とも言える『手塚治虫物語』では…誇大妄想的突発性錯乱症のコの字もモの字もサの字もなく、仕事にひたすら邁進する手塚像が描かれ…藤子不二雄Aの『まんが道』で、神になったというのに…『ブラック・ジャック創作秘話』では…と、言われて編集者が慌てて手塚先生愛用のユニの2Bを買ってくると…こんな人だとバラされましたとさ。いずれは歴史上の人物として、その一生が映像化もされるであろう偉人・手塚治虫。その際は「正史」に描かれた軌跡だけでなく、こういうぶっ飛びエピソードも入れてほしい。うしおそうじの『手塚治虫とボク』にも、若き日の手塚のぶっ飛びエピソード「手塚治虫の遺言」編もある。このブログでは敢えて紹介しなかったのだが、手塚という人が、スイッチ入ったらいかに「やめられない止まらない」人だったか分かるエピソードだ。ああいった秘話(?)も、漏れなく入れてほしいもの。
2024.04.29
-

鳥山明が『メトロポリス』(手塚治虫 1949年)にいた!
『釣りキチ三平』で有名な矢口高雄が初めて読んで衝撃を受けた手塚治虫作品は、『流線型事件』だったという。その一部始終を『ボクの手塚治虫』で詳しく描いているが、それは藤子不二雄、石ノ森章太郎といった後の巨匠たちが手塚漫画から受けた衝撃と驚くほど似通っている。ボクの手塚治虫【電子書籍】[ 矢口高雄 ]矢口少年は、利発で向学心に溢れた少年で、『流線型事件』にある車のデザイン理論に惹きつけられ、暗記するほど読んだという。内容は凄いのにオサムシなんて、変な名前だと思ったらしい。その矢口少年が、恋をしたかもしれないというのが『メトロポリス』のミッチィ。男にも女にもなるミッチィは、手塚漫画のヒーローの原型となったキャラクターというだけでなく、のちの少女漫画家にも大きな影響を与えたのではないかと思う。というのは、『メトロポリス』を実際に読んで気づいたのだが、昔々Mizumizuが読んでいた少女漫画のそこここに、そのイメージがあるからだ。『ボクの手塚治虫』で、矢口少年が『メトロポリス』を「解説」する場面がある。漫画家・矢口高雄が模写した『メトロポリス』の場面を引き合いに出しながら、少年・矢口高雄が、どこが面白いのかを生き生きと語るのだ。「へ~~、当時の男の子たちは、こんなふうに夢中になったんだ」ということがよく分かる。で、最近になって『メトロポリス』を初めて読んでみた。・・・特に面白くありませんでした。「デッサンをやってない」というのは、初期の手塚に浴びせられた悪評の代表例だが、なるほど、そう言われても仕方がない部分が目に付く。レッド公のプロポーションのデタラメぶりとか、脳が入っているとは思えない頭の形とか、骨格がないとしか思えない(いわゆるゴム人間)ヒゲオヤジとか。ただ、マンガだから、と言えば許容範囲の話で、ちゃんとそれなりに魅力のあるカタチになっているのは、さすが。だから、漫画家に対して、「絵が下手」というのは、あまり意味のない悪口だ。それを言ったら、絵画の世界だって、「下手くそ」な世界的画家はいくらでもいる。漫画のキャラクターの魅力は、デッサンが正確かどうかにあるのではない。しかし、Mizumizuにとって『メトロポリス』は、当時の少年たち、なかんずく漫画エリート少年に与えた影響を紐解く教材としての意味以上のものは見出しにくかった。子どものころに読めばまた別の感想を持ったかもしれないが、残念ながら、Mizumizuは手塚治虫には遅かった子供で、リアルタイムで読んでいたのは、手塚治虫および女手塚こと水野英子に影響を受けて漫画家になった世代の少女漫画家の作品。ただ、『メトロポリス』の後半、ミッチィが「覚醒」して、暴れまわるところには惹きつけられた。特に、人間に虐げられたロボットたちを従えて「メトロポリスへ!」と海の中を行進していくシーンは美しい。この発想は今読んでも衝撃的だ。手塚治虫の少年向けマンガに女の子のファンが多かったというのも頷ける。手塚作品に出てくる少女の多くは、「暴れまわりたい」という欲求を明確に持っていて、時にそれを実践するからだ。こういう少女像を描く男性の少年漫画家は少ない。で、その虐げられたロボット。「壊れるまで働かされる奴隷」のロボットが…これ↑なのだが、これを見て、そっこ~頭に浮かんだのが、鳥山明の自画像。似てませんか? これ。鳥山明は子供のころ、手塚治虫のロボットの模写をやっていたというから、『メトロポリス』のロボットも真似していたのかもしれない。しかし、「壊れるまで働かされる」ロボットって… 売れっ子漫画家のメタファーですか?
2024.04.28
-

俺は手塚に勝ったんだろうか?(By福井英一)
手塚治虫のチーフアシスタントだった福元一義によれば、1950年代、売れっ子すぎて他の漫画家から敬遠されがちだった手塚治虫と積極的に付き合っていたのが福井英一だったという。当時2人を担当した編集者の証言によれば、福井は、「なんであんなに手塚の線はきれいなんだ」「どんな道具を使っているんだ」と聞いたりしていたという。「俺が聞いたことは手塚には内緒だよ」などと口止めまでして。馬場のぼると3人でカンヅメにされたときは、3人で映画の物まねをして盛り上がり、原稿が進まず、それから出版社は漫画家同士を1つの場所にカンヅメにするのをやめたのだという。強烈なライバル意識とやっかみがあったのは、むしろ福井のほうで、酒の席で手塚に、「やい、この大阪人、あんまり儲けるなよ」「金のために描いているとしか思えねえ」などと難癖つけて絡んだりしている。手塚に自分の家で一緒に仕事をしようと持ち掛けたのも福井英一のほうだった。福元チーフはその場にいることになったのだが、二人の仕事ぶりは対照的だったという。福井のほうはキッチリ下絵を入れてペン入れをするオーソドックスなスタイル。うしおそうじと同じタイプだ。福井もうしおもアニメーター出身なので、似ているのかもしれない。手塚は簡単なアタリを入れて、すごい速さでペン入れをしていく独自のスタイル。当然、生産枚数は違ってくる。そのイライラもあったのでしょうが、よほど興奮したのか、ふだんは徹夜がまったくできなかった福井先生が、その晩は完全徹夜をしたのです。障子の外ですずめが鳴く声を聞いてビックリしたら夜が明けていたということで、福井先生自身喜んでいたのですが、最後のセリフは、「もう君とは二度と一緒に仕事しない」でした。手塚先生の超人的な仕事ぶりに、よほどリズムを狂わされたのでしょう。(福元一義『手塚先生、締め切り過ぎてます!』集英社新書より)【中古】 手塚先生、締め切り過ぎてます! 集英社新書/福元一義【著】酒を飲んで突っかかったと思ったら、一緒に仕事しようと誘っておいて、あげく「もう二度と一緒に仕事しない」とか、言いたい放題(苦笑)。明らかに福井は手塚に甘えている。1950年当時は、「手塚は絵が下手」などと言う先輩漫画家が多かったのだが、ちゃんと手塚タッチの美しさに気づいていたのはさすがの審美眼だが、その創作の秘密を探ろうとしたしたものの、一緒に仕事して、とても真似できるテクニックではないことを知ったのだろう。そこにいくと、素直に「驚倒した」「仰天した」と書いたうしおそうじは素直だ。ちなみに、うしおそうじは、福井英一が亡くなる前に、一度だけ彼に会っている。同じ東京下町の職人の倅同士ということで、すぐに打ち解けたのだが、そのわずか数日後に福井の訃報が舞い込む。電報で知らせてくれたのは手塚治虫だった。これは1953年の記事だが、「中卒」と「医学部卒」とか、書く必要あるのかね? これじゃ福井英一が気の毒だ。ちなみに手塚治虫が入学したのは阪大医学専門部だから、学歴詐称だというヘンな人がいるが、手塚卒業の年に医学部が医学専門部を吸収しているのだから、医学部卒と書いても別に間違いではない。https://www.museum.osaka-u.ac.jp/jp/exhibition/P13/TezukaChirashi.pdf手塚治虫が前代未聞の、年上にサバよむという年齢詐称(笑)をしていたのは事実なので、この記事では26歳とあるが、本当はまだ24歳だ。「この商売の寿命はほんの2年ぐらい」と言っているところを見ると、この頃は、売れなくなったら医者に戻ろうという気持ちもあったのかもしれない。手塚治虫の『ぼくはマンガ家』によれば、福井英一が手塚作品を褒めたのはたった一度。『弁慶』という時代物だった。手塚は歌舞伎の「勧進帳」の舞台を使ってユーモラスに弁慶を描いたそうだ。それを見て福井が「やりやがったな、うめえ」と、うなったのだという。だが、本当は福井は手塚作品を全部揃えて持っていた。それを手塚が聞かされたのは福井の葬儀の席でだった。「なあ、手塚さんよ」と、山根一二三氏がポツリと言った。「あいつは、俺にいつも、手塚がライバルなんだと言ってたぜ。そして、つい最近も『俺は手塚に勝ったんだろうか?』って訊いてた。あんた、気がついていたかい? 奴の家にはあんたの本が全部揃っていたんだ。こんな感じですか?コージィ城倉『チェイサー』より。主人公の漫画家・海徳光市が、隠し持っている手塚作品コレクションを読もうとしている場面。「手塚に勝ったんだろうか?」――この自問、どれだけ多くの人気を得た漫画家がしたことだろう?コージィ城倉も『チェイサー』で、主人公の海徳光市が、商業的成功を第一目標とする「ジャンプ」システムにのることで、子供だましの、自称「おバカ漫画」が大ヒットし、一時手塚作品以上に売れたとして「(俺は手塚に)勝ったのだが…」と言わせている。だが、主人公が一度は「勝った」はずの手塚は、どこまでも彼の先を行ってしまう。それを一番知っているのも主人公自身、という設定だ。現代にも続く正当派スポ根漫画『イガグリくん』と同時期に手塚が連載していたのは『ジャングル大帝』だが、当時は明らかに『イガグリくん』のほうが人気があった。『鉄腕アトム』より『鉄人28号』のがアンケートでは上だったと雑誌編集者が証言しているし、今では初期手塚の代表作と言われているSF大作『0マン』より寺田ヒロオの『スポーツマン金太郎』のほうが、やはりアンケートでは上だった。ちなみに、『ブラック・ジャック』も、アンケートが取れず、編集部がその人気に気づくのは、突然休載になったときに、編集部に抗議の電話が殺到したことがきっかけだった。手塚に勝つ――同時代の人気や作品の売り上げだけの話なら、「勝った」漫画家はいくらでもいるのだ。だが、例えば、ウィリアム・シェークスピアよりアガサ・クリスティのが読まれているからといって、アガサ・クリスティのがシェークスピアより偉大な作家だと言う人はいないだろう。先ごろ、1万円札の「顔」の候補に手塚治虫が挙がったが、漫画家で彼と競った人はいない。そういうことなのだ。
2024.04.27
-

複数の目から見た、手塚治虫の筆禍「イガグリくん」事件
1954年に起こった手塚治虫の筆禍事件、通称「イガグリくん事件」は当初は漫画仲間以外にはあまり知られていなかった。そして、この「事件」があってわずか数か月後に福井英一氏は過労死してしまう。手塚治虫が『ぼくはマンガ家』で、この「事件」を振り返って反省の弁を述べなければ案外忘れられた話だったかもしれない。正直なところ、そのころのぼくは福井氏の筆勢を羨んでいたのだった。(手塚治虫著『ぼくはマンガ家』毎日ワンズより)この「事件」の現場にいた人間は少ない。まず、チーフアシスタントの福元一義氏。福元氏の『手塚先生、締め切り過ぎてます!』によると、少年画報社でカンヅメになっていた手塚あてに福井英一が電話をかけてきた。その電話を取ったのは福元チーフで、福井英一はその時、「手塚君に話がある。その間、仕事を中断することになるけどいいかな」と言った。どういう話か知らなかった福元だが、心情的に編集者よりというよりは漫画家よりだった彼は、漫画の話でもするのだろうと軽い気持ちでOKしてしまったのだという。午後11時ごろに福井英一は、馬場のぼると一緒にやってきた。「やあやあ」と手塚治虫が迎えるのだが、だんだんと様子が変わってきたという。福元チーフはその時、隣りの部屋にいたのだが、大きな声がやがてヒソヒソ話になったかと思うと、手塚がやってきて「これから池袋の飲み屋に行ってくる」。そのまま手塚得意の遁走をされたら困ると思った福元チーフは「道具はココに置いていってくださいね」。道具があれば戻ってきてくれるだろうと思ってのことだ。つまり、この時点では、福元チーフは福井英一が手塚に「怒鳴り込んできた」とは思っていないのだ。それより仲のよい三人組で、締め切りを放り出してどこかに行かれては困ると、そっちを心配している。夜通しそわそわしながら福元チーフが待っていると、手塚治虫が戻ってきたのは明け方になってから。手塚「いやあ、参った、参った」福元「飲みに行ったんじゃないんですか」手塚「違うんだ、抗議だよ。強引にねじ込まれちゃって」現場にいた福元チーフが見聞きしたエピソードはこうだが、うしおそうじが、のちに現場にいた馬場のぼるから話を聞いたところ、コトはもっと大げさになっている。手塚治虫が『漫画少年』に連載していた「漫画教室」の1954年2月号にわずか数コマ(Mizumizuが見たところでは2コマだけ)のイガグリ君らしき絵に、福井英一が烈火の如く怒り、手塚・福井の共通の友人だった馬場のぼるの家に来て、「俺は今から手塚を糾弾しに行く」とまくしたて、馬場を強引にタクシーに押し込めたのだという。「これは明らかに俺の『イガグリ』だぞ! つまり手塚はこのイガグリを悪書漫画の代表としてこきおろして天下にさらしたんだ! 俺は勘弁ならねえんだ」(うしおそうじ『手塚治虫とボク』より)馬場は頭に血がのぼった福井英一が手塚に暴力でもふるったら、確実にマスコミの餌食になるだろう。自分が身を張ってでも決斗を防がねばと悲愴な覚悟をしたそうだ。そして、福井は手塚に会うやいなや、胸ぐらをつかんで、「やい、この野郎! 君は俺の作品を侮辱した。中傷した。謝れ! 謝らないなら表へ出ろ」と叫んだというのだ。手塚治虫著『ぼくはマンガ家』では、次のように書かれている。ある日、ぼくが少年画報社で打ち合わせをしていると福井英一が荒れ模様で入ってきて、「やあ、手塚、いたな。君に文句があるんだ!」「な、なんだい」「君は、俺の作品を侮辱した。中傷した。謝れ! 謝らないなら表へ出ろ」「いったいなんのことだか、ちっともわからない。説明してくれ」「ふざけるな」記者(Mizumizu注:記者と手塚は書いているが、編集者の間違い?)が、ぼくに耳打ちして、「先生、相当荒れていますからね。池袋へでもつきあわれたほうがいいですよ」そこへ、馬場のぼる氏がふらりとやってきた。ぼくは救いの神が来たとばかり馬場氏も誘い、3人で池袋の飲み屋に行った。綿のような雪の降る日だった。福井英一ははじめから馬場のぼるを伴って手塚糾弾に来たのだが、手塚治虫は、あとからたまたま馬場のぼるが来たのだと勘違いしている。ともあれ、3人は飲み屋に行って、そこで馬場のぼるの仲立ちもあって手塚が福井に頭を下げている。そして翌月の「漫画教室」で、福井氏と馬場氏らしいシルエットの人物に、主人公の漫画の先生がやり込められているシーンを描き、彼へのせめてもの答えとしたのだ。(『ぼくはマンガ家』より)これが「イガグリくん事件」の顛末だが、実際に「漫画教室」1954年2月号を見た中川右介は、そこに書かれたセリフを引用して、くだんの漫画教室はなにも福井個人批判ではなく、「(手塚)自身を揶揄しているよう」だと述べている。こういった表現が福井、馬場、うしお、手塚といった人たちによって、ますますドギツくなっていった。(「漫画教室」より)と、自分の名前も入れている。そのあとに、確かにイガグリ君のような髪形の頭を一部描いたコマも2つあるが、他にも渦巻状の線だけとか、空とか雲とか煙とかだけが描いたコマもある。そして、そういう表現をそのまま真似するのは避けた方がよい、と言っているだけだ。実際に問題となった「漫画教室」を見ていない人たちは、手塚治虫がイガグリくん人気に嫉妬して福井英一だけを中傷したと勘違いしているが、それは事実ではない。手塚はこのイガグリを悪書漫画の代表としてこきおろして天下にさらしたんだ!なんて、どう考えても過剰反応だ。数か月後に酒を飲んで過労死してしまったという事実を鑑みるに、福井英一は、この頃ハードスケジュールに追いまくられ、すでにかなり精神的に不安定な状態だったのだろう。福井英一が亡くなったのは1954年6月。漫画家の死が新聞に大きく取り上げられる時代ではなく、宮城にいた小野寺章太郎少年(のちの石ノ森章太郎)は、手塚治虫からのハガキで福井英一の死を知る。「福井英一氏が亡くなられた。今、葬儀の帰途だ。狭心症だった。徹夜で仕事をしたんだ。終わって飲みに出て倒れた。出版社――が殺したようなものだ。悲しい、どうにもやりきれない気持ちだ。おちついたら、また、のちほど、くわしく知らせるから」と、ハガキにはあった。手塚先生の悲しみが、行間からにじみ出ているようなハガキでした。福井英一は手塚先生の親友でした。ぼくは顔を見たこともないし、ファンレターを出したこともなかったのですが、それでもとても悲しくなりました。(石森章太郎著『マンガ家入門』より)この文面から分かるのは、天才・石ノ森章太郎は、当時、手塚治虫が「筆勢を羨む」ほど人気絶頂だった『イガグリくん』には興味がなかったということだ。もちろん、手塚治虫と福井英一の「(のちに大げさに広まる)確執」など知らない。二人は親友だと思っているし(実際に親しい仲だった)、手塚治虫の悲しみを思って自分も悲しんでいる。そして、漫画家という職業は体を壊すほど厳しく、忙しいものなのかと、不安になったと『マンガ家入門』に書いている。マンガ家入門【電子書籍】[ 石ノ森章太郎 ]
2024.04.25
-

そして、手塚治虫は神になった――うしおそうじが目撃した時代の転換点
少年漫画の世界に「週刊誌」が登場するのが1959年。うしおそうじは現役の売れっ子漫画家として、この大きな時代の転換点を目撃した一人だ。『手塚治虫とボク』には、来るべき週刊誌時代に備えてか、出版社側が「(月刊誌で)締切を守れない漫画家」をリストアップし、一斉追放に向けて布石を打ったのではと思われる、ある「懇談会」のエピソードが載っている。前回のエントリーでも紹介したように、下絵をきっちり描き、ペン先をいくつも付け替えて仕上げるスタイルのうしおそうじは遅筆だった。それにうしお自身、絵がうまくないことを自覚しており、驚異の手塚テクニックを目の当たりにしてからは、ますます自分の限界について考えるようになる。遅筆のうしおは「締切破りで悪名高い漫画家」の上位5位に必ずランクされていたが、ナンバーワンの締切破りは手塚治虫その人だった。もちろん手塚が締切を守れなかったのは、遅筆だからではない。仕事が多すぎたためだ。どちらにせよ、締切破りの漫画家は決まっており、1959年ごろのある日、そうした悪名高い漫画家が10名ほど呼ばれて、出版社側と「なぜ毎月の締め切りを守れないのか、その原因を探り、是正を考えよう」というお題目で懇談会が開かれたのだ。締切破り常連のうしおも当然呼び出されて参加したのだが、その懇談会にうしおはなにやら陰謀めいたものを感じ取る。それは、締切破りナンバーワンの手塚治虫が「どこかの出版社がカンヅメにした」といって、ドタキャンしたからだ。うしおの知るそのころの手塚という人は、約束をした以上は、たとえ終わり間際になろうと必ず現れる人だった。それが、最後まで来なかった。そして、締切り破りトップテン漫画家vs出版社の懇談会は、吊し上げをくらった漫画家側「担当者が、うちで出したメシに文句をつけていた」出版社の編集者側「風呂の釜焚きまでやらされた」「子供の送り迎えをやらされた」というような、本来の趣旨とはずれた私怨炸裂のオンパレードになり、2時間かけて何も明快な解決策はないまま終わる。うしおは参加した漫画家たちの、あまりのアホさ加減に呆れている。論客の手塚がいれば、違ったものになっただろう。だが、集まったのは頭脳プレイのできない漫画家ばかりだった。1959年は週刊サンデーと週刊マガジンが発行された年。うしおは後にその流れを鑑みて、この時の懇談会は出版社サイドによる「手こずらせ漫画家一斉追放」のための口実づくりではなかったかと結論づけている。そして1960年、うしおは漫画家を辞めてアニメと特撮の制作会社ピープロダクションを興す。では、手塚をカンヅメにして、懇談会に参加させなかった出版社はどこだろう? うしおはそれについては書いていない。だが、ひとつ言えるのは、週刊誌創刊に向けて、小学館と講談社が熾烈な「手塚獲得作戦」を繰り広げていたという事実だ。やがて到来する週刊誌時代の足音が聞こえてか聞こえずか、児童漫画家の一部楽天家たちは放埓に構え、無為に過ごしていた。そして運命の回り舞台はあっという間に回転して、週刊誌時代が訪れ、時代の波に乗れない児童漫画家たちはたちまち凋落していくのであった。それに対して、あれほど編集者たちのひんしゅくを買い、不倶戴天視されていた手塚治虫は、週刊誌時代を迎えてますます本領を発揮。名実ともに天下を制するようになる。(うしおそうじ著『手塚治虫とボク』より)手塚治虫とボク [ うしおそうじ ]週刊誌時代が到来する前は、手塚より年上の児童漫画家が子供漫画の世界で幅をきかせていた。また、児童漫画家のほかに「大人漫画家」という区別があり、大人漫画家と呼ばれる漫画家たちは児童漫画家たちを下に見ていて、特に手塚治虫を蛇蝎のごとく嫌い、「絵が下手」「話が荒唐無稽」と罵倒しまくっていたのだ。だが、『新宝島』、そしてそれに続く『ロスト・ワールド』『メトロポリス』『来るべき世界』のSF三部作に衝撃を受けた全国の才能ある少年たちが、続々と漫画家という道の職業に足を踏み入れ、頭角を現していくにつれ、手塚の評価は一変する。彼らにとっては、手塚治虫は神だった。神とその使徒たちが成し遂げた日本文化の革新は、明治維新を成し遂げた志士たちの偉業にも匹敵するだろう。大人たちは、戦後子供たちを夢中にさせ、破竹の勢いで世の中を席巻する新しいメディア、マンガを悪書といって糾弾し、焚書までした。それに真っ向立ち向かったのも手塚治虫だった。マスコミ関係者各社を筆頭にPTA、全国子供を守る会、地方自治体の教育機関、母と子供の会など、その手の団体の指弾のスケープゴートとして、決まって名を晒されるのが手塚治虫であった。そして、いちばん呼び出しの多かったのも手塚治虫である。当然のことながら手塚は憤然として、どの吊し上げの席にも出て行った。怖れず臆せず、逃げも隠れもせず、堂々と相手方と渡り合った。単独の時も複数の時もあった。ボクは彼のヒーローキャラの「レオ」のごとき獅子奮迅の働きに心から拍手喝采を送った。(前掲書より)手塚に続く漫画家たちは、手塚が矢面に立ってくれたからこそ、仕事を続けられたという側面がある。事実、手塚と同世代の漫画家の中には、「悪書」のレッテルを張られたことで意気消沈し、漫画家を廃業した者も多い。そして、手塚漫画を読んで育った子供たちは、長じて日本を世界トップの経済大国に押し上げたのだ。「学校の授業よりも何よりも、人生で大切なことを教わったのは手塚漫画」――これは昭和の時代に活躍した某女流作家の言葉。Mizumizuがこれを目にしたのはラサール石井の本が出るよりずっと前だ。そして今――日本のGDPがインドにも抜かれて世界第5位に転落するというニュースが流れている。一億総中流だった国は、もうどこにもない。あるのは明確な格差。そして、海外からの観光客を喜ばせる「なんでもかんでも安い国、ニッポン」。ただただ衰退の一途をたどる日本に、誰もなすすべもない。
2024.04.22
-

うしおそうじ(鷺巣富雄)は、手塚治虫の才能をもっとも早い時期に全方位で見抜いていた(後編)
後に「神業」と言われる手塚治虫の仕事ぶり。うしおそうじは1950年代初頭にその凄さを目撃している。現役の売れっ子漫画家から見ても、そのテクニックは想像をはるかに超えたものだった。まずはペンの使い方。うしおは3本のペン先を使い分けていた。きっちり下描きを入れてその上にペン入れをするのだが、太い線と細い線でペン先を替えていく。ペンを替えるから、当然時間はかかる。ところが手塚は、特に大切なメカニックな背景だけは一応ちゃんと下描きを入れるが、顔は丸、手足は2本線というようにラフな下描きを入れるだけ。ペンも1本で細い線を描く時はひっくり返し、あとは力加減で太い線・細い線を描き分けていた。鼻歌まじりに。しかも、どこでも描くことができる。机がなくても。特に記号のような下描きから、驚くべき速さで一気呵成に仕上げる手塚テクニックには「正直言って仰天した」という。もっと驚いたのはペン入れの順番。普通の漫画家はノンブルどおり1コマ目、2コマ目と順番にペン入れをするのだが、手塚は5ページ目の右から2コマ目を仕上げたかと思ったら、今度は3ページ目の下から2段目の左隅、次は6ページ目の一段目の右から3コマ目…というように縦横無尽にペン入れをしていくのだ。まるで牛若丸のごとく跳び跳びに埋めてゆきながら8ページ分描き終わる。仕上がりを見せてもらうと、驚くべきことに整然と、毛ほどの隙もなく完璧に仕上がって文句のつけようもなかった。(『手塚治虫とボク』より)手塚治虫とボク [ うしおそうじ ]ちなみに1955年。まだ週刊誌時代は始まっておらず、この頃は月刊誌時代だが、その当時も手塚治虫は月に10本以上の連載を抱え、なおかつ仲間と付き合い、飲んだり騒いだりしていたという。うしおは手塚の驚異的な量産の秘密は彼の描く速さにあり、なぜそこまで速いのかといえば、それは4ページだろうが、十数ページだろうが、紙に向かった時にはすでにコマ割りは手塚の頭の中で出来上がっていたことだと書いている。通しの吹き出し(セリフ)を全部入れてしまうと、ポイントごとに下描きのラフな記号風のものを描き入れて、その上に超絶テクを駆使してペン入れをする。この「手塚の神業」は業界では有名だったが、あまり一般の読者には知られることがなかったと思う。Mizumizuは小学校ぐらいのときに、漫画家の鈴木光明がアマチュア時代、手塚の仕事ぶりを初めて見たときの驚きを書いた文章を読んでいて、「こんなことができる漫画家がいるのか。本当に手塚治虫というのは別格の天才なんだな」と思ったのを今でも覚えている。手塚作品は読んでいなかったのだが。鈴木光明がその時目撃した手塚の仕事ぶりは、すでにアシスタントを使っていたのだが、自分は原稿を描きながら、口頭でアシスタントにコマ割りを指示する…という信じがたいもの。「こんなことができないとプロの漫画家になれないのかと思ったが、そんなことができるのは手塚先生だけだった」という鈴木フレーズが(多少言い回しは違うと思うが)、強烈に記憶に刻まれている。頭の中でコマ割りが全部出来上がっていて…というだけでも人間離れしていると思うのだが、それを作業しながら口頭でアシスタントに伝えるって…やはり、天才・石ノ森章太郎が言うように、手塚治虫は天才を超えた宇宙人だったのかもしれない。この神業を一般人にも広く知らしめたのが、『ブラック・ジャック創作秘話』というワケだ。[新品]ブラック・ジャック創作秘話 手塚治虫の仕事場から (1-5巻 全巻) 全巻セット
2024.04.21
-

うしおそうじ(鷺巣富雄)は、手塚治虫の才能をもっとも早い時期に全方位で見抜いていた(前編)
うしおそうじ(鷺巣富雄)と言ってもピンとこない人は多いと思う。手塚治虫原作の『マグマ大使』を実写化し、その高い特撮技術で名声を得た人物だが、今の若い世代には『新世紀エヴァンゲリオン劇場版』など庵野秀明作品の音楽担当鷺巣詩郎の父親だと言ったほうが、とおりがよいかもしれない。うしおそうじは、実弟の鷺巣政安(アニメプロデューサー、演出家)に「自分を引っ張り出してくれたのは手塚さんだ」と語っていたという。交際家として知られる手塚治虫だが、うしおそうじのもとにも、彼はある日突然やってくる。うしおが務めていた東宝で労働争議が激化したことで、うしおは赤本漫画のアルバイトを始めるのだが、自分でも予想外にうしおの漫画は好評を得る。うしおが駆け出しの漫画家としてスタートしたころ、年ではうしおより下の手塚治虫はすでに上昇気流にのって、全国にその名を轟かせる売れっ子漫画家になっていた。うしおは手塚の『ジャングル大帝』を読んで衝撃を受ける。その作者がいきなり自分を訪ねてきて驚くうしお。手塚は『漫画少年』(学童社)の編集者と一緒だった。そして、うしおの作品名を次々挙げて、「うしおさんの作品はよく読んでいます」と言って、うしおをさらに驚かせた。つまり、二人の訪問の目的は、『漫画少年』に連載をしてくれということだった。新しい漫画家を探している学童社に、うしおそうじを推薦したのが手塚だったのだ。うしおの手塚第一印象は「明るい」ということ。そして、その声と語り口に注目している。手塚のリズミカルな話しぶりを聞きながら、ひとつ気づいたことがあった。彼の声量と艶のある発声はあたかもオペラのバリトン歌手を思わせるのだ。それにしても、彼のこの快活な話しぶりは彼の天性か演技か、計りかねていた。初対面のボクにまったく無防備で接するはずはないとみるのが普通だし、決して下衆の勘ぐりとは言えまい。しかし、演技にしては彼はどこまでも自然体であった。いずれにしても、彼のこの天真さは天性と育ちの良さからくるものだろう。(うしおそうじ『手塚治虫とボク』早思社より)手塚治虫とボク [ うしおそうじ ]手塚治虫のトーク力には定評がある。漫画家の社会的地位を高めたのも手塚の知性とユーモアあふれるトーク力によるところも大きいだろう。一時漫画の仕事が減った時も、講演などの仕事依頼が来るので、手塚治虫がヒマだったことはないとチーフアシスタントは話している。手塚のコミュニケーション能力の高さ、その声、語り口の魅力に初対面でいちはやく気づき、こうした文章にしているうしおそうじは、のちに漫画家を廃業して制作会社を興すだけのことはあり、視点が実業家よりだ。うしおそうじが感じた戸惑いは、手塚治虫のトークを聞いた多くの人に共通するのではないだろうか。明るく、快活明瞭で、自然体。だが、どこか本音が見えないようなところもある。本心なのか巧みなウソなのか、分からない。やさしい雰囲気の中に、ふいにドキリとするような毒が混ざる。実は、そうした「つかみどころのなさ」が多くの人が手塚治虫という「人間」に惹きつけられる理由ではないだろうか。うしおは、同じ「漫画家」としての視点からも、手塚治虫の「神業」を記している。手塚に自主カンヅメを提案し、のちに手塚が頻繁に隠れ場所として使うことになる「ホテル・メトロ」を紹介したのもうしおだ。<次のエントリーに続く>
2024.04.20
-
芦田巌(別名:鈴木宏昌、芦田いわを)のロクでもない末路
うしおそうじは戦前、東宝でアニメーションの制作工程を学んだ人だった。そのときの室長が大石郁雄で、芦田巌(別名:鈴木宏昌、芦田いわを)はその門下生だった。その縁で、うしおは芦田とも面識があった。芦田は独立して三軒茶屋にアニメスタジオを持ったのだが、師匠の大石のところに来て話すのは、「生フィルムの入手が困難になった。このままでは零細プロは早晩消滅する」という愚痴ばかりだったという。その様子をうしおは見ていたが、師匠のところでときどき会う先輩アニメーターというだけで、個人的な付き合いはなかったようだ。その後、うしおは労働争議もあって東宝を辞め、漫画家からピープロの社長へと転身を重ねていく。ピープロの経営が軌道に乗ってきた1961年春、アトムが放映開始の2年間になるが、手塚治虫がうしおに突然連絡をしてきて、三軒茶屋まで来てほしいと言う。うしおがさっそく駆けつけると、芦田巌にアニメの肝心なコツを即席に教わりたくて、申し込んだら今日午後1時に来いと言われたので、一緒に来てほしいのだと。天下の手塚治虫が、なんで今さら芦田社長にアニメ即席入門の交渉を?――うしおはあきれ返ったが、手塚の目はキラキラ輝いて真剣そのもの。「じゃあ、とにかく芦田厳にボクから正式によろしく頼むと言って口添えすればいいのですね」手塚はそうだと言う。うしおは手塚に芦田という人間は態度が悪い、相手の目の前でせせら笑うような態度を取るので、そのつもりで会ったほうがよいと忠告する。2人で芦田をたずねると、手塚は自分は本気でアニメプロダクションを興すつもりだが、今、同族会社システムのアニメプロで成功しているのは芦田漫画しかないので、経営のコツやアニメーションの動かし方を教えてほしい。門下生としてこちらに自分が通うと真剣に話をする。その真摯な態度にうしおは脇で胸を打たれるのだが、肝心の芦田はうしおの言ったとおりの態度で、「君みたいな漫画家の頂点に立つ人間がいまさらアニメの一兵卒など務まるわけがない」「漫画家は絵が描ければすぐにでもアニメができるような幻想にとらわれる」「勘違いして、プロダクションを興そうなんて甘い」「アニメーションは絵と同じくらいに撮影の要素を大切に考えない者は失格。鷺巣君(うしおのこと)はそのことをいちばんよく知ってるから独立しても仕事が舞い込むんだ」そんな上からのお説教ばかりで、1時間話し合っても手塚の頼みを聞いてくれるのかくれないのか、いっこうに埒があかない。うしおが手塚に目配せすると、手塚も肝が決まったらしく、芦田に対してきっぱりと、「私の考えが甘かったので、これで失礼いたします」。その語気には、それでも自分はやるという覚悟の決意が込められていることを、うしおは感じ取った。表に出ると手塚は厳しい表情をしていた。それを見てうしおは、彼は必ずやるだろうと思い、無言で手を差し出すと、彼も無言で手を固く握りしめてきた。(うしおそうじ著『手塚治虫とボク』草思社より)その後、うしおのもとには手塚が『鉄腕アトム』の第一話、営業用のパイロットアニメに本格的に取り組んでいるという噂が流れてくる。テレビアニメ『鉄腕アトム』の誰も予想しなかった、恐ろしいばかりのヒットは、日本中が知るところだが、芦田巌はその後どうなったのだろう?芦田巌という名前は今ではほとんど忘れ去られているが、1940年代の後半から1960年代までは、アニメ界では知られた人物だったらしく、大塚康生も芦田の門を叩いている。(以下、大塚康生著『作画汗まみれ』アニメージュ文庫より引用)芦田漫画という会社は社長の芦田巌さんという方が戦前からのアニメーターで、山本(善次郎=早苗)部長とは古い友人という関係で東映動画から仕事が行っていました。実をいうと、私は東映動画に入る前に、そのころ三軒茶屋にあったその芦田漫画に「入れほしい」と頼みに行ったことがありました。そのときに、芦田巌さんが私の絵をみてこういわれました。「きみの絵はアニメーションに向いていないよ、絶対やめたほうがいい…」そういわれて、私はスゴスゴと引き揚げたことがあったのです。(引用終わり)手塚治虫も1947年、東京進出を考えて自作を手に出版社に営業をかけていたときに、たまたま京王電車の駅の電柱に漫画映画制作者の求人広告が貼ってあるのを見て、『新宝島』や自著の赤本数冊をかかえ、そのままその漫画映画のプロダクションに飛び込み、使ってほしいと頼んだという。しかし、「一度、出版界の味をしめてしまうと、報酬その他、割がいいもんだから、けた違いに不利な漫画映画などつくる気になれない。諦めるんだな」と、断られたという(手塚治虫著『ぼくはマンガ家』より)このエピソードは1967年の東京新聞「私の人生劇場」でも手塚自身が語っているが、何というプロダクションだったのかはどちらにも書かれていない。書かれていないが、それはどうやら芦田漫画だったらしく、手塚以外の著者(Mizumizuが見た中では、うしおそうじや中川右介)の本には、1947年に手塚が飛び込み入社志願をして断られたのは芦田漫画だと書かれている。ただ、手塚治虫本人がそう言ったのかどうか、Mizumizuとしては確認が取れない。ちなみに2012年9月の「虫ん坊」では、東京新聞「私の人生劇場」をもとに記事をまとめているので、昭和21年(1946年)となっているが、『ぼくはマンガ家』では、「ぼくが戦後はじめて東京の街を見たのは昭和22年(1947年)の夏だった」とあり、Mizumizuもこちらを採用している。なぜなら『新宝島』が発売になったのが1947年。手塚はその大ヒット作を持って東京の出版社に営業をかけるのだから、1946年ではおかしい。話は戻って、1947年に手塚が飛び込んだ会社がもし芦田漫画だとすると、手塚治虫は、まだ東京進出を果たしていない、駆け出しのころに1回、漫画界の頂点に立ち、アニメに進出する直前に1回の、計2回も芦田に弟子入りを志願したことになる。一時はアニメ界の第一線に立っていた、その芦田厳がその後どうなったのか、実はよく分かっていない。だが、うしおの前掲書には、芦田のその後が書かれている。手塚治虫がアトムのパイロットフィルムを制作しているという噂を、うしおが聞いてからしばらくたって、夕刊記事の三面記事に小さく、三軒茶屋のパチンコ店内で地回りのチンピラやくざの抗争でピストル発射事件があり、客の芦田厳氏にそれ弾が当たったが無事だという記事が載っていた。「ああ、相変わらず賭け事が止まらないのだな」とボクは概嘆した。(『手塚治虫とボク』より)さらに数十年経って、うしおは芦田漫画のあった場所の近くにたまたま行く機会があった。芦田漫画は畳屋にかわっていて、その畳屋の親爺にそれとなく芦田のことを聞いてみると、親爺は物凄い剣幕で怒りだし、畳を斬り落とす包丁を握りしめながら叫んだという。「あんたは芦田と親しいのか。親しいなら、芦田の現住所を教えろ。あいつには借地権の線引きでごまかされたんだ」。
2024.04.17
-

(旧)虫プロのアニメーターのワガママぶり――コーヒーブレイクにBGM、管理職の目を盗んで同業他社のアルバイト
うしおそうじ(鷺巣富雄)は、1950年代には手塚治虫と並ぶ人気漫画家だった。もう彼の漫画を覚えている人は少ないだろうが、漫画家をやめたのちに彼が手掛けた『マグマ大使』『怪傑ライオン丸』は、日本の特撮黎明期の優れた作品として記憶している人も多いだろう。そのうしおそうじの著作『手塚治虫とボク』は、実に面白い。手塚治虫とボク [ うしおそうじ ]うしおが手塚治虫と一緒に映画を見に行ったり、旅行したりして親しくつきあったのは1950年代前半。手塚が漫画の神様と呼ばれる前だ。そのころの手塚治虫の図抜けた才能を目の当たりにして、うしおそうじは「驚倒した」と言っているが、今日取り上げるエピソードは、うしおが漫画家をやめて制作会社ピープロの社長となり、手塚治虫は(旧)虫プロの社長となって『鉄腕アトム』で一大ブームを巻き起こし、同作が『アストロボーイ』として、アメリカで放映されると決まったころの話。うしおは『鉄腕アトム』が、1話1万ドル(当時のレートで360万)でアメリカに売れたという噂を聞き、手塚治虫に直接電話してお祝いの言葉を述べた。本人はそれだけで電話を切るつもりだったが、手塚治虫が折り入ってお願いしたいことがあり、今からそっちへ行きたいと言う。手塚のお願いというのは、うしおのピープロで『鉄腕アトム』を作ってほしいというものだった。驚いたうしおは「いいですけど、一体どうしたんですか」と聞く。すると手塚はすぐにうしおのもとに駆けつけてきて、こんなことを言ったという。「目下、うちの連中はアトムを作るのは嫌だと言い出したんです。飽きて、もううんざりだと言い、『ジャングル大帝』をカラーで製作したいと言う。体のいいサボタージュ気分が職場に蔓延してボクは困っているんです。そりゃあ、彼らの気持ちは分かるし・・・」「彼らの気持ちも分かるし・・・って、それはちょっとおかしくないですか。ボクはよそながら聞いてますが、虫プロの社員は会社に対して10時と3時にコーヒーブレイクをもうけ、就業中は有線でムーディなBGMを流せと要求して、会社はその要求をのんだともっぱらの噂ですよ」「ええ、その噂は一部本当です」うしおの詰問調の質問に、手塚は不快感をあらわにしたという。「だってうしおさん、ボクは仕事をしているとき、ムーディーなBGMが流れているほうが効率が上がるんですよ」「手塚さんが漫画家として仕事をしているときに名曲がバックに聞こえてくるほうが快適に仕事がはかどるということは分かります。だからといって、虫プロの職場で従業員たちの要求をなんでも受け入れてやる、その考え方は行き過ぎではないですか。」うしおは、虫プロはいまや業界だけでなく、あらゆる産業界でも注目する企業になってしまったのだと話すが、手塚は不機嫌になる一方。手塚治虫には話さなかったが、もっと呆れた虫プロのアニメーターの実態をうしおそうじは聞き及んでいた。本来なら『鉄腕アトム』の絵を描くべきところを、こっそり東映動画のアルバイト仕事をしているという話を何度も聞いていた。彼らはトレース台の下に東映動画の仕事を隠しておき、管理職の姿が見えなくなると、机の上の『鉄腕アトム』をどけて、それを取り出し、アルバイトに精を出しているというのだ。<以上、前掲書からそのまま引用>うしおは手塚治虫の顔色を見て、経営について口出しするのをやめ、アトムの仕事を引き受けている。最初は13本の約束だったが、結局、2年にまたがって39話分も応援をした。うしおそうじの証言は具体的で信憑性が高い。虫プロのアニメーターがあれがしたい、これは嫌だとワガママを言い、しかもこっそり他社のアルバイトまでしていたという話は今ではほとんど聞かないが、当時はどうやら業界内部では有名な話だったということだ。
2024.04.14
-

アニメーターの薄給は手塚治虫が元凶――は、明確なデマ
橋本一郎『鉄腕アトムの歌が聞こえる』という書籍があるが、著者はYou TUBE動画も開設して、手塚治虫とその時代について様々な証言を行っている。鉄腕アトムの歌が聞こえる ~手塚治虫とその時代~【電子書籍】[ 橋本一郎 ]その中に手塚治虫が率いていた(旧)虫プロのアニメーターの高待遇ぶりを語った動画がある。https://www.youtube.com/watch?v=dwvTatm6Qk88分17秒ぐらいから。(旧)虫プロのアニメーターは凄い勢いだった。東映動画から金に糸目をつけずに雇ってきたうえに、時間外が青天井だったため、とてつもない収入があった。自宅を(都内に)次々新築していき<Mizumizu注:虫プロで3年働くと都内に家が買えたという話もある>、虫プロの駐車場には高級車がずらりと並んでいた。<以上、発言をまとめたもの>これはなんといっても、『鉄腕アトム』の大ヒットとそれに伴うマーチャンダイジングの急拡大がもたらしたもの。 手塚治虫自身『ぼくはマンガ家』(1969年)というエッセイで、次のように書いている。<引用>「アトム」がそれほど話題にならなければ、類似作品も作られなかったろう。「アトム」が儲かるとわかるとスポンサーはどんなに大金を積んでも、どこかにテレビ漫画を作らせようと躍起になった。アニメーターたちの引き抜き合戦が始まり、アニメーターの報酬は、うなぎ登りに上がった。高校を出たか出ないかの若い者が 月々何十万もサラリーを稼ぎ<Mizumizu注:上掲の橋本氏の朝日ソノラマでの月給は、虫プロ全盛の時代に2万弱だったという>、マイカーを乗り回すといった狂った状態になった。<引用終わり>つまり、手塚治虫の『鉄腕アトム』がもたらしたのは、アニメーターバブルだったのだ。安い給料で奴隷労働させたなんて、デマもいいところ。手塚治虫が生きていれば、こんなデマはまかり通るはずがない。丹念な取材に定評があり、『手塚治虫とトキワ荘』の著者でもある中川右介は、以下のように総括している。https://gendai.media/articles/-/75170?page=4<引用>アトムを真似できなかった制作会社『鉄腕アトム』の放映開始は1963年だが、早くもこの年の秋に、3本の子供向けTVアニメが、制作・放映される。虫プロは『鉄腕アトム』を週に1本製作するため、技術面でさまざまな技法を編み出した。それは極力、絵を「動かさない」という本末転倒したもの、ようするに、「手抜き」なのだが、そのおかげで、日本のアニメは「ストーリー重視」になった。この手法はすぐに真似され、1963年秋からTCJ(現・エイケン)の『鉄人28号』『エイトマン』、東映動画の『狼少年ケン』が放映された。「アニメが儲からない」のは、虫プロではなく、この2社のせいである。TCJはテレビコマーシャルの制作会社で、当時のテレビCFにはアニメを使うものが多かったので、アニメ部門があった。『鉄腕アトム』の成功を見て、電通がTCJに発注したのが『鉄人28号』で、TBSが発注したのが『エイトマン』だった。TCJは虫プロと異なり、電通やTBSの下請けとして、安い価格で受注したのだ。このとき、利益の出る価格で受注していればいいのに、コマーシャルで儲けていたので、赤字覚悟で受注した。『鉄人28号』はTCJもアニメの著作権が持てたので、マーチャンダイジング収入があったが、『エイトマン』のアニメの権利はTBSと原作者の平井和正と桑田次郎にしかないので、キャラクター商品が売れてもTCJの収入にならない。『狼少年ケン』はNET(現・テレビ朝日)が放映した。NETは当時は東映の子会社で、東映社長の大川博がNETの社長だ。東映動画も、もちろん東映の子会社である。東映はNETに対し、「東映動画に適切な製作費を払うこと」と指示できる立場にあったが、そうしなかった。それでも東映動画は『狼少年ケン』の著作権は保持していたので、キャラクターのマーチャンダイジング収入は得た。テレビ局と広告代理店は、アニメの利益がキャラクター商品にあると分かると、その権利を得て、一度得ると手放さない。その結果、制作会社は低予算を押し付けられたあげく、著作権も持てず、経営は厳しくなり、社員の給料が安くなる構造が生まれる。これは、別に手塚治虫のせいではないのだ。さらに、東映動画はTVアニメに乗り出すと人員を増やしたが、今度は人件費が経営を圧迫して人員整理をし、労働争議になり、ますます正社員は採用しなくなり、下請け、孫請、フリーランスを使うようになっていく。その過程では、腕のいいアニメーターは正社員だった頃よりも収入は上がった。<引用終わり>東映動画のやり方は、実にエグい。だが、人員整理(つまりクビ切り)をして、正社員ではなく下請けにやらせるという構図は、なにもアニメ業界に限ったことではないし、そうやって東映動画は生き残ったのだ。 一方の虫プロは、テレビ局からの受注減、劇場公開長編アニメ映画の赤字、それに労働争議も重なって倒産した。 アニメーターバブルが弾けた時、多くのアニメーターは収入を減らしただろうが、才能のある一握りだけは、大きな組織を離れることで、逆に収入が上がる。これもよくある話だ。そして、手塚治虫が労働者であるアニメーターに、いかに「甘かった」か。それは、うしおそうじの『手塚治虫とボク』(草思社)に端的な例が書かれている。<以下、次のエントリーで>
2024.04.12
-

『手塚のセイダーズ』が喧伝する「アニメ制作費が安いのは手塚治虫のせい」は明らかに無理がある
アニメ制作費が安い――この話は今もよく聞くが、それを60年以上も昔の『鉄腕アトム』のせいだと信じている人が、いまだに一定数いることには呆れてしまう。『日本アニメ史』(中公新書 2022年)著者である津堅信之氏は、日本アニメ史 手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの100年/津堅信之【1000円以上送料無料】さすがにそれは「飛躍しすぎ」と結論づけているが、同氏のネット記事https://president.jp/articles/-/57267?page=5のタイトルはアニメ業界が激務薄給になった「元凶」と批判も…『鉄腕アトム』を激安で作った手塚治虫の誤算と、「中身をよく読まない」多くの一般ユーザーを誤解させるものになっている。しっかり中身を読んでみれば、同氏の結論は以下だ。(引用)『アトム』以来半世紀以上を経た現在まで、安い制作費の原因を手塚に押しつけるのは、話を飛躍させすぎている。自社が制作する作品の価値を認識し、それを権利として獲得することは、後続のアニメ制作会社にも課せられていたはずである。そういう後続他社の努力の欠如、もしくは変えられなかった責任を問う声は、なぜか小さい。(引用終わり)まったくの同感…というか、普通に考えたら、当たり前のことではないか? 60年も昔に、誰かが新しい分野を開拓した。不可能だといわれることをやってのけた。そのインパクトはあまりに大きく、新しいビジネス(キャラクター販売、アニソン、メディアミックスへの流れ)が生まれた。その実績は目覚ましいもので、恩恵を受けている後輩たちは枚挙にいとまがない。2024年現在、東京駅近くの地下には主にアニメのキャラクターグッズを売る店がずらりと並んでいる場所があるが、これだって端緒を開いたのはアトムだ。ところが、それをきちんと評価するアニメ関係者はほとんどおらず、逆にアニメーターの過酷な労働や低賃金は、手塚治虫のせいだというトンデモ説はいまだに跋扈している。キャラクターや関連グッズが売れるのは自分たちの手柄。でも、アニメの制作費が安く、アニメーターの待遇が悪いのは手塚のせい?おかしーわ!新しい分野に参入する時、戦略的に廉価設定をするのは、ビジネスシーンではよくあることだ。後続他社の努力の欠如や責任を問う声が「なぜか小さ」く、手塚治虫の死去後に「手塚のセイダーズ」がワラワラ出てきて、声が大きくなっていったのはなぜか。それは、だいたいみんな分かっているハズだ。手塚治虫が生きていれば間違いなく反論しただろう。皆忘れているが、漫画が悪書として「焚書」の憂き目にあった時も、新左翼と呼ばれるトンチンカンな評論家の酷評で漫画家たちが苦しめられた時も、「最前線」に自ら出向いて反論したのは、誰あろう手塚治虫だった。それを、彼がこの世を去り、何も反論できなくなくなったとたんに口汚く攻撃するなんて、実に卑劣ではないか。しかも、アトムに関しては、その過去の状況さえ、悪い方に脚色されている。(前掲ネット記事からの引用)まず、約4年間・全193話放送された『アトム』は、その期間ずっと1話55万円だったのではない。当時の虫プロスタッフの証言によると、話数を重ねる中で徐々に上積みし、最終的には1話300万円程度までになっている。また、1965年10月放送開始のテレビアニメ『ジャングル大帝』では、制作現場に投入される予算は1話250万円で管理された。さらに、『アトム』の当初契約1話55万円は、あまりにも安すぎるとして、手塚には告げない形で虫プロの事務方が再協議し、代理店(萬年社)が1話あたり100万円を補填ほてんして、合計155万円で制作していたとの証言もある。(引用終わり)津堅氏は、日本のアニメ史を俯瞰したうえでの客観的な記述を心がけている。中公新書の『日本アニメ史』には、上記のネット記事には載っていない関係者の証言も多くあり、できる限り幅広い業界人の声を集めようと努力している姿勢は尊敬に値する。今の日本のアニメ業界が抱える問題を語るなら、こうしたマジメな書籍を一読してからにしてほしい。
2024.04.09
-
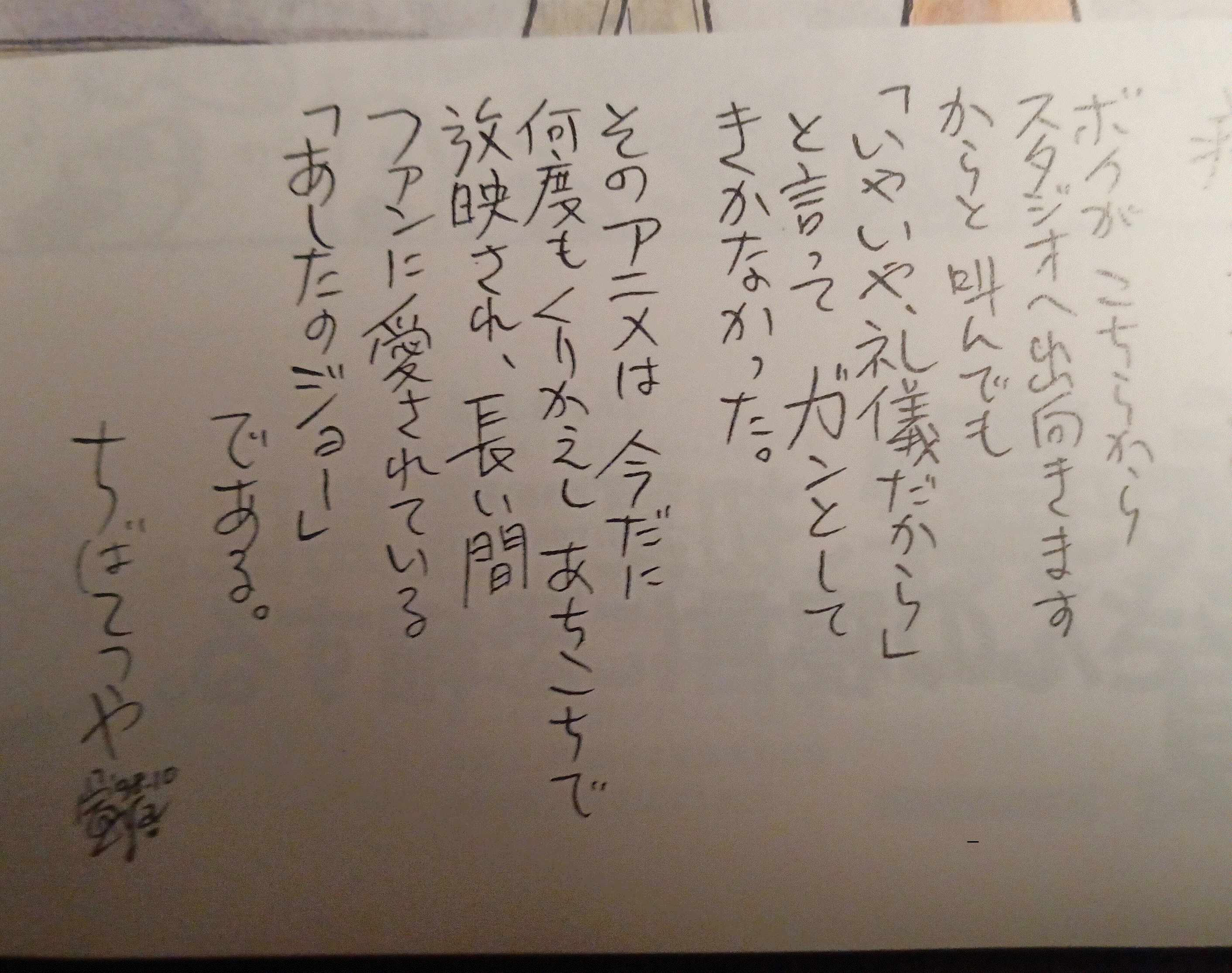
Wikipediaの嘘――虫プロ制作『あしたのジョー』に社長だった手塚治虫が関知しなかった
今でも時々メディアでお見かけする漫画家ちばてつや。いつどんな話を聞いても、本当に人柄の良い方だなぁと感服する。ちば氏の語る、亡くなってしまった昭和漫画界の巨匠との思い出話は貴重なうえにとても面白いのだが、『あしたのジョー』の初代テレビアニメについて、Wikiには吉田豪氏の丸山正雄氏へのインタビューからの引用として、「虫プロダクションでの制作であったが、社長の手塚治虫は本作品をライバル視していたため、アニメ版の制作にも関知しなかった」とある。だが、これはちばてつや氏の証言によれば、ウソだ。『ある日の手塚治虫』でちば氏は、『あしたのジョー』を(旧)虫プロでアニメ化する企画が持ち上がった時に、「手塚先輩がわざわざ打合せで訪ねてきてくださった」と書いている。工事中で道路に穴があいていて車が通れなかったので、手塚治虫は車を待たせ、穴のあいた道路にわたした板の上を歩いてきたそうで、その時の情景をちば氏がカラーで描いている。その絵の下の、ちば氏直筆の文が以下。危ない板を渡ってくる姿を見てあせったちば氏が「こちらからスタジオに出向きます」と叫んでも、手塚氏は「いやいや、礼儀だから」と言って、ガンとして聞かなかった、とある。『あしたのジョー』が「今だに何度もあちこちで放映され、長い間ファンに愛されている」アニメ作品になったことを、ちば氏が嬉しく思っているのは確かだ。ちばてつやのところに手塚治虫が打合せに行ったことを、インタビュー時には丸山正雄氏が忘れてしまっていただけのことかもしれない。しかし、原作者本人は20年たっても憶えていて、手塚氏の律儀さに恐縮しているのに、「ライバル視していたから関知しなかった」などと、事実と違う話を言いふらすのはいったいどういう了見なのだろう?
2024.04.05
-

手塚治虫とルドルフ・ヌレエフ
「手塚治虫の奇跡は、映画やショービジネスの世界ではなく、漫画という繊細で奥深い大衆娯楽によって生み出された。この飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続ける風変りな男のおかげで、漫画ははるか僻地の質素な家に住む人々をも夢見心地にさせた」これはローラン・プティの『ヌレエフとの密なる時』(新倉真由美訳)をパクって、『新宝島』から1950年代の「どこでも手塚(どの雑誌を開いても手塚治虫の作品が巻頭カラーを飾っているという意味)」時代をイメージして作った文章だ。変更したのは赤文字の部分。ヌレエフ→手塚治虫、バレエ→漫画、芸術→大衆娯楽に変えただけ。Mizumizuは個人的には手塚漫画は芸術だと思っているが、本人がそう言われるのを嫌ったので、あえて忖度した。【中古】 ヌレエフとの密なる時ある分野の人気のすそ野を爆発的に広げる革命児には似た部分が多い。バレエではヌレエフが手塚のポジションにいると思う。ヌレエフ以前にも偉大なバレエダンサーはいたし、バレエを好んで観る人たちも確かにいた。だが、ヌレエフの登場によって、それまである程度固まっていて、閉鎖的だった「バレエファン」は一挙に様変わりする。手塚治虫以前にも、もちろん売れっ子の漫画家はいた。だが、手塚の「映画的手法」によって、日本各地の少年少女が文字通り「夢見心地」になったのだ。矢口高雄の『ボクの手塚治虫』は、「はるか僻地」で質素な生活をしていた少年が、いかに手塚漫画に魅了され行動したかを生き生きと描いている。手塚作品を読みたいがために、矢口少年は、雪深い山道を何キロも歩いて町の本屋に行く。手塚作品を買いたいがためにきついアルバイトをして、本屋の主人に「このカネはどうした?」などと疑われ、憤慨して自分がどうやってそのお金を作ったかを説明し、そこから本屋の信頼を得ている。ボクの手塚治虫【電子書籍】[ 矢口高雄 ]このファンの熱情は、ヌレエフの公演を見ようと遠くからでも駆けつける新しいバレエファンの心理とダブる。そして、もう1つ、大いなる共通点。再び『ヌレエフとの密なる時』から。今度は改変なして。「驚いたことに、彼の出演料は非常な人気を博していた他の出し物に比べ比較的少なかった。そう、それは本当にささやかなものだった。『僕にとってそれはとても良いことだと思う。だってわかっていると思うけれど、僕は来年も踊っていたいから』それは理にかなっていた。天文学的な出演料を要求し、毎年踊る機会の減っているダンサーたちにとってなんという教訓だろう。この時期ヌレエフは1月から12月まで約250回の公演を行っていた。それはおそらく多すぎた」手塚治虫が原稿料にこだわらなかった、むしろマネージャーに「安くしろ」と言っていた話はよく知られている。ちばてつやの●分の1だったとか、アニメージュの編集長だった鈴木敏夫(現在はスタジオジブリ代表)に「僕の作品は単行本で売れるから、原稿料はいくらでもいい」と言ったとか。単行本で稼ぐから、というのも本当だろうけれど、実際のところ、長い間漫画界の第一線で活躍してきたこの大天才は、原稿料を上げたのちに人気が落ちて、あっけなく切られてしまう(一時的な)流行漫画家の姿をきっと見ていたのだろうと思う。若いころの手塚は、「この商売の人気は2年ぐらい」と言っていたし、売れなくなったら医者に戻ろうとしていた感もある。そのための道も残していた。たとえ人気がなくなっても、原稿料が安ければ頼むほうは頼みやすい。いったん原稿料を上げて、人気がなくなったら「下げますから仕事ヨロシク」と言っても、相手は依頼しようとはなかなか思わないものだ。だったら、最初からお手頃な値段設定にしておいたほうが、競争力を保てる。一種、企業家のような発想で入れ替わりの激しい漫画業界を40年以上も生き抜いたのだ。ヌレエフは非常に公演数の多いダンサーだった。手塚治虫もすごい量産漫画家だった。そしてその対価に大きなものは要求しなかった。「来年も踊っていたいから」というヌレエフの言葉は、「来年も描いていたいから」とすれば、そのまま手塚治虫の言葉だ。むろん、あちこちでスキャンダルを引き起こす奔放なバレエダンサーとそういった問題とは無縁の博覧強記の漫画家の生き方は大いに異なっている。だが、「死の病(当時)」がその体を蝕んでも、なんとか仕事を続けようとしたその執念は似ている。ヌレエフはダンサーとしてキャリアをスタートさせたのち、振付師としても名声を得た。晩年にはクラシックバレエのレパートリーを演奏するオケの指揮も行い、好評を得ていた。亡くなる3か月前、ヌレエフはローラン・プティの公演に指揮者として参加したいと自分から申し出ている。オケの指揮をするヌレエフ、なんて素敵なアイディアだろう!――プティは喜んで了承する。「なるたけ早く仕事に着手して暗譜したいから、急いで楽譜を送って」だが、二人の構想が実現することはない。亡くなる数週間前まで、ヌレエフは創作作品で自らも踊る意欲を持ち続けていた。当然と言えば当然だが、現実に彼にできたのは、楽屋で横になっていることだけだった。それでもヌレエフは楽屋にいて、亡くなる数日前になってようやく病院に戻った。手塚治虫も最晩年まで多くの仕事を抱え、新しい分野の構想や依頼もあった。病院のベッドで、寝かせようとしても必死になって起き上がろうとしたという。彼が亡くなった時、ニュースで速報が流れた。Mizumizuはその瞬間、たまたまテレビを見ていた。「60歳の生涯を終えた」というアナウンサーの言葉に、「えっ? うそ。違うでしょ」と思った。熱心な読者ではなかったのに、ちゃんと年齢のことが頭にあったのは、生年月日による性格占いなどの対象に手塚治虫がよくなっていたからだ。みんな手塚フィクションにいっぱい食わされていた。したり顔で手塚治虫がもって生まれた性格や運勢などを断定していた占い師には、笑ってしまう。ゲーテを想起させるような「手塚治虫最期の言葉」を知って感動するのは、もっと後のこと。「頼むから仕事をさせてくれ」――この最後とされるセリフが、ある種の手塚フィクションでも、あるいは本当の本当でも、それはどちらでもいい。手塚もゲーテ同様、歴史上の人物として語り継がれることになるのだから。ゲーテの臨終の言葉「もっと光を!」については、以下のサイトが詳しい。https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=277
2024.04.02
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- ヒルトン東京お台場 モーニング …
- (2024-11-27 21:01:12)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- コストコのホノルルクッキー★パイン…
- (2024-11-06 10:12:11)
-
-
-

- 日本全国のホテル
- ホテルルートイン 伊那インター
- (2024-11-28 06:00:12)
-







