2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年05月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
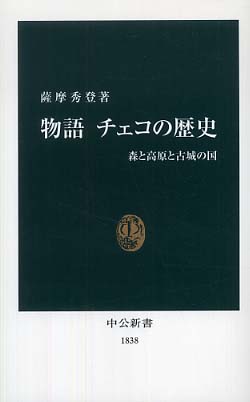
★ 薩摩秀登 『物語チェコの歴史』 中公新書(新刊)
▼ ご存知、中公新書の看板、『物語○○の歴史』シリーズの最新刊。今回の旅は、はるか歴史の彼方に消えさりながら、近年力強く復活した「中欧」、それもチェコへと足を踏み入れています。このシリーズは、記憶が確かなら、藤沢道郎『物語イタリアの歴史』から始まったはずだが、全体としては、玉石混交というイメージがありますね。どちらかといえば、文学関係者にやらせた方が、面白くなる傾向が無きにしもあらず、という印象を受けないではない。▼ とはいえ、それはどうやら杞憂に終わったようです。内容は10章立て。中世と現代では、必ずしも連続していない、チェコというネーションの歴史をまとめるという難しい作業が、丹念におこなわれていて面白い。これをお読みの皆様のためにも、簡単にまとめておきたい。▼ 第1章と第2章は、チェコの起源にスポットライトをあてています。第1章はモンゴル系遊牧民・アヴァール人支配下から独立した、スラブ系キリスト教国の中世モラヴィア王国のお話。モラヴィア王国は、自前の司教区として独立した教会をもちたいという念願を抱き、複雑な国際関係のアヤが絡んで、ビザンツ帝国に使節を派遣することになった。この動きが、めぐりめぐって、チェコ領内では断絶するものの(カトリック)、スラブ語典礼を生み、やがて現代につながる「スラブ語による典礼をおこなう教会」「キリル文字」の成立と普及の直接の端緒になったらしい。第2章は、中世チェコ王国の礎を築いた聖女アネシュカの話。王女の身でありながら、神聖ローマ帝国皇帝、シュタウフェン家との政略結婚を拒否。聖女アネシュカは、13世紀に盛んにおこなわれた、「清貧」を説くドメニク会・フランチェスコ会などの托鉢修道会運動に挺身する反面、教皇権・皇帝権のハザマの中で、出身一族プシェミスル家のために巧みにとりもってゆくという。▼ 全盛期中世チェコ王国は、濃密に描かれていて心地よい。第3章は、ルクセンブルク家カレル4世の、チェコ王・ドイツ王・神聖ローマ帝国皇帝の物語。カレル四世は、これ以上のドイツの混乱を避けるため、諸侯分立の現状を追認する金印勅書を発布した。それだけはなくカレル四世は、現在のチェコ共和国を中心としてシレジアまで含んだ諸邦に、王個人ではなく「聖ヴァ-ツラフの王冠」と呼ぶ王冠に忠誠を誓わせることによって、フランスやハンガリーと同様に王国の取りまとめに成功したらしい。その「チェコ王冠諸邦」と新帝国の中核が、プラハ。第4章は、そのプラハ大学を中心とした、「異端」説教師ヤン・フスたちの教会改革運動が取りあげられる。教皇の大空位時代、堕落した教会への不満は、神学者ジョン・ウィクリフの影響を受けて、最高の規範=聖書を根拠としての、教会・聖職者批判を巻きおこした。ローマ教会を否定まではしないフスの処刑。それは、教会・聖職者に不道徳がはびこる場合、世俗権力が悪を追放する様にもとめていたフス派(のちのプロテスタントと共通)の憤激を買い、「フス派戦争」をおこしたという。フス派は、三十年戦争で撲滅されるまでカトリックと共存したものの、やがて忘れ去られる。近代に入ると、フスはチェコ民族精神の誇り・栄光として語られ、1999年にはカトリック教会が名誉回復までおこなうと言うのだから、驚く他はない。▼ 近代のチェコには、多くのページがさかれています。第5章では、このフス戦争からハプスブルク期にかけて進んだ、居城を構え君臨する大貴族から、国王の宮廷に軍人として仕える地位へ転落した、モラヴィア貴族の一族史が語られています。また第6章では、フス派に近い出版業者メラントリフの活躍を通して、聖職者の独占から解き放たれ、ラテン語の読み書き、書籍を通じた知識・技能・教養がもとめられた、16世紀プラハの文化が描写され、たいへん興味深い。第7章では、チェコの「再カトリック化」の進行過程の検証。三十年戦争の発端地チェコでは、ハプスブルクの皇帝権とカトリック教会による絶対主義体制が築かれたという。だが、反宗教改革をめぐるイエズス会と既存修道会の主導権争いは、プラハ大学移管問題では、大学吸収を画策したイエズス会と「大学の自治」を守ろうとする大司教勢力の争い、として現れた。その過程で出現したカトリック派知識人たちは、チェコの文化・歴史・言語への愛着を深めてゆく。このように、「郷土愛」「郷土色豊かなカトリック」を通して、緩やかにカトリック化が推し進められていった様子は、改宗の暴力性を否定するだけでなく、受容側が普遍(カトリック)にいかなる役割を割り当てるかにもつながっていて、まことに興味深い。▼ 第8章は、生誕二五〇周年を意識したのか、モーツアルトのご登場! チェコとモーツアルトの、5年に満たない邂逅が描かれていて面白い。「啓蒙絶対主義」の下、社会の世俗化と強力な国家統合が推し進められたハプスブルク帝国。帝国政府による中央集権化に抵抗する形で、各領邦において「国おこし」「愛郷主義」の運動がもたげる。帝国の一地方都市へと転落したプラハでは、『フィガロの結婚』が空前の大ブームになり、モーツアルトを呼び寄せ、オペラ『ドン・ジョヴァンニ』の初演も行なわれたという。モーツアルトとプラハの幸福な出会いは、必見であろう。第9章では、内国産業博覧会をめぐる政治が、民族的自覚を強めつつあったスラブ系チェコ住民と、ドイツ系住民と対立を深めさせてゆく過程が描かれています。「レオポルト2世チェコ王戴冠一〇〇周年」記念する博覧会は、最終的にドイツ系資本家がボイコット。その博覧会は、気球・噴水・世界各国の飲食店といった遊園地スペクタクルを人びと提供しただけではない。経済・技術の分野でも、チェコ人が他民族に劣らない存在であるか誇示する場を超え、他のスラブ民族の民族意識を高揚させるイベントになったという。▼ 第10章は、かつてチェコに存在した、スロバキア人とドイツ人、ユダヤ人についての、あまり触れられたくない物語になっています。スロバキアは、「聖イシュトヴァーンの王冠」に忠誠を誓った、ハンガリー支配地域でした。彼らは、ハンガリー王国北方のスラブ人であって、チェコ人とは言語の違いもほとんどないという。第一次大戦後、「スロバキア語」を話す民として目覚めた彼らは、チェコ人とともに独立。ただ「チェコスロバキア人」とは名ばかりのチェコ人優位には、不満を抱かざるをえない。ナチス・ドイツの影響下での歴史上初めての独立国家、ならびにナチへのレジスタンスの経験は、スロバキア民族意識を高揚させ、「プラハの春」直後には連邦共和国制移行(1968)、やがて社会主義政権崩壊後における、現在の「チェコ」「スロバキア」の分離(1991)につながったという。またチェコ領内のユダヤ人の物語も、とても面白い。東欧は、西欧よりユダヤ人迫害は少なく、ユダヤ人を財産として国王保護下におき隔離する政策が採られていたものの、近世以降、ユダヤ人迫害は頻発した。啓蒙主義の影響下、職業・移住の自由がかつてなく認められたユダヤ人は、各地で「国民の創生」が行われると、チェコ人・ドイツ人に同化するものが急増する一方で、ヨーロッパ社会ではこれまでにない「異形」のものとして形象され、強力な「反ユダヤ主義」が生まれてくるようになる。1918年建国のチェコスロバキア共和国は、このユダヤ人に独立した民族として最初に公認した国家であり、そこでフランツ・カフカ、マックス・ブロードなど、ユダヤ人文学者・作曲家などの文化が華開いたという。▼ もともとチェコは、20世紀半ばに、人口の1/4以上を占めたドイツ人を、国外に追放して今に至る国家です。かつてのドイツ語文化圏、中欧文化圏の名残は、大学、墓碑、シナゴーグ、オペラ劇場など、今も街角の至る所に、痕跡の形でそのまま残されています。痕跡が語る「不在」は、ドイツやカタルーニャ、アイルランドといった歴史を叙述することとは違った楽しさの反面、否応なしに記述の困難さに帰着するでしょう。その困難さの中で、まとめられた「物語チェコの歴史」。非常に面白い作品として、お勧めできます。▼ ただどうでしょう。第8章のモーツアルトは……いささか反則技ではありませんか? たしかに、モーツアルトの方が、はるかに人口に膾炙するとはいえ、生誕二五〇周年に媚びた軽薄な感じがしないでもない。モーツアルト・オペラとプラハ劇場建設の皮相な解説に走るくらいなら、「国民楽派」のドヴォルザークと、ウィーンの音楽界の柱石、ブラームスとの関係をオーソドックスに描いても良かったのではないか。別にありふれていても、いいんだし。スメタナもいて、モーツアルトはないでしょう。19世紀における、ドイツ周辺諸国の「音楽と劇場文化」が、ドイツ・ナショナリズムの中核であったドイツ音楽の流入と覇権の確立を前にして、どのように受容・排斥・変容をとげていったのか。国民楽派なる概念の再検討を含めて、ドイツ文化圏内の「周縁」音楽文化を知りたかっただけに、残念な感じがします。また、6章と7章は内容も入り組んでいるのだから、別の話を描いても良かったような気が、しないでもありません。それこそ、ドイツ文学とチェコ文学の相克なりなんなり、書いて欲しかったと思う。▼ ワールドカップも近づいている今日。 ドイツ文化圏をチェコから眺めるのも、一興。ぜひ、ご覧あれ。追伸 断じて、ヤナーチェクを出さなかったから怒っているのではありません。 念のため。評価 ★★★☆価格: ¥861 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 31, 2006
コメント(2)
-
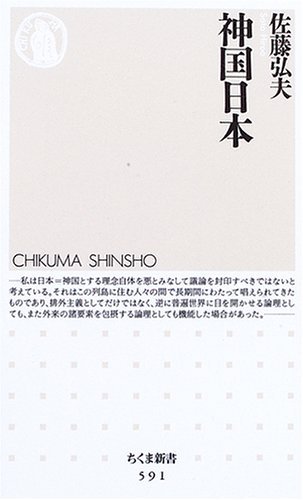
★ 佐藤弘夫 『神国日本』 ちくま新書(新刊)
「日本は天皇を中心とした神の国である」森首相のこの発言に、左右両派が入り乱れて論争したのは、記憶に新しい。ところが、「自民族中心主義」「天皇中心主義」と同義とされ、戦前は「国体の本義」で鼓吹された神国思想。実は本来、まったく逆の思想だったのだというのが、この書のキモになってます。これがまた、コギミよい位面白い。 神国思想、それは鎌倉の蒙古襲来から始まる。それまで日本人は、自国 社会について、仏教思想の影響下、悪人の群れ集う世紀末社会(末法)、 世界の中心から遠く離れた小島、「辺土粟散」と認識していた。それが 蒙古襲来によって一変。神国思想は、日本を神孫が君臨し、神々が守護 する聖地として丸ごと肯定するようになる。それは、日本的なるものの 自覚と深く結びつき、室町・江戸時代と継続する、日本人による 「日本固有の文化」の胎動であり、他国に対する自国の優越、を主張す るようになる始まりだったのだ…この通俗的神国思想理解を一刀両断。もともと、日本書紀から近現代にまで見られる「神国思想」は、論者によって差異がある。加えて、蒙古襲来以降に限ってもおかしい。そもそも神国思想は、他界の仏が「神」の姿をとって「垂迹」しているという考え方であって、インド・中国が「神国」ではないのは、別の姿をとって「垂迹」している(インドは釈迦)からにすぎない。事象の裏に共通の真理=「法身仏」をみるこの思想は、国土・民族の選別神秘化に本来なじまないものという。その衝撃的な議論を確認しておきましょう。そもそも、天皇の地位の神格化とともに、その祖先神・皇祖神たる「アマテラス」とそれを祭る伊勢神宮を頂点として各氏族の氏神の序列化がなされた。主要神社は、官社となって幣帛が下賜され、その代わり天皇の代わりに祈ることを義務づけられた。古代では、天皇は神仏を超越し、国家そのものだった。ところが、10世紀頃になると、古典的な律令体制が崩壊。国立大学であった寺院は、年貢を取りたてるため、競うように土地集積に乗り出し、「荘園公領制」といわれる体制が出現する。寺社は、氏族や共同体のもので無関係な者に門戸を閉ざしていた方針を転換、「人」「土地」を集めるため、参籠を呼びかけるようになった。「二十二社一宮」制度が出現し、「神々の下克上」時代に突入する。日吉山王社、春日大社、伊勢神宮外宮は、伊勢神宮の権威「社格」に挑戦。彼らは自己の威光と権威を主張し始め、土地を「神領」「仏土」と称して、排他的所有権を主張し始める。この移行にともない、神も性格が変化。それまで神は、遊行して祭祀の時でもない限り来訪しない、人間の都合では会えない存在だった。ところが、「神像」制作の開始と平行するかのように、神社に常駐して人々を監視し、老人や子供・女性に化けて人に指示を下す存在、「人格神」に変貌していくらしい。 こうした変化は、仏教のコスモロジーの下での「神仏習合」と、彼岸現象の拡大に典型的にあらわれるという。律令体制時代と違って、神宮寺と神社の力関係は逆転していた。神社の主導権は、供僧に握られ法会がおこなわれた。それとともに、本地(=仏)垂迹説が流行し始める。娑婆世界における差異を越えて、宇宙には一つの真理があり、神・仏に聖人(釈迦、孔子、孟子)は、それに気付かせるために使わされた使者=「垂迹」である。彼岸現象の拡大によって浄土往生を目指した人々は、「神=垂迹」への結縁をもとめ、霊地霊廟に足を運び帰依していった。 「神=垂迹」は、衆生を真の信仰に目覚めさせる、末法辺土の救世主であるという。そうした変化とともに、非合理的な存在「祟り」なすものから、合理的な応報「罰」を下す存在へと、「神」は変わってゆく。神国思想は、仏教的劣等観「末法辺土思想」を克服するために生み出されたのではない。末法辺土であるが故に強大な力をもつ「神」として現れる必要があった、いわば末法辺土の帰結、仏教の土着化の過程で産み落とされたもの、それが神国思想なのだという。新羅来寇とともに鼓吹され、古代にあっては仏教要素を排撃するための神国思想は、中世3回に渡って鼓吹された。1度目は院政期。大土地所有者にして国家鎮護をかねる寺社勢力は、寺社経営と年貢徴収、国衙・貴族勢力から所領を守るためにも、「悪僧」(僧兵)集団を必要としていた。彼ら権門寺社勢力の私闘の中止を呼びかけるものだったという。2度目は鎌倉新仏教興隆期。法然の専修念仏や禅宗に対して、南都北嶺側が迫害の口実として「神国」を使った。「垂迹」の権威を荘園支配のイデオロギーの基盤としていた権門寺社勢力にとっては、はなはだ都合が悪かったらしい。3度目は蒙古襲来。荘園体制が分割相続による所領分散化によって、深刻な危機・体制内矛盾を迎えていた時代、襲来は寺社勢力にとっても千載一遇の好機だったらしい。いずれも国家秩序全体の屋台骨を揺るがす時、支配勢力の側から鼓吹された、問題解決のための協調を要請した論理だったというから面白いではないか。また天皇は、神国の中心ではない。権門寺社体制下では、天皇は国王部分であって、イデオロギー部門である寺社と同レベルの、支配体制を総体として維持するための手段にすぎなかった。幼童天皇が出現したのは、天皇位の急速な低下があるという。中世になると、「国家=天皇」ではなくなり、国家にしめる天皇の比重は急低下、天皇は神罰が下される対象に転落・相対化されてしまっているという。神仏によって初めて光輝き、「悪行」をすれば公卿による首のすげ替えが当然視される天皇。天皇の権威は、儒教的徳治主義、仏教思想によって彩られる。と同時に、制度としての天皇は決して否定されない。それは、武家・権門自身が、天皇に代わるだけの支配勢力結集の核を持ちえず、体制の矛盾が深まれば深まるほど、実態はどうあれ、権門間の座標軸を定め権門同士の調整と支配秩序維持をおこなうために、「国王」=天皇を表面上押し立てねばならなかったこと。さらに、天皇家と人脈的につながっていた公家・権門にとっての敵は、天皇以外の人間が超越的権威と結びつき正当性を得ることであって、垂迹を否定して本地仏と直接結びつこうとする信仰=鎌倉新仏教の方がはるかに危険な存在だったこと。武家政権も、垂迹の権威に依存していて、彼岸の本地に全面的に依拠した国家を打ち立てることは前代未聞の冒険であって、現実的な選択肢にはならなかったこと、があげられるらしい。これが近世になると、一大転換をとげる。社会は世俗化。もはや超越的・絶対的な「仏」「天」は縮小してしまい、かつて現世の権力・体制を批判する根拠となっていたものが、現世支配を支える道具に矮小化してしまう。「一向一揆」「法華一揆」「キリシタン」は、彼岸の彼方の消滅とともに消える。神国思想は、普遍的世界観を失い、日本の特殊性から日本の「絶対優位」を説く思想へ変質してしまう。それとともに、中世神国思想では排除されていた天皇が、近世神国思想では中心に舞い戻る。思想・学問が、宗教的な束縛から解放された結果、儒者・国学者たちが何の気兼ねもなく様々な根拠を提示して「神国思想」を鼓吹したため、典型的近世神国思想がなんであったのか分からぬ時代、それが近世だという。中世的普遍主義も、近世的多様さも、抹殺して成立した近代神国思想には、独善的自尊意識を相対化するいかなる契機も存在していなかった―――そう語って本書は閉じられる。豆知識もなかなか豊富で飽きることはない。中世の起請文では、仏の次に、日本の神ではなく、中国の道教神が出てくるらしい。日本より中国の神様が偉かった中世世界。大嘗祭は天皇が天皇霊を身につける行為(折口信夫)。即位の際、「真言」を唱える儀式「即位灌頂」を通して天皇は根源的仏である「大日如来」に変身したらしい。とにかく、豊穣な中世の信仰世界には、圧倒されること請け合いです。いささか疑念なのは、この本の中核そのもの、神国思想が様々な機能を備えていたとして、それが明らかになった所で、何の意味があるのかが良く分からないことにあるかもしれません。彼はいう。自尊意識と普遍主義が共存する神国思想の研究成果は、世界各地の「自尊意識」と「普遍主義」の関わり方と共存の構造の解明に、何らかの学問的貢献をなし得るものだ、と。しかし「共存」とは何なのか。この本では、同時代に自尊意識と普遍主義の2つが「共存」している姿は、結局描くことに成功していない。どこに、「共存」した姿があったのか、いささか首を傾げてしまう。ある時代には、神国思想に「普遍主義」を摘出し、ある時代には神国思想に「自尊意識」を抽出しただけにしか見えないからだ。そんなものの「関わり方」の構造の解明など、そもそもやらなければならない必要があるとすら思えない。時代や論者によって、異なる機能が見いだされること。それを「共存」といえるのであるならば、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教、あるといえばあるし、ないといえばない、その程度のものではないのか。てか、どうみても、「反対物の一致」を手をかえ品をかえ語っているだけの様にしかみえない。また、機能的立場から論じるならば、神国思想の「自尊主義」側面が弱かったとしても、別のものが果たしていただけではないのか。たとえば「武威」概念だの、自尊意識ネタはいくらでも転がっている。しかも、一貫した神国思想の真実の提示とは裏腹に、近世にかけて日本のナショナリズムは、昂揚を続けていたという事実そのものに関しては、なんら検討が加えられていない。非常に面白かっただけに、ちょっと残念としかいえない。ただ、紹介しなければならない新刊本が山のようにたまっていて、呻吟しているのですが、それでもこの本はすばらしい。ぜひお読みいただきたい。評価 ★★★★価格: ¥ 756 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 24, 2006
コメント(3)
-

お知らせ
全然更新しないでごめんなさい。明日か明後日には、必ず復帰します。これからもよろしくお願いします。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 22, 2006
コメント(1)
-

★ 毎日新聞のプロパガンダを爆砕せよ! 名人戦問題にもの申す
毎日新聞が、とうとうメディアを総動員して牙をむき始めた。名人戦主催権に関して社をあげてのネガティブキャンペーンは、とうとう毎日新聞の今日付社説にまで及んだ。本ブログで予想した通り、名人戦を失うなら将棋界そのもの、将棋文化そのものを根絶やしにしてもいい、的な決意をしたに違いない。そして、名人戦主催を降りた時のための、周到な読者への言い訳であろう。これらのことは、すでに以下のブログ(1)、(2)、(3)において詳細に論じてあるが、今回の毎日新聞の社説は、特に醜悪にして不愉快なものである。徹底して批判されなければならない。腐臭をはなつゴミメディア、毎日新聞。そのプロパガンダを逐次徹底的に検証していこう。■ 社説:名人戦問題 まずボタンのかけ直しを将棋名人戦の主催を毎日新聞社から朝日新聞社へ移そうという日本将棋連盟(米長邦雄会長)の理事会の動きが明るみに出て1カ月余がたつ。この間、多くの読者から名人戦を守るという本社への励ましをいただいた。名人戦目当てで毎日新聞をとっている読者は多いのだから、「利己的」な読者が励ますのは当たり前のことだろう。読者をダシにした自己の正当化を図っているに過ぎない。 連盟から名人戦の第66期以降の契約解消をする旨を伝える「通知書」が送られてきたのは3月末だった。それと前後して本社を来訪した中原誠副会長はこの「通知」が、朝日新聞との間の隠密裏の交渉を踏まえての連盟理事会の「苦渋の選択」だと説明した。あのさ。毎日の社説子よ。たとえば企業買収にしても、オープンにしておこなう人が、どこにいるんだね。ふつう隠すでしょ。将棋連盟は、契約主体であることを理解していないのか?親にでもなったつもりかね。「隠密裏」というイメージ操作をする、そのセコさ、ちょっと許せない。 もともと現在の名人戦は本社の前身の東京日日新聞社が世襲名人位を買い取り、それを連盟に寄贈して創設した史上画期的な棋戦だった。戦後、契約更改紛糾につけこんだ朝日が連盟と毎日との交渉中に別契約を結んだことで朝日主催で行われた時期もある。しかし76年には連盟と朝日の交渉が決裂、連盟の懇請を受けた毎日に復帰した。この際毎日は、堂々と朝日の契約終了を確認し、通告した上で交渉を開始している。また、毎日新聞のプロパガンダか。この記述は、3点、読者を騙すためのウソが散りばめられている。一部重複するが書いておく。A 世襲名人位買い取りと連盟寄贈当たり前のことだが、一番最初のタイトル戦、「名人」と名をつけたいので、関根十三世名人を引退させるために渡した「名人」の代金のことにすぎない。分かりやすく今風にいえば、タイトル棋戦創設に払う契約金のことである。契約金と書いたら、格が下がるので、毎日新聞は「名人位買い取り」「寄贈」とプロパガンダしているのだ。こんなウソに騙される人もいるんだろうね。B 「契約更改紛糾につけこんだ朝日」「連盟の懇請 毎日」「契約更改紛糾につけこんだ」と朝日新聞を批判しながら、76年の移行に関しての毎日新聞に行動には「連盟の懇請」という表現を使う、プロパガンダ攻撃。だがよ、毎日新聞さん。あんたが始めたとはいえ、戦中戦後の混乱期、15年もたたぬうちに、朝日新聞に移ったのではないかな。その後、毎日新聞よりもはるかに長い、25年にも渡っての、朝日新聞が名人戦を主催する「歴史的経緯」があったではないか。76年当時の毎日新聞への移行は、「毎日新聞の論理」では「強奪」であって「復帰」ではない。自社と他社では、ダブルスタンダード。「連盟の懇請」というなら、現在の朝日新聞でも、一貫して「将棋連盟の懇請」を強調しているだろう。なぜ、「連盟の懇請 朝日新聞」と書かないんだね?C 「毎日は、堂々と朝日の契約終了を確認し、通告した上で交渉を開始」あのさ。朝日との交渉のあと、読売新聞と将棋連盟の交渉の一件はどうなったのかな。読売との交渉に決裂したから「契約終了を確認」できただけだし、朝日新聞が将棋連盟に訴訟をおこそうとしていたから、「通告」しとかないと、毎日新聞が困っただけだろう。今回の一件とは、何の関係もない。毎日新聞の一身上の都合にすぎない行為を「信義」なる美名でプロパガンダするな! 契約上はもちろん、こうした歴史的経緯に照らしても信義にもとる「通知」に対し、本社は一貫して撤回を求め、その上で66期以降の契約内容について誠実に話し合う意思を示している。しかし連盟理事会はこれを拒んだまま新たに名人戦の毎日・朝日共催という提案を行った。身勝手な構想を一方的に突きつけてくる非常識はともかく、不可解なのは米長会長ら理事会がこの間、ファン注視のこの問題について社会的な事情説明や意思表明をほとんど行っていないことだ。そればかりか朝日移管案をめぐる理事会決定や、本社とのやりとりについて、従来の説明や事実と異なる発言が飛び出し、その信義誠実への疑念まで呼び起こしているのはどうしたことか。おかしいね、毎日新聞さん。信義誠実がないのは、毎日新聞では?「自動更新しないため通知書を送った」と、将棋連盟が弁明したとき、毎日新聞は通知書撤回しても、第66期以降の契約内容は「連盟の懸念するような、自動更新されるようなことはない」と、将棋連盟棋士を集めて説明会を開いていたよね。違ったかな? 毎日新聞の説明が本当ならば、自動更新されることはないのだから、朝日新聞に移すことは「契約上はもちろん」「信義にもとる」「通知」のはずがないだろう。 将棋連盟は「永遠に毎日新聞以外には変更できない」けど、「自動更新されることはない」契約っていったい、どんな契約なんだよ(笑)。毎日新聞の言うとおりだと、毎日新聞の名人戦契約料提示額が嫌でも、他社に絶対変更できない、奴隷的な片務契約になっちまうだろ。そんな詐欺じみた契約を結んだのかい?それは絶対ないよな。棋士に説明したように「自動更新されない」のか、社説で言うように「自動更新される」のか(朝日に移すのは、もちろん契約に反する)どっちなんだい? ここまで「撤回」にこだわる以上、撤回させないと契約上、将棋連盟は、朝日新聞に移行させる権利が保留していることを意味しているのではないのかな。つまり、「契約上はもちろん」という毎日新聞の社説は、ウソだってことだ。連盟理事会は棋士には連盟の苦しい財政事情を訴えたという。だが、これまで本社はじめ棋戦を主催する新聞各社はみな経済動向を踏まえて契約金の上積みをしてきたではないか。なのになぜ財政難が生じたのか。またそれをどう克服しようというのか。その説明もせずに、まるでアメ細工のように勝手にスポンサーをすげかえたり結びつけたりして収入増を図ることができると思い描いたのならば、公益法人の運営に責任ある者として安易にすぎよう。キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!泥棒ウソつき新聞社、毎日新聞社の居直り、極まれり!!!名人位が格式の頂点である以上(賞金の頂点ではない)、名人戦タイトル料が押さえられている限り、他社主催棋戦のタイトル料は絶対あがらない。そのことは、読売囲碁名人戦騒動でとっくの昔に実証済である。将棋界タイトル戦価格のプライステイカー毎日新聞社によって、経済動向を踏まえない、雀の涙の契約金の上積みが横行していたのだ。将棋名人戦の契約料は2倍しか増えていない。しかし囲碁棋聖戦だとタイトル料は2・5倍、囲碁名人戦だと3倍近い。財政難が生じたのは、囲碁の場合は日本棋院にあっただろう。しかし将棋の場合、毎日新聞が名人戦にまともに金を払わない上、王将戦すら「まともに育ててこなかった」ことが原因であることは、断じて間違いではない。悪いのは、毎日新聞、おまえであって、公益法人なる理屈をつけて、将棋連盟のせいにしないでほしい(1万字超えたので<2>に続きます。応援ありがとうございます) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 16, 2006
コメント(3)
-

★ 茅田砂湖 『大鷲の誓い デルフィニア戦記外伝』 C・NOVELS Fantasia 中央公論新社(新刊)
▼ 大ファンなのにレビューを書くのが辛い作家、というのは、確かに実在するらしい。かなり前に出版されたのに、なかなか踏ん切りがつかない。そんな作家・漫画家は、みなさんの心の中にもいるでしょう。茅田砂湖先生の作品というのが、不肖、私にはそれにあたる。▼ なによりも、私はファンタジーを読んでいない。『ゲド戦記』も『指輪物語』も読んでいない。『スレイヤーズ』すら読んでいない。読んだものといえば『アルスラーン戦記』『風の大陸』ぐらいしか思い浮かばない。「剣と魔法」のお約束は、まったく分らない。▼ これが、ミステリーのように肥大化しすぎて、そもそも全体が「読める訳がない」ジャンルのファンならば、蛮勇をふるって感想のひとつでも書けるかもしれない。ところが、こちらは辛うじて読めるジャンルである、SFファン出身だからたまらない。つい最近まで、ジャンルSFの分野は、読破冊数の多寡で発言力が決まってしまう、なかなかハードな体育会系のノリがファンを覆っていた。大森望が「バカSF」論をいいだす前の話である。皆さんは、想像がつかないかもしれないが、つい20年前までは「ファンタジーはSFの属領」「SFのFはファンタジーのF」といわれていたものだ。怖い先輩達は、ファンタジーも読んでいる。読まないもの語るべからず。こんな雰囲気で、ファンタジーなんぞ、読んでいられるかい。小生、ダルコ・スーヴィンの「ファンタジーはSFの堕落」に賛成する訳ではないのだが、「堕落していない」SFばかり読んでいたものだ。いや~、モフィット、ウォマック、カンデル、チェリイ……ハヤカワSFはツマランかったなあ。面白さが分らないのは、俺がバカだからだと思いこまされていたよ……青春を返せ!金を返せ!▼ …………いかん、話を戻そう。そう、だから他の作品との比較なんてできない。SFファンの私は、それだけで狂乱状態になってしまう。紹介していいのか、と。けれど、茅田砂湖『デルフィニア戦記』全18巻のシリーズだけは、蛮勇をふるってお勧めしたい。ちょっと例のないお話なのである。▼ 女の子の薦めもあって読み始めたのだが、これが無茶苦茶面白い。あっというまに引きこまれ、全冊読み終えてしまうほどの面白さだった。あれから何年もたち、久しぶりの『外伝』の登場という。▼ 「本編」の衝撃は、今でも忘れられない。中世ヨーロッパ的な雰囲気を残す世界。デルフィニア王国の王座を追われた青年に、異世界からやってきた超人的能力をもつ美少女(ただし異世界では男だった)が、王座をとりかえしてやるばかりか、世界全土を平定して、美少女は異世界にかえってゆく。この美少女というのが、もう例をみない程、凄まじい。なんというか、ヘタすればラブ・ロマンスどころか、ほとんど噴飯モノのホラ話のような豪快な作品だった。どこまで話が広がるのか見当がつかないまま、どんどん膨れあがった本編。読み終えたとき、騙されたような気がしないではなかったことを告白せねばなるまい。▼ かの西洋音楽の大作曲家ブルックナーは、ワーグナーのオペラを見て呟いたという。 「なんで女が焼かれなければならないんだ?」と。▼ まったく逆なのが、『デルフィニア戦記』といえば、お分りだろうか。そこには、「断念」と引き換えの「救済」のカタルシスがまるで存在しない。デルフィニア戦記は何一つ「断念」されることなく、カタルシスもなく、主人公たちはどんな危機もすりぬけて救済されてしまう。めでたい、めでたい。みんな笑顔で手をふって別れ、大団円で終わってしまうのだ。「こんなのありかよ…」。これほどの大シリーズで、どんどん暴走した挙句、この終わり方は、スキャンダルに近い。話題にならなかったのが不思議だが、ただのハッピーエンドと好意的に捉えられているようだ。▼ 外伝は、良くできていることは間違いない。デルフィニア本編の前史。本編で大活躍のバルロとナシアスの友情の発端が丁寧に描かれていて楽しい。王室の親戚にあたるバルロの不潔さ【笑】とナシアスの潔癖さの対比、バルロとナシアスの入り組んだ「依存」の関係が丁寧に描かれていて、ファンから見れば垂涎の作品になっているのです。▼ 『スカーレット・ウィザード』全5巻(中央公論新社 C・NOVELSファンタジア)もそうだったが、この人は強い女性を主人公にした作品の印象がことの他強い。『デルフィニア』の王女グリンダしかり、『ウィザード』のジャスミンしかり。むろん、男性だって女性に劣らぬほど強いのだが、あまりにも女性が強烈な輝きをはなち、周囲を衛星に変えてしまう。どうしても、男性は脇役に甘んじてしまうしかない。彼女の小説に多くの女性ファンがつくのは、そのためでしょう。ただ、そうなると男女差が作品世界から消えてしまう。茅田の世界は、目移りしてしまうほど美男美女揃いでヨリドリミドリなのに、性的には驚くほどモノトーンだ。我々が普通イメージする、ラブ・ロマンスなど、ほとんど見られない。茅田砂湖のテーマとは、性差のない世界にあって男女は何に惹かれるのか、ではないだろうか。むろん、これはなかなかの難問。ジャスミンとケリーの関係の描き方にも通底する、「あの男の望む自分でいたい」という結びつき方は、一つの回答として読むとたいへん興味深い。ある種「やおい」的感性を感じないこともないのだが。▼ どうしても女性ファンが多い本書。ぜひ男性の方も手にとってみてはいかがでしょうか。(忙しく更新が滞りがちなのに応援してくださる方に感謝しています。ありがとうございます)評価 ★★★☆(シリーズ全体評価 『スカーレット・ウィザード』は★★★★)価格: ¥945 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 15, 2006
コメント(0)
-
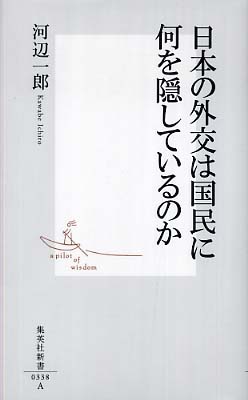
★ 川辺一郎 『日本の外交は国民に何を隠しているのか』 集英社新書(新刊) <2>
(承前)「日本外交の真の姿」とは、理屈もなく、理屈をつける必要も感じない者が、感情にまかせて力を振りかざしているだけにすぎない。国連を法的根拠にすることで、なし崩し的にイラク関与を強めた日本が、今まさに国連を否定し始めたことは、日本の行動に制約がなくなったことに他ならない。国連どころかアメリカを超えて暴走し始めた日本外交は、拉致問題における経済制裁に表れているという。日本は、南ア経済制裁に同調しないどころか、チリなどの「拉致問題」に対してさえ関心を示さない、他国民の人権侵害に一貫して寛容な国家だった。それが北朝鮮に対してだけ、変節してしまう。2005年5月、世界における傭兵非合法化の流れを受け、アメリカでさえ「民間軍事会社」なる用法で糊塗している「傭兵」がイラクで捕まったことに対して、日本人というだけで「英雄」的扱い。その反面、最も利他的であるNGO関係者を政府批判というだけで「自己責任」と断罪した読売・産経社説の論調は、民主主義・国際合意・犯罪か否か、といった論理を埒外においた、ヨーロッパは無論のことアメリカ保守派・イスラム原理主義派にもない、北朝鮮と最も類似する比較を絶した「利己主義」であるという。また、「勝者の裁判」東京裁判方式を過去のものにするためのICC(国際刑事裁判所)設立にあたって、日本は終始一貫して米国に同調して批判をおこないながら、この本の著者のように国内向けには政府は推進者のように装っているらしい。 ICCもイラク戦争も国連分担金問題も、対米追随ではなく官僚主導による独自路線で、一貫して国内向には「誠実な取組」を装いながら、国外向けにはまったく正反対の態度をとっていた。さらにいえば、国連分担金比率が近年問題となっているが、政府歳出比率が近年増加したことで自らの支出権限下の金額が減少する外務省のプロパガンダにすぎない。インド・ロシア・中国のせいではない。日本の分担率急増の2/3以上は、アメリカの肩代わり(22%まで)をしているためだという。しかも日本は、80年代まで新興途上国として「減免措置」を求めていながら、今では開発途上国減免措置に反対して中国に負担を求めているというのだから、支離滅裂である。二枚舌国家日本!すでに日本は世界の不安定要因の一つである!!筆者の糾弾は容赦がない。日本外交が何をしているのか実は、ジャーナリズムどころか政治家・官僚でさえ理解していない!!!。日本外交の、なんというおぞましさよ!!!この書には、末期的な日本の外交をとりまく状況が詳しく述べられています。日本の国連大使は日本が「決定的な影響力」を持つことを認めていながら、国内では「影響力がない」と二枚舌。自衛隊違憲をいう憲法学者は、日本の外交政策には関心を抱かない。ボルトン国連大使就任に関して巻きおこったアメリカでの論争を羨む一方で、法的整合性を維持するため政府が堅持してきた非核三原則・国連中心主義を官僚主導で捨てることを主張する審議会(竹内佐和子・有馬真喜子・西川恵(毎日新聞)・本田敬吉・御厨貴・村瀬信也・渡辺修)の座長、北岡伸一が国連大使に就任してもとりあげない朝日新聞。ボルトンは、アメリカの利害に沿って国連利用・妨害をおこなうのに長けた人材というのも、巷間に知られておらず、ありがたい。なによりも、イラク武力介入容認決議が安保理で通る、自衛隊を早い段階でイラクに派遣する必要はない、常任理事国入りに周辺諸国は賛成する、世界は日本の常任理事国入りを望んでいる……2001年以降、日本外交は、どの立場から見ても誤りであり、失敗が判明して他の分野(その一つが小泉首相の靖国参拝である)に大きな悪影響を与えておきながら、政府も国民も何一つ問題だと感じていない。政策決定過程に合理性があるかどうか、官僚が国際世論を正しく認識しているかどうか、分からない。民主主義下にありながら、さながら大本営発表で、国内外の説明が違い一貫した論理が存在せず検証もされない戦前の外交は、今も変わっていない。前原誠司前代表の「国連改革を支持」する発言も、本書では厳しく断罪されています。民主制のようなダイナミックな政治参加や、知的エリートなるものは、日本には存在せず向かないのではないか。この悲鳴のような叫びは胸を打つ。ただ、いささかゲンナリする部分もなくはない。必要以上に日本外交の「一貫性」を仮構した結果、そこからはみ出た部分を「支離滅裂」としてしまう感が無きにしもあらず、だからです。良い例が「常任理事国入り」における毎日・朝日新聞の論調批判でしょう。なるほど、国連中心主義を対米従属の中で遂行することを目的とした、産経新聞・読売新聞の常任理事国入り賛同は、理にかなっています。とはいえ、朝日・毎日新聞のように「常任理事国入り」して後も、対米自立・憲法の理念を活かせないとする理由はどこにあるのだろうか。そもそも改憲・靖国参拝・イラク戦争支持・集団的自衛権は、この書が問題にしている外務省とは別の「主体」ではないのか。どんなに方向性が同じように見えても、主体がまるで違う。ここに高度な一貫性を見出そうとするのは、ゲスの勘ぐりに近い。「憲法の理念」が世界に働きかけられない、まで確固とした改憲の流れは見えない。政権交替してしまえばどうなるのだろうか。否、こうもいえるでしょう。そもそも、このような「同床異夢」が可能であるからこそ、「常任理事国入り」は日本において強力な支持を取り付けることが可能ではないのか。様々な主体が勝手に抱く「同床異夢」によって生じるのが「幻想の共同体」であったとするならば、「支離滅裂な日本外交像」を描く上で切り捨てられたものは、かなり大きかったようにおもえるのだが、評者の気のせいだろうか。とはいえ、前半期において一読すべき貴重な新書であることは疑いも無く事実。ぜひお読みいただきたい。(暖かい応援ありがとうございました)評価 ★★★★価格: ¥693 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 9, 2006
コメント(3)
-
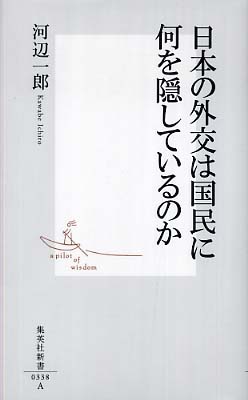
★ 川辺一郎 『日本の外交は国民に何を隠しているのか』 集英社新書(新刊) <1>
日本が国連分担金の恒常的滞納国であることを、貴方はご存じだろうか。平均6ヶ月、ひどいときは14ヶ月。日本は、期日以内に分担金を納めたことがない。アメリカと並ぶ確信犯的分担金滞納国。国連財政を悪化させた主犯は日本だった!!!!この驚愕というべき「知られざる国際的常識」を語る本書は、今や日本が北朝鮮よりもはるかに世界に害を及ぼしながら、アメリカ以上に自覚がない恐るべき外交を展開する、世界の問題国家であることを徹底的に暴きだしている快著なのです。皆さん、ぜひ図書館ならびに本屋に走って欲しい。これを読まずして日本外交は語れません。一体、日本は何のために滞納していたのか? 実は、「為替相場の良い時」に払うためなんだという。しかも為替相場の悪いとき、国連分担金を納付しても責任を採ったことがない。外務省は、「わずかな利益」で法を踏みにじっているだけでなく、経済的合理性・政治的合理性さえ欠く行為で、日本の国家的威信・国際的信用を傷つけているといわざるをえない。そればかりか、「分担金を誠実に払っている日本」「にもかかわらず影響力がない」ウソは、外相・外務省官僚にまで罹病しているらしく、キチンと払っているロシアを「払っていない大国」と逆に誹謗をおこなうなど、集団的ヒステリーの様相さえ帯びる始末なのです。 「6番目」の常任理事国といえる程の大きな力を安保理にもち、拠出金を通じて「国連へ決定的影響力」をもち、国連予算決定について拒否権をもち、国連事務局幹部職員と日本の外交担当者との重複もすすむ。それでありながら、日本外交は、政府答弁もウソと詭弁だらけ、大臣や官僚が問題を適切に認識しているかすら定かではない状態。これでは周辺諸国が、常任理事国入りに反対するのも当然なのだ。一体、日本は何のために常任理事国入りを目指したのか。これと、国連改革とは、どのような関係にあるのだろうか。そもそも、日米安保条約は日本国憲法に抵触する。そのため、国連憲章を根拠に締結したのですが、日本の「国連中心主義」外交とは、対米協力のカモフラージュにすぎないという。国内法と国際法を都合良く使い分け、法を二重基準の下に置くことが、外務省の役目らしい。武力行使は、安保理が認定した侵略者に対して国連として対処するか個別的・集団的自衛権しか許されていない。アメリカは加盟国だから以上の基準を満たさない戦争はしない、だからアメリカを支援しても国権の発動たる戦争ではない ……… アナン国連事務総長までアメリカを批判すると、このロジックは破綻してしまう。2003年3月以降、日本の右翼ジャーナリズムは、いっせいに「対米協力のカモフラージュとしての国連中心主義」の否定に走り出すが、意外なことに外務省は当初静観していたという。ところが2003年9月以降、内閣・外務省は、自衛隊派遣の理由にならないため―――従来はODA予算を財務省からぶんどるため、テロの原因として「貧困」を掲げていた―――答弁をいっせいに翻す 。アナン事務総長の発言をイラク戦争を支持するため批判しながら、その戦争を支援するためイラク特措法を国連に関係づける泥縄ぶりは、当初、自衛隊派遣を想定していなかったことの証拠。イラク戦争支持は正しくとも、判断を誤った証拠であるという。もともと、日本の常任理事国入りの動きは、1993年頃にまで遡れるらしい。リベラル・クリントン政権では、「国連重視」をかかげたため、米国の都合が悪い国連にならないように「国連改革」を行わなければならなかった。当時日本は、その動きに呼応する形で、常任理事国入りを目指したものの、道具としての国連利用にたけた共和党は、国連利用が難しくなる局面が現れるのなら、日本だけ常任理事国になるのは好ましくないとして反対していたという。外務省の暴走は、「イラク戦争」で頂点に達します。日頃安保条約の重要性を述べていた読売新聞や与党が、北朝鮮とイラクをリンケージ。あろうことか米国が安保条約を守るとは限らないと公然と不信感を述べ、日本政府の米国支持を正当化した破綻ぶりは記憶に新しい。日本政府は当然、イラク問題と北朝鮮問題を公式には絡めません。「知人だから犯罪に協力」という論法は、法的整合性がないばかりか、北朝鮮問題が解決するとイラク対応を変えねばならなくなるからです。国会内・外で二枚舌を使い、世論を煽ってゆく外務省・与党の姿。そのひとつが、イラク戦争参加に使われた「石油確保」論。欧米では,イラク戦争の当否が,問題の正当性や正義か否かで語られ,公式では語られることのなかった「石油確保」が横行した日本。イラク戦争で最も利己的な国家、石油のための戦争をした国家は、米国ではなく日本であったという衝撃の事実には、驚く他はないでしょう。しかし反戦の立場をとるメディアでさえ,日本が「やむをえず」ブッシュ政権を支持したものと考えているらしい。安保理の外で巨大な経済力を使い国連を軍事的方向に動かすため、激しい工作を仕掛けた「イラク戦争」の当事者であることが、まったく認識されていないばかりか、「安保理常任理事国入り」とはこの国連加盟国工作の失敗を糊塗するためのものというから、驚くではありませんか。あくまで、その目的に従い、国連中心主義を対米重視に従属させるため「常任理入り」をもとめた読売・産経に対して、「常任理入り」を対米自立・憲法理念を活かすためと捉える朝日・毎日の論調の蒙昧さ。靖国参拝・改憲・イラク戦争支持・集団的自衛権の容認などと連動した日本の「常任理入り」に対して、中国・韓国などで反対運動がおきるのは、ある意味当然のことでした。ところが、毎日新聞にいたっては、妄想がエスカレート。まさに廃棄されようとしている、9条・集団自衛権放棄の平和主義なる理由で、常任理事国入りを正統化して、中国・韓国の批判に反論する、信じられない痴性ぶりを示したのだから呆れる他はない。社説を書き政府諮問委員をつとめた記者が、政府の説明を額面どおり受け取って、政治的言動に関する政治感覚すら欠落させているとは!!(長くなりましたので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ?価格: ¥693 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
May 5, 2006
コメント(18)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










