2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年07月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

★ バカ右翼たちの迷走 ~ 昭和天皇の「靖国神社不参拝理由メモ」をめぐって
▼ いやー。昭和天皇の靖国神社メモ。「だから 私あれ以来参拝していない それが私の心だ」▼ 20日朝刊で『日経新聞』がスッパ抜いて以降、ネット界では、何だかバカ右翼たちが爆笑ものの右往左往ぶりを示しています。これほど笑えることが起きていたのに、今までまったく気づかんかった。これ、漫才のつもりなんでしょうかネ。▼ バカ右翼反応その1 『天皇を政治利用するな!』いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。そもそも、なんで左翼やリベラルが、天皇の政治利用なんかしなけりゃならんの? 天皇制なんて、打倒するためにあるものでしょ。せいぜい、京都御所にお引取りいただくのが、もっとも天皇家への暖かい対応ではないですか。 天皇を政治利用できるのは、あなた方のお仲間。「天皇の御心」を大事に思う方、すなわち保守・右翼しかありませんぜ。 左翼・リベラルな人々は、このようにキミたちに問いかけているだけです、靖国神社に行きたいなら、個人の勝手なんだから、好きに行けばよろしい、しかしそれは、お前らの思想信条と矛盾してはいないかね?、とね。キミたちは、今後2度と「戦後民主主義・個人主義が公を堕落させた」なんて言ってはいけません。もちろん、「個人主義」「自由主義」批判も、してはいけません。「天皇の大御心」という「公」に背き、「個人主義」に基づいて参拝するんだから。▼ バカ右翼反応その2 背後には政治的思惑が隠されている!!いやー、ホント馬鹿ちゃいます? 保守ちゃん、ウヨちゃん。ミーちゃん、ハーちゃんではあるまいし、今さら何カマトトぶってるんだヨ、おまえら。政治的思惑のない記事なんて存在する訳ないだろう。新聞はそもそも、編集会議で重要とおもわれる順に記事の大きさを決めてるんだから。世間における重要かどうかのラインに、政治性なるものが存在しないはずがない。ナイーブさを装ってる分だけ、キモすぎ。止めてくれんかな、ホント。▼ バカ右翼反応その3 日経報道は、安倍晋三潰しだ!!!いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。その程度で潰れんなら、そんな奴首相になる資格はねえよ。たしか彼のカルフォルニア大2年留学は、学歴詐称という話だったし(1年間は英会話学校で、1年しか行かなかったと言われてたけど、裁判どうなったんだよ? 安倍事務所はよー)、統一教会と深い関係のある政治家のようだし、パチンコ利権の鬼だし、安倍晋三なんて最初から首相の資格なんてない、といえばそうかもしれない。 まあとにかく、自意識過剰はキモイとだけ言っておきます。小沢民主党にとっては、君のようなオッチョコチョイの人間に首相になってもらった方が扱いやすいんだからネ。いい機会だから、首相になるの止めたら? まだ麻生とか谷垣の方が、なんぼかマシなんだから。▼ しっかし、アニメ・漫画オタクだからって、麻生支持する人いるらしいネー。俺の周りにもいたりする。ブルックナーとワグナーを愛聴したクラオタの小泉純一郎が首相になっても、ちっとも良いことは無かったことを忘れたのかなー。日本人って学習しませんねー。▼ バカ右翼反応その4 富田メモは、ニセモノだ!!!徳川侍従長の発言だ!!!いやー、ホント馬鹿ちゃいますか? 保守ちゃん、ウヨちゃん。ホント、今回、これが一番の大笑いでした。受けに受けた。そりゃそうだ。「天皇」に否定されたら、保守も右翼も終わり。「大御心」に背く逆賊。立つ瀬がないもんなー。分かるよ、その否定したがる気持ちは(笑)。 たとえば「依存症の独り言」。他にも色々あって実に笑える。そもそも、メモという書いた本人だけが分かればいいものに、メモ全体の記述やスタイルの「一貫性」を見つけようとして、いったい、どうするんだろう……… こいつら日記とかメモとか、書いたことないのか? 後でメモを読み直してみても、何を書きたかったのか分からないという、当たり前の経験さえしたことがないのか? 素直に読むしかないでしょ、詰まっても。 このネット騒動を見ても、日本人の知性の低下ぶりが良く分かる。 当然、徳川侍従長の発言メモだとしても、矛盾はいくらでも出てきてしまうでしょ。 たとえば、松平宮司に向かって、徳川侍従長が「親の心子知らず」というのか?なんだそれ。 そもそも、富田宮内庁長官が「私参拝しない」なんて侍従長発言メモって、いったい何の意味があるんだろう。理性のカケラもないのか保守はって、元々無いのかも知れないが (笑)▼ バカ右翼の迷走ぶりを心おきなく笑うためにも、毎日新聞の朝刊に出た特集をネット共通の資料にするため、転載させてもらいます。秦郁彦氏のこのメモの評価は、スタンダードとなるもんでしょう。ご本人から苦情がくれば削除します。では。● 合祀の手順の説明を 秦郁彦(日本大学講師)従来の推定を裏付ける第一級の歴史資料靖国神社は天皇参拝の中断覚悟で決断 日本経済新聞社が入手した故富田朝彦元宮内庁朝刊の日記とメモに、目を通す機会を得た。日記は1986年まで、メモ手帳は86年から昭和天皇が崩御される半年前の88年6月までで、両者は重複していない。 日記は害して簡潔だが、メモは天皇の発病(87年9月)以降は病状を記録する意味もあってか詳しくなり、昭和天皇も信頼する富田氏に言い残しておきたいとの気持ちもあってか、自らさまざまな話題を取り上げ、秘話的なエピソードを含めて語っている。皇室の内情に触れた部分もあり、全面公開は無理だろう。 第一級の歴史資料であることはすぐに分かったが、この時期に公開することによる波及効果の大きさを思いやった。 富田氏は天皇が亡くなられた直後の89年1月9日から数回、「亡き陛下をしのぶ」と題したエッセーを読売新聞夕刊に寄稿している。比べてみると、日記やメモを参照しつつ書かれたことは明らかだが、今回発表された靖国神社関連の話題への言及はない。 さて、論議の的になっている富田メモの靖国部分の全文についてだが、97年に故徳川義寛侍従長の「侍従長の遺言 昭和天皇との50年」(注 岩井克己 聞き書き・解説 朝日新聞社刊)が刊行されて以来、他の関連証言もあって、天皇不参拝の理由がA級戦犯の合祀にあったことは研究者の間では定説になっていた。徳川氏は松平永芳宮司とのやりとりを、「天皇の意を体して」とあからさまには書いていないものの、関係者や研究者はそのように読み取ってきた。 したがって、私は富田メモを読んでも格別の驚きはなく、「やはりそうだったか」との思いを深めると同時に「それが私の心だ」という昭和天皇発言の重みと言外に込められた哀切の情に打たれた。なぜか。 応対した徳川氏がA級合祀に疑問を呈したところ、「『そちらの勉強不足だ』みたいな感じで言われ、押し切られた」(「侍従長の遺言」)という。また、当時の靖国神社広報課長の馬場久夫氏によると、「こういう方をおまつりすると、お上(天皇)のお参りはできませんよ」(21日付毎日新聞朝刊)と宮内庁の担当者から釘を刺されたという。 つまり、当時の松平宮司は天皇の内意を知らされた時、今後の天皇参拝が不能となってもかまわないという覚悟のうえで合祀に踏み切ったことになる。それは「私は就任前から『すべて日本が悪い』という東京裁判史観を否定しないかぎり、日本の精神復興はできないと考えておりました」という松平氏独特の歴史観に発していた。 しかも、合祀を期待していなかったはずの遺族(と本人)の事前了解もとらず、神社の職員に口止めしてこっそりまつったため、半年後に共同通信がスクープ報道するまで、国民も知らされていない。松平路線を継承しているかに見える現在の靖国神社は、当然の手順を踏まなかった理由を説明する責任があると考える。▼ なんというか、真夏の漫才という雰囲気である。ぜひ、もっともっと笑わせてほしい。←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 28, 2006
コメント(64)
-
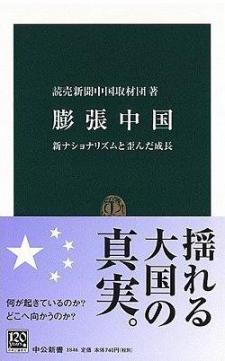
★ 読売新聞中国取材団 『膨張中国』 中公新書(新刊)
▼ 読売新聞中国支局を中心とした、総力をあげた中国ルポルタージュ。連載されていた途中、読まれた方もかなり多いのではないか。その取材団の成果が、1冊の本として中公新書にまとめられました。ひとまず、感謝しておきたい。▼ 章立ては以下の通り。 第1章 新ナショナリズム 第2章 揺らぐ社会主義 第3章 市場経済の虚実 第4章 きしむ周辺世界 第5章 米国との攻防▼ 第1章では、過熱する津波のようなインターネット世論や、競争が激化する新聞市場において発禁などの統制に苦慮する中国当局の姿が描かれている。1台4万円のパソコンが普及して、北京・上海・広東の三大都市圏以外にインターネット利用が拡大。中国大発展のチャンスに引かれて、以前とは違い留学する人間のほとんどが、中国に帰国しているのだという。豊かなものは欧米、貧しいものは日本に留学・出稼ぎに行くらしい。過剰な自負心は、過剰な民族意識をまねく。96年台湾総統選の屈辱から、日米の台湾介入を撥ねかえすために「大軍拡」を続け、「第一列島線(日本列島~フィリピン近海)」「第二列島線(小笠原諸島)」なる線を勝手に引き、アメリカ空母を迎えうつ準備をしているという。 ▼ 第2章では、権力と市場と資本がむすびついた開発独裁中国の社会が赤裸々に記されていて面白い。今の中国の富豪の6割は、不動産関連事業、いわゆる土地成金であるという。改革の重点は、農村から都市に移り、住宅バブルも発生。購入限度額が年収の数倍の日本とは違い、10倍でもマンションが売れるのだとか。「民工の都市流入」という人類史上最大の都市化は、「安い労働力」「富の農村移転」「農業労働力の削減」を担っているという。当局は、「民工」の労働組合に加入など、様々な体制取り込みが画策。1990年代半ば5%だった大学生進学率も、2004年には2割にまで上昇。大卒は、「普通の人」になってしまい「いい就職先」に苦労しているという。▼ 第3章では、人民元切り上げに直面する中国経済の虚実にせまる。切り上げ後も歯止めがかからない貿易黒字。「党の論理」での通貨管理は限界に近づいている一方、1993年に石油純輸入国に転落して以降、今では輸入依存度は4割、世界2位の輸入国になっているという。2010年度には輸入依存度は6割になるとみられ、中国石油・天然ガス集団(CNPC)のカナダ石油大手・ペトロカザフスタン買収を始めとした、資源外交を血眼で展開しているという。イラン、スーダン、ベネズエラ、中央アジア…石油だけでなく、石炭・原発も大々的に採掘・建設。恒常的な電力不足の一方、中国企業の海外進出は進み、04年の対外直接投資額は、前年比93%増の55億ドル。同年の受入額606億ドルとは比較にならないものの、日本の自動車部品メーカーはターゲットになっているらしい。日本を標的とした「愛国ビジネス」が栄える一方で、日系企業は、欧米や韓国系企業と比べても「中国人を見下す」ため、就職先としても魅力を失いつつあるという。台湾独立派の許文竜・奇美グループ会長の「転向」に見られるように、大陸に投資を呼び込み、「政経不可分」の強烈な圧力を加える中国。2003年頃を境として、香港経済は、完全に大陸の支配下におかれた。「台湾統一」の課題を果たすために、経済のみならず政治においても、香港は「金の卵を産むアヒル」になっているという。 ▼ 第4章では、周辺諸国に対する中国の影響力の強大さが描かれていて、背筋が凍る思いすらさせられる。毛沢東時代根絶寸前だった麻薬。今では覚せい剤「生産地&消費地」。中国と並ぶ麻薬基地・フィリピンは「覚せい剤天国」と化しており、中国マフィアのブラックマネーが、チャイナタウン・スラム街・政官界・経済界に流れこんでいるという。「中露蜜月」が演出される反面、極東ロシアにおける中国人とそのマネーの存在感は、「タタールのくびき」の記憶と嫌悪感を呼び覚まし、衝突が絶えないらしい。「改革開放路線」「3つの代表論」の移植など、「運命共同体」である中国・ベトナム両共産党が演じる「中越蜜月」。中国は、台湾海峡で海上封鎖を実施するため、ミサイルと潜水艦を増強しているのに対し、台湾では民進党政権誕生以降、外省人将校の退役後の大陸帰国が相次いでいるとのこと。国民党の妨害で、国防軍の装備刷新もママならない台湾。台湾当局の「南向政策」の掛け声むなしく、『中国時報』のように台湾メディアの「大陸資本による乗っ取り」が行われはじめているという。タイや韓国では、タイのシリントン王女や孔子学院を利用した、一大中国ブームによるかつてない「蜜月関係」にあるのだとか。▼ 第5章では、アメリカとの衝突の数々が描かれていて興味ふかい。ブッシュ政権は、「ステークホルダー」(利害関係者)を強調する国務省と、中国に「透明性」を要求する国防総省と、分裂気味に対応しているようにみえるが、対中国には「右手で棍棒、左手で握手」戦略で対処しているという。アメリカの大学・企業に潜む、中国人スパイ「赤い花」。大陸によるアメリカ議会ロビー活動は、1億ドルにも及び、イリノイ州選出議員などを中心として、「中国研究会」などの親中派議連が出現しているという。意外なことに、2005年10月の「神舟6号」打ち上げは、ステーション技術と偵察技術ゆえに、アメリカは「軍事的行動」と捉えて脅威に感じているらしい。核融合の原料となる「ヘリウム3」の争奪戦を防ぐためにも、月の所有権争いを解決する動きがあるというのだから驚くほかはない。弾圧を受けながらも増殖する共産党の統制下にない地下教会。民主化運動の指導者も、国外に出てしまえば、影響力を失ってしまう。何清蓮氏の今後の中国分析は、必見といえる。▼ とくに細かいマメ知識は面白かった。「八」が大好きな中国では、北京オリンピックは、2008年8月8日午後8時に開催され、28種目が行われるらしい。スポーツにおける観戦マナーの悪さに、啓蒙を施そうとする当局も大変そうだ。局長などのポストが賄賂で売買。「切り上げ」観測から輸入商品の「買い控え」が広まり、意外に自動車とか売れていないのだとか。2005年には、17万3000台を輸出し、自動車輸入国から輸出国へ転換していたという。 他にも、「香港返還記念日」における民主化デモの参列者数は、香港支配が順調かどうかを知るためのバロメーター。「六カ国協議」の裏側で着々とすすむ、レアメタルなど鉱山資源を狙っての北朝鮮「経済植民地化」。広東華僑の出身のタイのタクシン首相。英語授業をおこなうためシンガポールに留学する中国人。韓国における中国語学習熱と中国における韓流ブーム。華僑の中国Uターンとアメリカにおける中国語ブーム ………… アジア・世界における、中国の息吹は凄まじい。日本のプレゼンスのなさは、呆れかえる位である。「靖国参拝」などで喧嘩しても、中国に絶対勝てないことは、これを読めば良くわかるに違いない。▼ ただ総じて感じたことは、読売新聞をあげた中国総力取材の結果が、この程度の内容なのかという、失望感と驚きであろうか。とにかく、清水美和の一連の著作を読んだ人には、ヌルくてタルくて仕方がないばかりか、第1章の新ナショナリズムの冒頭の「反日デモ」部分は、清水の著作の盗作としか言いようがない。本当にいいのか?参考文献に清水の名前をあげずに、そんなことして。てか、既存の新書や専門書から、ツギハキのように引用しているだけ。政治の裏面への洞察力もなければ、社会や経済についての、新味が何もない。まず題名からして笑えてしまう。「歪んだ成長」―――そもそも、日本といい、イギリスといい、歪まない成長ってあっただろうか?? この表題からみても、中国への「偏見」を告白しているようなものだ。おまけに、朝日新聞のように、決して主流になることはないであろうからこそ、記憶に留めてめておくべき、中国社会の変革の萌芽―――環境問題への取組、草の根民主主義 etc. ―――の摘出もなく、ただ既報の中国社会像を焼きなおしてなぞるだけ。いったい何を伝えたくてこんな取材をしたのか、深刻な疑問を抱かざるを得ない。▼ おそらく、中国社会について何も知らない人しか、この本は読む価値がない。これまでの中国イメージのベクトルに従い、取材した事実を集め、並べただけにすぎないからだ。ただ、経済関連記事を中心に光るものがあるとはいえ、この本を読むくらいなら、清水美和を読んだ方がずっと良いとおもう。ここまで下らない特集だったとは、新聞紙上でこの特集をしばしば読んでいたものの、一冊の本に纏められるまでまったく気づかなかったネ。 つくづく使えない新聞社であるというか、使えない記者しかいない新聞社であることがわかる「使える新書」というか ……… 少なくとも、読売新聞取材団は、清水美和一人に及ばないことが良くわかる≪良書≫とは言えるかもしれない。▼ マジに読売新聞中国支局の奮起を期待したい。評価 ★★☆価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 22, 2006
コメント(7)
-

★ 中田英寿引退と「やおい」 ~ 2006年ドイツW杯徒然草
▼ W杯は、イタリアの優勝とともに幕を下ろした。終わってから1週間になるけど、ひるむことなく、よしなしごとを書いてみたい。▼ 82年W杯以降、優勝できなかったのは、タルデリとコンティの後継者に欠けているためではないか?という日記を書いてしまいながらの、イタリアの優勝である。イタリアは、長年応援していたチーム。準決勝の時点では、「イタリア以外のチームが優勝するのは、W杯への侮辱だろう」とさえ思っていた。だから優勝はとても嬉しいのだが、微妙に違和感が残る。82年と比較すると、マテラッツィがジェンティーレ役、カンナバーロがシレア役といった所。カンナバーロ、ブッフォンの超人的守備には、驚愕するしかありません。ランパード、ロナウジーニョが大失速した以上、エトーと並んでバロン・ドール、FIFA年間最優秀選手が狙える位置につけているとも思うのだが、どうだろう。ブッフォンになっちゃうのかなあ…▼ マルコ・タルデリ役をこなしたのは、結局、ローマのペロッタでしょう。不十分ながら、攻守にダイナミックに動いていて素晴らしかった。ただ、不世出の右ウイング、コンティ役がおらず、華が欠けた印象が否めない。ボールキープ力で相手を圧倒するポゼッション・サッカーを繰り広げながら、ジダン退場劇のマテラッツィの悪行のみ、クローズアップ。ダーティヒーローの役回りしか与えられなかったのは、そのためでしょう。▼ 今回、優勝するに足る人材をもったチームが、志半ばで去っていった。とても残念におもう。94年W杯以降、常々感じるのだが、アルゼンチンは中盤に人がいない。ボランチ・攻撃的MFの人材は、帯に短し、襷に長し。ベロンも、リケルメも、アルメイダも、カンビアッソも、すごくいい選手だけど、イマイチ迫力に欠けるんだよなー。断言してもいいが、リオネル・メッシクラスの身長の選手を揃えている限り、アルゼンチンに優勝は訪れないだろう。ブラジルは、順当負け。イングランドは、監督負け。オランダは、そもそも若すぎた。ドイツは、機能的な中盤の反面、理不尽なゲルマン魂が姿を消してしまった感じで、順当に負けてしまった。日本代表については、mocokoさんのブログでほとんど言われてしまっているので、あらためて言うことはない。「日本代表は大和魂を発露させよ!」「大和魂をなくしてしまった日本!」とか騒いでいたアホ右翼がいたが、無策のままいさぎよく散ってしまったことは、大和魂の発揮以外の何者でもあるまい。▼ 相変わらず、日本人のさもしい根性には、嫌気がさす。むろん、韓国のトーゴ戦勝利を喜ばない、それどころかクサしてしまう、ゲスな根性のことだ。マスコミが好意的にとりあげたため、「マスコミは、日本の勝利よりも、韓国の勝利を喜んでいる」「また審判を買収したか」など、またしても周囲から、意味不明なやっかみを聞かされてしまった。てか、いい加減、韓国はアジアサッカーの犯罪者・加害者であり、韓国のW杯勝利は、アジアサッカーへの贖罪である、という風に捉えればいいじゃん。ドーハの悲劇は、武田が時間稼ぎをしなかったためでも、オフトが試合を壊すことを教えなかったためではない。あり体にいえば、韓国が弱かったから。「アジア枠が2」しかなかったから、にすぎない。▼ 1954年、W杯スイス大会で、ハンガリーに「0-9」、トルコに「0-7」。当時のトルコに7点差負けだぞ? 「W杯にわざわざサッカーを学びに来る必要はない」と酷評されたのが、韓国チーム。62年チリ大会では、南米・ヨーロッパ以外、アジア・アフリカ諸国が本大会に進出できなかったのはまだいい。58年スウェーデン大会では、イスラエルが韓国を倒して本大会出場権をえたのに、急遽FIFAは、ウェールズとプレーオフさせて剥奪するという、信じがたいアンフェアがおこなわれたのである。今も続く、FIFAのアジア・アフリカ諸国軽視。その一端は、スイスW杯の韓国の不甲斐なさにあるのだ。「贖罪の一環」だと思えば、別に腹が立つこともないだろう。日本が出ても結果は似たようなもんだし、所詮、現実逃避の慰めにしかならないのだが。▼ そんでもって、中田英寿の引退である。▼ あまりにも「いろいろ語られ」尽くしたこのニュース。その批評のバリエーションも、ある程度決まっていて、読む気がしないくらい。誰も言わない領域から中田引退を語るとなれば、「やおいと中田英寿」しかあるまい。そういえば、俺って「やおい変換」「腐女子妄想」できるしな…ということでやってみた。▼ やってみた…。▼ やってみた…。▼ ダメだった。▼ この敗因(?)は、一体、何に起因するのだろう…って、冷静に考えてみると、カップリングが思いつかないことに尽きてしまう。そういえば昔、「中田英寿×城彰二」のやおい本があった記憶があるけど、それって「ジョホールバルの奇跡」の頃、あったにすぎないよなあ…… 今更「中田英寿×川口能活」というのも、とても「ケンコジか!コジケンか!!」に類するバトルには、なりそうもない。中田英寿は、カップリングの対象がない位、隔絶した位置にいたんだなあ… あらためて驚嘆してしまう次第。稲本潤一や小野伸二などの99年ワールドユース組とは、存在のあり方がまるでちがう。▼ そういえば、2002年日韓ワールドカップのとき、中国の某夕刊紙で「W杯、不細工ベストイレブン」という特集が組まれていた。スペインの闘将カルレス・プジョールと並んで、堂々ランクインしていたのが、なにあろう、わが日本代表、稲本潤一である。曰く、「日本人は彼をハンサムだと思っているが、世界的に見ればどうみても不細工の部類に入る」。稲本潤一をハンサムと感じるのは、ひょっとしたら「やおい」に犯された人間、「やおい」的感性なのではないか ……… なによりも、中田英寿には無理でも稲本潤一なら腐女子妄想ができる、この私が言うのだ。おそらく、間違いあるまい。嫌だなあ……▼ 閑話休題▼ 結局、このW杯は、「ジダンが決勝で退場したW杯」として、記憶されてしまうのだろう。前回のW杯が「誤審のW杯」としか記憶されなかったように。▼ こんな語られ方が横行してしまうのは、試合自体にあまり魅力がなかったからではないか。欧州のクラブチームこそ最先端、代表チームは組織力・熟成という点でクラブチームより劣るから ……… 。あまり言われていないようだが、今回のイタリアの優勝は、90年イタリア大会のドイツ以来、16年ぶりの純正白人チームの優勝でもある。今回のW杯とは、「テルミドールの反動」であったことはあまりにも明らかだ。▼ 美しきブラジルサッカー。それは、黒人の技術や身体能力をサッカーに初めて導入した、「世界最初のブラックパワー」であったことと無縁ではない。ブラジル以外、黒人を主体とした強豪といえる代表チームは、長らく存在しなかった。美しきブラジルの神話。88年オランダ、98年のフランスがそれに続いた。魅力的なサッカーには、黒人は欠かせない。今回、ひどく退屈にみえたのは、存外、そんな所に原因があるのかもしれない。2010年W杯は、南アフリカで開催される。魅力的なサッカーの復権が見られるのではないか?▼ よしなしごとを書き連ねてきた。ここまで読まれた方、ご静聴ありがとうございました。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 18, 2006
コメント(1)
-
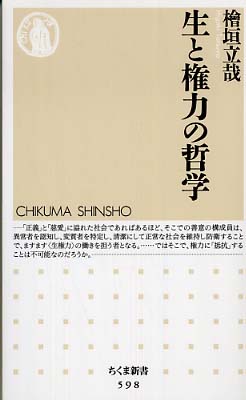
★ 檜垣立哉 『生と権力の哲学』 ちくま新書(新刊) <2>
(承前)▼ 果たして「抑圧されたものの解放」という構図に依拠しないで、政治的倫理的ビジョンを切り開くことはできるのだろうか。主体の概念に包摂されない「外」の記憶を呼びさまそうとして逝ったフーコー。▼ ドゥルーズは、フーコーが提示した調整管理的権力をひきつぎ、「管理=コントロール」権力を「規律訓育型」権力とまったく異なったものとしてとりあげる。もはや空間・時間の分割・配置はない。そこでは、コンピューター管理による環境そのものを流動的なまま管理=コントロールする仕組が作られている。抵抗は、「人間」が行うのではない。ドゥルーズは、われわれ自らが「人間」の「外」、すなわち「生命」の「力」を秘めていることに賭け、情報と生命のテクノロジーに希望を見いだそうとする。▼ ジョルジョ・アガンベンもまた、フーコーの仕事を引き継ぐものだという。アガンベンは、ギリシャでは「生」が「公共的」な「言説」のビオスと、「生きている」という事実だけのゾーエー、この2つに分けられていたことを明らかにする。彼は、近代における政治の戦略点として「ゾーエ」を捉えたフーコーを批判し、あらゆる政治的秩序(=主権)が出現する際、常に、「ゾーエ」は「例外状態」として「排除」されながら「包含」されてきたことを強調する。 「ビオス」には、「ゾーエ」がつきまとう。ギリシャのポリス的政治でも、ゾーエである「剥き出しの生」の排除によって初めて、ロゴスの境界線と「政治的なるもの」が確定されるのだ。▼ 「法的なもの」「超越的」なものの対極に≪生政治≫を置いたフーコー。アガンベンは、主権にゾーエが不可避である以上、主権とともに出現する「法的なもの」は、≪生政治≫的な空間に位置づけられなければならないと批判する。アガンベンは、近代の極北、「人種管理」「優生学」「民族浄化」について、旧来の「法的権力」が≪生権力≫に入り込む通路としか捉えず、「収容所」を軽視したフーコーに対し、≪生政治≫の枠組で思考することをやめない。「収容所」とは、ゾーエという「剥き出しの生」が露呈される空間の別名である。近代以降に出現した、それまでと異質の社会秩序は、ゾーエそのものが顕示されることで、言説的主体「ビオス」が壊滅的に低下すること、すなわち「収容所」の例外状態が恒常化した社会に他ならない。そこでは、ビオスとゾーエが曖昧な交差点をつくりだし、優生学・人体実験・脳死の身体………本来なら「収容所」的、例外的とみなされていたものが、政治として先鋭化する。もはや、近代的「法」「公共性」に依拠した論理・倫理では、その領域を捉えることができない。▼ アウシュビッツの「生き残り」とは、何か。アガンベンは、そこにグレイゾーンを見いだし、グレイゾーンにおける責任の取り方について思索する。誰が加害者で、誰が被害者か。そもそも「生き残り」は、被害者といえるのか。アウシュビッツで生き残ることは、仲間のユダヤ人を売り渡したことではないのか。否、生きることとは、何かを誰かに売ることを意味するのではないのか。アウシュビッツの証言等、「剥き出しの生」が現れるグレイゾーンの世界では、「法的」システムを前提とした、伝統的倫理学の「責任」では捉えられない。そこは、「無-責任」の世界ではないのか。▼ アウシュビッツが倫理の再考を迫るのは、責任を負うからではない。「排除」されて「見えなく」されていた、「倫理と非倫理」「人間と非人間」の境界が露呈するからである。「剥き出しの生」から、主体は立ち上げられるのか。可能だ。ただ主体は、「恥辱」を追うものとして現れる。「自己」において「自己に非ざるもの(非自己)」が現前して逃れられない。 「恥ずかしい」のは、レイプされることではない。感じてしまうこと―――被動であるはずなのに、能動と絡み合ってしまう地点―――にあるのだ。「生命」を生きる主体は、「責任」の「主体」ではない。アウシュビッツの意義とは、主体の構造―――主体は、言語が包摂しえず遺棄する他ない「生」と、それに引き渡されながらも排除することで出現する言語装置としての「人間」、この2つの揺れの中の「残りもの」として、「恥ずかしさ」という感情として現れる―――を明らかにしたことにあるという。▼ またアガンベンは、「法」と暴力について考察を深めてゆく。法から閉め出され、法が包摂するのは、「剥き出しの生」である。そして、言語同様、それ自身において基礎付けることができない「宙づり」状態にある。ただ、この「不在」であるが故に力をもつ「法」というデリダ的議論は、「無が無制限に存続することを許してしまう不完全なニヒリズム」「否定性を見るだけ」で、法システムの無批判な維持にしか結びつかない、と批判する。「法」の外部は「生」であって、その境界地域で「法」は消尽してしまう。アガンベンは、ここにベンヤミンの「法維持的暴力」「法措定的暴力(神話的権力)」―――前者は法内部で法的秩序維持に発動されるのに対し、後者は法無き場所に法を設定する「法の外」(例外状態)を内部に抱えこむ暴力―――を援用して、この2つの間の分かちがたい緊張―――外部が内部に、「剥き出しの生」が「法」に介入する―――をつなぐ、ベンヤミンの第三の暴力「神的暴力」―――「法措定的暴力」を浄化する純粋暴力―――こそ、「生」の領域の露呈であり「法」の根源ではないか、と提起する。それは、このベンヤミンの「神的暴力」をホロコーストと結びつけ「否定」してしまうデリダとシンクロしていて、たいへん興味深い。▼ 加えて、アントニオ・ネグリも、「ドゥルーズ-アガンベン」のラインから眺めると、また違った姿がみえて面白い。媒介(国家、代表制、寡占メディア)に依存せず、超越を想定せず、すべてが内在によって機能する、≪生政治学≫的な原理によって貫かれた社会。それが≪帝国≫という社会らしい。マルチチュードは、コンピュータなどによって、媒介に依存しないでダイレクトに参与する。「例外状態」、「剥き出しの生」をすべる警察……フーコーを世界システムに接続させたもの、それがネグリの議論だという。フーコーが明らかにしなかった、「法」の支配にとって代わる「生」の「生産」。ドゥルーズ「生産する『機械』」で提示されていない、カオス的不確定的「出来事」性を超えた、社会的動態の摘出。ネットワーク的生産とコミュニケーション的主体をとなえたイタリア・マルクス主義が把握できていない、≪生政治≫的、動態的文脈。ネグリは、フーコーが見いだした認識論と、ドゥルーズが解明しようとした後期資本主義社会の動態を、イタリア・マルクス主義の観点を組み込みながら、具体化しようとする。▼ ≪帝国≫は、グローバル化(均質化)とともに、ローカル化(差異化)を産出する。差異のポリティクスをのべるだけのポストモダンと、植民地主義の残滓を暴くだけのポストコロニアルは、敵を取り違えているにすぎない。「脱構築」は、批判に堕してしまうか、不可知な「他性」に向かう究極の「正義」としての「責任」の「主体」を、その空虚さにおいて強調してしまう。「他」を探す行為は、「内在」の力を取り出すことなく、「超越」を構成してしまう幻想の、いわば最後の砦になってしまう。同一化的装置を解体して、空虚な不在としての「他」を想定することもない、差異化の運動を取り出すため提起されるのが「マルチチュード」に他ならない。情報ネットワークによって可能になった、内在と直接性による、「公共性」とは違った共生の位相、それが「共(コモン)」であるという。マルチチュードの意義とは、伝統的共同体、理性的計算を前提としない、アイデンティティや、啓蒙的前衛など、いっさいの「超越」「近代的権力」を拒否する世界の肯定的描像を描いた所にある、として本書は締めくくられる。 ▼ なによりも、フーコーを軸とした壮大な現代思想の展開が、コンパクトにまとめられていて、「目から鱗」というしかない代物だ。フーコーがどれくらい毒々しい思想家であったか。執拗に述べられていて、たいへん面白い。自我中心性、自文化中心主義を持たない、他に向けられた「正義」の主体を構想する「レヴィナス~デリダ」的主体は、ビオスの議論に過ぎない。「不在」からくる相対主義を「他」性によって逃れようとするデリダとは違い、真理の生成をポジティブに肯定するフーコーには、「不在」が存在しないという。なによりも、強調されているのが抵抗の「中心」を考えることも無効、という議論であろう。生権力は、われわれの「生」に働きかけるが、守ろうとするものは「人間」の社会に他ならない。「人間」から抜け出し「生命」であることを掴み出すこと、ここに抵抗の拠点があるという。ローマの伝統的「生」の排除として、ただ廃棄されるだけの人間「ホモ・サケル(聖なる人間)」、どこにも「一」を形成しない「多」であること「マルチチュード」……… なによりも、抵抗のポストモダン的「主体」として「言語(情報)」「コミュニケーション(労働)」による「身体」を想定することは、フーコーやドゥルーズが拒絶した「超越」の復活になるのではないかというネグリ批判には、うならされる他はない。▼ むろん、哲学の概説書・入門書とは、役に立たないものの代名詞にすぎない。所詮、「問題意識」なくして読んだところで、益するものは何もないからである。さらに、哲学書のコンパクトな「まとめ」「教科書」自体、哲学そのものの自己否定のようなものかもしれない。哲学書そのものがもつ難解さとともに、面白さも消えるのが常だから。▼ でも、監視カメラって気味が悪くないか……ネットの情報管理強化って怖くないか…こんな不満・感情を抱く人には、この本は福音といってよい。その気味悪さの由来・理由・処方箋(試行錯誤でしかないが)が述べられているからです。「生命」レベルをターゲットにした権力に向き合うには、どうすればいいのか。「現代思想」の強力な流れ、「スピノザ~ドゥルーズ」のラインを押さえる教科書としては、最適の書物といえるでしょう。一家に一冊、常備しておきたい本の一つです。▼ お試しあれ。(長文にも関わらず、暖かい応援ありがとうございました)評価 ★★★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 12, 2006
コメント(5)
-
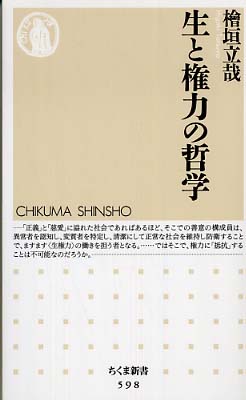
★ 檜垣立哉 『生と権力の哲学』 ちくま新書(新刊) <1>
▼ これはいい…。久しぶりに、素敵な入門書を読ませていただいた。▼ 著者が、その鮮烈な問題意識に即しながら、基本をきっちり押さえる入門書にもなっている。なおかつ、我々が現代社会を批判的に再考する際に視野を広げてくれる…。そんな芸当ができる書物は、かなり希少価値に近い。現代の「生」、そして「権力」とは何者なのか。近年提示される≪生権力≫に対する、使える本のひとつ、といえるでしょう。▼ 「生政治学」のミシェル・フーコー。「管理=コントロール社会」のジル・ドゥルーズ。「剥き出しの生」のジョルジョ・アガンベン…この3つを時間順に細やかにまとめていく。▼ 性と死。我々を根源的な規定するもの。言語的で「文化的」な我々の「生」は、その秩序形成において、そうした「自然的な生」、すなわち「生命」という主題とその「統治」という問題を抱えこまざるを得ない。文化的と自然的。この2つの領域の交差地点にこそ、政治の中心的テーマが析出され、精神医学的・遺伝的・医学的管理が、権力として機能する事態になる。▼ ≪生政治≫。▼ 旧来「権力」像は、超越的な「上」から、「死」を手段として、「禁止」「抑圧」してくるものであった。フーコーは、そんな中心的権力を想定しない。うごめく大衆を空間の配分自身によって「自己監視」させる―――いわゆるパノプティコン―――「規律=訓育」型権力を提示する。「生」が権力の対象となることは、「抵抗のあり方」や、西洋近代的な「主体像」ならびにと主体を前提とした「社会像」に、全面的な変更をせまる。フーコーは言う。権力が抑圧・禁止を通して発動される様に描かれるのは、いったい何故なのか。それは、抵抗するポーズをとるのに「都合がいい」からにすぎない。革命とは、管理=コントロール型権力が発揮される格好の実例であって、転覆の思想とは、排除されたもののルサンチマンに支えられる、権力の補完物にすぎないのだ、と。≪生政治≫的権力は、言語的「主体」の形成以前における、身体・生命レベル、無意識レベルの「生けるものの働き」に焦点をあてている。もはや、正義のロマンティシズムは、荒唐無稽である以前に、権力の作用について「鈍感」といわざるをえない。▼ 知の認識論的枠組「エピステーメー」の断絶・転換・非連続をとなえるフーコーは、歴史を全体として捉え「意味」を付与する思考を徹底的に批判する。しかしそれは、たんなる歴史相対主義ではない。相対主義は『「真理の不在」という真理』を当てにしている。フーコーが歴史的相対化をおこなう対象は、「真理」という発想そのもの、それを産出する「人間」という装置そのものに限られている。「真理への意思」を体現する、超越論的―経験論的二重体である「人間」の形成と消滅を探る、フーコー。かれは、「排除」(=「人間」の外部)によって出現した「正常」な「人間」を問題にした前期から、後期では「非人間」であるものがどのように「人間」を生成させてきたのかにテーマを移行させ、「言語」が内包している「排除的」「分節化」の原理から、「生命」にそなわった秩序の「生産」、にそのスタンスをかえてゆく。晩年には、≪生政治学≫からさえ逸脱し、ネグリ・アガンベン・ドゥルーズに大きな影響をあたえているという。▼ 「狂気」が排除されるから、われわれは不自由なのではない。 「自由」な主体へと解放されることが孕む徹底的な管理、すわなち「公正な空間」に配備されるがゆえに、決定的に不自由になるのだ………。フーコーは、近代について、「告白」というテクノロジーを使い修道院を母体に誕生した「規律訓育型権力」が、軍隊・病院・学校に増殖・拡散する時代と捉えた。そこでは、空間・時間・段階が網の目のように「分割」されていて、そこへ「主体」をくみこんで「矯正」してゆく。規律訓練型権力は、法的な違反とはちがう「『非行性』の生産」を通して、社会全体に自己監視を及ぼし、「監禁的なるもの」を蔓延させ、犯罪者と権力が奇妙な癒着した、ポリス=警察国家を作り出してしまう。非行性は、個人に付随せず、個人を形成した環境全体を問題にする。そのため、犯罪者は永遠に犯罪予備軍に他ならない。 ▼ またフーコーは、抑圧され、隠蔽されているが故に、「真理であること」「人間的なもの」として確保されてきた、「性」にまつわるフロイト主義的言説の相対化を試みることで、規律訓練型権力に止まらない、≪生政治学≫的な主体産出に向けての考察に足を踏み入れる。▼ 性は近代において扇情的であって抑圧されていない。超越的権力―――「否定的(死・追放など)」「2項対立的」「禁忌(存在してはならないものには存在しないふりをする)」「検閲」「統一性」―――に対して、≪生権力≫は隅々まで拡散して「下からくる」「内在によって機能する」「権力の中心がない」ものである。誰も権力の外には出ることができない。フーコーは云う。異常者・子供・女性・人口の4つの軸を通してテーマ化された「性」は、精神分析という知、家族制度、ブルジョアジー階級を介して、「性的欲望」の装置として機能している、と。 本来家族は、「法」と「契約」とを軸に形成される、「婚姻の装置」によって成立する社会システムであった。この空間に、「夫-妻-子供」の所謂「フロイトの三角形」が導入され、性と生殖にまつわる「生」のコントロールがおこなわれるとともに、性的倒錯の場所(近親相姦の忌避という「法」)が割り当てられ、「性的欲望」を喚起しつつコントロールが行われるようになる。フロイト主義以降、家族という空間は、「法的」なものに≪生権力≫が入り込んでしまい、≪生権力≫の舞台となる。また「自己管理」「自己確認」としての≪生権力≫は、ブルジョアジー階級の「自己確認」手段として精神分析という知を受け入れる一方、貴族階級が持つ「血」概念を戦略点として、生物学的・優生学的・医学的・遺伝的管理を展開するという。それは、「種」をターゲットにするがゆえに、「人種概念」「人種差別」「民族浄化」を生み落としてゆく。「フロイト主義」とは、≪生権力≫の衣をまといながら古い「法」的制度を結びつけることで、「抑圧」からの「解放」の倫理ビジョンを夢想・蔓延させる、反動的体制の極限に他ならない。このフロイト主義批判は、たいへん面白い。(またまた「まとめ」るのに長くなってしまったので、<2>に続きます。暖かい応援をおねがいします)評価 ★★★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 9, 2006
コメント(2)
-

★ 論座編集部 『リベラルからの反撃』 朝日選書(新刊) <2>
(承前)第3章「靖国と外交」もそれなりに面白い。「戦後60年の日本・アジア・世界」は、梅原猛×五百旗部真の対談集になっています。ナポレオン打倒後、ヨーロッパ大陸において「利権」を漁ろうとはせず、ウィーン体制によって平和をもたらしたイギリス。アメリカは、このときのイギリス同様、敗戦国にも「寛容」な戦後秩序を作り出したことで、世界をリードしていた。ところが近年、アメリカは、廃仏毀釈によって仏とともに神も死んだ日本とはまるで違い、キリスト教原理主義が年々力を強め、社会の寛容さが陰を潜めつつある。また、戦前の日本の行き詰まりは、中国での評判の悪さから、国際的にトランプのジョーカーとして扱われ、一緒に行動しようという国がなくなったことにあるという。もはや中国は、アジアの代表、大国に他ならない。中国での評判の悪さは、日本のイメージや将来を決定的に危うくするだろう。若宮啓文「靖国参拝が壊したアジアとの和解」では、自民党政権の「伝統回帰の動き」が「アジアとの和解の翌年」におきる、『翌年の法則』について述べられている。元号法(79)、建国記念日(66)…天皇に絡めた復古的な動きが今も続く一方、「A級戦犯を戦争犯罪人」とするなど、小泉は決して右派政治家とはいえないという。国民の象徴にある天皇が「アジアとの和解」を重視しているのに、政治の頂点にある小泉首相は、「和解」を傷つけて憚(はばか)らない。天皇と多くの国民が訪れることができる、そんな追悼施設を一刻も早く作ってほしい、と結論でまとめられる。細谷雄一「眠れる外交」は、年々不利な状況に追い込まれている国際環境の直視と、積極的な外交活動の再開が説かれている。職業外交官が冷徹に計算・交渉して最良の妥協を模索した「旧外交」の時代が去った。次の選挙に目を向けるポリティシャンが横行するポピュリズムの日本では、政治指導者はマスメディアから外交官を守ろうとしないため、外交が大きく損なわれているという。東アジアにおける冷戦の残滓を取りのぞき、長期的な平和の基礎をつくるという長期的な国益のため、一刻も早く目を覚ませ! その叫びは悲痛という他はない。本書の最後、姜尚中×田中明彦「『靖国』の土俵から降りなければ展望は開けない」の対談は、なかなか興味深い。現在の日本外交の混迷は、戦後、アジアの独裁国家群相手に属人主義的ネットワークでおこなってきたため、アジアの民主化とそれに付随するナショナリズムによって機能不全に陥ったことにあるという。枯れた日本から見れば、現代の近隣諸国のナショナリズムは「発情期」。なおかつ東北アジアでは、パワーシフトが引き起こされる激動期に他ならない。ところが肝心の外務省には、「外務省改革」がおこなわれ、外交が世論に左右されないためのバッファー(緩衝器)の役割を果たしていた鈴木ムネオが切られたことで、この激動期に泥をかぶる人がいなくなってしまったという。ムネオに替わるオルタナティブが用意されないまま、政治家と官僚が足を引っぱり合う、日本外交。その結果、外交の分野では、本来、プロフェッショナルな領域が必要でありながら、「改革」によって、必要ないという空気が蔓延してしまい、非「プロ的」な領域が拡大の一途をたどっているという。靖国参拝では、中韓どころか欧米も批判的なため、小泉には絶対勝ち目がない。しかし、今追悼施設を作ってしまうと、中韓の批判で作ったことになってしまい、そもそもの建設の意味がなくなってしまう。靖国のため、日本が主張できない、分野・領域がいかに多いことか!!! 靖国参拝によって何度も謝罪させられてしまう。謝罪は1回でいいのに何回やってるんだ! そんなことで国益をかけたタフな交渉が出来るか!!! その怒りには、思わず共感させられてしまう。端々に見られる、リベラル再建への意志。俺たちを「保守」「現実主義」だのと批判していた左翼リベラルはどこへ消えたという批判は、一抹の寂しさというよりも、論者の気概を感じさせて良い。しばしば見られる「侵略されたら逃げよう」派についても、彼らの現実逃避的認識より、その考えのエゴイズムぶり(逃げられない人はどうすればいいのか)が徹底的に批判されていて、たいへん心地よい。またハンチントンなどにみられるように、日本は「いつも世界最強の国と手を結ぶ」「中国が強くなれば、中国に近づく」ポリシーのない国家と思われているらしい。H・キッシンジャーが中国に表明したとされる、日本不信(なぜか読売はキッシンジャーが大好きだが)などを考えあわせると、とても一外交官・一学者(?)の寝言と看過できるような代物ではない。政治家は、国民の歓呼の声で迎えられた外務大臣松岡洋右を選ぶべきなのか。それとも、国賊の声で迎えられた小村寿太郎を選ぶか。「謝罪と和解の90年代」が、江沢民訪日で画竜点睛を欠いた後、小泉政権ではその揺り戻しが行われた様子は胸が痛む。他にも、序論に納められた「後藤田正晴の『遺言』」もとても面白い。神道では、氷川神社でも、八幡神社でも、伝統的に分祀可能であって、A級戦犯は分離できないというのは、靖国神社の大ウソらしい。サンフランシスコ講和条約では、判決を受け入れたのであって、東京裁判を受け入れたのではないという愚論に対しても、「負け惜しみ」「国際的責任の否定」と手厳しい。ただ、中国・韓国がサンフランシスコ講和条約違反などと言い募ることに対しては、「おまえら講和条約の当事者じゃないじゃん」とさりげない突っ込みが入っていて、楽しめる。 とはいえ、疑問点もつきない。まず、内容のバラツキが大きすぎる。井上達夫、長谷部恭男、佐伯啓思などの論説は、読むに価する内容と語り口をもつものであったが、後は微妙なものが多い。とくに櫻田淳、細谷雄一、梅原猛×五百旗部真の担当部分は、内容に新味がない上、エッセイとしてもどうか。わざわざ収録する必要があったとは、とても思えない。ほとんど、飲み屋の政治談義の類であろう。朝日論説主幹、若宮啓文『翌年の法則』も、とっくに朝日新聞上で書いていたためか、まったく新味がなくて、関心しなかった。「翌年の法則」だの「和解と伝統回帰の双方を追求できなくなった小泉政権」だのは、あまりにも通俗すぎて、具体的な政治過程を抜きにした愚論であろう。そもそも、番記者経験も長く、自民党政権の政策決定過程に、一番迫ることができる(だからこそ、結果的に誇大記事やウソを書かされることにもなるのだ)「政治記者」の身でありながら、この程度でお茶を濁すとは、期待外れもはなはだしい。政治学者としてもジャーナリストとしても、あまりにも中途半端。若宮は、石川真澄や早野透の爪の垢でも煎じて飲むべきだろう。くわえて、「リベラルとは何か?」が、ボヤ~っとしていて、こちらに伝わってこない。たとえば、井上達夫・五百旗部真や、仙谷由人などが、旧来の左翼とは異なる思想的立場として、「リベラル」を志向(たとえば、マルクス主義者はどこに消えた?など)しているのはあまりにも明らかだろう。またそれは、「保守」とも違うことは、言うまでもない。ところが、対談に出席している朝日新聞の薬師寺記者は、旧来的左翼の別名として「リベラル」を捉えているかのような懸念や質問を発しているし、その反対に「保守」と「リベラル」が、一緒にされていたりするような節も散見される。いい例が、「自・公・民」座談会だろう。「リベラル」とは何であるのか。外交におけるリベラルなどの表現も本書ではみられる。気づきだすと、苦痛以外の何者でもない。旧来の左翼を微温的に温存するための方便としてのリベラルなのか、それともロールズ的意味のリベラルなのか。どちらでもないなら、そもそも何なのか。本書は、最初から明示するべきではなかったか。なによりも、「リベラル側からの大きな物語を書く必要がある」と冒頭でも書かれているのに、結局、その課題が果たされていないことがあまりにも痛い。そもそもリベラルは、本当に「大きな物語」を必要としているのだろうか。むろん、近年の「大きな物語」を提供することによって、肥大化を続ける、非現実的な日本の「右傾」化現象に対し、リベラル(?)側も「大きな物語」を「分かりやすく」訴えなければ、という気持ちはわからないではない。とはいえ、「大きな物語」が、何のために必要なのか。そのことが、明らかにされないまま論稿が集められた結果、関係ない論考まで乗せられ、論点が拡散してしまっている。「靖国と外交」(特に後者)は、リベラルと関係あるのか。これだと、「リベラルの反撃」とは、限りなく「旧来の左翼の温存のための方便」にならざるをえないだろう。結果として、「リベラルとは何か?」が曖昧になってしまい、井上達夫などの鮮烈な問題提起が、印象を薄められてしまったのが惜しまれる。しかし、面白かった。皆さんにはぜひともご一読をお勧めしたい。評価 ★★★☆価格: ¥ 1,260 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jul 3, 2006
コメント(3)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










