2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年11月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
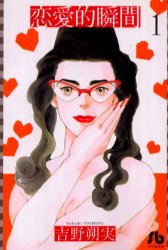
★ 女性的身体は、いかにして生みおとされるのか? 或いは「権力SF」についての一考察 ~ 吉野朔実 『ジュリエットの卵』から今野緒雪 『マリア様がみてる』へ ~
▼ 早川書房から、一通のアンケート依頼が後輩の所に届いた。 来年2月刊行の『SFが読みたい! 2007年版』に載せるものだという。 ▼ 一つは2006年度(2005年11月~2006年10月)に出版された本の中から、海外・国内それぞれベスト5を選ぶもの。 もう一つは、2000年代前半(1999年11月~2005年10月)に出版された本の中から、海外・国内それぞれベスト10を選ぶもの。 ▼ 21世紀初頭のベストSFかあ。 そういえば、読んでないなあ、SFなんて。 最近、売れてるんだろ。 それなら、読まなくてもいいし、ジジイの出番でもあるまい。 そう思いながら、茅田砂湖『スカーレット・ウィザード』が面白かった、そういえば佐藤大輔『地球連邦の興亡』はどうなった、とか考えていた所、天啓のように閃いた。 ▼ 「そうだ、『マリア様がみてる』があるじゃないか!!!!!!」▼ あれは、「シスター・ファンタジー」、略して、SFだ。 なによりも、あれはサイエンス・フィクション(←こっちが正しい)だ。▼ 暗黒の近未来社会、日本。 その社会では、もはや監視の主役はカメラではない。 もはやカメラは必要ではないのだ。 「銀色のロザリオ」こそ、女性を監視・束縛して訓練を施す主役である。 ロザリオは、学園内において、女子高生の手を転々とわたってゆく。 その過程の中で、「お姉さまに好かれる女性になりたい」、という意識が内面化され、「喜び」とともに、思想改造が施されてしまう ………▼ ああっ!!! なんという巧妙! なんという悪辣! そしてなんという華美!! 暗黒にして甘美な近未来社会を描いた、スペキュレイティブ・フィクションではないか!!!!!! (笑) ▼ こう書いてみると、その怖さは、オーウェル『1984年』の比じゃないぞ。 同じスペキュレイティブSFなら、バラード『結晶世界』よりも何十倍も面白いじゃないか。 バラードがつまんないだけだって?。 ええい、畜生。 なんとなく、ブラッドベリ『華氏451度』を感じさせる、問題意識さえ漂っている作品、でどうだ! ▼ そうだ、『マリみて』は、「権力SF」だ!! 『マリア様がみてる』は、「権力がいかにして従順な身体を生産するか」を描きぬいた、「権力SF」というジャンルを創出した作品なんだ!!! 21世紀の最初の5年を飾る、ベストSFには、『マリみて』こそふさわしい!!! ▼ ……と以上のように一人、悦に入ってしまった。 後輩に薦めておいたんだけど、どうなったのだろう。 はたして、来年2月、早川書房『SFが読みたい! 2007年版』に乗せられているかどうか。 ボツにされないことを祈るしかない。 剋目して待て、諸君!▼ 閑話休題▼ 最近、吉野朔実先生にはまってしまった。 本当にはまってしまった。 ああ。▼ たまたま、手にした「haRmony」に度肝を抜かれた。 凄い。 幸せな結婚を支えていたのは、まったく関係の無いように見えた音楽にからむ「思い出」であった。 その「思い出」がずたずたに壊されたとき、結婚そのものも破滅に向かうのか ………。 違う。 そうではない。 その「結婚」「思い出」、2つの否定態たる「子ども」によって、高次の次元で2名があらたに結ばれあうという、衝撃の結末。 すげえ。 ▼ あまりの凄さに、一度リアルタイムで読んでおきながら、「わかんないや」と投げ出していた『恋愛的瞬間』全3巻(小学館文庫)を買いなおした。 もう、涙が止まらないほど凄い。 全20話。 ひとつひとつがまったく違う。 そんな20もの恋愛の「切断面」が、止血措置を施されることなく、血があふれ出して滴り落ちている、そんな作品だった。 ▼ なぜ、10年前、この面白さを理解できなかったのだろう。 あまりにも幼かったためなのか。 自分の不明を悔やむしかない。 『いたいけな瞳』全5巻も、本当に素晴らしい。 ▼ 吉野朔実は、決して「恋愛」を縫合しようとしない。 痛みを和らげるようなハッピーエンドを用意しない。 意表を突くようなギャップが開かれて、読者に提示される。 傷口は、開かれたまま閉じない。 ただ恋愛にからむ「傷」が、ひたすら羅列されるだけだ。 ハッピーエンドなのか、悲劇なのかすら、定かではない。 ▼ そんな彼女には、短編が良く似あうのだろう。 あまりの凄さに驚愕して、かつて否定的な評価をあたえたことのある、『少年は荒野をめざす』を読み直した。 その評価は、変わらない。 あいもかわらず、荒野にポツンと置いてきぼりにさせられたような、そんな読後感が残る作品だった。▼ そんな彼女の長編作品で唯一、凄いと感じたのは、『ジュリエットの卵』全3巻(小学館文庫)である。 これが、もう、掛値なしに素晴らしい。 あまりにも鮮やかな、吉野朔実の絵柄とともに、これを機会に皆さんにお勧めしておきたい。▼ 双子の兄と妹。 父はいない。 母だけの母子家庭。 母からすべてを受け継ぐ兄。 女であることを呪う妹。 しかし兄と妹は、恋愛感情を抱いていて………。 あまり詳しく描きたくはない。 ラストへ向けた怒涛の展開がすさまじい、と記しておくことにとどめたい。 そして、「ジュリエット」=女性が生まれ落ちてゆく。 ▼ 呪われたもの、としての女性。 ▼ 今の時代だと、ピンと来ない人も多いかもしれない。 しかし、それは確かに存在したのだ。 1959年生まれである吉野朔実にとって、そしておそらく、1960年代生まれまでの女性にとって、この種の感覚は、納得しうるものだったに違いない。 「女だてらに」「女性たるもの…」「お前が男だったら」 … どれだけ言われていたことだろう。▼ そのような中で女性は、どのようにして生まれ落ちて、どのように孵化していったのか。 この双子の間に引かれた「断絶」をめぐる物語は、その美しい絵柄のみならず、今は失われた「時代の思潮に規定された物語」であるが故に、断固として語り継がなければならない。 そんな稀有の価値をもつ作品である。 ▼ 今や女性は、呪われていない。 スタイルの悪い女性など、繁華街には、ほとんどいない。 どの人も、とても美しくて、幸せそうに見える。 しかし、『マリみて』では、「幸せ」や「喜び」こそ、女性的身体を再生産する装置ではなかったか。 ▼ もはや権力は、抑圧するものでもなければ、呪いを与えるものでも、苦痛を与えるものでもない。 そんな「姿」で、権力が現れることはない。 われわれは、「幸せ」「喜び」を通して、操られているのではないか。 われわれは「幸せ」や「喜び」を通して、狡猾にも支配されているのではないか。▼ 『ジュリエットの卵』から『マリア様がみてる』へ。 1980年代と21世紀。 女性的身体を生み落とすものを描きぬいた2つの作品は、権力の編成原理の違いを的確にとらえている、というしかない。 冗談ではなく、「権力SF」にふさわしい。 否、今や「権力SF」こそ、時代の最先端ではないか。▼ 秋の夜長。 ぜひ、お試しあれ。 てか、お願い。 読んで。評価 ★★★★☆ (ジュリエットの卵)価格: 1巻・2巻¥ 620 3巻¥ 590 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 28, 2006
コメント(1)
-
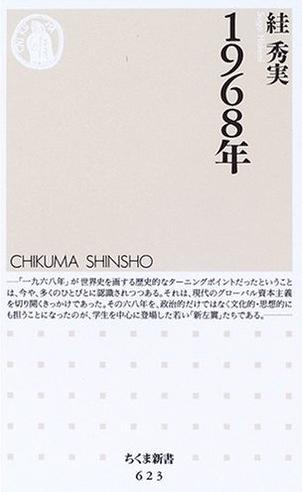
★ 糸圭 秀美 『1968年』 ちくま新書 (新刊) 前編
▼ 近年、歴史を「取り戻そう」とする運動が、どこでも盛んだ。 ただのオナニーからアカデミックなものまで。 そんな様々なものを、一緒くたに扱うことに一抹の不安がよぎるものの、冷戦終了後特有の現象といえなくもない。▼ 本書は、「1968年」の歴史的意義を問い直そうとする。 これまでの「1968年」は、先進資本主義国・東欧・ラテンアメリカの世界的動乱、であるとともに、「新左翼」の誕生、「思想的大転換」でもあった。 まさしく「68年の思想」は、「ポストモダン」(リオタール)であった。 しかし、動乱がどのような意味で「68年の思想」と結びついていたのか。 とくに、全共闘などの過激なデモンストレーションがおこなわれた日本では、「団塊の世代」論に絡められてしまい、その思想的意義がまったく論じられていない。 エコロジーやフェミニズム(マイノリティー問題)。 それに解体された大学(資格認定「ハローワーク」の場ですらない動物園化)を始めとして、新左翼が提起した社会的現実は、日本を覆いつくして、もはや保守派すら抗えないにも関わらず。▼ この「1968年」のもたらした思想的意義と断絶とを明らかにするために、1969年1月18・19日の「安田講堂」史観を粉砕して、あえて1970年7月7日「華青闘告発」中心史観を掲げて論じようとする。 なかなか、魅力的な見解ではないか。▼ 本書の概要をあげておこう。第1章 先進国の同時多発的現象第2章 無党派市民運動と学生革命第3章 「華青闘告発」とはなにか第4章 ヴァーチャルな世界のリアルな誕生第5章 内ゲバ/連合赤軍事件/革命▼ 「1968年」のおこした日本での革命。 これが何ゆえ認識されなかったのか。 それは、1968年の提起した課題が、「受動的革命」「反革命的」な形によって実現したためだという。 過激なまでの自由は、ネオ・リベラリズムに回収されて実現した。 これでは、リベラリズムは批判できない。▼ 豊かさの中の革命。 スターリン批判とともに誕生したことが知られる新左翼は、セックスと反抗を描いた青年小説『太陽の季節』を描いてスキャンダラスなスターとして登場した石原慎太郎と同様の、ナルシシズム=ナショナリズムを抱いていたという。 「全学連」結成に始まる大学の学生運動も、68年までは、自らも規律・訓練に参与する主体の一人として、知的優越性の証でもある学生服で、教員ともスクラムを組みながら、デモに出ていた。 ブント=全学連は、「反米愛国」を唱えアメリカの植民地になるなと訴えた社会党・共産党に、すでに日本は帝国主義化しているという批判をおこなったが、「もはや戦後ではない」というナショナリズム的心性に他ならない。 ブント=全学連は、「全世界を獲得する」という永続革命の理念を掲げたものの、それができる特権的な場(他ならぬ日本!)にいるということに他ならないからだ。 60年代の前哨戦、学費値上げ反対闘争でさえ、すでに「遊戯としての闘争」「闘争のための闘争」が始まっていた。▼ 第2章では、無党派市民の非暴力直接行動として評価されてきた「べ平連」の運動が、「党派を意識させられることが無かった」参加者の思惑とは別に、ソ連の仕掛ける「平和共存」路線においてのみ可能であったことが詳述される。 どうして、「ベトナム反戦運動」は高揚したのに、「イラク反戦運動」は沈滞しているのか。 それは、「アメリカが出て行け!」のあとに、ソ連がいたか、それともいないのか、にあるだけではない。 何よりも、小田実の「日本のアジア侵略の歴史」を問う「加害者の思想」は、非暴力主義・市民的反戦平和主義の枠内にあるためには、ソ連の「平和共存路線」を前提としておかなければならなかったためでありという。 「非転向」を貫いたがゆえに戦後進歩的知識人の憧憬であった、宮本顕治率いる日本共産党は、「ベ平連」に敵意を燃やして批判を展開していた。 「べ平連」運動の人脈は、日本共産党から除名された人々「ソ連派」も、合流していて大きな影響力を持っていて、いつのまにか中国派(66年以降、日本共産党から除名される)も賛同者から消えていくからである。 「べ平連」路線は、暴力革命主義の若者には生ぬるい。 とはいえ、全共闘と「べ平連」は、活動家がかぶっていたし、後者は前者のトンネルとして機能していた。 ▼ その「混じりあい」を可能にしたのは、1968年以降、世界的に展開していく市民の「非-市民」化への先駆としての、市民的規律・訓練を施す社会に対しての、違和感と反発にあった、という。 労働組合にも、学生自治体にも頼らない、べ平連の思想。 べ平連は、市民運動ではない。 その論証に、ユダを主題化する三島由紀夫の小説、「親切な機械」のモデルとなった、「アナーキスト」「ソ連派」「中国派」など、さまざまな仮面をもつ、「何も信じていない」山口健二を使って明らかにしていく下りは、本書の白眉と言えるだろう。 べ平連では、たしかにソ連派と「ソ連批判派」の新左翼や全共闘が奇妙に共存していた。 とはいえ、その奇妙な共存は、ソ連の「平和共存路線」を「親切な機械」として利用して、べ平連においてレーニン主義理論「帝国主義戦争を内乱へ」を貫徹しようとするものではなかったか。 「1968年」以降、全共闘は、ソ連「平和共存」路線と決定的に決別してしまい、べ平連とは距離をおいてしまう。 べ平連は、戦後民主主義=市民主義の定着を意味するものであるが、全共闘は「戦後民主主義=市民主義」へのサボタージュに他ならないからである。 かくて全共闘は、丸山を批判し、「学費値上げ反対」から「無期限ストライキ」にスローガンを変質させていく。▼ 第3章は、この状況下に引きおこされた、1970年7月7日「華青闘告発」の衝撃である。 「軍隊建設」をかかげていた新左翼諸党派は、在日華僑たちマイノリティーが強いられていた、入管闘争に興味を抱いていなかった。 盧溝橋事件33周年記念行事主催をめぐって、中核派と架橋青年闘争委員会は激突。 7月7日の集会は、「抑圧民族である日本人諸君」という挨拶から始まる異様なもので、侵略における大衆的民族的責任が問われる、歴史的にみて未曾有なものとなった。 そこでは、「怒れる若者」の抱く、道徳主義(PC)的なものに対する反感、すなわち「ナルシシズム=ナショナリズム」が徹底的に粉砕されてしまう。 日中国交回復よりも毛沢東国家転覆を目指していた新左翼は、このマイノリティー問題の噴出を前にして自己批判を迫られてしまう。 「血債の思想」とその精算 ――― 本来日本人で無くならない限りありえない以上、「無」でありながら「核」である主体を創出しなければならないが ――― を前面に打ち出して、自己否定の果てに現出するギリギリの「主体」の核「日本人」を模索せざるをえない。▼ 「革命の主体」たりえない ――― なりうるとすれば、在日や中国人、朝鮮人や部落民しかない ――― 日本人。 それは、宮本顕治と並ぶ、もう一つの「非転向」主体であると見なされていた部落解放同盟との提携の道を、新左翼に選ばせることになる。 「差別糾弾」闘争の展開。 しかし、それはかつて、部落解放の主張が、「我々も日本国民である」という主張を軸に展開され、その結果、水平社が「戦争協力」をおこなってしまう、いわばナショナリズムと共犯関係にあったことを忘却する道ではなかったか。 そして、本来は存在しないはずの「部落民」が、ナショナリティの核に追認されてしまうことではなかったか。 かくて、部落民が存在しない「核」であることを告発する、中上健次の文学が準備される。 「主体」であることの、「主体」を打ち立てることの、困難さ。 主体であることの責任を放棄する道は、これ以降、サブカルチャーを中心に準備されていく。(その<2>はこちらです。応援をよろしくお願いします)評価 ★★★☆価格: ¥ 903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 25, 2006
コメント(1)
-
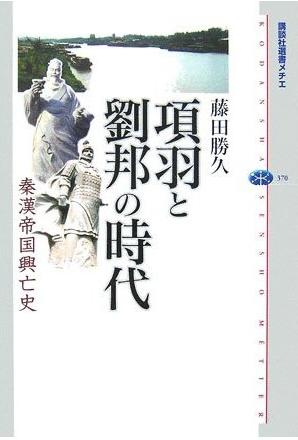
★ 藤田佳久 『項羽と劉邦の時代 ― 秦漢帝国興亡史』 講談社選書メチエ (新刊)
▼ 司馬遼太郎は、『項羽と劉邦』と『韃靼疾風録』くらいしか、読んだことがない。 何やら、司馬遼太郎自体に、いかがわしさを感じたのかもしれない。 それなのに、なぜか私は、『坂の上の雲』よりも何よりも、『項羽と劉邦』こそ司馬遼太郎の最高傑作である、と信じて疑わない。 小学生や中学生のとき、読んだ本というものは、一生の宝物になるのかもしれない。 ▼ そんな、過去をもつ恥ずかしい僕ではあるが、この本はなかなか楽しめるものであった。 目次は、こんな感じである。 序章 始皇帝と秦の統一 第1章 南方の大国・楚 第2章 秦帝国の地方社会 第3章 陳渉・呉広の叛乱―楚国の復興 第4章 項羽と劉邦の蜂起―楚懐王のもとで 第5章 秦帝国の滅亡―「鴻門の会」の謎 第6章 西楚覇王の体制―二つの社会システム 第7章 楚と漢の戦い―戦略と外交 第8章 項羽の敗北―第三の男、淮陰侯韓信 終章 漢王朝の成立―地域社会の統合▼ 司馬遼太郎を始めとして、『項羽と劉邦』とくれば、范増、韓信、陳平……綺羅星のようなスターたちの競演となるのが、普通であろう。 とはいえ、そのような類のものでは断じてない。 本書は、楚漢の2つの「システムの差異」に着目しようというのだ。なかなか意欲的ではないか。 ▼ 漢のシステムとは、元をたどれば、秦にいきつく。 この秦・楚2つのシステムは、「暦」「制度」、民の編成原理などに大きな違いがあったという。 ▼ 秦始皇の統一後、わずか15年で滅んでしまったのは、「天命を失った」というよりも、王朝の後継者争い、占領地である東方6国統治の失敗にある、らしい。 戦国中期では、秦・斉の2カ国が強盛を誇った大国であったし、「悼王」の時代、国都を占領されてしまったとはいえ、楚は強大な大国であった。 秦は、郡県制を各地で試行した。 楚も同様の方向性を志向するものの、独自の習俗をもつ、貴族制色の強い社会であったという。 しばしば、始皇帝が暗殺の危機にさらされながらも、執拗に諸国を巡行していたのは何故なのか。 それは、習俗を異にする東方六国の占領地行政がうまく浸透しておらず、行幸というデモンストレーションと滅ぼした諸国の祭祀を繰り返し執り行うことによって、秦の威光を天下に示そうとしたことにあるらしい。▼ そのような東方六国は、劉邦集団・グループにみられるように、県長・亭長の周りにも任侠・遊侠の徒がたむろする、任侠的結合が主流をなす社会だったという。 秦自体は、むやみと労役を課してはならない規定が存在していたものの、陳勝・呉広は、長雨で期日までに「戌卒」としてたどりつけることができず、腰斬の刑罰をおそれて、挙兵をおこなう。 これが引き金となって、東方6国社会は、相次いで蜂起。 劉邦は、沛県の地域社会でのつながりに、この任侠的な主客結合を持っていて、これが劉邦集団の中核を構成していく。 この人的結合の限界をのりこえるため、かれは項梁・項羽のグループに身を投じて「楚」の一員として参加していくことになる、という。▼ 秦攻略の功績で、「漢王」に封ぜられた劉邦。 そこから、「関中」を攻め落として、かの地を本拠として、楚との戦いに赴くことになる。 しかし、その根拠地化の過程では、古来から言われてきた、秦の戸籍・行政文書・法律文書をそのまま手に入れたことだけが重要だったのではない。 もうひとつ、劉邦がした決定的なことは、「秦の社稷」を廃して「漢の社稷」をたてたことにほかならない。 当時の情勢では、この行為は、楚の制度を導入しないこと、秦の制度を引き継ぐことを、「関中」の人間に対して宣言する効果をもち、そのことで秦の民に漢支配を受け入れさせることにつながったという。 ここに楚漢抗争は、楚と秦、2つの社会システムの抗争になっていく。 その過程で、戦場と生産地(領地)が隣接していて、闘えば闘うほど消耗していった項羽。 それに対して劉邦は、戦場と「関中」が離れていたこともあって、丞相・蕭何の「生産の安定」「軍糧輸送」の手腕の確かさによって、持久戦になるに従い、徐々に優位を確立していく。▼ 「四面楚歌」で知られる「垓下の戦い」が、項羽にとって決定的だったのではない。 それ以前の段階で、楚漢の決着はついていた、という。 蘇秦・張儀ばりの合従連衡の結果、韓信を味方に付け、項羽を滅ぼした劉邦。 このとき筆者は、項羽終焉の地、烏江の渡し守に語った、項羽の最後のセリフ「子弟8千人と長江を渡りながら、今一人も還ることなければ、どうして父老に顔をあわせることができようか」の言葉に、長江地域からの、人と物の組織化に失敗していた項羽陣営の惨状を見いだす。 なかなか感嘆させられる話ではないか。 この後、400年の漢王朝の支配が始まり、漢字・儒教を柱とする、東アジア世界が形成されることになる、として、本書は終わる。 このような過程を経て、東方6国の地域社会は、郡国制の下、劉氏一族の封土として組み入れられ、徐々に統合されていくという。▼ 劉邦は決して大人物だったわけではない。 項羽のブレーンが、人材が非常に友人・部下に限られている中で、劉邦のブレーンは、沛県の地域社会における本来劉邦の同輩連中まで含まれていて、かれらが劉邦をよく補佐することによって、天下人に押し上げていったという。 豆知識も面白い。 秦の正月は、10月。 科挙官僚以後、よく見られる官僚の本籍任用回避も、秦代のうちに、すでに「長吏以上は本籍任用不可」「長吏以下は現地採用」という形であらわれていて、たいへん興味深かった。 とくに2世皇帝胡亥は、母親が趙の一族で、その趙出身グループの力は、宰相李斯でさえ、どうにもならないほど強い政治的権力を持ちえていたというのには驚く他はあるまい。▼ なによりも面白かったのは、「鴻門の会」についてであろう。 劉邦が秦を下した後、函谷関を閉鎖してしまう。 激怒した項羽が攻め落とし、あわや一触即発。 宴席に劉邦を招いて、殺害を試みる有名な「鴻門の会」の一件は、実は、劉邦は秦を降伏させていない中でおきた、同じ「楚陣営」内の内輪モメであったらしい。 後に、劉邦は「関中の支配権」を楚の懐王から与えられたという正統性をデッチアゲるために、『史記』が「劉邦が秦を下した」という史実を捏造したのではないか? この筆者の提起には、唸らされる他はないだろう。▼ 従来、カリスマ論やリーダー論として捉えられてきた、楚漢抗争史。 筆者は、この従来の傾向に対して、「社会システムの違い」として捉えようとしている。 とはいえ、当初の課題はまったくといっていいほど、果たされていない。 竹簡や木簡で社会システムを復元しても面白くないこともあるのだろうか。 それとも、ドキュメント風の記述を心がけたためなのか。 従来の楚漢抗争史に「毛がはえた程度」のものになってしまった。 たしかに楚・秦の社会に違いがあることは、何度も強調されているので分かるものの、どのようなシステムの差異であるのか、レビューを書くために再読した後になっても、さっぱり理解できない。 郡県制、封国、郡国制の違いなどを語っているものの、所詮、政治体制の違いでしかない。 とても、社会システムの違いとはいえまい。 ▼ 「社会的説明を加えて、司馬遼太郎『項羽と劉邦』をツマンナくした本」。 そう結論付けるのは、言いすぎだろうか。▼ とはいえ、司馬遼太郎『項羽と劉邦』がお好きな方は、一読して決して損のない作品になっていることは言うまでもない。 とはいえ、中国古代史をよく知っている人間にとっては、たいして斬新な知見があるわけでもなし(あたりまえだ!)、読まれない方が身のためだろう。 評価 ★★★価格: ¥ 1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸陳瞬臣も、『太平天国』と『江は流れる』の途中で挫折して、読まなくなって久しい。 このたび、集英社新書から新刊を出されたようだ。 たまには、昔のように、襟を正して拝読したいとおもう。 ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 19, 2006
コメント(0)
-
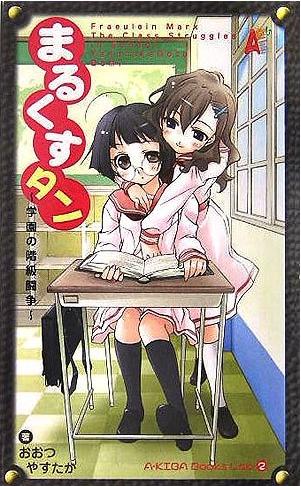
★ おおつやすたか 『まるくすタン ~学園の階級闘争』 サンデー社 (2005年12月)
▼ 「萌え」なる恥ずかしい単語が、「おたく界」で市民権を得たのは、いつ頃からだろうか?。 おいら的には、「ルリルリ」全盛の頃、初めて耳にしたような記憶があるのだが、すでに定かではない。▼ 『萌える英単語』が増刷を重ねる、現在。 この世には、『萌えるマルクス主義』ならぬ、『まるくすタン』と名のる「天下の奇書」が存在しているらしい。 カール・マルクスを美少女にして、マルクス主義の歴史を百合ラブコメ学園ものにしてしまえ! マルクス主義の登場人物は、すべて美少女。 下部構造は、「下半身の欲望」の別名になる。 むろん、「百合」にはエッチシーンあり。 「神をも恐れぬ所業」と帯書には書かれてあるが、この文句、ダテではない。 ▼ 小説のネタバレになるかもしれないが、面白さを損なわない程度に紹介しておこう。 とにかく、全編、爆笑もの。▼ 主人公は、理屈っぽく身もふたも無い、「まるくすタン」と呼ばれた美少女、丸楠かおる。 中学生のとき、新聞部に入ったものの、その顧問の美しい女性教師に、優しく手ほどきされるのが、「ヘーゲル左派」の思想、、、、、ありえねえー! ▼ そんな女性教師がいるものか! というなかれ。 やがて、放校された美少女・まるくすタンは、女子高に入ってしまう。 そこで、偏屈な彼女に恋をして支えてあげるのが、えんげるすタン。 女子高で繰り広げられる、百合な世界。▼ 冷静に社会構造を分析するまるくすタン。 人形レンシェンで秘密の行為をおこなう、えんげるすタン。 なぜか、ユリ同人誌を作っている同志の女子高生たち。 万国のモテざるもの、団結せよ! 「恋愛の自由」を唱え女子高で革命を起こした跳ね返りに、「革命の堕落だわ」という、まるくすタン。 う~む。 いちいち出典が分かる人には、たまらない小説だろう。 ▼ まるくすタン卒業のあと、この女子高に入ったのが、瓜谷しのぶこと、れーにんタン。 PNは「尼港玲」。 美少女中の美少女で、女性をくどきまくるというのも、本物を考えるとお約束のうちかもしれない。 「打倒!生徒会長!」「打倒!津在!」を唱え、まるくすタンの思想をうけついだ、れーにんタン。 れーにんタンは、すべての女子を自分のものにしたい欲望そのままに生きている。 まるくすタンと会ったことのある、ぷれはーのふタンを、まずは熱い抱擁とキスで篭絡してしまう。 反省室に入れられても、「恋愛の自由」を唱えるれーにんタンは、風紀委員を篭絡してしまうのだ。 挙句の果てに、れーにんタンのSMプレイの激しさに耐えかねて、逃げ出してしまう、とろつきータン。 なんなんだ、この小説は (笑)▼ まるとふタンが出てきてれーにんタンを糾弾するは、れーにんタンはひそかにすたーりんタンを頼りにしながらも邪険にあつかうは、けれんすきータンはれーにんタンに手篭めにされるは、、、、「タン」ばかりで本当に疲れてしまうんだけど、コレ。 ▼ れーにんタンが、「完全な自由恋愛を行うには、心身の美しさが足りないわ。革命の前衛である私たちのグループがすべてを管理するようにしなければならないのよ」というのには、キター!!という気分である。 しかし、れーにんタンの同志で後の最大の批判者になる、「るくせんぶるく兄貴」がいないのは、百合小説だからだろうか。 善哉のように甘い本書に、兄貴のきつい一言は、「一つまみの塩」になったかもしれないのに。▼ なによりも苦笑させられるのは、れーにんタンが、おともに連れるのは、勝気なポニーテールのとろつきータンと、ダブダブのオーバーオールの口数の少ない謎の少女すたーりんタン、の設定だろうか。 「アスカ/アヤナミ」的キャラをこういう様に配分されると、トロツキー、スターリン像が完膚なきまでに粉砕されてしまい楽しい。 ▼ マルクスの著書、『経済学批判』『資本論』『共産党宣言』が別の言葉に置き換えられているばかりか、オナニーにいちいち「下部構造の矛盾を解決している」という言葉をあてはめていく作者の根性には、アッパレという他はないだろう。 シベリア流刑地や牢獄は、「反省室」。 歴史の事件は、みーんな、学園百合ラブコメの事件に置き換えられていて、アホにしかみえない。 ってこれホメ言葉ですよ、念のため。 ▼ 惜しむらくは、まるくす主義、じゃなかった、マルクス主義の萌え萌えストーリー(歴史)を描きながら、彼らの最大のライバル、「ばくーにんタン」にまったく触れられていないことだろうか。 「ばくーにんタン」が存在しない、まるくす主義なんて、大根おろしと醤油なしで食べる、サンマの塩焼にひとしい。 ▼ さらに、これはマルクス主義をそれなりに知っている人には面白いだろうけど、百合目当ての人は楽しめるのか?という疑念がぬぐえないことであろう。 はっきりいって、百合のレベルは最低に近い。 おまえら、同じ百合で革命なら、つだみきよ『革命の日』(新書館ウィングス)でも見習え!!!! ・・・・・ウソです、ごめんなさい。 つだみきよ名義ではマトモなもの描いてます。▼ そんな愚痴とも紹介ともつかない話はさておき、『まるくすタン』の次回作だが(あるのか?)、できれば『はいでっがータン』か、『ふろいとタン』というのはどうだろう。 ひとらータンに一目ぼれする、はいでっがータン、というのもオツなもんではないか ?▼ シャレや冗談が分かる人はむろんのことだが、それよりもむしろ、本気の方にこそ、お勧めしたい。 ▼ 残部僅少。 欲しいものは、ただちに書店に走れ!評価 ★★★価格: ¥ 997 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 15, 2006
コメント(1)
-
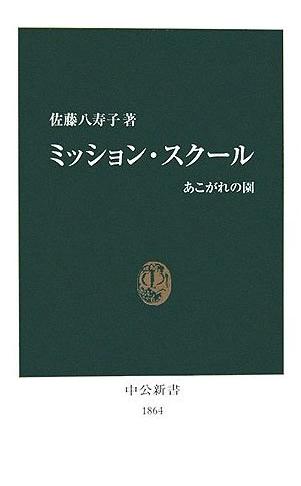
★ 佐藤八寿子 『ミッション・スクール』 中公新書 (新刊)
▼ 「評価に困る本」というのは、結構、こういう新書部門には多い。 とりわけ、意欲的でありながら、空回りしている作品だと、この可能性は極めて高くなるだろう。▼ ミッション・スクールは、なぜ東京以外の場所にまで、多数作られているのか。 それも、キリスト教の伝道活動の一環として設立され、名門校の主流を構成しているくらい広範に。 しかも、驚くべきことに、社会にはキリスト教徒はほとんどいないにも関わらず。 仏教徒のいない国に、名門校が仏教系である国なんて、想像することができるだろうか。 筆者は、そこに、ミッション・スクールのもつ、西欧文化導入と近代化のルートとしての機能をかぎつける。 ▼ 筆者によれば、ミッション・スクールに通わせることは、西洋的な礼儀作法・服装・身のこなしといった「プラティーク」であり「ハビトゥス」の表象を身につけさせることで、「清廉潔白・明朗・健全」といった、リスペクタビリティなる社会資本を獲得するための行為だったという。 1890年代以降、近代教育の制度化と大衆的情報メディア・ネットワークの確立は、新聞をうむ。 これは新しい「醜聞」をうみおとす。 リスペクタブルな国民像を推奨して身につけさせるための表裏一体の装置、「制度としてのスキャンダル」に、ミッション・スクールは巻きこまれざるをえない。 明治期以降も、依然として、忌避すべきものだった、キリスト教。 仏教界も、キリスト教に脅えて、「不敬」「非国民」バッシングに荷担する。 この「不敬」というスティグマは、ミッション・スクールのもつ、「ハイカラさ」「西洋的教養」というチャーター効果を削減するものの、内部から活性化させる機能を果たしていたという。 ▼ 筆者は、なおも問いかけをやめない。 男子校にもミッション・スクールはあるはずなのに、なぜ女子校・女学生だけイメージしてしまうのか。 このジェンダー・バイアスは、なにを意味しているのか。 肥大化するミッション・スクール幻想を提供したメディア、文学を丁寧に検証してゆく。▼ 徳富蘆花、島崎藤村などの小説をみれば、その理由は、近代的女学校の誕生が、遊郭ではない女性との交際を可能としたことにあるらしい。 文芸作品に流れる、ファム・ファタル(男を破滅に導く女性)としての、ミッション・ガール像。 それは、ヨーロッパのファム・ファタルが、商売女としてイメージされるのが通例であり、明治~大正時代には「毒婦」「妖婦」ものが流行していたのとは、まったく対極にあたる。 彼女たちミッション・ガールは、「知的」「清らか」「イノセント(無垢)」として形容されるのだ。 彼女たちは、「不良」の条件であるロマンティストでリベラルな風土であるミッション・スクールで育ったためか、文学趣味で芸術を愛好する「境界破壊者」として描かれる。 そこに筆者は、明治時代以降の正統イデオロギーであった「立身出世主義」「良妻賢母」に対する、近代日本知識人の欲望の陰画としてのミッション・ガールを嗅ぎつけていく。▼ 「教養ある自由人」。 これを目指してリベラル・アーツ教育をかかげたミッション・スクールの対極には、手芸・裁縫などを中心とする「良妻賢母」主義の官立女学校が存在している、という。 非産業的なリベラル・アーツに対して、生産に直結した後者。 近代都市文化に根ざしたミッション・スクールの洗練された教養主義は、近代日本における農民型刻苦勉励主義に支えられた「教養主義」とも違うものだ。 ミッション・スクール卒の女性は、同じ教養主義をもつ高学歴の男性と結婚しても、良妻賢母をもとめる夫の圧力によって、やがてはキリスト臭の教養主義を捨てざるをえない。 しかし高学歴男性は、「良妻賢母」教育の実科高等女学校よりも、リベラル・アーツ色の強い、ミッション・スクール卒の女性を求めたという。 ミッション・スクールとは、見合い履歴書の記号として絶大な威力を発揮することで、良妻賢母という「より大きな国民的規範」に統合されていったらしい。▼ 昭和期になると、正田美智子妃によって、ミッション・スクールが大フィーバーになる。 平民、恋愛結婚……「わたしも美智子さん」ブームは、近代家族の理想の頂点を皇室に見いだしたことで、この神話を完成させた。 ▼ 雅子妃も同様な境遇にもかかわらず、なぜフィーバーは起きないのか。 もはや「刻苦勉励」「立身出世主義」が退潮してしまい、立身出世主義者の愛憎をかきたてたファム・ファタルとしてのミッション・ガールも魅力を失っていたからだ、という。 ミッション・ガール(そしてボーイ)は、語学堪能・海外ブランド品を身につけたもの、としてチャーター効果をつなぎかえた。 今では、脱宗教化された時代の宗教学校というパラドキシカルな存在、ミッション・スクールは、オシャレでクラス感を感じさせる、「純粋培養された人々」、古色蒼然で笑いを誘うもの、性的倒錯の舞台など、様々にイメージを分裂させながらも、なおその価値を終えてはいない。 そう語って本書は閉じられる。 ▼ 『三四郎』美禰子のモデルは、平塚雷鳥であったという。 ミッション・スクールに「お坊ちゃん、お嬢様」学校のイメージがあるのは、日本では財産と社会・文化資本には密接な関係があるため、らしい。 ミッション・スクール的プラティークは、クリスマスなどだけではない。 ミサにおける「起立、唱歌、着席」儀礼が導入されることで唱歌がはじまっただけでなく、ミサは涅槃会・花祭の式次第にも影響を及ぼしているという。 なによりも、ミッション・スクールをまきこんだスキャンダルは、批判者と学校側で、存在しない事柄の是非をめぐる空中戦を生むことによって、「禁忌の制度化」過程、あらたなコードの定着過程でもあった、とする視点が面白い。 「キリスト教不敬事件」を通して、教育勅語のお辞儀の角度とかが定められていく姿は、毎日新聞佐賀支局・在日3世記者の「天皇不敬」が、ネットで話題になっていたことを考えると、戦前を彷彿とさせて面白い。 ▼ たいへん、魅力的な議論のように思えなくもない。 私も以下の事実を知らなかったら、諸手を挙げて賛成してしまい、コロっと、騙されてしまう所だったかもしれない。 前近代日本は、欧州(中国、インド、イスラムも)と比較すれば、隔絶した女子労働力比率をもつ、まれにみる「女性が社会に進出していた」社会だったことを。▼ となると、ミッション・スクールは、俄然、別の意味を帯びてきやしないか? ▼ なによりも、英語を学び社会進出するための手段、ミッション・スクールとは、女性版「立身出世主義」ではないのか。 実際、結婚が立身出世といえるのかは別にしても、高学歴男性と結婚する手段だったじゃないの。 はたまた、農家において「良妻賢母」であることは、可能だろうか。 「裁縫」技術は、わざわざ学校に行かせて倣わさなければならないほど、農家女性における実学として大きなウェートを占めているとはとても思えない。 女性は、朝から晩まで、裁縫以外にも農作業していたに決まっているだろう。 手芸をさせる暇のある農家など、いったい、どこにあるだろうか。 そもそも一般の農家が、実技系高等女学校に、娘を入れることができただろうか。 ▼ そう考えていくと、「ミッション・ガール」をめぐる欲望の回路は、立身出世主義の陰画では断じてない。 ミッション・スクールは、女性にとっては、語学教育などによる純粋な、『女性版立身出世主義』物語の一つではないのか。 なぜ彼女は、ミッション・スクールの社会資本を獲得することによって、女性側がどれくらい階級上昇に成功したのかを把握しようとしないのか。 ほとんど、男性側の幻想しか追っていない理由が分からない。 そもそも、女性側は、ミッション・スクールをどのように戦略として位置づけていたのか。 本書では、ほとんど分からない。▼ なぜ彼女のみならず、一般的の人々は、「女性は社会進出していなかった」と、考えてしまうだろうか。 ▼ 江戸時代、女性は働いていたし、働かない女性は、離縁されかねないものであった。 ところが、明治から大正にかけて、都市化・産業化によって中産階級が成立するとともに、その現象に変化が生じていく。 年齢別女性労働力比率は、「台形型」から「L字型」へとかわってしまう。 すなわち、社会の労働現場から、女性の退場がはじまってゆく。 人通りから、女性が少なくなる。 女性は、家庭に閉じこめられただけではない。 女性は、学校へも、閉じこめられていく。 そこに花咲いた女性の2つの類型。 これこそ、「良妻賢母」と「ミッション・ガール」ではなかったか。 「ミッション・ガール」も「良妻賢母」も、女性が社会から退場する社会条件が整備されることによって初めて現出した、男性のフェティシズムにすぎないのではないか。 ▼ 彼女は、根本的に間違っているのではないか。 「ミッション・スクール」幻想の終焉とは、立身出世主義の終わりではない。 女性の再社会進出とともに、「良妻賢母」幻想とともに「ミッション・スクール」幻想が消えたことに留意せねばならない。 それは、女性への幻想が「摩耗」してしまった結果なのだ………▼ むろん、これは、佐藤氏の出してきた資料や論点について、別のグランド・セオリー(大理論)で解釈しなおしてみたにすぎない。 しかし、いかようにも解釈できるような議論は、どんなに面白くても、空回りしている、破綻している、思いつきにすぎない、とは言えるかもしれない。▼ というわけで採点は辛い。 お許しあれ。 評価 ★★★価格: ¥ 798 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 11, 2006
コメント(2)
-

★ 黒野耐 『帝国陸軍の<改革と抵抗>』 講談社現代新書 (新刊)
▼ 講談社現代新書は、最近、まったく読まなくなった。 以前は、あの鮮やかでカラフルな装丁に騙されて、「くそう、ツマンナイ!」と、ずいぶん泣きをみたもんだ。 今思いかえしてみても、講談社現代新書で感動した本は、1冊もない。 最低でも、100冊は読んだはずなのに … 一番面白かったものの一つが、『動物化するポストモダン』だったことに、あらためて驚いてしまう。▼ 今の「お手軽な新書」路線の走りは、どう控えめに見ても、講談社現代新書だろう。 新潮新書、ソフトバンク新書……そういえば、昔、有斐閣新書というものもあったけど、今も続いているのかな、そのレーベル。 ▼ そんな、内容の薄い、「お手軽な知の入門書」の走り、講談社現代新書だけあって、この書も実につまんなかった。 黒野耐の前作、『参謀本部と陸軍大学校』や、『日本を滅ぼした国防方針』とかを読んでいて、それなりに面白かったので、期待してしまったのが、敗因かもしれない。 しくじった。 本当に残念でならない。▼ 陸軍三大改革として、桂太郎、宇垣一成、石原莞爾の改革があげられる。 本書は、なぜ桂太郎の改革のみが成功して、宇垣・石原莞爾の改革が失敗したのかを問うのだ。 とりあえず、目次だけは示しておきたい。 第1章 陸軍の創設 治安維持軍の建設 山県の陸軍掌握と国防軍への脱皮 第2章 桂太郎の陸軍改革―明治期の改革 対立する国防像 陸軍改革の始動 第一の衝突―統合参謀本部をめぐる攻防 第二の衝突―陸軍紛議 最後の衝突―月曜会事件 陸軍改革の完成 第3章 宇垣一成の軍制改革―大正期の改革 第一次世界大戦の衝撃 軍制改革への反動 軍制改革の断行と衝突 軍制改革の頓挫 第4章 石原莞爾の参謀本部改革―昭和期の改革 陸軍内の革新運動 革新という名の保革対立 陸軍による政治支配 石原莞爾の改革と挫折▼ 陸軍は、大村益次郎が設立するんだけど、当初、志願兵制の意見が強かった。 これを山県有朋は、ドイツ・フランスを参考にしながら、徴兵制度を採用する。 これは、西南戦争において、士族中心だった西郷軍に勝利することで、先見の明が明らかになった。 とはいえ、山県は、「権力掌握の牙城」として陸軍をつかい、政党勢力が統帥権を掌握することを防ぐため、参謀本部を設置して、天皇の下に直属させる。 内務省・司法省・枢密院・陸軍を横断して、山県自ら政・官・軍に権力を確立することで、分断した「政治」と「軍事」の隙間を埋めるものの、後の日本を破滅に導く遠因になる。▼ 清国との対立が高まる中で、この山県のあとを受けて陸軍を変革したのが、桂太郎であるという。 専守防御ではなくて、機動的防御ないし外征。 鎮台制から師団制。 フランス式からドイツ式。 学識あるもの、官吏、戸主なども徴兵の対象に加え、厳格なドイツ式皆兵主義としたのも、桂改革であるという。 欧州留学組で、近代教育を受けてきた、軍政の桂、軍令の川上操六、教育の児玉でタッグを組ませ、三浦・谷といった守旧派が、権力闘争においても、非主流派に属していたこともあって、排除に成功したらしい。 成功の要因は、3点あるという。 A 改革勢力の国防ビジョンのほうが、「開国進取」だったこと B 改革側に体系的・具体的施策を準備していたこと C 権力闘争にも勝つ陣容だったこと(大山・山県・西郷[従])ただ、統合参謀本部案は、三浦の本部長就任を防ぐという、山県の陸軍掌握の都合によって、一度は実施されたものの廃止されてしまう。 戦略の統一さえ、達成できない、昭和の陸海軍対立の遠因になる。 ▼ 宇垣軍制改革は、第一次大戦の総力戦の衝撃を受けて始められるが、短期決戦から総力戦への転換、軍隊数を削減して火力の増強という、改革ビジョンを実現できないまま終わってしまう。 それは、ポテンシャルがない日本の現実に直面し、「総力戦を戦うことに反対」する日露戦争型短期決戦主義派が、参謀本部を中心に台頭してしまったから、とされる。 精鋭主義と精神力主義で補うとする、上原勇作・荒木貞夫らの守旧派の勝利。 そこに筆者は、総理への野望を隠さない、宇垣一成の剛毅不屈というよりも傲慢な性格が、緊縮財政のためだけの体系的ではない軍縮、政府・与党と連絡を密にしないがため共有されないビジョン、というマイナスをまねいたことを見出そうとする。 宇垣には、衆知を糾合して改革をおこなう、リーダーの素質がない。 大命降下の際、陸軍にソッポを向かれる遠因、と結論づける。▼ 石原莞爾の改革とは、実際には「皇道派(保守派)VS統制派(改革派)」のことを指すらしい。 緊縮財政のみで、空手形になった宇垣軍制改革。 宇垣改革を葬った陸軍は、皇道派と統制派に陸軍は分裂してしまう。 満州事変以降、陸軍は国内でクーデターをやるかわりに、海外でクーデターを断行する形で、国内体制転換を図ってゆく。 総力戦・長期持久戦・国家総動員体制の確立を痛感する故・永田鉄山の衣鉢をつぐ統制派は、「2・26事件」以降、反乱鎮圧を担った功労者顔で、山県が陸軍を掌握するために作った統帥権独立と幕僚制度を利用して、陸軍中心とした政治支配にのりだした。梅津陸軍次官を中心として行われた、軍部大臣現役武官制、軍務局から兵務局の独立、陸相権限の強化。 石原莞爾は、この流れにのって参謀本部に入るものの、戦争指導の中核がないことに気づき、省部横断体制で改革に乗りだす。 だが、「国防方針(国策の基準)」は、陸海対立で「北守南進」「北進南守」を決めることすらできない。 そこで、「国防国策大綱」によって転覆を図り、「重要産業五カ年計画」などを策定したものの、板垣陸相実現をめぐって、梅津次官(板垣の先輩)と対立してしまう。 石原は、参謀本部を追い出された。 国防計画の体系と内容というソフトウェアと、参謀本部の組織改革というハードウェアの改革は、空中分解してしまった。 教訓としては、首脳が本気で改革する気はないのに、中堅幕僚がやろうとすることに無理があったという。▼ たしかに、読みやすいし、面白い部分も多い。 省部横断体制で下克上を図った石原の改革が、武藤・田中の省部横断の提携で潰された箇所とかは、「回る因果は風車」の趣があって、企業経営者の教訓などには、使えるかもしれない。 陸軍のみの改革では、失敗する。 大きな計画をおこなうには、明確な目標と、体系的・具体的な計画を準備して、計画を支持するスタッフと支持者(とくに首脳部の了解)をとりなさい。 社員を教訓するための素材には、うってつけなのかもしれない。 あと朝礼のときの挨拶か。▼ とはいえ、細部は問題が多すぎるだろう。 たとえば、平時には全力で産業振興をおこない、戦時には全国力で戦う、「産業立国主義」(犬養毅)が退けられたから、軍備削減も近代化も果たせなかったし、戦後不況も長引いたというのは、いったい何を根拠にしているのか、さっぱり理解できない。 1920年代の経済史の知見からみれば、ほとんど噴飯ものの意見といえよう。 さらに、桂改革を高く評価して、宇垣改革を批判するのも、まったく意味不明である。 そもそも、山県の庇護の下、進められた改革なら、それは「桂改革」ではなくて、「山県改革」ではないのか。 どうみても、桂は山県の使い走りにすぎないではないか、という疑念が、読みながらぬぐえない。 ▼ 最後の石原改革にいたっては、そもそも改革の名に値するのかすら、不明であろう。 国防計画と参謀本部組織の改革は、直接的には、総力戦・長期持久戦・国家総動員体制という統制派の目指したものと、まったく結びついていない。 本来介在しなければならない、企画院や商工省が抜け落ちているから、ただの陸軍内の権力闘争の次元で終わってしまう。 これで結論が「中堅幕僚だけ…」なんていわれても、そりゃ枠組が、最初から陸軍内では、そんな結論が出るのは当然だろう、としかいいようがない。 「総力戦体制」なんて、お題目は、いつのまにか消えてしまっている。 ▼ うーむ、講談社現代新書は、中公・岩波・ちくまの「新・御三家」に比べるとひどいねえ、と言うのが感想だったりする。 やっぱり、昔のカラフルな表紙に戻した方がいいんでないかい、と心底思うのであった。▼ 安いけど、図書館で借りて読むのがお勧め、てな感じ。評価 ★★☆価格: ¥ 735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 7, 2006
コメント(1)
-
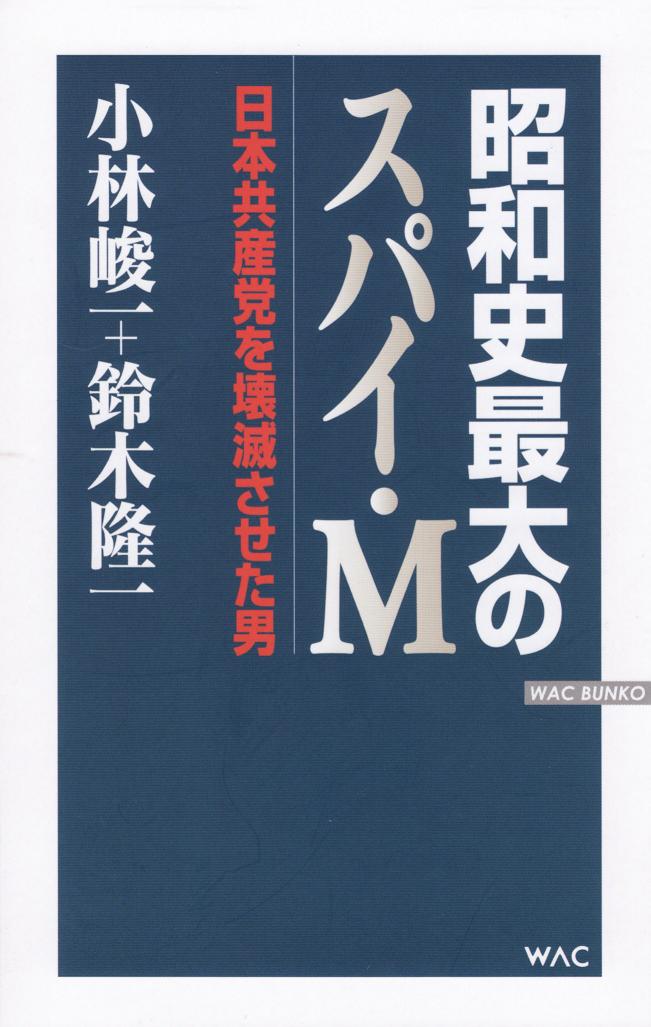
★ 小林 峻一・鈴木 隆一 『昭和史最大のスパイ・M―日本共産党を壊滅させた男』 ワック文庫 (新刊) <2>
(この日記は1からの続きですので、こちらからお読みください)▼ 「スパイM」は、シンパの金持ちの子弟に、家や銀行から多額の金や株券の「持ち逃げ」をさせ、32年3月から10月までの間に、9万円も稼いだらしい。 また、ゴロツキを集めて戦闘訓練をおこない、ギャング団まで組織したという。 その中には、戦後右翼の黒幕までいたというから、舌をまく他はない。 「スパイM」は、共産党を極左暴力集団に仕立て上げたい、毛利基・特高係長の意を汲んで、「エロ班」を結成。 生真面目な党員の献身的活動によって、女子大生を美人局(つつもたせ)にして金を巻きあげたり、エロ写真をとる活動まで手に染めさせてゆく。 これには、平塚雷鳥の激怒を始め、女性シンパの離反を招かないはずがない。 その行き着く先が、銀行強盗、いわゆる「川崎第百銀行大森支店襲撃事件」であったことは、いうまでもないだろう。 なぜなら、革命は一番大きなギャング。 革命という目的のためには、いかなる手段を採ろうとも許されるのだ。 ▼ 実は、毛利・特高係長でさえ、銀行強盗の話は知らなかったらしい。 極め付き優秀なスパイは、「2重スパイ」を帯びざるをえない。 「スパイM」と同様の、過激派の最高幹部=警察当局のスパイという図式は、ロシア革命時期、社会革命党戦闘団にも見られるらしいが、この組織の頭目だったアゼフは、スパイにも関わらず、否、スパイであるからこそ、ロシア帝国内相プレーヴェを暗殺してしまう。 アゼフとMとの違いは、革命的情勢の有無に着せられるにすぎない。 アゼフの活動は、社会革命党の信用を地に落としたものの、ボルシェビキの革命につながっていく。 しかし日本では………。 スパイMの犯罪が明らかにされると、日本共産党の信用は地に落ちた。 スパイMは、熱海事件以降、歴史の闇に消える。 その後の歴史はいうまでもあるまい。 スパイMは、満州にわたって、兄と建築業を営む。 帰国後は、共産党に報復されることにおびえながら、その生をおえる。 享年62 ▼ 「教会に行くか、バーに行くか、共産党員になるかしかない」といわれた戦前。 共産党もまたファッションだったという。 本気で革命をおこなおうとしていた当時、日本共産党幹部は、岩田義道を始めとして、拳銃を所有していたのに対して(第二次共産党の領袖、渡辺政之輔は銃撃戦の末、射殺)、警察の側は、せいぜいサーベルをぶら下げていただけ、とか、意外な事実に驚かれるであろう。 共産党幹部が料亭の待合を利用したのは、待合には臨検がなかったためとかは、当時の社会慣習を感じさせてたいへん面白い。 ▼ また、ロシア革命を成功させたボルシェビキは、赤色ギャングや紙幣の偽造をおこなっており、実行部隊の指揮者はスターリンだったらしい。 う~む、北朝鮮は、スターリンを真似ただけなのかー、な~んだ ……… って感心させられてしまう。 ▼ 何よりも、このノンフィクションを面白くしているのは、スパイMの対極に位置した、毛利基・特高係長について、キチンと描ききったことにあるだろう。 スパイMによって、異例の出世を遂げ、「毛利は俺が出世させてやったようなものだ」とまで言われた毛利基。 かれは、小卒の巡査がキャリアのスタートだったという。 人柄もよく、丁寧な性格。 猛勉強で特高畑のエキスパートになる。 終戦時、埼玉県県警本部長。 常に数珠を身に着けて、任務にあたっていた彼は、「オレはウソをいってリーダーシップをとってきた。国民に合わす顔がない」という言葉を残して、辞表を提出した。 スパイMと、毛利基。 対極でありながら、出自・性格とも似た2名が織り成した、重層的な物語。 どちらが欠けても、この物語は存在しなかったといってよい。▼ 実は、今も「スパイM」は、生き続けている、といったら驚かれるであろうか。 飯塚本人は、唱和40年9月4日に死亡したものの、それはニセの戸籍上でのこと。 火葬場で火葬を拒否されそうになったらしい。 今もなお、戸籍上では、生きていることになっている。 武装共産党を売った、スパイ小曾根勢四郎。 山本正美たち3名の中央委員を売り、「蟹工船」「党生活者」で知られた小林多喜二を売って、一人で組織を壊滅させた、スパイ三船留吉。 リンチ共産党時代、宮本顕治に査問された、スパイ大泉兼蔵。 政治組織にスパイを入れるのは、戦前だけの話ではない。 戦後、日本共産党において、最高・最大の機密決定であった、野坂参三・名誉議長の除名決議。 しかし公安警察は、発表1時間前に、スパイによって、最高機密を入手していたというのだ。 また、一水会のように、当局に情報を渡さない右翼には、厳しい弾圧をおこなう公安当局。 スパイMは、あなたの周りのどこにでもいて、今もその情報を送っているかもしれないのだ ……… と、言ってみたくなるというもの。▼ 難点としては、「スパイM」の戦後が余分に感じられることにあるかもしれない。 ▼ そんな、余裕があるならば、野呂栄太郎時代の共産党や、大泉・三船の事件を丁寧に描き、戦前共産党の最後をかざる「リンチ共産党」まで描いてほしかった。 恒常的にスパイが生まれている中における、筆者の強調したい「Mの特異性」が、いまいち感じられなかったからだ。 また、スパイMの凡庸な戦後を描くのであるなら、共産党を当局に売り渡した他のスパイたちの「戦後」についても、触れても良かったようにおもう。 そうなれば、さらに重層的なスパイの物語になっただろうに。 なんとなく物足りなさが残るラストだったことは否めない。▼ とはいえ、何よりも驚くのは、このような本が、渡部昇一や東条由布子など、売れ筋の計算がたつ、右翼関連の書物ばっかり出版していた、ワック株式会社から出版されたことにあるのではないか。(笑) 何か心変わりでもしたのならば、うれしい限りである。 このような良書を今後も出版してもらうためにも、ぜひご一読をお願いしたい。評価 ★★★☆価格: ¥ 980 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 3, 2006
コメント(4)
-

★ 祝!高尾紳路・実力制第六代「名人本因坊」誕生!
▼ とりあえず、おめでたいので、コッソリと祝福します。 おめでとう!▼ 実力制第6代と書いたけど、正確にいえばちがう。 家元制の本因坊は、実力のない人間がつくことがあっても、江戸時代以来、すべてを定先以下に打ちこまなければならない「名人碁所」の地位は、隔絶する実力がなければ就任できない。 ▼ 江戸時代は、本因坊算砂、中村道碩、安井算知、本因坊道策、井上因碩道節、 本因坊道知、本因坊察元、 本因坊丈和の8名。 明治以降、名人碁所はなくなった。 でも、「名人」は残った。 明治の名人は本因坊秀栄、大正~昭和にかけては本因坊秀哉。 21世本因坊秀哉が本因坊位を返上、引退をおこなって、現行のタイトル戦が始まった。 名人位になれなかった悲運の棋士は多い。▼ すべての碁打ちの理想、名人にして本因坊は、実力制以外にない。 でも、『坂田一代』などを読むと、名人位がタイトル戦の名前になって以降、初代の実力制名人・本因坊になった坂田栄男の喜びが伝わってきて、やっぱり「実力制」と呼んでおきたいなあ。▼ 名人・本因坊は、高尾で6人目。 坂田栄男以降、林海峰(台)、石田芳夫、趙治勲(韓)、張栩(台)の5名。 ▼ 趙治勲以降は、読売棋聖戦が始まってからになるし、「棋聖・名人・本因坊」の3つを制覇することを「大三冠」といって、趙治勲が2度達成しているけど、歴史や伝統の重みがまるでない。 だからこそ、名人本因坊はメデタイ。 小林光一なんて、3度も「大三冠」を狙って、本因坊戦に挑戦したけど、とうとうなれなかったものね。 小林光一なんて、歴代最強棋士の一人なのに。▼ 以前の4名の棋士は、囲碁史に残る最強棋士揃い。 張栩だって、世界タイトルをとってるし、絶対囲碁史にその名を残す………高尾大丈夫なのか??▼ 国際戦、高尾は本当に弱い。 中・韓の若手棋士に負けてばかり。 弱ったなあ。▼ これまで日本の名人といえば、小林光一、依田紀基、張栩と、 国際戦に強い棋士だらけだったのに…▼ それに、本因坊位にせっかくついたのに、自ら雅号を決めて「本因坊○○」を名乗る慣例が蔑ろにされているのはどうなのよ。 本因坊坂田栄寿、高川秀格、加藤剣正とか、みんな名のっていたのになあ。 林海峰・趙治勲先生を始めとした、「雅号」を決めない棋士の天下が長すぎたのか。 高尾紳路には付けてほしいよお▼ 書評サイトなので、こっそりと応援。 本当は11月5日に書いてるけど、2日に入れました。 メンゴ!▼ 明日は、キオスクで『週刊碁』買わないと……▼ それにしても、それにしても……▼ 依田に名人本因坊なって欲しかったなあ……2年前…… ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 2, 2006
コメント(1)
-
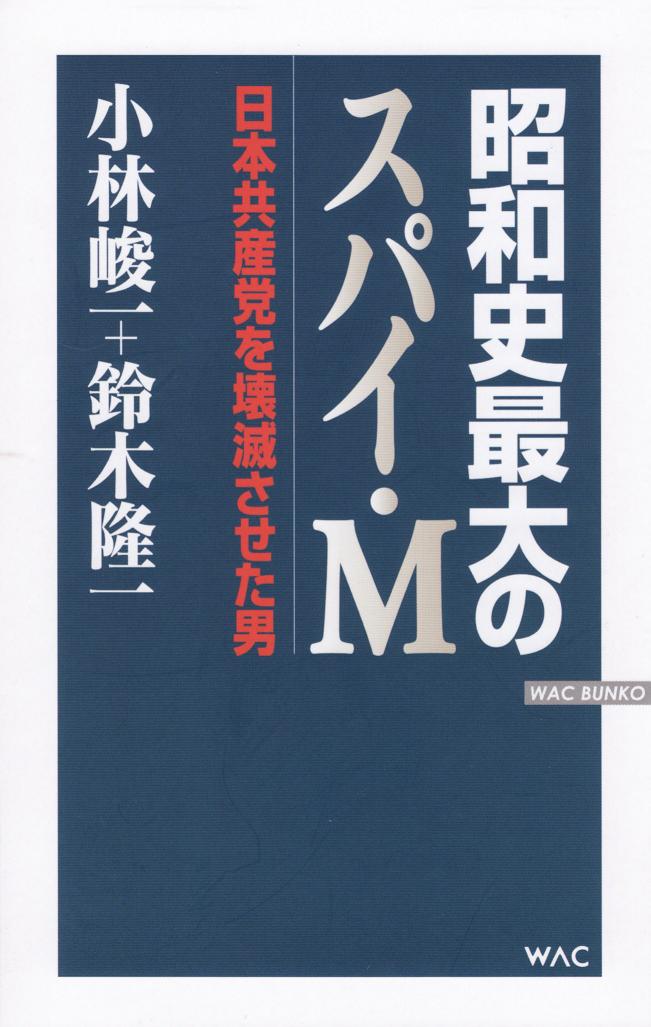
★ 小林 峻一・鈴木 隆一 『昭和史最大のスパイ・M―日本共産党を壊滅させた男』 ワック文庫 (新刊) <1>
▼ いやあ、面白い。 本書は、戦前、ファシズム国家によっておこなわれた、悪辣極まりない謀略の記録である。 毛利基・特高課長(兼係長)脚本、「スパイM」こと松村昇、本名飯塚盈延(みつのぶ)主演。 その演目は、「極左共産党の恐怖」とでも言えるだろうか。 ▼ 戦前日本において、2人の人間によって画策され遂行された、戦前最大の規模にまで達した、「官製・非常時日本共産党」の育成・膨張と、その破滅まで過程を描いた、一大ドキュメンタリー。 この謀略の伝記が、面白くないはずがない。 本書は、国家権力のオゾマシさについて、語り尽くしてあますところがない。▼ 章立ては以下のとおり。第1章 最後の賭け―熱海事件と非常時共産党の壊滅第2章 モスクワへの道―生い立ちからクートベ留学まで第3章 転回点―武装共産党時代第4章 背信と謀略―非常時共産党の再建と躍進第5章 闇の帝王―銀行ギャング事件第6章 転生―熱海事件以後、死まで▼ 従来の「1931年テーゼ」とは大幅に異なる、クレムリンの都合によって採択された、コミンテルン「1932年テーゼ」。 日本共産党の幹部でさえ、意見は割れて、大揺れに揺れた。 「党大会」による承認手続きは、避けて通れない。 1932年10月30日、その熱海における全国代表者会議を狙い、特高警察は「スパイM」の手引きによって、一斉検挙をおこなう。 世にいう「熱海事件」である。 これによって、事実上、日本共産党は息の根を止められてしまう。▼ しかし「スパイM」は、単純な特高のスパイではなかった。 毛利基の想定外の独自の行動をも、平然ととる人物であった。 後にかれは、スパイ時代のことについて、「自主独立の境地」であったと語っているらしい。 その「スパイM」の思惟は、どのようなものだったのか。 筆者2人は、丁寧にその過程を明らかにしていく。 ▼ 解きがたい苦悩の底に見出される希望の光でありながら、迫害者に対する英雄的テロリズムのはてしなき苦行の連続(BY 鍋山貞親)であった、社会主義。 その中で到来した、「自らの力で解放した」「労働者の政権」、ロシア革命の福音。 スパイMは、米騒動などで騒然とする中、日本共産党最初の労働者党員にして、革命運動の闘士、渡辺政之輔率いる東京合同組合に身を投じ、労働運動にかかわっていく。 「渡政」に見出され、1926年8月頃、「労働者の祖国」ソ連に派遣されるものの、この頃から彼は、「語学がまるでダメ」「陰鬱な奴」など、それまでの闘士とは違った姿を見せ始める。▼ 「スパイM」が、特高警察当局によって見出されるのは、1929年7月から1930年7月までの、「武装共産党時代」の指導者、田中清玄(当時23~24歳)の逮捕がキッカケとしてあるという。 「中央委員」クラスの党員を中心に、共産党再建が目指されるにちがいない。 中央委員をスパイとして育成せよ。 そうにらんで、網を張っていた、毛利・特高課長に捕らえられた、「スパイM」。 すでに帰国時には、実質的に「転向状態」にあった彼は、拷問されることもなく、自分の意思でスパイに志願したらしい。 彼はモスクワから帰国したばかりの風間丈吉に、指導者になることを要請。 1931年から始まる、非常時共産党の全権を掌握する「スパイM」。 すでに日本共産党再建のシナリオは、毛利基・特高係長と「スパイM」の間で、できあがっていたのだ。▼ しかし、スパイMは、1931年3月には、仲間からスパイ容疑がもたれていたらしい。 この苦難を乗りこえて、「スパイM」が非常時共産党の全権を握れたのは、風間・岩田たち指導部の全面的信頼と、コミンテルンとの連絡網を抑えることで党の資金ルートを握っていたからだという。 月々2千円が、コミンテルンから渡されていた、当時の日本共産党。 コミンテルンの指揮下に共産党が置かれたのでは、特高も「スパイM」も、都合が悪い。 そこで、上海租界のコミンテルン支部を当局に売って、日本共産党を「糸の切れたタコ」の状態にしてしまう。 「スパイM」は、党の非合法活動「テク」(技術部)を掌握して、資金作りを一手に担う。 風間・岩田も、資金を作ってもらう関係上、「スパイM」には頭があがらない。▼ 特高は、KGBのように、何でも許されているわけではない。 なによりも、スパイを使うことは、超法規的措置であって、使うことは許されていない。 そのため、Mがスパイであることを知っているのは、毛利係長だけなのであって、Mが事情を知らない他の部局に逮捕されてしまっては、お話にならないのだ。 とにかく「スパイM」は、非合法活動に関して能力に関して、極め付き優秀な人物であったらしい。 コミンテルンの援助がこない中、日本共産党の党勢は拡大の一途をたどってゆく。 講座派マルクス主義の学者をはじめとして、文春の創始者・菊池寛や太宰治までに及んだ、シンパの資金網。 Mは、月平均2万円もの資金集めをおこなっていたという。 1932年初頭、その資金網が特高に潰されると、いよいよ「スパイM」は、本領をあらわしはじめる。 佐野学・鍋山貞親の奪還計画を提案して、自ら特高に通報。 有能な活動家は、スパイの汚名を着せて、射殺させる。 (その<2>はこちらになる予定ですんで、応援をよろしくお願いします 長すぎて1日では終わらなかった…)評価 ★★★☆価格: ¥ 980 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Nov 1, 2006
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










